44 / 123
第三章 確執
四郎頼賢(一)
しおりを挟む
(まったく、父上がお悪いのだ…!)
六条堀河の邸の渡殿を足音荒く歩きながら、源為義の四男、四郎頼賢は苛立たしく呟いた。
(父上さえ態度をはっきりさせておけば、今になって義朝の兄上のあのような身勝手な振る舞いを許すような破目にならずに済んだものを)
長兄の義朝はこのところ、父の意向に楯突いてばかりいる。
一門の最大の庇護者である藤原摂関家にもろくに伺候しようともせず、それどころか父や自分たち兄弟のことをおおっぴらに『摂関家の走狗』などと言い散らし、見下げるような態度をみせている。
そういう自分がどれだけご立派なことをしているのかと思えば、舅である熱田の大宮司、藤原季範の伝手をたどって、鳥羽の院に接近し、わずかばかりの荘園を寄進して「北面の武士」の末席に潜りこんでいるだけなのだ。
そればかりか最近では、今上帝の中宮呈子の後宮に仕える雑仕女を妾として囲いこみ、そちらの方面からも宮廷に顔を繋ごうとしているらしいと聞く。
要は女の裳裾に縋って、世渡りをしているようなもので、そんな男に父や自分たちが非難されるいわれは一つもないとも思う。
(しかし……)
頼賢が苛立っているのは義朝に対してばかりではなかった。
(そもそも、義朝の兄上を東国へ遣られたは、義賢の兄上をこそ嫡男にたてる為、体よく都を追い払われる為ではなかったのか……! 白河院の近臣の娘を生母に持つ、義朝が嫡男では摂関家の御覚えも悪かろうと……。そう思われてのことではなかったのか!)
事実、義朝が都を離れた当初はその通りだったのだと思う。
しかし、今から四年前。
久安四年の二月。
兄、義朝が東国より、まるで凱旋将軍のような派手派手しい行列を仕立てて上洛してきて以来。
その風向きがなんとなく変ってきたのを頼賢をはじめとする在京の兄弟たちは感じていた。
父の為義は人情家である。
武家の棟梁にしては気が優しく情に脆い。
自らに仕える郎党が妻や子を亡くしたと聞いては、いちいち同情して涙ぐむほどなのだ。
頼賢は父のそんなところを歯がゆく思いながらも、家中の誰からも慕われ、親しみをもって「大殿、大殿」と敬慕されている父を尊敬していた。
が、この度ばかりはそれが凶と出ている。
幼くして親元から離され、生まれもつかぬ東国へとやられながら、己の力量で周囲の豪族たちに自分を認めさせ、『上総の御曹司』の敬称をもって呼ばれるようにまでなり、一回りもふた回りも逞しくなって戻った長男の姿を見て。
久しぶりに再会した長男に、
「父上。ただ今戻りました。某が戻りましたからには、もはや平氏などに遅れはとりませぬ。いよいよ、我ら源氏の名を京に轟かせる時にござりまするぞ!」
自信に満ち溢れた口調で言われた瞬間。
父、為義は顔をくしゃくしゃに歪ませて、咽び泣いたのだそうだ。
隣室に控えていたらしい女房の一人から、
「まるで昔物語の一場面のような。また、義朝さまが、八幡太郎義家さまがご再来になられたかのような凛々しくも雄々しい武者ぶりでいらっしゃって……」
と、うっとりとした口調でその時の様子を聞かされて以来。
頼賢はずっと嫌な予感がしていた。
次兄の義賢は、これが我らと血の繋がった兄弟かと疑いたくなるほど整った顔立ちをしている。
整っているといえば、長兄の義朝もなかなかの美男子ではあるのだが。
義賢の容貌は、下級の女官とはいえ宮仕えをしていたという生母の血筋のなせるわざだろうか。
白い肌に、黒目の勝った切れ長の瞳、すっきりと通った細い鼻筋に、自然と赤みを帯びた薄い唇など。
武家の御曹司というよりは、むしろ「公達」とでもいった呼び方がしっくりくるような貴族的な、品のいい面差しをしていた。
そのせいもあって、とりわけ、現在の摂関家の氏の長者である左大臣頼長の「お気に入り」だったりもするのだが。
その風貌を「軟弱な」「武家らしゅうもない」と言って、好ましくないように言う声が家中にひそかにあったことは確かだった。
それが、表立ってきたのは義朝の帰京以後のことである。
背丈がすらりと高く、肩幅の広い義朝はもともと甲冑などを着るとひどく着映えがするというか、爽やかな若武者ぶりが際立っていたのだが。
東国を放浪するうちに背丈に応じて、相応に筋肉がつき、体格が一回りも大きくなったというか。
以前は背ばかり高い印象だったのが、いかにも逞しく頼もしい武家の御曹司の風格を漂わせている。
目鼻立ちのはっきりとした精悍な顔立ちは、浅黒く日にやけたことでますます野性的な魅力を増していて。
古参の郎党のなかにも、
「太郎君の凛々しくも頼もしい武者ぶりよ」
「さすがはご嫡男。次代の棟梁の座にふさわしい」
などと褒めそやすものが出てきた。
それはまだいい。
頼賢が、腹に据えかねているのはそういった郎党たちの間に広がる空気に父の為義までもが影響され始めていることなのだ。
義朝と為義は血の繋がった親子とはいえ、良くも悪くも対称的な存在である。
人は自分とまったく異質なものを前にした時、嫌悪し退けようとするか、もしくは憧れて慕わしく思うかのどちらかだと思うのだが。
最近の為義は、義朝のなかに自分にはない「荒々しく勇ましい武家の棟梁」としての資質を見出して、それに賭けてみたいような意思を見せている、ような気がする。
もちろん、義朝に協調するということは摂関家とは距離をおき、鳥羽の院に近侍することになってしまうから、現時点ではそう簡単にゆく筈はないのだが。
為義の一の郎党、鎌田通清は義朝の乳父である。
一の郎党……とはいっても、もともとは乳兄弟として育った間柄で、為義との間の絆はともすると、実の親子である自分たちとよりもよほど強い。
また、気が弱くすぐに落ち込んでしまう為義と、豪放磊落で快活な性質の通清は主従の枠をこえてうまがあうらしく。
為義が、他の誰よりも通清を重んじ、頼っていることは誰の目からみても明らかだった。
その通清は、最近では事あるごとに
「若君は、我が殿を父君として敬い、たててゆかれようというお心が足りぬ。 あのような不忠不孝の君ではとても臣下はついてゆくまい…」
などと批判がましいことを言ってはいるが。
その実、養い君として他の子息たちとは一線を隠した情愛を抱いていることは明白である。
思いいれがあるからこそ、苦言も口にするのだ。
通清の子息、次郎正清は、その父親同士がそうであったように乳兄弟として義朝の側に片時も離れずにつき従っている。
通清が個人的な野心で、為義に要らぬ進言をするような人間ではないということはよく分かっているが…。
通清とて、ひとりの人間で、人の親である。
父親として我が子が仕える御曹司を後継者にと望むのは当然のことではないだろうか。
(もし、このまま義朝の兄上が棟梁の座につくようなことがあらば…)
頼賢は苦々しい思いで考える。
『摂関家の走狗に成り下がりたくはない』
そう公言して憚らないあの異母兄のことだ。
自らが棟梁の座につけば、父・為義の今までの血が滲むような苦労などはまったく省みずに、摂関家とは距離をおき、鳥羽の院に接近してゆくことであろう。
「摂関家の走狗にはなりたくなくて、王家の犬に成り下がるのは構わぬというのですか」
面と向かって皮肉を言ってやりたいほどだが、義朝のなかでその二つの事象はなんの矛盾もきたしていないようであった。
鳥羽の院は、ご在位中の昔より平氏をご重用なさっておられる。
それだけではない。
現在の平氏の棟梁、平清盛は風説によると故・白河院のご落胤だというではないか。
噂の真偽は確かではないが。
それが万が一、真実だとすれば、言うも憚られることながら平氏の棟梁と鳥羽の院は血の繋がった叔父、甥ということになる。
『源平』などと並び称されてはいても片方の棟梁が皇族の血を引いているとすれば、自分たち源氏がお側に侍って、いくら追従してみたところで、平氏を越えるどころか並び立つことさえ不可能なのではないだろうか。
そのあたりを、あの直情的な兄は何も考えていないように思える。
父、為義は確かに今は、藤原摂関家の使い走りのような地位に甘んじている。
夜盗の真似事をさせられたり、左大臣の意に叶わぬという理由のみで公卿の邸を襲わされたり。
武士としての誇りを踏みにじられるような屈辱的な思いを重ねながら、白塗りの青白い公家たちの足元に頭を垂れ続けている。
けれど、それは心に抱いた志があってのことなのだ。
鳥羽の院の御世で、いくら王家に媚を売っても、そこで源氏は平氏を越えることは出来ない。
決して出来ない。
確かに摂関家はいまや、往時の勢威を失い、白河院、鳥羽院と続く『治天の君』の御世のもと、そのご意向に従わざるを得ない立場に貶められてはいるが。
今上帝の御世には、お二人のお后が並び立たれている。
摂政・忠通さまのご養女であられる中宮・呈子さま。
左大臣・頼長さまのご息女であられる皇后・多子さま。
どちらも藤家の血を引く姫君であられる。
特に左大臣、頼長さまは『悪左府』という異名をとられるほど、苛烈にして聡明、怜悧な御方である。
その教養見識の高さは古今に比類なきものとして、称えられている。
もし、多子さまに男皇子ご誕生のことあらば、どのような手段を使ってでも、まだむつきにくるまっておられる年齢の若宮を東宮として立て。
いずれはご自身が帝の外祖父として権力を握られることは間違いないであろう。
為義は、それを見据えたうえで。
世人に「走狗」と蔑まれているのは承知の上で、その可能性に源氏の未来を賭けているのだ。
そんな父の痛ましいまでの心中を慮ろうともしない、それどころか見下すような態度をみせて憚らない、傲慢で身勝手な男が次代の棟梁の座につくなど、あって良い筈がなかった。
六条堀河の邸の渡殿を足音荒く歩きながら、源為義の四男、四郎頼賢は苛立たしく呟いた。
(父上さえ態度をはっきりさせておけば、今になって義朝の兄上のあのような身勝手な振る舞いを許すような破目にならずに済んだものを)
長兄の義朝はこのところ、父の意向に楯突いてばかりいる。
一門の最大の庇護者である藤原摂関家にもろくに伺候しようともせず、それどころか父や自分たち兄弟のことをおおっぴらに『摂関家の走狗』などと言い散らし、見下げるような態度をみせている。
そういう自分がどれだけご立派なことをしているのかと思えば、舅である熱田の大宮司、藤原季範の伝手をたどって、鳥羽の院に接近し、わずかばかりの荘園を寄進して「北面の武士」の末席に潜りこんでいるだけなのだ。
そればかりか最近では、今上帝の中宮呈子の後宮に仕える雑仕女を妾として囲いこみ、そちらの方面からも宮廷に顔を繋ごうとしているらしいと聞く。
要は女の裳裾に縋って、世渡りをしているようなもので、そんな男に父や自分たちが非難されるいわれは一つもないとも思う。
(しかし……)
頼賢が苛立っているのは義朝に対してばかりではなかった。
(そもそも、義朝の兄上を東国へ遣られたは、義賢の兄上をこそ嫡男にたてる為、体よく都を追い払われる為ではなかったのか……! 白河院の近臣の娘を生母に持つ、義朝が嫡男では摂関家の御覚えも悪かろうと……。そう思われてのことではなかったのか!)
事実、義朝が都を離れた当初はその通りだったのだと思う。
しかし、今から四年前。
久安四年の二月。
兄、義朝が東国より、まるで凱旋将軍のような派手派手しい行列を仕立てて上洛してきて以来。
その風向きがなんとなく変ってきたのを頼賢をはじめとする在京の兄弟たちは感じていた。
父の為義は人情家である。
武家の棟梁にしては気が優しく情に脆い。
自らに仕える郎党が妻や子を亡くしたと聞いては、いちいち同情して涙ぐむほどなのだ。
頼賢は父のそんなところを歯がゆく思いながらも、家中の誰からも慕われ、親しみをもって「大殿、大殿」と敬慕されている父を尊敬していた。
が、この度ばかりはそれが凶と出ている。
幼くして親元から離され、生まれもつかぬ東国へとやられながら、己の力量で周囲の豪族たちに自分を認めさせ、『上総の御曹司』の敬称をもって呼ばれるようにまでなり、一回りもふた回りも逞しくなって戻った長男の姿を見て。
久しぶりに再会した長男に、
「父上。ただ今戻りました。某が戻りましたからには、もはや平氏などに遅れはとりませぬ。いよいよ、我ら源氏の名を京に轟かせる時にござりまするぞ!」
自信に満ち溢れた口調で言われた瞬間。
父、為義は顔をくしゃくしゃに歪ませて、咽び泣いたのだそうだ。
隣室に控えていたらしい女房の一人から、
「まるで昔物語の一場面のような。また、義朝さまが、八幡太郎義家さまがご再来になられたかのような凛々しくも雄々しい武者ぶりでいらっしゃって……」
と、うっとりとした口調でその時の様子を聞かされて以来。
頼賢はずっと嫌な予感がしていた。
次兄の義賢は、これが我らと血の繋がった兄弟かと疑いたくなるほど整った顔立ちをしている。
整っているといえば、長兄の義朝もなかなかの美男子ではあるのだが。
義賢の容貌は、下級の女官とはいえ宮仕えをしていたという生母の血筋のなせるわざだろうか。
白い肌に、黒目の勝った切れ長の瞳、すっきりと通った細い鼻筋に、自然と赤みを帯びた薄い唇など。
武家の御曹司というよりは、むしろ「公達」とでもいった呼び方がしっくりくるような貴族的な、品のいい面差しをしていた。
そのせいもあって、とりわけ、現在の摂関家の氏の長者である左大臣頼長の「お気に入り」だったりもするのだが。
その風貌を「軟弱な」「武家らしゅうもない」と言って、好ましくないように言う声が家中にひそかにあったことは確かだった。
それが、表立ってきたのは義朝の帰京以後のことである。
背丈がすらりと高く、肩幅の広い義朝はもともと甲冑などを着るとひどく着映えがするというか、爽やかな若武者ぶりが際立っていたのだが。
東国を放浪するうちに背丈に応じて、相応に筋肉がつき、体格が一回りも大きくなったというか。
以前は背ばかり高い印象だったのが、いかにも逞しく頼もしい武家の御曹司の風格を漂わせている。
目鼻立ちのはっきりとした精悍な顔立ちは、浅黒く日にやけたことでますます野性的な魅力を増していて。
古参の郎党のなかにも、
「太郎君の凛々しくも頼もしい武者ぶりよ」
「さすがはご嫡男。次代の棟梁の座にふさわしい」
などと褒めそやすものが出てきた。
それはまだいい。
頼賢が、腹に据えかねているのはそういった郎党たちの間に広がる空気に父の為義までもが影響され始めていることなのだ。
義朝と為義は血の繋がった親子とはいえ、良くも悪くも対称的な存在である。
人は自分とまったく異質なものを前にした時、嫌悪し退けようとするか、もしくは憧れて慕わしく思うかのどちらかだと思うのだが。
最近の為義は、義朝のなかに自分にはない「荒々しく勇ましい武家の棟梁」としての資質を見出して、それに賭けてみたいような意思を見せている、ような気がする。
もちろん、義朝に協調するということは摂関家とは距離をおき、鳥羽の院に近侍することになってしまうから、現時点ではそう簡単にゆく筈はないのだが。
為義の一の郎党、鎌田通清は義朝の乳父である。
一の郎党……とはいっても、もともとは乳兄弟として育った間柄で、為義との間の絆はともすると、実の親子である自分たちとよりもよほど強い。
また、気が弱くすぐに落ち込んでしまう為義と、豪放磊落で快活な性質の通清は主従の枠をこえてうまがあうらしく。
為義が、他の誰よりも通清を重んじ、頼っていることは誰の目からみても明らかだった。
その通清は、最近では事あるごとに
「若君は、我が殿を父君として敬い、たててゆかれようというお心が足りぬ。 あのような不忠不孝の君ではとても臣下はついてゆくまい…」
などと批判がましいことを言ってはいるが。
その実、養い君として他の子息たちとは一線を隠した情愛を抱いていることは明白である。
思いいれがあるからこそ、苦言も口にするのだ。
通清の子息、次郎正清は、その父親同士がそうであったように乳兄弟として義朝の側に片時も離れずにつき従っている。
通清が個人的な野心で、為義に要らぬ進言をするような人間ではないということはよく分かっているが…。
通清とて、ひとりの人間で、人の親である。
父親として我が子が仕える御曹司を後継者にと望むのは当然のことではないだろうか。
(もし、このまま義朝の兄上が棟梁の座につくようなことがあらば…)
頼賢は苦々しい思いで考える。
『摂関家の走狗に成り下がりたくはない』
そう公言して憚らないあの異母兄のことだ。
自らが棟梁の座につけば、父・為義の今までの血が滲むような苦労などはまったく省みずに、摂関家とは距離をおき、鳥羽の院に接近してゆくことであろう。
「摂関家の走狗にはなりたくなくて、王家の犬に成り下がるのは構わぬというのですか」
面と向かって皮肉を言ってやりたいほどだが、義朝のなかでその二つの事象はなんの矛盾もきたしていないようであった。
鳥羽の院は、ご在位中の昔より平氏をご重用なさっておられる。
それだけではない。
現在の平氏の棟梁、平清盛は風説によると故・白河院のご落胤だというではないか。
噂の真偽は確かではないが。
それが万が一、真実だとすれば、言うも憚られることながら平氏の棟梁と鳥羽の院は血の繋がった叔父、甥ということになる。
『源平』などと並び称されてはいても片方の棟梁が皇族の血を引いているとすれば、自分たち源氏がお側に侍って、いくら追従してみたところで、平氏を越えるどころか並び立つことさえ不可能なのではないだろうか。
そのあたりを、あの直情的な兄は何も考えていないように思える。
父、為義は確かに今は、藤原摂関家の使い走りのような地位に甘んじている。
夜盗の真似事をさせられたり、左大臣の意に叶わぬという理由のみで公卿の邸を襲わされたり。
武士としての誇りを踏みにじられるような屈辱的な思いを重ねながら、白塗りの青白い公家たちの足元に頭を垂れ続けている。
けれど、それは心に抱いた志があってのことなのだ。
鳥羽の院の御世で、いくら王家に媚を売っても、そこで源氏は平氏を越えることは出来ない。
決して出来ない。
確かに摂関家はいまや、往時の勢威を失い、白河院、鳥羽院と続く『治天の君』の御世のもと、そのご意向に従わざるを得ない立場に貶められてはいるが。
今上帝の御世には、お二人のお后が並び立たれている。
摂政・忠通さまのご養女であられる中宮・呈子さま。
左大臣・頼長さまのご息女であられる皇后・多子さま。
どちらも藤家の血を引く姫君であられる。
特に左大臣、頼長さまは『悪左府』という異名をとられるほど、苛烈にして聡明、怜悧な御方である。
その教養見識の高さは古今に比類なきものとして、称えられている。
もし、多子さまに男皇子ご誕生のことあらば、どのような手段を使ってでも、まだむつきにくるまっておられる年齢の若宮を東宮として立て。
いずれはご自身が帝の外祖父として権力を握られることは間違いないであろう。
為義は、それを見据えたうえで。
世人に「走狗」と蔑まれているのは承知の上で、その可能性に源氏の未来を賭けているのだ。
そんな父の痛ましいまでの心中を慮ろうともしない、それどころか見下すような態度をみせて憚らない、傲慢で身勝手な男が次代の棟梁の座につくなど、あって良い筈がなかった。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末
松風勇水(松 勇)
歴史・時代
旧題:剣客居酒屋 草間の陰
第9回歴史・時代小説大賞「読めばお腹がすく江戸グルメ賞」受賞作。
本作は『剣客居酒屋 草間の陰』から『剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末』と改題いたしました。
2025年11月28書籍刊行。
なお、レンタル部分は修正した書籍と同様のものとなっておりますが、一部の描写が割愛されたため、後続の話とは繋がりが悪くなっております。ご了承ください。
酒と肴と剣と闇
江戸情緒を添えて
江戸は本所にある居酒屋『草間』。
美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。
自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。
多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。
その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。
店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。
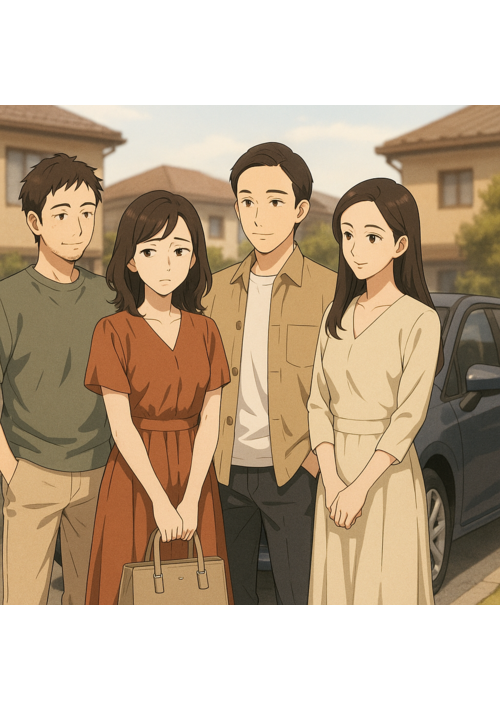


還暦の性 若い彼との恋愛模様
MisakiNonagase
恋愛
還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。
そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。
その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。
全7話

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳の主婦・加恋。冷え切った家庭で孤独に苛まれる彼女を救い出したのは、ネットの向こう側にいた二十歳(はたち)と偽っていた17歳の少年・晴人だった。
「未成年との不倫」という、社会から断罪されるべき背徳。それでも二人は、震える手で未来への約束を交わす。少年が大学生になり、社会人となり、守られる存在から「守る男」へと成長していく中で、加恋は自らの手で「妻」という仮面を脱ぎ捨てていく…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















