93 / 156
第3章 戦い開始
13
しおりを挟む
烈王の炎が全身を焼き焦がしたのか。彼はすっかり痛みを感じずにいた。きっと死んだのだ。黒焦げになった死体が大地に転がり、肥料にでもなるのだろう。さしずめ自分はあの世にいるのだと、流星は思った。
「こうなると思った」
聞いたことのある声だ。夕美か。
「あなたは何も理解していない」
なんだ、自分は死んでいないのか?
「烈王に通常の物理攻撃は効かないのに。馬鹿ね、あなたって人は」
「なぜ、ここへ……」
「そんなのどうだっていいわ。まずあなたは、王の力の使い方を学ばないとね」
「杖のことか?」
「ええそれよ。あなた杖の中の悪霊をどう使いこなすの?」
「いろいろコケにされていますよ。お前の信念はそんなものかとか、なんだのと」
「早速悪霊のいいなりなのね。それじゃ困るでしょう?」
「こいつは一体何者何です?」
「影」
「影とは?」
「影は影よ。物体は皆影を持つ。それを操る力が杖にはある。私の、これは闇を司る」
夕美は右手につけた黒い腕輪を差し出した。
「あなたはてっきり水の使い手かと」
「王の特性を知れば、水でもなんでも生かせるわ。水以外でも、大地に生い茂る森、高くそびえる山、深い海もなんでも」
「森や、山、海が一体闇とどういうつながりが?」
「大ありよ。闇はどこにでも潜むもの。日差しが届かない深い樹林に、深い海の底に闇は潜んでいる。闇は至る所にいる。人の心にも闇は根差すし、私はそれらを大いに利用している」
「私は? 自分の王の力を生かせていないと?」
「ええ全くね。影を一体も召喚しないし、何よりもそれをただの棒切れのように振り回しているだけだから」
「どうすればこいつを使えこなせると?」
「それはあなた次第よ。生憎私は影使いではないから。王の宝に巣くう悪霊に聞くしかない。ただ、悪霊の言うことを聞いていると肉体を乗っ取られ最後は魂ごと食いつくされることになる」
「なるほど……恐ろしい。命は粗末にしたくない」
「次期に王の命は尽きるから遅かれ早かれ魂を差し出す羽目になるけど、使いこなせれば、当分は生きられるわ」
「どれぐらい?」
「百年でも、千年でも……」
「あなたはどれほど生きながらえていますか?」
「さあ忘れたわ。あなたには関係の無いことでしょう?」
「一度ならず、二度も救われるとは」
「もう助けないわ。あと、ゆめゆめ聖都に戻らない事ね。西王が与えた軍は、全滅。あなたは戻っても軍法会議にかけられるわ」
「全滅……」
「己が何をしたか思い返しなさい。自分の部下を置いて、烈王に単身決闘を挑んだ愚かさを振り返ることね」
「全滅」
「あなた一人で南都は落とさないといけないのよ? もはや烈王軍が次期に聖都にやってくる。他国の支援をしている暇はない」
「孤立無援ですね。かえってやりやすいか」
「まあどうするかはあなた次第よ。じゃあね、幸運を祈っているわ。王様」
夕美はそう言って消え去った。相変わらず足が速い。あれも闇の力なのか。わからない。脚力と闇が何の接点があるのか?
『お困りのようだな? 青二才よ』
「まったく。人が不愉快な時に、現れる……」
『俺はお前が望んだ時にしか現れんよ』
「王の力、影の力というやつを教えてくれないか?」
『ほう、ようやく王の特性について質問が出たな』
「早くしてくれ。俺にはやることがある」
『まあそう急くな。仇討ちなどじっくり時間をかけて……』
「伍の国の民は、こうしている間に耐え難い苦しみの中にいる。悠長なことは言っていられない。早くしてくれ」
『ほお、敵討ちはあきらめたか! なるほど、慈善活動でもやるのか』
影は大きくはしゃいだ。
「優先順位だ。まずは民を悪の手から救い出し、民意を得る。その後正式に玉座につき、他国と連携し、烈王の首を取る。その算段で行く」
『少しは理性的になったようだな』
「そういうことだ、早くしてくれ。杖で俺は何ができる?」
『できることといえば、生きとし生けるものの影を操れることかな』
「具体的に?」
『なら逆に聞く。他人の影を操れるとしたらお前は何をしたい?』
「影を操れるならだと?」
『そうだ。王の力は、学校の教科書のように、指南してくれる物があるわけではない。まずは己の意思だ。お前が影を使ってどうしたいか言わなければ、俺は何もしてやれん。今のままでは、杖はただの棒切れだ』
影を操るだと?
流星は戸惑った。夢にも思ってもみなかった。
『お前の言う通りこれはまず優先順位だ。国民の救済、烈王の討伐という御大層なことより、まずはやるべきことがあるな』
「他人の影を切り取り、剣にする。実体のない影ならいくらでも加工可能だろう?」
「剣にしてどうする?」
「相手を切る」
影は流星の意見を聞き、笑い転げる。
『あーはは! お前ときたら斬ることしか頭にないのだな』
「そういう人生だ」
『ま、少し知恵を授けてやろう。確かに斬ることも可能だ。人も家も大方のものは切り刻めるな。だが火や、水、といったとらえどころのないものはどうする?』
「そうか」
「わかったか? 烈王は火の使い手と言われただろう? 影を刀に見立てたところで、切れるのか?」
流星は首を横に振る。ならどうする?
『さあ考えろ。お前の矮小な脳みそで答えを出してみるがいい』
「こうなると思った」
聞いたことのある声だ。夕美か。
「あなたは何も理解していない」
なんだ、自分は死んでいないのか?
「烈王に通常の物理攻撃は効かないのに。馬鹿ね、あなたって人は」
「なぜ、ここへ……」
「そんなのどうだっていいわ。まずあなたは、王の力の使い方を学ばないとね」
「杖のことか?」
「ええそれよ。あなた杖の中の悪霊をどう使いこなすの?」
「いろいろコケにされていますよ。お前の信念はそんなものかとか、なんだのと」
「早速悪霊のいいなりなのね。それじゃ困るでしょう?」
「こいつは一体何者何です?」
「影」
「影とは?」
「影は影よ。物体は皆影を持つ。それを操る力が杖にはある。私の、これは闇を司る」
夕美は右手につけた黒い腕輪を差し出した。
「あなたはてっきり水の使い手かと」
「王の特性を知れば、水でもなんでも生かせるわ。水以外でも、大地に生い茂る森、高くそびえる山、深い海もなんでも」
「森や、山、海が一体闇とどういうつながりが?」
「大ありよ。闇はどこにでも潜むもの。日差しが届かない深い樹林に、深い海の底に闇は潜んでいる。闇は至る所にいる。人の心にも闇は根差すし、私はそれらを大いに利用している」
「私は? 自分の王の力を生かせていないと?」
「ええ全くね。影を一体も召喚しないし、何よりもそれをただの棒切れのように振り回しているだけだから」
「どうすればこいつを使えこなせると?」
「それはあなた次第よ。生憎私は影使いではないから。王の宝に巣くう悪霊に聞くしかない。ただ、悪霊の言うことを聞いていると肉体を乗っ取られ最後は魂ごと食いつくされることになる」
「なるほど……恐ろしい。命は粗末にしたくない」
「次期に王の命は尽きるから遅かれ早かれ魂を差し出す羽目になるけど、使いこなせれば、当分は生きられるわ」
「どれぐらい?」
「百年でも、千年でも……」
「あなたはどれほど生きながらえていますか?」
「さあ忘れたわ。あなたには関係の無いことでしょう?」
「一度ならず、二度も救われるとは」
「もう助けないわ。あと、ゆめゆめ聖都に戻らない事ね。西王が与えた軍は、全滅。あなたは戻っても軍法会議にかけられるわ」
「全滅……」
「己が何をしたか思い返しなさい。自分の部下を置いて、烈王に単身決闘を挑んだ愚かさを振り返ることね」
「全滅」
「あなた一人で南都は落とさないといけないのよ? もはや烈王軍が次期に聖都にやってくる。他国の支援をしている暇はない」
「孤立無援ですね。かえってやりやすいか」
「まあどうするかはあなた次第よ。じゃあね、幸運を祈っているわ。王様」
夕美はそう言って消え去った。相変わらず足が速い。あれも闇の力なのか。わからない。脚力と闇が何の接点があるのか?
『お困りのようだな? 青二才よ』
「まったく。人が不愉快な時に、現れる……」
『俺はお前が望んだ時にしか現れんよ』
「王の力、影の力というやつを教えてくれないか?」
『ほう、ようやく王の特性について質問が出たな』
「早くしてくれ。俺にはやることがある」
『まあそう急くな。仇討ちなどじっくり時間をかけて……』
「伍の国の民は、こうしている間に耐え難い苦しみの中にいる。悠長なことは言っていられない。早くしてくれ」
『ほお、敵討ちはあきらめたか! なるほど、慈善活動でもやるのか』
影は大きくはしゃいだ。
「優先順位だ。まずは民を悪の手から救い出し、民意を得る。その後正式に玉座につき、他国と連携し、烈王の首を取る。その算段で行く」
『少しは理性的になったようだな』
「そういうことだ、早くしてくれ。杖で俺は何ができる?」
『できることといえば、生きとし生けるものの影を操れることかな』
「具体的に?」
『なら逆に聞く。他人の影を操れるとしたらお前は何をしたい?』
「影を操れるならだと?」
『そうだ。王の力は、学校の教科書のように、指南してくれる物があるわけではない。まずは己の意思だ。お前が影を使ってどうしたいか言わなければ、俺は何もしてやれん。今のままでは、杖はただの棒切れだ』
影を操るだと?
流星は戸惑った。夢にも思ってもみなかった。
『お前の言う通りこれはまず優先順位だ。国民の救済、烈王の討伐という御大層なことより、まずはやるべきことがあるな』
「他人の影を切り取り、剣にする。実体のない影ならいくらでも加工可能だろう?」
「剣にしてどうする?」
「相手を切る」
影は流星の意見を聞き、笑い転げる。
『あーはは! お前ときたら斬ることしか頭にないのだな』
「そういう人生だ」
『ま、少し知恵を授けてやろう。確かに斬ることも可能だ。人も家も大方のものは切り刻めるな。だが火や、水、といったとらえどころのないものはどうする?』
「そうか」
「わかったか? 烈王は火の使い手と言われただろう? 影を刀に見立てたところで、切れるのか?」
流星は首を横に振る。ならどうする?
『さあ考えろ。お前の矮小な脳みそで答えを出してみるがいい』
0
お気に入りに追加
11
あなたにおすすめの小説
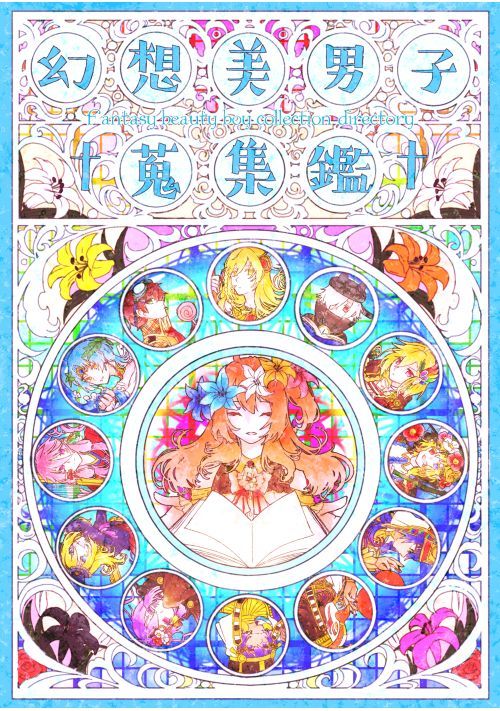
幻想美男子蒐集鑑~夢幻月華の書~
紗吽猫
ファンタジー
ーー さぁ、世界を繋ぐ旅を綴ろう ーー
自称美男子愛好家の主人公オルメカと共に旅する好青年のソロモン。旅の目的はオルメカコレクションー夢幻月下の書に美男子達との召喚契約をすること。美男子の噂を聞きつけてはどんな街でも、時には異世界だって旅して回っている。でもどうやらこの旅、ただの逆ハーレムな旅とはいかないようでー…?
美男子を見付けることのみに特化した心眼を持つ自称美男子愛好家は出逢う美男子達を取り巻く事件を解決し、無事に魔導書を完成させることは出来るのか…!?
時に出逢い、時に闘い、時に事件を解決し…
旅の中で出逢う様々な美男子と取り巻く仲間達との複数世界を旅する物語。
※この作品はエブリスタでも連載中です。

『ラノベ作家のおっさん…異世界に転生する』
来夢
ファンタジー
『あらすじ』
心臓病を患っている、主人公である鈴也(レイヤ)は、幼少の時から見た夢を脚色しながら物語にして、ライトノベルの作品として投稿しようと書き始めた。
そんなある日…鈴也は小説を書き始めたのが切っ掛けなのか、10年振りに夢の続きを見る。
すると、今まで見た夢の中の男の子と女の子は、青年の姿に成長していて、自分の書いている物語の主人公でもあるヴェルは、理由は分からないが呪いの攻撃を受けて横たわっていた。
ジュリエッタというヒロインの聖女は「ホーリーライト!デスペル!!」と、仲間の静止を聞かず、涙を流しながら呪いを解く魔法を掛け続けるが、ついには力尽きて死んでしまった。
「へっ?そんな馬鹿な!主人公が死んだら物語の続きはどうするんだ!」
そんな後味の悪い夢から覚め、風呂に入ると心臓発作で鈴也は死んでしまう。
その後、直ぐに世界が暗転。神様に会うようなセレモニーも無く、チートスキルを授かる事もなく、ただ日本にいた記憶を残したまま赤ん坊になって、自分の書いた小説の中の世界へと転生をする。
”自分の書いた小説に抗える事が出来るのか?いや、抗わないと周りの人達が不幸になる。書いた以上責任もあるし、物語が進めば転生をしてしまった自分も青年になると死んでしまう
そう思い、自分の書いた物語に抗う事を決意する。

けだものだもの~虎になった男の異世界酔夢譚~
ちょろぎ
ファンタジー
神の悪戯か悪魔の慈悲か――
アラフォー×1社畜のサラリーマン、何故か虎男として異世界に転移?する。
何の説明も助けもないまま、手探りで人里へ向かえば、言葉は通じず石を投げられ騎兵にまで追われる有様。
試行錯誤と幾ばくかの幸運の末になんとか人里に迎えられた虎男が、無駄に高い身体能力と、現代日本の無駄知識で、他人を巻き込んだり巻き込まれたりしながら、地盤を作って異世界で生きていく、日常描写多めのそんな物語。
第13章が終了しました。
申し訳ありませんが、第14話を区切りに長期(予定数か月)の休載に入ります。
再開の暁にはまたよろしくお願いいたします。
この作品は小説家になろうさんでも掲載しています。
同名のコミック、HP、曲がありますが、それらとは一切関係はありません。

辺境領主は大貴族に成り上がる! チート知識でのびのび領地経営します
潮ノ海月@書籍発売中
ファンタジー
旧題:転生貴族の領地経営~チート知識を活用して、辺境領主は成り上がる!
トールデント帝国と国境を接していたフレンハイム子爵領の領主バルトハイドは、突如、侵攻を開始した帝国軍から領地を守るためにルッセン砦で迎撃に向かうが、守り切れず戦死してしまう。
領主バルトハイドが戦争で死亡した事で、唯一の後継者であったアクスが跡目を継ぐことになってしまう。
アクスの前世は日本人であり、争いごとが極端に苦手であったが、領民を守るために立ち上がることを決意する。
だが、兵士の証言からしてラッセル砦を陥落させた帝国軍の数は10倍以上であることが明らかになってしまう
完全に手詰まりの中で、アクスは日本人として暮らしてきた知識を活用し、さらには領都から避難してきた獣人や亜人を仲間に引き入れ秘策を練る。
果たしてアクスは帝国軍に勝利できるのか!?
これは転生貴族アクスが領地経営に奮闘し、大貴族へ成りあがる物語。

異世界着ぐるみ転生
こまちゃも
ファンタジー
旧題:着ぐるみ転生
どこにでもいる、普通のOLだった。
会社と部屋を往復する毎日。趣味と言えば、十年以上続けているRPGオンラインゲーム。
ある日気が付くと、森の中だった。
誘拐?ちょっと待て、何この全身モフモフ!
自分の姿が、ゲームで使っていたアバター・・・二足歩行の巨大猫になっていた。
幸い、ゲームで培ったスキルや能力はそのまま。使っていたアイテムバッグも中身入り!
冒険者?そんな怖い事はしません!
目指せ、自給自足!
*小説家になろう様でも掲載中です

42歳メジャーリーガー、異世界に転生。チートは無いけど、魔法と元日本最高級の豪速球で無双したいと思います。
町島航太
ファンタジー
かつて日本最強投手と持て囃され、MLBでも大活躍した佐久間隼人。
しかし、老化による衰えと3度の靭帯損傷により、引退を余儀なくされてしまう。
失意の中、歩いていると球団の熱狂的ファンからポストシーズンに行けなかった理由と決めつけられ、刺し殺されてしまう。
だが、目を再び開くと、魔法が存在する世界『異世界』に転生していた。

異世界に来ちゃったよ!?
いがむり
ファンタジー
235番……それが彼女の名前。記憶喪失の17歳で沢山の子どもたちと共にファクトリーと呼ばれるところで楽しく暮らしていた。
しかし、現在森の中。
「とにきゃく、こころこぉ?」
から始まる異世界ストーリー 。
主人公は可愛いです!
もふもふだってあります!!
語彙力は………………無いかもしれない…。
とにかく、異世界ファンタジー開幕です!
※不定期投稿です…本当に。
※誤字・脱字があればお知らせ下さい
(※印は鬱表現ありです)

異世界産業革命。
みゆみゆ
ファンタジー
あらすじ
非モテ軍オタが転生して理想の帝国を樹ち立てる話です。
美末(みすえ)の『手の平』からは色々と出て来ますが、主人公はその『能力』をなるべく使わず、自然な形で産業革命を起こし、世界統一を目指さんとします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















