11 / 17
ストーリー
9
しおりを挟む
気づけば、夕暮れ時だ。1日の時間が経つのが速すぎる。私は40手前位になり、一日があっという間に終わってしまう事実に驚きを隠せない。
しかし、本来なら事件など起きない方がよい。ただ時間が無益に過ぎていくことの方がどれだけまともだろうか。
「じゃあ探偵さん。また明日もよろしく」
迎えに来たタクシーに私たちは乗り込み、魅惑の妖精の別れの言葉を受ける。
翌日は土曜日だった。私たちはのんびりとした朝を迎え、遅めの朝食をとると散歩がてら、彼女の屋敷に歩いて向かった。いつもと同じような平凡な日が始まろうとしていた。
一度通った道を、新出は忘れたことがない。基本彼の脳細胞は、細部に至るまでほとんど記憶している。海辺の道をしばらくまっすぐ、時折やってくる車に気を付けながら、私たちは歩いていき、途中から山道に入った。やがてアーチが見えてきて、そこから先は私道だ。私たちが何のためらう間もなく屋敷への私道に入ろうとした時だ。
「おい、あんた方。そっちは私道だ」
背後から恐る恐る人を警戒したうえで発した声がする。
「はい、僕らはこちらに用があるんです」
「え? 美果ちゃんに? ね、失礼ですがどちら様?」
「ああ私は、私立探偵の新出傑と申します。彼は助手の小林卓。実は一昨日美果さんと知り合いになり、彼女が怪しい人物に襲われたものだから調査を依頼されているんです」
「調査?」
彼の頭は完全に禿げかかり、顔は皺ができ、目の周りには黒いくまできていた。この初老の老人は、近くに住むものかもしれない。
「ええ、失礼ですが、こちらの先にある屋敷の近所に住む方ですか?」
「ああ。まあ。探偵さんか。道理で」
ああ、ああと息を切らしながら言う。彼は新出傑の名前を知っていたらしい。
「探偵さん。よろしければ私の内に来ませんか? 美果ちゃんはさっき出かけたからね」
「ほう、どちらか分かります?」
「さあ。昔からあっちへテクテク。こっちへテクテク。実に気ままな子だからな。来ないのかね?」
「伺います」
こっちじゃと老人は私たちを手引きした。
老人の家は、さほど遠くないところに合った。美果の屋敷と比べれば、小さな素朴な小屋のような家に彼らは夫婦として住んでいた。名前を松島隆、愛子といった。
「おーい。お客様だ!」
はーいと快活な声がして、これまた六十過ぎの丸みの帯びたふっくらした奥様が登場した。当初、怪しげな視線を送ってきたが、高名な探偵であるという説明を受けるとすぐに
気を許したのか満面の笑みで我々は歓待を受けた。
小さくて素朴な檜のテーブルの周りにあった椅子に腰かけるよう松島老は勧める。時を得ずして、有馬焼の淹れられた温かいお茶を振舞われ、水羊羹を差し出された。
「まあ! 存じ上げておりますわ。テレビや雑誌で新出先生のことは、本当によく見ておりますの。もちろん助手の小林さんのご活躍もかねがね」
甲高い声である。私たちは、奥様が実にミステリー好きだという事実を理解した。やれ、この地域には紙で書かれているような事件が本当に起こると信じているようだ。私がいくらか脚色した新出のこれまで事件に、すっかりはまってしまったらしい。
「はは、嬉しいですね。奥様は実に私共の他愛もない事件に精通されてらっしゃる」
「ええ。特にあの何でしたかしら? 政財界を揺るがした財務大臣の贈賄の摘発。権力者へ悠然と立ち向かう姿には感銘を受けました。えーとあれは確か。」
「財政の伏魔殿でしょうか?」
私は彼女が思い出せないタイトルを言った。
そうだ、そうだとまた甲高い声が素朴な部屋に鳴り響いた。
「奥様は実に私共があったご婦人の中では最も機知に富んでらっしゃる。ぜひ、ここはひとつご協力いただきたいのです。あなたは美果さんや、亡くなった彼女のおじい様とはずいぶんと親しかったのでしょうか?」
「もちろんですわ」
「やはり、ミステリーなどで大いにお話が盛り上がっていそうだ」
「それだけはございませんわ。私共は、先代、先々代からずいぶんとよしなにさせて頂いておりますの」
「美果さんが、幼い時のこともご存じですね?」
「ええ、ええ。本当に可愛らしいお嬢さんで。ゆくゆくは、妹さんと二人で大女優になるはずなのに。なぜかしら? 美果さんはやめてしまわれて」
「ほう、なぜでしょうね?」
「わかりませんわ」
「彼女はここ最近危ない目に合っているというのはご存知?」
「ええ。もう、こないだ美果ちゃんに遭いましたら。右手を押さえていて。大丈夫だから心配しないでと」
「いつのお話です?」
「ひと月前です。車のブレーキが利かなくなったとか、それで、それで。」
「実にひどい話ですね?」
涙ぐむ奥さんを、松島老がそっと寄り添い、支えていた。よき夫婦像がそこにあった。
「業者に見てもらったら、中の機材が壊れているとか」
奥さんは、実に美果を不憫に思っているようで彼女の人柄の良さがうかがえた。
「後がないものではなく、なぜ未来ある若者の命が狙われるのでしょう? 全く、許せません」
「本当だ」
しばらく黙っていた松島老がボソリと話に入ってきた。
「では、あなた方は美果さんの周りに集まるご友人たちや親せきについても詳しいでしょうね?」
「あのよくこちらに来られる家庭教師の方や、株をやっている方のことでしょうか?」
「ええ、ええ」
「うーむ。美果ちゃんの周りにはどうもその手の、言い方がよくないが、金目の連中のような気がして」
「確かに、どこか。僕は株をやっている彼女がどうにも」
私は相槌を挟んだ。
「そうだ、あの娘は卑しい出だろう。でも美果ちゃんは人柄がいいのか。分け隔てなく、人を差別せず付き合って。本当におじいさん譲りで」
「松島さん。あの、ご存知でしょう? 美果さんの家政婦の娘を。メイド服をよく来ている」
「あ、ああ」
「その子はどうです?」
「もちろん知っている。気立てのいいお嬢さんで、家は山菜を栽培しているが、よく分けてあげるときに、丁寧な応対をしてくれて嬉しいよ」
「そうですか。実に気立てのいい娘さんですね」
「ところで。ああ、ずいぶんと旅行に行かれているみたいですね」
「ああ。その写真は、ああどこだったかな。なあ、母さん。これはどこへ行ったやつだったかな?」
ええ、と奥に引っ込んでいた奥さんの甲高い声が響き、こっちにやってきた。何度か話していくうちに、色々思い出したようでイタリアのヴェネツィアだと判明した。
「いいですね。イタリアは行ったことがない」
「ほう。それではぜひ行ってみるといい。ローマ、フィレンツェ、ナポリ。わしらは、西洋の建築がすきでね」
新出は、古びた机に置かれたご夫婦の仲睦まじい写真を眺めて、それらしい感想を述べていた。写真には彼が話を振ったおかげで、私は彼らの懐古趣味について長々と聞かされる羽目になった。
老人の皺だらけの顔に、少年のような無邪気な笑顔が広がった。
「でしたら、伊豆は隠居生活に最適な場所ですね。こんな山地で田畑を耕して、時に海風に吹かれて」
「そうだろう。探偵さんも、のんきな生活をしたいのかな?」
「ええ。私もこっちに来たのは、半ば静養だけではなく、隠居をぼちぼち考えてます」
「ほう。まだ若いのに」
「ええ」
ご老人の長話に付き合わされた私たちは、思いもよらぬ丁重な扱いを受けた。とりあえず出されたものに預からないのは、失礼だったので私たちは細やかな水羊羹を口にし、二言三言適当にしゃべって失礼した。
「ずいぶんと親切な御夫婦だったじゃないか?」
私は正直に物申した。でもあまのじゃく気味な新出はそうは感じていなかった。
「なあに、それにしても仲がいい。いや、実に絵に描いたような仲のいい夫婦を演じているだけかもね」
全く、実にあれだけの歓待を受けてけしからんやつだと思うが、疑うことをやめてしまったら、探偵は務まらないし、それが性というものだろう。
「今の段階では、どんな人物も秋月美果を狙う下手人にしか思えないよ」
「じゃ、昨日犯人の目星が付いたというのは?」
「真犯人を油断させるため。お目にかかっていないストーカーがやることにしては、ずいぶんと美果の家に詳しすぎる。内部に手助けした者の存在を考えたら、ワザと事件は解決に向かっていると仕向けた方がいい。やつの方がから動き出す」
なるほど、のろけにばかりに染まっていなくてよかった。
「さ、余興はおしまいだ。依頼人の元へ行こう」
しかし、本来なら事件など起きない方がよい。ただ時間が無益に過ぎていくことの方がどれだけまともだろうか。
「じゃあ探偵さん。また明日もよろしく」
迎えに来たタクシーに私たちは乗り込み、魅惑の妖精の別れの言葉を受ける。
翌日は土曜日だった。私たちはのんびりとした朝を迎え、遅めの朝食をとると散歩がてら、彼女の屋敷に歩いて向かった。いつもと同じような平凡な日が始まろうとしていた。
一度通った道を、新出は忘れたことがない。基本彼の脳細胞は、細部に至るまでほとんど記憶している。海辺の道をしばらくまっすぐ、時折やってくる車に気を付けながら、私たちは歩いていき、途中から山道に入った。やがてアーチが見えてきて、そこから先は私道だ。私たちが何のためらう間もなく屋敷への私道に入ろうとした時だ。
「おい、あんた方。そっちは私道だ」
背後から恐る恐る人を警戒したうえで発した声がする。
「はい、僕らはこちらに用があるんです」
「え? 美果ちゃんに? ね、失礼ですがどちら様?」
「ああ私は、私立探偵の新出傑と申します。彼は助手の小林卓。実は一昨日美果さんと知り合いになり、彼女が怪しい人物に襲われたものだから調査を依頼されているんです」
「調査?」
彼の頭は完全に禿げかかり、顔は皺ができ、目の周りには黒いくまできていた。この初老の老人は、近くに住むものかもしれない。
「ええ、失礼ですが、こちらの先にある屋敷の近所に住む方ですか?」
「ああ。まあ。探偵さんか。道理で」
ああ、ああと息を切らしながら言う。彼は新出傑の名前を知っていたらしい。
「探偵さん。よろしければ私の内に来ませんか? 美果ちゃんはさっき出かけたからね」
「ほう、どちらか分かります?」
「さあ。昔からあっちへテクテク。こっちへテクテク。実に気ままな子だからな。来ないのかね?」
「伺います」
こっちじゃと老人は私たちを手引きした。
老人の家は、さほど遠くないところに合った。美果の屋敷と比べれば、小さな素朴な小屋のような家に彼らは夫婦として住んでいた。名前を松島隆、愛子といった。
「おーい。お客様だ!」
はーいと快活な声がして、これまた六十過ぎの丸みの帯びたふっくらした奥様が登場した。当初、怪しげな視線を送ってきたが、高名な探偵であるという説明を受けるとすぐに
気を許したのか満面の笑みで我々は歓待を受けた。
小さくて素朴な檜のテーブルの周りにあった椅子に腰かけるよう松島老は勧める。時を得ずして、有馬焼の淹れられた温かいお茶を振舞われ、水羊羹を差し出された。
「まあ! 存じ上げておりますわ。テレビや雑誌で新出先生のことは、本当によく見ておりますの。もちろん助手の小林さんのご活躍もかねがね」
甲高い声である。私たちは、奥様が実にミステリー好きだという事実を理解した。やれ、この地域には紙で書かれているような事件が本当に起こると信じているようだ。私がいくらか脚色した新出のこれまで事件に、すっかりはまってしまったらしい。
「はは、嬉しいですね。奥様は実に私共の他愛もない事件に精通されてらっしゃる」
「ええ。特にあの何でしたかしら? 政財界を揺るがした財務大臣の贈賄の摘発。権力者へ悠然と立ち向かう姿には感銘を受けました。えーとあれは確か。」
「財政の伏魔殿でしょうか?」
私は彼女が思い出せないタイトルを言った。
そうだ、そうだとまた甲高い声が素朴な部屋に鳴り響いた。
「奥様は実に私共があったご婦人の中では最も機知に富んでらっしゃる。ぜひ、ここはひとつご協力いただきたいのです。あなたは美果さんや、亡くなった彼女のおじい様とはずいぶんと親しかったのでしょうか?」
「もちろんですわ」
「やはり、ミステリーなどで大いにお話が盛り上がっていそうだ」
「それだけはございませんわ。私共は、先代、先々代からずいぶんとよしなにさせて頂いておりますの」
「美果さんが、幼い時のこともご存じですね?」
「ええ、ええ。本当に可愛らしいお嬢さんで。ゆくゆくは、妹さんと二人で大女優になるはずなのに。なぜかしら? 美果さんはやめてしまわれて」
「ほう、なぜでしょうね?」
「わかりませんわ」
「彼女はここ最近危ない目に合っているというのはご存知?」
「ええ。もう、こないだ美果ちゃんに遭いましたら。右手を押さえていて。大丈夫だから心配しないでと」
「いつのお話です?」
「ひと月前です。車のブレーキが利かなくなったとか、それで、それで。」
「実にひどい話ですね?」
涙ぐむ奥さんを、松島老がそっと寄り添い、支えていた。よき夫婦像がそこにあった。
「業者に見てもらったら、中の機材が壊れているとか」
奥さんは、実に美果を不憫に思っているようで彼女の人柄の良さがうかがえた。
「後がないものではなく、なぜ未来ある若者の命が狙われるのでしょう? 全く、許せません」
「本当だ」
しばらく黙っていた松島老がボソリと話に入ってきた。
「では、あなた方は美果さんの周りに集まるご友人たちや親せきについても詳しいでしょうね?」
「あのよくこちらに来られる家庭教師の方や、株をやっている方のことでしょうか?」
「ええ、ええ」
「うーむ。美果ちゃんの周りにはどうもその手の、言い方がよくないが、金目の連中のような気がして」
「確かに、どこか。僕は株をやっている彼女がどうにも」
私は相槌を挟んだ。
「そうだ、あの娘は卑しい出だろう。でも美果ちゃんは人柄がいいのか。分け隔てなく、人を差別せず付き合って。本当におじいさん譲りで」
「松島さん。あの、ご存知でしょう? 美果さんの家政婦の娘を。メイド服をよく来ている」
「あ、ああ」
「その子はどうです?」
「もちろん知っている。気立てのいいお嬢さんで、家は山菜を栽培しているが、よく分けてあげるときに、丁寧な応対をしてくれて嬉しいよ」
「そうですか。実に気立てのいい娘さんですね」
「ところで。ああ、ずいぶんと旅行に行かれているみたいですね」
「ああ。その写真は、ああどこだったかな。なあ、母さん。これはどこへ行ったやつだったかな?」
ええ、と奥に引っ込んでいた奥さんの甲高い声が響き、こっちにやってきた。何度か話していくうちに、色々思い出したようでイタリアのヴェネツィアだと判明した。
「いいですね。イタリアは行ったことがない」
「ほう。それではぜひ行ってみるといい。ローマ、フィレンツェ、ナポリ。わしらは、西洋の建築がすきでね」
新出は、古びた机に置かれたご夫婦の仲睦まじい写真を眺めて、それらしい感想を述べていた。写真には彼が話を振ったおかげで、私は彼らの懐古趣味について長々と聞かされる羽目になった。
老人の皺だらけの顔に、少年のような無邪気な笑顔が広がった。
「でしたら、伊豆は隠居生活に最適な場所ですね。こんな山地で田畑を耕して、時に海風に吹かれて」
「そうだろう。探偵さんも、のんきな生活をしたいのかな?」
「ええ。私もこっちに来たのは、半ば静養だけではなく、隠居をぼちぼち考えてます」
「ほう。まだ若いのに」
「ええ」
ご老人の長話に付き合わされた私たちは、思いもよらぬ丁重な扱いを受けた。とりあえず出されたものに預からないのは、失礼だったので私たちは細やかな水羊羹を口にし、二言三言適当にしゃべって失礼した。
「ずいぶんと親切な御夫婦だったじゃないか?」
私は正直に物申した。でもあまのじゃく気味な新出はそうは感じていなかった。
「なあに、それにしても仲がいい。いや、実に絵に描いたような仲のいい夫婦を演じているだけかもね」
全く、実にあれだけの歓待を受けてけしからんやつだと思うが、疑うことをやめてしまったら、探偵は務まらないし、それが性というものだろう。
「今の段階では、どんな人物も秋月美果を狙う下手人にしか思えないよ」
「じゃ、昨日犯人の目星が付いたというのは?」
「真犯人を油断させるため。お目にかかっていないストーカーがやることにしては、ずいぶんと美果の家に詳しすぎる。内部に手助けした者の存在を考えたら、ワザと事件は解決に向かっていると仕向けた方がいい。やつの方がから動き出す」
なるほど、のろけにばかりに染まっていなくてよかった。
「さ、余興はおしまいだ。依頼人の元へ行こう」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
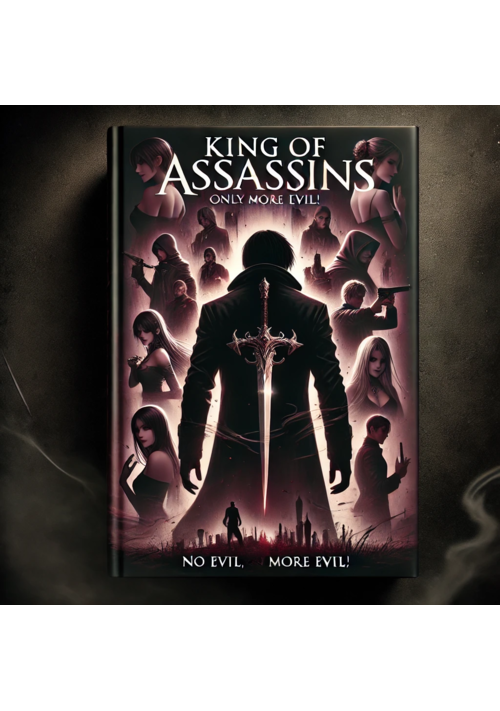

深木志麻
戸笠耕一
ミステリー
高校生作家の深木志麻が一年後の二〇二三年六月六日に死ぬと宣言して本当に志麻は死んでしまう。その死因はわからなかった。一年後の八月七日、文芸部員の松崎陽花、樫原実歩、藤垣美星、白樺真木、銀杏小夏は、志麻の遺言書に沿って彼女の死因をテーマにした小説の朗読を定例会で行う。最も優れた小説を書いた者に志麻の未発表原稿と文芸部会長の地位を得ることになる。天才深木志麻の後を継ぐのは誰かーー?

友よ、お前は何故死んだのか?
河内三比呂
ミステリー
「僕は、近いうちに死ぬかもしれない」
幼い頃からの悪友であり親友である久川洋壱(くがわよういち)から突如告げられた不穏な言葉に、私立探偵を営む進藤識(しんどうしき)は困惑し嫌な予感を覚えつつもつい流してしまう。
だが……しばらく経った頃、仕事終わりの識のもとへ連絡が入る。
それは洋壱の死の報せであった。
朝倉康平(あさくらこうへい)刑事から事情を訊かれた識はそこで洋壱の死が不可解である事、そして自分宛の手紙が発見された事を伝えられる。
悲しみの最中、朝倉から提案をされる。
──それは、捜査協力の要請。
ただの民間人である自分に何ができるのか?悩みながらも承諾した識は、朝倉とともに洋壱の死の真相を探る事になる。
──果たして、洋壱の死の真相とは一体……?

幻影のアリア
葉羽
ミステリー
天才高校生探偵の神藤葉羽は、幼馴染の望月彩由美と共に、とある古時計のある屋敷を訪れる。その屋敷では、不可解な事件が頻発しており、葉羽は事件の真相を解き明かすべく、推理を開始する。しかし、屋敷には奇妙な力が渦巻いており、葉羽は次第に現実と幻想の境目が曖昧になっていく。果たして、葉羽は事件の謎を解き明かし、屋敷から無事に脱出できるのか?

【毎日20時更新】アンメリー・オデッセイ
ユーレカ書房
ミステリー
からくり職人のドルトン氏が、何者かに殺害された。ドルトン氏の弟子のエドワードは、親方が生前大切にしていた本棚からとある本を見つける。表紙を宝石で飾り立てて中は手書きという、なにやらいわくありげなその本には、著名な作家アンソニー・ティリパットがドルトン氏とエドワードの父に宛てた中書きが記されていた。
【時と歯車の誠実な友、ウィリアム・ドルトンとアルフレッド・コーディに。 A・T】
なぜこんな本が店に置いてあったのか? 不思議に思うエドワードだったが、彼はすでにおかしな本とふたつの時計台を巡る危険な陰謀と冒険に巻き込まれていた……。
【登場人物】
エドワード・コーディ・・・・からくり職人見習い。十五歳。両親はすでに亡く、親方のドルトン氏とともに暮らしていた。ドルトン氏の死と不思議な本との関わりを探るうちに、とある陰謀の渦中に巻き込まれて町を出ることに。
ドルトン氏・・・・・・・・・エドワードの親方。優れた職人だったが、職人組合の会合に出かけた帰りに何者かによって射殺されてしまう。
マードック船長・・・・・・・商船〈アンメリー号〉の船長。町から逃げ出したエドワードを船にかくまい、船員として雇う。
アーシア・リンドローブ・・・マードック船長の親戚の少女。古書店を開くという夢を持っており、謎の本を持て余していたエドワードを助ける。
アンソニー・ティリパット・・著名な作家。エドワードが見つけた『セオとブラン・ダムのおはなし』の作者。実は、地方領主を務めてきたレイクフィールド家の元当主。故人。
クレイハー氏・・・・・・・・ティリパット氏の甥。とある目的のため、『セオとブラン・ダムのおはなし』を探している。

嘘つきカウンセラーの饒舌推理
真木ハヌイ
ミステリー
身近な心の問題をテーマにした連作短編。六章構成。狡猾で奇妙なカウンセラーの男が、カウンセリングを通じて相談者たちの心の悩みの正体を解き明かしていく。ただ、それで必ずしも相談者が満足する結果になるとは限らないようで……?(カクヨムにも掲載しています)

時雨荘
葉羽
ミステリー
時雨荘という静かな山間の別荘で、著名な作家・鳴海陽介が刺殺される事件が発生する。高校生の天才探偵、葉羽は幼馴染の彩由美と共に事件の謎を解明するために動き出す。警察の捜査官である白石涼と協力し、葉羽は容疑者として、鳴海の部下桐生蓮、元恋人水無月花音、ビジネスパートナー九条蒼士の三人に注目する。
調査を進める中で、葉羽はそれぞれの容疑者が抱える嫉妬や未練、過去の関係が事件にどのように影響しているのかを探る。特に、鳴海が残した暗号が事件の鍵になる可能性があることに気づいた葉羽は、容疑者たちの言動や行動を鋭く観察し、彼らの心の奥に隠された感情を読み解く。
やがて、葉羽は九条が鳴海を守るつもりで殺害したことを突き止める。嫉妬心と恐怖が交錯し、事件を引き起こしたのだった。九条は告白し、鳴海の死の背後にある複雑な人間関係と感情の絡まりを明らかにする。
事件が解決した後、葉羽はそれぞれの登場人物が抱える痛みや後悔を受け止めながら、自らの探偵としての成長を誓う。鳴海の思いを胸に、彼は新たな旅立ちを迎えるのだった。

明日の夢、泡沫の未来
七三 一二十
ミステリー
高校生の多岐川一馬は、時折少し未来の「予知夢」をみることがある特異体質。ある夜、彼は予知夢の中で同級生で密かに思いを寄せている細川珠希が、何者かに後ろからナイフで襲われる光景を目撃してしまう!
何としても珠希を助けたい一馬は、友人で彼の予知夢のことも知っている切れ者の同級生・端波秀臣に相談を持ちかける。ところが端波の態度は淡白で、何故か甚だ非協力的なものだった。業を煮やした一馬は端波と袂を分かち、1人で珠希を守ることを決意するのだが……!?
※本作は小説家になろう様、ノベルアップ+様にも投稿しております(ノベプラ様でのみタイトルが『明日の夢、不可視の未来』となってます)。
※本作はノベプラのイヤミス短編コンテストに応募した作品を改題したものです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















