132 / 183
フレンチでリッチな夜でした
その36
しおりを挟む
*
午後八時に近付く頃には辺りも随分と暗くなっていた。
空は斜陽の光と夜の翳りとが半分ずつを占め、次第次第に宵がその領域を広げて行く。夏も終わりに近付いた今、日の沈む時刻も少しずつ早まって来ていたのだった。
諸々の農作業も終わりを迎え、人気の無くなった田畑に夜の翳りが音も無く降り積もって行く。村の中心を伸びる道路には何台かの警察車両が今も停められていたが、それもまた徐々に他所へと走り出して行った。
街灯の灯り始めた村を、リウドルフは一人散策していた。
道端から水の流れる音が軽やかに伝わって来る。未だ諦め悪く鳴き続ける蝉を別とすれば、昼の様々な喧騒が裾を収めつつある黄昏時の農村を瘦身の孤影は黙して歩き続けた。
いつもと何ら変わらぬのだろう夕刻の田園風景が辺りには広がっていたのであった。
ややあって、如何にも頼り無い痩せこけた背中に弾んだ声が投げ掛けられる。
「先生! 先生!」
リウドルフが肩越しに首を巡らせてみれば、村の中央に建つコミュニティセンターの方から女が一人駆けて来る所であった。薄暗い中でも、やや細身の体型と朗らかなその声から何者であるかはすぐに察せられる。
帰り支度を既に整えた後であろうか。
ボディバッグを背に回し、右の肩からは大きな水筒を下げたゾエ・サマンが小走りになって道端のリウドルフへと駆け寄った。
「何だ、先生、表の方にいたんですか」
息を整えつつほっとしたような声を上げたゾエを見て、リウドルフも相好を崩した。
「ああ、丁度君を探していた所でね」
「そうだったんですか。じゃ、丁度良かったですね」
雀卵斑の浮かんだ頬を上気させて、ゾエもまた微笑んだ。
そうして一組の人影は夕時の村を揃って歩き出した。
昼の活動の名残であろうか。辺りには時折、清涼感を伴う薬剤の匂いが何処からともなく漂って来るのだった。
西日の染める空が赤味を深めつつも少しずつ領域を縮めて行く。
やがて村の外を囲う畑が細道の向こうに見えて来た辺りで、ゾエは傍らを歩く先達へ気遣う眼差しを遣した。
「まあ、そう落ち込まないで下さい、先生。昼間の作戦は目ぼしい成果を上げられませんでしたけど、捜査の対象は大分絞られて来た訳でしょう? また新しい手を考えればいいじゃないですか」
「いや、そう簡単に言ってくれるがねぇ……」
リウドルフは半ばお道化るようにして苦笑交じりに呟いた。
「実際の所、あれだけ大掛かりな真似をしておいて収穫が全然無いのでは頂けない。警察に無駄に手間と金を注ぎ込ませただけに終わってしまったし、これで周囲から益々孤立してしまうか……」
「そんな気弱な事を仰らないで下さい」
細い肩を落として愚痴を零した相手をゾエは傍らから励ました。それと一緒に、彼女は肩に掛けた水筒を抱え直す。
「人が少なくなった方が却ってやり易くなる事だってあるでしょうから」
「そうかも知れんが、格好を付けた手前、結果がこれではなぁ……」
重みのまるで無い嘆息を涼しさを増した夜風が吹き流して行った。
程無く、両者は刈り取りの終わったラベンダー畑の前で足を止めた。
誰の姿も最早認められない夕時の畑は、ただ夜風が奔放に遊び回るばかりである。微かに漂うラベンダーの香りが朱色の空の下に佇む二人の間に寄せた。
リウドルフは地平へ吸い込まれようとする西日を眺めながら小さな肩を竦めた。
「……遺憾ながら手詰まりかな。神出鬼没の獣程、向こうに回して厄介なものは無い」
「ええっ!? それじゃ、これからどうなさるんです?」
出し抜けに、それこそ煙草の吸い止しでも投げて遣すかのようにして放たれた宣告に、ゾエは吃驚も露わに詰問した。
「どうもこうも後は警察に任せるしかない。このままじゃ良くて千日手に陥るだけだし、こちらも日程にそこまでの余裕は無い。もうすぐ新学期が始まるんだ」
困り顔すら浮かべたゾエへ答えてから、リウドルフは片手を開いて見せた。
「お手上げ、と言う奴だな」
「そんなぁ……」
実に無念そうに嘆息を漏らしたゾエへリウドルフは鼻息をついて見せた。
「誠に遺憾ながら、素人に出来る捜査ごっこはここまでだ。残念だが、そうした締め括りだって往々にして起こるさ。世の中、何もかも思い通りに手繰れる程甘くもない」
しんみりとしたリウドルフの言葉にゾエは口先を尖らせた。
「残念ですね……」
「まあな……」
何やら湿っぽい遣り取りを交わす両者の間を行き摺りの夜風が冷やかした。
畑の向こうで蛙が鳴き始めた。
ややあってゾエは徐に一礼する。
「では、私はこれで」
「ああ。そちらもこの数日間、無駄にロデーズから通わせてしまったな。宿泊費と交通費込みで『IOSO』から特別手当を出すよう要請しておくよ」
リウドルフが詫びの言葉を入れるとゾエは笑った。
「有難う御座います。お休みなさい、先生」
「ああ……」
一度頷いた後、リウドルフはスラックスのポケットをやおら弄り始めた。
「気付かない内に随分と暗くなった。これで足元を照らして行くと良い」
そう言って彼がポケットから取り出したのは小型のペンライトであり、スイッチを入れてすぐその足先に紫色の光が照射された。
「どうも色々と済みません」
照れ臭そうに笑って、ゾエはリウドルフへと近付いて行く。宵闇の沈降して行く中でも、その面持ちには欠片の翳りも淀んではいなかった。
そこで不意に、全く出し抜けにリウドルフはペンライトを持った手首の角度を変えたのだった。足元より翻った紫の光が、向かい立つゾエの体の中心付近へと速やかに据えられる。
途端、彼女の両腕と衣服に、水色に光り輝く染みのようなものが突如として浮かび上がったのであった。
「……え……?」
ライトの光を正面から唐突に浴びせられたゾエは、眩しさに目を細めつつも咄嗟の出来事に呆然とした表情を浮かべた。
対してリウドルフはその面持ちを、一転して冷たいものへと変えていたのであった。静かに両目を細め、彼は目の前の『事実』を在りのまま双眸に収めた。
「……初回でビンゴを引くとは、この場合あまり喜ぶ気にもなれんな……」
寂しげな独白がその唇より漏れ出した。
一方のゾエは著しく困惑した様子で、強張った笑みを相手へと向ける。
「な、何です、先生? これは一体何の真似ですか? どういう趣旨でこんな……」
黄昏時の暗がりの中でも自身の体に鮮烈に浮かび上がった、不気味ですらある無数の青白い染みを見て、ゾエはひたぶるに周章狼狽の体を晒すばかりであった。
「……君に、君の『ペット』に戯れに殺された人々の怨念を見えるようにした、とでも言った所か」
対するリウドルフは冷たく硬い声を目の前に立つ相手へと向けた。日本の怪談に登場する人魂を平面にして貼り付けたような、鮮やかな水色の輝きを浮かび上がらせたゾエを、リウドルフは手にしたライトで尚も照らし続ける。
「クローデル警視以外には伝えていなかった事だが、用水路に昼間流し込んだ溶液には薄荷油の他にもう一つ別の薬剤を混ぜてあったのだ。主に『キニーネ』を溶かし込んだ薬液をな」
ゾエは最後に出て来た名前を聞くなり、はっとした面持ちで今も水色の光を放つ自分の体を見下ろした。
リウドルフは僅かに顎を引き、上目遣いに相手を見つめる。
「薬剤に詳しいのなら判るだろう。『キニーネ』は紫外線を照射されると蛍光反応を起こす。今互いに目にしている通りだ」
平淡な声でそこまでを告げた後、リウドルフはゾエへ、体を斑に光らせる目の前の女へ刺すような眼差しを遣した。
「つまり、君は薬剤の流し込まれた『水』にわざわざ近付いて『触れて』いた事になる。しかも、その有様ではかなり執拗に『接触』を繰り返していたようだな。何故そんな真似をした? 『獣』が潜んでいるかも知れないと予め警告が出ていた水場に、それも迂闊に触れれば目や喉の粘膜を傷めかねない濃度のメントールとシオネールが溶け込んだ用水路に近付いて、一体『何』をしていたんだ?」
鋭い詰問にゾエは言葉を詰まらせた。
リウドルフの目元が俄かに険しさを増した。
「おい、惚けるなよ。元々あの『獣』は自然発生するような代物ではない。それを『創り出した』者が何処かに必ず存在する。奔放に暴れ回っているように見えても、付かず離れず世話を焼いている『何者か』がいた筈だ。用心深い『犯人』であれば、不測の事態が生じた際には取り敢えず『回収』に向かうだろうと最初から踏んでいた」
夜風が道端の並木を騒がせた。
風に乗って何処からか届く微かな薄荷の匂いが鼻先に漂う中、ゾエは静かに笑みを浮かべた。
口元の形はそれまでと何が変わるでもない。
然るにその目元には、これまでに無い傲然たる態度が立ち昇っていたのであった。
鼻息を一度ついた後、彼女は目の前で険しい顔を晒し続ける痩身の男を顎を少し持ち上げて見下ろした。
「……あなたもよくよく底意地の悪い人ね。万事その調子じゃ、今時女の子にもモテないわよ?」
人の鼻先をくすぐるような、それでいて肌を毛羽立たせるような、穏やかな中に棘の隠された物言いであった。
ゾエはこれまでの陽気で前向きな態度を奥に引っ込め、打って変わって嘲笑う口調で言い放った。
その双眸に嘲りと共に確かな敵意を漲らせながら。
リウドルフは手元のUVライトを消しつつ、本性を現した同僚を睨み据える。
「だとしても、貴様のような異常犯罪者に咎められる話でもあるまい」
尚も仏頂面を崩さぬリウドルフへ、ゾエはからかうように問い掛ける。
「いつから目を付けられていたのかしら?」
「あの怪物が俺達の前に姿を覗かせてからだ。俺としても最後まで信じたくはなかったがな。あんな『もの』を今になって新たに創り上げる馬鹿が出て来たなどと……」
実に不快げにリウドルフは答えた。
「……『あれ』とて一応は『人工生命体』の一種、なまじの知識と技術で生み出せるものではない。化学薬学全般に相当以上の学識を持つ者でなければ制作不可能と来れば、自ずと対象は絞られて来る。最新の化学にも古代の伝承にも詳しい者に限られれば尚更に」
「まあ、あなたみたいな生きた化石からすれば、見破るのも初めから容易かったのかしらねぇ」
ゾエは慌てるでもなく一笑に付した。
通りすがりの人物を線路へ突き落しておいて、自身は至って涼しい顔を覗かせるように。
そのゾエへとリウドルフは一歩を踏み出して問う。
「……『あれ』を何処へ隠した?」
「それを聞いてどうするの?」
「無論速やかに処分する。二百年前、『あれ』がこの国でどれ程の惨事を引き起こしたか、どれ程の狂気の中で生まれたものか、わざわざ思い返すのも忌々しいからだ」
今にも歯軋りせんばかりの剣幕で唸るように言ったリウドルフに対し、ゾエはまた笑みを湛えた。
「あなた程の人が言うのなら、私は逆に頼もしく思えて来るわね。自慢の『息子』がそこまで恐れられていたなんて……」
言いながら、彼女は肩に掛けた金属製の水筒をゆっくりと下ろした。容積としては四リットル程の物であろうか。大型の水筒の蓋を掴み、ゾエは双眸を俄かに輝かせる。
「さあ出てらっしゃい、『坊や』! 光栄な事に、あちらも貴方をお待ちかねよ!」
直後、蓋を外された水筒の中より『何か』が外へと勢い良く飛び出した。
緋色の空の下に微かな煌めきが生じる。
ゾエの足元へとうねるようにして降り立った『それ』を見るなり、リウドルフは顔を大きく顰めたのだった。
「やはり、か……!」
臍を嚙むリウドルフの前で、『それ』は外気を吸って俄然勢い付いたようであった。
うっすらと透き通った水銀の塊のような物体が彼の目の前で蠢いていた。
定まった形を生来持たず、固体と液体の中間にあるかのような軟体性の生き物である。アメーバ、若しくは粘菌を肥大させたような原始的な外見の生物が夕闇の中で細かに揺らめき動く。金属のような銀色の体表に夕日の輝きを絶えずてからせながら。
「……『ジェヴォーダンの獣』!!」
「そう。私の最高傑作よ」
吐き捨てたリウドルフの前で、ゾエは己の脚に絡み付く銀色の不定形生物を愛おしげに見下ろした。
「大事な大事な『我が子』……」
微笑すら湛えた彼女の足元で、二百年の時を経て蘇った『獣』はこそばゆげに体表を波打たせたのだった。
午後八時に近付く頃には辺りも随分と暗くなっていた。
空は斜陽の光と夜の翳りとが半分ずつを占め、次第次第に宵がその領域を広げて行く。夏も終わりに近付いた今、日の沈む時刻も少しずつ早まって来ていたのだった。
諸々の農作業も終わりを迎え、人気の無くなった田畑に夜の翳りが音も無く降り積もって行く。村の中心を伸びる道路には何台かの警察車両が今も停められていたが、それもまた徐々に他所へと走り出して行った。
街灯の灯り始めた村を、リウドルフは一人散策していた。
道端から水の流れる音が軽やかに伝わって来る。未だ諦め悪く鳴き続ける蝉を別とすれば、昼の様々な喧騒が裾を収めつつある黄昏時の農村を瘦身の孤影は黙して歩き続けた。
いつもと何ら変わらぬのだろう夕刻の田園風景が辺りには広がっていたのであった。
ややあって、如何にも頼り無い痩せこけた背中に弾んだ声が投げ掛けられる。
「先生! 先生!」
リウドルフが肩越しに首を巡らせてみれば、村の中央に建つコミュニティセンターの方から女が一人駆けて来る所であった。薄暗い中でも、やや細身の体型と朗らかなその声から何者であるかはすぐに察せられる。
帰り支度を既に整えた後であろうか。
ボディバッグを背に回し、右の肩からは大きな水筒を下げたゾエ・サマンが小走りになって道端のリウドルフへと駆け寄った。
「何だ、先生、表の方にいたんですか」
息を整えつつほっとしたような声を上げたゾエを見て、リウドルフも相好を崩した。
「ああ、丁度君を探していた所でね」
「そうだったんですか。じゃ、丁度良かったですね」
雀卵斑の浮かんだ頬を上気させて、ゾエもまた微笑んだ。
そうして一組の人影は夕時の村を揃って歩き出した。
昼の活動の名残であろうか。辺りには時折、清涼感を伴う薬剤の匂いが何処からともなく漂って来るのだった。
西日の染める空が赤味を深めつつも少しずつ領域を縮めて行く。
やがて村の外を囲う畑が細道の向こうに見えて来た辺りで、ゾエは傍らを歩く先達へ気遣う眼差しを遣した。
「まあ、そう落ち込まないで下さい、先生。昼間の作戦は目ぼしい成果を上げられませんでしたけど、捜査の対象は大分絞られて来た訳でしょう? また新しい手を考えればいいじゃないですか」
「いや、そう簡単に言ってくれるがねぇ……」
リウドルフは半ばお道化るようにして苦笑交じりに呟いた。
「実際の所、あれだけ大掛かりな真似をしておいて収穫が全然無いのでは頂けない。警察に無駄に手間と金を注ぎ込ませただけに終わってしまったし、これで周囲から益々孤立してしまうか……」
「そんな気弱な事を仰らないで下さい」
細い肩を落として愚痴を零した相手をゾエは傍らから励ました。それと一緒に、彼女は肩に掛けた水筒を抱え直す。
「人が少なくなった方が却ってやり易くなる事だってあるでしょうから」
「そうかも知れんが、格好を付けた手前、結果がこれではなぁ……」
重みのまるで無い嘆息を涼しさを増した夜風が吹き流して行った。
程無く、両者は刈り取りの終わったラベンダー畑の前で足を止めた。
誰の姿も最早認められない夕時の畑は、ただ夜風が奔放に遊び回るばかりである。微かに漂うラベンダーの香りが朱色の空の下に佇む二人の間に寄せた。
リウドルフは地平へ吸い込まれようとする西日を眺めながら小さな肩を竦めた。
「……遺憾ながら手詰まりかな。神出鬼没の獣程、向こうに回して厄介なものは無い」
「ええっ!? それじゃ、これからどうなさるんです?」
出し抜けに、それこそ煙草の吸い止しでも投げて遣すかのようにして放たれた宣告に、ゾエは吃驚も露わに詰問した。
「どうもこうも後は警察に任せるしかない。このままじゃ良くて千日手に陥るだけだし、こちらも日程にそこまでの余裕は無い。もうすぐ新学期が始まるんだ」
困り顔すら浮かべたゾエへ答えてから、リウドルフは片手を開いて見せた。
「お手上げ、と言う奴だな」
「そんなぁ……」
実に無念そうに嘆息を漏らしたゾエへリウドルフは鼻息をついて見せた。
「誠に遺憾ながら、素人に出来る捜査ごっこはここまでだ。残念だが、そうした締め括りだって往々にして起こるさ。世の中、何もかも思い通りに手繰れる程甘くもない」
しんみりとしたリウドルフの言葉にゾエは口先を尖らせた。
「残念ですね……」
「まあな……」
何やら湿っぽい遣り取りを交わす両者の間を行き摺りの夜風が冷やかした。
畑の向こうで蛙が鳴き始めた。
ややあってゾエは徐に一礼する。
「では、私はこれで」
「ああ。そちらもこの数日間、無駄にロデーズから通わせてしまったな。宿泊費と交通費込みで『IOSO』から特別手当を出すよう要請しておくよ」
リウドルフが詫びの言葉を入れるとゾエは笑った。
「有難う御座います。お休みなさい、先生」
「ああ……」
一度頷いた後、リウドルフはスラックスのポケットをやおら弄り始めた。
「気付かない内に随分と暗くなった。これで足元を照らして行くと良い」
そう言って彼がポケットから取り出したのは小型のペンライトであり、スイッチを入れてすぐその足先に紫色の光が照射された。
「どうも色々と済みません」
照れ臭そうに笑って、ゾエはリウドルフへと近付いて行く。宵闇の沈降して行く中でも、その面持ちには欠片の翳りも淀んではいなかった。
そこで不意に、全く出し抜けにリウドルフはペンライトを持った手首の角度を変えたのだった。足元より翻った紫の光が、向かい立つゾエの体の中心付近へと速やかに据えられる。
途端、彼女の両腕と衣服に、水色に光り輝く染みのようなものが突如として浮かび上がったのであった。
「……え……?」
ライトの光を正面から唐突に浴びせられたゾエは、眩しさに目を細めつつも咄嗟の出来事に呆然とした表情を浮かべた。
対してリウドルフはその面持ちを、一転して冷たいものへと変えていたのであった。静かに両目を細め、彼は目の前の『事実』を在りのまま双眸に収めた。
「……初回でビンゴを引くとは、この場合あまり喜ぶ気にもなれんな……」
寂しげな独白がその唇より漏れ出した。
一方のゾエは著しく困惑した様子で、強張った笑みを相手へと向ける。
「な、何です、先生? これは一体何の真似ですか? どういう趣旨でこんな……」
黄昏時の暗がりの中でも自身の体に鮮烈に浮かび上がった、不気味ですらある無数の青白い染みを見て、ゾエはひたぶるに周章狼狽の体を晒すばかりであった。
「……君に、君の『ペット』に戯れに殺された人々の怨念を見えるようにした、とでも言った所か」
対するリウドルフは冷たく硬い声を目の前に立つ相手へと向けた。日本の怪談に登場する人魂を平面にして貼り付けたような、鮮やかな水色の輝きを浮かび上がらせたゾエを、リウドルフは手にしたライトで尚も照らし続ける。
「クローデル警視以外には伝えていなかった事だが、用水路に昼間流し込んだ溶液には薄荷油の他にもう一つ別の薬剤を混ぜてあったのだ。主に『キニーネ』を溶かし込んだ薬液をな」
ゾエは最後に出て来た名前を聞くなり、はっとした面持ちで今も水色の光を放つ自分の体を見下ろした。
リウドルフは僅かに顎を引き、上目遣いに相手を見つめる。
「薬剤に詳しいのなら判るだろう。『キニーネ』は紫外線を照射されると蛍光反応を起こす。今互いに目にしている通りだ」
平淡な声でそこまでを告げた後、リウドルフはゾエへ、体を斑に光らせる目の前の女へ刺すような眼差しを遣した。
「つまり、君は薬剤の流し込まれた『水』にわざわざ近付いて『触れて』いた事になる。しかも、その有様ではかなり執拗に『接触』を繰り返していたようだな。何故そんな真似をした? 『獣』が潜んでいるかも知れないと予め警告が出ていた水場に、それも迂闊に触れれば目や喉の粘膜を傷めかねない濃度のメントールとシオネールが溶け込んだ用水路に近付いて、一体『何』をしていたんだ?」
鋭い詰問にゾエは言葉を詰まらせた。
リウドルフの目元が俄かに険しさを増した。
「おい、惚けるなよ。元々あの『獣』は自然発生するような代物ではない。それを『創り出した』者が何処かに必ず存在する。奔放に暴れ回っているように見えても、付かず離れず世話を焼いている『何者か』がいた筈だ。用心深い『犯人』であれば、不測の事態が生じた際には取り敢えず『回収』に向かうだろうと最初から踏んでいた」
夜風が道端の並木を騒がせた。
風に乗って何処からか届く微かな薄荷の匂いが鼻先に漂う中、ゾエは静かに笑みを浮かべた。
口元の形はそれまでと何が変わるでもない。
然るにその目元には、これまでに無い傲然たる態度が立ち昇っていたのであった。
鼻息を一度ついた後、彼女は目の前で険しい顔を晒し続ける痩身の男を顎を少し持ち上げて見下ろした。
「……あなたもよくよく底意地の悪い人ね。万事その調子じゃ、今時女の子にもモテないわよ?」
人の鼻先をくすぐるような、それでいて肌を毛羽立たせるような、穏やかな中に棘の隠された物言いであった。
ゾエはこれまでの陽気で前向きな態度を奥に引っ込め、打って変わって嘲笑う口調で言い放った。
その双眸に嘲りと共に確かな敵意を漲らせながら。
リウドルフは手元のUVライトを消しつつ、本性を現した同僚を睨み据える。
「だとしても、貴様のような異常犯罪者に咎められる話でもあるまい」
尚も仏頂面を崩さぬリウドルフへ、ゾエはからかうように問い掛ける。
「いつから目を付けられていたのかしら?」
「あの怪物が俺達の前に姿を覗かせてからだ。俺としても最後まで信じたくはなかったがな。あんな『もの』を今になって新たに創り上げる馬鹿が出て来たなどと……」
実に不快げにリウドルフは答えた。
「……『あれ』とて一応は『人工生命体』の一種、なまじの知識と技術で生み出せるものではない。化学薬学全般に相当以上の学識を持つ者でなければ制作不可能と来れば、自ずと対象は絞られて来る。最新の化学にも古代の伝承にも詳しい者に限られれば尚更に」
「まあ、あなたみたいな生きた化石からすれば、見破るのも初めから容易かったのかしらねぇ」
ゾエは慌てるでもなく一笑に付した。
通りすがりの人物を線路へ突き落しておいて、自身は至って涼しい顔を覗かせるように。
そのゾエへとリウドルフは一歩を踏み出して問う。
「……『あれ』を何処へ隠した?」
「それを聞いてどうするの?」
「無論速やかに処分する。二百年前、『あれ』がこの国でどれ程の惨事を引き起こしたか、どれ程の狂気の中で生まれたものか、わざわざ思い返すのも忌々しいからだ」
今にも歯軋りせんばかりの剣幕で唸るように言ったリウドルフに対し、ゾエはまた笑みを湛えた。
「あなた程の人が言うのなら、私は逆に頼もしく思えて来るわね。自慢の『息子』がそこまで恐れられていたなんて……」
言いながら、彼女は肩に掛けた金属製の水筒をゆっくりと下ろした。容積としては四リットル程の物であろうか。大型の水筒の蓋を掴み、ゾエは双眸を俄かに輝かせる。
「さあ出てらっしゃい、『坊や』! 光栄な事に、あちらも貴方をお待ちかねよ!」
直後、蓋を外された水筒の中より『何か』が外へと勢い良く飛び出した。
緋色の空の下に微かな煌めきが生じる。
ゾエの足元へとうねるようにして降り立った『それ』を見るなり、リウドルフは顔を大きく顰めたのだった。
「やはり、か……!」
臍を嚙むリウドルフの前で、『それ』は外気を吸って俄然勢い付いたようであった。
うっすらと透き通った水銀の塊のような物体が彼の目の前で蠢いていた。
定まった形を生来持たず、固体と液体の中間にあるかのような軟体性の生き物である。アメーバ、若しくは粘菌を肥大させたような原始的な外見の生物が夕闇の中で細かに揺らめき動く。金属のような銀色の体表に夕日の輝きを絶えずてからせながら。
「……『ジェヴォーダンの獣』!!」
「そう。私の最高傑作よ」
吐き捨てたリウドルフの前で、ゾエは己の脚に絡み付く銀色の不定形生物を愛おしげに見下ろした。
「大事な大事な『我が子』……」
微笑すら湛えた彼女の足元で、二百年の時を経て蘇った『獣』はこそばゆげに体表を波打たせたのだった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

#この『村』を探して下さい
案内人
ホラー
『この村を探して下さい』。これは、とある某匿名掲示板で見つけた書き込みです。全ては、ここから始まりました。
この物語は私の手によって脚色されています。読んでも発狂しません。
貴方は『■■■』の正体が見破れますか?

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る
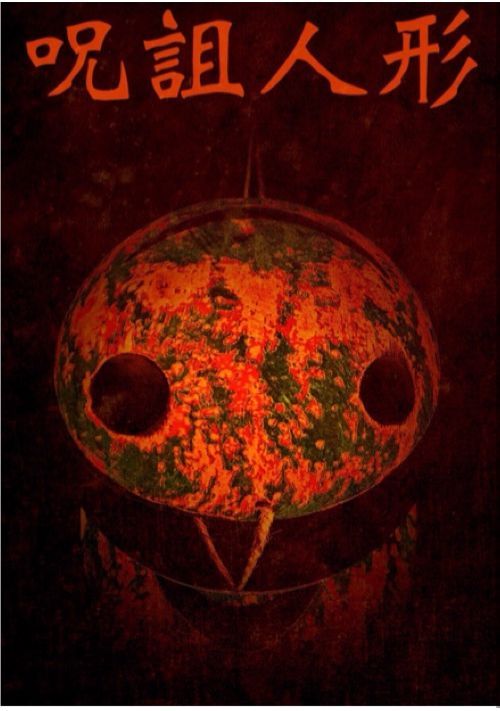
呪詛人形
斉木 京
ホラー
大学生のユウコは意中のタイチに近づくため、親友のミナに仲を取り持つように頼んだ。
だが皮肉にも、その事でタイチとミナは付き合う事になってしまう。
逆恨みしたユウコはインターネットのあるサイトで、贈った相手を確実に破滅させるという人形を偶然見つける。
ユウコは人形を購入し、ミナに送り付けるが・・・
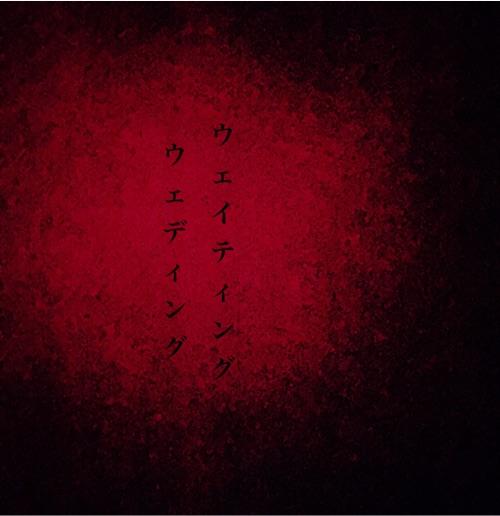
ウェイティングウェディング
ナシノツブテ
ホラー
一人の男が長年ストーカーしてきた女の結婚式で殺人事件を起こす。
その事件の巻き添えをくらった人たちの最後の瞬間までの出来事を短編にした作品。
登場人物全員狂ってる…


サクッと読める意味が分かると怖い話
異世界に憧れるとある青年
ホラー
手軽に読めるホラーストーリーを書いていきます。
思いつくがままに書くので基本的に1話完結です。
小説自体あまり書かないので、稚拙な内容は暖かい目で見てもらえると幸いです。

復讐のナイトメア
はれのいち
ホラー
悪夢で復讐請負います。
夢を支配出来る特殊な能力を持つ高校生真山 瞬の物語である。
俺には秘密がある。
俺は相手の夢を支配する事が出来る。
毎晩毎晩……悪夢をみせる事も可能だ。
親の権力を振りかざし虐める奴ら、
蟻の様に群がり集団で虐める奴ら、
俺が悪夢で皆んな成敗してやるよ……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















