5 / 6
5th episode 〔zombie〕
しおりを挟む
空に円が見えることを言った時、知り合いにはほとんどに、嫌な顔をされた。
あの円はただ見えるだけ。
幽霊を見ることができる、と主張しているのと何ら変わりはない。
そんなことを真剣に言おうものなら、良いとこ変わり者扱い、大抵の場合は嘘つき呼ばわりなのだ。
だから、何度か円の話をしているうちに、元々そう多くはない友人とは自然と距離遠くなったし、他に同じような知り合いもいない。
そんな中で、興味津々で話しかけてくれた咲凜は、正直な話、救いだった。
「円が見えるってのは君!? ねえねえ、もっとその話詳しく!!」
咲凜にとっては百パーセント純粋な好奇心だったろうけど、そんな風に僕の話を何の疑いもなく聞いてくれる人は、新鮮だった。
だから咲凜には出来るだけ協力する。ああして僕と友達になってくれた恩返しをしたくて。
そう、思っていたけれど。
校門前の男がかざしたスマホ写真。その中に写る咲凜の背後に、バスケットボールが見えた。
だから阿澄さんが森から駆けつけて、庇ってくれた後、僕が真っ先に向かったのは体育倉庫だった。
校門をよじ登り、一直線に校庭の奥にある体育倉庫を目指した。鍵がかかっているはずの倉庫の扉は開いていて、当たりだと確信した。
咲凜の無事を確認して、連れ出す。
それからはどうしたらいい?
まずは警察署だろうか。阿澄さんのことは伏せるとして、不審者に襲われたのだからそれが正解だと思う。
咲凜も男の顔は見ているだろうし、一緒に証言すれば……。
そんなことを考えていたけれど、一気に思考全てが、頭から消え去る。
僕は膝から崩れ落ちる。理解はできない。納得もできない。
でもじゃあ、倉庫を開けた先にある、人の形をした真っ暗な物体をどう捉えたらいい。
僕は人の形をしたそれに近づき、触ろうとした。
「生かしているわけがない」
だが、僕は肩を掴まれ、乱暴に押し飛ばされる。
男が顔や腕、色々なところを負傷しながらも、僕の前に立っていた。
「その子を拐かしたのは勘違いだったけど、生かしておけば、その子は僕のことを誰かに言うだろ。円の見えない者を殺したのは不本意ではあるが、リスク管理だ。仕方ない」
男の言葉のほとんどが、僕の耳を通り過ぎていくけれど、男も僕に話していると言うより、ただくどくどと独り言をつぶやいているだけのようだった。
「阿澄さん、は……」
「あの女のこと? 苦労したけど、首を焼き切った。彼女の殻には、僕の炎も効かなかったからね。君も残念だったね。あの女がどうして君を庇ったのか知らないけれど、それも関係ないな」
男は、僕を指さす。
「君も円が見える。ならば死なないといけない」
「どうして」
「円が見える者は、異端だよ。世界の異端。あの円は世界の綻びだ。だから、あの綻びを見える者は世界の綻びの影響を受けるんだ。異能を持つんだよ。異能は更に世界に綻びをうみ、その綻びからまた世界が綻ぶ。だから、円が見える者は死ぬべきだ。世界のために。僕はそれを実行できる。だから死んでもらう」
そんな到底理解できない言葉を冷静に語る男を見ていて、その男の声をどこかで聞いたことがある理由に思い至った。
「ユークリ?」
僕がつぶやくと、優しげな声で男は息を吐いて笑った。
「耳が良いんだな、君は」
男は再び、倒れる僕に向けて手を掲げた。男の掌に、さっきと同じように炎が集まる。にわかには信じられない光景だけれど、間違いなく僕の目の前で熱気が強く圧縮され、男の掌に集約される。
「君はまだ異能を持たないようだが、だからこそ今のうち消えるべきだ。君も世界の脅威になんてなりたくないだろ」
それでもやっぱり、意味がわからない。
この男の話す言葉の一つとして、理解できるものがない。
男の炎から逃げようと、手を伸ばして、焼け果てた死体の指が僕の手に触れた。
信じたくないと言う陰りと、胸の奥から湧き上がる爆発しそうな激情が同時に僕の頭を占める。
わからない。わからないわからない。
だけど、この男は。
僕は強く唇を噛む。
口から顎へ、つうと血が垂れる。
震える手で倉庫の床を無意識に引っ掻いて、爪もぼろぼろになる。
顔が熱くなり、大声で叫び散らかしたかった。
「僕は世界を正せる。そのための力がある。だから、その責任もある。円が見える世界の綻び全てを滅ぼして、最後には自分を燃やす」
そうして相変わらず、くどくどと語る男の身体に、影がさした。
僕は男の背後にそびえる巨体を見上げた。
男も違和感に気付き、振り向いたが、遅かった。
「あ」
男の胸が、貫かれる。
阿澄さんが、右手のハサミを背中から男の胸に刺していた。
「? 確かに首を焼き切ったのに」
男の掌に集まっていた炎の玉が、急速に鎮火した。
阿澄さんが右手を男の胸から引き抜く。
そのままどさりと仰向けに男は倒れた。
どくどくと血が倉庫内に流れて行く。
「いや、そうか。わかった。とっくに死んでいたのか」
弱々しい瞳で、男は改めて僕を見た。
「まだ異能を持たないなんて、とんでもない。僕が戦っていたのは、君だったのか」
続いて自身を見下ろす阿澄さんを見上げた。
「気付いていたか? この女はずっと、死んでいたんだ。おい君、君だよ。彼女を動かしていたのは」
未だ言葉を紡ぎ続ける男に飽きたかのように、阿澄さんの脚が、男の顔を踏み潰した。
「阿澄さん……」
阿澄さんの顔は、火傷でひどく崩れている。いや、崩れているなんてもんじゃない。
上頭部は燃え尽きている。
鼻から下だけの顔のまま、阿澄さんは男の胸元をハサミで探った。
阿澄さんは男のワイシャツの内ポケットから、ネックレスを取り出した。
そのネックレスは、阿澄さんが塾のティーチングアシスタントだった時にも毎日身に付けていたものだ。
ああそうか。
阿澄さんが夜な夜なその姿のまま、街を探していたのはそれなのだと、わかった。
それが何かは僕にはわからないけれど、阿澄さんにとっては、とても大切なものだったのだろう。
阿澄さんは、ハサミで傷つけないように、ぎゅっとそれを自身の胸に抱く。
ありがとう。
彼女の口がそう、動いたかと思うと、さらさらと彼女の身体はまるで砂のように崩れ、風に吹かれていった。
あの円はただ見えるだけ。
幽霊を見ることができる、と主張しているのと何ら変わりはない。
そんなことを真剣に言おうものなら、良いとこ変わり者扱い、大抵の場合は嘘つき呼ばわりなのだ。
だから、何度か円の話をしているうちに、元々そう多くはない友人とは自然と距離遠くなったし、他に同じような知り合いもいない。
そんな中で、興味津々で話しかけてくれた咲凜は、正直な話、救いだった。
「円が見えるってのは君!? ねえねえ、もっとその話詳しく!!」
咲凜にとっては百パーセント純粋な好奇心だったろうけど、そんな風に僕の話を何の疑いもなく聞いてくれる人は、新鮮だった。
だから咲凜には出来るだけ協力する。ああして僕と友達になってくれた恩返しをしたくて。
そう、思っていたけれど。
校門前の男がかざしたスマホ写真。その中に写る咲凜の背後に、バスケットボールが見えた。
だから阿澄さんが森から駆けつけて、庇ってくれた後、僕が真っ先に向かったのは体育倉庫だった。
校門をよじ登り、一直線に校庭の奥にある体育倉庫を目指した。鍵がかかっているはずの倉庫の扉は開いていて、当たりだと確信した。
咲凜の無事を確認して、連れ出す。
それからはどうしたらいい?
まずは警察署だろうか。阿澄さんのことは伏せるとして、不審者に襲われたのだからそれが正解だと思う。
咲凜も男の顔は見ているだろうし、一緒に証言すれば……。
そんなことを考えていたけれど、一気に思考全てが、頭から消え去る。
僕は膝から崩れ落ちる。理解はできない。納得もできない。
でもじゃあ、倉庫を開けた先にある、人の形をした真っ暗な物体をどう捉えたらいい。
僕は人の形をしたそれに近づき、触ろうとした。
「生かしているわけがない」
だが、僕は肩を掴まれ、乱暴に押し飛ばされる。
男が顔や腕、色々なところを負傷しながらも、僕の前に立っていた。
「その子を拐かしたのは勘違いだったけど、生かしておけば、その子は僕のことを誰かに言うだろ。円の見えない者を殺したのは不本意ではあるが、リスク管理だ。仕方ない」
男の言葉のほとんどが、僕の耳を通り過ぎていくけれど、男も僕に話していると言うより、ただくどくどと独り言をつぶやいているだけのようだった。
「阿澄さん、は……」
「あの女のこと? 苦労したけど、首を焼き切った。彼女の殻には、僕の炎も効かなかったからね。君も残念だったね。あの女がどうして君を庇ったのか知らないけれど、それも関係ないな」
男は、僕を指さす。
「君も円が見える。ならば死なないといけない」
「どうして」
「円が見える者は、異端だよ。世界の異端。あの円は世界の綻びだ。だから、あの綻びを見える者は世界の綻びの影響を受けるんだ。異能を持つんだよ。異能は更に世界に綻びをうみ、その綻びからまた世界が綻ぶ。だから、円が見える者は死ぬべきだ。世界のために。僕はそれを実行できる。だから死んでもらう」
そんな到底理解できない言葉を冷静に語る男を見ていて、その男の声をどこかで聞いたことがある理由に思い至った。
「ユークリ?」
僕がつぶやくと、優しげな声で男は息を吐いて笑った。
「耳が良いんだな、君は」
男は再び、倒れる僕に向けて手を掲げた。男の掌に、さっきと同じように炎が集まる。にわかには信じられない光景だけれど、間違いなく僕の目の前で熱気が強く圧縮され、男の掌に集約される。
「君はまだ異能を持たないようだが、だからこそ今のうち消えるべきだ。君も世界の脅威になんてなりたくないだろ」
それでもやっぱり、意味がわからない。
この男の話す言葉の一つとして、理解できるものがない。
男の炎から逃げようと、手を伸ばして、焼け果てた死体の指が僕の手に触れた。
信じたくないと言う陰りと、胸の奥から湧き上がる爆発しそうな激情が同時に僕の頭を占める。
わからない。わからないわからない。
だけど、この男は。
僕は強く唇を噛む。
口から顎へ、つうと血が垂れる。
震える手で倉庫の床を無意識に引っ掻いて、爪もぼろぼろになる。
顔が熱くなり、大声で叫び散らかしたかった。
「僕は世界を正せる。そのための力がある。だから、その責任もある。円が見える世界の綻び全てを滅ぼして、最後には自分を燃やす」
そうして相変わらず、くどくどと語る男の身体に、影がさした。
僕は男の背後にそびえる巨体を見上げた。
男も違和感に気付き、振り向いたが、遅かった。
「あ」
男の胸が、貫かれる。
阿澄さんが、右手のハサミを背中から男の胸に刺していた。
「? 確かに首を焼き切ったのに」
男の掌に集まっていた炎の玉が、急速に鎮火した。
阿澄さんが右手を男の胸から引き抜く。
そのままどさりと仰向けに男は倒れた。
どくどくと血が倉庫内に流れて行く。
「いや、そうか。わかった。とっくに死んでいたのか」
弱々しい瞳で、男は改めて僕を見た。
「まだ異能を持たないなんて、とんでもない。僕が戦っていたのは、君だったのか」
続いて自身を見下ろす阿澄さんを見上げた。
「気付いていたか? この女はずっと、死んでいたんだ。おい君、君だよ。彼女を動かしていたのは」
未だ言葉を紡ぎ続ける男に飽きたかのように、阿澄さんの脚が、男の顔を踏み潰した。
「阿澄さん……」
阿澄さんの顔は、火傷でひどく崩れている。いや、崩れているなんてもんじゃない。
上頭部は燃え尽きている。
鼻から下だけの顔のまま、阿澄さんは男の胸元をハサミで探った。
阿澄さんは男のワイシャツの内ポケットから、ネックレスを取り出した。
そのネックレスは、阿澄さんが塾のティーチングアシスタントだった時にも毎日身に付けていたものだ。
ああそうか。
阿澄さんが夜な夜なその姿のまま、街を探していたのはそれなのだと、わかった。
それが何かは僕にはわからないけれど、阿澄さんにとっては、とても大切なものだったのだろう。
阿澄さんは、ハサミで傷つけないように、ぎゅっとそれを自身の胸に抱く。
ありがとう。
彼女の口がそう、動いたかと思うと、さらさらと彼女の身体はまるで砂のように崩れ、風に吹かれていった。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


空の蒼 海の碧 山の翠
佐倉 蘭
ライト文芸
アガイティーラ(ティーラ)は、南島で漁師の家に生まれた今年十五歳になる若者。
幼い頃、両親を亡くしたティーラは、その後網元の親方に引き取られ、今では島で一目置かれる漁師に成長した。
この島では十五歳になる若者が海の向こうの北島まで遠泳するという昔ながらの風習があり、今年はいよいよティーラたちの番だ。
その遠泳に、島の裏側の浜で生まれ育った別の網元の跡取り息子・クガニイルも参加することになり…
※毎日午後8時に更新します。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

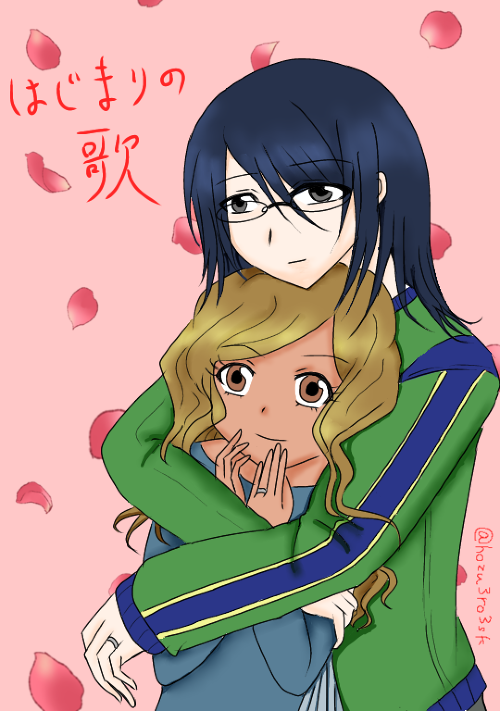
【10】はじまりの歌【完結】
ホズミロザスケ
ライト文芸
前作『【9】やりなおしの歌』の後日譚。
11月最後の大安の日。無事に婚姻届を提出した金田太介(カネダ タイスケ)と歌(ララ)。
晴れて夫婦になった二人の一日を軸に、太介はこれまでの人生を振り返っていく。
「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ10作目。(登場する人物が共通しています)。単品でも問題なく読んでいただけます。
※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















