48 / 48
設定資料
知っておきたいワイン知識
しおりを挟む
【分かっているといいかもしれないワイン講座】
まず、ワインはブドウを原料にして作られます。
ブドウを収穫し、潰したり、発酵させたりして、お酒に仕上げていきます。
分類分けすると、
①スティルワイン(よく見かける赤ワインとか白ワインとか)
②スパークリングワイン(あわあわしゅわしゅわ、シャンパンとか)
③フォーティファイドワイン(作る過程で、アルコールの強い酒を入れる)
④フレーバードワイン(薬草とかハーブとかで香りをつけたワイン。ヴェルモットなど)
の4種類に分けられます。
①スティルワイン
さらに
・赤ワイン
・白ワイン
・ロゼワイン(ピンクっぽいワイン)
と分けられます。
赤ワインは、主に黒ブドウから作ります。
赤ワインのあの濃い色は、ブドウの皮の色から出るのです。
白ワインは色の薄い白ブドウから作るのですが、
時々、皮を取った黒ブドウからも作ります。(ピノ・ノワールがよくやります)
ロゼは作る段階で、色が濃くなる前に黒ブドウの皮を途中で除くタイプと、赤ワインと白ワインを混ぜちゃうタイプとふた通りあります。
歴史は古く、ローマ時代にはもう飲まれており、聖書にも登場します。
また、ブドウの種の周りには、タンニンという渋ーい物質があり、黒ブドウにはこれが多く含まれていることが多いです。そのため、赤ワインには渋みがあるものが多いです。
②スパークリングワイン
ほとんどが白ブドウから作られる、発泡ワインです。
(ピノ・ノワールという例外もいます)
主に食前酒やパーティで飲まれることが多い、華やかでスッキリとしたワインです。
①のワインを発酵途中で瓶に詰めてしまうことで、瓶内で泡が発生し(瓶内二次発酵)、
きめ細やかな美しい泡が閉じ込められます。
フランスの僧侶のいい加減さから生まれたワインです。
③フォーティファイドワイン
酒精強化ワインとも言います。アルコールが高めのお酒です。
イギリスやフランスの戦争に大きく関わっており、
船で輸出する際、酒とはいえ品質が悪くなったりするため、
それを防ごうと、アルコールの強い酒を足したのが始まりです。
ブドウは糖を含み、これを発酵でアルコールに変えることで、ワインになります。
発酵途中でアルコールを入れることで、その発酵を止めちゃいます。
そうすると、とろりと甘く、アルコールの強い、傷みにくい酒が出来上がりました。
船で旅するワイン、と覚えると、わかりやすいかもです。
④フレーバードワイン
あまりお店などでは見かけないかもです。
①のワインにハーブや薬草で香りづけします。
他に、①の中で《貴腐ワイン》というものがあります。
ブドウによっては、皮の厚いもの、薄いものとあり、
ボトリティス・シネレアというカビ菌がつくことで、
ブドウの水分が失われ、皮の薄いものは破れて、腐ってしまいます。
しかし、中には腐って水分が抜けることで、糖分が凝縮し、
とてもあま~いブドウができることがあります。
これをワインにしたものが、貴腐ワインです。
限定された状況下でしかできないため、高級ワインになります。
同じような原理で、
アイスワイン(ブドウが凍ることで水分が抜ける)
などがあります。
白ブドウで作るのですが、ワインの色は黄金色で、舌触りもとろりとしており、絶品です。
以上が分類分けです。
ブドウの産地ですが、
ワイン大国として知られるのは、フランス、ついでイタリアです。
特にフランスでは、地域、作る人、さらには畑ごとにブランドがあったりし、細かく格付けがされています。
同じ地域、ブドウでも、お隣さんの畑で作ったもの同士を混ぜてはいけない、など、ルールは厳しいです。
ワインベルトというものがあり、フランス、イタリア、スペイン、日本などを含む、地球をぐるりと一周した経度の範囲が、適しております(私もあまり分かっていない)
フランスには多彩な気候や土地があり、様々な味わいを楽しめます。
勉強の際はフランスから始めることをお勧めします。
元々、ワインはヨーロッパで盛んに作られていたもので、16世紀くらいにアメリカ大陸にヨーロッパの人々が移住したことで、アメリカにもワインが伝わりました。
そのため、ヨーロッパより後にワインが作られ始めた国を総称して、《新世界》と呼びます。
アメリカ、南米、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどがそうです。
おそらく日本もここに入ります。
日本に入ってきたのは、戦国時代、ポルトガルの宣教師によって、ブランデーが持ち込まれたことだと言われています。シャンパンも一緒に入ってきました。
ブランデーはワインを蒸留して作る、アルコールの強い酒です。また別記します。
このような酒は日本と交易をするために、接待のために用いられました。
こんな飲み物があるのか、と日本人の興味を引きます。
はじめに飲んだのは、織田信長という話です。
それから、明治時代くらいから本格的に栽培、生産が始まります。
ブドウによっては、土地や気候の好き嫌いがあります。
あったかいところでのびのび過ごすのが好きなブドウや、寒いところで、ぎゅうぎゅうして糖分を高めていくブドウなど、性格や好き嫌いも様々です。カベルネやメルローのように、あまり好き嫌いしないものもいます。
また、ブドウも人間と同じく、育った土地や環境が性格に反映されます。
暖かい地方で育ったブドウで作ったワインは、なんだか太陽の味がします。(え!?)
寒い地方で育ったワインは、雪で凍える大地や、冷たい風を感じます。
それから、土の香りを感じたり、その地方で咲き乱れる花の香りを感じたり。
そこまで分かるようになると、ソムリエになれちゃいますね。
いきなり、産地の話をしても、慣れない方はわからないと思います。
私がそうでした。
ブルゴーニュ、ロワールなどと言われても、いったいどんなワインなのか、さっぱりでした。
でも、ブドウ品種から入ることで、なんとなく、その地方のワインの性格がわかるようになりました。
そういう分けで、キャラクターの性格を、濃くしていきたいなと思います。
お店でラベルを見てみると、赤ワインの多くがカベルネ・ソーヴィニョンの名前があると思います。
非常にタフで、どんな土地でも、期待通り、それ以上の成績を出してくれます。
特に、南アメリカやオーストラリアなどの暖かい地域でよりパワフルになるため、多くワインが生産されています。
一方、白ワインではシャルドネが多く見られます。涼しい方が好みですが、アメリカやオーストラリアでも人気で、世界中の産地で生産されています。
ワインを作る上でたくさん決まりごとがあり、フランスではワインの法律まであります。
その中で、主要品種と言われているのが、
黒
・カベルネ・ソーヴィニョン
・メルロー
・ピノ・ノワール
・シラー
白
・シャルドネ
・セミヨン
・シュナン・ブラン
・ソーヴィニョン・ブラン
・リースリング
です。
言ってみれば、成績優秀者ですね。
これらは品質の良いワインを作り出せたり、土地への適応力が高かったりして、人気があるものです。
しかし、彼らだけでは作れないワインもあり、補助する品種も必要です。
カベルネとメルローは支え合っていますし、
ピノ・ノワールに至っては、赤ワインも白ワインもスパークリングワインも作るつわものですが、
シラーはグルナッシュやムールヴェドルという品種と活躍してますし、
逆にシュナン・ブランは補助に回ることが多いです。
主要品種にはなっていませんが、
イタリアワインの王と呼ばれるネッビオーロや、
世界三大貴腐ワインを作るフルミントやゲヴュルツ・トラミネールも外せません。
日本では甲州が絶賛売り出し中で、世界でも認められています。
ブドウ同士のつながりも面白いです。
例えば、カベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フラン、
彼らは親子です。
力強さのあるソーヴィニョンに比べ、フランは軽め、エレガントな印象を持ちます。
そのため、DNA鑑定が行われるまで長い間、フランはソーヴィニョンの出来の悪い地味な息子だと思われていました。実際は逆だった分けです。
また、メルロー、カルメネールとソーヴィニョンは、片親違いの兄弟です。
ソーヴィニョンの片親はソーヴィニョン・ブラン。二人の名を取ってカベルネ・ソービニョンになったわけです。出生が判明するまで、違う名前でした。
また、カベルネソービニョンはつい最近まで主要品種でなく、ボルドーでは主に
カルメネールとマルベックが主役を務めていました。
しかし、19世紀に流行した、フィロキセラという害虫のため、周りが混乱にさらされた時、
代わりに補助品種だったカベルネソービニョンが、その穴を埋めました。
それ以降、彼の有能さが認められ、椅子取りゲームのごとく、
二人の活躍の場をかっさらっていきました。
新世界に職場を移した二人ですが、そこでもまた、カベルネソービニョンがやってきて、
人気をとられつつあります。
ただ、そんなカベルネソーヴィニョンにも勝てない相手がおり、
ピノ・ノワールに対しては、新世界でも二番手になってしまいます。
メルローやグルナッシュは、カベルネやシラーだけでなく、
多くの品種の補助に入ります。
彼らはまろやかさやコクがあることで、
シラーやカベルネ、カリニャン、テンプラニーリョのような、
力強いが深みに欠ける品種をバックアップするのに適しています。
時には主役になりますが、補助として立ち回る方が、彼らにはしっくりくるようです。
ピノ・ノワールは一人で既に華やか、奥深く、複雑で、
他品種がいるより、一人でいる方が輝きます。
そして、育てるのがとても難しく、
どんどん変種が生まれてしまい、純粋なピノ・ノワールはほとんどいないとも言われています。
変種としては、
ピノムニエ、ピノグリ、ピノブランなどなど、他にもたくさんいます。
また、古くからいるブドウは自然交配で生まれましたが、
最近の品種は、人工交配がほとんどです。
日本の品種を多く生み出した、ワインの父と呼ばれる川上さんという方がおり、
マスカット・ベーリーAやブラック・クイーン、アリカント・べーリーAが川上品種と呼ばれています。
また、川上さんはアメリカや外から日本にあった品種を多く連れてきており、
ナイアガラ、セイベル、コンコードなども、それに当てはまります。
セイベルはほとんどワインには使われません。
主に品種改良のための交配品種です。
1950、2522、などなど、細かく品種番号がふられています。
ブランデーについても触れておきますね。
ブランデーはワインではありませんが、ワインから作ります。
ワインを蒸留して作るアルコールが強ーい酒で、これもフォーティファイドと同じく、
保存目的で考えられました。
こういった酒は、品種はごちゃまぜで、単一で作られるものはほぼありません。
あえて代表してあげるなら、
ユニ・ブラン(トレッビアーノ)、コロンバールです。
他にもありますが、ワインの残りカスで作るだとか、
ブドウではなくサクランボやリンゴを使う(キルシュやカルヴァドス)などもブランデーに入るため、
ブドウ品種を特定してあげるのは、やや難しいです。
でも、こちらもワインに関わりがあるため、使っていきたいと思います。
調べていくと、本当に面白いです。
雑多に書きましたが、ちょっとでも知識の足しにしていただければ幸いです。
このように、ワインは色々な要素が詰まって作られます。
そのつながりや性格に翻弄されながら、身近に感じてもらえるような、そんな作品にしたいです。
重要なマリアージュやテイスティングについてままた後ほど。
【触れておきたいワイン講座】
●テイスティング
ワインは色、アロマと呼ばれる香りで、ブドウの特徴がよく出ます。
暖かい地方、寒い地方、アルコールや糖度が高い、豊かな土地で育った、雨が多かった、太陽がよく当たっていた、海が近い、などなど、
ワインを見、味わうことでそのワインの特徴を感じ取ります。
また、ワインが悪くなっていないか、飲み頃かどうか、などといったこともテイスティングで判断します。
●マリアージュ
ワインと料理の食べ合わせ、これを結婚《マリアージュ》と呼びます。
ワインはなんでも食べ合わせがいいわけではなく、
一般的に赤ワインには肉料理、白ワインには魚料理と言われますが、
ワインによってはサラダに合わせたり、デザートに合わせたりもします。
最近では和食に合うワインも提案されているようです。
●ワインの偽造
やはり、ワインの偽造も出回るもので、似たような味わいのワインのラベルを張り替え、市場に出したり、
雑多なワインを混ぜたりして作った、粗末なものも出回ったりしています。
中にはプロでもその区別がつかないものもあるといいます。
多くは中国、香港など、富裕層がいるが、知識は豊富でない地域に輸出されているようです。
そして高級ワインは多くの審査を受け、信頼のあるルートを通って売り出されますが、
偽造ワインの多くは、個人の取引であったり、貿易会社を通さず行われます。
現在、審査を受けたラベルに認可証を施したりするなど、偽造ワインの流通を防いだり、
取り締まりを厳しくしているようです。
また最近では、アメリカで偽造ワインを売っていた人物が逮捕され、映画にもなり話題になっていました。
こういった取り締まりをする探偵のような人物もいるようです。
●病害
ワインに限らず、他の作物や農家にとっても、病害は天敵です。
シネレアは副産物をもたらしますが、多くはワイン産業に打撃を与えます。
特に、19世紀に起きたフィロキセラの流行は、ヨーロッパのワイン農家にとって、重大な事件でした。
ワインを語るのに、これはは外せない事柄です。
近年でも、第二のフィロキセラと呼ばれる、害虫による被害が流行したことがありました。
ワインの衰退にもなりますが、代わって、カベルネが注目されるなど、発展する場合もあります。
●歴史
ワインは古くから、食卓、もてなしの場に深く関わっていました。
宗教、貿易、戦争などにも関与し、流行したり、禁止されたり、世界を一周したり。
ワインを追うごとに、世界の歴史が紐解かれます。
ガメイも古くからいる品種ですが、ピノ・ノワールが好きだった当時のフランスの地方の王に、
栽培を禁止されたという歴史があります。
パロミノが作り出すシェリーも、イベリア半島に侵攻してきたアラブ人により、ワインの製造を禁じられてしまいます。
その後、シェリーはレコンキスタにより、再び復活します。
シャンパンは日本の開国に大きな役割を持ちました。
まず、ワインはブドウを原料にして作られます。
ブドウを収穫し、潰したり、発酵させたりして、お酒に仕上げていきます。
分類分けすると、
①スティルワイン(よく見かける赤ワインとか白ワインとか)
②スパークリングワイン(あわあわしゅわしゅわ、シャンパンとか)
③フォーティファイドワイン(作る過程で、アルコールの強い酒を入れる)
④フレーバードワイン(薬草とかハーブとかで香りをつけたワイン。ヴェルモットなど)
の4種類に分けられます。
①スティルワイン
さらに
・赤ワイン
・白ワイン
・ロゼワイン(ピンクっぽいワイン)
と分けられます。
赤ワインは、主に黒ブドウから作ります。
赤ワインのあの濃い色は、ブドウの皮の色から出るのです。
白ワインは色の薄い白ブドウから作るのですが、
時々、皮を取った黒ブドウからも作ります。(ピノ・ノワールがよくやります)
ロゼは作る段階で、色が濃くなる前に黒ブドウの皮を途中で除くタイプと、赤ワインと白ワインを混ぜちゃうタイプとふた通りあります。
歴史は古く、ローマ時代にはもう飲まれており、聖書にも登場します。
また、ブドウの種の周りには、タンニンという渋ーい物質があり、黒ブドウにはこれが多く含まれていることが多いです。そのため、赤ワインには渋みがあるものが多いです。
②スパークリングワイン
ほとんどが白ブドウから作られる、発泡ワインです。
(ピノ・ノワールという例外もいます)
主に食前酒やパーティで飲まれることが多い、華やかでスッキリとしたワインです。
①のワインを発酵途中で瓶に詰めてしまうことで、瓶内で泡が発生し(瓶内二次発酵)、
きめ細やかな美しい泡が閉じ込められます。
フランスの僧侶のいい加減さから生まれたワインです。
③フォーティファイドワイン
酒精強化ワインとも言います。アルコールが高めのお酒です。
イギリスやフランスの戦争に大きく関わっており、
船で輸出する際、酒とはいえ品質が悪くなったりするため、
それを防ごうと、アルコールの強い酒を足したのが始まりです。
ブドウは糖を含み、これを発酵でアルコールに変えることで、ワインになります。
発酵途中でアルコールを入れることで、その発酵を止めちゃいます。
そうすると、とろりと甘く、アルコールの強い、傷みにくい酒が出来上がりました。
船で旅するワイン、と覚えると、わかりやすいかもです。
④フレーバードワイン
あまりお店などでは見かけないかもです。
①のワインにハーブや薬草で香りづけします。
他に、①の中で《貴腐ワイン》というものがあります。
ブドウによっては、皮の厚いもの、薄いものとあり、
ボトリティス・シネレアというカビ菌がつくことで、
ブドウの水分が失われ、皮の薄いものは破れて、腐ってしまいます。
しかし、中には腐って水分が抜けることで、糖分が凝縮し、
とてもあま~いブドウができることがあります。
これをワインにしたものが、貴腐ワインです。
限定された状況下でしかできないため、高級ワインになります。
同じような原理で、
アイスワイン(ブドウが凍ることで水分が抜ける)
などがあります。
白ブドウで作るのですが、ワインの色は黄金色で、舌触りもとろりとしており、絶品です。
以上が分類分けです。
ブドウの産地ですが、
ワイン大国として知られるのは、フランス、ついでイタリアです。
特にフランスでは、地域、作る人、さらには畑ごとにブランドがあったりし、細かく格付けがされています。
同じ地域、ブドウでも、お隣さんの畑で作ったもの同士を混ぜてはいけない、など、ルールは厳しいです。
ワインベルトというものがあり、フランス、イタリア、スペイン、日本などを含む、地球をぐるりと一周した経度の範囲が、適しております(私もあまり分かっていない)
フランスには多彩な気候や土地があり、様々な味わいを楽しめます。
勉強の際はフランスから始めることをお勧めします。
元々、ワインはヨーロッパで盛んに作られていたもので、16世紀くらいにアメリカ大陸にヨーロッパの人々が移住したことで、アメリカにもワインが伝わりました。
そのため、ヨーロッパより後にワインが作られ始めた国を総称して、《新世界》と呼びます。
アメリカ、南米、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどがそうです。
おそらく日本もここに入ります。
日本に入ってきたのは、戦国時代、ポルトガルの宣教師によって、ブランデーが持ち込まれたことだと言われています。シャンパンも一緒に入ってきました。
ブランデーはワインを蒸留して作る、アルコールの強い酒です。また別記します。
このような酒は日本と交易をするために、接待のために用いられました。
こんな飲み物があるのか、と日本人の興味を引きます。
はじめに飲んだのは、織田信長という話です。
それから、明治時代くらいから本格的に栽培、生産が始まります。
ブドウによっては、土地や気候の好き嫌いがあります。
あったかいところでのびのび過ごすのが好きなブドウや、寒いところで、ぎゅうぎゅうして糖分を高めていくブドウなど、性格や好き嫌いも様々です。カベルネやメルローのように、あまり好き嫌いしないものもいます。
また、ブドウも人間と同じく、育った土地や環境が性格に反映されます。
暖かい地方で育ったブドウで作ったワインは、なんだか太陽の味がします。(え!?)
寒い地方で育ったワインは、雪で凍える大地や、冷たい風を感じます。
それから、土の香りを感じたり、その地方で咲き乱れる花の香りを感じたり。
そこまで分かるようになると、ソムリエになれちゃいますね。
いきなり、産地の話をしても、慣れない方はわからないと思います。
私がそうでした。
ブルゴーニュ、ロワールなどと言われても、いったいどんなワインなのか、さっぱりでした。
でも、ブドウ品種から入ることで、なんとなく、その地方のワインの性格がわかるようになりました。
そういう分けで、キャラクターの性格を、濃くしていきたいなと思います。
お店でラベルを見てみると、赤ワインの多くがカベルネ・ソーヴィニョンの名前があると思います。
非常にタフで、どんな土地でも、期待通り、それ以上の成績を出してくれます。
特に、南アメリカやオーストラリアなどの暖かい地域でよりパワフルになるため、多くワインが生産されています。
一方、白ワインではシャルドネが多く見られます。涼しい方が好みですが、アメリカやオーストラリアでも人気で、世界中の産地で生産されています。
ワインを作る上でたくさん決まりごとがあり、フランスではワインの法律まであります。
その中で、主要品種と言われているのが、
黒
・カベルネ・ソーヴィニョン
・メルロー
・ピノ・ノワール
・シラー
白
・シャルドネ
・セミヨン
・シュナン・ブラン
・ソーヴィニョン・ブラン
・リースリング
です。
言ってみれば、成績優秀者ですね。
これらは品質の良いワインを作り出せたり、土地への適応力が高かったりして、人気があるものです。
しかし、彼らだけでは作れないワインもあり、補助する品種も必要です。
カベルネとメルローは支え合っていますし、
ピノ・ノワールに至っては、赤ワインも白ワインもスパークリングワインも作るつわものですが、
シラーはグルナッシュやムールヴェドルという品種と活躍してますし、
逆にシュナン・ブランは補助に回ることが多いです。
主要品種にはなっていませんが、
イタリアワインの王と呼ばれるネッビオーロや、
世界三大貴腐ワインを作るフルミントやゲヴュルツ・トラミネールも外せません。
日本では甲州が絶賛売り出し中で、世界でも認められています。
ブドウ同士のつながりも面白いです。
例えば、カベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フラン、
彼らは親子です。
力強さのあるソーヴィニョンに比べ、フランは軽め、エレガントな印象を持ちます。
そのため、DNA鑑定が行われるまで長い間、フランはソーヴィニョンの出来の悪い地味な息子だと思われていました。実際は逆だった分けです。
また、メルロー、カルメネールとソーヴィニョンは、片親違いの兄弟です。
ソーヴィニョンの片親はソーヴィニョン・ブラン。二人の名を取ってカベルネ・ソービニョンになったわけです。出生が判明するまで、違う名前でした。
また、カベルネソービニョンはつい最近まで主要品種でなく、ボルドーでは主に
カルメネールとマルベックが主役を務めていました。
しかし、19世紀に流行した、フィロキセラという害虫のため、周りが混乱にさらされた時、
代わりに補助品種だったカベルネソービニョンが、その穴を埋めました。
それ以降、彼の有能さが認められ、椅子取りゲームのごとく、
二人の活躍の場をかっさらっていきました。
新世界に職場を移した二人ですが、そこでもまた、カベルネソービニョンがやってきて、
人気をとられつつあります。
ただ、そんなカベルネソーヴィニョンにも勝てない相手がおり、
ピノ・ノワールに対しては、新世界でも二番手になってしまいます。
メルローやグルナッシュは、カベルネやシラーだけでなく、
多くの品種の補助に入ります。
彼らはまろやかさやコクがあることで、
シラーやカベルネ、カリニャン、テンプラニーリョのような、
力強いが深みに欠ける品種をバックアップするのに適しています。
時には主役になりますが、補助として立ち回る方が、彼らにはしっくりくるようです。
ピノ・ノワールは一人で既に華やか、奥深く、複雑で、
他品種がいるより、一人でいる方が輝きます。
そして、育てるのがとても難しく、
どんどん変種が生まれてしまい、純粋なピノ・ノワールはほとんどいないとも言われています。
変種としては、
ピノムニエ、ピノグリ、ピノブランなどなど、他にもたくさんいます。
また、古くからいるブドウは自然交配で生まれましたが、
最近の品種は、人工交配がほとんどです。
日本の品種を多く生み出した、ワインの父と呼ばれる川上さんという方がおり、
マスカット・ベーリーAやブラック・クイーン、アリカント・べーリーAが川上品種と呼ばれています。
また、川上さんはアメリカや外から日本にあった品種を多く連れてきており、
ナイアガラ、セイベル、コンコードなども、それに当てはまります。
セイベルはほとんどワインには使われません。
主に品種改良のための交配品種です。
1950、2522、などなど、細かく品種番号がふられています。
ブランデーについても触れておきますね。
ブランデーはワインではありませんが、ワインから作ります。
ワインを蒸留して作るアルコールが強ーい酒で、これもフォーティファイドと同じく、
保存目的で考えられました。
こういった酒は、品種はごちゃまぜで、単一で作られるものはほぼありません。
あえて代表してあげるなら、
ユニ・ブラン(トレッビアーノ)、コロンバールです。
他にもありますが、ワインの残りカスで作るだとか、
ブドウではなくサクランボやリンゴを使う(キルシュやカルヴァドス)などもブランデーに入るため、
ブドウ品種を特定してあげるのは、やや難しいです。
でも、こちらもワインに関わりがあるため、使っていきたいと思います。
調べていくと、本当に面白いです。
雑多に書きましたが、ちょっとでも知識の足しにしていただければ幸いです。
このように、ワインは色々な要素が詰まって作られます。
そのつながりや性格に翻弄されながら、身近に感じてもらえるような、そんな作品にしたいです。
重要なマリアージュやテイスティングについてままた後ほど。
【触れておきたいワイン講座】
●テイスティング
ワインは色、アロマと呼ばれる香りで、ブドウの特徴がよく出ます。
暖かい地方、寒い地方、アルコールや糖度が高い、豊かな土地で育った、雨が多かった、太陽がよく当たっていた、海が近い、などなど、
ワインを見、味わうことでそのワインの特徴を感じ取ります。
また、ワインが悪くなっていないか、飲み頃かどうか、などといったこともテイスティングで判断します。
●マリアージュ
ワインと料理の食べ合わせ、これを結婚《マリアージュ》と呼びます。
ワインはなんでも食べ合わせがいいわけではなく、
一般的に赤ワインには肉料理、白ワインには魚料理と言われますが、
ワインによってはサラダに合わせたり、デザートに合わせたりもします。
最近では和食に合うワインも提案されているようです。
●ワインの偽造
やはり、ワインの偽造も出回るもので、似たような味わいのワインのラベルを張り替え、市場に出したり、
雑多なワインを混ぜたりして作った、粗末なものも出回ったりしています。
中にはプロでもその区別がつかないものもあるといいます。
多くは中国、香港など、富裕層がいるが、知識は豊富でない地域に輸出されているようです。
そして高級ワインは多くの審査を受け、信頼のあるルートを通って売り出されますが、
偽造ワインの多くは、個人の取引であったり、貿易会社を通さず行われます。
現在、審査を受けたラベルに認可証を施したりするなど、偽造ワインの流通を防いだり、
取り締まりを厳しくしているようです。
また最近では、アメリカで偽造ワインを売っていた人物が逮捕され、映画にもなり話題になっていました。
こういった取り締まりをする探偵のような人物もいるようです。
●病害
ワインに限らず、他の作物や農家にとっても、病害は天敵です。
シネレアは副産物をもたらしますが、多くはワイン産業に打撃を与えます。
特に、19世紀に起きたフィロキセラの流行は、ヨーロッパのワイン農家にとって、重大な事件でした。
ワインを語るのに、これはは外せない事柄です。
近年でも、第二のフィロキセラと呼ばれる、害虫による被害が流行したことがありました。
ワインの衰退にもなりますが、代わって、カベルネが注目されるなど、発展する場合もあります。
●歴史
ワインは古くから、食卓、もてなしの場に深く関わっていました。
宗教、貿易、戦争などにも関与し、流行したり、禁止されたり、世界を一周したり。
ワインを追うごとに、世界の歴史が紐解かれます。
ガメイも古くからいる品種ですが、ピノ・ノワールが好きだった当時のフランスの地方の王に、
栽培を禁止されたという歴史があります。
パロミノが作り出すシェリーも、イベリア半島に侵攻してきたアラブ人により、ワインの製造を禁じられてしまいます。
その後、シェリーはレコンキスタにより、再び復活します。
シャンパンは日本の開国に大きな役割を持ちました。
0
お気に入りに追加
2
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

隣の家に住むイクメンの正体は龍神様でした~社無しの神とちびっ子神使候補たち
鳴澤うた
キャラ文芸
失恋にストーカー。
心身ともにボロボロになった姉崎菜緒は、とうとう道端で倒れるように寝てしまって……。
悪夢にうなされる菜緒を夢の中で救ってくれたのはなんとお隣のイクメン、藤村辰巳だった。
辰巳と辰巳が世話する子供たちとなんだかんだと交流を深めていくけれど、子供たちはどこか不可思議だ。
それもそのはず、人の姿をとっているけれど辰巳も子供たちも人じゃない。
社を持たない龍神様とこれから神使となるため勉強中の動物たちだったのだ!
食に対し、こだわりの強い辰巳に神使候補の子供たちや見守っている神様たちはご不満で、今の現状を打破しようと菜緒を仲間に入れようと画策していて……
神様と作る二十四節気ごはんを召し上がれ!
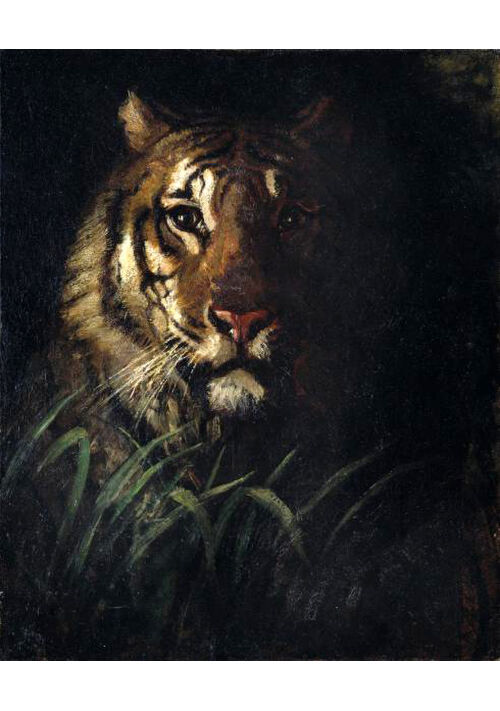
男、虎となりて人里へ流れお賃金をもらう
七谷こへ
キャラ文芸
【あらすじ】
海と山にはさまれたのどかなある田舎町に、ひとりの男が流れついた。
男は、なんの因果かある日虎へと姿を変じてしまった元人間であった。
虎へと変わった直後は嘆き、苦しみ、山のいただきにて涙を流すこともあったが、冷静になってみると二足歩行できるししゃべれるし住民も受けいれてくれるしでなんやかんやそこに住むことになった。快適。
その町の小さな書店で働いてお賃金をありがたくいただきながら過ごす日々であったが、ある日悲鳴が聞こえてある女性を助けると、
「その声は、トラくん!? もしかしてぼくの友だち、ペンネーム『✝月下の美しき美獣✝』のトラくんかい!?」
と昔のペンネームを叫ばれ、虎は思い出したくない黒歴史におそわれ情緒がぐっちゃぐちゃになるのであった。
【表紙】
アボット・ハンダーソン・セイヤー『トラ』1874年頃

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

月宮殿の王弟殿下は怪奇話がお好き
星来香文子
キャラ文芸
【あらすじ】
煌神国(こうじんこく)の貧しい少年・慧臣(えじん)は借金返済のために女と間違えられて売られてしまう。
宦官にされそうになっていたところを、女と見間違うほど美しい少年がいると噂を聞きつけた超絶美形の王弟・令月(れいげつ)に拾われ、慧臣は男として大事な部分を失わずに済む。
令月の従者として働くことになったものの、令月は怪奇話や呪具、謎の物体を集める変人だった。
見えない王弟殿下と見えちゃう従者の中華風×和風×ファンタジー×ライトホラー
※カクヨム等にも掲載しています

八奈結び商店街を歩いてみれば
世津路 章
キャラ文芸
こんな商店街に、帰りたい――
平成ノスタルジー風味な、なにわ人情コメディ長編!
=========
大阪のどっかにある《八奈結び商店街》。
両親のいない兄妹、繁雄・和希はしょっちゅうケンカ。
二人と似た境遇の千十世・美也の兄妹と、幼なじみでしょっちゅうコケるなずな。
5人の少年少女を軸に織りなされる、騒々しくもあたたかく、時々切ない日常の物語。


💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活
XD
恋愛
誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















