15 / 19
本編
大きな赤い宝石と白無垢人形のイヤリング 後編
しおりを挟む
3日後の例の西村の友人大阪優斗が訪ねてくる朝のこと、琢二は店先に看板をかけると遠くから尚が走ってくるのを見かけ、慌てて店の奥に入った。数分も経たぬうちに尚は入ってくる。
「しおちゃん!おっはよー今そこで琢二さんの姿見かけたから急いで来たんだけど、どこにいるの?また店の奥?それとも隣?」
言葉通り全力疾走してきたらしくはぁはぁと肩で息をしながら、カウンター越しに店奥を覗き込みながら言った。
呆れ顔のしおりは、そばにあった塩の塊を尚の頭と肩に乗せると、くるっと尚の向きを変え、店から追い出した。された尚はびっくりである。憤慨しながら、これはどう言うことかとしおりに詰め寄る。
「ちょっとこれはどういうこと?!こんなことされる必要ないと思うんだけど!?」
「オーナー命令ですので。それ以上はなんとも。店にとって害あるものとしてオーナーが決めたことですから、私に言われても困ります。尚さん、こないだ私言いましたよね?勢いがあって突撃してくる人はオーナーが嫌いなんです。」
「嫌いだからってこんなことする必要性ある?」
「もっと言いましょうか?仕事をサボったり、ドタキャンしたりする人はオーナーの地雷を踏むんですよ。ていうか踏んじゃったんですよ、尚さん。こないだ。見るのも嫌だっていう人に自分の職場を荒らされたくないんですよ。オーナーがいない時で私に永遠と愛を語るぐらいは許しますけど。」
「えー。何その地雷ー。しつれーい。まぁ確かにぃ?荒巻かなともをだしに店に来たことは謝るけど、塩乗っけるとかなくない?そこまで嫌われてんのー?心せまーい。でもそこがかっこいいー!!」
怒ったり、笑ったり、呆れたりする尚に、「すまん」と誤った西村の困った顔を思い出すしおり。そんなこんなで店先であーだこーだと言いやう二人の元に、荒巻がやってきた。尚の顔を見ると、心底嫌そうな顔で「何故お前がいるんだ」と言いたげな感じではあったが、チラリと見るだけで店内に入っていった。
尚は、そんな荒巻のことも「心がせまいやつ」としか見れないのか、またねと言ってカフェの方に入っていった。ふと、遠くから手を振っている男性二人が目の端に写ったのを感じだしおりは、そちらの方をむく。するとそこには、ラフな格好をした西村と、青いポロシャツに黄土色のチノパンを履き、大きなリュックを背負って立っている男を見つけた。
「おーいしおりさーん。おはよう!さっきの尚だろ?あいつ何しに来たんだ?」
「いつものオーナー見つけた。です。」
「あぁ。で、あいつに本当に塩乗っけたのか。」
「えぇ、心が狭いだの嬉しいだのと色々言ってましたけど、多分理解してないですね。」
「だろうなぁ。あ、そうそう忘れちゃいけねーや。こいつがフィギュアを作ってくれる大阪優斗。」
大きなリュックを下ろしながら、ペコリと頭を下げる優斗。そして、にこりと笑った。
「よろしくお願いします。大阪優斗です。」
「こちらこそ、お願いします。依頼人はもう中に入られたのでどうぞ。」
しおりは、優斗を店の中に誘う。優斗、しおり、西村の順で店に入る。冷房が効いてひんやりした店内は、とても心地よい。朝すぐに冷房をつけておいて良かったなとしおりは思った。
「あぁ、いらっしゃいませ。当店つくもがみ骨董店店主の篠原琢二です。しおちゃ・・・・じゃなかった、そっちの女性は日比野しおり、ここの店員です。そして、こちらにいらっしゃるのが、依頼人の荒巻かなとも様。」
「よろしくお願いします。大阪優斗です。」
「よろしく。荒巻かなともよ。このネックレスに憑いている者を具現化した感じのフィギュアを作って欲しいの。」
優斗に赤いネックレスを手渡しながら言った。
「ついてるですか?どういうこと?」
「この店、曰く付きが多いって話したろ?」
「うん、それは聞いた。」
「それにも憑いてんだよ。赤髪でスペイン人の若い女性が。」
なんともなしに当たり前のように優斗に説明する西村。その様子を見ながら、琢二はしおりに耳打ちをする。
「西村、うちの臨時店員でも十分やっていけそうだよね。」
「むしろもう臨時店員では?」
コソコソと話す二人に、西村は首を傾げる。優斗は「赤髪かぁ」と言いながら、スケッチブックと色鉛筆を取り出した。そこにスッとカーネーションの香りが過ぎ去った。過ぎ去った方向を見ると、彼女が立っている。フワッとスカートを持つとお辞儀をする。まるで地位の高いに淑女がカテーシーをするように。それに合わせるように有線から軽やかなギターの音が鳴り響く。
店内はまるでフラメンコの舞台のようになった。情熱的にそして悲しげに踊る「フラメンコ・レディー」。
その様子を必死にスケッチブックに描き留めていく優斗。一曲分踊りきると憂いの無くなった晴々とした顔で「フラメンコ・レディー」は消えていった。興奮したかのように優斗は、消えていった方向を指差しながら喋る。
「すごい!すごいよ!!こんなの初めてだ!たくさんスケッチしたけどまだ足りないなぁ。どこかにフラメンコ教えてるところないかな?そこにいけば・・・・」
興奮冷めやらぬ優斗の様子に、3人は呆気に取られる。そんな様子にいつの間にか隣からケーキセットを持ってきていた西村が皆の前にプレートを置きつつ、苦笑して言った。
「優斗はああなると落ち着くまでほったらかしでいいよ。それよりこれを見てくれ。スペインの国花はカーネーション!ってことでカーネーションをモチーフにしたケーキをどうぞ。珈琲は、ブルーマウンテンを用意してみた。」
カーネーションの花びらのようなフリルがいっぱいのったピンクと黄色のクリームに、マンゴーが挟まったショートケーキが目を楽しませてくれる。珈琲の香りが漂う店内で荒巻としおりは、ケーキに舌鼓をうった。
琢二は、面白そうにケーキを食べながら、興奮してあーだこーだと一人騒がしい優斗を見て笑っている。その横で、「あいつの分も用意したけど食べるかな」と言いながら、自分ようにとっておいたケーキを食べる西村。そんな楽しげな様子だったが、12時になった時計から鳩が飛び出てくる。
「あー、もう12時か。昼ごはん前にケーキとか食べちゃったな。昼ご飯にすれば良かったか?」
失敗したなーと西村が反省したように言ったが、女性二人はフルフルと頭を振ってグッジョブと言った。そして、そういえばと言葉を続けた。
「尚の同級生がどうも例の人形のアクセサリーを持っているんじゃないかって話なんだよなぁ。」
「そうなの?」
「らしいって話で、実際どうなのか知らないけど尚に聞いてみる?隣でちょっと青い顔してたけど。風邪ひいてんのかなあいつ。」
「聞いてみるのは構わないが、僕は奥に引っ込むよ。彼女は嫌いだ。」
「だと思いましたー。そのつもりで呼ぶんで大丈夫ですよ。でも荒巻さんはいてくださいね。さすがに持ち主いないと合ってるかわからないから。」
「もちろん。」
「彼女の好きなお菓子取ってきます。」
西村が、歩きながらそう言うとしおりは奥から「尚さん用」と書かれたお菓子ボックスを持ってきた。しばらくするとあーだこーだ言い合う男女の声が聞こえたかとおもうと、扉がカランと音を立てて開き、もっと大きな声でぎゃぁぎゃぁ言い合う男女が入ってきた。その二人のこえで我に返った優斗が一言言った。
「なーかず、うるさい。」
「「まとめんな!!」」
一斉に優斗にツッこむ。二人からの抗議にニヤニヤしながら、対応している優斗にしおりはふふふと笑った。
「あれー。琢二さんまた中に入っちゃったの?私の話は聞かないっていうのー?ひどいなぁ。」
「とことん嫌われたんだろ。」
「なーさま、猪突猛進で他人がどうなっても知らない感じだもんね。」
「ちょっと二人ともひどくない!?いつあたしがそんなことしたっていうのよ。」
「こないだ、私をだしにしてオーナーさんに会いにきた人が何を言ってるのかしら?」
食ってかかる尚を尻目に珈琲を飲んでいた荒巻が言った。
「そ、それは申し訳なかったっていうか。ごめんなさい。」
素直に謝る尚。珍しいこともあるんだなとおもう3人。
「で、用件を早く言ってください。」
しおりは、隣の琢二がさっきまで座っていたであろう椅子をポンポンと叩くと尚を座らせ、耳元で「さっきまでそこにオーナーが座ってたんですよ」とささやいた。一気に顔が輝き上機嫌になった尚は、「尚さん用」お菓子ボックスからクッキーの包みをとると食べ出して言った。
「学校の同級生にね、あぁ、アクセサリー科の子なんだけどちょっと様子がっていうか、ちょっとどころじゃないぐらい変なの。というか怖い。髪を結った白無垢のスペイン系の女性が怒った状態で彼女に張り付いてるのが、時々鏡ごしで見えてさー。みんな怖がって近づかなくなっちゃったんだけど、最近全然見かけなくなっちゃって噂では下半身付随になって実家に帰ったとか死んだとか言われてんの。で、ここからが本題なんだけど、そのアクセサリーどこ探しても守んちに無いんだって!」
「白無垢の女性・・・・」
そう言うとゴソゴソとカバンの中から液晶が大きなタブレットを出して、これかしらと尚の前に画像を出した。
「そうそうこれこれ。ここに通い始めたあたりかなぁ、ちょっとなんだろ見えるようになったって言うか、なんとなくだけどわかるようになってきて、さすがに鏡越しで見えるようになっちゃったら、マジじゃない?」
「マジだな。俺も似たようなもんだけど、お前のその同級生ってさ、男っぽい名前のやつ?確か「まも」なんとか。」
「そこまで言っててなんで覚えてないのよ。「まもる」よ、ま・も・る!」
西村の釈然としない物言いに、尚はあきれ返った感じで叫んだ。するとどうだろうか、さっきまで静かだった「フラメンコ・レディー」がカタカタと揺れ出した。
カタカタからガタガタと揺れだし、店中のモノたちが揺れ始めてまるで地震が起きているように揺れ出したが、どれも落ちる気配は無い。そのまま数分揺れると何事もなかったように一瞬にして止まった。
「正解のようですね。」
「これって正解っていうの?」
しおりの納得したような言葉に、疑問を浮かべた荒巻が困ったように言った。
「それは、何か由来があって揺れてんだろう。誰かの持ち物だったとか、モチーフがこの「フラメンコ・レディー」みたいだったとか。」
「オーナー、出てきていいんですか?」
「隣は何も感じなかったそうだが、さすがに尋常じゃないぐらい店が揺れたしな。しかも腰より下は揺れてない。最初見たときは悪い感じもなかったし、いつの間にかこの店に馴染んで気配が分からなくなってしまったものだ。何かあるんでしょう?荒巻さん。」
店奥から顔を出した琢二は、こちらを見ている尚には目にもくれず、真剣な顔で荒巻のそばにしおりと入れ替わるように座った。
「私の妹クリスティンの父方のケイライド家のものよ。知らない間に家のギャラリーに置いてあって、長期出張に行く前に彼に教えて和解したばかりだったの。置いていった犯人は多分クリスティンの実母だと思うの、でも自分でもこんなの作ったっけなって思うぐらい自然と馴染んでて分からなかったんだけど、最近盗まれたって話したら、悲しそうな顔をしてたけど、ただ「そうか」って言われただけで何も言えなくなってしまって。」
「もしかして、関わる人の中に下半身付随の方がいるのでは?」
「どうして知ってるの?妹が下半身不随だわ。」
びっくりした顔で荒巻は、琢二の顔を見た。
「さっき僕が言ったこと覚えてます?「腰より下は揺れてない」って。腰より下が動いてないということはそういうことだろうさ。しかしまいったな。加島さんの言う通りならば、またどこかに行ってしまったか、誰かに持って行かれたってことならば、待つしかないかな。」
「近いうちにやってきそうですけどね。特にあの人のとこから。」
「ありそうなんだよなぁ。良くも悪くもあの人が持ってきたものだしな。」
しおりと琢二は、困った顔で互いの顔を見ながらそして他の4人の方に体を向けると、はぁとため息をついた。
「ねーねーそれよりさぁ、守はどうなったと思う?」
ため息をついて椅子に座り直した二人に、尚は作業台に突っ伏しながら言った。
「噂通りなんでしょうね。まぁ、最も妹さんと”同じ”では無いでしょうけど。」
何がなんでも尚と話をしたくない琢二は店先をずっと見ているため、しおりは琢二の代わりに答えた。答えたが、しおりの言った言葉に優斗は、意味を理解してしまい背筋が凍るのを少々感じて身震いをして言った。
「こえぇ。」
怖いと身震いする優斗のそばで青い顔をしている西村を見てしおりは、畳み掛けるように言った。
「怖いでしょう?これが貴方が行った代償ですよ?西村さん。貴方が発端ですからね?分かってます?」
「もう嫌って言うほど感じてるよ。ヴィーナスにしろロレックスにしろ、アクセサリーにしろ、本当にこの店に曰く付きしかないってことぐらい感じてるよ。でもさ、なんで「フラメンコ・レディー」じゃなくて、そっちを持っていったんだろうな。」
ふと西村は、目立つ「フラメンコ・レディー」ではなく、白無垢人形の方を持っていったのかが気になりそんなことを言う。
確かに、と皆はうーんと悩み出したが、尚がポンと手を叩くとある雑誌を取り出した。
「そうそう、この雑誌にさぁ載ってたんだよね。その白無垢のやつ。ほらコレコレ。これに「珍しい荒巻かなともの和装アクセサリー」って書いてあるの。」
「こんなの出てたの・・・・ていうか、これどこの雑誌?うちのギャラリー、取材は勝手にできないようになってるんだけど。」
「ケイティーっていう雑誌だよ?確か荒野クリスティンの特集やって本人に怒られたとこ。未だにパパラッチみたいなことやってあっちこっちのアーティストの神経逆撫でして記事書いてるみたいだけど。守、これ見て気がついたんじゃないかぁー。盗品って気がついてたなら、返せばいいのにね。野心家って話だったから、これを気にお近づきになれたらとか思ってたのかな。」
「「お前みたいにな。」」
「ちょっと!いつアタシがそんなことしたって言うのよ!!」
「私と話をするっていう名目で毎日店に顔を出しに来るのはそういうことでは?まぁ暇なんで別にいいですけど。」
「うー。」
優斗と西村が笑いながら、尚に総ツッコミをし、言い返す尚にトドメをさしてくるしおりに、膨れっ面をして拗ねる尚、それぞれ楽しそうに言い合いをしながら、時間がすぎた。
1時間ぐらいなんともない話をしながら、ふと優斗が言う。
「その白無垢の人形ってこんな感じの人形っすかね。」
スケッチブックに白無垢女性と紋付袴の男性を描いて見せる。ふとしおりにはその白無垢女性が笑った気がして、あぁモノは無くてもここには戻ってきているんだなと感じた。
「優斗さん、それもフィギュアにすることって出来ます?」
「ん?出来るよ?なんかねー今降りてきた感じだったんだよね。帰ってきましたって聞こえた気がしてさ。」
「そうですね、帰ってこられたんですよ。今。」
優斗としおりは顔を見合わせてふふふと笑う。そんな二人を見て琢二は、
「荒巻さん、この白無垢女性と紋付袴の二人がどんなだったかをフィリップさんに聞いて、彼に詳細を渡してください。優斗くんは、「フラメンコ・レディー」を出来るだけ凛々しくかっこいい女性として作って欲しい。店頭に飾れるような感じでね。」
「わかりました!荒巻さん、これ僕のメールアドレスです。写真とかがあれば嬉しいけど、無ければ家族の人の写真とかでもいいです。「フラメンコ・レディー」の方は今からフラメンコ教室探して通って作ってきます!出来上がりは来月とかになるかもしれないですけどそれでもいいですか?」
「わざわざフラメンコ教室通うの!?すごいねキミ。」
「優斗はこだわると、とことんこだわるからなぁ。」
「優くんは、こだわり強すぎるんだよ。」
「うるさい。こだわりがなさすぎるなーさまよりマシ。」
「なんですってぇ!?」
ぎゃいぎゃいと言い合う3人。そんな3人を放っておく店主と店員と帰り支度を始めた荒巻。
「フィリップには、フィギュアが出来上がり次第ここに来るように伝えます。もし、アクセサリーが戻ってきたなら、それも一緒で。「フラメンコ・レディー」は、フィギュアと一緒に買ってくれる人が来るまで、ここで預かっていてください。」
「わかりました。店頭に出す際はまたご連絡を差し上げます。イヤリングの方もかしこまりました。」
カランカランと軽い音を鳴らして店先の扉を開けると、深々と頭を下げて荒巻は帰宅の途についた。言い合いをしていた3人はそれぞれ、荒巻が出ていくと帰り支度を始めた。そして、優斗はニコニコと笑うと「じゃあ1ヶ月後ぐらいに!」と元気よく言うとスキップしながら帰っていった。尚は、奥に早々に引っ込んでしまった琢二を恨めしそうに見ていたが、相手にされないことを確認するとしおりに「バイバーイ」と言って肩を落として、帰っていった。
西村はと言うと、食器とポットを両手に持ち、しおりが開けたカフェに繋がる扉を通り片付けに行った。琢二は尚が帰ったことを確認すると「尚さん用」ボックスを持って定位置に置いて、しおりに声をかけた。
「しおちゃん、イヤリングは帰ってくると思うか?」
「実物がですか?憑いたものがですか?」
「両方。憑いたものはさっき帰ってきたが。」
「さぁ、どうなんでしょうね。さっきも言いましたけど、足代さんが持ってきそうです。何かしらの形で。」
「そうか。その時はよろしく。正直、僕はあの人にはあまり会いたくない。」
1ヶ月後の昼、嬉々として優斗が店に現れた。そして作業台兼カウンターにぺシャリと突っ伏した。
「聞いてくださいよー。フラメンコって女性だけが踊るんじゃないんですねー。粘り強く交渉して踊る方もやってみたんですけど、あれはむりだーほんと無理ー。でもトケが上手って言われたんで、そっちで通うことにしたんですよー。」
「君、フラメンコ教室本気で通うようにしたの。で、トケって何。」
「あー琢二さん!こんにちわ。トケはギター演奏のことですよ。エレキギターは触ったことあったんで、その応用が効くんですけど、踊りは無理っすね。後学のための勉強の一環で始めることにしたんですけど、親にびっくりされました。」
「急にそんなこと言い出せば、そりゃぁびっくりされるだろ。で、そんな1ヶ月で出来上がったのが、これか。今にも動き出しそうだな。」
軽やかにそして凛々しく踊る赤髪の女性の人形を作業台の真ん中に置いて、笑いながら琢二は言った。
ふと、しおりはスッと横から赤い髪が揺れるのを感じてそちらの方を向くと、目の前に彼女が来たことに少々驚いた。いつも驚かせてくれる。上から下まで隅々見渡すと「さすが私ね、かっこいいわ」と囁いて楽しそうにクルクルと回った。
「ところで、白無垢女性はどうなりました?」
「あ、あれね、一応写真とか見せてもらったんだけど、中々うまくまとまらなくって苦労してるんだよね。こないだスラスラって描いたのが嘘のように全然描けないんだ。」
クルクルと回る「フラメンコ・レディー」に目線をやりつつ優斗と会話していたしおりだが、優斗の「描けない」という言葉に、手を顎に添えると考え込んだ。
「まだ、その時じゃないんでしょうね。」
「そうなのかな、あの時は確かに「ただいま戻りました」って聞こえたからなぁ。この人に聞かせるためだったのかな。あれ。」
「かもしれませんね。あれから一度も声も姿も見えませんからどこか遠くに行ってしまったのでしょうね。」
優斗としょんぼりした顔でしおりは、ため息をつく。そんな二人を横目で見つつ、再び店奥に入っていった琢二と入れ替わるようにカランカランと隣の喫茶店から、扉を開く音がして西村が顔を出した。
「よぉ、優斗来てたんだな。来てたんなら言えよ、お前の分の食事ないぞ。」
「一弥はいつもここに昼ごはん出しにくるの?」
「ここの店主も、しおりさんも料理が壊滅的にダメでな、黒い物体しか作り出せないからビルオーナーの命令でずっと俺が賄いとして作ってんの。今なら店に出さない賄い料理をお前にも食べさせてやれるんだが、いるか?」
「そんなこと言われたら、いる!って言うしかないよね。一弥のご飯って美味しいよね、奥さんになる人いいなー。一弥、僕の嫁に来ない?」
「絶対やだ。なんで俺がお前の嫁にならなきゃならねーんだ。」
しおりの前にプレートを置きながら、優斗とそんな話をする。男同士の和気藹々とした雰囲気を楽しみながら、しおりはお昼の賄いに手をつけた。
「今日の賄いは、ビルオーナーの独断と偏見による地中海料理!チョリソとひよこ豆の煮込み、海鮮のパエリア、空豆のポタージュ、レアチーズのエスプレッソソースがけです!」
「何その、料理名。」
最初は元気よく言いつつ、徐々に声を落としながら一気に言い放った西村に、優斗は唖然とした顔で言う。
「仕方ないだろ、オーナーの言葉そのままなんだし。本当は、パエリアより蕎麦とかとうもろこしとかでガレット作りたかったんだけど、なんでかパエリア愛のオーナーに一蹴された。」
「洋上さんは、一時期毎日朝昼晩とパエリア続きで、奥さんが心底海鮮は3ヶ月ぐらいは見たくないって言わせるほどのパエリア愛が物凄いからな。」
「何それ怖い。」
店の奥から琢二が、急須と湯呑みの乗ったお盆を持ってきながら、呆れた顔で出てきた。台にお盆を置くと3人分の湯呑みにカランと氷の入った急須からお茶を入れると、優斗としおりの前に置いた。それを見て「じゃ、待ってろ優斗、お前のも持ってくる。琢二さん俺にもお茶ください」と、琢二に言うと喫茶店のほうに歩き出した。
「あいつ、こっちで自分も食べる気だな。」
「そうでしょうね。たまにはいいんじゃないですか?」
ふふふとしおりは笑った。ややあって、西村は”二人分の”賄いを持ってきて、作業台の上に置いた。
「そういや、例の人形を持って行ったやつ、あのあと色々聞き込みして回ったんだが、いまだに行方不明らしい。捜索願も出されてるけど家族も友達も行方が本当に分からなくて、ほぼ諦めてるそうだ。」
「樫屋さんだっけ?その人。」
「そう樫屋守。あと、荒巻さんとこで盗み働いたやつは、1ヶ月前に彼女がここにきた同じ日に風呂場で首を掻っ切って死んでんのを家族が発見したんだと、それはもうひどい形相で死んでたらしいから、ってテレビ見なかったの?」
「お前な、飯食ってる時にそんな話すんな。あと、うちにはテレビなんてものは無い。」
食べながら、そんな話をする西村に呆れながら琢二が言う。
「テレビ無いの、世間事情は何で得てんの琢二さん。しおりさんは?」
「私は、携帯のニュース見てます。テレビは情報量と画面越しに見えるナニカのせいで疲れるんで。」
「僕もしおちゃんも見えちゃうから、テレビは鬼門なんだよね。」
琢二としおりのちょっと困った顔と言葉に、「あぁ。」と言って何かを察した西村はそれ以上何も言わなかった。黙々と食べていた優斗はふと、
「その風呂場でっていう人さ、レディア・アレクサンドさんと同じ死に方だよね、それ。」
「そういやそうだな。これも因果関係あんの?」
優斗の言葉に「そう言えば」と付け加えて西村は、しおりと琢二の方をむいて言った。
「そうですね。多分、その樫屋さんって方はそれだけじゃ無いんでしょうけど。」
「何、まだあんの。怖いなぁもうこの店。絶対まだなんか出てくんだろ。俺のせいだけど。」
はぁ、とため息をつきつつ、自分の作った料理に舌鼓を打ちながらそんなことを言った。
「まぁ、西村さんのせいでもありますけど、おかげでっていうのもありますよね。特にロレックスとか。」
「あぁ、あれなぁ。元の持ち主のとこに戻ってったやつだろ?でもまだあの関係もまだ続きそうなんだろ?」
「どうやって”来る”かは分かりませんけど、次でおしまいでしょうねぇ。今回のこれもここで終わりが一番いいんでしょうけど、まだ時間かかりそう。そうだ、オーナー、荒巻様に電話をしないといけませんね。フィギュアはこうして届いたので。」
「そうだな、店頭にも飾らないとな。こいつが売れるのはいつになるやら。」
「誰が買うんでしょうね。後で値段交渉しないと。何となく関係する人が来そうですけど。」
店の扉に寄りかかっている「フラメンコ・レディー」を見ながら、ふと彼女の目に優しいものが写っているように見えたしおりは優しい気持ちになりながら言った。
昼を食べ、4人分のプレートを回収した西村は「じゃ、また今度!」と優斗に手を振ると喫茶店に戻っていった。西村が戻っていくのを確認しすると、優斗は席を立つと、
「白無垢の方は、何か進展あったら連絡お願いします。僕も何か起きたら一弥経由で知らせますね。」
「あぁ、勉強がんばれよ。」
「はい!じゃぁまた今度!」
元気に返事をして優斗は、店を出た。喫茶店方向に歩いていく彼の後ろ姿を目で追いながら、しおりはふと琢二に言った。
「彼もまた何かの因果を持ってきそうですね。」
「あぁ、特にロレックスの子に関係しそうだよな。」
「盗ってった方ですか?」
「そう、盗ってった方。」
琢二もまた優斗が出て行った昼下がりの午後の通りを見ながらため息をついた。
優斗が人形を持ってきた日から4ヶ月が経ったある日のこと、尚がとても困った顔をしてちょうどお使いでしおりのいない店内に入ってきた。
「あ、琢二さんだー。しおりんいないの?あのねー、あたしと話したく無いのはわかってるんだけど、この店の前で号泣してる外国人がいるんだけど、どうしよう?」
「外国人?どれ見て泣いてる。」
ものすごく遠慮がちに、そしてものすごく困った顔をしている尚にちょっとびっくりしている琢二は、続く言葉を促すように尚に向き直った。
「ほら、優斗が作った人形があるじゃん?アレの前。滝のような涙で泣いてて、すっごく異様。」
「買い手が来たか。」
尚の困った顔を見つつ「案外早かったな」と独りごちると、足早に店を扉を開けてそとに出てびっくりした。さめざめと泣いているものだと思った琢二は、大の大人がわんわん泣いている様を見て、若干どころかとってもひいた。その男を目の前にしてお使いの入った籠ごと手元から落下させ慌てているしおりの姿を発見して、頭を抱えた。卵割れてないといいけど。と。
「あの、うちの店の前で何をしているんですか?」
恐る恐る何喚いている男の肩を叩いて、琢二は聞く。
「Quién eres tú?」
帰ってきた言葉は、聞き覚えのない言葉だった。
「・・・・誰か、通訳!!!」
「荒巻さん呼びますか?」
「お願いしおちゃん!多分関係者!!」
「Es esto algo que vendes? ¡toma esto! Esta es ella! Se llama Lady. Estas escuchando?」
矢継ぎ早にしゃべる男性に四苦八苦しながら、琢二は店の中に連れていく、しおりはそんな様子を横目で見つつ籠の中の卵を見て割れていないのを確認すると、尚に「籠を持って一緒に入ってきて」と籠を渡すと、店の電話で荒巻に電話した。
「あ、荒巻さん!今大丈夫ですか?」
「えぇ、大丈夫だけど、どうしたのそんなに慌てて。」
「フラメンコ・レディーの前で号泣していた外国人の方がいらっしゃるんですが、言葉がわからなくって困ってるんです。レディーって言ってるのだけ聞こえてて、あの人誰って状態です。早くきてください!というか助けて!」
とても早口にしゃべるしおりに若干気圧され気味の荒巻は、「今近くにいるからすぐいくわ!」と答えると電話をきった。
30分経っても未だ言葉が通じずに四苦八苦してる琢二と謎の外国人の二人を見ながら、困り顔のしおりと尚は隣から何事かと覗きにきた西村が、ちょうどその手におやつを持ってきたことを見てこれ幸いと男二人の間にずずいと割って入った。
「とりあえず、ティータイムにしませんか?」
「la hora del té?」
「いいな、話が通じずに困ってたんだ。」
しおりに促され、謎の外国人と琢二は席につく。その様子を確認すると西村は紅茶のポットと、蜂蜜の匂いのするケーキを机においた。
「今日のおやつは、カモミールとグレープフルーツのフレーバーティー、蜂蜜とリンゴのカスタードケーキの爽やかセットだよ!」
恐る恐るティーカップに手を伸ばし、一口飲んでから謎の外国人は一息ついた。そしてフォークでサクリとケーキをさすと少し匂いを嗅ぎながら、口へと入れとてもにこやかに微笑んだ。
その様子を見つつ、一時休戦とばかりに琢二もそれに倣った。尚は、しおりに「喫茶店のほうにいるから終わったら教えてね。結果が気になる」と言い残し、西村に手を振ると喫茶店のある扉の方に向かった。時同じくして、尚と入れ替わるように店の扉が開き荒巻が飛び込んで来た。
「グリス!!」
「Aramaki!」
「あなたどうしてここにいるの!?スペインに帰ったんじゃなかったの!?」
「Regresé a España una vez.でも、呼ばれてる気がしてまた戻ってきた。」
「「え、こっちの言葉喋れるの!?」」
急に外国語でないこちらの言葉を喋り出したグリスという名の男にびっくりするしおりと琢二。何だかよくわからないけど、荒巻が来たなら、彼女の分も用意しようと西村は席を立ち、喫茶店の方に向かい手に新たにケーキとティーカップを持って再び現れると、荒巻に席につくように促して西村は店の奥に引っ込んだ。
ケーキとフレーバーティーを食べて飲んだ後に荒巻の胸ぐらを勢いよく掴むと荒々しく揺さぶりながら叫んだ。
「なぁ、Aramaki。レディーの人形がこんな店にあるんだい?知ってたのか?あんな生きてる時には見かけなかった人形はどこで手に入れたんだ?あんなのがあるならこの僕に教えてくれたっていいじゃないか!無くなったなんて嘘だったんだろう!?」
「ちょ、ちょっとグリスさん!待ってください!確かに荒巻様の家からあのネックレスは盗まれ、そして色々なところを回ってこの店にたどり着きました!」
「だったら、この女に教えればよかったじゃないか!!彼女が!!生きてる間に!!見せれたかもしれないじゃないか!!!」
「あれが盗まれたのは、レディーが死んでからよ!!」
「だったら、何で!!早く!人形も一緒だったんだろう!!」
「人形は僕が4ヶ月前に作ったんですよ?」
叫んだグリスに答えるように、優斗が店に入ってきた。「ああいいところに・・・・」と続けた琢二は、にこやかにとても嫌な笑顔を貼り付けた足代が優斗の後ろにいるのを見て、苦々しい顔をした。
「あら、どうしたの琢二くんそんな顔をして、日比野さん久しぶりね。何とかやっていけてるみたいじゃない。どうしたの?この男の子知り合いかしら?あぁそれと表に見えてる赤いネックレスなんだけど、あれうちの店にくれないかしら。あんな人形どこで見つけてきたの?あれがあるんならうちでも扱えるじゃない。ね、鍵どこ?持って帰るわ。」
「すみませんが、足代さん。そのネックレスはここにいるグリスさんが購入されることになっていますから、勝手に持って帰ろうとしないでください。」
「そうなの?じゃぁ、そのグリスさんから買うことにするわ。いいでしょ?300万でどう?赤い宝石なんて男の人はいらないでしょ?恋人にやるならそんな人形付きよりもいいものがうちにあるわ。これとかどう?白無垢人形のイヤリング。最近、店に来たイヤリングなんだけど、服飾専門学校に通ってた子の持ち物なんだけど、いらないって言われたから買ったのよね。琢二くん、あなたのとこなら扱えるでしょ?変なものいっぱいあるもの。で、そこのグリスさんとやら、300万で買ってあげるからそのネックレス私にくれないかしら?」
長々と喋り続けていたが、グリスに向き直ると馬鹿にしたような声で何度も「300万で買ってあげる」と催促した。
そんな足代の様子を見ていた荒巻は、声に若干の怒気を含ませて静かに言った。
「おあいにくですが、そのネックレスは私のギャラリーから盗まれた盗品なんですよね。ですので、所有の権利はこの店の店主にあるのではなく、私にあるんです。私が、店主に預かっておいてくれと頼んだものを貴女が持っていくですって?しかも「買ってあげる」などと、強引な。そもそもこのネックレスは私の友人に送るプレゼントだったもの。貴女に所有の権利はありませんよ?」
「あら、だから買ってあげるって言ってるじゃない。」
「これは彼女の遺品だ!貴女に渡すわけないじゃないか!」
「人形がってこと?それともネックレスが?」
「どっちもだ!!」
「でもさっきそこの男の子が「僕が作った」って言ってなかった?」
「足代さん、荒巻様からお願いされてその子が作ったんですよ。」
「じゃぁ、そのネックレスと人形のセットをこのイヤリングと交換ってどう?いい考えでしょ?で、300万でグリスさんがうちから買うってのはどう?」
「貴女、人の話聞いてるの?」
荒巻は、言葉が全く通じてない足代を見て驚愕した。と同時にグリスは「何だこいつ!?」という顔もした。
「それ、結局足代さんが得するだけの提案ですよね。イヤリングは何だか嫌な感じがするから、オーナーに押し付けたい。かといってネックレスと人形のセットは捨てがたいから、代わりに買ってくれればそれでいいって感じですか?」
「そうよー。何だ日比野さんはわかってくれてるじゃない。貴女なら売ってくれるわよね?」
「いやです。」
「あらどうして?いい提案でしょ?」
「いいえ。足代さんが入ってくる前に商談は成立しているので、無理です。それに行き先が決まったものは変えられないんですよ?もちろん、そのイヤリングも。」
しおりは目線を足代の手にやると、ティーカップを持って少し飲むと再び足代の方に向いて言った。
「それ、うちの店から盗まれた盗品だって知ってました?」
「え。」
「その持ってた女性、下半身付随で精神崩壊してて要領が得ないとして家族の誰かが売りに来たんでしょう?」
「え、えぇそうよ。どうしてそんなことを知ってるの?調べたの?」
「足代さんは知っての通り、私は分かるので。オーナーもわかってますよ?それ探してたんです。行方が分からなくなってたので、よかった。持ってきてくれたんですね。足代さんが。」
最後の言葉を強く言うと、足代の手から滑り落ちるようにしおりの手に収まった。手元に戻ってきたイヤリングをしおりは、荒巻の目の前に置く。
「荒巻様、お客様のギャラリーにて盗難され、当店でも盗難されたイヤリングです。手にとって本物かどうかお確かめください。」
少し手を震わせながら荒巻はイヤリングを手に取るとさめざめと泣き出した。
「ケイライド家のものに間違いないわ、イヤリングの後ろに”最愛なる母 アリス”の文字が彫ってあるわ。お帰りなさい曾曾お祖母様。」
「な!ちょっとこれはどういうこと!?」
「こういうことですよ?」
「イヤリングとネックレスを交換って言ったじゃない!」
「誰も交換するなんて一言も言ってませんよ?盗品が帰ってきたんですから、盗難届を引き下げなければなりませんね。」
「たかだかイヤリング一個に盗難届ですって!?貴女たち頭がおかしいんじゃないの!?」
「店のモノに保険かけるの当たり前じゃないですか。むしろ貴女が何言ってるんですか。足代さん、貴女の店だって品物に保険ぐらいかけてるでしょう。」
地団駄を踏んで怒る60代の胡散臭い女性を見ながら、呆れた声で琢二は言った。
「で、いいかげん商談に答えなさい、300万で買ってあげるって言ってるんだからさっさとよこしなさいよ。私が気に入ったの。私の店に飾る権利があるわ。もともと私の店にあったものよ?」
「貴女の店ではなく、客が貴女の店のゴミ箱にポイ捨てしたモノでしょ?商品として展示ではなくゴミ箱に入ったモノだからいらないって言って持ってきたの貴女でしょう。それに盗品だって言いましたよね?何回言わせるんですか?あと、そこを探しても鍵は見つかりませんよ?帰ってください、邪魔です。」
琢二としおりを押しのけてズカズカとカウンターの後ろにある棚をあちこち開けまくる足代に、羽交い締めするように琢二が捕まえると店の扉を開けているしおりにウインクをしながら足代を外に追い出した。ちょうどその時、言い合いになったしおりと足代の様子を見て西村がビルの上階に電話しておいたことが功を奏したのか、佳奈が降りてきたところだった。
「あら、みずえ。こんなとこで貴女何してるの?洋上さんに見つかったら警察呼ばれちゃうわよ?」
「先輩。聞いてくださいな。私があの赤いネックレス300万で買ってあげるって言ってるのに、あの客頑として売らないっていうのよ、どうかしてるわ。」
「あぁ、あのネックレスね。私のお友達の荒巻かなともの作品で、盗難されてここに行きついてそれから、とっても腕のいい人形作り男の子がフラメンコを踊ってる人形作ってくれて、そしてそのネックレス縁の購入主が現れたってことよね?それを買ってあげるですって?貴女、どれだけ自分勝手なのかしら?そんなだから、嫌われるのよ?」
「嫌われてなんかないわ、先輩。しかもイヤリングも買いもせずに客に渡すなんてどうかしてるわ。」
「イヤリングって白無垢の?あれも盗品でしょう?元の持ち主のところに帰るのは当たり前じゃない?というか、貴女ここがそういう店だっていうこと忘れてない?貴女の弟子の店でしょう?」
「オカルトは信じないわ。ここは私の倉庫みたいな店よ。私の持ち物だから何をしてもいいのよ。先輩。」
「オカルトは信じない」の言葉に、琢二としおりはやっぱりかと納得しつつ、相変わらずこの人は自分勝手で人をバカにして生きているんだなと思った。そして、ドヤ顔でふんぞりかえる足代に佳奈は、はぁとため息つくとふとクスクスと笑いながら言った。
「貴女の店ですって?ふふふ、陣屋くんがいなくなった時にこの建物ごとうちの旦那が購入したわ。店も土地の権利も我が三島コーポレーションの持ち物よ?その意味わかるかしら?」
「・・・・・・・・。そ、そうなの。琢二くん、これは貸しだから。あぁそれとそこの一弥くんだっけ?こんな店やめてうちに来ないかしら?きっといい店員になれるわ。琢二くんじゃ尊敬できないでしょ?うちに来ればいいわ。今の倍の値段で雇ってあげる。」
扉から顔を出して佳奈がいることを確認して店奥に戻ろとした西村を呼び止めた足代はこう言った。言われた西村は一瞬「倍の値段」というところで考えるようなフリをしたが、語尾の「あげる」という言葉にやれやれといった顔をすると、足代の前でペコリと頭を下げた。その様子を足代は満足げに頷いていたが、西村の次の一言で顔色を変えた。
「結構です。俺は、洋上さんに直接雇われてますし、ましてや骨董店ではなく隣の喫茶店の副店長なんでその申し出はお断りします。第一、俺「~~あげる」っていう言い方する人、大っ嫌いなんですよね。あと、貸しって何ですか、勝手に来て勝手に喚いて、それ大人のやつことっすか。大体、盗品だって言ってるの聞いてました?貴女の店って言うからには全て把握してたんですよね?だから持ってきた。それなのに。」
「貴方、ここの人間に毒されてない?大丈夫?オカルトなんて馬鹿げたこと大人になっても言い張って、陣屋くんがかわいそうだわ。あの子そんな力なくても存分に発揮できたのに、やっぱり「出来損ない」だったのね。私に言われた通りに店をやってれば逃げる必要なんてなかったのに。ほんと、琢二くんにしろ日比野さんにしろ出来損ないが多いわね。いいわ、今日はこれで引いてあげるわ。じゃぁねまた来るわ。」
一人、ぶつくさ文句を言うと来た時と同じ笑顔を顔に貼り付けると颯爽と去っていった。疲れた顔をした琢二としおりはフラフラと店の中に入っていく様子を見ながら、西村は佳奈に詰め寄った。
「なんなんですか、あの人!出来損ないなんて!」
「みずえは、自分以外は全て「出来損ない」扱いするから気にしなくていいわ。気にして逃げたのは彼だけでいいのよ。」
「そんな」と青い顔をして、急いで奥から塩の塊を持って戻ってきた西村が店の前に塩を叩きつけるのを見ながら、佳奈が頭を抱えて店の壁に寄り掛かった。
「一弥くん、教えてくれてありがとうね。旦那は、来客中だったから対応出来なかったんだけど、私でよかったわ。彼だったら、速攻で警察読んでたところね。今度から彼女が少しでもこの店で見かけたら、私を呼んで。駆け下りてくるわ。」
「転ばないように駆け下りてきてくださいね。足、痛いんでしょ?」
壁に寄り掛かって少し左足を痛そうにさすっている佳奈に苦笑いをしながら「中に入りましょう」と促す。
店の中では、ほったらかされていたグリスと荒巻が、足を引きずりつつ入ってきた佳奈に席を譲る。そして、店奥から湿布の入った箱を持ってきたしおりが、西村に湿布を出して渡すと靴下を脱いで痛そうな左足首に貼った。小さくヒャッと声をあげるとその場に小さな笑いが起きた。その小さな笑いが大きくなると、西村は湿布を箱に戻すとポットにお湯を入れ、人数分のティーカップにお茶を注ぎ込んだ。
「ところで、さっきの人は何者?」
「あれは、厄介な人だよ。あれを見たら逃げなさい。ろくなことが起きない。」
優斗の疑問に、お茶を飲みながら琢二が苦々しい顔をしながらそう言った。その顔と言葉に何かを察した優斗は荒巻の手元にあるイヤリングを見て、「あぁ」と何か納得するように頷いた。
「4ヶ月前に、僕、白無垢の人全然描けないって言ったこと覚えてます?」
「あぁ、覚えてる。」
「イヤリング見て思っちゃったんだ、帰ってくるからいらないってことなんだろうなぁ。ねぇ、琢二さん、これからも僕を起用してくれますか。こことは僕、とても相性が合いそう。何となくだけど、また呼ばれそうな気がするんですよね。」
「そうか。構わないよ。あぁ、しおちゃん隣で心配そうに見てる彼女呼んできたら?」
「尚さんですか?そうですね。嵐は去りましたし、呼んでも大丈夫かな。」
「あいついなくてよかったっすね。あいついると絶対火に油注ぐことになる。」
ニヤリと笑う琢二に、西村が苦笑しながら言った。
しおりは隣と接している扉を開くと尚を手招いて、店の中に誘導した。
「大丈夫だった?すっごい剣幕で喋ってるおばさんいたけど。」
「何とか撃退したんで大丈夫です。それよりこの近くであの人見かけたら、私か佳奈さん、西村さんにでもいいですけど言ってくださいね、ろくなことにならないので。」
「オッケー。あ、そうそう。守、見つかったらしいよ。こないだ下半身血塗れで公園に倒れてたんだって。今は気がおかしくなってずっとフィリップ!!って叫んででよくわからないっておばさんたちが心底疲れて言ってたんだよね。フィリップって誰?って感じ。」
荒巻と優斗の間の席に誘導されながら、尚は消息不明だった樫屋守の話をした。フィリップという名を聞いて、慌てて荒巻は携帯を取り出して店を出ると、誰かに電話をかけているようだった。
「忘れかけるところだったわ。イヤリングが戻ってきたら、彼に電話するって言ってたの忘れてた。今2ブロック先の時計店にいるらしいから、あと30分もあれば来れるみたいよ。ところで、グリス貴方このネックレス、どれくらいで購入するつもり?タダで売るわけにはいかないわ。」
「当然だ。店にあるモノだろ?そうだな。でも、僕には価値がわからないんだ。君がレディーから石を買い取った時はどれくらいした?」
「20万ぐらいだったかしら。確かそのくらいよ。間違っっても300万とかじゃないわ。それに人形に関しては彼に聞いたほうがいいんじゃないかしら?」
グリスと話しながら人形のことになると荒巻は、優斗の方を見ながら言った。食べ損なっていたケーキを啄みつつ耳をかたむけていた優斗は、急にふられた話に少々むせた。
「に、人形の値段ですか?僕、まだ一体も人形売りに出したことなくって。どれぐらいがいいんですかね。」
困った顔をして優斗は琢二を見る。琢二は面食らったような顔をしたが、腕を組んでうーんと唸った。
「前回の双子人形の時と同じでいいんじゃないですか?」
しおりは先日親元に帰って行った双子を思い出しつつ言った。
「それはちょっと高すぎるな。まだ優斗は学生だ、その半分でいいだろう。職人としてやっていく前のまだ見習い段階だろ。優斗、5万でどうだ?」
「5万ですか?いいですよ?」
「5万でいいの?だったら、優斗くん今度私のギャラリーに来て作って欲しい人形があるの。貴方の腕ならきっといいのができると思うのよね。それからその人形に加島さん、貴方服作らない?今度の展示会、学生と作る展示会にしたいのよね。」
「!!ぜひ!!」
「やったぁ!憧れの荒巻かなともと仕事!!友達に自慢しちゃおう!」
手を取り合って「わーいわーい」と喜ぶ優斗と尚を見て、皆朗らかな気持ちになった。ちょうどその時店の扉が開いて車椅子の女性と男性二人が入ってきた。
「姉さん!」
「あら、クリス貴女も一緒だったの?」
車椅子が店のあちこちにある段差に引っかかりつつも四苦八苦して入ってくる3人に、しおりは「この店バリアフリーにした方がいいのでは?」とその様子に琢二に耳打ちをした。
「意外とこの店、段差があるな。全然気がつかなかった。」
「ですよねー。こないだの老婦人はここにくる前は車椅子だと聞いてたけど、店にくるなり普通に歩いていたし、誰も引っかかる様子はなかったので、失念してました。やっぱりオーナー、一度全部のモノ出してリフォームすべきじゃないですか。」
「やるかー?でもやるとしたら、店の半分ずつだな。何が起きるかわかったもんじゃないし。」
「ですね。」
二人のそんな会話を聞いて、荒巻はふふふと笑うと3人を紹介してくれた。
「車椅子に座っているのは、私の義妹の荒野クリスティン。その車椅子を押しているのが彼女の夫の樫屋範久、イヤリングに釘つけになっているのが、フィリップ・ケイライド。あぁ、守って子とは別の家系の樫屋だから、彼女は親族でも何でもないわ。」
樫屋と聞いてハッとした尚を見て、困り顔で荒巻は付け加えた。そして、机の上に置いてあったイヤリングを取ると、フィリップの方に向き、その手にイヤリングをのせた。
「フィリップ、曾曾お祖母様のイヤリング帰ってきたわ。はい、どうぞ。」
「あ、あぁ。帰ってきたか、そうか。ずっと探していた。自分がクリスに渡すものだとずっと思っていたものだ。よかったこれで、これで、クリスも戻ってきてくれると嬉しいんだがな。自分のせいではあるんだが。範久、君が持っていてくれるか。君たちの間に生まれてくるかもしれないが、もし生まれてこなかったとしても、ともの子でもいい、「娘が生まれたら娘の結婚式で使いなさい、息子が生まれたらその子の娘に使いなさい」それが、ケイライド家に伝わる家宝の保存方法だ。」
「はい、お義父さん。」
範久の手にイヤリングを載せると、しかとその手を包み込むと声を震わせながらそう呟いた。そしてぼんやりと焦点のあってない顔をした娘の頭に手をやると愛おしそうに撫でた。何故撫でられているのかといった顔をしたクリスは、寂しそうに笑う父を見てふわっと花が咲くように笑った。その笑う顔に徐々に泣き笑いになったフィリップだが、しばらくすると罰が悪そうな顔をしてただ「すまない」と言った。
「よかった。これでこの件は解決だな。」
「そうですね。」
しおりと琢二は、少し離れたところに立ちその様子を見ていた。そして、彼らの後ろで窓際に座りこちらを見ている白無垢から赤い髪を覗かせた中年の女性が頭を下げ消えていく瞬間と、フラメンコレディーが軽やかにそして楽しげに踊り消えていく瞬間を見て、本当に長かった出来事が終わりを迎えたことに二人は、そっと胸を撫で下ろした。
その日、グリスは荒巻たちと喫茶店~HOUSE~で、最近やっているというディナーを食べて帰った。
西村が「まだオーナーのパエリア愛が続いているんすよ!!」と涙目で文句を言いつつ、しっかりと美味しいパエリアを作った彼の料理をフィリップとグリスが褒めたことで少しは気が紛れたらしく、次も頑張ります!と宣言したことにより、三島洋上によるパエリア期間が伸びたことは彼が知るよしもなかった。
「しおちゃん!おっはよー今そこで琢二さんの姿見かけたから急いで来たんだけど、どこにいるの?また店の奥?それとも隣?」
言葉通り全力疾走してきたらしくはぁはぁと肩で息をしながら、カウンター越しに店奥を覗き込みながら言った。
呆れ顔のしおりは、そばにあった塩の塊を尚の頭と肩に乗せると、くるっと尚の向きを変え、店から追い出した。された尚はびっくりである。憤慨しながら、これはどう言うことかとしおりに詰め寄る。
「ちょっとこれはどういうこと?!こんなことされる必要ないと思うんだけど!?」
「オーナー命令ですので。それ以上はなんとも。店にとって害あるものとしてオーナーが決めたことですから、私に言われても困ります。尚さん、こないだ私言いましたよね?勢いがあって突撃してくる人はオーナーが嫌いなんです。」
「嫌いだからってこんなことする必要性ある?」
「もっと言いましょうか?仕事をサボったり、ドタキャンしたりする人はオーナーの地雷を踏むんですよ。ていうか踏んじゃったんですよ、尚さん。こないだ。見るのも嫌だっていう人に自分の職場を荒らされたくないんですよ。オーナーがいない時で私に永遠と愛を語るぐらいは許しますけど。」
「えー。何その地雷ー。しつれーい。まぁ確かにぃ?荒巻かなともをだしに店に来たことは謝るけど、塩乗っけるとかなくない?そこまで嫌われてんのー?心せまーい。でもそこがかっこいいー!!」
怒ったり、笑ったり、呆れたりする尚に、「すまん」と誤った西村の困った顔を思い出すしおり。そんなこんなで店先であーだこーだと言いやう二人の元に、荒巻がやってきた。尚の顔を見ると、心底嫌そうな顔で「何故お前がいるんだ」と言いたげな感じではあったが、チラリと見るだけで店内に入っていった。
尚は、そんな荒巻のことも「心がせまいやつ」としか見れないのか、またねと言ってカフェの方に入っていった。ふと、遠くから手を振っている男性二人が目の端に写ったのを感じだしおりは、そちらの方をむく。するとそこには、ラフな格好をした西村と、青いポロシャツに黄土色のチノパンを履き、大きなリュックを背負って立っている男を見つけた。
「おーいしおりさーん。おはよう!さっきの尚だろ?あいつ何しに来たんだ?」
「いつものオーナー見つけた。です。」
「あぁ。で、あいつに本当に塩乗っけたのか。」
「えぇ、心が狭いだの嬉しいだのと色々言ってましたけど、多分理解してないですね。」
「だろうなぁ。あ、そうそう忘れちゃいけねーや。こいつがフィギュアを作ってくれる大阪優斗。」
大きなリュックを下ろしながら、ペコリと頭を下げる優斗。そして、にこりと笑った。
「よろしくお願いします。大阪優斗です。」
「こちらこそ、お願いします。依頼人はもう中に入られたのでどうぞ。」
しおりは、優斗を店の中に誘う。優斗、しおり、西村の順で店に入る。冷房が効いてひんやりした店内は、とても心地よい。朝すぐに冷房をつけておいて良かったなとしおりは思った。
「あぁ、いらっしゃいませ。当店つくもがみ骨董店店主の篠原琢二です。しおちゃ・・・・じゃなかった、そっちの女性は日比野しおり、ここの店員です。そして、こちらにいらっしゃるのが、依頼人の荒巻かなとも様。」
「よろしくお願いします。大阪優斗です。」
「よろしく。荒巻かなともよ。このネックレスに憑いている者を具現化した感じのフィギュアを作って欲しいの。」
優斗に赤いネックレスを手渡しながら言った。
「ついてるですか?どういうこと?」
「この店、曰く付きが多いって話したろ?」
「うん、それは聞いた。」
「それにも憑いてんだよ。赤髪でスペイン人の若い女性が。」
なんともなしに当たり前のように優斗に説明する西村。その様子を見ながら、琢二はしおりに耳打ちをする。
「西村、うちの臨時店員でも十分やっていけそうだよね。」
「むしろもう臨時店員では?」
コソコソと話す二人に、西村は首を傾げる。優斗は「赤髪かぁ」と言いながら、スケッチブックと色鉛筆を取り出した。そこにスッとカーネーションの香りが過ぎ去った。過ぎ去った方向を見ると、彼女が立っている。フワッとスカートを持つとお辞儀をする。まるで地位の高いに淑女がカテーシーをするように。それに合わせるように有線から軽やかなギターの音が鳴り響く。
店内はまるでフラメンコの舞台のようになった。情熱的にそして悲しげに踊る「フラメンコ・レディー」。
その様子を必死にスケッチブックに描き留めていく優斗。一曲分踊りきると憂いの無くなった晴々とした顔で「フラメンコ・レディー」は消えていった。興奮したかのように優斗は、消えていった方向を指差しながら喋る。
「すごい!すごいよ!!こんなの初めてだ!たくさんスケッチしたけどまだ足りないなぁ。どこかにフラメンコ教えてるところないかな?そこにいけば・・・・」
興奮冷めやらぬ優斗の様子に、3人は呆気に取られる。そんな様子にいつの間にか隣からケーキセットを持ってきていた西村が皆の前にプレートを置きつつ、苦笑して言った。
「優斗はああなると落ち着くまでほったらかしでいいよ。それよりこれを見てくれ。スペインの国花はカーネーション!ってことでカーネーションをモチーフにしたケーキをどうぞ。珈琲は、ブルーマウンテンを用意してみた。」
カーネーションの花びらのようなフリルがいっぱいのったピンクと黄色のクリームに、マンゴーが挟まったショートケーキが目を楽しませてくれる。珈琲の香りが漂う店内で荒巻としおりは、ケーキに舌鼓をうった。
琢二は、面白そうにケーキを食べながら、興奮してあーだこーだと一人騒がしい優斗を見て笑っている。その横で、「あいつの分も用意したけど食べるかな」と言いながら、自分ようにとっておいたケーキを食べる西村。そんな楽しげな様子だったが、12時になった時計から鳩が飛び出てくる。
「あー、もう12時か。昼ごはん前にケーキとか食べちゃったな。昼ご飯にすれば良かったか?」
失敗したなーと西村が反省したように言ったが、女性二人はフルフルと頭を振ってグッジョブと言った。そして、そういえばと言葉を続けた。
「尚の同級生がどうも例の人形のアクセサリーを持っているんじゃないかって話なんだよなぁ。」
「そうなの?」
「らしいって話で、実際どうなのか知らないけど尚に聞いてみる?隣でちょっと青い顔してたけど。風邪ひいてんのかなあいつ。」
「聞いてみるのは構わないが、僕は奥に引っ込むよ。彼女は嫌いだ。」
「だと思いましたー。そのつもりで呼ぶんで大丈夫ですよ。でも荒巻さんはいてくださいね。さすがに持ち主いないと合ってるかわからないから。」
「もちろん。」
「彼女の好きなお菓子取ってきます。」
西村が、歩きながらそう言うとしおりは奥から「尚さん用」と書かれたお菓子ボックスを持ってきた。しばらくするとあーだこーだ言い合う男女の声が聞こえたかとおもうと、扉がカランと音を立てて開き、もっと大きな声でぎゃぁぎゃぁ言い合う男女が入ってきた。その二人のこえで我に返った優斗が一言言った。
「なーかず、うるさい。」
「「まとめんな!!」」
一斉に優斗にツッこむ。二人からの抗議にニヤニヤしながら、対応している優斗にしおりはふふふと笑った。
「あれー。琢二さんまた中に入っちゃったの?私の話は聞かないっていうのー?ひどいなぁ。」
「とことん嫌われたんだろ。」
「なーさま、猪突猛進で他人がどうなっても知らない感じだもんね。」
「ちょっと二人ともひどくない!?いつあたしがそんなことしたっていうのよ。」
「こないだ、私をだしにしてオーナーさんに会いにきた人が何を言ってるのかしら?」
食ってかかる尚を尻目に珈琲を飲んでいた荒巻が言った。
「そ、それは申し訳なかったっていうか。ごめんなさい。」
素直に謝る尚。珍しいこともあるんだなとおもう3人。
「で、用件を早く言ってください。」
しおりは、隣の琢二がさっきまで座っていたであろう椅子をポンポンと叩くと尚を座らせ、耳元で「さっきまでそこにオーナーが座ってたんですよ」とささやいた。一気に顔が輝き上機嫌になった尚は、「尚さん用」お菓子ボックスからクッキーの包みをとると食べ出して言った。
「学校の同級生にね、あぁ、アクセサリー科の子なんだけどちょっと様子がっていうか、ちょっとどころじゃないぐらい変なの。というか怖い。髪を結った白無垢のスペイン系の女性が怒った状態で彼女に張り付いてるのが、時々鏡ごしで見えてさー。みんな怖がって近づかなくなっちゃったんだけど、最近全然見かけなくなっちゃって噂では下半身付随になって実家に帰ったとか死んだとか言われてんの。で、ここからが本題なんだけど、そのアクセサリーどこ探しても守んちに無いんだって!」
「白無垢の女性・・・・」
そう言うとゴソゴソとカバンの中から液晶が大きなタブレットを出して、これかしらと尚の前に画像を出した。
「そうそうこれこれ。ここに通い始めたあたりかなぁ、ちょっとなんだろ見えるようになったって言うか、なんとなくだけどわかるようになってきて、さすがに鏡越しで見えるようになっちゃったら、マジじゃない?」
「マジだな。俺も似たようなもんだけど、お前のその同級生ってさ、男っぽい名前のやつ?確か「まも」なんとか。」
「そこまで言っててなんで覚えてないのよ。「まもる」よ、ま・も・る!」
西村の釈然としない物言いに、尚はあきれ返った感じで叫んだ。するとどうだろうか、さっきまで静かだった「フラメンコ・レディー」がカタカタと揺れ出した。
カタカタからガタガタと揺れだし、店中のモノたちが揺れ始めてまるで地震が起きているように揺れ出したが、どれも落ちる気配は無い。そのまま数分揺れると何事もなかったように一瞬にして止まった。
「正解のようですね。」
「これって正解っていうの?」
しおりの納得したような言葉に、疑問を浮かべた荒巻が困ったように言った。
「それは、何か由来があって揺れてんだろう。誰かの持ち物だったとか、モチーフがこの「フラメンコ・レディー」みたいだったとか。」
「オーナー、出てきていいんですか?」
「隣は何も感じなかったそうだが、さすがに尋常じゃないぐらい店が揺れたしな。しかも腰より下は揺れてない。最初見たときは悪い感じもなかったし、いつの間にかこの店に馴染んで気配が分からなくなってしまったものだ。何かあるんでしょう?荒巻さん。」
店奥から顔を出した琢二は、こちらを見ている尚には目にもくれず、真剣な顔で荒巻のそばにしおりと入れ替わるように座った。
「私の妹クリスティンの父方のケイライド家のものよ。知らない間に家のギャラリーに置いてあって、長期出張に行く前に彼に教えて和解したばかりだったの。置いていった犯人は多分クリスティンの実母だと思うの、でも自分でもこんなの作ったっけなって思うぐらい自然と馴染んでて分からなかったんだけど、最近盗まれたって話したら、悲しそうな顔をしてたけど、ただ「そうか」って言われただけで何も言えなくなってしまって。」
「もしかして、関わる人の中に下半身付随の方がいるのでは?」
「どうして知ってるの?妹が下半身不随だわ。」
びっくりした顔で荒巻は、琢二の顔を見た。
「さっき僕が言ったこと覚えてます?「腰より下は揺れてない」って。腰より下が動いてないということはそういうことだろうさ。しかしまいったな。加島さんの言う通りならば、またどこかに行ってしまったか、誰かに持って行かれたってことならば、待つしかないかな。」
「近いうちにやってきそうですけどね。特にあの人のとこから。」
「ありそうなんだよなぁ。良くも悪くもあの人が持ってきたものだしな。」
しおりと琢二は、困った顔で互いの顔を見ながらそして他の4人の方に体を向けると、はぁとため息をついた。
「ねーねーそれよりさぁ、守はどうなったと思う?」
ため息をついて椅子に座り直した二人に、尚は作業台に突っ伏しながら言った。
「噂通りなんでしょうね。まぁ、最も妹さんと”同じ”では無いでしょうけど。」
何がなんでも尚と話をしたくない琢二は店先をずっと見ているため、しおりは琢二の代わりに答えた。答えたが、しおりの言った言葉に優斗は、意味を理解してしまい背筋が凍るのを少々感じて身震いをして言った。
「こえぇ。」
怖いと身震いする優斗のそばで青い顔をしている西村を見てしおりは、畳み掛けるように言った。
「怖いでしょう?これが貴方が行った代償ですよ?西村さん。貴方が発端ですからね?分かってます?」
「もう嫌って言うほど感じてるよ。ヴィーナスにしろロレックスにしろ、アクセサリーにしろ、本当にこの店に曰く付きしかないってことぐらい感じてるよ。でもさ、なんで「フラメンコ・レディー」じゃなくて、そっちを持っていったんだろうな。」
ふと西村は、目立つ「フラメンコ・レディー」ではなく、白無垢人形の方を持っていったのかが気になりそんなことを言う。
確かに、と皆はうーんと悩み出したが、尚がポンと手を叩くとある雑誌を取り出した。
「そうそう、この雑誌にさぁ載ってたんだよね。その白無垢のやつ。ほらコレコレ。これに「珍しい荒巻かなともの和装アクセサリー」って書いてあるの。」
「こんなの出てたの・・・・ていうか、これどこの雑誌?うちのギャラリー、取材は勝手にできないようになってるんだけど。」
「ケイティーっていう雑誌だよ?確か荒野クリスティンの特集やって本人に怒られたとこ。未だにパパラッチみたいなことやってあっちこっちのアーティストの神経逆撫でして記事書いてるみたいだけど。守、これ見て気がついたんじゃないかぁー。盗品って気がついてたなら、返せばいいのにね。野心家って話だったから、これを気にお近づきになれたらとか思ってたのかな。」
「「お前みたいにな。」」
「ちょっと!いつアタシがそんなことしたって言うのよ!!」
「私と話をするっていう名目で毎日店に顔を出しに来るのはそういうことでは?まぁ暇なんで別にいいですけど。」
「うー。」
優斗と西村が笑いながら、尚に総ツッコミをし、言い返す尚にトドメをさしてくるしおりに、膨れっ面をして拗ねる尚、それぞれ楽しそうに言い合いをしながら、時間がすぎた。
1時間ぐらいなんともない話をしながら、ふと優斗が言う。
「その白無垢の人形ってこんな感じの人形っすかね。」
スケッチブックに白無垢女性と紋付袴の男性を描いて見せる。ふとしおりにはその白無垢女性が笑った気がして、あぁモノは無くてもここには戻ってきているんだなと感じた。
「優斗さん、それもフィギュアにすることって出来ます?」
「ん?出来るよ?なんかねー今降りてきた感じだったんだよね。帰ってきましたって聞こえた気がしてさ。」
「そうですね、帰ってこられたんですよ。今。」
優斗としおりは顔を見合わせてふふふと笑う。そんな二人を見て琢二は、
「荒巻さん、この白無垢女性と紋付袴の二人がどんなだったかをフィリップさんに聞いて、彼に詳細を渡してください。優斗くんは、「フラメンコ・レディー」を出来るだけ凛々しくかっこいい女性として作って欲しい。店頭に飾れるような感じでね。」
「わかりました!荒巻さん、これ僕のメールアドレスです。写真とかがあれば嬉しいけど、無ければ家族の人の写真とかでもいいです。「フラメンコ・レディー」の方は今からフラメンコ教室探して通って作ってきます!出来上がりは来月とかになるかもしれないですけどそれでもいいですか?」
「わざわざフラメンコ教室通うの!?すごいねキミ。」
「優斗はこだわると、とことんこだわるからなぁ。」
「優くんは、こだわり強すぎるんだよ。」
「うるさい。こだわりがなさすぎるなーさまよりマシ。」
「なんですってぇ!?」
ぎゃいぎゃいと言い合う3人。そんな3人を放っておく店主と店員と帰り支度を始めた荒巻。
「フィリップには、フィギュアが出来上がり次第ここに来るように伝えます。もし、アクセサリーが戻ってきたなら、それも一緒で。「フラメンコ・レディー」は、フィギュアと一緒に買ってくれる人が来るまで、ここで預かっていてください。」
「わかりました。店頭に出す際はまたご連絡を差し上げます。イヤリングの方もかしこまりました。」
カランカランと軽い音を鳴らして店先の扉を開けると、深々と頭を下げて荒巻は帰宅の途についた。言い合いをしていた3人はそれぞれ、荒巻が出ていくと帰り支度を始めた。そして、優斗はニコニコと笑うと「じゃあ1ヶ月後ぐらいに!」と元気よく言うとスキップしながら帰っていった。尚は、奥に早々に引っ込んでしまった琢二を恨めしそうに見ていたが、相手にされないことを確認するとしおりに「バイバーイ」と言って肩を落として、帰っていった。
西村はと言うと、食器とポットを両手に持ち、しおりが開けたカフェに繋がる扉を通り片付けに行った。琢二は尚が帰ったことを確認すると「尚さん用」ボックスを持って定位置に置いて、しおりに声をかけた。
「しおちゃん、イヤリングは帰ってくると思うか?」
「実物がですか?憑いたものがですか?」
「両方。憑いたものはさっき帰ってきたが。」
「さぁ、どうなんでしょうね。さっきも言いましたけど、足代さんが持ってきそうです。何かしらの形で。」
「そうか。その時はよろしく。正直、僕はあの人にはあまり会いたくない。」
1ヶ月後の昼、嬉々として優斗が店に現れた。そして作業台兼カウンターにぺシャリと突っ伏した。
「聞いてくださいよー。フラメンコって女性だけが踊るんじゃないんですねー。粘り強く交渉して踊る方もやってみたんですけど、あれはむりだーほんと無理ー。でもトケが上手って言われたんで、そっちで通うことにしたんですよー。」
「君、フラメンコ教室本気で通うようにしたの。で、トケって何。」
「あー琢二さん!こんにちわ。トケはギター演奏のことですよ。エレキギターは触ったことあったんで、その応用が効くんですけど、踊りは無理っすね。後学のための勉強の一環で始めることにしたんですけど、親にびっくりされました。」
「急にそんなこと言い出せば、そりゃぁびっくりされるだろ。で、そんな1ヶ月で出来上がったのが、これか。今にも動き出しそうだな。」
軽やかにそして凛々しく踊る赤髪の女性の人形を作業台の真ん中に置いて、笑いながら琢二は言った。
ふと、しおりはスッと横から赤い髪が揺れるのを感じてそちらの方を向くと、目の前に彼女が来たことに少々驚いた。いつも驚かせてくれる。上から下まで隅々見渡すと「さすが私ね、かっこいいわ」と囁いて楽しそうにクルクルと回った。
「ところで、白無垢女性はどうなりました?」
「あ、あれね、一応写真とか見せてもらったんだけど、中々うまくまとまらなくって苦労してるんだよね。こないだスラスラって描いたのが嘘のように全然描けないんだ。」
クルクルと回る「フラメンコ・レディー」に目線をやりつつ優斗と会話していたしおりだが、優斗の「描けない」という言葉に、手を顎に添えると考え込んだ。
「まだ、その時じゃないんでしょうね。」
「そうなのかな、あの時は確かに「ただいま戻りました」って聞こえたからなぁ。この人に聞かせるためだったのかな。あれ。」
「かもしれませんね。あれから一度も声も姿も見えませんからどこか遠くに行ってしまったのでしょうね。」
優斗としょんぼりした顔でしおりは、ため息をつく。そんな二人を横目で見つつ、再び店奥に入っていった琢二と入れ替わるようにカランカランと隣の喫茶店から、扉を開く音がして西村が顔を出した。
「よぉ、優斗来てたんだな。来てたんなら言えよ、お前の分の食事ないぞ。」
「一弥はいつもここに昼ごはん出しにくるの?」
「ここの店主も、しおりさんも料理が壊滅的にダメでな、黒い物体しか作り出せないからビルオーナーの命令でずっと俺が賄いとして作ってんの。今なら店に出さない賄い料理をお前にも食べさせてやれるんだが、いるか?」
「そんなこと言われたら、いる!って言うしかないよね。一弥のご飯って美味しいよね、奥さんになる人いいなー。一弥、僕の嫁に来ない?」
「絶対やだ。なんで俺がお前の嫁にならなきゃならねーんだ。」
しおりの前にプレートを置きながら、優斗とそんな話をする。男同士の和気藹々とした雰囲気を楽しみながら、しおりはお昼の賄いに手をつけた。
「今日の賄いは、ビルオーナーの独断と偏見による地中海料理!チョリソとひよこ豆の煮込み、海鮮のパエリア、空豆のポタージュ、レアチーズのエスプレッソソースがけです!」
「何その、料理名。」
最初は元気よく言いつつ、徐々に声を落としながら一気に言い放った西村に、優斗は唖然とした顔で言う。
「仕方ないだろ、オーナーの言葉そのままなんだし。本当は、パエリアより蕎麦とかとうもろこしとかでガレット作りたかったんだけど、なんでかパエリア愛のオーナーに一蹴された。」
「洋上さんは、一時期毎日朝昼晩とパエリア続きで、奥さんが心底海鮮は3ヶ月ぐらいは見たくないって言わせるほどのパエリア愛が物凄いからな。」
「何それ怖い。」
店の奥から琢二が、急須と湯呑みの乗ったお盆を持ってきながら、呆れた顔で出てきた。台にお盆を置くと3人分の湯呑みにカランと氷の入った急須からお茶を入れると、優斗としおりの前に置いた。それを見て「じゃ、待ってろ優斗、お前のも持ってくる。琢二さん俺にもお茶ください」と、琢二に言うと喫茶店のほうに歩き出した。
「あいつ、こっちで自分も食べる気だな。」
「そうでしょうね。たまにはいいんじゃないですか?」
ふふふとしおりは笑った。ややあって、西村は”二人分の”賄いを持ってきて、作業台の上に置いた。
「そういや、例の人形を持って行ったやつ、あのあと色々聞き込みして回ったんだが、いまだに行方不明らしい。捜索願も出されてるけど家族も友達も行方が本当に分からなくて、ほぼ諦めてるそうだ。」
「樫屋さんだっけ?その人。」
「そう樫屋守。あと、荒巻さんとこで盗み働いたやつは、1ヶ月前に彼女がここにきた同じ日に風呂場で首を掻っ切って死んでんのを家族が発見したんだと、それはもうひどい形相で死んでたらしいから、ってテレビ見なかったの?」
「お前な、飯食ってる時にそんな話すんな。あと、うちにはテレビなんてものは無い。」
食べながら、そんな話をする西村に呆れながら琢二が言う。
「テレビ無いの、世間事情は何で得てんの琢二さん。しおりさんは?」
「私は、携帯のニュース見てます。テレビは情報量と画面越しに見えるナニカのせいで疲れるんで。」
「僕もしおちゃんも見えちゃうから、テレビは鬼門なんだよね。」
琢二としおりのちょっと困った顔と言葉に、「あぁ。」と言って何かを察した西村はそれ以上何も言わなかった。黙々と食べていた優斗はふと、
「その風呂場でっていう人さ、レディア・アレクサンドさんと同じ死に方だよね、それ。」
「そういやそうだな。これも因果関係あんの?」
優斗の言葉に「そう言えば」と付け加えて西村は、しおりと琢二の方をむいて言った。
「そうですね。多分、その樫屋さんって方はそれだけじゃ無いんでしょうけど。」
「何、まだあんの。怖いなぁもうこの店。絶対まだなんか出てくんだろ。俺のせいだけど。」
はぁ、とため息をつきつつ、自分の作った料理に舌鼓を打ちながらそんなことを言った。
「まぁ、西村さんのせいでもありますけど、おかげでっていうのもありますよね。特にロレックスとか。」
「あぁ、あれなぁ。元の持ち主のとこに戻ってったやつだろ?でもまだあの関係もまだ続きそうなんだろ?」
「どうやって”来る”かは分かりませんけど、次でおしまいでしょうねぇ。今回のこれもここで終わりが一番いいんでしょうけど、まだ時間かかりそう。そうだ、オーナー、荒巻様に電話をしないといけませんね。フィギュアはこうして届いたので。」
「そうだな、店頭にも飾らないとな。こいつが売れるのはいつになるやら。」
「誰が買うんでしょうね。後で値段交渉しないと。何となく関係する人が来そうですけど。」
店の扉に寄りかかっている「フラメンコ・レディー」を見ながら、ふと彼女の目に優しいものが写っているように見えたしおりは優しい気持ちになりながら言った。
昼を食べ、4人分のプレートを回収した西村は「じゃ、また今度!」と優斗に手を振ると喫茶店に戻っていった。西村が戻っていくのを確認しすると、優斗は席を立つと、
「白無垢の方は、何か進展あったら連絡お願いします。僕も何か起きたら一弥経由で知らせますね。」
「あぁ、勉強がんばれよ。」
「はい!じゃぁまた今度!」
元気に返事をして優斗は、店を出た。喫茶店方向に歩いていく彼の後ろ姿を目で追いながら、しおりはふと琢二に言った。
「彼もまた何かの因果を持ってきそうですね。」
「あぁ、特にロレックスの子に関係しそうだよな。」
「盗ってった方ですか?」
「そう、盗ってった方。」
琢二もまた優斗が出て行った昼下がりの午後の通りを見ながらため息をついた。
優斗が人形を持ってきた日から4ヶ月が経ったある日のこと、尚がとても困った顔をしてちょうどお使いでしおりのいない店内に入ってきた。
「あ、琢二さんだー。しおりんいないの?あのねー、あたしと話したく無いのはわかってるんだけど、この店の前で号泣してる外国人がいるんだけど、どうしよう?」
「外国人?どれ見て泣いてる。」
ものすごく遠慮がちに、そしてものすごく困った顔をしている尚にちょっとびっくりしている琢二は、続く言葉を促すように尚に向き直った。
「ほら、優斗が作った人形があるじゃん?アレの前。滝のような涙で泣いてて、すっごく異様。」
「買い手が来たか。」
尚の困った顔を見つつ「案外早かったな」と独りごちると、足早に店を扉を開けてそとに出てびっくりした。さめざめと泣いているものだと思った琢二は、大の大人がわんわん泣いている様を見て、若干どころかとってもひいた。その男を目の前にしてお使いの入った籠ごと手元から落下させ慌てているしおりの姿を発見して、頭を抱えた。卵割れてないといいけど。と。
「あの、うちの店の前で何をしているんですか?」
恐る恐る何喚いている男の肩を叩いて、琢二は聞く。
「Quién eres tú?」
帰ってきた言葉は、聞き覚えのない言葉だった。
「・・・・誰か、通訳!!!」
「荒巻さん呼びますか?」
「お願いしおちゃん!多分関係者!!」
「Es esto algo que vendes? ¡toma esto! Esta es ella! Se llama Lady. Estas escuchando?」
矢継ぎ早にしゃべる男性に四苦八苦しながら、琢二は店の中に連れていく、しおりはそんな様子を横目で見つつ籠の中の卵を見て割れていないのを確認すると、尚に「籠を持って一緒に入ってきて」と籠を渡すと、店の電話で荒巻に電話した。
「あ、荒巻さん!今大丈夫ですか?」
「えぇ、大丈夫だけど、どうしたのそんなに慌てて。」
「フラメンコ・レディーの前で号泣していた外国人の方がいらっしゃるんですが、言葉がわからなくって困ってるんです。レディーって言ってるのだけ聞こえてて、あの人誰って状態です。早くきてください!というか助けて!」
とても早口にしゃべるしおりに若干気圧され気味の荒巻は、「今近くにいるからすぐいくわ!」と答えると電話をきった。
30分経っても未だ言葉が通じずに四苦八苦してる琢二と謎の外国人の二人を見ながら、困り顔のしおりと尚は隣から何事かと覗きにきた西村が、ちょうどその手におやつを持ってきたことを見てこれ幸いと男二人の間にずずいと割って入った。
「とりあえず、ティータイムにしませんか?」
「la hora del té?」
「いいな、話が通じずに困ってたんだ。」
しおりに促され、謎の外国人と琢二は席につく。その様子を確認すると西村は紅茶のポットと、蜂蜜の匂いのするケーキを机においた。
「今日のおやつは、カモミールとグレープフルーツのフレーバーティー、蜂蜜とリンゴのカスタードケーキの爽やかセットだよ!」
恐る恐るティーカップに手を伸ばし、一口飲んでから謎の外国人は一息ついた。そしてフォークでサクリとケーキをさすと少し匂いを嗅ぎながら、口へと入れとてもにこやかに微笑んだ。
その様子を見つつ、一時休戦とばかりに琢二もそれに倣った。尚は、しおりに「喫茶店のほうにいるから終わったら教えてね。結果が気になる」と言い残し、西村に手を振ると喫茶店のある扉の方に向かった。時同じくして、尚と入れ替わるように店の扉が開き荒巻が飛び込んで来た。
「グリス!!」
「Aramaki!」
「あなたどうしてここにいるの!?スペインに帰ったんじゃなかったの!?」
「Regresé a España una vez.でも、呼ばれてる気がしてまた戻ってきた。」
「「え、こっちの言葉喋れるの!?」」
急に外国語でないこちらの言葉を喋り出したグリスという名の男にびっくりするしおりと琢二。何だかよくわからないけど、荒巻が来たなら、彼女の分も用意しようと西村は席を立ち、喫茶店の方に向かい手に新たにケーキとティーカップを持って再び現れると、荒巻に席につくように促して西村は店の奥に引っ込んだ。
ケーキとフレーバーティーを食べて飲んだ後に荒巻の胸ぐらを勢いよく掴むと荒々しく揺さぶりながら叫んだ。
「なぁ、Aramaki。レディーの人形がこんな店にあるんだい?知ってたのか?あんな生きてる時には見かけなかった人形はどこで手に入れたんだ?あんなのがあるならこの僕に教えてくれたっていいじゃないか!無くなったなんて嘘だったんだろう!?」
「ちょ、ちょっとグリスさん!待ってください!確かに荒巻様の家からあのネックレスは盗まれ、そして色々なところを回ってこの店にたどり着きました!」
「だったら、この女に教えればよかったじゃないか!!彼女が!!生きてる間に!!見せれたかもしれないじゃないか!!!」
「あれが盗まれたのは、レディーが死んでからよ!!」
「だったら、何で!!早く!人形も一緒だったんだろう!!」
「人形は僕が4ヶ月前に作ったんですよ?」
叫んだグリスに答えるように、優斗が店に入ってきた。「ああいいところに・・・・」と続けた琢二は、にこやかにとても嫌な笑顔を貼り付けた足代が優斗の後ろにいるのを見て、苦々しい顔をした。
「あら、どうしたの琢二くんそんな顔をして、日比野さん久しぶりね。何とかやっていけてるみたいじゃない。どうしたの?この男の子知り合いかしら?あぁそれと表に見えてる赤いネックレスなんだけど、あれうちの店にくれないかしら。あんな人形どこで見つけてきたの?あれがあるんならうちでも扱えるじゃない。ね、鍵どこ?持って帰るわ。」
「すみませんが、足代さん。そのネックレスはここにいるグリスさんが購入されることになっていますから、勝手に持って帰ろうとしないでください。」
「そうなの?じゃぁ、そのグリスさんから買うことにするわ。いいでしょ?300万でどう?赤い宝石なんて男の人はいらないでしょ?恋人にやるならそんな人形付きよりもいいものがうちにあるわ。これとかどう?白無垢人形のイヤリング。最近、店に来たイヤリングなんだけど、服飾専門学校に通ってた子の持ち物なんだけど、いらないって言われたから買ったのよね。琢二くん、あなたのとこなら扱えるでしょ?変なものいっぱいあるもの。で、そこのグリスさんとやら、300万で買ってあげるからそのネックレス私にくれないかしら?」
長々と喋り続けていたが、グリスに向き直ると馬鹿にしたような声で何度も「300万で買ってあげる」と催促した。
そんな足代の様子を見ていた荒巻は、声に若干の怒気を含ませて静かに言った。
「おあいにくですが、そのネックレスは私のギャラリーから盗まれた盗品なんですよね。ですので、所有の権利はこの店の店主にあるのではなく、私にあるんです。私が、店主に預かっておいてくれと頼んだものを貴女が持っていくですって?しかも「買ってあげる」などと、強引な。そもそもこのネックレスは私の友人に送るプレゼントだったもの。貴女に所有の権利はありませんよ?」
「あら、だから買ってあげるって言ってるじゃない。」
「これは彼女の遺品だ!貴女に渡すわけないじゃないか!」
「人形がってこと?それともネックレスが?」
「どっちもだ!!」
「でもさっきそこの男の子が「僕が作った」って言ってなかった?」
「足代さん、荒巻様からお願いされてその子が作ったんですよ。」
「じゃぁ、そのネックレスと人形のセットをこのイヤリングと交換ってどう?いい考えでしょ?で、300万でグリスさんがうちから買うってのはどう?」
「貴女、人の話聞いてるの?」
荒巻は、言葉が全く通じてない足代を見て驚愕した。と同時にグリスは「何だこいつ!?」という顔もした。
「それ、結局足代さんが得するだけの提案ですよね。イヤリングは何だか嫌な感じがするから、オーナーに押し付けたい。かといってネックレスと人形のセットは捨てがたいから、代わりに買ってくれればそれでいいって感じですか?」
「そうよー。何だ日比野さんはわかってくれてるじゃない。貴女なら売ってくれるわよね?」
「いやです。」
「あらどうして?いい提案でしょ?」
「いいえ。足代さんが入ってくる前に商談は成立しているので、無理です。それに行き先が決まったものは変えられないんですよ?もちろん、そのイヤリングも。」
しおりは目線を足代の手にやると、ティーカップを持って少し飲むと再び足代の方に向いて言った。
「それ、うちの店から盗まれた盗品だって知ってました?」
「え。」
「その持ってた女性、下半身付随で精神崩壊してて要領が得ないとして家族の誰かが売りに来たんでしょう?」
「え、えぇそうよ。どうしてそんなことを知ってるの?調べたの?」
「足代さんは知っての通り、私は分かるので。オーナーもわかってますよ?それ探してたんです。行方が分からなくなってたので、よかった。持ってきてくれたんですね。足代さんが。」
最後の言葉を強く言うと、足代の手から滑り落ちるようにしおりの手に収まった。手元に戻ってきたイヤリングをしおりは、荒巻の目の前に置く。
「荒巻様、お客様のギャラリーにて盗難され、当店でも盗難されたイヤリングです。手にとって本物かどうかお確かめください。」
少し手を震わせながら荒巻はイヤリングを手に取るとさめざめと泣き出した。
「ケイライド家のものに間違いないわ、イヤリングの後ろに”最愛なる母 アリス”の文字が彫ってあるわ。お帰りなさい曾曾お祖母様。」
「な!ちょっとこれはどういうこと!?」
「こういうことですよ?」
「イヤリングとネックレスを交換って言ったじゃない!」
「誰も交換するなんて一言も言ってませんよ?盗品が帰ってきたんですから、盗難届を引き下げなければなりませんね。」
「たかだかイヤリング一個に盗難届ですって!?貴女たち頭がおかしいんじゃないの!?」
「店のモノに保険かけるの当たり前じゃないですか。むしろ貴女が何言ってるんですか。足代さん、貴女の店だって品物に保険ぐらいかけてるでしょう。」
地団駄を踏んで怒る60代の胡散臭い女性を見ながら、呆れた声で琢二は言った。
「で、いいかげん商談に答えなさい、300万で買ってあげるって言ってるんだからさっさとよこしなさいよ。私が気に入ったの。私の店に飾る権利があるわ。もともと私の店にあったものよ?」
「貴女の店ではなく、客が貴女の店のゴミ箱にポイ捨てしたモノでしょ?商品として展示ではなくゴミ箱に入ったモノだからいらないって言って持ってきたの貴女でしょう。それに盗品だって言いましたよね?何回言わせるんですか?あと、そこを探しても鍵は見つかりませんよ?帰ってください、邪魔です。」
琢二としおりを押しのけてズカズカとカウンターの後ろにある棚をあちこち開けまくる足代に、羽交い締めするように琢二が捕まえると店の扉を開けているしおりにウインクをしながら足代を外に追い出した。ちょうどその時、言い合いになったしおりと足代の様子を見て西村がビルの上階に電話しておいたことが功を奏したのか、佳奈が降りてきたところだった。
「あら、みずえ。こんなとこで貴女何してるの?洋上さんに見つかったら警察呼ばれちゃうわよ?」
「先輩。聞いてくださいな。私があの赤いネックレス300万で買ってあげるって言ってるのに、あの客頑として売らないっていうのよ、どうかしてるわ。」
「あぁ、あのネックレスね。私のお友達の荒巻かなともの作品で、盗難されてここに行きついてそれから、とっても腕のいい人形作り男の子がフラメンコを踊ってる人形作ってくれて、そしてそのネックレス縁の購入主が現れたってことよね?それを買ってあげるですって?貴女、どれだけ自分勝手なのかしら?そんなだから、嫌われるのよ?」
「嫌われてなんかないわ、先輩。しかもイヤリングも買いもせずに客に渡すなんてどうかしてるわ。」
「イヤリングって白無垢の?あれも盗品でしょう?元の持ち主のところに帰るのは当たり前じゃない?というか、貴女ここがそういう店だっていうこと忘れてない?貴女の弟子の店でしょう?」
「オカルトは信じないわ。ここは私の倉庫みたいな店よ。私の持ち物だから何をしてもいいのよ。先輩。」
「オカルトは信じない」の言葉に、琢二としおりはやっぱりかと納得しつつ、相変わらずこの人は自分勝手で人をバカにして生きているんだなと思った。そして、ドヤ顔でふんぞりかえる足代に佳奈は、はぁとため息つくとふとクスクスと笑いながら言った。
「貴女の店ですって?ふふふ、陣屋くんがいなくなった時にこの建物ごとうちの旦那が購入したわ。店も土地の権利も我が三島コーポレーションの持ち物よ?その意味わかるかしら?」
「・・・・・・・・。そ、そうなの。琢二くん、これは貸しだから。あぁそれとそこの一弥くんだっけ?こんな店やめてうちに来ないかしら?きっといい店員になれるわ。琢二くんじゃ尊敬できないでしょ?うちに来ればいいわ。今の倍の値段で雇ってあげる。」
扉から顔を出して佳奈がいることを確認して店奥に戻ろとした西村を呼び止めた足代はこう言った。言われた西村は一瞬「倍の値段」というところで考えるようなフリをしたが、語尾の「あげる」という言葉にやれやれといった顔をすると、足代の前でペコリと頭を下げた。その様子を足代は満足げに頷いていたが、西村の次の一言で顔色を変えた。
「結構です。俺は、洋上さんに直接雇われてますし、ましてや骨董店ではなく隣の喫茶店の副店長なんでその申し出はお断りします。第一、俺「~~あげる」っていう言い方する人、大っ嫌いなんですよね。あと、貸しって何ですか、勝手に来て勝手に喚いて、それ大人のやつことっすか。大体、盗品だって言ってるの聞いてました?貴女の店って言うからには全て把握してたんですよね?だから持ってきた。それなのに。」
「貴方、ここの人間に毒されてない?大丈夫?オカルトなんて馬鹿げたこと大人になっても言い張って、陣屋くんがかわいそうだわ。あの子そんな力なくても存分に発揮できたのに、やっぱり「出来損ない」だったのね。私に言われた通りに店をやってれば逃げる必要なんてなかったのに。ほんと、琢二くんにしろ日比野さんにしろ出来損ないが多いわね。いいわ、今日はこれで引いてあげるわ。じゃぁねまた来るわ。」
一人、ぶつくさ文句を言うと来た時と同じ笑顔を顔に貼り付けると颯爽と去っていった。疲れた顔をした琢二としおりはフラフラと店の中に入っていく様子を見ながら、西村は佳奈に詰め寄った。
「なんなんですか、あの人!出来損ないなんて!」
「みずえは、自分以外は全て「出来損ない」扱いするから気にしなくていいわ。気にして逃げたのは彼だけでいいのよ。」
「そんな」と青い顔をして、急いで奥から塩の塊を持って戻ってきた西村が店の前に塩を叩きつけるのを見ながら、佳奈が頭を抱えて店の壁に寄り掛かった。
「一弥くん、教えてくれてありがとうね。旦那は、来客中だったから対応出来なかったんだけど、私でよかったわ。彼だったら、速攻で警察読んでたところね。今度から彼女が少しでもこの店で見かけたら、私を呼んで。駆け下りてくるわ。」
「転ばないように駆け下りてきてくださいね。足、痛いんでしょ?」
壁に寄り掛かって少し左足を痛そうにさすっている佳奈に苦笑いをしながら「中に入りましょう」と促す。
店の中では、ほったらかされていたグリスと荒巻が、足を引きずりつつ入ってきた佳奈に席を譲る。そして、店奥から湿布の入った箱を持ってきたしおりが、西村に湿布を出して渡すと靴下を脱いで痛そうな左足首に貼った。小さくヒャッと声をあげるとその場に小さな笑いが起きた。その小さな笑いが大きくなると、西村は湿布を箱に戻すとポットにお湯を入れ、人数分のティーカップにお茶を注ぎ込んだ。
「ところで、さっきの人は何者?」
「あれは、厄介な人だよ。あれを見たら逃げなさい。ろくなことが起きない。」
優斗の疑問に、お茶を飲みながら琢二が苦々しい顔をしながらそう言った。その顔と言葉に何かを察した優斗は荒巻の手元にあるイヤリングを見て、「あぁ」と何か納得するように頷いた。
「4ヶ月前に、僕、白無垢の人全然描けないって言ったこと覚えてます?」
「あぁ、覚えてる。」
「イヤリング見て思っちゃったんだ、帰ってくるからいらないってことなんだろうなぁ。ねぇ、琢二さん、これからも僕を起用してくれますか。こことは僕、とても相性が合いそう。何となくだけど、また呼ばれそうな気がするんですよね。」
「そうか。構わないよ。あぁ、しおちゃん隣で心配そうに見てる彼女呼んできたら?」
「尚さんですか?そうですね。嵐は去りましたし、呼んでも大丈夫かな。」
「あいついなくてよかったっすね。あいついると絶対火に油注ぐことになる。」
ニヤリと笑う琢二に、西村が苦笑しながら言った。
しおりは隣と接している扉を開くと尚を手招いて、店の中に誘導した。
「大丈夫だった?すっごい剣幕で喋ってるおばさんいたけど。」
「何とか撃退したんで大丈夫です。それよりこの近くであの人見かけたら、私か佳奈さん、西村さんにでもいいですけど言ってくださいね、ろくなことにならないので。」
「オッケー。あ、そうそう。守、見つかったらしいよ。こないだ下半身血塗れで公園に倒れてたんだって。今は気がおかしくなってずっとフィリップ!!って叫んででよくわからないっておばさんたちが心底疲れて言ってたんだよね。フィリップって誰?って感じ。」
荒巻と優斗の間の席に誘導されながら、尚は消息不明だった樫屋守の話をした。フィリップという名を聞いて、慌てて荒巻は携帯を取り出して店を出ると、誰かに電話をかけているようだった。
「忘れかけるところだったわ。イヤリングが戻ってきたら、彼に電話するって言ってたの忘れてた。今2ブロック先の時計店にいるらしいから、あと30分もあれば来れるみたいよ。ところで、グリス貴方このネックレス、どれくらいで購入するつもり?タダで売るわけにはいかないわ。」
「当然だ。店にあるモノだろ?そうだな。でも、僕には価値がわからないんだ。君がレディーから石を買い取った時はどれくらいした?」
「20万ぐらいだったかしら。確かそのくらいよ。間違っっても300万とかじゃないわ。それに人形に関しては彼に聞いたほうがいいんじゃないかしら?」
グリスと話しながら人形のことになると荒巻は、優斗の方を見ながら言った。食べ損なっていたケーキを啄みつつ耳をかたむけていた優斗は、急にふられた話に少々むせた。
「に、人形の値段ですか?僕、まだ一体も人形売りに出したことなくって。どれぐらいがいいんですかね。」
困った顔をして優斗は琢二を見る。琢二は面食らったような顔をしたが、腕を組んでうーんと唸った。
「前回の双子人形の時と同じでいいんじゃないですか?」
しおりは先日親元に帰って行った双子を思い出しつつ言った。
「それはちょっと高すぎるな。まだ優斗は学生だ、その半分でいいだろう。職人としてやっていく前のまだ見習い段階だろ。優斗、5万でどうだ?」
「5万ですか?いいですよ?」
「5万でいいの?だったら、優斗くん今度私のギャラリーに来て作って欲しい人形があるの。貴方の腕ならきっといいのができると思うのよね。それからその人形に加島さん、貴方服作らない?今度の展示会、学生と作る展示会にしたいのよね。」
「!!ぜひ!!」
「やったぁ!憧れの荒巻かなともと仕事!!友達に自慢しちゃおう!」
手を取り合って「わーいわーい」と喜ぶ優斗と尚を見て、皆朗らかな気持ちになった。ちょうどその時店の扉が開いて車椅子の女性と男性二人が入ってきた。
「姉さん!」
「あら、クリス貴女も一緒だったの?」
車椅子が店のあちこちにある段差に引っかかりつつも四苦八苦して入ってくる3人に、しおりは「この店バリアフリーにした方がいいのでは?」とその様子に琢二に耳打ちをした。
「意外とこの店、段差があるな。全然気がつかなかった。」
「ですよねー。こないだの老婦人はここにくる前は車椅子だと聞いてたけど、店にくるなり普通に歩いていたし、誰も引っかかる様子はなかったので、失念してました。やっぱりオーナー、一度全部のモノ出してリフォームすべきじゃないですか。」
「やるかー?でもやるとしたら、店の半分ずつだな。何が起きるかわかったもんじゃないし。」
「ですね。」
二人のそんな会話を聞いて、荒巻はふふふと笑うと3人を紹介してくれた。
「車椅子に座っているのは、私の義妹の荒野クリスティン。その車椅子を押しているのが彼女の夫の樫屋範久、イヤリングに釘つけになっているのが、フィリップ・ケイライド。あぁ、守って子とは別の家系の樫屋だから、彼女は親族でも何でもないわ。」
樫屋と聞いてハッとした尚を見て、困り顔で荒巻は付け加えた。そして、机の上に置いてあったイヤリングを取ると、フィリップの方に向き、その手にイヤリングをのせた。
「フィリップ、曾曾お祖母様のイヤリング帰ってきたわ。はい、どうぞ。」
「あ、あぁ。帰ってきたか、そうか。ずっと探していた。自分がクリスに渡すものだとずっと思っていたものだ。よかったこれで、これで、クリスも戻ってきてくれると嬉しいんだがな。自分のせいではあるんだが。範久、君が持っていてくれるか。君たちの間に生まれてくるかもしれないが、もし生まれてこなかったとしても、ともの子でもいい、「娘が生まれたら娘の結婚式で使いなさい、息子が生まれたらその子の娘に使いなさい」それが、ケイライド家に伝わる家宝の保存方法だ。」
「はい、お義父さん。」
範久の手にイヤリングを載せると、しかとその手を包み込むと声を震わせながらそう呟いた。そしてぼんやりと焦点のあってない顔をした娘の頭に手をやると愛おしそうに撫でた。何故撫でられているのかといった顔をしたクリスは、寂しそうに笑う父を見てふわっと花が咲くように笑った。その笑う顔に徐々に泣き笑いになったフィリップだが、しばらくすると罰が悪そうな顔をしてただ「すまない」と言った。
「よかった。これでこの件は解決だな。」
「そうですね。」
しおりと琢二は、少し離れたところに立ちその様子を見ていた。そして、彼らの後ろで窓際に座りこちらを見ている白無垢から赤い髪を覗かせた中年の女性が頭を下げ消えていく瞬間と、フラメンコレディーが軽やかにそして楽しげに踊り消えていく瞬間を見て、本当に長かった出来事が終わりを迎えたことに二人は、そっと胸を撫で下ろした。
その日、グリスは荒巻たちと喫茶店~HOUSE~で、最近やっているというディナーを食べて帰った。
西村が「まだオーナーのパエリア愛が続いているんすよ!!」と涙目で文句を言いつつ、しっかりと美味しいパエリアを作った彼の料理をフィリップとグリスが褒めたことで少しは気が紛れたらしく、次も頑張ります!と宣言したことにより、三島洋上によるパエリア期間が伸びたことは彼が知るよしもなかった。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

硝子のカーテンコール
鷹栖 透
ミステリー
七年前の学園祭。演劇部のスター、二階堂玲奈は舞台から転落死した。事故として処理された事件だったが、七年の時を経て、同窓会に集まったかつての仲間たちに、匿名の告発状が届く。「二階堂玲奈の死は、あなたたちのうちの一人による殺人です。」 告発状の言葉は、封印されていた記憶を解き放ち、四人の心に暗い影を落とす。
主人公・斎藤隆は、恋人である酒井詩織、親友の寺島徹、そして人気女優となった南葵と共に、過去の断片を繋ぎ合わせ、事件の真相に迫っていく。蘇る記憶、隠された真実、そして、複雑に絡み合う四人の関係。隆は、次第に詩織の不可解な言動に気づき始める。果たして、玲奈を殺したのは誰なのか? そして、告発状の送り主の目的とは?
嫉妬、裏切り、贖罪。愛と憎しみが交錯する、衝撃のミステリー。すべての謎が解き明かされた時、あなたは、人間の心の闇の深さに戦慄するだろう。ラスト数ページのどんでん返しに、あなたは息を呑む。すべての真相が明らかになった時、残るのは希望か、それとも絶望か。

思いつき犯罪の極み
つっちーfrom千葉
ミステリー
自分の周囲にいる人間の些細なミスや不祥事を強く非難し、社会全体の動向を日々傍観している自分だけが正義なのだと、のたまう男の起こす奇妙な事件。ダイエットのための日課の散歩途中に、たまたま巡り合わせた豪邸に、まだ見ぬ凶悪な窃盗団が今まさに触手を伸ばしていると夢想して、本当に存在するかも分からぬ老夫婦を救うために、男はこの邸宅の内部に乗り込んでいく。

旧校舎のフーディーニ
澤田慎梧
ミステリー
【「死体の写った写真」から始まる、人の死なないミステリー】
時は1993年。神奈川県立「比企谷(ひきがやつ)高校」一年生の藤本は、担任教師からクラス内で起こった盗難事件の解決を命じられてしまう。
困り果てた彼が頼ったのは、知る人ぞ知る「名探偵」である、奇術部の真白部長だった。
けれども、奇術部部室を訪ねてみると、そこには美少女の死体が転がっていて――。
奇術師にして名探偵、真白部長が学校の些細な謎や心霊現象を鮮やかに解決。
「タネも仕掛けもございます」
★毎週月水金の12時くらいに更新予定
※本作品は連作短編です。出来るだけ話数通りにお読みいただけると幸いです。
※本作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係ありません。
※本作品の主な舞台は1993年(平成五年)ですが、当時の知識が無くてもお楽しみいただけます。
※本作品はカクヨム様にて連載していたものを加筆修正したものとなります。

四次元残響の檻(おり)
葉羽
ミステリー
音響学の権威である変わり者の学者、阿座河燐太郎(あざかわ りんたろう)博士が、古びた洋館を改装した音響研究所の地下実験室で謎の死を遂げた。密室状態の実験室から博士の身体は消失し、物証は一切残されていない。警察は超常現象として捜査を打ち切ろうとするが、事件の報を聞きつけた神藤葉羽は、そこに論理的なトリックが隠されていると確信する。葉羽は、幼馴染の望月彩由美と共に、奇妙な音響装置が残された地下実験室を訪れる。そこで葉羽は、博士が四次元空間と共鳴現象を利用した前代未聞の殺人トリックを仕掛けた可能性に気づく。しかし、謎を解き明かそうとする葉羽と彩由美の周囲で、不可解な現象が次々と発生し、二人は見えない恐怖に追い詰められていく。四次元残響が引き起こす恐怖と、天才高校生・葉羽の推理が交錯する中、事件は想像を絶する結末へと向かっていく。
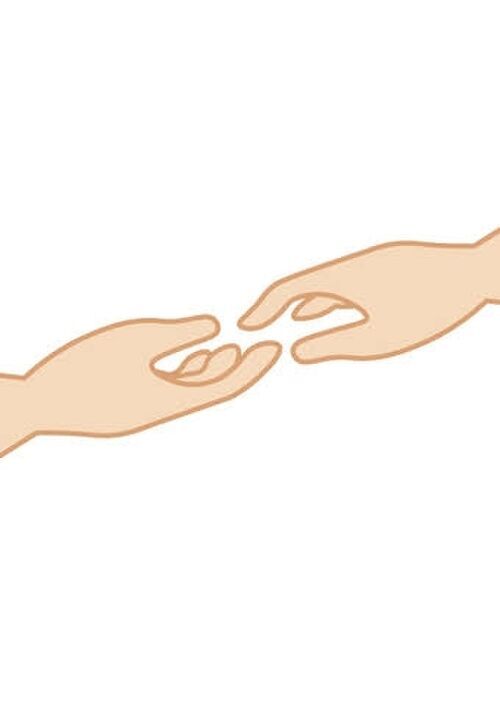

この満ち足りた匣庭の中で 三章―Ghost of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
幾度繰り返そうとも、匣庭は――。
『満ち足りた暮らし』をコンセプトとして発展を遂げてきたニュータウン、満生台。
その裏では、医療センターによる謎めいた計画『WAWプログラム』が粛々と進行し、そして避け得ぬ惨劇が街を襲った。
舞台は繰り返す。
三度、二週間の物語は幕を開け、定められた終焉へと砂時計の砂は落ちていく。
変わらない世界の中で、真実を知悉する者は誰か。この世界の意図とは何か。
科学研究所、GHOST、ゴーレム計画。
人工地震、マイクロチップ、レッドアウト。
信号領域、残留思念、ブレイン・マシン・インターフェース……。
鬼の祟りに隠れ、暗躍する機関の影。
手遅れの中にある私たちの日々がほら――また、始まった。
出題篇PV:https://www.youtube.com/watch?v=1mjjf9TY6Io

愛憎シンフォニー
はじめアキラ
ミステリー
「私、萬屋君のことが好きです。付き合ってください」
萬屋夏樹は唖然とした。今日転校してきたばかりの美少女、八尾鞠花に突然愛の告白を受けたのだから。
一目惚れ?それとも、別の意図がある?
困惑する夏樹だったが、鞠花は夏樹が所属する吹奏楽部にも追いかけるように入部してきて……。
鞠花が現れてから、夏樹の周囲で起き始める異変。
かつて起きた惨劇と、夏樹の弟の事故。
過去と現在が交錯する時、一つの恐ろしい真実が浮き彫りになることになる――。

騙し屋のゲーム
鷹栖 透
ミステリー
祖父の土地を騙し取られた加藤明は、謎の相談屋・葛西史郎に救いを求める。葛西は、天才ハッカーの情報屋・後藤と組み、巧妙な罠で悪徳業者を破滅へと導く壮大な復讐劇が始まる。二転三転する騙し合い、張り巡らされた伏線、そして驚愕の結末!人間の欲望と欺瞞が渦巻く、葛西史郎シリーズ第一弾、心理サスペンスの傑作! あなたは、最後の最後まで騙される。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















