14 / 24
キューピッドドール
2
しおりを挟む
平日の放課後、初は頭を悩ませていた。文字通り抱え込んで、自分の席にいながら、とあるグループを後方から睨みつけていた。
「何? 何でまだ帰らないの? ……というか、何あの人たち。いったい、何やってんの? あれが、俗に言う井戸端会議? 休み時間中だってずっと喋ってたくせに、まだ話し足りないの? ぐだぐだぐだぐだ、いつまでも……しかも、カバンの用意すらしてないし! ……いつになったら、帰り始めるんだか……!」
放課後に突入してから、既に三十分が経過していた。教室内は既にまばらで、廊下にも人気はあまりない。普段ならば、初はこんな用もない場所とはさっさとおさらばして、寄り道などせずにまっすぐ家に帰っている頃だというのに。
初は一刻も早く、愛しいかなでに会いたかった。いつもなら、何も考えずに自室へまっしぐらなのだが、しかし、今日はそういうわけにはいかない。昨日、決めたのだ。目的を遂行するために、ぐっと我慢しなければ。
「だいたい、奏ちゃんがいた頃は、すんなり行動していたくせに……まったく、中心に立つ人がいないだけで、集団っていうものは、あんなにもだらけちゃうものなのかな……」
あとどれだけかかるのだろうかと、初は頬杖をつきながら用意し終わったカバンを枕代わりに、うつ伏せになる。半眼がデフォルトになったら、一体全体どうしてくれる……そう、初が胸中で唾を吐きながらチラリと横目で確認した彼女たちは、昨日アルバムで発見したメンバーたちそのもので。彼女のなけなしの記憶は間違っていなかったと、当人はこれでも少しホッとしたものだ。
「ちゃんと全員が同じクラスだったし、一人も漏れていないし、人違いもしていない。会話から名前も確認済みだし、よくも今までたったの一人も覚えてこなかったものだよね」
とまあ、関心がないとはこういうことなのかと、自身の興味のなさに、初はむしろ感心さえしていた。
「あ、やっと動き始めたー……って、荷物纏めるところから? もう、遅いんだから……無駄が多すぎる。何をのろのろしてるの? わたしの貴重な時間が、どんどんなくなっていっちゃうじゃない……。まったく、どうしてくれるんだか。わたしは、あなたたちみたいに暇じゃないっていうのに。……あー、もう、イライラする! ……何も考えずにのうのうと生きて、文句ばっか垂れてるから、あんなふうにへらへら笑ってられるんでしょうね。まったく、どいつもこいつも、よくもそんな生き方ができるよね。信じらんない。それで、よく奏ちゃんのそばにいられたよね。奏ちゃんが優しいからって、図に乗っちゃってさ。本来なら、あんたたちみたいなやつ、奏ちゃんとは釣り合わないんだから。……努力に努力を重ねて、才能をひけらかさず、文句の一つも、悪口だって言わずに、ひたむきに頑張ってきた奏ちゃんの苦労なんて、『天才』の軽い一言で片付けられちゃうあんたたちには、何もわかりっこない。一生、わかるわけがない。自分たちが可哀想だと思われていることにすら気付けないんだから、本当に面の皮が厚いよね」
初が言い終わって、溜息を零したと同時。彼女たちが、ようやくカバンを手に教室を出て行った。初は、やれやれと肩を落としながらもその後についていく。
やっとのこと、スタートラインに立てた気分だった。
「えーっと? やっぱり、皆同じ方向だよね。それで……もう、ダラダラ歩かないでよ。遅いし、通行人の邪魔になってる! なんで横に広がって歩くのよ。周りなんて、全然見えてないんだから。本当にイライラする……!」
まるで、亀の後を追いかけているようだ。初は後ろから突っつきたい衝動を抑えながら、何とか一定の距離を保ち、後をつけていく。しばらくすると、例の事故現場に到着した。
先頭を行く髪の長い子が、隅に置かれていた花束に気付いた。あれから、もう約一ヶ月が経とうとしている。毎日のように通り過ぎるのだから、いちいち手を合わせろとは言わない。だけど、冷ややかな目で一瞥し、何も見なかったかのように無視をして通り過ぎるのはどうだろうかと、初は怒りを自覚した。
仮にもクラスメイト。しかも、小学校からずっと一緒だった、友達。そんな彼女が亡くなった、事故現場。いつまでも悲しめなんて、そんなことはいくら初でも、もちろん言わない。だけど、今の態度はどうだ。いくらなんでも、ひどいんじゃないだろうか。初がそう思いながら他の子を見ると、彼女はそこで言葉を失うしかなかった。
誰もが皆、同じ反応をしていたのだ。同じ顔が四つ、並んで歩いていたのだ。
「ふふ、ふふふふふ……そうか。そうかそうか。わたしがあの人たちのことを覚えられなかったのは、関心がなかったのもそうだけど、それだけじゃなかったんだね」
彼女たちには、これといった個性がない。突出した意見もないし、いつだって右にならえ、前にならえ。誰かに付き従って、ただただうんうんと首を縦に振って、頷いているだけの人間だ。
だから、見分けられない。のっぺりとした笑顔を貼り付けた、仮面だらけのクラスメイトたち。そんなの、初にしてみれば、顔を覚えられるはずがなかった。
「……何なの? この人たち……生きていて、ちゃんと楽しいの? これなら、かなでの方が、ドールの方が、ずっと可愛いし、輝いてる」
無個性の塊なんて、手を煩わせるだけ無駄だ。操り人形みたいに、意思もなく時間を浪費するだけ浪費して、輝かしい未来なんて想像すらできていないくせに。それなのに、どうして自分たちが守ってもらったなんて発想が、できたのだろうか。
「……だったら、返せよ。守ってもらったなら、その恩を奏ちゃんに返せよ。ちゃんと返して、彼女の分までしっかりと、これからは自分の意思を持って、夢を持って生きていきますって、大根なりに演じて見せろよ……! ……言っていたくせに、口だけなんて許さない。絶対に許さない」
嘘泣きで大人を騙した、悲劇のヒロインたちには、お望み通り悲劇を与えてあげましょう。乗り越えられたなら、今度こそ本物になれるよ。だって、主人公には物語を彩るために、数々の試練を経験してもらわなければならないんだから。それをすべて乗り越えてこそ、感動の物語が、幸福な結末が待っているっていうものでしょう?
「……ちやほやされたいなら、妄想を描くなら、少しくらい、努力しないとね。仕方ないから、その手伝いをわたしがしてあげる。このわたしが、あなたたちの灰色でモノクロの、つまらなそうなその人生の景色を、彩ってあげようじゃない。……大丈夫。喜んで。嬉しいでしょ? だって皆、奏ちゃんの友達だもんね? 奏ちゃんが喜ぶことなら、皆だって嬉しいでしょ? 喜んでくれるはずだよね? そうだよね? だから、そんなに表舞台に立ちたいなら、引きずり出してあげるよ。スポットライトを浴びるっていうのが、どういうことなのか。どれだけ眩しく、暑いのか。華やかだけじゃないってことを、教えてあげる」
それができないなら――終わりだよね。
「その時は、奏ちゃんに返してもらうから。貴重な命、返してもらうからね」
献花に手を合わせて、初は小走りをした。その先で、髪の長い子がとある一件の家に入っていくのをみる。
「ロングが武田朝――彼女の家が、ここ、ね……。よし、次」
残り三人となったクラスメイトたちの後を、初はそのままつけていく。すぐの分かれ道で、初と奏の家とは別方向へと、そのうちの二人は進んでいった。
そして残りの一人は、初の家の方向へと歩いて行ったのだ。
「あの子の家は、知ってる。奏ちゃんの家の隣だから……名前は、昨日知ったけど」
ギリと苦い思い出を噛むように、小柄な背中を睨みつける。あの子がいたせいで、行きも帰りも、初と奏は絶対的に二人きりにはなれなかった。
彼女は、芹沢煌。奏の幼なじみで、周りからは何故か「きらら」と呼ばれている。保育園から一緒で、親同士も仲が良く、誰よりも奏とは長い付き合いだった。
「だからって、何だっていうの? 小学校では、ずーっと隣のクラスだったくせに。わたしなんて、六年間同じだったんだから! わたしの方が、ずっと奏ちゃんの近くにいたんだから! だいたい、事故の時、何もしなかったくせに!」
べーっと舌を出して、初はぷいっと顔を背ける。あの子のことは、とりあえずいい。今は、残りの二人の家を特定しなきゃと、初は小走りで二人を追いかけた。すると、二人が同じマンションのエントランスへと入って行くのを目撃した。
「同じマンションの住人……」
マンションから少し離れて上階を見上げると、一人は三階、もう一人は五階の廊下を歩いているのが見えた。しかし、ここからではどの部屋に入って行ったのかまでは、わからない。
「あ、郵便受け!」
閃いたとばかりに、初はエントランスへ戻って郵便受けの名前を確認する。そこには、思った通りに名字が記載されていた。
「どっちも一号室……覚えやすくてわかりやすい」
とりあえずと、初はそのマンションを離れて家路を急いだ。幼なじみの彼女も、とっくに家の中だろう。それでも、今日は構わない。全員の家が特定できたことで、作戦を立てられるようになることが、初の本日の目的であったからだ。
「とはいえ、どうしたものかな……」
一人を相手することですら成功したことがないのに、いきなり四人を相手とは――。しかも、失敗は許されない。
「全員、普段電車には乗らないから、バラバラドール事件の時みたいに、突き落としたり轢かせるわけにはいかないし、引き裂きドール事件の時みたいに、そう都合よくスピード超過の車が走ってくるわけないし……。でも、わたしが直接手を下せば、わたしが捕まっちゃう。まだまだやらないといけないことがいっぱいあるんだから、それはだめ。それに、そんなことになったらかなでと引き離されちゃうよ。……結構、難しいな……罰を与えるって、どうすればいいんだろう? わたしが捕まらずに、失敗もせずに、すべてが上手くいく方法か……」
たとえば、一人一人ターゲットを絞っていくというのはどうだろうかと、初は考える。四人を同時に相手にしようとするから難しくなるのであって、一人ずつ突き飛ばして車に轢かせるとか、階段の上から突き落とすとか、深い池か何かに沈めるとか……女子中学生一人の力でできることといったら、この辺のことじゃないだろうか。まさか、毒物を用意するなんてことできるわけがないし、ナイフで刺すとか、思いっきり殴るとか、そういう方法は、初は自分が上手くできるとは思えなかった。
「これは、絶対に捕まっちゃいけないんだ。絶対にわたしだとバレてはいけないし、失敗は許されない。欲を言うなら、轢かれてしまった奏ちゃんと同じ目に合わせたい。運転手やあの親子みたいに、同じ目に合わせてやりたい」
初は、同じような苦しみを、同じような痛みを、ターゲットである彼女たちにも味わわせてやりたかった。
「でも、そんなことを言ってたら、一向に終わらないよね。手段を選んではいられないか……」
とはいえ、初は他の関係ない人を巻き込むつもりはなかった。だから、家に火をつけるとか、そういったことをするつもりはない。
「あーあ……良いアイデアはないかなー?」
自室のベッドで、ごろりと横になる初。今日の事故現場での様子を思い出し、途端、腹が立った。
「あー……そうだよ。同じ目? 何言ってるんだろうね。そんなの、温いよね。同じ目じゃだめなんだ。だめだめ。だめだよ。同じじゃ、だめだ」
のそりと起き上がり、口端を吊り上げる。初はかなでを抱き寄せ、頭を撫でた。
「なーにが、同じ目に合わせてやりたいだよ。同じような苦しみ? 痛み? 何言ってんの? そんなので、足りるわけないよね。だって、奏ちゃんは今でも苦しめられてる。好き勝手言われて、奉られて、退屈を凌ぐための悲劇にされてる。辱められていて、今でも苦痛を与えられているのに、どうして同じ目に合わさなきゃいけないの? ……倍だよ。倍以上にして、もっともっともっともっと苦しめなきゃ。そうだよね、かなで」
覗き込んだ可愛らしい顔は、相変わらずの微笑みを湛えていた。初にだけ向けられる、初だけの微笑み。天使の微笑み。女神の微笑。初を否定することなどない、絶対的な肯定の微笑だ。
「かなでも、わたしに賛成してくれている。応援してくれている。そばにいて、力を与えていてくれる。……揺るがない味方。裏切ることのない、絶対的な安心感。そのかなでが肯定してくれるんだから、間違っているわけがない。間違いなんて、あるはずがない。わたしが、間違うはずがない」
そう――わたしの判断に間違いはありえないと、初は心から信じていた。
「よし……そうとなれば、徹底的にやらないとね」
ふふふふふと初の笑い声が、部屋に響き渡る。その様子を知るのはもちろん、愛しいかなで、ただ一人だった。
「何? 何でまだ帰らないの? ……というか、何あの人たち。いったい、何やってんの? あれが、俗に言う井戸端会議? 休み時間中だってずっと喋ってたくせに、まだ話し足りないの? ぐだぐだぐだぐだ、いつまでも……しかも、カバンの用意すらしてないし! ……いつになったら、帰り始めるんだか……!」
放課後に突入してから、既に三十分が経過していた。教室内は既にまばらで、廊下にも人気はあまりない。普段ならば、初はこんな用もない場所とはさっさとおさらばして、寄り道などせずにまっすぐ家に帰っている頃だというのに。
初は一刻も早く、愛しいかなでに会いたかった。いつもなら、何も考えずに自室へまっしぐらなのだが、しかし、今日はそういうわけにはいかない。昨日、決めたのだ。目的を遂行するために、ぐっと我慢しなければ。
「だいたい、奏ちゃんがいた頃は、すんなり行動していたくせに……まったく、中心に立つ人がいないだけで、集団っていうものは、あんなにもだらけちゃうものなのかな……」
あとどれだけかかるのだろうかと、初は頬杖をつきながら用意し終わったカバンを枕代わりに、うつ伏せになる。半眼がデフォルトになったら、一体全体どうしてくれる……そう、初が胸中で唾を吐きながらチラリと横目で確認した彼女たちは、昨日アルバムで発見したメンバーたちそのもので。彼女のなけなしの記憶は間違っていなかったと、当人はこれでも少しホッとしたものだ。
「ちゃんと全員が同じクラスだったし、一人も漏れていないし、人違いもしていない。会話から名前も確認済みだし、よくも今までたったの一人も覚えてこなかったものだよね」
とまあ、関心がないとはこういうことなのかと、自身の興味のなさに、初はむしろ感心さえしていた。
「あ、やっと動き始めたー……って、荷物纏めるところから? もう、遅いんだから……無駄が多すぎる。何をのろのろしてるの? わたしの貴重な時間が、どんどんなくなっていっちゃうじゃない……。まったく、どうしてくれるんだか。わたしは、あなたたちみたいに暇じゃないっていうのに。……あー、もう、イライラする! ……何も考えずにのうのうと生きて、文句ばっか垂れてるから、あんなふうにへらへら笑ってられるんでしょうね。まったく、どいつもこいつも、よくもそんな生き方ができるよね。信じらんない。それで、よく奏ちゃんのそばにいられたよね。奏ちゃんが優しいからって、図に乗っちゃってさ。本来なら、あんたたちみたいなやつ、奏ちゃんとは釣り合わないんだから。……努力に努力を重ねて、才能をひけらかさず、文句の一つも、悪口だって言わずに、ひたむきに頑張ってきた奏ちゃんの苦労なんて、『天才』の軽い一言で片付けられちゃうあんたたちには、何もわかりっこない。一生、わかるわけがない。自分たちが可哀想だと思われていることにすら気付けないんだから、本当に面の皮が厚いよね」
初が言い終わって、溜息を零したと同時。彼女たちが、ようやくカバンを手に教室を出て行った。初は、やれやれと肩を落としながらもその後についていく。
やっとのこと、スタートラインに立てた気分だった。
「えーっと? やっぱり、皆同じ方向だよね。それで……もう、ダラダラ歩かないでよ。遅いし、通行人の邪魔になってる! なんで横に広がって歩くのよ。周りなんて、全然見えてないんだから。本当にイライラする……!」
まるで、亀の後を追いかけているようだ。初は後ろから突っつきたい衝動を抑えながら、何とか一定の距離を保ち、後をつけていく。しばらくすると、例の事故現場に到着した。
先頭を行く髪の長い子が、隅に置かれていた花束に気付いた。あれから、もう約一ヶ月が経とうとしている。毎日のように通り過ぎるのだから、いちいち手を合わせろとは言わない。だけど、冷ややかな目で一瞥し、何も見なかったかのように無視をして通り過ぎるのはどうだろうかと、初は怒りを自覚した。
仮にもクラスメイト。しかも、小学校からずっと一緒だった、友達。そんな彼女が亡くなった、事故現場。いつまでも悲しめなんて、そんなことはいくら初でも、もちろん言わない。だけど、今の態度はどうだ。いくらなんでも、ひどいんじゃないだろうか。初がそう思いながら他の子を見ると、彼女はそこで言葉を失うしかなかった。
誰もが皆、同じ反応をしていたのだ。同じ顔が四つ、並んで歩いていたのだ。
「ふふ、ふふふふふ……そうか。そうかそうか。わたしがあの人たちのことを覚えられなかったのは、関心がなかったのもそうだけど、それだけじゃなかったんだね」
彼女たちには、これといった個性がない。突出した意見もないし、いつだって右にならえ、前にならえ。誰かに付き従って、ただただうんうんと首を縦に振って、頷いているだけの人間だ。
だから、見分けられない。のっぺりとした笑顔を貼り付けた、仮面だらけのクラスメイトたち。そんなの、初にしてみれば、顔を覚えられるはずがなかった。
「……何なの? この人たち……生きていて、ちゃんと楽しいの? これなら、かなでの方が、ドールの方が、ずっと可愛いし、輝いてる」
無個性の塊なんて、手を煩わせるだけ無駄だ。操り人形みたいに、意思もなく時間を浪費するだけ浪費して、輝かしい未来なんて想像すらできていないくせに。それなのに、どうして自分たちが守ってもらったなんて発想が、できたのだろうか。
「……だったら、返せよ。守ってもらったなら、その恩を奏ちゃんに返せよ。ちゃんと返して、彼女の分までしっかりと、これからは自分の意思を持って、夢を持って生きていきますって、大根なりに演じて見せろよ……! ……言っていたくせに、口だけなんて許さない。絶対に許さない」
嘘泣きで大人を騙した、悲劇のヒロインたちには、お望み通り悲劇を与えてあげましょう。乗り越えられたなら、今度こそ本物になれるよ。だって、主人公には物語を彩るために、数々の試練を経験してもらわなければならないんだから。それをすべて乗り越えてこそ、感動の物語が、幸福な結末が待っているっていうものでしょう?
「……ちやほやされたいなら、妄想を描くなら、少しくらい、努力しないとね。仕方ないから、その手伝いをわたしがしてあげる。このわたしが、あなたたちの灰色でモノクロの、つまらなそうなその人生の景色を、彩ってあげようじゃない。……大丈夫。喜んで。嬉しいでしょ? だって皆、奏ちゃんの友達だもんね? 奏ちゃんが喜ぶことなら、皆だって嬉しいでしょ? 喜んでくれるはずだよね? そうだよね? だから、そんなに表舞台に立ちたいなら、引きずり出してあげるよ。スポットライトを浴びるっていうのが、どういうことなのか。どれだけ眩しく、暑いのか。華やかだけじゃないってことを、教えてあげる」
それができないなら――終わりだよね。
「その時は、奏ちゃんに返してもらうから。貴重な命、返してもらうからね」
献花に手を合わせて、初は小走りをした。その先で、髪の長い子がとある一件の家に入っていくのをみる。
「ロングが武田朝――彼女の家が、ここ、ね……。よし、次」
残り三人となったクラスメイトたちの後を、初はそのままつけていく。すぐの分かれ道で、初と奏の家とは別方向へと、そのうちの二人は進んでいった。
そして残りの一人は、初の家の方向へと歩いて行ったのだ。
「あの子の家は、知ってる。奏ちゃんの家の隣だから……名前は、昨日知ったけど」
ギリと苦い思い出を噛むように、小柄な背中を睨みつける。あの子がいたせいで、行きも帰りも、初と奏は絶対的に二人きりにはなれなかった。
彼女は、芹沢煌。奏の幼なじみで、周りからは何故か「きらら」と呼ばれている。保育園から一緒で、親同士も仲が良く、誰よりも奏とは長い付き合いだった。
「だからって、何だっていうの? 小学校では、ずーっと隣のクラスだったくせに。わたしなんて、六年間同じだったんだから! わたしの方が、ずっと奏ちゃんの近くにいたんだから! だいたい、事故の時、何もしなかったくせに!」
べーっと舌を出して、初はぷいっと顔を背ける。あの子のことは、とりあえずいい。今は、残りの二人の家を特定しなきゃと、初は小走りで二人を追いかけた。すると、二人が同じマンションのエントランスへと入って行くのを目撃した。
「同じマンションの住人……」
マンションから少し離れて上階を見上げると、一人は三階、もう一人は五階の廊下を歩いているのが見えた。しかし、ここからではどの部屋に入って行ったのかまでは、わからない。
「あ、郵便受け!」
閃いたとばかりに、初はエントランスへ戻って郵便受けの名前を確認する。そこには、思った通りに名字が記載されていた。
「どっちも一号室……覚えやすくてわかりやすい」
とりあえずと、初はそのマンションを離れて家路を急いだ。幼なじみの彼女も、とっくに家の中だろう。それでも、今日は構わない。全員の家が特定できたことで、作戦を立てられるようになることが、初の本日の目的であったからだ。
「とはいえ、どうしたものかな……」
一人を相手することですら成功したことがないのに、いきなり四人を相手とは――。しかも、失敗は許されない。
「全員、普段電車には乗らないから、バラバラドール事件の時みたいに、突き落としたり轢かせるわけにはいかないし、引き裂きドール事件の時みたいに、そう都合よくスピード超過の車が走ってくるわけないし……。でも、わたしが直接手を下せば、わたしが捕まっちゃう。まだまだやらないといけないことがいっぱいあるんだから、それはだめ。それに、そんなことになったらかなでと引き離されちゃうよ。……結構、難しいな……罰を与えるって、どうすればいいんだろう? わたしが捕まらずに、失敗もせずに、すべてが上手くいく方法か……」
たとえば、一人一人ターゲットを絞っていくというのはどうだろうかと、初は考える。四人を同時に相手にしようとするから難しくなるのであって、一人ずつ突き飛ばして車に轢かせるとか、階段の上から突き落とすとか、深い池か何かに沈めるとか……女子中学生一人の力でできることといったら、この辺のことじゃないだろうか。まさか、毒物を用意するなんてことできるわけがないし、ナイフで刺すとか、思いっきり殴るとか、そういう方法は、初は自分が上手くできるとは思えなかった。
「これは、絶対に捕まっちゃいけないんだ。絶対にわたしだとバレてはいけないし、失敗は許されない。欲を言うなら、轢かれてしまった奏ちゃんと同じ目に合わせたい。運転手やあの親子みたいに、同じ目に合わせてやりたい」
初は、同じような苦しみを、同じような痛みを、ターゲットである彼女たちにも味わわせてやりたかった。
「でも、そんなことを言ってたら、一向に終わらないよね。手段を選んではいられないか……」
とはいえ、初は他の関係ない人を巻き込むつもりはなかった。だから、家に火をつけるとか、そういったことをするつもりはない。
「あーあ……良いアイデアはないかなー?」
自室のベッドで、ごろりと横になる初。今日の事故現場での様子を思い出し、途端、腹が立った。
「あー……そうだよ。同じ目? 何言ってるんだろうね。そんなの、温いよね。同じ目じゃだめなんだ。だめだめ。だめだよ。同じじゃ、だめだ」
のそりと起き上がり、口端を吊り上げる。初はかなでを抱き寄せ、頭を撫でた。
「なーにが、同じ目に合わせてやりたいだよ。同じような苦しみ? 痛み? 何言ってんの? そんなので、足りるわけないよね。だって、奏ちゃんは今でも苦しめられてる。好き勝手言われて、奉られて、退屈を凌ぐための悲劇にされてる。辱められていて、今でも苦痛を与えられているのに、どうして同じ目に合わさなきゃいけないの? ……倍だよ。倍以上にして、もっともっともっともっと苦しめなきゃ。そうだよね、かなで」
覗き込んだ可愛らしい顔は、相変わらずの微笑みを湛えていた。初にだけ向けられる、初だけの微笑み。天使の微笑み。女神の微笑。初を否定することなどない、絶対的な肯定の微笑だ。
「かなでも、わたしに賛成してくれている。応援してくれている。そばにいて、力を与えていてくれる。……揺るがない味方。裏切ることのない、絶対的な安心感。そのかなでが肯定してくれるんだから、間違っているわけがない。間違いなんて、あるはずがない。わたしが、間違うはずがない」
そう――わたしの判断に間違いはありえないと、初は心から信じていた。
「よし……そうとなれば、徹底的にやらないとね」
ふふふふふと初の笑い声が、部屋に響き渡る。その様子を知るのはもちろん、愛しいかなで、ただ一人だった。
0
あなたにおすすめの小説

それなりに怖い話。
只野誠
ホラー
これは創作です。
実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。
本当に、実際に起きた話ではございません。
なので、安心して読むことができます。
オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。
不定期に章を追加していきます。
2026/1/13:『こえ』の章を追加。2026/1/20の朝4時頃より公開開始予定。
2026/1/12:『あけてはいけない』の章を追加。2026/1/19の朝4時頃より公開開始予定。
2026/1/11:『みきさー』の章を追加。2026/1/18の朝4時頃より公開開始予定。
2026/1/10:『つかまれる』の章を追加。2026/1/17の朝8時頃より公開開始予定。
2026/1/9:『ゆうじんのかお』の章を追加。2026/1/16の朝4時頃より公開開始予定。
2026/1/8:『ついてきたもの』の章を追加。2026/1/15の朝4時頃より公開開始予定。
2026/1/7:『かわぞいのみち』の章を追加。2026/1/14の朝4時頃より公開開始予定。
※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。


意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

百物語 厄災
嵐山ノキ
ホラー
怪談の百物語です。一話一話は長くありませんのでお好きなときにお読みください。渾身の仕掛けも盛り込んでおり、最後まで読むと驚くべき何かが提示されます。
小説家になろう、エブリスタにも投稿しています。


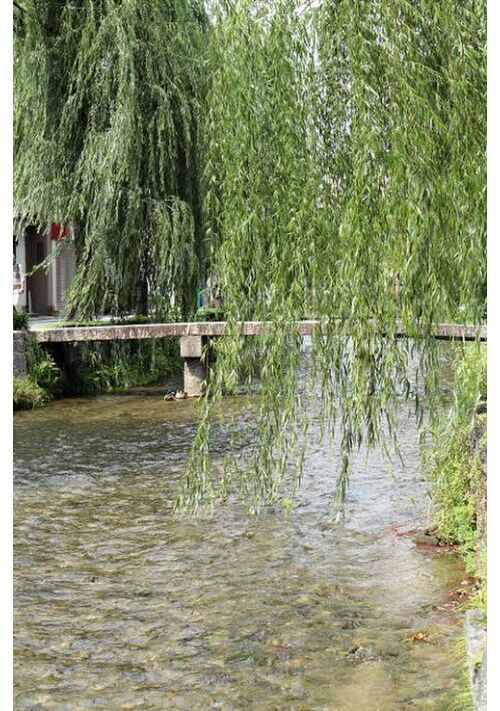

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















