1 / 19
本編
01
しおりを挟む
姫路紫はいくらこの学園に中等部から在籍していても、そして同性愛を否定していなくても、自分が同性と付き合うなんて思ってもみなかった。
それはこの紫の友人、誰もが思った事だろう。
告白は向こうから。
告白当時の紫は相手を知っていてもそこには何の感情もなく丁重に断りを入れたのだが、相手はどうやらそうではなかったようでひと月、毎日毎日紫にさりげなくアピールをし続けた。
紫はそのひと月で相手の様々な様子をみ、彼に対して恋愛感情とまでいかなくても好意を持ち始めていた。
そして再びの告白。
今度は「今はまだ好きじゃなくても良い。好きになってもらえる可能性があるのに、このままでいて他の人に取られたら、そんなのは耐えられない!恋人になりたい」と彼らしくない必死さで。
そのあまりの表情と「友情を超えられなかったら、別れていいから」との一言もあり、紫は彼、松前冬夜と付き合い始めたのである。
そばにいて恋人として接されてしまうと絆されるというのか、彼の誰も見ていないだろう恋人へ向ける側面に触れたからか、二人の気持ちが同じ意味を持つまでにそこまで時間はかからなかった。
好きだと、自分も恋愛感情で好きだと告げてからの紫は今までぽややんとしているというか、のんびりしている姿に隠していたらしい尽くす一面を出していた。
食堂は苦手と聞けば同室者に手ほどきを受けて料理を覚えたし、冬夜の生活リズムに合わせるようにもなった。
それらは本人は全く苦にしておらず、紫の意外な一面に周りは驚きもしたが健気な姿に応援するものが多数だ。
冬夜はこの学園独特の“親衛隊”なるものを持つ人気者である。
この親衛隊は対象者と隊長如何で大きく変わってくるとはいえ、対象者が恋人や親しい人間を作ると“制裁”と言ういじめを始める隊もあった。
それは冬夜の隊も例外ではなかったのだが、不思議と彼らは紫に何もしなかった。
紫自身が親衛隊を持っていない──持つには一定以上の隊員が必要なのだ──とは言えどちらかと言えば人気者と言える生徒だからかもしれないが、それにしては隊長と副隊長が心配そうな顔をしていたのを付き合い出した当初はよく見受けられ、それを目撃した生徒たちは首を捻ったものでもある。
一学年目半ばで付き合い出した二人が二学年に進級した頃には、隊長を含め親衛隊全体で──紫のキャラクターのおかげなのか──二人を暖かく見守り、二人の交際を応援するようになり、付き合い出した時の心配そうな表情を見たものもそれらを忘れていった。
二学年になった冬夜は生徒会副会長職につき、生徒会に関われない紫はそれ以外で冬夜を支え、『ぽやぽやしてマイペースな紫だけれど、尽くすし健気』と誰もが思うようになってから事件は起きた。
寮の部屋でせっせと、翌日の弁当の下拵えをしていた紫のスマートフォンが着信を教える。
着信音は冬夜専用で、彼の好きなクラシック音楽だ。
キッチン内で嬉しそうに頬を染めスマートフォンを手にした紫は、出るなり冬夜から告げられていく発言にどんどんと顔色を変え、真っ白になって「うそ」と呟いたまま動かない。
それをリビングという共有スペースから見ていた紫の同室者──この学園の寮は基本的に二人一部屋。しかしそれぞれに個室が用意されている2DKで寮としては豪華である──である来原萌葱が眉を寄せて立ち上がった。
彼は見た目も行動も不良であるが、紫には世話焼きでもあった。
「紫、どうした?」
萌葱はキッチンで俯いたままの紫の手からスマートフォンを取り台の上に置くと、しゃがみこみ下から紫の顔を覗き込む。
紫は唇をぎゅっと噛みしめ目に涙を溜めたと萌葱が見て取れた途端、萌葱の体を押し倒す勢いで萌葱に抱きついた。
筋肉と身体の大きさのおかげでなんとか頭から倒れずに済んだ萌葱は紫を抱きかかえ、先ほどまで座っていたソファまで行くとそこに紫を座らせようとする。しかし
「紫、なにか飲み物を持ってくるから。座ってろ」
紫は、萌葱の背中にまわした震える手で必死にしがみつき離れようとしない。
困ったなと萌葱はソファに腰掛け、膝の上で向かい合うように紫を置き直し、小さい声と共に泣き出した紫の背中を優しく撫でた。
「喧嘩でもしたか?それとも何かあったのか?どうした?」
寮は基本的に同室者が変わる事はない仕組みだ。この二人の付き合いも二年目に入る。
萌葱は冬夜にアピールされる前の紫も、されはじめてから付き合い出して、そして今に至るまでの紫、そして冬夜を見てきた。それもかなりの時間。
冬夜は萌葱の事を気に入る事もなければ友人となろうと思ったりはしていなかったようだが、「紫に何かあったら教えて欲しい」と言い、萌葱も冬夜の親衛隊の動向が気になり二人は連絡先を交換している。
だから冬夜が告白されている現場を目撃し落ち込んでいる紫を慰め、冬夜に現状を伝えてやった事もあるのだ。
様々な場面を見てきたが、紫がこんな風に泣きじゃくるような事はなかったし、同時に冬夜がこんな風に紫を泣かせるような事をするとは萌葱には思えなかった。
ただただ背中を撫でていると息を整えた紫は萌葱の胸に顔を埋めるようにして、ぽつりとこぼした。
「ふられちゃった。別れようって」
紫も寝耳に水だっただろうが、萌葱もそうだ。
今日さっきまで、別れるような事になるそんな気配は感じられなかった。
昼は二人でくっついて昼食を食べていたし、放課後は冬夜がわざわざ部屋まで送ってきたしその時の顔は普段となに一つ変わりはなかったのに。
「本当にそれ、松前が言ったのか?」
紫はこくりと頷く。
じっと胸に顔をつけて微動だにしない紫の頭を見下ろしていた萌葱に、紫のか細い声が届いた。
「よく、わからない、けど、もうこれっきりだって。なにをいっても、なにをしても、よりをもどすきはない、って」
ぽつりぽつり「ぼくのいけんは、聞く気はないって」と言ってまた紫は泣いた。
一方的過ぎる冬夜の発言に怒りよりも何よりも前に、萌葱はただ疑問だけが湧き、泣いている紫をなんとか紫の部屋のベッドで寝かしつけると冬夜の親衛隊隊長に明日話したい事があると約束を取り付け、キッチンを片付けると萌葱もいつもよりずっと早いがベッドに横になる。
(明日は、あんなに泣いちゃ熱出しそうだな……脅してでも休ませるか)
そう決めて萌葱も目を閉じた。
それから一週間。
冬夜と紫が別れたと噂が事実となって広がっている。
噂ではなく事実であると決定的になったのは、別れの電話から六日目の朝の話だ。
紫がやっと冬夜を捕まえる事に成功し「別れる理由が知りたい」と聞いたのである。大きな声で話す紫ではないし、冬夜も同じくであったので空き教室に移動した。だがしかし、二人を見つけ追いかけた生徒がいた。それに気がついたにもかかわらず冬夜は「もう必要がなくなったからですよ。よりをもどす気もありません。ですから、付き纏わないでください」とはっきり答えたのである。
これが二人の事の顛末を知りたい生徒を中心に一気に広がり、別れの電話から七日目の今日はすでに二人の破局が知れ渡っていた。
紫は周りの視線に辟易するよりも、未だに振られた原因が解らず気持ちを処理する方法も解らず、友人に心配をかけないように元気のない笑顔を浮かべている。
今の紫の隣にはほぼ常に萌葱がおり、今これを見る人たちはこの二人が並んでいる姿を自然に見ているかもしれないが、実は紫が冬夜と付き合っている頃は萌葱が冬夜に遠慮してだろう、こうして二人が一緒にいる事は珍しかった。二人が一緒にいるところを見た人がいる方が少なかったはずだ。
しかしたった七日で二人が一緒にいる事を自然に感じる。それだけ萌葱は今の紫を一人に出来なかった。
紫は今のようにまた萌葱が隣にいてくれる事をありがたく思っている。
「萌葱くん、ありがとね」
「あー?良いんだよ。俺、基本的にボッチだからな」
「萌葱くんは迫力系男子だからね!迫力に気圧されちゃうんだよ」
「迫力系ってなにそれ、初めて聞いた。それ、ただの不良じゃね?」
呆れた顔でけれど笑う萌葱を見上げて、紫もほっとしたように微笑む。
紫に友人がいないわけではない。
けれど今は誰もが言葉や視線の端々に「なぜ冬夜と別れたのか」というそれを聞きたそうにしている。
別れた事実は広がっても、その理由までは誰も知らない。
なにせ当事者である紫でさえ知らないのだ。
その視線に今、紫は耐えられない。
知らない事を、想像出来ない事を、考えさせる視線は予想以上に紫の傷ついたばかりの心を刺激した。
その点、萌葱はいつもとなにも変わらない。
同室者で時間を多く共有したからか、それとも
(萌葱くんが隠すのが上手いのかな)
萌葱はそんな事一切見せず、普通にいつものと同じ調子で紫と共にいる。
「萌葱くんは今日はなに食べる?」
「脂っこいやつ」
「大雑把過ぎるよ。せめて揚げ物とか焼き物とか言おうよ」
「脂っこくて、ガツガツ食べるやつ」
言葉は増えたが大して変わらない返事に、ほっこりと笑った紫は「僕はエビのトマトクリームパスタにするよ!」と言い萌葱に促されるように食堂に入った。
二人が食堂の奥の席で食事を始め、パスタも萌葱が“脂っこいガツガツ食べるやつ”という理由で注文したバターチキンカレーと豚カツを半分以上食べ終わった頃、食堂の入り口から悲鳴が聞こえてきた。
この悲鳴は学園の有名人、特に生徒会役員や風紀委員会の幹部が登場した時におきる。たったそれだけでこれだが、これがこの学園の普通であった。
萌葱がちらりと正面に座る紫を見ると、ピクリと肩を跳ねて反応したものの顔色も変わっていないし表情もさして変化がない。これなら気分が──今以上と注釈をつけて、だけれど──重くはならないだろう萌葱が豚カツを口に入れた時だ。
「ユカリ!」
騒めく食堂に響いた冬夜の声。
紫は驚きフォークを皿の上に落とし、顔を声の方に向けて立ち上がった。
ゆかりは冬夜だけが使う、紫のあだ名だ。
なんで“むらさき”ではなく“ゆかり”なのか、と呼ばれ始めて紫は聞いた事がある。
彼は「自分だけ使える呼び名が欲しくて。特別を一つでも多く、持っていたいんです」と答えていた。
この学園で冬夜が“ゆかり”と呼ぶのは一人だけ。
紫が反応するのは当然だ。
しかし冬夜は紫ではなく、食堂のほぼ中央で“ユカリ”を抱きしめている。
冬夜の親衛隊だろう悲鳴の中、紫や萌葱の耳には“ユカリ”と冬夜の会話が聞こえてきた。
紫はその内容は耳から耳に通り抜けていくようだし、驚く萌葱も、そして呆然とする周りもこれで納得した。
なぜ、紫と別れたのかと。
血管が一、二本切れた気がするほどの遣る瀬無さや怒りを覚えた萌葱が恐ろしい形相で立ち上がると、萌葱の腕を掴み紫が留まらせる。
顔を俯かせ必死に首を振る紫に萌葱は舌打ちをし、自分の腕を掴む紫の腕を逆の手で掴み、食堂の裏口から足早に退出した。
ズンズンと歩き裏庭まで行くと萌葱は立ち止まる。
「殴るくらい、良いじゃねえか」
静かに怒る萌葱に紫は首を振るだけだ。
ユカリの身長は紫と同じくらいだった。
これは抱きしめる冬夜との比較でなんとなく解る。
髪の毛は黒いアフロみたいな──きっとカツラだろうが──もので覆われていたし、顔を見る事も出来なかったけれど、紫はその姿と呼びかける声で地獄に叩き落とされた。
一瞬で、痛みや怒りや悲しさを感じるまもなく、なぜ冬夜が自分と付き合ったのか、なぜ“ゆかり”と呼ばれたのか、なぜ別れる事になったのか、目で耳で全てで理解してしまった。
萌葱に殴りに行かないでほしいと紫が言うのは萌葱のためでもある。でも、それだけじゃない。
「萌葱くんが、あそこで殴ったら、僕はもっと情けないっ!」
ショックで呆然として、文句の一つも言えずに、きっと萌葱の腕を掴まなければ逃げていただろう。友達に自分の代わりに殴ってもらうなんて。
「萌葱くん、僕が彼を好きでいろいろした時間って、無駄だったのかなあ」
地面に座り込んだ紫の正面に同じ様に座り込んだ萌葱は、俯きしゃくりを上げはじめた紫の頭を優しく撫でた。
「無駄じゃねえだろ」
こんな時、スマートなやつはなんと励ますのかと萌葱は考えたが元々そういうキャラじゃないから閃きもしない。
「そうかな、無駄じゃないかなあ」と嗚咽を上げ始めた紫にスマートじゃない萌葱は言った。
「まあ、なんだ──────花嫁修行だと思えば、無駄じゃねえだろ」
ぐちゃぐちゃの泣き顔をあげた紫は、ぽかんとした後困った様に笑った。
それはこの紫の友人、誰もが思った事だろう。
告白は向こうから。
告白当時の紫は相手を知っていてもそこには何の感情もなく丁重に断りを入れたのだが、相手はどうやらそうではなかったようでひと月、毎日毎日紫にさりげなくアピールをし続けた。
紫はそのひと月で相手の様々な様子をみ、彼に対して恋愛感情とまでいかなくても好意を持ち始めていた。
そして再びの告白。
今度は「今はまだ好きじゃなくても良い。好きになってもらえる可能性があるのに、このままでいて他の人に取られたら、そんなのは耐えられない!恋人になりたい」と彼らしくない必死さで。
そのあまりの表情と「友情を超えられなかったら、別れていいから」との一言もあり、紫は彼、松前冬夜と付き合い始めたのである。
そばにいて恋人として接されてしまうと絆されるというのか、彼の誰も見ていないだろう恋人へ向ける側面に触れたからか、二人の気持ちが同じ意味を持つまでにそこまで時間はかからなかった。
好きだと、自分も恋愛感情で好きだと告げてからの紫は今までぽややんとしているというか、のんびりしている姿に隠していたらしい尽くす一面を出していた。
食堂は苦手と聞けば同室者に手ほどきを受けて料理を覚えたし、冬夜の生活リズムに合わせるようにもなった。
それらは本人は全く苦にしておらず、紫の意外な一面に周りは驚きもしたが健気な姿に応援するものが多数だ。
冬夜はこの学園独特の“親衛隊”なるものを持つ人気者である。
この親衛隊は対象者と隊長如何で大きく変わってくるとはいえ、対象者が恋人や親しい人間を作ると“制裁”と言ういじめを始める隊もあった。
それは冬夜の隊も例外ではなかったのだが、不思議と彼らは紫に何もしなかった。
紫自身が親衛隊を持っていない──持つには一定以上の隊員が必要なのだ──とは言えどちらかと言えば人気者と言える生徒だからかもしれないが、それにしては隊長と副隊長が心配そうな顔をしていたのを付き合い出した当初はよく見受けられ、それを目撃した生徒たちは首を捻ったものでもある。
一学年目半ばで付き合い出した二人が二学年に進級した頃には、隊長を含め親衛隊全体で──紫のキャラクターのおかげなのか──二人を暖かく見守り、二人の交際を応援するようになり、付き合い出した時の心配そうな表情を見たものもそれらを忘れていった。
二学年になった冬夜は生徒会副会長職につき、生徒会に関われない紫はそれ以外で冬夜を支え、『ぽやぽやしてマイペースな紫だけれど、尽くすし健気』と誰もが思うようになってから事件は起きた。
寮の部屋でせっせと、翌日の弁当の下拵えをしていた紫のスマートフォンが着信を教える。
着信音は冬夜専用で、彼の好きなクラシック音楽だ。
キッチン内で嬉しそうに頬を染めスマートフォンを手にした紫は、出るなり冬夜から告げられていく発言にどんどんと顔色を変え、真っ白になって「うそ」と呟いたまま動かない。
それをリビングという共有スペースから見ていた紫の同室者──この学園の寮は基本的に二人一部屋。しかしそれぞれに個室が用意されている2DKで寮としては豪華である──である来原萌葱が眉を寄せて立ち上がった。
彼は見た目も行動も不良であるが、紫には世話焼きでもあった。
「紫、どうした?」
萌葱はキッチンで俯いたままの紫の手からスマートフォンを取り台の上に置くと、しゃがみこみ下から紫の顔を覗き込む。
紫は唇をぎゅっと噛みしめ目に涙を溜めたと萌葱が見て取れた途端、萌葱の体を押し倒す勢いで萌葱に抱きついた。
筋肉と身体の大きさのおかげでなんとか頭から倒れずに済んだ萌葱は紫を抱きかかえ、先ほどまで座っていたソファまで行くとそこに紫を座らせようとする。しかし
「紫、なにか飲み物を持ってくるから。座ってろ」
紫は、萌葱の背中にまわした震える手で必死にしがみつき離れようとしない。
困ったなと萌葱はソファに腰掛け、膝の上で向かい合うように紫を置き直し、小さい声と共に泣き出した紫の背中を優しく撫でた。
「喧嘩でもしたか?それとも何かあったのか?どうした?」
寮は基本的に同室者が変わる事はない仕組みだ。この二人の付き合いも二年目に入る。
萌葱は冬夜にアピールされる前の紫も、されはじめてから付き合い出して、そして今に至るまでの紫、そして冬夜を見てきた。それもかなりの時間。
冬夜は萌葱の事を気に入る事もなければ友人となろうと思ったりはしていなかったようだが、「紫に何かあったら教えて欲しい」と言い、萌葱も冬夜の親衛隊の動向が気になり二人は連絡先を交換している。
だから冬夜が告白されている現場を目撃し落ち込んでいる紫を慰め、冬夜に現状を伝えてやった事もあるのだ。
様々な場面を見てきたが、紫がこんな風に泣きじゃくるような事はなかったし、同時に冬夜がこんな風に紫を泣かせるような事をするとは萌葱には思えなかった。
ただただ背中を撫でていると息を整えた紫は萌葱の胸に顔を埋めるようにして、ぽつりとこぼした。
「ふられちゃった。別れようって」
紫も寝耳に水だっただろうが、萌葱もそうだ。
今日さっきまで、別れるような事になるそんな気配は感じられなかった。
昼は二人でくっついて昼食を食べていたし、放課後は冬夜がわざわざ部屋まで送ってきたしその時の顔は普段となに一つ変わりはなかったのに。
「本当にそれ、松前が言ったのか?」
紫はこくりと頷く。
じっと胸に顔をつけて微動だにしない紫の頭を見下ろしていた萌葱に、紫のか細い声が届いた。
「よく、わからない、けど、もうこれっきりだって。なにをいっても、なにをしても、よりをもどすきはない、って」
ぽつりぽつり「ぼくのいけんは、聞く気はないって」と言ってまた紫は泣いた。
一方的過ぎる冬夜の発言に怒りよりも何よりも前に、萌葱はただ疑問だけが湧き、泣いている紫をなんとか紫の部屋のベッドで寝かしつけると冬夜の親衛隊隊長に明日話したい事があると約束を取り付け、キッチンを片付けると萌葱もいつもよりずっと早いがベッドに横になる。
(明日は、あんなに泣いちゃ熱出しそうだな……脅してでも休ませるか)
そう決めて萌葱も目を閉じた。
それから一週間。
冬夜と紫が別れたと噂が事実となって広がっている。
噂ではなく事実であると決定的になったのは、別れの電話から六日目の朝の話だ。
紫がやっと冬夜を捕まえる事に成功し「別れる理由が知りたい」と聞いたのである。大きな声で話す紫ではないし、冬夜も同じくであったので空き教室に移動した。だがしかし、二人を見つけ追いかけた生徒がいた。それに気がついたにもかかわらず冬夜は「もう必要がなくなったからですよ。よりをもどす気もありません。ですから、付き纏わないでください」とはっきり答えたのである。
これが二人の事の顛末を知りたい生徒を中心に一気に広がり、別れの電話から七日目の今日はすでに二人の破局が知れ渡っていた。
紫は周りの視線に辟易するよりも、未だに振られた原因が解らず気持ちを処理する方法も解らず、友人に心配をかけないように元気のない笑顔を浮かべている。
今の紫の隣にはほぼ常に萌葱がおり、今これを見る人たちはこの二人が並んでいる姿を自然に見ているかもしれないが、実は紫が冬夜と付き合っている頃は萌葱が冬夜に遠慮してだろう、こうして二人が一緒にいる事は珍しかった。二人が一緒にいるところを見た人がいる方が少なかったはずだ。
しかしたった七日で二人が一緒にいる事を自然に感じる。それだけ萌葱は今の紫を一人に出来なかった。
紫は今のようにまた萌葱が隣にいてくれる事をありがたく思っている。
「萌葱くん、ありがとね」
「あー?良いんだよ。俺、基本的にボッチだからな」
「萌葱くんは迫力系男子だからね!迫力に気圧されちゃうんだよ」
「迫力系ってなにそれ、初めて聞いた。それ、ただの不良じゃね?」
呆れた顔でけれど笑う萌葱を見上げて、紫もほっとしたように微笑む。
紫に友人がいないわけではない。
けれど今は誰もが言葉や視線の端々に「なぜ冬夜と別れたのか」というそれを聞きたそうにしている。
別れた事実は広がっても、その理由までは誰も知らない。
なにせ当事者である紫でさえ知らないのだ。
その視線に今、紫は耐えられない。
知らない事を、想像出来ない事を、考えさせる視線は予想以上に紫の傷ついたばかりの心を刺激した。
その点、萌葱はいつもとなにも変わらない。
同室者で時間を多く共有したからか、それとも
(萌葱くんが隠すのが上手いのかな)
萌葱はそんな事一切見せず、普通にいつものと同じ調子で紫と共にいる。
「萌葱くんは今日はなに食べる?」
「脂っこいやつ」
「大雑把過ぎるよ。せめて揚げ物とか焼き物とか言おうよ」
「脂っこくて、ガツガツ食べるやつ」
言葉は増えたが大して変わらない返事に、ほっこりと笑った紫は「僕はエビのトマトクリームパスタにするよ!」と言い萌葱に促されるように食堂に入った。
二人が食堂の奥の席で食事を始め、パスタも萌葱が“脂っこいガツガツ食べるやつ”という理由で注文したバターチキンカレーと豚カツを半分以上食べ終わった頃、食堂の入り口から悲鳴が聞こえてきた。
この悲鳴は学園の有名人、特に生徒会役員や風紀委員会の幹部が登場した時におきる。たったそれだけでこれだが、これがこの学園の普通であった。
萌葱がちらりと正面に座る紫を見ると、ピクリと肩を跳ねて反応したものの顔色も変わっていないし表情もさして変化がない。これなら気分が──今以上と注釈をつけて、だけれど──重くはならないだろう萌葱が豚カツを口に入れた時だ。
「ユカリ!」
騒めく食堂に響いた冬夜の声。
紫は驚きフォークを皿の上に落とし、顔を声の方に向けて立ち上がった。
ゆかりは冬夜だけが使う、紫のあだ名だ。
なんで“むらさき”ではなく“ゆかり”なのか、と呼ばれ始めて紫は聞いた事がある。
彼は「自分だけ使える呼び名が欲しくて。特別を一つでも多く、持っていたいんです」と答えていた。
この学園で冬夜が“ゆかり”と呼ぶのは一人だけ。
紫が反応するのは当然だ。
しかし冬夜は紫ではなく、食堂のほぼ中央で“ユカリ”を抱きしめている。
冬夜の親衛隊だろう悲鳴の中、紫や萌葱の耳には“ユカリ”と冬夜の会話が聞こえてきた。
紫はその内容は耳から耳に通り抜けていくようだし、驚く萌葱も、そして呆然とする周りもこれで納得した。
なぜ、紫と別れたのかと。
血管が一、二本切れた気がするほどの遣る瀬無さや怒りを覚えた萌葱が恐ろしい形相で立ち上がると、萌葱の腕を掴み紫が留まらせる。
顔を俯かせ必死に首を振る紫に萌葱は舌打ちをし、自分の腕を掴む紫の腕を逆の手で掴み、食堂の裏口から足早に退出した。
ズンズンと歩き裏庭まで行くと萌葱は立ち止まる。
「殴るくらい、良いじゃねえか」
静かに怒る萌葱に紫は首を振るだけだ。
ユカリの身長は紫と同じくらいだった。
これは抱きしめる冬夜との比較でなんとなく解る。
髪の毛は黒いアフロみたいな──きっとカツラだろうが──もので覆われていたし、顔を見る事も出来なかったけれど、紫はその姿と呼びかける声で地獄に叩き落とされた。
一瞬で、痛みや怒りや悲しさを感じるまもなく、なぜ冬夜が自分と付き合ったのか、なぜ“ゆかり”と呼ばれたのか、なぜ別れる事になったのか、目で耳で全てで理解してしまった。
萌葱に殴りに行かないでほしいと紫が言うのは萌葱のためでもある。でも、それだけじゃない。
「萌葱くんが、あそこで殴ったら、僕はもっと情けないっ!」
ショックで呆然として、文句の一つも言えずに、きっと萌葱の腕を掴まなければ逃げていただろう。友達に自分の代わりに殴ってもらうなんて。
「萌葱くん、僕が彼を好きでいろいろした時間って、無駄だったのかなあ」
地面に座り込んだ紫の正面に同じ様に座り込んだ萌葱は、俯きしゃくりを上げはじめた紫の頭を優しく撫でた。
「無駄じゃねえだろ」
こんな時、スマートなやつはなんと励ますのかと萌葱は考えたが元々そういうキャラじゃないから閃きもしない。
「そうかな、無駄じゃないかなあ」と嗚咽を上げ始めた紫にスマートじゃない萌葱は言った。
「まあ、なんだ──────花嫁修行だと思えば、無駄じゃねえだろ」
ぐちゃぐちゃの泣き顔をあげた紫は、ぽかんとした後困った様に笑った。
13
お気に入りに追加
85
あなたにおすすめの小説

思い出して欲しい二人
春色悠
BL
喫茶店でアルバイトをしている鷹木翠(たかぎ みどり)。ある日、喫茶店に初恋の人、白河朱鳥(しらかわ あすか)が女性を伴って入ってきた。しかも朱鳥は翠の事を覚えていない様で、幼い頃の約束をずっと覚えていた翠はショックを受ける。
そして恋心を忘れようと努力するが、昔と変わったのに変わっていない朱鳥に寧ろ、どんどん惚れてしまう。
一方朱鳥は、バッチリと翠の事を覚えていた。まさか取引先との昼食を食べに行った先で、再会すると思わず、緩む頬を引き締めて翠にかっこいい所を見せようと頑張ったが、翠は朱鳥の事を覚えていない様。それでも全く愛が冷めず、今度は本当に結婚するために翠を落としにかかる。
そんな二人の、もだもだ、じれったい、さっさとくっつけ!と、言いたくなるようなラブロマンス。
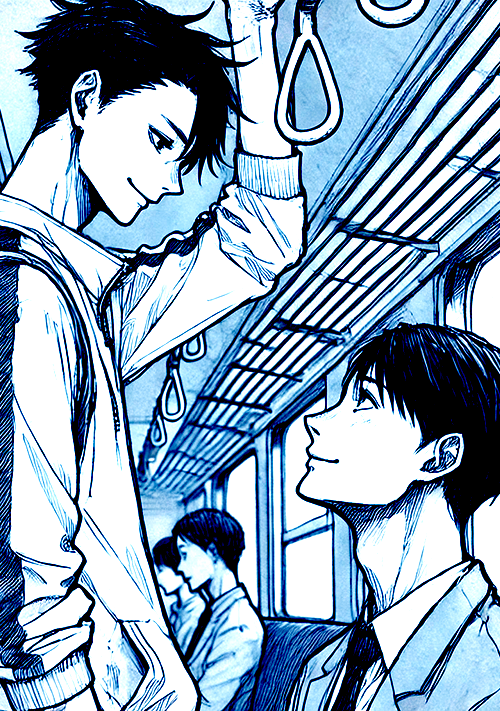
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……


キミの次に愛してる
Motoki
BL
社会人×高校生。
たった1人の家族である姉の由美を亡くした浩次は、姉の結婚相手、裕文と同居を続けている。
裕文の世話になり続ける事に遠慮する浩次は、大学受験を諦めて就職しようとするが……。
姉への愛と義兄への想いに悩む、ちょっぴり切ないほのぼのBL。

【完結】はじめてできた友だちは、好きな人でした
月音真琴
BL
完結しました。ピュアな高校の同級生同士。友達以上恋人未満な関係。
人付き合いが苦手な仲谷皇祐(なかたにこうすけ)は、誰かといるよりも一人でいる方が楽だった。
高校に入学後もそれは同じだったが、購買部の限定パンを巡ってクラスメートの一人小此木敦貴(おこのぎあつき)に懐かれてしまう。
一人でいたいのに、強引に誘われて敦貴と共に過ごすようになっていく。
はじめての友だちと過ごす日々は楽しいもので、だけどつまらない自分が敦貴を独占していることに申し訳なくて。それでも敦貴は友だちとして一緒にいてくれることを選んでくれた。
次第に皇祐は嬉しい気持ちとは別に違う感情が生まれていき…。
――僕は、敦貴が好きなんだ。
自分の気持ちに気づいた皇祐が選んだ道とは。
エブリスタ様にも掲載しています(完結済)
エブリスタ様にてトレンドランキング BLジャンル・日間90位
◆「第12回BL小説大賞」に参加しています。
応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ピュアな二人が大人になってからのお話も連載はじめました。よかったらこちらもどうぞ。
『迷いと絆~友情か恋愛か、親友との揺れる恋物語~』
https://www.alphapolis.co.jp/novel/416124410/923802748

目立たないでと言われても
みつば
BL
「お願いだから、目立たないで。」
******
山奥にある私立琴森学園。この学園に季節外れの転入生がやってきた。担任に頼まれて転入生の世話をすることになってしまった俺、藤崎湊人。引き受けたはいいけど、この転入生はこの学園の人気者に気に入られてしまって……
25話で本編完結+番外編4話

【完結】I adore you
ひつじのめい
BL
幼馴染みの蒼はルックスはモテる要素しかないのに、性格まで良くて羨ましく思いながらも夏樹は蒼の事を1番の友達だと思っていた。
そんな時、夏樹に彼女が出来た事が引き金となり2人の関係に変化が訪れる。
※小説家になろうさんでも公開しているものを修正しています。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















