1 / 82
1、あの日
しおりを挟む
――思えば、全ては5年前のあの日から始まった。
冷たい雨が、降っていた。黒い雲に覆われた、暗い一日。
私の人生が、生きる意味が、あの日を境にまるで変った。
避けられない、運命。生まれ持った、宿命。
そんな言葉で、片づけたくはないんだけれど。
普通に生きられなくなった私は、今でもあの日を、忘れることなどできなかった――。
「もうヤダ。まだスマホ通じないよ・・・一体どれだけ山奥なのよ、ここは?」
4人乗りセダンカーの内部に、鈴のような声が響く。
少女の問いに、応える者はいなかった。聞こえてくるのは、車窓を叩く雨の音色とリズミカルなワイパー。そして、低く唸るエンジン音。
クリーム色のブレザーに身を包んだ少女は、隣席の姉に向かって唇を尖らせた。
「ねえってば。天音、私のこと無視しないでよ」
「無視なんか、してないわ」
「してるじゃない。さっきからみんな、ずっと黙って・・・あのお屋敷を出てから、誰も一言も話さないじゃない。なんなのよ、この空気・・・」
少女の指先が、繋がらないスマホを何度も叩いた。
トントンと、耳障りな音が車内に響く。
前列の両親からも、隣の姉からも変わらず反応はなかった。重苦しい沈黙がまとわりつく。
「・・・どうせまた、私ひとりのけ者なんでしょ」
口をへの字に曲げた少女は、液晶画面から窓の外へと、視線を移す。
左から右へと、次々に流れていく深い樹々。青い光に照らされた顔が、真っ暗な窓に反射している。
雨のそぼ降る夜の山道に、他に光は見えなかった。
「そんな、のけ者だなんて・・・」
「郁美。お姉ちゃんは疲れてるの。突っかかるのはやめなさい」
助手席から届く母親の声には、わずかながらも険があった。
家族だから、些細な変化もすぐにわかる。かくいう母親も、疲れているのだ。肉体からのものではない、恐らくは精神面からきているそれが、普段は物静かな母を若干苛立たせている。
「・・・なによ。お母さんは、いっつも天音の味方だもんね。そりゃあ、優等生の姉の方が落ちこぼれの妹より可愛いんでしょうけど」
「バカなことを言うんじゃありません」
「大事な用事がある、っていうから、こんな山奥までついてきたのに・・・ずっと3人でコソコソ、コソコソ。高校休んでまで、私が来る必要あったの? 天音だけいれば十分だったじゃない」
「そのことについては、いずれきちんと話すと言ったでしょう」
「ほら、やっぱりのけ者にしてるじゃない! 昨日、あのお屋敷に着いてからず~~っとそうよ。私ひとり、邪魔者扱い。あからさまに天音と対応変えるなら、最初から連れてかないでよ!」
「郁美っ!」
ルームミラー越しに、母が女子高生を叱りつける。
勝気さを示すように、少女は睨み返してきた。思わず実の母親は、身震いしそうになる。怖い、わけではない。ブレザー姿の少女が醸す、麗しさに、だ。
妹の名は、四乃宮郁美。
鋭い目付きをしていると、16歳とは思えぬ色香があった。我が子ながら、よくここまで端整に・・・と感心するほどの美形だ。
すっと隣に、視線を移す。
同じ顔を持つ美女が、後部座席に並んでいた。
4歳年上の姉、天音。
黒のワンピースを身に着けた以外は、身長も含め、ほとんど姉妹に違いはなかった。双子のような容貌だけでなく、バランスよく張り出すべきところは張り出したスタイルもそっくりだ。
明らかに異なる点といえば、柔らかなウェーブがかかったセミロングの髪が、天音は漆黒で郁美はブラウン、という色くらいか。
細かくみていけば、姉の天音には顎の右に小さな黒子があるのがわかるが、かえってそれが艶やかさを増していた。じっくり比べれば、年齢差相応には、姉妹の間で成熟の度合いは違っている。
近所でも評判の、いや、一部ネットではファンサイトが作られるほどの美人姉妹は、むろん母親にとっても自慢の娘たちであった。
妹の郁美にしても、普段はこんな跳ね返りではない。親目線の贔屓を除いたとしても、心優しい娘であった。
それが今日に限って苛立っているのは、単に鬱蒼とした森林や冷たい雨のせいではないだろう。
「ごめんね、郁美」
スマホを叩く手を、横から伸びた柔らかな掌が包む。
温かかな、手だった。姉は同じ顔の妹と、正面から向き合う。
「あなたを不機嫌にさせているのは、私よ。すべては私が、望んだことなの」
「・・・なにソレ? 意味わかんないよ・・・」
ルームミラーに映る母親の顔が泣きそうに歪んだのを、郁美は気付けなかった。
天音が向ける、真剣で深刻な眼差しに、瞳を逸らすことができなかった。
「感じているんでしょ? あの屋敷で、何が起こったかはわからなくても、何かが起こったことは。それが尋常ではないことと気付いているから、郁美は私のことを心配して苛立っているのね」
「し、心配なんて、ベツに・・・」
頬を赤く染めながら、郁美はこの二日間、山奥の洋館で起こった出来事を思い返す。
確かに、何かが起こったのは感じていた。
いや、よほど鈍感な者でなければ、恐らく誰もがこの異様さには気付く。それほど奇妙な二日間だった。
まず第一に、ケータイの電波も届かぬほどの山深くに、レンガ造りの巨大な屋敷が、一軒だけポツリと建っているのが不自然であった。
父親の話によれば、親戚縁者が所有する別荘なのだという。今回連れて来られるまで、こんな場所があるなど聞いたこともなかった。
次に驚いたのが、屋敷に集まったのは、四乃宮家の者だけではなかったことだ。
その日、血縁関係者が一堂に集められたのだという。だからこその特別な日であり、多人数を収容できるだけの巨大な屋敷だった。
とはいえ、親戚であるはずの彼らに、郁美が見知った顔はひとつもなかった。
何世代も前からの縁者、という名目で集合した人々。それが2、3家族ではない。ざっと見て、20は下らぬ家族が集まっていたのだ。
唐突に増えた、20もの親戚縁者。それだけでも動揺するというのに、ひとつ屋根の下で一泊二日をともにするという、不思議。
「ねえ、なんだったの。アレは?」
すでに何度も繰り返している質問を、郁美は口にした。
そのたびに、父も母も姉も、ただ下を向いた。「いつか話すから」とだけ答えて。
しかし、今の天音は真っ直ぐ妹を見詰め続けた。
「親戚が集まってパーティー、なんてノリじゃなかったよね。なんであのひとたち、あんなにピリピリしてたの? 息が張り詰めそうなくらいに。これからケンカでもするのかと思ったよ」
「・・・それは」
「それに、女の子ばっかりだった。あそこにいた家族の子供たち、みんな。私たちも含めて。これって偶然じゃないよね? 年頃の娘ばかりをあそこに連れてきたのは、なぜ?」
口を挟みかけた母親を、運転席の父が制する。
相変わらず、ヘッドランプにはくねくねと続くカーブと斜めに降る雨が映っていた。
「そして、これが最大の謎よ。・・・どうして天音だけ、ひとり別室に連れていかれたの? 一体、天音の身に何が起こってるの!?」
柔らかな姉の掌を、郁美は両手で強く握り返した。
美しき姉妹が、互いを見つめあう。天井を叩く雨音が、静寂のなかに響いた。
「郁美」
それまで黙っていた父親が、初めて口を開く。
出張が多いことを除けば、ごく普通のサラリーマンである父は、四乃宮家では絶対の存在だった。怒ることも、強制することもほとんどない、静かな男。だが、母親も娘ふたりも、時に発せられる父の言葉を尊重している。
「物事には、知らない方が幸せ、ということもある」
「・・・そんなこと、わかってるケドさ」
「君にも、いつか必ず、全てを知ってもらう時が来るだろう。けれど、今はその時ではない、というのがボクたちの判断だ」
やや厚めの唇を、ブレザー姿の少女はわずかに噛んだ。
「それは私が、まだ子供だから?」
「君を愛するが故の判断だと言っても、信用してくれないかな」
フロントガラスを叩く雨が、一段と強くなった。
闇のなかで、風が勢いを増しているようだった。
「オメガ」
不意に郁美が漏らした、ひとつの言葉。
天音の瞳が、大きく開く。一瞬にして、車内の空気は緊迫した。
「あの屋敷で、たったひとりだけ仲良くなった女の子が言ったの。あれ、知らないんだ? って。それ以上は何も教えてくれなかったけど・・・この言葉にどんな意味があるの?」
再び車内を、沈黙が包み込んだ。
口を開いたのは、麗しき二十歳の乙女だった。
「お父さん。私はやっぱり、郁美にもきちんと説明しておくべきだと思います」
耐え切れなくなったように、母は白いハンカチを取り出した。
目頭を、抑える。五十代になったとは思えぬ白い指先が、細かく震えた。
すすり泣く横で、父は静かに声を発した。
「君がそう言うのなら、ボクは止めはしないよ」
「ありがとう、お父さん。大丈夫です、このコならきっと・・・受け止めてくれます」
強い光を放つ姉の瞳に、女子高生は自然に姿勢を正していた。
なんて美しく、澄み切った瞳だろう。
同じ顔を持ちながら、郁美は天音の美貌に身震いする想いがした。大きく、魅惑的な瞳。すっと高く通った鼻梁。ややぼってりとした、艶やかな桜色の唇・・・。卵型の輪郭にバランスよく配置された造形は、美神の仕業としか思えぬ奇跡。
過酷な現実を聞こうという直前、陶酔にも似た心地が少女を襲ったのは、不可思議な現象だった。
あるいはそれは、どこか心理的な逃避が作用したためだったのかもしれない。
だが、その先の告白が紡がれる前に、悲劇は起きた。
ドオオオオオッッ!!!
「あッ!?」
突如立ち昇った轟音と火花が、フロントガラスを覆い尽くした。
浮き上がった4人乗りのセダンカーは、ガードレールを越えて、崖下へと転落していった。
冷たい雨が、降っていた。黒い雲に覆われた、暗い一日。
私の人生が、生きる意味が、あの日を境にまるで変った。
避けられない、運命。生まれ持った、宿命。
そんな言葉で、片づけたくはないんだけれど。
普通に生きられなくなった私は、今でもあの日を、忘れることなどできなかった――。
「もうヤダ。まだスマホ通じないよ・・・一体どれだけ山奥なのよ、ここは?」
4人乗りセダンカーの内部に、鈴のような声が響く。
少女の問いに、応える者はいなかった。聞こえてくるのは、車窓を叩く雨の音色とリズミカルなワイパー。そして、低く唸るエンジン音。
クリーム色のブレザーに身を包んだ少女は、隣席の姉に向かって唇を尖らせた。
「ねえってば。天音、私のこと無視しないでよ」
「無視なんか、してないわ」
「してるじゃない。さっきからみんな、ずっと黙って・・・あのお屋敷を出てから、誰も一言も話さないじゃない。なんなのよ、この空気・・・」
少女の指先が、繋がらないスマホを何度も叩いた。
トントンと、耳障りな音が車内に響く。
前列の両親からも、隣の姉からも変わらず反応はなかった。重苦しい沈黙がまとわりつく。
「・・・どうせまた、私ひとりのけ者なんでしょ」
口をへの字に曲げた少女は、液晶画面から窓の外へと、視線を移す。
左から右へと、次々に流れていく深い樹々。青い光に照らされた顔が、真っ暗な窓に反射している。
雨のそぼ降る夜の山道に、他に光は見えなかった。
「そんな、のけ者だなんて・・・」
「郁美。お姉ちゃんは疲れてるの。突っかかるのはやめなさい」
助手席から届く母親の声には、わずかながらも険があった。
家族だから、些細な変化もすぐにわかる。かくいう母親も、疲れているのだ。肉体からのものではない、恐らくは精神面からきているそれが、普段は物静かな母を若干苛立たせている。
「・・・なによ。お母さんは、いっつも天音の味方だもんね。そりゃあ、優等生の姉の方が落ちこぼれの妹より可愛いんでしょうけど」
「バカなことを言うんじゃありません」
「大事な用事がある、っていうから、こんな山奥までついてきたのに・・・ずっと3人でコソコソ、コソコソ。高校休んでまで、私が来る必要あったの? 天音だけいれば十分だったじゃない」
「そのことについては、いずれきちんと話すと言ったでしょう」
「ほら、やっぱりのけ者にしてるじゃない! 昨日、あのお屋敷に着いてからず~~っとそうよ。私ひとり、邪魔者扱い。あからさまに天音と対応変えるなら、最初から連れてかないでよ!」
「郁美っ!」
ルームミラー越しに、母が女子高生を叱りつける。
勝気さを示すように、少女は睨み返してきた。思わず実の母親は、身震いしそうになる。怖い、わけではない。ブレザー姿の少女が醸す、麗しさに、だ。
妹の名は、四乃宮郁美。
鋭い目付きをしていると、16歳とは思えぬ色香があった。我が子ながら、よくここまで端整に・・・と感心するほどの美形だ。
すっと隣に、視線を移す。
同じ顔を持つ美女が、後部座席に並んでいた。
4歳年上の姉、天音。
黒のワンピースを身に着けた以外は、身長も含め、ほとんど姉妹に違いはなかった。双子のような容貌だけでなく、バランスよく張り出すべきところは張り出したスタイルもそっくりだ。
明らかに異なる点といえば、柔らかなウェーブがかかったセミロングの髪が、天音は漆黒で郁美はブラウン、という色くらいか。
細かくみていけば、姉の天音には顎の右に小さな黒子があるのがわかるが、かえってそれが艶やかさを増していた。じっくり比べれば、年齢差相応には、姉妹の間で成熟の度合いは違っている。
近所でも評判の、いや、一部ネットではファンサイトが作られるほどの美人姉妹は、むろん母親にとっても自慢の娘たちであった。
妹の郁美にしても、普段はこんな跳ね返りではない。親目線の贔屓を除いたとしても、心優しい娘であった。
それが今日に限って苛立っているのは、単に鬱蒼とした森林や冷たい雨のせいではないだろう。
「ごめんね、郁美」
スマホを叩く手を、横から伸びた柔らかな掌が包む。
温かかな、手だった。姉は同じ顔の妹と、正面から向き合う。
「あなたを不機嫌にさせているのは、私よ。すべては私が、望んだことなの」
「・・・なにソレ? 意味わかんないよ・・・」
ルームミラーに映る母親の顔が泣きそうに歪んだのを、郁美は気付けなかった。
天音が向ける、真剣で深刻な眼差しに、瞳を逸らすことができなかった。
「感じているんでしょ? あの屋敷で、何が起こったかはわからなくても、何かが起こったことは。それが尋常ではないことと気付いているから、郁美は私のことを心配して苛立っているのね」
「し、心配なんて、ベツに・・・」
頬を赤く染めながら、郁美はこの二日間、山奥の洋館で起こった出来事を思い返す。
確かに、何かが起こったのは感じていた。
いや、よほど鈍感な者でなければ、恐らく誰もがこの異様さには気付く。それほど奇妙な二日間だった。
まず第一に、ケータイの電波も届かぬほどの山深くに、レンガ造りの巨大な屋敷が、一軒だけポツリと建っているのが不自然であった。
父親の話によれば、親戚縁者が所有する別荘なのだという。今回連れて来られるまで、こんな場所があるなど聞いたこともなかった。
次に驚いたのが、屋敷に集まったのは、四乃宮家の者だけではなかったことだ。
その日、血縁関係者が一堂に集められたのだという。だからこその特別な日であり、多人数を収容できるだけの巨大な屋敷だった。
とはいえ、親戚であるはずの彼らに、郁美が見知った顔はひとつもなかった。
何世代も前からの縁者、という名目で集合した人々。それが2、3家族ではない。ざっと見て、20は下らぬ家族が集まっていたのだ。
唐突に増えた、20もの親戚縁者。それだけでも動揺するというのに、ひとつ屋根の下で一泊二日をともにするという、不思議。
「ねえ、なんだったの。アレは?」
すでに何度も繰り返している質問を、郁美は口にした。
そのたびに、父も母も姉も、ただ下を向いた。「いつか話すから」とだけ答えて。
しかし、今の天音は真っ直ぐ妹を見詰め続けた。
「親戚が集まってパーティー、なんてノリじゃなかったよね。なんであのひとたち、あんなにピリピリしてたの? 息が張り詰めそうなくらいに。これからケンカでもするのかと思ったよ」
「・・・それは」
「それに、女の子ばっかりだった。あそこにいた家族の子供たち、みんな。私たちも含めて。これって偶然じゃないよね? 年頃の娘ばかりをあそこに連れてきたのは、なぜ?」
口を挟みかけた母親を、運転席の父が制する。
相変わらず、ヘッドランプにはくねくねと続くカーブと斜めに降る雨が映っていた。
「そして、これが最大の謎よ。・・・どうして天音だけ、ひとり別室に連れていかれたの? 一体、天音の身に何が起こってるの!?」
柔らかな姉の掌を、郁美は両手で強く握り返した。
美しき姉妹が、互いを見つめあう。天井を叩く雨音が、静寂のなかに響いた。
「郁美」
それまで黙っていた父親が、初めて口を開く。
出張が多いことを除けば、ごく普通のサラリーマンである父は、四乃宮家では絶対の存在だった。怒ることも、強制することもほとんどない、静かな男。だが、母親も娘ふたりも、時に発せられる父の言葉を尊重している。
「物事には、知らない方が幸せ、ということもある」
「・・・そんなこと、わかってるケドさ」
「君にも、いつか必ず、全てを知ってもらう時が来るだろう。けれど、今はその時ではない、というのがボクたちの判断だ」
やや厚めの唇を、ブレザー姿の少女はわずかに噛んだ。
「それは私が、まだ子供だから?」
「君を愛するが故の判断だと言っても、信用してくれないかな」
フロントガラスを叩く雨が、一段と強くなった。
闇のなかで、風が勢いを増しているようだった。
「オメガ」
不意に郁美が漏らした、ひとつの言葉。
天音の瞳が、大きく開く。一瞬にして、車内の空気は緊迫した。
「あの屋敷で、たったひとりだけ仲良くなった女の子が言ったの。あれ、知らないんだ? って。それ以上は何も教えてくれなかったけど・・・この言葉にどんな意味があるの?」
再び車内を、沈黙が包み込んだ。
口を開いたのは、麗しき二十歳の乙女だった。
「お父さん。私はやっぱり、郁美にもきちんと説明しておくべきだと思います」
耐え切れなくなったように、母は白いハンカチを取り出した。
目頭を、抑える。五十代になったとは思えぬ白い指先が、細かく震えた。
すすり泣く横で、父は静かに声を発した。
「君がそう言うのなら、ボクは止めはしないよ」
「ありがとう、お父さん。大丈夫です、このコならきっと・・・受け止めてくれます」
強い光を放つ姉の瞳に、女子高生は自然に姿勢を正していた。
なんて美しく、澄み切った瞳だろう。
同じ顔を持ちながら、郁美は天音の美貌に身震いする想いがした。大きく、魅惑的な瞳。すっと高く通った鼻梁。ややぼってりとした、艶やかな桜色の唇・・・。卵型の輪郭にバランスよく配置された造形は、美神の仕業としか思えぬ奇跡。
過酷な現実を聞こうという直前、陶酔にも似た心地が少女を襲ったのは、不可思議な現象だった。
あるいはそれは、どこか心理的な逃避が作用したためだったのかもしれない。
だが、その先の告白が紡がれる前に、悲劇は起きた。
ドオオオオオッッ!!!
「あッ!?」
突如立ち昇った轟音と火花が、フロントガラスを覆い尽くした。
浮き上がった4人乗りのセダンカーは、ガードレールを越えて、崖下へと転落していった。
0
お気に入りに追加
14
あなたにおすすめの小説


セクスカリバーをヌキました!
桂
ファンタジー
とある世界の森の奥地に真の勇者だけに抜けると言い伝えられている聖剣「セクスカリバー」が岩に刺さって存在していた。
国一番の剣士の少女ステラはセクスカリバーを抜くことに成功するが、セクスカリバーはステラの膣を鞘代わりにして収まってしまう。
ステラはセクスカリバーを抜けないまま武闘会に出場して……

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~
桂
ファンタジー
探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。
そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。
そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。
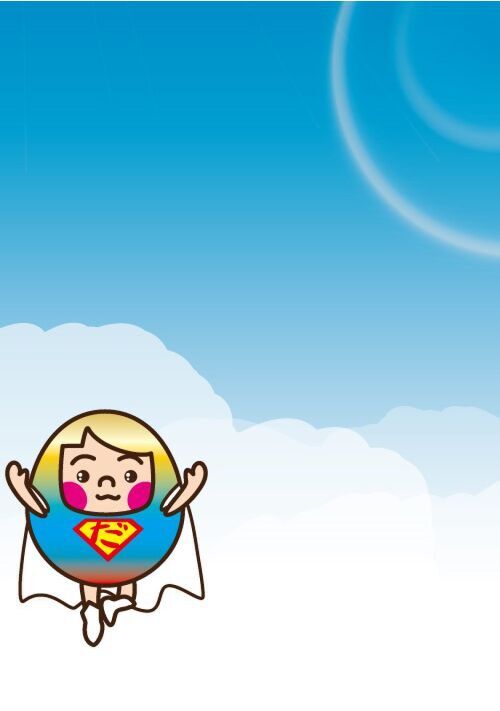
エスカレーター・ガール
転生新語
SF
永遠不変の一八才である、スーパーヒロインの私は、決戦の直前を二十代半ばの恋人と過ごしている。
戦うのは私、一人。負ければ地球は壊滅するだろう。ま、安心してよ私は勝つから。それが私、エスカレーター・ガールだ!
カクヨム、小説家になろうに投稿しています。
カクヨム→https://kakuyomu.jp/works/16817330660868319317
小説家になろう→https://ncode.syosetu.com/n5833ii/

魔法少女になれたなら【完結済み】
M・A・J・O
ファンタジー
【第5回カクヨムWeb小説コンテスト、中間選考突破!】
【第2回ファミ通文庫大賞、中間選考突破!】
【第9回ネット小説大賞、一次選考突破!】
とある普通の女子小学生――“椎名結衣”はある日一冊の本と出会う。
そこから少女の生活は一変する。
なんとその本は魔法のステッキで?
魔法のステッキにより、強引に魔法少女にされてしまった結衣。
異能力の戦いに戸惑いながらも、何とか着実に勝利を重ねて行く。
これは人間の願いの物語。
愉快痛快なステッキに振り回される憐れな少女の“願い”やいかに――
謎に包まれた魔法少女劇が今――始まる。
・表紙絵はTwitterのフォロワー様より。

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!

【R18】幼馴染がイケメン過ぎる
ケセラセラ
恋愛
双子の兄弟、陽介と宗介は一卵性の双子でイケメンのお隣さん一つ上。真斗もお隣さんの同級生でイケメン。
幼稚園の頃からずっと仲良しで4人で遊んでいたけど、大学生にもなり他にもお友達や彼氏が欲しいと思うようになった主人公の吉本 華。
幼馴染の関係は壊したくないのに、3人はそうは思ってないようで。
関係が変わる時、歯車が大きく動き出す。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















