お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!



隠せぬ心臓
MPE事業部
ホラー
これは江戸川乱歩の命名の元にもなったアメリカの作家 エドガー アラン ポーの短すぎる短編 The Tell-Tale Heart をわかりやすい日本語に翻訳したものです。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

怪物どもが蠢く島
湖城マコト
ホラー
大学生の綿上黎一は謎の組織に拉致され、絶海の孤島でのデスゲームに参加させられる。
クリア条件は至ってシンプル。この島で二十四時間生き残ることのみ。しかしこの島には、組織が放った大量のゾンビが蠢いていた。
黎一ら十七名の参加者は果たして、このデスゲームをクリアすることが出来るのか?
次第に明らかになっていく参加者達の秘密。この島で蠢く怪物は、決してゾンビだけではない。

煩い人
星来香文子
ホラー
陽光学園高学校は、新校舎建設中の間、夜間学校・月光学園の校舎を昼の間借りることになった。
「夜七時以降、陽光学園の生徒は校舎にいてはいけない」という校則があるのにも関わらず、ある一人の女子生徒が忘れ物を取りに行ってしまう。
彼女はそこで、肌も髪も真っ白で、美しい人を見た。
それから彼女は何度も狂ったように夜の学校に出入りするようになり、いつの間にか姿を消したという。
彼女の親友だった美波は、真相を探るため一人、夜間学校に潜入するのだが……
(全7話)
※タイトルは「わずらいびと」と読みます
※カクヨムでも掲載しています
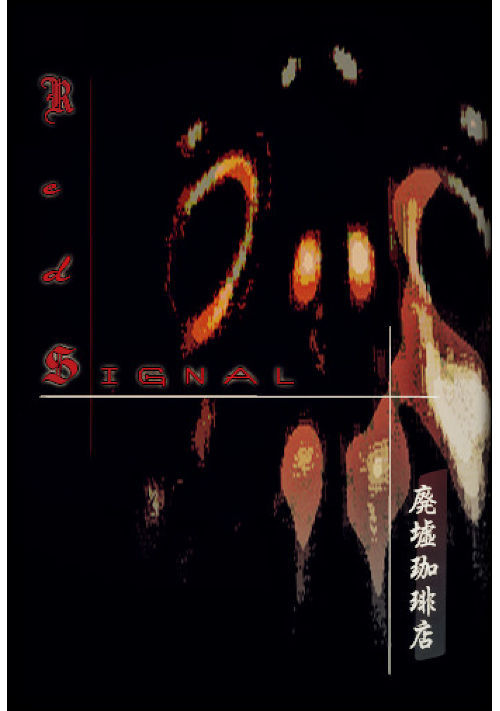
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















