2 / 25
ふたりだけのランチタイム1
しおりを挟む
皆川がホワイトボードに、『サイズ、新書版』と書き込んだ。
「では、文庫版ではなく新書版で刊行することにしましょう。次に、大まかな執筆者を決めませんか」
「梶先生はどうでしょうか。九月に他社で発行した新刊も好調のようです」
ひとりの編集者の提案に皆川が返事をしない。少し表情に翳りが見える。
逢坂は持っていた書類を、音を立てて机に置いた。
「梶竜一郎はやめておこう。流行っているけれど、書き下ろしだから慎重に行きたい」
部下たちが顔を見合わせ、声を潜めている。皆川の顔を見つめている者もいる。
逢坂はこめかみを押さえてしばし考えた。
「宇津木先生はどうだ。先生はちょうどターゲットと同世代だ。読者の共感が得られると思う。それに、先月掲載した短編も好評だったからな」
多くの部下が頷く。逢坂は息を吐いた。
(意見を覆すには、別の案を出すのが一番早い)
皆川を見ると目線だけで礼の合図をしてきた。逢坂は頷いた。
昼前に会議は終了した。昼休みまで少し時間があったが、解散することにした。部下たちが次々と会議室を出て行く。
ひとりが皆川に近づいた。さっき、梶を推した編集者だった。
「困るんだよな、梶先生の元恋人がいると。なかなか意見が通らないよ」
小さな声だったが、逢坂は聞き逃さなかった。
「おい、待て」
立ち上がり、足早に部下に近づく。肩を掴んで振り向かせた。
(こういうときは、怒りを秘めて静かに楽しく笑え)
逢坂は心の内で自分に言い聞かせた。腹に力を溜める。唇を歪めて言った。
「そんなに梶先生にご執心なら、あいつの別荘に行ってもいいんだぞ。先生は最近、男に飢えているそうだ。もちろん、有給休暇をやろう」
結構です、と言って部下は顔を引きつらせた。慌てて会議室を出て行く。走り去る音を聞いていると、張りつめていたものが弛むのを感じた。
「ありがとうございます、編集長」
逢坂は、礼を言う皆川の肩にそっと手を置いた。
「気にするな。本当は違うんだから」
「編集長、行きましょう。早くお昼にしましょうよ」
中島に急かされ、逢坂は会議室を出た。もう少し皆川を励ましたかった。狭い廊下を逢坂と中島は、並んで歩いた。
「皆川さん、つらいですよね。梶先生の話題が出る度に変な目で見られていますよ。でも」
一拍置いて、中島が口を開いた。
「編集長は皆川さんを気にし過ぎですよ。過保護というか、親みたいだ……」
逢坂は中島を見た。冷たく表情を消した顔だった。
「あれこれ詮索されて、なかったことまで周りから言われているんだぞ。皆川の気持ちを考えると助けたくなるだろ?」
中島の返事はなかった。
噂の原因は、皆川が前の編集部にいたときに起こった。
皆川が原稿を取りに行こうと梶の家に行ったら、迫られた。皆川が逃げたので未遂に終わった。
噂では、ふたりは付き合っていたとことになっている。
逢坂は皆川本人から、真実を聞いていた。
逢坂は梶の姿を思い浮かべた。
髪を暗い赤に染めて緩やかなパーマをかけている。丁寧な物腰だが、会う度に表情が読み取れない男だなと思っている。
梶の切れ長の瞳と囁くような小さな声を思い出し、心の底をくすぐられたような気がした。
「昔の梶は誠実だったのになあ。どうして変ったんだろう」
「昔って、梶先生と知り合いなんですか」
逢坂は、ジャケットの上から胃の辺りを撫でた。
「梶は大学の後輩だ。それだけだ」
中島は意外そうな顔をした。逢坂はそれ以上、語らなかった。
編集部へ戻ると、逢坂と中島は、昼食を取った。他の編集者は皆、外へ食べに行っている。
編集部員のデスクの端に、古びた革張りのソファと低いガラスのテーブルがある。
逢坂と中島は直角に置いてあるソファにそれぞれ座った。互いのジャケットは、それぞれのデスクの椅子にかけてある。
テーブルにはいつものように青い小型ラジオを置いた。逢坂が家から持ってきたものだ。
司会者の女性がリスナーの投稿を読み上げていた。耳を傾けながら、逢坂と中島は話をしていた。
「中島。おまえ、またパンにしたのか。夜まで持たないぞ。駅前の定食屋に行ったらどうだ」
「俺は編集長と食べたいからいいんです。編集長こそ、そんな女子高生みたいな弁当じゃ貧血で倒れますよ。しっかり食べて、もっと太ったほうがいいです」
「燃費がいいから大丈夫だよ」
本当は、少しでも食べ過ぎると胃がもたれてしまって、そのあとがつらくなるからだった。両手に乗るくらいのこの弁当箱でも、多いと感じることがある。
中島の食事は、いつものようにあんぱんと缶コーヒーだった。もうふたつあるうちのひとつを食べ終え、二個目に手をつけている。
「編集長はまめですよね。ひとり暮らしなのに、弁当作って、お茶まで持ってくるなんて」
「作れば安いし、残り物が片付くんだよ」
「それじゃあ、俺のも作ってください」
「え!?」
予想外の返事に、逢坂は大きな声で聞き返した。中島は親指についたあんこを舐めながら、逢坂を見た。
「食事代は負担しますから。お揃いの弁当にしましょうよ」
「おまえな……そんな恥ずかしいことできるわけないだろ。親と暮らしているなら、作ってもらったらいいじゃないか」
「この歳で親の弁当なんて恥ずかしいです」
「中島。上司に作ってもらうほうがずっと恥ずかしいんじゃないか……?」
中島はときどき、平然と突拍子もないことを言う。この発想が会議での斬新な意見に繋がるのかと逢坂は感心していた。
歳の離れた弟ができたような気持ちがして、こうして一緒に過ごすのは楽しい。昼食の時間はあっという間に過ぎてしまう。
中島は缶コーヒーをひとくち飲むと、困ったように笑った。
「最近親が、結婚しろとか、彼女はいないのかって煩いんですよ。俺、まだ二十七なのに」
「それは、孫の顔が見たいのかもしれないな。俺も結婚したときは母親によく言われたよ。早く子供を作れってさ」
「そういえば、編集長は結婚していたんですよね」
「ああ。でも再婚したとしても、もう母親がいないから見せられないな。親父も俺が大学生のときに亡くなったし」
中島が笑みを消して、缶コーヒーを置いた。そうですか、とだけ呟いた。逢坂は箸を置いて中島を見た。話題を変えたほうがいいと感じた。
「では、文庫版ではなく新書版で刊行することにしましょう。次に、大まかな執筆者を決めませんか」
「梶先生はどうでしょうか。九月に他社で発行した新刊も好調のようです」
ひとりの編集者の提案に皆川が返事をしない。少し表情に翳りが見える。
逢坂は持っていた書類を、音を立てて机に置いた。
「梶竜一郎はやめておこう。流行っているけれど、書き下ろしだから慎重に行きたい」
部下たちが顔を見合わせ、声を潜めている。皆川の顔を見つめている者もいる。
逢坂はこめかみを押さえてしばし考えた。
「宇津木先生はどうだ。先生はちょうどターゲットと同世代だ。読者の共感が得られると思う。それに、先月掲載した短編も好評だったからな」
多くの部下が頷く。逢坂は息を吐いた。
(意見を覆すには、別の案を出すのが一番早い)
皆川を見ると目線だけで礼の合図をしてきた。逢坂は頷いた。
昼前に会議は終了した。昼休みまで少し時間があったが、解散することにした。部下たちが次々と会議室を出て行く。
ひとりが皆川に近づいた。さっき、梶を推した編集者だった。
「困るんだよな、梶先生の元恋人がいると。なかなか意見が通らないよ」
小さな声だったが、逢坂は聞き逃さなかった。
「おい、待て」
立ち上がり、足早に部下に近づく。肩を掴んで振り向かせた。
(こういうときは、怒りを秘めて静かに楽しく笑え)
逢坂は心の内で自分に言い聞かせた。腹に力を溜める。唇を歪めて言った。
「そんなに梶先生にご執心なら、あいつの別荘に行ってもいいんだぞ。先生は最近、男に飢えているそうだ。もちろん、有給休暇をやろう」
結構です、と言って部下は顔を引きつらせた。慌てて会議室を出て行く。走り去る音を聞いていると、張りつめていたものが弛むのを感じた。
「ありがとうございます、編集長」
逢坂は、礼を言う皆川の肩にそっと手を置いた。
「気にするな。本当は違うんだから」
「編集長、行きましょう。早くお昼にしましょうよ」
中島に急かされ、逢坂は会議室を出た。もう少し皆川を励ましたかった。狭い廊下を逢坂と中島は、並んで歩いた。
「皆川さん、つらいですよね。梶先生の話題が出る度に変な目で見られていますよ。でも」
一拍置いて、中島が口を開いた。
「編集長は皆川さんを気にし過ぎですよ。過保護というか、親みたいだ……」
逢坂は中島を見た。冷たく表情を消した顔だった。
「あれこれ詮索されて、なかったことまで周りから言われているんだぞ。皆川の気持ちを考えると助けたくなるだろ?」
中島の返事はなかった。
噂の原因は、皆川が前の編集部にいたときに起こった。
皆川が原稿を取りに行こうと梶の家に行ったら、迫られた。皆川が逃げたので未遂に終わった。
噂では、ふたりは付き合っていたとことになっている。
逢坂は皆川本人から、真実を聞いていた。
逢坂は梶の姿を思い浮かべた。
髪を暗い赤に染めて緩やかなパーマをかけている。丁寧な物腰だが、会う度に表情が読み取れない男だなと思っている。
梶の切れ長の瞳と囁くような小さな声を思い出し、心の底をくすぐられたような気がした。
「昔の梶は誠実だったのになあ。どうして変ったんだろう」
「昔って、梶先生と知り合いなんですか」
逢坂は、ジャケットの上から胃の辺りを撫でた。
「梶は大学の後輩だ。それだけだ」
中島は意外そうな顔をした。逢坂はそれ以上、語らなかった。
編集部へ戻ると、逢坂と中島は、昼食を取った。他の編集者は皆、外へ食べに行っている。
編集部員のデスクの端に、古びた革張りのソファと低いガラスのテーブルがある。
逢坂と中島は直角に置いてあるソファにそれぞれ座った。互いのジャケットは、それぞれのデスクの椅子にかけてある。
テーブルにはいつものように青い小型ラジオを置いた。逢坂が家から持ってきたものだ。
司会者の女性がリスナーの投稿を読み上げていた。耳を傾けながら、逢坂と中島は話をしていた。
「中島。おまえ、またパンにしたのか。夜まで持たないぞ。駅前の定食屋に行ったらどうだ」
「俺は編集長と食べたいからいいんです。編集長こそ、そんな女子高生みたいな弁当じゃ貧血で倒れますよ。しっかり食べて、もっと太ったほうがいいです」
「燃費がいいから大丈夫だよ」
本当は、少しでも食べ過ぎると胃がもたれてしまって、そのあとがつらくなるからだった。両手に乗るくらいのこの弁当箱でも、多いと感じることがある。
中島の食事は、いつものようにあんぱんと缶コーヒーだった。もうふたつあるうちのひとつを食べ終え、二個目に手をつけている。
「編集長はまめですよね。ひとり暮らしなのに、弁当作って、お茶まで持ってくるなんて」
「作れば安いし、残り物が片付くんだよ」
「それじゃあ、俺のも作ってください」
「え!?」
予想外の返事に、逢坂は大きな声で聞き返した。中島は親指についたあんこを舐めながら、逢坂を見た。
「食事代は負担しますから。お揃いの弁当にしましょうよ」
「おまえな……そんな恥ずかしいことできるわけないだろ。親と暮らしているなら、作ってもらったらいいじゃないか」
「この歳で親の弁当なんて恥ずかしいです」
「中島。上司に作ってもらうほうがずっと恥ずかしいんじゃないか……?」
中島はときどき、平然と突拍子もないことを言う。この発想が会議での斬新な意見に繋がるのかと逢坂は感心していた。
歳の離れた弟ができたような気持ちがして、こうして一緒に過ごすのは楽しい。昼食の時間はあっという間に過ぎてしまう。
中島は缶コーヒーをひとくち飲むと、困ったように笑った。
「最近親が、結婚しろとか、彼女はいないのかって煩いんですよ。俺、まだ二十七なのに」
「それは、孫の顔が見たいのかもしれないな。俺も結婚したときは母親によく言われたよ。早く子供を作れってさ」
「そういえば、編集長は結婚していたんですよね」
「ああ。でも再婚したとしても、もう母親がいないから見せられないな。親父も俺が大学生のときに亡くなったし」
中島が笑みを消して、缶コーヒーを置いた。そうですか、とだけ呟いた。逢坂は箸を置いて中島を見た。話題を変えたほうがいいと感じた。
0
お気に入りに追加
95
あなたにおすすめの小説

【完結】別れ……ますよね?
325号室の住人
BL
☆全3話、完結済
僕の恋人は、テレビドラマに数多く出演する俳優を生業としている。
ある朝、テレビから流れてきたニュースに、僕は恋人との別れを決意した。
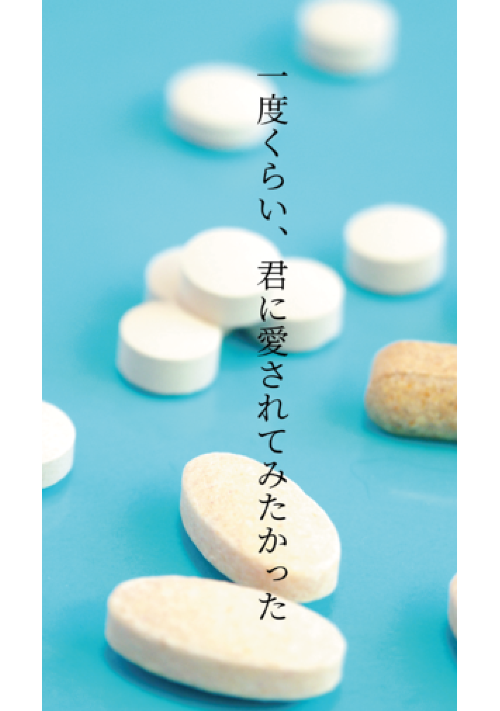

冴えないおじさんが雌になっちゃうお話。
丸井まー(旧:まー)
BL
馴染みの居酒屋で冴えないおじさんが雌オチしちゃうお話。
イケメン青年×オッサン。
リクエストをくださった棗様に捧げます!
【リクエスト】冴えないおじさんリーマンの雌オチ。
楽しいリクエストをありがとうございました!
※ムーンライトノベルズさんでも公開しております。

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!
灯璃
BL
家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。
何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。
仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。
思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。
みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。
※完結しました!ありがとうございました!

お客様と商品
あかまロケ
BL
馬鹿で、不細工で、性格最悪…なオレが、衣食住提供と引き換えに体を売る相手は高校時代一度も面識の無かったエリートモテモテイケメン御曹司で。オレは商品で、相手はお客様。そう思って毎日せっせとお客様に尽くす涙ぐましい努力のオレの物語。(*ムーンライトノベルズ・pixivにも投稿してます。)

有能社長秘書のマンションでテレワークすることになった平社員の俺
高菜あやめ
BL
【マイペース美形社長秘書×平凡新人営業マン】会社の方針で社員全員リモートワークを義務付けられたが、中途入社二年目の営業・野宮は困っていた。なぜならアパートのインターネットは遅すぎて仕事にならないから。なんとか出社を許可して欲しいと上司に直談判したら、社長の呼び出しをくらってしまい、なりゆきで社長秘書・入江のマンションに居候することに。少し冷たそうでマイペースな入江と、ちょっとビビりな野宮はうまく同居できるだろうか? のんびりほのぼのテレワークしてるリーマンのラブコメディです

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語
紅林
BL
『桜田門学院高等学校』
日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ
しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ
そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















