31 / 37
第六章
31
しおりを挟む
この一年、どれだけこの路線を使っただろう。鮎原は、東京駅から在来線に乗り換え武村のマンションに向っていた。降り立つホームも自動改札も、駅から続く商店街を抜け少し坂を上がり、見えてきた斜め向かいにある喫茶店も、いわば通い慣れた道だ。
歩きながら鮎原は少し笑っている自分に気づく。武村には明け方メールを入れていた。今さら何だ、と言われるのも覚悟の上だ。いつかのように逃げない。たとえ罵倒されようと、会うと決めた。
エレベーターで上がり、武村の部屋の前で鮎原は一呼吸置く。そしてインターフォンを押した。
「……やあ」
心を決めてきた割りには、かなり間の抜けた挨拶が口から出た。しかし、おはよう、でもないしさりとて、こんにちは、と言うのも何か微妙だ、などとどうでもいいことが頭を過ぎり、結局のところ落ち着きをなくしていると自覚する。
そんな鮎原に、どこか憔悴しているようにも見えた武村は、体をずらし中に入るよう顎をしゃくる。
「なんか久しぶりだな、お前の部屋」
思えば随分来ていなかった。上がってすぐのダイニングキッチン、見渡した先の流しに、洗って伏せられていた二つの色違いのカップに気づく。食器棚の前に飾られた二体のマスコット人形。すべて自分の知らないものだった。
それをとやかく言うつもりは毛頭なかった。鮎原はただ事実として胸にしまう。
続きの居間に向かい、形ばかりに並べた応接セットに腰を下ろした。テーブルの上の灰皿には、吸殻が積み上がっていた。
同じように座った武村が、撫でつけていない髪をかき上げて、横に置いていた煙草に手を伸ばす。
「灰皿、片づけろよ。山になってる」
「……後でやるさ」
火を点け紫煙を吐き出した武村に、鮎原は「じゃあ」と言って投げ出されていた煙草から一本取ると、銜えて自分も火を点けた。
滅多にない行動を見せた鮎原に、武村は何も言わなかった。
「あの、さ」
何から話そうと惑いながら、鮎原はさほど長くなっていない煙草の灰を灰皿に落とす。
「今日、来たのは……」
「仕事ミスっちまった」
切り出した鮎原に、武村の声が被さる。
「ミス?」
鮎原は、武村のらしくない話に聞き返した。
「……なに、大したことはないんだ。ただ、ちょっとした連絡ミスで。商談に穴空けそうになった」
すぐに気づいてフォローをしたから大事には至らなかったと続けるも、これまで完璧にやってきた仕事に水を差すのには十分だったと吐露する。
「……お前、相変わらずか。自分が分かっているからって、周囲も分かってると思っちまう」
営業課で机を並べていたころは、武村のそんな一面についつい気を揉んだものだ。
「そうなんだよな。で、思い出してしまったんだ。本社にいたころは、お前がフォローをしてくれていたんだなって」
それを、つまらないことで今さらのように思い出してしまったと、武村は静かに息をついた。
話が途切れて、武村が二本目の煙草に手を伸ばした。その煙草が半分ほど灰になったころ、ようやく口を開いた。
「今まで、俺何やってたんだろうな」
「武村――、お前はいつだって頑張ってきただろ。仕事だって誰よりも結果出して」
気弱を見せた武村の代わりに弁解する。鮎原の知る武村は、いつも人の中心にいて前を向いていた。
「だが、それはお前が……お前がいてくれたからだ。なのに、そんな一番肝心のことを忘れて。俺は、自分だけの力でやってきたんだって勘違いして」
武村は頭を抱えて顔を伏せた。
「本当は、お前はもっと仕事ができるのに自分を二の次にして支えていてくれたのに。俺はいつの間にか、お前を重いと感じるようになっていたんだ。驕りもいいとこだ」
「お前のせいじゃない。俺だって、尽くしているって、自分に酔ってたんだ。そうすることがお前への気持ちに応えることだと。重いと思われて当然だよ。勘違いしてたんだ、俺も」
武村に応えることこそが自分の存在理由。求めてくれた手を失いたくない一心で。
どう気持ちを返せばいいのか分からず、武村のために、と思ってやっていたことは、つまるところ独善だった。
東京転勤が決まったときに、一緒について行っていれば、また違っていたのかもしれない、とふと思う。しかし遠からず触れ合わせているはずの気持ちに距離を覚えただろう。どんなに近くにいても届かないもどかしさ。体を重ねていてもずれていく心。もしかしたらそのときどき、ずれを覚えたときに自分の正直な気持ちを伝えていればあるいは、と縋りつくには脆すぎる考えも浮かぶ。まだこの手を伸ばせば、互いの心に触れることはできるだろうか。そんな思いも、今なお胸にあるのは否定しないけれど。
だがもう、過ぎてしまったことだ。何度も繰り返し巡らせて、答えを出したのだ。もう還ることはない。
「佳史――どうしてそんなことを言うんだ。何で責めないんだ」
「責められるわけない。お前が悪いわけじゃない」
吐き出された言葉が苦く鮎原の胸を締めつける。こんな愛し方しかできなかった自分の誤りだった。
「ずっとお前に甘えていたんだな。バカだ、俺は。お前が合わせてくれていたなんて考えもしないで、自分勝手で」
「武村」
自分たちは似ていたのだと鮎原は改めて思った。仕事に打ち込む武村を支えることで自分を見い出していた鮎原と、鮎原の存在を当たり前だと寄りかかっていた武村。一見正反対の性格のようでも心のベクトルは同じ。互いが依存し合うことで、均衡を保っていた。
そんな愛の形もあるだろう。けれど自分は、違った。
本当は認められたくて、負けたくなくて、自我の塊を抱えていたのに。嫉妬、羨望、武村と対等でありたいというジレンマ、尽くしていると思うことで抑え込んでいた。
何かバランスを崩せば引っ繰り返ってしまいそうな不安から目を逸らして、安易に流されることをしてしまった。
武村が三本目の煙草に手を伸ばして火を点ける。鮎原も勧められたが、今度は手に取らなかった。
煙草の先端が赤く燃えていく。そして灰になって落とされるのを見つめ、鮎原は口を開いた。このために来たのだ。
「俺はお前の傍にはいられない」
ずっと傍にいたかった。いて欲しかった。そう願った気持ちも確かにあったけれど。武村に向ける思いは、もう恋と呼ぶことはできない。
「和仁――終わらせよう」
終止符だ。ぎゅっと何かが胸を締めつける。鮎原は込み上げてくるものを嚥下した。
「終わるのか、佳史」
武村も何かを飲み込むように、目を伏せた。
これから武村と過ごした時間、抱き合った夜も、すべてが彼方に遠い日となるのだ。
忘れない。憎み合って別れるわけではない。ただ次に恋をするなら、同じ間違いはするまいと胸に刻む。思いやっていると履き違えた自己満足は要らない。
歩きながら鮎原は少し笑っている自分に気づく。武村には明け方メールを入れていた。今さら何だ、と言われるのも覚悟の上だ。いつかのように逃げない。たとえ罵倒されようと、会うと決めた。
エレベーターで上がり、武村の部屋の前で鮎原は一呼吸置く。そしてインターフォンを押した。
「……やあ」
心を決めてきた割りには、かなり間の抜けた挨拶が口から出た。しかし、おはよう、でもないしさりとて、こんにちは、と言うのも何か微妙だ、などとどうでもいいことが頭を過ぎり、結局のところ落ち着きをなくしていると自覚する。
そんな鮎原に、どこか憔悴しているようにも見えた武村は、体をずらし中に入るよう顎をしゃくる。
「なんか久しぶりだな、お前の部屋」
思えば随分来ていなかった。上がってすぐのダイニングキッチン、見渡した先の流しに、洗って伏せられていた二つの色違いのカップに気づく。食器棚の前に飾られた二体のマスコット人形。すべて自分の知らないものだった。
それをとやかく言うつもりは毛頭なかった。鮎原はただ事実として胸にしまう。
続きの居間に向かい、形ばかりに並べた応接セットに腰を下ろした。テーブルの上の灰皿には、吸殻が積み上がっていた。
同じように座った武村が、撫でつけていない髪をかき上げて、横に置いていた煙草に手を伸ばす。
「灰皿、片づけろよ。山になってる」
「……後でやるさ」
火を点け紫煙を吐き出した武村に、鮎原は「じゃあ」と言って投げ出されていた煙草から一本取ると、銜えて自分も火を点けた。
滅多にない行動を見せた鮎原に、武村は何も言わなかった。
「あの、さ」
何から話そうと惑いながら、鮎原はさほど長くなっていない煙草の灰を灰皿に落とす。
「今日、来たのは……」
「仕事ミスっちまった」
切り出した鮎原に、武村の声が被さる。
「ミス?」
鮎原は、武村のらしくない話に聞き返した。
「……なに、大したことはないんだ。ただ、ちょっとした連絡ミスで。商談に穴空けそうになった」
すぐに気づいてフォローをしたから大事には至らなかったと続けるも、これまで完璧にやってきた仕事に水を差すのには十分だったと吐露する。
「……お前、相変わらずか。自分が分かっているからって、周囲も分かってると思っちまう」
営業課で机を並べていたころは、武村のそんな一面についつい気を揉んだものだ。
「そうなんだよな。で、思い出してしまったんだ。本社にいたころは、お前がフォローをしてくれていたんだなって」
それを、つまらないことで今さらのように思い出してしまったと、武村は静かに息をついた。
話が途切れて、武村が二本目の煙草に手を伸ばした。その煙草が半分ほど灰になったころ、ようやく口を開いた。
「今まで、俺何やってたんだろうな」
「武村――、お前はいつだって頑張ってきただろ。仕事だって誰よりも結果出して」
気弱を見せた武村の代わりに弁解する。鮎原の知る武村は、いつも人の中心にいて前を向いていた。
「だが、それはお前が……お前がいてくれたからだ。なのに、そんな一番肝心のことを忘れて。俺は、自分だけの力でやってきたんだって勘違いして」
武村は頭を抱えて顔を伏せた。
「本当は、お前はもっと仕事ができるのに自分を二の次にして支えていてくれたのに。俺はいつの間にか、お前を重いと感じるようになっていたんだ。驕りもいいとこだ」
「お前のせいじゃない。俺だって、尽くしているって、自分に酔ってたんだ。そうすることがお前への気持ちに応えることだと。重いと思われて当然だよ。勘違いしてたんだ、俺も」
武村に応えることこそが自分の存在理由。求めてくれた手を失いたくない一心で。
どう気持ちを返せばいいのか分からず、武村のために、と思ってやっていたことは、つまるところ独善だった。
東京転勤が決まったときに、一緒について行っていれば、また違っていたのかもしれない、とふと思う。しかし遠からず触れ合わせているはずの気持ちに距離を覚えただろう。どんなに近くにいても届かないもどかしさ。体を重ねていてもずれていく心。もしかしたらそのときどき、ずれを覚えたときに自分の正直な気持ちを伝えていればあるいは、と縋りつくには脆すぎる考えも浮かぶ。まだこの手を伸ばせば、互いの心に触れることはできるだろうか。そんな思いも、今なお胸にあるのは否定しないけれど。
だがもう、過ぎてしまったことだ。何度も繰り返し巡らせて、答えを出したのだ。もう還ることはない。
「佳史――どうしてそんなことを言うんだ。何で責めないんだ」
「責められるわけない。お前が悪いわけじゃない」
吐き出された言葉が苦く鮎原の胸を締めつける。こんな愛し方しかできなかった自分の誤りだった。
「ずっとお前に甘えていたんだな。バカだ、俺は。お前が合わせてくれていたなんて考えもしないで、自分勝手で」
「武村」
自分たちは似ていたのだと鮎原は改めて思った。仕事に打ち込む武村を支えることで自分を見い出していた鮎原と、鮎原の存在を当たり前だと寄りかかっていた武村。一見正反対の性格のようでも心のベクトルは同じ。互いが依存し合うことで、均衡を保っていた。
そんな愛の形もあるだろう。けれど自分は、違った。
本当は認められたくて、負けたくなくて、自我の塊を抱えていたのに。嫉妬、羨望、武村と対等でありたいというジレンマ、尽くしていると思うことで抑え込んでいた。
何かバランスを崩せば引っ繰り返ってしまいそうな不安から目を逸らして、安易に流されることをしてしまった。
武村が三本目の煙草に手を伸ばして火を点ける。鮎原も勧められたが、今度は手に取らなかった。
煙草の先端が赤く燃えていく。そして灰になって落とされるのを見つめ、鮎原は口を開いた。このために来たのだ。
「俺はお前の傍にはいられない」
ずっと傍にいたかった。いて欲しかった。そう願った気持ちも確かにあったけれど。武村に向ける思いは、もう恋と呼ぶことはできない。
「和仁――終わらせよう」
終止符だ。ぎゅっと何かが胸を締めつける。鮎原は込み上げてくるものを嚥下した。
「終わるのか、佳史」
武村も何かを飲み込むように、目を伏せた。
これから武村と過ごした時間、抱き合った夜も、すべてが彼方に遠い日となるのだ。
忘れない。憎み合って別れるわけではない。ただ次に恋をするなら、同じ間違いはするまいと胸に刻む。思いやっていると履き違えた自己満足は要らない。
0
波奈海月/ブログ
【オレンジとシェリー】
【オレンジとシェリー】
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

セカンドコンタクト
アカネラヤ
BL
弥汲佑哉(ヤクミユウヤ)は、とあるネットゲームに執心する二十七歳のサラリーマン。そこで出逢ったギルドメンバーであるゲームネーム《セカイ》と、ひょんなことからお互い共通の通話アプリのIDを持っていることが判明し。そこからほぼ毎週、彼と通話をしながらネットゲームをするのが常となっていた。通話を通じるうちにだんだんとセカイに惹かれていく弥汲。
そんなある時。いつものように通話をする予定が、セカイの通話が不調になり彼の様子もおかしいため、弥汲は単身東京から大阪にあるセカイ邸に向かう事を決意するのだった。
長年想いを密かに募らせていた相手の自宅に到着し来客すると、そこにはとんでもない姿の想い人が立っていて……?

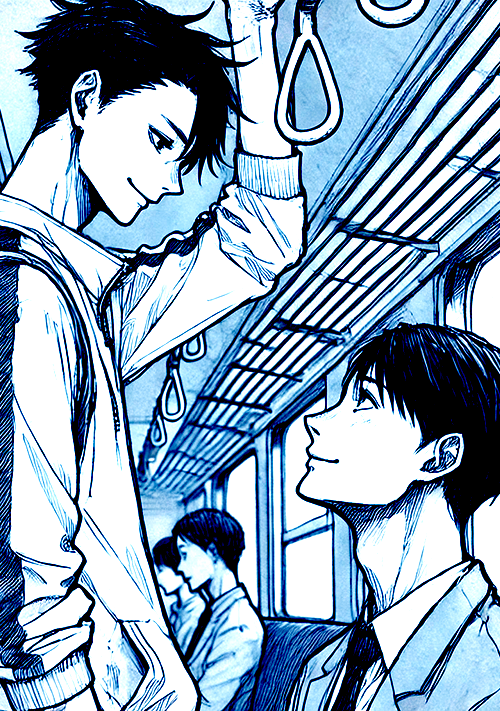
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

【完結】ぎゅって抱っこして
かずえ
BL
幼児教育学科の短大に通う村瀬一太。訳あって普通の高校に通えなかったため、働いて貯めたお金で二年間だけでもと大学に入学してみたが、学費と生活費を稼ぎつつ学校に通うのは、考えていたよりも厳しい……。
でも、頼れる者は誰もいない。
自分で頑張らなきゃ。
本気なら何でもできるはず。
でも、ある日、金持ちの坊っちゃんと心の中で呼んでいた松島晃に苦手なピアノの課題で助けてもらってから、どうにも自分の心がコントロールできなくなって……。

金色の恋と愛とが降ってくる
鳩かなこ
BL
もう18歳になるオメガなのに、鶯原あゆたはまだ発情期の来ていない。
引き取られた富豪のアルファ家系の梅渓家で
オメガらしくないあゆたは厄介者扱いされている。
二学期の初めのある日、委員長を務める美化委員会に
転校生だというアルファの一年生・八月一日宮が参加してくれることに。
初のアルファの後輩は初日に遅刻。
やっと顔を出した八月一日宮と出会い頭にぶつかって、あゆたは足に怪我をしてしまう。
転校してきた訳アリ? 一年生のアルファ×幸薄い自覚のない未成熟のオメガのマイペース初恋物語。
オメガバースの世界観ですが、オメガへの差別が社会からなくなりつつある現代が舞台です。
途中主人公がちょっと不憫です。
性描写のあるお話にはタイトルに「*」がついてます。

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語
紅林
BL
『桜田門学院高等学校』
日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ
しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ
そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である

禁断の祈祷室
土岐ゆうば(金湯叶)
BL
リュアオス神を祀る神殿の神官長であるアメデアには専用の祈祷室があった。
アメデア以外は誰も入ることが許されない部屋には、神の像と燭台そして聖典があるだけ。窓もなにもなく、出入口は木の扉一つ。扉の前には護衛が待機しており、アメデア以外は誰もいない。
それなのに祈祷が終わると、アメデアの体には情交の痕がある。アメデアの聖痕は濃く輝き、その強力な神聖力によって人々を助ける。
救済のために神は神官を抱くのか。
それとも愛したがゆえに彼を抱くのか。
神×神官の許された神秘的な夜の話。
※小説家になろう(ムーンライトノベルズ)でも掲載しています。

Take On Me
マン太
BL
親父の借金を返済するため、ヤクザの若頭、岳(たける)の元でハウスキーパーとして働く事になった大和(やまと)。
初めは乗り気でなかったが、持ち前の前向きな性格により、次第に力を発揮していく。
岳とも次第に打ち解ける様になり…。
軽いノリのお話しを目指しています。
※BLに分類していますが軽めです。
※他サイトへも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















