6 / 37
第二章
6
しおりを挟む
【2】
「そろそろ寝るかな。まだちょっと早いけど」
明日の土曜日は、武村がこっちに来る番だった。だから午前中に部屋の片づけと買い物を済ませておけばいい。鮎原はそう予定を立てていた。
椎名に頼まれた商品写真は、妹尾のおかげもあって木曜にはすべて撮り終え、データベース化した。これでいつでも部内のパソコンで参照できる。後は必要に応じて出力して台帳として使えばいい。
考えてみれば、営業と商品管理、同じようなことをしている。だったらデータをはじめから共有できるようにしておけば、無駄を省けるというものだ。次シーズンには提案してみるのもいいかなと思う。もっとも妹尾は商品を勉強するため個人的に撮っていたようだったが。
「誰だ? 今時分――」
響いたインターフォンに、鮎原は訝しげに玄関に向かう。まさか妹尾が、と一瞬過ぎったが、家まで教えていない。
「た…け、むら……どうしたんだ、明日じゃ……」
ドアを開ければ、武村が立っていた。
来るのは明日のはずだった。昼ぐらいに東京を出て、鮎原の部屋に来るのは三時ごろの――。
「何だ、迷惑だったのか?」
「いや、そんなことないよ。そんなはずないだろ。びっくりしたんだよ。急だから。明日だとばかり思っていたから」
いきなりの驚きのほうが大きく、会えた喜びが湧き上がってくるのまでのタイムラグが後ろめたい。鮎原はそんな自分の揺らぎに蓋をするため、つい意味もなく言葉を重ねた。
武村は、ネクタイを外し、スーツにビジネスバッグ一つという軽装だった。どうも退社後直接来たようだ。身の回りの物は鮎原の部屋に置いてあるし、必要なものならコンビにでも買いに行けばいいから、体一つで来て困ることはない。
「たまにはいいだろ、こういうのも新鮮で」
武村が苦笑しながら部屋に上がる。鮎原は急いで武村の背を追った。
「そりゃそうだけど、いったいどうして?」
「明日出勤なんだ。今日も残業あったが早めに切り上げた。で、その足でこっちに来た――佳史」
まずは挨拶代わり、と名を呼ばれて抱き寄せられる。すぐに口づけが降りてくる。もう何度もかわし、馴染んでいる行為だ。少し口の中に広がる煙草の香りもいつもと同じ。
「た…、んっ、武、村――。何? 明日、出勤?」
重ねる唇を僅かにずらして空気を取り込む。武村に名を呼ばれても、照れが手伝い同じように名前を呼んで返すことができない。
「そうなんだ。だから今夜こっちにな」
東京と名古屋、どちらで過ごすにしても、土曜日に会って日曜に戻るという一泊二日の逢瀬、それが二人で決めた週末だった。しかし会社勤めをしている以上、急な仕事が入ればプライベートよりも優先されるのは仕方がない。
「じゃ、始発で戻るのか?」
「昼前に行けばいいから、朝ってことはない。それにここは駅に近いからな。少し余裕あるよ」
本陣にある鮎原のアパートは名古屋駅まで地下鉄で二駅だった。
「――お、お前、メシは?」
「新幹線で弁当食ってきたよ。ほら一週間ぶりなんだ、もう少し味わわせろ」
「ま、待てよ……そんな……来てすぐ……あっ」
武村の手が鮎原の敏感なところを撫でる。布越しでも覚える刺激が、鮎原の体に熱を呼び始める。
「ったく。嫌なのか?」
「そういうわけじゃないけど、明日も仕事ならそんなに……」
このままベッドにもつれ込んでしまいそう雰囲気に身を任せたくなる。けれど始発ではないにしろ昼前に東京に戻るのなら、ここを出るのは平日と変わらない時間になるだろう。
「こっちは、今夜はどうやってお前を抱こうかずっと考えてきたんだぞ」
「武村……」
自分を求める武村の声は甘く、感じ出している体はいっそう煽られていく。「しょうがないな」と鮎原は、言葉の裏に嬉しさを隠して武村の背に腕を回した。
「イイ子だ」
部屋の奥のベッドに口づけながら移動し、横たわらせられる。上着を脱いだ武村が覆いかぶさり、鮎原の着ているのシャツを捲り上げた。
「まだ跡残ってるな」
あらわになった胸元から首へと武村の指がたどり、薄くなった先週の名残を強く押す。
「知らない間につけるなよ。着替えてるとき見つけて焦ったんだぞ」
文句をつけるわけではなかった。ちょっとぼやいてみたかっただけだった。
「いいだろ、お前は俺のだっていう印だ」
武村も、鮎原がただ言っているだけなのは分かってくれている。襟元を開けなければ見えない位置なのだから気にすることはない、とまた同じところをきつく吸い上げた。
「あ、んっ。眼鏡外せよ。当たってフレームが歪むぞ」
鮎原は、ちりっとする小さな痛みに、抗議のように声を上げる。
「ああ。最近ネジが緩くなってきたんだ。眼鏡屋行って調整してもらうかな、一度」
下を向くとずり落ちてくるんだよな、と言って武村は外した眼鏡を枕の横に置いた。そして鮎原の下肢を覆うズボンを取り去る。
「うわっ」
「もうこんなにしてるんだ」
「お前がしたんだろ――あっ」
勃ち上がっている鮎原のものは、武村の指に弾かれて震えた。
「そうだな。お前が俺をこんなにしたんだ」
武村も前を緩めて、すでに猛っている自分のものを取り出す。そして二つの熱を重ねた。
「佳史……」
武村の甘く内耳を刺激する声が鮎原に届く。扱かれて熱がさらに膨らんでいる。
「うん、あれ使って」
「ああ」
鮎原の首筋に顔を埋めながら武村が手探りで、ヘッドボードの引き出しを開ける。抱き合うために用意していたローションが入っていた。
じっくり慣らされて体を開かされるのは、気恥ずかしくとも嫌ではない。けれど早く繋がりたいと思う気持ちもある。繋がって得られる濃密な充足感は、今二人が一緒にいるという証だ。
「くっ…んっ」
ひんやりとした滑りを最奥に感じる。武村の指が、閉ざしていた鮎原の窄まりを捏ねて広げていく。
「入れるぞ」
鮎原は小さく頷いた。
足を左右に広げられ、熱が体に押し入ってくる。何度もしている行為でも、この瞬間は身が割り裂かれてしまいそうで慣れることはない。
しかし熱を中に収め、揺さぶられ出すと、意識は高く放たれる瞬間を目指して駆け上っていく。抉るように突かれ、擦り上げられる内壁への圧迫感で呼吸もままならなくなっても、武村が自分の中に白濁を迸らせるまで、動きに合わせて自身を高めていった。
「そろそろ寝るかな。まだちょっと早いけど」
明日の土曜日は、武村がこっちに来る番だった。だから午前中に部屋の片づけと買い物を済ませておけばいい。鮎原はそう予定を立てていた。
椎名に頼まれた商品写真は、妹尾のおかげもあって木曜にはすべて撮り終え、データベース化した。これでいつでも部内のパソコンで参照できる。後は必要に応じて出力して台帳として使えばいい。
考えてみれば、営業と商品管理、同じようなことをしている。だったらデータをはじめから共有できるようにしておけば、無駄を省けるというものだ。次シーズンには提案してみるのもいいかなと思う。もっとも妹尾は商品を勉強するため個人的に撮っていたようだったが。
「誰だ? 今時分――」
響いたインターフォンに、鮎原は訝しげに玄関に向かう。まさか妹尾が、と一瞬過ぎったが、家まで教えていない。
「た…け、むら……どうしたんだ、明日じゃ……」
ドアを開ければ、武村が立っていた。
来るのは明日のはずだった。昼ぐらいに東京を出て、鮎原の部屋に来るのは三時ごろの――。
「何だ、迷惑だったのか?」
「いや、そんなことないよ。そんなはずないだろ。びっくりしたんだよ。急だから。明日だとばかり思っていたから」
いきなりの驚きのほうが大きく、会えた喜びが湧き上がってくるのまでのタイムラグが後ろめたい。鮎原はそんな自分の揺らぎに蓋をするため、つい意味もなく言葉を重ねた。
武村は、ネクタイを外し、スーツにビジネスバッグ一つという軽装だった。どうも退社後直接来たようだ。身の回りの物は鮎原の部屋に置いてあるし、必要なものならコンビにでも買いに行けばいいから、体一つで来て困ることはない。
「たまにはいいだろ、こういうのも新鮮で」
武村が苦笑しながら部屋に上がる。鮎原は急いで武村の背を追った。
「そりゃそうだけど、いったいどうして?」
「明日出勤なんだ。今日も残業あったが早めに切り上げた。で、その足でこっちに来た――佳史」
まずは挨拶代わり、と名を呼ばれて抱き寄せられる。すぐに口づけが降りてくる。もう何度もかわし、馴染んでいる行為だ。少し口の中に広がる煙草の香りもいつもと同じ。
「た…、んっ、武、村――。何? 明日、出勤?」
重ねる唇を僅かにずらして空気を取り込む。武村に名を呼ばれても、照れが手伝い同じように名前を呼んで返すことができない。
「そうなんだ。だから今夜こっちにな」
東京と名古屋、どちらで過ごすにしても、土曜日に会って日曜に戻るという一泊二日の逢瀬、それが二人で決めた週末だった。しかし会社勤めをしている以上、急な仕事が入ればプライベートよりも優先されるのは仕方がない。
「じゃ、始発で戻るのか?」
「昼前に行けばいいから、朝ってことはない。それにここは駅に近いからな。少し余裕あるよ」
本陣にある鮎原のアパートは名古屋駅まで地下鉄で二駅だった。
「――お、お前、メシは?」
「新幹線で弁当食ってきたよ。ほら一週間ぶりなんだ、もう少し味わわせろ」
「ま、待てよ……そんな……来てすぐ……あっ」
武村の手が鮎原の敏感なところを撫でる。布越しでも覚える刺激が、鮎原の体に熱を呼び始める。
「ったく。嫌なのか?」
「そういうわけじゃないけど、明日も仕事ならそんなに……」
このままベッドにもつれ込んでしまいそう雰囲気に身を任せたくなる。けれど始発ではないにしろ昼前に東京に戻るのなら、ここを出るのは平日と変わらない時間になるだろう。
「こっちは、今夜はどうやってお前を抱こうかずっと考えてきたんだぞ」
「武村……」
自分を求める武村の声は甘く、感じ出している体はいっそう煽られていく。「しょうがないな」と鮎原は、言葉の裏に嬉しさを隠して武村の背に腕を回した。
「イイ子だ」
部屋の奥のベッドに口づけながら移動し、横たわらせられる。上着を脱いだ武村が覆いかぶさり、鮎原の着ているのシャツを捲り上げた。
「まだ跡残ってるな」
あらわになった胸元から首へと武村の指がたどり、薄くなった先週の名残を強く押す。
「知らない間につけるなよ。着替えてるとき見つけて焦ったんだぞ」
文句をつけるわけではなかった。ちょっとぼやいてみたかっただけだった。
「いいだろ、お前は俺のだっていう印だ」
武村も、鮎原がただ言っているだけなのは分かってくれている。襟元を開けなければ見えない位置なのだから気にすることはない、とまた同じところをきつく吸い上げた。
「あ、んっ。眼鏡外せよ。当たってフレームが歪むぞ」
鮎原は、ちりっとする小さな痛みに、抗議のように声を上げる。
「ああ。最近ネジが緩くなってきたんだ。眼鏡屋行って調整してもらうかな、一度」
下を向くとずり落ちてくるんだよな、と言って武村は外した眼鏡を枕の横に置いた。そして鮎原の下肢を覆うズボンを取り去る。
「うわっ」
「もうこんなにしてるんだ」
「お前がしたんだろ――あっ」
勃ち上がっている鮎原のものは、武村の指に弾かれて震えた。
「そうだな。お前が俺をこんなにしたんだ」
武村も前を緩めて、すでに猛っている自分のものを取り出す。そして二つの熱を重ねた。
「佳史……」
武村の甘く内耳を刺激する声が鮎原に届く。扱かれて熱がさらに膨らんでいる。
「うん、あれ使って」
「ああ」
鮎原の首筋に顔を埋めながら武村が手探りで、ヘッドボードの引き出しを開ける。抱き合うために用意していたローションが入っていた。
じっくり慣らされて体を開かされるのは、気恥ずかしくとも嫌ではない。けれど早く繋がりたいと思う気持ちもある。繋がって得られる濃密な充足感は、今二人が一緒にいるという証だ。
「くっ…んっ」
ひんやりとした滑りを最奥に感じる。武村の指が、閉ざしていた鮎原の窄まりを捏ねて広げていく。
「入れるぞ」
鮎原は小さく頷いた。
足を左右に広げられ、熱が体に押し入ってくる。何度もしている行為でも、この瞬間は身が割り裂かれてしまいそうで慣れることはない。
しかし熱を中に収め、揺さぶられ出すと、意識は高く放たれる瞬間を目指して駆け上っていく。抉るように突かれ、擦り上げられる内壁への圧迫感で呼吸もままならなくなっても、武村が自分の中に白濁を迸らせるまで、動きに合わせて自身を高めていった。
0
波奈海月/ブログ
【オレンジとシェリー】
【オレンジとシェリー】
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

鬼上司と秘密の同居
なの
BL
恋人に裏切られ弱っていた会社員の小沢 海斗(おざわ かいと)25歳
幼馴染の悠人に助けられ馴染みのBARへ…
そのまま酔い潰れて目が覚めたら鬼上司と呼ばれている浅井 透(あさい とおる)32歳の部屋にいた…
いったい?…どうして?…こうなった?
「お前は俺のそばに居ろ。黙って愛されてればいい」
スパダリ、イケメン鬼上司×裏切られた傷心海斗は幸せを掴むことができるのか…
性描写には※を付けております。

セカンドコンタクト
アカネラヤ
BL
弥汲佑哉(ヤクミユウヤ)は、とあるネットゲームに執心する二十七歳のサラリーマン。そこで出逢ったギルドメンバーであるゲームネーム《セカイ》と、ひょんなことからお互い共通の通話アプリのIDを持っていることが判明し。そこからほぼ毎週、彼と通話をしながらネットゲームをするのが常となっていた。通話を通じるうちにだんだんとセカイに惹かれていく弥汲。
そんなある時。いつものように通話をする予定が、セカイの通話が不調になり彼の様子もおかしいため、弥汲は単身東京から大阪にあるセカイ邸に向かう事を決意するのだった。
長年想いを密かに募らせていた相手の自宅に到着し来客すると、そこにはとんでもない姿の想い人が立っていて……?

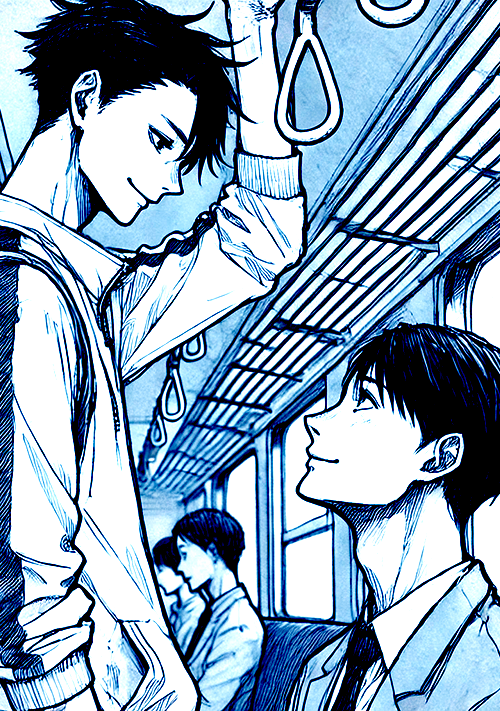
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

【完結】ぎゅって抱っこして
かずえ
BL
幼児教育学科の短大に通う村瀬一太。訳あって普通の高校に通えなかったため、働いて貯めたお金で二年間だけでもと大学に入学してみたが、学費と生活費を稼ぎつつ学校に通うのは、考えていたよりも厳しい……。
でも、頼れる者は誰もいない。
自分で頑張らなきゃ。
本気なら何でもできるはず。
でも、ある日、金持ちの坊っちゃんと心の中で呼んでいた松島晃に苦手なピアノの課題で助けてもらってから、どうにも自分の心がコントロールできなくなって……。

金色の恋と愛とが降ってくる
鳩かなこ
BL
もう18歳になるオメガなのに、鶯原あゆたはまだ発情期の来ていない。
引き取られた富豪のアルファ家系の梅渓家で
オメガらしくないあゆたは厄介者扱いされている。
二学期の初めのある日、委員長を務める美化委員会に
転校生だというアルファの一年生・八月一日宮が参加してくれることに。
初のアルファの後輩は初日に遅刻。
やっと顔を出した八月一日宮と出会い頭にぶつかって、あゆたは足に怪我をしてしまう。
転校してきた訳アリ? 一年生のアルファ×幸薄い自覚のない未成熟のオメガのマイペース初恋物語。
オメガバースの世界観ですが、オメガへの差別が社会からなくなりつつある現代が舞台です。
途中主人公がちょっと不憫です。
性描写のあるお話にはタイトルに「*」がついてます。

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語
紅林
BL
『桜田門学院高等学校』
日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ
しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ
そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である

Take On Me
マン太
BL
親父の借金を返済するため、ヤクザの若頭、岳(たける)の元でハウスキーパーとして働く事になった大和(やまと)。
初めは乗り気でなかったが、持ち前の前向きな性格により、次第に力を発揮していく。
岳とも次第に打ち解ける様になり…。
軽いノリのお話しを目指しています。
※BLに分類していますが軽めです。
※他サイトへも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















