5 / 37
第一章
5
しおりを挟む
「あれ? 鮎原さん、残業ですか? でしたら手伝いましょうか」
「妹尾か。大丈夫だよ。サンプルの写真撮るだけだから」
終業の定時も過ぎ、人気のないショールームで三脚にカメラをセットしていた鮎原は、覗いた顔に答えた。
一日の業務を終えてからの写真撮りも、二日目になっていた。日中はどうしても営業としての仕事に追われ、それに肝心のサンプルが商談で持ち出されてしまっているからだ。
「でもひとりでやるより二人でやったほうが楽でしょう? 手伝いますって」
「けどこれは営業の仕事だし、商管のお前に悪いよ」
商品管理部の妹尾に、部署が違うのに手伝ってもらうのは気が引け、「もう帰るところなんだろ?」とつけ加えて言えば、妹尾は「帰ってもひとりだし」と答えた。
「それに、オレもいくつか撮ってるんですよ、写真。注文来てもどういうのかすぐ分かるように。だからそれと合わせれば、全部撮る必要ないでしょ? 鮎原さんが撮る分でこっちにないものを使わせてもらったらオレも助かるし」
遠慮など要りませんよ、と妹尾が着ていた上着を脱いで鮎原の横に来る。袖口のボタンも外し、すでに手伝う満々だ。
そこまでやる気を見せられたら、断れない。
「じゃあ頼むかな」
つまり持ちつ持たれつ、互いのデータを共有すれば、ここですべて撮る必要はなくなる。それに手伝いの申し出は実際助かった。
ファインダーを覗き、フレーム内に収まるよう並べた商品の位置を確認し、ずれていたらまた修正して。一つ撮るにも何度か商品とカメラの間を往復しなければならない。手間もかかるし時間を食う。
「これは写真あるから……」
妹尾は展示してある手近なサンプルに手を伸ばした。
「悪い、妹尾。そこまでのシリーズはもう撮ってあるんだ。隣のシリーズから頼む」
妹尾の手の先を見て取った鮎原は、すかさずすでに撮り終わった物だと告げる。
「そうですか。じゃあ、これからいきますね」
ディスプレイピンを使って壁面に飾ってあったサンプルを外し、妹尾はそれを撮影のために鮎原が空けていた展示台に置いた。色違いのアイテムも一緒に並べることも心得ていた。
「これでいいですか?」
「ああ。そうだそれ、袖口にポイントがあったよな。見えるように手前に出してくれないか」
ファインダーを覗きながら鮎原は指示をする。少し右が下がっているとも。
「分かりました」
妹尾は鮎原の言うとおりにたたんでいた袖を広げ、右肩を上にずらした。妹尾が離れたところで鮎原はシャッターを切る。
「後でオレが撮った写真データ持ってきますね。USBでいいですか?」
このシリーズもあるから、と妹尾は自分が撮ったという物を飛ばして、手際よく取り替えていく。
「メディアは何でもいいよ。CDに焼いてくれてもいいし。返すときこっちのデータを入れておくな」
今日撮影を予定していたサンプルの半分ほどは、妹尾のデータで済ませられそうだった。商談中でまだ戻ってきていない物の写真もあるようだ。
「そうそう、鮎原さん、普段どんな曲聴くんです? RB、J‐POP、K‐POP――好きな曲って何ですか?」
互いの呼吸もつかみ作業に余裕が出てくると、残業という通常の勤務時間とは違うせいか、妹尾は鮎原の趣味を聞いてきた。ちょっとした話題のつもりなのだろう。対して鮎原も、まだ仕事中とヤボなことは言わない。
「そうだな、よく聴くのはやっぱりJ‐POPかな。あ、でも、好きといえば、あれかなあ」
最近の流行も聴くが、好きな曲といえばすぐに脳裏に浮かぶものがあった。
「アレ? それって何ですか?」
普段聴く曲と分けるように言った鮎原に興味を持ったのか、妹尾が聞き返す。
「昔観た映画で使われていた曲なんだけど」
子供のころ、たまたまテレビでやっていたのを観たものだった。どんな話だったのか、おぼろげな筋しか記憶にない。ただ主人公の少女が歌っていた曲だけが印象に残った。
以来ふとしたときに頭の中で流れるのだ。レコード針が引っかかったようなノイズも一緒に再生される。
「映画? 何ていう映画です?」
サンプルを並べていた手を止めて妹尾が振り返った。
よほど意外に思われてしまったのだろうか。ファインダーを覗く鮎原の目はレンズ越しに、じっとこちらを見る妹尾を捉えていた。
「へん、かな? 俺が映画の曲が好きって」
鮎原は、屈んでいた腰を伸ばし、直接妹尾を見る。
「あ、いえ。そんなつもりじゃ。オレ実は映画好きなんですよ。だからどんなのかなって」
「映画好き? そうだったんだ、妹尾って。ならちょっとタイトル言うの恥ずかしいな。最近のものじゃないんだ。子供のときテレビで一回観ただけでそれも途中からで……」
この年にもなってその映画のタイトルを口にするのは、正直気恥ずかしかった。
「恥ずかしいって、どうしてですか? もしかして年齢制限のあるのですか? 案外スケベなんだ、鮎原さんって」
妹尾がにやりとする。
「ち、違うっ、何考えてるっ! 子供のときって言ったろ。『オズの魔法使い』だっ」
誤解するな、と鮎原はつい語気が強くなった。
「オズ?」
妹尾が目を瞬かせた。鮎原の口から出たタイトルをまたも意外に思ったのかもしれない。
オズといえば往年のファンタジー映画だ。鮎原はバツ悪く息をついた。まだ最近のものなら特撮やCGが面白いから、という理由もつけ加えられたのだが、もう開き直るほかないだろう。
「いい年をしてオズなんておかしいだろ? その映画の中で女の子が歌っていた曲なんだ」
てっきり笑うと思っていたが、しかし妹尾は、目を大きく開き顔を輝かせ始める。
「オズの魔法使い? 何言ってるんですか。名作じゃないですか。一九三九年制作。竜巻で飛ばされて気がつけば見知らぬ国。家に帰りたいドロシーは偉大なる魔法使いオズのところに行って頼むけど、叶えてもらえなくて、でも北の魔女グリンダが代わりに叶えてくれるんですよね」
「……願いを叶えてくれるのは、オズじゃなかったのか」
一気に語り出した妹尾に、今度は鮎原が目を瞬かせた。話す勢いに押されてか、思わず一歩下がってしまいそうになる。
「ええ。オズのもとにたどり着いたドロシーたちは願いを叶えてもらうために西の魔女退治という試練を受けて――」
今観るとライオンの尻尾を吊るすテグスが丸見えだったりするが、撮影技法は当時画期的だったとか、オープニングとエンディングのカンザスの風景はセピア色、オズの国ではカラーに切り替えられる心憎い演出とか。主人公の少女ドロシーの愛犬、テリー犬のトトが可愛い。それに、正式な邦題では「オズの魔法使い」の「魔法使い」に送り仮名の「い」はつかないのだと、まるで何年か前にやっていた番組が取り上げそうな秘話めいたことまで語る。
制作年数をそらんじて言えるだけでも内心驚いていた鮎原は、そんなコアな話についていけず、悪いけど、と話の端を折る機会を窺った。妹尾はどこかで止めないとずっと語り続けそうだった。
「ごめん、話はほとんど覚えていないんだ。子供のころホントに何かのときにテレビでやったのを一回観ただけだから。カカシとかラオインが出ていたのは覚えているけど、曲だけ耳に残って……」
「そうそう曲です。好きな曲の話でしたね」
好きな曲を聞いたはずなのに、とはたと話を止めた妹尾は、映画について熱く語ってしまったのを照れ臭そうに、頭をかいた。
「オズはミュージカル映画ですからいろんな曲が歌われましたけど、女の子が、っていうなら、主演のジュディ・ガーランドが歌って今も歌い継がれているあれですね。『虹の彼方に』、ここではないどこか、Somewhere――」
有名な冒頭のフレーズまで言って曲名を口にした妹尾に、主演女優の名すら知らなかった鮎原は頷くしかない。まさかここまで語られるなど思いもしなかった。
「詳しいんだな、妹尾って」
「オレが映画好きになったきっかけの映画だったんでつい語っちゃいました」
ペコリと頭を下げるも、今度一緒に観ましょう、オズのDVDをレンタルしてきます、とまで言い始める。
「えっと、妹尾?」
何でそういう展開になるのか、鮎原は分からない。まったく馴れ馴れしいというか、ただでは起きない。
「迷惑ですか? せっかく好きな映画について語り合えると思ったんですけど」
ここで「嫌だ」と本気で言えば、妹尾はきっとこれ以上誘いはしないだろう。鮎原は、そうなるのは何だかつまらないと思った。
こんな、屈託なく笑顔を向けられて、拒否をするなんて。
互いが好きな同じ映画を一緒に観るのも悪くない。
鮎原の場合は映画ではなく曲のほうだったが、一度ちゃんと観ておくのもいい。
「いいよ、今度、な」
会社の同僚と、レンタルしてきた映画を一緒に観る、だけのこと。
馴れ馴れしく言うが、悪いヤツではないのだ。
「本当ですか? じゃあ、借りてきたら連絡しますね。だから、その、教えてくれませんか? 鮎原さんの携帯の番号」
やっぱり厚かましい。気遣わせたら悪いと思ったのに。
「お前――」
だったらこれくらいはいいだろうと、少し悪戯心を出して言ってみる。
「覚えられたらな」
「え?」
何を? ときょとんとした顔がおかしかった。
「俺の番号、今から言うから。この場で覚えられたらな。メモ取るのはナシだ」
「え、え? そういうこと?」
鮎原は、困ったように眉根を寄せて固まった妹尾を無視して、自分の携帯電話を取り出すと、表示させた番号を読み上げた。
「妹尾か。大丈夫だよ。サンプルの写真撮るだけだから」
終業の定時も過ぎ、人気のないショールームで三脚にカメラをセットしていた鮎原は、覗いた顔に答えた。
一日の業務を終えてからの写真撮りも、二日目になっていた。日中はどうしても営業としての仕事に追われ、それに肝心のサンプルが商談で持ち出されてしまっているからだ。
「でもひとりでやるより二人でやったほうが楽でしょう? 手伝いますって」
「けどこれは営業の仕事だし、商管のお前に悪いよ」
商品管理部の妹尾に、部署が違うのに手伝ってもらうのは気が引け、「もう帰るところなんだろ?」とつけ加えて言えば、妹尾は「帰ってもひとりだし」と答えた。
「それに、オレもいくつか撮ってるんですよ、写真。注文来てもどういうのかすぐ分かるように。だからそれと合わせれば、全部撮る必要ないでしょ? 鮎原さんが撮る分でこっちにないものを使わせてもらったらオレも助かるし」
遠慮など要りませんよ、と妹尾が着ていた上着を脱いで鮎原の横に来る。袖口のボタンも外し、すでに手伝う満々だ。
そこまでやる気を見せられたら、断れない。
「じゃあ頼むかな」
つまり持ちつ持たれつ、互いのデータを共有すれば、ここですべて撮る必要はなくなる。それに手伝いの申し出は実際助かった。
ファインダーを覗き、フレーム内に収まるよう並べた商品の位置を確認し、ずれていたらまた修正して。一つ撮るにも何度か商品とカメラの間を往復しなければならない。手間もかかるし時間を食う。
「これは写真あるから……」
妹尾は展示してある手近なサンプルに手を伸ばした。
「悪い、妹尾。そこまでのシリーズはもう撮ってあるんだ。隣のシリーズから頼む」
妹尾の手の先を見て取った鮎原は、すかさずすでに撮り終わった物だと告げる。
「そうですか。じゃあ、これからいきますね」
ディスプレイピンを使って壁面に飾ってあったサンプルを外し、妹尾はそれを撮影のために鮎原が空けていた展示台に置いた。色違いのアイテムも一緒に並べることも心得ていた。
「これでいいですか?」
「ああ。そうだそれ、袖口にポイントがあったよな。見えるように手前に出してくれないか」
ファインダーを覗きながら鮎原は指示をする。少し右が下がっているとも。
「分かりました」
妹尾は鮎原の言うとおりにたたんでいた袖を広げ、右肩を上にずらした。妹尾が離れたところで鮎原はシャッターを切る。
「後でオレが撮った写真データ持ってきますね。USBでいいですか?」
このシリーズもあるから、と妹尾は自分が撮ったという物を飛ばして、手際よく取り替えていく。
「メディアは何でもいいよ。CDに焼いてくれてもいいし。返すときこっちのデータを入れておくな」
今日撮影を予定していたサンプルの半分ほどは、妹尾のデータで済ませられそうだった。商談中でまだ戻ってきていない物の写真もあるようだ。
「そうそう、鮎原さん、普段どんな曲聴くんです? RB、J‐POP、K‐POP――好きな曲って何ですか?」
互いの呼吸もつかみ作業に余裕が出てくると、残業という通常の勤務時間とは違うせいか、妹尾は鮎原の趣味を聞いてきた。ちょっとした話題のつもりなのだろう。対して鮎原も、まだ仕事中とヤボなことは言わない。
「そうだな、よく聴くのはやっぱりJ‐POPかな。あ、でも、好きといえば、あれかなあ」
最近の流行も聴くが、好きな曲といえばすぐに脳裏に浮かぶものがあった。
「アレ? それって何ですか?」
普段聴く曲と分けるように言った鮎原に興味を持ったのか、妹尾が聞き返す。
「昔観た映画で使われていた曲なんだけど」
子供のころ、たまたまテレビでやっていたのを観たものだった。どんな話だったのか、おぼろげな筋しか記憶にない。ただ主人公の少女が歌っていた曲だけが印象に残った。
以来ふとしたときに頭の中で流れるのだ。レコード針が引っかかったようなノイズも一緒に再生される。
「映画? 何ていう映画です?」
サンプルを並べていた手を止めて妹尾が振り返った。
よほど意外に思われてしまったのだろうか。ファインダーを覗く鮎原の目はレンズ越しに、じっとこちらを見る妹尾を捉えていた。
「へん、かな? 俺が映画の曲が好きって」
鮎原は、屈んでいた腰を伸ばし、直接妹尾を見る。
「あ、いえ。そんなつもりじゃ。オレ実は映画好きなんですよ。だからどんなのかなって」
「映画好き? そうだったんだ、妹尾って。ならちょっとタイトル言うの恥ずかしいな。最近のものじゃないんだ。子供のときテレビで一回観ただけでそれも途中からで……」
この年にもなってその映画のタイトルを口にするのは、正直気恥ずかしかった。
「恥ずかしいって、どうしてですか? もしかして年齢制限のあるのですか? 案外スケベなんだ、鮎原さんって」
妹尾がにやりとする。
「ち、違うっ、何考えてるっ! 子供のときって言ったろ。『オズの魔法使い』だっ」
誤解するな、と鮎原はつい語気が強くなった。
「オズ?」
妹尾が目を瞬かせた。鮎原の口から出たタイトルをまたも意外に思ったのかもしれない。
オズといえば往年のファンタジー映画だ。鮎原はバツ悪く息をついた。まだ最近のものなら特撮やCGが面白いから、という理由もつけ加えられたのだが、もう開き直るほかないだろう。
「いい年をしてオズなんておかしいだろ? その映画の中で女の子が歌っていた曲なんだ」
てっきり笑うと思っていたが、しかし妹尾は、目を大きく開き顔を輝かせ始める。
「オズの魔法使い? 何言ってるんですか。名作じゃないですか。一九三九年制作。竜巻で飛ばされて気がつけば見知らぬ国。家に帰りたいドロシーは偉大なる魔法使いオズのところに行って頼むけど、叶えてもらえなくて、でも北の魔女グリンダが代わりに叶えてくれるんですよね」
「……願いを叶えてくれるのは、オズじゃなかったのか」
一気に語り出した妹尾に、今度は鮎原が目を瞬かせた。話す勢いに押されてか、思わず一歩下がってしまいそうになる。
「ええ。オズのもとにたどり着いたドロシーたちは願いを叶えてもらうために西の魔女退治という試練を受けて――」
今観るとライオンの尻尾を吊るすテグスが丸見えだったりするが、撮影技法は当時画期的だったとか、オープニングとエンディングのカンザスの風景はセピア色、オズの国ではカラーに切り替えられる心憎い演出とか。主人公の少女ドロシーの愛犬、テリー犬のトトが可愛い。それに、正式な邦題では「オズの魔法使い」の「魔法使い」に送り仮名の「い」はつかないのだと、まるで何年か前にやっていた番組が取り上げそうな秘話めいたことまで語る。
制作年数をそらんじて言えるだけでも内心驚いていた鮎原は、そんなコアな話についていけず、悪いけど、と話の端を折る機会を窺った。妹尾はどこかで止めないとずっと語り続けそうだった。
「ごめん、話はほとんど覚えていないんだ。子供のころホントに何かのときにテレビでやったのを一回観ただけだから。カカシとかラオインが出ていたのは覚えているけど、曲だけ耳に残って……」
「そうそう曲です。好きな曲の話でしたね」
好きな曲を聞いたはずなのに、とはたと話を止めた妹尾は、映画について熱く語ってしまったのを照れ臭そうに、頭をかいた。
「オズはミュージカル映画ですからいろんな曲が歌われましたけど、女の子が、っていうなら、主演のジュディ・ガーランドが歌って今も歌い継がれているあれですね。『虹の彼方に』、ここではないどこか、Somewhere――」
有名な冒頭のフレーズまで言って曲名を口にした妹尾に、主演女優の名すら知らなかった鮎原は頷くしかない。まさかここまで語られるなど思いもしなかった。
「詳しいんだな、妹尾って」
「オレが映画好きになったきっかけの映画だったんでつい語っちゃいました」
ペコリと頭を下げるも、今度一緒に観ましょう、オズのDVDをレンタルしてきます、とまで言い始める。
「えっと、妹尾?」
何でそういう展開になるのか、鮎原は分からない。まったく馴れ馴れしいというか、ただでは起きない。
「迷惑ですか? せっかく好きな映画について語り合えると思ったんですけど」
ここで「嫌だ」と本気で言えば、妹尾はきっとこれ以上誘いはしないだろう。鮎原は、そうなるのは何だかつまらないと思った。
こんな、屈託なく笑顔を向けられて、拒否をするなんて。
互いが好きな同じ映画を一緒に観るのも悪くない。
鮎原の場合は映画ではなく曲のほうだったが、一度ちゃんと観ておくのもいい。
「いいよ、今度、な」
会社の同僚と、レンタルしてきた映画を一緒に観る、だけのこと。
馴れ馴れしく言うが、悪いヤツではないのだ。
「本当ですか? じゃあ、借りてきたら連絡しますね。だから、その、教えてくれませんか? 鮎原さんの携帯の番号」
やっぱり厚かましい。気遣わせたら悪いと思ったのに。
「お前――」
だったらこれくらいはいいだろうと、少し悪戯心を出して言ってみる。
「覚えられたらな」
「え?」
何を? ときょとんとした顔がおかしかった。
「俺の番号、今から言うから。この場で覚えられたらな。メモ取るのはナシだ」
「え、え? そういうこと?」
鮎原は、困ったように眉根を寄せて固まった妹尾を無視して、自分の携帯電話を取り出すと、表示させた番号を読み上げた。
0
波奈海月/ブログ
【オレンジとシェリー】
【オレンジとシェリー】
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説

セカンドコンタクト
アカネラヤ
BL
弥汲佑哉(ヤクミユウヤ)は、とあるネットゲームに執心する二十七歳のサラリーマン。そこで出逢ったギルドメンバーであるゲームネーム《セカイ》と、ひょんなことからお互い共通の通話アプリのIDを持っていることが判明し。そこからほぼ毎週、彼と通話をしながらネットゲームをするのが常となっていた。通話を通じるうちにだんだんとセカイに惹かれていく弥汲。
そんなある時。いつものように通話をする予定が、セカイの通話が不調になり彼の様子もおかしいため、弥汲は単身東京から大阪にあるセカイ邸に向かう事を決意するのだった。
長年想いを密かに募らせていた相手の自宅に到着し来客すると、そこにはとんでもない姿の想い人が立っていて……?
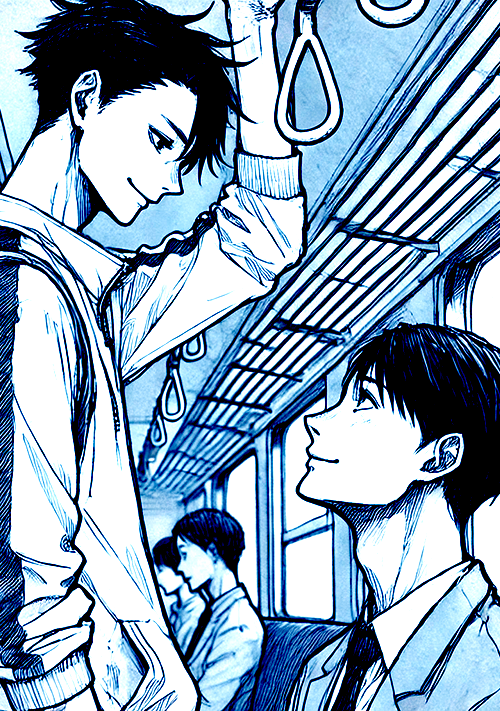
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

金色の恋と愛とが降ってくる
鳩かなこ
BL
もう18歳になるオメガなのに、鶯原あゆたはまだ発情期の来ていない。
引き取られた富豪のアルファ家系の梅渓家で
オメガらしくないあゆたは厄介者扱いされている。
二学期の初めのある日、委員長を務める美化委員会に
転校生だというアルファの一年生・八月一日宮が参加してくれることに。
初のアルファの後輩は初日に遅刻。
やっと顔を出した八月一日宮と出会い頭にぶつかって、あゆたは足に怪我をしてしまう。
転校してきた訳アリ? 一年生のアルファ×幸薄い自覚のない未成熟のオメガのマイペース初恋物語。
オメガバースの世界観ですが、オメガへの差別が社会からなくなりつつある現代が舞台です。
途中主人公がちょっと不憫です。
性描写のあるお話にはタイトルに「*」がついてます。

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語
紅林
BL
『桜田門学院高等学校』
日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ
しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ
そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である


お客様と商品
あかまロケ
BL
馬鹿で、不細工で、性格最悪…なオレが、衣食住提供と引き換えに体を売る相手は高校時代一度も面識の無かったエリートモテモテイケメン御曹司で。オレは商品で、相手はお客様。そう思って毎日せっせとお客様に尽くす涙ぐましい努力のオレの物語。(*ムーンライトノベルズ・pixivにも投稿してます。)

モテる兄貴を持つと……(三人称改訂版)
夏目碧央
BL
兄、海斗(かいと)と同じ高校に入学した城崎岳斗(きのさきやまと)は、兄がモテるがゆえに様々な苦難に遭う。だが、カッコよくて優しい兄を実は自慢に思っている。兄は弟が大好きで、少々過保護気味。
ある日、岳斗は両親の血液型と自分の血液型がおかしい事に気づく。海斗は「覚えてないのか?」と驚いた様子。岳斗は何を忘れているのか?一体どんな秘密が?

後輩に嫌われたと思った先輩と その先輩から突然ブロックされた後輩との、その後の話し…
まゆゆ
BL
澄 真広 (スミ マヒロ) は、高校三年の卒業式の日から。
5年に渡って拗らせた恋を抱えていた。
相手は、後輩の久元 朱 (クモト シュウ) 5年前の卒業式の日、想いを告げるか迷いながら待って居たが、シュウは現れず。振られたと思い込む。
一方で、シュウは、澄が急に自分をブロックしてきた事にショックを受ける。
唯一自分を、励ましてくれた先輩からのブロックを時折思い出しては、辛くなっていた。
それは、澄も同じであの日、来てくれたら今とは違っていたはずで仮に振られたとしても、ここまで拗らせることもなかったと考えていた。
そんな5年後の今、シュウは住み込み先で失敗して追い出された途方に暮れていた。
そこへ社会人となっていた澄と再会する。
果たして5年越しの恋は、動き出すのか?
表紙のイラストは、Daysさんで作らせていただきました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















