26 / 58
二十六、蛍会 ~ほたるえ~ 2
しおりを挟む「その装いもいいな。よく似合う」
神事の衣装を脱ぎ、装いを新たにした白朝を見て、石工が声を弾ませる。
「あら、そう?天女が地に落ちたと言って、残念がるかと思ったけど」
「地に居てもらわねば困る。白朝は、俺の正妃となるのだから」
天女の如く美しい、などという戯言は、神事の特別な衣装が見せた幻だと信じて疑わない白朝が、つんと澄まして言うも、石工は気にも留めない風で白朝の前に立った。
「俺は、果報者だ。叶うことなら、このまま誰の目にも触れさせたくない。隠しておきたい」
「それは叶わぬ夢というものよ。さ、行きましょ」
情緒も何もなく切り捨てる白朝を、石工が止める。
「いや、待て。もう少しだけでも、ふたりきりで」
「何を言っているのよ。私達が遅れれば、それだけ皇様や雪舞様も遅れるのよ?みんなを待たせてしまうじゃないの」
「いいじゃないか。少しくらい」
「どこがよ。よくないに決まっているでしょうが。ほら、行くわよ」
何とか、と食い下がる石工に発破をかけ、白朝はさっさと歩き出す。
「白朝は、自分がどれほど美しく、注目されるのか知らないから、そのような事が言える」
「はあ。何を言っているのだか。それは、石工の方でしょう。それだけの美丈夫。ときめく乙女たちの声が聞こえてきそうだわ。いえ、婚姻している方々だって、目の保養だと言いそう」
音にすれば、それは確かな現実となってやって来る、すぐそこに迫っている未来に違いないと確信し、白朝は遠い目になった。
「だったら、尚の事」
「遅れるのは、却下。来ないのなら、置いて行くけど?」
天幕の入り口付近で腰に手を当てた白朝にそう言われ、石工は渋々と皆が待つ場へと行くため、白朝へと向かって歩き出す。
「石工。笑顔」
「誰も求めていないだろう。俺の笑顔など」
「私は、石工に笑っていてほしいな」
「え?」
「石工は?私が、石工の隣で仏頂面していた方が嬉しいの?」
そう言って、窺うように首を傾げる白朝に、石工は大きく首を横に振った。
「いや。誰彼となく笑い掛けて欲しくはないが、白朝が楽しくないのは望まない」
「私を気にしてくれるの?人目とか、そういうことじゃなくて」
正妃となる媛が、その夫となる皇子の横で仏頂面をしている。
それは、ふたりの仲が険悪なのでは、と他者に勘ぐらせる行為のため避けたい、というような事を言われると思っていた白朝は、予想外の石工の答えに動揺してしまう。
「他者はどうでもいいだろう。肝心なのは、白朝の心だ。例え、他者が褒めるような仲でも、真実が伴っていなければ意味はない。逆に、他者がどう言おうと、白朝が俺の隣で心からの笑みを浮かべられる関係なら、それがいいと思っている」
「何を言っているのよ。そもそも、私が石工の隣で心からの笑みを浮かべていたら、他のひとも悪くは言わない・・・こともないか」
笑って言いかけた白朝は、何があっても白朝と石工を貶めようとする筆頭、扇と若竹の顔を思い浮かべて、肩を竦めた。
「そういうことだ。立場上、まったく気にしないわけにもいかないが、お互いの気持ちがしっかりしていれば、周りに何を言われても揺らぐことは無い」
「確かに・・・駄目ね。あの愛妾誤解の件で学んだはずなのに、私ってば進歩が無いわ」
「ああ・・・困ったな」
しょんぼりと肩を落とした白朝を見つめ呟く石工に、呆れられてしまったかと白朝が縮こまる。
起こった事柄からきちんと学べないなんて、期待外れだって言われるのかな。
『俺の正妃となる者が、そのような未熟では困る』
そう言う石工の声さえ聞こえて、白朝は、ぎゅっと手にした団扇を握り締めた。
「白朝が、俺に怯えているという事実はよろしくないし望まない。だが、そんな風に怯えた兎のような白朝も可愛い」
「え?」
「本当だぞ?白朝は、何時いかなる時も可愛すぎて、とてつもない破壊力だ。どんな武器を持ってしてでも敵わない」
「・・・・・正気?」
「もちろん、正気だ。だから言っているだろう。隠しておきたいと」
真顔で言い切られ、白朝は信じられないものを見るように、石工を見つめた。
「結局、皇様と雪舞様をお待たせしてしまったような」
「大した時間ではない。それに、あのふたりとて、ふたりで居られる時間の方が嬉しいだろう」
「そういう問題じゃない気がする」
今日は、蛍会。
多くの貴族達が集まり、今は神事の舞を終えた皇と雪舞を待っている状態なのである。
今年は、石工と白朝も共に舞うという異例の事態により、皇と雪舞は、石工と白朝が場に戻った後に戻るという段取りになっているため、石工と白朝の戻りが遅れれば、それだけ皇と雪舞の戻りも遅くなってしまう。
「気に病むほどの遅れではない。はあ。面倒だが仕方ない。行くか」
「面倒って・・・もう。笑顔でね!」
念押しをして、白朝が石工と共に場へと戻れば、すぐに盛大な歓迎を受けた。
「石工皇子様と白朝媛様のお戻りだ!」
「いやあ、実に素晴らしい舞でした」
「殊に、蛍と共に舞うなど。この上ない慶事」
「お祝い申し上げます」
「ありがとうございます」
次々かけられる声に、石工は、にこやかではないものの、丁寧な口調で答えていく。
「白朝!僕とも神事の舞を舞う栄誉を与えてやる!」
その和やかな雰囲気を打ち壊す声が突如として響き、若竹が人垣を掻き分けて白朝の前に立った。
「さあ。さっさと僕とも神事の舞を舞うんだ。そうすれば、僕の正妃としてやる。感謝するがいい」
は!?
何をふざけたことを、おっしゃってくれちゃっているのかしら!?
「若竹皇子様とのご縁は、既に立ち消えております」
内心の苛立ちをきれいに隠して言った白朝に、若竹は尚も食って掛かる。
「その生意気な言葉遣いは何事だ。僕が望むと言ったなら、喜んで受け入れるのが妥当というものだろうに。今なら未だ許してやる。お前に、僕を皇子様と呼ぶ権利をやると言っているんだ。嬉しいだろうが」
「畏れながら、わたくしが皇子様とお呼びするのは、石工皇子様ただおひとりでございます」
皇子様、と女人が呼ぶのを許されるのは、婚姻を結んだ妃か、婚姻の約束をした媛のみ。
「可愛げのないことを。元は僕をそう呼んでいたのだから、またそうなればいいだけのことじゃないか。いいから、僕と神事の舞を舞うんだ。そして僕の正妃となれ」
何を言っても聞こうとしない、駄々を捏ねる子どものような若竹に白朝が辟易していると、藤宮家当主の秋永が、何かを言おうとした石工に目配せをし、自らが若竹の前へと進み出る。
「若竹殿。神事の舞は、大いなる吉祥と共に奉納を終えました。まさか、ご存じないとは申しますまい」
「そ、それは」
「吉祥?それはあの、光る虫が大量に発生した事を言っているのかしら」
口ごもる若竹に代わるよう、団扇を大きく動かしながら、扇が美鈴を伴ってやって来た。
その場違いに派手な衣装は、胸元が零れ落ちそうな着付けをしていて、白朝の内心はあちらこちらで驚きを隠せない。
む、虫の大量発生!?
確かに、蛍は虫だけれど、蛍会はその蛍を吉とする神事の舞を奉納するのが大きな目的なのに、その言い方はどうなの。
仮にも、皇の正妃であられる方が。
それに、あのお衣装はちょっと・・・危ない気が。
「扇殿。蛍会における最大の吉祥に対する言葉とは思えませぬな」
「虫は虫でしょう。白朝は下賤だから、平気だったようだけれど」
「げせん、げせん」
扇の隣で、美鈴が白朝を指さして笑う。
そのふたりから白朝を隠すよう、石工がすっと前に出た。
「下賤とは、これまた。神事の舞を舞う白朝は、さながら美しい蝶のようでしたよ。下賤などとは程遠い。ああ。もしや、舞うことの出来ない方は、舞える蝶が羨ましいのですか。これは失礼をいたしました」
「なっ」
扇は、未だに蛍会における神事の舞を舞えない。
それを踏まえての石工の言葉に、扇の顔が真っ赤に染まった。
「何を無礼な!お前も所詮は下賤ではないの。ああ、下賤な者同士お似合いということね!」
「扇殿。度が過ぎていませんか」
「我が娘に対する侮蔑の言葉、取り消し謝罪を求める」
不快そうな声を出した香城家当主、雪舞の兄である奏楽津と、その後に続いた和智の目に怒りの炎が宿るも、神聖なる蛍会の場での諍いは避けるべきと、ふたりは心を落ち着けるべく息を大きく吸った。
「何を偉そうに。大体、このような神事がふよ」
「扇。若竹、美鈴ともども、即刻この場を去れ」
「た、武那賀様」
性懲りもなく、再び『このような神事は不要』とふてぶてしく言いかけた扇の言葉を静かに遮り、ゆったりとその場に現れた皇は、冷え冷えとした目を扇に向ける。
「父上!僕にも機会を」
「機会なら与えた。それをものにできなかったのは、其の方だ。さっさと去ね」
「わかたけ、えらい、おまえ、げせん」
その時、美鈴がそう言って皇に団扇を突きつけた。
のみならず、そのまま団扇を振り上げ、皇を叩こうと動く。
「皇に、何ということを!」
即座に間に入った和智が、美鈴を取り押さえるよう護衛に命じ、美鈴はばたばたと暴れながら連れ出されて行く。
「美鈴!・・・和智殿!僕が白朝より美鈴を選んだからといって、失礼が過ぎる!」
「ほう。これは異なことを申される。今この場で、そのような理由で動いたとでも?」
「さっ、些細な理由で美鈴を愚弄するのが、何よりの証拠だろう!」
「皇に無礼を働く、実際に害を加えることが、些細だと?」
目を細め言う和智の迫力にたじたじとなった若竹を見た扇が、苛立ちを隠すことなく白朝に団扇を突きつけた。
「そもそも!白朝が悪いのではないの!こちらの執務も放棄するから、とうとう若竹は領を取り上げられてしまったのよ!?どうしてくれるのよ!この性悪!」
叫ぶと同時、扇は団扇を白朝めがけて投げつけるも、石工がそれを容易に受け止めたため、益々苛立った様子で奇声を発する。
「扇よ。其方は正妃としての役目を何ひとつ果たせぬばかりか、その立場を弁えるということも出来ぬのだな。そのように乱れた姿を、他者に晒すなど恥と知れ」
「皇の正妃なればこそ、そこらの媛如きに舐められるような真似は出来ません」
「はあ。もうよい。己が邸に戻れ」
皇が軽く手を振れば、護衛が扇と若竹を連れて歩き出す。
「扇殿。お忘れ物です」
その扇に、石工は投げつけられ、受け止めた団扇を護衛を介して渡した。
「嫌味な」
憎々し気に石工を睨み、白朝を睨んで、扇は殊更ゆっくりとした歩みで去って行く。
「皇。まさかまた、何も罰をお与えにならないおつもりで?」
「当然だろう。扇は正妃、若竹は皇子なのだから」
納得がいかない。
そう表情に出している宮家の面々や、鷹城を除く貴族を代表するように藤宮家の秋永が言えば、鷹城家の焔が揚々と胸を張る。
「毒草は、根から排除すべきであろう?」
そしてそれに答える皇の瞳に感じる、底知れぬ何か。
毒草は、根から排除すべき?
それって、遺恨を残さないよう徹底的にということ?
一体、皇様は何を探っていらっしゃるの?
扇の事を毒草と称した皇の意図に気づいたらしい面々と、そうでない人々。
まるで国を二分するようなその縮図に、これから何か途方もないことが起こりそうな気がして、白朝は隣に立つ石工の袖を思わず強く握っていた。
~・~・~・~・~・
いいね、エール、お気に入り登録、そして投票も!ありがとうございます。
10
お気に入りに追加
28
あなたにおすすめの小説

東洲斎写楽の懊悩
橋本洋一
歴史・時代
時は寛政五年。長崎奉行に呼ばれ出島までやってきた江戸の版元、蔦屋重三郎は囚われの身の異国人、シャーロック・カーライルと出会う。奉行からシャーロックを江戸で世話をするように脅されて、渋々従う重三郎。その道中、シャーロックは非凡な絵の才能を明らかにしていく。そして江戸の手前、箱根の関所で詮議を受けることになった彼ら。シャーロックの名を訊ねられ、咄嗟に出たのは『写楽』という名だった――江戸を熱狂した写楽の絵。描かれた理由とは? そして金髪碧眼の写楽が江戸にやってきた目的とは?

忠義の方法
春想亭 桜木春緒
歴史・時代
冬木丈次郎は二十歳。うらなりと評判の頼りないひよっこ与力。ある日、旗本の屋敷で娘が死んだが、屋敷のほうで理由も言わないから調べてくれという訴えがあった。短編。完結済。

吉宗のさくら ~八代将軍へと至る道~
裏耕記
歴史・時代
破天荒な将軍 吉宗。民を導く将軍となれるのか
―――
将軍?捨て子?
貴公子として生まれ、捨て子として道に捨てられた。
その暮らしは長く続かない。兄の不審死。
呼び戻された吉宗は陰謀に巻き込まれ将軍位争いの旗頭に担ぎ上げられていく。
次第に明らかになる不審死の謎。
運命に導かれるようになりあがる吉宗。
将軍となった吉宗が隅田川にさくらを植えたのはなぜだろうか。
※※
暴れん坊将軍として有名な徳川吉宗。
低迷していた徳川幕府に再び力を持たせた。
民の味方とも呼ばれ人気を博した将軍でもある。
徳川家の序列でいくと、徳川宗家、尾張家、紀州家と三番目の家柄で四男坊。
本来ならば将軍どころか実家の家督も継げないはずの人生。
数奇な運命に付きまとわれ将軍になってしまった吉宗は何を思う。
本人の意思とはかけ離れた人生、権力の頂点に立つのは幸運か不運なのか……
突拍子もない政策や独創的な人事制度。かの有名なお庭番衆も彼が作った役職だ。
そして御三家を模倣した御三卿を作る。
決して旧来の物を破壊するだけではなかった。その効用を充分理解して変化させるのだ。
彼は前例主義に凝り固まった重臣や役人たちを相手取り、旧来の慣習を打ち破った。
そして独自の政策や改革を断行した。
いきなり有能な人間にはなれない。彼は失敗も多く完全無欠ではなかったのは歴史が証明している。
破天荒でありながら有能な将軍である徳川吉宗が、どうしてそのような将軍になったのか。
おそらく将軍に至るまでの若き日々の経験が彼を育てたのだろう。
その辺りを深堀して、将軍になる前の半生にスポットを当てたのがこの作品です。
本作品は、第9回歴史・時代小説大賞の参加作です。
投票やお気に入り追加をして頂けますと幸いです。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

ナポレオンの妊活・立会い出産・子育て
せりもも
歴史・時代
帝国の皇子に必要なのは、高貴なる青き血。40歳を過ぎた皇帝ナポレオンは、早急に子宮と結婚する必要があった。だがその前に、彼は、既婚者だった……。ローマ王(ナポレオン2世 ライヒシュタット公)の両親の結婚から、彼がウィーンへ幽閉されるまでを、史実に忠実に描きます。
カクヨムから、一部転載
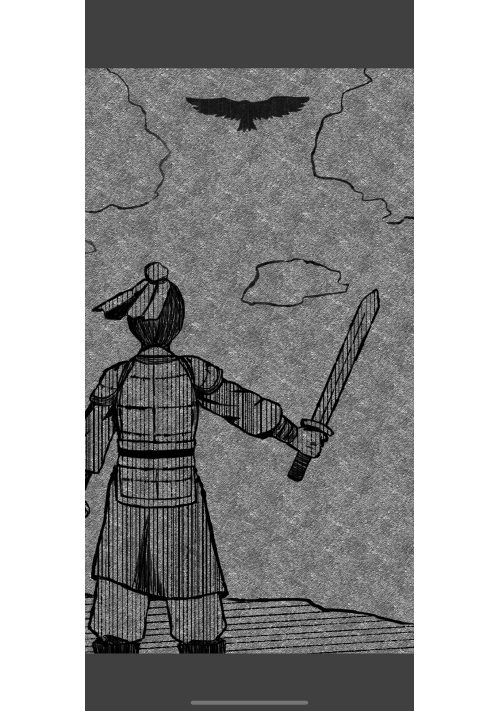
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

【架空戦記】蒲生の忠
糸冬
歴史・時代
天正十年六月二日、本能寺にて織田信長、死す――。
明智光秀は、腹心の明智秀満の進言を受けて決起当初の腹案を変更し、ごく少勢による奇襲により信長の命を狙う策を敢行する。
その結果、本能寺の信長、そして妙覚寺の織田信忠は、抵抗の暇もなく首級を挙げられる。
両名の首級を四条河原にさらした光秀は、織田政権の崩壊を満天下に明らかとし、畿内にて急速に地歩を固めていく。
一方、近江国日野の所領にいた蒲生賦秀(のちの氏郷)は、信長の悲報を知るや、亡き信長の家族を伊勢国松ヶ島城の織田信雄の元に送り届けるべく安土城に迎えに走る。
だが、瀬田の唐橋を無傷で確保した明智秀満の軍勢が安土城に急速に迫ったため、女子供を連れての逃避行は不可能となる。
かくなる上は、戦うより他に道はなし。
信長の遺した安土城を舞台に、若き闘将・蒲生賦秀の活躍が始まる。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した
若き日の滝川一益と滝川義太夫、
尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として
天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が
からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















