124 / 147
第七章
ビュクシ攻防戦5
しおりを挟む
――声?
〈空飛ぶヒトデ〉がくり出す何度めかの直撃を躱しながら彼女は人間の発する声を感じとった。グレアムのものではない。もっと遠くのほうから馬の嘶くような叫び声が聞こえてくる。それはまったく止む様子がないどころか、むしろひと呼吸置く間にハヤブサのような速度で接近してくる。
不確定要素が飛び込んできたことで、ルツィエのなかで意識の停滞が生じ、チェイカの操作に乱れが生じた。依然尽きることなき〈死霊〉の矢が頭上を雨霰のように飛び交い、動作の止まった彼女めがけ致命的な一撃になろうとしている。
綱渡りの先は唐突に暗闇だったようだ。身の危険に背筋が凍りつき、ルツィエは反射的に目を瞑った。
だが――
覚悟した衝撃はいつまで経っても訪れなかった。
視線をあげると目前には味方のチェイカが割り込んでおり、その操縦士が敵の放った〈死霊〉の矢を防御魔法ではじき返していた。眼を凝らし状況を確かめようとするも、それを遮るように若い男の声が背中越しに聞こえた。
「危ないところだったな、ルツィエ?」
確認するまでもなかった。その馴染み深い声色を聞き、彼女はこの場で何が起きたか理解できた。
ルツィエを身を挺して守った声の主はパベルだった。きっとどこかで戦況を見守っていたに違いない。先ほど耳にした正体不明の叫び声も兄の発した警告か何かだったわけだ。
――助かったわ、ベル兄様。
彼女は反射的に感謝の言葉を発しかけた。しかしそれが口を突くことはなかった。なぜなら先に声を発したのは機体を寄せたパベルのほうだったからだ。
「ルツィエ。お前に命令がある」
上位の指揮者が指示を飛ばす場合、一部の高級将校は水素伝達という魔法を使うことができる。だがパベルはそれを行わず、直接言葉を伝えに来た。
その意味をルツィエは大まかに想像できた。魔力の無駄な消費を嫌がったか、それとも敵への漏洩を恐れたか。いずれにしろそこから先は見当もつかなかったが、詳細はパベルの口が直に語ってくれた。
「戦況が悪いので、少々汚いが背に腹はかえられない。お前は街の西にある穀物倉庫を灼け。敵がビュクシを占領する価値がそれで半減する。ついで公共施設から順に破壊の準備をしろ。余は敵の指揮官に破壊を避けたければ講和に応じるよう呼びかける。だがもちろん、和平など結ばない。対話を生み出すチャンスをつくりだし、敵指揮官にありったけの〈凍結〉を注ぎ込む。その根回しは他の鉄兜団員とも通じ合い、手はずは整っている。お前は敵指揮官の態度次第で街を破壊していき、圧力をかけるのだ。相手が強攻策に出ることがわかれば、住宅地を灼いて構わない。ビュクシを火の海にせよ」
普段のパベルと比べれば凛然とした声は、住民に悲惨な死をもたらす命令を淡々と述べていき、聞き役となったルツィエはその命令の意味を驚きを隠せぬまま理解していった。
もっとも重要な点は穀物倉庫が灼け落ちれば街を占領しても食糧がなくなることだろう。これでもし敗北を喫したとしても相手は統治能力を喪失し、ビュクシの住民は危機に瀕する。
だが人命軽視の命令を伝えたパベルは、目的を遂げて気を良くしたのか、口許に余裕を浮かべ狡猾な獣のように笑った。
こうなると位階で劣るルツィエは、一方的に告げられた指示に頷くより他ない。
確かにパベルの言うとおりになれば、敵方は戦略的に言えば負けと等しい目に遭う。それを避けようとして焦って譲歩に踏み出せば、騙し討ちが待っている。
到底モラルを重んじる戦い方ではなかったが、司令官であるパベルは住民軽視の判断をしたときからとっくに悪魔のカードを手にしていた。よって今さら心変わりすることなく、戦況をひっくり返すべく最善のカードを切ってきたわけだ。
そんな彼は、妹を心配する兄の顔を見せると同時に「街を火の海にせよ」と厳命した。深く考えるまでもない、それは事前に使用許可を出した〈爆縮〉を用いろ、という意味だ。
ただし薄い笑みを浮かべたパベルは、一度放った命令に簡単な補足事項をくわえた。
「燃焼過多が行き渡ると大気中のマナが薄くなり魔法が使用不能に陥る。したがって攻性魔法の発動はできるだけ現況の戦闘地域から離れた場所で行い、また穀物倉庫周辺から外側に延焼させないよう気をつけろ」
この発言を聞き取ったルツィエは、パベルが想定どおり〈爆縮〉の使用を促していることを理解した。なぜなら熱を内部に閉じ込める〈爆縮〉は、その破壊力に比して街全体を灼かずに済む点でいまさっき下された命令に沿うものであったからだ。
いずれにせよこのとき、ビュクシという街の運命が恐ろしく短いやり取りの末に決められてしまったことは確かである。
「それでは順次、滞りなく仕事を果たしてくれ」
兄は妹への端的な命令を終えると、この空域で起きている戦闘は自分たちが引き取ると宣言した後、ルツィエに離脱を命じた。
それを承諾した彼女はチェイカのペダルを思いきり踏み込み、戦闘空域を離れた瞬間、戦慄を覚えた。ルツィエはパベルの命令を反復させながら心の底から思ったのだ。自分の長兄がついに本性を露にし、まだ見ぬ人格を持った何者かへ化けたに違いないと。
確かに〈爆縮〉の使用許可こそ出てはいたが、街を焦土にしろという前提は存在しなかった。ゆえに結局は、悪人になりきれないパベルが住民の殺戮を避けたがっているという思いがルツィエの抱く本心だった。
しかしいま示された命令は、そうした見方を完全に覆すものだ。
城内をチェイカで移動しながら、ルツィエは動揺に打ちのめされてしまった。自分のひとを見る目がいかに曇っていたか、孤独になるにつれ痛切に感じとったからだ。
心優しい兄という外見をかぶった戦争の鬼。勝利にこだわる人並みはずれた執念。認識できる機会は何度もあったはずだが、気づいたときには時既に遅しである。
というのも、彼女はどこかで固く信じていたのだ。自分のほうが政治家、軍人として格上な存在だと。それは前世の成功がもたらす認識だが、この異世界ではまだ思い上がりでしかなかった。
――ひょっとして妾は不覚をとったのかしら。
無駄な思考はルツィエから時間を奪い、気づけば彼女はめざすべき街の西側へと侵入していく。だが目的の空域に飛び込んだ刹那、後方から魔獣のあげた不気味な悲鳴が聞こえてくる。
背後を振り返れば、先ほど交戦したエディッサが視野に入った。パベルは戦闘を引き取るとは言ったものの、その防御網は易々と突破されたと思われる。
「――ベル兄のうそつき!」
ルツィエは苛立たしげにチェイカを蹴りあげ、同じ怒りを自分の到らなさにぶつけた。そして戦況がパベル優位で動くことにどす黒い感情を燃え上がらせた。
パベルは他の鉄兜団員とも連携済みと言っていた。その狙いどおり事態が進行すれば、戦勝の手柄は彼が手にするだろう。そうなったらルツィエはたんなる露払いである。
ビュクシ攻防戦にはっきり爪痕を残し、立場を逆転するみちはもうひとつしかない。それはパベルの意志に従ってみせながら、彼の行動に想像もしなかった弱点を見つけだすこと。
「フヒハハ。さぁ、どうする、スターリンよ?」
軍服にしまったペンダントがふわりと浮かび、そこからグレアムが嫌らしい笑い声を立てた。多くを語らないが、その問いはルツィエと同じ認識を共有していたと思われる。
「このままではジリ貧だわ。どうにかしないと」
普段なら言い争いになりそうな場面だが、ルツィエは真剣な表情でつぶやき返す。
叛乱軍を鎮圧した功績が転がり込めば、王位継承をめぐる競争でパベルは名声を高め、おそらく出世をはたすだろう。それが実現した暁には、自分は二度と追いつけないのではないか。ソ連共産党内部における生死をかけた権力闘争の勝者、つまりスターリンにはそのことが肌感覚としてわかっていた。
それでもこのとき、相次ぐ不利に心が折れるどころか、一段と戦意をかき立てる辺り、さすが数々の修羅場をくぐり抜けた独裁者だと言えよう。
グレアムは彼女の行動を邪魔する気はなかったのか無駄口を止め、たいするルツィエは眼下に捉えた目標、すなわち穀物倉庫とおぼしき建造物を眺めとった。そして迷いなく術式を展開しはじめる。
「内なる崩壊を解き放て――〈爆縮〉」
詠唱を短縮したぶん、魔法の発動は早かった。パベルの命令どおりに動くのは癪だが、彼女は巨大な魔方陣を思わせる術式を前方に現しめ、チェイカを自在に操りながら、追いすがる魔獣の背後へまわり込む。
程なくして直径二〇メーテル以上の火球が一瞬で発生し、街の上空を赤い閃光で染めた。
ルツィエは市街戦であることを考慮し、魔法の規模を制御しながら、その火球を魔獣の中心に向けて撃ち放った。大気や塵を巻き込みんだ〈爆縮〉は、内側に向かう激しい圧力を発生させ、周囲の物質を原子レベルで崩壊させていく。
もちろん、そんなミクロの世界の出来事を人間が見ることはできない。
しかし確かな現象として、魔法の詠唱からたった十数秒の間に目が眩むほどの激しい発熱反応が起き、ついで天地を揺るがすような破壊音が街全体に広がった。
その直後、火球の中心部に発生した爆風がエディッサのもつ触手を根こそぎ吹き飛ばすと、ヒトデ型の体はあっという間に原形を失い、無惨にも崩れ落ちていった。その一方、眼下に目を落とせば、穀物倉庫に炎が降り注ぎ、狙いどおりの火災が起きはじめていた。
ここまでの展開はパベルの命令したとおりになった。しかし大きく息を吐いたルツィエは、興奮覚めやらぬ頭で兄が街の破壊を最初はこの程度に抑えた理由を考えだす。目的は敵指揮官を引きずり出し、講和を持ちかけ、騙し討ちにすることだった。けれど本当にそれだけだろうか?
答えはおそらくノーだ。なぜなら徹底的な破壊はビュクシという街の消滅を意味する。不況の煽りを受け、ただでさえ国民一人ひとりの生活が苦しいなか、統治の正統性に汚点をつける真似はだれだって避けたい。そんな危ういリスクはいくら王族のパベルといえど引き受けるわけにいかないだろう。このイェドノタ連邦においてそれが許される人物は、ルツィエの父である《魔王》以外に存在しない。
だいいちパベルがやろうとしているのは取引だ。講和をもちかけ、それを拒めば街を灼いてまわるという駆け引き。そこに隙を生じさせ、敵指揮官のみを狙い撃ちにするという打算。
ポイントは巧妙に織り込んだ条件づけだった。仮に相手が時間稼ぎなどを企てれば、パベルの指示に則りルツィエは街の破壊を進めていき、その責任はむろん敵指揮官らの側に帰する。
判定を担うのは言うまでもなく名も無き民衆だろう。
敵側の大義名分は先刻撒かれたビラにあったとおり、魔人族の統治者が大多数のヒト族の困窮を見て見ぬふりをしてきたことへの異議申し立てにある。
しかしたとえ解放者を名乗っても、自分たちの財産を破壊する連中を人は味方と認めない。そもそもエディッサを連れてきた時点で、彼らは破壊者の汚名を負うリスクを冒している。パベルはルツィエに破壊を命じながら、同時に自軍が正義を名乗る余地を残すつもりなのだ。
ここまで全て計算ずくだとするなら、軍人としての手腕もさることながら、パベルの才覚は政治家としても一流と言える。
「くそ畜生。何とかして出し抜かなくちゃ!」
いよいよ後がなくなった焦りでルツィエが白髪をかきむしったとき、ふいに何者かの声が城内全体に響き渡った。
『トルナバの新町長よ、そこにいるのは承知済みである。余の話を心して聞いて貰えないか?』
空気を震わせたその声は、声質からして兄のものだとわかった。しかも街の隅々にまで届くような音量であることから察して、魔法の効果、すなわち水素伝達を最大限利用したものだと判じられた。
視線をめぐらせれば、彼は戦闘空域を抜け出し、行政府庁舎を上空のチェイカから見下ろしている。敵指揮官がそこに潜んでいることを、おそらく部下の索敵を通じて掴んだのだろう。
パベルの周囲には無傷の鉄兜団員らがいた。各々敵の追尾を切り抜け、あるいは戦線を離脱しながら街の中央部に集結したようだ。
裏を返せば襲撃側は防衛軍の各個撃破を望んだ形でなしえておらず、あの銀髪の魔導師も数的不利を悟ってどこかへ退却したのかもしれない。
いずれにせよ戦況を立て直した自信はパベルの声色に表れていた。彼は少し早口だが、それでも落ち着いた物言いで庁舎に向かって語りかけはじめた。
『貴公が行政官に送った上訴状は読ませて貰った。そこにこの度の叛乱行為に到った核心的動機について書いてあったのを覚えている。この世界に調和を取り戻さねばならない。貴公はそう記した。端的に申しあげると余はその主張に共感を覚えた』
上訴状の中身を読んだことのないルツィエにとってその文言は初耳だった。同時にパベルが妙に紳士的な口ぶりであることにも思いを馳せた。それは彼の言葉が敵指揮官のみならず、ビュクシに住む民衆一人ひとりに語りかけたものであることを意味していた。
『貴公がご存知かは知らないが、この世界には最善説という考えがある。どんなに悪があろうと、それには目的があり、正しい世界全体の一部であるという考えだ。この世界を不調和の縮図と見なす貴公は最善説など信じておらず、むしろアンチであろう。とはいえその思想は、余もかねてより支持しているものだ』
眼をべつの空域に移せば、戦闘は依然継続中だった。見たところ、行政府庁舎を挟んだ東壁でひとつ、北壁のほうでもうひとつ、エディッサを巻き込みながら味方と敵が入り乱れている。
そしてこの最中、どこかに狙撃手が潜んでいるのだろう。だが敵指揮官は不意討ちを恐れているのか、依然姿を見せない。けれどパベルは想定内とばかりに一方的な演説を続けるのだった。
『余は聖隷教会の敬虔な信徒だが、この世界は《主》が実現した調和によってバランスがとれているという考えは非現実的だと思っている。不調和の種となる悪は存在し、それは容赦なく取り除かねばならない。悪さえも正しい世界の一部ではないのだ。むろん悪を取り除くのは生半可なことではないだろう。しかし人類はそこにわずかでも近づく努力が必要と考えている。そうなったとき、余と貴公の思想的な距離はないに等しい。産業に乏しい辺境は深刻化する不況に苦しんでいる。改善をめざしてともに力を尽くさないか。余は貴公のような人物の貢献が連邦のためになると信じている』
ルツィエはパベルの思惑を知っているから、この演説が迫真の演技であることが理解できる。
そう言えば先ほどからグレアムは沈黙したままである。天界の住人として宗教には一家言ありそうに思えるが、やかましく介入するのを止め、純粋にルツィエの行動を見守るつもりなのだろうか。
ところが彼女がパベルから注意をそらしたとき、行政府庁舎の地上階で動きが起こった。
おもむろに姿を現したのは一匹の翼竜だ。そこに二体の人間がまたがっている。前方が女で、後方が男だった。二人は防塵マスクを顔に着け、どうやら〈爆縮〉がもたらしかねない被害へ対処したことが判じられる。
見れば、男は戦場において場違いな格好をしていた。その装いは政治家が着る国民服である。
パベルでさえ軍服を着ているのに、そこには違和感しかない。
自分は軍人でも冒険者でもなく、政治家なのだという強烈な自己主張。わざわざそんなことをやってのける人間は一人しか思い浮かばない。
あれが敵指揮官なのだ。
そして操縦役の女はよりによって僧服を着ている。この世界にはビショップがおり、したがって冒険者の一種と見えなくもないが、叛乱軍という立場を考えるとこれまた違和感をかき立てられる。しかも敵指揮官との距離感から察するに、護衛兼参謀といった雰囲気が醸しだされていた。
――だとすれば、あの僧職がオフラーナ要員なのかしら?
まるで図ったかのごとく、戦争の当事者たちが街の中央部に顔を揃えつつあった。目視しえない場所には狙撃手も隠れているのだろう。ありったけの〈凍結〉を注ぎ込む、とパベルは言った。騙し討ちの準備は万全と見るのが当然だった。
事態をつまびらかに把握している者であればあるほど、息つくことさえ躊躇われる緊張が体内を駆けめぐったことだろう。ルツィエはしかし、こんなときですら、うっすらと笑みを浮かべるだけだった。
やがてそのしぐさと連動して、庁舎に出現した翼竜の上から宙を引き裂くような甲高い絶叫があがった。(続く
〈空飛ぶヒトデ〉がくり出す何度めかの直撃を躱しながら彼女は人間の発する声を感じとった。グレアムのものではない。もっと遠くのほうから馬の嘶くような叫び声が聞こえてくる。それはまったく止む様子がないどころか、むしろひと呼吸置く間にハヤブサのような速度で接近してくる。
不確定要素が飛び込んできたことで、ルツィエのなかで意識の停滞が生じ、チェイカの操作に乱れが生じた。依然尽きることなき〈死霊〉の矢が頭上を雨霰のように飛び交い、動作の止まった彼女めがけ致命的な一撃になろうとしている。
綱渡りの先は唐突に暗闇だったようだ。身の危険に背筋が凍りつき、ルツィエは反射的に目を瞑った。
だが――
覚悟した衝撃はいつまで経っても訪れなかった。
視線をあげると目前には味方のチェイカが割り込んでおり、その操縦士が敵の放った〈死霊〉の矢を防御魔法ではじき返していた。眼を凝らし状況を確かめようとするも、それを遮るように若い男の声が背中越しに聞こえた。
「危ないところだったな、ルツィエ?」
確認するまでもなかった。その馴染み深い声色を聞き、彼女はこの場で何が起きたか理解できた。
ルツィエを身を挺して守った声の主はパベルだった。きっとどこかで戦況を見守っていたに違いない。先ほど耳にした正体不明の叫び声も兄の発した警告か何かだったわけだ。
――助かったわ、ベル兄様。
彼女は反射的に感謝の言葉を発しかけた。しかしそれが口を突くことはなかった。なぜなら先に声を発したのは機体を寄せたパベルのほうだったからだ。
「ルツィエ。お前に命令がある」
上位の指揮者が指示を飛ばす場合、一部の高級将校は水素伝達という魔法を使うことができる。だがパベルはそれを行わず、直接言葉を伝えに来た。
その意味をルツィエは大まかに想像できた。魔力の無駄な消費を嫌がったか、それとも敵への漏洩を恐れたか。いずれにしろそこから先は見当もつかなかったが、詳細はパベルの口が直に語ってくれた。
「戦況が悪いので、少々汚いが背に腹はかえられない。お前は街の西にある穀物倉庫を灼け。敵がビュクシを占領する価値がそれで半減する。ついで公共施設から順に破壊の準備をしろ。余は敵の指揮官に破壊を避けたければ講和に応じるよう呼びかける。だがもちろん、和平など結ばない。対話を生み出すチャンスをつくりだし、敵指揮官にありったけの〈凍結〉を注ぎ込む。その根回しは他の鉄兜団員とも通じ合い、手はずは整っている。お前は敵指揮官の態度次第で街を破壊していき、圧力をかけるのだ。相手が強攻策に出ることがわかれば、住宅地を灼いて構わない。ビュクシを火の海にせよ」
普段のパベルと比べれば凛然とした声は、住民に悲惨な死をもたらす命令を淡々と述べていき、聞き役となったルツィエはその命令の意味を驚きを隠せぬまま理解していった。
もっとも重要な点は穀物倉庫が灼け落ちれば街を占領しても食糧がなくなることだろう。これでもし敗北を喫したとしても相手は統治能力を喪失し、ビュクシの住民は危機に瀕する。
だが人命軽視の命令を伝えたパベルは、目的を遂げて気を良くしたのか、口許に余裕を浮かべ狡猾な獣のように笑った。
こうなると位階で劣るルツィエは、一方的に告げられた指示に頷くより他ない。
確かにパベルの言うとおりになれば、敵方は戦略的に言えば負けと等しい目に遭う。それを避けようとして焦って譲歩に踏み出せば、騙し討ちが待っている。
到底モラルを重んじる戦い方ではなかったが、司令官であるパベルは住民軽視の判断をしたときからとっくに悪魔のカードを手にしていた。よって今さら心変わりすることなく、戦況をひっくり返すべく最善のカードを切ってきたわけだ。
そんな彼は、妹を心配する兄の顔を見せると同時に「街を火の海にせよ」と厳命した。深く考えるまでもない、それは事前に使用許可を出した〈爆縮〉を用いろ、という意味だ。
ただし薄い笑みを浮かべたパベルは、一度放った命令に簡単な補足事項をくわえた。
「燃焼過多が行き渡ると大気中のマナが薄くなり魔法が使用不能に陥る。したがって攻性魔法の発動はできるだけ現況の戦闘地域から離れた場所で行い、また穀物倉庫周辺から外側に延焼させないよう気をつけろ」
この発言を聞き取ったルツィエは、パベルが想定どおり〈爆縮〉の使用を促していることを理解した。なぜなら熱を内部に閉じ込める〈爆縮〉は、その破壊力に比して街全体を灼かずに済む点でいまさっき下された命令に沿うものであったからだ。
いずれにせよこのとき、ビュクシという街の運命が恐ろしく短いやり取りの末に決められてしまったことは確かである。
「それでは順次、滞りなく仕事を果たしてくれ」
兄は妹への端的な命令を終えると、この空域で起きている戦闘は自分たちが引き取ると宣言した後、ルツィエに離脱を命じた。
それを承諾した彼女はチェイカのペダルを思いきり踏み込み、戦闘空域を離れた瞬間、戦慄を覚えた。ルツィエはパベルの命令を反復させながら心の底から思ったのだ。自分の長兄がついに本性を露にし、まだ見ぬ人格を持った何者かへ化けたに違いないと。
確かに〈爆縮〉の使用許可こそ出てはいたが、街を焦土にしろという前提は存在しなかった。ゆえに結局は、悪人になりきれないパベルが住民の殺戮を避けたがっているという思いがルツィエの抱く本心だった。
しかしいま示された命令は、そうした見方を完全に覆すものだ。
城内をチェイカで移動しながら、ルツィエは動揺に打ちのめされてしまった。自分のひとを見る目がいかに曇っていたか、孤独になるにつれ痛切に感じとったからだ。
心優しい兄という外見をかぶった戦争の鬼。勝利にこだわる人並みはずれた執念。認識できる機会は何度もあったはずだが、気づいたときには時既に遅しである。
というのも、彼女はどこかで固く信じていたのだ。自分のほうが政治家、軍人として格上な存在だと。それは前世の成功がもたらす認識だが、この異世界ではまだ思い上がりでしかなかった。
――ひょっとして妾は不覚をとったのかしら。
無駄な思考はルツィエから時間を奪い、気づけば彼女はめざすべき街の西側へと侵入していく。だが目的の空域に飛び込んだ刹那、後方から魔獣のあげた不気味な悲鳴が聞こえてくる。
背後を振り返れば、先ほど交戦したエディッサが視野に入った。パベルは戦闘を引き取るとは言ったものの、その防御網は易々と突破されたと思われる。
「――ベル兄のうそつき!」
ルツィエは苛立たしげにチェイカを蹴りあげ、同じ怒りを自分の到らなさにぶつけた。そして戦況がパベル優位で動くことにどす黒い感情を燃え上がらせた。
パベルは他の鉄兜団員とも連携済みと言っていた。その狙いどおり事態が進行すれば、戦勝の手柄は彼が手にするだろう。そうなったらルツィエはたんなる露払いである。
ビュクシ攻防戦にはっきり爪痕を残し、立場を逆転するみちはもうひとつしかない。それはパベルの意志に従ってみせながら、彼の行動に想像もしなかった弱点を見つけだすこと。
「フヒハハ。さぁ、どうする、スターリンよ?」
軍服にしまったペンダントがふわりと浮かび、そこからグレアムが嫌らしい笑い声を立てた。多くを語らないが、その問いはルツィエと同じ認識を共有していたと思われる。
「このままではジリ貧だわ。どうにかしないと」
普段なら言い争いになりそうな場面だが、ルツィエは真剣な表情でつぶやき返す。
叛乱軍を鎮圧した功績が転がり込めば、王位継承をめぐる競争でパベルは名声を高め、おそらく出世をはたすだろう。それが実現した暁には、自分は二度と追いつけないのではないか。ソ連共産党内部における生死をかけた権力闘争の勝者、つまりスターリンにはそのことが肌感覚としてわかっていた。
それでもこのとき、相次ぐ不利に心が折れるどころか、一段と戦意をかき立てる辺り、さすが数々の修羅場をくぐり抜けた独裁者だと言えよう。
グレアムは彼女の行動を邪魔する気はなかったのか無駄口を止め、たいするルツィエは眼下に捉えた目標、すなわち穀物倉庫とおぼしき建造物を眺めとった。そして迷いなく術式を展開しはじめる。
「内なる崩壊を解き放て――〈爆縮〉」
詠唱を短縮したぶん、魔法の発動は早かった。パベルの命令どおりに動くのは癪だが、彼女は巨大な魔方陣を思わせる術式を前方に現しめ、チェイカを自在に操りながら、追いすがる魔獣の背後へまわり込む。
程なくして直径二〇メーテル以上の火球が一瞬で発生し、街の上空を赤い閃光で染めた。
ルツィエは市街戦であることを考慮し、魔法の規模を制御しながら、その火球を魔獣の中心に向けて撃ち放った。大気や塵を巻き込みんだ〈爆縮〉は、内側に向かう激しい圧力を発生させ、周囲の物質を原子レベルで崩壊させていく。
もちろん、そんなミクロの世界の出来事を人間が見ることはできない。
しかし確かな現象として、魔法の詠唱からたった十数秒の間に目が眩むほどの激しい発熱反応が起き、ついで天地を揺るがすような破壊音が街全体に広がった。
その直後、火球の中心部に発生した爆風がエディッサのもつ触手を根こそぎ吹き飛ばすと、ヒトデ型の体はあっという間に原形を失い、無惨にも崩れ落ちていった。その一方、眼下に目を落とせば、穀物倉庫に炎が降り注ぎ、狙いどおりの火災が起きはじめていた。
ここまでの展開はパベルの命令したとおりになった。しかし大きく息を吐いたルツィエは、興奮覚めやらぬ頭で兄が街の破壊を最初はこの程度に抑えた理由を考えだす。目的は敵指揮官を引きずり出し、講和を持ちかけ、騙し討ちにすることだった。けれど本当にそれだけだろうか?
答えはおそらくノーだ。なぜなら徹底的な破壊はビュクシという街の消滅を意味する。不況の煽りを受け、ただでさえ国民一人ひとりの生活が苦しいなか、統治の正統性に汚点をつける真似はだれだって避けたい。そんな危ういリスクはいくら王族のパベルといえど引き受けるわけにいかないだろう。このイェドノタ連邦においてそれが許される人物は、ルツィエの父である《魔王》以外に存在しない。
だいいちパベルがやろうとしているのは取引だ。講和をもちかけ、それを拒めば街を灼いてまわるという駆け引き。そこに隙を生じさせ、敵指揮官のみを狙い撃ちにするという打算。
ポイントは巧妙に織り込んだ条件づけだった。仮に相手が時間稼ぎなどを企てれば、パベルの指示に則りルツィエは街の破壊を進めていき、その責任はむろん敵指揮官らの側に帰する。
判定を担うのは言うまでもなく名も無き民衆だろう。
敵側の大義名分は先刻撒かれたビラにあったとおり、魔人族の統治者が大多数のヒト族の困窮を見て見ぬふりをしてきたことへの異議申し立てにある。
しかしたとえ解放者を名乗っても、自分たちの財産を破壊する連中を人は味方と認めない。そもそもエディッサを連れてきた時点で、彼らは破壊者の汚名を負うリスクを冒している。パベルはルツィエに破壊を命じながら、同時に自軍が正義を名乗る余地を残すつもりなのだ。
ここまで全て計算ずくだとするなら、軍人としての手腕もさることながら、パベルの才覚は政治家としても一流と言える。
「くそ畜生。何とかして出し抜かなくちゃ!」
いよいよ後がなくなった焦りでルツィエが白髪をかきむしったとき、ふいに何者かの声が城内全体に響き渡った。
『トルナバの新町長よ、そこにいるのは承知済みである。余の話を心して聞いて貰えないか?』
空気を震わせたその声は、声質からして兄のものだとわかった。しかも街の隅々にまで届くような音量であることから察して、魔法の効果、すなわち水素伝達を最大限利用したものだと判じられた。
視線をめぐらせれば、彼は戦闘空域を抜け出し、行政府庁舎を上空のチェイカから見下ろしている。敵指揮官がそこに潜んでいることを、おそらく部下の索敵を通じて掴んだのだろう。
パベルの周囲には無傷の鉄兜団員らがいた。各々敵の追尾を切り抜け、あるいは戦線を離脱しながら街の中央部に集結したようだ。
裏を返せば襲撃側は防衛軍の各個撃破を望んだ形でなしえておらず、あの銀髪の魔導師も数的不利を悟ってどこかへ退却したのかもしれない。
いずれにせよ戦況を立て直した自信はパベルの声色に表れていた。彼は少し早口だが、それでも落ち着いた物言いで庁舎に向かって語りかけはじめた。
『貴公が行政官に送った上訴状は読ませて貰った。そこにこの度の叛乱行為に到った核心的動機について書いてあったのを覚えている。この世界に調和を取り戻さねばならない。貴公はそう記した。端的に申しあげると余はその主張に共感を覚えた』
上訴状の中身を読んだことのないルツィエにとってその文言は初耳だった。同時にパベルが妙に紳士的な口ぶりであることにも思いを馳せた。それは彼の言葉が敵指揮官のみならず、ビュクシに住む民衆一人ひとりに語りかけたものであることを意味していた。
『貴公がご存知かは知らないが、この世界には最善説という考えがある。どんなに悪があろうと、それには目的があり、正しい世界全体の一部であるという考えだ。この世界を不調和の縮図と見なす貴公は最善説など信じておらず、むしろアンチであろう。とはいえその思想は、余もかねてより支持しているものだ』
眼をべつの空域に移せば、戦闘は依然継続中だった。見たところ、行政府庁舎を挟んだ東壁でひとつ、北壁のほうでもうひとつ、エディッサを巻き込みながら味方と敵が入り乱れている。
そしてこの最中、どこかに狙撃手が潜んでいるのだろう。だが敵指揮官は不意討ちを恐れているのか、依然姿を見せない。けれどパベルは想定内とばかりに一方的な演説を続けるのだった。
『余は聖隷教会の敬虔な信徒だが、この世界は《主》が実現した調和によってバランスがとれているという考えは非現実的だと思っている。不調和の種となる悪は存在し、それは容赦なく取り除かねばならない。悪さえも正しい世界の一部ではないのだ。むろん悪を取り除くのは生半可なことではないだろう。しかし人類はそこにわずかでも近づく努力が必要と考えている。そうなったとき、余と貴公の思想的な距離はないに等しい。産業に乏しい辺境は深刻化する不況に苦しんでいる。改善をめざしてともに力を尽くさないか。余は貴公のような人物の貢献が連邦のためになると信じている』
ルツィエはパベルの思惑を知っているから、この演説が迫真の演技であることが理解できる。
そう言えば先ほどからグレアムは沈黙したままである。天界の住人として宗教には一家言ありそうに思えるが、やかましく介入するのを止め、純粋にルツィエの行動を見守るつもりなのだろうか。
ところが彼女がパベルから注意をそらしたとき、行政府庁舎の地上階で動きが起こった。
おもむろに姿を現したのは一匹の翼竜だ。そこに二体の人間がまたがっている。前方が女で、後方が男だった。二人は防塵マスクを顔に着け、どうやら〈爆縮〉がもたらしかねない被害へ対処したことが判じられる。
見れば、男は戦場において場違いな格好をしていた。その装いは政治家が着る国民服である。
パベルでさえ軍服を着ているのに、そこには違和感しかない。
自分は軍人でも冒険者でもなく、政治家なのだという強烈な自己主張。わざわざそんなことをやってのける人間は一人しか思い浮かばない。
あれが敵指揮官なのだ。
そして操縦役の女はよりによって僧服を着ている。この世界にはビショップがおり、したがって冒険者の一種と見えなくもないが、叛乱軍という立場を考えるとこれまた違和感をかき立てられる。しかも敵指揮官との距離感から察するに、護衛兼参謀といった雰囲気が醸しだされていた。
――だとすれば、あの僧職がオフラーナ要員なのかしら?
まるで図ったかのごとく、戦争の当事者たちが街の中央部に顔を揃えつつあった。目視しえない場所には狙撃手も隠れているのだろう。ありったけの〈凍結〉を注ぎ込む、とパベルは言った。騙し討ちの準備は万全と見るのが当然だった。
事態をつまびらかに把握している者であればあるほど、息つくことさえ躊躇われる緊張が体内を駆けめぐったことだろう。ルツィエはしかし、こんなときですら、うっすらと笑みを浮かべるだけだった。
やがてそのしぐさと連動して、庁舎に出現した翼竜の上から宙を引き裂くような甲高い絶叫があがった。(続く
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説

八百長試合を引き受けていたが、もう必要ないと言われたので圧勝させてもらいます
海夏世もみじ
ファンタジー
月一に開催されるリーヴェ王国最強決定大会。そこに毎回登場するアッシュという少年は、金をもらう代わりに対戦相手にわざと負けるという、いわゆる「八百長試合」をしていた。
だが次の大会が目前となったある日、もうお前は必要ないと言われてしまう。八百長が必要ないなら本気を出してもいい。
彼は手加減をやめ、“本当の力”を解放する。
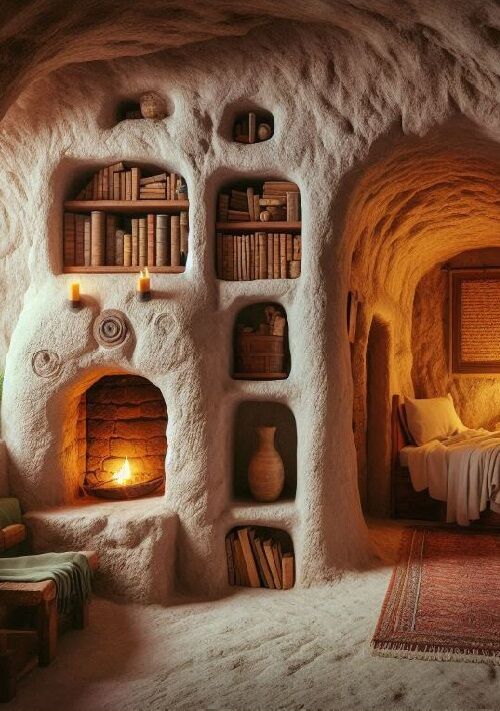
リフォーム分譲ダンジョン~庭にダンジョンができたので、スキルを使い改装して、分譲販売することにした。あらぬ罪を着せてた奴らにざまぁしてやる~
喰寝丸太
ファンタジー
俺はソフトウェア開発会社の社員だった。
外注費を架空計上して横領した罪に問われ会社を追われた。
不幸は続く。
仲の良かった伯父さんが亡くなった。
遺産が転がり込むかと思われたら、貰った家の庭にダンジョンができて不良物件に。
この世界は10年前からダンジョンに悩まされていた。
ダンジョンができるのは良く聞く話。
ダンジョンは放っておくとスタンピードを起こし、大量のモンスターを吐き出す。
防ぐ手段は間引きすることだけ。
ダンジョンの所有者にはダンジョンを管理する義務が発生しますとのこと。
そして、スタンピードが起きた時の損害賠償は所有者である俺にくるらしい。
ダンジョンの権利は放棄できないようになっているらしい。
泣く泣く自腹で冒険者を雇い、討伐する事にした。
俺が持っているスキルのリフォームはダンジョンにも有効らしい。
俺はダンジョンをリフォーム、分譲して売り出すことにした。

女神の代わりに異世界漫遊 ~ほのぼの・まったり。時々、ざまぁ?~
大福にゃここ
ファンタジー
目の前に、女神を名乗る女性が立っていた。
麗しい彼女の願いは「自分の代わりに世界を見て欲しい」それだけ。
使命も何もなく、ただ、その世界で楽しく生きていくだけでいいらしい。
厳しい異世界で生き抜く為のスキルも色々と貰い、食いしん坊だけど優しくて可愛い従魔も一緒!
忙しくて自由のない女神の代わりに、異世界を楽しんでこよう♪
13話目くらいから話が動きますので、気長にお付き合いください!
最初はとっつきにくいかもしれませんが、どうか続きを読んでみてくださいね^^
※お気に入り登録や感想がとても励みになっています。 ありがとうございます!
(なかなかお返事書けなくてごめんなさい)
※小説家になろう様にも投稿しています

追放した回復術師が、ハーレムを連れて「ざまぁ」と言いに来た。
夏目くちびる
ファンタジー
ある日、世界の命運を背負って旅をする冒険者パーティーの勇者シロウは、チート級の実力を持つ回復術師であるクロウを追放した。
それに対してクロウは「俺がこのパーティで一番強いんだぞ!?」と猛反対。しかし、シロウはそんな戯言には聞く耳を持たず、「わかってるよ、じゃあな」」と彼を見送った。
そして出会ったのは、新たな二人の若い冒険者。彼らを仲間にしたパーティーの四人は、悪魔を倒すために手を取り合い、様々な人種族が共に住まう統一国家となった広大な世界の、未だ何処にあるのかも明らかになっていない諸悪の根源である魔王の城を目指して旅を続けるのだった。
果たして、彼らは度々因縁を付けに来る事となった回復術師のチーレムパーティーと、一体どうやって付き合っていくのだろうか。そして、無事に魔王城を探し出し、世界を救う事が出来るのだろうか。
イマドキの器用で無気力な若者タンク、アオヤ。殺意の波動に目覚めたジェノサイドアタッカー、モモコ。(仕事でだけ)リアリズムを追求するおっさん勇者、シロウ。そして、ただ宝具を扱えるだけの一般サポーターな主人公、キータ。彼らの送る、世直し系痛快ブラックコメディ冒険譚、開幕。
※この物語に登場する全ては、現実に存在する団体や個人とは一切関係はありません。
※5/5追記:長編の都合上、元ネタとなった短編を深堀していった結果、意図せず物語の主軸が『リベンジざまぁ』よりも『冒険バトル物』に寄ってしまったので、大筋をなぞった別作品として楽しんで頂けると幸いです。

夫の書斎から渡されなかった恋文を見つけた話
束原ミヤコ
恋愛
フリージアはある日、夫であるエルバ公爵クライヴの書斎の机から、渡されなかった恋文を見つけた。
クライヴには想い人がいるという噂があった。
それは、隣国に嫁いだ姫サフィアである。
晩餐会で親し気に話す二人の様子を見たフリージアは、妻でいることが耐えられなくなり離縁してもらうことを決めるが――。

転生して異世界の第7王子に生まれ変わったが、魔力が0で無能者と言われ、僻地に追放されたので自由に生きる。
黒ハット
ファンタジー
ヤクザだった大宅宗一35歳は死んで記憶を持ったまま異世界の第7王子に転生する。魔力が0で魔法を使えないので、無能者と言われて王族の籍を抜かれ僻地の領主に追放される。魔法を使える事が分かって2回目の人生は前世の知識と魔法を使って領地を発展させながら自由に生きるつもりだったが、波乱万丈の人生を送る事になる
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















