27 / 55
隔離室
しおりを挟む
彩は、実年齢より若く見られることにコンプレックスを持っていた。
若く見られるのはいいことだが、彼女の場合、幼く見えると言ったほうがいいだろう。
そのせいか、両親も彩のことを子供扱いするところがある。
特に父親は、彩に近づく男性を見つけると、いつもしつこく彩に尋ねてきた。
しかし、母親のほうは、そろそろ身を固めてほしいと思っていたようだが。
「お父さん、そんなこと聞くもんじゃないですよ」
そう父をたしなめる母親に
「変な誤解しないで。少し前に、偶然お会いしたことがあっただけよ。今日は心配してわざわざお見舞いに来て下さったの」
と彩が慌てて説明する。
「優しい人じゃないか。ああいう人が、お前の旦那さんになってくれればねえ」
目を伏せて、母は言った。
「やめてよ、お母さん」
顔を赤くして、彩が言葉を返す。
「分かってるよ。でも、お前の花嫁姿が見たかった・・・」
涙ぐむ母親を見て、彩はそれ以上は何も言わなかった。
皆が沈黙している中、ノックの音がした。
「失礼します」
彩の応答に反応して、白衣を着た女性が入ってきた。彩に検査結果を告げに来たうちの一人だ。
「新しい病室が準備できましたので、これからご案内します」
女性の後ろから、電動の車椅子がついて来た。これに乗って移動するということなのだろう。
「隔離室に移動するのですか?」
彩が問いかける。
「安心して下さい。あなたを束縛するようなことはいたしません。しかし、少し不自由を感じるかも知れません。それについては、どうかご了承下さいませ」
女性は事務的に回答した。
「私、場所を知りたいから、いっしょについて行ってもいいですか?」
麻子が女性に尋ねた。
「それは構いませんよ。では、ご案内しますから、こちらの車椅子にお乗り下さい」
女性は、少し笑みを浮かべながら、彩にやさしく話しかけた。
結局、両親と麻子、それにドナもいっしょに付いていくことになった。
昨日から彩の病室にいたアンドロイドの名前はモニカ。これから、彩の身のまわりの世話を担当するということで、彼女も同伴している。
そして白衣を着た女性の名前はフィオナ。彼女もアンドロイドで、彩の主治医となることを告げた。
「これから、いろいろと大変だと思うけど、私たちができるだけサポートしますね」
出発の前に、モニカが笑顔で彩に話しかけてくれたおかげで、彩の緊張も少しほぐれたようだ。
感染者用の病室は、病院の上層階にある。万が一、インフェクターと化した感染者が病室から飛び出したとき、外へ逃げる可能性を小さくするためであろう。
エレベーターから出て、最初に目に飛び込んだのは、入り口に付けられた金属製の扉だ。この先に入れば、容易に抜け出せないのは明らかだった。
「まるで牢獄ね」
彩がポツリと言った。
「そう見えるかも知れません。外出も基本的にはできませんから」
フィオナは、彩のほうを見て説明した。
扉の前には、守衛らしき人が立っている。
「今日から、この病棟へ移ることになった葉月彩さんです」
フィオナが守衛に彩を紹介した。
「話は伺っています。はじめまして葉月さん。私はここで守衛をしているアンドロイドのアーサーです。どうかお見知り置き下さい」
ハンサムという言葉がピッタリ合うような顔にさわやかな笑みを浮かべ、守衛のアーサーはあいさつした。
「きれいなお花ですね」
彩のひざに乗せられた花束に目を移し、アーサーは笑顔を絶やさず話を続ける。
「ありがとう。お見舞いにもらったの」
「長期保存できるように加工するといいですよ。専用の樹脂で固めれば、100年は保存できます」
「そんなに長生きできるわけでもないし・・・」
ほとんど聞こえないほどの小さな声で、彩は応える。それが自分に言い聞かせているように思えて、麻子は彩の顔に目を向けた。彩は前を、扉の方をじっと見つめていた。
扉が自動的に開き、中へ入る。廊下は程よい光で照らされ、影はどこにも見当たらない。
淡いグレーの床は柔らかく、まるで泥の上を歩いているような感覚だ。白い壁にも、同じ素材を使っているように見える。おそらく、インフェクターが自傷行為をしても、できるだけダメージを少なくするための配慮であろう。
両側の壁に並んだ扉には窓がなく、中に人がいるのかどうかさえ分からない。いったい、この病棟に何人の感染者がいるのか、彩は気になった。
「ここには、他にも誰かいるのですか?」
彩がモニカに尋ねる。
「現在、あなたの他に18名います」
意外にも数が多く、彩は少し驚いた。
「少し前に、スラム街で大量の感染者が見つかって、一気に15人増えたんです。この人たちは、警察の管理化にあるので会うことはできませんが、他の3名の方とは、お話することもできますよ」
「どんな方たちなのですか?」
「男女が一人ずつ、それから小さな男の子が一人います」
「子供が・・・」
彩は、思わず麻子のほうを見ていた。麻子と目が合い、慌てて視線をそらす。
「ここが、あなたの病室ですよ」
分厚い扉を開けると、中は普通の病室よりもかなり広く、しかし殺風景だった。家具などはどこにも見当たらない。
「何もないのね・・・」
彩の母親が、率直な感想を述べた。
「クローゼットや収納棚は壁の中に埋め込まれています。テーブルや椅子も、このように・・・」
モニカが壁にある手のマークに軽く触れると、少し離れた場所で、床からテーブルと椅子が現れた。
テーブルには角がなく、全体的に丸みを帯びている。そして椅子は円筒形で、背もたれはなかった。
「怪我をしないよう、徹底されているのね」
彩がテーブルを見て言った。
「この、手のマークのところに触れると、家具が現れたり、棚が開いたりします。このマークに手をきちんと合わせてくださいね。そうしないと作動しませんから」
彩が試しにマークに触れてみると、テーブルと椅子が床に収納された。
ベッドにモニタ、オーディオ機器など、設備は充実していた。窓からは明るい日差しが降り注ぐ。しかし、その窓はかなり高い位置に設置されていた。
「景色が見られないのは残念ね」
彩の言葉を聞いて
「心配ありませんわ。景色を眺められる場所もあるのです。今度はその場所をご案内しましょう」
と、モニカが明るい声で応えた。
「今回は、何をチェックすればいいんだ?」
両手を頭の後ろで組んだ状態で椅子に座っていた鬼神は、マリーへ顔を向けて尋ねた。
「私たちがスラム街へ到着する前に、『ノア』とジャフェスが向かったと思われるD-6エリアの商業スペースの解析結果です。実は以前、顔を隠して移動している者がいないかチェックしていましたが、そのような人物は見つかりませんでした。しかし・・・」
マリーが言いよどんだのを見て、鬼神は
「しかし、どうした?」
と先を促した。
「商業スペースですから呼び込みも多くて、着ぐるみ姿については対象外にしていたのです。もしかしたら、その中に紛れている可能性はないかという話になりまして」
「そいつらの中で、仕事もせずに移動している者がいれば、怪しいんじゃないか?」
「いいえ、そのような者はいません。全員が、店が閉まるまでの間、呼び込みをしていました」
鬼神は、上を向いたまま、しばらくの間じっとしていたが、やがて
「一応、調べてみるか。しかし、着ぐるみを付けていたら、全く区別は付かないけどな」
と言いながら、モニタのほうへと顔を向けた。
様々な着ぐるみが画面に登場する。子供向け番組に登場するヒーローや、魔法使いのヒロイン、ピンクのうさぎに派手な電飾のロボットなど、夜にもかかわらず出歩いている子供に囲まれていたり、通りの人々に完全に無視されて素通りされていたり、扱いも様々だ。
当然、中に誰が入っているのか分かるはずもない。それでも、鬼神は真剣に画面に見入っていた。
そして、ある写真が映し出されたときである。
「ストップ!」
鬼神が叫んだ。
「もしかして、見つかったのですか?」
マリーが写真を見ながら尋ねた。
その写真には、お菓子メーカーのキャラクターの女の子が写っていた。おかっぱ頭の大きな顔に、手足の短い二頭身の姿で、子供たちに囲まれて何やらポーズをとっている。
その近くで、年配の男性が笑顔で子供たちにお菓子を配っていた。
「この男、背格好は『ノア』によく似ているな」
鬼神は、画面を凝視しながらつぶやいた。
「顔はどうなのですか?」
マリーの問いには
「全く違う。この男は顔に特徴があるな。エラが張って、目の間が離れている上に、出っ歯だ」
と答えるが、視線は画面から離さない。
「目だ。目元は違うが、この黒い瞳は『ノア』のものだ」
「では、『ノア』はやはり変装していると? しかし、変装なら、ある程度までは見破ることができます」
「そういうレベルじゃないな。顔の輪郭も違うから、骨格自体を変えているらしい。しかし、そんなことは可能なのか?」
「アンドロイドと同じ仕組みを人間に適用することは可能だと思います。当然、顔面を全て作り変えることになりますが」
「作り物だと分からないようにだぞ」
「鬼神さんは、私達の顔だけを見て、すぐにアンドロイドだと気づきますか?」
鬼神は、マリーのほうへ顔を向けた。しばらくの間、その顔を眺めていたが、やがて
「念のため、こいつらがこの後どこへ向かったのか調べられるか?」
と尋ねた。
竜崎は、椅子に腰掛けた上司と机を挟んで相対していた。その机の上には、『退職届』と大きく書かれた白い封筒が置かれている。
上司は、その封筒を一瞥して
「今の時代に『退職届』とは、古風な男だな」
と竜崎に話しかけた。
「けじめは、きちんとつけておきたいですから」
竜崎の言葉を聞いて、上司はフンと鼻を鳴らした。
「ついさっき、幹部殿がここにもやって来たよ。かなり冠を曲げていたな。なんて言ってたと思う?」
竜崎は何も答えず、下を向いていた。それを眺めていた上司は、一言
「犯人を挙げろ、だ」
と言った。
竜崎は、上司の顔を見た。
「お前が辞めて犯人が捕まるわけでもない。こんなものは受理できん」
上司はそう言って、机の上の封筒をポンと叩く。
「しかし、今回の失態は私に責任が・・・」
「お前は、規定に従っただけだ。落ち度はないさ」
「もう少し慎重になっていれば、防げたかも知れないのです」
「我々は、予言者じゃないんだ。常に最善の結果が得られればハッピーだが、残念ながらそれは不可能だ。いいか、死んだあのカップルがスラム街に入らなければ、2人は死なずに済んだ。スラム街をもっと早く捜索していれば、多くの人間が救われただろう。こんな地下都市なんてなければ病気に感染する人間は現れなかった」
竜崎は、反論できず黙っていた。
「うじうじと後悔している暇があったら、手掛かりを見つけてこい。お前ができる唯一の償いは、ホシを挙げることだ」
「・・・分かりました」
竜崎が一礼すると、上司はまた鼻を鳴らし
「それにしても汚い字だ。今度書く時は、もう少しマシな字になってからだ」
と言って微笑んだ。
休憩室には、竜崎以外に誰もいない。
ただ一人、コーヒーの入った紙コップを手に、ベンチに腰掛けていた。
竜崎は、刑事を辞める覚悟をしていた。一人の人間の人生を、自分のミスで狂わせてしまったことが、どうしても許せないのだ。
しかし、それはできなかった。少なくとも、犯人を捕まえるまでは。
上司の説教で、少し頭が冷えたらしい。たしかに、自分が辞めたところで状況が改善されるわけでもないし、そもそも辞めてからどうするのか、何も考えがなかった。
今できるのは、『ノア』を逮捕すること、それだけだ。
そして、竜崎は、その先のことを考えていた。
『ノア』を捕らえることができたら、もう一度、彩に謝罪するつもりだった。それで許される話ではないが、謝罪しなければ自分の気が済まなかった。
そして、その後どうするか。
竜崎は、手に持ったコーヒーを一口飲んで、大きなため息をついた。
「ハム、紫龍麻子はまだ戻らないのか?」
ジャフェスが、茶色の帽子をかぶった男に話しかけた。
あたりは暗闇が支配している。2人の近くにある大きな建物の周囲だけ、申し訳程度に明かりが灯っていた。
「ああ。それがどうかしたか?」
「もし戻っていたのなら、どんな娘なのか教えてほしくてな」
ハムという名のその男は、訝しげな顔で
「そんなことを聞いてどうする?」
と尋ねた。
「大した理由などない。興味があるだけだ」
ジャフェスは、大きな口を横に広げ、歯を見せて笑った。
その顔を見たハムは、大きなため息をついた。
「お前、また手を出すつもりか?」
「おいおい、俺はもう去勢したんだ。手を出したくても、何もできないさ」
「ふん、今度やったら、手足を切り取るか。そうすれば、本当に何もできなくなるぜ」
「実際に会うわけではないんだ。話を聞くだけなら問題はないだろ?」
「色情の芽は生やすな。お前が拷問を受けた時の、長老のお言葉だ。お前に教えることなどできん」
ハムの言葉に、ジャフェスは舌打ちした。
「ならば、直に見るまでだ」
「監視カメラに写れば、ここに隠れていた意味がなくなるだろ」
「大丈夫だ。いい手を思いついたんだよ」
ジャフェスは、もう一度笑った。しかし、その笑顔には残忍な本性がにじみ出ているようだった。
若く見られるのはいいことだが、彼女の場合、幼く見えると言ったほうがいいだろう。
そのせいか、両親も彩のことを子供扱いするところがある。
特に父親は、彩に近づく男性を見つけると、いつもしつこく彩に尋ねてきた。
しかし、母親のほうは、そろそろ身を固めてほしいと思っていたようだが。
「お父さん、そんなこと聞くもんじゃないですよ」
そう父をたしなめる母親に
「変な誤解しないで。少し前に、偶然お会いしたことがあっただけよ。今日は心配してわざわざお見舞いに来て下さったの」
と彩が慌てて説明する。
「優しい人じゃないか。ああいう人が、お前の旦那さんになってくれればねえ」
目を伏せて、母は言った。
「やめてよ、お母さん」
顔を赤くして、彩が言葉を返す。
「分かってるよ。でも、お前の花嫁姿が見たかった・・・」
涙ぐむ母親を見て、彩はそれ以上は何も言わなかった。
皆が沈黙している中、ノックの音がした。
「失礼します」
彩の応答に反応して、白衣を着た女性が入ってきた。彩に検査結果を告げに来たうちの一人だ。
「新しい病室が準備できましたので、これからご案内します」
女性の後ろから、電動の車椅子がついて来た。これに乗って移動するということなのだろう。
「隔離室に移動するのですか?」
彩が問いかける。
「安心して下さい。あなたを束縛するようなことはいたしません。しかし、少し不自由を感じるかも知れません。それについては、どうかご了承下さいませ」
女性は事務的に回答した。
「私、場所を知りたいから、いっしょについて行ってもいいですか?」
麻子が女性に尋ねた。
「それは構いませんよ。では、ご案内しますから、こちらの車椅子にお乗り下さい」
女性は、少し笑みを浮かべながら、彩にやさしく話しかけた。
結局、両親と麻子、それにドナもいっしょに付いていくことになった。
昨日から彩の病室にいたアンドロイドの名前はモニカ。これから、彩の身のまわりの世話を担当するということで、彼女も同伴している。
そして白衣を着た女性の名前はフィオナ。彼女もアンドロイドで、彩の主治医となることを告げた。
「これから、いろいろと大変だと思うけど、私たちができるだけサポートしますね」
出発の前に、モニカが笑顔で彩に話しかけてくれたおかげで、彩の緊張も少しほぐれたようだ。
感染者用の病室は、病院の上層階にある。万が一、インフェクターと化した感染者が病室から飛び出したとき、外へ逃げる可能性を小さくするためであろう。
エレベーターから出て、最初に目に飛び込んだのは、入り口に付けられた金属製の扉だ。この先に入れば、容易に抜け出せないのは明らかだった。
「まるで牢獄ね」
彩がポツリと言った。
「そう見えるかも知れません。外出も基本的にはできませんから」
フィオナは、彩のほうを見て説明した。
扉の前には、守衛らしき人が立っている。
「今日から、この病棟へ移ることになった葉月彩さんです」
フィオナが守衛に彩を紹介した。
「話は伺っています。はじめまして葉月さん。私はここで守衛をしているアンドロイドのアーサーです。どうかお見知り置き下さい」
ハンサムという言葉がピッタリ合うような顔にさわやかな笑みを浮かべ、守衛のアーサーはあいさつした。
「きれいなお花ですね」
彩のひざに乗せられた花束に目を移し、アーサーは笑顔を絶やさず話を続ける。
「ありがとう。お見舞いにもらったの」
「長期保存できるように加工するといいですよ。専用の樹脂で固めれば、100年は保存できます」
「そんなに長生きできるわけでもないし・・・」
ほとんど聞こえないほどの小さな声で、彩は応える。それが自分に言い聞かせているように思えて、麻子は彩の顔に目を向けた。彩は前を、扉の方をじっと見つめていた。
扉が自動的に開き、中へ入る。廊下は程よい光で照らされ、影はどこにも見当たらない。
淡いグレーの床は柔らかく、まるで泥の上を歩いているような感覚だ。白い壁にも、同じ素材を使っているように見える。おそらく、インフェクターが自傷行為をしても、できるだけダメージを少なくするための配慮であろう。
両側の壁に並んだ扉には窓がなく、中に人がいるのかどうかさえ分からない。いったい、この病棟に何人の感染者がいるのか、彩は気になった。
「ここには、他にも誰かいるのですか?」
彩がモニカに尋ねる。
「現在、あなたの他に18名います」
意外にも数が多く、彩は少し驚いた。
「少し前に、スラム街で大量の感染者が見つかって、一気に15人増えたんです。この人たちは、警察の管理化にあるので会うことはできませんが、他の3名の方とは、お話することもできますよ」
「どんな方たちなのですか?」
「男女が一人ずつ、それから小さな男の子が一人います」
「子供が・・・」
彩は、思わず麻子のほうを見ていた。麻子と目が合い、慌てて視線をそらす。
「ここが、あなたの病室ですよ」
分厚い扉を開けると、中は普通の病室よりもかなり広く、しかし殺風景だった。家具などはどこにも見当たらない。
「何もないのね・・・」
彩の母親が、率直な感想を述べた。
「クローゼットや収納棚は壁の中に埋め込まれています。テーブルや椅子も、このように・・・」
モニカが壁にある手のマークに軽く触れると、少し離れた場所で、床からテーブルと椅子が現れた。
テーブルには角がなく、全体的に丸みを帯びている。そして椅子は円筒形で、背もたれはなかった。
「怪我をしないよう、徹底されているのね」
彩がテーブルを見て言った。
「この、手のマークのところに触れると、家具が現れたり、棚が開いたりします。このマークに手をきちんと合わせてくださいね。そうしないと作動しませんから」
彩が試しにマークに触れてみると、テーブルと椅子が床に収納された。
ベッドにモニタ、オーディオ機器など、設備は充実していた。窓からは明るい日差しが降り注ぐ。しかし、その窓はかなり高い位置に設置されていた。
「景色が見られないのは残念ね」
彩の言葉を聞いて
「心配ありませんわ。景色を眺められる場所もあるのです。今度はその場所をご案内しましょう」
と、モニカが明るい声で応えた。
「今回は、何をチェックすればいいんだ?」
両手を頭の後ろで組んだ状態で椅子に座っていた鬼神は、マリーへ顔を向けて尋ねた。
「私たちがスラム街へ到着する前に、『ノア』とジャフェスが向かったと思われるD-6エリアの商業スペースの解析結果です。実は以前、顔を隠して移動している者がいないかチェックしていましたが、そのような人物は見つかりませんでした。しかし・・・」
マリーが言いよどんだのを見て、鬼神は
「しかし、どうした?」
と先を促した。
「商業スペースですから呼び込みも多くて、着ぐるみ姿については対象外にしていたのです。もしかしたら、その中に紛れている可能性はないかという話になりまして」
「そいつらの中で、仕事もせずに移動している者がいれば、怪しいんじゃないか?」
「いいえ、そのような者はいません。全員が、店が閉まるまでの間、呼び込みをしていました」
鬼神は、上を向いたまま、しばらくの間じっとしていたが、やがて
「一応、調べてみるか。しかし、着ぐるみを付けていたら、全く区別は付かないけどな」
と言いながら、モニタのほうへと顔を向けた。
様々な着ぐるみが画面に登場する。子供向け番組に登場するヒーローや、魔法使いのヒロイン、ピンクのうさぎに派手な電飾のロボットなど、夜にもかかわらず出歩いている子供に囲まれていたり、通りの人々に完全に無視されて素通りされていたり、扱いも様々だ。
当然、中に誰が入っているのか分かるはずもない。それでも、鬼神は真剣に画面に見入っていた。
そして、ある写真が映し出されたときである。
「ストップ!」
鬼神が叫んだ。
「もしかして、見つかったのですか?」
マリーが写真を見ながら尋ねた。
その写真には、お菓子メーカーのキャラクターの女の子が写っていた。おかっぱ頭の大きな顔に、手足の短い二頭身の姿で、子供たちに囲まれて何やらポーズをとっている。
その近くで、年配の男性が笑顔で子供たちにお菓子を配っていた。
「この男、背格好は『ノア』によく似ているな」
鬼神は、画面を凝視しながらつぶやいた。
「顔はどうなのですか?」
マリーの問いには
「全く違う。この男は顔に特徴があるな。エラが張って、目の間が離れている上に、出っ歯だ」
と答えるが、視線は画面から離さない。
「目だ。目元は違うが、この黒い瞳は『ノア』のものだ」
「では、『ノア』はやはり変装していると? しかし、変装なら、ある程度までは見破ることができます」
「そういうレベルじゃないな。顔の輪郭も違うから、骨格自体を変えているらしい。しかし、そんなことは可能なのか?」
「アンドロイドと同じ仕組みを人間に適用することは可能だと思います。当然、顔面を全て作り変えることになりますが」
「作り物だと分からないようにだぞ」
「鬼神さんは、私達の顔だけを見て、すぐにアンドロイドだと気づきますか?」
鬼神は、マリーのほうへ顔を向けた。しばらくの間、その顔を眺めていたが、やがて
「念のため、こいつらがこの後どこへ向かったのか調べられるか?」
と尋ねた。
竜崎は、椅子に腰掛けた上司と机を挟んで相対していた。その机の上には、『退職届』と大きく書かれた白い封筒が置かれている。
上司は、その封筒を一瞥して
「今の時代に『退職届』とは、古風な男だな」
と竜崎に話しかけた。
「けじめは、きちんとつけておきたいですから」
竜崎の言葉を聞いて、上司はフンと鼻を鳴らした。
「ついさっき、幹部殿がここにもやって来たよ。かなり冠を曲げていたな。なんて言ってたと思う?」
竜崎は何も答えず、下を向いていた。それを眺めていた上司は、一言
「犯人を挙げろ、だ」
と言った。
竜崎は、上司の顔を見た。
「お前が辞めて犯人が捕まるわけでもない。こんなものは受理できん」
上司はそう言って、机の上の封筒をポンと叩く。
「しかし、今回の失態は私に責任が・・・」
「お前は、規定に従っただけだ。落ち度はないさ」
「もう少し慎重になっていれば、防げたかも知れないのです」
「我々は、予言者じゃないんだ。常に最善の結果が得られればハッピーだが、残念ながらそれは不可能だ。いいか、死んだあのカップルがスラム街に入らなければ、2人は死なずに済んだ。スラム街をもっと早く捜索していれば、多くの人間が救われただろう。こんな地下都市なんてなければ病気に感染する人間は現れなかった」
竜崎は、反論できず黙っていた。
「うじうじと後悔している暇があったら、手掛かりを見つけてこい。お前ができる唯一の償いは、ホシを挙げることだ」
「・・・分かりました」
竜崎が一礼すると、上司はまた鼻を鳴らし
「それにしても汚い字だ。今度書く時は、もう少しマシな字になってからだ」
と言って微笑んだ。
休憩室には、竜崎以外に誰もいない。
ただ一人、コーヒーの入った紙コップを手に、ベンチに腰掛けていた。
竜崎は、刑事を辞める覚悟をしていた。一人の人間の人生を、自分のミスで狂わせてしまったことが、どうしても許せないのだ。
しかし、それはできなかった。少なくとも、犯人を捕まえるまでは。
上司の説教で、少し頭が冷えたらしい。たしかに、自分が辞めたところで状況が改善されるわけでもないし、そもそも辞めてからどうするのか、何も考えがなかった。
今できるのは、『ノア』を逮捕すること、それだけだ。
そして、竜崎は、その先のことを考えていた。
『ノア』を捕らえることができたら、もう一度、彩に謝罪するつもりだった。それで許される話ではないが、謝罪しなければ自分の気が済まなかった。
そして、その後どうするか。
竜崎は、手に持ったコーヒーを一口飲んで、大きなため息をついた。
「ハム、紫龍麻子はまだ戻らないのか?」
ジャフェスが、茶色の帽子をかぶった男に話しかけた。
あたりは暗闇が支配している。2人の近くにある大きな建物の周囲だけ、申し訳程度に明かりが灯っていた。
「ああ。それがどうかしたか?」
「もし戻っていたのなら、どんな娘なのか教えてほしくてな」
ハムという名のその男は、訝しげな顔で
「そんなことを聞いてどうする?」
と尋ねた。
「大した理由などない。興味があるだけだ」
ジャフェスは、大きな口を横に広げ、歯を見せて笑った。
その顔を見たハムは、大きなため息をついた。
「お前、また手を出すつもりか?」
「おいおい、俺はもう去勢したんだ。手を出したくても、何もできないさ」
「ふん、今度やったら、手足を切り取るか。そうすれば、本当に何もできなくなるぜ」
「実際に会うわけではないんだ。話を聞くだけなら問題はないだろ?」
「色情の芽は生やすな。お前が拷問を受けた時の、長老のお言葉だ。お前に教えることなどできん」
ハムの言葉に、ジャフェスは舌打ちした。
「ならば、直に見るまでだ」
「監視カメラに写れば、ここに隠れていた意味がなくなるだろ」
「大丈夫だ。いい手を思いついたんだよ」
ジャフェスは、もう一度笑った。しかし、その笑顔には残忍な本性がにじみ出ているようだった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

願いを叶えるだけの僕と人形
十四年生
SF
人がいいだけのお人よしの僕が、どういうわけか神様に言われて、人形を背中に背負いながら、滅びたという世界で、自分以外の願いを叶えて歩くことになったそんなお話。

電脳理想郷からの脱出
さわな
SF
かつてメタバースと呼ばれた仮想空間がリアルワールドとなった西暦2923年の地球。人類はエルクラウドと呼ばれる電脳空間にすべての社会活動を移していた。肉体が存在する現実世界と精神が存在する電脳空間のふたつの世界に疑問を持っていたアイコは、秘密を知る人物、ヒデオに出会う。
理想郷と呼ばれた電脳空間からの脱出劇が始まる……!
この作品は以下のサイトにも掲載しています。
*小説家になろう
*note(別名義)
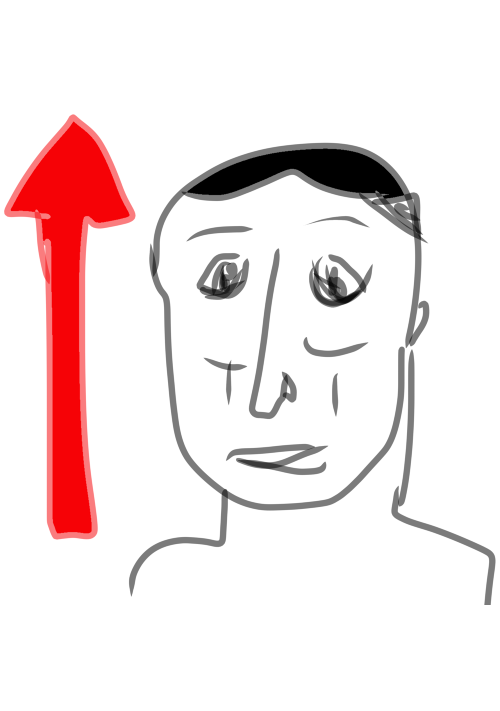
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

関西訛りな人工生命体の少女がお母さんを探して旅するお話。
虎柄トラ
SF
あるところに誰もがうらやむ才能を持った科学者がいた。
科学者は天賦の才を得た代償なのか、天涯孤独の身で愛する家族も頼れる友人もいなかった。
愛情に飢えた科学者は存在しないのであれば、創造すればいいじゃないかという発想に至る。
そして試行錯誤の末、科学者はありとあらゆる癖を詰め込んだ最高傑作を完成させた。
科学者は人工生命体にリアムと名付け、それはもうドン引きするぐらい溺愛した。
そして月日は経ち、可憐な少女に成長したリアムは二度目の誕生日を迎えようとしていた。
誕生日プレゼントを手に入れるため科学者は、リアムに留守番をお願いすると家を出て行った。
それからいくつも季節が通り過ぎたが、科学者が家に帰ってくることはなかった。
科学者が帰宅しないのは迷子になっているからだと、推察をしたリアムはある行動を起こした。
「お母さん待っててな、リアムがいま迎えに行くから!」
一度も外に出たことがない関西訛りな箱入り娘による壮大な母親探しの旅がいまはじまる。

惑星保護区
ラムダムランプ
SF
この物語について
旧人類と別宇宙から来た種族との出来事にまつわる話です。
概要
かつて地球に住んでいた旧人類と別宇宙から来た種族がトラブルを引き起こし、その事が発端となり、地球が宇宙の中で【保護区】(地球で言う自然保護区)に制定され
制定後は、他の星の種族は勿論、あらゆる別宇宙の種族は地球や現人類に対し、安易に接触、交流、知能や技術供与する事を固く禁じられた。
現人類に対して、未だ地球以外の種族が接触して来ないのは、この為である。
初めて書きますので読みにくいと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

鋼殻牙龍ドラグリヲ
南蛮蜥蜴
ファンタジー
歪なる怪物「害獣」の侵攻によって緩やかに滅びゆく世界にて、「アーマメントビースト」と呼ばれる兵器を操り、相棒のアンドロイド「カルマ」と共に戦いに明け暮れる主人公「真継雪兎」
ある日、彼はとある任務中に害獣に寄生され、身体を根本から造り替えられてしまう。 乗っ取られる危険を意識しつつも生きることを選んだ雪兎だったが、それが苦難の道のりの始まりだった。
次々と出現する凶悪な害獣達相手に、無双の機械龍「ドラグリヲ」が咆哮と共に牙を剥く。
延々と繰り返される殺戮と喪失の果てに、勇敢で臆病な青年を待ち受けるのは絶対的な破滅か、それともささやかな希望か。
※小説になろう、カクヨム、ノベプラでも掲載中です。
※挿絵は雨川真優(アメカワマユ)様@zgmf_x11dより頂きました。利用許可済です。

地球人類永久不滅計画 ~機械仕掛けの『NE-1097』~
クライン・トレイン
SF
地球人類の永久不滅計画が実施されていた
それは長きにわたる資本主義の終焉に伴う技術進化の到来であった
そのオカルトティックと言われていた現象を現実のものとしたのは
博士号を持った博士たちであった
そしてそんな中の一人の博士は
技術的特異点など未来観測について肯定的であり楽観主義者であった
そんな中
人々の中で技術的特異点についての討論が成されていた
ドローン監視社会となった世界で人間の為の変革を成される
正にそのタイミングで
皮肉な研究成果を生み出す事実を博士も人類も今だ知らなかった

トライアルズアンドエラーズ
中谷干
SF
「シンギュラリティ」という言葉が陳腐になるほどにはAIが進化した、遠からぬ未来。
特別な頭脳を持つ少女ナオは、アンドロイド破壊事件の調査をきっかけに、様々な人の願いや試行に巻き込まれていく。
未来社会で起こる多様な事件に、彼女はどう対峙し、何に挑み、どこへ向かうのか――
※少々残酷なシーンがありますので苦手な方はご注意ください。
※この小説は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリス、エブリスタ、novelup、novel days、nola novelで同時公開されています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















