15 / 16
『手を出したら殺しますよ』
6
しおりを挟む
綺麗に整理整頓された部屋。無駄なものが一切無く、緻密に計算された空間演出。
相変わらず結城さんの部屋はモデルルームみたいだった。とても素敵なんだけど、どこか空気がひんやりしてる。それに、ちょっとさみしい感じも。
自分の部屋と何が違うのか……。考えてみて気付いたのは、気配だ。
そう。この部屋、人の気配が極端にない。人数がどうという事ではなく、物のひとつひとつに温度を感じないというか……つまり、生活感が圧倒的に感じられない。
だから、彼の部屋はモデルルームの様だったんだ。展示された間取りが、そのままここへ移ってきたみたいに。
「我が家はそんなに不思議な場所ですか?」
あからさまにキョロキョロしないように……と気を付けていたつもりだけど、結城さんにはバレてしまった。
「えっ」
肩で驚きの返事をした私の前に紅茶を置き、自分はコーヒーを一口口にする。結城さんは目で私に「どうぞ」と紅茶をすすめた。
「仕事が忙しくて自宅にいる時間が少ないですからね。あまり生活感が無くてさびしいものでしょう?」
花音さんの部屋とは違って、と結城さんは笑った。
「貴女の部屋は、とても温かみのある可愛らしいお部屋ですから。同じ一人暮らしでも全く違うモノですよね、本当」
「私の部屋は散らかってるし、細々したものが多いから……。それだけですよ。片付け苦手なんです」
「そうですか? そうは見えませんでしたけど。雑貨選びのセンスも飾り方も、とても良いじゃないですか。あの店にも花音さんの様なセンスが加わるとまた違うんでしょうねぇ」
自分の好きなものを褒められるとやっぱり嬉しい。部屋作りは、誰にも言ってないけど結構こだわっているので尚更だ。こんなに洗練された部屋に住んでいる人に「センスがいい」と言われるのは、悪い気がしなかった。
「あそこは、あの感じだからいいんです。まっさらで、でも見えない何かが満ちてる……。そうだな、優しい感じ?」
「優しい、ですか」
コーヒーの香りが揺れた。私の手元からは紅茶の香り。
「それは……セツナとナユタが聞いたらきっと喜ぶでしょうね」
結城さんは目を細めて静かに笑うと、カップを傾ける。
その仕草がちょっと色っぽくて、私は小さな羞恥を誤魔化す様に視線と意識を紅茶へと落とした。
今は深夜だと忘れてしまいそうだった。昼間、あのお店で彼と過ごしている様な錯覚に陥る。
今日ずっと、こういう時間を送りたかった自分がいたのだと改めて認識したみたいで、とても恥ずかしかった。
「それで。聞きたかったというお話についてですが……」
結城さんの声にハッとなった。
そうだ。私はそれが聞きたくて、彼の帰りを待ち、そしてここに来たのだ。ウットリとお茶の楽しみに浸ってる場合ではなかった。
「はい! あの後……あの子」
「残念ですが、花音さんの期待していた結果にはならなかったんです」
「……え?」
「彼の探していた母親は、見つける事が出来なかったので」
「見つけ……え?」
アッサリと告げられた結果。
呆然と結城さんを見る。私から目を逸らす事無く、結城さんは淡々と説明を続けた。
「ですから、親子は再会を果たしていません。……そうなると当然、彼をいつまでもあの店に足止めさせて置く……という訳にもいきませんでした。然るべき場へ彼を案内するしか他なかったんです」
「それは……警察、とか……?」
対応しきれなかった迷子の行き先なんて、決まってる。あえて聞く事でもない。
それでも出てしまった言葉に、結城さんは少し困った様子を見せた。
「そんな……。だって」
「出来る事はいつだって限られています。残念でしたが……」
「でも! じゃあ、零さんは……? あの人、あの子のお母さんの事を知ってるって……!」
あんな風に店を出ていったけど、零さんは最終的には連れてきてくれるかと思ってた。
結城さんが母親を見つけ出すのが早いか、それとも零さんが連れてくる方が先か。どっちかだろうと思ってたのに……!
「零ですか……」
コトン、とカップをテーブルに置く音。心なしか音が乱暴だ。
ふと顔を上げ私は、しまった、と思った。
なんでそんな事を思ったか分からない。分からないけど、そう感じ身構える。
「たった一度挨拶を交わしただけなのに、随分と親しげに名を呼んで、あまつさえ彼の事を信じたりもするんですね」
結城さんが笑う。
「さすが花音さん。人懐っこさは、性分ですか?……これはまた随分厄介な……」
嘘、目が笑ってない。
それに最後の一言のトーンが地を這うような低さって……。なんなんだ、怖すぎる!
「結城、さん……?」
「私は心配ですよ、貴女が」
ふぅと短く息を吐いた結城さんは、反射的にひきつる私の顔を見て口元を和らげる。言葉がいつもの穏やかな調子に戻った。
「迷子には過度の感情移入。初対面の者でも信じようとする純至。……まあ、それが花音さんが故なんですけど」
席を立ち、低い声。
「時々不安になります。その“過ぎるもの”は影になりやすい。貴女にとっては特に……」
そう言う結城さんの表情は、複雑。困ってる様にも見えるし、戸惑ってる様にも見える。どことなく怒ってるみたいにも。
……どうして……?
「影……ですか?」
「えぇ。そろそろ自覚してくださらないと」
「はぁ……」
(自覚って言われてもな……)
具体的に何をどうしろと?
首を傾げていると、私の後ろへと歩いていく結城さん。
椅子から振り向く様に目で追ったら、彼はベランダへ続く窓を開けに行っていた。
――無言の間。
ほんの少し開けた隙間から、外の涼しい風が足元に滑り込んできて。
向き直り、私は今のこの不自然な間を理由付けたくてまだ温かな紅茶を口に含む。
でも理由なんかちっとも思い浮かばない。何故だか焦る。何か言わなきゃ……!
「涼しいですね、今日は。もうすっかり秋めいちゃって……」
…………。
出た言葉の何と不自然な事か。今更、井戸端会議開始の挨拶みたいな事を言ってどうする!
呆れてるかもしれない。
背中越しの静かな相手を思いながら、私は残りの紅茶を一気に飲み干した。
「花音さん」
私がカップをソーサーに置いたのと、結城さんの手が私の肩に置かれたのは、ほぼ同時だった。
びっくりして飛ぶ上がるかと思った。結城さんが近づいたり触れたりするのは、いつも突然なんだもの。
「貴女の人の良さを否定するつもりはありません。ですが、零は……」
置かれていただけだった手が、肩を掴む様に動いた。
「あの零という男だけは信じないでください」
決してです、低い声が斜め上で聞こえる。手には力が籠められた。
「っ……。なんで」
痛い。
肩の皮膚上にチリッと痛熱さ。服の上からでも、爪を立てられたのだと分かる。
私には何故そこまでするのか、されるのか理解できない。なんで? と、斜め上に抗議を申し立てようと思って。……でも無理で。
「花音さんはいつもこうです。毎回毎回、注意をしてもすぐに忘れて……」
「……っ」
動かしかけた頭を縛り付けてくる――低く妖艶な声音。
私の動きは、結城さんを見上げる寸前で封じられた。この至近距離は危険な距離。それだけは無意に体が覚えてた。ピタリと驚く程に止まる。
「こんな遅い時間に、誘われるがまま男の部屋に上がる。駄目じゃないですか」
「だ、だって……結城さんが」
「私だから応じた? その言葉、嬉しく受け取りたいものですが、残念ながら今の貴女の信用は低いんですよ。花音さん」
すぐ耳許で声がする。結城さんの甘く低いテノール。口調までも低い。だけどそこには全く甘さなんて無く……厳しさだけがあった。
「どうして貴女はそうなんですか。いつもいつも、馬鹿みたいに油断して隙を作って。忠告なんてまるで聞かない」
「私、あの……そんなつもりは」
「今日だって――」
言いかけた結城さんはそこでストップ。背後で、空気がピリッと固まった気がした。
――また無言の間。数秒の隙間に私は自分の言葉を滑り込ませる。
「結城さん? どうしたん」
ですか?
という自分の声は、ガタン! と椅子が立てた音で消された。
その音はまさに私が立てたものだった。膝裏が椅子を勢いよく弾いて。
背後に引っ張られる右腕に、体が斜めについて行く。
「わっ!?」
よろめく体はそのまま結城さんによって器用に方向転換され、回れ右。案の定、一瞬で私は彼の胸元へ飛び込む形となった。
抱きすくめられる事に慣れた、なんて決してない。
自分の体がすっぽり長身に包まれて、体格差や耐性の無い他人の体温、香りを感じると頭の奥がクラクラしてくる。拒否反応とは明らかに違う反応が、自分の内で沸き起こる。そういうのにまだ戸惑いを感じるのだ。
「駄目ですよ、花音さん」
結城さんは囁いた。私を抱きしめたまま、内緒話するみたいに声を潜める。長身を少し屈ませ身体を密着させて。猫がすり寄る様に頬を私の頭へくっつけた。
――花音。
その時、そう呼ばれた気がしたのは気のせいだろうか?
早鐘を打つ心臓の音に邪魔されて、よく分からない……。
――花音。何処にいるの?
「…………え?」
結城さんの唇がこめかみに触れ、吐息がかかる。そのあたたかさにビクッと大袈裟なほど反応してしまう私。心も同時に震えた。
(……なに? これ……)
見知らぬ感覚に少し恐怖を覚える。
だって結城さんは何も声を発しなかった。届いたのは吐息だけ。だとしたら、今微かに聞こえたのは誰の声だというんだろう。
「花音さん」
――花音。
「花音さん」
――花音、
「駄目だといったばかりです」
――何処にいる?
重なる声がまるで二重奏の様に。
響いて、届いて、
「……?」
訳が分からなくて。
余り身動き取れない中で、私は声のした方を見た。
「貴女って人は本当に……。なんて聞き分けのない」
見上げた結城さんの瞳はいつも以上に色が濃い。勿論、呆れと嘲りに近い色で、だ。
それをたたえたまま綺麗な顔を僅か数センチまで近づけ、結城さんは、
「ここまで手を煩わせますか……」
唇の端を引き上げて不敵に笑った。
「ならば私も、少しばかり意地悪を企みましょう」
意図が読めない呟きに、私はそもそもから疑問を感じる。
――これは私に向けられてる言葉?
(目は合ってるのに、見られてない感じが、する……?)
こんな至近距離。ピントもボヤけそうな近さで、自分がそう思うことも不思議だけど。
心臓は相変わらず騒いでいる。それが、一層激しくなる事態になったのは、直後の事だった。
「―――, ―――.」
結城さんの吐息が耳に侵入してきた。何かを囁いたらしいけど、掠れた音は不鮮明すぎて聞き取れない。
耳に触れる吐息は熱い。含んだ空気が多い分、くすぐったさが皮膚を弄ぶ。
感覚の恥ずかしさに身をよじって逃げようとしたけど、結城さんは腰に回した手に力を入れて許してはくれなかった。
「いえ。……少し待って」
「……!」
囁き。髪に彼の指が絡む。大きな手が後頭部を抑える。
がんじがらめの状態で半分パニックの私に、容赦ない仕打ちは続いた。
「……っ!?」
耳朶をやんわりと食む唇は、突然の刺激に驚き跳ねた私を笑う。
そして更に、一ミリも離れることなく、ささやかな刺激をちょっとだけ攻撃的にしてきた。
甘噛みされた耳朶。背中がゾクゾクして、全身の肌が粟立った。
「……んっ」
「―――, ――――.」
結城さんはまた何かを耳に囁いた。今度は反対側の耳へ。そして、同じ様に唇で耳を食み、少し刺激的に歯を立て甘噛み。
「んんっ……!」
「……花音さん?」
両耳にそんな事されたら、全くたまったもんじゃない。危うく膝から崩れ落ちるかと思った。
「大丈夫ですか? でも」
力が半分以上抜けてしまった私を、結城さんは支えながら笑う。
「予想以上に、イイ声で。ここ以外では出さないでくださいよ?」
「……出すわけ……っ! 結城さんが変な事するからじゃないですか!」
「嗚呼……残念」
グッと相手の胸元を押し出す。足に力を入れ、手先に抗議を籠めると、結城さんの体は意外にもすんなりと離れてくれた。
「あともう少し、かな……? と思ったんですけど」
「な、な、何がですかっ!」
結城さんの微笑みが意地悪に見えた。すっごい意味深。
なのに……。
それ以上は何も言わずに、けろっと何事もなかった様に「紅茶、お代わり飲みます?」と聞いてくる結城さん。ひどい。やっぱり意地悪。
私は首を振った。こういう時の追求は諦めるしかないって事くらいは、もういい加減気付いてる。
「いえ。……あの、結城さん」
それよりも、さっき中途半端に終わっている話が気になった。
「ん?」
立ったまま半分に減った紅茶を見、私は結城さんに言った。
「あの子……。お母さんにちゃんと会えます……よね?」
書いて貰った自分の似顔絵を思い出す。
丁寧に描かれた、お母さんの絵も。
笑顔と不安げなあの子の表情を思うと、力になれなかった無力さがどっしりと胸にのし掛かった。
今更……。今更なんだけど。
「…………」
結城さんは、すぐには答えてくれなかった。
「想いは通じますから」
やっと一言だけ言ってくれた結城さん。
「またお店に来てくれると良いですね」
私が仲良く親子連れで現れる事を期待すると、彼はフッと小さく笑った。
「……えぇ……叶うならば」
そういう口調が何となく重い。結城さんも私と同じで、男の子の件では無力感を感じてるのかもしれない、と思う。ずっと外であの子の母親を探し続けていたのは、他ならぬ彼だったのだから。
「…………」
「そういえば話は変わりますが、花音さんのアルバイト先はあの店から近かったですよね」
「あ。そうですね……。割と近いかも」
「今度、仕事っぷりを拝見に伺おうかな」
「え。……大丈夫ですから!?」
何が大丈夫なんだか。
ひきつった頬を向けると結城さんは楽しそうに笑ってる。重い空気を彼が変えてくれたのは分かったので、私もやれやれ……と笑った。
「……って、結城さん!? 本当にそれだけで来ないでくださいよ!?」
「客として行く分には問題無い訳ですよね。行ったらたまたま花音さんの姿を見かけて……。うん。いいですよ?」
「“いいですよ”って何ですか……もう」
結城さんの事だから、教えなくてもバッチリシフトに合わせて来店するに違いない。
(どうか面倒な事にだけはなりませんように……)
好奇心の塊で元々結城さんに興味がある友人と、時々おかしな勘違いをする先輩。
二人の顔を思い出しながら私は「明日からのバイトは違う意味で気が抜けない……」とこっそり思うしかなかった……。
相変わらず結城さんの部屋はモデルルームみたいだった。とても素敵なんだけど、どこか空気がひんやりしてる。それに、ちょっとさみしい感じも。
自分の部屋と何が違うのか……。考えてみて気付いたのは、気配だ。
そう。この部屋、人の気配が極端にない。人数がどうという事ではなく、物のひとつひとつに温度を感じないというか……つまり、生活感が圧倒的に感じられない。
だから、彼の部屋はモデルルームの様だったんだ。展示された間取りが、そのままここへ移ってきたみたいに。
「我が家はそんなに不思議な場所ですか?」
あからさまにキョロキョロしないように……と気を付けていたつもりだけど、結城さんにはバレてしまった。
「えっ」
肩で驚きの返事をした私の前に紅茶を置き、自分はコーヒーを一口口にする。結城さんは目で私に「どうぞ」と紅茶をすすめた。
「仕事が忙しくて自宅にいる時間が少ないですからね。あまり生活感が無くてさびしいものでしょう?」
花音さんの部屋とは違って、と結城さんは笑った。
「貴女の部屋は、とても温かみのある可愛らしいお部屋ですから。同じ一人暮らしでも全く違うモノですよね、本当」
「私の部屋は散らかってるし、細々したものが多いから……。それだけですよ。片付け苦手なんです」
「そうですか? そうは見えませんでしたけど。雑貨選びのセンスも飾り方も、とても良いじゃないですか。あの店にも花音さんの様なセンスが加わるとまた違うんでしょうねぇ」
自分の好きなものを褒められるとやっぱり嬉しい。部屋作りは、誰にも言ってないけど結構こだわっているので尚更だ。こんなに洗練された部屋に住んでいる人に「センスがいい」と言われるのは、悪い気がしなかった。
「あそこは、あの感じだからいいんです。まっさらで、でも見えない何かが満ちてる……。そうだな、優しい感じ?」
「優しい、ですか」
コーヒーの香りが揺れた。私の手元からは紅茶の香り。
「それは……セツナとナユタが聞いたらきっと喜ぶでしょうね」
結城さんは目を細めて静かに笑うと、カップを傾ける。
その仕草がちょっと色っぽくて、私は小さな羞恥を誤魔化す様に視線と意識を紅茶へと落とした。
今は深夜だと忘れてしまいそうだった。昼間、あのお店で彼と過ごしている様な錯覚に陥る。
今日ずっと、こういう時間を送りたかった自分がいたのだと改めて認識したみたいで、とても恥ずかしかった。
「それで。聞きたかったというお話についてですが……」
結城さんの声にハッとなった。
そうだ。私はそれが聞きたくて、彼の帰りを待ち、そしてここに来たのだ。ウットリとお茶の楽しみに浸ってる場合ではなかった。
「はい! あの後……あの子」
「残念ですが、花音さんの期待していた結果にはならなかったんです」
「……え?」
「彼の探していた母親は、見つける事が出来なかったので」
「見つけ……え?」
アッサリと告げられた結果。
呆然と結城さんを見る。私から目を逸らす事無く、結城さんは淡々と説明を続けた。
「ですから、親子は再会を果たしていません。……そうなると当然、彼をいつまでもあの店に足止めさせて置く……という訳にもいきませんでした。然るべき場へ彼を案内するしか他なかったんです」
「それは……警察、とか……?」
対応しきれなかった迷子の行き先なんて、決まってる。あえて聞く事でもない。
それでも出てしまった言葉に、結城さんは少し困った様子を見せた。
「そんな……。だって」
「出来る事はいつだって限られています。残念でしたが……」
「でも! じゃあ、零さんは……? あの人、あの子のお母さんの事を知ってるって……!」
あんな風に店を出ていったけど、零さんは最終的には連れてきてくれるかと思ってた。
結城さんが母親を見つけ出すのが早いか、それとも零さんが連れてくる方が先か。どっちかだろうと思ってたのに……!
「零ですか……」
コトン、とカップをテーブルに置く音。心なしか音が乱暴だ。
ふと顔を上げ私は、しまった、と思った。
なんでそんな事を思ったか分からない。分からないけど、そう感じ身構える。
「たった一度挨拶を交わしただけなのに、随分と親しげに名を呼んで、あまつさえ彼の事を信じたりもするんですね」
結城さんが笑う。
「さすが花音さん。人懐っこさは、性分ですか?……これはまた随分厄介な……」
嘘、目が笑ってない。
それに最後の一言のトーンが地を這うような低さって……。なんなんだ、怖すぎる!
「結城、さん……?」
「私は心配ですよ、貴女が」
ふぅと短く息を吐いた結城さんは、反射的にひきつる私の顔を見て口元を和らげる。言葉がいつもの穏やかな調子に戻った。
「迷子には過度の感情移入。初対面の者でも信じようとする純至。……まあ、それが花音さんが故なんですけど」
席を立ち、低い声。
「時々不安になります。その“過ぎるもの”は影になりやすい。貴女にとっては特に……」
そう言う結城さんの表情は、複雑。困ってる様にも見えるし、戸惑ってる様にも見える。どことなく怒ってるみたいにも。
……どうして……?
「影……ですか?」
「えぇ。そろそろ自覚してくださらないと」
「はぁ……」
(自覚って言われてもな……)
具体的に何をどうしろと?
首を傾げていると、私の後ろへと歩いていく結城さん。
椅子から振り向く様に目で追ったら、彼はベランダへ続く窓を開けに行っていた。
――無言の間。
ほんの少し開けた隙間から、外の涼しい風が足元に滑り込んできて。
向き直り、私は今のこの不自然な間を理由付けたくてまだ温かな紅茶を口に含む。
でも理由なんかちっとも思い浮かばない。何故だか焦る。何か言わなきゃ……!
「涼しいですね、今日は。もうすっかり秋めいちゃって……」
…………。
出た言葉の何と不自然な事か。今更、井戸端会議開始の挨拶みたいな事を言ってどうする!
呆れてるかもしれない。
背中越しの静かな相手を思いながら、私は残りの紅茶を一気に飲み干した。
「花音さん」
私がカップをソーサーに置いたのと、結城さんの手が私の肩に置かれたのは、ほぼ同時だった。
びっくりして飛ぶ上がるかと思った。結城さんが近づいたり触れたりするのは、いつも突然なんだもの。
「貴女の人の良さを否定するつもりはありません。ですが、零は……」
置かれていただけだった手が、肩を掴む様に動いた。
「あの零という男だけは信じないでください」
決してです、低い声が斜め上で聞こえる。手には力が籠められた。
「っ……。なんで」
痛い。
肩の皮膚上にチリッと痛熱さ。服の上からでも、爪を立てられたのだと分かる。
私には何故そこまでするのか、されるのか理解できない。なんで? と、斜め上に抗議を申し立てようと思って。……でも無理で。
「花音さんはいつもこうです。毎回毎回、注意をしてもすぐに忘れて……」
「……っ」
動かしかけた頭を縛り付けてくる――低く妖艶な声音。
私の動きは、結城さんを見上げる寸前で封じられた。この至近距離は危険な距離。それだけは無意に体が覚えてた。ピタリと驚く程に止まる。
「こんな遅い時間に、誘われるがまま男の部屋に上がる。駄目じゃないですか」
「だ、だって……結城さんが」
「私だから応じた? その言葉、嬉しく受け取りたいものですが、残念ながら今の貴女の信用は低いんですよ。花音さん」
すぐ耳許で声がする。結城さんの甘く低いテノール。口調までも低い。だけどそこには全く甘さなんて無く……厳しさだけがあった。
「どうして貴女はそうなんですか。いつもいつも、馬鹿みたいに油断して隙を作って。忠告なんてまるで聞かない」
「私、あの……そんなつもりは」
「今日だって――」
言いかけた結城さんはそこでストップ。背後で、空気がピリッと固まった気がした。
――また無言の間。数秒の隙間に私は自分の言葉を滑り込ませる。
「結城さん? どうしたん」
ですか?
という自分の声は、ガタン! と椅子が立てた音で消された。
その音はまさに私が立てたものだった。膝裏が椅子を勢いよく弾いて。
背後に引っ張られる右腕に、体が斜めについて行く。
「わっ!?」
よろめく体はそのまま結城さんによって器用に方向転換され、回れ右。案の定、一瞬で私は彼の胸元へ飛び込む形となった。
抱きすくめられる事に慣れた、なんて決してない。
自分の体がすっぽり長身に包まれて、体格差や耐性の無い他人の体温、香りを感じると頭の奥がクラクラしてくる。拒否反応とは明らかに違う反応が、自分の内で沸き起こる。そういうのにまだ戸惑いを感じるのだ。
「駄目ですよ、花音さん」
結城さんは囁いた。私を抱きしめたまま、内緒話するみたいに声を潜める。長身を少し屈ませ身体を密着させて。猫がすり寄る様に頬を私の頭へくっつけた。
――花音。
その時、そう呼ばれた気がしたのは気のせいだろうか?
早鐘を打つ心臓の音に邪魔されて、よく分からない……。
――花音。何処にいるの?
「…………え?」
結城さんの唇がこめかみに触れ、吐息がかかる。そのあたたかさにビクッと大袈裟なほど反応してしまう私。心も同時に震えた。
(……なに? これ……)
見知らぬ感覚に少し恐怖を覚える。
だって結城さんは何も声を発しなかった。届いたのは吐息だけ。だとしたら、今微かに聞こえたのは誰の声だというんだろう。
「花音さん」
――花音。
「花音さん」
――花音、
「駄目だといったばかりです」
――何処にいる?
重なる声がまるで二重奏の様に。
響いて、届いて、
「……?」
訳が分からなくて。
余り身動き取れない中で、私は声のした方を見た。
「貴女って人は本当に……。なんて聞き分けのない」
見上げた結城さんの瞳はいつも以上に色が濃い。勿論、呆れと嘲りに近い色で、だ。
それをたたえたまま綺麗な顔を僅か数センチまで近づけ、結城さんは、
「ここまで手を煩わせますか……」
唇の端を引き上げて不敵に笑った。
「ならば私も、少しばかり意地悪を企みましょう」
意図が読めない呟きに、私はそもそもから疑問を感じる。
――これは私に向けられてる言葉?
(目は合ってるのに、見られてない感じが、する……?)
こんな至近距離。ピントもボヤけそうな近さで、自分がそう思うことも不思議だけど。
心臓は相変わらず騒いでいる。それが、一層激しくなる事態になったのは、直後の事だった。
「―――, ―――.」
結城さんの吐息が耳に侵入してきた。何かを囁いたらしいけど、掠れた音は不鮮明すぎて聞き取れない。
耳に触れる吐息は熱い。含んだ空気が多い分、くすぐったさが皮膚を弄ぶ。
感覚の恥ずかしさに身をよじって逃げようとしたけど、結城さんは腰に回した手に力を入れて許してはくれなかった。
「いえ。……少し待って」
「……!」
囁き。髪に彼の指が絡む。大きな手が後頭部を抑える。
がんじがらめの状態で半分パニックの私に、容赦ない仕打ちは続いた。
「……っ!?」
耳朶をやんわりと食む唇は、突然の刺激に驚き跳ねた私を笑う。
そして更に、一ミリも離れることなく、ささやかな刺激をちょっとだけ攻撃的にしてきた。
甘噛みされた耳朶。背中がゾクゾクして、全身の肌が粟立った。
「……んっ」
「―――, ――――.」
結城さんはまた何かを耳に囁いた。今度は反対側の耳へ。そして、同じ様に唇で耳を食み、少し刺激的に歯を立て甘噛み。
「んんっ……!」
「……花音さん?」
両耳にそんな事されたら、全くたまったもんじゃない。危うく膝から崩れ落ちるかと思った。
「大丈夫ですか? でも」
力が半分以上抜けてしまった私を、結城さんは支えながら笑う。
「予想以上に、イイ声で。ここ以外では出さないでくださいよ?」
「……出すわけ……っ! 結城さんが変な事するからじゃないですか!」
「嗚呼……残念」
グッと相手の胸元を押し出す。足に力を入れ、手先に抗議を籠めると、結城さんの体は意外にもすんなりと離れてくれた。
「あともう少し、かな……? と思ったんですけど」
「な、な、何がですかっ!」
結城さんの微笑みが意地悪に見えた。すっごい意味深。
なのに……。
それ以上は何も言わずに、けろっと何事もなかった様に「紅茶、お代わり飲みます?」と聞いてくる結城さん。ひどい。やっぱり意地悪。
私は首を振った。こういう時の追求は諦めるしかないって事くらいは、もういい加減気付いてる。
「いえ。……あの、結城さん」
それよりも、さっき中途半端に終わっている話が気になった。
「ん?」
立ったまま半分に減った紅茶を見、私は結城さんに言った。
「あの子……。お母さんにちゃんと会えます……よね?」
書いて貰った自分の似顔絵を思い出す。
丁寧に描かれた、お母さんの絵も。
笑顔と不安げなあの子の表情を思うと、力になれなかった無力さがどっしりと胸にのし掛かった。
今更……。今更なんだけど。
「…………」
結城さんは、すぐには答えてくれなかった。
「想いは通じますから」
やっと一言だけ言ってくれた結城さん。
「またお店に来てくれると良いですね」
私が仲良く親子連れで現れる事を期待すると、彼はフッと小さく笑った。
「……えぇ……叶うならば」
そういう口調が何となく重い。結城さんも私と同じで、男の子の件では無力感を感じてるのかもしれない、と思う。ずっと外であの子の母親を探し続けていたのは、他ならぬ彼だったのだから。
「…………」
「そういえば話は変わりますが、花音さんのアルバイト先はあの店から近かったですよね」
「あ。そうですね……。割と近いかも」
「今度、仕事っぷりを拝見に伺おうかな」
「え。……大丈夫ですから!?」
何が大丈夫なんだか。
ひきつった頬を向けると結城さんは楽しそうに笑ってる。重い空気を彼が変えてくれたのは分かったので、私もやれやれ……と笑った。
「……って、結城さん!? 本当にそれだけで来ないでくださいよ!?」
「客として行く分には問題無い訳ですよね。行ったらたまたま花音さんの姿を見かけて……。うん。いいですよ?」
「“いいですよ”って何ですか……もう」
結城さんの事だから、教えなくてもバッチリシフトに合わせて来店するに違いない。
(どうか面倒な事にだけはなりませんように……)
好奇心の塊で元々結城さんに興味がある友人と、時々おかしな勘違いをする先輩。
二人の顔を思い出しながら私は「明日からのバイトは違う意味で気が抜けない……」とこっそり思うしかなかった……。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。
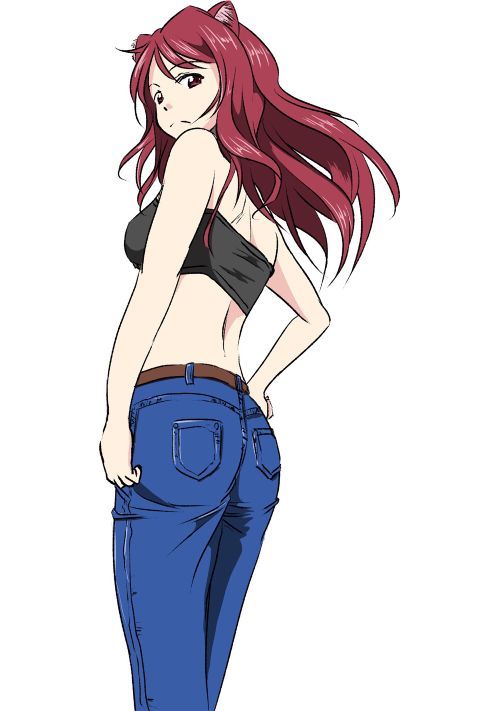
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

イケメン政治家・山下泉はコメントを控えたい
どっぐす
キャラ文芸
「コメントは控えさせていただきます」を言ってみたいがために政治家になった男・山下泉。
記者に追われ満を持してコメントを控えるも、事態は収拾がつかなくなっていく。
◆登場人物
・山下泉 若手イケメン政治家。コメントを控えるために政治家になった。
・佐藤亀男 山下の部活の後輩。無職だし暇でしょ?と山下に言われ第一秘書に任命される。
・女性記者 地元紙の若い記者。先頭に立って山下にコメントを求める。

春風さんからの最後の手紙
平本りこ
キャラ文芸
初夏のある日、僕の人生に「春風さん」が現れた。
とある証券会社の新入社員だった僕は、成果が上がらずに打ちひしがれて、無様にも公園で泣いていた。春風さんはそんな僕を哀れんで、最初のお客様になってくれたのだ。
春風さんは僕を救ってくれた恩人だった。どこか父にも似た彼は、様々なことを教えてくれて、僕の人生は雪解けを迎えたかのようだった。
だけどあの日。いけないことだと分かっていながらも、営業成績のため、春風さんに嘘を吐いてしまった夜。春風さんとの関係は、無邪気なだけのものではなくなってしまう。
風のように突然現れて、一瞬で消えてしまった春風さん。
彼が僕に伝えたかったこととは……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















