お気に入りに追加
1,459
あなたにおすすめの小説

少女は自重を知らない~私、普通ですよね?
チャチャ
ファンタジー
山部 美里 40歳 独身。
趣味は、料理、洗濯、食べ歩き、ラノベを読む事。
ある日、仕事帰りにコンビニ強盗と鉢合わせになり、強盗犯に殺されてしまう。
気づいたら異世界に転生してました!
ラノベ好きな美里は、異世界に来たことを喜び、そして自重を知らない美里はいろいろな人を巻き込みながら楽しく過ごす!
自重知らずの彼女はどこへ行く?

聖女なんかじゃありません!~異世界で介護始めたらなぜか伯爵様に愛でられてます~
トモモト ヨシユキ
ファンタジー
川で溺れていた猫を助けようとして飛び込屋敷に連れていかれる。それから私は、魔物と戦い手足を失った寝たきりの伯爵様の世話人になることに。気難しい伯爵様に手を焼きつつもQOLを上げるために努力する私。
そんな私に伯爵様の主治医がプロポーズしてきたりと、突然のモテ期が到来?
エブリスタ、小説家になろうにも掲載しています。

異世界転生雑学無双譚 〜転生したのにスキルとか貰えなかったのですが〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
エドガーはマルディア王国王都の五爵家の三男坊。幼い頃から神童天才と評されていたが七歳で前世の知識に目覚め、図書館に引き篭もる事に。
そして時は流れて十二歳になったエドガー。祝福の儀にてスキルを得られなかったエドガーは流刑者の村へ追放となるのだった。
【カクヨムにも投稿してます】

【幸せスキル】は蜜の味 ハイハイしてたらレベルアップ
カムイイムカ(神威異夢華)
ファンタジー
僕の名前はアーリー
不慮な事故で死んでしまった僕は転生することになりました
今度は幸せになってほしいという事でチートな能力を神様から授った
まさかの転生という事でチートを駆使して暮らしていきたいと思います
ーーーー
間違い召喚3巻発売記念として投稿いたします
アーリーは間違い召喚と同じ時期に生まれた作品です
読んでいただけると嬉しいです
23話で一時終了となります

異世界転生したので森の中で静かに暮らしたい
ボナペティ鈴木
ファンタジー
異世界に転生することになったが勇者や賢者、チート能力なんて必要ない。
強靭な肉体さえあれば生きていくことができるはず。
ただただ森の中で静かに暮らしていきたい。
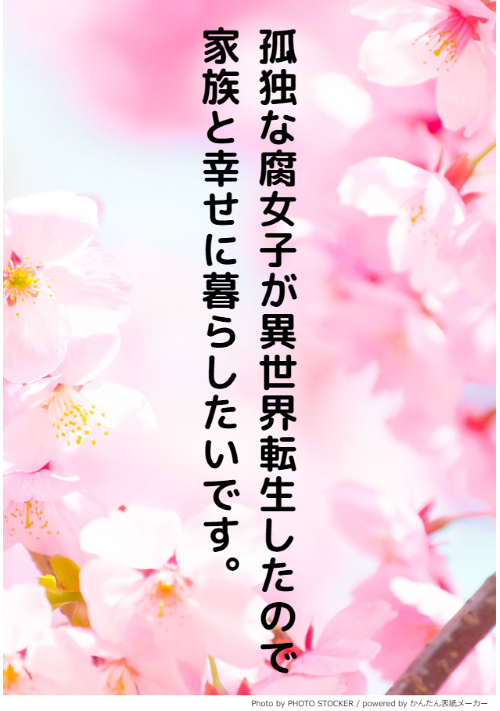
孤独な腐女子が異世界転生したので家族と幸せに暮らしたいです。
水都(みなと)
ファンタジー
★完結しました!
死んだら私も異世界転生できるかな。
転生してもやっぱり腐女子でいたい。
それからできれば今度は、家族に囲まれて暮らしてみたい……
天涯孤独で腐女子の桜野結理(20)は、元勇者の父親に溺愛されるアリシア(6)に異世界転生!
最期の願いが叶ったのか、転生してもやっぱり腐女子。
父の同僚サディアス×父アルバートで勝手に妄想していたら、実は本当に2人は両想いで…!?
※BL要素ありますが、全年齢対象です。

小さいぼくは最強魔術師一族!目指せ!もふもふスローライフ!
ひより のどか
ファンタジー
ねぇたまと、妹と、もふもふな家族と幸せに暮らしていたフィリー。そんな日常が崩れ去った。
一見、まだ小さな子どもたち。実は国が支配したがる程の大きな力を持っていて?
主人公フィリーは、実は違う世界で生きた記憶を持っていて?前世の記憶を活かして魔法の世界で代活躍?
「ねぇたまたちは、ぼくがまもりゅのら!」
『わふっ』
もふもふな家族も一緒にたくましく楽しく生きてくぞ!

異世界道中ゆめうつつ! 転生したら虚弱令嬢でした。チート能力なしでたのしい健康スローライフ!
マーニー
ファンタジー
※ほのぼの日常系です
病弱で閉鎖的な生活を送る、伯爵令嬢の美少女ニコル(10歳)。対して、亡くなった両親が残した借金地獄から抜け出すため、忙殺状態の限界社会人サラ(22歳)。
ある日、同日同時刻に、体力の限界で息を引き取った2人だったが、なんとサラはニコルの体に転生していたのだった。
「こういうときって、神様のチート能力とかあるんじゃないのぉ?涙」
異世界転生お約束の神様登場も特別スキルもなく、ただただ、不健康でひ弱な美少女に転生してしまったサラ。
「せっかく忙殺の日々から解放されたんだから…楽しむしかない。ぜっっったいにスローライフを満喫する!」
―――異世界と健康への不安が募りつつ
憧れのスローライフ実現のためまずは健康体になることを決意したが、果たしてどうなるのか?
魔法に魔物、お貴族様。
夢と現実の狭間のような日々の中で、
転生者サラが自身の夢を叶えるために
新ニコルとして我が道をつきすすむ!
『目指せ健康体!美味しいご飯と楽しい仲間たちと夢のスローライフを叶えていくお話』
※はじめは健康生活。そのうちお料理したり、旅に出たりもします。日常ほのぼの系です。
※非現実色強めな内容です。
※溺愛親バカと、あたおか要素があるのでご注意です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















