2 / 2
小太刀の籐伍奇譚帖〜鬼神狩り《後編》
しおりを挟む
第四幕 蹴速を継ぐ者
(一)
《鴻池隠居所に於ける鬼没盗捕縛書留め》より抜粋
河原崎突入組にて捕縛せし賊四名
阿刀関所にて捕縛せし賊三名
隠居所奉公人に死傷者なし
捕り方に怪我人五名
隠居所に待機せし二名、賊一名と交戦するも捕縛ならず
逃走者一名
捕縛した賊の取調べにより、逃走せし一名が本件「鬼没盗」の首領と思われる。
鬼没盗の残党と首領を捕縛するためには、捕らえた七名からさらなる情報を引き出す必要があった。だがその取調べは籐伍ではなく吟味方の他の与力や同心の役目となっていた。
それは籐伍には賊を取り調べる基礎技術が不足し、またその技量も未熟なためだった。老練な吟味方の与力、同心の方がその役目には適していた。それでも籐伍には鬼没盗残党の継続探索が下命された。
ここからはまた籐伍一人で鬼没盗を追うことになったのである。
奉行所での一連の後始末を終えてから鴻池の隠居所に赴くと、そこに渦彦の姿がなかった。少彦名神社に戻っているのかと思い、同修町に行っても渦彦の姿はない。
宮司に聞いてもまだ帰ってきていないという。渦彦は元々大坂に地縁のない人間である。隠居所や少彦名神社以外に行くところなどないはずだった。急に元いた京の五條天神宮に帰ったとも思えなかった。それならば少彦名神社の宮司は知っているはずである。
昨日まであったはずの渦彦の痕跡が、ぷっつりと消えていた。
籐伍は最初この状況をどうしてよいのか分からなかった。心の半分が渦彦と一緒に消えてしまったように感じていた。
その日の夕餉には、久しぶりに阿刀家の全員が顔を揃えていた。元々お役繁多な父念十郎は家に戻らぬことが多かったし、鬼没盗の探索に入っていた籐伍も夕餉を空けることも珍しくなかった。それにこの一ヶ月余りは念十郎と鈴、燕は隠居所と隠れ家に移り住んでいたので全員が顔を合わせることもなかった。
やっとひと段落ついて、天満橋北の家に全員が揃ったのである。久しぶりの夕餉を共にしているというのに、どこか籐伍の食欲は進まなかった。
「どないしたん、全然ご飯食べてへんで」
最初に箸をつけたきりの膳を見た燕が、揶揄うように籐伍の顔を覗いた。
籐伍は反論するでもなく、黙って膳の茶碗を持ち上げた。口元まで運んだのだがそこまでで箸を動かすことはしなかった。
籐伍の心がこの場にないように見えた。
「籐伍、渦彦殿はどないしとるんや。一度招いて礼をせなあかんと思うとる。わしも燕も、渦彦殿に助けられたからのう。都合ええ日を聞いてんか」
父の言葉に、籐伍は一瞬ビクッとした。何か失敗を見つけられた子供のようだった。しばらく沈黙していたが、告白するように父の方に向かった。
「いてへんようになりました。どこにもいてへんのです。隠居所にも少彦名神社にも。まるで大坂から消えてしまったみたいに」
それだけいうと、そのまま押し黙ってしまった。
家族は互いに顔を見合わせ、誰が口を開くかという雰囲気になった。三人ともいいたいことは同じのようだった。
いつも控えめでしとやかな鈴が、珍しく強い調子で口を開いた。
「あんた、それで今までじっとしてたん。渦彦はんには事情があって大坂にいてるんは皆よう知ってる。その大坂からいてへんようなったいうことは、どうしてやと思うの。渦彦はんの事情が変わったからや。ほんまもんの友達やったら、すぐにでも助けに行ってやらなあかんのとちゃうの」
籐伍は鈴に叱られたという記憶がほとんどない。いつも優しく見守ってくれている姉だった。こんな調子で叱られたのは初めてである。死んだ母に叱られているような気がした。
「そやけど、どこに行ったかもようわかりません。どうやって助けいうんですか。鴻池の御隠居に問い合わせても無しの礫です」
二人の言葉を聞いていた念十郎が静かに口を開いた。
「探しにいく場所はあるんとちゃうか」
籐伍は「何処へ」という表情になった。
「渦彦殿が大坂にいてへんようなったいうことは、この前鬼没盗と戦うたときに何かあったからや。それはお前も想像してるやろ。お前自身が最初に指摘した鬼没盗と徳陀子神社との繋がりについて、何ぞ思い当たることがあったからや。そしたら行くとこは徳陀子神社しかあらへんで。多分何かを確かめにな。そこまではお前かて分かってるやろ。鈴は分かってるのに何で動かんのやと怒ってるんや」
念十郎が優しく籐伍を諭した。まるで姉と父が役目を交代したような言い方だった。
籐伍は一瞬言葉に詰まった。だがまるで言い訳のように呟いた。
「お役目があります。大和へ行くにはお奉行の許しも要ります」
「お前はいつからそんな杓子定規な人間になったんや。好きな芝居のためやったらお役目忘れてたお前は何処へいった。わしはそんな籐伍の方が好きやったわ。鈴もそう思うてるから怒ってるんや」
昔の父や姉と言うことが真逆だと籐伍は感じた。それは籐伍が少し大人になり、父や姉が大人として籐伍を扱っているからだった。ただ籐伍にまだその自覚がなかった。
二人は大人の男として、何を置いても友を助けるべきではないかと諭していた。理由を付けて動かないのは大人でも男でもないと。
「色々と忙しかったからいえてなかったけどな、一つ籐伍に教えとかなあかんことがある。わしと燕が賊と戦うたときのことや」
父が何をいおうとしているのかわからなかった。
「わしと燕二人とも、前におる賊から背中を蹴られるいう妙な攻撃を受けたんや。賊は何とも不思議な武術を使う奴やったようや」
念十郎は何かを思い出すように少し沈黙した。
「しかも賊と渦彦殿が戦うたときには、二人は同じような構えと戦い方をしてた。その技を賊は『蹴速』と呼んどった。詳しいことは分からへんが、二人は同流の武技を学んどるらしい。そやから渦彦殿も相手のことに思い当たることがあったんやろ。それを確かめに大和に戻ったんとちゃうか」
父の言葉に、初めて渦彦と戦ったときのことを思い出した。
確かに渦彦は不思議な武術を使い、籐伍の八艘を外してさらに反撃してきた。渦彦はそれを徳陀子神社に伝わる体術だといっていた。
だとしたら、賊もまた徳陀子神社の体術を学んでいることになる。渦彦はそれを確かめに大和に戻ったに違いなかった。なら渦彦を追うことは賊の出自を追うことにもなる。これはお役目にあたると籐伍は即座に閃いた。
「わかりました。明朝すぐに大和への探索願いをお奉行に出します。渦彦を本気で助けるためにも、大和へはお役目として参ります」
そう宣言すると、やっと籐伍は何かを吹っ切ったように茶碗の飯を急いで食べ始めた。燕が空になった籐伍の茶碗に飯を盛っていった。それは家族の役回りを皆で交代したような風景だった。
翌朝早々に提出された籐伍の大和探索願いは、期限付きながらも許可された。来月は西町奉行所の非番月なので、その月内という期限だった。
鈴と燕に手伝われて旅支度を整えた籐伍は、二人に旅立ちの挨拶をして家を出発した。
早朝だったが、父はすでに奉行所に出仕していなかった。隠居を決めてお役目の引継ぎ中のはずだが、なかなか手が離れないようだった。諸色方からは隠居後も今度は念十郎が「仮役」としてお役目の継続を求められているらしい。それではたとえ隠居しても、親子の役回りが逆になるだけのように思えた。
籐伍はまだ一人旅をしたことがなかった。旅どころか、大坂をまともに出たこともない。大阪の武家や町人は京や宇治、あるいは石清水八幡宮、遠くは伊勢までも寺社詣に出かけることはよくある。江戸後期の天保時代は人々に旅が流行った時代だった。
だがこれまで時間があると芝居小屋に入り浸っていた籐伍は、そうした流行りとは無縁の生活をしていた。隣国とはいえ生駒山を越えて大和にまで入るのは初めてのことだった。
大坂から大和に向かうには幾つかの街道がある。徳陀子神社のある葛城山には、生駒山脈南の切れ目である松原から王子に抜ける古道、竹内街道を通るのが通常だった。
この竹内街道は日本最古の官道ともいわれ、推古二一(六一三)年に整備された難波宮と飛鳥京を結ぶ大道である。籐伍の住む天満橋からは真っ直ぐに南下して八尾に至り、さらに南の松原から東へ抜けることになる。生駒山脈南端の竹内峠を東に抜ければそこはもう当麻の地だった。葛城山はその当麻の南に聳える山塊にある。
初めての旅でしかも慣れない道ではあったが、この道程を籐伍はほぼ三日で歩き抜いた。途中に籐伍の気を惹く美しい風景や珍しい文物も多々あったが見向きもしなかった。
途中何度も里人に尋ねながら葛城山東麓にまで来たとき、古びた大きな神社があった。これが徳陀子神社かと中に入っていった。だがそこは一言主神社という別の社だった。
実はここに至るまでも数々の古社に行き合っていた。その度に籐伍はそこが徳陀子神社かと思い、中に入っては確かめてきたのである。一体大和には幾つの神社がるのだと思い、少し辟易していたところだった。
だがこの一言主神社の禰宜が徳陀子神社のことを教えてくれた。
「うちの社の裏にある山道を登って行ったら途中に少し開けた場所があるよって、そこから尾根沿いに北に進みなはれ。そしたら少し家のある山里に出るよって、そこの人らに聞いたらええ。徳陀子さんはその里の奥や。そやけど大坂のお武家はんが何の用があんねん。あそこは修験か病抱えて薬を求める人ぐらいしか行かへんで」
禰宜は少し訝しそうに籐伍を見た。
籐伍はそれには答えず礼だけをいって社裏の山道に入っていった。もう陽が傾きかけているので夜までに着けるのだろうか不安になっていた。
山の陽が落ちるのは想像以上に早かった。明りを持っていない籐伍は暗闇の尾根道を歩くことになった。
「もう何処かで野宿した方がいいかもしれない」と思い始めたとき、遠くに明りが見えた。あれが山里の明りかとホッとした籐伍は、その明りに向かって疲れた足を奮い立たせて歩いていった。
明りの灯った家の戸を叩きながら、声を大きくして案内を請うた。
中からは最初返事がなかったが、声を怪しんだか逆に不憫に思ったのか、戸の閂が外されて少しだけ開かれた。
中からは小さな老人がじっと籐伍を見ていた。籐伍が言葉を出す前に老人が怒鳴った。
「ここにゃあ、金目のもんも食いもんも何もありゃへんで。爺と婆だけの家じゃ。物取りなら他に行け」
それだけいい放つと、すぐに戸を閉めようとした。籐伍は閉まりかけた戸を必死に抑え、老人が興奮しないように静かに尋ねた。
「わいは徳陀子神社を探して大坂から来ました。神社の息子、巨勢渦彦の友人です。神社への道を教えてくれまへんか」
渦彦の名に老人が少し反応した。そして恐る恐るだが戸を半分ほど開いた。開いた戸の陰で老人は左手に鎌を持っていた。戸に隠していたのだ。籐伍が怪しい動きをしたなら、鎌で反撃するつもりだったのだろう。
「渦坊の友達いうんはほんまか。嘘やったらいてまうで」
そういいながらも老人は戸を開き、「まあ入れ」といってくれた。
籐伍はホッとして、小屋の中に入っていった。囲炉裏のそばでは老婦が手招きしていた。
「こんな夜に山を登って来たんは大変やったやろ。白湯でも飲み」
そういって温かい湯を差し出してくれた。
籐伍は白湯を飲みながら、大坂で出会った渦彦のことや徳陀子神社の御神宝を探す手伝いをしていることなどを語った。そして大坂から渦彦がいなくなったので、心配になり徳陀子神社にまで探しに来たのだと告げた。
籐伍の話を聞いてから老人はしみじみといった。
「宮司様が逝かれてから神社は大変や。綿津見はんは体が弱いし、渦坊も京へ修行に行ったきり帰ってこれへん。その上宮司様が死んだほんまの理由もよう分からへんしな。神社から何ぞ盗まれたもんがあったいうんは初めて聞いたが、それを探しに渦坊は大坂へいっとったんか」
籐伍は老人の口走った「死んだ本当の理由がわからない」という言葉に反応した。
「渦彦の父上は自害と聞いていますが違うんですか」
籐伍の言葉に、老人は一瞬「しもた」という顔をした。だが籐伍を渦彦の友達と信じているせいか、宮司が死んだ状況を詳しく話してくれた。
この老人は時々、祭礼などで徳陀子神社の臨時神人をしていたので、幼い頃から渦彦をよく知っていたのだった。そして死んだ宮司を祖霊舎の前で発見した張本人だった。
「宮司様は確かに前屈みになって倒れてはった。ほんで手に短刀を持って胸を突かれてたように見えた。そやけどな、わいには流れ出てる血が少ないなと最初思えたんや。それに……背中のあたりが変に曲がっとった。なんや後ろからでっかい丸太で叩かれたみたいにな。わいはとりあえず、宮司様を綺麗に寝かしてから神社に知らせにいたんや。その後は綿津見はんが村人に頼んで甲斐甲斐しゅうに葬りはったわ。厨様(母親)は泣いてばかりやから、綿津見はんも大変やったやろなぁ」
そうしんみりと語った老人は少し涙も流していた。
「朝に神社へ連れていったるさかい今夜はここに泊まれ。山の夜道は危ないさかいな」
老人はそれ以上もう何も語らなかった。
翌朝、籐伍は老人に連れられて徳陀子神社に向かった。朝でも危ない箇所もある尾根道だったので、夜歩けば本当に谷底に落ちたかもしれない。
辿り着いた徳陀子神社は古色深い社だった。まるで山懐に隠れているようにも見えた。
老人が先に神社の中に入り、籐伍のことを伝えているようだった。少し経った頃に、白装束に袴姿の若い男が出て来た。
巨勢綿津見、渦彦の兄でありこの社の新しい宮司だった。
神社の拝殿で、籐伍と綿津見は対面した。互いに挨拶をしてから、少し硬かった二人の表情が柔らかくなった。
「弟からの文で阿刀様のことはよく存じております。大坂ではいろいろと渦彦がお世話になりました。お礼申し上げます」
綿津見が深々と頭を下げた。
「いえ、渦彦にはわいの方が助けられています。渦彦がおらなんだら、鬼没盗を捕えることもできまへんでした。全部渦彦の協力のおかげです。それに渦彦と友達になれて、わいはほんまに喜んでいます。ですからここにもやって来たんです。渦彦が急に大坂からおらんようになりましたさかい」
籐伍は先日の未然記囮一座の顛末と、その後に渦彦が大坂から姿を消したことを語った。
理由はわからないが、鬼没盗の中に渦彦と同じ技を使う者がいたようで、その賊は技の名を「蹴速」と呼んでいたらしい。それが姿を消した理由ではないかと籐伍は語った。
籐伍の話をじっと聞いていた綿津見は、沈黙してから籐伍に礼を述べた。
「阿刀様は何も語らぬ我が弟のために、大坂からここまで来てくだされました。それは誠にありがたいことです。確かに蹴速は我が神社に、いえ我が一族に伝えられている体術です。この体術は門外不出、口外不可の秘伝とされています。その家禁を守った渦彦は阿刀様にも何も語れなかったんやと思います」
綿津見の言葉に籐伍が待ったをした。
「阿刀様はやめてください。綿津見殿は友の兄上ですから、籐伍と呼んでください。それに多分わいの方が年下です」
籐伍は綿津見が従兄弟の恭一郎と同じぐらいの歳だろうかと思った。綿津見は苦笑しながらも籐伍の言い分を受け入れた。
「では籐伍殿、そう呼ばせていただきましょう。そして渦彦が向かった先はここではのうて、多分桜井やと思います。そこには我ら兄弟に蹴速を教えてくれた叔父がおります。父上が亡くなった今となっては、蹴速について訊けるのはこの叔父しかおらんでしょう。ですから渦彦はここへは寄らず、叔父の元に向かったんやと思います」
綿津見の言葉に、これで渦彦の後が追えると籐伍は喜んだ。
「是非にも叔父上様の居所をお教えください。わいは何としても渦彦の力になりたいんです。鬼没盗捕縛の協力を承知してもろうたときに、渦彦の力になると約束しました。今はそれを果たしたい」
籐伍は綿津見に頭を下げた。その姿を見た綿津見は嬉しそうに微笑んだ。
「渦彦は大坂で誠にええ友を得たようですね。わかりました、ことは我が一族にも関わることですよって、籐伍殿だけにお任せする訳にはいきまへん。私も参ります。桜井は遠くはないですが、今から出発したら夜になってしまいます。明朝、私と一緒に参りましょう。今日はここでゆっくり休んでください。大坂からの旅の疲れもあるでしょうし」
そういうと、「おい、夕凪はいてるか」と拝殿の奥に声をかけた。
ほどんなくして十歳ほどの少女がやって来た。
「これは妹の夕凪です、お見知り置きを」
そして夕凪に向かって「お客人を客間にご案内しなさい。それと母上に湯と食事の支度をするようにお願いしてんか」と指示をした。
籐伍は自分一人で桜井に行くつもりだったので、綿津見の言葉に戸惑った。だが確かに旅の疲れもあったし、また巨勢の一族に関わることだけに綿津見のいうこともわかる。ここは素直に好意に甘えることにした。
そう考えると今まで張り詰めていた気持ちが緩んだせいか、一挙に旅の疲れを感じ始めた。今夜はゆっくり休ませてもらった方が良いなと思った。
(二)
翌朝、籐伍と綿津見は桜井にある叔父の剣術道場に向かった。
叔父の椎根津は桜井に猿飛陰流の剣術道場を開いていた。桜井は奈良盆地南部の東に位置し、西に位置する葛城山とは五里ほどの距離がある。健脚の人間なら半日で歩ける距離だった。
かつて綿津見と渦彦の兄弟に蹴速術を教えるために、椎根津は毎日桜井と葛城山を往復していたらしい。恐るべき健脚である。
体の弱い綿津見が桜井まで行くことに母親は初め難色を示した。だがこれは巨勢一族の惣領の役目であるという綿津見の強い言葉と、籐伍の無事にお連れしますという説得で母親も渋々納得した。
「私はこうして葛城山を降りるのは久しぶりなのです。いつもは渦彦に頼っていましたから。今回は籐伍殿がいてくれて助かりました。私一人では母上も納得しなかったでしょう」
そう呟くと、青い秋空を見上げて気持ちよさそうに微笑んだ。綿津見は惣領の役目を果たすために必死なのだと籐伍は感じた。母親を安心させる為に、自由に旅をすることも許されないのだと。
早朝に徳陀子神社を出発したのだが、綿津見の足の速さに合わせた為に桜井には昼を過ぎてから到着した。
道場には昔一度行ったことがあるという綿津見だったが、当時と様子も変わっていたので、少し迷って里人に尋ねながらの道行きになった。
やっと叔父椎根津の剣術道場にたどり着いたとき、道場からは大きな音がしていた。まるで中で多くの人が戦っているような音だった。
道場の格子窓から、籐伍と綿津見はそっと中を覗き見た。そこで二人が見たのは、数人の稽古着を来た人間と闘う渦彦の姿だった。
稽古着の人間は手に木刀を持っていた。それに対して渦彦は空拳で対している。それにも拘らず渦彦は一撃も木刀の攻撃を受けず、逆に相手を投げ飛ばしたり、手刀で相手を打ち据えたりしている。
乱取り稽古だとは理解できたが、このように一対数人というのはなかなかない光景である。
その光景をじっと見ていた綿津見はそっと籐伍に囁いた。
「これは準備運動です。蹴速は本来複数人を相手にする技ですから」
そういった綿津見だが、渦彦が蹴速術の足技を一切使っていないことに気がついていた。
きっと稽古着の男たちは叔父の剣術「猿飛陰流」の門弟で、彼らによって渦彦の手技を鍛えているのだと思った。そして蹴速術本来の足技は叔父との二人稽古で修練しているのだろうと思った。
渦彦の乱取り稽古が一段落ついたと思える頃、綿津見は表玄関から中に声をかけた。
「叔父上、ご無沙汰しております。綿津見です。お話があって参りました。中に入ってもよろしいでしょうか」
綿津見の声に呼応するように、椎根津が道場に号令をかけた。
「本日の稽古はこれまでとする。各々、体を整えてから下がるように。渦彦はそのままここに、綿津見はそなたにも用があるやろう」
道場の神棚前から立ち上がった椎根津が玄関にまで出て来た。そこで綿津見と籐伍の前に立った。
「お前も来るやろうとは思うとったわ。意外に早かったようやな。それでそちらの御仁は」
綿津見から籐伍の方に視線を向けた。籐伍は前に出て名乗りをあげた。
「初めてお目もじいたします。私は阿刀籐伍と申します。大坂西町奉行所の仮役与力ですが、ここへは巨勢渦彦の友として参りました。どうぞお見知り置きください」
籐伍の声に、「えっ」と驚いた渦彦が道場から玄関の方を振り向いた。そこには久しぶりに見る籐伍の姿があった。
「なるほど、渦彦から話は聞いております。あなたが鬼没盗を追う小太刀使いの籐伍殿か」
何か面白いのかまじまじと籐伍を見てから、「中に入られよ」といって元いた道場の神棚前に戻っていった。
籐伍と綿津見は道場に入ると、渦彦の座る横に並んだ。渦彦と籐伍は一瞬視線を合わせたが、言葉は発しなかった。椎根津を前にして、三人が並んで対するような形になった。
籐伍が何から聞こうかと迷っていると、椎根津の方が言葉を向けてきた。
「お前たちがここに来た訳はおおよそわかっておる。渦彦と同じ用件やろう。各々に語るのも面倒ゆえ、揃うのを待っておった。渦彦の修練も至急に終えねばならぬかったからの」
そういうと、深刻な表情になった椎根津がまず渦彦に語りかけた。
「お前との約束では、わしから一本取れたなら知りたいことを教えてやろうというたが、少し順番が狂うてしもうた。まだお前はわしから一本取れておらんが、ここまでお前を案じてやって来た兄と友に免じて最初の質問に答えてやろう」
そして目を瞑った椎根津は、何か苦い記憶を思い出すように語り始めた。
「最初の質問は、なぜ蹴速を使う者が我ら以外におるのかということやったな。……お前たち兄弟とわし以外に、今この世にはもう一人だけ蹴速を使える者がおる。それはかつてわしの弟子やった男や。名を古瀬稀人(こせまれひと)という」
椎根津の言葉に三人は一瞬息を飲んだ。
籐伍もだが、渦彦、綿津見の兄弟にとっては衝撃的な叔父の言葉である。巨勢宗家の者以外に蹴速術を使える者がいる。それは千年の禁忌を破ることを意味していた。
何かをいおうとした綿津見に、椎根津はそれを抑えて話を続けた。
「稀人は最初わしの剣術の弟子やった。猿飛陰流のな。こやつは武芸に天賦の才があったようで、わずか一、二年で猿飛陰流の全てを吸収してしもうたわ。わしは皆伝を授けようとしたが、稀人はそれを拒みよった。そして別の物を要求して来た。それは……完全なる蹴速の教授じゃった」
三人と椎根津はしばらく重苦しい沈黙の中にいた。
「何故その者は蹴速の存在を知っておるのですか。蹴速は門外不出、口外不可の禁があります。宗家以外の者が知るはずがありまへん」
綿津見が絞り出すような声で尋ねた。その言葉に椎根津は深く頷いた。
「その通りじゃが、長い時の中では秘密が秘密でのうなることもある。まさに稀人がそのような例であった」
ここで椎根津は、自分の過去を悔やむような表情をした。今でも悔いているようだった。
「稀人の家には蹴速の一部が伝わっておったのじゃ。稀人は不完全ながらも蹴蹴を修得しておった。わしも驚いたが紛れもない蹴速の技じゃった」
不完全な蹴速術がいつから稀人の家に伝えられていたのかは分からない。それは太古から宗家以外の別流として存在したのか、あるいはどこかの時代に宗家から分流したのか。稀人の苗字が「古瀬」であることから、「巨勢」からの派生であるのかもしれない。ならば元は同族だった可能性も高いのだった。
直近の歴史で考えてもこの可能性はあるのだった。巨勢宗家の惣領が仙薬法を継ぎ、次男が蹴速術を継ぐという仕来りは、いずれ分流を生む下地になっていた。
例えば椎根津が宗家の子以外に、自分の子にも蹴速術を教えたならどうなるのか。それは禁忌ではあるがないことではない。せっかく身につけた秘術を自分の子に伝えたいという欲望はいつの時代にも存在しえるのである。長い時間の中ではこの過ちは十分に起こりうることだった。
「稀人がここに入門してきたんは最初から蹴速が目的やったのかもしれへんが、武芸の天才であることもまた事実やった。猿飛陰流を修めたからこそ、蹴速の話も出したんやろう。そしてわしもそれに心を動かされた」
稀人の蹴速の技は不完全ではあったが、それでも十分に強かった。そして椎根津もある夢を見たのだった。
「この天才に完全な蹴速を教えたら、どこまで強くなれるのだろうか」と。
この思いは武芸者の願望だった。また椎根津が猿飛陰流を学んだ理由の一つでもあった。
椎根津は若い頃、いかに蹴速を極めようともそれは生涯表の世界に出すことはできない強さだということに悩み、絶望した。宗家の禁忌がそれを許さないのだ。
だから表の世界で強さを試せる猿飛陰流を学んだのだ。だが猿飛陰流を極めれば極めるほど、余計に蹴速の強さが心に残った。
もし猿飛陰流を使う自分と蹴速を使う自分が戦ったなら、勝つのは蹴速を使う自分だろうと思った。
それは生涯表に出せない強さだった。宗家に生まれた自分はこの理不尽な禁忌から逃れることは許されない。それは理解していた。
だが稀人ならどうなのだろうかと思った。自分が夢見てできなかったことができるのかもしれない。たとえできなくとも、自分の最強の敵になれるかもしれない。椎根津もまた、最強の蹴速を振るえる相手が欲しかったのだった。
稀人が元は巨勢の同族かもしれないという思いは、椎根津の罪の意識を慰めてくれた。外に出すのではなく、同じ巨勢に教えるのだと自分にいい聞かせていたのだ。
「結局、わしは稀人に蹴速を教授した。それはちょうどお前たち兄弟に指南し始めたのと同じ頃やったか。稀人はお前たちには存在してはならぬ兄弟子になるんや」
椎根津の言葉は巨勢宗家の人間としの贖罪だった。
沈黙して聞いていた籐伍が、ここで急に椎根津に質問した。
「叔父上殿のお話はわかりましたが、一つ質問があります。なぜ巨勢家は長男に仙薬法、次男に蹴速術という分けた継承方法をとっているんですか。すべてを惣領に継がせれば秘術が外に出る可能性も少ないでしょうに」
何気ないつもりでいった質問だったが、それは巨勢家のより大きな闇を明らかにする言葉だった。
椎根津は籐伍を改めて見詰めて、「勘の良い与力殿じゃな」と感心したように呟いた。そして綿津見にその答えを求めた。
「綿津見、お前は籐伍殿の質問に答えられるやろ。死んだ兄上からまだすべてを口伝されてはおらんかもしれんが、この答えは持っておるはずや。何より十年前にお前自身がしたことやからな」
椎根津の言葉に、綿津見は一瞬体を固めた。そして下を向いたまま黙ってしまった。籐伍も渦彦も、綿津見の行動の意味がよくわからなかった。
「わしは今、巨勢の秘密を語っとる。外の人である籐伍殿にも聞かせる為にな。これは巨勢の禁忌に触れることやが、古瀬稀人を生み出してしもうたわしの罪滅ぼしでもある。もういい加減わしらはこの禁忌から解き放たれる必要があると思うとる。その罪過は全てわしが背負うつもりや。兄上もお許しくださるやろう」
この場に相応しくない微笑みを浮かべた椎根津は、籐伍の方に向かった。
「籐伍殿、今のお尋ねにお答えいたそう。なぜ次男に蹴速を継がせるのか。それは蹴速を継ぐためには命を賭けねばならぬからや。家を継ぐ惣領に命懸けの試練はさせられぬからのう」
籐伍と渦彦は椎根津の言葉の意味がわからなかった。ただ綿津見だけが下を向いていた。その顔は蒼白になっていた。
椎根津は蹴速術を継承するための儀式について語り始めた。それは宗家の次男が十歳になったときに行われるという。次男が十歳になったときある仙薬が処方されるのだった。その仙薬は「鬼変薬」と呼ばれる一種の肉体強化薬だという。鬼変薬を飲んで適合できるかどうかを試すのである。
適合できれば人を超える力や速さ、そして肉体の強靭さが獲得できる。
だが適合できなければどうなるのか。それは人によって異なるが、悪くすれば副作用で即死するらしい。死ぬまで行かなくても重度の健康障害が起こり、寿命も短くなるかもしれない。
このような危険な薬を家を継ぐ役目の惣領に試させる訳にはいかなかった。だから次男で適合するかどうかを試すのである。次男なら死んでも代わりがいるのだった。それは秘術と家系の両方を守るための苦肉の選択なのかもしれなかった。
唖然と椎根津の話を聞いていた籐伍と渦彦だが、急に渦彦が尋ねた。
「そんな危ない鬼変薬に何で適合できるか試さなあかんのですか。それにわいは十歳のときにそんな薬を飲んだことありまへん」
椎根津は少し悲しそうな表情で渦彦に答えた。
「それは鬼変薬を飲んで強化された肉体は、まるで鬼のような強さと能力を獲得できるからや。そして強化された肉体で蹴速術を使うたら、人には不可能な強さを発揮できるようになる。それを我が一族は『鬼神術』と呼んどる。鬼変薬と蹴速術の二つで完成される鬼神術を使う者は、天下無敵になれるということや。それはそもそもの巨勢のお役目のために必要な強さやったらしい」
その昔、古代において巨勢一族は朝廷や大豪族の戦闘兵団だった。誰にも負けぬ兵士の強さが求められたのである。そのために編み出されたのが蹴速術であり鬼変薬だった。鬼変薬を作り出すために様々な薬も研究され、それが転じて巨勢の仙薬法になったのだという。
伝説によると、あるとき蹴速術よりも強い武技を操る兵団が出現し、巨勢は一時その地位を失ったことがあるらしい。その復権のために創り出されたのが鬼変薬だという。武技が同水準ならば肉体能力の高い方が戦いに勝つ。
だがこの薬の開発には困難を極めた。そしてやっと完成した鬼変薬にも適合する人間と、そうでない人間がいた。そのためにこの鬼変薬で多くの一族が命を失ったらしい。
巨勢の力を守るためにこの蹴速術と鬼変薬は一族の秘術として今日まで守られ、伝えられて来たのだった。今となってはもう失なわれた役目のための、無用の無敵の強さではあったが。
呆然と椎根津の話を聞いていた渦彦は兄の方に向いた。
「わいは何も知りまへんでした。兄上は知ってはったんですか」
渦彦の無邪気な問いが、綿津見の過去の罪を暴こうとしていた。
十年前に渦彦がもう十歳になろうとしたとき、父飫肥人は宗家の仕来り通りに渦彦に鬼変薬を試そうとした。その試練に生き残らなければ巨勢宗家の次男として、蹴速術継承者の役目は果たせないのだった。
父から鬼変薬の製法を口伝された綿津見は、いわれるままに渦彦に飲ませる鬼変薬を用意した。
だが理不尽な仕来りに対する怒りと弟への愛情から、綿津見はその薬を渦彦に飲ませることをしなかった。代わりに父には黙って綿津見自身が鬼変薬を飲んだのだった。
その結果、綿津見は鬼変薬に適合しなかった。死にこそしなかったが、何日も苦しんだ挙句に重度の健康障害に陥ったのだ。
父飫肥人は綿津見の行為と結果に驚き嘆いた。そして苦しんだのだった。やがて弟の椎根津にも今後のことを相談した。
二人が出した結論は二つだった。一つ目は渦彦が鬼変薬を飲んだとして、次の子供が生まれるまで今は渦彦に鬼変薬を試さぬこと。もし渦彦に試して渦彦まで不適合ならば、巨勢宗家が途絶えることにもなってしまう。健康障害を起こした綿津見は、元々病弱な子だったとして扱うことだった。
そして二つ目は早急に三男が生まれるのを待つことだった。その後に三人目の子供は生まれたが、それは期待に沿わぬ女児だった。妹の夕凪である。その後今まで、渦彦に鬼変薬を試されることはなかったのだった。
淡々と語られる椎根津の言葉に、籐伍も渦彦も言葉が出なかった。
十年前に兄が自分の身代わりになっていたことを渦彦は知らなかった。今兄が不自由な生活を強いられているのは、自分を救うためだったのだ。
渦彦は半分泣き出しそうな顔で兄を見詰めた。どういう言葉を発してよいのか、全くわからなかった。
「綿津見は一切語らんやろうが、お前が今生きておられるのは綿津見のお陰といってもよいやろう。しかしなぁ、こうしたことは巨勢の歴史の中では稀にあるんや。わしと兄上との間にもそれはあった、また別の形やがな」
椎根津は遠い日を思い返すように天を仰いだ。
「わしと兄上の間にはもう一人兄弟がおった。本当の巨勢の次男坊や。その次男坊は鬼変薬の試しで結局死んでしもうたわ。そして三男やったわしが繰り上がった。そこまでして一族が継いできた蹴速術なんや。たとえ表に出せずとも継がぬ訳にはいかん。ただわしは稀人ならば蹴速をどのように使うかが見たかった。その欲がわしの過ちや」
椎根津の言葉に籐伍が再び尋ねた。
「では鬼没盗が、いえ古瀬稀人が徳陀子神社から盗んだ御神宝とはその鬼変薬なのですか」
籐伍の疑問に、下を向いていた綿津見が顔を上げて答えた。
「いや、それはないと思います。あの薬を作作るにはかなり特殊な薬種が必要やよって、父がそれを集めた跡がありまへん。勿論口伝を明かすこともないでしょう。そやから……父上は殺されたんかもしれまへん」
ここで初めて、綿津見は父の死が自害ではなく、殺害だと口にした。それは綿津見がずっと考えていた可能性だった。
実は綿津見も父の遺体を見たときにある異変に気がついていた。胸の刺し傷ではなく、折られたような背骨の曲がりに。
父の遺骸を発見した老人が最初に指摘した異変だったが、綿津見はそれを他にいわぬように口止めしたのだった。それはその損傷が蹴速の一撃によってできた損傷に似ていたからだった。
一族以外に蹴速が使える者などいるはずがない。そう思ったからこその口止めである。
だが一族の他にも蹴速が使える人物がいるとなると、話は変わってくる。椎根津の話を聞くうちに、父の背中の損傷は蹴速の一撃によるものに違いないと思えてきたのだった。
「もしかしたら父上は、その古瀬稀人に鬼変薬の秘密を求められ、拒んだから殺されたのかもしれまへん。古瀬稀人が誠に蹴速術を自分のものにするためには、どうしても鬼変薬が必要でしょう。蹴速術から究極の鬼神術に化けるためにも」
綿津見の淡々とした言葉に、渦彦は少し驚いていた。渦彦にとって綿津見は常に優しく、愛情深い人間だと思っていたからだ。その綿津見が今は冷たすぎる表情で父の死の理由を語っていた。それは激しい怒りを覆うための綿津見の仮面だったのかもしれないが。
「稀人はかつてわしにいうたことがある。天はなぜ何の役目もない自分に、このような才を与えたのかと。稀人は蹴速術自体よりも、巨勢宗家の重い宿命が欲しかったのかもしれへん。自分が天賦の才を持つ理由をな。それが今の自分にないことを嘆いとった。もし稀人が本当にその鬼没盗ならば、どこかでその理由を手に入れたからかもしれへんな」
椎根津の言葉に対して、決然とした綿津見がいい返した。
「それは父上を殺す理由にはなりまへん。自分の天命は自分で見つけるものです。他人から奪うべきでものではありまへん。私は自らにてもそうしてきました。私の天命は家族を守ることやと思いました。ですから父上の命や巨勢の仕来りに背いても、渦彦に鬼変薬を飲ませへんかったんです」
綿津見は椎根津に対してというよりも、まだ姿の見えない稀人に抗議するように叫んだ。この場の全員が綿津見の内側で赤く燃える埋火を見たような気がした。
普段にない声を出したせいか、綿津見は激しく咳こんだ。渦彦も籐伍も綿津見を心配して近寄ろうとしたが、綿津見は大丈夫だというように二人を制止した。
その様子を見た椎根津が、「昔のお前を見るようやな」と呟いた。
「急にいろいろと語りすぎたかもしれへんな。一編に全部を受け入れるんは難しいやろ。綿津見には葛城山からの疲れもあるやろうから、今日はゆっくり休め。明日また聞きたいことがあったら話したる。それに今からは急ぎ渦彦に仕上げの修練もさせなあかんからな」
そういって、籐伍と綿津見を奥の部屋に下がらせた。
道場にただ一人残った渦彦に向かって、「これから温羅(うら)の蹴速を修練する」と椎根津が静かに告げた。それはまだ渦彦が聞いたことのない蹴速術だった。
(三)
「温羅の蹴速」とは、音の転化から別に「裏の蹴速」とも呼ばれる蹴速の隠し技である。
元々蹴速術の原点は大和の当麻ではなく、遥か西国の一族が持つ武闘術だったらしい。その一族は「鬼の温羅」と呼ばれる戦闘に優れた一族で、古代大和の権力者たちにはなかなか服さなかった。
それゆえ大和は侵略軍によってこの鬼の温羅一族を滅ぼそうとしたのである。侵略軍の将軍は吉備津彦命と呼ばれ、後の桃太郎伝説の原型にもなったといわれている。
吉備津彦命は第十代崇神天皇の時代に発せられた四道将軍の一人だといわれていた。大和の政権が全国を征服しようとした時代の、地方征服を命じられた将軍だった。
吉備津彦命の侵略軍により、温羅一族は滅ぼされたとされている。そしてその一部は俘囚として大和に連行されたのだった。
温羅の俘囚たちが蹴速術の始祖・当麻蹴速になったのかどうかはわからない。ただその武闘術を巨勢などの氏族に伝えただけなのかもしれなかった。だが伝えたにしても全てを伝えたわけではなかった。まだ温羅の蹴速と呼ばれる秘密の技があったのだ。
この技は普通の肉体能力では使うことが困難だったことから、表の蹴速としては伝えなかったともされている。だから裏の蹴速と呼ばれたのだ。
鬼の温羅一族の肉体は人としては異常なほどの強靭さと力だったらしい。その異常な肉体能力を前提にした技が温羅の蹴速である。
だがいつの時代かに鬼変薬が生まれた。結局この鬼変薬は太古の鬼の温羅一族の肉体能力を再現するための薬だったのかもしれない。温羅一族はその二つ名の通り、人には真似できない鬼の肉体能力を持っていたのだ。
鬼変薬の登場によって温羅の蹴速は再び意味を持つようになった。その技は代々の巨勢宗家次男にしか伝えられない隠し技になったのだ。鬼変薬を試すことがない惣領には無用の技だからである。
その温羅の蹴速を椎根津は渦彦に伝えようとしているのだった。
「お前がこの先、鬼変薬を試さぬならばこの温羅の蹴速は無駄になる。温羅の蹴速はわしの代で途絶えることになろう。それはそれでよい。それでもわしが温羅の蹴速を渦彦に伝えなあかんのは、それは……古瀬稀人が温羅の蹴速をも盗み取っているからや」
椎根津の言葉に渦彦は驚愕した。宗家に生まれた自分さえも知らぬ蹴速術を、他家の稀人がすでに修得している。
「なんでそんなことがあるんですか。叔父上が教授されたんですか」
渦彦の質問に椎根津は悲しそうに首を振った。
「稀人が誠に武芸の天才であったということが、このときはっきりした。わしが教えぬ温羅の蹴速を稀人は目で盗み取ったんや」
まだ稀人が椎根津の弟子だった頃、毎夜行われていた椎根津のたった一人の修練を、稀人が盗み見ていたのだった。
夜の修練には表の蹴速もあったが、ときに温羅の蹴速が修練されることもある。無論椎根津は稀人が見ていることなど知らぬままに、全力の温羅の蹴速を修練した。
武術には見取り稽古という方法がある。言葉や手取り足取りではなく、ただ先人の動きを見て、その技を理解し目に焼きつける。そして技を複写するのだ。
並の修行者にはまず不可能な修練だが、稀人のような天才にはそれが可能だった。稀人は椎根津が教える表の蹴速のみならず、温羅の蹴速さえもその目で盗み取っていったのだ。
それがはっきりしたのは、四年前に稀人が道場から出奔したときだった。
理由もいわぬまま、ある日稀人は道場から姿を消した。その三日後の夜、再び道場に戻ってきた稀人は一つの要求をした。
「先生には何の遺恨も不満もありませんが、ただひとつ心残りがあって戻ってまいりました。ぜひとも私と蹴速でお立ち会いください。私は自分がどこまで強くなったのかを知りたいのです。それを知るには先生と戦うしかありません」
二人の間に言葉や問答など必要なかった。それは椎根津もまた長年夢見ていた夢だったからだ。やっと全力の蹴速で戦うことができる。それだけで椎根津にも十分だった。
その夜、決着はついに着かなかった。
椎根津が押したと思えば、稀人もすぐに逆襲した。そして稀人が満を持したように温羅の蹴速を繰り出してきた。
椎根津はまさかと思ったが、それは紛れもなく温羅の蹴速、撃ノ壱・鬼神蹴りだった。究極の速さと感知不能な角度から相手を襲う殺人技である。椎根津がその技に倒れなかったのは、稀人が鬼変薬を飲んでおらず鬼の肉体能力を持っていないからに過ぎなかった。
稀人が温羅の蹴速を使ってくることは想像の外だった。
自然と椎根津も温羅の蹴速を使って応戦した。撃ノ弐・打神脚、撃ノ参・空震弾と技を繰り出したが稀人は見事に受けていた。
稀人が温羅の蹴速を修得しているのは明白だった。
いつ終わるともしれぬ二人の攻防が続く中で、稀人は急に戦いの構えを解いた。そして満足したようにその場に正座した。椎根津に対して深く深く頭を下げていた。
「ありがとうございます。これ以上やればお互いの技に倒れる前に、温羅の蹴速に身体の方が持ちますまい。しかし私は先生に匹敵するほど強くなれたと自分を確信しました。あとは鬼の身体を手に入れるだけです」
それだけを告げると、稀人は来たときと同じように風のように道場から去って行った。
椎根津は後を追うこともできずに、その場に倒れ込んでいた。普通の身体のまま温羅の蹴速を濫用したことで、身体中の筋肉や骨が悲鳴を上げているのがわかった。
「叔父上は鬼変薬に適合しているのでしょう。鬼神術が使えるのになぜ稀人と互角に終わったのですか」
渦彦の問いに椎根津は残念そうに説明した。
「鬼変薬に適合したというても一度だけのこと。鬼変薬の肉体強化、鬼化の効能は一刻ほどで終わるんや。一度薬を飲めばずっと鬼化されるわけではない。普段は普通の肉体に戻ってしまう。そやから昔の兵士は戦いの前にだけ鬼変薬を飲んで鬼神術を使うたらしい」
椎根津の説明に渦彦は少し不満げな表情を見せた。命をかけて鬼変薬に適合しても、効果が一刻ほどしかないという。そんな一瞬に命をかける意味などあるのだろうかと思った。そのために兄は健康を失っているのだ。
椎根津も渦彦の気持ちはわかったが、まだ語っていない恐ろしい事実があった。それは鬼変薬に適合したとしても、鬼変薬を幾度も服用すればやがては不適合と同じような障害が体に起こるということである。
結局のところ、それは人を超える力を得たための負債を後で支払うようなものである。世の道理はそうやって保たれているのかもしれなかった。
「お前が温羅の蹴速など必要ないと考えるなら、敢えて伝授はせえへん。そやけどこの後、もし稀人と戦うつもりなら必要な技になるやろう。それに今のお前は四年前にわしと最後に戦うたときの稀人よりも弱い。それは温羅の蹴速以前の段階で、表の蹴速で稀人に劣ってるいうことや。今遣り合えばお前は必ず負けてまう」
椎根津の残酷な宣告だった。渦彦の心は様々な思いに分裂していった。
今のままでは父の仇かもしれない古瀬稀人には勝てない。それは椎根津に改めていわれなくても、先日の隠居所での戦いで実感していた。二、三手の技を合わせただけだが、その感じた強さは確かに異常だった。今は戦っても勝てないかもしれない。
しかも自分の命は兄の綿津見が身を犠牲にして守ってくれたものなのだ。なのに今温羅の蹴速を学べば、いつの日か鬼変薬を試し、鬼神術を求めることになるかもしれない。その一歩目が温羅の蹴速の修得である。
どうしてよいのか渦彦は迷いに迷った。どちらを選択しても悔いが残るだろうと思う。
心底誰かに相談したいと思った。
初めに浮かんだのは兄の顔だったが、同時に兄はダメだとも感じた。兄は自分の健康や命を賭けて渦彦を守ったのだ。この先鬼神術を求めることをよしとはしないだろう。
次に浮かんだのは何故か籐伍の顔だった。
緊張感のない顔で笑っていた。あまり役立ちそうには思えなかったが何故か心がほっとした。そして前に語っていた籐伍の夢の話を思い出した。
「ほんまは奉行所の役人仕事は好きやないけど、好きなことをするためには背負わなあかん重荷もあるんや。それを投げ出したら、好きなもんも面白うは感じんようになってまう。この世に生きるということは、好きなもんだけやとあかんのやと思う。そやからわいは奉行所仕事をしながら、芝居を書こうと思うてるんや。いつかこの鬼没盗のことも、渦彦のことも芝居にしようと思うてるで。そう考えると奉行所の仕事も面白うに感じるし、芝居を見る目も変わった。浮世には芝居以上におもろいことがいっぱいやと気がついたんや」
能天気な籐伍の考えだったが、どこか柔らかさを感じる言葉だった。何もどちらかだけと思わなくても良いのだ、二つが両立する新しい道を探せば良いと教えてくれいていた。
「あのボーッとした籐伍が、たまには良いことをいう」
そう思うことにした。そして自分に正直な道を探そうと思った。
それは巨勢宗家の次男としての役目を果たし、同時に兄の思いにも答える生き方だった。もし本当に古瀬稀人が父の仇なら、たとえ自分の方が弱くても必ず仇を討つ。それが並び立つ生き方を探そうと決心した。
そのためにも温羅の蹴速は必要だった。今は巨勢宗家の次男の役目と、古瀬稀人に近づくために温羅の蹴速を学ぼう。そして必要がなくなれば封印しようと思った。自分のような思いを誰にもして欲しくないと思った。
何かを決心したように渦彦は立ち上がると、徐に鬼骨の構えをとった。それは椎根津に温羅の蹴速を催促する意志表示だった。
「ほう、ええ顔になったな。迷いがのうなっとる」
そう呟いた椎根津は、それまで渦彦が見たことのない速さで肉迫してきた。そして何をどうされたのかも分からないうちに、道場の端まで吹き飛ばされていた。何故か背中に大きな激痛が走っていた。
「撃ノ壱、鬼神蹴りや。まずはこれを見切れ。他の技はそれからや。時間がないから連続で行く。まずは動きに着いてこい」
そこから数え切れないほど、渦彦は蹴り飛ばされ続けた。夜に始まった修練だったが、それは本当に夜が明けようかという頃まで続いた。
だが外で千鳥のさえずりが聞こえ始めたとき、椎根津の描く鬼神蹴りの軌跡が一瞬見えたような気がした。その軌跡は千鳥のさえずりの「ちっちっちっちっ」という声に、どこか同調しているように感じた。
渦彦はさえずりの調子の先を読むように、鎧脚で鬼神蹴りを防ごうと動いていた。そして初めて鬼神蹴りを彈くことに成功した。
だが同時にもう次の鬼神蹴りが渦彦の背後から襲ってきていた。渦彦は再び道場の端まで吹き飛ばされていた。
「ひとつ止めたからと安心するんやない。鬼神蹴りは相手が立っとる限り襲い続けるんや。ならばどうする」
答えは単純だった。相手が鬼神蹴りを放てないようにするまでだった。その夜初めて渦彦は攻勢に出た。そして鬼神蹴りが渦彦に至る瞬間に、稲妻脚を椎根津に向けて蹴り上げていた。相打ち覚悟の蹴りだったが、その蹴りで椎根津は少し退き、渦彦は鬼神蹴りの衝撃に耐えていた。椎根津が退いたことで鬼神蹴りが弱まっていた。
この夜初めて椎根津の攻撃が止まった。
「今夜はここまででええやろ。わしも少し無理しすぎたみたいや」
そう呟く椎根津が、その場に座り込んでいた。普通の肉体で温羅の蹴速を連発していた椎根津は、遠に限界を超えていたのだ。そのまま崩れるように横たわっていった。
「叔父上」と叫びながら、走り寄った渦彦はそこに意識のない椎根津を見た。こんな姿の叔父を見たのは生まれて初めてのことだった。
この夜の修練は椎根津にも過酷なものだったのか、夜が明けるまで目覚めなかった。
だが道場に門弟がやってくる刻限になると、椎根津は誰かに起こされたかのように目を覚まし、普段通りに門弟の稽古を見ていた。渦彦は恐るべき精神力だと思った。まだ温羅の蹴速の影響で身体は軋んでいるに違いなかったが、それを誰にも悟らせはしなかった。
そして夜になると、再び渦彦との温羅の蹴速の修練に臨んでいた。二人の修練を垣間見た綿津見は、まるで椎根津が自分の命を削りながら稽古をつけているように見えた。
温羅の蹴速は、鬼変薬を服用せぬ限り使う方にも苦痛を強いる。しかし渦彦に温羅の蹴速の全てを伝えるためには、椎根津は自分の身を犠牲にしても厭わぬ覚悟のようだった。それが椎根津に残された最後の仕事であるかのような覚悟と悲壮な姿だった。
十日ほど過ぎた頃、綿津見は温羅の蹴速の修練を休むように懇願した。そして今までできなかった話をしたいと求めたのだった。
「まだお前の質問には答えておらなんだな。よかろう、今宵はその時間に当てよう」
そう了承した椎根津は夕餉のあとの時間を話に当ててくれた。
「古瀬稀人は父上との面識があったのでしょうか。鬼変薬はともかく、神社の仙薬洞から奪われたらしい物もあります。それは鬼没盗が盗みに入るときに使われた夢沈香です。父上が渡したとは思えまへん。何故古瀬稀人は夢沈香の存在を知っていたのでしょうか」
それは綿津見と籐伍の共通の疑問だった。渦彦が温羅の蹴速の修練をしている間、二人はこれまでの鬼没盗事件のあらましを話し合い共有していた。そしていくつかの疑問を導き出していたのだった。
椎根津は少し考え込んでから自分の推察を語った。
「兄上と稀人は知らん間柄ではないやろうな。わしからの使いとして葛城山にも行ったことは幾度かあるし、稀人自身が神社の薬を知人のためと称して贖ったこともあるらしい。それに……稀人の古瀬家には蹴速以外の戦の方法も伝わっておったようや。夢沈香は元々戦の際に使われた相手方陣内への撹乱方法のひとつと聞いたことがある。古瀬家に夢沈香の存在が知れていても不思議やないやろう。それをどうやって奪ったかは謎やがな。一番単純なんは盗みに入ることやろうか」
どの段階、どの時期から古瀬稀人が鬼没盗の一味と繋がっていたかはわからないが、警戒の薄い徳陀子神社から何かを盗み出すのは難しくはないだろう。それが口伝ではなく、冊子に記された調合法だと尚更である。
「では、稀人は我が巨勢宗家の内情をある程度知っていたということですか。ならば再び鬼変薬を奪いに神社を襲うこともあるということでは」
だがその質問には椎根津はしばらく答えなかった。稀人がどこまで鬼変薬に執着しているのかは不明だが、兄の飫肥人が死んだとなればその可能性は低いと思っていた。
当然神社も何らかの警戒をするだろうし、実弟である椎根津の耳にも入る。そうであれば神社を襲うことはさらに難しくなる。もし椎根津が警戒にあたれば、今度こそ師弟の決着をつけることになる。そのとき必ず稀人が勝てる保証はないのだ。
もし椎根津が鬼変薬を用いれば普通の肉体の稀人には勝ち目は薄いだろう。そんな理由から椎根津は神社襲撃の可能性は低いと考えていた。
話を聞いていた籐伍にも疑問があった。
「わいには今だに古瀬稀人が殺しをするような人間には思えんのです。鬼没盗も死人を出してません。渦彦との戦いでも勝ててたかも知れへんのに、さっさと逃げてもうてる。何や殺しは避けてるようにも見えます。叔父上殿の話から強うになることには貪欲やけど、それ以外のところではあんまり無理強いをしてません。それに……」
籐伍は話の腰を折ることを恐れるように、基本的な疑問を口にした。
「何より何で稀人は骨董品ばかりを奪う盗賊をしてるんかが不思議なんです。稀人は昔から骨董が好きやったんですか」
素朴な籐伍の疑問はいつも何かの扉を開ける切っ掛けになった。
少し考えた椎根津は、自分でも忘れていたある伝承を思い出していた。
「稀人は武辺の男やったから、骨董好きということはないやろ。ただ鬼変薬のことを話してて、今思い出したことがあるわ。それは……鬼変薬の出自に関する伝承や。鬼変薬を巨勢に齎したんは、聖徳太子やいう言い伝えがあるんや」
椎根津の言葉に籐伍と綿津見は驚いた。鬼没盗の狙う骨董が聖徳太子絡みの骨董ではないのかという推測があったからである。
椎根津はその言い伝えについて語った。
「鬼変薬も元は支那からの渡来の薬やという伝承がある。聖徳太子の周囲には支那や韓の人間が仰山こといてて、まず薬は太子の元に齎され、そして太子の腹心やった巨勢にも伝わったという話が残ってる。巨勢としては自分たちで生み出したとしたいとこやが、どうも元はその辺りからの薬らしい。巨勢のご先祖様はそれを自分たち用に改良したんやろ。稀人はその辺りの経緯をどこかで知ってるんかも知れへん。巨勢から奪えなんだ鬼変薬を、伝承の中から探すつもりで手がかりを太子絡みの骨董に求めてるんかもしれへんな」
籐伍はそうかもしれないと思った。渦彦の父を死なせたことで、鬼変薬にはおいそれとは手が届かなくなった。
ならば巨勢の鬼変薬が生まれた頃の痕跡を探したらどうなるのか。稀人はそこから鬼変薬を再現しようと考えたのかも知れない。
だとしたら必ずそうしたことに詳しい協力者か黒幕がいるに違いなかった。飛鳥や聖徳太子の歴史も薬の製法も、素人が手に負えるような物ではない。だが鬼没盗は聖徳太子の痕跡を集めるように盗みを続けている。きっと鬼変薬再現に向かう道筋を示している人物がいるのではないのか。
「だとしたら、古瀬稀人と鬼没盗はまだまだ盗みを続けるいうことです。この前捕まえた賊はただの尻尾や。稀人か黒幕を捕まえん限り、鬼没盗は止まらんいうことやで」
籐伍は嘆息するように呟いた。それに渦彦が嬉しそうに答えた。
「それはわいらには好都合や。また稀人と戦る機会があるいうことや。今度こそ鬼没盗と稀人を捕まえたる。籐伍もそうしたいんやろ」
渦彦が能天気な希望をいうと、逆に籐伍が渋い表情になった。その鬼没盗を追う手掛かりが今は途切れているのだった。
どこかで二人の性格が影響し合っているようだった。能天気な籐伍の考えを渦彦が吸収し、渦彦の責任感を籐伍が持ち始めていた。
「もしも本当に古瀬稀人や鬼没盗が鬼変薬の独自再現を考えてるんやったら、彼らが大坂を根城にしているのも少し頷けます。大坂はこの国すべての薬種が集まる場所やし、また医術や薬方に長けた人物も仰山こといます。それに西洋の知識を持つ蘭方の学者や塾も多いと聞きました。鬼変薬を研究するには格好の場所です。できれば私も蘭方医たちと鬼変薬や仙薬について語ってみたいものです。私の知らない知識と意見を戦かわせたらどんなに楽しいことか……」
綿津見の夢見るような呟きに、渦彦は「えっ」と思った。兄のそうした夢を渦彦は知らなかったのだ。
確かに綿津見は今まで葛城山を出ることがなく、また外の世界で勉強することもなかった。健康のこともあるが、生まれてからずっと巨勢宗家の惣領として葛城山に閉じ籠るような生活である。外に出るのはいつも渦彦の役目だった。
渦彦は京で修行の日々も体験しているし、大坂で探索の苦労もしている。だが綿津見には千年前からの知識と宗家の仕来りだけがあった。
本当は綿津見にも外の世界で自分を試してみたいという夢があったのだ。ただその夢は家族のために心の奥底に押し込めているのだった。
そんな兄弟の思いを知らぬ籐伍が能天気な提案をした。
「綿津見殿も大坂に来はったらどないですか。そしたらわいも随分と助かります。鬼変薬を作るいう鬼没盗や古瀬稀人を探すには綿津見殿の薬の知識に頼るしかありまへん。渦彦は少彦名神社や隠居所の居候やから無理やろうけど、わいの家には空いてる部屋もありますよって、いつまででもいてください。父上も歓迎すると思います」
あっけらかんと籐伍が、良い思いつきだというように皆にいった。巨勢家の三人は、戸惑ったような顔をすることしかできなかった。
(四)
椎根津との話で判明したのは二つの事実だった。
ひとつは鬼没盗に加わっている古瀬稀人の存在が判明したこと。
そして彼らが飛鳥や聖徳太子絡みの骨董を盗むのは、巨勢家の仙薬の一つ、鬼変薬を再現する手掛かりを求めてかも知れなということだった。
籐伍は新たに判明したことから、この先どう鬼没盗を追い詰めようかという思案を続けた。
その間も渦彦はひたすら椎根津との温羅の蹴速の修行に勤しんでいる。籐伍はその修練を見ることは許されなかったが、その壮絶さは想像できた。毎朝修練を終えた二人が、意識を失うように寝床に倒れ込んでいった。
だが椎根津はその一刻ほど後には、もう猿飛陰流の門弟の稽古を見ているのだった。籐伍は椎根津が本当に倒れるのではないのかと心配になった。
桜井の道場に来てから昼間は手持ち無沙汰なこともあって、籐伍は猿飛陰流の稽古に参加することが日課になっていた。
勿論籐伍の剣術は中条流平法だったが、他流派の剣士と稽古することは色々と勉強になった。そもそも他流派の剣士と剣を鍛える機会などそうそうあることではない。
自流では当たり前のことがここではそうではなかった。籐伍は剣の技以上に、世の多様さということに気がつかされていた。正解は一つではないのだとつくづく感じていた。
そんな籐伍だったが、そろそろ大和探索の期限が近づきつつあった。西町奉行所の当番月までには大坂に戻らなければならなかった。
ある日、温羅の蹴速の修練から目覚めた渦彦にそのことを相談した。当然渦彦の温羅の蹴速の修練に終りというものはないだろ。武芸とは本来果てしないのだ。もし渦彦がまだ修練を続けるつもりなら、大坂へは一人で戻ろうと考えていた。
だが案に相違して、渦彦もまた籐伍と一緒に大坂に戻るつもりだと語った。今渦彦の第一の目的は温羅の蹴速の完全修得ではなく、鬼没盗や古瀬稀人との決着をつけることだった。渦彦は何よりも稀人に問いただしたかったのだ。
「本当に鬼変薬を奪うために、父を殺したのか」ということを。そのために温羅の蹴速を学んでいると籐伍にいった。
たとえまだ稀人に勝てずとも、一撃入れるぐらいではないと稀人と話もできない。それは巨勢宗家に生まれた蹴速術継承者の誇りでもあった。
今の状況では、むしろ稀人の方が蹴速術の継承者といっても過言ではない。表の蹴速で渦彦を上回り、温羅の蹴速をも使いこなしているという。
渦彦の中では鬼没盗捕縛や父の仇を討つということ以上に、稀人との間で蹴速術継承者を争う戦いのようにも感じていた。
それに……渦彦はまだ誰にもいってはいないが、不気味な畏怖を感じていた。それは「稀人は巨勢宗家そのものを奪おうとしている」という漠然とした恐怖だった。
蹴速術は稀人の方が渦彦よりも優れ、また鬼変薬も再現しようとしている。もしも温羅の蹴速と鬼変薬の両方を手にして、究極の鬼神術を使えるようになった稀人は、もはや巨勢宗家そのものといってもよいのではないのかと思った。
千年間一族が守ってきた巨勢宗家を、古瀬稀人はたった一代で作り上げようとしている。そして巨勢の宿命さえも奪おうとしていた。そんな漠とした恐怖だった。
かつて稀人が椎根津に語ったという、「天はなぜ何の役目もない自分にこのような才を与えたのか」という嘆きが、何故か恐ろしい略奪宣言のように思えていた。稀人の天才は技や薬だけではなく、人や一族の運命まで奪おうとしている。それはもう人ではなく魔物か鬼神のようだと思った。
古代中国、殷の時代に四凶の一つとされる「饕餮(とうてつ)」という鬼神がいたと伝説は語る。饕餮はこの世にあるすべての物、食物から財産まで何でも喰らい、やがて世の善や悪、神や魔までも喰らったといわれる。殷の青銅器や玉器にはこの饕餮を謳う饕餮文が刻まれていたらしい。
渦彦は幼い頃に父からこの饕餮の伝説を聞いて、恐ろしさで眠れなかった思い出があった。今はその伝説を思い出していた。
「古瀬稀人はまるで饕餮のようだ」
その饕餮と渦彦は戦おうとしているのだ。神代の世界の話だと思った。
「三日後に籐伍と共に大坂に戻ります」
翌日温羅の蹴速の修練の後に、渦彦は椎根津にそう告げた。それはいよいよ稀人と戦うという宣言に等しかった。
椎根津はただ「そうか」とだけ応えて、何故か初めて渦彦に対して深く頭を下げた。
「わしの過ちの尻拭いをさせるようですまぬなぁ。稀人は誠に強いが、決してお前が勝てぬ相手ではあるまい。必要なのは一度、蹴速を忘れることや。個々の技に固執しては動きを読まれる。要はいかに天衣無縫に戦うか。特に自分よりも優れた相手とはな。お前が知る技は稀人も全て知る技と思え。そうすれば稀人の先を取れよう。わしからの最後の教えや」
そして稽古場の板間に正座すると渦彦にも座るようにいった。
「これより名渡しの儀を行う。わしは今日より巨勢椎根津の名を捨て、お前に渡す。椎根津の名は巨勢宗家の次男が代々受け継ぐ名前や。この名を名乗る者こそ、巨勢家伝の蹴速術継承者と認められるんや。今すぐやのうても構わへん。お前が真に蹴速術を継承できたと思うたとき、椎根津を名乗れ。わしもそうやった。それまではわしも昔、渦彦やった。渦彦から椎根津に名変わりすることこそ継承の儀や」
これまで渦彦も知らなかったが、叔父もまた若い頃「渦彦」と呼ばれ、真に継承がなったときに椎根津と名乗ったのだった。そうやって代々、椎根津の名を?いできた。重くそして捨てられぬ、一族の宿命を繋ぐための名前だった。
渦彦は自分が椎根津を名乗る日が本当に来るのだろうかと思った。それは少なくとも古瀬稀人に勝てなければ名乗れない名前だと感じていた。
三日後、籐伍、渦彦、綿津見の三人がいよいよ桜井の道場から葛城山に出発しようとしたとき、椎根津は今までに見せたことがないような優しい笑顔で見送ってくれた。
「叔父上、古瀬稀人と決着したならまたここに戻ってきます。そしてそのときこそ完全なる温羅の蹴速をご教授ください」
決意を語った渦彦に、椎根津は微笑むだけだった。応とも否とも答えなかった。
ただ椎根津は三人へ順に言葉をかけた。
「籐伍殿、あなた様は誠に良き男や。この後も綿津見や渦彦の良き友でいてくだされ。我が兄飫肥人に成り代りお願い致す。鬼没盗捕縛というお役目の成就を願っております」
綿津見には一冊の本を渡した。
「これは兄上が亡くなる前に借りてた本や。返しそびれてたさかい、代わりにお前に返すわ。お前は身体は弱いが心が強い。それは昔から変わらんええとこや。この後も惣領として皆の頼りになるんやで」
そう笑いながらいうと、今度は渦彦の方に顔を向けた。何かをいおうとしたが、「やめた」とだけ呟いた。
渦彦に掛ける言葉はもうないようだった。今日までの温羅の蹴速の修練で、もう十分に語り尽くしていると思ったからだ。言葉以上に、交わした技の数々で二人はずっと語り合っていたのだ。それに渦彦に渡すべきものはもう全て渡したと満足している。
渦彦にもそのことがよくわかった。後は椎根津から受け取ったものをどう活かすかだけだった。
「では叔父上、葛城山に帰ります。冬には好物の葛城の干し柿を届けますので楽しみに待っていてください。それまでご健勝で」
綿津見の挨拶に頷き、三人が見えなくなるまでずっと道場の前で見送ってくれていた。
道場からしばらく歩き、椎根津の姿はもうとうに見えない処まできていた。だが渦彦は名残惜しそうに、道場の方を何度も何度も振り返っていた。
椎根津は生まれてからずっと渦彦の師だった。厳しすぎることもあったが、今はその意味がよくわかる。椎根津は巨勢宗家次男の持つ過酷な運命に負けぬように、渦彦を鍛えてくれていたのだ。
振り返った渦彦の視野が何故か涙で滲んでいた。
「あれ、変やな。何で涙が出てるんやろ」
渦彦は自分が涙を浮かべていることを不思議に思った。
三年前に家族と離れて、京へ神人修行に旅立つときも涙は流さなかった。なのに今は不思議と涙が出てくる。
籐伍はそんな渦彦を見ながら、少し揶揄うような調子でいった。
「名残り惜しいんやったら、今から桜井に戻ってもええんやで」
そう軽くいった籐伍だったが、不意に何かに気がついたようにその場に立ち竦んだ。
「あっ、あかんわ。これはあかんかもしれへん……。何で今まで気づかへんかったんや」
籐伍の様子に驚いた綿津見が、不思議そうに顔を覗き込んできた。
「籐伍殿、どないしはったんですか。何ぞ忘れもんでも」
そう問う綿津見に籐伍が慌てた様子で答えた。
「わいの考えすぎやったらええんやけど……、叔父上殿のことが気にかかります。もしかしたら叔父上殿は……」
籐伍のいわんとすることが綿津見にもわかった。籐伍は椎根津が自害するかもしれないといっているのだった。
確かに最後の挨拶は少し奇妙に感じていた。まるで二度と会えないようないい方だった。それに椎根津は最初に、「この責は全て自分が背負う」といっていたではないか。
今は渦彦に蹴速の全てを伝えたのだ。自分の役目がそれで終わったと思ったのならば、後は責任を取るだけだった。
古瀬稀人を生み出した責任。
禁忌を破り蹴速術を外の人間に開示した責任。
そして何より兄である飫肥人を死なせてしまった責任。
椎根津が自分を責める罪過は幾つもあった。
そのことに気がついた綿津見は、急いで桜井に戻ろうと踵を返した。それを制した籐伍は、渦彦に向かって叫んでいた。
「お前が一番足が速い。とにかく道場に戻って叔父上殿の無事を確認せえ。わいは綿津見殿と戻るさかい。一刻を争うかもしれへん、とにかく急げ」
言葉の意味を理解した渦彦は、「先に行きます」と兄に叫ぶと全力でその場から走り出した。
その後ろ姿を見ながら、籐伍は綿津見に肩を貸して早足で桜井への道を歩き出した。自分の不安が杞憂であってくれと、籐伍は生まれて初めてどこか空の彼方にいるという神仏に向って祈っていた。
渦彦が息を切らせながら道場に駆け込んで行くと、そこに人の気配はなかった。いつもなら猿飛陰流の稽古をしている刻限である。
「叔父上どこですか」
叫びながら家の中を探したが椎根津はいなかった。そして最後に稽古場に入っていくと、その真ん中に座っている椎根津を発見した。
椎根津は稽古着ではなく、葛城山にいた頃の白装束の姿をしていた。
「叔父上、ここにいてはったんですか」
渦彦は嫌な想像を打ち消すように軽い調子で語りかけ、椎根津の座る正面に回った。
そこで前屈みに倒れ込んでいる椎根津の姿を見た。武家ではない椎根津は腹を切ってはいなかったが、小太刀で首筋を鋭く断っていた。
どす黒く流れる血が辺りに広がっていたが、少し時間が経っているせいか稽古場の板敷の色と同化しようとしていた。
稽古場に入った瞬間から血の広がりは見えていた。だが渦彦はそれが見えていないかのように椎根津に話しかけていたのだ。
渦彦は椎根津の前に座り込んでしまった。何をしてよいのか全くわからなかった。
ただただ座り込むことしかできず、そして声さえも出せないまま、本当に大粒の涙が止めどなく頬を流れ落ちていった。
どのくらいの時間、渦彦がそうしていたのかはわからなかった。
ふっと気がつくと自分の後ろには兄と籐伍が立っていた。
「兄上、これは誰のせいですか。叔父上は何で死ななあかんのですか」
答えなど分かっていたが、そう聞かずにはいられなかった。
渦彦と綿津見は半年前の父に続いて、今また叔父も失ったのだ。
「叔父上殿を横にして楽にしたれ。ほんで二人はここで弔いや。あとのことは全部わいがするさかい、二人は叔父上殿をゆっくりお見送りせえ」
それだけを告げると、籐伍は振り返らずにその場を後にした。
これからするべき仕事を一つ一つ頭に思い描いた。そうしないと籐伍も悲しみで心が折れそうだと思った。
短いとはいえ、籐伍もまた椎根津の弟子だった。桜井に滞在中は猿飛陰流の稽古に加わり、師弟の礼もとっていた。その師が今亡くなったのだ。
自分の悲しみなど、二人に比べれば小さなものだと思おうとした。それでも知らぬ間に籐伍の頬が涙で濡れていた。その涙を無理やり拭うと自分の顔を両手で叩いた。
「今はわいがしっかりせなあかんのや。二人をこれ以上苦しめたらあかん」
そう思うと、籐伍は急いで一番近い家に向かって走っていった。
まずは椎根津の弔いの用意が必要だった。その後は猿飛陰流の門弟たちにも知らせ、この地の名主にも告げる必要があるだろう。そんな細々とした仕事が次々にあるのだ。それは全部自分の役目だと思った。
思わぬ椎根津の自害を受けて、三人はそのまま葛城山に戻ることはできなくなった。結局は初七日を終え、さらに様々な事後処理をしたところで、三人はやっと葛城山への帰路につくことができたのだった。
綿津見のためにゆっくりと歩んだ道のりだったが、もう徳陀子神社に着こうかというときに綿津見は籐伍と渦彦に決意を告げた。
「父上の死と叔父上の自害で、私も少し思うところがあります。これは私からの願いなのですが、鬼没盗、いえ古瀬稀人の探索に私も加えていただきたのです。この件はもはや父上の死の謎解きという以上に、巨勢宗家の問題になっていると思います。そやから惣領の私の手で決着をつけたいのです。籐伍殿や渦彦には迷惑をかけるかもしれませんが、何卒、私の願いをお聞き届け願いたい」
その言葉には綿津見の決意が滲んでいた。
徳陀子神社に戻った綿津見と渦彦は久々に母に会い、そして叔父椎根津の死の顛末を語った。椎根津の死は手紙で知らせていたが、その経緯は詳しくは知らせていない。父の死と、叔父の自害が関連しているかもしれないという事実に、母も言葉を失っていた。
さらに綿津見は「この謎と原因を究明するために、私は大坂に探索に行くつもりです。これは巨勢宗家の棟梁の役目と存じます」と宣言した。
綿津見には珍しく、相談ではなく決めたことだと宣言したのだった。それに綿津見は初めて自分のこと棟梁といった。それまでの惣領という一歩引いた表現ではなかった。
母は言葉を失ったように、しばらく黙ったままだった。張り詰めた空気を和ごませようと籐伍は母に綿津見の身を請け負った。
「綿津見殿のお身は我が家でお世話させていただきます。うちには姉も二人おり女手は余ってますから、十分にお世話できると思います。どうぞご安心ください」
少しは安心したようだったが、それでも母の不安は拭切れなかった。
「兄さま、大坂に行ってきたらええ。兄さまがいてへん間はうちがお母はんの面倒みるし。そやから心配せんでええで」
突然、部屋の端から声がした。見ると襖から半分だけ顔を出している夕凪がいた。皆がまだ子供だと思っていた夕凪が、このときは不思議に大人びた表情をしていた。
気勢を削がれたような母が、何かを紛議ったように頷いて夕凪を側に呼んだ。そして夕凪を膝に抱きながら、籐伍の方に向かって頭を下げていた。
「阿刀様、息子たちのことよろしゅうにお願いいたします。まだまだ足りんとこがありますが、どうぞよしなに」
そう呟くと綿津見に向かった。
「あんたやっと巨勢の棟梁の顔になったなぁ。棟梁の言葉には従わなあかんからな。あんたの好きなようにしなさい」
そういって初めて少し微笑んだ。綿津見も渦彦も母の微笑みを見て初めてほっとした。
綿津見の大坂行きは決まったが、それなりに不在の間の神社への手当てが必要だった。女だけの神社は無用心である。
綿津見は自分が不在の間の用心に、籐伍を泊めた元神人の老夫妻に神社への一時住み込みを依頼した。老夫妻はその依頼を承諾し、さらに山里の若衆には日替わりで神社への泊り番をするように話をつけてくれた。それでまずは綿津見も安心をした。
もう西町奉行所への帰還期限が真近に迫っていた籐伍が、まず綿津見と共に大坂へ出発することになった。渦彦は二人より何日か遅れて出発することにしたが、渦彦の足の速さと綿津見の足の遅さを勘案したら、到着はそう変わらないだろうと思えた。
それに渦彦にとっては久々の母や妹との生活である。籐伍はその時間を渦彦に与えようと考えたのだった。
大坂の阿刀家には大和より手紙を出し、帰還の日と客人を連れ帰るのでその受け入れ準備を頼んでいた。そうした準備をした上で、二人は大和から大坂への旅路を歩んだのだった。籐伍には二度目の旅路になるが、大和から初めて出る綿津見には全てが物珍しくまた刺激的だった。
大坂の市中に入ってから綿津見はその喧騒と人の多さ、そして繁栄ぶりに目を丸くした。これが日の本一の商都かと感嘆したのだ。
松屋町筋の大坂西町奉行所の前を通り過ぎ、同修町に差し掛かった。
「この辺りが薬の街と呼ばれる同修町です。この奥にあるんが渦彦が世話になってる少彦名神社です」
歩きながら説明する籐伍に綿津見が反応した。
「籐伍殿、少し寄り道してもよろしいか。渦彦がお世話になっているご挨拶もしたいが、薬種問屋や少彦名神社を見てみたのです」
目をキラキラさせている綿津見を籐伍は面白そうに眺めた。
「少彦名神社の手前に茶店がありますよって、そこで休みましょう」
二人が茶店の縁台に座って休息の茶と名物のきな粉餅を食べていると、その前を見知った人物が通り過ぎようとした。
「阿刀様、お久しゅにございます。今日はまたどのような御用でこちらへ」
声を掛けてきたのは少彦名神社の阿曽宮司だった。
「これは宮司殿」
籐伍が立ち上がりながら挨拶すると、宮司は隣に座っていた綿津見の方をチラッと見た。籐伍は仕方ないなと思い綿津見を紹介した。
「実は渦彦を探しに大和に行っておりました。こちらは渦彦の兄上の巨勢綿津見殿です。渦彦とも無事に会えましたので、綿津見殿を大坂まで先にご案内してきた次第です」
そう簡潔に説明すると、宮司の方が驚きそして喜んだ。
「渦彦はんのお兄上ということは大和の徳陀子神社の宮司様か」
そういってから自分の紹介を始めた。
「わてはこの同修町にある少彦名神社の宮司をしてる阿曽と申します。以後よろしゅうにお願いいたします。それで渦彦はんは見つかりはったんですか。それはよろしおました、御隠居様も喜びはるわ。それに渦彦はんのお兄上、徳陀子神社の宮司様にお会いできるとはなんという僥倖や」
綿津見は立ち上がると、何かを察したように挨拶を返した。
「巨勢綿津見です。宮司様には弟が大変お世話になっていると聞いております。誠にありがとうございます。いろいろと事情があり弟はいっとき大和に帰っておりました。弟もおっつけ大坂に戻りますが、先に私が阿刀様のご案内で大坂に参りました。少彦名神社には改めてご挨拶に伺う所存です。ここでお会いできたのは少彦名様のお引き合わせでしょう」
そう綿津見が返すと、宮司も「そうですなぁ。これはまさに少彦名様のお引き合わせや」と嬉しそうに同意した。
「今日はこれから急ぎの用がありますよってここで失礼いたしますが、いずれ改めてお話したい。どちらに逗留されるご予定ですか」
尋ねる宮司に「我が家に逗留していただきます」と籐伍が答えた。
そう聞いて納得した宮司は、「ではまた改めて」と告げて忙しそうに立ち去っていった。籐伍はやれやれというように宮司の後ろ姿を見送った。
「悪い人ではないんですが、私は少し苦手なんです」
呟く籐伍に綿津見も少し頷いていた。
「さすが大坂の宮司様や。大和で見知る神職の方々と違い、まるで商人のように見えますね」
籐伍も成程その通りだと思った。
予定外の邂逅もあったが、籐伍と綿津見は無事大坂に到着したのだった。
幕間ノ挿話
それはまだ大坂に鬼没盗が出来する前のことである。
大坂東町奉行所の組与力、大塩平八郎正高の屋敷に訪問者があった。
大塩は自宅に「洗心洞」という陽明学の塾を開いていた。そのため学問や社会改革を唱える者どもが多く訪れてくる。その日の訪問者もそんな一人だと思い、大塩は対応したのだった。
訪問者はまだ若い男だった。男は自らを江戸の国学者だと名乗り、この国に原初からある正義や夢を探していると語った。
「大塩先生は世の改革を唱えられ、実際に奉行所の施策にも生かされておられる。誠に尊敬いたします。ただ一つ、足りぬことがあると思います。それはこの国が始まったときの大義を考えられておらぬこと。国学者の目でいうならば、徳川の世は長いこの国の歴史の中で、いっとき天朝より任されたる世です。鎌倉や室町の世と何ら変わりはない。ですから徳川の次の世を見据えるべきではありませんか。それにはこの国の原初にあった夢と正義が必要です」
大塩は大それたことをいう男だと思った。だがこの手合いはたまにいた。次に出す卑小な個人的要求の為のはったりの場合が多いのだった。
「またまた、ご大層なる物言いやな。それに一つお間違いになられてはる。私は何も世の改革などは唱えておりまへん。ただ陽明学の摂理に合う、世の正しい運営方法を述べておるだけのこと。徳川の次の世のことなど考えたこともありまへん」
そう返してから、男が来訪したときに出してきた名刺を見返した。
「ところで、何でこの名刺には姓名がないんや。ここに書いてあるんは字名か雅号や。初訪問の相手に出すには不適切な名刺やで」
大塩が手に持つ名刺には中央に「徐市」とあり、その脇には小さく「蓬莱山住人」と記してあった。
大塩の不満げな言葉に、男は同意するように薄く笑った。
「この世での通り名を記せば、先生は多分私の言葉に先入観を持たれると思います。ですから私の立ち位置だけを示す名刺をお出ししました」
自分の立ち位置? と大塩は一瞬訝ったが、確かにその名刺は男の立ち位置を暗示しているようだった。
「蓬莱山とは支那の地にて夢見られた東方の三つの神仙山の名の一つや。他に方丈と瀛州がある。その蓬莱山に棲むといわはるか」
そして再び徐市の文字を見た。そこで大塩はひとつの伝説を思い出した。
蓬莱山に住む徐市といえば連想される人物がいた。
古代支那で秦の始皇帝を誑かし、東方の海に財宝や童男童女三千人と共に消えていった、不老不死の仙薬を蓬莱山に求めたという方士「徐福」である。徐市は徐福の別名か幼名といわれていた。
「立ち位置か、確かにのう。ではこの地に神仙の国を作るといわはるか」
男は大塩がやっと自分の出した名刺の意味を理解してくれたことに、本当に嬉しそうに頷いた。そして一つ訂正を入れた。
「神仙の国ではありません。神の棲まわる国を再興したいのです。昔遥か西方にあったという神の国を。それが私の求める夢であり正義です。太古この国にはその志がありました」
自分の横に置いてある風呂敷包みを徐に大塩の前に差し出した。
大塩が「なんや」という顔をすると、男は真面目な顔で告げた。
「これは私が徐市である証であり、また先生と同志になるための契りの品です。どうぞお納めください」
そう慇懃にうと男は深く頭を下げた。
大塩は包みを解くと、そこに黒塗りの文箱があることがわかった。
男の「どうぞ中をお改めください」という言葉のままに、文箱の蓋を開けてみた。中には古色が深い紙の文書が入っていた。
「これはなんや。私は国学者やないから昔の文には興味はないで。私が欲しいのは未来への指針や」
大塩が皮肉を込めていうと、男は「それはよかった」とだけ呟いた。そして文箱の中の古い紙を徐に広げて見せた。その最初の部分に書かれていた文字を見て、大塩は一瞬体が固まったように思えた。
冒頭には古い墨文字で、「未然本記」と読める字があった。未然とはなんやと最初思ったが、大塩の脳裏に一つの知識が蘇ってきた。
日本書紀にも記されている「太子兼知未然」とある文節だった。
「太子、兼(か)ねてより未(いま)だ然(し)らざるを知る」と読み、伝説では聖徳太子の記した未来予言書「未然記」の記載だとされていた。
「これが未然記やというんか。大嘘にしてもまた面白い物を持ってきたな」
大塩は半分呆れたように声を出したが、同時に面白そうに笑い出してしまった。これまで土産を持ってきた来訪者も多くいたが、こんな土産を持ってきた者はいなかった。本物かどうかは別に、面白い思い付きをする男だと感心した。
「先生が疑われるのはごもっともです。ですがこの書は本物の写本です。幾つかに書き分けられた内の一つのようです。少なくとも四百年程前まではそう信じられていました。おそらく楠木正成公が読まれた物と同じなのでしょう。ただ残なことに、この文書には徳川の世の先の事は記されておりません。それはまた別の書にあるのだと思います。それが手に入れば、また先生にお届けいたします。それこそが先生の求められている未来への指針でしょうから」
そう告げた男は、もう用は済んだというように立ち上がっていた。
男の行動に戸惑った大塩は、逆に男に尋ねていた。
「お主は結局何のためにここにきたんや。何の所望もなく、また論も講じなんだ。そしてこの未然記のみをわしに献じようとする。目的は何なんや」
大塩はなぜかこの男に不気味な恐ろしさを感じ始めていた。知らぬ間にまるで魔物と契約を結んでしまったような怖さだった。
「私の目的はもう果たされました。私は先生の真ん中にあるものを見極めたかったし、感じたかった。この未然本記はそれに対する私からのお礼です。先生は私に対し何もしていただく必要はありません。我らは未来への同志ですが、お互いに独立しています。連携する必要はありません。ただこの後も先生の思われる陽明学による世の運営を押し進めください。それが私の願う神の棲まう国再興への助けともなります」
そういい残した男は、まるで風に吹き消えるように大塩の屋敷を後にしていった。後には呆然とした表情の大塩と、未然記と称される古文書だけが手に残されていた。
大塩の屋敷を出た男が暗闇の中の道を歩んでいた。するとどこから現れたのか、並ぶように黒い人影が寄り添って歩いていた。
「大塩はどうだった。お前の眼に叶ったのか」
黒い人影が突然声を発した。それは意外なほど綺麗な声で、夜には相応しくない太陽の香りを感じさせる明るい声音だった。
男は「ふふっ」笑うと、ちらりと横の人影を見た。その瞳には喜びが溢れているようだった。
「久々に良い人と巡り合えました。私の謎掛けを見事に返された。しかも本当に不動の意志をお持ちのようです。あなたと初めて出会ったときのことを思い出しましたよ。大塩先生はあなたに並ぶ人材です」
男の言葉に人影は嫌な顔をした。人影は他者と比較されたり、並べられることを極端に嫌っていた。それを知っているからこその男の言葉だった。
ふたりは同時に天を仰いだ。そこには凍てついた冬の夜空に大きく広がる、天の川の銀色に輝く帯が煌めいていた。
「お前はいつも天から皆を見下ろしている。あの天の川のようにな。それはお前自身の名がいっていることだ、そうだろ天河。それが本当の名かどうかは知らんがな」
人影の言葉に男は初めて眉を潜めた。その名を呼ばれることが嫌というよりも、誰かに聞かれることを嫌っているようだった。
「人の名は呪のとば口になります。不用意に口にするものではありませんよ。それはあなたにとってもそうです、稀人さん」
天河と呼ばれた男はいい返したが、呪など知らない人影、稀人は気にもかけなかった。
「それより求める物は手に入ったのですか。大和からの帰りがずいぶんと遅かったですが」
天河は隣を歩く稀人に尋ねた。その問いに稀人は渋い顔になった。
「残念だが二つは手には入らなかった。手にできたのは宸翰のみよ。それに求めた仙薬は期待したようなものではないようだ。宗家は自ら仙薬を飲んで俺に挑んできたよ。だが……結局仙薬への不適合からか、戦いの最中に命が尽きてしまった。優しい俺は不適合の苦しみから救ってやったがな」
そうあっけらかんと、大和であったことを天河に語った。
「あんな不完全な仙薬などとても怖くて使えぬわ。宗家の奴らはよくそれを千年も守ってきたものだ。宗家は千年もの間、穴蔵に入ったままで外に出ようとはしていない。だから俺は違う道を行くことにした。お前のいうように皆を等しく神仙に変える薬を新たに作り出す。それが正しいやり方だ。宗家のように過去の虜にはならんさ」
サバサバとした表情で稀人は夜空の天の川に向かって語った。天の川がまるで天河自身であるかのようないい方だった。
「そうですか、わかりました。それでは急ぎ太子と飛鳥の記録を調べましょう。そこにきっと仙薬に至る手掛りがあるはずです。あなたにも当然働いてもらいますよ。元々あなたの夢なんだから」
そういった天河だったが、新しい遊びを始めるときのようなワクワクとした気分になっていた。大坂の街もこれから面白くなりそうだと感じた。
月のない冬の夜空では、天の川の星の輝きが世界を導く燈明のように見えた。それは世界における天河の存在意味を表しているようでもあった。
第五幕 太秦の神紋
(一)
天満橋北の阿刀家に到着した籐伍と綿津見は、やっと大和からの旅装を解くことができた。綿津見も旅の間は気持ちが張っていたせいか不調をいわなかったが、到着した夜より床に着くことになった。
そんな綿津見の世話を甲斐甲斐しくしたのは燕だった。籐伍は少し意外な気がしたが、どうも鈴と燕の間で役目を決めているようだった。
少し後に籐伍は鈴から、燕がどうしても「綿津見様のお世話は私がしたい」と望んだことを聞いた。どうやら鈴の見るところ、燕が綿津見にひと目で懸想したのかもしれないと笑いながら語っていた。
籐伍は綿津見が復調するまでの間に、父念十郎に大和であったことを報告した。話を聞いていた念十郎は「そこまで話してええんか」と巨勢の秘密を公にすることを心配した。
「鬼没盗に関わる人々には知っていてもらいたいと綿津見殿の意向です」
その言葉に念十郎は感慨深げに頷いた。
「綿津見殿はきっと叔父上殿の決意と気持ちを汲まれたんやろうな。自分や渦彦殿を含めた巨勢の人々をいにしえの呪縛から解き放つという、叔父上殿の命を捨てた決断を重んじられたんや。これはできることやないで。千年にも及ぶ家禁を破るんや、綿津見殿は器の大きなお人のようやな」
念十郎の言葉に籐伍も深く同意した。
「叔父上殿の死を無駄にせぬためにも、新たな鬼変薬を作ろうとする古瀬稀人は捕らえねばなりまへん。わいも二人同様に叔父上殿より後のことを託されたんやと思います。それに……わいには叔父上殿がどこかで古瀬稀人もまた救いたいのではないのかと感じました。ですから本来無関係な私にも秘事を明かされたのではないかと思います。巨勢の兄弟にそれを求めるのはあまりに酷ですから」
籐伍の言葉に、念十郎は「ほぉ」という顔をした。そして改めて少し成長した息子の顔を見つめた。
「お前、大人になったなぁ。自分以外がよう見えるようになってるわ」
父親としても与力としても籐伍の成長を認めた言葉だった。
「それでどないするつもりや。確かに鬼没盗首領のことはわかったが、それだけでは鬼没盗にはまだ届かへんで。どうやって捕縛するんや」
念十郎は初めて籐伍に今後の探索指針を尋ねた。
「それは考えています。綿津見殿の回復を待って、共に薬種問屋、医師、薬局などを回るつもりです。綿津見殿によると、鬼変薬を作るには特殊な薬種や素材がかなり必要やということです。それを集める者の情報や、研究する学者を当ります。きっと古瀬稀人や黒幕もそこに接触しているはずやと思います」
籐伍の答えに念十郎は満足したように頷いた。
「お前の好きなようにしたらええ。これはお前の捕り物や」
そして付け加えるように籐伍に告げた。
「お奉行より隠居のお許しがやっと出たわ。まぁ条件付きやがな」
籐伍が「条件?」と尋ねると、念十郎は困ったというように頭を掻いた。
「お前が鬼没盗を完全に捕縛したら隠居してもええいわれたわ。それまでは大坂の面倒をまだ見いいうことや。しくじったら楽隠居もできへんで」
そう苦笑したが、あまり心配している様子ではなかった。念十郎は大人に成長した籐伍を十分に信頼していた。
籐伍もそれにどう答えようかとちょっと迷った。だが結局やることは同じだと思った。
「お役目に精進いたします。それまでは父上も大坂をお願いします。それが我らの務めですから」
力むことなく答えた。それが大人の対応だと籐伍にも理解できていた。
床から復帰した綿津見は、早速大坂市中に薬方の探索に出ようとした。だがそれは籐伍と一緒ではなかった。綿津見の大坂での行動には燕が付き添うことになったのだ。
一つには奉行所役人と一緒では、なかなか核心の話をしてくれないだろうという不安があった。薬には秘事の部分がとても多いのだ。ここは純粋に薬の研究者同士として巡った方が、先方も胸襟を開いて話してくれるのではないかという思惑である。
燕は綿津見の助手兼大坂の案内人として供をするという。女性連れの方が確かに先方も警戒しないだろう。
綿津見は燕を供に連れることを念十郎に許可を求めた。
「お父上様、燕殿を危険な目には合わしまへんので探索の供をすることをお許しください」
念十郎に平伏する綿津見に対して、なぜか燕も隣で両手を付いて頭を下げていた。
念十郎は不思議そうに二人を見ながら、ちょっと困った表情をした。
「なんや、燕を嫁にくれといわれてるみたいやで。燕は小太刀も使えるし、先日の隠居所でも賊と闘うてるお転婆や。なんぼでも供させて構いまへん。お役に立ててください」
そう答えながら、逆に燕に厳しくいいつけた。
「綿津見殿のお身体をきっと守るんやで。大和のお母上様には籐伍がそう約束してるんや。これは巨勢家に対する阿刀家の誓約やからな、破る訳にはいかへん。それに綿津見殿は籐伍の助けのために大坂にいらしたんや。その御恩を忘れたらあかん」
そう念十郎は念を押したが、燕は言葉とは裏腹にどこか楽しそうだった。
こうして綿津見と燕の大坂での薬方探索が始まったのだった。
綿津見との同行を外された籐伍は、改めて鬼没盗の狙いそうな聖徳太子絡みの歴史的遺物を当たり始めていた。大坂、京にありそうな遺物の情報を集めようと考えたのだった。
だがこれはなかなかに難事だった。もともと歴史や骨董には造詣がない籐伍である。骨董屋に聴取するにも勘所がわからなかった。
そうした状況を嘲笑うように、このひと月の間にも鬼没盗は出来していたのだった。
聖徳太子の遺物を追う籐伍と、鬼変薬の研究を追う綿津見。どちらも一朝一夕には探索が前に進まない状況が続いていた。
そんなとき、不意に渦彦から籐伍の元に連絡があった。渦彦は大坂に戻ってからも隠居所にいるようだった。その御隠居が籐伍に会いたいといっているという。囮一座が解散してから籐伍も御隠居には会っていなかった。
久々に隠居所を訪れた籐伍は、御隠居に無沙汰の挨拶と大和でのことを話そうとした。
その籐伍に向かって御隠居は手をあげて話を止めた。
「大体のとこは渦彦から聞きました。誠に難儀な宿命が世にはあるもんやと、つくづくと思いましたわ。そのことはお互いに胸にしまいまひょう。今はこのこと、秘するが華やと存じます。今日は別の話で籐伍様には来てもらいました」
前置きをした御隠居は、籐伍の隣に座る渦彦に向かって語りはじめた。
「渦彦は鬼没盗に邂逅したときに一緒やった清兵衛のことお覚えてるか」
御隠居の突然の言葉に、渦彦は少し戸惑った。渦彦を閻魔の市に送り込んだのが御隠居であることを、籐伍には語っていなかった。
籐伍も誰からも聞いてはいないが、もしかしたらそうかもしれないという想像は持っていた。
「閻魔の市のことはもう気にせんでもええで。隠居所を鬼没盗の囮に提供するときに、お奉行様とは色々と手打ちしたからな。それであのとき眠らされた清兵衛やが、この前面白い話を持ってきたんや」
御隠居は二人に清兵衛の面白い物語を話し始めた。
「あの男も鬼没盗にはえらい頭に来たみたいでな、あれ以来執念深こうに調べ始めたみたいなんや。まぁわてが鬼没盗の囮に協力したいうこともあるやろうが、あいつもなかなかにしつこい性格やからな。しかもお役人の籐伍様の視点とは違いう調べ方やったみたいや」
籐伍は「違う視点」という御隠居の言葉に少し訝しんだ。籐伍の不審げな表情に御隠居は満足そうだった。
「清兵衛は商人でお役人様とは違うから、見える風景もまた違ういうことですわ。清兵衛はもし自分が鬼没盗を組織したなら、どう移動して逃走するかの方法にまず目が行ったようや」
移動や逃走の方法という意味が、二人にはよくわからなかった。
「盗人働きをした後に、どうやって現場から逃れてるんかいうことですわ」
御隠居は謎解きを楽しんでいるように微笑んでいた。
「清兵衛はまず、鬼没盗が出来した夜の月を調べたらしい。もちろん明るい夜より暗い夜の方がええに決まってるが、やはり鬼没盗が出来したんは新月から三日月までの闇夜やったらしい。二人が初めて新町で出会おうたときも二日月やったはずや」
御隠居の言葉に、籐伍は木津川の土手道で初めて対決したときのことを思い出した。籐伍の突き技八艘を渦彦が躱し、逆に渦彦の掌底を小太刀の柄で打ち返した夜である。二人はそれ以来の縁となって、今日まで共に歩んでいるといってよかった。
「まあ闇夜やいうんは予想がつくが、清兵衛にはもう一つ気になることがあったんや。それはあいつの下り酒(上方から江戸へ送られる酒)の商いにも関係するんやが、その闇夜に出帆する船があるいう噂を聞きつけてたらしい。普通なら下り酒は灘郷や西宮からこの大坂天保山に船で運ばれ、そして天保山の港で北前船に積み替えられて江戸に向かうんや。それは早朝か昼間に行われるんが普通や。風待ちなんかでよっぽどのことがない限りな。ところが不思議なことに、鬼没盗が出来した夜に限って闇夜の中で天保山を出入りする船があるいう噂があったんや。慣れた航路とはいえ、これは滅多にないことやで」
籐伍と渦彦は御隠居の話に釘付けになっていた。
「そこで清兵衛はもしかしたら鬼没盗は船で移動してるんとちゃうかと思い至ったらしい。確かに渦彦が新町に出た賊を見失のうたんは木津川の傍やし、この隠居所から大川もまた近い。いやそんなことより大坂中に運河やら堀や川が網の目のように通ってるわ。これだけ籐伍様や奉行所が懸命に探してもその足跡がわからんのは、陸地やのうて川か海を逃げ道にしてるからやないかと考えたんや」
籐伍と渦彦はゴクリと唾を飲み込んだ。それはありうることである。確かに今までいかに陸上の道を塞いでも、それでもこぼれ落ちる賊がいた。何より古瀬稀人を隠居所より取り逃しているのだ。
「もしそうなら、これはなかなかに捕らえることは難しゅうなるで。この大坂中の水主から廻船屋、末は船頭までみんな調べなあかん。清兵衛も流石にここで諦めかけたんやが、実はその先があった」
御隠居は二人の反応を楽しむようににやりと笑うと一呼吸おいた。そして徐に銀の煙管を取り出すと、ゆっくりとその先に煙草を詰めていった。
御隠居の様子に焦れた渦彦が、「それで、その先とは何ですか」と御隠居が望む反応をした。籐伍は「渦彦は御隠居の思うようにされてるなぁ」と可笑しくなった。御隠居は焦れた様子を楽しんでいるのだと感じた。
籐伍も御隠居の楽しみを壊さぬように話の先を求めた。
「清兵衛殿は船に別の目星を持ってたいうことですか」
御隠居は籐伍の方をちらっと見て「さすがやなぁ」という顔をした。
「まぁあんまり焦らしても悪いさかいな、教えたるわ。清兵衛は天保山を闇夜に出入りする船に、不思議な紋所があることを聞きつけてたんや。そう、こんな紋や」
御隠居は二人の前に、懐から見知らぬ紋が書かれた紙を差し出した。
それは不思議な紋所だった。十六菊花紋の真ん中に「太」という字があしらわれている紋である。十六菊花紋というのは本来京の天朝の紋所である。だがその菊花紋の中心部分には「太」の文字が重ねられていた。
この時代、紋所は重要な印である。武家、公家を問わず、商家でさえも紋を使う。そしてその紋は身分証明にもなっているのだった。
籐伍は武士の一般教養としても奉行所役人の業務知識としても、多くの紋所を承知していた。だがこの紋所は知らなかった。
しばらく籐伍が御隠居の示した紋を見ながら唸っていると、横の渦彦がハッと何かに気がついたように籐伍の持つ紙を手にした。
「わい、この紋所知ってるわ。いっぺん見たことがある気がします。確か京にいてるときに天神宮の御用で太秦へ行ったとき……」
紙を天に掲げると、記憶の断片を蘇らせたように断定した。
「これ太秦の広隆寺はんの紋とちゃいますか。同じ紋が提灯にあった覚えがあります」
そういった渦彦に、御隠居が「ほぉ」という驚いた顔をした。まさかこの紋所を知っているとは想像していなかったようである。
「渦彦は凄いなあ。この紋を知ってるとは。わても方々に聞き合わせしてやっとわかった紋やいうのに。やっぱり鬼没盗と渦彦はどっかで縁が繋がってるんやな」
御隠居は不思議な感嘆の仕方で渦彦の解答を褒めた。だが今度は籐伍の方が渦彦の答えに異論を持ち出した。
「ちょっと待ってください。それがほんまやとしても、何で広隆寺はんの紋所が船にあるんですか。京のお寺はんが下り酒商うてるなんて聞いたこともありまへん。しかも闇夜の危ないときに商い船を運行させるやなんて」
籐伍は心に浮かんだ疑問を次々に口に出していった。御隠居は籐伍の言葉に少しほっとしたような顔をした。本来はこうした疑問が溢れてくることを期待していたのだ。
「籐伍様のいう通りですわ。そやけど広隆寺の紋があるんは別の意味からかもしれまへんで。わてら商家の家紋やのうて広隆寺はんの紋があったら、船手奉行なんかの調べはありまへんよって」
御隠居の言葉に籐伍は反論できなかった。確かに寺社奉行支配のものには町奉行も船手奉行も手が出せない。それは籐伍自身が嫌というほど経験したことだった。
鬼没盗がその船に乗っているという確かな証拠でもない限り、船の検閲も乗り込みもできないのだ。鬼没盗が移動や逃走にこの船を使ったなら、まず手出しはできないだろう。
これは盲点だった。幕府の制度を実に巧妙に利用した方法である。
しばらく考え込んでいた籐伍は、まだ残る疑問を口にした。
「しかし偽紋ならばともかく、広隆寺が鬼没盗に協力してるとも思えまへん。それに実際に闇夜に船を運行するんは水主や船頭です。その人たちをどうやって集めるんですか。盗人の仲間集めるんとは訳が違います。皆真っ当な生活をしてる船乗りたちや」
籐伍の最後の疑問に、御隠居は満足そうに頷いていた。
「さすがに籐伍様は世の中がよう見えてはるわ。確かに全部籐伍様のいわはる通りや。真っ当でない者が扱える船なんかありまへん。そんなんは芝居か物語の中だけの話や。船を使ういうんは、金、人、物といろんなものが係ります。信用や金がないとどれも動かせまへん。そやけど逆にそれがある者が真ん中に立ったら、危ない闇夜でも船を出せるし、広隆寺の紋も使えるかもしれんいうことですわ」
じっと二人の話を聞いていた渦彦が声を出した。
「信用ある者って誰ですか。そんな盗人の手助けするような奴は」
少し怒ったような声だった。御隠居は渦彦を愛おしそうに見た。
「江戸の三井家や」
静かにいった御隠居の言葉に、籐伍は一瞬体が固まった。
江戸の三井家、それは目前にいる御隠居の鴻池家に勝るとも劣らない日本屈指の大商人である。確かに三井家ならば広隆寺の紋を利用することも、危険な闇夜に船を出させることも可能だろう。
その大商家が何故盗賊の手助けをするのか。そこが理解できなかった。
その疑問を理解しているのか、御隠居はあえて別のことを語り始めた。
「何で広隆寺の紋のある船を、三井家が鬼没盗のために動かしてるんかはようわからへん。そやけど三井と広隆寺、そして船を動かしてるらしい木乃嶋衆との関係は少しわかってます」
御隠居の「船を動かしてる木乃嶋衆」という言葉に渦彦が反応した。
「木乃嶋衆って何ですか」
「木乃嶋衆は太秦にある木嶋坐天照御霊神社の氏子衆による水主の組や」
太秦にある広隆寺と木島坐天照御霊神社(通称「蚕ノ社」)は大変近い場所にある寺と神社である。そしてこの寺と神社は同じ時期に同じ一族によって建立されたといわれていた。つまりこの二つは寺と神社の別はあっても、ほぼ同一の存在といってもよかった。
広隆寺は寺伝によると推古一一(六〇三)年に秦河勝によって建立されたとされている。建立当初は蜂岡寺とか秦公寺とも呼ばれていた。それはまだ京に都(平安京)が遷都される二百年も前のことである。それゆえ広隆寺は京で最古の寺とされている。
また木嶋坐天照御霊神社も同じ時期に、やはり河勝と同じ秦氏によって建立された秦氏の氏社である。正確な年号や建立者はわからないが、この頃まだ辺境の地であった山城国の太秦一帯を、秦氏が開墾していたらしい。そのため太秦近くに松尾大社、南には伏見稲荷など秦氏によって建立された神社も多い。
渡来民の秦氏がこの国にもたらしたものとして養蚕と酒造りが有名である。それを示すかのように木嶋坐天照御霊神社は蚕ノ社の名が表すように養蚕の神を祀り、松尾大社は酒造りの神を祀っている。また広隆寺にも寺内社として大酒神社という酒神を祀る社があった。
御隠居は自分の探索成果を自慢するように語り出した。
「実はな、天保山の港を出入りする船の水主が木乃嶋衆かもしれんいうんを嗅ぎつけたんは清兵衛やった。清兵衛の使う水主と闇夜に出入りする船の水主が、昔に一緒の仕事をしたことがあったらしい。それで顔を覚えてたらしいわ。それにその船の水主たちはおもろい紋が入った半被を着てたらしい。それは綺麗な双葉葵の紋やいうことや」
籐伍も渦彦も双葉葵といわれてもピンとこなかった。
「双葉葵はおもろい謂れの紋やが、木嶋坐天照御霊神社や松尾大社の神紋にもなってる。つまり元は秦氏の家紋ということやな。それで双葉葵を背負う船の水主たちが木乃嶋衆やとわかった」
ここまで語った御隠居は、別のこともいいかけたがそれは辞めていた。本筋の話とは関係がないし、一度に多くを語り過ぎると籐伍と渦彦が混乱すると思ったからだ。
御隠居が語ろうとして辞めたのは、将軍家である徳川の家紋「三つ葉葵」との関係だった。徳川家の三つ葉葵の家紋の歴史は浅い。そしてこの三つ葉葵の元になったのが秦氏の家紋「双葉葵」であるという考察があった。
本来三つ葉葵は自然界には存在しない架空の植物だった。現実世界の葵は双葉のみである。徳川の三つ葉葵紋は秦氏の双葉葵紋を変化させて作ったものかもしれなかった。もしかしたら徳川家興隆の陰に、双葉葵の一族がいたかもしれないという憶測があった。
ここから御隠居は独自の探索結果を話し始めた。それはちょっと自慢げだった。
「その木乃嶋衆と江戸の三井が何でつるんでるんかは最初ようわからんかった。単に大枚を叩いた依頼主かも知れへんしな。やが三井が鬼没盗のために大枚叩く理由もようわからへんわ。それに船乗りの誇りは高いんや、金だけで盗人の手助けをするとも思えへん」
そこまでいって、御隠居は喋り疲れたというように前に置いた茶に手を伸ばしていた。確かに御隠居が話を始めてから少し時間が経っていた。かなりの長口舌になっている。
籐伍と渦彦も誘われたように茶を飲んだ。少し沈黙した御隠居は最後の謎解きを始めた。
「実は木乃嶋衆と三井家は裏で繋がってたんや。同じ氏子としてな」
御隠居の言葉に二人は「えっ」と思った。
木嶋坐天照御霊神社は京の太秦の神社だし、三井は江戸の豪商である。その両者が結びつくとは急には思えなかった。
「三井もあれだけの大所帯やからな、江戸だけやのうて京や大坂、あるいは大元の松阪にも店はあるんや。そやけどな、ただ店が近くにあるいう薄い繋がりやあらへんで。三井は京の木嶋坐天照御霊神社自体を江戸の向島に灌頂して、新しい社として「三囲(みめぐり)神社」を作ってるんや。それを三井家の守護社にしてると聞くわ。何せ日本中で木嶋坐天照御霊神社にしかあらへんという三本柱鳥居を三井家内にも祀り、さらにそれを三囲神社にも祀ってると聞いたで。いうたら木嶋坐天照御霊神社と三井は一体になってるんや。木乃嶋衆と三井が深こうに繋がってるんもこれで頷けるで。金のためやのうて同じ氏子の仕事やからな。損得抜きで協力するわ」
籐伍はここで深く考え込んでしまった。
どうやら鬼没盗の後ろには三井家がいるのかもしれない。いや、三井家というよりも木嶋坐天照御霊神社というべきか。確かにそれだと鬼没盗の行動力や資金力も頷ける。盗んだ物を売買しなくても盗賊団を維持する資金はあるのだ。
だがそうなると鬼没盗のことがまたわからなくなってきた。鬼没盗は古瀬稀人が鬼変薬を再現するために作った盗賊団ではないのか。今までどこにも、大和の椎根津の口からも木嶋坐天照御霊神社や三井家の名は出てきていない。自分たちが知らない、もう一段深い謎が鬼没盗にはあるのかもしれなかった。
籐伍が黙って考えていると、御隠居は最後に謎の欠片を投げかけてきた。
「そうや、いい忘れてたけどな、先の広隆寺やがここは聖徳太子を祀る寺やで。広隆寺を作った秦河勝は、太子が摂政時代に最側近の豪族やったらしい。その記憶を留めるために作ったんが広隆寺や。御本尊として聖徳太子像と太子から賜った弥勒菩薩像があるいうことや。つまり広隆寺は聖徳太子の寺なんや。そやから紋所の十六菊花紋に太の字も、太秦の「太」ではのうて太子の「太」を取ったともいわれている。まぁ地名の太秦自体が太子と秦氏を並べたような字面やからな、どこからとっても同じなんかもしれへんけどな。そやけどこれで広隆寺もまた、鬼没盗の狙う聖徳太子と重なってしもうた。まるで聖徳太子が鬼没盗を手助けしてるみたいや。どこまで絡んでくるんやろうな」
御隠居もまた、新たな謎の重なりに困惑しているようだった。
(二)
綿津見と燕による大坂の薬方探索もすでに十日が過ぎていた。だがまだめぼしい成果は上がってはいなかった。
それというのも大坂には、いや同修町に限っても薬種問屋、薬局、あるいは薬の調合者、薬師、研究者は星の数ほどいるのだった。大坂全体では無数にいるといっても嘘ではない。
それは日本各地で採取できる薬種、鉱物、あるいは生薬などが一度全て大坂に集まる流通経路になっているためだった。
漢方の薬種だけではなく、西洋からの蘭方の薬や外国からの文物も長崎経由で大坂に集められた。つまりこの国の薬に関わる全ての物が一度大坂に留まることになるのだ。
そうなれば当然、薬を扱う漢方医も蘭方医も大坂に集まった。ここにいれば研究材料には事欠かないし、また最新の情報もいち早く吸収できた。後の世に緒方洪庵の適塾が大坂にできたのもそうした理由である。江戸は薬の巨大な消費地ではあったが、研究や製造の場ではなかったのだ。
そんな薬と研究の坩堝のような大坂の街を毎日歩き回る綿津見だったが、あまり効率よく探索できたとはいえなかった。疲れを見せ始める綿津見に燕は助言をした。
「綿津見様。うちは薬のことはようわからへんけど、これはまるで大河で砂粒を探すような大変なお仕事やと思います。ここは薬の世界の案内人を立ててみてはどうですか。その方が無駄は少ないと存じます」
綿津見を見かねたように燕が提案した。
「しかし大坂には大和と違い案内してくれる方がいてまへん。大和ならば交流のある薬種商や薬の調合者などもいるのですが」
綿津見の言葉に、燕は大きく首を振った。
「いてるやないですか、あそこに」
そういいながら、道の先に見える鳥居を指さしていた。それは同修町の真ん中にある少彦名神社の鳥居だった。
薬方探索の初日に、綿津見は燕と共に少彦名神社へ挨拶に行っていた。渦彦の身を預かってくれている礼をするためだった。
宮司の阿曽は話し上手ではあったが、薬の知識に関してはあまり無いようだった。それで綿津見は薬方探索の詳しいことは話さずに、挨拶だけで退いたのである。
だが黙って聞いていた燕の見る目は少し違っているようだった。
「阿曽宮司はんはまぁおしゃべりやし、薬の事はようわかってへんみたいやけど、この街の噂話はびっくりするぐらいよう知ってはりりましたわ。つまり、誰が何をしてるか知ってるいうことです。深い内容は理解してへんでも、綿津見様が知りたいこと知ってるんとちゃいますか。それになんといっても顔の広さと信用があります。案内人にはぴったりや」
燕は阿曽宮司をうまく使えば、良い案内人になると見た。逆に薬の知識が乏しい分、綿津見の探索の真意も悟られずに済むと考えていたのだ。
「わかりました、阿曽宮司様にお願いしてみましょう。今は時を無駄にはできままへん」
綿津見は渦彦からの手紙で、阿曽宮司が徳陀子神社の仙薬を欲していることを知っていた。だから前回会ったときにも、話がそちらに行かないように気をつけていたのだった。
だがこの十日間薬方を巡ってみて、綿津見にも心境の変化があった。それは「皆必死で薬開発に前へ進んでいる」という思いだった。薬の世界は驚くほど進化していた。どこかで自分も仙薬を前に進めなければという思いが芽生えていた。
思いを改めた綿津見は、再び少彦名神社に宮司を訪ねた。綿津見は面会した阿曽宮司に、今回来坂した目的を少し修正してだが正直に話した。
「今回大坂に来ましたんは、我が家に伝わる秘薬の改良のためです。ですがあまりに多い大坂の薬業の人々に、訪れるべき人や場所もままなりまへん。ここは大坂の薬に通じてはる宮司様にお導きいただけないかと考え参上いたしました。何卒、ご協力賜りたいのです」
そう述べてから、綿津見は阿曽宮司に手をついて深々と頭を下げた。綿津見の後ろに座る燕も同じ様に頭を下げていた。
綿津見の口上に気を良くしていた阿曽は、まあまあお手を上げくださいという様に綿津見の手をとっていた。そして後ろで頭を下げる燕に対しても、「奥方様も頭をお上げくだされ」と声をかけていた。
前回訪問したときにちゃんと紹介しなかったせいで、阿曽は燕のことを綿津見の妻だと思い込んでいた。綿津見は阿曽の誤解を訂正しようと口を開きかけたが、先に阿曽が早口に喋り始めていた。
「よろしおます。私が綿津見殿の先導役となりまひょ。もともと渦彦殿とのご縁もあることやし、また京の五條天神宮はんとの繋がりもお互いに深い。ここはこの少彦名神社と徳陀子神社も互いに兄弟の契りを結ぼうやおまへんか。それが互いの社の利にもなります。綿津見殿は誠に薬の調合に詳しいし、秘伝の薬もお持ちや。うちにはそれがないが、売り捌く力と周旋の力があります。この二つが協力したら鬼に金棒や」
そう嬉しそうにして、綿津見の手をしっかりと握っていた。
後ろでは燕も、「ありがとうございます」という様に再び頭を下げていた。燕もまた阿曽の誤解を解こうとはしていなかった。
話のまとまった阿曽と綿津見は、互いに必要な情報の提供を話し合った。綿津見は幾種類かの薬種と鉱物を書き出し、これらを扱う薬種問屋とその研究や調合をする薬師の名を求めた。
代わりにという様に阿曽はいくつかの効能を書き出して、それに相応しい秘薬の提供を求めてきた。
お互いにこの場で直ぐに答えることができないので、三日後に再び少彦名神社を訪れることで話がついた。
帰り際に阿曽が燕に、「奥方様も遠路ご苦労でしたな」と大和からの長旅を労ってきた。綿津見はこの機会を逃してはいかんというように、改めて燕を宮司に紹介した。
「こちらは私の妻ではなく、逗留先の阿刀様の御息女、燕殿です。大坂に不案内な私の案内をしていただいております」
阿曽は驚いたような表情をしたが、何かを納得するように頷いていた。
「おお、これは失礼をいたしましたな。しかしそうか、阿刀様の御息女ということは籐伍様のお姉上か。噂は鴻池の御隠居様から伺っておりますぞ。えらい別嬪はんの姉上様の噂。何でも賊とも戦われたいう女丈夫という……、いやこれはまた失礼を」
宮司はそこで言葉を切った。だが改めて二人をしげしげと見て独言した。
「しかし、見れば見るほどええご夫婦に見えはるわ。失礼ついでにいうときますわ。もしこの後、その様なことになられはるんでしたら婚礼の儀はうちでお願いします。徳陀子はんとは兄弟の契りを結んだんや。お安うにしときまっさかいに。阿刀様にもよろしゅうにいうといてください」
阿曽は最後まで商人のようなことをいってきた。綿津見が答えられないでいると、代わりに燕がにこやかに答えた。
「ありがとうございます。その折にはよろしゅうにお願いします。せやけどうちにはお足はあらしまへんで。宮司様のご好意に甘えせていただきとうございます」
そう朗らかに、燕もまた宮司に負けていない返し方をした。
「何をまた、阿刀様といえば西町の諸色方大番役与力様や。ご婚儀の費用なぞ大坂中の商人がこぞって出しますわ。何やったら、その周旋をわてがしてもよろしおます。良き話をお待ちしておりますぞ」
そう笑いながら深々と燕に向かって頭を下げた。燕も宮司に頭を下げると、「さあ参りましょう」と綿津見の手を取って歩き出していた。
しばらく歩き少彦名神社から離れたところで、燕は綿津見に謝った。
「綿津見様、勝手にお答えしてしもうてすみまへん。せやけどあのくらのことは大坂では普通のやり取りです。気にせんでもよろしいですよ。宮司はんも冗談のようにして、少しだけ本音を潜ませてるんです。そこを上手いこと感じなんだら、大坂での交渉事はできまへん。話半分に聞いとくんがちょうどええんです」
そう説明する燕だったが、やはりどこか嬉しそうだった。
三日間は綿津見にとっても丁度よい休息になった。勿論その間に阿曽宮司の求める功能の薬を選別していた。外に出してよい仙薬と、綿津見自身が効能を確認したい仙薬からの選別だった。
これまでは神社での配布を主としていたので、仙薬の功能の確認はあまりできていない。それに服用者の反応も知りたかった。薬の治験をしてみたかったのだ。大坂に来てから綿津見の内側に「科学者の心」が芽生えていた証だった。
再び少彦名神社を訪れた綿津見は、宮司の求める効能の薬をいくつか示した。だがあくまで薬名とその処方、効能だけである。大坂で必要になるとは思っていなかったので、仙薬の見本は持参していなかった。
阿曽宮司も自分の懐から長い巻紙を出して、その巻紙を広げていった。
「ここに先日綿津見殿がいわれた薬種を取り扱う問屋や店、薬局を書いておきました。この先頭に書いてある肥前屋はんはうちからも近いし、一番多くの薬種も取り扱われてはるようです。ここの軒先をお借りになられて薬の見本を作られてはいかがですか。話はもう先方にはしてあリまっさかいに、いつでも行ってくだい」
そう綿津見に提案すると、秘薬名と処方の紙を大事そうに胸に仕舞った。
綿津見も阿曽宮司の示した巻紙に書いてある問屋や薬局の一覧を見て少し驚いていた。わずか三日でよくここまで調べ上げたものだと感心した。話の軽さや薬に関する知識の無さとは逆に、この街の人々のことを実によく心得ていると思った。
少彦名神社から肥前屋に向かう途中、綿津見は燕に対して礼をいった。
「燕殿の見る目の方がやはり正しかったようです。阿曽宮司様は期待以上の答えを出してくだされました。全て燕殿のおかげです」
そこに肥前屋の暖簾が見えるところで、綿津見は深々と燕に頭を下げた。
「うちのおかげやおへん。大坂ならこれくらいは当たり前です。無駄なようなお喋りしながら、ちゃんと相手を観察してはる。そやから綿津見様の知りたいことも知ってはるんです。うちが少しだけそんな大坂のやり方に慣れてるだけや。これがうちの役目やさかい」
そして燕は綿津見の手を取って肥前屋の入り口に向かおうとした。いつの間にか二人は互いの手を取ることに慣れ始めていた。
その日から数日、綿津見は肥前屋に通いつめた。
綿津見は本来の目的を忘れるほどに、肥前屋での見本薬作りを楽しんでいた。そして薬種商や薬師の考える今の時代の「薬」というものの概念を新たに学ぶことにもなった。
綿津見にとって薬とは人に良い効能を足していく「足し算」だった。だが大坂の薬師たちは違っていた。彼らにとって薬は「毒の引き算」だった。
良い効能というものは結局人体に対する「弱い毒」であり、弱い毒性を利用して人の体の悪い箇所を攻撃(あるいは修復)する。だから強い効能のある薬(=強い毒)には、必ず裏側に副作用として負の影響があると認識していた。その負の影響を如何に少なく(引き算)するかが重要なのだ。
この言葉を聞いたときに、綿津見はハッとして鬼変薬のことを思った。肉体強化、鬼化という強烈な効能の裏に、不適合という健康障害がある。つまり弱い毒ではなく、強い毒で人の肉体を強制的に変化させたために、負の影響が大きく出ているのだと思った。
阿曽宮司に渡す仙薬を調合しながら、綿津見は密かに従来の鬼変薬の改良に着手することを心に誓っていた。奇しくもそれは古瀬稀人が考える新たな鬼変薬と同じ方向性だった。綿津見と稀人はここ大坂で同じ目的の薬を作り出そうとし始めていたのだった。
少彦名神社に委託する仙薬の見本を完成した綿津見は、それ持って阿曽宮司の元を訪れた。見本を渡しながら処方について事細かに伝えた。
「これらの薬はそれぞれ十日分、そして十人分を用意しました。ただこの地で調合したので従来通りの効能が出るかどうかはまだわかりまへん。ですから必ず服用される方には服用とその後の変化について記録を採っていただきたいのです。それによっては、少し薬剤の分量の修正が必要になるかもしれまへん。もし服用された方に急変あるときは至急私にお知らせください。これは人の命と健康を守るための大切なことです」
阿曽は綿津見から受け取った薬を、大切に薬箱に仕舞っていった。そして社の奥から神人の藤吉を呼んだ。藤吉にこの薬箱を神社の薬庫に保管するようにいいつけた。
藤吉が去るのを待って、阿曽が綿津見に秘薬改良の進展を尋ねた。
「今の秘薬作りに専心していたので、今日より戴いた名簿を廻る所存です」
答える綿津見に、阿曽は「それはよかった」というように、一枚の紙を差し出してきた。
そこにはある住所と、「華陀庵 大辟辰砂(おおさけしんしゃ)」という名前が書かれていた。綿津見は一瞬「ふざけた名前やなあ」と思った。
「この前お渡しした一覧には入れてへんお方ですが、このお方もお知らせした方がええ思いましてな、今回新たにお渡しします」
「このお方はどういう方ですか」という問いに対して、阿曽は少し悩むような顔をした。
「わてもよう知りまへんのや。ただあの後、何人かの問屋さんに聞いところ最近一番仰山ことの水銀を買われたんがこの方やということです。何でも元は赤穂の漢学者はんやということですが、大坂に来てからは蘭学の方々とも何やらされてるいう話ですわ。何で水銀を買われてるんかはようわかりまへんが、下手な薬局より仰山こと所望してるとか。不思議に思った薬種屋の主人が目的を尋ねたところ、『鬼を作っている』といわはったいう噂が伝わっております。鬼が何を意味してるんかは謎ですが、大坂で一番水銀を使うてるんは間違いないこと。綿津見殿の役に立つかと思いお知らせしました」
宮司の説明に綿津見は慄然とした。水銀は多くの薬に使われる素材の一つだが、毒性が高く大量には使われない。
古代世界において水銀は「不老不死の妙薬」とされ、丹や朱とも呼ばれた。特に支那では煉丹術という「不老不死の薬」作りが盛んだった。支那の陵墓や日本の古墳からも水銀朱が多く出土している。そして綿津見の知る鬼変薬の素材の重要な一つでもあった。
綿津見は改めて渡された紙の名前を凝視した。
華佗庵 大辟辰砂
華佗とは後漢末にいたといわれる医者で、神医とも呼ばれた伝説の名医である。そして辰砂は水銀を精錬する前の赤い鉱物、硫化水銀化合物の名前だった。辰砂の名はこの赤い鉱物の大産地が支那の辰州にあったことに由来する。
この名前の人物が水銀を大量に購うことは不思議ではない。この人物が古瀬稀人と繋がっているのならば、「鬼を作る」という言葉の意味は明白だった。新たな鬼変薬を作っているに違いなかった。
綿津見は少彦名神社を後にすると、急いで阿刀家に戻った。
「至急にこの場所に行きたいのです。本当の探索がやっと始められるかもしれまへん」
息席切る綿津見の言葉に、厨仕事をしていた燕が濡れた手を拭きながら示された紙を見た。だが書かれる住所に見覚えがなかった。
「これどこやろ」
そう呟きながら、傍にやってきた鈴と女中の小春に紙を見せた。
「どっか外れの村かもしれへんなぁ」という鈴の言葉に、燕も頷いていた。市中から離れるとなると、大坂育ちの二人にもわからぬ土地もある。
頭を捻っていた二人のそばで小春が「あっ、あそこかもしれへん」といい出した。
「佃村の方とちゃいますか。ほら埋め立てられた神崎川の河口のあたり」
小春の言葉に、鈴と燕も思いあたる場所があった。
この佃村はある意味有名だった。幕府開闢の時代に家康により江戸湾の小島に集団移住させられ、佃島を名乗ったのだ。後の時代にはそこで名物の佃煮も生まれたのである。
「佃村の方やったらここから少し距離もあるけど、何より川渡しに乗らなあかんなぁ。それやったら今から行くんは少ししんどいかもしれんわ。渡しが終わってるかもしれへん」
燕はそう呟くと鈴と顔を見合わせた。困り顔の燕を察したのか、鈴が綿津見にいった。
「綿津見様、本日は同修町の少彦名神社にも行かれてお疲れでしょう。それに連日のお薬作りでしたからお休みになられたと思います。佃村には明日の朝に行かれるのが上策やと思いますよ。明日ならうちもお供できます、急かば廻れと申しますよって」
嫋やかだが凛とした響きの言葉に、綿津見は自分の少し焦った要求に気がついた。
「鈴殿のいわれる通り明朝向かうのが上策でしょう。我が儘を申しあげすみませぬ」
謝る綿津見に、「今日はお休みになられた方がよろしいです」と燕が手を取って部屋に誘った。
厨から去る二人の後ろ姿に向かって、「燕ちゃん一つ貸しやで」という呟きを鈴が洩らした。隣で聞いていた小春が面白そうに笑った。
(三)
大坂北西部の神崎川河口にある佃村あたりは、川と湿地が入り組んだ場所だった。田はあまりなく、少しの畑と河岸に繋がれた船が目につく普通の漁村である。
三人は村人に阿曽宮司がくれた住所を見せ、華佗庵はどのあたりかを尋ねた。村人は最初よくわからないようだったが、何人目かが「ああ、あの飲兵衛はんか」と思い当たる人物を教えてくれた。
綿津見がどのような人物なのかを尋ねると、皆笑いながら「飲兵衛のど助平や」と妙に意見が一致した。「そんでも素面のときは物知りの先生やな」という別の評も語った。
鈴と燕を見て「気付けなはれや。すぐにおいどぐらい触りにくるで」とも忠告をした。
二人は一瞬顔を顰めたが、すぐに笑って「そしたらあそこ切り落としたるわ」と燕が返していた。
村人の教えてくれた場所に迷いながらも三人はたどり着けた。もう川に接する河岸で、古屋のような家には桟橋があった。川船が直接着けられる家のようだ。
「大辟先生は御在宅でしょうか。お願いの儀があって参りました」
綿津見の大きな声の呼びかけに最初は何の返答もなかった。
綿津見は重ねて声をかけた。
「私は巨勢綿津見と申します。薬の調合を学ぶ者です。大辟先生にぜひご教授願いたく参りました。お顔をお見せ願いたい」
返答はなかったが、少し濁った声でぶっきらぼうな声がした。
「教えるような事は何もないぞ。さっさといね、わしはもういっぺん寝る」
それだけだった。だがここで綿津見に替わって燕が声をかけた。
「大辟先生、失礼とは存じましたが手土産に灘のお酒をお持ちいたしました。せめてこれだけでもお受け取りくださいまへんか。持ち帰るには重うございます。お願い申し上げます」
燕の声に反応するように、どたどたと足音が戸口に近づいてきた。
「灘の酒か、ならば受け取ろう。どこにある」
戸を開けながらしゃがれた声で叫んだ。それが大辟辰砂だった。
ボサボサの髪を後ろで縄に結び着物もヨレヨレだが、不思議に薄汚れた感じがしないのは風呂には入っているらしい。歳は四十絡みに見えたが、意外にもっと年長かもしれなかった。
大辟は前にいる綿津見には目もくれず、周囲を見て酒を探した。
「申し訳ございません。お酒は後ほど村の者がこちらに持ってきてくれることになっております。それまでお話しいただけませんか」
燕が交換条件のようにいった。大辟はボサボサの頭を掻きながら「今ここにないんか。……しゃあない、酒が来るまでやったら話したるわ」と渋々燕の言葉を受け入れた。
「入れ」ともいわなかったが、奥に戻っていったのでそれに続いて三人も家に入って行った。
奥に入って三人は驚いた。家財道具はほぼないのに、あたり一面に堆高く積まれた本の塔が幾つも天に伸びていたのだった。本の塔の間を縫うように進んだ大辟は、開けた場所に敷かれた布団に面倒臭そうに座り込んだ。
「その辺に座れ、じゃが本は崩すなよ。必要な本が何処にあるかわからんようになる」
そういうと今度は鈴と燕をしげしげと眺め、感心したようにいった。
「お主もわしと同じで女に妙な趣味があるようやな。そこは気が合いそうや。双子とまぐわうたことはわしもまだない。どないや、顔は同じでも下の方はまた違うんか」
綿津見は最初何をいわれたのかわからなかったが、大辟が二人を舐めるように見ていたのでその意味をやっと理解した。
「こちらは私がお世話になっている逗留先の御息女です。本日こちらまで案内していただいたのです。疚しい関係ではありません」
綿津見の返答に「何や、つまらんなぁ」と、ぼそっと大辟は呟いた。
「では娘ご、すまんが厨から水を持ってきてくれんか。昨夜飲み過ぎて喉がカラカラや。これでは話もでけん」
鈴と燕は二人で厨に向かった。どちらかが残ることが不安だったのだ。
二人の後ろ姿、尻あたりを見ながら大辟はやっと綿津見に声をかけた。
「ほんで、何が聞きたいんや。わしは薬師やないで、薬のこと聞かれても何もわからへん」
そういいながらボリボリと首筋を掻いた。
「私は今、水銀を使った薬の調合をしております。それで同じように水銀を使われている方々にお話しを伺っているのです。大辟先生は大量の水銀を薬種商から買われたとお聞きしました。それで先生がどのように水銀を使われているのかをお聞きしたいのです。まずどのような薬に使われておるのでしょうか。私の研究する薬の参考のためにも是非お教えください」
質問に大辟は大きな欠伸をしながら、「よう知らん」とだけ答えた。
そこに茶碗に水を入れた鈴が戻ってきた。その茶碗を大辟に渡しながら「厨が少し散らかっていましたので、今妹が片付けております。よろしいですか」と尋ねた。
茶碗の水を一気に飲み干した大辟は、もう一杯というように空の茶碗を突き出した。
「片付けてくれるんは構わへんけど、窓際の瓶には触ったらあかんで。いろいろ危ない薬も入ってるからな」
それだけいうと、綿津見の方に向かった。
「確かにわしは仰山こと水銀を買てるけどな、それで何を作ってるんかはようわからん。わしは漢籍にある通りに作ってるだけや。わしは漢学者やからな、漢籍を解読しながら調合してるんや。薬作りは金のためや。それで稼がんと酒も飲めんし遊郭にもいけへん」
大辟は興味がなさそうに答えた。
「しかし先生は薬種商に『鬼を作っている』といわれたと聞きました。何故そのように答えられたのですか」
綿津見の重ねた質問に少し面倒臭そうにした。
「詰まらんこというてしもうたな。しゃあない、灘の酒のためや答えたるわ。わしが水銀で調合してる薬の作り方を書いてる漢籍に、「鬼身乃剤」というくだりがあったからや。それでなるほどこれは鬼の身体のための薬かと思うた。問屋がひつこうに聞くんで『鬼の薬や』と答えんたんや。鬼を作るとはいうてない気がするけどな」
綿津見はその返答に考え込んだ。嘘をついているようには見えなかった。
「よろしければ先生が読まれた漢籍をお見せくださいませんか。私も多少は漢籍が読めます。薬のことも存じていますので、何の薬かわかると存じます。お願いできませぬか」
綿津見の申し出を大辟は少し考え込んだが、結局それを拒否した。
「あかんというよりも無理やな。その漢籍は依頼人が持って帰ってしもうた。それに……灘の酒ではここまでやで。もっと別の褒美でもないとお主に協力する謂れもないわ」
そして厨に向かって声をあげた。
「灘の酒はいつ来るんや。もうだいぶ経つで」
大辟に対して燕が返事をした。
「村の人に対岸の酒屋にまで買いに行って貰うてるんで、もう少しかと思います。しばらくお待ちください」
燕の声を聞いた大辟は、下卑た表情をして綿津見に秘密の交渉をも持ちかけてきた。
「ええ褒美を思いついたわ。これ融通してくれたらお主の申し出に応えたろうやないか」
大辟の言葉に「褒美とは何ですか」と綿津見が尋ねた。大辟は手招くような素振りをして、綿津見の耳元に顔を寄せた。
「二人とはいわへんから、あの娘のどっちかをわしに貸してくれ。どっちもええ女やで、二人ともおいどが大きいのがええなぁ。そういう女は床の中も激しいよって」
大辟の言葉に、綿津見は二の句が継げなかった。
「わしに水を持ってきた姉の方でええで。妹の方はどうやらお主に惚れてるようやな。そういうんは仕草を見てたら大体わかるからな。どうや、お主にも損はないやろ」
そこまでいったときに、鈴と燕が部屋に戻ってきた。
「厨の片付けを大体終わりました。それでお話は進みましたか」
朗らかな燕の声に、大辟が驚いたことに今の内緒話を始めた。
「今なあ、この男にあんたら姉妹のどっちかを貸してくれというてたとこや。そしたらこの男の聞きたいこと全部教えたるとな。あんたらはどないや、この男の手助けしたいんやろ。別に嫁になれいうんとちゃうで、ようある一夜の伽や」
鈴と燕は驚きを通り越したような表情になった。そのとき、綿津見が怒って立ち上がった。
「その申し出は取り消していただきたい。私は誰かを犠牲にして望みを叶えるつもりはありまへん。お二人に対しても失礼極まりない」
大辟が「固いやっちゃなあ」と呟くと、その言葉に被せるように表から大きな声が響いてきた。
「先生、お客はんからの酒やで。戸口に置いとくさかいな」
ちょっと機先を封じられたように、綿津見がその場に立ち止まっていた。鈴が綿津見を宥めるように、再び座るように促した。その間に燕は表戸へ酒を取りに行った。
怒った顔の綿津見から、鈴は大辟に顔を向けて静かに話しだした。
「先生、女子としては殿方に求められるんはありがたい話やけど、残念なことにうちらはもう売れ先が決まってます。特にうちの許嫁はんはそれは嫉妬深こうて。奉行所の同心様やからもし今の話耳に入ったら、先生のこと科がのうてもしょっぴくかもしれまへんで。そうなったらえらいことやわ。いつ帰れるかもわからへんし、悪うしたらそのままご牢内で……ということもようありますよって」
鈴が少し怖いことを真面目な顔でいった。大辟もギョッとした表情になった。そこに酒徳利を抱えた燕が戻ってきた。酒徳利を大辟の前に置き、そのまま厨に行って盃替わりになりそうな茶碗を持ってきた。
酒徳利と茶碗が大辟と綿津見の間に置かれていた。鈴は二人の茶碗に少しの酒を注ぎ、「まあ、まずはお気持ちを鎮められて」と二人にいった。
「それにうちの妹は気が強いさかい、今まででも何人もの男衆の楽しみを奪ったことか分かりまへん。先程も村の人に先生がうちらのおいど触わるかもといわれたら、そしたらあそこ切り落としたるっていうてましたわ。妹は小太刀が使えるさかい、これまで無いことやおへん。先生もそうなったらもう他の女子も抱けしまへんで」
燕は最初鈴が何の話をしているのかわからなかったが、途中から大辟を脅しているのだと気がついた。それで胸元に刺していた懐剣を鞘ごと抜くと、静かに大辟との間に置いた。そして微笑むように大辟を見つめた。
大辟は置かれた酒に手を伸ばすと、「わかった、わかった。冗談やからもういじめんといてくれ」と音を上げて酒を煽った。そして諦めたように綿津見に変な忠告をしてきた。
「お主、気つけや。この二人のどっちかを嫁にしたら、長生きできんかもしれへんで。床の中で精を吸われて死ぬか、浮気して殺されるかは判らへんけどな」
大辟は飲み干した茶碗を燕に突き出そうとしたが、何を思ったのか鈴の方に変えた。どうやら牢屋よりも切り落とされる方が嫌な様子である。
少し毒気を抜かれた綿津見も冷静さを取り戻した。前に置かれた茶碗を大辟の方に掲げると、そのまま飲み干していった。
「失礼いたしました。私も少し興奮しました」
そして居住まいを糺すと、再び大辟に問い始めた。
「先生が調合に使われている漢籍がここにないことは承知しました。ではそれを持ってきた人物は何というお方ですか。それをお教え願いたい」
綿津見の質問に大辟は少し考え込んだ。
「それはいわん方がええやろ。依頼人との信義もあるが、お主と依頼人との関係も判らん。わしも変ないざこざに巻き込まれるんは迷惑やからな」
そう答える大辟に綿津見は諦めずに更に聞いた。
「では私がいう名前に否応でお答えくださいませぬか。それならば依頼人との信義は守れます」
綿津見の言葉に逡巡していた大辟は、思わず鈴が注いでくれていた茶碗の酒に手を伸ばそうとした。だが鈴がその茶碗の上に手を置いて、柔かな表情で首を振った。暗に「お答えいただいてからです」といっていた。
「依頼人は古瀬稀人という者ではありませんか」
綿津見の言葉に大辟は少しホッとしたような表情で、「違うな」とだけ答えた。そして鈴が蓋をしていた茶碗を持ちあげると、美味そうに飲み干していった。
その答えに綿津見は少し意外な気がした。大辟が嘘を答えている可能性もあったが、先程のホッとした表情は嘘とは思えなかった。
だとしたら、大辟に水銀を使った薬の調合を依頼したのは古瀬稀人ではなく、その目的は鬼変薬の再現ではないのかと思った。
少しの間考え込んでいた綿津見は、別の疑問を感じていた。
いかに漢籍から薬を再現するにしても、なぜ依頼人はこの不真面目な男を選んだのだろうかと思った。漢籍が読める薬の調合者は他にもいるし、漢方学者なら基本漢籍は読める。
「失礼ながら、なぜ依頼人はこの仕事を先生に頼まれたのですか。先生は薬には精通しておられない。漢籍から薬を再現するにしても相応しくないと思われます。何か他の理由がおありかと思えますが」
不躾な言葉に大辟は一瞬顔を顰めたが、すぐに大笑いをし始めていた。
「お主もそう思うか。それが当たり前やで。わしのような飲兵衛の漢学者に頼む仕事ではないわ。しかしなぁ、どうしてもわしではのうてはあかん理由があんのや」
綿津見は思わず「その理由とは何ですか」と尋ねていた。大辟は嬉しそうに「聞きたいか」と答えた。綿津見が頷くと、大辟は置かれた酒徳利を手にとって少しそれを振った。
「酒が少うなったな。もう一瓶都合してくれたら話したるわ。どないや」
色気の次は酒の要求だった。大辟の我が儘な交換条件に、燕がすぐに立ち上がった。
「うちが川向こうまで買いに行ってまいりますわ。それまでお話を続けください。先生の夜伽はできまへんけど、お酒の酌ならできますよって。でもその間に姉に変なことしはったら、ほんまにあそこ切り落としますさかいな。どうぞお気をつけて」
そういい置くと、いそいそと家の外に出ていった。
燕の後ろ姿を見ながら「ええ女なんやがなぁ、情が深すぎるわ。あれでは好いた男も食い殺してまうで」と大辟は呟いた。
同意を求めるように綿津見に「そう思うやろ」と語ってきた。先程の夜伽の要求をもう忘れたような悪気のなさだった。
この大辟という男、本当に酒と女が好きなだけで、悪い人間ではないのかもしれないと綿津見も感じ始めた。
「それで先生やないとあかん理由とは何ですか」
鈴に注いでもらった酒を喉に流し込みながら。大辟は少し誇らしげに逆に聞いてきた。
「お主は漢籍が読めるというたな。ならば蓬莱山東渡伝説を知っておるか」
大辟の口から思いも寄らない言葉が飛び出してきた。
「蓬莱山東渡伝説? ……確か前漢の史書『史記』の中にあった方士徐福の話かと思いますが、それが何か関係あるんですか」
綿津見の返答に大辟は満足したように頷いた。
「知っておるか、ならば話が早いわ。わしはな、元々はその蓬莱山東渡伝説が語る徐福を研究しておったんじゃ。徐福が東の海の果てにある蓬莱山に不老不死の仙薬を求めたという伝説、それを解き明かそうとしておったのよ。まあ簡単にうと、不老不死の仙薬とは何かを特定するために薬の世界にも足を踏み入れたんや。じゃがこれはなかなかに大変で迷路のような研究での、しかも薬の実物を手に入れるには金もかかる。それでこの仕事を請け負うた。ええ金になるんでな。それにこの仕事はわしの研究にも少し絡んでおる。不老不死の仙薬の一つが、漢籍にある水銀を使うた薬かもしれへんと依頼人はいうてきたんじゃ」
徐福が求めた不老不死の仙薬、そんなものがこの世にあるのかと綿津見は思った。
だが鬼変薬ももしかしたら不老不死を実現するための薬の一つなのかもしれないと思った。「人間の肉体能力を極限まで強化する」という点だけを見れば、不老不死への第一歩である。
少し考え込んでいた綿津見に大辟は意外なことをいってきた。
「お主は名を巨勢と名乗ったな。ならばご先祖は大辟と意外に近いかもしれへんで」
この言葉に綿津見はさらに思い悩んだ。
「うちの親族に大辟という家はありまへんが」
少し間の抜けた返答に、大辟は間違いを指摘する教師のようにいった。
「ちゃうわ、もっと大昔の話や。ええか、わしの出は赤穂の坂越の浜にある大避神社というとこや。この大避神社では秦河勝という人物を我が家の祖神として御祭神に祀ってるんや。つまり大辟家は元秦氏やちゅうことや。お主は巨勢やろう、巨勢と秦の共通点は何や」
急に教師のような口調で綿津見に問いかけてきた。
巨勢氏と秦氏の共通点といえば……共に飛鳥時代には聖徳太子の側近の豪族であったことだ。
「わしが何で徐福の求めた仙薬を探してると思う。それはまず一つには先祖の秦氏が徐福の末裔かもしれへんからや。そしてな、我らの先祖が仕えた聖徳太子もまた不老不死の仙薬に因縁が深いんや。この国には各地に徐福来訪伝説があるが、実はその地の多くは古代に秦氏の入植した地でもあるんや。つまり徐福の巡った地は、不老不死の仙薬を探した地であり、また秦氏が開墾した地でもある。京の太秦なんかはその実例やで。広隆寺もその東の木乃嶋神社、西の松尾大社なんか全部秦氏のもんや」
綿津見は籐伍から聞いた、広隆寺と木乃嶋衆の紋所の話を思い出した。
思わぬところで話が繋がってきた。徐福に秦氏、太秦、そして聖徳太子。
「先生がいわれた、聖徳太子もまた不老不死の仙薬に縁があるというのは、どういうことですか。そのような話は流石に聞いたことはありまへんが」
綿津見が確認するように大辟に問うた。
「まぁ普通は知らぬのも無理はない。じゃが太子の伝略の中に『甲斐の黒駒に乗って、一夜にして飛鳥から富士山に舞い降りた』という話が残っておる。富士山近くの寺にはその時を描いた太子の絵もあるらしいわ。考えてもみい、何故飛鳥におった太子が無理をして遥か東国の富士に行ったという伝説が生まれたのかを。しかも富士のある甲斐の馬に乗って。それはそこに不老不死の仙薬があって、太子もまたそれを探しに甲斐へ探索を出したからや。もしかしたら協力者がおったんかもしれへん、それが甲斐の黒駒や。秦河勝の主人であった太子は、当然徐福の求めた不老不死の仙薬の伝説を知っておったはずじゃ。それに……」
大辟はここで少し居住まいを糺した。
「今でこそ富士じゃがな、かつては不二とも不死とも書かれた山やで。徐福の求めた蓬莱山がそこであってもおかしゅうはない。それにこの伝説の大元は支那の神話の中にもあるんや。古代支那の伝説の帝王、三皇五帝の一人である神農が蓬莱山に渡り不老不死の仙薬を作ったという神話がある。神農は薬の神様やからな、昔の支那ではこの神話はよう知られておったらしい。それに蓬莱山に住む神仙とはこの神農の裔やともいわれておった。そやから秦の始皇帝も、徐福の『蓬莱山に不老不死の仙薬を探しに行く』という言葉を疑うことなく信じたんや。船団を用意してやるほどにな」
大辟は楽しそうに、ここまでを一気に語ってきた。きっと世人にはあまり語れない話だけに話すことが楽しいのだろう。それはある種、自分の研究の自慢でもあった。
だがこの話もまた、叔父椎根津が語った「聖徳太子に伝来した薬が鬼変薬の元になった」という内容と符合していた。
綿津見にはいったい何が真実なのかだんだんわからなくなっていた。だが綿津見は本来の目的を思い出し、大辟に確認をした。
「では先生が作られている水銀を使った薬は、徐福や秦氏が探した不老不死の仙薬の一部ということですか。先生の依頼人はあまり相応しくはないが不老不死の仙薬の研究をされている先生に薬の再現を依頼したと。先生も貰った漢籍に基づいて薬を再現しているだけであるというのですね」
綿津見の整理した言葉に、大辟は「まぁおおよそはそういうこっちゃな」とだけ答えた。
手に持っていた茶碗を名残惜しそうに舐めると「ホンマにもうないんか」と鈴に聞いた。
鈴は徳利を逆さにしたが酒は一滴も溢れなかった
「妹が戻るまでもう少しお待ちください」
鈴の言葉に残念そうにした大辟だっが、意外に早くその燕が戻ってきた。
走り戻ってきた燕は、胸に抱いた四合徳利から「先生どうぞ」といいながら大辟の茶碗に新しい酒を注いでいった。
大辟は美味そうに注がれた酒を飲みながら、空いていた右手で燕の尻をさっと触ってきたのだった。それは皆が唖然とする速さと手際だった。
触られた燕自身も最初唖然としていたが、ゆっくりと立ち上がると胸元から懐剣を引き抜いた。その短い刃を勢いよく大辟の前に突き立てた。
「お約束です。先生のあそこ断ち切らせていただきます。お覚悟をされよ」
本気の声音で燕が大辟に宣言した。燕の表情は綿津見がまだ見たことがないような鬼気迫るものだった。綿津見は思わず鈴の顔を見たが、鈴には別に驚いた様子がなかった。それで燕に任せておいて良いのだと理解した。
「すまん、あんまりええ肉付きのおいどやったから、思わず手が出てしもうた。謝るし何でもするさかい、許してくれ。お主からも何かいうてくれ。息子と生き別れしたら、この先何を楽しみにしたらええんかわからへんわ」
大辟は燕の方を見ずに、綿津見に助けを求めてきた。怒った燕を止められるのは、惚れられた綿津見だけだと直感したようだった。
「私にはどうすることもできまへんが、薬の依頼人の名前をお教えいただければ妹殿も納得されるかもしれまへん。いかがですか」
綿津見の言葉に燕が少し頷いた。だがそれには大辟が「それは無理や」と聞こえないほどの音量で首を振った。
「では私にはどうしようもありまへん。妹殿の気が済むようにするしか」
綿津見の突き放した言葉に大辟は代わりの提案をいってきた。
「名前はいえへんが、居てるかもしれん場所なら教えたるわ。わしも普段連絡するときはそこに飛脚を走らすさかい。それなら売ったことにもならんやろ。多分水銀の金を払うてもろうてる薬種屋も知ってる場所や」
「そこはどこですか、大坂市中ですか」
綿津見の当てずっぽうを、大辟はすぐさま否定した。
「ちゃう摂津の西、灘郷の方や。青木の浜から北の金鳥山へ少し登ったところに保久良神社という古社がある。そこの離れ家に依頼人は普段いてるということや。名前は言えんが行けばわかるはずや。これでどないや、もう勘弁してくれ」
大辟の泣きつくような言葉に、綿津見は燕に向かって頷いて見せた。それを見た燕は、ゆっくりと突き刺した懐剣を引き抜くと鞘に戻していった。
「先生、女子には好いたお方になら許せることも、他の男衆にはあかんことがあります。釈迦に説法かもしれまへんけどお気を付けくださいね」
スッキリしたように燕は深々と大辟に頭を下げた。
全身から力が抜けたように大辟は座る布団の上で息をついた。だが手に持った酒の茶碗は放そうとはせずに、それを鈴の方にそっと差し出した。まだ酒を飲むつもりらしかった。
鈴も燕も大辟の筋金入りの酒と女好きの様に呆れるしかなかった。綿津見はそれを見ながら大辟からこれ以上聞けることはなさそうだと思った。
「大辟先生、ありがとうございました。急なる訪問にもかかわらず多くのご教授に感謝いたします。またお騒がせして申し訳ありません。本日はこれにてお暇させていただきます」
綿津見がそう挨拶して立つと、鈴と燕も立ち上がった。
「先生、あんまりオイタが過ぎはったら、ほんまにあそこ切り取る女も出てくるさかいな」
燕が笑いながら忠告した。大辟もまた苦笑しながらも「わかっておる」と頷いていた。
三人が家を出ようとしたとき、何かを思い出した大辟が声をかけてきた。
「そうや、忘れてたわ。お主も水銀を使うた薬を調合しておるといっておったな。どないな薬か知らんが、薬種の組み合わせには気付けることや。わしの読んだ漢籍の中に『組毒』という言葉があった。水銀と何の薬種の組み合わせがあかんのかは書いてなかったが、どうやら頭がやられる毒が生まれるらしい。それを飲んだら人が人やのうなるとあったわ。気つけることや、その情の深い娘が悲しむよってな、わしからの忠告や」
その言葉に綿津見は「承知いたしました。最後までありがとうございます」と答え、三人が同時に大辟に向かって頭を下げていた。
「やはり悪い人間ではないようだ」と三人は同じ感想を抱いた。
大辟の家を出て川渡しまで戻ったとき、綿津見は鈴と燕に謝罪した。
「不快な思いをさせてすみませんでした。しかし成果はありました、お二人のおかげです」
綿津見の言葉を燕が訂正してきた。
「二人やおへん。うちのおいどのおかげや」
綿津見の方に尻を向けると、自慢するように「パンッ」と尻を叩いた。
武家の娘らしくない行動に綿津見は面食らった。
そして大辟が最後にいった「情の深い娘」という言葉が頭をよぎった。確かにそうかもしれないとどこかで納得していた。
(四)
鴻池の御隠居から闇夜に出帆する不審船の話を聞いてから、籐伍と渦彦の二人は幾日も天保山で夜を過ごしていた。対岸の灘や西宮の浜では金蔵と銀蔵も見張り番を続けている。
この二組は闇夜に動く船を探っていたのだった。だがなかなかその成果はあがっていなかった。やはり闇夜に動く船などなかなか見つけられなかったのだ。
ただ灘に出張っていた銀蔵が、ある日の明け方、灘の東にある青木の浜で開かれたばかりの舟屋があることに気が付いた。そしてその舟屋の中に広隆寺の神紋が印された帆布を発見したのである。
そこは普段は閉じられたままの舟屋らしいのだが、その日は船の修繕か船底の貝殻落としの作業をするために開かれたようだった。
偶然に夜の見張りを終えて帰ろうとした銀蔵がその光景に出くわしていた。銀蔵は何食わぬ顔をしながら、開かれた舟屋の中を覗き込んだ。船横に畳まれた帆布の上には黒く染められている広隆寺の紋所、十六菊花紋に太の字があった。
銀蔵が帆布に染められた紋を凝視していると、背後から声が響いた。
「おまえ、どこのもんや。何でここへ入ってるんや」
潮焼けしたいかつい体格の水主が二人、入り口に立ち塞がっていた。
銀蔵は「まずい」と思ったが動揺は表には出さず、何気ない調子で二人に尋ねていた。
「ここは西海屋はんの舟屋とちゃうんか。今日夜明け前に来るようにいわれたんやけど、大坂もんやからこの辺りがようわからんよって。西海屋の紋とちゃうんかと見とったんや」
いかにもなりたての水主が迷っている風を演じたのだった。少し銀蔵を怪しんでいた水主だったが、「西海屋の舟屋はもっと西や。ここはちゃうで」とぶっきらぼうに答えた。
「それはすまなんだな、間違えたわ。そやけどここはどこの舟屋なん? 作りも立派やし、この紋もよう知らんわ」
銀蔵は間違えた振りを好機とばかりに、この舟屋の持ち主を聞いてみた。
水主二人は顔を見合わせて少し躊躇したが、「越後屋や」とだけ答えた。
「越後屋って……あの江戸の大店の?」
銀蔵はわざとらしく驚いてみせた。越後屋は三井家の屋号である。
「へぇー、やっぱり立派な舟屋のはずや。西海屋はんのはもっとしょぼいとこやろ。間違うてすまなんだな、ほならそっちへ行くわ」
銀蔵が舟屋から立ち去ろうとしたとき、水主が声をかけてきた。
「おまえ、名前は何や。今度西海屋のもんに聞くさかい」
「わいは銀蔵や。渦彦の紹介で入ったていうてくれたらわかるやろ」
そうあっさり答えると、「ほなな」といって歩き出した。しばらく行くと銀蔵は後ろを振り返った。二人の水主はもう銀蔵に興味がなくなったのか、舟屋に入ろうとしていた。
だが銀蔵は二人の背に、「双葉葵」の紋があることを確認していた。木乃嶋衆の神紋である。銀蔵は「ここが当たりやな」と少しほくそ笑んだ。
急いで大坂に戻り籐伍に伝えねばと思った。それに清兵衛の西海屋にも伝えておく必要があるだろう。問い合わせられ、怪しまれたら舟屋の発見が台無しになってしまう。拠点を移されては元も子もなくなるからだ。
朝焼けの中、銀蔵は意気揚々と大坂の籐伍の元に急いだのだった。
銀蔵からの報告を受け、籐伍はいよいよ次の新月の夜に鬼没盗を一網打尽にする策略を渦彦や恭一郎、河原崎と相談したのだった。
捕縛策は捕り方を二手に分け、鬼没盗が出来する確率の高い新月前後の夜に天保山と青木の浜で盗賊仕事を終えた鬼没盗を待ち伏せるのである。
天保山側はあくまで追い出し役、到着する青木の浜で船ごと捕える策だった。天保山側で全員の捕縛を試みる手もあるが、万が一船を逃した場合に追えなくなる。ここは獣の猟と同じく、巣に追い込んでから仕留める方が上策だと考えたのだった。
しかし問題が二つあった。それはまず青木の浜の管轄権である。
本来西宮から西の地域は元々尼崎藩の領地である。大坂奉行所に捕縛の権はなかったのだ。ただ西宮や灘五郷の酒作りが盛んになったことで、少し前から状況が変わっていた。
西宮から灘五郷に至る浜から内陸一里ほどまでにある村々は幕府に公収されて天領扱いになっていた。大坂城代の支配が及ぶように制度が変わっていたのである。そうなるとそこの司法権を大坂奉行所が代行することも可能になる。直接的ではないが大坂城代の許可があれば奉行所による捕縛も可能になるのだった。大坂城代と奉行所との政治的合意が必要だった。
青木の浜での捕縛は、大坂城代、大坂奉行所の睨み合い状態の地で行われることになるのだ。籐伍はここにおいても鬼没盗はうまく幕府の管轄の盲点を突いていると感じた。
籐伍は全体の捕縛策を立案すると、その捕縛処方を吟味方筆頭与力の丹羽に上申したのだった。籐伍の上申書を読んだ丹羽は渋い顔になった。無理難題が多過ぎたからである。
「兎に角お奉行に相談申し上げるさかい、少し待っとれ」
丹羽は少しといったが、そこから結局三日ほど吟味方と奉行の協議にはかかった。そしてやっと出た結論は計画の一部修正だった。
当初の計画では天保山での追出し役を河原崎の同心衆に担当させ、籐伍は青木の浜での捕縛に臨む予定だった。それが変更させられた。
籐伍が天保山での追出し組の指揮を取り、青木の浜での捕縛組の指揮は父の念十郎が取るように奉行から申し渡されたのだ。それに加えて大坂城代との交渉役も父念十郎が担当することになった。
確かに籐伍ではまだ政治的交渉は無理だった。それに比べ念十郎は経済政策を長年執行していただけに、大坂城代にも大きく顔が効いた。念十郎の経済政策の恩恵を受けているからである。交渉相手が念十郎となると大凡のことは拒否できなかった。奉行と丹羽の慧眼というべきだった。
だがこの人事変更でも解決できない問題があった。それは綿津見が掴んできた鬼変薬製造の黒幕らしい人物の居所である。
青木の浜から北の金鳥山に登った保久良神社。
青木の浜の至近ということは鬼没盗の黒幕に間違いないように思えたし、もしかしたら鬼没盗の本拠地が保久良神社にあるのかもしれなかった。しかしその場所が問題だった。完全に尼崎藩領内になってしまい、保久良神社に関しては交渉の余地もなかった。
だが黒幕や本拠地を放って置く訳にはいかなかった。もし古瀬稀人と鬼没盗一味を全員捕縛できたとしても、この黒幕が再び鬼没盗を組織するかもしれないのだ。
悩む籐伍たちに、隅で話を聞いていた綿津見が静かに手を挙げていた。
「私が参ります。私は奉行所の人間ではないし、この話を掴んできたのも私です。私が行くのが筋と思います。私はその黒幕にどうしても聞きたいことがあるのです。これは他人には任せられない、巨勢の棟梁の役目です」
渦彦が「わいが兄上と共に保久良神社に行きます」と発言した。皆は渦彦を見ながらそれが良いのかもしれないと思った。だがそれに対しては綿津見自身が反対をした。
「それはあかんで。渦彦には古瀬稀人と決着をつけるいう役目がある。これは叔父上から託された命や。そやから温羅の蹴速を学んだんやろ。私は巨勢の棟梁としての役目を果たすさかい、渦彦は蹴速術継承者の責を果たさなあかんで。私は一人で参ります。ご心配されるな、私も蹴速術を使えるのです。普通の相手になら負けまへん」
皆を安心させるように明るくいった。
「この話は少し待っていただきたい。父上の意見を聞いて決めたいと思いますよって」
籐伍は一時保留を申し出た。青木方面の指揮者は念十郎である。籐伍の判断に皆が頷いていた。
その翌夜念十郎は綿津見と何かを語り合った後、籐伍に結論を告げた。
「保久良神社には綿津見殿に行ってもらうことにしよう。ただお体のこともあるさかいな、手前の西宮までは燕と鈴を同行させる。ほんで神社には金蔵に一緒に行ってもらおうと思う。いざというときに私の元へ走るためにな。お前の手勢が減るがかまわへんか」
父の言葉に籐伍は深く頷いていた。金蔵は天保山で籐伍の配下に入る予定だった。
こうして鬼没盗との最後の決着つける布陣が決まったのだった。
天保山の追出し組には籐伍と渦彦、河原崎や同心、小者衆。
一方、青木の浜の捕縛組には、父念十郎と恭一郎の同心衆、先乗りとして越後屋の舟屋を見張るために銀蔵が青木に先発した。
そして保久良神社には綿津見と金蔵が向かうことになった。
これを鬼没盗との最後の捕縛にすべく、全ての準備がなされた。
その夜はすでに三日月まで月が満ちていた。籐伍の追出し組が新月前夜から始めた張り込みも四夜目になろうとしていた。
もう夏が終わったような涼しい風が天保山の埠頭を渡っている。昼間はまだ蒸し暑い日が続いていたのだが、夜には変わって秋が忍び寄っていた。
天保山の埠頭にはあまり建物がなかった。
少し離れると荷積み倉庫が沢山あるのだが埠頭には何もない。籐伍たちが隠れる場所がないのだ。埠頭横には船手番所があるが、人が集まると警戒されてしまう可能性がある。
結局それを解決してくれたのは清兵衛の西海屋の荷船だった。天保山に停泊する西海屋の荷船を提供してもらい、その船に潜むことにしたのである。交代の同心や小者は少し離れた荷積み倉庫に控えていた。
夜も更けた頃、空の三日月が雲に隠れようとしていた。もともと少ない月の光がなくなり、辺りを闇が支配するようになっていった。
そのとき、沖から一艘の帆船が港に入ってきた。埠頭の突端には常夜灯があるとはいえ、闇夜に入港するのはかなり危険がある。
荷掛けの帆布の隙間から外を警戒していた籐伍と渦彦は、入港してきた船に注目した。多分燐船で同じように警戒にあっっている河原崎たち同心衆も気づいているはずだった。
張り込みをしている籐伍らが音を立てずに凝視する中、入港してきた船は静かに天保山の岸壁に接岸していったのだった。
静かに、そして手早く船中から黒い影絵の水主が現れ、言葉を一切発せずに接岸作業を開始していた。船から綱を岸壁に投げ、そこに降り立った別の水主は黙ったまま綱を岸壁の杭に舫っていった。
この光景を凝視していた渦彦が少し焦れたのか動こうとした。
その動きを隣の籐伍が腕を強く掴んで制止した。まだ動くべき刻ではないと示した。
渦彦も分かっていたが、頭よりも体が動き出そうとしていたのだった。
そのまま、影絵の水主たちが船を岸壁に固定し終えると、再びあたりを夜の静寂が支配していった。まんじりともせずに籐伍たちは荷船の中で刻を待っていた。
やがて天保山に至る安治川の上流方向から一艘の三十石船が港に入ってきた。京の伏見から大坂の八軒家までの物流や人流のために淀川や大川でよく使われている川船である。
その三十石船が静かに天保山の桟橋に入っていった。しばらくするともう一隻、三十石船が桟橋に入ってきた。三十石船ぐらいの小舟だと海面から高い天保山の岸壁には直接接岸できないので桟橋に船を着けるのである。この二隻は普通の荷や人を運ぶ船とは少し異なり、屋根が設えられた屋形船になっていた。
天保山の安治川に面した場所の桟橋と、大坂湾に面した岸壁に接岸した帆船との間には少し距離があった。この距離こそが今夜の舞台だと感じた。
鬼没盗は市中を三十石船で移動し、天保山で帆船に乗り移って大坂湾外の海に脱出する。人目につかずまた奉行所の取締りの網にも掛からない絶妙の方法だと籐伍は思った。
ただ天保山での乗り換えの機を除いてである。それが今だった。
籐伍は目を凝らしながら、船から人が降りて来るのを待っていた。
だが桟橋についた三十石船からは人が降りてこない。少し経つが人の動きがなかった。
「何ぞ警戒してるんか」
籐伍も次第に焦れながら待っていると、夜空の雲が少し切れてきた。全くなかった光がわずかに戻り、三日月の光が天保山の埠頭を僅かながら照らし出していた。
僅かな光の下に、屋形船から降り立った人々の影が映されていた。前の三十石船から四人、後ろの三十石船からも四人の影が見えた。
合計八人、思ったよりも多人数である。
こちらはこの荷船に籐伍と渦彦に小者一人の三人、隣の荷船にも河原崎と同心一人、それに小者の三人である。まずはこの六人で屋形船を降りてきた八人の帆船への乗船を阻止する必要があった。
河原崎が合図の呼び笛を吹けば、近い荷積み倉庫に控えている加勢の捕り方が天保山の港から内陸への出入口を塞ぎ、同時に荷船に隠れる六人の加勢に入ることになっていた。
それに天保山の捕り方はあくまで追い出し役である。一人でも多く捕縛するに越したことはないが、全員を捕らえる必要はなかった。帆船に逃した賊は青木の浜で念十郎の捕縛組が捕らえるのだ。
だが籐伍と渦彦はただ一人、古瀬稀人だけはここで捕縛したいと考えていた。他の者は青木の念十郎に任せてもよい。二人にとって師である椎根津の死の原因である稀人だけは逃したくはなかった。
船から降りた人影の五人が、帆船とのちょうど中間地点に差し掛かった。
そのときを待っていた様に籐伍は被っていた帆布を素早く静かに除けると、荷船から飛び降りて天保山の岸壁に着地した。そして腰に差していた鈍い銀色の十手を引き抜いていた。
ここまでの籐伍の動きは実に素早かった。だがそれよりも早かったのが渦彦だった。
籐伍が体勢を整えて走り出そうとしたとき、渦彦は前を走っていた。
まるで黒い稲妻が地を疾っている様に見えた。屋形船から降りた影法師は渦彦の接近にまだ気がついていなかった。速く、それ以上に静かな疾走だったのだ。
だが渦彦が影法師に到達する前に、闇を切り開くような鋭い笛の音が鳴り響いていた。隣船から降りた河原崎が鳴らした呼び笛の音だった。笛の音が天保山に響いていた。
その笛が事態を急変させた。影法師は急接近する渦彦に気がついた。そして瞬時に五つの影法師が扇型に広がると、渦彦への迎撃態勢をとっていた。それは光に突進する虫を捕らえようとする蜘蛛の巣の様にも見えた。
後を追う籐伍は一瞬「あっ」と思った。相手の動きが驚くほど早く、また統制が取れていた。鴻池の隠居所で捕えた賊とは何かが違って見えた。
「よく訓練された賊だ」
籐伍が思ったときには、渦彦の姿を包む様に扇が閉じていった。
渦彦の体が瞬間、宙を舞った様に見えた。
それは宙を舞ったのではなく、前面にいた影法師を足技で一撃した後、影法師を踏み台にして宙を駆け登っていたのだった。
渦彦は宙空の一点で体を旋回させると、右側にいた影法師の頭部を旋回する左足が薙いでいった。
籐伍は渦彦が薙いだ左足で影法師の頭部が消失した様に見えた。
だが影法師の頭部は消失してはいなかった。いや寧ろ反撃に蹴り上げた影法師の足が、渦彦の薙いだ左足を受け止めていたのだった。
それは渦彦と同種の技だと直感できた。
「影法師も蹴速術を使っている」
そう思った籐伍は、あの影法師が古瀬稀人なのかと思った。
だがその思いはすぐに掻き消されていた。
渦彦が最初に一撃したはずの影法師が、今度は地の底から伸び上がる様な上への蹴りを空の渦彦に向かって放ったのだった。蹴速術の基本蹴りの一つ、昇龍脚である。
「あの影法師も蹴速の蹴りを使っている」
いや下からだけではなく、左側の影法師もまた、渦彦に向かって蜻蛉を切る様に逆回転しながら上方から蹴り下げてきたのだった。
三方からの攻撃に一瞬止まった渦彦は、下から蹴り上げられた昇龍脚の足裏に右足を逆に当てて踏み台にした。そして横に大きく体をひねりながら逃れていった。
五つの影法師から少し離れた地に着地した渦彦は、そこで腰を深く沈ませながら影法師の出方を待ったのだった。蛙の構えである。
渦彦も驚愕の事実に気がついていた。影法師五人は皆が蹴速術を使えるのだということを。
「渦彦、前に出過ぎるんやない。加勢が来るまで皆で囲むんや」
叫ぶ籐伍が渦彦のすぐ後ろに到達していた。その後ろからは更に河原崎らの三人が距離を詰めようしていた。
まずは数的有利を作ってから一人ずつ捕縛する。それが最初の計画である。そうすれば数的有利を維持しながらも、荷積み倉庫から駆け着ける加勢の捕り方とも合流できるのだ。
渦彦と籐伍は並んで五人の影法師に対峙した。お互いがしばし沈黙の中で睨み合う格好になった。その間に河原崎たちは横に回り込み、影法師と岸壁の帆船との間に入った。上手い位置取りだった。
これで帆船に至るにはどちらかの囲みを突破しなければならない。どちらかを抜こうとすれば、もう一方の囲みが背後から捕縛に入れるのだ。
膠着した状態が続くうちに、二人の小者が長刺股を持ってそれぞれの後ろに控えていた。やがて荷積み倉庫の捕り方も加勢にやって来るだろう。
籐伍はこの状態を維持できればこちらの策通りだと思った。
だがそうはならなかった。影法師は互いに何かを示し合わせると、同時にそれぞれが異なった方向に向かって同時に走り出していた。
籐伍はここで判断が遅れた。自分たちの左側を走る抜ける影法師と、右側を迂回して走る影法師、どちらを捕らえるのかを一瞬躊躇してしまった。
「籐伍、右を捕らえ。左はわいが抑える」
渦彦の怒鳴り声に、籐伍も考えるよりも早く足が出ていた。
右側の敵は迂回しながら、後ろに控える刺股を持つ小者を狙っていた。長い獲物の敵から潰すという理に適った攻撃だった。
籐伍が振り向きざまに小者の方に走ろうとしたが、それよりも早く影法師が小者に到着しようとしていた。だが小者とて刺股が使えるのだ。すぐにはやられまいと思った。
定石通りに接近する影法師に刺股を鋭く突き出した小者だったが、その二股に割れた間から影法師の姿が消えていた。いや、消えたのではなく刺股の長柄の上にまで飛んでいたのだった。そして長柄の上をまるで走る様に移動すると、そのまま小者の脳天に蹴り上げた踵を落としていた。
蹴速の技、落月踵だった。
声も上げずに小者はその場に崩れ落ちていった。
籐伍がそこに至ったときには、影法師は小者の向う側に着地していた。そして倒れた小者を挟んで籐伍と対峙したのである。
反対側では渦彦がもう一人の影法師と戦っていた。
左側を走り抜けようとした影法師に、渦彦は低い位置での旋回脚を繰り出していた。それはまるで大地の草を刈り取る大鎌のような軌跡を描いていた。相手を倒すためというよりも逃げる足を狙ったものだった。
影法師が走る足を止めて、少し足を浮かして旋回脚を避けた。だがそれが隙になった。
一瞬留まった影法師に対して、渦彦はその低い位置のままから瞬時に接近すると昇龍脚を放っていた。
影法師はその蹴りを鎧手で防いだが、渦彦は間髪を入れずに第二の昇龍脚を放った。
かろうじて鎧手で横に避けた影法師の体と鎧手の間に生じた隙間に、第三の昇龍脚をねじ込んだ。渦彦の足は影法師の顎を砕いていった。
昇龍三蓮華、回避不能の連続技である。この技を避けるには防ぐのではなく攻撃し返す必要がった。隠居所で稀人が放った昇龍三蓮華を渦彦が落月踵で切り返したように。
「こいつら蹴速術は使えるが、技はあれへんな。それにそれほど強うない」
そう観察した渦彦は、倒れていく影法師ではなく周囲の状況を素早く確認しようとした。
これくらいの強さなら籐伍や河原崎でも足止めはできると感じた。ただそれは古瀬稀人以外の相手ならばではあるが。
二組による囲みが破られたことで、五人の後ろから接近していた三人の影法師が獣のような速さで二組の間を駆け抜けていった。
「あの三人の中に稀人がいる」
渦彦は直感的にそう思った。渦彦は迷うことなく三人の影法師を追った。
一方、籐伍は対峙する影法師を凝視しながら、手に持っていた十手を後ろ腰に差し戻した。そして徐に脇差しの柄に手を添えた。
「こういう手の内がようわからん相手には、不慣れな十手や大太刀やと不覚を取るわ。わいにはやっぱり小太刀の方がええな」
この影法師が本当に蹴速術の使い手ならば、是非とも試してみたい事があった。かつて渦彦と対戦したときに外された八艘である。
籐伍はずっとあの対戰を考えていた。そして八艘で渦彦に勝てる方法はないものかと思案していたのである。意外にもその解決の糸口を与えてくれたのは椎根津だった。大和で猿飛陰流の稽古に参加していたときに、籐伍はその思案を椎根津にぶつけてみた。
椎根津は蹴速術も剣術も使えるので、良い思案があるかもと思った。
椎根津は微笑みながら「ただ相手をよう見ることやな。そしたら『後の先』が取れるさかい。人は攻撃しようとした瞬間に一番隙が見えるんや」とだけ教えた。
最初は何を教えられたのかわからなかったが、言葉を反芻しながら幾度も渦彦との対戦を思い返してみたのだった。
そしてある結論に至ったのである。
「後の先を取るいうんは、結局後出しの石拳(じゃんけん)やな」と思った。要はこちらに勝てると思って出す相手の技にこそ、つけ込む隙があるのだと理解した。
そういえば渦彦との戦いでも、籐伍の刀を封じるために出した渦彦の掌底に、逆に一死を報いることができたのだ。渦彦も読みきれなかった自分の負けだと自嘲していた。
八艘が技として駄目なのではなく、相手の隙に叩き込めない自分が駄目なのだと理解した。
「ではこの相手に椎根津先生の教えを試してみよう」
そう覚悟を決めた籐伍が、ゆっくりと影法師に近づき始めた。その歩みはかつて渦彦と戦ったときと同じように力みのない自然体の歩みだった。
籐伍は口元に微笑みさえ浮かべていた。だが口元とは裏腹に全身の五感が周囲に蜘蛛の糸のような探知の網を張っている。そして影法師が攻撃に出る瞬間を捉えようとしていた。
第六幕 灘のひとつ火、そして……
(一)
渦彦は帆船に向かって逃げる三人の影法師を追った。
影法師は帆船にたどり着くと、最初の一人が舷側に張られている荒縄で編まれた網にしがみついた。その網をよじ登って船に上がっていったのだった。次の影法師もそれに倣い網に取り付くと甲板に登っていった。
最後の影法師が岸壁で立ち止まると渦彦の方を振り向いていた。そしてまるで「こっちへこい」とでもいうように手招きをした。
渦彦は最初手招きが何の意味かわからなかった。だが影法師が自分を誘っているということに気がついた。影法師は古瀬稀人に違いないと思った。
その影法師が突如声を出してきた。
「お前、宗家の者だろう。ならば俺にも好都合だ。ここで決着をつけようではないか。お前にその覚悟があるならだがな」
そう言い捨てるとスルスルと網を掴んで登っていった。渦彦は稀人の言葉にあざけるような笑いが込められているように感じた。
突然の誘いに渦彦に躊躇が生まれ、少しの間立ち止まっていた。
その一瞬の隙を突くように、突如後方上空から蹴り下ろしてくる殺気を感じた。見なくてもそれが天空斬の回転蹴りであることがわかった。
渦彦は無意識の中で上から襲う天空斬に鬼神蹴りを放っていた。
天空斬を仕掛けてきた影法師は、宙空にいる間に鬼神蹴りの餌食になっていた。
「どさっ」という音と共に、影法師の体は大地に叩きつけられた。
影法師が大地に落ちる音で我に帰った渦彦は、籐伍やほかの捕吏のことを思い出した。そして思わず後方を振り返っていた。
その視界の遥か向こうで、信じられない光景が目に入ってきた。
籐伍が影法師の放った落月踵の動きを一歩先取りしていた。落月踵を躱しながらも、八艘の突きが影法師の蹴り上げた脚を貫く姿が見えたのだ。
蹴速の落月踵に対して小太刀の突きで攻撃し返していた。
「あんな返し方があるんか」
思わず渦彦は自分の目を疑った。籐伍が蹴速の蹴り技を打ち破っているのだった。
他の場所でも河原崎が同心と二人がかりで一人の影法師を取り押さえようとしていた。埠頭の入り口からは、松明を手にした加勢の捕り方がこちらに走り寄ってきていた。
「これで五人は捕縛できるやろう」と渦彦はひとまずの成果を確信した。
残るのは帆船に登っていった古瀬稀人を含めた三人である。
そして天保山での捕り物にはもう渦彦の役目はないと思った。
ならば古瀬稀人との決着を着けようと即座に決心した。
「籐伍、わいはどうしても古瀬稀人と決着を着けたい。あとは頼んだで」
そう叫ぶと同時に、帆船に向かって走り出していた。
帆船の前後では、岸壁に結ばれた固定の舫綱を手斧で断ち切ろうとする水主の姿が見えた。
渦彦は岸壁に接岸する船端まで来ると、影法師と同じように荒縄の網に飛びついていた。そして甲板に向かって登り始めた。
八艘で影法師の落月踵を粉砕した籐伍のもとに、加勢の捕り方が殺到してきた。貫かれた足を抱える影法師を捕り押さえようとした。
捕縛を加勢の捕り方に任せた籐伍は、周囲の状況を確認した。
三箇所で個別に捕縛が行われていた。そして帆船への途上に二人の人間が倒れていた。渦彦が昇龍三蓮華と鬼神蹴りで撃ち倒した賊である。
このとき籐伍はさっき聞いた渦彦の声を思い出した。
「あとは頼んだで」という叫びである。そしてその前には「古瀬稀人と決着」という言葉があったように思えた。
「あいつ、残りの賊を追ったんか」と思いながら帆船の方向を見た。そこには暗がりの中で舷側にしがみついている人の姿があった。あれは賊を追って船に乗り込もうとしている渦彦だと察した。
籐伍は一瞬どうすべきかを迷った。
天保山での役目はあくまで鬼没盗の乗る船の追い出しで、青木の浜で待つ父の捕縛の網に追い込む事である。賊の数を削っておく必要はあったが、それも半ば達成できている。
籐伍のもとに河原崎が近寄ってきた。捕縛した賊は加勢の捕り方に任せたようだった。
「こちらは大方策通りに進みましたな。あとは青木の浜で仕上げるだけや」
河原崎のほっとしたような言葉に籐伍が頷きながら尋ねた。
「青木への早馬はもう出たんですか」
籐伍の確認する言葉に河原崎は大きく頷いた。
「私の呼び笛と同時に早馬がここから青木に向かうように手配してますよって、もう遠に出発してますわ。船足がいかに早うても、まだ天保山を出てへん船よりは先に青木に着くでしょう。それでお父上の捕縛組があの帆船を捕らえることになります。鬼没盗騒動も今夜で終りですわ」
河原崎はやれやれというように答えた。
「そうですか」と呟くと、何かをじっと考えていた籐伍は、徐に右手に持つ脇差しの小太刀を鞘に戻した。腰に帯びていた大太刀を鞘ごと引き抜き、それに後ろ腰に差していた十手を抜いて重ねた。その二つを河原崎に手渡すように突き出していた。
籐伍の意図がわからないまま、河原崎は出された大太刀と十手を受け取った。河原崎の不思議そうな顔に向かって、籐伍はゆっくりと礼をいった。
「ここまでこれたんは、河原崎さんのお陰です。恭兄には与力が同心に礼いうたらあかんといわれましたが、今はやっぱり礼をいいたい。ホンマにありがとうございました。そやけど……そやけどもう一人、渦彦のお陰でもあります。そやからわいは、渦彦に礼をいうためにあの船を追いかけます。与力やのうて友達として」
そういってから、もう出航しかけている帆船を指差した。
河原崎は「えっと」思ったが、同時に分かり切った忠告をした。
「あの船に乗り込むお許しは船手奉行からも寺社奉行からも得てまへんで。今籐伍様があれに乗り込むんは法度破りになります。ええんですか、後で処罰もありますよって」
河原崎の言葉に籐伍は頷きながら、微笑みで返していた。
その表情を見た河原崎は、「こりゃ、言うてもあかんな」と止める事を諦めた。子供のような我儘だが、不思議とそんな我儘が嫌ではなかった。
「すんまへんが、後をお願いします」
そういうと、籐伍はもう離岸しようとしている帆船に向かって走りだしていた。そして岸壁に着くと、大きく飛び付くよう帆船に向って跳躍した。
届かないとも思えたが、籐伍の左手はギリギリで網を掴んでいた。そしてしっかりと両手で網を握りしめると、今度は足を網にかけてゆっくりと上に登り始めていた。
その姿を黙って見ていた河原崎は面白そうに笑うと、すぐに元の生真面目な表情に戻っていた。そして近寄ってきた小者に新しい命令を発した。
「天保山で捕まえた賊は全員最寄りの番所にしょっぴくで。それから次の早馬を青木に出す手筈を取ってんか。伝言は『船に乗り込んでる賊は全部で三人、そんで……籐伍様と渦彦もなんでか乗り込んでる』とな。ほんまに難儀なぼんぼんやで。これやから子供の守りは嫌なんや、もう子供の守りは絶対にせえへん積りやったのになぁ」
それだけをいうと、捕縛した賊たちが集められている方向に歩き出した。
天保山の埠頭は、先ほどまでの捕り物騒ぎが嘘のように静けさが戻っていた。岸壁に打ち付ける波の音だけが闇の中に響いていた。
帆船の上甲板に登った渦彦は、その向こうに男が待っているのを見た。
黒ずくめの衣装が影法師のようにも見えていたが、何故か今は頭巾を取っていた。そして渦彦にその顔を堂々と晒していた。
古瀬稀人。渦彦は初めて因果の果てにいる男を目の当たりにした。
甲板の少し広いところで立ち止まった渦彦は声を出した。
「お前が古瀬稀人か。巨勢の全てを奪おうとする鬼神饕餮であり、我が師椎根津叔父の死の元凶」
そう感情を抑えた低い声で罪状を読み上げるように叫んだ。
稀人は面白そうに渦彦を見ながら、やれやれと首を振った。
「私の名を知っているのか。なるほど先生に聞いたようだな。先生を叔父と呼ぶということは宗家の息子か。確か二人いたはずだが」
そういうと少し考え、舳先や艫に集まる水主と鬼没盗の仲間に大声で指示した。
「お前ら、浜に着くまで手を出すなよ。手出ししてもお前らでは歯が立たたん。怪我したくなかったらそこにおれ」
そして渦彦の方に改めて向かうと、まるで親しい年長者が教え諭すように話し出した。
「先生は身内に甘いなぁ、ちゃんと礼儀を教えておらんとは。よいか、俺はお前の兄弟子になる。その俺に対しているのだ、礼を持ってまず名を名乗ってから話をしろ」
稀人の言葉に一瞬気勢が削がれたが、告発の言葉を止めなかった。
「我が名は巨勢渦彦。巨勢宗家の次男であり次の蹴速術継承者や。お前には叔父上の自害の責と、父の死の真相を話してもらう。必要ならばお前をここで討ち取ることも厭わぬ」
渦彦の告発に稀人は少し苦笑しながら、「まあ、落ち着け」というように傍にあった積荷の酒樽に腰をかけた。
「聞いているとまるで大罪人のようないわれようだな。ではその大罪人に幾つか答えてもらおうか。まず先生の死の責とはなんだ。俺は先生と真剣勝負はしたが殺してはおらんぞ。それに巨勢から全てを奪う鬼神饕餮とはどういう意味だ。以前幾らかの薬は貰ったが、全てを奪ったわけではない。お前の言い分の中で意味がわかるのは宗家の死の真相だけだな」
本当に心当たりがないというように、稀人は渦彦を正面に見据えながら少し首を振った。ただこのときの稀人は、渦彦との問答を楽しんでいるようにも見えた。
渦彦は稀人の悪びれた様子がないことに逆に怒りが湧いてきた。
鬼没盗を作って騒動を起こし、巨勢宗家には取り返しのつかない害禍を及ぼしている。だが張本人である稀人にはその自覚がなかった。別の世界の人間と話をしているような気分だった。
渦彦と稀人のあまり噛み合わない問答だったが、そのとき船縁に籐伍が登ってきた。
甲板に新たな人間が登ってきたことに稀人は少し驚いたが、それ以上に渦彦が籐伍の顔を見て吃驚した。籐伍は賊を捕縛しているはずだからだ。
「今日は全く不思議な日だな。役人の待ち伏せに遭ったり、この秘密の船に次々と客人が来るとは。あいつの神通力も今日はまったく効いてはおらぬようだ。……それで次の客人は誰方かな。まずは名乗ってもろうか。この後どう処分するかが決められぬわ」
稀人の薄笑いを含んだ問いかけに籐伍は戸惑った。だが稀人と渦彦を交互に見てその位置関係を確認すると、ちょっと姿勢を正して稀人に向かって声を出した。
「わいは大坂西町奉行所の仮役与力、阿刀籐伍や。今宵、天保山での鬼没盗捕縛の責を負うている。そやけど今はそこの巨勢渦彦の友として来た。渦彦が因果の糸を断ち切る助太刀をするため推参した」
籐伍のまるで歌舞伎の大見得のような口上に、稀人はまた変な奴が来たという表情になった。だが奉行所の与力という点は捨て置けないと思った。
「邪魔が入ったがどうする。さっきの話を続けるか。それともすぐにここで戦ってもよいぞ。俺にとても好都合なんだよ。お前が蹴速術の継承者を名乗るならば、そのお前を下せば俺が継承者になる。椎根津先生の許しを得ずとも我らの間でそれは決しよう」
稀人の言葉に渦彦の感情がついに沸騰した。話の続きのように椎根津の自害を語った。
「叔父上はお前の盗賊働きや父上への仕儀を知り、自らその責を負うて自害された。この世界にあってはならぬ、蹴速を使う古瀬稀人を生み出した責任を取られたんや」
少し涙に詰まっていた。対して稀人の声が急に堅くなった。声から戯けた部分が消えていた。
「それはお前が教えたのか。先生は何も知らないはずだ。俺はずっと先生とは無縁の世界で生きていた。だが……そうか先生は知ってしまったのか。ならば責の大半はお前にあろう。知らなければ先生は死を選ばずに済んだのだ。先生が自害へ歩まれたのならば、それはお前の告げ口のせいだ」
稀人のいう理に渦彦は言葉を失った。叔父に蹴速を使う者が自分達以外にいるのかと問うたばかりに、叔父は自らの罪過を自覚してしまった。それが自害への第一歩となった。
稀人の理は勝手極まりない考え方だが、まったくの的外れとも思えなかた。渦彦の心の中でもこの理はずっと静かに沈殿していたのだった。
言葉を失っている渦彦に代わって、少し離れた場所から籐伍が反論した。
「それはちゃうで。椎根津先生はたとえお前の盗賊働きを知らずとも、ずっと渦彦の父上の死を怪しいでおられた。しかもその死因が蹴速によるものかもしれへんと気づいてたんや。そやから渦彦の父上の死は古瀬稀人の仕業かも知れへんと心を痛めておられた。わいが桜井の道場で稽古してたときにも、椎根津先生はそう懺悔されていた。ただそれをいうと渦彦を苦しめるよって、いわなんだんや。わいに蹴速の存在や巨勢の秘事をあえて明かされたんは、渦彦らがお前に底無しの恨みを抱かんようにするためや。椎根津先生はホンマに誰も恨んではおられなんだ。そやから先生はわいに……わいにお前さえも救うて欲しいと願われて後を託されたんや」
籐伍は堅い表情になっていた稀人に思いをぶつけた。
椎根津は巨勢だけではなく弟子の稀人も救いたいと考えていたのだと。
籐伍の言葉に、稀人と渦彦は打ちひしがれたように体から力が抜けたように見えた。籐伍は重ねて、罪を償うように促そうとした。
だがその言葉を口に出す前に、突如稀人が前に出た。それは渦彦との距離を一瞬で詰めるような思議な気配のない移動だった。
稀人はまるで瞬間移動したように突如渦彦の全面に達した。そして不可解な方向から、渦彦に向かって稲妻のような蹴りが襲っていた。籐伍にはそれがまるで突然もうひとり稀人が出現して、別の稀人が渦彦の背後から襲ったように見えた。
だがそれこそが鬼神蹴りだった。伝説の温羅の蹴速撃ノ壱である。まさに鬼神の名に相応しい予測や回避不能な蹴りだった。その蹴りに渦彦の体が貫かれたと思った。
だが稀人の鬼神蹴りは虚空を貫き、渦彦の姿はその場にはなかった。その光景はかつて籐伍が八艘の突きを外された瞬間と同じように見えた。
「下か」と思って稀人の足元を見たが、渦彦の姿はそこにもなかった。そして同時に稀人の頭上からは竜巻のような蹴り下げが襲ってきていた。
温羅の蹴速撃ノ参、空震弾だった。
稀人を襲った上からの竜巻が甲板上で弾けたと思えたとき、稀人と渦彦が位置を入れ替えたように新たな対峙する場所にいた。
籐伍は竜巻が弾けた場所の甲板が、大きく裂けていることに気がついた。大海の嵐にも耐える甲板が、今の渦彦の攻撃で破壊されているのだった。
「この前よりはできるようになったか。温羅の蹴速も仕入れたようだしな」
不敵な声で稀人が呟いた。
少し離れた場所に移動していた渦彦は片足立ちの姿勢から、右足を大きく後ろに回した構えをとっていた。蹴速術基本の構え、鬼骨の構えである。
時と場所が異なるとはいえ、同じ師に同じ技を習った二人である。相手の技は未来が視えるように予測できていた。
籐伍は今の攻防を見ただけで、とても手が出せないと感じた。
先ほどの天保山で戦った影法師の技とは雲泥の差があった。
影法師の蹴速術には「後の先」も取れたが、今の二人の攻防では正直何が行われていたのかもよく理解できなかった。「後の先」どころの話ではない、籐伍には技そのものが見えていないのだった。
「先生はやっぱり甘い人だ。蹴速を巨勢から奪おうとする俺を救いたいとは。その甘さが結局は先生を滅ぼし、蹴速の真の価値を考えられなかったのだ。千年の禁忌を破れなかった先生の限界よ」
稀人の挑発する言葉に渦彦は反応をしなかった。
少し前から静かで音のない世界にいる感覚が渦彦を支配していた。
激した感情の向こう側に広がっている無音の世界、その中に渦彦は佇んでいた。さっきの稀人の奇襲攻撃にも反応できたのは、この感覚を纏っていたからだった。この無音の世界に進入する存在のわずかな波動が、考える前に渦彦を動かしていた。
反撃の空震弾を使ったことさえも渦彦の意識にはなかった。
そんな状態の渦彦を詰まらないと思ったのか、逆に厄介と感じたのか、稀人が意外な話を始めた。
「お前の父、巨勢宗家の死に際を教えてやろうか。どのように無様に逝ったのかを」
その言葉に渦彦がわずかに反応した。無音の世界から騒めきの世界が蘇っていった。
渦彦の変化を感じ取った稀人は、満足そうに話を続けた。
「俺は宗家に巨勢に伝わる鬼変薬と聖徳太子伝来の宸翰の譲渡を申し入れた。もしそれが受け入れられぬのならば、まずは今の蹴速術継承者である椎根津先生を殺すとな。そしてその後には次の継承者も倒すと。蹴速術の継承者がいなくては鬼変薬も意味がなくなる。そして……宗家は誠に面白い提案を返してきた。自分と戦い勝てばその二つを譲渡しようといったのだ。笑えるだろ、宗家も蹴速術は使えるのだろうが継承者ではない。俺は真の継承者である椎根津先生と互角なのだ。宗家なぞ敵ではない」
渦彦はそのときの父の気持ちを想像した。
かつて兄の綿津見は自分を守るために代わりに鬼変薬を飲んだ。そして父は……敵わぬかもしれぬと思っていても、弟と子供を守る為にこの古瀬稀人に戦いを挑もうとした。二人とも同じように自分の大切な人を守ろうとして命を賭けたのだ。
「まず宗家は俺との間に求めた一つ目の太子の宸翰を置くと、胸元から皮袋を取り出したのさ。そして俺に『これが鬼変薬じゃ』といってその皮袋に入ったものを飲み干し出したわ。俺は黙ってそれを見ていたが、やがて宗家は奇妙な変貌を始めた。そう、鬼の身体にな」
その後の戦いは椎根津とのものとはまた違っていたらしい。渦彦の父は温羅の蹴速を修めてないので鬼神術は使えない。繰り出されてきたのは表の蹴速術だった。だがその一撃、一撃の打撃の力は師である椎根津の使う温羅の蹴速に劣らないものだったらしい。
繰り出される一撃が異常に重く、稀人の骨や筋肉を軋ませた。
そして稀人にとっては大した技ではないはずが、その繰り出す速さと初動から到達までの時間が普通とは違っていた。見切ったはずの技が稀人に次々に当たっていったのだ。
「だが少し経つと宗家の様子が変わっていった。まるで俺が見えていないかのように虚空に攻撃を始めたのさ。俺は構えを解いて暴れる宗家をしばらく見ていた。その間も宗家はまるで幻と戦うように唸り声を上げ、天に向かって咆哮をしていた。その姿は理性を失った狂った鬼そのものだったぞ。そして最後の刻がやってきた。宗家は何かに縋り付くように座り込むと、腰に差していた懐剣を引き抜いて、突如胸元を突いたのさ。その様はまるで鬼変薬の苦しみから逃れるために自決したようにも見えた」
稀人が宗家に近づくと、息絶えたはずの体が突如掴みかかってきた。そしてそのまま懐剣の刃で稀人の胸を貫こうとした。稀人は一撃で息絶えるように、鬼神蹴りで宗家の背骨を叩き折ったという。
「幻に浮かされて俺を襲ったのか、あるいは相討ちを狙って俺を誘ったかはわからぬが、どちらにしても宗家は千年守ってきた仙薬に殺されたのさ。歴史の檻の中で生きた巨勢宗家には相応わしい死に方だな。どうだ、これがお前たち一族の未来の姿だ。俺はそうはならぬために、新しい鬼変薬を作る。そして巨勢そのものを過去の遺物にしてやるつもりだ」
話しながら古瀬稀人は恍惚としていた。自分の描く未来図に酔っているように見えた。
渦彦はそんな稀人を見ながら「この男はやっぱり饕餮だ」と感じた。
今は巨勢の全て喰らおうとしている。そして巨勢を喰らった後は、また別の何かを喰らおうとするのだろう。それはこの男が滅びるまで続く地獄絵図だと思った。
最早父や叔父の死の元凶というだけではない。どこかこの世界にいてはならない存在だと感じた。そのために渦彦はこの男を討とうと決心した。
それはもう単に仇討ちではなく、神話世界の勇者が世界を乱す魔獣を滅するために戦うことを決めたのに近かった。
渦彦が静かに一歩前に進み、稀人と最後の戦いに挑もうとした。
そのとき船の舳先にいた水主が叫んだ。
「ひとつ火が見えるで。灘のひとつ火や」
船上の人々の目が、一斉に暗闇の中に聳える北の六甲山の方向を見た。
そこには小さいがなぜか目を魅きつける赤い灯火が見えた。それは太古より古事記や日本書紀にも語られている海に浮ぶ炎の道標、灘のひとつ火の焔明りだった。
(二)
暗い山道を綿津見は登っていた。少し前を金蔵が静かに歩いている。その歩みは音を消した獣のような歩みだった。金蔵の前身は盗賊と聞いていたが、その頃の技のようだった。
突然、少し先の闇の中に「ぼーっ」とした明りが灯った。それはまるで闇夜を照ら道標のようにも見えた。
気がつくと、さっきまで先を行っていた金蔵の姿が消えていた。
この明りを怪しいと睨んだのか、山道から外れたようだった。綿津見は保久良神社のある金鳥山麓の宿に鈴と燕を残してきて良かったと思った。
一行は三日前に金鳥山麓にある本山村に到着したが、しばらくは休息を取りながら天保山からの鬼没盗出来の知らせを待っていたのだ。だが三日経っても知らせがなかった。
今一番気をつけるべきは相手に気取られることである。そのために天保山で動きがあるまで動くことを控えていた。
だが闇夜といえるのも今夜が最後だった。今夜を逃せば新月はまたひと月先になると思った綿津見は、保久良神社への登拝を決心したのである。そして金蔵と二人で金鳥山を登り始めたのだった。
ゆっくりと山道を登る綿津見だったが、その先の暗闇に突如灯った明りの正体を見た。
それは巨大な石灯籠ともいえるような灯火台だった。神社にあるような綺麗に細工された灯籠ではない。まるで幾つかの自然石を組み合わせて作った祠か磐座に近い荒らしい威容の灯火台である。
巨大な灯火台のすぐそばに人影があった。手に松明のような物を持っているので、この人影が灯火台に火を点けたのだと思った。綿津見はそれでも沈黙したまま山道を登り続け、もうすぐにも煌々と焔が焚かれている灯火台に到着しようとした。
人影はずっと前から綿津見に気が付いていたらしく、南に広がる黒々とした瀬戸の海ではなく綿津見の方を見ているようだった。
「このような闇夜に神参りとは珍しい。まるでこのひとつ火に招かれたみたいですね」
灯火台の焔で綿津見の顔が見えるのか、人影が口を開いた。
人影からは焔に照らされた綿津見の顔がよく見えているのだろう。だが綿津見からは人影がまるで光背を背負った仏像のように逆光になり、その顔はよく見えていなかった。
「ですが闇参りはあまり感心しません。昼は神の庭である社も、闇夜には魍魎たちの宴の場にもなります。夜が明けてからの参拝をお薦めしますよ」
それだけをいうと、人影は灯火台のすぐ横にある巨大な石に腰を降ろした。そしてまだ闇の中にある瀬戸の海を眺めだした。
綿津見は石に座った人影、まだ若そうな男の五間ほどの近くまでくると声をかけた。
「保久良社のお方でしょうか。私も大和で神職をしております。闇参りへのご忠告はかたじけないが、どうしても今夜でなくてはならない理由があって参りました。少しお話をしてもよろしいか」
綿津見の言葉に頷いた男は、綿津見の近くの巨石へ手を差した。座れということらしい。
巨石に座った綿津見は、少し角度が変わったせいで男の顔と服装がよく見えた。最初若いと思った顔は、思った以上に年老いているようにも感じた。灯火台の明りで顔に強い陰影が生じているせいか、どこか底知れない闇を内包しているようにも見えた。
それに服装が少し変だった。
保久良神社の人間ならば神職姿のはずだが、男は不思議な貫頭衣のような衣を着ていた。まるで異国の衣か、古代から蘇った人物のように見えた。
「私はここの社の離れ家にいると聞きく、ある方を尋ねて参りました。ご存知ならば教えていただきたいのです。その方は大坂の漢学者に丹を使う薬を研究させているらしいのです。私も丹を使う薬を学んでおりますゆえ、どうしても会ってお話ししたいのです」
綿津見の静かな声が闇に響いていた。
「なぜ今宵なのですか。昼間の方が良いと思いますが」
まるで彫像か仏像のような陰影深い男の口から声がした。
綿津見はここが切所と感じ、切り込むように鬼没盗のことを言葉にした。
「それは今宵、鬼没盗が出来しているかもしれないからです。私が訪ねる方はその賊と関わりがあるゆえ、今宵でないと会えぬかもしれません」
綿津見の言葉に男は微動だにしなかった。依然黒い瀬戸の海を見ているだけだった。
「それは何よりです、あなたの思いは天に通じたのでしょう。鬼没盗は今宵、大坂に出来しているはずですから。それで、なんといわれる方を訪ねていらっしゃったのですか。それにあなたのお名と用件を聞いてもよろしいか。そうでないと私の答も変わってきます」
陰影の深い彫像が向きを変えた。綿津見を正面から見るように正対した。
「その方の名は残念なことにわかりません。ただこの地を教えていただいた漢学者からは、徐福が古代に求めた不老不死の仙薬に関わる方とだけ聞きました。私の学ぶ水銀を用いた薬とも関係があるとも。私は水銀の仙薬を伝える大和葛城山にある徳陀子神社の宮司、巨勢綿津見と申します」
綿津見はそう名乗ってから、どう出てくるだろうかと緊張した。
ここまでいえば、ここに来た理由は分かるだろう。この男が本当に鬼没盗の首魁か黒幕ならば、逃げるか反撃に来るかもしれないと思った。
長時間の戦いは無理でも、一撃か二撃なら自分にも蹴速術が使えると思っている。知らぬうちに体の筋肉に力が入っていた。
だが、目の前の男は突如笑い出した。そしてにこやかな表情に変わって語りかけてきた。
「そのように身体に力を入れずともよろしいです。それに力が入れば逆に技は出ぬものですよ。なるほど巨勢のお方か。ならば私もあなたにお会いしたかった。同じ徐福の遺産を繋ぐ者として、今日までの永のご苦労にお礼を申し上げたい」
男は立ち上がって、深々と綿津見に向かって頭を下げてきた。
「我が名は徐市といいます。太古に生きた初代徐福の後継者と思っていただいて結構です。ただ今の世ではときに別の名も名乗っておりますが。あなたの訪ねる離れ屋の住人とは多分私でしょう。ただ少し誤解もあります。あなたは私を鬼没盗の仲間と思っておられるようだが、それは違います。私は単に稀人さんの同志として、できる協力をしているだけです。我らはそれぞれに独立した行動と目的を持っていますから」
そう語ると綿津見を繁々と眺め、何かを思い出すように考え込んだ。
「少し前にあなたとよく似た名の少年に逢ったように思います。名は確か……渦彦、巨勢渦彦と聞いた気がします。すみません、何せ膨大な記憶を引き継いでいるので最近のことが少しあやふやで」
徐市と名乗った男の言葉に綿津見は驚いた。渦彦とこの男が出会っているのかと思った。
「渦彦は私の弟です」
綿津見の答えに徐市は嬉しそうに頷いた。
「確かにあなたによく似た男の子でした。なるほど、少し歴史の歯車が動いているのかもしれませんね。稀人さんに出会ってから、様々な人と会えました。私の今生での役目がやっと果たせるのかもしれません」
そのとき、徐市は突如懐から小さな鉛玉を取り出すと、目にも止まらぬ速さで親指に挟んで撃ち出していた。鉛玉は少し離れた雑木林で、何かに当たったように弾かれていった。
「うっ」という押し殺した呻きと供に、雑木林から転げ出る人の姿があった。山道から姿を消していた金蔵だった。
転げ出た金蔵は、獣のような速さで山道を走り降っていった。
「少し前から気になっていたのです。あなたとこの先の話をするにしても、余人に聞かれては不都合な内容もありますので」
ここで徐市は少し堅い表情になって、綿津見に尋ねてきた。
「それであなたの本当の目的は何ですか。私を鬼没盗の仲間として捕らえることか、それとも……私も少し手を染めている丹の仙薬を再現するための意見を交わすことか。それ次第ではこの地を洩らした大辟先生にも仕置きせねばなりません」
綿津見はドキッとした。自分の心中を見透かされていると思った。確かに本来綿津見は鬼没盗の捕縛を目的にして、保久良神社にやってきた。
だがその実、本心では捕縛自体よりも鬼変薬改良への手掛かりが欲しかったのだった。古瀬稀人と共に動いているらしいこの男は、何かその手掛かりを持っていると感じていた。
それは大辟の家を訪れて以来考えていたことだった。だからこの男に会いたかった。阿刀家での寄り合いで保久良神社に行くと申し出たのもその思惑があったからだ。
だが念十郎には何か別の狙いがあるのではないかと問われた。この人の目は騙せないと感じた綿津見は、念十郎には本当の目的を語ったのだった。
静かに話を聞いた念十郎はただ一言、「では行きなされ」とだけいってくれた。後のことは金蔵に上手くさせるので気にするなとも。
「私が今夜ここにきたのは、鬼没盗や古瀬稀人を捕らえるためではありません。いえ……それも私の願いですが、今はそれを弟の渦彦に全て託しています。私の望みはこれ以上巨勢が苦しまぬために、鬼変薬を作り替えることです。あなたはその手掛かりを持っていると思います。私はそれが欲しいのです」
綿津見は振り絞るような思いで自分の気持ちを語った。徐市は顔の表情を変えずにただ少し頷いていた。
「ならば……我らは同志になれます。私の役目は多くの同志を存立して、それらの者を手助けすることですから。ですがだからといって私に何かを返す必要はりません。また私の命に従う必要もありません。我らは互いに独立し自立した存在なのです。それは私と稀人さんの関係と同じです。私と私の一族はそうやってこの国の歴史を紡いできました。ですから、あなたにも私のできることを協力しましょう。それが私の使命ですから」
そこまでいった後に、徐市は突然灯火台の方を指差した。
「あなたはこれをご存知ですか。この篝火は太古より人々の道標として存在している灯火なのです。人々はこれを『灘のひとつ火』と呼んでいます。記紀神話においては、神功皇后の三韓征伐の帰途や、日本武尊命の熊襲征伐から大和への帰路に、瀬戸の海の道標になったと記されています。ですが本当はそれよりも遥か昔、まだこの国に歴史が記される前の時代からひとつ火は存在しました。そしてこの海を、いえ歴史の闇の中を彷徨う人々の標となっていたのです。それは今も同じです。今この時も、稀人さんや木乃嶋衆はこの火を目指して航海していることでしょう。このひとつ火こそ私の役目であり、わが一族の存在理由なのですよ」
徐市が木乃嶋衆と口にしたことで、綿津見ははっと気がついた。豪商三井家や広隆寺、木乃嶋神社を動かしているのはこの男なのかも知れない。同時に、ではこの徐市と名乗る男は一体何者なのだろうかとも思った。
鬼没盗の背後にはこの徐市がいるのだろう。だがそれは黒幕とか影の首領とも少し違って思えた。何かもっと上位にいる存在で、大きな時流自体の画策者。いうならば鬼没盗という歌舞伎役者を使っている興行主のようなような存在だと感じた。
そう思ったときに、綿津見は急に強い畏怖を感じた。そんな男に助言を求めても良いのだろうか。何も要求せず、ただ協力するとこの男はいった。
だが逆にそれにはどこか底知れない怖さがあった。後にもっと大きなものをこの男に差し出さねばならなくなるような怖さである。
綿津見はしばらく沈黙した。この後どうするべきかを考えた。
「迷いがあるようですね。本当はいくらでも考えていただいて構わないのですが、今宵は少し時間がないのかもしれません。こうして灘のひとつ火をずっと灯しているですが、海からの返事がまだありません。どうやら稀人さんの元でも何か異変があったのかもしれませんね。あなたがここに来たのだから、稀人さんの元には渦彦くんが訪れているのでしょうか」
徐市は困った様子でもなく飄々として呟いた。そして綿津見に不思議な話を語りだした。
「今宵はあなたに差し上げるべき土産の用意がありません。代わりにあなたの迷いを解くための伝説をお話しましょう。あなたたち巨勢や鬼変薬の誕生にも関わる伝説です」
徐市は微笑みながら自然な調子で壮大な物語りを始めた。
それは遥かなる太古、まだこの日ノ本に「クニ」というものができる前の時代だという。
ある彷徨える一族が気の遠くなるような時間と道のりを超えて、遥か西方からやってきた。彼らは幾つかの集団に別れ、経路を分けながらも東に東にと歩み、この地に到着したという。
彼らは途中の国々でもその地の王や権力者に協力し、幾度も良き国を作ろうとしたらしい。一族はその時代にそぐわないほどの高い知識と優れた技術、そして「神の理」を持っていたのだった。
だが不思議なことに、それらの国々は一度は繁栄するものの、その後には必ずといってよいほど滅びていった。それは彼ら一族のせいというよりも、その地や時代にそぐわぬほどの高い知識や技術を与えたからかもしれなかった。
人は身に合わぬ高い知識や技術を手に入れると、必ずどこかで暴走した。知識の高さと精神の高さの均衡が取れていないからだ。
不思議なことに彼ら一族はそれぞれの地に自らの王国や国を建てようとはしなかった。それは彼らの持つ「神の理」に反する行為だったからだ。「神の理が支配する神の国は天上にのみ存在する」と信じていた。人々の生活を改善させようとはするが、そこに自らの利益を求めるような国を建てようとはしなかったのだ。
そうした集団の一つが徐福の率いる集団だったという。
彼らは巨大な統一国家を作った秦帝国から、知識や技術の全てを譲渡するように迫まられた。だが秦帝国の推し進める統治は、彼ら一族の持つ「神の理」には反した施策だった。
徐福は秦帝国からの逃亡を考えたが、すでに広大な大陸のほとんどは秦帝国の版図だった。もう逃げるべき場所が大陸にはどこにもなかった。
そんなときに先行して東進していた一族の別の集団から、「蓬莱ノ島」の情報を得たのだった。秦の遥か東の海上にある蓬莱ノ島は穏やかな人々が暮らす地で、食べ物も豊富で争いものないという。蓬莱での争いは大陸から移動してきた人々による争いだけだった。
そして何より重要だったのは、蓬莱ノ島の人々が彼ら一族の「神の理」を理解したような、神と共棲する生き方をしているということだった。
徐福は一族の集団と、彼らと行動を供にする近しい氏族と一緒に、蓬莱ノ島に渡ることを決めた。だが彼の集団も他氏族も合わせれば膨大な人数である。そこで渡海のために徐福は秦の始皇帝を誑かすという驚きの賭けに出たのだった。
これが後の世にいわれた「徐福の蓬莱山東渡伝説」である。
このとき徐福が始皇帝を騙すために使ったのが、彼らの知識にある「不老不死の仙薬」だった。丹を用いた不死の仙薬、ただ始皇帝に示したのは不完全な失敗作だった。他者に再現されることを恐れた徐福は敢えて失敗作を始皇帝に示し、完全なる仙薬を取りに蓬莱山に行くと説得したのだ。
徐福の目論見通り、始皇帝は二度にわたる蓬莱山東渡のための許可と援助をしたのだった。徐福と膨大な人数の一団は無事に蓬莱ノ島に渡ることに成功し、逆に始皇帝は不死の仙薬を手にすることはできなかった。
「徐福と私の先人たちはこの島に至り、そして不二の地に都を作ったといいます。この地に暮らす人々が豊かになる知識は与えましたが、全てではありませんでした。それが後の世の悲劇に繋がるのですが」
徐市の話に魅了されていた綿津見は、思わず「悲劇とは何ですか」と尋ねていた。
灯火台の焔が突然風に揺らめき、徐市の顔の陰影が変化した。綿津見にはそれがまるで徐市が泣いているように見えた。
「徐福の都は不二の大噴火によって火に焼かれ、その全てが失われたのです。彼らの知識も技術も、その神の理さえも。そしてその都の跡も押し寄せる焼け爛れた泥流に飲み込まれてしまいました。徐福とその一団がこの地にもたらした全てのものが、溶岩の下に眠ってしまったのです」
徐市は自分が大災厄に出会った当事者のようにうなだれていた。
不二、つまり富士(山)はこの十万年ほどの間に急速に成長した若い活動的な活火山である。歴史時代に入ってからも、十六回噴火したという記録が史書にある。
「噴火で失われた徐福の知識の一つが、あなた方巨勢に伝わる仙薬であり、鬼変薬なのかもしれません。私は是非にもこの徐福の知識や技を、何よりも神の理を再び復活させたいのです。ですから……稀人さんにもあなたにも等しく協力しようとするのですよ。誰が復活させるかは重要ではありません。復活することが重要なのです」
そこまで一気に語った徐市は少し息をついた。そして綿津見がこの話にどこまでついてこられているかを観察した。
綿津見はこの壮大で久遠な話に魅了されながらも、少し前からなぜか違和感を感じていた。それはどこかこの徐市が、まるで不二の都を失った当事者のように熱く語っていることだった。
彼が本当に徐福の末裔であり、また様々な伝承や記録を持っているとしてもそれはあり得ることだろう。巨勢もそうした意味では同じである。だが綿津見は自分を祭祀する祖神の後継者と考えたことはない。祖神の一族ではあってもそれは遠い時の彼方の話である。
いや、この国に住む多くの古代から続く一族の末裔も同じだろう。稀に大辟辰砂のような一族の出自に興味を持ちそれを探る人物も出てくるが、それあくまで今の時代での個人の思いや興味である。
だがこの徐市は何かが少し違っていた。まるで自分が徐福を知り、あるいは滅びた不二の都に住んでいたように熱く語っている。彼にとって古代とは終わった歴史ではなく、まだ継続している身近な出来事のように思っている証だった。
「徐市殿。一つ伺いたいのだがそれらの知識は書物で学ばれたのですか、それとも一族の口伝で覚えられたのですか。あなたはまるであなた自身が徐福に会ったり、不二の都の住人だったかのように語られている。私はそれをどこか奇異に感じます。まるでそれは……噂に聞く頭を病んだ病人のようです。自分を過去に存在した人物のように思い込んでいる痴れ人です」
綿津見は思い切って徐市に失礼な言葉を使った。だがそこまでいわなければ、本当の答えは返ってこないようにも思えた。この言葉に徐市は怒るのか、それとも……。
徐市は驚いたように綿津見を凝視した。その顔は少し歪んでいるようにも見えた。
だが徐市は怒るでもなく、また一笑に付するわけでもなかった。ただどこか嬉しそうな表情に見えていた。
「綿津見殿でしたか……あなたが優れた観察力と思考の持ち主であることがよくわかりました。実に素晴らしいです。私に対してそのような評価をしたのはあなたが久々です。私は初めてあなたに同志ではなく、友になって頂きたいと思いましたよ。実は同じことを常々私も思っているのです。私は頭の病ではないのかとね」
そう苦笑するように徐市は告白した。だがさらに残念そうに新たな告白を加え始めた。
「あなたはこの国の正史である古事記をご存知ですか。できればその成立の経緯もお知りならありがたいが」
急な問いかけに綿津見は戸惑いながらも頷き、自分の知る古事記編纂の知識を語った。
「確か天武天皇の勅命により、時の大臣藤原不比等が編纂したと学びました。編者は太安麻呂。帝紀、旧辞などの史書に記されている内容を誦習していた稗田阿礼の言葉を、安麻呂が筆録し編集したと」
簡潔な綿津見の返答に徐市は満足そうだった。
「あなたの学ばれた編纂経緯には一箇所間違いがあります。古事記編纂開始当時、すでに帝紀も旧辞も散逸と焼失で存在しませんでした。それは乙巳の変で死した大臣蘇我蝦夷の館と一緒に火災で焼失したと記されている『天皇記』と『国記』が、実のところ阿礼が誦習したという『帝紀』や『旧辞』と同一の書だったからです。阿礼は書物としての帝紀や旧辞を誦習したのではなく、この二書をまだ記憶する人々からその記憶を奪っていったのですよ。そう……私が先代の徐市の記憶を奪ったのと同じようにね」
徐市は思わず自分の顔半分を片手で覆い心の苦痛を隠すようにした。だがそれでも手から溢れる口端は笑っているようにも見えた。
「あなたには信じられないかもしれませんが、私の中には千年以上続く歴代徐市の記憶が積み重なって存在しているのです。徐市になる者はそうやって前の徐市の記憶を全て奪写して新たな徐市となるのです。失われた徐福の遺産のうち僅かに生き残った神の理なのです。他人の記憶を奪い写すこの『奪写の法』は。阿礼は書物としてはすでに失われている内容を、まだ記憶する生きた人間から奪っていった結果が古事記になったのですよ。阿礼にとって人間とは文字通り生きた史書と同じだったのです」
徐市の新たな告白を、綿津見はもう嘘か真かを判断できなくなっていた。
いや最初からこの男の話の真偽など判断できなかった。一番簡単な考え方が「徐市は痴れ人である」という解答だったのだ。
綿津見はどこかで簡この解答に縋ろうとする自分に気がついていた。
(三)
「灘のひとつ火」という水主の叫び声に呼応するように、渦彦と稀人は同時に宙を駆け登るように跳躍した。
互いに一瞬で蛙の構えから宙に至ると、身体を捻ってそれぞれの技を出そうとした。
渦彦は捻り回転させる身体から、まるで鞭が伸びたような旋回脚で、稀人のいた空間を上下に両断するように見えた。
一方の稀人は体を縦方向に回転させながら、大鉈を振り下ろすかのように天空斬の脚を渦彦の旋回脚にぶつけていった。
籐伍には回転する大鎌と振り下ろされた大鉈が、互いに相手の刃を叩き折ろうとしているかのように見えた。
一瞬、宙に火花が飛んだように感じた。
勿論しなやかな肉体同士のぶつかりなので火花はない。火花はないが二人の脚技が絡まるように交わると、互いの衝撃を反動にして大きく二つの影に分離していった。
渦彦の鎌も、稀人の鉈も傷付いてはいなかった。それはあらかじめ二人とも予期していたような攻撃だった。むしろ相手の力量を正確に測るために、互いに攻撃をしかけたようにさえ見えた。
甲板に着地した稀人は、仕方なさそうに呟きを漏らしていた。
「兄弟弟子というのは厄介な代物だな。思った以上に攻撃への入り方や組み立てが似てしまう。俺は無論だが、お前も椎根津先生の教えがその体に染みついているとみえる。それだけ優秀な弟子だったということなのだろう。だが逆にそれが俺には勝てぬ理由にもなる」
稀人の残念そうな呟きに、渦彦も叔父椎根津の言葉を思い出していた。
「お前の知る技は稀人も全て知ると思え」
その通りだと思った。稀人の動きはまるで叔父椎根津に瓜二つだった。自分よりもよっぽど上手く叔父の技を学んでいると感じた。ならばこのまま戦えばいずれ負けてしまうだろう。叔父に勝てなかった自分は、叔父に最も近い稀人にはきっと勝てない。
同時に叔父椎根津が最後にくれた教えが脳裏を掠めた。
それは「一度、蹴速を忘れろ」という謎の言葉だった。
蹴速の技があればこそ、自分は稀人ともこうして戦えている。だがそれを忘れろという。言葉の意味はわからなかったが、どうすれば良いのか考えようとした。だが考える猶予さえもなさそうだった。
稀人はまるで渦彦の全てをもう見切ったというように、ゆっくりと歩み出していた。渦彦がどういう技を出そうとも、もう全てに対応できるという自信があるように見えた。
「次で決着がつく」と二人を見ていた籐伍は感じた。
そして何故か「渦彦が負ける」とも思っていた。籐伍には蹴速術の上下は見分けられないが、武術や戦でいうところの「位攻め」に近いものを感じたのだった。
技や展開の良し悪しではなく、まるで「天意を味方にした方が必ず勝つ」といった感覚である。今は稀人が天の意を背負っているが如く、位の高さがあるように見えた。
だが渦彦が負けて良いはずがないと強烈に思った。籐伍は何か手がないのかと必死に考えた。そして最初に二人がこの船上で戦った場面を思い出していた。あの時渦彦は位負けしていない。二人の動きを籐伍は認識できなかったが、その攻撃は同等だと感じていた。
そう思い至った籐伍は渦彦に叫んでいた。
「最初の動きを思い出せ。あのとき渦彦は稀人と互角やった」
悲痛に響く籐伍の言葉を捉えつつ、渦彦も同じことを感じていた。
最初に出した空震弾は確かに無意識だった。自分が周囲に感じていた静かな無音の世界に侵入してきた何かを、まるで寄ってきた小虫を叩くように空震弾で思わず叩き落としていた。小虫が鬼神蹴りを放った稀人だと分かったのは、少し後の認識である。
「あの瞬間、わいは蹴速を忘れてたんか」
そうとしか思えなかった。鬼神蹴りに対抗しようとしたのではなく、また何か別の蹴速の攻撃を考えたわけでもない。ただただ手元にあった道具で、邪魔に感じた何かを振り払ったに近かった。
あの感覚は何だったのだろうと思った。自分も相手もいない静寂の世界。
そこに紛れ込んだ違和感に対して考える前に反応していた。それが叔父椎根津のいった、蹴速を忘れるということなのだろうか。
「もう一度あれをやるしかない」
目前に迫っている稀人見ながら、渦彦はあの瞬間を再現しようとした。激昂した感情の向こう側に広がっていた静かな世界。
それは激昂したが故に思考が一時停止し、考えることを放棄した瞬間だった。そして全てを研ぎ澄まされた五感に委ね、自分自身を天に解き放ったような世界である。
勝つとか負けるとか、あるいは相手を倒そうと考えたわけではない。ただただこの静寂を守ろうとした感覚だった。
渦彦の周囲に静かなる世界が再び蘇っていった。そして渦彦はこの世界の全てを忘れたように感じた。そんな一瞬、再び小虫が静かな世界を横断しようとしていると感じた。それが次に稀人が放とうとした空震弾であると理解したのは、少し後のことだった。
稀人が渦彦の前面から姿を消していた。
籐伍を含めた船上の全員にそう見えていた。
だが同じ瞬間に、艫から暗い夜空に向かって一発の花火が打ち上げられた。それは火薬が爆発する轟音と、目を眩ませる光を放ちながら天へ飛翔する光体だった。艫にいた水主が放った緊急用の信号弾である。船に何か不測の事態が生じたときに、灘のひとつ火に向けて上げる警戒信号だった。
空震弾の動作に入っていた稀人は一瞬その花火に気を取られた。だが失った何分の一かの注意力を瞬時に補い、稀人は渦彦の頭上に空震弾を落としていった。それは誰から見ても稀人自身にも完璧な空震弾だった。
ただ一人、渦彦の展開した静寂の感覚を除いては。
渦彦は静寂の世界の中に迷い込んできた一匹の小虫を、思わず叩き落とそうとした。叩き落とすために使った道具は打神脚だった。
渦彦にとって温羅の蹴速の中で撃ノ弍・打神脚は最も馴染んでいない技である。馴染んでいないというよりも使い辛い技だった。それはまだ成長過程の肉体を持つ渦彦にとっては、負荷が大きすぎる技だからだ。鬼神蹴りが回転力、空震弾は跳躍力、そして打神脚は静止した状態からの筋肉の瞬発力をその撃破の源泉にしている。打神脚は渦彦に最も備わっていない鬼の筋力を必要としたのだった。
だが、不思議と違和感なく打神脚はその小虫を振り払っていた。それは小虫の羽ばたく道の先が見えていたからだった。
稀人が花火で外らせた何分の一かの気を、渦彦は隙と捉えていたのかもしれなかった。
心が空っぽだった渦彦は、自分の得手不得手とは別の感覚で技を選択した。そして打神脚は渦彦を襲う大気の強烈な渦巻きごと、稀人本体を薙ぎ払っていった。それは些細な要素を無視し、強引で暴力的な力で薙ぎ払う打神脚だからこそできたのかもしれない。
籐伍は一瞬の空白の後に、何かが帆柱に向かって弾け飛んで行くのを感じた。そして視線をそちらに向けると、帆柱に叩きつけられた黒装束の稀人がいた。
「やったのか」と思い渦彦の方を見ると、渦彦もまたその場に崩れ落ちようとしていた。
渦彦の打神脚は稀人の本体を貫いたが、同時に稀人の放っていた空震弾を避けてもいなかった。空震弾が僅かに渦彦を襲ったときに、その隙を狙うように稀人本体を打神脚が襲ったのだ。偶然にも稀人の「後の先」を取ることになった。
無意識の感覚が打神脚を選択したのは、渦彦の身の安全を些細な要素として捨て去った結果だった。その選択が天の理に適っていたのだ。空震弾は避けられない、だが空震弾を放った本体は捕まえられると。それは勝とうとしたのではなく、邪魔な小虫を薙ぎ払うためだけの選択だった。
籐伍は後にこの瞬間を何度も思い返し、ある結論に至った。
「蹴速の技は稀人が優っていた。だがあの瞬間天は渦彦に微笑んだ」と。
崩れ落ちる渦彦に走り寄った籐伍は、抱きかかえるように渦彦の体を支えていた。渦彦の体には力がなく、身体中の筋肉がさざめくように痙攣していた。それが稀人から受けた空震弾の打撃の影響なのか、強引に打神脚を使った反動なのかはわからなかった。
ただ意識は朦朧としながらも失ってはいないようだった。しかし肩辺りが不気味に折れ曲がっている。空震弾で破壊されたのかもしれなかった。
帆柱に踞る稀人のそばに、別の黒装束が走り寄り抱き起こそうとした。支えられながら起きる稀人には意識があるようだった。起きかけた稀人も少しふらつき、壊れた体を確認するように左脚の付け根を押さえている。
もしこのまま稀人が復活すれば、渦彦はもう戦えないし勝てないだろうと思った。渦彦の肉体は依然細かな痙攣を続けていた。
籐伍は自分がやるしかないと心を決めていた。手負いとはいえ稀人に正面からでは勝てないだろう。だがここで勝つ必要はないのだとも考えていた。青木の浜に着くまでの時間を稼げばよいだけだと割り切っている。
籐伍は稀人にではなく、船に乗る水主たちに向かって叫んだ。
「木乃嶋衆の水主たち。お主たちの身元も、この船の主も既に割れてるで。今はこれ以上争うんやない。この海にお前たちの帰る港はもうどこにもないんや。天保山にも、目的の青木の浜にも奉行所の手が回ってる。他の浜につけたところでおんなじや。おとなしゅうに船を青木に着けて裁きを受けんかい。お前らが鬼没盗と関係ないんは奉行所もようわかってる。そやからもうこれ以上争うな」
籐伍の叫びに、船の水主がざわめいた。自分たちの身元や船主、それに目的地まで割れているという驚きである。籐伍の言葉にしばらくの間水主たちは動けなかった。沈黙と逡巡の空気が船上に満ちていった。
籐伍は船を操る水主と鬼没盗の乖離を図ったのだった。水主を味方につければこの場は勝てると思った。
ふらふらとしながら立ち上がった稀人が、船内の動揺した気持ちを抑えるように叫んだ。
「役人のいうことなんぞ信じるな。此奴らは皆同じ盗賊としてお前たちも捕らえ、待っているのは打首だけだ。幕府は自分に逆らう者を決して許さぬ。それはお前ら自身が一番知っていることだろうが。この海の覇者だった木乃嶋衆を陸に押し込めたのはどこの誰だ。それは幕府の始祖、家康だろう。家康の天下取りに力を尽くしたお前たちを、役目が終れば簡単に捨てた。お前たちを救ったのは太秦の一族だけだった。今はその命を守れ。あやつらはこれまでも海のひとつ火として道を示してくれたのだぞ」
そこまで叫ぶと、稀人は喉元を抑えると何かを口から吐き出していた。どす黒く、そして命の滴りのような赤い何か。それは大量の血潮だった。
渦彦の打神脚は肉体の一点を破壊しただけでなく、波動としても肉体全体に衝撃を与えていた。衝撃は稀人の内臓をも傷つけていたのだ。
うずくまろうとする稀人の言葉を打ち消すために、再び籐伍が皆の気持ちを挫くように叫んだ。
「お前たちのひとつ火はもうないで。見てみい、さっきまであったひとつ火はもう消えてる。昔のことは知らんが、今はお上にも情けも道理もある。もうこれ以上争うんやない」
そして灯火が見えていた黒い六甲山の山並みを指さした。そこにはさっきまで輝いていたはずの灘のひとつ火が、すでに消えていたのだった。
動きがとれない稀人は、仲間に支えられながら籐伍と睨み合った。
ただ二人とも今が動くべき時ではないとも考えていた。多分程なく青木の浜に着く、そのときこそが仕掛け時だと思った。
籐伍と稀人の間の緊張を取りなすように、一人の歳老いた水主が二人の間に進み出てきた。
「お二人ともしばし待たれい。この船の上でのこれ以上の争いは船の長であるわいが許さん。ええか、動いてはならんで」
そういうと静かに二人の間に座り込んだ。
「確かにわいらは木乃嶋衆やが、盗賊の仲間やない。それを奉行所が認めてくれるんやったらこれ以上の手出しはせん。ただわいらにはわいらの掟と信義がある。それは守らなあかん。お若い与力殿よ、よろしいか」
籐伍に確認するように、その長はゆっくりと籐伍と渦彦の方を見た。思わず籐伍は「承知した」というように頷いていた。
歳年老いた長が今度は稀人に向かって語りかけ始めた。
「客人殿、わいらは太秦からの指示でこの船を動かしておる。しかしわいらは客人殿の仲間になったわけではない。わいらはあくまで木乃嶋衆として動いておる、そこは間違えたらあかんで。客人殿が何をしようとわいらは口を出さんが、それはわいらにもいえること。わいらが何をしようとも客人殿には無縁や、よろしいか」
そう稀人に念を押すようにいうと、静かに稀人を見詰めていた。
稀人と籐伍の間に張り詰めていた緊張の糸を、この歳老いた長が見事に手繰り寄せそしてその懐の内に仕舞っていった。
その長は若い水主を側に呼ぶと何事かを耳打ちした。長の言葉を聞いた若い水主は一瞬ギョッとした表情になったが、黙って頷くと元いた水主の集団の中に戻っていった。
その行動に何を感じ取ったのか、血を吐く稀人が長に確認するように問い質していた。
「この期に及んで太秦の命に背くとは思わんが、何を企んでいる。今はその役人の始末が先だぞ」
その言葉を口にした稀人が激しく咳き込み新たな血を吐いた。
座り込んだ長は、宥めるようにゆっくりと稀人の方を向いた。
「それは言わずもがなのこと。そやけど青木に着くまでは全てわいらの責や。客人殿もそれまでは黙っててんか。それでも不安があるんやったらわいを盾にしたらええ。それで木乃嶋衆は手を出さん」
そう言った長は腰の懐剣を抜き、それを「どんっ」と自分の前の甲板に置いた。不服ならばこの刃で自分を殺せという意思に見えた。
「もうすぐ青木の浜に着く。それまではこの船での争いはならんで。船の上では長の言葉が法度や。お二人ともそう心得てんか」
そう声高に宣言すると長は目を閉じた。青木の浜に着くまでの、短いが永遠とも思えるジリジリとした時間を、まるで凍結させたように船上の人間の動きを静止させていた。
舳先で海を観測していた水主が、遠くに丸く動く光を見つけた。
それは神紋の船を受け入れるはずの青木の浜からの知らせだった。ただこのときの光は青木の舟屋にいた水主に白状させた恭一郎の手による偽の信号だった。
「長、浜から入港の合図がきましたで。このまま浜に入りますか」
舳先の水主が瞑目する長に叫んできた。長は静かにうなずくと船の全員に号令をした。
「青木に船を着ける。奉行所が待っていようが関係ない。わいらのお役目は無事にこの船を浜に着け、客人殿を送り届けることや。着いた後のことはわいらには無縁や。後は客人殿とそこのお役人に勝手にしてもらおう。お二人それでええな」
長の凛とした声が稀人と籐伍を縛っていた。逆にいえば浜に着く前にどちらかが相手方を制圧しようとしたならば、その時は木乃嶋衆が相手になるという宣言でもある。
沈黙している稀人を長が手招いた。次の状況への行動を考えていた稀人が、ふらつきながら近寄っていった。
「何だ、浜に着くまで動くなとお前がいったばかりだぞ」
呟く稀人に、長は声を潜めて他には聞こえないように囁いた。
「船が桟橋に入ったら仲間の二人を右の船縁に、客人殿はわしを盾にして左の船縁に移動せい。そして右の二人を役人の囮にするために海へ飛び込ませるんや。客人殿はその隙に左側から海へ忍べ。そのまま海中を東に泳いで青木の浜から離れるんや。少し東に行けば西宮の浜や。そこに木乃嶋衆の舟屋があるよって、そこに隠れたらええ。朝までにはあのお方の助けが来るよって。これが赤花火を上げたときの太秦の指示や。ええか仲間を助けようとは思うな。あのお方は客人殿のみを落とせといわれた。今はそれを守るしかない」
手が回ったときの脱出方法が指示されていたことに、稀人は少し驚いた。
「さすが天河はよく先を読んでいる。奴が太秦の力を操れるはずだ」
そう納得したがまだ一つ気になることがあった。折角時間をかけて蹴速術を教え込んだ仲間と木乃嶋衆のことだった。自分は逃げ切れても彼らは奉行所に捕縛されるだろう。
その懸念を問うと、長は苦笑いしながらあっさりと答えた。
「わいらとお仲間は捕縛されよう。しかし今はそれでええんや。後で太秦の力で解き放たれるからの。奉行所の裁きなぞ何ぼでも上から変えられる。太秦ならそれくらいのことはできよう。じゃが賊の首領と目される客人殿はそうはいかん。待っているのは打首だけや。そやから客人殿だけは船から落とせということや。ええな、この事仲間にも他言無用や」
長が怖い顔で稀人に念を押した。稀人は一瞬迷ったがすぐに仕方ないと割り切った。蹴速術の仲間はまた作ればよいと思いを切り替えたのだった。
長の言葉は半分本当だが半分は嘘だった。それは稀人にこの後に変な動きをさせないためだった。
暗闇の海がやがて途切れ、目前に桟橋が近づいてきていた。そこでは二人の男が明かりをゆっくりと回していた。二つの光の円に引き寄せられるように船は桟橋に入っていった。
稀人に指示を受けた鬼没盗の二人は右の舷側から身を乗り出すようにしていた。桟橋に接岸した瞬間に、二人は海に飛び込んで逃走を謀る予定だった。奉行所の捕り方がどこに潜んでいるかは分からないが、夜の海に紛れれば逃げ切れるかもしれなかった。
同じように稀人は、長にもたれかかるようにして左側の舷側に移動した。
長と稀人の姿を籐伍と渦彦は目を凝らし見ていた。渦彦はまだ完全に動くことはできず、籐伍も木乃嶋衆の動きを注意しながらの凝視だった。
長の背後から稀人は懐剣で首筋には刃を当てていた。先ほど長がいったように人質にとっているように見えた。
「接岸するまでは動けへん。そやけどこの船を降りても、もう逃げ場はどこにもないで。これで鬼没盗も古瀬稀人も詰みや」
そう思った籐伍は少し気が抜けたように感じた。これが半年以上追い続けてきた鬼没盗事件の結末なのかと思った。
体の痙攣が治ってきた渦彦も、稀人の姿を喰い入るように見ている。渦彦は「何かある」とどこかで感じていた。それは稀人の体からまだ闘気が失われていないと感じていたからだ。たった一人で念十郎の捕縛組を突破するつもりかもしれないとさえ思えた。
「籐伍、気抜いたらあかんで。あいつは諦めてへん。何かするつもりや」
渦彦の言葉に、籐伍は「あっ」と思った。籐伍にもこのまま終わりを迎えるとは思えない妙な予感がさっきからしていたのだ。何かかがそう感じさせていた。
左側舷側に背をもたらせていた稀人が、思い出したように突如渦彦に向かって叫んだ。
「巨勢渦彦、残念だが今日のところは相打ちにしておいてやる。邪魔なその役人がおらねばとどめを刺していたのだがな。それは次の機会にするとしよう。それまでは力不足だが我が弟弟子に蹴速術継承者の座を預けておく。だが次には必ず鬼神饕餮となって巨勢の全てを喰らってやろう」
渦彦にそう宣言すると、苦しそうに再び咳き込んだ。稀人もまた手負であることがよくわかった。
船がゆっくりと桟橋を擦るように接岸していった。ギシギシという摩擦音をかき消すように、右の舷側から突然人の叫び声がした。
「な、何や。何でや」という声ととともに、「ギヤー」という叫び声も聞こえてきた。
籐伍と渦彦は思わず声のした方向に視線を動かせた。暗闇の中で右の舷側にいた鬼没盗二人が、背後から水主たちに押し囲まれ何かで突き刺されている影絵が見えた。
黒装束に包まれた一人の賊の後ろに二、三人の水主が集まり、手に持つ得物で背後から黒装束を貫いている。同じ光景がすぐ隣にいる鬼没盗にも起こっていた。
二人の絶叫が闇の中かに響いていた。そして二人とも船縁からもんどりうって暗い海に落ちていったのだった。
それは船が接岸するのと同じ瞬間だった。船が停止しするのと同時に、二人の賊が黒い海に落ちていったのだ。
「ギシッギシッ」という接岸の音と、二人の賊が海に落ちる「ドブンッ」という音が重なって聞こえていた。
その光景を唖然として見ていた籐伍は、ハッとして反対側にいる稀人の方を見た。そこでも不思議な光景が繰り広げられていた。
仲間の絶叫に振り向いた稀人の隙を突くように、何かを逆手に持っている長が稀人の下腹部にその逆手に持つ物を突き刺していた。
「うっ」という低い声とともに、稀人は長から少し離れた。そしてフラフラとしながら左の船縁に寄り掛かろうとした。
長の手に光るものが見えた。それは細い金属で先が鋭く尖っている。最初何を持っているのかよく分からなかったが、どうやら千枚通しのような刺突物だった。
その千枚通しで稀人の下腹部を貫いたのだ。下腹を押さえながら船縁にもたれかかる稀人に向かって、長は老人とは思えぬ速度で体当たりをした。
平衡を失った稀人は、そのまま船縁から海へ落ちていった。
こちら側でも稀人が海に落ちる音がしたが、その音は船体に打ち付ける波音に掻き消され、どれが稀人の落水音か聞き分けることができなかった。
長は稀人の落ちていった先を確認するように黒い海面を見た。そして聞こえないほどの声で、「これもまた太秦の命や」とだけ呟いていた。その言葉は籐伍や渦彦には聞こえていなかった。
程なくして青木の浜に接岸した船の上に、念十郎たち捕縛組が乗船してきた。念十郎がそこで見たのは、賊を刺殺した水主たちが座り、前に小太刀を差し出した姿だった。その先頭には船の長が座り、前にはやはり血の着いた千枚通しが置かれていた。
それは天保山で乗ったはずの鬼没盗と古瀬稀人の姿だけが、船上から忽然と消え去った不思議な光景だった。
(四)
徐市の告白物語を聴き終えた綿津見は、結論を出せないでいた。
そんな綿津見を徐市は面白そうに眺めていた。そうした二人の均衡を破るように、夜空に赤い光の花が咲いた。まるで祭の花火のような美しい光輪だった。
「少し話が長くなりすぎたようです。しかし海からの返事がやっと来ました。この赤い花が咲いたということは、あちらでも危急なことがあったようですね。ひとつ火も今宵は用済みのようです」
そういうと徐市は手早く灯火台の焔を消し始めた。大きな焔だったが、徐市は手慣れた作業のように灘のひとつ火の焔を鎮火させていった。
ひとつ火が消えると、あたりは再び闇が支配した。その闇の中に徐市は立っていた。綿津見からは姿がもうはっきりとは視認できなくなっていた。
「では、次にお会いできるときを楽しみにしています。あなたがどこまで私の友に相応しく成長しているのか、早く見たいものです」
闇の中で徐市の立ち去る足音だけがした。
「ザクッ、ザクッ」と鳴る足音が次第に遠ざかっていった。その足音を追うように綿津見は思わず声をかけた。
「あなたはまた鬼没盗を作って、鬼変薬再現を続けるつもりですか」
それは綿津見の心からの叫びに近かった。もうこんな人々や巨勢を苦しめるようなことは辞めて欲しいという願いである。
徐市の足音が止まった。姿は見えないが振り向く気配がした。
「それは私にはわかりません。鬼変薬の再現は稀人さんの夢で、私のではありませんから。もしあの暗闇の海で稀人さんがまだ生きているのなら、それもあるかもしれません。ですが……夢とは儚いものです。だからこそ美しい。私は夢を見ないので、他人の美しい夢を見るのが好きなのです。徐市の役目以上に、これは私個人の嗜好なのでしょうね。以前に先の徐市にも注意されたのですが、持って生まれたものはなかなか治りません。幾百人もの記憶を有しようとも、こればかりは私だけのものです。だから私はあなたの見せてくれる美しい夢を見てみたい。期待していますよ」
その声が止むと、再び足音が遠ざかり始めた。そして足音さえも聞こえなくなった。徐市は闇の中に完全に消え去ったのだった。
綿津見は消えた徐市の後を追おうとはしなかった。いや追えなかった。徐市自身よりも彼の持つ果てしない時の暗闇がどこか怖かったのだ。
綿津見はさっきまで徐市が座っていた灯火台側の巨石にまで行き、そこに座ってみた。そこからは暗黒のような海が見えていた。
果ても底も分からない暗黒の海。徐市はいつもこんな風景を見ているのではないのかとふと感じた。だとしたら標となるひとつ火を求めているのは、本当は徐市自身なのかも知れないと思った。
綿津見はそこで時間が過ぎるのも忘れて暗黒の海を見ていた。やがて山道の方から灯りが登ってきた。灯りは二つあるので二人組のようだった。
顔が確認できるまで灯りが近づくと、それが恭一郎と金蔵だとわかった。恭一郎は巨石に座る綿津見を見つけると駆け寄ってきた。
「綿津見殿ご無事か。不審な人物と遭遇したと金蔵に聴きましたが」
恭一郎は綿津見の無事を確認すると、ほっとしたように蹲み込んだ。
「青木での捕縛はどうなりましたか。鬼没盗は捕縛できたのですか」
綿津見の質問に恭一郎と金蔵は顔を見合わせて少し沈黙した。
「捕縛はできました。まぁあれを捕縛というのならばですが」
恭一郎は青木の状況を語り辛そうにした。ただそれは綿津見も同様だった。この地であったことをすぐには語れなかった。
「渦彦と籐伍もひとまず無事ですから安心してください。ですからすぐにも山を降りて叔父上の手勢に合流しましょう」
恭一郎の言葉に綿津見は少し安堵した。もしかしたら渦彦は古瀬稀人との戦いで倒されているかも知れないと思っていたからだ。
三人は恭一郎の持つ灯りを先導にして山道を降り始めた。少し歩いていると、東の空が薄紫色に染まり始めた。夜明けがもう近いようだった。
どんな暗闇の夜にいても必ず朝が来る。それが世の理である。だが綿津見はあの徐市には朝が来るのだろうかと思った。徐市は今も果てのない暗闇の海を彷徨っているのではないのかと感じた。
綿津見は初めて徐市のことを少し憐れに思った。人の世の理を離れるとは、そういうことなのかも知れないと深く考え込んでしまった。
念十郎は青木での捕縛の顛末について西町奉行に報告をした。
念十郎の報告に加え、天保山での捕縛の報告を同心の河原崎が行った。これらの報告に対して西町奉行も吟味方も大いに喜び、また結果的に鬼没盗殲滅を成し遂げられたことに安堵したのである。
奉行所は捕縛に関わった捕り方に褒美を取らせた。ただ一人、阿刀籐伍を除いては。
籐伍に対しては天保山における途中からの役目放棄と、船への無断乗船の責任が問われた。ただこれは他所に対する西町奉行所の言い訳のような責任追及だったので、処分は最も軽いものになった。
籐伍に下された処分は「三十日間の慎み」だった。当時の謹慎処分で、閉門して昼間の外出を控えるものである。ただ見張りなどは厳しくなく、夜間の外出は概して大目に見られた。
だが「慎み」は「慎み」なので、籐伍は天満橋北の家に閉居して外出は控えていた。そんな状態なので昼間に道頓堀に芝居を見に行くわけにもいかない。結局は戯作を書いたり、過去の芝居台本を読むしかやることがなかった。毎日自分の部屋でゴロゴロとして時間を潰していたのだった。
そんなある日、恭一郎が阿刀家を訪れた。奉行所が出した鬼没盗に対する裁きを知らせるためである。
「天保山と前に隠居所で捕縛した賊は全員、遠島に決まったで。打首いう案もあったが、捕まったったんは皆下っ端やったし、殺しもしてへんからな。それに打首にするには江戸の御老中の裁可もいるさかい色々と面倒いんや。お奉行もそのあたりを嫌うたんやろ。主犯格の賊は死んでもてるしな。これで鬼没盗もこの世から消滅したいうことやな。あと木乃嶋衆と越後屋は結局お構いなしになったで。強迫されてたいうんもあるし、主犯格の賊を殺してるからな。ただ船の長だけはこれまでの責を問われて手鎖五十日の処分になったわ。まぁこの辺りが落とし処ということらしい」
淡々と裁きを語る恭一郎に、籐伍はあまり反応をしなかった。
「そんなものか」という感慨が強かったし、正直鬼没盗に対してはもう怒りがあまりなかった。むしろ渦彦や綿津見がこの裁きを聞いたらどう思うだろうと思った。
そんな籐伍に、恭一郎は小耳に挟んでいた奇妙な噂を話さなかった。
それは木乃嶋衆と越後屋の裁きに対して、江戸の幕閣より口添えがあったという噂だった。幕閣の誰かは不明だが、情状を斟酌せよとの達しがあったらしい。その為にお構いなしになったとは思わないが、恭一郎には全てを長の手鎖に押しつけたようにも見えていた。
籐伍はもう興味なさそうに話題を変えた。
「そやけど、渦彦も燕姉もなかなか大和から帰ってきいへんなぁ。渦彦はいろいろあるから仕方ないけど、燕姉も遅過ぎるわ。このまま成し崩しに綿津見殿のところに嫁入りでもするつもりやろか」
籐伍の愚痴ともいえない呟きに、恭一郎は笑いながら応えた。
「さすがにそれはないやろ。燕ちゃんがほんまにそのつもりやっても、叔父さんがさすがに許さんわ。向うの母上様に筋通す為にもまずは誰か婚姻の使者を立ててるて」
そうはいったが、これは恭一郎にも関わりかねないことだった。
もし思いがけず燕の嫁入り話が進めば、恭一郎と鈴の婚姻にも影響が出るかもしれなかった。
籐伍が慎みの閉居に入る直前に、大坂での目的を終えた綿津見が燕と渦彦と一緒に大和へ帰ったのだった。
綿津見は一度旅した道なので一人で大和へ帰ると主張したが、阿刀家としてはそうはいかなかった。結局、燕が大和まで綿津見を送ることになった。それが念十郎の指示なのか、燕自身の希望だったのかを籐伍はよく知らなかった。渦彦も護衛として二人に同行することになったが、それは渦彦の今後の処遇にも関わることだった。
綿津見が旅立つ前に、巨勢兄弟は今後のことに関してかなり深く相談したらしい。元々は徳陀子神社の御神宝を探す為に渦彦は大坂にきたのだ。その目的がひと段落したとなれば、元の京の五條天神宮に戻って神人修行に復帰するのが道理だった。
だが渦彦は大坂に残って、古瀬稀人の痕跡を探したいと願ったのである。渦彦は奉行所の結論とは異なり、稀人がまだ生きているのではないのかと考えていた。再び鬼変薬再現に動き出すかもしれないと恐れていた。
それは綿津見が保久良神社で出会ったという徐市の話からもそう想像したようだった。
綿津見は大坂に戻ってから徐市との邂逅を語った。皆は一様にその話を信じられなかった。話が突拍子なさすぎたし、聞く人の想像を超えていたからだ。ただ綿津見をよく知る彼らは嘘をついているとは思わなかった。
渦彦が一番気にしたのは、徐市の「稀人が生きていればまたもあるかもしれない」と、「再び会うのを楽しみにしている」という言葉だった。渦彦にはそれが逆襲の予告に聞こえていた。
もし徐市や稀人が再び動くとしたら、それは大坂である可能性が高い。それを阻止する為にも渦彦は大坂残留を望んだのだった。
綿津見は渦彦の願いを聞き入れた。五條天神宮には渦彦の神人修行中断を、少彦名神社には新たに神人修行受け入れを申し入れした。懇意な両社なので希望はすんなりと受け入れられた。こうして渦彦の神人修行は今後少彦名神社で行うことになったのである。
そうした事情を考えれば、暫くは大和に帰郷できない渦彦の帰坂が遅れても仕方ないと籐伍も思った。だが燕もまた帰ってこないのだ。
籐伍は渦彦や綿津見をもう兄弟のように思っているので、何だか自分だけが除け者にされたように感じた。慎みで家を出られない状況が余計にそう思わせていた。
恭一郎が急に思い出したように籐伍を慰めてきた。
「そういうたら叔父さんの隠居願い、今回はあかんようになったんやてな。まぁ家督相続する籐伍が慎みの最中やからな、お奉行も直ぐに隠居を許可するわけにはいかんかったんやろ。それに諸色方からも隠居を待ってもらうようにお奉行へ嘆願が出てたらしいで。何せ叔父さん一人で三人分の仕事してたっていう噂やからな。おいそれとは手放しとうはないわ」
父の隠居願いが先延ばしになったことを、籐伍が残念に思ってはいなかった。むしろ老け込むにはまだ早いと思っている。好きだったという道頓堀の芝居小屋通いはまたしばらくできなくなるだろうが、父にはそのほうが良いのではないかとさえ思った。
籐伍は何もかもが詰まらなそうに、ゴロリと部屋に寝転んでしまった。目には天井の見慣れた杉模様が飛び込んできた。
「前にもこの杉模様、こうして見てたなぁ」と不意に思った。それがいつのことだったのかはすぐには思い出せなかった。
籐伍にとってはこの半年間以上、鬼没盗を追っている時間がとてつもなく濃密に感じ、それ以前の記憶がどこか希薄だった。
「早いこと奉行所に戻りたいなぁ。仕事せえへんのがこないに辛いとは思わなんだわ」
何気ない籐伍の呟きに、恭一郎は驚きと共に成長を感じた。
やる気もなく何もできなかったあの籐伍が、今は奉行所に戻りたがっている。籐伍が大人になっていると思った。
「そないに焦らんでも来月には復帰できる。そしたら今度は寝る間もない位に面倒臭い役目振られるで。皆が投げ出してた鬼没盗殲滅の立て役者やからな、覚悟しとき。それまではゆっくり休むことや」
恭一郎の慰めるような言葉は半分本当だろう。
最初は何にも使えない仮役与力だったが、今回の捕り物で見せた意外な探索の鋭さと行動力を奉行所も放っては置かないだろう。
吟味方の丹羽がいうように慢性的人手不足の奉行所が、籐伍の活用法を真剣に考えても不思議ではなかった。
籐伍はもう半年以上、自分が道頓堀の芝居見物に赴いていないことが不思議だった。以前はあれほど日参していたのに、今はそのことさえも忘れている。芝居を見に行けないことをさほど寂しいとも思っていなかった。
きっと父もこんな気持ちなのかもしれないと漠然と想像した。それは籐伍の大人への成長を感じさせる想像だった。
終幕ノ逸話
鬱蒼とした木々が生茂っている山道を二人の旅人が歩いていた。一人の男がかなり前に先行して歩き、もう一人の同行者は少し足を引きずりながらも遅れまいとしていた。
二人の旅装はかなりの軽装で、ちょっと近くの温泉地に湯治に行くか、宮参りにでも向かうような格好だった。それだけに偶に行き合う旅人にも全く注目はされなかった。
先行していた男が、峠の頂上に到着したようだった。頂上で「やれやれ」というように大きく背伸びをすると、後ろを振り返った。
「やっと国境の峠に着きましたよ。ここからは下り道だから、次の宿場まで何とか陽のある内に着けるでしょう。あなたに合わせていたら随分と時間がかかってしまいました。足の具合はどうですか、まだ痛みますか」
峠に立つ男は、後ろからやってくる同行者を労わるように声をかけた。ただその言い方は労わりよりも、どこか揶揄っているようにも聞こえた。
同行者は返事もせずに、ただ黙って歩みを進めていた。よく見ると同行者は少し怪我をしているようだった。腹に巻かれたサラシからは脇腹あたりに血が滲んでいるのがわかる。さらに左足の付け根あたりを痛めているのか少し抑えているようだった。それでも同行者は弱音を吐くことはなく黙々と歩いていた。
峠で微笑んで待っている男の元に、遅れていた同行者がやっと辿り着いた。少し息が上がっていたが、それでも鋭い視線で男を見据えていた。
いや、今だけではなく山道を歩いている間中、同行者はずっと前を歩いている男を鋭い視線で見ていた。男に少しでも隙があったら、襲い掛かろうと考えていたのだ。
実は襲う隙は今までに幾度もあったのだ。その度に同行者は男を葬る技の組み立てを考えていた。だが不思議と戦いの結末では自分が倒されている想像が襲ってきた。
同行者は達人といっても過言ではないほどの武芸者だった。たとえ怪我をしていても普通ならば負けるはずがなかった。だが何故か最後には自分が負ける想像が襲ってくる。
男の隙は敢えて自分に見せている隙なのだと思った。
「こいつ俺を誘ってやがる」
それは男の遊びだと思った。自分を誘って楽しんでいると。
峠に立つ男は眩しそうに青い空を見上げていた。まるでこの蒼穹は全て自分の物だといわんばかりの表情だった。
「俺はまだお前を許したわけではないぞ。お前や背後にいる太秦が表に出ようとしないことは知っている。だがその為にお前たちは俺や仲間を擦り潰して自分たちを隠したんだ。この責任は必ず取ってもらう」
同行者は少し押し殺した声で男にいった。だが男はそんな言葉を気にかけもしないように、同行者に微笑み返した。
「嫌だなあ。何度もいったように、私はあの暗闇の海から助けてあげたんですよ。あなたもあなたの仲間も、あの時点ですでに奉行所には負けていたんです。だからせめてあなたには生まれ変わる機会を作ってあげたんですよ。暗闇の海で鬼没盗首領は死んだ、そして新たな命と名前をあなたは獲得したんです。仲間は信じる王のために殉死したんですよ。王を護るために臣下のとる立派な務めです」
男は悪びれることもなく、不思議に古臭い言い回しで断言した。
「それに面白いじゃないですか。あなたには蹴速の遊び相手ができたし、私は成長が楽しみな人と出会えました。楽しいのはこれからですよ。悔やむことなど何もありません。臣下など必要ならまた集めればよいのです」
男はあっさりとしていた。擦り潰した命の替りなどいくらでもあるといいたげだった。
同行者はその言い方をどこか歪に感じた。今まではあまり気づかなかったが、この男はどこか歪んでいると不意に気がついた。
「これからどうする。行くべき場所も今はない。仙薬の再現は頓挫したし、直ぐには大坂での再開は難しいだろう。結局手元に残ったのは聖徳太子の宸翰だけだ。これで何ができる」
それを聞いた男は微笑みながら諭すように語った。
「聖徳太子の宸翰は次の時代を迎える為の起爆剤になります。しかるべき人が持てば、この国に大きな乱を引き起こせますよ、倭国大乱です。それまでは大事に持っていてください」
そして同行者の顔近くに顔を寄せると、当然のように囁いた。
「それに行くべき場所はもう決まっているじゃありませんか」
男の言葉に、同行者は不審げに尋ねた。
「どこだそれは」
男は再び蒼天を仰ぎながら、少し恍惚とした表情になった。
「勿論、神の棲まわる国ですよ」
男の陶酔したような表情を見た同行者は、その中に妖しい魔物が棲んでいるように感じた。
「神の名を語る魔物」
同行者は男のことを、そんな名の怪物だと初めて気づいたのだった。
(了)
- 1 -
(一)
《鴻池隠居所に於ける鬼没盗捕縛書留め》より抜粋
河原崎突入組にて捕縛せし賊四名
阿刀関所にて捕縛せし賊三名
隠居所奉公人に死傷者なし
捕り方に怪我人五名
隠居所に待機せし二名、賊一名と交戦するも捕縛ならず
逃走者一名
捕縛した賊の取調べにより、逃走せし一名が本件「鬼没盗」の首領と思われる。
鬼没盗の残党と首領を捕縛するためには、捕らえた七名からさらなる情報を引き出す必要があった。だがその取調べは籐伍ではなく吟味方の他の与力や同心の役目となっていた。
それは籐伍には賊を取り調べる基礎技術が不足し、またその技量も未熟なためだった。老練な吟味方の与力、同心の方がその役目には適していた。それでも籐伍には鬼没盗残党の継続探索が下命された。
ここからはまた籐伍一人で鬼没盗を追うことになったのである。
奉行所での一連の後始末を終えてから鴻池の隠居所に赴くと、そこに渦彦の姿がなかった。少彦名神社に戻っているのかと思い、同修町に行っても渦彦の姿はない。
宮司に聞いてもまだ帰ってきていないという。渦彦は元々大坂に地縁のない人間である。隠居所や少彦名神社以外に行くところなどないはずだった。急に元いた京の五條天神宮に帰ったとも思えなかった。それならば少彦名神社の宮司は知っているはずである。
昨日まであったはずの渦彦の痕跡が、ぷっつりと消えていた。
籐伍は最初この状況をどうしてよいのか分からなかった。心の半分が渦彦と一緒に消えてしまったように感じていた。
その日の夕餉には、久しぶりに阿刀家の全員が顔を揃えていた。元々お役繁多な父念十郎は家に戻らぬことが多かったし、鬼没盗の探索に入っていた籐伍も夕餉を空けることも珍しくなかった。それにこの一ヶ月余りは念十郎と鈴、燕は隠居所と隠れ家に移り住んでいたので全員が顔を合わせることもなかった。
やっとひと段落ついて、天満橋北の家に全員が揃ったのである。久しぶりの夕餉を共にしているというのに、どこか籐伍の食欲は進まなかった。
「どないしたん、全然ご飯食べてへんで」
最初に箸をつけたきりの膳を見た燕が、揶揄うように籐伍の顔を覗いた。
籐伍は反論するでもなく、黙って膳の茶碗を持ち上げた。口元まで運んだのだがそこまでで箸を動かすことはしなかった。
籐伍の心がこの場にないように見えた。
「籐伍、渦彦殿はどないしとるんや。一度招いて礼をせなあかんと思うとる。わしも燕も、渦彦殿に助けられたからのう。都合ええ日を聞いてんか」
父の言葉に、籐伍は一瞬ビクッとした。何か失敗を見つけられた子供のようだった。しばらく沈黙していたが、告白するように父の方に向かった。
「いてへんようになりました。どこにもいてへんのです。隠居所にも少彦名神社にも。まるで大坂から消えてしまったみたいに」
それだけいうと、そのまま押し黙ってしまった。
家族は互いに顔を見合わせ、誰が口を開くかという雰囲気になった。三人ともいいたいことは同じのようだった。
いつも控えめでしとやかな鈴が、珍しく強い調子で口を開いた。
「あんた、それで今までじっとしてたん。渦彦はんには事情があって大坂にいてるんは皆よう知ってる。その大坂からいてへんようなったいうことは、どうしてやと思うの。渦彦はんの事情が変わったからや。ほんまもんの友達やったら、すぐにでも助けに行ってやらなあかんのとちゃうの」
籐伍は鈴に叱られたという記憶がほとんどない。いつも優しく見守ってくれている姉だった。こんな調子で叱られたのは初めてである。死んだ母に叱られているような気がした。
「そやけど、どこに行ったかもようわかりません。どうやって助けいうんですか。鴻池の御隠居に問い合わせても無しの礫です」
二人の言葉を聞いていた念十郎が静かに口を開いた。
「探しにいく場所はあるんとちゃうか」
籐伍は「何処へ」という表情になった。
「渦彦殿が大坂にいてへんようなったいうことは、この前鬼没盗と戦うたときに何かあったからや。それはお前も想像してるやろ。お前自身が最初に指摘した鬼没盗と徳陀子神社との繋がりについて、何ぞ思い当たることがあったからや。そしたら行くとこは徳陀子神社しかあらへんで。多分何かを確かめにな。そこまではお前かて分かってるやろ。鈴は分かってるのに何で動かんのやと怒ってるんや」
念十郎が優しく籐伍を諭した。まるで姉と父が役目を交代したような言い方だった。
籐伍は一瞬言葉に詰まった。だがまるで言い訳のように呟いた。
「お役目があります。大和へ行くにはお奉行の許しも要ります」
「お前はいつからそんな杓子定規な人間になったんや。好きな芝居のためやったらお役目忘れてたお前は何処へいった。わしはそんな籐伍の方が好きやったわ。鈴もそう思うてるから怒ってるんや」
昔の父や姉と言うことが真逆だと籐伍は感じた。それは籐伍が少し大人になり、父や姉が大人として籐伍を扱っているからだった。ただ籐伍にまだその自覚がなかった。
二人は大人の男として、何を置いても友を助けるべきではないかと諭していた。理由を付けて動かないのは大人でも男でもないと。
「色々と忙しかったからいえてなかったけどな、一つ籐伍に教えとかなあかんことがある。わしと燕が賊と戦うたときのことや」
父が何をいおうとしているのかわからなかった。
「わしと燕二人とも、前におる賊から背中を蹴られるいう妙な攻撃を受けたんや。賊は何とも不思議な武術を使う奴やったようや」
念十郎は何かを思い出すように少し沈黙した。
「しかも賊と渦彦殿が戦うたときには、二人は同じような構えと戦い方をしてた。その技を賊は『蹴速』と呼んどった。詳しいことは分からへんが、二人は同流の武技を学んどるらしい。そやから渦彦殿も相手のことに思い当たることがあったんやろ。それを確かめに大和に戻ったんとちゃうか」
父の言葉に、初めて渦彦と戦ったときのことを思い出した。
確かに渦彦は不思議な武術を使い、籐伍の八艘を外してさらに反撃してきた。渦彦はそれを徳陀子神社に伝わる体術だといっていた。
だとしたら、賊もまた徳陀子神社の体術を学んでいることになる。渦彦はそれを確かめに大和に戻ったに違いなかった。なら渦彦を追うことは賊の出自を追うことにもなる。これはお役目にあたると籐伍は即座に閃いた。
「わかりました。明朝すぐに大和への探索願いをお奉行に出します。渦彦を本気で助けるためにも、大和へはお役目として参ります」
そう宣言すると、やっと籐伍は何かを吹っ切ったように茶碗の飯を急いで食べ始めた。燕が空になった籐伍の茶碗に飯を盛っていった。それは家族の役回りを皆で交代したような風景だった。
翌朝早々に提出された籐伍の大和探索願いは、期限付きながらも許可された。来月は西町奉行所の非番月なので、その月内という期限だった。
鈴と燕に手伝われて旅支度を整えた籐伍は、二人に旅立ちの挨拶をして家を出発した。
早朝だったが、父はすでに奉行所に出仕していなかった。隠居を決めてお役目の引継ぎ中のはずだが、なかなか手が離れないようだった。諸色方からは隠居後も今度は念十郎が「仮役」としてお役目の継続を求められているらしい。それではたとえ隠居しても、親子の役回りが逆になるだけのように思えた。
籐伍はまだ一人旅をしたことがなかった。旅どころか、大坂をまともに出たこともない。大阪の武家や町人は京や宇治、あるいは石清水八幡宮、遠くは伊勢までも寺社詣に出かけることはよくある。江戸後期の天保時代は人々に旅が流行った時代だった。
だがこれまで時間があると芝居小屋に入り浸っていた籐伍は、そうした流行りとは無縁の生活をしていた。隣国とはいえ生駒山を越えて大和にまで入るのは初めてのことだった。
大坂から大和に向かうには幾つかの街道がある。徳陀子神社のある葛城山には、生駒山脈南の切れ目である松原から王子に抜ける古道、竹内街道を通るのが通常だった。
この竹内街道は日本最古の官道ともいわれ、推古二一(六一三)年に整備された難波宮と飛鳥京を結ぶ大道である。籐伍の住む天満橋からは真っ直ぐに南下して八尾に至り、さらに南の松原から東へ抜けることになる。生駒山脈南端の竹内峠を東に抜ければそこはもう当麻の地だった。葛城山はその当麻の南に聳える山塊にある。
初めての旅でしかも慣れない道ではあったが、この道程を籐伍はほぼ三日で歩き抜いた。途中に籐伍の気を惹く美しい風景や珍しい文物も多々あったが見向きもしなかった。
途中何度も里人に尋ねながら葛城山東麓にまで来たとき、古びた大きな神社があった。これが徳陀子神社かと中に入っていった。だがそこは一言主神社という別の社だった。
実はここに至るまでも数々の古社に行き合っていた。その度に籐伍はそこが徳陀子神社かと思い、中に入っては確かめてきたのである。一体大和には幾つの神社がるのだと思い、少し辟易していたところだった。
だがこの一言主神社の禰宜が徳陀子神社のことを教えてくれた。
「うちの社の裏にある山道を登って行ったら途中に少し開けた場所があるよって、そこから尾根沿いに北に進みなはれ。そしたら少し家のある山里に出るよって、そこの人らに聞いたらええ。徳陀子さんはその里の奥や。そやけど大坂のお武家はんが何の用があんねん。あそこは修験か病抱えて薬を求める人ぐらいしか行かへんで」
禰宜は少し訝しそうに籐伍を見た。
籐伍はそれには答えず礼だけをいって社裏の山道に入っていった。もう陽が傾きかけているので夜までに着けるのだろうか不安になっていた。
山の陽が落ちるのは想像以上に早かった。明りを持っていない籐伍は暗闇の尾根道を歩くことになった。
「もう何処かで野宿した方がいいかもしれない」と思い始めたとき、遠くに明りが見えた。あれが山里の明りかとホッとした籐伍は、その明りに向かって疲れた足を奮い立たせて歩いていった。
明りの灯った家の戸を叩きながら、声を大きくして案内を請うた。
中からは最初返事がなかったが、声を怪しんだか逆に不憫に思ったのか、戸の閂が外されて少しだけ開かれた。
中からは小さな老人がじっと籐伍を見ていた。籐伍が言葉を出す前に老人が怒鳴った。
「ここにゃあ、金目のもんも食いもんも何もありゃへんで。爺と婆だけの家じゃ。物取りなら他に行け」
それだけいい放つと、すぐに戸を閉めようとした。籐伍は閉まりかけた戸を必死に抑え、老人が興奮しないように静かに尋ねた。
「わいは徳陀子神社を探して大坂から来ました。神社の息子、巨勢渦彦の友人です。神社への道を教えてくれまへんか」
渦彦の名に老人が少し反応した。そして恐る恐るだが戸を半分ほど開いた。開いた戸の陰で老人は左手に鎌を持っていた。戸に隠していたのだ。籐伍が怪しい動きをしたなら、鎌で反撃するつもりだったのだろう。
「渦坊の友達いうんはほんまか。嘘やったらいてまうで」
そういいながらも老人は戸を開き、「まあ入れ」といってくれた。
籐伍はホッとして、小屋の中に入っていった。囲炉裏のそばでは老婦が手招きしていた。
「こんな夜に山を登って来たんは大変やったやろ。白湯でも飲み」
そういって温かい湯を差し出してくれた。
籐伍は白湯を飲みながら、大坂で出会った渦彦のことや徳陀子神社の御神宝を探す手伝いをしていることなどを語った。そして大坂から渦彦がいなくなったので、心配になり徳陀子神社にまで探しに来たのだと告げた。
籐伍の話を聞いてから老人はしみじみといった。
「宮司様が逝かれてから神社は大変や。綿津見はんは体が弱いし、渦坊も京へ修行に行ったきり帰ってこれへん。その上宮司様が死んだほんまの理由もよう分からへんしな。神社から何ぞ盗まれたもんがあったいうんは初めて聞いたが、それを探しに渦坊は大坂へいっとったんか」
籐伍は老人の口走った「死んだ本当の理由がわからない」という言葉に反応した。
「渦彦の父上は自害と聞いていますが違うんですか」
籐伍の言葉に、老人は一瞬「しもた」という顔をした。だが籐伍を渦彦の友達と信じているせいか、宮司が死んだ状況を詳しく話してくれた。
この老人は時々、祭礼などで徳陀子神社の臨時神人をしていたので、幼い頃から渦彦をよく知っていたのだった。そして死んだ宮司を祖霊舎の前で発見した張本人だった。
「宮司様は確かに前屈みになって倒れてはった。ほんで手に短刀を持って胸を突かれてたように見えた。そやけどな、わいには流れ出てる血が少ないなと最初思えたんや。それに……背中のあたりが変に曲がっとった。なんや後ろからでっかい丸太で叩かれたみたいにな。わいはとりあえず、宮司様を綺麗に寝かしてから神社に知らせにいたんや。その後は綿津見はんが村人に頼んで甲斐甲斐しゅうに葬りはったわ。厨様(母親)は泣いてばかりやから、綿津見はんも大変やったやろなぁ」
そうしんみりと語った老人は少し涙も流していた。
「朝に神社へ連れていったるさかい今夜はここに泊まれ。山の夜道は危ないさかいな」
老人はそれ以上もう何も語らなかった。
翌朝、籐伍は老人に連れられて徳陀子神社に向かった。朝でも危ない箇所もある尾根道だったので、夜歩けば本当に谷底に落ちたかもしれない。
辿り着いた徳陀子神社は古色深い社だった。まるで山懐に隠れているようにも見えた。
老人が先に神社の中に入り、籐伍のことを伝えているようだった。少し経った頃に、白装束に袴姿の若い男が出て来た。
巨勢綿津見、渦彦の兄でありこの社の新しい宮司だった。
神社の拝殿で、籐伍と綿津見は対面した。互いに挨拶をしてから、少し硬かった二人の表情が柔らかくなった。
「弟からの文で阿刀様のことはよく存じております。大坂ではいろいろと渦彦がお世話になりました。お礼申し上げます」
綿津見が深々と頭を下げた。
「いえ、渦彦にはわいの方が助けられています。渦彦がおらなんだら、鬼没盗を捕えることもできまへんでした。全部渦彦の協力のおかげです。それに渦彦と友達になれて、わいはほんまに喜んでいます。ですからここにもやって来たんです。渦彦が急に大坂からおらんようになりましたさかい」
籐伍は先日の未然記囮一座の顛末と、その後に渦彦が大坂から姿を消したことを語った。
理由はわからないが、鬼没盗の中に渦彦と同じ技を使う者がいたようで、その賊は技の名を「蹴速」と呼んでいたらしい。それが姿を消した理由ではないかと籐伍は語った。
籐伍の話をじっと聞いていた綿津見は、沈黙してから籐伍に礼を述べた。
「阿刀様は何も語らぬ我が弟のために、大坂からここまで来てくだされました。それは誠にありがたいことです。確かに蹴速は我が神社に、いえ我が一族に伝えられている体術です。この体術は門外不出、口外不可の秘伝とされています。その家禁を守った渦彦は阿刀様にも何も語れなかったんやと思います」
綿津見の言葉に籐伍が待ったをした。
「阿刀様はやめてください。綿津見殿は友の兄上ですから、籐伍と呼んでください。それに多分わいの方が年下です」
籐伍は綿津見が従兄弟の恭一郎と同じぐらいの歳だろうかと思った。綿津見は苦笑しながらも籐伍の言い分を受け入れた。
「では籐伍殿、そう呼ばせていただきましょう。そして渦彦が向かった先はここではのうて、多分桜井やと思います。そこには我ら兄弟に蹴速を教えてくれた叔父がおります。父上が亡くなった今となっては、蹴速について訊けるのはこの叔父しかおらんでしょう。ですから渦彦はここへは寄らず、叔父の元に向かったんやと思います」
綿津見の言葉に、これで渦彦の後が追えると籐伍は喜んだ。
「是非にも叔父上様の居所をお教えください。わいは何としても渦彦の力になりたいんです。鬼没盗捕縛の協力を承知してもろうたときに、渦彦の力になると約束しました。今はそれを果たしたい」
籐伍は綿津見に頭を下げた。その姿を見た綿津見は嬉しそうに微笑んだ。
「渦彦は大坂で誠にええ友を得たようですね。わかりました、ことは我が一族にも関わることですよって、籐伍殿だけにお任せする訳にはいきまへん。私も参ります。桜井は遠くはないですが、今から出発したら夜になってしまいます。明朝、私と一緒に参りましょう。今日はここでゆっくり休んでください。大坂からの旅の疲れもあるでしょうし」
そういうと、「おい、夕凪はいてるか」と拝殿の奥に声をかけた。
ほどんなくして十歳ほどの少女がやって来た。
「これは妹の夕凪です、お見知り置きを」
そして夕凪に向かって「お客人を客間にご案内しなさい。それと母上に湯と食事の支度をするようにお願いしてんか」と指示をした。
籐伍は自分一人で桜井に行くつもりだったので、綿津見の言葉に戸惑った。だが確かに旅の疲れもあったし、また巨勢の一族に関わることだけに綿津見のいうこともわかる。ここは素直に好意に甘えることにした。
そう考えると今まで張り詰めていた気持ちが緩んだせいか、一挙に旅の疲れを感じ始めた。今夜はゆっくり休ませてもらった方が良いなと思った。
(二)
翌朝、籐伍と綿津見は桜井にある叔父の剣術道場に向かった。
叔父の椎根津は桜井に猿飛陰流の剣術道場を開いていた。桜井は奈良盆地南部の東に位置し、西に位置する葛城山とは五里ほどの距離がある。健脚の人間なら半日で歩ける距離だった。
かつて綿津見と渦彦の兄弟に蹴速術を教えるために、椎根津は毎日桜井と葛城山を往復していたらしい。恐るべき健脚である。
体の弱い綿津見が桜井まで行くことに母親は初め難色を示した。だがこれは巨勢一族の惣領の役目であるという綿津見の強い言葉と、籐伍の無事にお連れしますという説得で母親も渋々納得した。
「私はこうして葛城山を降りるのは久しぶりなのです。いつもは渦彦に頼っていましたから。今回は籐伍殿がいてくれて助かりました。私一人では母上も納得しなかったでしょう」
そう呟くと、青い秋空を見上げて気持ちよさそうに微笑んだ。綿津見は惣領の役目を果たすために必死なのだと籐伍は感じた。母親を安心させる為に、自由に旅をすることも許されないのだと。
早朝に徳陀子神社を出発したのだが、綿津見の足の速さに合わせた為に桜井には昼を過ぎてから到着した。
道場には昔一度行ったことがあるという綿津見だったが、当時と様子も変わっていたので、少し迷って里人に尋ねながらの道行きになった。
やっと叔父椎根津の剣術道場にたどり着いたとき、道場からは大きな音がしていた。まるで中で多くの人が戦っているような音だった。
道場の格子窓から、籐伍と綿津見はそっと中を覗き見た。そこで二人が見たのは、数人の稽古着を来た人間と闘う渦彦の姿だった。
稽古着の人間は手に木刀を持っていた。それに対して渦彦は空拳で対している。それにも拘らず渦彦は一撃も木刀の攻撃を受けず、逆に相手を投げ飛ばしたり、手刀で相手を打ち据えたりしている。
乱取り稽古だとは理解できたが、このように一対数人というのはなかなかない光景である。
その光景をじっと見ていた綿津見はそっと籐伍に囁いた。
「これは準備運動です。蹴速は本来複数人を相手にする技ですから」
そういった綿津見だが、渦彦が蹴速術の足技を一切使っていないことに気がついていた。
きっと稽古着の男たちは叔父の剣術「猿飛陰流」の門弟で、彼らによって渦彦の手技を鍛えているのだと思った。そして蹴速術本来の足技は叔父との二人稽古で修練しているのだろうと思った。
渦彦の乱取り稽古が一段落ついたと思える頃、綿津見は表玄関から中に声をかけた。
「叔父上、ご無沙汰しております。綿津見です。お話があって参りました。中に入ってもよろしいでしょうか」
綿津見の声に呼応するように、椎根津が道場に号令をかけた。
「本日の稽古はこれまでとする。各々、体を整えてから下がるように。渦彦はそのままここに、綿津見はそなたにも用があるやろう」
道場の神棚前から立ち上がった椎根津が玄関にまで出て来た。そこで綿津見と籐伍の前に立った。
「お前も来るやろうとは思うとったわ。意外に早かったようやな。それでそちらの御仁は」
綿津見から籐伍の方に視線を向けた。籐伍は前に出て名乗りをあげた。
「初めてお目もじいたします。私は阿刀籐伍と申します。大坂西町奉行所の仮役与力ですが、ここへは巨勢渦彦の友として参りました。どうぞお見知り置きください」
籐伍の声に、「えっ」と驚いた渦彦が道場から玄関の方を振り向いた。そこには久しぶりに見る籐伍の姿があった。
「なるほど、渦彦から話は聞いております。あなたが鬼没盗を追う小太刀使いの籐伍殿か」
何か面白いのかまじまじと籐伍を見てから、「中に入られよ」といって元いた道場の神棚前に戻っていった。
籐伍と綿津見は道場に入ると、渦彦の座る横に並んだ。渦彦と籐伍は一瞬視線を合わせたが、言葉は発しなかった。椎根津を前にして、三人が並んで対するような形になった。
籐伍が何から聞こうかと迷っていると、椎根津の方が言葉を向けてきた。
「お前たちがここに来た訳はおおよそわかっておる。渦彦と同じ用件やろう。各々に語るのも面倒ゆえ、揃うのを待っておった。渦彦の修練も至急に終えねばならぬかったからの」
そういうと、深刻な表情になった椎根津がまず渦彦に語りかけた。
「お前との約束では、わしから一本取れたなら知りたいことを教えてやろうというたが、少し順番が狂うてしもうた。まだお前はわしから一本取れておらんが、ここまでお前を案じてやって来た兄と友に免じて最初の質問に答えてやろう」
そして目を瞑った椎根津は、何か苦い記憶を思い出すように語り始めた。
「最初の質問は、なぜ蹴速を使う者が我ら以外におるのかということやったな。……お前たち兄弟とわし以外に、今この世にはもう一人だけ蹴速を使える者がおる。それはかつてわしの弟子やった男や。名を古瀬稀人(こせまれひと)という」
椎根津の言葉に三人は一瞬息を飲んだ。
籐伍もだが、渦彦、綿津見の兄弟にとっては衝撃的な叔父の言葉である。巨勢宗家の者以外に蹴速術を使える者がいる。それは千年の禁忌を破ることを意味していた。
何かをいおうとした綿津見に、椎根津はそれを抑えて話を続けた。
「稀人は最初わしの剣術の弟子やった。猿飛陰流のな。こやつは武芸に天賦の才があったようで、わずか一、二年で猿飛陰流の全てを吸収してしもうたわ。わしは皆伝を授けようとしたが、稀人はそれを拒みよった。そして別の物を要求して来た。それは……完全なる蹴速の教授じゃった」
三人と椎根津はしばらく重苦しい沈黙の中にいた。
「何故その者は蹴速の存在を知っておるのですか。蹴速は門外不出、口外不可の禁があります。宗家以外の者が知るはずがありまへん」
綿津見が絞り出すような声で尋ねた。その言葉に椎根津は深く頷いた。
「その通りじゃが、長い時の中では秘密が秘密でのうなることもある。まさに稀人がそのような例であった」
ここで椎根津は、自分の過去を悔やむような表情をした。今でも悔いているようだった。
「稀人の家には蹴速の一部が伝わっておったのじゃ。稀人は不完全ながらも蹴蹴を修得しておった。わしも驚いたが紛れもない蹴速の技じゃった」
不完全な蹴速術がいつから稀人の家に伝えられていたのかは分からない。それは太古から宗家以外の別流として存在したのか、あるいはどこかの時代に宗家から分流したのか。稀人の苗字が「古瀬」であることから、「巨勢」からの派生であるのかもしれない。ならば元は同族だった可能性も高いのだった。
直近の歴史で考えてもこの可能性はあるのだった。巨勢宗家の惣領が仙薬法を継ぎ、次男が蹴速術を継ぐという仕来りは、いずれ分流を生む下地になっていた。
例えば椎根津が宗家の子以外に、自分の子にも蹴速術を教えたならどうなるのか。それは禁忌ではあるがないことではない。せっかく身につけた秘術を自分の子に伝えたいという欲望はいつの時代にも存在しえるのである。長い時間の中ではこの過ちは十分に起こりうることだった。
「稀人がここに入門してきたんは最初から蹴速が目的やったのかもしれへんが、武芸の天才であることもまた事実やった。猿飛陰流を修めたからこそ、蹴速の話も出したんやろう。そしてわしもそれに心を動かされた」
稀人の蹴速の技は不完全ではあったが、それでも十分に強かった。そして椎根津もある夢を見たのだった。
「この天才に完全な蹴速を教えたら、どこまで強くなれるのだろうか」と。
この思いは武芸者の願望だった。また椎根津が猿飛陰流を学んだ理由の一つでもあった。
椎根津は若い頃、いかに蹴速を極めようともそれは生涯表の世界に出すことはできない強さだということに悩み、絶望した。宗家の禁忌がそれを許さないのだ。
だから表の世界で強さを試せる猿飛陰流を学んだのだ。だが猿飛陰流を極めれば極めるほど、余計に蹴速の強さが心に残った。
もし猿飛陰流を使う自分と蹴速を使う自分が戦ったなら、勝つのは蹴速を使う自分だろうと思った。
それは生涯表に出せない強さだった。宗家に生まれた自分はこの理不尽な禁忌から逃れることは許されない。それは理解していた。
だが稀人ならどうなのだろうかと思った。自分が夢見てできなかったことができるのかもしれない。たとえできなくとも、自分の最強の敵になれるかもしれない。椎根津もまた、最強の蹴速を振るえる相手が欲しかったのだった。
稀人が元は巨勢の同族かもしれないという思いは、椎根津の罪の意識を慰めてくれた。外に出すのではなく、同じ巨勢に教えるのだと自分にいい聞かせていたのだ。
「結局、わしは稀人に蹴速を教授した。それはちょうどお前たち兄弟に指南し始めたのと同じ頃やったか。稀人はお前たちには存在してはならぬ兄弟子になるんや」
椎根津の言葉は巨勢宗家の人間としの贖罪だった。
沈黙して聞いていた籐伍が、ここで急に椎根津に質問した。
「叔父上殿のお話はわかりましたが、一つ質問があります。なぜ巨勢家は長男に仙薬法、次男に蹴速術という分けた継承方法をとっているんですか。すべてを惣領に継がせれば秘術が外に出る可能性も少ないでしょうに」
何気ないつもりでいった質問だったが、それは巨勢家のより大きな闇を明らかにする言葉だった。
椎根津は籐伍を改めて見詰めて、「勘の良い与力殿じゃな」と感心したように呟いた。そして綿津見にその答えを求めた。
「綿津見、お前は籐伍殿の質問に答えられるやろ。死んだ兄上からまだすべてを口伝されてはおらんかもしれんが、この答えは持っておるはずや。何より十年前にお前自身がしたことやからな」
椎根津の言葉に、綿津見は一瞬体を固めた。そして下を向いたまま黙ってしまった。籐伍も渦彦も、綿津見の行動の意味がよくわからなかった。
「わしは今、巨勢の秘密を語っとる。外の人である籐伍殿にも聞かせる為にな。これは巨勢の禁忌に触れることやが、古瀬稀人を生み出してしもうたわしの罪滅ぼしでもある。もういい加減わしらはこの禁忌から解き放たれる必要があると思うとる。その罪過は全てわしが背負うつもりや。兄上もお許しくださるやろう」
この場に相応しくない微笑みを浮かべた椎根津は、籐伍の方に向かった。
「籐伍殿、今のお尋ねにお答えいたそう。なぜ次男に蹴速を継がせるのか。それは蹴速を継ぐためには命を賭けねばならぬからや。家を継ぐ惣領に命懸けの試練はさせられぬからのう」
籐伍と渦彦は椎根津の言葉の意味がわからなかった。ただ綿津見だけが下を向いていた。その顔は蒼白になっていた。
椎根津は蹴速術を継承するための儀式について語り始めた。それは宗家の次男が十歳になったときに行われるという。次男が十歳になったときある仙薬が処方されるのだった。その仙薬は「鬼変薬」と呼ばれる一種の肉体強化薬だという。鬼変薬を飲んで適合できるかどうかを試すのである。
適合できれば人を超える力や速さ、そして肉体の強靭さが獲得できる。
だが適合できなければどうなるのか。それは人によって異なるが、悪くすれば副作用で即死するらしい。死ぬまで行かなくても重度の健康障害が起こり、寿命も短くなるかもしれない。
このような危険な薬を家を継ぐ役目の惣領に試させる訳にはいかなかった。だから次男で適合するかどうかを試すのである。次男なら死んでも代わりがいるのだった。それは秘術と家系の両方を守るための苦肉の選択なのかもしれなかった。
唖然と椎根津の話を聞いていた籐伍と渦彦だが、急に渦彦が尋ねた。
「そんな危ない鬼変薬に何で適合できるか試さなあかんのですか。それにわいは十歳のときにそんな薬を飲んだことありまへん」
椎根津は少し悲しそうな表情で渦彦に答えた。
「それは鬼変薬を飲んで強化された肉体は、まるで鬼のような強さと能力を獲得できるからや。そして強化された肉体で蹴速術を使うたら、人には不可能な強さを発揮できるようになる。それを我が一族は『鬼神術』と呼んどる。鬼変薬と蹴速術の二つで完成される鬼神術を使う者は、天下無敵になれるということや。それはそもそもの巨勢のお役目のために必要な強さやったらしい」
その昔、古代において巨勢一族は朝廷や大豪族の戦闘兵団だった。誰にも負けぬ兵士の強さが求められたのである。そのために編み出されたのが蹴速術であり鬼変薬だった。鬼変薬を作り出すために様々な薬も研究され、それが転じて巨勢の仙薬法になったのだという。
伝説によると、あるとき蹴速術よりも強い武技を操る兵団が出現し、巨勢は一時その地位を失ったことがあるらしい。その復権のために創り出されたのが鬼変薬だという。武技が同水準ならば肉体能力の高い方が戦いに勝つ。
だがこの薬の開発には困難を極めた。そしてやっと完成した鬼変薬にも適合する人間と、そうでない人間がいた。そのためにこの鬼変薬で多くの一族が命を失ったらしい。
巨勢の力を守るためにこの蹴速術と鬼変薬は一族の秘術として今日まで守られ、伝えられて来たのだった。今となってはもう失なわれた役目のための、無用の無敵の強さではあったが。
呆然と椎根津の話を聞いていた渦彦は兄の方に向いた。
「わいは何も知りまへんでした。兄上は知ってはったんですか」
渦彦の無邪気な問いが、綿津見の過去の罪を暴こうとしていた。
十年前に渦彦がもう十歳になろうとしたとき、父飫肥人は宗家の仕来り通りに渦彦に鬼変薬を試そうとした。その試練に生き残らなければ巨勢宗家の次男として、蹴速術継承者の役目は果たせないのだった。
父から鬼変薬の製法を口伝された綿津見は、いわれるままに渦彦に飲ませる鬼変薬を用意した。
だが理不尽な仕来りに対する怒りと弟への愛情から、綿津見はその薬を渦彦に飲ませることをしなかった。代わりに父には黙って綿津見自身が鬼変薬を飲んだのだった。
その結果、綿津見は鬼変薬に適合しなかった。死にこそしなかったが、何日も苦しんだ挙句に重度の健康障害に陥ったのだ。
父飫肥人は綿津見の行為と結果に驚き嘆いた。そして苦しんだのだった。やがて弟の椎根津にも今後のことを相談した。
二人が出した結論は二つだった。一つ目は渦彦が鬼変薬を飲んだとして、次の子供が生まれるまで今は渦彦に鬼変薬を試さぬこと。もし渦彦に試して渦彦まで不適合ならば、巨勢宗家が途絶えることにもなってしまう。健康障害を起こした綿津見は、元々病弱な子だったとして扱うことだった。
そして二つ目は早急に三男が生まれるのを待つことだった。その後に三人目の子供は生まれたが、それは期待に沿わぬ女児だった。妹の夕凪である。その後今まで、渦彦に鬼変薬を試されることはなかったのだった。
淡々と語られる椎根津の言葉に、籐伍も渦彦も言葉が出なかった。
十年前に兄が自分の身代わりになっていたことを渦彦は知らなかった。今兄が不自由な生活を強いられているのは、自分を救うためだったのだ。
渦彦は半分泣き出しそうな顔で兄を見詰めた。どういう言葉を発してよいのか、全くわからなかった。
「綿津見は一切語らんやろうが、お前が今生きておられるのは綿津見のお陰といってもよいやろう。しかしなぁ、こうしたことは巨勢の歴史の中では稀にあるんや。わしと兄上との間にもそれはあった、また別の形やがな」
椎根津は遠い日を思い返すように天を仰いだ。
「わしと兄上の間にはもう一人兄弟がおった。本当の巨勢の次男坊や。その次男坊は鬼変薬の試しで結局死んでしもうたわ。そして三男やったわしが繰り上がった。そこまでして一族が継いできた蹴速術なんや。たとえ表に出せずとも継がぬ訳にはいかん。ただわしは稀人ならば蹴速をどのように使うかが見たかった。その欲がわしの過ちや」
椎根津の言葉に籐伍が再び尋ねた。
「では鬼没盗が、いえ古瀬稀人が徳陀子神社から盗んだ御神宝とはその鬼変薬なのですか」
籐伍の疑問に、下を向いていた綿津見が顔を上げて答えた。
「いや、それはないと思います。あの薬を作作るにはかなり特殊な薬種が必要やよって、父がそれを集めた跡がありまへん。勿論口伝を明かすこともないでしょう。そやから……父上は殺されたんかもしれまへん」
ここで初めて、綿津見は父の死が自害ではなく、殺害だと口にした。それは綿津見がずっと考えていた可能性だった。
実は綿津見も父の遺体を見たときにある異変に気がついていた。胸の刺し傷ではなく、折られたような背骨の曲がりに。
父の遺骸を発見した老人が最初に指摘した異変だったが、綿津見はそれを他にいわぬように口止めしたのだった。それはその損傷が蹴速の一撃によってできた損傷に似ていたからだった。
一族以外に蹴速が使える者などいるはずがない。そう思ったからこその口止めである。
だが一族の他にも蹴速が使える人物がいるとなると、話は変わってくる。椎根津の話を聞くうちに、父の背中の損傷は蹴速の一撃によるものに違いないと思えてきたのだった。
「もしかしたら父上は、その古瀬稀人に鬼変薬の秘密を求められ、拒んだから殺されたのかもしれまへん。古瀬稀人が誠に蹴速術を自分のものにするためには、どうしても鬼変薬が必要でしょう。蹴速術から究極の鬼神術に化けるためにも」
綿津見の淡々とした言葉に、渦彦は少し驚いていた。渦彦にとって綿津見は常に優しく、愛情深い人間だと思っていたからだ。その綿津見が今は冷たすぎる表情で父の死の理由を語っていた。それは激しい怒りを覆うための綿津見の仮面だったのかもしれないが。
「稀人はかつてわしにいうたことがある。天はなぜ何の役目もない自分に、このような才を与えたのかと。稀人は蹴速術自体よりも、巨勢宗家の重い宿命が欲しかったのかもしれへん。自分が天賦の才を持つ理由をな。それが今の自分にないことを嘆いとった。もし稀人が本当にその鬼没盗ならば、どこかでその理由を手に入れたからかもしれへんな」
椎根津の言葉に対して、決然とした綿津見がいい返した。
「それは父上を殺す理由にはなりまへん。自分の天命は自分で見つけるものです。他人から奪うべきでものではありまへん。私は自らにてもそうしてきました。私の天命は家族を守ることやと思いました。ですから父上の命や巨勢の仕来りに背いても、渦彦に鬼変薬を飲ませへんかったんです」
綿津見は椎根津に対してというよりも、まだ姿の見えない稀人に抗議するように叫んだ。この場の全員が綿津見の内側で赤く燃える埋火を見たような気がした。
普段にない声を出したせいか、綿津見は激しく咳こんだ。渦彦も籐伍も綿津見を心配して近寄ろうとしたが、綿津見は大丈夫だというように二人を制止した。
その様子を見た椎根津が、「昔のお前を見るようやな」と呟いた。
「急にいろいろと語りすぎたかもしれへんな。一編に全部を受け入れるんは難しいやろ。綿津見には葛城山からの疲れもあるやろうから、今日はゆっくり休め。明日また聞きたいことがあったら話したる。それに今からは急ぎ渦彦に仕上げの修練もさせなあかんからな」
そういって、籐伍と綿津見を奥の部屋に下がらせた。
道場にただ一人残った渦彦に向かって、「これから温羅(うら)の蹴速を修練する」と椎根津が静かに告げた。それはまだ渦彦が聞いたことのない蹴速術だった。
(三)
「温羅の蹴速」とは、音の転化から別に「裏の蹴速」とも呼ばれる蹴速の隠し技である。
元々蹴速術の原点は大和の当麻ではなく、遥か西国の一族が持つ武闘術だったらしい。その一族は「鬼の温羅」と呼ばれる戦闘に優れた一族で、古代大和の権力者たちにはなかなか服さなかった。
それゆえ大和は侵略軍によってこの鬼の温羅一族を滅ぼそうとしたのである。侵略軍の将軍は吉備津彦命と呼ばれ、後の桃太郎伝説の原型にもなったといわれている。
吉備津彦命は第十代崇神天皇の時代に発せられた四道将軍の一人だといわれていた。大和の政権が全国を征服しようとした時代の、地方征服を命じられた将軍だった。
吉備津彦命の侵略軍により、温羅一族は滅ぼされたとされている。そしてその一部は俘囚として大和に連行されたのだった。
温羅の俘囚たちが蹴速術の始祖・当麻蹴速になったのかどうかはわからない。ただその武闘術を巨勢などの氏族に伝えただけなのかもしれなかった。だが伝えたにしても全てを伝えたわけではなかった。まだ温羅の蹴速と呼ばれる秘密の技があったのだ。
この技は普通の肉体能力では使うことが困難だったことから、表の蹴速としては伝えなかったともされている。だから裏の蹴速と呼ばれたのだ。
鬼の温羅一族の肉体は人としては異常なほどの強靭さと力だったらしい。その異常な肉体能力を前提にした技が温羅の蹴速である。
だがいつの時代かに鬼変薬が生まれた。結局この鬼変薬は太古の鬼の温羅一族の肉体能力を再現するための薬だったのかもしれない。温羅一族はその二つ名の通り、人には真似できない鬼の肉体能力を持っていたのだ。
鬼変薬の登場によって温羅の蹴速は再び意味を持つようになった。その技は代々の巨勢宗家次男にしか伝えられない隠し技になったのだ。鬼変薬を試すことがない惣領には無用の技だからである。
その温羅の蹴速を椎根津は渦彦に伝えようとしているのだった。
「お前がこの先、鬼変薬を試さぬならばこの温羅の蹴速は無駄になる。温羅の蹴速はわしの代で途絶えることになろう。それはそれでよい。それでもわしが温羅の蹴速を渦彦に伝えなあかんのは、それは……古瀬稀人が温羅の蹴速をも盗み取っているからや」
椎根津の言葉に渦彦は驚愕した。宗家に生まれた自分さえも知らぬ蹴速術を、他家の稀人がすでに修得している。
「なんでそんなことがあるんですか。叔父上が教授されたんですか」
渦彦の質問に椎根津は悲しそうに首を振った。
「稀人が誠に武芸の天才であったということが、このときはっきりした。わしが教えぬ温羅の蹴速を稀人は目で盗み取ったんや」
まだ稀人が椎根津の弟子だった頃、毎夜行われていた椎根津のたった一人の修練を、稀人が盗み見ていたのだった。
夜の修練には表の蹴速もあったが、ときに温羅の蹴速が修練されることもある。無論椎根津は稀人が見ていることなど知らぬままに、全力の温羅の蹴速を修練した。
武術には見取り稽古という方法がある。言葉や手取り足取りではなく、ただ先人の動きを見て、その技を理解し目に焼きつける。そして技を複写するのだ。
並の修行者にはまず不可能な修練だが、稀人のような天才にはそれが可能だった。稀人は椎根津が教える表の蹴速のみならず、温羅の蹴速さえもその目で盗み取っていったのだ。
それがはっきりしたのは、四年前に稀人が道場から出奔したときだった。
理由もいわぬまま、ある日稀人は道場から姿を消した。その三日後の夜、再び道場に戻ってきた稀人は一つの要求をした。
「先生には何の遺恨も不満もありませんが、ただひとつ心残りがあって戻ってまいりました。ぜひとも私と蹴速でお立ち会いください。私は自分がどこまで強くなったのかを知りたいのです。それを知るには先生と戦うしかありません」
二人の間に言葉や問答など必要なかった。それは椎根津もまた長年夢見ていた夢だったからだ。やっと全力の蹴速で戦うことができる。それだけで椎根津にも十分だった。
その夜、決着はついに着かなかった。
椎根津が押したと思えば、稀人もすぐに逆襲した。そして稀人が満を持したように温羅の蹴速を繰り出してきた。
椎根津はまさかと思ったが、それは紛れもなく温羅の蹴速、撃ノ壱・鬼神蹴りだった。究極の速さと感知不能な角度から相手を襲う殺人技である。椎根津がその技に倒れなかったのは、稀人が鬼変薬を飲んでおらず鬼の肉体能力を持っていないからに過ぎなかった。
稀人が温羅の蹴速を使ってくることは想像の外だった。
自然と椎根津も温羅の蹴速を使って応戦した。撃ノ弐・打神脚、撃ノ参・空震弾と技を繰り出したが稀人は見事に受けていた。
稀人が温羅の蹴速を修得しているのは明白だった。
いつ終わるともしれぬ二人の攻防が続く中で、稀人は急に戦いの構えを解いた。そして満足したようにその場に正座した。椎根津に対して深く深く頭を下げていた。
「ありがとうございます。これ以上やればお互いの技に倒れる前に、温羅の蹴速に身体の方が持ちますまい。しかし私は先生に匹敵するほど強くなれたと自分を確信しました。あとは鬼の身体を手に入れるだけです」
それだけを告げると、稀人は来たときと同じように風のように道場から去って行った。
椎根津は後を追うこともできずに、その場に倒れ込んでいた。普通の身体のまま温羅の蹴速を濫用したことで、身体中の筋肉や骨が悲鳴を上げているのがわかった。
「叔父上は鬼変薬に適合しているのでしょう。鬼神術が使えるのになぜ稀人と互角に終わったのですか」
渦彦の問いに椎根津は残念そうに説明した。
「鬼変薬に適合したというても一度だけのこと。鬼変薬の肉体強化、鬼化の効能は一刻ほどで終わるんや。一度薬を飲めばずっと鬼化されるわけではない。普段は普通の肉体に戻ってしまう。そやから昔の兵士は戦いの前にだけ鬼変薬を飲んで鬼神術を使うたらしい」
椎根津の説明に渦彦は少し不満げな表情を見せた。命をかけて鬼変薬に適合しても、効果が一刻ほどしかないという。そんな一瞬に命をかける意味などあるのだろうかと思った。そのために兄は健康を失っているのだ。
椎根津も渦彦の気持ちはわかったが、まだ語っていない恐ろしい事実があった。それは鬼変薬に適合したとしても、鬼変薬を幾度も服用すればやがては不適合と同じような障害が体に起こるということである。
結局のところ、それは人を超える力を得たための負債を後で支払うようなものである。世の道理はそうやって保たれているのかもしれなかった。
「お前が温羅の蹴速など必要ないと考えるなら、敢えて伝授はせえへん。そやけどこの後、もし稀人と戦うつもりなら必要な技になるやろう。それに今のお前は四年前にわしと最後に戦うたときの稀人よりも弱い。それは温羅の蹴速以前の段階で、表の蹴速で稀人に劣ってるいうことや。今遣り合えばお前は必ず負けてまう」
椎根津の残酷な宣告だった。渦彦の心は様々な思いに分裂していった。
今のままでは父の仇かもしれない古瀬稀人には勝てない。それは椎根津に改めていわれなくても、先日の隠居所での戦いで実感していた。二、三手の技を合わせただけだが、その感じた強さは確かに異常だった。今は戦っても勝てないかもしれない。
しかも自分の命は兄の綿津見が身を犠牲にして守ってくれたものなのだ。なのに今温羅の蹴速を学べば、いつの日か鬼変薬を試し、鬼神術を求めることになるかもしれない。その一歩目が温羅の蹴速の修得である。
どうしてよいのか渦彦は迷いに迷った。どちらを選択しても悔いが残るだろうと思う。
心底誰かに相談したいと思った。
初めに浮かんだのは兄の顔だったが、同時に兄はダメだとも感じた。兄は自分の健康や命を賭けて渦彦を守ったのだ。この先鬼神術を求めることをよしとはしないだろう。
次に浮かんだのは何故か籐伍の顔だった。
緊張感のない顔で笑っていた。あまり役立ちそうには思えなかったが何故か心がほっとした。そして前に語っていた籐伍の夢の話を思い出した。
「ほんまは奉行所の役人仕事は好きやないけど、好きなことをするためには背負わなあかん重荷もあるんや。それを投げ出したら、好きなもんも面白うは感じんようになってまう。この世に生きるということは、好きなもんだけやとあかんのやと思う。そやからわいは奉行所仕事をしながら、芝居を書こうと思うてるんや。いつかこの鬼没盗のことも、渦彦のことも芝居にしようと思うてるで。そう考えると奉行所の仕事も面白うに感じるし、芝居を見る目も変わった。浮世には芝居以上におもろいことがいっぱいやと気がついたんや」
能天気な籐伍の考えだったが、どこか柔らかさを感じる言葉だった。何もどちらかだけと思わなくても良いのだ、二つが両立する新しい道を探せば良いと教えてくれいていた。
「あのボーッとした籐伍が、たまには良いことをいう」
そう思うことにした。そして自分に正直な道を探そうと思った。
それは巨勢宗家の次男としての役目を果たし、同時に兄の思いにも答える生き方だった。もし本当に古瀬稀人が父の仇なら、たとえ自分の方が弱くても必ず仇を討つ。それが並び立つ生き方を探そうと決心した。
そのためにも温羅の蹴速は必要だった。今は巨勢宗家の次男の役目と、古瀬稀人に近づくために温羅の蹴速を学ぼう。そして必要がなくなれば封印しようと思った。自分のような思いを誰にもして欲しくないと思った。
何かを決心したように渦彦は立ち上がると、徐に鬼骨の構えをとった。それは椎根津に温羅の蹴速を催促する意志表示だった。
「ほう、ええ顔になったな。迷いがのうなっとる」
そう呟いた椎根津は、それまで渦彦が見たことのない速さで肉迫してきた。そして何をどうされたのかも分からないうちに、道場の端まで吹き飛ばされていた。何故か背中に大きな激痛が走っていた。
「撃ノ壱、鬼神蹴りや。まずはこれを見切れ。他の技はそれからや。時間がないから連続で行く。まずは動きに着いてこい」
そこから数え切れないほど、渦彦は蹴り飛ばされ続けた。夜に始まった修練だったが、それは本当に夜が明けようかという頃まで続いた。
だが外で千鳥のさえずりが聞こえ始めたとき、椎根津の描く鬼神蹴りの軌跡が一瞬見えたような気がした。その軌跡は千鳥のさえずりの「ちっちっちっちっ」という声に、どこか同調しているように感じた。
渦彦はさえずりの調子の先を読むように、鎧脚で鬼神蹴りを防ごうと動いていた。そして初めて鬼神蹴りを彈くことに成功した。
だが同時にもう次の鬼神蹴りが渦彦の背後から襲ってきていた。渦彦は再び道場の端まで吹き飛ばされていた。
「ひとつ止めたからと安心するんやない。鬼神蹴りは相手が立っとる限り襲い続けるんや。ならばどうする」
答えは単純だった。相手が鬼神蹴りを放てないようにするまでだった。その夜初めて渦彦は攻勢に出た。そして鬼神蹴りが渦彦に至る瞬間に、稲妻脚を椎根津に向けて蹴り上げていた。相打ち覚悟の蹴りだったが、その蹴りで椎根津は少し退き、渦彦は鬼神蹴りの衝撃に耐えていた。椎根津が退いたことで鬼神蹴りが弱まっていた。
この夜初めて椎根津の攻撃が止まった。
「今夜はここまででええやろ。わしも少し無理しすぎたみたいや」
そう呟く椎根津が、その場に座り込んでいた。普通の肉体で温羅の蹴速を連発していた椎根津は、遠に限界を超えていたのだ。そのまま崩れるように横たわっていった。
「叔父上」と叫びながら、走り寄った渦彦はそこに意識のない椎根津を見た。こんな姿の叔父を見たのは生まれて初めてのことだった。
この夜の修練は椎根津にも過酷なものだったのか、夜が明けるまで目覚めなかった。
だが道場に門弟がやってくる刻限になると、椎根津は誰かに起こされたかのように目を覚まし、普段通りに門弟の稽古を見ていた。渦彦は恐るべき精神力だと思った。まだ温羅の蹴速の影響で身体は軋んでいるに違いなかったが、それを誰にも悟らせはしなかった。
そして夜になると、再び渦彦との温羅の蹴速の修練に臨んでいた。二人の修練を垣間見た綿津見は、まるで椎根津が自分の命を削りながら稽古をつけているように見えた。
温羅の蹴速は、鬼変薬を服用せぬ限り使う方にも苦痛を強いる。しかし渦彦に温羅の蹴速の全てを伝えるためには、椎根津は自分の身を犠牲にしても厭わぬ覚悟のようだった。それが椎根津に残された最後の仕事であるかのような覚悟と悲壮な姿だった。
十日ほど過ぎた頃、綿津見は温羅の蹴速の修練を休むように懇願した。そして今までできなかった話をしたいと求めたのだった。
「まだお前の質問には答えておらなんだな。よかろう、今宵はその時間に当てよう」
そう了承した椎根津は夕餉のあとの時間を話に当ててくれた。
「古瀬稀人は父上との面識があったのでしょうか。鬼変薬はともかく、神社の仙薬洞から奪われたらしい物もあります。それは鬼没盗が盗みに入るときに使われた夢沈香です。父上が渡したとは思えまへん。何故古瀬稀人は夢沈香の存在を知っていたのでしょうか」
それは綿津見と籐伍の共通の疑問だった。渦彦が温羅の蹴速の修練をしている間、二人はこれまでの鬼没盗事件のあらましを話し合い共有していた。そしていくつかの疑問を導き出していたのだった。
椎根津は少し考え込んでから自分の推察を語った。
「兄上と稀人は知らん間柄ではないやろうな。わしからの使いとして葛城山にも行ったことは幾度かあるし、稀人自身が神社の薬を知人のためと称して贖ったこともあるらしい。それに……稀人の古瀬家には蹴速以外の戦の方法も伝わっておったようや。夢沈香は元々戦の際に使われた相手方陣内への撹乱方法のひとつと聞いたことがある。古瀬家に夢沈香の存在が知れていても不思議やないやろう。それをどうやって奪ったかは謎やがな。一番単純なんは盗みに入ることやろうか」
どの段階、どの時期から古瀬稀人が鬼没盗の一味と繋がっていたかはわからないが、警戒の薄い徳陀子神社から何かを盗み出すのは難しくはないだろう。それが口伝ではなく、冊子に記された調合法だと尚更である。
「では、稀人は我が巨勢宗家の内情をある程度知っていたということですか。ならば再び鬼変薬を奪いに神社を襲うこともあるということでは」
だがその質問には椎根津はしばらく答えなかった。稀人がどこまで鬼変薬に執着しているのかは不明だが、兄の飫肥人が死んだとなればその可能性は低いと思っていた。
当然神社も何らかの警戒をするだろうし、実弟である椎根津の耳にも入る。そうであれば神社を襲うことはさらに難しくなる。もし椎根津が警戒にあたれば、今度こそ師弟の決着をつけることになる。そのとき必ず稀人が勝てる保証はないのだ。
もし椎根津が鬼変薬を用いれば普通の肉体の稀人には勝ち目は薄いだろう。そんな理由から椎根津は神社襲撃の可能性は低いと考えていた。
話を聞いていた籐伍にも疑問があった。
「わいには今だに古瀬稀人が殺しをするような人間には思えんのです。鬼没盗も死人を出してません。渦彦との戦いでも勝ててたかも知れへんのに、さっさと逃げてもうてる。何や殺しは避けてるようにも見えます。叔父上殿の話から強うになることには貪欲やけど、それ以外のところではあんまり無理強いをしてません。それに……」
籐伍は話の腰を折ることを恐れるように、基本的な疑問を口にした。
「何より何で稀人は骨董品ばかりを奪う盗賊をしてるんかが不思議なんです。稀人は昔から骨董が好きやったんですか」
素朴な籐伍の疑問はいつも何かの扉を開ける切っ掛けになった。
少し考えた椎根津は、自分でも忘れていたある伝承を思い出していた。
「稀人は武辺の男やったから、骨董好きということはないやろ。ただ鬼変薬のことを話してて、今思い出したことがあるわ。それは……鬼変薬の出自に関する伝承や。鬼変薬を巨勢に齎したんは、聖徳太子やいう言い伝えがあるんや」
椎根津の言葉に籐伍と綿津見は驚いた。鬼没盗の狙う骨董が聖徳太子絡みの骨董ではないのかという推測があったからである。
椎根津はその言い伝えについて語った。
「鬼変薬も元は支那からの渡来の薬やという伝承がある。聖徳太子の周囲には支那や韓の人間が仰山こといてて、まず薬は太子の元に齎され、そして太子の腹心やった巨勢にも伝わったという話が残ってる。巨勢としては自分たちで生み出したとしたいとこやが、どうも元はその辺りからの薬らしい。巨勢のご先祖様はそれを自分たち用に改良したんやろ。稀人はその辺りの経緯をどこかで知ってるんかも知れへん。巨勢から奪えなんだ鬼変薬を、伝承の中から探すつもりで手がかりを太子絡みの骨董に求めてるんかもしれへんな」
籐伍はそうかもしれないと思った。渦彦の父を死なせたことで、鬼変薬にはおいそれとは手が届かなくなった。
ならば巨勢の鬼変薬が生まれた頃の痕跡を探したらどうなるのか。稀人はそこから鬼変薬を再現しようと考えたのかも知れない。
だとしたら必ずそうしたことに詳しい協力者か黒幕がいるに違いなかった。飛鳥や聖徳太子の歴史も薬の製法も、素人が手に負えるような物ではない。だが鬼没盗は聖徳太子の痕跡を集めるように盗みを続けている。きっと鬼変薬再現に向かう道筋を示している人物がいるのではないのか。
「だとしたら、古瀬稀人と鬼没盗はまだまだ盗みを続けるいうことです。この前捕まえた賊はただの尻尾や。稀人か黒幕を捕まえん限り、鬼没盗は止まらんいうことやで」
籐伍は嘆息するように呟いた。それに渦彦が嬉しそうに答えた。
「それはわいらには好都合や。また稀人と戦る機会があるいうことや。今度こそ鬼没盗と稀人を捕まえたる。籐伍もそうしたいんやろ」
渦彦が能天気な希望をいうと、逆に籐伍が渋い表情になった。その鬼没盗を追う手掛かりが今は途切れているのだった。
どこかで二人の性格が影響し合っているようだった。能天気な籐伍の考えを渦彦が吸収し、渦彦の責任感を籐伍が持ち始めていた。
「もしも本当に古瀬稀人や鬼没盗が鬼変薬の独自再現を考えてるんやったら、彼らが大坂を根城にしているのも少し頷けます。大坂はこの国すべての薬種が集まる場所やし、また医術や薬方に長けた人物も仰山こといます。それに西洋の知識を持つ蘭方の学者や塾も多いと聞きました。鬼変薬を研究するには格好の場所です。できれば私も蘭方医たちと鬼変薬や仙薬について語ってみたいものです。私の知らない知識と意見を戦かわせたらどんなに楽しいことか……」
綿津見の夢見るような呟きに、渦彦は「えっ」と思った。兄のそうした夢を渦彦は知らなかったのだ。
確かに綿津見は今まで葛城山を出ることがなく、また外の世界で勉強することもなかった。健康のこともあるが、生まれてからずっと巨勢宗家の惣領として葛城山に閉じ籠るような生活である。外に出るのはいつも渦彦の役目だった。
渦彦は京で修行の日々も体験しているし、大坂で探索の苦労もしている。だが綿津見には千年前からの知識と宗家の仕来りだけがあった。
本当は綿津見にも外の世界で自分を試してみたいという夢があったのだ。ただその夢は家族のために心の奥底に押し込めているのだった。
そんな兄弟の思いを知らぬ籐伍が能天気な提案をした。
「綿津見殿も大坂に来はったらどないですか。そしたらわいも随分と助かります。鬼変薬を作るいう鬼没盗や古瀬稀人を探すには綿津見殿の薬の知識に頼るしかありまへん。渦彦は少彦名神社や隠居所の居候やから無理やろうけど、わいの家には空いてる部屋もありますよって、いつまででもいてください。父上も歓迎すると思います」
あっけらかんと籐伍が、良い思いつきだというように皆にいった。巨勢家の三人は、戸惑ったような顔をすることしかできなかった。
(四)
椎根津との話で判明したのは二つの事実だった。
ひとつは鬼没盗に加わっている古瀬稀人の存在が判明したこと。
そして彼らが飛鳥や聖徳太子絡みの骨董を盗むのは、巨勢家の仙薬の一つ、鬼変薬を再現する手掛かりを求めてかも知れなということだった。
籐伍は新たに判明したことから、この先どう鬼没盗を追い詰めようかという思案を続けた。
その間も渦彦はひたすら椎根津との温羅の蹴速の修行に勤しんでいる。籐伍はその修練を見ることは許されなかったが、その壮絶さは想像できた。毎朝修練を終えた二人が、意識を失うように寝床に倒れ込んでいった。
だが椎根津はその一刻ほど後には、もう猿飛陰流の門弟の稽古を見ているのだった。籐伍は椎根津が本当に倒れるのではないのかと心配になった。
桜井の道場に来てから昼間は手持ち無沙汰なこともあって、籐伍は猿飛陰流の稽古に参加することが日課になっていた。
勿論籐伍の剣術は中条流平法だったが、他流派の剣士と稽古することは色々と勉強になった。そもそも他流派の剣士と剣を鍛える機会などそうそうあることではない。
自流では当たり前のことがここではそうではなかった。籐伍は剣の技以上に、世の多様さということに気がつかされていた。正解は一つではないのだとつくづく感じていた。
そんな籐伍だったが、そろそろ大和探索の期限が近づきつつあった。西町奉行所の当番月までには大坂に戻らなければならなかった。
ある日、温羅の蹴速の修練から目覚めた渦彦にそのことを相談した。当然渦彦の温羅の蹴速の修練に終りというものはないだろ。武芸とは本来果てしないのだ。もし渦彦がまだ修練を続けるつもりなら、大坂へは一人で戻ろうと考えていた。
だが案に相違して、渦彦もまた籐伍と一緒に大坂に戻るつもりだと語った。今渦彦の第一の目的は温羅の蹴速の完全修得ではなく、鬼没盗や古瀬稀人との決着をつけることだった。渦彦は何よりも稀人に問いただしたかったのだ。
「本当に鬼変薬を奪うために、父を殺したのか」ということを。そのために温羅の蹴速を学んでいると籐伍にいった。
たとえまだ稀人に勝てずとも、一撃入れるぐらいではないと稀人と話もできない。それは巨勢宗家に生まれた蹴速術継承者の誇りでもあった。
今の状況では、むしろ稀人の方が蹴速術の継承者といっても過言ではない。表の蹴速で渦彦を上回り、温羅の蹴速をも使いこなしているという。
渦彦の中では鬼没盗捕縛や父の仇を討つということ以上に、稀人との間で蹴速術継承者を争う戦いのようにも感じていた。
それに……渦彦はまだ誰にもいってはいないが、不気味な畏怖を感じていた。それは「稀人は巨勢宗家そのものを奪おうとしている」という漠然とした恐怖だった。
蹴速術は稀人の方が渦彦よりも優れ、また鬼変薬も再現しようとしている。もしも温羅の蹴速と鬼変薬の両方を手にして、究極の鬼神術を使えるようになった稀人は、もはや巨勢宗家そのものといってもよいのではないのかと思った。
千年間一族が守ってきた巨勢宗家を、古瀬稀人はたった一代で作り上げようとしている。そして巨勢の宿命さえも奪おうとしていた。そんな漠とした恐怖だった。
かつて稀人が椎根津に語ったという、「天はなぜ何の役目もない自分にこのような才を与えたのか」という嘆きが、何故か恐ろしい略奪宣言のように思えていた。稀人の天才は技や薬だけではなく、人や一族の運命まで奪おうとしている。それはもう人ではなく魔物か鬼神のようだと思った。
古代中国、殷の時代に四凶の一つとされる「饕餮(とうてつ)」という鬼神がいたと伝説は語る。饕餮はこの世にあるすべての物、食物から財産まで何でも喰らい、やがて世の善や悪、神や魔までも喰らったといわれる。殷の青銅器や玉器にはこの饕餮を謳う饕餮文が刻まれていたらしい。
渦彦は幼い頃に父からこの饕餮の伝説を聞いて、恐ろしさで眠れなかった思い出があった。今はその伝説を思い出していた。
「古瀬稀人はまるで饕餮のようだ」
その饕餮と渦彦は戦おうとしているのだ。神代の世界の話だと思った。
「三日後に籐伍と共に大坂に戻ります」
翌日温羅の蹴速の修練の後に、渦彦は椎根津にそう告げた。それはいよいよ稀人と戦うという宣言に等しかった。
椎根津はただ「そうか」とだけ応えて、何故か初めて渦彦に対して深く頭を下げた。
「わしの過ちの尻拭いをさせるようですまぬなぁ。稀人は誠に強いが、決してお前が勝てぬ相手ではあるまい。必要なのは一度、蹴速を忘れることや。個々の技に固執しては動きを読まれる。要はいかに天衣無縫に戦うか。特に自分よりも優れた相手とはな。お前が知る技は稀人も全て知る技と思え。そうすれば稀人の先を取れよう。わしからの最後の教えや」
そして稽古場の板間に正座すると渦彦にも座るようにいった。
「これより名渡しの儀を行う。わしは今日より巨勢椎根津の名を捨て、お前に渡す。椎根津の名は巨勢宗家の次男が代々受け継ぐ名前や。この名を名乗る者こそ、巨勢家伝の蹴速術継承者と認められるんや。今すぐやのうても構わへん。お前が真に蹴速術を継承できたと思うたとき、椎根津を名乗れ。わしもそうやった。それまではわしも昔、渦彦やった。渦彦から椎根津に名変わりすることこそ継承の儀や」
これまで渦彦も知らなかったが、叔父もまた若い頃「渦彦」と呼ばれ、真に継承がなったときに椎根津と名乗ったのだった。そうやって代々、椎根津の名を?いできた。重くそして捨てられぬ、一族の宿命を繋ぐための名前だった。
渦彦は自分が椎根津を名乗る日が本当に来るのだろうかと思った。それは少なくとも古瀬稀人に勝てなければ名乗れない名前だと感じていた。
三日後、籐伍、渦彦、綿津見の三人がいよいよ桜井の道場から葛城山に出発しようとしたとき、椎根津は今までに見せたことがないような優しい笑顔で見送ってくれた。
「叔父上、古瀬稀人と決着したならまたここに戻ってきます。そしてそのときこそ完全なる温羅の蹴速をご教授ください」
決意を語った渦彦に、椎根津は微笑むだけだった。応とも否とも答えなかった。
ただ椎根津は三人へ順に言葉をかけた。
「籐伍殿、あなた様は誠に良き男や。この後も綿津見や渦彦の良き友でいてくだされ。我が兄飫肥人に成り代りお願い致す。鬼没盗捕縛というお役目の成就を願っております」
綿津見には一冊の本を渡した。
「これは兄上が亡くなる前に借りてた本や。返しそびれてたさかい、代わりにお前に返すわ。お前は身体は弱いが心が強い。それは昔から変わらんええとこや。この後も惣領として皆の頼りになるんやで」
そう笑いながらいうと、今度は渦彦の方に顔を向けた。何かをいおうとしたが、「やめた」とだけ呟いた。
渦彦に掛ける言葉はもうないようだった。今日までの温羅の蹴速の修練で、もう十分に語り尽くしていると思ったからだ。言葉以上に、交わした技の数々で二人はずっと語り合っていたのだ。それに渦彦に渡すべきものはもう全て渡したと満足している。
渦彦にもそのことがよくわかった。後は椎根津から受け取ったものをどう活かすかだけだった。
「では叔父上、葛城山に帰ります。冬には好物の葛城の干し柿を届けますので楽しみに待っていてください。それまでご健勝で」
綿津見の挨拶に頷き、三人が見えなくなるまでずっと道場の前で見送ってくれていた。
道場からしばらく歩き、椎根津の姿はもうとうに見えない処まできていた。だが渦彦は名残惜しそうに、道場の方を何度も何度も振り返っていた。
椎根津は生まれてからずっと渦彦の師だった。厳しすぎることもあったが、今はその意味がよくわかる。椎根津は巨勢宗家次男の持つ過酷な運命に負けぬように、渦彦を鍛えてくれていたのだ。
振り返った渦彦の視野が何故か涙で滲んでいた。
「あれ、変やな。何で涙が出てるんやろ」
渦彦は自分が涙を浮かべていることを不思議に思った。
三年前に家族と離れて、京へ神人修行に旅立つときも涙は流さなかった。なのに今は不思議と涙が出てくる。
籐伍はそんな渦彦を見ながら、少し揶揄うような調子でいった。
「名残り惜しいんやったら、今から桜井に戻ってもええんやで」
そう軽くいった籐伍だったが、不意に何かに気がついたようにその場に立ち竦んだ。
「あっ、あかんわ。これはあかんかもしれへん……。何で今まで気づかへんかったんや」
籐伍の様子に驚いた綿津見が、不思議そうに顔を覗き込んできた。
「籐伍殿、どないしはったんですか。何ぞ忘れもんでも」
そう問う綿津見に籐伍が慌てた様子で答えた。
「わいの考えすぎやったらええんやけど……、叔父上殿のことが気にかかります。もしかしたら叔父上殿は……」
籐伍のいわんとすることが綿津見にもわかった。籐伍は椎根津が自害するかもしれないといっているのだった。
確かに最後の挨拶は少し奇妙に感じていた。まるで二度と会えないようないい方だった。それに椎根津は最初に、「この責は全て自分が背負う」といっていたではないか。
今は渦彦に蹴速の全てを伝えたのだ。自分の役目がそれで終わったと思ったのならば、後は責任を取るだけだった。
古瀬稀人を生み出した責任。
禁忌を破り蹴速術を外の人間に開示した責任。
そして何より兄である飫肥人を死なせてしまった責任。
椎根津が自分を責める罪過は幾つもあった。
そのことに気がついた綿津見は、急いで桜井に戻ろうと踵を返した。それを制した籐伍は、渦彦に向かって叫んでいた。
「お前が一番足が速い。とにかく道場に戻って叔父上殿の無事を確認せえ。わいは綿津見殿と戻るさかい。一刻を争うかもしれへん、とにかく急げ」
言葉の意味を理解した渦彦は、「先に行きます」と兄に叫ぶと全力でその場から走り出した。
その後ろ姿を見ながら、籐伍は綿津見に肩を貸して早足で桜井への道を歩き出した。自分の不安が杞憂であってくれと、籐伍は生まれて初めてどこか空の彼方にいるという神仏に向って祈っていた。
渦彦が息を切らせながら道場に駆け込んで行くと、そこに人の気配はなかった。いつもなら猿飛陰流の稽古をしている刻限である。
「叔父上どこですか」
叫びながら家の中を探したが椎根津はいなかった。そして最後に稽古場に入っていくと、その真ん中に座っている椎根津を発見した。
椎根津は稽古着ではなく、葛城山にいた頃の白装束の姿をしていた。
「叔父上、ここにいてはったんですか」
渦彦は嫌な想像を打ち消すように軽い調子で語りかけ、椎根津の座る正面に回った。
そこで前屈みに倒れ込んでいる椎根津の姿を見た。武家ではない椎根津は腹を切ってはいなかったが、小太刀で首筋を鋭く断っていた。
どす黒く流れる血が辺りに広がっていたが、少し時間が経っているせいか稽古場の板敷の色と同化しようとしていた。
稽古場に入った瞬間から血の広がりは見えていた。だが渦彦はそれが見えていないかのように椎根津に話しかけていたのだ。
渦彦は椎根津の前に座り込んでしまった。何をしてよいのか全くわからなかった。
ただただ座り込むことしかできず、そして声さえも出せないまま、本当に大粒の涙が止めどなく頬を流れ落ちていった。
どのくらいの時間、渦彦がそうしていたのかはわからなかった。
ふっと気がつくと自分の後ろには兄と籐伍が立っていた。
「兄上、これは誰のせいですか。叔父上は何で死ななあかんのですか」
答えなど分かっていたが、そう聞かずにはいられなかった。
渦彦と綿津見は半年前の父に続いて、今また叔父も失ったのだ。
「叔父上殿を横にして楽にしたれ。ほんで二人はここで弔いや。あとのことは全部わいがするさかい、二人は叔父上殿をゆっくりお見送りせえ」
それだけを告げると、籐伍は振り返らずにその場を後にした。
これからするべき仕事を一つ一つ頭に思い描いた。そうしないと籐伍も悲しみで心が折れそうだと思った。
短いとはいえ、籐伍もまた椎根津の弟子だった。桜井に滞在中は猿飛陰流の稽古に加わり、師弟の礼もとっていた。その師が今亡くなったのだ。
自分の悲しみなど、二人に比べれば小さなものだと思おうとした。それでも知らぬ間に籐伍の頬が涙で濡れていた。その涙を無理やり拭うと自分の顔を両手で叩いた。
「今はわいがしっかりせなあかんのや。二人をこれ以上苦しめたらあかん」
そう思うと、籐伍は急いで一番近い家に向かって走っていった。
まずは椎根津の弔いの用意が必要だった。その後は猿飛陰流の門弟たちにも知らせ、この地の名主にも告げる必要があるだろう。そんな細々とした仕事が次々にあるのだ。それは全部自分の役目だと思った。
思わぬ椎根津の自害を受けて、三人はそのまま葛城山に戻ることはできなくなった。結局は初七日を終え、さらに様々な事後処理をしたところで、三人はやっと葛城山への帰路につくことができたのだった。
綿津見のためにゆっくりと歩んだ道のりだったが、もう徳陀子神社に着こうかというときに綿津見は籐伍と渦彦に決意を告げた。
「父上の死と叔父上の自害で、私も少し思うところがあります。これは私からの願いなのですが、鬼没盗、いえ古瀬稀人の探索に私も加えていただきたのです。この件はもはや父上の死の謎解きという以上に、巨勢宗家の問題になっていると思います。そやから惣領の私の手で決着をつけたいのです。籐伍殿や渦彦には迷惑をかけるかもしれませんが、何卒、私の願いをお聞き届け願いたい」
その言葉には綿津見の決意が滲んでいた。
徳陀子神社に戻った綿津見と渦彦は久々に母に会い、そして叔父椎根津の死の顛末を語った。椎根津の死は手紙で知らせていたが、その経緯は詳しくは知らせていない。父の死と、叔父の自害が関連しているかもしれないという事実に、母も言葉を失っていた。
さらに綿津見は「この謎と原因を究明するために、私は大坂に探索に行くつもりです。これは巨勢宗家の棟梁の役目と存じます」と宣言した。
綿津見には珍しく、相談ではなく決めたことだと宣言したのだった。それに綿津見は初めて自分のこと棟梁といった。それまでの惣領という一歩引いた表現ではなかった。
母は言葉を失ったように、しばらく黙ったままだった。張り詰めた空気を和ごませようと籐伍は母に綿津見の身を請け負った。
「綿津見殿のお身は我が家でお世話させていただきます。うちには姉も二人おり女手は余ってますから、十分にお世話できると思います。どうぞご安心ください」
少しは安心したようだったが、それでも母の不安は拭切れなかった。
「兄さま、大坂に行ってきたらええ。兄さまがいてへん間はうちがお母はんの面倒みるし。そやから心配せんでええで」
突然、部屋の端から声がした。見ると襖から半分だけ顔を出している夕凪がいた。皆がまだ子供だと思っていた夕凪が、このときは不思議に大人びた表情をしていた。
気勢を削がれたような母が、何かを紛議ったように頷いて夕凪を側に呼んだ。そして夕凪を膝に抱きながら、籐伍の方に向かって頭を下げていた。
「阿刀様、息子たちのことよろしゅうにお願いいたします。まだまだ足りんとこがありますが、どうぞよしなに」
そう呟くと綿津見に向かった。
「あんたやっと巨勢の棟梁の顔になったなぁ。棟梁の言葉には従わなあかんからな。あんたの好きなようにしなさい」
そういって初めて少し微笑んだ。綿津見も渦彦も母の微笑みを見て初めてほっとした。
綿津見の大坂行きは決まったが、それなりに不在の間の神社への手当てが必要だった。女だけの神社は無用心である。
綿津見は自分が不在の間の用心に、籐伍を泊めた元神人の老夫妻に神社への一時住み込みを依頼した。老夫妻はその依頼を承諾し、さらに山里の若衆には日替わりで神社への泊り番をするように話をつけてくれた。それでまずは綿津見も安心をした。
もう西町奉行所への帰還期限が真近に迫っていた籐伍が、まず綿津見と共に大坂へ出発することになった。渦彦は二人より何日か遅れて出発することにしたが、渦彦の足の速さと綿津見の足の遅さを勘案したら、到着はそう変わらないだろうと思えた。
それに渦彦にとっては久々の母や妹との生活である。籐伍はその時間を渦彦に与えようと考えたのだった。
大坂の阿刀家には大和より手紙を出し、帰還の日と客人を連れ帰るのでその受け入れ準備を頼んでいた。そうした準備をした上で、二人は大和から大坂への旅路を歩んだのだった。籐伍には二度目の旅路になるが、大和から初めて出る綿津見には全てが物珍しくまた刺激的だった。
大坂の市中に入ってから綿津見はその喧騒と人の多さ、そして繁栄ぶりに目を丸くした。これが日の本一の商都かと感嘆したのだ。
松屋町筋の大坂西町奉行所の前を通り過ぎ、同修町に差し掛かった。
「この辺りが薬の街と呼ばれる同修町です。この奥にあるんが渦彦が世話になってる少彦名神社です」
歩きながら説明する籐伍に綿津見が反応した。
「籐伍殿、少し寄り道してもよろしいか。渦彦がお世話になっているご挨拶もしたいが、薬種問屋や少彦名神社を見てみたのです」
目をキラキラさせている綿津見を籐伍は面白そうに眺めた。
「少彦名神社の手前に茶店がありますよって、そこで休みましょう」
二人が茶店の縁台に座って休息の茶と名物のきな粉餅を食べていると、その前を見知った人物が通り過ぎようとした。
「阿刀様、お久しゅにございます。今日はまたどのような御用でこちらへ」
声を掛けてきたのは少彦名神社の阿曽宮司だった。
「これは宮司殿」
籐伍が立ち上がりながら挨拶すると、宮司は隣に座っていた綿津見の方をチラッと見た。籐伍は仕方ないなと思い綿津見を紹介した。
「実は渦彦を探しに大和に行っておりました。こちらは渦彦の兄上の巨勢綿津見殿です。渦彦とも無事に会えましたので、綿津見殿を大坂まで先にご案内してきた次第です」
そう簡潔に説明すると、宮司の方が驚きそして喜んだ。
「渦彦はんのお兄上ということは大和の徳陀子神社の宮司様か」
そういってから自分の紹介を始めた。
「わてはこの同修町にある少彦名神社の宮司をしてる阿曽と申します。以後よろしゅうにお願いいたします。それで渦彦はんは見つかりはったんですか。それはよろしおました、御隠居様も喜びはるわ。それに渦彦はんのお兄上、徳陀子神社の宮司様にお会いできるとはなんという僥倖や」
綿津見は立ち上がると、何かを察したように挨拶を返した。
「巨勢綿津見です。宮司様には弟が大変お世話になっていると聞いております。誠にありがとうございます。いろいろと事情があり弟はいっとき大和に帰っておりました。弟もおっつけ大坂に戻りますが、先に私が阿刀様のご案内で大坂に参りました。少彦名神社には改めてご挨拶に伺う所存です。ここでお会いできたのは少彦名様のお引き合わせでしょう」
そう綿津見が返すと、宮司も「そうですなぁ。これはまさに少彦名様のお引き合わせや」と嬉しそうに同意した。
「今日はこれから急ぎの用がありますよってここで失礼いたしますが、いずれ改めてお話したい。どちらに逗留されるご予定ですか」
尋ねる宮司に「我が家に逗留していただきます」と籐伍が答えた。
そう聞いて納得した宮司は、「ではまた改めて」と告げて忙しそうに立ち去っていった。籐伍はやれやれというように宮司の後ろ姿を見送った。
「悪い人ではないんですが、私は少し苦手なんです」
呟く籐伍に綿津見も少し頷いていた。
「さすが大坂の宮司様や。大和で見知る神職の方々と違い、まるで商人のように見えますね」
籐伍も成程その通りだと思った。
予定外の邂逅もあったが、籐伍と綿津見は無事大坂に到着したのだった。
幕間ノ挿話
それはまだ大坂に鬼没盗が出来する前のことである。
大坂東町奉行所の組与力、大塩平八郎正高の屋敷に訪問者があった。
大塩は自宅に「洗心洞」という陽明学の塾を開いていた。そのため学問や社会改革を唱える者どもが多く訪れてくる。その日の訪問者もそんな一人だと思い、大塩は対応したのだった。
訪問者はまだ若い男だった。男は自らを江戸の国学者だと名乗り、この国に原初からある正義や夢を探していると語った。
「大塩先生は世の改革を唱えられ、実際に奉行所の施策にも生かされておられる。誠に尊敬いたします。ただ一つ、足りぬことがあると思います。それはこの国が始まったときの大義を考えられておらぬこと。国学者の目でいうならば、徳川の世は長いこの国の歴史の中で、いっとき天朝より任されたる世です。鎌倉や室町の世と何ら変わりはない。ですから徳川の次の世を見据えるべきではありませんか。それにはこの国の原初にあった夢と正義が必要です」
大塩は大それたことをいう男だと思った。だがこの手合いはたまにいた。次に出す卑小な個人的要求の為のはったりの場合が多いのだった。
「またまた、ご大層なる物言いやな。それに一つお間違いになられてはる。私は何も世の改革などは唱えておりまへん。ただ陽明学の摂理に合う、世の正しい運営方法を述べておるだけのこと。徳川の次の世のことなど考えたこともありまへん」
そう返してから、男が来訪したときに出してきた名刺を見返した。
「ところで、何でこの名刺には姓名がないんや。ここに書いてあるんは字名か雅号や。初訪問の相手に出すには不適切な名刺やで」
大塩が手に持つ名刺には中央に「徐市」とあり、その脇には小さく「蓬莱山住人」と記してあった。
大塩の不満げな言葉に、男は同意するように薄く笑った。
「この世での通り名を記せば、先生は多分私の言葉に先入観を持たれると思います。ですから私の立ち位置だけを示す名刺をお出ししました」
自分の立ち位置? と大塩は一瞬訝ったが、確かにその名刺は男の立ち位置を暗示しているようだった。
「蓬莱山とは支那の地にて夢見られた東方の三つの神仙山の名の一つや。他に方丈と瀛州がある。その蓬莱山に棲むといわはるか」
そして再び徐市の文字を見た。そこで大塩はひとつの伝説を思い出した。
蓬莱山に住む徐市といえば連想される人物がいた。
古代支那で秦の始皇帝を誑かし、東方の海に財宝や童男童女三千人と共に消えていった、不老不死の仙薬を蓬莱山に求めたという方士「徐福」である。徐市は徐福の別名か幼名といわれていた。
「立ち位置か、確かにのう。ではこの地に神仙の国を作るといわはるか」
男は大塩がやっと自分の出した名刺の意味を理解してくれたことに、本当に嬉しそうに頷いた。そして一つ訂正を入れた。
「神仙の国ではありません。神の棲まわる国を再興したいのです。昔遥か西方にあったという神の国を。それが私の求める夢であり正義です。太古この国にはその志がありました」
自分の横に置いてある風呂敷包みを徐に大塩の前に差し出した。
大塩が「なんや」という顔をすると、男は真面目な顔で告げた。
「これは私が徐市である証であり、また先生と同志になるための契りの品です。どうぞお納めください」
そう慇懃にうと男は深く頭を下げた。
大塩は包みを解くと、そこに黒塗りの文箱があることがわかった。
男の「どうぞ中をお改めください」という言葉のままに、文箱の蓋を開けてみた。中には古色が深い紙の文書が入っていた。
「これはなんや。私は国学者やないから昔の文には興味はないで。私が欲しいのは未来への指針や」
大塩が皮肉を込めていうと、男は「それはよかった」とだけ呟いた。そして文箱の中の古い紙を徐に広げて見せた。その最初の部分に書かれていた文字を見て、大塩は一瞬体が固まったように思えた。
冒頭には古い墨文字で、「未然本記」と読める字があった。未然とはなんやと最初思ったが、大塩の脳裏に一つの知識が蘇ってきた。
日本書紀にも記されている「太子兼知未然」とある文節だった。
「太子、兼(か)ねてより未(いま)だ然(し)らざるを知る」と読み、伝説では聖徳太子の記した未来予言書「未然記」の記載だとされていた。
「これが未然記やというんか。大嘘にしてもまた面白い物を持ってきたな」
大塩は半分呆れたように声を出したが、同時に面白そうに笑い出してしまった。これまで土産を持ってきた来訪者も多くいたが、こんな土産を持ってきた者はいなかった。本物かどうかは別に、面白い思い付きをする男だと感心した。
「先生が疑われるのはごもっともです。ですがこの書は本物の写本です。幾つかに書き分けられた内の一つのようです。少なくとも四百年程前まではそう信じられていました。おそらく楠木正成公が読まれた物と同じなのでしょう。ただ残なことに、この文書には徳川の世の先の事は記されておりません。それはまた別の書にあるのだと思います。それが手に入れば、また先生にお届けいたします。それこそが先生の求められている未来への指針でしょうから」
そう告げた男は、もう用は済んだというように立ち上がっていた。
男の行動に戸惑った大塩は、逆に男に尋ねていた。
「お主は結局何のためにここにきたんや。何の所望もなく、また論も講じなんだ。そしてこの未然記のみをわしに献じようとする。目的は何なんや」
大塩はなぜかこの男に不気味な恐ろしさを感じ始めていた。知らぬ間にまるで魔物と契約を結んでしまったような怖さだった。
「私の目的はもう果たされました。私は先生の真ん中にあるものを見極めたかったし、感じたかった。この未然本記はそれに対する私からのお礼です。先生は私に対し何もしていただく必要はありません。我らは未来への同志ですが、お互いに独立しています。連携する必要はありません。ただこの後も先生の思われる陽明学による世の運営を押し進めください。それが私の願う神の棲まう国再興への助けともなります」
そういい残した男は、まるで風に吹き消えるように大塩の屋敷を後にしていった。後には呆然とした表情の大塩と、未然記と称される古文書だけが手に残されていた。
大塩の屋敷を出た男が暗闇の中の道を歩んでいた。するとどこから現れたのか、並ぶように黒い人影が寄り添って歩いていた。
「大塩はどうだった。お前の眼に叶ったのか」
黒い人影が突然声を発した。それは意外なほど綺麗な声で、夜には相応しくない太陽の香りを感じさせる明るい声音だった。
男は「ふふっ」笑うと、ちらりと横の人影を見た。その瞳には喜びが溢れているようだった。
「久々に良い人と巡り合えました。私の謎掛けを見事に返された。しかも本当に不動の意志をお持ちのようです。あなたと初めて出会ったときのことを思い出しましたよ。大塩先生はあなたに並ぶ人材です」
男の言葉に人影は嫌な顔をした。人影は他者と比較されたり、並べられることを極端に嫌っていた。それを知っているからこその男の言葉だった。
ふたりは同時に天を仰いだ。そこには凍てついた冬の夜空に大きく広がる、天の川の銀色に輝く帯が煌めいていた。
「お前はいつも天から皆を見下ろしている。あの天の川のようにな。それはお前自身の名がいっていることだ、そうだろ天河。それが本当の名かどうかは知らんがな」
人影の言葉に男は初めて眉を潜めた。その名を呼ばれることが嫌というよりも、誰かに聞かれることを嫌っているようだった。
「人の名は呪のとば口になります。不用意に口にするものではありませんよ。それはあなたにとってもそうです、稀人さん」
天河と呼ばれた男はいい返したが、呪など知らない人影、稀人は気にもかけなかった。
「それより求める物は手に入ったのですか。大和からの帰りがずいぶんと遅かったですが」
天河は隣を歩く稀人に尋ねた。その問いに稀人は渋い顔になった。
「残念だが二つは手には入らなかった。手にできたのは宸翰のみよ。それに求めた仙薬は期待したようなものではないようだ。宗家は自ら仙薬を飲んで俺に挑んできたよ。だが……結局仙薬への不適合からか、戦いの最中に命が尽きてしまった。優しい俺は不適合の苦しみから救ってやったがな」
そうあっけらかんと、大和であったことを天河に語った。
「あんな不完全な仙薬などとても怖くて使えぬわ。宗家の奴らはよくそれを千年も守ってきたものだ。宗家は千年もの間、穴蔵に入ったままで外に出ようとはしていない。だから俺は違う道を行くことにした。お前のいうように皆を等しく神仙に変える薬を新たに作り出す。それが正しいやり方だ。宗家のように過去の虜にはならんさ」
サバサバとした表情で稀人は夜空の天の川に向かって語った。天の川がまるで天河自身であるかのようないい方だった。
「そうですか、わかりました。それでは急ぎ太子と飛鳥の記録を調べましょう。そこにきっと仙薬に至る手掛りがあるはずです。あなたにも当然働いてもらいますよ。元々あなたの夢なんだから」
そういった天河だったが、新しい遊びを始めるときのようなワクワクとした気分になっていた。大坂の街もこれから面白くなりそうだと感じた。
月のない冬の夜空では、天の川の星の輝きが世界を導く燈明のように見えた。それは世界における天河の存在意味を表しているようでもあった。
第五幕 太秦の神紋
(一)
天満橋北の阿刀家に到着した籐伍と綿津見は、やっと大和からの旅装を解くことができた。綿津見も旅の間は気持ちが張っていたせいか不調をいわなかったが、到着した夜より床に着くことになった。
そんな綿津見の世話を甲斐甲斐しくしたのは燕だった。籐伍は少し意外な気がしたが、どうも鈴と燕の間で役目を決めているようだった。
少し後に籐伍は鈴から、燕がどうしても「綿津見様のお世話は私がしたい」と望んだことを聞いた。どうやら鈴の見るところ、燕が綿津見にひと目で懸想したのかもしれないと笑いながら語っていた。
籐伍は綿津見が復調するまでの間に、父念十郎に大和であったことを報告した。話を聞いていた念十郎は「そこまで話してええんか」と巨勢の秘密を公にすることを心配した。
「鬼没盗に関わる人々には知っていてもらいたいと綿津見殿の意向です」
その言葉に念十郎は感慨深げに頷いた。
「綿津見殿はきっと叔父上殿の決意と気持ちを汲まれたんやろうな。自分や渦彦殿を含めた巨勢の人々をいにしえの呪縛から解き放つという、叔父上殿の命を捨てた決断を重んじられたんや。これはできることやないで。千年にも及ぶ家禁を破るんや、綿津見殿は器の大きなお人のようやな」
念十郎の言葉に籐伍も深く同意した。
「叔父上殿の死を無駄にせぬためにも、新たな鬼変薬を作ろうとする古瀬稀人は捕らえねばなりまへん。わいも二人同様に叔父上殿より後のことを託されたんやと思います。それに……わいには叔父上殿がどこかで古瀬稀人もまた救いたいのではないのかと感じました。ですから本来無関係な私にも秘事を明かされたのではないかと思います。巨勢の兄弟にそれを求めるのはあまりに酷ですから」
籐伍の言葉に、念十郎は「ほぉ」という顔をした。そして改めて少し成長した息子の顔を見つめた。
「お前、大人になったなぁ。自分以外がよう見えるようになってるわ」
父親としても与力としても籐伍の成長を認めた言葉だった。
「それでどないするつもりや。確かに鬼没盗首領のことはわかったが、それだけでは鬼没盗にはまだ届かへんで。どうやって捕縛するんや」
念十郎は初めて籐伍に今後の探索指針を尋ねた。
「それは考えています。綿津見殿の回復を待って、共に薬種問屋、医師、薬局などを回るつもりです。綿津見殿によると、鬼変薬を作るには特殊な薬種や素材がかなり必要やということです。それを集める者の情報や、研究する学者を当ります。きっと古瀬稀人や黒幕もそこに接触しているはずやと思います」
籐伍の答えに念十郎は満足したように頷いた。
「お前の好きなようにしたらええ。これはお前の捕り物や」
そして付け加えるように籐伍に告げた。
「お奉行より隠居のお許しがやっと出たわ。まぁ条件付きやがな」
籐伍が「条件?」と尋ねると、念十郎は困ったというように頭を掻いた。
「お前が鬼没盗を完全に捕縛したら隠居してもええいわれたわ。それまでは大坂の面倒をまだ見いいうことや。しくじったら楽隠居もできへんで」
そう苦笑したが、あまり心配している様子ではなかった。念十郎は大人に成長した籐伍を十分に信頼していた。
籐伍もそれにどう答えようかとちょっと迷った。だが結局やることは同じだと思った。
「お役目に精進いたします。それまでは父上も大坂をお願いします。それが我らの務めですから」
力むことなく答えた。それが大人の対応だと籐伍にも理解できていた。
床から復帰した綿津見は、早速大坂市中に薬方の探索に出ようとした。だがそれは籐伍と一緒ではなかった。綿津見の大坂での行動には燕が付き添うことになったのだ。
一つには奉行所役人と一緒では、なかなか核心の話をしてくれないだろうという不安があった。薬には秘事の部分がとても多いのだ。ここは純粋に薬の研究者同士として巡った方が、先方も胸襟を開いて話してくれるのではないかという思惑である。
燕は綿津見の助手兼大坂の案内人として供をするという。女性連れの方が確かに先方も警戒しないだろう。
綿津見は燕を供に連れることを念十郎に許可を求めた。
「お父上様、燕殿を危険な目には合わしまへんので探索の供をすることをお許しください」
念十郎に平伏する綿津見に対して、なぜか燕も隣で両手を付いて頭を下げていた。
念十郎は不思議そうに二人を見ながら、ちょっと困った表情をした。
「なんや、燕を嫁にくれといわれてるみたいやで。燕は小太刀も使えるし、先日の隠居所でも賊と闘うてるお転婆や。なんぼでも供させて構いまへん。お役に立ててください」
そう答えながら、逆に燕に厳しくいいつけた。
「綿津見殿のお身体をきっと守るんやで。大和のお母上様には籐伍がそう約束してるんや。これは巨勢家に対する阿刀家の誓約やからな、破る訳にはいかへん。それに綿津見殿は籐伍の助けのために大坂にいらしたんや。その御恩を忘れたらあかん」
そう念十郎は念を押したが、燕は言葉とは裏腹にどこか楽しそうだった。
こうして綿津見と燕の大坂での薬方探索が始まったのだった。
綿津見との同行を外された籐伍は、改めて鬼没盗の狙いそうな聖徳太子絡みの歴史的遺物を当たり始めていた。大坂、京にありそうな遺物の情報を集めようと考えたのだった。
だがこれはなかなかに難事だった。もともと歴史や骨董には造詣がない籐伍である。骨董屋に聴取するにも勘所がわからなかった。
そうした状況を嘲笑うように、このひと月の間にも鬼没盗は出来していたのだった。
聖徳太子の遺物を追う籐伍と、鬼変薬の研究を追う綿津見。どちらも一朝一夕には探索が前に進まない状況が続いていた。
そんなとき、不意に渦彦から籐伍の元に連絡があった。渦彦は大坂に戻ってからも隠居所にいるようだった。その御隠居が籐伍に会いたいといっているという。囮一座が解散してから籐伍も御隠居には会っていなかった。
久々に隠居所を訪れた籐伍は、御隠居に無沙汰の挨拶と大和でのことを話そうとした。
その籐伍に向かって御隠居は手をあげて話を止めた。
「大体のとこは渦彦から聞きました。誠に難儀な宿命が世にはあるもんやと、つくづくと思いましたわ。そのことはお互いに胸にしまいまひょう。今はこのこと、秘するが華やと存じます。今日は別の話で籐伍様には来てもらいました」
前置きをした御隠居は、籐伍の隣に座る渦彦に向かって語りはじめた。
「渦彦は鬼没盗に邂逅したときに一緒やった清兵衛のことお覚えてるか」
御隠居の突然の言葉に、渦彦は少し戸惑った。渦彦を閻魔の市に送り込んだのが御隠居であることを、籐伍には語っていなかった。
籐伍も誰からも聞いてはいないが、もしかしたらそうかもしれないという想像は持っていた。
「閻魔の市のことはもう気にせんでもええで。隠居所を鬼没盗の囮に提供するときに、お奉行様とは色々と手打ちしたからな。それであのとき眠らされた清兵衛やが、この前面白い話を持ってきたんや」
御隠居は二人に清兵衛の面白い物語を話し始めた。
「あの男も鬼没盗にはえらい頭に来たみたいでな、あれ以来執念深こうに調べ始めたみたいなんや。まぁわてが鬼没盗の囮に協力したいうこともあるやろうが、あいつもなかなかにしつこい性格やからな。しかもお役人の籐伍様の視点とは違いう調べ方やったみたいや」
籐伍は「違う視点」という御隠居の言葉に少し訝しんだ。籐伍の不審げな表情に御隠居は満足そうだった。
「清兵衛は商人でお役人様とは違うから、見える風景もまた違ういうことですわ。清兵衛はもし自分が鬼没盗を組織したなら、どう移動して逃走するかの方法にまず目が行ったようや」
移動や逃走の方法という意味が、二人にはよくわからなかった。
「盗人働きをした後に、どうやって現場から逃れてるんかいうことですわ」
御隠居は謎解きを楽しんでいるように微笑んでいた。
「清兵衛はまず、鬼没盗が出来した夜の月を調べたらしい。もちろん明るい夜より暗い夜の方がええに決まってるが、やはり鬼没盗が出来したんは新月から三日月までの闇夜やったらしい。二人が初めて新町で出会おうたときも二日月やったはずや」
御隠居の言葉に、籐伍は木津川の土手道で初めて対決したときのことを思い出した。籐伍の突き技八艘を渦彦が躱し、逆に渦彦の掌底を小太刀の柄で打ち返した夜である。二人はそれ以来の縁となって、今日まで共に歩んでいるといってよかった。
「まあ闇夜やいうんは予想がつくが、清兵衛にはもう一つ気になることがあったんや。それはあいつの下り酒(上方から江戸へ送られる酒)の商いにも関係するんやが、その闇夜に出帆する船があるいう噂を聞きつけてたらしい。普通なら下り酒は灘郷や西宮からこの大坂天保山に船で運ばれ、そして天保山の港で北前船に積み替えられて江戸に向かうんや。それは早朝か昼間に行われるんが普通や。風待ちなんかでよっぽどのことがない限りな。ところが不思議なことに、鬼没盗が出来した夜に限って闇夜の中で天保山を出入りする船があるいう噂があったんや。慣れた航路とはいえ、これは滅多にないことやで」
籐伍と渦彦は御隠居の話に釘付けになっていた。
「そこで清兵衛はもしかしたら鬼没盗は船で移動してるんとちゃうかと思い至ったらしい。確かに渦彦が新町に出た賊を見失のうたんは木津川の傍やし、この隠居所から大川もまた近い。いやそんなことより大坂中に運河やら堀や川が網の目のように通ってるわ。これだけ籐伍様や奉行所が懸命に探してもその足跡がわからんのは、陸地やのうて川か海を逃げ道にしてるからやないかと考えたんや」
籐伍と渦彦はゴクリと唾を飲み込んだ。それはありうることである。確かに今までいかに陸上の道を塞いでも、それでもこぼれ落ちる賊がいた。何より古瀬稀人を隠居所より取り逃しているのだ。
「もしそうなら、これはなかなかに捕らえることは難しゅうなるで。この大坂中の水主から廻船屋、末は船頭までみんな調べなあかん。清兵衛も流石にここで諦めかけたんやが、実はその先があった」
御隠居は二人の反応を楽しむようににやりと笑うと一呼吸おいた。そして徐に銀の煙管を取り出すと、ゆっくりとその先に煙草を詰めていった。
御隠居の様子に焦れた渦彦が、「それで、その先とは何ですか」と御隠居が望む反応をした。籐伍は「渦彦は御隠居の思うようにされてるなぁ」と可笑しくなった。御隠居は焦れた様子を楽しんでいるのだと感じた。
籐伍も御隠居の楽しみを壊さぬように話の先を求めた。
「清兵衛殿は船に別の目星を持ってたいうことですか」
御隠居は籐伍の方をちらっと見て「さすがやなぁ」という顔をした。
「まぁあんまり焦らしても悪いさかいな、教えたるわ。清兵衛は天保山を闇夜に出入りする船に、不思議な紋所があることを聞きつけてたんや。そう、こんな紋や」
御隠居は二人の前に、懐から見知らぬ紋が書かれた紙を差し出した。
それは不思議な紋所だった。十六菊花紋の真ん中に「太」という字があしらわれている紋である。十六菊花紋というのは本来京の天朝の紋所である。だがその菊花紋の中心部分には「太」の文字が重ねられていた。
この時代、紋所は重要な印である。武家、公家を問わず、商家でさえも紋を使う。そしてその紋は身分証明にもなっているのだった。
籐伍は武士の一般教養としても奉行所役人の業務知識としても、多くの紋所を承知していた。だがこの紋所は知らなかった。
しばらく籐伍が御隠居の示した紋を見ながら唸っていると、横の渦彦がハッと何かに気がついたように籐伍の持つ紙を手にした。
「わい、この紋所知ってるわ。いっぺん見たことがある気がします。確か京にいてるときに天神宮の御用で太秦へ行ったとき……」
紙を天に掲げると、記憶の断片を蘇らせたように断定した。
「これ太秦の広隆寺はんの紋とちゃいますか。同じ紋が提灯にあった覚えがあります」
そういった渦彦に、御隠居が「ほぉ」という驚いた顔をした。まさかこの紋所を知っているとは想像していなかったようである。
「渦彦は凄いなあ。この紋を知ってるとは。わても方々に聞き合わせしてやっとわかった紋やいうのに。やっぱり鬼没盗と渦彦はどっかで縁が繋がってるんやな」
御隠居は不思議な感嘆の仕方で渦彦の解答を褒めた。だが今度は籐伍の方が渦彦の答えに異論を持ち出した。
「ちょっと待ってください。それがほんまやとしても、何で広隆寺はんの紋所が船にあるんですか。京のお寺はんが下り酒商うてるなんて聞いたこともありまへん。しかも闇夜の危ないときに商い船を運行させるやなんて」
籐伍は心に浮かんだ疑問を次々に口に出していった。御隠居は籐伍の言葉に少しほっとしたような顔をした。本来はこうした疑問が溢れてくることを期待していたのだ。
「籐伍様のいう通りですわ。そやけど広隆寺の紋があるんは別の意味からかもしれまへんで。わてら商家の家紋やのうて広隆寺はんの紋があったら、船手奉行なんかの調べはありまへんよって」
御隠居の言葉に籐伍は反論できなかった。確かに寺社奉行支配のものには町奉行も船手奉行も手が出せない。それは籐伍自身が嫌というほど経験したことだった。
鬼没盗がその船に乗っているという確かな証拠でもない限り、船の検閲も乗り込みもできないのだ。鬼没盗が移動や逃走にこの船を使ったなら、まず手出しはできないだろう。
これは盲点だった。幕府の制度を実に巧妙に利用した方法である。
しばらく考え込んでいた籐伍は、まだ残る疑問を口にした。
「しかし偽紋ならばともかく、広隆寺が鬼没盗に協力してるとも思えまへん。それに実際に闇夜に船を運行するんは水主や船頭です。その人たちをどうやって集めるんですか。盗人の仲間集めるんとは訳が違います。皆真っ当な生活をしてる船乗りたちや」
籐伍の最後の疑問に、御隠居は満足そうに頷いていた。
「さすがに籐伍様は世の中がよう見えてはるわ。確かに全部籐伍様のいわはる通りや。真っ当でない者が扱える船なんかありまへん。そんなんは芝居か物語の中だけの話や。船を使ういうんは、金、人、物といろんなものが係ります。信用や金がないとどれも動かせまへん。そやけど逆にそれがある者が真ん中に立ったら、危ない闇夜でも船を出せるし、広隆寺の紋も使えるかもしれんいうことですわ」
じっと二人の話を聞いていた渦彦が声を出した。
「信用ある者って誰ですか。そんな盗人の手助けするような奴は」
少し怒ったような声だった。御隠居は渦彦を愛おしそうに見た。
「江戸の三井家や」
静かにいった御隠居の言葉に、籐伍は一瞬体が固まった。
江戸の三井家、それは目前にいる御隠居の鴻池家に勝るとも劣らない日本屈指の大商人である。確かに三井家ならば広隆寺の紋を利用することも、危険な闇夜に船を出させることも可能だろう。
その大商家が何故盗賊の手助けをするのか。そこが理解できなかった。
その疑問を理解しているのか、御隠居はあえて別のことを語り始めた。
「何で広隆寺の紋のある船を、三井家が鬼没盗のために動かしてるんかはようわからへん。そやけど三井と広隆寺、そして船を動かしてるらしい木乃嶋衆との関係は少しわかってます」
御隠居の「船を動かしてる木乃嶋衆」という言葉に渦彦が反応した。
「木乃嶋衆って何ですか」
「木乃嶋衆は太秦にある木嶋坐天照御霊神社の氏子衆による水主の組や」
太秦にある広隆寺と木島坐天照御霊神社(通称「蚕ノ社」)は大変近い場所にある寺と神社である。そしてこの寺と神社は同じ時期に同じ一族によって建立されたといわれていた。つまりこの二つは寺と神社の別はあっても、ほぼ同一の存在といってもよかった。
広隆寺は寺伝によると推古一一(六〇三)年に秦河勝によって建立されたとされている。建立当初は蜂岡寺とか秦公寺とも呼ばれていた。それはまだ京に都(平安京)が遷都される二百年も前のことである。それゆえ広隆寺は京で最古の寺とされている。
また木嶋坐天照御霊神社も同じ時期に、やはり河勝と同じ秦氏によって建立された秦氏の氏社である。正確な年号や建立者はわからないが、この頃まだ辺境の地であった山城国の太秦一帯を、秦氏が開墾していたらしい。そのため太秦近くに松尾大社、南には伏見稲荷など秦氏によって建立された神社も多い。
渡来民の秦氏がこの国にもたらしたものとして養蚕と酒造りが有名である。それを示すかのように木嶋坐天照御霊神社は蚕ノ社の名が表すように養蚕の神を祀り、松尾大社は酒造りの神を祀っている。また広隆寺にも寺内社として大酒神社という酒神を祀る社があった。
御隠居は自分の探索成果を自慢するように語り出した。
「実はな、天保山の港を出入りする船の水主が木乃嶋衆かもしれんいうんを嗅ぎつけたんは清兵衛やった。清兵衛の使う水主と闇夜に出入りする船の水主が、昔に一緒の仕事をしたことがあったらしい。それで顔を覚えてたらしいわ。それにその船の水主たちはおもろい紋が入った半被を着てたらしい。それは綺麗な双葉葵の紋やいうことや」
籐伍も渦彦も双葉葵といわれてもピンとこなかった。
「双葉葵はおもろい謂れの紋やが、木嶋坐天照御霊神社や松尾大社の神紋にもなってる。つまり元は秦氏の家紋ということやな。それで双葉葵を背負う船の水主たちが木乃嶋衆やとわかった」
ここまで語った御隠居は、別のこともいいかけたがそれは辞めていた。本筋の話とは関係がないし、一度に多くを語り過ぎると籐伍と渦彦が混乱すると思ったからだ。
御隠居が語ろうとして辞めたのは、将軍家である徳川の家紋「三つ葉葵」との関係だった。徳川家の三つ葉葵の家紋の歴史は浅い。そしてこの三つ葉葵の元になったのが秦氏の家紋「双葉葵」であるという考察があった。
本来三つ葉葵は自然界には存在しない架空の植物だった。現実世界の葵は双葉のみである。徳川の三つ葉葵紋は秦氏の双葉葵紋を変化させて作ったものかもしれなかった。もしかしたら徳川家興隆の陰に、双葉葵の一族がいたかもしれないという憶測があった。
ここから御隠居は独自の探索結果を話し始めた。それはちょっと自慢げだった。
「その木乃嶋衆と江戸の三井が何でつるんでるんかは最初ようわからんかった。単に大枚を叩いた依頼主かも知れへんしな。やが三井が鬼没盗のために大枚叩く理由もようわからへんわ。それに船乗りの誇りは高いんや、金だけで盗人の手助けをするとも思えへん」
そこまでいって、御隠居は喋り疲れたというように前に置いた茶に手を伸ばしていた。確かに御隠居が話を始めてから少し時間が経っていた。かなりの長口舌になっている。
籐伍と渦彦も誘われたように茶を飲んだ。少し沈黙した御隠居は最後の謎解きを始めた。
「実は木乃嶋衆と三井家は裏で繋がってたんや。同じ氏子としてな」
御隠居の言葉に二人は「えっ」と思った。
木嶋坐天照御霊神社は京の太秦の神社だし、三井は江戸の豪商である。その両者が結びつくとは急には思えなかった。
「三井もあれだけの大所帯やからな、江戸だけやのうて京や大坂、あるいは大元の松阪にも店はあるんや。そやけどな、ただ店が近くにあるいう薄い繋がりやあらへんで。三井は京の木嶋坐天照御霊神社自体を江戸の向島に灌頂して、新しい社として「三囲(みめぐり)神社」を作ってるんや。それを三井家の守護社にしてると聞くわ。何せ日本中で木嶋坐天照御霊神社にしかあらへんという三本柱鳥居を三井家内にも祀り、さらにそれを三囲神社にも祀ってると聞いたで。いうたら木嶋坐天照御霊神社と三井は一体になってるんや。木乃嶋衆と三井が深こうに繋がってるんもこれで頷けるで。金のためやのうて同じ氏子の仕事やからな。損得抜きで協力するわ」
籐伍はここで深く考え込んでしまった。
どうやら鬼没盗の後ろには三井家がいるのかもしれない。いや、三井家というよりも木嶋坐天照御霊神社というべきか。確かにそれだと鬼没盗の行動力や資金力も頷ける。盗んだ物を売買しなくても盗賊団を維持する資金はあるのだ。
だがそうなると鬼没盗のことがまたわからなくなってきた。鬼没盗は古瀬稀人が鬼変薬を再現するために作った盗賊団ではないのか。今までどこにも、大和の椎根津の口からも木嶋坐天照御霊神社や三井家の名は出てきていない。自分たちが知らない、もう一段深い謎が鬼没盗にはあるのかもしれなかった。
籐伍が黙って考えていると、御隠居は最後に謎の欠片を投げかけてきた。
「そうや、いい忘れてたけどな、先の広隆寺やがここは聖徳太子を祀る寺やで。広隆寺を作った秦河勝は、太子が摂政時代に最側近の豪族やったらしい。その記憶を留めるために作ったんが広隆寺や。御本尊として聖徳太子像と太子から賜った弥勒菩薩像があるいうことや。つまり広隆寺は聖徳太子の寺なんや。そやから紋所の十六菊花紋に太の字も、太秦の「太」ではのうて太子の「太」を取ったともいわれている。まぁ地名の太秦自体が太子と秦氏を並べたような字面やからな、どこからとっても同じなんかもしれへんけどな。そやけどこれで広隆寺もまた、鬼没盗の狙う聖徳太子と重なってしもうた。まるで聖徳太子が鬼没盗を手助けしてるみたいや。どこまで絡んでくるんやろうな」
御隠居もまた、新たな謎の重なりに困惑しているようだった。
(二)
綿津見と燕による大坂の薬方探索もすでに十日が過ぎていた。だがまだめぼしい成果は上がってはいなかった。
それというのも大坂には、いや同修町に限っても薬種問屋、薬局、あるいは薬の調合者、薬師、研究者は星の数ほどいるのだった。大坂全体では無数にいるといっても嘘ではない。
それは日本各地で採取できる薬種、鉱物、あるいは生薬などが一度全て大坂に集まる流通経路になっているためだった。
漢方の薬種だけではなく、西洋からの蘭方の薬や外国からの文物も長崎経由で大坂に集められた。つまりこの国の薬に関わる全ての物が一度大坂に留まることになるのだ。
そうなれば当然、薬を扱う漢方医も蘭方医も大坂に集まった。ここにいれば研究材料には事欠かないし、また最新の情報もいち早く吸収できた。後の世に緒方洪庵の適塾が大坂にできたのもそうした理由である。江戸は薬の巨大な消費地ではあったが、研究や製造の場ではなかったのだ。
そんな薬と研究の坩堝のような大坂の街を毎日歩き回る綿津見だったが、あまり効率よく探索できたとはいえなかった。疲れを見せ始める綿津見に燕は助言をした。
「綿津見様。うちは薬のことはようわからへんけど、これはまるで大河で砂粒を探すような大変なお仕事やと思います。ここは薬の世界の案内人を立ててみてはどうですか。その方が無駄は少ないと存じます」
綿津見を見かねたように燕が提案した。
「しかし大坂には大和と違い案内してくれる方がいてまへん。大和ならば交流のある薬種商や薬の調合者などもいるのですが」
綿津見の言葉に、燕は大きく首を振った。
「いてるやないですか、あそこに」
そういいながら、道の先に見える鳥居を指さしていた。それは同修町の真ん中にある少彦名神社の鳥居だった。
薬方探索の初日に、綿津見は燕と共に少彦名神社へ挨拶に行っていた。渦彦の身を預かってくれている礼をするためだった。
宮司の阿曽は話し上手ではあったが、薬の知識に関してはあまり無いようだった。それで綿津見は薬方探索の詳しいことは話さずに、挨拶だけで退いたのである。
だが黙って聞いていた燕の見る目は少し違っているようだった。
「阿曽宮司はんはまぁおしゃべりやし、薬の事はようわかってへんみたいやけど、この街の噂話はびっくりするぐらいよう知ってはりりましたわ。つまり、誰が何をしてるか知ってるいうことです。深い内容は理解してへんでも、綿津見様が知りたいこと知ってるんとちゃいますか。それになんといっても顔の広さと信用があります。案内人にはぴったりや」
燕は阿曽宮司をうまく使えば、良い案内人になると見た。逆に薬の知識が乏しい分、綿津見の探索の真意も悟られずに済むと考えていたのだ。
「わかりました、阿曽宮司様にお願いしてみましょう。今は時を無駄にはできままへん」
綿津見は渦彦からの手紙で、阿曽宮司が徳陀子神社の仙薬を欲していることを知っていた。だから前回会ったときにも、話がそちらに行かないように気をつけていたのだった。
だがこの十日間薬方を巡ってみて、綿津見にも心境の変化があった。それは「皆必死で薬開発に前へ進んでいる」という思いだった。薬の世界は驚くほど進化していた。どこかで自分も仙薬を前に進めなければという思いが芽生えていた。
思いを改めた綿津見は、再び少彦名神社に宮司を訪ねた。綿津見は面会した阿曽宮司に、今回来坂した目的を少し修正してだが正直に話した。
「今回大坂に来ましたんは、我が家に伝わる秘薬の改良のためです。ですがあまりに多い大坂の薬業の人々に、訪れるべき人や場所もままなりまへん。ここは大坂の薬に通じてはる宮司様にお導きいただけないかと考え参上いたしました。何卒、ご協力賜りたいのです」
そう述べてから、綿津見は阿曽宮司に手をついて深々と頭を下げた。綿津見の後ろに座る燕も同じ様に頭を下げていた。
綿津見の口上に気を良くしていた阿曽は、まあまあお手を上げくださいという様に綿津見の手をとっていた。そして後ろで頭を下げる燕に対しても、「奥方様も頭をお上げくだされ」と声をかけていた。
前回訪問したときにちゃんと紹介しなかったせいで、阿曽は燕のことを綿津見の妻だと思い込んでいた。綿津見は阿曽の誤解を訂正しようと口を開きかけたが、先に阿曽が早口に喋り始めていた。
「よろしおます。私が綿津見殿の先導役となりまひょ。もともと渦彦殿とのご縁もあることやし、また京の五條天神宮はんとの繋がりもお互いに深い。ここはこの少彦名神社と徳陀子神社も互いに兄弟の契りを結ぼうやおまへんか。それが互いの社の利にもなります。綿津見殿は誠に薬の調合に詳しいし、秘伝の薬もお持ちや。うちにはそれがないが、売り捌く力と周旋の力があります。この二つが協力したら鬼に金棒や」
そう嬉しそうにして、綿津見の手をしっかりと握っていた。
後ろでは燕も、「ありがとうございます」という様に再び頭を下げていた。燕もまた阿曽の誤解を解こうとはしていなかった。
話のまとまった阿曽と綿津見は、互いに必要な情報の提供を話し合った。綿津見は幾種類かの薬種と鉱物を書き出し、これらを扱う薬種問屋とその研究や調合をする薬師の名を求めた。
代わりにという様に阿曽はいくつかの効能を書き出して、それに相応しい秘薬の提供を求めてきた。
お互いにこの場で直ぐに答えることができないので、三日後に再び少彦名神社を訪れることで話がついた。
帰り際に阿曽が燕に、「奥方様も遠路ご苦労でしたな」と大和からの長旅を労ってきた。綿津見はこの機会を逃してはいかんというように、改めて燕を宮司に紹介した。
「こちらは私の妻ではなく、逗留先の阿刀様の御息女、燕殿です。大坂に不案内な私の案内をしていただいております」
阿曽は驚いたような表情をしたが、何かを納得するように頷いていた。
「おお、これは失礼をいたしましたな。しかしそうか、阿刀様の御息女ということは籐伍様のお姉上か。噂は鴻池の御隠居様から伺っておりますぞ。えらい別嬪はんの姉上様の噂。何でも賊とも戦われたいう女丈夫という……、いやこれはまた失礼を」
宮司はそこで言葉を切った。だが改めて二人をしげしげと見て独言した。
「しかし、見れば見るほどええご夫婦に見えはるわ。失礼ついでにいうときますわ。もしこの後、その様なことになられはるんでしたら婚礼の儀はうちでお願いします。徳陀子はんとは兄弟の契りを結んだんや。お安うにしときまっさかいに。阿刀様にもよろしゅうにいうといてください」
阿曽は最後まで商人のようなことをいってきた。綿津見が答えられないでいると、代わりに燕がにこやかに答えた。
「ありがとうございます。その折にはよろしゅうにお願いします。せやけどうちにはお足はあらしまへんで。宮司様のご好意に甘えせていただきとうございます」
そう朗らかに、燕もまた宮司に負けていない返し方をした。
「何をまた、阿刀様といえば西町の諸色方大番役与力様や。ご婚儀の費用なぞ大坂中の商人がこぞって出しますわ。何やったら、その周旋をわてがしてもよろしおます。良き話をお待ちしておりますぞ」
そう笑いながら深々と燕に向かって頭を下げた。燕も宮司に頭を下げると、「さあ参りましょう」と綿津見の手を取って歩き出していた。
しばらく歩き少彦名神社から離れたところで、燕は綿津見に謝った。
「綿津見様、勝手にお答えしてしもうてすみまへん。せやけどあのくらのことは大坂では普通のやり取りです。気にせんでもよろしいですよ。宮司はんも冗談のようにして、少しだけ本音を潜ませてるんです。そこを上手いこと感じなんだら、大坂での交渉事はできまへん。話半分に聞いとくんがちょうどええんです」
そう説明する燕だったが、やはりどこか嬉しそうだった。
三日間は綿津見にとっても丁度よい休息になった。勿論その間に阿曽宮司の求める功能の薬を選別していた。外に出してよい仙薬と、綿津見自身が効能を確認したい仙薬からの選別だった。
これまでは神社での配布を主としていたので、仙薬の功能の確認はあまりできていない。それに服用者の反応も知りたかった。薬の治験をしてみたかったのだ。大坂に来てから綿津見の内側に「科学者の心」が芽生えていた証だった。
再び少彦名神社を訪れた綿津見は、宮司の求める効能の薬をいくつか示した。だがあくまで薬名とその処方、効能だけである。大坂で必要になるとは思っていなかったので、仙薬の見本は持参していなかった。
阿曽宮司も自分の懐から長い巻紙を出して、その巻紙を広げていった。
「ここに先日綿津見殿がいわれた薬種を取り扱う問屋や店、薬局を書いておきました。この先頭に書いてある肥前屋はんはうちからも近いし、一番多くの薬種も取り扱われてはるようです。ここの軒先をお借りになられて薬の見本を作られてはいかがですか。話はもう先方にはしてあリまっさかいに、いつでも行ってくだい」
そう綿津見に提案すると、秘薬名と処方の紙を大事そうに胸に仕舞った。
綿津見も阿曽宮司の示した巻紙に書いてある問屋や薬局の一覧を見て少し驚いていた。わずか三日でよくここまで調べ上げたものだと感心した。話の軽さや薬に関する知識の無さとは逆に、この街の人々のことを実によく心得ていると思った。
少彦名神社から肥前屋に向かう途中、綿津見は燕に対して礼をいった。
「燕殿の見る目の方がやはり正しかったようです。阿曽宮司様は期待以上の答えを出してくだされました。全て燕殿のおかげです」
そこに肥前屋の暖簾が見えるところで、綿津見は深々と燕に頭を下げた。
「うちのおかげやおへん。大坂ならこれくらいは当たり前です。無駄なようなお喋りしながら、ちゃんと相手を観察してはる。そやから綿津見様の知りたいことも知ってはるんです。うちが少しだけそんな大坂のやり方に慣れてるだけや。これがうちの役目やさかい」
そして燕は綿津見の手を取って肥前屋の入り口に向かおうとした。いつの間にか二人は互いの手を取ることに慣れ始めていた。
その日から数日、綿津見は肥前屋に通いつめた。
綿津見は本来の目的を忘れるほどに、肥前屋での見本薬作りを楽しんでいた。そして薬種商や薬師の考える今の時代の「薬」というものの概念を新たに学ぶことにもなった。
綿津見にとって薬とは人に良い効能を足していく「足し算」だった。だが大坂の薬師たちは違っていた。彼らにとって薬は「毒の引き算」だった。
良い効能というものは結局人体に対する「弱い毒」であり、弱い毒性を利用して人の体の悪い箇所を攻撃(あるいは修復)する。だから強い効能のある薬(=強い毒)には、必ず裏側に副作用として負の影響があると認識していた。その負の影響を如何に少なく(引き算)するかが重要なのだ。
この言葉を聞いたときに、綿津見はハッとして鬼変薬のことを思った。肉体強化、鬼化という強烈な効能の裏に、不適合という健康障害がある。つまり弱い毒ではなく、強い毒で人の肉体を強制的に変化させたために、負の影響が大きく出ているのだと思った。
阿曽宮司に渡す仙薬を調合しながら、綿津見は密かに従来の鬼変薬の改良に着手することを心に誓っていた。奇しくもそれは古瀬稀人が考える新たな鬼変薬と同じ方向性だった。綿津見と稀人はここ大坂で同じ目的の薬を作り出そうとし始めていたのだった。
少彦名神社に委託する仙薬の見本を完成した綿津見は、それ持って阿曽宮司の元を訪れた。見本を渡しながら処方について事細かに伝えた。
「これらの薬はそれぞれ十日分、そして十人分を用意しました。ただこの地で調合したので従来通りの効能が出るかどうかはまだわかりまへん。ですから必ず服用される方には服用とその後の変化について記録を採っていただきたいのです。それによっては、少し薬剤の分量の修正が必要になるかもしれまへん。もし服用された方に急変あるときは至急私にお知らせください。これは人の命と健康を守るための大切なことです」
阿曽は綿津見から受け取った薬を、大切に薬箱に仕舞っていった。そして社の奥から神人の藤吉を呼んだ。藤吉にこの薬箱を神社の薬庫に保管するようにいいつけた。
藤吉が去るのを待って、阿曽が綿津見に秘薬改良の進展を尋ねた。
「今の秘薬作りに専心していたので、今日より戴いた名簿を廻る所存です」
答える綿津見に、阿曽は「それはよかった」というように、一枚の紙を差し出してきた。
そこにはある住所と、「華陀庵 大辟辰砂(おおさけしんしゃ)」という名前が書かれていた。綿津見は一瞬「ふざけた名前やなあ」と思った。
「この前お渡しした一覧には入れてへんお方ですが、このお方もお知らせした方がええ思いましてな、今回新たにお渡しします」
「このお方はどういう方ですか」という問いに対して、阿曽は少し悩むような顔をした。
「わてもよう知りまへんのや。ただあの後、何人かの問屋さんに聞いところ最近一番仰山ことの水銀を買われたんがこの方やということです。何でも元は赤穂の漢学者はんやということですが、大坂に来てからは蘭学の方々とも何やらされてるいう話ですわ。何で水銀を買われてるんかはようわかりまへんが、下手な薬局より仰山こと所望してるとか。不思議に思った薬種屋の主人が目的を尋ねたところ、『鬼を作っている』といわはったいう噂が伝わっております。鬼が何を意味してるんかは謎ですが、大坂で一番水銀を使うてるんは間違いないこと。綿津見殿の役に立つかと思いお知らせしました」
宮司の説明に綿津見は慄然とした。水銀は多くの薬に使われる素材の一つだが、毒性が高く大量には使われない。
古代世界において水銀は「不老不死の妙薬」とされ、丹や朱とも呼ばれた。特に支那では煉丹術という「不老不死の薬」作りが盛んだった。支那の陵墓や日本の古墳からも水銀朱が多く出土している。そして綿津見の知る鬼変薬の素材の重要な一つでもあった。
綿津見は改めて渡された紙の名前を凝視した。
華佗庵 大辟辰砂
華佗とは後漢末にいたといわれる医者で、神医とも呼ばれた伝説の名医である。そして辰砂は水銀を精錬する前の赤い鉱物、硫化水銀化合物の名前だった。辰砂の名はこの赤い鉱物の大産地が支那の辰州にあったことに由来する。
この名前の人物が水銀を大量に購うことは不思議ではない。この人物が古瀬稀人と繋がっているのならば、「鬼を作る」という言葉の意味は明白だった。新たな鬼変薬を作っているに違いなかった。
綿津見は少彦名神社を後にすると、急いで阿刀家に戻った。
「至急にこの場所に行きたいのです。本当の探索がやっと始められるかもしれまへん」
息席切る綿津見の言葉に、厨仕事をしていた燕が濡れた手を拭きながら示された紙を見た。だが書かれる住所に見覚えがなかった。
「これどこやろ」
そう呟きながら、傍にやってきた鈴と女中の小春に紙を見せた。
「どっか外れの村かもしれへんなぁ」という鈴の言葉に、燕も頷いていた。市中から離れるとなると、大坂育ちの二人にもわからぬ土地もある。
頭を捻っていた二人のそばで小春が「あっ、あそこかもしれへん」といい出した。
「佃村の方とちゃいますか。ほら埋め立てられた神崎川の河口のあたり」
小春の言葉に、鈴と燕も思いあたる場所があった。
この佃村はある意味有名だった。幕府開闢の時代に家康により江戸湾の小島に集団移住させられ、佃島を名乗ったのだ。後の時代にはそこで名物の佃煮も生まれたのである。
「佃村の方やったらここから少し距離もあるけど、何より川渡しに乗らなあかんなぁ。それやったら今から行くんは少ししんどいかもしれんわ。渡しが終わってるかもしれへん」
燕はそう呟くと鈴と顔を見合わせた。困り顔の燕を察したのか、鈴が綿津見にいった。
「綿津見様、本日は同修町の少彦名神社にも行かれてお疲れでしょう。それに連日のお薬作りでしたからお休みになられたと思います。佃村には明日の朝に行かれるのが上策やと思いますよ。明日ならうちもお供できます、急かば廻れと申しますよって」
嫋やかだが凛とした響きの言葉に、綿津見は自分の少し焦った要求に気がついた。
「鈴殿のいわれる通り明朝向かうのが上策でしょう。我が儘を申しあげすみませぬ」
謝る綿津見に、「今日はお休みになられた方がよろしいです」と燕が手を取って部屋に誘った。
厨から去る二人の後ろ姿に向かって、「燕ちゃん一つ貸しやで」という呟きを鈴が洩らした。隣で聞いていた小春が面白そうに笑った。
(三)
大坂北西部の神崎川河口にある佃村あたりは、川と湿地が入り組んだ場所だった。田はあまりなく、少しの畑と河岸に繋がれた船が目につく普通の漁村である。
三人は村人に阿曽宮司がくれた住所を見せ、華佗庵はどのあたりかを尋ねた。村人は最初よくわからないようだったが、何人目かが「ああ、あの飲兵衛はんか」と思い当たる人物を教えてくれた。
綿津見がどのような人物なのかを尋ねると、皆笑いながら「飲兵衛のど助平や」と妙に意見が一致した。「そんでも素面のときは物知りの先生やな」という別の評も語った。
鈴と燕を見て「気付けなはれや。すぐにおいどぐらい触りにくるで」とも忠告をした。
二人は一瞬顔を顰めたが、すぐに笑って「そしたらあそこ切り落としたるわ」と燕が返していた。
村人の教えてくれた場所に迷いながらも三人はたどり着けた。もう川に接する河岸で、古屋のような家には桟橋があった。川船が直接着けられる家のようだ。
「大辟先生は御在宅でしょうか。お願いの儀があって参りました」
綿津見の大きな声の呼びかけに最初は何の返答もなかった。
綿津見は重ねて声をかけた。
「私は巨勢綿津見と申します。薬の調合を学ぶ者です。大辟先生にぜひご教授願いたく参りました。お顔をお見せ願いたい」
返答はなかったが、少し濁った声でぶっきらぼうな声がした。
「教えるような事は何もないぞ。さっさといね、わしはもういっぺん寝る」
それだけだった。だがここで綿津見に替わって燕が声をかけた。
「大辟先生、失礼とは存じましたが手土産に灘のお酒をお持ちいたしました。せめてこれだけでもお受け取りくださいまへんか。持ち帰るには重うございます。お願い申し上げます」
燕の声に反応するように、どたどたと足音が戸口に近づいてきた。
「灘の酒か、ならば受け取ろう。どこにある」
戸を開けながらしゃがれた声で叫んだ。それが大辟辰砂だった。
ボサボサの髪を後ろで縄に結び着物もヨレヨレだが、不思議に薄汚れた感じがしないのは風呂には入っているらしい。歳は四十絡みに見えたが、意外にもっと年長かもしれなかった。
大辟は前にいる綿津見には目もくれず、周囲を見て酒を探した。
「申し訳ございません。お酒は後ほど村の者がこちらに持ってきてくれることになっております。それまでお話しいただけませんか」
燕が交換条件のようにいった。大辟はボサボサの頭を掻きながら「今ここにないんか。……しゃあない、酒が来るまでやったら話したるわ」と渋々燕の言葉を受け入れた。
「入れ」ともいわなかったが、奥に戻っていったのでそれに続いて三人も家に入って行った。
奥に入って三人は驚いた。家財道具はほぼないのに、あたり一面に堆高く積まれた本の塔が幾つも天に伸びていたのだった。本の塔の間を縫うように進んだ大辟は、開けた場所に敷かれた布団に面倒臭そうに座り込んだ。
「その辺に座れ、じゃが本は崩すなよ。必要な本が何処にあるかわからんようになる」
そういうと今度は鈴と燕をしげしげと眺め、感心したようにいった。
「お主もわしと同じで女に妙な趣味があるようやな。そこは気が合いそうや。双子とまぐわうたことはわしもまだない。どないや、顔は同じでも下の方はまた違うんか」
綿津見は最初何をいわれたのかわからなかったが、大辟が二人を舐めるように見ていたのでその意味をやっと理解した。
「こちらは私がお世話になっている逗留先の御息女です。本日こちらまで案内していただいたのです。疚しい関係ではありません」
綿津見の返答に「何や、つまらんなぁ」と、ぼそっと大辟は呟いた。
「では娘ご、すまんが厨から水を持ってきてくれんか。昨夜飲み過ぎて喉がカラカラや。これでは話もでけん」
鈴と燕は二人で厨に向かった。どちらかが残ることが不安だったのだ。
二人の後ろ姿、尻あたりを見ながら大辟はやっと綿津見に声をかけた。
「ほんで、何が聞きたいんや。わしは薬師やないで、薬のこと聞かれても何もわからへん」
そういいながらボリボリと首筋を掻いた。
「私は今、水銀を使った薬の調合をしております。それで同じように水銀を使われている方々にお話しを伺っているのです。大辟先生は大量の水銀を薬種商から買われたとお聞きしました。それで先生がどのように水銀を使われているのかをお聞きしたいのです。まずどのような薬に使われておるのでしょうか。私の研究する薬の参考のためにも是非お教えください」
質問に大辟は大きな欠伸をしながら、「よう知らん」とだけ答えた。
そこに茶碗に水を入れた鈴が戻ってきた。その茶碗を大辟に渡しながら「厨が少し散らかっていましたので、今妹が片付けております。よろしいですか」と尋ねた。
茶碗の水を一気に飲み干した大辟は、もう一杯というように空の茶碗を突き出した。
「片付けてくれるんは構わへんけど、窓際の瓶には触ったらあかんで。いろいろ危ない薬も入ってるからな」
それだけいうと、綿津見の方に向かった。
「確かにわしは仰山こと水銀を買てるけどな、それで何を作ってるんかはようわからん。わしは漢籍にある通りに作ってるだけや。わしは漢学者やからな、漢籍を解読しながら調合してるんや。薬作りは金のためや。それで稼がんと酒も飲めんし遊郭にもいけへん」
大辟は興味がなさそうに答えた。
「しかし先生は薬種商に『鬼を作っている』といわれたと聞きました。何故そのように答えられたのですか」
綿津見の重ねた質問に少し面倒臭そうにした。
「詰まらんこというてしもうたな。しゃあない、灘の酒のためや答えたるわ。わしが水銀で調合してる薬の作り方を書いてる漢籍に、「鬼身乃剤」というくだりがあったからや。それでなるほどこれは鬼の身体のための薬かと思うた。問屋がひつこうに聞くんで『鬼の薬や』と答えんたんや。鬼を作るとはいうてない気がするけどな」
綿津見はその返答に考え込んだ。嘘をついているようには見えなかった。
「よろしければ先生が読まれた漢籍をお見せくださいませんか。私も多少は漢籍が読めます。薬のことも存じていますので、何の薬かわかると存じます。お願いできませぬか」
綿津見の申し出を大辟は少し考え込んだが、結局それを拒否した。
「あかんというよりも無理やな。その漢籍は依頼人が持って帰ってしもうた。それに……灘の酒ではここまでやで。もっと別の褒美でもないとお主に協力する謂れもないわ」
そして厨に向かって声をあげた。
「灘の酒はいつ来るんや。もうだいぶ経つで」
大辟に対して燕が返事をした。
「村の人に対岸の酒屋にまで買いに行って貰うてるんで、もう少しかと思います。しばらくお待ちください」
燕の声を聞いた大辟は、下卑た表情をして綿津見に秘密の交渉をも持ちかけてきた。
「ええ褒美を思いついたわ。これ融通してくれたらお主の申し出に応えたろうやないか」
大辟の言葉に「褒美とは何ですか」と綿津見が尋ねた。大辟は手招くような素振りをして、綿津見の耳元に顔を寄せた。
「二人とはいわへんから、あの娘のどっちかをわしに貸してくれ。どっちもええ女やで、二人ともおいどが大きいのがええなぁ。そういう女は床の中も激しいよって」
大辟の言葉に、綿津見は二の句が継げなかった。
「わしに水を持ってきた姉の方でええで。妹の方はどうやらお主に惚れてるようやな。そういうんは仕草を見てたら大体わかるからな。どうや、お主にも損はないやろ」
そこまでいったときに、鈴と燕が部屋に戻ってきた。
「厨の片付けを大体終わりました。それでお話は進みましたか」
朗らかな燕の声に、大辟が驚いたことに今の内緒話を始めた。
「今なあ、この男にあんたら姉妹のどっちかを貸してくれというてたとこや。そしたらこの男の聞きたいこと全部教えたるとな。あんたらはどないや、この男の手助けしたいんやろ。別に嫁になれいうんとちゃうで、ようある一夜の伽や」
鈴と燕は驚きを通り越したような表情になった。そのとき、綿津見が怒って立ち上がった。
「その申し出は取り消していただきたい。私は誰かを犠牲にして望みを叶えるつもりはありまへん。お二人に対しても失礼極まりない」
大辟が「固いやっちゃなあ」と呟くと、その言葉に被せるように表から大きな声が響いてきた。
「先生、お客はんからの酒やで。戸口に置いとくさかいな」
ちょっと機先を封じられたように、綿津見がその場に立ち止まっていた。鈴が綿津見を宥めるように、再び座るように促した。その間に燕は表戸へ酒を取りに行った。
怒った顔の綿津見から、鈴は大辟に顔を向けて静かに話しだした。
「先生、女子としては殿方に求められるんはありがたい話やけど、残念なことにうちらはもう売れ先が決まってます。特にうちの許嫁はんはそれは嫉妬深こうて。奉行所の同心様やからもし今の話耳に入ったら、先生のこと科がのうてもしょっぴくかもしれまへんで。そうなったらえらいことやわ。いつ帰れるかもわからへんし、悪うしたらそのままご牢内で……ということもようありますよって」
鈴が少し怖いことを真面目な顔でいった。大辟もギョッとした表情になった。そこに酒徳利を抱えた燕が戻ってきた。酒徳利を大辟の前に置き、そのまま厨に行って盃替わりになりそうな茶碗を持ってきた。
酒徳利と茶碗が大辟と綿津見の間に置かれていた。鈴は二人の茶碗に少しの酒を注ぎ、「まあ、まずはお気持ちを鎮められて」と二人にいった。
「それにうちの妹は気が強いさかい、今まででも何人もの男衆の楽しみを奪ったことか分かりまへん。先程も村の人に先生がうちらのおいど触わるかもといわれたら、そしたらあそこ切り落としたるっていうてましたわ。妹は小太刀が使えるさかい、これまで無いことやおへん。先生もそうなったらもう他の女子も抱けしまへんで」
燕は最初鈴が何の話をしているのかわからなかったが、途中から大辟を脅しているのだと気がついた。それで胸元に刺していた懐剣を鞘ごと抜くと、静かに大辟との間に置いた。そして微笑むように大辟を見つめた。
大辟は置かれた酒に手を伸ばすと、「わかった、わかった。冗談やからもういじめんといてくれ」と音を上げて酒を煽った。そして諦めたように綿津見に変な忠告をしてきた。
「お主、気つけや。この二人のどっちかを嫁にしたら、長生きできんかもしれへんで。床の中で精を吸われて死ぬか、浮気して殺されるかは判らへんけどな」
大辟は飲み干した茶碗を燕に突き出そうとしたが、何を思ったのか鈴の方に変えた。どうやら牢屋よりも切り落とされる方が嫌な様子である。
少し毒気を抜かれた綿津見も冷静さを取り戻した。前に置かれた茶碗を大辟の方に掲げると、そのまま飲み干していった。
「失礼いたしました。私も少し興奮しました」
そして居住まいを糺すと、再び大辟に問い始めた。
「先生が調合に使われている漢籍がここにないことは承知しました。ではそれを持ってきた人物は何というお方ですか。それをお教え願いたい」
綿津見の質問に大辟は少し考え込んだ。
「それはいわん方がええやろ。依頼人との信義もあるが、お主と依頼人との関係も判らん。わしも変ないざこざに巻き込まれるんは迷惑やからな」
そう答える大辟に綿津見は諦めずに更に聞いた。
「では私がいう名前に否応でお答えくださいませぬか。それならば依頼人との信義は守れます」
綿津見の言葉に逡巡していた大辟は、思わず鈴が注いでくれていた茶碗の酒に手を伸ばそうとした。だが鈴がその茶碗の上に手を置いて、柔かな表情で首を振った。暗に「お答えいただいてからです」といっていた。
「依頼人は古瀬稀人という者ではありませんか」
綿津見の言葉に大辟は少しホッとしたような表情で、「違うな」とだけ答えた。そして鈴が蓋をしていた茶碗を持ちあげると、美味そうに飲み干していった。
その答えに綿津見は少し意外な気がした。大辟が嘘を答えている可能性もあったが、先程のホッとした表情は嘘とは思えなかった。
だとしたら、大辟に水銀を使った薬の調合を依頼したのは古瀬稀人ではなく、その目的は鬼変薬の再現ではないのかと思った。
少しの間考え込んでいた綿津見は、別の疑問を感じていた。
いかに漢籍から薬を再現するにしても、なぜ依頼人はこの不真面目な男を選んだのだろうかと思った。漢籍が読める薬の調合者は他にもいるし、漢方学者なら基本漢籍は読める。
「失礼ながら、なぜ依頼人はこの仕事を先生に頼まれたのですか。先生は薬には精通しておられない。漢籍から薬を再現するにしても相応しくないと思われます。何か他の理由がおありかと思えますが」
不躾な言葉に大辟は一瞬顔を顰めたが、すぐに大笑いをし始めていた。
「お主もそう思うか。それが当たり前やで。わしのような飲兵衛の漢学者に頼む仕事ではないわ。しかしなぁ、どうしてもわしではのうてはあかん理由があんのや」
綿津見は思わず「その理由とは何ですか」と尋ねていた。大辟は嬉しそうに「聞きたいか」と答えた。綿津見が頷くと、大辟は置かれた酒徳利を手にとって少しそれを振った。
「酒が少うなったな。もう一瓶都合してくれたら話したるわ。どないや」
色気の次は酒の要求だった。大辟の我が儘な交換条件に、燕がすぐに立ち上がった。
「うちが川向こうまで買いに行ってまいりますわ。それまでお話を続けください。先生の夜伽はできまへんけど、お酒の酌ならできますよって。でもその間に姉に変なことしはったら、ほんまにあそこ切り落としますさかいな。どうぞお気をつけて」
そういい置くと、いそいそと家の外に出ていった。
燕の後ろ姿を見ながら「ええ女なんやがなぁ、情が深すぎるわ。あれでは好いた男も食い殺してまうで」と大辟は呟いた。
同意を求めるように綿津見に「そう思うやろ」と語ってきた。先程の夜伽の要求をもう忘れたような悪気のなさだった。
この大辟という男、本当に酒と女が好きなだけで、悪い人間ではないのかもしれないと綿津見も感じ始めた。
「それで先生やないとあかん理由とは何ですか」
鈴に注いでもらった酒を喉に流し込みながら。大辟は少し誇らしげに逆に聞いてきた。
「お主は漢籍が読めるというたな。ならば蓬莱山東渡伝説を知っておるか」
大辟の口から思いも寄らない言葉が飛び出してきた。
「蓬莱山東渡伝説? ……確か前漢の史書『史記』の中にあった方士徐福の話かと思いますが、それが何か関係あるんですか」
綿津見の返答に大辟は満足したように頷いた。
「知っておるか、ならば話が早いわ。わしはな、元々はその蓬莱山東渡伝説が語る徐福を研究しておったんじゃ。徐福が東の海の果てにある蓬莱山に不老不死の仙薬を求めたという伝説、それを解き明かそうとしておったのよ。まあ簡単にうと、不老不死の仙薬とは何かを特定するために薬の世界にも足を踏み入れたんや。じゃがこれはなかなかに大変で迷路のような研究での、しかも薬の実物を手に入れるには金もかかる。それでこの仕事を請け負うた。ええ金になるんでな。それにこの仕事はわしの研究にも少し絡んでおる。不老不死の仙薬の一つが、漢籍にある水銀を使うた薬かもしれへんと依頼人はいうてきたんじゃ」
徐福が求めた不老不死の仙薬、そんなものがこの世にあるのかと綿津見は思った。
だが鬼変薬ももしかしたら不老不死を実現するための薬の一つなのかもしれないと思った。「人間の肉体能力を極限まで強化する」という点だけを見れば、不老不死への第一歩である。
少し考え込んでいた綿津見に大辟は意外なことをいってきた。
「お主は名を巨勢と名乗ったな。ならばご先祖は大辟と意外に近いかもしれへんで」
この言葉に綿津見はさらに思い悩んだ。
「うちの親族に大辟という家はありまへんが」
少し間の抜けた返答に、大辟は間違いを指摘する教師のようにいった。
「ちゃうわ、もっと大昔の話や。ええか、わしの出は赤穂の坂越の浜にある大避神社というとこや。この大避神社では秦河勝という人物を我が家の祖神として御祭神に祀ってるんや。つまり大辟家は元秦氏やちゅうことや。お主は巨勢やろう、巨勢と秦の共通点は何や」
急に教師のような口調で綿津見に問いかけてきた。
巨勢氏と秦氏の共通点といえば……共に飛鳥時代には聖徳太子の側近の豪族であったことだ。
「わしが何で徐福の求めた仙薬を探してると思う。それはまず一つには先祖の秦氏が徐福の末裔かもしれへんからや。そしてな、我らの先祖が仕えた聖徳太子もまた不老不死の仙薬に因縁が深いんや。この国には各地に徐福来訪伝説があるが、実はその地の多くは古代に秦氏の入植した地でもあるんや。つまり徐福の巡った地は、不老不死の仙薬を探した地であり、また秦氏が開墾した地でもある。京の太秦なんかはその実例やで。広隆寺もその東の木乃嶋神社、西の松尾大社なんか全部秦氏のもんや」
綿津見は籐伍から聞いた、広隆寺と木乃嶋衆の紋所の話を思い出した。
思わぬところで話が繋がってきた。徐福に秦氏、太秦、そして聖徳太子。
「先生がいわれた、聖徳太子もまた不老不死の仙薬に縁があるというのは、どういうことですか。そのような話は流石に聞いたことはありまへんが」
綿津見が確認するように大辟に問うた。
「まぁ普通は知らぬのも無理はない。じゃが太子の伝略の中に『甲斐の黒駒に乗って、一夜にして飛鳥から富士山に舞い降りた』という話が残っておる。富士山近くの寺にはその時を描いた太子の絵もあるらしいわ。考えてもみい、何故飛鳥におった太子が無理をして遥か東国の富士に行ったという伝説が生まれたのかを。しかも富士のある甲斐の馬に乗って。それはそこに不老不死の仙薬があって、太子もまたそれを探しに甲斐へ探索を出したからや。もしかしたら協力者がおったんかもしれへん、それが甲斐の黒駒や。秦河勝の主人であった太子は、当然徐福の求めた不老不死の仙薬の伝説を知っておったはずじゃ。それに……」
大辟はここで少し居住まいを糺した。
「今でこそ富士じゃがな、かつては不二とも不死とも書かれた山やで。徐福の求めた蓬莱山がそこであってもおかしゅうはない。それにこの伝説の大元は支那の神話の中にもあるんや。古代支那の伝説の帝王、三皇五帝の一人である神農が蓬莱山に渡り不老不死の仙薬を作ったという神話がある。神農は薬の神様やからな、昔の支那ではこの神話はよう知られておったらしい。それに蓬莱山に住む神仙とはこの神農の裔やともいわれておった。そやから秦の始皇帝も、徐福の『蓬莱山に不老不死の仙薬を探しに行く』という言葉を疑うことなく信じたんや。船団を用意してやるほどにな」
大辟は楽しそうに、ここまでを一気に語ってきた。きっと世人にはあまり語れない話だけに話すことが楽しいのだろう。それはある種、自分の研究の自慢でもあった。
だがこの話もまた、叔父椎根津が語った「聖徳太子に伝来した薬が鬼変薬の元になった」という内容と符合していた。
綿津見にはいったい何が真実なのかだんだんわからなくなっていた。だが綿津見は本来の目的を思い出し、大辟に確認をした。
「では先生が作られている水銀を使った薬は、徐福や秦氏が探した不老不死の仙薬の一部ということですか。先生の依頼人はあまり相応しくはないが不老不死の仙薬の研究をされている先生に薬の再現を依頼したと。先生も貰った漢籍に基づいて薬を再現しているだけであるというのですね」
綿津見の整理した言葉に、大辟は「まぁおおよそはそういうこっちゃな」とだけ答えた。
手に持っていた茶碗を名残惜しそうに舐めると「ホンマにもうないんか」と鈴に聞いた。
鈴は徳利を逆さにしたが酒は一滴も溢れなかった
「妹が戻るまでもう少しお待ちください」
鈴の言葉に残念そうにした大辟だっが、意外に早くその燕が戻ってきた。
走り戻ってきた燕は、胸に抱いた四合徳利から「先生どうぞ」といいながら大辟の茶碗に新しい酒を注いでいった。
大辟は美味そうに注がれた酒を飲みながら、空いていた右手で燕の尻をさっと触ってきたのだった。それは皆が唖然とする速さと手際だった。
触られた燕自身も最初唖然としていたが、ゆっくりと立ち上がると胸元から懐剣を引き抜いた。その短い刃を勢いよく大辟の前に突き立てた。
「お約束です。先生のあそこ断ち切らせていただきます。お覚悟をされよ」
本気の声音で燕が大辟に宣言した。燕の表情は綿津見がまだ見たことがないような鬼気迫るものだった。綿津見は思わず鈴の顔を見たが、鈴には別に驚いた様子がなかった。それで燕に任せておいて良いのだと理解した。
「すまん、あんまりええ肉付きのおいどやったから、思わず手が出てしもうた。謝るし何でもするさかい、許してくれ。お主からも何かいうてくれ。息子と生き別れしたら、この先何を楽しみにしたらええんかわからへんわ」
大辟は燕の方を見ずに、綿津見に助けを求めてきた。怒った燕を止められるのは、惚れられた綿津見だけだと直感したようだった。
「私にはどうすることもできまへんが、薬の依頼人の名前をお教えいただければ妹殿も納得されるかもしれまへん。いかがですか」
綿津見の言葉に燕が少し頷いた。だがそれには大辟が「それは無理や」と聞こえないほどの音量で首を振った。
「では私にはどうしようもありまへん。妹殿の気が済むようにするしか」
綿津見の突き放した言葉に大辟は代わりの提案をいってきた。
「名前はいえへんが、居てるかもしれん場所なら教えたるわ。わしも普段連絡するときはそこに飛脚を走らすさかい。それなら売ったことにもならんやろ。多分水銀の金を払うてもろうてる薬種屋も知ってる場所や」
「そこはどこですか、大坂市中ですか」
綿津見の当てずっぽうを、大辟はすぐさま否定した。
「ちゃう摂津の西、灘郷の方や。青木の浜から北の金鳥山へ少し登ったところに保久良神社という古社がある。そこの離れ家に依頼人は普段いてるということや。名前は言えんが行けばわかるはずや。これでどないや、もう勘弁してくれ」
大辟の泣きつくような言葉に、綿津見は燕に向かって頷いて見せた。それを見た燕は、ゆっくりと突き刺した懐剣を引き抜くと鞘に戻していった。
「先生、女子には好いたお方になら許せることも、他の男衆にはあかんことがあります。釈迦に説法かもしれまへんけどお気を付けくださいね」
スッキリしたように燕は深々と大辟に頭を下げた。
全身から力が抜けたように大辟は座る布団の上で息をついた。だが手に持った酒の茶碗は放そうとはせずに、それを鈴の方にそっと差し出した。まだ酒を飲むつもりらしかった。
鈴も燕も大辟の筋金入りの酒と女好きの様に呆れるしかなかった。綿津見はそれを見ながら大辟からこれ以上聞けることはなさそうだと思った。
「大辟先生、ありがとうございました。急なる訪問にもかかわらず多くのご教授に感謝いたします。またお騒がせして申し訳ありません。本日はこれにてお暇させていただきます」
綿津見がそう挨拶して立つと、鈴と燕も立ち上がった。
「先生、あんまりオイタが過ぎはったら、ほんまにあそこ切り取る女も出てくるさかいな」
燕が笑いながら忠告した。大辟もまた苦笑しながらも「わかっておる」と頷いていた。
三人が家を出ようとしたとき、何かを思い出した大辟が声をかけてきた。
「そうや、忘れてたわ。お主も水銀を使うた薬を調合しておるといっておったな。どないな薬か知らんが、薬種の組み合わせには気付けることや。わしの読んだ漢籍の中に『組毒』という言葉があった。水銀と何の薬種の組み合わせがあかんのかは書いてなかったが、どうやら頭がやられる毒が生まれるらしい。それを飲んだら人が人やのうなるとあったわ。気つけることや、その情の深い娘が悲しむよってな、わしからの忠告や」
その言葉に綿津見は「承知いたしました。最後までありがとうございます」と答え、三人が同時に大辟に向かって頭を下げていた。
「やはり悪い人間ではないようだ」と三人は同じ感想を抱いた。
大辟の家を出て川渡しまで戻ったとき、綿津見は鈴と燕に謝罪した。
「不快な思いをさせてすみませんでした。しかし成果はありました、お二人のおかげです」
綿津見の言葉を燕が訂正してきた。
「二人やおへん。うちのおいどのおかげや」
綿津見の方に尻を向けると、自慢するように「パンッ」と尻を叩いた。
武家の娘らしくない行動に綿津見は面食らった。
そして大辟が最後にいった「情の深い娘」という言葉が頭をよぎった。確かにそうかもしれないとどこかで納得していた。
(四)
鴻池の御隠居から闇夜に出帆する不審船の話を聞いてから、籐伍と渦彦の二人は幾日も天保山で夜を過ごしていた。対岸の灘や西宮の浜では金蔵と銀蔵も見張り番を続けている。
この二組は闇夜に動く船を探っていたのだった。だがなかなかその成果はあがっていなかった。やはり闇夜に動く船などなかなか見つけられなかったのだ。
ただ灘に出張っていた銀蔵が、ある日の明け方、灘の東にある青木の浜で開かれたばかりの舟屋があることに気が付いた。そしてその舟屋の中に広隆寺の神紋が印された帆布を発見したのである。
そこは普段は閉じられたままの舟屋らしいのだが、その日は船の修繕か船底の貝殻落としの作業をするために開かれたようだった。
偶然に夜の見張りを終えて帰ろうとした銀蔵がその光景に出くわしていた。銀蔵は何食わぬ顔をしながら、開かれた舟屋の中を覗き込んだ。船横に畳まれた帆布の上には黒く染められている広隆寺の紋所、十六菊花紋に太の字があった。
銀蔵が帆布に染められた紋を凝視していると、背後から声が響いた。
「おまえ、どこのもんや。何でここへ入ってるんや」
潮焼けしたいかつい体格の水主が二人、入り口に立ち塞がっていた。
銀蔵は「まずい」と思ったが動揺は表には出さず、何気ない調子で二人に尋ねていた。
「ここは西海屋はんの舟屋とちゃうんか。今日夜明け前に来るようにいわれたんやけど、大坂もんやからこの辺りがようわからんよって。西海屋の紋とちゃうんかと見とったんや」
いかにもなりたての水主が迷っている風を演じたのだった。少し銀蔵を怪しんでいた水主だったが、「西海屋の舟屋はもっと西や。ここはちゃうで」とぶっきらぼうに答えた。
「それはすまなんだな、間違えたわ。そやけどここはどこの舟屋なん? 作りも立派やし、この紋もよう知らんわ」
銀蔵は間違えた振りを好機とばかりに、この舟屋の持ち主を聞いてみた。
水主二人は顔を見合わせて少し躊躇したが、「越後屋や」とだけ答えた。
「越後屋って……あの江戸の大店の?」
銀蔵はわざとらしく驚いてみせた。越後屋は三井家の屋号である。
「へぇー、やっぱり立派な舟屋のはずや。西海屋はんのはもっとしょぼいとこやろ。間違うてすまなんだな、ほならそっちへ行くわ」
銀蔵が舟屋から立ち去ろうとしたとき、水主が声をかけてきた。
「おまえ、名前は何や。今度西海屋のもんに聞くさかい」
「わいは銀蔵や。渦彦の紹介で入ったていうてくれたらわかるやろ」
そうあっさり答えると、「ほなな」といって歩き出した。しばらく行くと銀蔵は後ろを振り返った。二人の水主はもう銀蔵に興味がなくなったのか、舟屋に入ろうとしていた。
だが銀蔵は二人の背に、「双葉葵」の紋があることを確認していた。木乃嶋衆の神紋である。銀蔵は「ここが当たりやな」と少しほくそ笑んだ。
急いで大坂に戻り籐伍に伝えねばと思った。それに清兵衛の西海屋にも伝えておく必要があるだろう。問い合わせられ、怪しまれたら舟屋の発見が台無しになってしまう。拠点を移されては元も子もなくなるからだ。
朝焼けの中、銀蔵は意気揚々と大坂の籐伍の元に急いだのだった。
銀蔵からの報告を受け、籐伍はいよいよ次の新月の夜に鬼没盗を一網打尽にする策略を渦彦や恭一郎、河原崎と相談したのだった。
捕縛策は捕り方を二手に分け、鬼没盗が出来する確率の高い新月前後の夜に天保山と青木の浜で盗賊仕事を終えた鬼没盗を待ち伏せるのである。
天保山側はあくまで追い出し役、到着する青木の浜で船ごと捕える策だった。天保山側で全員の捕縛を試みる手もあるが、万が一船を逃した場合に追えなくなる。ここは獣の猟と同じく、巣に追い込んでから仕留める方が上策だと考えたのだった。
しかし問題が二つあった。それはまず青木の浜の管轄権である。
本来西宮から西の地域は元々尼崎藩の領地である。大坂奉行所に捕縛の権はなかったのだ。ただ西宮や灘五郷の酒作りが盛んになったことで、少し前から状況が変わっていた。
西宮から灘五郷に至る浜から内陸一里ほどまでにある村々は幕府に公収されて天領扱いになっていた。大坂城代の支配が及ぶように制度が変わっていたのである。そうなるとそこの司法権を大坂奉行所が代行することも可能になる。直接的ではないが大坂城代の許可があれば奉行所による捕縛も可能になるのだった。大坂城代と奉行所との政治的合意が必要だった。
青木の浜での捕縛は、大坂城代、大坂奉行所の睨み合い状態の地で行われることになるのだ。籐伍はここにおいても鬼没盗はうまく幕府の管轄の盲点を突いていると感じた。
籐伍は全体の捕縛策を立案すると、その捕縛処方を吟味方筆頭与力の丹羽に上申したのだった。籐伍の上申書を読んだ丹羽は渋い顔になった。無理難題が多過ぎたからである。
「兎に角お奉行に相談申し上げるさかい、少し待っとれ」
丹羽は少しといったが、そこから結局三日ほど吟味方と奉行の協議にはかかった。そしてやっと出た結論は計画の一部修正だった。
当初の計画では天保山での追出し役を河原崎の同心衆に担当させ、籐伍は青木の浜での捕縛に臨む予定だった。それが変更させられた。
籐伍が天保山での追出し組の指揮を取り、青木の浜での捕縛組の指揮は父の念十郎が取るように奉行から申し渡されたのだ。それに加えて大坂城代との交渉役も父念十郎が担当することになった。
確かに籐伍ではまだ政治的交渉は無理だった。それに比べ念十郎は経済政策を長年執行していただけに、大坂城代にも大きく顔が効いた。念十郎の経済政策の恩恵を受けているからである。交渉相手が念十郎となると大凡のことは拒否できなかった。奉行と丹羽の慧眼というべきだった。
だがこの人事変更でも解決できない問題があった。それは綿津見が掴んできた鬼変薬製造の黒幕らしい人物の居所である。
青木の浜から北の金鳥山に登った保久良神社。
青木の浜の至近ということは鬼没盗の黒幕に間違いないように思えたし、もしかしたら鬼没盗の本拠地が保久良神社にあるのかもしれなかった。しかしその場所が問題だった。完全に尼崎藩領内になってしまい、保久良神社に関しては交渉の余地もなかった。
だが黒幕や本拠地を放って置く訳にはいかなかった。もし古瀬稀人と鬼没盗一味を全員捕縛できたとしても、この黒幕が再び鬼没盗を組織するかもしれないのだ。
悩む籐伍たちに、隅で話を聞いていた綿津見が静かに手を挙げていた。
「私が参ります。私は奉行所の人間ではないし、この話を掴んできたのも私です。私が行くのが筋と思います。私はその黒幕にどうしても聞きたいことがあるのです。これは他人には任せられない、巨勢の棟梁の役目です」
渦彦が「わいが兄上と共に保久良神社に行きます」と発言した。皆は渦彦を見ながらそれが良いのかもしれないと思った。だがそれに対しては綿津見自身が反対をした。
「それはあかんで。渦彦には古瀬稀人と決着をつけるいう役目がある。これは叔父上から託された命や。そやから温羅の蹴速を学んだんやろ。私は巨勢の棟梁としての役目を果たすさかい、渦彦は蹴速術継承者の責を果たさなあかんで。私は一人で参ります。ご心配されるな、私も蹴速術を使えるのです。普通の相手になら負けまへん」
皆を安心させるように明るくいった。
「この話は少し待っていただきたい。父上の意見を聞いて決めたいと思いますよって」
籐伍は一時保留を申し出た。青木方面の指揮者は念十郎である。籐伍の判断に皆が頷いていた。
その翌夜念十郎は綿津見と何かを語り合った後、籐伍に結論を告げた。
「保久良神社には綿津見殿に行ってもらうことにしよう。ただお体のこともあるさかいな、手前の西宮までは燕と鈴を同行させる。ほんで神社には金蔵に一緒に行ってもらおうと思う。いざというときに私の元へ走るためにな。お前の手勢が減るがかまわへんか」
父の言葉に籐伍は深く頷いていた。金蔵は天保山で籐伍の配下に入る予定だった。
こうして鬼没盗との最後の決着つける布陣が決まったのだった。
天保山の追出し組には籐伍と渦彦、河原崎や同心、小者衆。
一方、青木の浜の捕縛組には、父念十郎と恭一郎の同心衆、先乗りとして越後屋の舟屋を見張るために銀蔵が青木に先発した。
そして保久良神社には綿津見と金蔵が向かうことになった。
これを鬼没盗との最後の捕縛にすべく、全ての準備がなされた。
その夜はすでに三日月まで月が満ちていた。籐伍の追出し組が新月前夜から始めた張り込みも四夜目になろうとしていた。
もう夏が終わったような涼しい風が天保山の埠頭を渡っている。昼間はまだ蒸し暑い日が続いていたのだが、夜には変わって秋が忍び寄っていた。
天保山の埠頭にはあまり建物がなかった。
少し離れると荷積み倉庫が沢山あるのだが埠頭には何もない。籐伍たちが隠れる場所がないのだ。埠頭横には船手番所があるが、人が集まると警戒されてしまう可能性がある。
結局それを解決してくれたのは清兵衛の西海屋の荷船だった。天保山に停泊する西海屋の荷船を提供してもらい、その船に潜むことにしたのである。交代の同心や小者は少し離れた荷積み倉庫に控えていた。
夜も更けた頃、空の三日月が雲に隠れようとしていた。もともと少ない月の光がなくなり、辺りを闇が支配するようになっていった。
そのとき、沖から一艘の帆船が港に入ってきた。埠頭の突端には常夜灯があるとはいえ、闇夜に入港するのはかなり危険がある。
荷掛けの帆布の隙間から外を警戒していた籐伍と渦彦は、入港してきた船に注目した。多分燐船で同じように警戒にあっっている河原崎たち同心衆も気づいているはずだった。
張り込みをしている籐伍らが音を立てずに凝視する中、入港してきた船は静かに天保山の岸壁に接岸していったのだった。
静かに、そして手早く船中から黒い影絵の水主が現れ、言葉を一切発せずに接岸作業を開始していた。船から綱を岸壁に投げ、そこに降り立った別の水主は黙ったまま綱を岸壁の杭に舫っていった。
この光景を凝視していた渦彦が少し焦れたのか動こうとした。
その動きを隣の籐伍が腕を強く掴んで制止した。まだ動くべき刻ではないと示した。
渦彦も分かっていたが、頭よりも体が動き出そうとしていたのだった。
そのまま、影絵の水主たちが船を岸壁に固定し終えると、再びあたりを夜の静寂が支配していった。まんじりともせずに籐伍たちは荷船の中で刻を待っていた。
やがて天保山に至る安治川の上流方向から一艘の三十石船が港に入ってきた。京の伏見から大坂の八軒家までの物流や人流のために淀川や大川でよく使われている川船である。
その三十石船が静かに天保山の桟橋に入っていった。しばらくするともう一隻、三十石船が桟橋に入ってきた。三十石船ぐらいの小舟だと海面から高い天保山の岸壁には直接接岸できないので桟橋に船を着けるのである。この二隻は普通の荷や人を運ぶ船とは少し異なり、屋根が設えられた屋形船になっていた。
天保山の安治川に面した場所の桟橋と、大坂湾に面した岸壁に接岸した帆船との間には少し距離があった。この距離こそが今夜の舞台だと感じた。
鬼没盗は市中を三十石船で移動し、天保山で帆船に乗り移って大坂湾外の海に脱出する。人目につかずまた奉行所の取締りの網にも掛からない絶妙の方法だと籐伍は思った。
ただ天保山での乗り換えの機を除いてである。それが今だった。
籐伍は目を凝らしながら、船から人が降りて来るのを待っていた。
だが桟橋についた三十石船からは人が降りてこない。少し経つが人の動きがなかった。
「何ぞ警戒してるんか」
籐伍も次第に焦れながら待っていると、夜空の雲が少し切れてきた。全くなかった光がわずかに戻り、三日月の光が天保山の埠頭を僅かながら照らし出していた。
僅かな光の下に、屋形船から降り立った人々の影が映されていた。前の三十石船から四人、後ろの三十石船からも四人の影が見えた。
合計八人、思ったよりも多人数である。
こちらはこの荷船に籐伍と渦彦に小者一人の三人、隣の荷船にも河原崎と同心一人、それに小者の三人である。まずはこの六人で屋形船を降りてきた八人の帆船への乗船を阻止する必要があった。
河原崎が合図の呼び笛を吹けば、近い荷積み倉庫に控えている加勢の捕り方が天保山の港から内陸への出入口を塞ぎ、同時に荷船に隠れる六人の加勢に入ることになっていた。
それに天保山の捕り方はあくまで追い出し役である。一人でも多く捕縛するに越したことはないが、全員を捕らえる必要はなかった。帆船に逃した賊は青木の浜で念十郎の捕縛組が捕らえるのだ。
だが籐伍と渦彦はただ一人、古瀬稀人だけはここで捕縛したいと考えていた。他の者は青木の念十郎に任せてもよい。二人にとって師である椎根津の死の原因である稀人だけは逃したくはなかった。
船から降りた人影の五人が、帆船とのちょうど中間地点に差し掛かった。
そのときを待っていた様に籐伍は被っていた帆布を素早く静かに除けると、荷船から飛び降りて天保山の岸壁に着地した。そして腰に差していた鈍い銀色の十手を引き抜いていた。
ここまでの籐伍の動きは実に素早かった。だがそれよりも早かったのが渦彦だった。
籐伍が体勢を整えて走り出そうとしたとき、渦彦は前を走っていた。
まるで黒い稲妻が地を疾っている様に見えた。屋形船から降りた影法師は渦彦の接近にまだ気がついていなかった。速く、それ以上に静かな疾走だったのだ。
だが渦彦が影法師に到達する前に、闇を切り開くような鋭い笛の音が鳴り響いていた。隣船から降りた河原崎が鳴らした呼び笛の音だった。笛の音が天保山に響いていた。
その笛が事態を急変させた。影法師は急接近する渦彦に気がついた。そして瞬時に五つの影法師が扇型に広がると、渦彦への迎撃態勢をとっていた。それは光に突進する虫を捕らえようとする蜘蛛の巣の様にも見えた。
後を追う籐伍は一瞬「あっ」と思った。相手の動きが驚くほど早く、また統制が取れていた。鴻池の隠居所で捕えた賊とは何かが違って見えた。
「よく訓練された賊だ」
籐伍が思ったときには、渦彦の姿を包む様に扇が閉じていった。
渦彦の体が瞬間、宙を舞った様に見えた。
それは宙を舞ったのではなく、前面にいた影法師を足技で一撃した後、影法師を踏み台にして宙を駆け登っていたのだった。
渦彦は宙空の一点で体を旋回させると、右側にいた影法師の頭部を旋回する左足が薙いでいった。
籐伍は渦彦が薙いだ左足で影法師の頭部が消失した様に見えた。
だが影法師の頭部は消失してはいなかった。いや寧ろ反撃に蹴り上げた影法師の足が、渦彦の薙いだ左足を受け止めていたのだった。
それは渦彦と同種の技だと直感できた。
「影法師も蹴速術を使っている」
そう思った籐伍は、あの影法師が古瀬稀人なのかと思った。
だがその思いはすぐに掻き消されていた。
渦彦が最初に一撃したはずの影法師が、今度は地の底から伸び上がる様な上への蹴りを空の渦彦に向かって放ったのだった。蹴速術の基本蹴りの一つ、昇龍脚である。
「あの影法師も蹴速の蹴りを使っている」
いや下からだけではなく、左側の影法師もまた、渦彦に向かって蜻蛉を切る様に逆回転しながら上方から蹴り下げてきたのだった。
三方からの攻撃に一瞬止まった渦彦は、下から蹴り上げられた昇龍脚の足裏に右足を逆に当てて踏み台にした。そして横に大きく体をひねりながら逃れていった。
五つの影法師から少し離れた地に着地した渦彦は、そこで腰を深く沈ませながら影法師の出方を待ったのだった。蛙の構えである。
渦彦も驚愕の事実に気がついていた。影法師五人は皆が蹴速術を使えるのだということを。
「渦彦、前に出過ぎるんやない。加勢が来るまで皆で囲むんや」
叫ぶ籐伍が渦彦のすぐ後ろに到達していた。その後ろからは更に河原崎らの三人が距離を詰めようしていた。
まずは数的有利を作ってから一人ずつ捕縛する。それが最初の計画である。そうすれば数的有利を維持しながらも、荷積み倉庫から駆け着ける加勢の捕り方とも合流できるのだ。
渦彦と籐伍は並んで五人の影法師に対峙した。お互いがしばし沈黙の中で睨み合う格好になった。その間に河原崎たちは横に回り込み、影法師と岸壁の帆船との間に入った。上手い位置取りだった。
これで帆船に至るにはどちらかの囲みを突破しなければならない。どちらかを抜こうとすれば、もう一方の囲みが背後から捕縛に入れるのだ。
膠着した状態が続くうちに、二人の小者が長刺股を持ってそれぞれの後ろに控えていた。やがて荷積み倉庫の捕り方も加勢にやって来るだろう。
籐伍はこの状態を維持できればこちらの策通りだと思った。
だがそうはならなかった。影法師は互いに何かを示し合わせると、同時にそれぞれが異なった方向に向かって同時に走り出していた。
籐伍はここで判断が遅れた。自分たちの左側を走る抜ける影法師と、右側を迂回して走る影法師、どちらを捕らえるのかを一瞬躊躇してしまった。
「籐伍、右を捕らえ。左はわいが抑える」
渦彦の怒鳴り声に、籐伍も考えるよりも早く足が出ていた。
右側の敵は迂回しながら、後ろに控える刺股を持つ小者を狙っていた。長い獲物の敵から潰すという理に適った攻撃だった。
籐伍が振り向きざまに小者の方に走ろうとしたが、それよりも早く影法師が小者に到着しようとしていた。だが小者とて刺股が使えるのだ。すぐにはやられまいと思った。
定石通りに接近する影法師に刺股を鋭く突き出した小者だったが、その二股に割れた間から影法師の姿が消えていた。いや、消えたのではなく刺股の長柄の上にまで飛んでいたのだった。そして長柄の上をまるで走る様に移動すると、そのまま小者の脳天に蹴り上げた踵を落としていた。
蹴速の技、落月踵だった。
声も上げずに小者はその場に崩れ落ちていった。
籐伍がそこに至ったときには、影法師は小者の向う側に着地していた。そして倒れた小者を挟んで籐伍と対峙したのである。
反対側では渦彦がもう一人の影法師と戦っていた。
左側を走り抜けようとした影法師に、渦彦は低い位置での旋回脚を繰り出していた。それはまるで大地の草を刈り取る大鎌のような軌跡を描いていた。相手を倒すためというよりも逃げる足を狙ったものだった。
影法師が走る足を止めて、少し足を浮かして旋回脚を避けた。だがそれが隙になった。
一瞬留まった影法師に対して、渦彦はその低い位置のままから瞬時に接近すると昇龍脚を放っていた。
影法師はその蹴りを鎧手で防いだが、渦彦は間髪を入れずに第二の昇龍脚を放った。
かろうじて鎧手で横に避けた影法師の体と鎧手の間に生じた隙間に、第三の昇龍脚をねじ込んだ。渦彦の足は影法師の顎を砕いていった。
昇龍三蓮華、回避不能の連続技である。この技を避けるには防ぐのではなく攻撃し返す必要がった。隠居所で稀人が放った昇龍三蓮華を渦彦が落月踵で切り返したように。
「こいつら蹴速術は使えるが、技はあれへんな。それにそれほど強うない」
そう観察した渦彦は、倒れていく影法師ではなく周囲の状況を素早く確認しようとした。
これくらいの強さなら籐伍や河原崎でも足止めはできると感じた。ただそれは古瀬稀人以外の相手ならばではあるが。
二組による囲みが破られたことで、五人の後ろから接近していた三人の影法師が獣のような速さで二組の間を駆け抜けていった。
「あの三人の中に稀人がいる」
渦彦は直感的にそう思った。渦彦は迷うことなく三人の影法師を追った。
一方、籐伍は対峙する影法師を凝視しながら、手に持っていた十手を後ろ腰に差し戻した。そして徐に脇差しの柄に手を添えた。
「こういう手の内がようわからん相手には、不慣れな十手や大太刀やと不覚を取るわ。わいにはやっぱり小太刀の方がええな」
この影法師が本当に蹴速術の使い手ならば、是非とも試してみたい事があった。かつて渦彦と対戦したときに外された八艘である。
籐伍はずっとあの対戰を考えていた。そして八艘で渦彦に勝てる方法はないものかと思案していたのである。意外にもその解決の糸口を与えてくれたのは椎根津だった。大和で猿飛陰流の稽古に参加していたときに、籐伍はその思案を椎根津にぶつけてみた。
椎根津は蹴速術も剣術も使えるので、良い思案があるかもと思った。
椎根津は微笑みながら「ただ相手をよう見ることやな。そしたら『後の先』が取れるさかい。人は攻撃しようとした瞬間に一番隙が見えるんや」とだけ教えた。
最初は何を教えられたのかわからなかったが、言葉を反芻しながら幾度も渦彦との対戦を思い返してみたのだった。
そしてある結論に至ったのである。
「後の先を取るいうんは、結局後出しの石拳(じゃんけん)やな」と思った。要はこちらに勝てると思って出す相手の技にこそ、つけ込む隙があるのだと理解した。
そういえば渦彦との戦いでも、籐伍の刀を封じるために出した渦彦の掌底に、逆に一死を報いることができたのだ。渦彦も読みきれなかった自分の負けだと自嘲していた。
八艘が技として駄目なのではなく、相手の隙に叩き込めない自分が駄目なのだと理解した。
「ではこの相手に椎根津先生の教えを試してみよう」
そう覚悟を決めた籐伍が、ゆっくりと影法師に近づき始めた。その歩みはかつて渦彦と戦ったときと同じように力みのない自然体の歩みだった。
籐伍は口元に微笑みさえ浮かべていた。だが口元とは裏腹に全身の五感が周囲に蜘蛛の糸のような探知の網を張っている。そして影法師が攻撃に出る瞬間を捉えようとしていた。
第六幕 灘のひとつ火、そして……
(一)
渦彦は帆船に向かって逃げる三人の影法師を追った。
影法師は帆船にたどり着くと、最初の一人が舷側に張られている荒縄で編まれた網にしがみついた。その網をよじ登って船に上がっていったのだった。次の影法師もそれに倣い網に取り付くと甲板に登っていった。
最後の影法師が岸壁で立ち止まると渦彦の方を振り向いていた。そしてまるで「こっちへこい」とでもいうように手招きをした。
渦彦は最初手招きが何の意味かわからなかった。だが影法師が自分を誘っているということに気がついた。影法師は古瀬稀人に違いないと思った。
その影法師が突如声を出してきた。
「お前、宗家の者だろう。ならば俺にも好都合だ。ここで決着をつけようではないか。お前にその覚悟があるならだがな」
そう言い捨てるとスルスルと網を掴んで登っていった。渦彦は稀人の言葉にあざけるような笑いが込められているように感じた。
突然の誘いに渦彦に躊躇が生まれ、少しの間立ち止まっていた。
その一瞬の隙を突くように、突如後方上空から蹴り下ろしてくる殺気を感じた。見なくてもそれが天空斬の回転蹴りであることがわかった。
渦彦は無意識の中で上から襲う天空斬に鬼神蹴りを放っていた。
天空斬を仕掛けてきた影法師は、宙空にいる間に鬼神蹴りの餌食になっていた。
「どさっ」という音と共に、影法師の体は大地に叩きつけられた。
影法師が大地に落ちる音で我に帰った渦彦は、籐伍やほかの捕吏のことを思い出した。そして思わず後方を振り返っていた。
その視界の遥か向こうで、信じられない光景が目に入ってきた。
籐伍が影法師の放った落月踵の動きを一歩先取りしていた。落月踵を躱しながらも、八艘の突きが影法師の蹴り上げた脚を貫く姿が見えたのだ。
蹴速の落月踵に対して小太刀の突きで攻撃し返していた。
「あんな返し方があるんか」
思わず渦彦は自分の目を疑った。籐伍が蹴速の蹴り技を打ち破っているのだった。
他の場所でも河原崎が同心と二人がかりで一人の影法師を取り押さえようとしていた。埠頭の入り口からは、松明を手にした加勢の捕り方がこちらに走り寄ってきていた。
「これで五人は捕縛できるやろう」と渦彦はひとまずの成果を確信した。
残るのは帆船に登っていった古瀬稀人を含めた三人である。
そして天保山での捕り物にはもう渦彦の役目はないと思った。
ならば古瀬稀人との決着を着けようと即座に決心した。
「籐伍、わいはどうしても古瀬稀人と決着を着けたい。あとは頼んだで」
そう叫ぶと同時に、帆船に向かって走り出していた。
帆船の前後では、岸壁に結ばれた固定の舫綱を手斧で断ち切ろうとする水主の姿が見えた。
渦彦は岸壁に接岸する船端まで来ると、影法師と同じように荒縄の網に飛びついていた。そして甲板に向かって登り始めた。
八艘で影法師の落月踵を粉砕した籐伍のもとに、加勢の捕り方が殺到してきた。貫かれた足を抱える影法師を捕り押さえようとした。
捕縛を加勢の捕り方に任せた籐伍は、周囲の状況を確認した。
三箇所で個別に捕縛が行われていた。そして帆船への途上に二人の人間が倒れていた。渦彦が昇龍三蓮華と鬼神蹴りで撃ち倒した賊である。
このとき籐伍はさっき聞いた渦彦の声を思い出した。
「あとは頼んだで」という叫びである。そしてその前には「古瀬稀人と決着」という言葉があったように思えた。
「あいつ、残りの賊を追ったんか」と思いながら帆船の方向を見た。そこには暗がりの中で舷側にしがみついている人の姿があった。あれは賊を追って船に乗り込もうとしている渦彦だと察した。
籐伍は一瞬どうすべきかを迷った。
天保山での役目はあくまで鬼没盗の乗る船の追い出しで、青木の浜で待つ父の捕縛の網に追い込む事である。賊の数を削っておく必要はあったが、それも半ば達成できている。
籐伍のもとに河原崎が近寄ってきた。捕縛した賊は加勢の捕り方に任せたようだった。
「こちらは大方策通りに進みましたな。あとは青木の浜で仕上げるだけや」
河原崎のほっとしたような言葉に籐伍が頷きながら尋ねた。
「青木への早馬はもう出たんですか」
籐伍の確認する言葉に河原崎は大きく頷いた。
「私の呼び笛と同時に早馬がここから青木に向かうように手配してますよって、もう遠に出発してますわ。船足がいかに早うても、まだ天保山を出てへん船よりは先に青木に着くでしょう。それでお父上の捕縛組があの帆船を捕らえることになります。鬼没盗騒動も今夜で終りですわ」
河原崎はやれやれというように答えた。
「そうですか」と呟くと、何かをじっと考えていた籐伍は、徐に右手に持つ脇差しの小太刀を鞘に戻した。腰に帯びていた大太刀を鞘ごと引き抜き、それに後ろ腰に差していた十手を抜いて重ねた。その二つを河原崎に手渡すように突き出していた。
籐伍の意図がわからないまま、河原崎は出された大太刀と十手を受け取った。河原崎の不思議そうな顔に向かって、籐伍はゆっくりと礼をいった。
「ここまでこれたんは、河原崎さんのお陰です。恭兄には与力が同心に礼いうたらあかんといわれましたが、今はやっぱり礼をいいたい。ホンマにありがとうございました。そやけど……そやけどもう一人、渦彦のお陰でもあります。そやからわいは、渦彦に礼をいうためにあの船を追いかけます。与力やのうて友達として」
そういってから、もう出航しかけている帆船を指差した。
河原崎は「えっと」思ったが、同時に分かり切った忠告をした。
「あの船に乗り込むお許しは船手奉行からも寺社奉行からも得てまへんで。今籐伍様があれに乗り込むんは法度破りになります。ええんですか、後で処罰もありますよって」
河原崎の言葉に籐伍は頷きながら、微笑みで返していた。
その表情を見た河原崎は、「こりゃ、言うてもあかんな」と止める事を諦めた。子供のような我儘だが、不思議とそんな我儘が嫌ではなかった。
「すんまへんが、後をお願いします」
そういうと、籐伍はもう離岸しようとしている帆船に向かって走りだしていた。そして岸壁に着くと、大きく飛び付くよう帆船に向って跳躍した。
届かないとも思えたが、籐伍の左手はギリギリで網を掴んでいた。そしてしっかりと両手で網を握りしめると、今度は足を網にかけてゆっくりと上に登り始めていた。
その姿を黙って見ていた河原崎は面白そうに笑うと、すぐに元の生真面目な表情に戻っていた。そして近寄ってきた小者に新しい命令を発した。
「天保山で捕まえた賊は全員最寄りの番所にしょっぴくで。それから次の早馬を青木に出す手筈を取ってんか。伝言は『船に乗り込んでる賊は全部で三人、そんで……籐伍様と渦彦もなんでか乗り込んでる』とな。ほんまに難儀なぼんぼんやで。これやから子供の守りは嫌なんや、もう子供の守りは絶対にせえへん積りやったのになぁ」
それだけをいうと、捕縛した賊たちが集められている方向に歩き出した。
天保山の埠頭は、先ほどまでの捕り物騒ぎが嘘のように静けさが戻っていた。岸壁に打ち付ける波の音だけが闇の中に響いていた。
帆船の上甲板に登った渦彦は、その向こうに男が待っているのを見た。
黒ずくめの衣装が影法師のようにも見えていたが、何故か今は頭巾を取っていた。そして渦彦にその顔を堂々と晒していた。
古瀬稀人。渦彦は初めて因果の果てにいる男を目の当たりにした。
甲板の少し広いところで立ち止まった渦彦は声を出した。
「お前が古瀬稀人か。巨勢の全てを奪おうとする鬼神饕餮であり、我が師椎根津叔父の死の元凶」
そう感情を抑えた低い声で罪状を読み上げるように叫んだ。
稀人は面白そうに渦彦を見ながら、やれやれと首を振った。
「私の名を知っているのか。なるほど先生に聞いたようだな。先生を叔父と呼ぶということは宗家の息子か。確か二人いたはずだが」
そういうと少し考え、舳先や艫に集まる水主と鬼没盗の仲間に大声で指示した。
「お前ら、浜に着くまで手を出すなよ。手出ししてもお前らでは歯が立たたん。怪我したくなかったらそこにおれ」
そして渦彦の方に改めて向かうと、まるで親しい年長者が教え諭すように話し出した。
「先生は身内に甘いなぁ、ちゃんと礼儀を教えておらんとは。よいか、俺はお前の兄弟子になる。その俺に対しているのだ、礼を持ってまず名を名乗ってから話をしろ」
稀人の言葉に一瞬気勢が削がれたが、告発の言葉を止めなかった。
「我が名は巨勢渦彦。巨勢宗家の次男であり次の蹴速術継承者や。お前には叔父上の自害の責と、父の死の真相を話してもらう。必要ならばお前をここで討ち取ることも厭わぬ」
渦彦の告発に稀人は少し苦笑しながら、「まあ、落ち着け」というように傍にあった積荷の酒樽に腰をかけた。
「聞いているとまるで大罪人のようないわれようだな。ではその大罪人に幾つか答えてもらおうか。まず先生の死の責とはなんだ。俺は先生と真剣勝負はしたが殺してはおらんぞ。それに巨勢から全てを奪う鬼神饕餮とはどういう意味だ。以前幾らかの薬は貰ったが、全てを奪ったわけではない。お前の言い分の中で意味がわかるのは宗家の死の真相だけだな」
本当に心当たりがないというように、稀人は渦彦を正面に見据えながら少し首を振った。ただこのときの稀人は、渦彦との問答を楽しんでいるようにも見えた。
渦彦は稀人の悪びれた様子がないことに逆に怒りが湧いてきた。
鬼没盗を作って騒動を起こし、巨勢宗家には取り返しのつかない害禍を及ぼしている。だが張本人である稀人にはその自覚がなかった。別の世界の人間と話をしているような気分だった。
渦彦と稀人のあまり噛み合わない問答だったが、そのとき船縁に籐伍が登ってきた。
甲板に新たな人間が登ってきたことに稀人は少し驚いたが、それ以上に渦彦が籐伍の顔を見て吃驚した。籐伍は賊を捕縛しているはずだからだ。
「今日は全く不思議な日だな。役人の待ち伏せに遭ったり、この秘密の船に次々と客人が来るとは。あいつの神通力も今日はまったく効いてはおらぬようだ。……それで次の客人は誰方かな。まずは名乗ってもろうか。この後どう処分するかが決められぬわ」
稀人の薄笑いを含んだ問いかけに籐伍は戸惑った。だが稀人と渦彦を交互に見てその位置関係を確認すると、ちょっと姿勢を正して稀人に向かって声を出した。
「わいは大坂西町奉行所の仮役与力、阿刀籐伍や。今宵、天保山での鬼没盗捕縛の責を負うている。そやけど今はそこの巨勢渦彦の友として来た。渦彦が因果の糸を断ち切る助太刀をするため推参した」
籐伍のまるで歌舞伎の大見得のような口上に、稀人はまた変な奴が来たという表情になった。だが奉行所の与力という点は捨て置けないと思った。
「邪魔が入ったがどうする。さっきの話を続けるか。それともすぐにここで戦ってもよいぞ。俺にとても好都合なんだよ。お前が蹴速術の継承者を名乗るならば、そのお前を下せば俺が継承者になる。椎根津先生の許しを得ずとも我らの間でそれは決しよう」
稀人の言葉に渦彦の感情がついに沸騰した。話の続きのように椎根津の自害を語った。
「叔父上はお前の盗賊働きや父上への仕儀を知り、自らその責を負うて自害された。この世界にあってはならぬ、蹴速を使う古瀬稀人を生み出した責任を取られたんや」
少し涙に詰まっていた。対して稀人の声が急に堅くなった。声から戯けた部分が消えていた。
「それはお前が教えたのか。先生は何も知らないはずだ。俺はずっと先生とは無縁の世界で生きていた。だが……そうか先生は知ってしまったのか。ならば責の大半はお前にあろう。知らなければ先生は死を選ばずに済んだのだ。先生が自害へ歩まれたのならば、それはお前の告げ口のせいだ」
稀人のいう理に渦彦は言葉を失った。叔父に蹴速を使う者が自分達以外にいるのかと問うたばかりに、叔父は自らの罪過を自覚してしまった。それが自害への第一歩となった。
稀人の理は勝手極まりない考え方だが、まったくの的外れとも思えなかた。渦彦の心の中でもこの理はずっと静かに沈殿していたのだった。
言葉を失っている渦彦に代わって、少し離れた場所から籐伍が反論した。
「それはちゃうで。椎根津先生はたとえお前の盗賊働きを知らずとも、ずっと渦彦の父上の死を怪しいでおられた。しかもその死因が蹴速によるものかもしれへんと気づいてたんや。そやから渦彦の父上の死は古瀬稀人の仕業かも知れへんと心を痛めておられた。わいが桜井の道場で稽古してたときにも、椎根津先生はそう懺悔されていた。ただそれをいうと渦彦を苦しめるよって、いわなんだんや。わいに蹴速の存在や巨勢の秘事をあえて明かされたんは、渦彦らがお前に底無しの恨みを抱かんようにするためや。椎根津先生はホンマに誰も恨んではおられなんだ。そやから先生はわいに……わいにお前さえも救うて欲しいと願われて後を託されたんや」
籐伍は堅い表情になっていた稀人に思いをぶつけた。
椎根津は巨勢だけではなく弟子の稀人も救いたいと考えていたのだと。
籐伍の言葉に、稀人と渦彦は打ちひしがれたように体から力が抜けたように見えた。籐伍は重ねて、罪を償うように促そうとした。
だがその言葉を口に出す前に、突如稀人が前に出た。それは渦彦との距離を一瞬で詰めるような思議な気配のない移動だった。
稀人はまるで瞬間移動したように突如渦彦の全面に達した。そして不可解な方向から、渦彦に向かって稲妻のような蹴りが襲っていた。籐伍にはそれがまるで突然もうひとり稀人が出現して、別の稀人が渦彦の背後から襲ったように見えた。
だがそれこそが鬼神蹴りだった。伝説の温羅の蹴速撃ノ壱である。まさに鬼神の名に相応しい予測や回避不能な蹴りだった。その蹴りに渦彦の体が貫かれたと思った。
だが稀人の鬼神蹴りは虚空を貫き、渦彦の姿はその場にはなかった。その光景はかつて籐伍が八艘の突きを外された瞬間と同じように見えた。
「下か」と思って稀人の足元を見たが、渦彦の姿はそこにもなかった。そして同時に稀人の頭上からは竜巻のような蹴り下げが襲ってきていた。
温羅の蹴速撃ノ参、空震弾だった。
稀人を襲った上からの竜巻が甲板上で弾けたと思えたとき、稀人と渦彦が位置を入れ替えたように新たな対峙する場所にいた。
籐伍は竜巻が弾けた場所の甲板が、大きく裂けていることに気がついた。大海の嵐にも耐える甲板が、今の渦彦の攻撃で破壊されているのだった。
「この前よりはできるようになったか。温羅の蹴速も仕入れたようだしな」
不敵な声で稀人が呟いた。
少し離れた場所に移動していた渦彦は片足立ちの姿勢から、右足を大きく後ろに回した構えをとっていた。蹴速術基本の構え、鬼骨の構えである。
時と場所が異なるとはいえ、同じ師に同じ技を習った二人である。相手の技は未来が視えるように予測できていた。
籐伍は今の攻防を見ただけで、とても手が出せないと感じた。
先ほどの天保山で戦った影法師の技とは雲泥の差があった。
影法師の蹴速術には「後の先」も取れたが、今の二人の攻防では正直何が行われていたのかもよく理解できなかった。「後の先」どころの話ではない、籐伍には技そのものが見えていないのだった。
「先生はやっぱり甘い人だ。蹴速を巨勢から奪おうとする俺を救いたいとは。その甘さが結局は先生を滅ぼし、蹴速の真の価値を考えられなかったのだ。千年の禁忌を破れなかった先生の限界よ」
稀人の挑発する言葉に渦彦は反応をしなかった。
少し前から静かで音のない世界にいる感覚が渦彦を支配していた。
激した感情の向こう側に広がっている無音の世界、その中に渦彦は佇んでいた。さっきの稀人の奇襲攻撃にも反応できたのは、この感覚を纏っていたからだった。この無音の世界に進入する存在のわずかな波動が、考える前に渦彦を動かしていた。
反撃の空震弾を使ったことさえも渦彦の意識にはなかった。
そんな状態の渦彦を詰まらないと思ったのか、逆に厄介と感じたのか、稀人が意外な話を始めた。
「お前の父、巨勢宗家の死に際を教えてやろうか。どのように無様に逝ったのかを」
その言葉に渦彦がわずかに反応した。無音の世界から騒めきの世界が蘇っていった。
渦彦の変化を感じ取った稀人は、満足そうに話を続けた。
「俺は宗家に巨勢に伝わる鬼変薬と聖徳太子伝来の宸翰の譲渡を申し入れた。もしそれが受け入れられぬのならば、まずは今の蹴速術継承者である椎根津先生を殺すとな。そしてその後には次の継承者も倒すと。蹴速術の継承者がいなくては鬼変薬も意味がなくなる。そして……宗家は誠に面白い提案を返してきた。自分と戦い勝てばその二つを譲渡しようといったのだ。笑えるだろ、宗家も蹴速術は使えるのだろうが継承者ではない。俺は真の継承者である椎根津先生と互角なのだ。宗家なぞ敵ではない」
渦彦はそのときの父の気持ちを想像した。
かつて兄の綿津見は自分を守るために代わりに鬼変薬を飲んだ。そして父は……敵わぬかもしれぬと思っていても、弟と子供を守る為にこの古瀬稀人に戦いを挑もうとした。二人とも同じように自分の大切な人を守ろうとして命を賭けたのだ。
「まず宗家は俺との間に求めた一つ目の太子の宸翰を置くと、胸元から皮袋を取り出したのさ。そして俺に『これが鬼変薬じゃ』といってその皮袋に入ったものを飲み干し出したわ。俺は黙ってそれを見ていたが、やがて宗家は奇妙な変貌を始めた。そう、鬼の身体にな」
その後の戦いは椎根津とのものとはまた違っていたらしい。渦彦の父は温羅の蹴速を修めてないので鬼神術は使えない。繰り出されてきたのは表の蹴速術だった。だがその一撃、一撃の打撃の力は師である椎根津の使う温羅の蹴速に劣らないものだったらしい。
繰り出される一撃が異常に重く、稀人の骨や筋肉を軋ませた。
そして稀人にとっては大した技ではないはずが、その繰り出す速さと初動から到達までの時間が普通とは違っていた。見切ったはずの技が稀人に次々に当たっていったのだ。
「だが少し経つと宗家の様子が変わっていった。まるで俺が見えていないかのように虚空に攻撃を始めたのさ。俺は構えを解いて暴れる宗家をしばらく見ていた。その間も宗家はまるで幻と戦うように唸り声を上げ、天に向かって咆哮をしていた。その姿は理性を失った狂った鬼そのものだったぞ。そして最後の刻がやってきた。宗家は何かに縋り付くように座り込むと、腰に差していた懐剣を引き抜いて、突如胸元を突いたのさ。その様はまるで鬼変薬の苦しみから逃れるために自決したようにも見えた」
稀人が宗家に近づくと、息絶えたはずの体が突如掴みかかってきた。そしてそのまま懐剣の刃で稀人の胸を貫こうとした。稀人は一撃で息絶えるように、鬼神蹴りで宗家の背骨を叩き折ったという。
「幻に浮かされて俺を襲ったのか、あるいは相討ちを狙って俺を誘ったかはわからぬが、どちらにしても宗家は千年守ってきた仙薬に殺されたのさ。歴史の檻の中で生きた巨勢宗家には相応わしい死に方だな。どうだ、これがお前たち一族の未来の姿だ。俺はそうはならぬために、新しい鬼変薬を作る。そして巨勢そのものを過去の遺物にしてやるつもりだ」
話しながら古瀬稀人は恍惚としていた。自分の描く未来図に酔っているように見えた。
渦彦はそんな稀人を見ながら「この男はやっぱり饕餮だ」と感じた。
今は巨勢の全て喰らおうとしている。そして巨勢を喰らった後は、また別の何かを喰らおうとするのだろう。それはこの男が滅びるまで続く地獄絵図だと思った。
最早父や叔父の死の元凶というだけではない。どこかこの世界にいてはならない存在だと感じた。そのために渦彦はこの男を討とうと決心した。
それはもう単に仇討ちではなく、神話世界の勇者が世界を乱す魔獣を滅するために戦うことを決めたのに近かった。
渦彦が静かに一歩前に進み、稀人と最後の戦いに挑もうとした。
そのとき船の舳先にいた水主が叫んだ。
「ひとつ火が見えるで。灘のひとつ火や」
船上の人々の目が、一斉に暗闇の中に聳える北の六甲山の方向を見た。
そこには小さいがなぜか目を魅きつける赤い灯火が見えた。それは太古より古事記や日本書紀にも語られている海に浮ぶ炎の道標、灘のひとつ火の焔明りだった。
(二)
暗い山道を綿津見は登っていた。少し前を金蔵が静かに歩いている。その歩みは音を消した獣のような歩みだった。金蔵の前身は盗賊と聞いていたが、その頃の技のようだった。
突然、少し先の闇の中に「ぼーっ」とした明りが灯った。それはまるで闇夜を照ら道標のようにも見えた。
気がつくと、さっきまで先を行っていた金蔵の姿が消えていた。
この明りを怪しいと睨んだのか、山道から外れたようだった。綿津見は保久良神社のある金鳥山麓の宿に鈴と燕を残してきて良かったと思った。
一行は三日前に金鳥山麓にある本山村に到着したが、しばらくは休息を取りながら天保山からの鬼没盗出来の知らせを待っていたのだ。だが三日経っても知らせがなかった。
今一番気をつけるべきは相手に気取られることである。そのために天保山で動きがあるまで動くことを控えていた。
だが闇夜といえるのも今夜が最後だった。今夜を逃せば新月はまたひと月先になると思った綿津見は、保久良神社への登拝を決心したのである。そして金蔵と二人で金鳥山を登り始めたのだった。
ゆっくりと山道を登る綿津見だったが、その先の暗闇に突如灯った明りの正体を見た。
それは巨大な石灯籠ともいえるような灯火台だった。神社にあるような綺麗に細工された灯籠ではない。まるで幾つかの自然石を組み合わせて作った祠か磐座に近い荒らしい威容の灯火台である。
巨大な灯火台のすぐそばに人影があった。手に松明のような物を持っているので、この人影が灯火台に火を点けたのだと思った。綿津見はそれでも沈黙したまま山道を登り続け、もうすぐにも煌々と焔が焚かれている灯火台に到着しようとした。
人影はずっと前から綿津見に気が付いていたらしく、南に広がる黒々とした瀬戸の海ではなく綿津見の方を見ているようだった。
「このような闇夜に神参りとは珍しい。まるでこのひとつ火に招かれたみたいですね」
灯火台の焔で綿津見の顔が見えるのか、人影が口を開いた。
人影からは焔に照らされた綿津見の顔がよく見えているのだろう。だが綿津見からは人影がまるで光背を背負った仏像のように逆光になり、その顔はよく見えていなかった。
「ですが闇参りはあまり感心しません。昼は神の庭である社も、闇夜には魍魎たちの宴の場にもなります。夜が明けてからの参拝をお薦めしますよ」
それだけをいうと、人影は灯火台のすぐ横にある巨大な石に腰を降ろした。そしてまだ闇の中にある瀬戸の海を眺めだした。
綿津見は石に座った人影、まだ若そうな男の五間ほどの近くまでくると声をかけた。
「保久良社のお方でしょうか。私も大和で神職をしております。闇参りへのご忠告はかたじけないが、どうしても今夜でなくてはならない理由があって参りました。少しお話をしてもよろしいか」
綿津見の言葉に頷いた男は、綿津見の近くの巨石へ手を差した。座れということらしい。
巨石に座った綿津見は、少し角度が変わったせいで男の顔と服装がよく見えた。最初若いと思った顔は、思った以上に年老いているようにも感じた。灯火台の明りで顔に強い陰影が生じているせいか、どこか底知れない闇を内包しているようにも見えた。
それに服装が少し変だった。
保久良神社の人間ならば神職姿のはずだが、男は不思議な貫頭衣のような衣を着ていた。まるで異国の衣か、古代から蘇った人物のように見えた。
「私はここの社の離れ家にいると聞きく、ある方を尋ねて参りました。ご存知ならば教えていただきたいのです。その方は大坂の漢学者に丹を使う薬を研究させているらしいのです。私も丹を使う薬を学んでおりますゆえ、どうしても会ってお話ししたいのです」
綿津見の静かな声が闇に響いていた。
「なぜ今宵なのですか。昼間の方が良いと思いますが」
まるで彫像か仏像のような陰影深い男の口から声がした。
綿津見はここが切所と感じ、切り込むように鬼没盗のことを言葉にした。
「それは今宵、鬼没盗が出来しているかもしれないからです。私が訪ねる方はその賊と関わりがあるゆえ、今宵でないと会えぬかもしれません」
綿津見の言葉に男は微動だにしなかった。依然黒い瀬戸の海を見ているだけだった。
「それは何よりです、あなたの思いは天に通じたのでしょう。鬼没盗は今宵、大坂に出来しているはずですから。それで、なんといわれる方を訪ねていらっしゃったのですか。それにあなたのお名と用件を聞いてもよろしいか。そうでないと私の答も変わってきます」
陰影の深い彫像が向きを変えた。綿津見を正面から見るように正対した。
「その方の名は残念なことにわかりません。ただこの地を教えていただいた漢学者からは、徐福が古代に求めた不老不死の仙薬に関わる方とだけ聞きました。私の学ぶ水銀を用いた薬とも関係があるとも。私は水銀の仙薬を伝える大和葛城山にある徳陀子神社の宮司、巨勢綿津見と申します」
綿津見はそう名乗ってから、どう出てくるだろうかと緊張した。
ここまでいえば、ここに来た理由は分かるだろう。この男が本当に鬼没盗の首魁か黒幕ならば、逃げるか反撃に来るかもしれないと思った。
長時間の戦いは無理でも、一撃か二撃なら自分にも蹴速術が使えると思っている。知らぬうちに体の筋肉に力が入っていた。
だが、目の前の男は突如笑い出した。そしてにこやかな表情に変わって語りかけてきた。
「そのように身体に力を入れずともよろしいです。それに力が入れば逆に技は出ぬものですよ。なるほど巨勢のお方か。ならば私もあなたにお会いしたかった。同じ徐福の遺産を繋ぐ者として、今日までの永のご苦労にお礼を申し上げたい」
男は立ち上がって、深々と綿津見に向かって頭を下げてきた。
「我が名は徐市といいます。太古に生きた初代徐福の後継者と思っていただいて結構です。ただ今の世ではときに別の名も名乗っておりますが。あなたの訪ねる離れ屋の住人とは多分私でしょう。ただ少し誤解もあります。あなたは私を鬼没盗の仲間と思っておられるようだが、それは違います。私は単に稀人さんの同志として、できる協力をしているだけです。我らはそれぞれに独立した行動と目的を持っていますから」
そう語ると綿津見を繁々と眺め、何かを思い出すように考え込んだ。
「少し前にあなたとよく似た名の少年に逢ったように思います。名は確か……渦彦、巨勢渦彦と聞いた気がします。すみません、何せ膨大な記憶を引き継いでいるので最近のことが少しあやふやで」
徐市と名乗った男の言葉に綿津見は驚いた。渦彦とこの男が出会っているのかと思った。
「渦彦は私の弟です」
綿津見の答えに徐市は嬉しそうに頷いた。
「確かにあなたによく似た男の子でした。なるほど、少し歴史の歯車が動いているのかもしれませんね。稀人さんに出会ってから、様々な人と会えました。私の今生での役目がやっと果たせるのかもしれません」
そのとき、徐市は突如懐から小さな鉛玉を取り出すと、目にも止まらぬ速さで親指に挟んで撃ち出していた。鉛玉は少し離れた雑木林で、何かに当たったように弾かれていった。
「うっ」という押し殺した呻きと供に、雑木林から転げ出る人の姿があった。山道から姿を消していた金蔵だった。
転げ出た金蔵は、獣のような速さで山道を走り降っていった。
「少し前から気になっていたのです。あなたとこの先の話をするにしても、余人に聞かれては不都合な内容もありますので」
ここで徐市は少し堅い表情になって、綿津見に尋ねてきた。
「それであなたの本当の目的は何ですか。私を鬼没盗の仲間として捕らえることか、それとも……私も少し手を染めている丹の仙薬を再現するための意見を交わすことか。それ次第ではこの地を洩らした大辟先生にも仕置きせねばなりません」
綿津見はドキッとした。自分の心中を見透かされていると思った。確かに本来綿津見は鬼没盗の捕縛を目的にして、保久良神社にやってきた。
だがその実、本心では捕縛自体よりも鬼変薬改良への手掛かりが欲しかったのだった。古瀬稀人と共に動いているらしいこの男は、何かその手掛かりを持っていると感じていた。
それは大辟の家を訪れて以来考えていたことだった。だからこの男に会いたかった。阿刀家での寄り合いで保久良神社に行くと申し出たのもその思惑があったからだ。
だが念十郎には何か別の狙いがあるのではないかと問われた。この人の目は騙せないと感じた綿津見は、念十郎には本当の目的を語ったのだった。
静かに話を聞いた念十郎はただ一言、「では行きなされ」とだけいってくれた。後のことは金蔵に上手くさせるので気にするなとも。
「私が今夜ここにきたのは、鬼没盗や古瀬稀人を捕らえるためではありません。いえ……それも私の願いですが、今はそれを弟の渦彦に全て託しています。私の望みはこれ以上巨勢が苦しまぬために、鬼変薬を作り替えることです。あなたはその手掛かりを持っていると思います。私はそれが欲しいのです」
綿津見は振り絞るような思いで自分の気持ちを語った。徐市は顔の表情を変えずにただ少し頷いていた。
「ならば……我らは同志になれます。私の役目は多くの同志を存立して、それらの者を手助けすることですから。ですがだからといって私に何かを返す必要はりません。また私の命に従う必要もありません。我らは互いに独立し自立した存在なのです。それは私と稀人さんの関係と同じです。私と私の一族はそうやってこの国の歴史を紡いできました。ですから、あなたにも私のできることを協力しましょう。それが私の使命ですから」
そこまでいった後に、徐市は突然灯火台の方を指差した。
「あなたはこれをご存知ですか。この篝火は太古より人々の道標として存在している灯火なのです。人々はこれを『灘のひとつ火』と呼んでいます。記紀神話においては、神功皇后の三韓征伐の帰途や、日本武尊命の熊襲征伐から大和への帰路に、瀬戸の海の道標になったと記されています。ですが本当はそれよりも遥か昔、まだこの国に歴史が記される前の時代からひとつ火は存在しました。そしてこの海を、いえ歴史の闇の中を彷徨う人々の標となっていたのです。それは今も同じです。今この時も、稀人さんや木乃嶋衆はこの火を目指して航海していることでしょう。このひとつ火こそ私の役目であり、わが一族の存在理由なのですよ」
徐市が木乃嶋衆と口にしたことで、綿津見ははっと気がついた。豪商三井家や広隆寺、木乃嶋神社を動かしているのはこの男なのかも知れない。同時に、ではこの徐市と名乗る男は一体何者なのだろうかとも思った。
鬼没盗の背後にはこの徐市がいるのだろう。だがそれは黒幕とか影の首領とも少し違って思えた。何かもっと上位にいる存在で、大きな時流自体の画策者。いうならば鬼没盗という歌舞伎役者を使っている興行主のようなような存在だと感じた。
そう思ったときに、綿津見は急に強い畏怖を感じた。そんな男に助言を求めても良いのだろうか。何も要求せず、ただ協力するとこの男はいった。
だが逆にそれにはどこか底知れない怖さがあった。後にもっと大きなものをこの男に差し出さねばならなくなるような怖さである。
綿津見はしばらく沈黙した。この後どうするべきかを考えた。
「迷いがあるようですね。本当はいくらでも考えていただいて構わないのですが、今宵は少し時間がないのかもしれません。こうして灘のひとつ火をずっと灯しているですが、海からの返事がまだありません。どうやら稀人さんの元でも何か異変があったのかもしれませんね。あなたがここに来たのだから、稀人さんの元には渦彦くんが訪れているのでしょうか」
徐市は困った様子でもなく飄々として呟いた。そして綿津見に不思議な話を語りだした。
「今宵はあなたに差し上げるべき土産の用意がありません。代わりにあなたの迷いを解くための伝説をお話しましょう。あなたたち巨勢や鬼変薬の誕生にも関わる伝説です」
徐市は微笑みながら自然な調子で壮大な物語りを始めた。
それは遥かなる太古、まだこの日ノ本に「クニ」というものができる前の時代だという。
ある彷徨える一族が気の遠くなるような時間と道のりを超えて、遥か西方からやってきた。彼らは幾つかの集団に別れ、経路を分けながらも東に東にと歩み、この地に到着したという。
彼らは途中の国々でもその地の王や権力者に協力し、幾度も良き国を作ろうとしたらしい。一族はその時代にそぐわないほどの高い知識と優れた技術、そして「神の理」を持っていたのだった。
だが不思議なことに、それらの国々は一度は繁栄するものの、その後には必ずといってよいほど滅びていった。それは彼ら一族のせいというよりも、その地や時代にそぐわぬほどの高い知識や技術を与えたからかもしれなかった。
人は身に合わぬ高い知識や技術を手に入れると、必ずどこかで暴走した。知識の高さと精神の高さの均衡が取れていないからだ。
不思議なことに彼ら一族はそれぞれの地に自らの王国や国を建てようとはしなかった。それは彼らの持つ「神の理」に反する行為だったからだ。「神の理が支配する神の国は天上にのみ存在する」と信じていた。人々の生活を改善させようとはするが、そこに自らの利益を求めるような国を建てようとはしなかったのだ。
そうした集団の一つが徐福の率いる集団だったという。
彼らは巨大な統一国家を作った秦帝国から、知識や技術の全てを譲渡するように迫まられた。だが秦帝国の推し進める統治は、彼ら一族の持つ「神の理」には反した施策だった。
徐福は秦帝国からの逃亡を考えたが、すでに広大な大陸のほとんどは秦帝国の版図だった。もう逃げるべき場所が大陸にはどこにもなかった。
そんなときに先行して東進していた一族の別の集団から、「蓬莱ノ島」の情報を得たのだった。秦の遥か東の海上にある蓬莱ノ島は穏やかな人々が暮らす地で、食べ物も豊富で争いものないという。蓬莱での争いは大陸から移動してきた人々による争いだけだった。
そして何より重要だったのは、蓬莱ノ島の人々が彼ら一族の「神の理」を理解したような、神と共棲する生き方をしているということだった。
徐福は一族の集団と、彼らと行動を供にする近しい氏族と一緒に、蓬莱ノ島に渡ることを決めた。だが彼の集団も他氏族も合わせれば膨大な人数である。そこで渡海のために徐福は秦の始皇帝を誑かすという驚きの賭けに出たのだった。
これが後の世にいわれた「徐福の蓬莱山東渡伝説」である。
このとき徐福が始皇帝を騙すために使ったのが、彼らの知識にある「不老不死の仙薬」だった。丹を用いた不死の仙薬、ただ始皇帝に示したのは不完全な失敗作だった。他者に再現されることを恐れた徐福は敢えて失敗作を始皇帝に示し、完全なる仙薬を取りに蓬莱山に行くと説得したのだ。
徐福の目論見通り、始皇帝は二度にわたる蓬莱山東渡のための許可と援助をしたのだった。徐福と膨大な人数の一団は無事に蓬莱ノ島に渡ることに成功し、逆に始皇帝は不死の仙薬を手にすることはできなかった。
「徐福と私の先人たちはこの島に至り、そして不二の地に都を作ったといいます。この地に暮らす人々が豊かになる知識は与えましたが、全てではありませんでした。それが後の世の悲劇に繋がるのですが」
徐市の話に魅了されていた綿津見は、思わず「悲劇とは何ですか」と尋ねていた。
灯火台の焔が突然風に揺らめき、徐市の顔の陰影が変化した。綿津見にはそれがまるで徐市が泣いているように見えた。
「徐福の都は不二の大噴火によって火に焼かれ、その全てが失われたのです。彼らの知識も技術も、その神の理さえも。そしてその都の跡も押し寄せる焼け爛れた泥流に飲み込まれてしまいました。徐福とその一団がこの地にもたらした全てのものが、溶岩の下に眠ってしまったのです」
徐市は自分が大災厄に出会った当事者のようにうなだれていた。
不二、つまり富士(山)はこの十万年ほどの間に急速に成長した若い活動的な活火山である。歴史時代に入ってからも、十六回噴火したという記録が史書にある。
「噴火で失われた徐福の知識の一つが、あなた方巨勢に伝わる仙薬であり、鬼変薬なのかもしれません。私は是非にもこの徐福の知識や技を、何よりも神の理を再び復活させたいのです。ですから……稀人さんにもあなたにも等しく協力しようとするのですよ。誰が復活させるかは重要ではありません。復活することが重要なのです」
そこまで一気に語った徐市は少し息をついた。そして綿津見がこの話にどこまでついてこられているかを観察した。
綿津見はこの壮大で久遠な話に魅了されながらも、少し前からなぜか違和感を感じていた。それはどこかこの徐市が、まるで不二の都を失った当事者のように熱く語っていることだった。
彼が本当に徐福の末裔であり、また様々な伝承や記録を持っているとしてもそれはあり得ることだろう。巨勢もそうした意味では同じである。だが綿津見は自分を祭祀する祖神の後継者と考えたことはない。祖神の一族ではあってもそれは遠い時の彼方の話である。
いや、この国に住む多くの古代から続く一族の末裔も同じだろう。稀に大辟辰砂のような一族の出自に興味を持ちそれを探る人物も出てくるが、それあくまで今の時代での個人の思いや興味である。
だがこの徐市は何かが少し違っていた。まるで自分が徐福を知り、あるいは滅びた不二の都に住んでいたように熱く語っている。彼にとって古代とは終わった歴史ではなく、まだ継続している身近な出来事のように思っている証だった。
「徐市殿。一つ伺いたいのだがそれらの知識は書物で学ばれたのですか、それとも一族の口伝で覚えられたのですか。あなたはまるであなた自身が徐福に会ったり、不二の都の住人だったかのように語られている。私はそれをどこか奇異に感じます。まるでそれは……噂に聞く頭を病んだ病人のようです。自分を過去に存在した人物のように思い込んでいる痴れ人です」
綿津見は思い切って徐市に失礼な言葉を使った。だがそこまでいわなければ、本当の答えは返ってこないようにも思えた。この言葉に徐市は怒るのか、それとも……。
徐市は驚いたように綿津見を凝視した。その顔は少し歪んでいるようにも見えた。
だが徐市は怒るでもなく、また一笑に付するわけでもなかった。ただどこか嬉しそうな表情に見えていた。
「綿津見殿でしたか……あなたが優れた観察力と思考の持ち主であることがよくわかりました。実に素晴らしいです。私に対してそのような評価をしたのはあなたが久々です。私は初めてあなたに同志ではなく、友になって頂きたいと思いましたよ。実は同じことを常々私も思っているのです。私は頭の病ではないのかとね」
そう苦笑するように徐市は告白した。だがさらに残念そうに新たな告白を加え始めた。
「あなたはこの国の正史である古事記をご存知ですか。できればその成立の経緯もお知りならありがたいが」
急な問いかけに綿津見は戸惑いながらも頷き、自分の知る古事記編纂の知識を語った。
「確か天武天皇の勅命により、時の大臣藤原不比等が編纂したと学びました。編者は太安麻呂。帝紀、旧辞などの史書に記されている内容を誦習していた稗田阿礼の言葉を、安麻呂が筆録し編集したと」
簡潔な綿津見の返答に徐市は満足そうだった。
「あなたの学ばれた編纂経緯には一箇所間違いがあります。古事記編纂開始当時、すでに帝紀も旧辞も散逸と焼失で存在しませんでした。それは乙巳の変で死した大臣蘇我蝦夷の館と一緒に火災で焼失したと記されている『天皇記』と『国記』が、実のところ阿礼が誦習したという『帝紀』や『旧辞』と同一の書だったからです。阿礼は書物としての帝紀や旧辞を誦習したのではなく、この二書をまだ記憶する人々からその記憶を奪っていったのですよ。そう……私が先代の徐市の記憶を奪ったのと同じようにね」
徐市は思わず自分の顔半分を片手で覆い心の苦痛を隠すようにした。だがそれでも手から溢れる口端は笑っているようにも見えた。
「あなたには信じられないかもしれませんが、私の中には千年以上続く歴代徐市の記憶が積み重なって存在しているのです。徐市になる者はそうやって前の徐市の記憶を全て奪写して新たな徐市となるのです。失われた徐福の遺産のうち僅かに生き残った神の理なのです。他人の記憶を奪い写すこの『奪写の法』は。阿礼は書物としてはすでに失われている内容を、まだ記憶する生きた人間から奪っていった結果が古事記になったのですよ。阿礼にとって人間とは文字通り生きた史書と同じだったのです」
徐市の新たな告白を、綿津見はもう嘘か真かを判断できなくなっていた。
いや最初からこの男の話の真偽など判断できなかった。一番簡単な考え方が「徐市は痴れ人である」という解答だったのだ。
綿津見はどこかで簡この解答に縋ろうとする自分に気がついていた。
(三)
「灘のひとつ火」という水主の叫び声に呼応するように、渦彦と稀人は同時に宙を駆け登るように跳躍した。
互いに一瞬で蛙の構えから宙に至ると、身体を捻ってそれぞれの技を出そうとした。
渦彦は捻り回転させる身体から、まるで鞭が伸びたような旋回脚で、稀人のいた空間を上下に両断するように見えた。
一方の稀人は体を縦方向に回転させながら、大鉈を振り下ろすかのように天空斬の脚を渦彦の旋回脚にぶつけていった。
籐伍には回転する大鎌と振り下ろされた大鉈が、互いに相手の刃を叩き折ろうとしているかのように見えた。
一瞬、宙に火花が飛んだように感じた。
勿論しなやかな肉体同士のぶつかりなので火花はない。火花はないが二人の脚技が絡まるように交わると、互いの衝撃を反動にして大きく二つの影に分離していった。
渦彦の鎌も、稀人の鉈も傷付いてはいなかった。それはあらかじめ二人とも予期していたような攻撃だった。むしろ相手の力量を正確に測るために、互いに攻撃をしかけたようにさえ見えた。
甲板に着地した稀人は、仕方なさそうに呟きを漏らしていた。
「兄弟弟子というのは厄介な代物だな。思った以上に攻撃への入り方や組み立てが似てしまう。俺は無論だが、お前も椎根津先生の教えがその体に染みついているとみえる。それだけ優秀な弟子だったということなのだろう。だが逆にそれが俺には勝てぬ理由にもなる」
稀人の残念そうな呟きに、渦彦も叔父椎根津の言葉を思い出していた。
「お前の知る技は稀人も全て知ると思え」
その通りだと思った。稀人の動きはまるで叔父椎根津に瓜二つだった。自分よりもよっぽど上手く叔父の技を学んでいると感じた。ならばこのまま戦えばいずれ負けてしまうだろう。叔父に勝てなかった自分は、叔父に最も近い稀人にはきっと勝てない。
同時に叔父椎根津が最後にくれた教えが脳裏を掠めた。
それは「一度、蹴速を忘れろ」という謎の言葉だった。
蹴速の技があればこそ、自分は稀人ともこうして戦えている。だがそれを忘れろという。言葉の意味はわからなかったが、どうすれば良いのか考えようとした。だが考える猶予さえもなさそうだった。
稀人はまるで渦彦の全てをもう見切ったというように、ゆっくりと歩み出していた。渦彦がどういう技を出そうとも、もう全てに対応できるという自信があるように見えた。
「次で決着がつく」と二人を見ていた籐伍は感じた。
そして何故か「渦彦が負ける」とも思っていた。籐伍には蹴速術の上下は見分けられないが、武術や戦でいうところの「位攻め」に近いものを感じたのだった。
技や展開の良し悪しではなく、まるで「天意を味方にした方が必ず勝つ」といった感覚である。今は稀人が天の意を背負っているが如く、位の高さがあるように見えた。
だが渦彦が負けて良いはずがないと強烈に思った。籐伍は何か手がないのかと必死に考えた。そして最初に二人がこの船上で戦った場面を思い出していた。あの時渦彦は位負けしていない。二人の動きを籐伍は認識できなかったが、その攻撃は同等だと感じていた。
そう思い至った籐伍は渦彦に叫んでいた。
「最初の動きを思い出せ。あのとき渦彦は稀人と互角やった」
悲痛に響く籐伍の言葉を捉えつつ、渦彦も同じことを感じていた。
最初に出した空震弾は確かに無意識だった。自分が周囲に感じていた静かな無音の世界に侵入してきた何かを、まるで寄ってきた小虫を叩くように空震弾で思わず叩き落としていた。小虫が鬼神蹴りを放った稀人だと分かったのは、少し後の認識である。
「あの瞬間、わいは蹴速を忘れてたんか」
そうとしか思えなかった。鬼神蹴りに対抗しようとしたのではなく、また何か別の蹴速の攻撃を考えたわけでもない。ただただ手元にあった道具で、邪魔に感じた何かを振り払ったに近かった。
あの感覚は何だったのだろうと思った。自分も相手もいない静寂の世界。
そこに紛れ込んだ違和感に対して考える前に反応していた。それが叔父椎根津のいった、蹴速を忘れるということなのだろうか。
「もう一度あれをやるしかない」
目前に迫っている稀人見ながら、渦彦はあの瞬間を再現しようとした。激昂した感情の向こう側に広がっていた静かな世界。
それは激昂したが故に思考が一時停止し、考えることを放棄した瞬間だった。そして全てを研ぎ澄まされた五感に委ね、自分自身を天に解き放ったような世界である。
勝つとか負けるとか、あるいは相手を倒そうと考えたわけではない。ただただこの静寂を守ろうとした感覚だった。
渦彦の周囲に静かなる世界が再び蘇っていった。そして渦彦はこの世界の全てを忘れたように感じた。そんな一瞬、再び小虫が静かな世界を横断しようとしていると感じた。それが次に稀人が放とうとした空震弾であると理解したのは、少し後のことだった。
稀人が渦彦の前面から姿を消していた。
籐伍を含めた船上の全員にそう見えていた。
だが同じ瞬間に、艫から暗い夜空に向かって一発の花火が打ち上げられた。それは火薬が爆発する轟音と、目を眩ませる光を放ちながら天へ飛翔する光体だった。艫にいた水主が放った緊急用の信号弾である。船に何か不測の事態が生じたときに、灘のひとつ火に向けて上げる警戒信号だった。
空震弾の動作に入っていた稀人は一瞬その花火に気を取られた。だが失った何分の一かの注意力を瞬時に補い、稀人は渦彦の頭上に空震弾を落としていった。それは誰から見ても稀人自身にも完璧な空震弾だった。
ただ一人、渦彦の展開した静寂の感覚を除いては。
渦彦は静寂の世界の中に迷い込んできた一匹の小虫を、思わず叩き落とそうとした。叩き落とすために使った道具は打神脚だった。
渦彦にとって温羅の蹴速の中で撃ノ弍・打神脚は最も馴染んでいない技である。馴染んでいないというよりも使い辛い技だった。それはまだ成長過程の肉体を持つ渦彦にとっては、負荷が大きすぎる技だからだ。鬼神蹴りが回転力、空震弾は跳躍力、そして打神脚は静止した状態からの筋肉の瞬発力をその撃破の源泉にしている。打神脚は渦彦に最も備わっていない鬼の筋力を必要としたのだった。
だが、不思議と違和感なく打神脚はその小虫を振り払っていた。それは小虫の羽ばたく道の先が見えていたからだった。
稀人が花火で外らせた何分の一かの気を、渦彦は隙と捉えていたのかもしれなかった。
心が空っぽだった渦彦は、自分の得手不得手とは別の感覚で技を選択した。そして打神脚は渦彦を襲う大気の強烈な渦巻きごと、稀人本体を薙ぎ払っていった。それは些細な要素を無視し、強引で暴力的な力で薙ぎ払う打神脚だからこそできたのかもしれない。
籐伍は一瞬の空白の後に、何かが帆柱に向かって弾け飛んで行くのを感じた。そして視線をそちらに向けると、帆柱に叩きつけられた黒装束の稀人がいた。
「やったのか」と思い渦彦の方を見ると、渦彦もまたその場に崩れ落ちようとしていた。
渦彦の打神脚は稀人の本体を貫いたが、同時に稀人の放っていた空震弾を避けてもいなかった。空震弾が僅かに渦彦を襲ったときに、その隙を狙うように稀人本体を打神脚が襲ったのだ。偶然にも稀人の「後の先」を取ることになった。
無意識の感覚が打神脚を選択したのは、渦彦の身の安全を些細な要素として捨て去った結果だった。その選択が天の理に適っていたのだ。空震弾は避けられない、だが空震弾を放った本体は捕まえられると。それは勝とうとしたのではなく、邪魔な小虫を薙ぎ払うためだけの選択だった。
籐伍は後にこの瞬間を何度も思い返し、ある結論に至った。
「蹴速の技は稀人が優っていた。だがあの瞬間天は渦彦に微笑んだ」と。
崩れ落ちる渦彦に走り寄った籐伍は、抱きかかえるように渦彦の体を支えていた。渦彦の体には力がなく、身体中の筋肉がさざめくように痙攣していた。それが稀人から受けた空震弾の打撃の影響なのか、強引に打神脚を使った反動なのかはわからなかった。
ただ意識は朦朧としながらも失ってはいないようだった。しかし肩辺りが不気味に折れ曲がっている。空震弾で破壊されたのかもしれなかった。
帆柱に踞る稀人のそばに、別の黒装束が走り寄り抱き起こそうとした。支えられながら起きる稀人には意識があるようだった。起きかけた稀人も少しふらつき、壊れた体を確認するように左脚の付け根を押さえている。
もしこのまま稀人が復活すれば、渦彦はもう戦えないし勝てないだろうと思った。渦彦の肉体は依然細かな痙攣を続けていた。
籐伍は自分がやるしかないと心を決めていた。手負いとはいえ稀人に正面からでは勝てないだろう。だがここで勝つ必要はないのだとも考えていた。青木の浜に着くまでの時間を稼げばよいだけだと割り切っている。
籐伍は稀人にではなく、船に乗る水主たちに向かって叫んだ。
「木乃嶋衆の水主たち。お主たちの身元も、この船の主も既に割れてるで。今はこれ以上争うんやない。この海にお前たちの帰る港はもうどこにもないんや。天保山にも、目的の青木の浜にも奉行所の手が回ってる。他の浜につけたところでおんなじや。おとなしゅうに船を青木に着けて裁きを受けんかい。お前らが鬼没盗と関係ないんは奉行所もようわかってる。そやからもうこれ以上争うな」
籐伍の叫びに、船の水主がざわめいた。自分たちの身元や船主、それに目的地まで割れているという驚きである。籐伍の言葉にしばらくの間水主たちは動けなかった。沈黙と逡巡の空気が船上に満ちていった。
籐伍は船を操る水主と鬼没盗の乖離を図ったのだった。水主を味方につければこの場は勝てると思った。
ふらふらとしながら立ち上がった稀人が、船内の動揺した気持ちを抑えるように叫んだ。
「役人のいうことなんぞ信じるな。此奴らは皆同じ盗賊としてお前たちも捕らえ、待っているのは打首だけだ。幕府は自分に逆らう者を決して許さぬ。それはお前ら自身が一番知っていることだろうが。この海の覇者だった木乃嶋衆を陸に押し込めたのはどこの誰だ。それは幕府の始祖、家康だろう。家康の天下取りに力を尽くしたお前たちを、役目が終れば簡単に捨てた。お前たちを救ったのは太秦の一族だけだった。今はその命を守れ。あやつらはこれまでも海のひとつ火として道を示してくれたのだぞ」
そこまで叫ぶと、稀人は喉元を抑えると何かを口から吐き出していた。どす黒く、そして命の滴りのような赤い何か。それは大量の血潮だった。
渦彦の打神脚は肉体の一点を破壊しただけでなく、波動としても肉体全体に衝撃を与えていた。衝撃は稀人の内臓をも傷つけていたのだ。
うずくまろうとする稀人の言葉を打ち消すために、再び籐伍が皆の気持ちを挫くように叫んだ。
「お前たちのひとつ火はもうないで。見てみい、さっきまであったひとつ火はもう消えてる。昔のことは知らんが、今はお上にも情けも道理もある。もうこれ以上争うんやない」
そして灯火が見えていた黒い六甲山の山並みを指さした。そこにはさっきまで輝いていたはずの灘のひとつ火が、すでに消えていたのだった。
動きがとれない稀人は、仲間に支えられながら籐伍と睨み合った。
ただ二人とも今が動くべき時ではないとも考えていた。多分程なく青木の浜に着く、そのときこそが仕掛け時だと思った。
籐伍と稀人の間の緊張を取りなすように、一人の歳老いた水主が二人の間に進み出てきた。
「お二人ともしばし待たれい。この船の上でのこれ以上の争いは船の長であるわいが許さん。ええか、動いてはならんで」
そういうと静かに二人の間に座り込んだ。
「確かにわいらは木乃嶋衆やが、盗賊の仲間やない。それを奉行所が認めてくれるんやったらこれ以上の手出しはせん。ただわいらにはわいらの掟と信義がある。それは守らなあかん。お若い与力殿よ、よろしいか」
籐伍に確認するように、その長はゆっくりと籐伍と渦彦の方を見た。思わず籐伍は「承知した」というように頷いていた。
歳年老いた長が今度は稀人に向かって語りかけ始めた。
「客人殿、わいらは太秦からの指示でこの船を動かしておる。しかしわいらは客人殿の仲間になったわけではない。わいらはあくまで木乃嶋衆として動いておる、そこは間違えたらあかんで。客人殿が何をしようとわいらは口を出さんが、それはわいらにもいえること。わいらが何をしようとも客人殿には無縁や、よろしいか」
そう稀人に念を押すようにいうと、静かに稀人を見詰めていた。
稀人と籐伍の間に張り詰めていた緊張の糸を、この歳老いた長が見事に手繰り寄せそしてその懐の内に仕舞っていった。
その長は若い水主を側に呼ぶと何事かを耳打ちした。長の言葉を聞いた若い水主は一瞬ギョッとした表情になったが、黙って頷くと元いた水主の集団の中に戻っていった。
その行動に何を感じ取ったのか、血を吐く稀人が長に確認するように問い質していた。
「この期に及んで太秦の命に背くとは思わんが、何を企んでいる。今はその役人の始末が先だぞ」
その言葉を口にした稀人が激しく咳き込み新たな血を吐いた。
座り込んだ長は、宥めるようにゆっくりと稀人の方を向いた。
「それは言わずもがなのこと。そやけど青木に着くまでは全てわいらの責や。客人殿もそれまでは黙っててんか。それでも不安があるんやったらわいを盾にしたらええ。それで木乃嶋衆は手を出さん」
そう言った長は腰の懐剣を抜き、それを「どんっ」と自分の前の甲板に置いた。不服ならばこの刃で自分を殺せという意思に見えた。
「もうすぐ青木の浜に着く。それまではこの船での争いはならんで。船の上では長の言葉が法度や。お二人ともそう心得てんか」
そう声高に宣言すると長は目を閉じた。青木の浜に着くまでの、短いが永遠とも思えるジリジリとした時間を、まるで凍結させたように船上の人間の動きを静止させていた。
舳先で海を観測していた水主が、遠くに丸く動く光を見つけた。
それは神紋の船を受け入れるはずの青木の浜からの知らせだった。ただこのときの光は青木の舟屋にいた水主に白状させた恭一郎の手による偽の信号だった。
「長、浜から入港の合図がきましたで。このまま浜に入りますか」
舳先の水主が瞑目する長に叫んできた。長は静かにうなずくと船の全員に号令をした。
「青木に船を着ける。奉行所が待っていようが関係ない。わいらのお役目は無事にこの船を浜に着け、客人殿を送り届けることや。着いた後のことはわいらには無縁や。後は客人殿とそこのお役人に勝手にしてもらおう。お二人それでええな」
長の凛とした声が稀人と籐伍を縛っていた。逆にいえば浜に着く前にどちらかが相手方を制圧しようとしたならば、その時は木乃嶋衆が相手になるという宣言でもある。
沈黙している稀人を長が手招いた。次の状況への行動を考えていた稀人が、ふらつきながら近寄っていった。
「何だ、浜に着くまで動くなとお前がいったばかりだぞ」
呟く稀人に、長は声を潜めて他には聞こえないように囁いた。
「船が桟橋に入ったら仲間の二人を右の船縁に、客人殿はわしを盾にして左の船縁に移動せい。そして右の二人を役人の囮にするために海へ飛び込ませるんや。客人殿はその隙に左側から海へ忍べ。そのまま海中を東に泳いで青木の浜から離れるんや。少し東に行けば西宮の浜や。そこに木乃嶋衆の舟屋があるよって、そこに隠れたらええ。朝までにはあのお方の助けが来るよって。これが赤花火を上げたときの太秦の指示や。ええか仲間を助けようとは思うな。あのお方は客人殿のみを落とせといわれた。今はそれを守るしかない」
手が回ったときの脱出方法が指示されていたことに、稀人は少し驚いた。
「さすが天河はよく先を読んでいる。奴が太秦の力を操れるはずだ」
そう納得したがまだ一つ気になることがあった。折角時間をかけて蹴速術を教え込んだ仲間と木乃嶋衆のことだった。自分は逃げ切れても彼らは奉行所に捕縛されるだろう。
その懸念を問うと、長は苦笑いしながらあっさりと答えた。
「わいらとお仲間は捕縛されよう。しかし今はそれでええんや。後で太秦の力で解き放たれるからの。奉行所の裁きなぞ何ぼでも上から変えられる。太秦ならそれくらいのことはできよう。じゃが賊の首領と目される客人殿はそうはいかん。待っているのは打首だけや。そやから客人殿だけは船から落とせということや。ええな、この事仲間にも他言無用や」
長が怖い顔で稀人に念を押した。稀人は一瞬迷ったがすぐに仕方ないと割り切った。蹴速術の仲間はまた作ればよいと思いを切り替えたのだった。
長の言葉は半分本当だが半分は嘘だった。それは稀人にこの後に変な動きをさせないためだった。
暗闇の海がやがて途切れ、目前に桟橋が近づいてきていた。そこでは二人の男が明かりをゆっくりと回していた。二つの光の円に引き寄せられるように船は桟橋に入っていった。
稀人に指示を受けた鬼没盗の二人は右の舷側から身を乗り出すようにしていた。桟橋に接岸した瞬間に、二人は海に飛び込んで逃走を謀る予定だった。奉行所の捕り方がどこに潜んでいるかは分からないが、夜の海に紛れれば逃げ切れるかもしれなかった。
同じように稀人は、長にもたれかかるようにして左側の舷側に移動した。
長と稀人の姿を籐伍と渦彦は目を凝らし見ていた。渦彦はまだ完全に動くことはできず、籐伍も木乃嶋衆の動きを注意しながらの凝視だった。
長の背後から稀人は懐剣で首筋には刃を当てていた。先ほど長がいったように人質にとっているように見えた。
「接岸するまでは動けへん。そやけどこの船を降りても、もう逃げ場はどこにもないで。これで鬼没盗も古瀬稀人も詰みや」
そう思った籐伍は少し気が抜けたように感じた。これが半年以上追い続けてきた鬼没盗事件の結末なのかと思った。
体の痙攣が治ってきた渦彦も、稀人の姿を喰い入るように見ている。渦彦は「何かある」とどこかで感じていた。それは稀人の体からまだ闘気が失われていないと感じていたからだ。たった一人で念十郎の捕縛組を突破するつもりかもしれないとさえ思えた。
「籐伍、気抜いたらあかんで。あいつは諦めてへん。何かするつもりや」
渦彦の言葉に、籐伍は「あっ」と思った。籐伍にもこのまま終わりを迎えるとは思えない妙な予感がさっきからしていたのだ。何かかがそう感じさせていた。
左側舷側に背をもたらせていた稀人が、思い出したように突如渦彦に向かって叫んだ。
「巨勢渦彦、残念だが今日のところは相打ちにしておいてやる。邪魔なその役人がおらねばとどめを刺していたのだがな。それは次の機会にするとしよう。それまでは力不足だが我が弟弟子に蹴速術継承者の座を預けておく。だが次には必ず鬼神饕餮となって巨勢の全てを喰らってやろう」
渦彦にそう宣言すると、苦しそうに再び咳き込んだ。稀人もまた手負であることがよくわかった。
船がゆっくりと桟橋を擦るように接岸していった。ギシギシという摩擦音をかき消すように、右の舷側から突然人の叫び声がした。
「な、何や。何でや」という声ととともに、「ギヤー」という叫び声も聞こえてきた。
籐伍と渦彦は思わず声のした方向に視線を動かせた。暗闇の中で右の舷側にいた鬼没盗二人が、背後から水主たちに押し囲まれ何かで突き刺されている影絵が見えた。
黒装束に包まれた一人の賊の後ろに二、三人の水主が集まり、手に持つ得物で背後から黒装束を貫いている。同じ光景がすぐ隣にいる鬼没盗にも起こっていた。
二人の絶叫が闇の中かに響いていた。そして二人とも船縁からもんどりうって暗い海に落ちていったのだった。
それは船が接岸するのと同じ瞬間だった。船が停止しするのと同時に、二人の賊が黒い海に落ちていったのだ。
「ギシッギシッ」という接岸の音と、二人の賊が海に落ちる「ドブンッ」という音が重なって聞こえていた。
その光景を唖然として見ていた籐伍は、ハッとして反対側にいる稀人の方を見た。そこでも不思議な光景が繰り広げられていた。
仲間の絶叫に振り向いた稀人の隙を突くように、何かを逆手に持っている長が稀人の下腹部にその逆手に持つ物を突き刺していた。
「うっ」という低い声とともに、稀人は長から少し離れた。そしてフラフラとしながら左の船縁に寄り掛かろうとした。
長の手に光るものが見えた。それは細い金属で先が鋭く尖っている。最初何を持っているのかよく分からなかったが、どうやら千枚通しのような刺突物だった。
その千枚通しで稀人の下腹部を貫いたのだ。下腹を押さえながら船縁にもたれかかる稀人に向かって、長は老人とは思えぬ速度で体当たりをした。
平衡を失った稀人は、そのまま船縁から海へ落ちていった。
こちら側でも稀人が海に落ちる音がしたが、その音は船体に打ち付ける波音に掻き消され、どれが稀人の落水音か聞き分けることができなかった。
長は稀人の落ちていった先を確認するように黒い海面を見た。そして聞こえないほどの声で、「これもまた太秦の命や」とだけ呟いていた。その言葉は籐伍や渦彦には聞こえていなかった。
程なくして青木の浜に接岸した船の上に、念十郎たち捕縛組が乗船してきた。念十郎がそこで見たのは、賊を刺殺した水主たちが座り、前に小太刀を差し出した姿だった。その先頭には船の長が座り、前にはやはり血の着いた千枚通しが置かれていた。
それは天保山で乗ったはずの鬼没盗と古瀬稀人の姿だけが、船上から忽然と消え去った不思議な光景だった。
(四)
徐市の告白物語を聴き終えた綿津見は、結論を出せないでいた。
そんな綿津見を徐市は面白そうに眺めていた。そうした二人の均衡を破るように、夜空に赤い光の花が咲いた。まるで祭の花火のような美しい光輪だった。
「少し話が長くなりすぎたようです。しかし海からの返事がやっと来ました。この赤い花が咲いたということは、あちらでも危急なことがあったようですね。ひとつ火も今宵は用済みのようです」
そういうと徐市は手早く灯火台の焔を消し始めた。大きな焔だったが、徐市は手慣れた作業のように灘のひとつ火の焔を鎮火させていった。
ひとつ火が消えると、あたりは再び闇が支配した。その闇の中に徐市は立っていた。綿津見からは姿がもうはっきりとは視認できなくなっていた。
「では、次にお会いできるときを楽しみにしています。あなたがどこまで私の友に相応しく成長しているのか、早く見たいものです」
闇の中で徐市の立ち去る足音だけがした。
「ザクッ、ザクッ」と鳴る足音が次第に遠ざかっていった。その足音を追うように綿津見は思わず声をかけた。
「あなたはまた鬼没盗を作って、鬼変薬再現を続けるつもりですか」
それは綿津見の心からの叫びに近かった。もうこんな人々や巨勢を苦しめるようなことは辞めて欲しいという願いである。
徐市の足音が止まった。姿は見えないが振り向く気配がした。
「それは私にはわかりません。鬼変薬の再現は稀人さんの夢で、私のではありませんから。もしあの暗闇の海で稀人さんがまだ生きているのなら、それもあるかもしれません。ですが……夢とは儚いものです。だからこそ美しい。私は夢を見ないので、他人の美しい夢を見るのが好きなのです。徐市の役目以上に、これは私個人の嗜好なのでしょうね。以前に先の徐市にも注意されたのですが、持って生まれたものはなかなか治りません。幾百人もの記憶を有しようとも、こればかりは私だけのものです。だから私はあなたの見せてくれる美しい夢を見てみたい。期待していますよ」
その声が止むと、再び足音が遠ざかり始めた。そして足音さえも聞こえなくなった。徐市は闇の中に完全に消え去ったのだった。
綿津見は消えた徐市の後を追おうとはしなかった。いや追えなかった。徐市自身よりも彼の持つ果てしない時の暗闇がどこか怖かったのだ。
綿津見はさっきまで徐市が座っていた灯火台側の巨石にまで行き、そこに座ってみた。そこからは暗黒のような海が見えていた。
果ても底も分からない暗黒の海。徐市はいつもこんな風景を見ているのではないのかとふと感じた。だとしたら標となるひとつ火を求めているのは、本当は徐市自身なのかも知れないと思った。
綿津見はそこで時間が過ぎるのも忘れて暗黒の海を見ていた。やがて山道の方から灯りが登ってきた。灯りは二つあるので二人組のようだった。
顔が確認できるまで灯りが近づくと、それが恭一郎と金蔵だとわかった。恭一郎は巨石に座る綿津見を見つけると駆け寄ってきた。
「綿津見殿ご無事か。不審な人物と遭遇したと金蔵に聴きましたが」
恭一郎は綿津見の無事を確認すると、ほっとしたように蹲み込んだ。
「青木での捕縛はどうなりましたか。鬼没盗は捕縛できたのですか」
綿津見の質問に恭一郎と金蔵は顔を見合わせて少し沈黙した。
「捕縛はできました。まぁあれを捕縛というのならばですが」
恭一郎は青木の状況を語り辛そうにした。ただそれは綿津見も同様だった。この地であったことをすぐには語れなかった。
「渦彦と籐伍もひとまず無事ですから安心してください。ですからすぐにも山を降りて叔父上の手勢に合流しましょう」
恭一郎の言葉に綿津見は少し安堵した。もしかしたら渦彦は古瀬稀人との戦いで倒されているかも知れないと思っていたからだ。
三人は恭一郎の持つ灯りを先導にして山道を降り始めた。少し歩いていると、東の空が薄紫色に染まり始めた。夜明けがもう近いようだった。
どんな暗闇の夜にいても必ず朝が来る。それが世の理である。だが綿津見はあの徐市には朝が来るのだろうかと思った。徐市は今も果てのない暗闇の海を彷徨っているのではないのかと感じた。
綿津見は初めて徐市のことを少し憐れに思った。人の世の理を離れるとは、そういうことなのかも知れないと深く考え込んでしまった。
念十郎は青木での捕縛の顛末について西町奉行に報告をした。
念十郎の報告に加え、天保山での捕縛の報告を同心の河原崎が行った。これらの報告に対して西町奉行も吟味方も大いに喜び、また結果的に鬼没盗殲滅を成し遂げられたことに安堵したのである。
奉行所は捕縛に関わった捕り方に褒美を取らせた。ただ一人、阿刀籐伍を除いては。
籐伍に対しては天保山における途中からの役目放棄と、船への無断乗船の責任が問われた。ただこれは他所に対する西町奉行所の言い訳のような責任追及だったので、処分は最も軽いものになった。
籐伍に下された処分は「三十日間の慎み」だった。当時の謹慎処分で、閉門して昼間の外出を控えるものである。ただ見張りなどは厳しくなく、夜間の外出は概して大目に見られた。
だが「慎み」は「慎み」なので、籐伍は天満橋北の家に閉居して外出は控えていた。そんな状態なので昼間に道頓堀に芝居を見に行くわけにもいかない。結局は戯作を書いたり、過去の芝居台本を読むしかやることがなかった。毎日自分の部屋でゴロゴロとして時間を潰していたのだった。
そんなある日、恭一郎が阿刀家を訪れた。奉行所が出した鬼没盗に対する裁きを知らせるためである。
「天保山と前に隠居所で捕縛した賊は全員、遠島に決まったで。打首いう案もあったが、捕まったったんは皆下っ端やったし、殺しもしてへんからな。それに打首にするには江戸の御老中の裁可もいるさかい色々と面倒いんや。お奉行もそのあたりを嫌うたんやろ。主犯格の賊は死んでもてるしな。これで鬼没盗もこの世から消滅したいうことやな。あと木乃嶋衆と越後屋は結局お構いなしになったで。強迫されてたいうんもあるし、主犯格の賊を殺してるからな。ただ船の長だけはこれまでの責を問われて手鎖五十日の処分になったわ。まぁこの辺りが落とし処ということらしい」
淡々と裁きを語る恭一郎に、籐伍はあまり反応をしなかった。
「そんなものか」という感慨が強かったし、正直鬼没盗に対してはもう怒りがあまりなかった。むしろ渦彦や綿津見がこの裁きを聞いたらどう思うだろうと思った。
そんな籐伍に、恭一郎は小耳に挟んでいた奇妙な噂を話さなかった。
それは木乃嶋衆と越後屋の裁きに対して、江戸の幕閣より口添えがあったという噂だった。幕閣の誰かは不明だが、情状を斟酌せよとの達しがあったらしい。その為にお構いなしになったとは思わないが、恭一郎には全てを長の手鎖に押しつけたようにも見えていた。
籐伍はもう興味なさそうに話題を変えた。
「そやけど、渦彦も燕姉もなかなか大和から帰ってきいへんなぁ。渦彦はいろいろあるから仕方ないけど、燕姉も遅過ぎるわ。このまま成し崩しに綿津見殿のところに嫁入りでもするつもりやろか」
籐伍の愚痴ともいえない呟きに、恭一郎は笑いながら応えた。
「さすがにそれはないやろ。燕ちゃんがほんまにそのつもりやっても、叔父さんがさすがに許さんわ。向うの母上様に筋通す為にもまずは誰か婚姻の使者を立ててるて」
そうはいったが、これは恭一郎にも関わりかねないことだった。
もし思いがけず燕の嫁入り話が進めば、恭一郎と鈴の婚姻にも影響が出るかもしれなかった。
籐伍が慎みの閉居に入る直前に、大坂での目的を終えた綿津見が燕と渦彦と一緒に大和へ帰ったのだった。
綿津見は一度旅した道なので一人で大和へ帰ると主張したが、阿刀家としてはそうはいかなかった。結局、燕が大和まで綿津見を送ることになった。それが念十郎の指示なのか、燕自身の希望だったのかを籐伍はよく知らなかった。渦彦も護衛として二人に同行することになったが、それは渦彦の今後の処遇にも関わることだった。
綿津見が旅立つ前に、巨勢兄弟は今後のことに関してかなり深く相談したらしい。元々は徳陀子神社の御神宝を探す為に渦彦は大坂にきたのだ。その目的がひと段落したとなれば、元の京の五條天神宮に戻って神人修行に復帰するのが道理だった。
だが渦彦は大坂に残って、古瀬稀人の痕跡を探したいと願ったのである。渦彦は奉行所の結論とは異なり、稀人がまだ生きているのではないのかと考えていた。再び鬼変薬再現に動き出すかもしれないと恐れていた。
それは綿津見が保久良神社で出会ったという徐市の話からもそう想像したようだった。
綿津見は大坂に戻ってから徐市との邂逅を語った。皆は一様にその話を信じられなかった。話が突拍子なさすぎたし、聞く人の想像を超えていたからだ。ただ綿津見をよく知る彼らは嘘をついているとは思わなかった。
渦彦が一番気にしたのは、徐市の「稀人が生きていればまたもあるかもしれない」と、「再び会うのを楽しみにしている」という言葉だった。渦彦にはそれが逆襲の予告に聞こえていた。
もし徐市や稀人が再び動くとしたら、それは大坂である可能性が高い。それを阻止する為にも渦彦は大坂残留を望んだのだった。
綿津見は渦彦の願いを聞き入れた。五條天神宮には渦彦の神人修行中断を、少彦名神社には新たに神人修行受け入れを申し入れした。懇意な両社なので希望はすんなりと受け入れられた。こうして渦彦の神人修行は今後少彦名神社で行うことになったのである。
そうした事情を考えれば、暫くは大和に帰郷できない渦彦の帰坂が遅れても仕方ないと籐伍も思った。だが燕もまた帰ってこないのだ。
籐伍は渦彦や綿津見をもう兄弟のように思っているので、何だか自分だけが除け者にされたように感じた。慎みで家を出られない状況が余計にそう思わせていた。
恭一郎が急に思い出したように籐伍を慰めてきた。
「そういうたら叔父さんの隠居願い、今回はあかんようになったんやてな。まぁ家督相続する籐伍が慎みの最中やからな、お奉行も直ぐに隠居を許可するわけにはいかんかったんやろ。それに諸色方からも隠居を待ってもらうようにお奉行へ嘆願が出てたらしいで。何せ叔父さん一人で三人分の仕事してたっていう噂やからな。おいそれとは手放しとうはないわ」
父の隠居願いが先延ばしになったことを、籐伍が残念に思ってはいなかった。むしろ老け込むにはまだ早いと思っている。好きだったという道頓堀の芝居小屋通いはまたしばらくできなくなるだろうが、父にはそのほうが良いのではないかとさえ思った。
籐伍は何もかもが詰まらなそうに、ゴロリと部屋に寝転んでしまった。目には天井の見慣れた杉模様が飛び込んできた。
「前にもこの杉模様、こうして見てたなぁ」と不意に思った。それがいつのことだったのかはすぐには思い出せなかった。
籐伍にとってはこの半年間以上、鬼没盗を追っている時間がとてつもなく濃密に感じ、それ以前の記憶がどこか希薄だった。
「早いこと奉行所に戻りたいなぁ。仕事せえへんのがこないに辛いとは思わなんだわ」
何気ない籐伍の呟きに、恭一郎は驚きと共に成長を感じた。
やる気もなく何もできなかったあの籐伍が、今は奉行所に戻りたがっている。籐伍が大人になっていると思った。
「そないに焦らんでも来月には復帰できる。そしたら今度は寝る間もない位に面倒臭い役目振られるで。皆が投げ出してた鬼没盗殲滅の立て役者やからな、覚悟しとき。それまではゆっくり休むことや」
恭一郎の慰めるような言葉は半分本当だろう。
最初は何にも使えない仮役与力だったが、今回の捕り物で見せた意外な探索の鋭さと行動力を奉行所も放っては置かないだろう。
吟味方の丹羽がいうように慢性的人手不足の奉行所が、籐伍の活用法を真剣に考えても不思議ではなかった。
籐伍はもう半年以上、自分が道頓堀の芝居見物に赴いていないことが不思議だった。以前はあれほど日参していたのに、今はそのことさえも忘れている。芝居を見に行けないことをさほど寂しいとも思っていなかった。
きっと父もこんな気持ちなのかもしれないと漠然と想像した。それは籐伍の大人への成長を感じさせる想像だった。
終幕ノ逸話
鬱蒼とした木々が生茂っている山道を二人の旅人が歩いていた。一人の男がかなり前に先行して歩き、もう一人の同行者は少し足を引きずりながらも遅れまいとしていた。
二人の旅装はかなりの軽装で、ちょっと近くの温泉地に湯治に行くか、宮参りにでも向かうような格好だった。それだけに偶に行き合う旅人にも全く注目はされなかった。
先行していた男が、峠の頂上に到着したようだった。頂上で「やれやれ」というように大きく背伸びをすると、後ろを振り返った。
「やっと国境の峠に着きましたよ。ここからは下り道だから、次の宿場まで何とか陽のある内に着けるでしょう。あなたに合わせていたら随分と時間がかかってしまいました。足の具合はどうですか、まだ痛みますか」
峠に立つ男は、後ろからやってくる同行者を労わるように声をかけた。ただその言い方は労わりよりも、どこか揶揄っているようにも聞こえた。
同行者は返事もせずに、ただ黙って歩みを進めていた。よく見ると同行者は少し怪我をしているようだった。腹に巻かれたサラシからは脇腹あたりに血が滲んでいるのがわかる。さらに左足の付け根あたりを痛めているのか少し抑えているようだった。それでも同行者は弱音を吐くことはなく黙々と歩いていた。
峠で微笑んで待っている男の元に、遅れていた同行者がやっと辿り着いた。少し息が上がっていたが、それでも鋭い視線で男を見据えていた。
いや、今だけではなく山道を歩いている間中、同行者はずっと前を歩いている男を鋭い視線で見ていた。男に少しでも隙があったら、襲い掛かろうと考えていたのだ。
実は襲う隙は今までに幾度もあったのだ。その度に同行者は男を葬る技の組み立てを考えていた。だが不思議と戦いの結末では自分が倒されている想像が襲ってきた。
同行者は達人といっても過言ではないほどの武芸者だった。たとえ怪我をしていても普通ならば負けるはずがなかった。だが何故か最後には自分が負ける想像が襲ってくる。
男の隙は敢えて自分に見せている隙なのだと思った。
「こいつ俺を誘ってやがる」
それは男の遊びだと思った。自分を誘って楽しんでいると。
峠に立つ男は眩しそうに青い空を見上げていた。まるでこの蒼穹は全て自分の物だといわんばかりの表情だった。
「俺はまだお前を許したわけではないぞ。お前や背後にいる太秦が表に出ようとしないことは知っている。だがその為にお前たちは俺や仲間を擦り潰して自分たちを隠したんだ。この責任は必ず取ってもらう」
同行者は少し押し殺した声で男にいった。だが男はそんな言葉を気にかけもしないように、同行者に微笑み返した。
「嫌だなあ。何度もいったように、私はあの暗闇の海から助けてあげたんですよ。あなたもあなたの仲間も、あの時点ですでに奉行所には負けていたんです。だからせめてあなたには生まれ変わる機会を作ってあげたんですよ。暗闇の海で鬼没盗首領は死んだ、そして新たな命と名前をあなたは獲得したんです。仲間は信じる王のために殉死したんですよ。王を護るために臣下のとる立派な務めです」
男は悪びれることもなく、不思議に古臭い言い回しで断言した。
「それに面白いじゃないですか。あなたには蹴速の遊び相手ができたし、私は成長が楽しみな人と出会えました。楽しいのはこれからですよ。悔やむことなど何もありません。臣下など必要ならまた集めればよいのです」
男はあっさりとしていた。擦り潰した命の替りなどいくらでもあるといいたげだった。
同行者はその言い方をどこか歪に感じた。今まではあまり気づかなかったが、この男はどこか歪んでいると不意に気がついた。
「これからどうする。行くべき場所も今はない。仙薬の再現は頓挫したし、直ぐには大坂での再開は難しいだろう。結局手元に残ったのは聖徳太子の宸翰だけだ。これで何ができる」
それを聞いた男は微笑みながら諭すように語った。
「聖徳太子の宸翰は次の時代を迎える為の起爆剤になります。しかるべき人が持てば、この国に大きな乱を引き起こせますよ、倭国大乱です。それまでは大事に持っていてください」
そして同行者の顔近くに顔を寄せると、当然のように囁いた。
「それに行くべき場所はもう決まっているじゃありませんか」
男の言葉に、同行者は不審げに尋ねた。
「どこだそれは」
男は再び蒼天を仰ぎながら、少し恍惚とした表情になった。
「勿論、神の棲まわる国ですよ」
男の陶酔したような表情を見た同行者は、その中に妖しい魔物が棲んでいるように感じた。
「神の名を語る魔物」
同行者は男のことを、そんな名の怪物だと初めて気づいたのだった。
(了)
- 1 -
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

居候同心
紫紺
歴史・時代
臨時廻り同心風見壮真は実家の離れで訳あって居候中。
本日も頭の上がらない、母屋の主、筆頭与力である父親から呼び出された。
実は腕も立ち有能な同心である壮真は、通常の臨時とは違い、重要な案件を上からの密命で動く任務に就いている。
この日もまた、父親からもたらされた案件に、情報屋兼相棒の翔一郎と解決に乗り出した。
※完結しました。

名残雪に虹を待つ
小林一咲
歴史・時代
「虹は一瞬の美しさとともに消えゆくもの、名残雪は過去の余韻を残しながらもいずれ溶けていくもの」
雪の帳が静かに降り、時代の終わりを告げる。
信州松本藩の老侍・片桐早苗衛門は、幕府の影が薄れゆく中、江戸の喧騒を背に故郷へと踵を返した。
変わりゆく町の姿に、武士の魂が風に溶けるのを聴く。松本の雪深い里にたどり着けば、そこには未亡人となったかつての許嫁、お篠が、過ぎし日の幻のように佇んでいた。
二人は雪の丘に記憶を辿る。幼き日に虹を待ち、夢を語ったあの場所で、お篠の声が静かに響く——「まだあの虹を探しているのか」。早苗衛門は答えを飲み込み、過去と現在が雪片のように交錯する中で、自らの影を見失う。
町では新政府の風が吹き荒れ、藩士たちの誇りが軋む。早苗衛門は若者たちの剣音に耳を傾け、最後の役目を模索する。
やがて、幕府残党狩りの刃が早苗衛門を追い詰める。お篠の庇う手を振り切り、彼は名残雪の丘へ向かう——虹を待ったあの場所へ。
雪がやみ、空に淡い光が差し込むとき、追っ手の足音が近づく。
早苗衛門は剣を手に微笑み、お篠は遠くで呟く——「あなたは、まだ虹を待っていたのですね」
名残雪の中に虹がかすかに輝き、侍の魂は静かに最後の舞を舞った。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい
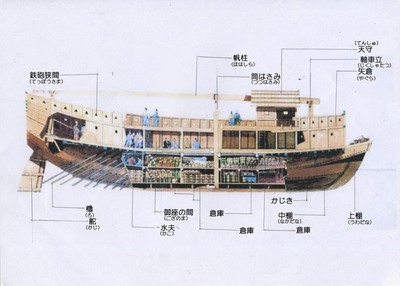

死は悪さえも魅了する
春瀬由衣
歴史・時代
バケモノと罵られた盗賊団の頭がいた。
都も安全とはいえない末法において。
町はずれは、なおのこと。
旅が命がけなのは、
道中無事でいられる保証がないから。
けれどーー盗みをはたらく者にも、逃れられない苦しみがあった。

東へ征(ゆ)け ―神武東征記ー
長髄彦ファン
歴史・時代
日向の皇子・磐余彦(のちの神武天皇)は、出雲王の長髄彦からもらった弓矢を武器に人喰い熊の黒鬼を倒す。磐余彦は三人の兄と仲間とともに東の国ヤマトを目指して出航するが、上陸した河内で待ち構えていたのは、ヤマトの将軍となった長髄彦だった。激しい戦闘の末に長兄を喪い、熊野灘では嵐に遭遇して二人の兄も喪う。その後数々の苦難を乗り越え、ヤマト進撃を目前にした磐余彦は長髄彦と対面するが――。
『日本書紀』&『古事記』をベースにして日本の建国物語を紡ぎました。
※この作品はNOVEL DAYSとnoteでバージョン違いを公開しています。

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜
かまぼこのもと
歴史・時代
1615年5月。
徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。
堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……
豊臣家に味方する者はいない。
西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。
しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。
全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















