1 / 2
小太刀の籐伍奇譚帖〜鬼神狩り《前編》
しおりを挟む「小太刀の籐伍奇譚帖~鬼神狩り」
灘猿丸
開幕ノ余話
ここに一つの伝説がある。
第十一代垂仁天皇七(紀元前二三)年七月七日、日本書記によると当麻蹴速と野見宿禰による角力勝負が日本で初めて行われた。
当麻蹴速は大和国の当麻に棲む豪遊無双の戦士で、命をかけて戦える相手を求めていたという。このことを聞いた垂仁天皇は出雲国の戦士である野見宿禰を召し寄せ、両者を角力で対戦させた。
二人は凄まじい蹴り合いを演じ、最後には当麻蹴速が野見宿禰に腰を蹴り折られて死んだと伝わっている。そして当麻蹴速の領地は没収され、勝者の野見宿禰に与えられた。この後、野見宿禰は垂仁天皇に久しく仕えたといわれている。
この伝説から垂仁天皇時代の角力とは、現在と異なり蹴り技が主体の格闘技だと思われる。当麻の地には蹴速塚という墓があり、当麻蹴速の墓だといわれている。
ただこの墓が本当に当麻蹴速の墓かは疑わしい。なぜなら当麻蹴速という名前自体が「当麻に住んでいる蹴り技が速い(=蹴速の)男」という意味である。それは特定の人物の名というよりも、この神速の蹴り技を修得した戦士たちの総称と思えるからだ。
また野見宿禰は出雲国から召されたと日本書記にはあるが、この角力勝負が行われとされる穴師坐兵主神社の近くに出雲村という村があった。野見宿禰はこの出雲村の人間であったという伝承がある。
角力勝負が行われたという穴師坐兵主神社という名前も面白い。
穴師は地名だが、坐兵主はかつて大兵主とも書かれ、文字面からは「最強の兵士が居る場所」という意味に読める。だとしたらこの神社は古代の兵士の練兵場か演習場であったのかもしれない。
そう考えると当麻蹴速と野見宿禰による戦いは単に個人の力くらべではなく、当麻に本拠を持つ戦士兵団と出雲村に本拠を置く戦士兵団の演習あるいは実戦とも想像できる。
垂仁天皇による角力勝負は、古代の天皇軍を選考するための御前試合だったのかもしれない。それゆえ負けた当麻兵団は勝った出雲兵団に吸収され、領地も奪われたのだ。
実際垂仁天皇前後の時代は全国に大和の軍勢が侵出し、東北や丹波、吉備に四道将軍が派遣(十代崇神天皇)され、また日本武尊命による出雲や熊襲への征伐(十二代景行天皇)も行われる。この時代には天皇軍の整備が急がれていたのかもしれない。
ただ吸収された当麻兵団の神速の脚技「蹴速」が失われたわけではなかった。なぜならその技を繋ぐ一族がいたからだ。その技は時を超えても脈々と継ながれ、今に至るまで伝えられているのである。
第一幕 鬼没盗出来(きぼつとうしゅったい)
(一)
ドン、ドドンドンドン
ドンドンドン
ピーヒャラ、ヒャララピー
どこかから太鼓の打ち鳴らされる音が響いていた。重ねるように笛の音も奏で始められている。
きっとどこかの小屋が芝居の開幕を知らせているのだろう。もうすぐ木戸が閉まるという見物客への合図である。この街はいつも祭りが行われているような賑わいに溢れていた。
周囲には艶やかな色とりどりの歌舞伎の幟旗や、役者たちの名前を記した大見得看板が所狭しと掲げられている。籐伍(とうご)は今日もまた、道頓堀の芝居小屋街にまできてしまっていた。
午前中に西町奉行所での書き物仕事を終えた後、市中見廻りと届けて街に出た。出がけに従兄弟の同心、真壁恭一郎(まかべきょういちろう)が声をかけてきた。
「籐伍、くれぐれも道頓堀には近づいたらあかんで。お前の見廻り区域は船場以北なんやからな。わざわざ叔父さんが上役に頼んで管轄を変更して貰うたんや。また芝居小屋に入り浸ったら、叔父さんの顔潰すで。仮役とはいえ与力が何遍も定法破ったら格好つかへん」
父から見張りを頼まれているのか、恭一郎は籐伍の行動をよく見ているようだった。
「わかってるわ。そないに心配せんでも芝居小屋には行かへんて。恭兄にいわれんでも、この前親父にこってり叱られたさかいな」
先日籐伍は道頓堀にある角座の歌舞伎芝居に熱中し過ぎて、奉行所への帰還を忘れてしまった。その為奉所では一騒動となった。上役からも父からも大目玉を喰らっていた。
そんな父や恭一郎、上役の顔がチラチラと脳裏を過ぎっているのか、籐伍は目前の中座の木戸を潜る決心がなかなかつかなかった。
籐伍が迷いを振り切って一歩前に出ようとしたとき、通りの向こうから声がかかった。
「やっぱりここにいてはったわ。船場あたりにいてへんよって、どこに行きはったんか探しましたで。殿さんにここへ来たらあかんいわれてはるのに、ぼんはしゃあないなぁ」
声は父が手下にしている御用聞の金蔵だった。籐伍も子供の頃から見知っている。
「なんや金蔵かい。びっくりさせんといて。まさか父上のお目付か」
中座の前で足を止めたまま、籐伍はあたりを伺った。他にも見張りがいるかもしれないと少し不安になった。
「今日は上役はんの御用やよって。ぼんが中座の前で思案してはったんは黙っておきますさかい、急いで奉行所に戻ってください。なんや特別な御用が振られるいうことらしいですわ」
籐伍は仕方ないという表情になり、後ろ髪を引かれながらも中座の前を渋々離れた。今日は中座で新作の歌舞伎演目が演じられる初日だった。籐伍は何日も前からこの日を楽しみにしていたのだった。
松屋町筋にある大坂西町奉行所に戻った籐伍が上役の元に出向くと、そのまますぐに吟味方筆頭与力の部屋に行くようにいわれた。
普段籐伍に指図するのは廻り方の上役与力だったが、吟味方筆頭与力から直々の差配を受けるのは初めてのことである。仮役与力になって半年ほど経つが、少し緊張しながら初めて吟味方筆頭与力の部屋に入っていった。
「おお阿刀(あとう)か、ご苦労であったな。まあそこに座れ。どないや、出仕してしばらくになるが奉行所務めにはもう慣れたか。お主の父御も色々と気を揉んでおるようや。会う度によしなにと頼んでくるで」
吟味方筆頭与力の丹羽主膳(にわしゅぜん)は、鷹揚な様子で話を始めた。この丹羽も何代か遡れば籐伍の阿刀家と親戚筋になるのかもしれなかった。そのせいか部下に対してというよりも、親戚の甥っ子に話すような調子である。
江戸に幕府が開かれ、幕府直轄地の大坂の東西に町奉行所が置かれた当初、江戸より鉄砲足軽、徒士らが与力や同心として大坂に赴任し、一代限りの役職とした。だがやがて彼らは大坂に土着して、家業のように奉行所の役職を親子親族で世襲している。
さらに奉行所設置からこの天保年間までの二百年に及ぶ時間が、奉行所内で幾重もの婚姻を重ねさせ、多くが親戚筋にもなっていた。
阿刀籐伍と五歳上の従兄弟の真壁恭一郎が仮役与力と同心を同時期に務めているのも、そうした事情である。恭一郎は三年前に父親の同心役を引き継いでいた。
籐伍は大坂西町奉行所の与力、阿刀念十郎が歳を経てからできた男子だった。その為元服してまだ数年だが、半年前より仮役として奉行所の職に就いていた。
大阪町奉行所の人員は与力東西各三十騎、同心各五十人と定められていたが、慢性的な人手不足もあり、その子弟を仮役(臨時や見習い)として役につけることも多い。隠居も近い念十郎は息子籐伍に早く仕事を覚えさせる為に、早々に仮役与力に就けたのだった。
「それでなあ、荷が重たいかもしれへんけど、面倒な案件を担当してもらいたんや。お奉行からも直々のご下命があってな。それできてもろうた」
籐伍は丹羽の話を上手く理解できなかった。どうやらお奉行からの難題を押し付けられるらしということは理解した。
「どないな案件でしょうか。私はまだ一人で案件処理に当たったことはありまへんけど、ええんでしょうか」
奉行所の与力、同心はその担当が多岐にわたっている。大きくは司法分野と行政分野に分かれるのだが、籐伍は司法分野の基本業務の廻り方として見習いをしているのだ。
奉行所の業務はそれぞれに専門性も高く、新人がいきなり担当できるものではない。案件の単独担当となると、どの分野でもある程度の練度が必要とされるのだった。
「阿刀ももうわかると思うけど、奉行所は人手が足らんのや。日々のお役目だけでも手いっぱいやのに、そこにお奉行からの特別なご下命や。担当する奴がおらへん。そこで少し早いとは思うが、仮役のお主にも案件を担当させることになったんや。しかもこれはお奉行からお主への直々のご下命やで。ありがたく拝命しとき」
恩着せがましくいっているが、奉行からの追加仕事にまだ使えない籐伍を当てたのだろう。
「どないな案件ですか? 直接のご下命やいわはるけど、お奉行には初出仕のご挨拶と、誓紙の奉呈のときにしか逢うたこともありまへん。直々のご下命やいわれても……」
籐伍は丹羽に対し疑問を口にした。
大坂町奉行所の与力・同心は町奉行の臣下ではない。形式的には徳川家が主家の直参である。町奉行はあくまで業務上の上役、組頭といった位置付けだった。その為、町奉行が交代するたびに、奉行所の与力・同心は町奉行に対して誓紙と由緒書(自分と家の履歴書)を提出した。臣下ではないが町奉行の命令に従うという誓いと身元の開示である。
仮役として出仕するときに籐伍もこの誓紙と由緒書を提出した。その折に奉行とはいくつか言葉を交わしただけだった。
「それや、そのときにお奉行はお主に目をつけはったようや。同流の剣技やいうてな」
籐伍も武士の子として当然のように幼い頃より剣術を習っている。ただその流派が少し変わっていた。一刀流や新陰流など将軍家や大名家が指南を受け、多くの武士が学ぶ有名流派ではなく、少し変わったこの時代には不人気な流派の剣だった。
中条流平法、長刀ではなく小太刀を戦闘の主力にした流派である。
元は戦国時代に起こった流派らしいが、今はあまり著名ではない。小太刀を主とした流派としても富田流などの方が有名である。
なぜ籐伍が今はあまり主流ではない中条流平法を習ったのかというと、もちろん本人の意志ではなかった。父の念十郎の合理精神が籐伍に中条流平法を学ばせていたのだ。
今の太平の世では、長刀を振るう機会などそうそうあるものではない。それに与力は捕り方としても、様々な場面で捕縛に臨む。そうした多くの場合、長刀は扱い辛いのだった。近接戦闘や室内においての有用性は小太刀の方が上である。それは念十郎の経験が導き出した答えだった。
だが奇妙な因縁なのか、今の大坂西町奉行もこの中条流平法の門下だった。元々は江戸の旗本である奉行が、知る者もいない遠国の大坂で旧友に出会ったように感じても不思議ではない。この時代、同流や同門の剣士は同窓生に近い。西町奉行が初対面の籐伍を心に留めたのもそうした心理からだった。
「この案件は阿刀にやらせよとのご下命があったんや。幸運なこっちゃ」
多分、丹羽はこの下命を最初渋ったのだろう。そこで奉行はまだ無役の籐伍にやらせろといったのかもしれない。
「それで担当の案件とは結局何なんですか。お奉行からのご下命はありがたいですが、何をやればよいのかさっぱり解りません」
籐伍は少し焦れて丹羽に迫った。丹羽がなかなか本題をいわないのは、それだけ厄介な案件なのだろうと想像がついた。
「ああ、そうやたったな。担当してもらうのはあれや、最近噂になっとる骨董品専門の盗賊の件や。えっとなんて呼ばれてたかいな」
丹羽は急に名前を忘れた振りをした。
「この前、同修町の薬種問屋に押入ったいう鬼没盗のことですか」
籐伍は少し唖然としながら盗賊の名を口にした。今、大坂市中で噂になっている神出鬼没の盗賊だった。
「そうや、鬼没盗や。その探索を阿刀にやってもらおう思う。ここだけの話やが、どうもお奉行がご城代に捕縛を約束されたらしいのや。それで専属を置けいわれてな。定町廻りの方でもう探索してるいうても聞いてくれへん。まあそれで阿刀にお鉢が回ったんや。詳しいことは定町の同心に聞いたらええ」
そういいながら丹羽は籐伍に、冊子を押付けるように渡した。
冊子を受け取り、「これは」という顔をした籐伍に丹羽が告げた。
「それはこれまでの鬼没盗に関する調書や。大体のことはそこに書いてるさかい、よう読んどき。それと今後の探索の報告は廻り方やのうて吟味方に出してんか。お奉行に進捗を聞かれたら答えなあかんからな」
それだけいうと、もうこの件は終わりというように丹羽は別の書き付けに目を落しだした。すでに自分の手は離れたといいたげな様子である。
籐伍は仕方なく一礼をして丹羽の部屋を後にするしかなかった。
さて、これからどうしようと悩みながら奉行所の廊下を歩いていると、書き付け部屋の襖が突然開いて中に引き込まれた。見ると従兄弟の恭一郎が籐伍の腕を掴んでいた。
「今、丹羽様から鬼没盗の件聞いたんか。またえらい面倒くさい事件を振られたなぁ」
恭一郎は耳元で囁いた。もうすでに話は知っているようだった。
「そんなに面倒いい事件なんか鬼没盗て。家人が寝てるうちに忍び入って、知らんうちにお宝盗んでるって聞いてるで。金も盗まんし人も殺してへん。何や幽霊みたいな盗人や」
籐伍は自分が知る鬼没盗のことを語った。そのほとんどが奉行所内の噂話だった。
「阿保か、やから面倒いねん。何の痕跡もあらへんし、手がかりもない。探索のとっかりがないんや。どうやって追っかけるんや」
恭一郎は籐伍の認識の甘さを突っ込んだ。
「定町廻りの方では何か掴んでないんか」
恭一郎が籐伍への下命を知っているということは、同心衆には吟味方より通達が出ているのだろう。鬼没盗は仮役与力の阿刀籐伍が担当すると。
「まだ何も判かってへん。それにお前が担当になったことで、この件はほぼ棚晒しやで。責任取ってくれる奴ができたさかいな」
籐伍はえっと思った。丹羽はお奉行からの下命といっていたが、結局は責任のタライ廻し先を籐伍に持ってきただけのようだった。
「お奉行は早いとこ江戸に帰りたいんや。勝手のわからへん大坂で頑張ってもなかなか手柄も上げられへんからな。今の大坂城代の堀部様は来年には御老中になるいう噂やさかい、ここで点数稼ぎたいんやろ。それで話に出た鬼没盗を捕まえますいうたんや。まあ籐伍に下命したのも、お奉行と丹羽様の妥協点いうところやな」
恭一郎は実によく裏の事情を認識しているようである。
「わかった。皆が投げ出したんやったら、わいが捕まえたる。それでまた道頓堀行っても誰も文句いわん手柄にしたるわ」
籐伍は事件解決の困難さよりも、これを芝居通い再開の切掛けにしようと思った。探索に当たる者として実に不純な動機である。
「籐伍がやる気になるんはええことやが、あんまり無茶はせんとき。お前が出しゃばったら定町の同心はええ気はせんからな。その辺は程々にすることや。丹羽様は誰か廻り方の同心付けてくれたか?」
籐伍はブスっとした表情で首をふった。
「ほれみい。ほんまに解決するつもりやったら、誰かようできる同心付けてはるわ。手足も無しでどうやって探索するつもりや」
恭一郎は実によく状況を判断していた。確かに恭一郎のいう通りである。
定町廻り同心の積極的な協力もなく、また探索に長けた廻り方同心もいない。それでどうやって鬼没盗を追えというのか。目の前に現実を突きつけられて、籐伍は「ぐぅ」の音も出なかった。
「まあ、わいが分かることは教えたるさかい、まずは鬼没盗が出たとこの定町廻りに聞いて回れ。そこから何かでけそうなことあったら考えてみ。あんまり手付かんかったら流石にお奉行の手前、丹羽様も困るさかいな。報告できるぐらいのことはやっとき」
それだけいうと、恭一郎はそそくさと部屋を出ようとした。
「恭兄、ありがとう。参考になったわ」
幼い頃から恭一郎には色々なことを教えてもらっていた。男兄弟のいない籐伍にとっては実の兄のような存在である。恭一郎は「かまへん」というように手を左右に振った。だが最後にいつもの言葉を付け加えた。
「鈴(りん)ちゃんには、あんじょういうといてや。今度ウチのおかんが作った特製の牡丹餅持って行くさかい」
恭一郎は笑いながらいったが、実はこちらの方が本当の目的かもしれなかった。
恭一郎は籐伍の三つ歳上の双子の姉、一方の鈴を幼い頃から好いているようだった。まだ奉行所に出仕して三年目だが、父親のように早く定町廻りになって、鈴を迎えたいと思っているらしい。それで従兄弟という以上に籐伍のことも世話を焼いているのだ。
その夜、奉行所から戻った籐伍は、自室で丹羽から渡された鬼没盗の調書を読んでいた。読めば読むほどその内容が不思議だった。
鬼没盗には特徴が二点あった。
まず第一点は一切の金品には手を触れず、その家の持つ骨董的逸品のみを奪っていた。その為損害額も公式には高額にならず、奉行所があまり本気で探索に入らない理由でもある。
そして第二点目は、賊の侵入にほとんど翌朝まで家人も気がつかない。また押し込みでありながら人の被害も出ていない。誰も傷つけず、また殺していないのだ。本当に幽霊のように気がつかぬ内に骨董品だけを盗んでいるのである。
その神出鬼没の有様から「鬼没盗」と名付けられているのだった。
これまで五件の被害が奉行所に届けられているが、最初は事件の存在自体が信じられていなかった。二件目、三件目の被害届により、やっとその存在が認められたのだ。
籐伍は調書を横に放り投げて天井の杉模様を眺めるように寝転がった。
恭一郎がいったように、本当に手の着けようがなかった。仕方ないので、明日からは事件の起こった地の定町廻りからまず話を聞いてみようかとぼんやりと考えた。
「籐伍さん、少しええかしら。お父様が戻られたんやけど、籐伍さんにお話があるっていわはってて。書院に来るようにいうてますよ」
襖越しの廊下から姉、鈴の声がした。
父から話とは、最近は叱られるとき以外あまりないことである。特に十年前に母が亡くなって以来、ちゃんと話もしていない。
父の念十郎は今、西町奉行所諸色方の大番役を勤めていた。いわば大坂経済の舵取り役である。そのため帰りも連日遅く、また宴席などで帰らない日もある。
珍しいなと思ったが、「お奉行からのご下命の件やな」と想像はついた。
あまり気乗りはしないが、姉の声に従って父の書院に向かった。
阿刀家の拝領屋敷は大坂城の北側、天満橋を渡ったあたりにある。知行は他の与力同様に二百石を少し超えるぐらいで、直参としても貧しくはない。それに町奉行所の役人には商人からの付け届けも色々とある。特に諸色方与力にはそれが多かった。
拝領屋敷もそれなりに広く、父の書院は籐伍の部屋から少し離れていた。
書院の前で籐伍は中に声をかけた。
「籐伍です、お呼びやと聞きました。入ってもよろしいですか」
しばらく沈黙があってから、「入りなさい」という落ち着いた父の声がかかった。
書院に入った籐伍は、書見をしていた父の少し後方に座った。
父は手にしていた書き付けを書見台に戻すと、籐伍の方に体を向けた。
少し籐伍の顔を繁々と眺めてから、徐に口を開いた。
「吟味方からおもろい仕事が割り当てられたそうやな。恭一郎が昼間知らせてくれたわ」
父は少し笑っていた。いつも難しい顔ばかりしているように父を思っていた籐伍は意外な気がした。
「そんな面白いお役目やありまへん。皆が投げ出した貧乏籤です」
籐伍は不満げな声で答えた。
「そやから面白いんや。みんなが投げ出したいうことは、何をやっても文句が出えへんいうこっちゃ。ええか、皆がやりたがるお役目いうのは、大体もう筋書きが決まっとる。そないなんは面白うないお役目や。どこに落ち着くかわからへんお役目こそ面白いんや。お前はあれだけ芝居に通っていながら、そんなこともわからへんのか。筋の読めん演目こそ面白いんとちゃうんか」
籐伍は父の言葉に少し意外な気がした。振られた探索に手を抜くなとか、また小言をいわれると思っていたのだ。だが様子が少し違った。それにお役目を芝居に擬えることなど今までなかった。
「しかし、全く手がかりもありまへん。そんな事件を面白がれいわれても」
「そやから余計に面白いんや。お前は芝居小屋に入り浸っとるが、その芝居の元はこの浮世やで。やったら逆に、この浮世に起こることを芝居やと思うて眺めてみい。お前やったらどんな筋を考えるんや。もし鬼没盗が舞台の上に立っとったら、この先どう演じると思う。お前が考える筋の中で、一番おもろい筋を辿ってみい。それだけでおもろい仕事になるで」
籐伍は父の言葉にハッとした。これまでの事件の結果をただ辿るのではなく、その結果からこの先を、未来の鬼没盗の行動を予測せよといっているのだと気がついた。
よしんばそれが外れたとしても、元々皆が投げ出した探索である。父のいうように誰からも文句は出ないだろう。考えようでは面白い役目だった。
だが意外なのは、また父が芝居の筋書きになぞらえたことだった。仕事一辺倒の父が芝居を知っているとは思えなかった。思わずその疑問が籐伍の口をついて出ていた。
「父上は芝居のことをなんでよう知ってはるんですか?」
父は珍しくはにかんだような表情をした。籐伍が初めて見る表情である。
「お前はまだ小さかったから覚えてへんかもしれんけどな、昔はお母はんや鈴、燕と皆でよう道頓堀の芝居小屋に行ったんやで。お役目が忙しゅうなって行けんようになってしもうたけどな。大体やな、若い頃にお母はんと二人で道頓堀の芝居小屋通いしたんが始まりや。お前の芝居通いなんぞまだまだ年季が入ってへん」
この言葉が一番籐伍を驚かせた。お役目だけの父と思っていたのに、母と二人で芝居小屋通いをしていたというのだ。とても今の姿からは想像できなかった。
「難儀なことから力抜いたらあかんで。面白い面白ない以上に、まずは自分の全力で当れ。力抜く癖がついたら人はそこで終いや。もう成長があらへん。最初のお役目がおもろいやつでお前は幸せやで」
それだけ言うと、父は再び書見台の書き付けを手にした。多分市中の経済状況の報告書で、それを夜中まで読んでいるのだろう。
鬼没盗が面白い事件かどうかは別にしても、役目から力を抜かない姿勢だけは息子としても頭が下がった。ただ同じものを自分に求められても、少し迷惑だなとは感じたが。
翌朝、籐伍が起きたときにはもう父は奉行所に出仕していなかった。双子のもう一人の姉、燕(えん)と女中の小春に給仕をされながら朝餉を摂っているときに、昨夜の父の言葉を思い出した。
「燕姉は昔に父上と芝居小屋に行かはったんですか?」
籐伍の突然の質問に、燕は「えっ」という表情をした。籐伍の質問の意味を少しばかり考えた。双子の姉、鈴と燕は姿形が本当に瓜二つなのだが、性格はかなり違っていた。
鈴は誰にも優しく、また阿刀家の母親代わりのように何にでもよく気が付く。一方、燕は弟から見てもかなり大雑把で男勝りの性格だった。幼い頃には取っ組み合いの喧嘩をよくした覚えがある。燕と籐伍の喧嘩を従兄弟の恭一郎がよく仲裁してくれた。
何故か怪しい笑みを浮かべて燕は籐伍を見た。燕がこの表情をするときはあまりよくないことが多い。
「そやなぁ、あんたがまだオシメしてる頃によう行ったかなぁ。あんたいつも芝居の途中で泣き出したり、おしっこ漏らしたりで大変やったわ。父上も母上も芝居に夢中で、泣き出したあんたを鈴ちゃんにひょいと渡すねん。鈴ちゃんとうちは仕方なしに外に出てあんたをあやしてた。今となっては感謝して欲しいわ」
横で小春がご飯をよそおいながら、「ぼんは泣き虫やったからなぁ」と付け加えた。燕が同意するように何度も頷いた。小春は籐伍が生まれる前から阿刀家に奉公している。
「そんなんええねん。そやけど父上が芝居好きとは知らんかったわ」
籐伍は昨夜の父の言葉は本当だったのかと少し納得した。
「あんたは母上が亡くなったとき、お役目で帰ってきいへんかった父上にえらい怒ってたからなぁ。あれ以来父上とちゃんと話もせんようなってしもうた。よう知らんのも無理ないわ」
燕は笑いながら、「もうご飯はええん」と聞いてきた。籐伍は慌てて残った膳を平らげていった。これは燕がいつも示す「はよう奉行所にいきいな」という合図だった。
燕にせかされながら身支度を整えると天満橋北の家を後にした。今日からは鬼没盗の出た町々を回るつもりだった。奉行所勤めをして初めて、少しだけ一日に目的ができたように思えていた。
(二)
京、五條天神宮。
その境内で大きなあくびをしながら、参道を掃除する神職姿の若い男がいた。名を巨勢渦彦(こせうずひこ)という。まだ少年のように見えるが十七の歳は超えていた。
朝の清々しい空気の中で、渦彦は少し遠い東山の山並みを眺めていた。その山並みに故郷大和の葛城山の姿を重ねてみた。
「みんな元気にしてるかなぁ」
三年前に出てきた実家のことを思った。大和の葛城山中腹にある千年の古社、徳陀子神社(とくたこじんじゃ)が渦彦の実家だった。
渦彦は神職修行のために、五條天神宮で神人(じにん)として生活している。祭礼から社領経営まで、神社にまつわる全ての仕事を学ぶために五條天神宮で修行しているのだ。
ただ渦彦は徳陀子神社の跡取りではなかった。渦彦には兄、綿津見(わだつみ)がいた。綿津見が徳陀子神社の惣領息子なのだ。だが綿津見は体が弱く、あまり神社の実務が行えないと思われた。それで次男の渦彦が兄に替わって神職修行をしているのだ。
「今日は梅園の枝の剪定せなあかんなぁ」
ぼんやりと今日の仕事を考えていると、神人の棟梁、由兵衛が渦彦の方に走ってきた。
「渦彦、大和から飛脚で文が届いたで。なんや急なこととちゃうか」
いつも慇懃に落ち着いている棟梁にしては珍しく慌てている様子だ。渦彦は棟梁から飛脚が届けた文を受け取ると、裏の差出人を見た。父ではなく兄綿津見からだった。
兄からの文というのは珍しかった。嫌な予感がして慌てて文を開いた。
文には兄の筆で思いがけない内容が記されていた。
「父の飫肥人(おびと)が自害して亡くなった」とあった。
詳しい事情は記されていなかったが、何か神社の神宝を奪われて、その責を取ったためらしい。綿津見は文に「修行で忙しいだろうが、ひとときでも葛城山に戻ってはこられないだろうか」と記していた。
渦彦は震える手を必死に抑え、動揺を隠して棟梁の方に向かった。
「親父が身罷ったと兄から知らせがありました。すんまへんけど、ひととき大和に戻ってもよろしいでしゃろか」
そう告げ、渦彦は顔を見られないように参道の残った部分の掃除を再開した。渦彦の瞳には、知らぬうちに大粒の涙が溜まっていた。それを悟られないように必死に掃除を続けた。ただその掃き跡は大きく乱れたものになっていた。
渦彦が葛城山に帰り着いたのは、兄からの文をもらった七日後だった。身内の不幸とはいえ、担当の仕事の目処がついてからの旅立ちだったからだ。棟梁の由兵衛はすぐにも大和に戻れと再三いったが、渦彦は父の教え通りに仕事を途中で投げ出すことをしなかった。
葛城山の実家に戻ると、父の遺体は神葬式で葬られた後だった。
実家で渦彦は父の御霊が移された霊璽の前で深く頭を下げた。霊璽は仏式の位牌のような存在で、神棚や祖霊舎に祀られる。
少し遅ればせだったが、やっと父の御霊への挨拶を終えた。
すぐに渦彦は兄に質問を投げかけた。
「父上はなんで自害しはったんですか」
少し怒った表情で、渦彦は兄と憔悴している母に尋ねた。だが二人とも詳しい状況は分からないと、ただ俯いて首を振った。
父は神社から少し離れた山中にある巨勢家の祖霊舎の前で倒れた姿で村人に発見されたらしい。その時の姿が自害したときとよく似た前屈みの格好だった。そして胸を刺したらしい刃も手にあった。
だが、当初父がなぜ自刃したのかは判然としなかった。兄も母も、その前に変わった様子はなかったといった。
父を葬ってから、兄は父の部屋で日誌を発見したらしい。そこに父には珍しく乱れた字で、「このまま巨勢の御神宝を奪われてはご先祖に申し訳が立たぬ。何としても阻止せねば」と書かれていた。
その後に続く記述はなかったが、理由らしいものはそれしか思いあたらないとのことだ。ただその記述は、父が自害するひと月ほど前の日付で書かれていたらしい。全てのことが要として知れず、父の死は謎のまま今日に至っていると兄は語った。
「ほんまに巨勢の御神宝を失ったことが原因なんやろううか。大体御神宝とは何ですか? 誰がそんなものを奪うというんです」
渦彦は溢れる疑問が次々に口をついた。それに兄や母が答えられないのは明白だったが、言葉にせずにはいられなかった。
渦彦も父の死を消化しきれずに、悲しみと怒りが渦巻いていた。
「それを渦彦と一緒に解き明かしていきたいんや。それで京から戻ってきてもろうた」
兄は初めて少し疲れた様子を見せた。きっと今日まで父の急死で様々な苦労があっただろう。それに気落ちしている母や妹も支えなければならない。悲しみと怒りで叫び出したいのは、本当は兄の方だったかもしれない。
だが綿津見は常に冷静で、言葉を荒げることはまずなかった。体が弱く思索的な性格なせいか、自制する術を知っていた。渦彦が兄に決して勝てないと思っている点だった。
「わかりました。しばらくここに留まり、兄上をお助けします。京の五條天神宮には、父上の死の整理で少し時間がかかりそうだと文を書きますのでご安心してください」
そう告げると兄と母は初めて少し安堵したような表情になった。一番若く元気な自分が家族を支えなければならないと、渦彦はやっと気がついた。
翌日から綿津見と渦彦は父の遺品の整理をはじめた。同時に久しぶりに神社の社庫を開いて、その中も確認していった。
惣領の綿津見は父とよく社庫の中に入っていたらしいが、京に修行へ行った渦彦は久々だった。社庫には神社の宝物や神器なども仕舞われていた。
綿津見は社庫の品目一覧の冊子を見ながら、一つ一つ読み上げては渦彦に探させた。ない品目があればそれが奪われたかも知れない神宝候補になる。そうした整理と確認が毎日行われたが、社庫の品目はよく整理されていて欠品はなかなか見つからなかった。
父の遺品も整理していったが、自害の原因になりそうな物は発見できなかった。
ただ、徳陀子神社本殿の奥には立ち入り禁止の部屋があった。そこは父と惣領の綿津見だけが入ることを許された部屋だった。
仙薬洞、それが部屋の名前である。幼い頃、渦彦はこの部屋に入ることを禁止されていた。渦彦が入りたいと駄々をこねると、綿津見は優しく渦彦を諭した。
「この部屋にはな、危ない薬やら毒が置いてあんねん。渦彦がそれに触ったら危ないさかいな、入ったらあかんねん」
徳陀子神社には古代から伝わる秘伝の薬物群があった。その製法は一子相伝とされ、惣領だけに伝えられるのである。薬物の一部は秘薬として氏子や参拝者に有償で配られ、徳陀子神社の大きな収入源にもなっていた。そのことは渦彦もよく知っていた。
そもそも徳陀子神社の祭神には医薬の神々が並んでいる。少彦名命、大己貴命、神農炎帝、そして巨勢氏の祖神である。
渦彦が京で修行する五條天神宮もまた医薬の神を祀る神社で、少彦名命、大己貴命を主祭神としていた。そうした謂れからか両社には交流があった。それで父の飫肥人は渦彦の神職修行の地に五條天神宮を選んだのだ。
そして徳陀子神社にはもう一つ秘伝の技があった。それは薬ではなく体術だった。
「蹴速術(けはやじゅつ)」と呼ばれる門外不出の古代闘技である。
社伝によると、蹴速術は神話に出てくる日本最初の相撲勝負、当麻蹴速と野見宿禰が戦ったときに使われた闘技だと伝わっていた。
この蹴速術を渦彦は幼い頃から修練していた。綿津見が仙薬洞で薬の調合を学んでいるとき、渦彦は蹴速術を修練しているのが常だったのだ。
蹴速術は父や叔父の椎根津(しいねつ)が主に教えたが、ときに兄も練習の相手になってくれた。体の弱い綿津見には珍しいことだったが、渦彦は兄との修練が大好きだった。
「仙薬洞には父上のもんはないんやろか」
渦彦が綿津見に尋ねた。
「最近はあんまり洞には来てへんかったからな。ほぼ俺任せやった」
そうはいったが綿津見は渦彦を仙薬洞に招き入れ、「薬に触ったらあかんで」といいながら部屋の隅々を確認していった。
渦彦も薬に触らないように部屋を見回した。
中に見覚えのある壷があった。幼い頃にどうしてもこの室に入りたくて、忍び入った時に見た壷だった。何気なくその壺の蓋を開けると、なんとも芳しく不思議な甘い香りがした。
「それは沈香の壺や。興奮したときに落ち着かせてくれる匂いや。昔渦彦が大泣きしたときに、それ嗅がせて泣き止ませたことあるわ。あとで父上にはえらい叱られたけどな」
綿津見は昔を懐かしそうにした。
天井に届くほどの棚には幾冊もの薬の調合法を記した冊子が積んであった。あたらしい紙の冊子もあったが、そのほとんど古紙のような古びた紙の冊子だった。
その冊子をぱらぱらとめ捲って中を確認していた綿津見が、少し不審げな表情をした。そして何度も冊子を見返していった。
「何冊か薬の調合法の本があらへんようになってるわ。父上が持ち出したんやろか。持ち出し禁止にしたんは父上なんやけど」
棚に積み上げられた冊子を渦彦に降ろさせて、綿津見はそれを一冊づつ確認を始めた。
陽が傾くほどの時間が経った頃に、綿津見はため息混じりに何かを手控に書き付けた。
「兄上、本がのうなってるんか」
綿津見の様子を見ていた渦彦が口にした。
「ああ、沈香ノ編が半分ほどあらへん。父上が持っていったとは思えへんけどな。簡単な調合法やし、父上なら空で覚えてるはずや」
神宝ではないが、なくなっているものあるのだと初めて二人は認識した。
「のうなった御神宝て、秘伝の薬の調合法のことやろうか」
渦彦は想像を口にした。だが綿津見はすぐにそれを否定した。
「それはないやろ。大切な部分は紙に書いてへんからな。父上からは直接口伝されてるわ」
だが渦彦にはいわなかったが、少し気にかかる冊子がなくなっていた。沈香法の中でも「夢沈香」と呼ばれる特殊な用法の沈香である。それは使いようによっては厄介な作用をする沈香だった。
結局十日ほどかけて父の遺品や社庫の中を確認したが、神宝らしきものが失われている様子はなかった。ただ目録にある掛け軸が何幅かなくなっていた。それは御神宝というような高価なものではなかったようだが。
父の自害の原因探索に行き詰まった二人は、この後どうするべきかを悩んだ。父の遺品や神社の財産を調べても何も出てきそうにはないと思えた。
ここで渦彦は京で見聞きしたあることを思い出した。それは寺社からの盗品などを密売する闇の競市の噂だった。
盗まれた物が世に知られた逸品であればあるほど、その換金は難しい。そうした物品を売り捌く闇の競市があるというのだ。どこかに常設されているのではなく、出品物があるときに開かれる臨時の闇市だという。
実は寺社仏閣の宝物や御神体、仏像などは盗難に遭いやすい。蔵に保管されているものもあるが、一般に開帳されている場合も多く、警備がしっかりとあるとは言い難かった。
また世の中の好事家、分限者などには、そうした寺社の宝物を欲して買う者も多かった。その両者を結ぶのが闇の競市である。
京の寺社でもそうした盗難被害に遭うことが稀にある。そのとき寺社は本尊や御神体の盗難を隠すために自ら闇の競市に参加して、盗難された宝を取り返すことがあるらしい。
当然競市だから金を払うのだが、下手に表沙汰になって永遠に宝物が失われるよりもよいと考える場合もあるのだ。このことを渦彦は話した。
「兄上、奪われた御神宝が何かわからへんけど、賊が金目当てなら闇の競市に出るかもしれへん。それを探してみてはどうやろう」
渦彦の提案に綿津見は眉を顰めた。徳陀子神社はそれほど資産を持つ神社ではない。僅かな社領から穫れる米と、氏子からの賽銭や寄進、神事での玉串料、それに仙薬の販売代金が収入の全てだった。
もし闇の競市でそれらしき物を発見しても贖う資金がなかった。
「そやけど金がないで。見つけても買い取られへん」
だが渦彦は諦めなかった。何より父の死の原因が知りたかった。
「別にそこで買い取らんでもええんとちゃうか。まず何が奪われた御神宝かを確認することが先決や。それがわかれば父上の自害の原因もわかるかも知れへん。御神宝は競市で落札した人に後で返してくれるように頼んでもええし。金が必要ならそのとき考えよう」
まだ世間知らずの渦彦は楽観的な目論みを語った。とにかく今は御神宝を探し出さないと話が進まないと思った。ここで思案しても埒が明かない。
「渦彦は闇の競市がいつ開かれるかわかるんか。盗賊の密売市やで」
綿津見は少し不安そうに考えた。
「京の修行でもそこまではわかれへんけど、棟梁やったら知ってると思うわ。この話してくれたんは棟梁やさかい」
五條天神宮の神人棟梁の由兵衛が、闇の競市のことを渦彦に教えたのだった。由兵衛はある神社の代理人として闇の競市に参加したこともあると語っていた。神人歴が長い由兵衛ならではの経験なのだ。
由兵衛なら闇の競市の手がかりを知っているのではないかと思った。
徳陀子神社内での探索は引き続き兄に任せ、渦彦は一度京に戻って由兵衛に競市の話を聞いてくることにした。母は不安そうにしたが、兄が京に行ってこいといってくれたので、母も一応の納得をした。どちらにしても探索に動けるのは渦彦だけだった。
急いで大和から京に戻った渦彦は、由兵衛に徳陀子神社の置かれた状況を説明した。そして奪われた御神宝を探すために、闇の競市のことを詳しく教えて欲しいと願った。
渦彦の話を聞いた由兵衛は、難しい顔をして何かを思い巡らせている表情だった。
「ちょっとここで待っとり」
そういって宮司が控える奥の庫裏の方に去っていった。渦彦は陽が傾く頃までそのまま待つことになった。
夕方、ようやく戻ってきた由兵衛はあまり芳しくない話を始めた。
ここ何年も京では闇の競市の噂は聞いたことがないという。もしやと思い宮司にも話を聞いてみたが、やはり競市が京で催されたという噂は知らないということだった。
ただ宮司は少し前に大坂でよく似た市が開かれた噂を聞いたことがあるらしい。五條天神宮には大坂に懇意の社があるのだが、そこの宮司が二年ほど前に京を訪れたとき、そんな噂話をしていったという。どこまで本当かは分からないが。
今度は渦彦が唸ってしまった。
京ならば伝手を頼って探ることもできると思っていたのだが、全く知り人も縁もない大坂となると探索の目処も立たなかった。渦彦も闇の競市に多くを期待してたわけではないが探索の糸口さえも失ってしまった。
しばらくうな垂れている渦彦を不憫に思った由兵衛が、宮司の別の言葉を伝えてきた。
「宮司はんも徳陀子神社のことえらい心配しはっててな。元々渦彦の父御と宮司はんは馴染みやしな。そやからお前の神人修行もここでするようになった。そやからほんまはなぁ、わても宮司はんも渦彦に危ないことさせとうないねん。ただどうしても渦彦が御神宝を探したいいうんやたったら、手はあるかもしれへんと宮司はんがおっしゃててな」
あとの言葉を由兵衛は途切らせた。あまり勧めたくはない手のようだ。
「大坂であったいう闇の競市を探しに、渦彦が大坂に行ってはどないやろうと宮司はんがいわはった」
渦彦はえっと思った。大坂に行って探索することは藪坂ではないが、大坂には何のとっかかりもない。自分のような大和の田舎者が大坂に行っても途方に暮れるだけだと思った。
「競市の噂をされはった宮司はんいうのは、大坂の同修町にある少彦名神社の宮司はんなんやけど、元々この神社は何十年か前にうちの神さんの少彦名様を勧請してでけた神社やいうことや。それに少彦名神社の最初の宮司はんは元はうちの禰宜はんやったいうことで気安いねん。紹介状書くよって、そこの宮司はんとこに世話になって探してみてはどないやと宮司はんはいわはってるんや。ただ盗人相手の探しもんやからな、危ないこともあるかもしれへん。渦彦に危ないことはして欲しゅうないねんけどな」
いつもは仕事や生活に厳しい由兵衛だったが、渦彦のことを心配していた。だが渦彦はこの糸のような手がかりでも掴みたかった。
渦彦は由兵衛に深々と頭を下げた。
「ぜひ宮司様にご紹介お願いしますとお伝え下さい。私も兄も、父の死の原因と失った御神宝が何やったんかを知りたいんです。そうでないと新しい一歩が踏み出せまへん」
由兵衛は仕方なしに、渦彦の申し出を受け入れた。それにはまだ半人前の息子を修行の旅に出すような切なさがあった。
「京と大坂は近いさかい、何ぞあったら戻っておいで。お前には先祖伝来の?角力技?があるさかい心配ないかもしれへんけど、危ないことしたらあかんで」
それだけいうと、由兵衛は大きくため息をついた。子供のいない由兵衛は、どこかで渦彦を子供のように思っていた。
京での様々な始末を終えてから渦彦は大坂に向かった。三年とはいえ慣れ親しんだ京を離れるのは若い渦彦も少し寂しかった。
大和の兄には闇の競市探索のために大坂に行くと事後承諾になるが文で許を乞うた。父の亡くなった今となっては兄が巨勢家の家長である。身の異動には許可が必要だと思った。
大坂同修町は医薬の町である。町内には大小多くの薬種問屋が軒を並べ、また町売りの薬の店も多く出ている。そんな街中に少彦名神社はあった。
由兵衛が語ったようにこの少彦名神社の歴史はまだ浅い。
安永九(一七八〇)年に元々は薬種商たちの会所に祀られていた古代中国の医薬の神・神農炎帝に、日本の医薬の神である少彦名命を京の五條天神宮から勧請して合祀したのが始まりの社だった。まさに医薬の町同修町ならではの成り立ちである。
今の阿曽宮司は四代目になるらしく、就任してからあまり時間が経っていない若い宮司だった。
阿曽宮司は五條天神宮からの紹介状をゆっくりと読み進めると、それをくるくると巻き直して元の状態にして渦彦の前に置いた。
「天神宮はんからの言上はようわりました。せやけどなぁ、なかなか難しい話やなこれは。盗人の探索やいうのはどないやろ。ほんまにできるんか怪しいで。まあしばらくうちに来るんは構わへんけど、他の神人の手前特別扱いはできへんで。それと渦彦はんが自分の時間に競市探索するんはええんやけど、うちに危ないことは持ち込まんといてや」
そうはいった宮司だったが「天神宮はんにはいつも世話になってるさかいな、まあしゃあないわ」と呟き、自分を納得させるように頷いていた。
渦彦も宮司の頷きを見て少しほっとした。これで曲がりなりにも大坂での探索の拠点ができたことになった。
宮司はもう別のことを考えているのか、渦彦の顔を面白そうに眺めた。
「それより渦彦はんは大和の徳陀子神社の出なんやろ。わいも徳陀子神社の薬の噂聞いたことあるで。どないな薬があるんか、いっぺん見せてくれへんか。何やったらうちで売り出してもええで。同じ神さん祀ってるんやから色々協力したいしなぁ」
宮司は徳陀子神社の仙薬のことを知りたいようだった。
「薬のことは私にはようわかりまへん。全ては兄に相伝されてるんで。大和に帰ったら話はしてみますが……」
渦彦の素っ気ない返事に、それ以上この話を進めてはこなかった。
「あと、この手紙に書いてある渦彦はんの修める?角力技?いうんは何なん。相撲の元祖みたいな体術って書いてあるけど強いんか。強いんやったら色々と使い道はあるさかいなあ。最近は大坂にもけったいな賊が出よってな、危のうてしゃあない。うちにはたいしたお宝なんぞあらへんけど、この前もすぐ傍の薬種問屋に賊が入ったいうてえらい騒ぎやったわ。渦彦はんが強いんやったらうちも安心できるさかいな」
渦彦はなし崩しに、まずは少彦名神社の警備を担う神人をすることになった。だがそれは渦彦にも好都合な仕事だった。
夜間や祭礼での警備が主な仕事だったので昼間は大坂の町を出歩けた。それでまず大坂の地理と町を知ろうと考えた。こうして渦彦の大坂での神宝探索の日々が始まったのだった。
(三)
盗賊の探索というものは一朝一夕に始められるものではない。盗賊といえどもそれなりの歴史や人の繋がりというものがある。
そもそもどうやって目的の場所に押し入っているのか。盗賊はいきなり押し入りはしない。それなりに準備をして情報を集めるのだ。
多くの場合、目的の場所に仲間を潜り込ませ手引きさせる。あるいは内側の人間を買収などで仲間にすることもある。そうした場合、盗賊働きの後にはその人物が消えていることがほとんどだ。
だが鬼没盗の場合、押し込みの後に消えた人物はいなかった。
「内側からの手引きで押し入ってるんやないんか」
籐伍はこの点をまず不思議に思った。
それに盗みの目的である骨董品の情報はさらに掴み辛い。余程の自慢好きでもない限り、自分の持つ骨董のことなど口にするものではない。誰がどんな骨董品を持つかは外の人間にはわからないのだ。
籐伍は先日訪れた同修町にある薬種問屋の肥前屋で、つくづくそのことを考えさせられた。主人は奪われた骨董品を入手したことを家族や内儀にも伏せていたのだ。
なのにある夜忽然と骨董品が消えたのである。最初は自分が仕舞った場所を思い違いしたのかと思ったほどだったという。家人や奉公人に尋ねても、誰もその盗失した夜に異変に気づかなかった。驚くほど家中の皆が深い眠りに落ちていたのだった。それは主人も同様だったらしい。
結局、肥前屋主人の証言だけが事件の存在を主張したのである。
肥前屋の事件を担当する定町廻り同心の河原崎は、今だに主人の狂言ではないのかと半分疑っていた。ただ奪われたという骨董品の入手先で裏を取ると、確かに肥前屋に売り渡したという証言があったらしい。骨董は拓本の掛け軸らしく、大店の主人が狂言するほどの値のものではなかった。
河原崎は探索に行き詰まる籐伍のことを哀れに思ったのか、助言めいたことを語った。
「阿刀様も難儀なお役目振られて大変やけど、まずは個々の事件やのうて鬼没盗が何で骨董品ばっかり奪うんかを追ってみはったらどないですか。賊がお宝を狙う目的は大きくいうと二つや。金か因縁です。どうも私には鬼没盗が金目当てとは思えまへん。ならどんな因縁が鬼没盗に盗みをさせてるんか、そこを追ってみたらどうですか。忙しい定町廻りにはでけん探索ですが、阿刀様は自由も効くんでええんとちゃいますか」
籐伍はこの言葉にハッとした。父の言葉を思い出したのだった。
「もし鬼没盗が舞台の上に立っとったら、この先どう演じると思う。お前が考えられる筋の中で一番おもろい筋を辿ってみい」
河原崎は父と同じことをいっていると思った。盗みの目的、因果が解れば鬼没盗の次の行動も推察できる。それは放し飼い状態の籐伍にしかできない探索かもしれなかった。
多少皮肉まじりかもしれないが、河原崎の指摘は的を得ていた。
「ありがとうございます。少し糸口が見えたような気がします」
籐伍は礼をいった。仮役とはいえ与力が同心に取る態度ではなかったのかもしれないが、まだ奉行所内の身分に慣れていない籐伍は素直に河原崎に深々と頭を下げていた。
面映ゆい表情をした河原崎は、困ったようにぷいっと横を向いた。
「御父君には昔随分世話になりましたからな、恩返しということで」
それだけいうと籐伍に向かって深々と礼をし、これ以上語ることはもうないというようにその場から立ち去っていった。
籐伍はもう一度事件の詳細を振り返ろうと思った。鬼没盗の事件には隠れた秘密があるのではないのかと思えたからだ。それが盗みの因縁に繋がるのかもしれないと想像した。
その日の夕刻、同心控え部屋で報告書を書いていた河原崎のそばに恭一郎が立っていた。
「河原崎はん、籐伍にあんじょうしてもろてすみません。定町廻り一の遣り手に助言もろたら、籐伍も少しはやることが見える思いますわ。あのままやったらうろうろする迷子犬と同じやさかい」
河原崎は書き手を止めずに答えた。
「あれでよかったかどうかはまだわからへん。それに阿刀様にはここでの身の処し方をもう少し教えた方がええな。同心が与力に頭下げられたら、どないな悪さしとんかと思われるわ。素直すぎるんはここに向いてへんで。こすっからいぐらいがちょうどええんや」
そう呟いた河原崎だが、あまり不快に思ってはいないようだった。
「籐伍にはしっかりいうておきます。まだ子供なんです。でも……なんか昔の河原崎はんに似てませんか。うちの父やんに付いてた頃の兄やんに。あの頃は兄やんもえらい素直やったのになぁ」
恭一郎がいたずらっ子の顔になり、河原崎の顔を覗き込んだ。
河原崎はかつて恭一郎の父に付いて同心修行を始めたのだった。まだ子供だった恭一郎はよくその河原崎に遊んで貰った。「兄やん、兄やん」と呼んで河原崎に纏わり付いていた。
家や親族の中では兄役をすることが多い恭一郎だったが、河原崎と一緒の時は弟になれた。それは恭一郎にとって肩の荷物を下ろしたような楽な時間だった。
「兄やんいうな、ここは奉行所やで。変な餓鬼のお守りしたばっかりに、今だに祟られるわ。もう二度と餓鬼のお守りはせえへん。阿刀様はお前が面倒みい」
怒った顔でそういいながら、河原崎は書き上げたばかりの書き付けを恭一郎に渡した。 恭一郎は受け取りながら、「これは何ですか」という表情をした。
河原崎は面倒臭そうにしているが、かなり綿密に書かれた意見書だった。
「それ、ホンマは上に報告しよう思うとった鬼没盗に関する報告書や。自分で探索できんよって、目星だけは報告しよう思うてな。そやけど結局は忙しゅうて誰も手が着かんやろ。やったら素人とはいえまだ阿刀様にやってもろうた方がええ思うてな。お前から阿刀様に渡してんか。参考にしてもええし、せんでもええ。ただ探索には別な角度の視点も必要やよって、迷うたときに見るぐらいにしたらええいうてな」
それだけいうと、河原崎はもう別の書き付けに筆を走らせ始めていた。
恭一郎が書き付けに目を落とすと、そこにはかなり事細かく事件に対する河原崎の所見が書かれ、しかもまず何から手を着けるべきかが順を追って記されていた。まるで鬼没盗に関する探索手引書のような内容だった。
恭一郎は河原崎の面倒見の良さと優しさが変わってへんなぁと、不思議な感動を得た。自分の得にならないのに探索情報や手法の開示など普通の同心は他人にしない。
恭一郎が弟扱いする籐伍を、河原崎もまた弟分として扱っているのだと感じた。
「兄やんはやっぱりええ人やなあ。昔のまんまや」
恭一郎は子供に戻ったように、河原崎の背に抱きついた。その背中は昔同様に頼りがいのある大きな背中だった。
「やめえ、気色悪い」
河原崎がそう叫ぶと、恭一郎は大きく後ろに転がされていた。河原崎が柔術の達人であったことを恭一郎は久しぶりに思い出した。
ここ何日か籐伍は自室に篭って、鬼没盗事件を自分なりに再整理しようとしていた。
丹羽に渡された事件の調書、各事件を担当する定町廻り同心に聞いた内容、そして事件現場を訪れた自分自身の観察などを箇条書きにして、それらを細かく短冊にしていた。
その幾十枚の短冊を共通点ごとにまとめてみたり、また無作為に並べたりしている。それをボーッと眺めながら、何か閃きか啓示がないものかと考え込んでいた。
だがこれまで何も閃いてはいない。短冊の群れの背後に鬼没盗の姿を見出そうとしているのだが、一向にその陰さえ見えなかった。
籐伍は畳の上に大の字になり、天井の見慣れた杉模様を眺めていた。
「こんなんではわいは戯作者にはなれへんなぁ。舞台に立った鬼没盗が全然想像できへんし筋も見えてこん。まだ観察や思案が足らへんのやろうか」
事件のことを考えていたはずが、いつのまにか自分の密かな願望である芝居の戯作者になりたいという夢のことを思っていた。
籐伍は常々、家業として奉行所与力になることは仕方ないとしても、余技として戯作者になれればと思っていた。実は奉行所の中にも、様々な分野に手を出す役人がいる。武家文化一辺倒の江戸と違い、町人文化の華やかな大坂では武士もまた精神的には町人化しており、その生き方はかなり自由だった。
「まあ、大塩のおじさんみたいに有名な陽明学者とはいかんでも、いつか道頓堀の芝居小屋でわいの書いた芝居が上演されたら、こんな嬉しいことはないなぁ」
籐伍が思った大塩とは、父念十郎の親友で東町奉行所与力の大塩平八郎のことである。
大塩は東町の与力というだけでなく陽明学者としても高名だった。陽明学の私塾を開き門下生が百人以上いるという。東町の与力ながら西町奉行にも意見を聞かれる存在で、政策提言もしている。前の飢饉の折も数々の提言をしてそれが取り入れられたと聞いた。
大塩は父念十郎と同時期に奉行所に出仕したためか、若い頃から仲が良かった。籐伍も阿刀家に遊びに来る大塩を子供の頃からよく見知っていた。籐伍にとって大塩は理想の生き方をする大人だった。
ぼんやりとそんな思索にふけっていると、離れた厨のほうから大きな笑い声が聞こえてきた。夕餉の時刻はもう過ぎていたし、来客があるような時刻でもない、当然父はまだ帰宅していないだろう。
笑い声は姉や女中の小春のようだが、何を笑っているのだろうと少し気になった。思案に行き詰まっていた籐伍は、気晴らしになるかと思い厨に向かった。
厨では五人の人間が車座になってお茶を飲んでいた。その中心には艶々として大振りの牡丹餅が幾つも皿に盛られている。
「おお籐伍、家に帰っても探索とはご苦労やな。なんかええ目星は思いついたか」
大きな牡丹餅を頬張りながら恭一郎が声をかけてきた。その場には姉の鈴と燕、女中の小春、恭一郎の真壁家の女中、梅がいた。
「こんな時間に何してはるんですか」
小春が籐伍のお茶を入れに席を立った。その空席に座った籐伍は、皆の顔を順番に見回した。皆おかしそうに籐伍を見ていた。
「いえな、昔籐伍と燕ちゃんが喧嘩してあんたが大泣きしたときのこと話しててん。あのときも真壁の叔母様が持ってきてくれはった牡丹餅みんなで食べて、あんたもそれで泣き止んだんなぁ、いうて」
鈴が面白そうに語った。
「籐伍の機嫌直すには、牡丹餅食わすか芝居小屋連れてったらええんとちゃうかいうたら、皆が納得してもた」
どやらそれが笑い声の理由らしかった。
「今日、うちのオカンが仰山こと牡丹餅作ってな。鈴ちゃんとこ持って行きいわれて。わいも奉行所帰りで疲れてたけど仕方なしに持ってきたんや。それで一休みついでに皆で昔話しとった」
恭一郎の言葉に燕が茶々を入れた。
「仕方なしなんて嘘やな。ホンマは鈴ちゃんに会える思うて喜んできたくせに。それにおばちゃんは鈴ちゃんにって、うちのことはいわなんだん? えらい差別やわぁ」
燕は少し拗ねた振りをした。
「牡丹餅で機嫌直るやなんて、そんな単純な大人いてへんで。わいはもう少し複雑なんや」
籐伍はそういいながらも、小春が持ってきてくれたお茶と箸を渡されると、さっそく牡丹餅に箸をつけて頬張っていった。
すると全員が「ほらな」というように、笑いを押し殺していた。
その姿を見届け、恭一郎は懐から一通の書き付けを取り出した。
「さすがに今日は牡丹餅だけやとあかん思うてな、もう一つお前の喜ぶもんを持ってきたで。多分、今お前が一番欲しいもんや」
恭一郎が牡丹餅を頬張る籐伍の前に書き付けを置いた。
「えっ」という顔した籐伍は、慌てて牡丹餅を飲み込んで書き付けを手にした。
表には「鬼没盗私見」とあり、裏側には流麗な文字で「河原崎」とあった。中を確認すると細かい几帳面そうな筆跡で、大量の文章が綴られている。
籐伍は「これはどういうことですか」と尋ねた。
「まぁ簡単にいうたら、探索の下請け指示やな。河原崎はんは忙しいよって、思い通りの探索ができへん。それで暇な籐伍に河原崎はんが目星をつけた探索をやってもらおういうことや。全部書いてある通りせんでもええけど、まずは自分の目星と比べて納得できるところから手着けてみい。自分一人であかんかったら、人の意見も取り入れてみることや。それで探索の袋小路から出られることもあるよってな」
鈴と燕が同時に「へぇ~」と感嘆の声を出して、籐伍の持つ書き付けを覗き込んだ。二人は探索の内容は知らないが、恭一郎が重要な手助けをしてくれたのだと理解した。
籐伍は慌てて書き付けを走り読みしたが、すぐに下に置いた。
「あかんわ、わいの思いもしてへんこと書いてある。ようできる定町廻りはやっぱりすごいなぁ」
籐伍は恭一郎と、その向こうにいる河原崎に深々と頭を下げた。そして明日にでも河原崎に礼をいいに行くと呟いた。
「あかんで籐伍。表で与力が同心に礼いうたらあかん。たとえ探索の指南受けても、同心にとっては当たり前のことや。礼いわれたら河原崎はんが困る。ええか、奉行所では与力と同心は天と地ほど立場が違うんや。お役目で与力は同心をどう扱うてもええし、それで文句いう同心はいてへん。ほんまにありがたい思うとんのやったら、別の形で礼はせなあかん。そうやって同心と与力は信頼を築くんや。お前は行動が素直すぎる。相手のことを考えてから行動せえ。協力してくれる人もおらんようなるで」
恭一郎に思いもしない言葉で嗜められて、籐伍は唖然とした。自分は今まで素直に同心衆に礼をしてきたが、それが逆に相手を困らせていたことを初めて知ったのだった。
世の中は複雑で、子供のように素直なことが良いばかりではない。少し厄介な大人の世界を突き付けられたような気がした。
「わかった。牡丹餅やのうて別の礼の仕方考える。河原崎さんが喜ぶような礼をな」
それだけいうと籐伍は慌てて立ち上がった。部屋にある短冊をこの意見書に当てはめてみようと思ったのだ。そこに何が見えてくるのか、ワクワクする気持ちになっていた。
籐伍は厨を出るとき大きな声で燕に釘をさした。
「燕姉、牡丹餅全部食うたらあかんで。明日もまだ食べるさかいな」
そういうと、急ぎ足で自室に向かった。いわれた燕は少しムッとしたようにいい返した。
「うちがどれがけ食いしん坊や思うてんねん。こないに仰山ことある牡丹餅、一晩で食べきれへんわ」
そして同意を求めるように鈴や恭一郎の顔を見た。二人は苦笑いのような表情をしていた。心のどこかで籐伍の言葉が必ずしも的外れではないと思っていたからだ。
燕が女性として大食いなことを二人はよく知っていたのである。
(四)
大坂での渦彦の生活が始まって早々と三ヶ月が過ぎていた。新たな社、少彦名神社での仕事や生活にも徐々に慣れていた。仕事がないとき渦彦は大坂の街を歩き回り、その地理と町々の特質を学んでいった。
大和の山育ちの渦彦にとって、大阪はとてつもなく巨大な街だった。
以前は京を大きな街と思っていたが、今では大坂が京を超えていると感じている。大坂の道は延々と続いていた。どこかで山にぶつかる京の道とは異なる点である。
渦彦は神人仲間で年の近い藤吉に御神宝探しのことを相談した。
「渦彦の探すもんは神社のお宝なんやろ。やったら骨董街にでも行ったほうがええで。そこでこんなお宝が出たら教えて欲しいって頼んどくんや。そしたら骨董屋が目ぼしい出物があったときに教えてくれるさかいな。そやけど金はかかるで」
渦彦と同じにまだ若い藤吉だったが、大坂生まれの為か遥かに世間をよく知っていた。
大坂に骨董街はいくつかあるが、一番大きい場所は西天満近くにある老松町だった。渦彦は同修町から老松町に日参した。骨董屋の店頭で「最近、神社の宝物のような出物はありませか」と、なんとも要領を得ない質問をして回ったのだった。
最初は上客と思って丁寧に相手をしてくれた骨董屋の主人たちも、要を得ない渦彦の言葉にただの冷やかしと思い、次第に真面目に相手をしないようになってしまった。それでも渦彦は老松町に日参した。今はここしか糸口がないという思いが渦彦にはあった。
邪険に扱われても老松町に通うことを辞めない渦彦を不憫に思ったのか、何軒かの骨董屋が少し話をしてくれるようになっていった。
そうした主人たちに渦彦は闇の競市についても聞いてみた。だが皆一様に競市については硬く口をつぐんだ。
そんなある日、渦彦が収穫のないまま老松町から少彦名神社に帰ろうとしたとき、ひと気のない裏通りで怪しい風体の男たちに取り囲まれた。皆一様に懐に得物を呑んでいるかのように、不自然な膨らみを見せていた。
「坊主、なんや盗人のこと色々聞き回っとるらしいな。何を探っとんのか、ちーと聞かしてくれへんか。痛い目に会いとうなかったら素直にしいや」
兄貴格の男が渦彦の前を塞いでいた。他の男は渦彦が逃げないように周りを囲んでいる。
渦彦は老松町に日参した成果がやっと現れたのかと一瞬思い、少しほくそ笑んだ。骨董屋からは実のある話が聞けなかったが、別のところから反応があったのだ。今は相手が盗人でも何でも行き会えたことが嬉しかった。
「神社のお宝や骨董品を盗む盗賊を探してんねん。あんたら盗賊の仲間か? もしそうなら盗品を売り買いするいう闇の競市のこと教えてんか」
実に直截な言葉だった。いわれた男たちの方が少し驚いた。
「聞いてどないすんねん。坊主、奉行所の下人か。やったらいてまうで」
動揺を隠すように、兄貴格の男が渦彦に向かって凄んで見せた。周囲を囲む男たちも懐から手を出して戦闘態勢をとっていた。
渦彦は前と周囲の男たちを順番に観察した。そして実に簡単な倒し方を考えた。
「こいつら、みんな弱いなぁ」
それが渦彦の偽らざる感想だった。このうちの何人かを痛めつければ何か聞き出せるだろうかと思った。だがこんなことに先祖伝来の蹴速術を使えば、死んだ父や大和の兄に叱られるかしれないという畏怖の方が脳裏に浮かんでいた。
「盗人のこと話してもらうで。手加減はするさかい、なるべく痛うないようにするわ」
渦彦の言葉に男たちは逆にいきり立った。
周囲を囲む男たちが間合いを詰めようと一歩前に出たとき、誰の眼にも止まらぬ速さで渦彦は兄貴格の男の足元に沈み込んでいた。そして左右の手刀で踝を打った。
この攻撃で兄貴格の男の足首が壊れた。これで逃げられることはないと思った。
後は容易かった。まずは得物の匕首を持つ二人の男に向かって、掌底で肘を打って関節を外した。これでもう刃物の攻撃はない。本人たちも唖然とするうちに匕首が地に落ちていた。
残りの男たちは素手だったので、なるべく痛くないように投げ技にした。一見優しく撫ぜたように見えたが、一瞬の後に三人の男がもんどり打って大地に叩きつけられていた。
ここまでに要した時間はほんのわずかである。
全てを終えた渦彦は、大地に叩き付けられた一人の男の腹に蹴り上げた踵を落としていった。男は声も上げられず唸ることしかできなかった。
倒れたり蹲ったりしている六人の男たちを渦彦は冷静に観察し、誰が一番話せそうかと思った。やはり最初に倒した兄貴格の男がいいと思った。
「さあ、盗人のこと話してもらうで。何でもええんや。盗人が開くいう闇の競市はどこでやってるんや。次はいつ開かれる。それを教えてくれたらもう手荒なことはせんさかい」
何度も立ち上がろうとするがすぐに転んでしまう兄貴格の男に、渦彦はいい聞かすよう尋ねた。兄貴格の男は自分が何で立ち上がれないのか理解できないようだった。
何度目かに転んだ男は、赦しを乞うように渦彦に叫んでいた。
「ちゃうねん、わいらは盗人やあらへん。この辺りを締めとる地廻りや。最近けったいな小僧がよう来るいう苦情があったさかい、締めとかなあかんいうことになったんや。それこそ盗人の下調べかもしれん思うて」
それだけ叫ぶと男は再び立ち上がり損ねてひっくり返った。
声を聞きながら渦彦は失望感に苛まれた。盗人ではなかったのかと。
裏通りではあったが、騒ぎを聞きつけた住人が何人か門口から覗いていた。道の両端からも通行人が立ち止まって様子を伺っている。皆一様に関わりにならないように距離をとっていた。だが多くの人間にこの戦いを目撃されたのは間違いなかった。
渦彦は父からの禁訓である「蹴速の技を見せるなかれ」という教えを思い出していた。「まずいな」と感じた渦彦は、倒れている男たちには見向きもせずに、その場から走りだしていた。
渦彦の行く手にいた人々は慌てて左右に避けた。その間を疾風の速さで渦彦は駆け抜けていった。後には呆然と渦彦の後ろ姿を見送る人々と、通りに転がっている六人の地廻りが取り残されていた。
渦彦は走りながら、「しばらくは老松町には近寄れへんなぁ」と折角掴みかけた探索の糸口を失ったことを悔やんでいた。
それからも渦彦は少彦名神社での仕事をこなしながら、次の探索の糸口を考えていた。別の骨董街に行ってみようかとも考えたが、老松町の一件が伝わっているかもしれなかった。地廻りが仕返しに自分を探しているかもしれない。そうなると少し厄介になる。
そんな考え事をしながら少彦名神社境内の掃き掃除をしていた。
少彦名神社の境内には銀杏の木が多くあった。そのため舞い落ちる病葉が多い。秋になればきっと黄色い布を敷いたような見事な景色を出現させるだろう。それは徳陀子神社の風景に少し似ているかもしれないと思った。
掃除をしていると小さな物体が飛んできた。普通なら気が付かない死角からだった。
渦彦はその物体を気にするでもなく、わずかな身のこなしだけで避けた。するとまた死角の方角から物体が飛来した。それも気付かぬふりで避けると、その死角方向に声をかけた。
「どなたか知りまへんけど、掃除の邪魔になるんで止めてくれまへんか」
死角の方向を見ると、書生風の男が社殿前の石段に座っていた。さっきまでは誰もいなかったはずだが、いつからそこにいたのだろうと少し不思議に思った。
男は手に炒り豆を幾つか持って、ぼりぼりと食べている。さっきからの飛来物はその炒り豆のようだった。
だが炒り豆を投げたにしては距離がある。軽い豆では届かないだろう。
「すまんすまん。あんまり美しい掃き姿だったんでね、少し乱してみたくなった。当てるつもりで飛ばしたんだが、見事に避けられてしまったね。しかもこちらに悟られないように。君はここの神人かい? それにしては見事な体捌きだ」
男はその言葉が終わらない内に、指に編んでいた炒り豆を親指の動きだけで撃ち出してきた。
「指弾」と思った瞬間、渦彦の頬のそばを炒り豆が通過して行った。
今の炒り豆も確かに避けたはずだったが、肌を擦りそうな位置を通過している。炒り豆の速度が渦彦の目算より格段に速かったのだ。
「また外れたか。今度こそ当てるつもりで撃ち出したんだが、凄いねえ」
男は石段で立ち上がると、尻の埃を払いながら社殿の中に向かって声をかけた。
「御隠居、多分彼で間違いないと思いますよ。老松町の地廻りを一瞬で叩きのめしたという若者は。実際にやらなくても今の捌き方だけで大体強さはわかりました」
男の言葉に誘われたように、社殿の観音扉が大きく左右に割れた。その奥には身だしなみの上品な老人が立っていた。老人の後ろの暗がりには少彦名神社の宮司も控えている。
老人が社殿の縁側に出てくると、入れ替わるように男が下がって老人の後ろに並んだ。
「仕事の邪魔してすまなんだな。実は人を探しとってな、それがお前さんらしいと聞いて先生に目利きしてもろうたんや。もちろん宮司はんのお許しは貰うてるよって」
渦彦が老人の言葉を聞きいていると、暗がりにいる宮司が頷いていた。
「どないな人をお探しか知りまへんけど、人間違いやおまへんか。わいはただの修行中の神人やよって」
そういって深くお辞儀をすると、再び掃除に戻ろうとした。
「名は巨勢渦彦はんやったかいな。大和の出で京の五條天神宮からの預かり神人と聞いてる。まあ、そないに警戒せんでもよろしい。わては老松町の地廻りとは無縁やから。ただあんたの強さと、大坂に来はった目的に少し興味があるんや。宮司はんにもお許しを得たよって、ちょこっと話ししてんか。あんたはんにもええ話や思うで」
老人はニコニコしながら、渦彦を宥めるように語った。後ろの宮司が続いて話だした。
「渦彦はん。わても初めて御隠居様に聞いたんやけど、ほんまにえらい強いらしいなぁ。御隠居様が渦彦はんの強さと盗人探しに興味持ちはったようで、どうしても話してみたいとのことや。これも仕事や思うてお相手してんか。何せ御隠居様はうちの元氏子総代やよって。寄進も仰山ことしてくれてはるんや」
宮司の少しおもねるような言葉に、渦彦は可笑しくなった。それに自分に興味を持ったというこの御隠居は誰なのだろうかと思った。身なりの良さやその口ぶり、宮司の下にもおかない態度からかなりの大物だと思えた。
「わかりました。宮司はんのお指図となると断れまへん。お話しさせていただきます。ですが、一体何を話せば良いのですか。わいには話すようなことありまへんけど」
老人に返答した。ただ斜め後ろにいる男には注意を怠らなかった。話している間、男はずっと指弾の構えを密かにとっていた。渦彦の注意が男から逸れたら、即座にまた炒り豆を撃ってくるように思えた。
いや炒り豆ならよいがもっと別の物を撃ち出されたら、避けられないかもしれないという恐怖があった。
拝殿奥にある大きな祈祷部屋で、渦彦達四人の男が座っていた。
渦彦と老人が正対し、渦彦の斜め後ろに宮司が座り、老人の斜め後ろに男が座ってる。宮司が老人を紹介するように話し始めた。
「こちらは両替屋や酒蔵で高名な鴻池御本家の御隠居様や。少彦名神社の前の氏子総代やし、今度の秋の祭礼の願主でもあられる。うちの神社も季節ごとにあんじょうしてもろうてる大恩あるお方や」
続いて老人の後ろに控える男を紹介しようとしたが、宮司は男の正体をよく知らなかった。御隠居の付き人か護衛と思っていた。それを察したように御隠居が話だした。
「改めて名乗るけど、わては前の鴻池の主人、鴻池善右衛門や。今はもう隠居してるけどな。そしてこちらは国学者の秦天河(はたのあまかわ)先生。まだお若いが俊英の学者はんや。江戸のお方やけども、今は大坂に寺社の研究にいらしてはる。先生は学問だけやのうて武術も修めてはるんで、渦彦はんの強さの目利きをお願いしたんや。まさかあんな技をお持ちとは知らなんだけどな」
御隠居、鴻池善右衛門は少し感心したようにいった。
国学者の秦天河と紹介された男は、少し微笑みながら渦彦に頭を下げた。だが渦彦から注意を外していないことは確かだった。
渦彦はずっと天河からの殺気にも似た探索の気を感じていた。その気が緊張を誘うのか、じわりと冷や汗をかいていた。まるで猛獣と対峙しているように感じている。
そんな渦彦には無頓着に善右衛門は話始めた。
「実はわては隠居後の楽しみで、骨董やら歴史の遺物なんぞを集めてるんや。金目の骨董やないで、この国の秘密を解き明かすような歴史の逸品を探してる。こちらの天河先生は収集の相談相手でもあられる。それで大坂中の骨董屋にも色々と伝手があってな、この間の老松町での地廻りとの一件も耳に入ってきたんや。神社のお宝を探してるどこぞの若者が、地廻り六人を一瞬で叩きのめしたいう噂をな。興味を惹かれたわては方々に人をやってその若者を探したんや。そやけどなかなか見つからへんかったわ。そしたらつい先日、それらしい若者を同修町あたりで見かけたいう骨董屋がおったんや。灯台下暗しとはこのことやな。わても長いことこの少彦名神社の総代してたから馴染みもあるよって、まずは宮司はんに人探しの相談を持ち掛けた。そしたら話とよう似た謂れを持つ神人がいてるといわはったんや。わての探す若者かどうかは解らんけど、実家の神社の神宝を探す若い神人がいてるとな。話がぴったりやよって、今日天河先生に目利きをお願いしたんや」
ここまで一気にしゃべった善右衛門は、少し息をついて前に置かれた茶に手を伸ばした。善右衛門はどうやら宮司から渦彦が大坂に来た経緯を聞いているようだった。
渦彦は改まって、まず宮司に詫びた。
「宮司様。折角ご好意でここに置いてもろうてるのに、地廻りなんぞと諍いを起こしてすみまへん。確かに御隠居様がいわはるように、先日老松町で喧嘩ごとをしました。ここに危ないことを持ちこまへんいう約束を破ったことになります。どうぞご処分してください」
渦彦は宮司の方に向き、両手を畳につけて謝った。謝られた宮司は少し困った顔をした。
「ええんや、そのことはもう宮司はんも怒ってへん。ただほんまに渦彦はんがえらい強いんやいうことにびっくりしてはるだけや」
なぜか宮司に代わって善右衛門が渦彦の謝罪に答えてきた。
宮司はただ「そういうこっちゃ」とだけ呟いた。何かを言い含められているようだった。
「ただなぁ、わてが渦彦はんを見つけたように老松町の地廻りも渦彦はんを見つけるかも知しれへん。それでここに押しかけてきたら、えらいことになると心配されてるんや」
善右衛門の言葉に宮司は大きく頷いた。
「それで宮司はんは、ほとぼりが冷めるまで少しここを離れた方がええんちゃうかとお考えのようや。それでどないやろ、しばらくわての隠居所にきてくれへんか。元々実家の神宝を探してるいう話も面白い思うたんや。それに渦彦はんほど強かったら護衛もできるさかいな。もうすぐ天河先生がいてへんようなるよって、わても安心できるいうもんや」
善右衛門の言葉に初めて天河が口を開いた。
「私は研究でもう大坂を離れるのでね。君はその後釜ということだよ」
天河はこれで荷が降ろせるというように渦彦に微笑みかけた。
渦彦は天河から発せられていた猛獣のような殺気が消えていることに気がついた。今は温厚な兄、綿津見のような優しい気が満ちている。よく見ると天河は兄と同じぐらいの年頃でしかも物柔らかさが似ていた。
「君はずっと私の殺気に反応していたね。それは大変に良いことだ。敵はどこから来るか解らない。それだけに気を読める力は武術以上に役に立つ。君ならば安心して御隠居をお願いできる。何せ私の研究の大切な援助者なのでね、何かあっては困るんだよ」
天河は渦彦が思わず魅入られるような笑顔になった。さっきまでの得体の知れない猛獣と同一人物とはとても思えなかった。
ここで割って入るように宮司が渦彦と善右衛門にいった。
「渦彦はん、御隠居様のとこに行くんはいっときのことや。渦彦はんの身分は少彦名神社の神人のままやで。ほとぼりが冷めるまでの後隠居様への『一時貸出し』やな。京の天神宮はんとの約束もあるよって、先のことは心配せんでもええ。それでよろしおますな」
宮司は妙に強気で善右衛門に念を押した。
実は宮司と善右衛門の間で、渦彦を貸出すにあたってかなり高額の寄進が約束されていたのだ。天河が渦彦の品定めをしている間に宮司と善右衛門の間で取り交わされた約束である。宮司にとって渦彦は文字通り「金の卵を産む鶏」になっていたのだった。
そのあたりの事情をよく知らない渦彦は、あれよあれよという間に自分の運命が変わっていくことに唖然としていた。何より御隠居のところに行ったら、闇の競市の探索ができるのだろうかという不安がよぎった。
「私が大坂に来たのは、寺社のお宝や骨董を売買する闇の競市を探索するためです。御隠居様の元に行くんは構いまへんが、この探索は続けますのでそれはご承知ください」
全員に宣言するように声を上げた。
渦彦の言葉に、御隠居が「勿論かまへんで」と頷いた。しかも渦彦にとってそれ以上の答えが宮司から返ってきた。
「元々わてに闇の競市の話をしてくれはったんは御隠居様やからな。そこにおったらまた競市の話があるかもしれへんで。渦彦はんにとっても一番の近道とちゃうか」
あっけらかんとした表情の宮司が告げた。
「なんでそれを最初に教えてくれへんかったんですか」と思い、思わずムッとした表情で宮司の顔を見た。
だが、老松町の事件で途絶えたと思われた探索の糸が再び繋がったのだった。これは思いもしなかった幸運である。渦彦は心の底からこの幸運に感謝した。
第二幕 閻魔の市襲撃
(一)
籐伍は河原崎から託された探索指示を読み込み、鬼没盗に関する探索を進めようとした。
気がついたのは盗まれた骨董品に共通する妙な類似点だった。
籐伍も日本の歴史に知識が深いわけではないが、盗まれた骨董品には歴史の一時期と妙な因縁があるように思われた。盗まれた骨董品がどこかで飛鳥時代と関連があるのではないかと思えたのだ。
盗まれた骨董品自体は別の時代に作られたり複製や修復されているものもあったが、その内容が飛鳥時代に関連しているのかも知れないと思えた。
飛鳥時代とは大和の飛鳥地方に都が置かれていた時代で、一般的には推古天皇から持統天皇に至る時代といわれている。歴史に詳しくない籐伍も、「聖徳太子」「大化の改新」「壬申の乱」といった人や事件が思い浮かぶ時代だと理解している。
そして肥前屋から盗まれた拓本の掛け軸も、拓本自体は室町時代あたりのものだが、その内容が聖徳太子に関連しているらしかった。肥前屋の主人や掛け軸を売った売主によると、聖徳太子のある秘密の言葉が拓本で写されていたというのである。
他の鬼没盗に奪われた骨董品もどこかその時代に因縁があった。それは飛鳥時代の仏像の複製であったり、飛鳥京にあった木簡だったりしたのだ。
ただあまり関連がないのではと思える盗難品も一点あった。それは楠木正成が筆写したという古文書だった。
それが何を写した文書かは最初よく解らなかったが、どうも四天王寺の極秘文書らしいということが判明した。四天王寺は飛鳥時代に聖徳太子が建立した寺である。その寺の極秘文書となると、どこかで飛鳥と繋がっているのかもしれなかった。
「飛鳥に関わるお宝を盗んでるなんて、どこかの寺か神社の奴らか? そんなもん今更盗んで何の役に立つんや」
少しだけ因縁が見えたかに思えたが、因縁の先はまだまだ解らなかった。
それよりも籐伍が河原崎の私見の中で一番注目したのは、不定期に行われるという骨董品や表で売買できないお宝の「闇の競市」の存在だった。
籐伍にはそうした闇社会の知識はなかったが、定町廻りの河原崎はその存在を知っていた。そして鬼没盗の盗品の換金先として、闇の競市があるかもしれないと着目したのだ。
籐伍は「そんな競市があるんか」と世間の裏を見た気がした。
だがこの河原崎の私見に籐伍はあまり同意できなかった。それは河原崎自身がいった「鬼没盗は金目当てとは思えへん」という意見に、籐伍も共感していたからだった。
金目当てでないのなら、それを換金する競市とは無関係ではないのかと思えた。籐伍はむしろ次に鬼没盗が狙う骨董品は何だろうかと考えていた。それが予測できれば鬼没盗の先を取れると。だがその答えは要として予測できていなかった。
しかし闇の競市というものが存在するのなら、その競市に鬼没盗の狙うお宝が出品される可能性はある。籐伍は処分先としての競市よりも、強奪先としての競市に興味を持った。
広い大坂で飛鳥時代に関連する骨董品を探すのは大河で砂粒を探すようなものである。それよりは表で売り買いできない骨董品やお宝が集まる闇の競市の方が、鬼没盗の狙うお宝に近いのではないかと思った。
「外れてるかもしれへんけど、淀川で砂粒探すよりもよっぽどええわ。それに闇の競市に押し込む鬼没盗の姿は舞台の上でも映えるしなぁ」
父念十郎がいった「おもろい筋立て追ってみい」という言葉を思い出していた。どうせ追うなら面白い方を追ってみようと思った。
それに河原崎の見立てが全く外れているとも思えない。奉行所内での河原崎の評判を聞くと、「腕利き同心」というひと言に尽きた。その河原崎が全く的外れの目星を付けるとも思えなかった。
「どっちにしても、鬼没盗に一番近いんは競市かもしれへん」
そう方針を決めた籐伍は闇の競市の情報を当たり始めた。奉行所で闇の競市に心当たりがないかを聴取すると同時に、「盗人のことは盗人に聞くんが一番ちゃうか」と思った。
籐伍に盗人の知り合いなどまだなかったが、元盗人なら身近にいた。父が手下にする御用聞の金蔵と銀蔵の兄弟である。
彼らは十数年前に、父念十郎がまだ吟味方与力の時代に捕縛した盗賊団の若い下人だった。彼らの父親が盗賊団の一人だったので否応なしにその下人にされていたのだ。
兄弟を不憫に思った念十郎は、彼らを手下として使い更生させることにしたのだった。下人とはいえ盗賊である。身のこなしの軽さと得物使いはうまかった。だが念十郎は彼らに得物を捨てさせた。兄の金蔵には十手術を、弟の銀蔵には棒術を教えた。そして探索のために裏の世界の情報収集に当たらせたのである。
諸色方大番役となった念十郎が盗賊探索に関わることはなくなった。今は市中の経済分析の基となる情報や噂を集めさせている。
籐伍は西町奉行所のある松屋町筋の団子屋で牡丹餅を買った。そして京伏見からの三十石船が着く大川端の川港、八軒家近くにある金蔵、銀蔵の住む長屋に向かった。
籐伍の突然の来訪に兄弟は少し驚いた。主家の惣領息子が手下の家に来ることなどまずない。用があれば呼びつけられるのが普通だ。
だが籐伍はそうは思っていなかった。彼らは父の手下であり阿刀家の下人ではない。その彼らに物を頼むにはそれなりの礼が必要だと思ったのだ。
「すまんけど頼みごとがあんねん。勿論これは父上の指図やない。わいの願いごとや。わいが今担当してる鬼没盗の探索に力貸して欲しいねん。父上からの仕事があるやろうけど、どうしても二人の力が必要なんや」
そういいながら頭を下げると、持参した牡丹餅を二人の方に押しやった。まだ無禄の自分にはこれが精一杯だといった。
探索の報酬が牡丹餅とは、まるで桃太郎が猿、雉、犬に渡す吉備団子のようである。二人は籐伍の子供のような発想に思わず笑い出してしまった。
「ぼん、自分とこの御用聞にこんなことしたらあきまへん。殿さんからはちゃんと銭もろうてるさかい、何でも指図してください。それに殿さん、いうてはりましたで。殿さんが隠居したら新しい殿さんはぼんやから、お前らが苦労せんようにしっかり探索のイロハを教えたってんかって」
そう金蔵がいうと、追いかけるように銀蔵が言葉を繋げた。
「殿さん、ぼんは世間知らずの芝居好きやから苦労するやろうけど、よろしゅうに頼むっていわはって、臨時の銭もくれはりましたわ。ほんまにええ殿さんや」
「あほっ、それいうたらあかんやつや」と、金蔵は弟の頭を叩いた。
籐伍は父の手回しにびっくりした。いずれ二人に頼むだろうと見越していたのだ。まだまだ自分は父の思慮には追いつけていないと思った。
籐伍は鬼没盗を追うために闇の競市を探したいと語った。盗賊や裏の世界に伝手のある二人に何か知らないかと質問した。
二人はしばらくの間頭を絞っていたが、頷きあって首を振った。
「昔にそんな噂を聞いたことはあるけど、今はとんとありまへん。それに最近は殿さんの商い絡みの探索ばっかりやから裏の方は少し疎いんで。そやけどほんのちょこっと時をいただけたら、昔の伝手に聞き込みしますさかい任せてください」
金蔵がそう請け負うと、銀蔵も嬉しそうに続けた。
「ほんまはわいらも盗人の探索の方が性にあってんるんや。殿さんの今の仕事難しゅうてようわからへん。ぼんが吟味方になってくれて嬉しいわ」
銀蔵は本当に嬉しそうに笑っていた。
「ほなら、よろしゅうに頼むは。何でもええからわかったことはいつでも知らせてんか」
籐伍はほっとしたように立ち上がると、兄弟の長屋を後にしようとした。外に出た籐伍を追っかけるように、銀蔵が戸口から顔だけを突き出してそっと囁いた。
「これ覚えといてくらはりますか。わいら二人とも甘い牡丹餅よりも酒の当てになるしょっぱい味噌田楽の方が好きでっさかい、次の土産にはぜひお願いします」
銀蔵の頭の上で金蔵も頷いていた。大人への手土産は牡丹餅ではあかんのやと、籐伍は初めて知った気がした。
鴻池善右衛門の隠居所で渦彦がする家人仕事はほとんどなかった。もうすでに優秀な女中や奉公人が多数いたからだ。渦彦が当面任せられた仕事は、御隠居が出かけるときの護衛と、天河の助言で手を尽くして集めたという国史関連の膨大な書物の整理だった。
その天河は渦彦が隠居所に移ってくるのと入れ替わるように、次の研究地である丹後に向かって旅立っていった。天河は別れ際に何かを確認するように聞いてきた。
「渦彦君のご実家は大和と聞いたが、どのあたりなんだい。もしかしたら葛城かい」
天河は渦彦の詳しい事情は御隠居から聞いていないようだった。あの日は渦彦の強さを確認する為だけに同行していたらしい。
「その通りですが、どうしてわかりはったんですか」
渦彦は天河を不思議な人だと思った。何かを聞かなくても全てを見透かすような恐さを感じさせていた。
「やっぱりそうか。葛城あたりは飛鳥時代、古代氏族である巨勢氏の本貫地だからね。君はその古代氏族の末裔なのだろう。ならば君とはまた会うことになるかもしれない。私はこの国を造った海人族の研究をしているのだが、その先には巨勢などの氏族たちもいる。早くそこまで辿り着きたいものだ」
夢見るような表情で天河が語った。
「いったい何のために、そんな昔のこと研究してはるんですか」
ちょっと不思議な気分で渦彦が尋ねた。天河は悪戯を見つけられた子供のように、はにかんだ表情になった。
「実はそれが私にもよくわからない。ただこの国の始まりが知りたいんだと思うよ。いや、始まりの時代にあった正しさや夢というべきかな。この国は今、決して太古に夢見られた姿ではないんだ。それを糺すための歴史の真実を探しているのかもしれない」
渦彦は天河の語る言葉がほとんど理解できなかった。やっぱりこの人は不思議な人だと思った。
ただ渦彦の日々の仕事の大半を占める書物の整理は、天河が御隠居に助言して集めさせたものらしい。渦彦はこの書物を整理し、目録を作るように御隠居に指図された。そのためには書物の中身もある程度読まなければならなかった。
いかに神社育ちの渦彦でも、天河のように国学の基礎があるわけではないのでこの作業には苦労した。否応なしに歴史の知識も必要になってくる。
神人修行のために京の五條天神宮に行くまで、学問を父や兄に学んだ日々を思い出した。あのときもっと真面目に歴史を学んでおけばよかったと、今更ながら悔やまれた。
そんなある日、まだ隠居所の皆が起きてこない早朝に、渦彦は裏庭で蹴速術の修練をしていた。体をほぐす程度の修練ではなく、細かい技の確認を実践さながらに行っていた。それは目にも留まらぬ疾風の速さを持つ体捌きだった。
それを見ている人物がいた。
他ならぬ御隠居である。御隠居は老齢だし当然体術などできない。だが一点、自分の気配を透明にすることができるようだった。それは長年の命賭けの商いの中で獲得した、生き残るための能力だったのかもしれない。気を感じ取る渦彦が、この御隠居の気をこの時は見逃していたのだ。
渦彦がハッと気がつくと、渡り廊下に佇む御隠居の姿があった。
「もう起きられてはったんですか」と、気がつかなかった自分を恥じるように、渦彦は御隠居に向かって挨拶をした。
「なかなか凄いなぁ。何がどう凄いんかはようわからへんけど、凄いということだけはわかる」
御隠居は渦彦の蹴速術をそう評した。
「天河先生が『彼は強いですよ』といわはった言葉が思い出されるわ。疑うてたわけやないけど、今はそれがほんまやとわかった」
御隠居は何かを納得するように頷いていた。そして褒美を与えるように語り出した。
「今度な、渦彦に新町遊廓に行ってもらおう思うてるんや。遊びやないで、遊廓で秘密の寄合があるよってその護衛にな。ほんまは自分で出席したいんやけど、顔を見られるわけにはいかんので代理人を出すことにした。渦彦にはその代理人の護衛を頼むは。まぁ護衛というよりも見張りやけどな」
御隠居の言葉に渦彦は首を傾げた。商いの寄合に護衛がいるのかと。しかも見張りとはどういうことなのだろうと思った。
だが御隠居はにやりと笑って訝しむ渦彦を見た。
「新町の寄合は表にはいえへん集まりや。そやから護衛も見張りも必要なんや。多分渦彦が一番行きたいと思うてる集まりやで」
渦彦はここで初めて気がついた。その寄合とは闇の競市ではないのかと。
渦彦がそれをいいかけると、御隠居は口に指を立てて言葉を止めさせた。世に御法度の闇の競市に、豪商鴻池の御隠居が参加してはいけないのだと気がついた。
渦彦は言葉を飲み込んで「承知いたしました」とだけ応えた。
代わりに、思わず禁じ手の脚技「稲妻脚」を空に向かって放った。
老松町でも渦彦は手技しか出していない。だが本来の蹴速術とは文字通り、蹴速=神速の蹴り技を主力とする闘技なのである。手技はあくまで補助技でしかない。渦彦はまだ本当の強さの片鱗も見せてはいなかった。
同じ頃、金蔵と銀蔵が密かに籐伍のもとを訪れていた。それは二人にとっても初めて念十郎に報告しない行動である。
「ぼん、掴めましたで。例の競市の噂」
何か胸騒ぎがしていたのか、籐伍は朝から奉行所の道場で中条流平法の稽古に汗を流していた。籐伍は中条流平法が性に合っているのか上達がめざましかった。既に目録まで進み、皆伝まであと少しというところである。
「わかったんか、盗人どもの競市が。いつや、いつどこであるんや」
流れる汗も拭かず、籐伍は詰め寄った。すぐにでも競市に乗り込みそうな勢いだった。
勢い込む籐伍を宥めるように、金蔵があらましを説明し始めた。
「裏の世界でもなかなか競市の噂は掴めまへんでしたが、意外な所からその話を聞き込みました。殿さんの御用である廻船問屋に聞き込みしてたら、そこの主人が秘密の骨董品の市に呼ばれてるいうこと、吐きよったんですわ。なんでも紹介者があって信用ある分限者にしか声かけん市らしゅうて、『閻魔の市』と呼ばれてる外には絶対漏れへん競市やいうことです。それを聞き出しましたよって」
金蔵はあっさりと「聞き出した」といっているが、実際は半分の脅しと半分の目溢しを餌に主人を懐柔したのだった。この辺りは情報収集を仕事とする金蔵の常套手段だった。
「今月の晦日に、新町遊廓で御贔屓ばっかりを呼んでの秘密の催しがあるらしいんやけど、どうやらそこで趣向の一つに閻魔の市も行われるようです。勿論催しには招待客しか入れしまへんけど、その前やったら遊廓には入れるかもしれまへん。捕り物やのうて、ぼんおひとりのお遊びやいうことで。遊廓の方も奉行所と諍いを起こしとうはないんで、遊びに来た与力を追い返すことはしまへん。それで何とか遊廓の中には入れる思います。あとは中に入ったぼんの腕ひとつや」
金蔵がニヤニヤしながら籐伍の顔を覗き込んだ。金蔵は籐伍がまだ遊廓に行ったことがないだろうと思っていた。もしかしたら女の体もまだ知らないかもしれない。その籐伍が遊廓内でうまく隠密の探索ができるのか、興味深々に思っていた。
「ぼん、下見に一度新町に行かはりますか。わいらお供しまっせ」
銀蔵も隣で何度かうなずいていた。ここはなんとしても皆で新町に繰り出さねば、お役目が果たせないといいたそうだった。
「あほっ、新町なんぞに雁首揃えて行けるかい。芝居でも新町には忍んでいくもんやと相場が決まってるわ。わいも芝居研究のために忍んだことは何遍かあるで。父上や姉上らには内緒やけど馴染みもいてる」
籐伍は実にあっさりと言い切った。
兄弟はその言葉に唖然とした。行動が子供だと思っていた籐伍が、そっち方面だけは既に大人だということに妙な感動を覚えた。
「それよりも晦日の手配や。新町にはわい一人で上がるけど、周りは固めなあかん。奉行所から何人か小者を出してもらうさかい、お前らは小者を指揮せえ。新町に集まる分限者の身元の確認と、もし新町から逃げるも者がおったらしょっぴくんや。特に来る分限者がわかったら次に鬼没盗の押し込む先がわかるかもしれへん。みんな骨董好きの金持ちやからな」
籐伍は一気に今回の探索のあらましを二人に指示した。それは実にすっきりとした方針だった。今回が与力として初めての探索指揮とはとても思えない手慣れたやり方である。
二人は籐伍が子供なのかもう大人なのか、よくわからなくなっていた。
(二)
あまり気乗りしない様子で、籐伍は遊女愛染の体を弄っていた。気が乗らないというよりも心が別のところにあった。それはこの遊廓「月読楼」の別棟で行われているという秘密の催しと、遊廓の周りに伏せている金蔵、銀蔵や小者たちのことである。
「みんな、あんじょうやってるやろか」
そう思えば思うほど、愛染を弄る手にいつもの真剣さがなかった。
「どないしはったん。心ここにあらずやわ。もううちにあきはったん」
愛染は拗ねたように自分の体からお座なりな手を押し除けた。
「女の扱いは難しいなぁ」と感じながら、これも修行だと籐伍は観念した。
戯作を書くにも探索をするにも、女の扱いが第一歩だと思った。特に今夜は愛染の協力が必要だった。
「愛染、今日はこの廓でなんやら催しがあるて聴いてるけど、なんとかそれをちょこっとでも覗き見することはできへんやろか。今度書く戯作のために於大尽の秘密のお遊びを見てみたいんや」
愛染は籐伍のことを芝居好きのぼんぼんだと思っている。奉行所の仮役与力になっていることは知らなかった。
「別棟へは今日はいったらあかんていわれてるさかい、なんぼ主さまの願いでも無理やわ」
困ったようにいった愛染だったが、少し考える振りをしてから怪しい表情になった。
「せやけど、あっちの棟に入ったところに道具や布団を置いてる部屋があんねんけど、そこまでやったら物探す振りして行ってあげてもええで。覗きはでけんでも、声ぐらいは聞こえるかもしれへん。そこでこの間、廓の小女と客の付き人がしけ込んでて、えらい騒ぎになったことがあんねん。隣の部屋でしてる声を聴いてて興奮したんやて。そこで盗み聞きしながらやったら、主さまのこっちも元気になるんちゃうの」
そういいながら、愛染の手が籐伍の股間を弄ってきた。愛染は今夜の別棟の催しを単純な男女の狂宴だと思っていた。
愛染には露出の癖があるらしく、籐伍と交わるときにもわざと少し襖や窓を開けて、自分たちの声を外に聞こえるようにしていた。籐伍はそんな愛染の行為を芝居のネタになる面白い癖だと思って、あえて止めることはしなかった。今は別棟の部屋で狂宴の声を聞きながら、見つかるかどうかの興奮で行為に臨みたいようだった。
籐伍も迂闊に別棟に入ってつまみ出されるより、愛染の癖に応じたふりをした方が催しに近づけるかも知れないと思った。
「よし、ええで。他所様の声聞きながらやったらわいも元気出るかも知れへん。しけ込んでみよか。これも戯作のためのええ経験や」
籐伍がそう答えると愛染は瞳を輝かせた。愛染の方が少し興奮しだしているようだった。
二人は怪しまれぬよう、欲情でもたれかかるように装いながら廓の中を移動した。そして人目がないことを確認してから、別棟すぐにある道具部屋にそっと入り込んでいった。
部屋には明かりや外窓がないので暗かった。だが不思議に隣部屋の音がよく聞こえていた。
最初隣と思った音は実は隣ではなく、間に二部屋ほど挟んだ大広間の音のようだ。何かの寄合を進行する仕切り役の男の声が聞こえてきている。
声の聞こえを不思議に思った籐伍は、少し隙間のある天井板に気がついてずらしてみた。そこから天井裏を覗き込んでみると、天井裏にいくつかの樋管のようなものが走っていた。
「何だ」と思ったが、どうも樋管が大広間の音を伝えているらしい。
籐伍はそこで昔読んだ遊廓の話を思い出した。遊廓には他の部屋を監視したり、覗くための仕掛けがあるというものだ。
それは遊女や客の痴話話を確認したり、足抜けの相談などを盗聴する仕掛けである。あるいは秘密の会合などを盗み聞くこともあるらしい。本当にそうした仕掛けがあるのかどうか籐伍も知らなかったが、この道具部屋はそうした目的に作られたのかもしれない。
だから普段は客や遊女が使わない道具部屋にしているのだ。小女と付き人がここにしけ込んでいたのも、人目につかない場所を探して行き着いたのかもしれなかった。
部屋に潜み声を聞いていると、大広間では次の出し品が紹介された。
「さて次なる閻魔の市の競り品は若狭より齎されました、人魚の遺骸やということです。まずは現物をじっくりとご覧ください」
進行役の男の声に続いて、「おおっ」というどよめきとも唸り声とも思える声が響いてきた。籐伍はその声から、大広間の光景を想像した。どうやら閻魔の市が順調に進行されているようだった。
籐伍が必死に聞き耳を立てていると、愛染が音を立てないように敷布を延べた。そこに座り込むと自分の襦袢の腰紐をスルスルと解いていった。
籐伍の耳元にそっと唇を寄せると、「主さまはよう」と囁いた。愛染の右手はもう籐伍のふんどしの中に手を差し込んでいる。愛染は自分の興奮をもう抑えられないようだった。
「もうちょっと待ってんか。あっちの部屋でお祭りが始まったらこっちも始めようや。それまではじっくり準備しよう」
そういうと片腕で愛染の肩を抱き、もう一方の手で愛染のもう濡れ始めている女陰を優しく触りはじめた。籐伍は意識を大広間の声に集中させながら、愛染の機嫌も取らなければならなかった。
不思議な均衡を保ちながら閻魔の市を盗聴することに苦闘した。
声から想像する光景を思い浮かべながらも、だんだんと快楽に流されそうになる自分を必死に押しとどめようとした。
籐伍が別棟の物置部屋に潜む少し前、渦彦は月読楼近くの茶屋で御隠居の代理として閻魔の市に参加する清兵衛と落ち合っていた。
清兵衛は鴻池の奉公人ではなく、自称御隠居の弟子だという酒問屋の主人である。商売でも骨董でもいろいろと世話になっているらしく、御隠居を随分と尊敬しているようだった。かなりの野心を持った人物らしく鴻池に匹敵する商人になりたいと考えていた。
御隠居もそれを知っており、その野心を面白いとも思っている。
だが能力が高く野心のある人間はどこかで全幅の信頼は置けない。だから今夜の競市の代理人としても渦彦を目付にしたのだった。
御隠居にとって渦彦はわかりやすい人間だった。欲という点ではほとんどなくただ目的があるだけである。その目的に沿っている間、渦彦には信用がおける。清兵衛に欠ける信用を渦彦に補わさせているのだった。
「なるほど、御隠居様に聞いた以上に若いお方やな。せやけど今宵、競市の間は同等の相棒や。よろしゅうにお願いしますわ」
清兵衛は慇懃に渦彦に頭をさげた。
渦彦は清兵衛を不思議な気の持ち主だと感じた。闘気ではないが不気味な圧迫感があった。怖くはないが薄気味が悪い。自分を飲み込もうとする蛇を眺めている気分である。
「わいは骨董のことや金子のことは一切わかりまへんのでお任せします。ただある神社の御神宝を探しています。市でそれについてのご意見を伺うかもしれませんので、その折はよろしゅうお願いします。御隠居様より清兵衛どのの身の安全はきつくいわれておりますのでおまかせください」
それだけいうと、清兵衛に合わせるように深く頭をさげた。清兵衛は初めて微笑みながら急に砕けた調子になった。
「そないに堅苦しゅうならんでもええですわ。わてらは互いに半分信用と半分猜疑を持つ身や。あんたはんを見てすぐにわかったわ。こりゃわての手管には乗らんお人やなと。さすが御隠居様やで、わての人たらしでは無理な人選や。渦彦はんに少しでも欲があったらすぐに渦彦はんを取り込むんやが、それは無理のようやで。今宵はお互いの役目に専心しまひょ」
笑いながら清兵衛は酒に口をつけた。
「もうすぐここに月読楼からの迎えが来ますよって、それまではゆっくりしましょう。渦彦はんは今夜の市について何かいわれてはりますか?」
清兵衛は少し渦彦を覗き込むように語ってきた。
「いえ何も。骨董の目利きについては全て清兵衛どのに従うようにとだけです。ただどうしても裏の世界のことなので、清兵衛どのと落札品の安全は守るようにいわれました」
清兵衛は薄く笑いながら訂正してきた。
「順番があるんちゃいますか、守る順番が。一番に落札品、二番がわてや」
渦彦は「おっ」と思った。御隠居の指示はその通りだった。
「まあそれはよろしい。それよりも御隠居様には渦彦はんがえらい強いと聞きました。そやから今回はわても自分の護衛を用意せなんだ。それが誤りやったら困ります。二番目にしてもわてが安全やいう証が見たい」
清兵衛は徳利から酒を猪口に注ぎ直すと、一息に飲み干した。そして「どうや?」という表情をした。
渦彦は一瞬どうしようかと迷った。こんなところで蹴速術を披露する訳にもいかない。だが直ぐに、「あれ」を座興にやって見せようと思った。
「私も一杯いただいてよろしいですか」というと、清兵衛の前の徳利を取り上げた。そして徳利から酒を直接飲むように口をつけた。清兵衛の見る前で徳利の酒を口に含むと、徳利を卓に戻した。それは少し清兵衛から離した位置だった。
不思議そうに見守る清兵衛の前で、渦彦は突如口から酒を噴出した。それはまるで口から一条の糸が延びるように置かれた徳利に到達した。
「ぱきっん」という乾いた音ともに、徳利の首の部分が消失していた。正確にはくびれた部分が薄い刃物で斬られたように切断され、上の部分が後ろの壁に飛んでいた。
清兵衛は今何が起こったのかわからなかった。だが目の前の徳利上部がいきなり消失した。上部は後ろの壁にぶつかって下の畳に転がっている。
唖然とした表情で徳利と後ろに飛んだ上部、そして渦彦の顔を見返した。
「わいが子供の頃に覚えた水切りです。両手が使えんときには意外に役に立ちます」
それだけいうと口に残っていた酒を飲み込んでいった。
渦彦はまだ酒を飲んだことはなかったので、その味と初めての刺激に吐き出しそうになってしまった。咽せて何度か咳こみやっと息をついた。
清兵衛は何度も徳利と渦彦の顔を見ながら、何がおかしいのか笑い出してしまった。
「不思議な技を使うと御隠居様もいわはったが、何やねんこれは。奇術みたいな技やな」
半分呆れた表情で清兵衛は呟いた。だが渦彦が底しれぬ力を持っていることは理解した。「なるほど御隠居様が気に入る訳や」と変な納得もした。
場を取り繕うように清兵衛は渦彦に素直に詫びた。
「いや、疑ってすまなんだな。渦彦はんのこと頼りにしますよって、今夜はよろしゅうにお願いします」
上部の切れた徳利から猪口に注ぐと、渦彦に献杯をした。渦彦はさっき飲み込んだ酒の味を思い出して献杯は丁寧に断った。またあんなものを飲まされてはかなわないと思った。
そんな遣り取りをしている内に、約束の刻限がきたようだった。二人がいる茶屋に月読楼から「催し」の案内人が迎にきたのだ。
渦彦はとうとう闇の競市に臨めることに、心が早やった。父が死んでから数ヶ月、様々な苦労をしながらやっとここにたどり着けたという感慨と、失われた御神宝や父の死の原因にやっと近づけると期待したのだ。
清兵衛と渦彦は案内人に、新町遊郭の中心部にある月読楼別棟にある大広間に案内された。そこは遊廓の少し浮かれた風情とは異なる、まるで神社か寺の祭壇がしつらわれたような場所だった。
大広間に集まってくる出席者を観察しながら、渦彦は競市の開始を待っていた。
何人かの参会者は清兵衛に目で挨拶をしてきた。名前は互いに口にしないがこうした場での顔見知りらしい。
参会者がほぼ集まったと思われる頃に、祭壇の裏から一人の男が出てきた。まるで神職のような白装束だったが、一つ異なっているのは芝居の黒子のような顔を隠す薄い布の頭巾を被っていた。人々に自分は見えない存在であるという暗喩を示しているようである。
「さて皆様方、本日はようことおいでくらはりました。今宵の市はあの世とこの世の間で執り行われる閻魔の市でございます。ここにお集まりの方々は皆様地獄の亡者、そして市の競り品はあの世の宝物。浮世の道理とは無縁でございます。閻魔の市で起こることは一切聞かず、語らず、覚えずをご定法とされておりまする。そのこと特とご納得いただけましたなら、閻魔の市のご開帳でございます」
白装束の男が口上を述べると、まるで歌舞伎の囃子のような拍子木が打ち鳴らされた。
参会者が沈黙でそれに応えると、白装束の男は祭壇の裏に身を隠した。
すると入れ替わるように稚児姿の禿が錦の布団に載せた小さな像を運んできた。それを恭しく祭壇に置くと静かに去っていく。参会者の視線が一斉にその像に注がれた。
「まず第一品目の競りでございます。こちらは豊前国、宇佐の宮において二之御殿で奉られておりました比売大神の御神像でございまする。特とご覧くださいませ」
姿を隠している男の声に促せられて、皆が一斉に体を乗り出した。
暫く皆がその神像を眺めると、一人の参会者が徐に手を挙げた。
すると先ほどの稚児姿の禿が再び現れた。そして手を挙げた男の元へ行くと、その手を取って神像が置かれている祭壇に導いた
男は祭壇でしばらく神像を観察すると、「百両」とだけいって自分の席に戻っていった。
次に別の男が手を挙げた。再び稚児姿の禿がその男を祭壇に誘った。そしてやはりしげしげと神像を眺めると、「百五十両」と宣言してから自分の席に戻っていった。
これが閻魔の市での競りだった。
新たに挙手をする参会者が現れる限り、この行為が続けられた。そして手が挙がらないと、最後に値付けをした参会者が落札者となるのである。
淡々と行われていく競りを見続けながら、渦彦はここに徳陀子神社の御神宝が出品されるのだろうかと少しやきもきした。
もしそうなれば自分はどうすべきかを深刻に考え始めた。
清兵衛にいって落札してもらうべきか、あるいは落札した参会者を覚えて後に返還交渉をするべきだろうかと迷った。だがどちらも渦彦には難しい。競りに参加するかどうかはすべて清兵衛の判断である。落札者を特定することはさらに難しいだろう。御法度の闇の競市に参加しているのだ、身元がわかるとは思えなかった。
結局渦彦にとって利があるのは「大和の徳陀子神社」という出自が読み上げられることだけだった。盗まれた御神宝が何だったかだけは判明する。
だが本当にそれだけだった。最初はそれだけでもいいと思って探索した競市だった。しかし目の前に徳陀子神社の御神宝が現れて、それを他人に持ち去られることが我慢できるだろうかと思った。
反問しながら競市を見ている渦彦に、清兵衛が小声で語りかけてきた。
「やっとええ顔になりはりましたな。何やったらわてが協力しまひょうか」
いわれた渦彦は、ハッとして隣の清兵衛の顔を見た。その瞬間、清兵衛が自分を飲み込もうとしている巨大な蛇に見えた。薄気味悪いだけではなく恐ろしい大蛇に変貌している。
「自分は今、この人の手管に落ちかけている」
そんな警鐘が頭の中に鳴り響いた。自分に欲や迷いが生じた瞬間、清兵衛に飲み込まれようとしているのだと悟ったのだ。
もしかしたら御隠居はこの可能性を考えた上で、自分と清兵衛をこの市に派遣したのかもしれない。清兵衛に取り込まれる危険性を承知した上で。
だがそれは御隠居が自分に仕掛けた罠だとも感じた。もし御隠居の信頼に応えられなかったときは、渦彦の価値は無に帰するだろう。そうやって御隠居は人を目利きしているのだ。
そう考えたとき、御隠居も清兵衛も怖い人だと感じた。ちゃんと人間の価値を判断する冷徹さを持っている。本当に商いで命の売り買いをしている人なのだと感じた。
「いえ、ご心配無用。ただ競市の気迫に少し興奮しただけです。ですが今回清兵衛どのはどのような出品物を待っておられるんですか。それがわかればわいも警戒がしやすくなりますよって」
心を見透かされたと感じた渦彦は、話題を変えて今夜の目的を尋ねた。
清兵衛は自分の間合いが外されたかと、少し残念そうな表情になった。だが周りに聞こえないように渦彦の耳元に口を寄せると、小さな声で「聖徳太子」と囁いた。
聖徳太子?
渦彦は心の中で反芻すると、言葉の持つ意味を推察した。そういえば隠居所での仕事である書物整理でも、この名前は幾度も出てきている。御隠居の集めた書物には聖徳太子に関係するものも実に多かったのだ。
そして表では取引できない閻魔の市で聖徳太子の遺物を待っているという。それがどういう繋がりなのかはわからないが、御隠居の骨董集めの主題に「聖徳太子」があることだけは理解した。
「わかりました、よく注意しておきましょう。清兵衛どのは競りにご専心ください。わいは周囲を警戒します」
それだけ呟くと、渦彦は頭の中から徳陀子神社の御神宝のことをひとまず排除した。余念があっては全てが中途半端になる。今は自分の役目を第一に考えようと思った。
そして叔父椎根津に蹴速術の隠し技として昔習った「木霊」を試してみた。一対一での気を感じ取れる渦彦は、その応用である「気の反響観測」も訓練していた。それは自分の微量な気を周囲に発することで、その反応を観察する技である。
殺気などの気づかれ易い大きな気ではなく、小さな細波ほどの気を発すると、人は必ずその細波の違和感に反応する。小さな気だから反応した本人も気づいていない。その反応する無意識の気「木霊」を捉えることで、人の居場所がおおよそ感じ取れるのだった。
身を隠しても関係はない、渦彦は木霊で周囲に潜む人々を感じ取ろうとした。
まず目前の祭壇の後ろに多くの木霊がある。ほとんどは主催者側の人間の反応だろう。祭壇裏か隣の部屋に何人か潜んでいるらしい。広間の周囲にも木霊があった。これは接待役の女中や参会者の護衛なのだろうか。
近くに不審に思えるような木霊はなかったが、上方からも気になる木霊があった。
「上?」と一瞬思ったが、階上の人間の反応かもしれなかった。
このとき渦彦が月読楼別棟の構造をよく知っていたら、大広間の上には部屋がないことに気づいただろう。そうならば上からの木霊にもう少し警戒したかもしれなかった。
(三)
籐伍は興奮が解けない愛染に少し困っていた。
大広間ではなかなか男女の狂宴が始まらないことに焦れた愛染が、強引に籐伍の上に跨ってきたのだ。広間の声とは無関係に、愛染は自分の欲望を満たそうとしていた。
ここで諍うのはまずいと思ったのでしばらく愛染にされるがままになっている。それをいいことに、愛染は自分から籐伍を貪って昇り詰めようとしていた。
いかに役目とはいえ籐伍も若い男である。経験も手管もある遊女にかかれば、籐伍の体の方が勝手に反応していく。
頭のどこかで「あかん」と思いながらも愛染に反応していた。広間から聞こえる競りの声を細い蜘蛛の糸のように感じながら、最後のところで理性が踏ん張っていた。
「一度満足させた方が良いかもしれない」とも思ったが、そうしたらその後がまずかった。
もし事態が急変したときに対応ができなくなる。特に肉体的にまずいと思った。男が一度達した後はしばらく肉体的に回復が難しい。特に腰や脚に力が入らなくなれば捕り物にも戦いにも遅れを取るだろう。
今夜の目的はあくまで隠密の探索で個人的な遊びではない。こうした状況の経験がない籐伍は愛染のいなし方がわからなかった。
「興奮したら喉乾いてきたわ。お前の口移しで酒でも飲もう。ここにもって来れへんか」
そういうと、「よいしょ」と愛染の下から自分の体を横に外した。
「もぅ、これからがええとこやのに」
愛染は昇り始めた興奮を抑えるように小さく愚痴をこぼした。だがそこは遊廓の客の要求である。従わない訳にはいかなかった。
愛染は心底残念そうに襦袢を着直すと、恨めし気な視線を籐伍に向けた。だがそれ以上は何も言わずに道具部屋をそっと後にした。酒を取ってここに戻ってくるにはしばらく間があるはずだった。
そのとき、籐伍は不思議な香りを嗅いだ。甘い御香のような匂いである。
「どこぞの部屋で香でも焚いてるんか」
遊廓で香を焚くこと自体は不思議ではないが、この別棟には他の客はいないはずだった。大広間の声も香を炊くようなことはいっていない。
「変やな」とは思ったが、それ以上はあまり深くは考えなかった。
いや考えなかったのではなく、考えられなくなっていた。
不思議な香りを嗅いでから何故か集中力がなくなっていた。そして自分でも不思議なことに、先ほどから急激な睡魔が襲いかかってきている。
今日はこの夜の探索のために夕方まで仮眠をとり、一晩中でも行動ができるように準備をしていた。なのに睡魔が襲ってきている。
「どうないしたんや、わいわ」
籐伍は何度か自分の頬を叩いてみたり、太腿をつねってみた。だが睡魔は引かず、頬や太腿への刺激もどこか鈍く感じている。先程までの快感と興奮が驚くほど消え失せていた。
段々と朦朧としてくる意識の先で、大広間からの声がわずかに聞こえている。そこでは次の出品が読み上げられようとしていた。
「さてここからは本日の閻魔の市での目玉でございます。まずは聖徳太子伝来といわれます、西播磨斑鳩寺よりの地中石をご覧くだされ。今の時代に二つとはない、この世の秘宝でござりまする」
声の後しばらくして、大広間に「おおっ」というため息が漏れた。
籐伍は朦朧とする意識の中で「聖徳太子」という言葉に意識が目覚めた気がした。それは鬼没盗の事件を調べていて、不思議と登場してきた飛鳥時代最大の有名人の名だった。
その名が籐伍に鞭を入れた。「鬼没盗が来るかも知れへん」と思った。
籐伍は「ここにおったらあかん」と即座に判断して、慌てて道具部屋から走り出た。別棟と本館を繋ぐ渡り廊下まで移動した。そよぐ夜風が籐伍に新鮮な空気を吸わせた。
さっきまで朦朧としていた籐伍の意識が少しはっきりとしてきた。別棟の方を見ると、何故か物音がしていないように思えた。
「何かが起こってる」と籐伍は直感した。
きっとさっきの籐伍と同じように別棟にいる人々は意識が朦朧としているのか、もう眠っているのかも知れないと思えた。
「これは鬼没盗が出た商家と同じなんとちゃうやろか」
これまで鬼没盗に襲われた商家の住人は皆朝まで気づかずに眠っていたと証言している。そして朝になると忽然と骨董品が消えているのだ。実は被害にあった商家には寝ずの番を置いていた家もあった。だがその「寝ずの番」も不思議と寝落ちしていたという。
不思議な術か、誠に妖怪変化の仕業かも知れないと思わせる点だった。
意識のはっきりしてきた籐伍は先程の予感を再び感じた。
「きっと鬼没盗が来るに違いない」
確信に近い思いが籐伍を占めていった。だが別棟に戻ったら再び意識が朦朧として眠らされてしまうかもしれない。それが鬼没盗の使う手管なのだと思った。
籐伍は急いで愛染と元いた部屋に戻ろうとした。今は寝間着のようなものしか羽織っておらず得物もない。これではもし鬼没盗と出会ってもまともに戦えない。
部屋に戻ろうとした籐伍は、酒を道具部屋に運ぶ愛染と行き合った。
「すまんけど、急な用事ができてしもうたわ。急いで行かなあかん。この裏はきっと返すさかい今日は堪忍やで」
それだけいうと、愛染の手を引いて元いた部屋に急いだ。
愛染は全く訳がわからなかったが、籐伍の切迫した様子に何かを感じたのか黙って籐伍に従った。そして部屋で手早く籐伍の着付けを手伝った。
最後に小太刀を渡すとき、「この責任、きっと取ってもらうさかいな」とだけ呟いて小太刀を掴んだ籐伍の右手親指の付け根に噛みついた。それは籐伍との契りの印だった。
月読楼に登楼したときと同じ着流しに小太刀を帯びた籐伍は、再び別棟を目指した。
もしかしたらもう鬼没盗が襲った後かも知れないと思えたが、まだ遠くへは逃げていないだろう。それに月読楼の周囲には金蔵、銀蔵や小者も伏せている。逃げる者がいたら彼らがきっと追っているはずだった。
そう信じた籐伍はとにかく現場の別棟大広間に急いだ。
淡々と進行している閻魔の市だったが、少し前から様子がおかしかった。大広間に満ちていた強烈な欲望の気がどこか緩んでいる。
いや、競り自体は今も熱気を帯びているのだが、その熱気が何となくぼやけていた。熱気の焦点が合っていないのだ。
「何か変やな」と渦彦は感じたが、その原因がわからなかった。甘ったるい濃密な香りに、大広間全体が包まれているような不思議な感じである。
競りは依然継続されているが、参加者の意識が集中力を欠いているように見えた、
白装束の黒子が次の競り品を読み上げた。
「聖徳太子伝来の地中石」
そう声がかかったとき、渦彦は反射的に清兵衛の横顔を見た。清兵衛が先ほどいっていた品である。だが清兵衛の様子がおかしかった。しっかりと競り品を見ているようで、その焦点が微妙に合っていないように感じた。
意識を持ったまま眠りかけている。
そう感じた渦彦は、周囲に気づかれないように清兵衛の手にそっと触れ、強く小指の関節を逆方向に締め付けた。
ハッとしたように清兵衛は自分の小指を見返した。そして何事もなかったように渦彦の手を外すと、徐に競りの手を挙げた。
手順に乗っとって、稚児装束の禿が清兵衛の手を取りにやってきた。
このとき渦彦も急激な睡魔に襲われていた。不思議だったが、どうしようもなく眠いのだ。つねるぐらいの刺激では眠気が抑えられなかった。
禿と共に競り品の方に去っていく清兵衛の後ろ姿が僅かに揺れている。揺れているのが清兵衛なのか、自分の視野なのかがわからなかった。
「これはあかん」と思った渦彦は、自分で自分の小指の関節を強引に捻って外した。
強烈な痛みが背筋を駆け上って頭を刺激した。その瞬間、渦彦を覆っていた甘ったるい空気が周囲から消えたように感じた。
少し明瞭に戻った視野で周囲を見回すと、多くの参会者が座ったままの姿で動いていない。先程の渦彦同様に座ったまま寝落ちしているのかも知れない。
「そうや清兵衛どのはどないした」と思い出し、競り品の置かれている祭壇の方を見た。
祭壇の前では清兵衛と禿が折り重なるように崩れ落ちていた。まるで歩きながら眠り込んで倒れたような姿である。
そして二人の前の神棚に置かれていたはずの競り品「聖徳太子伝来の地中石」なるものが消え失せていた。
先程確かに禿がその場所に石の塊のような物を置いたはずだった。不思議な文様のような凹凸のある塊で、どこが聖徳太子伝来なのだろうと思った記憶がある。
だがそれがなくなっている。
再び濃密な甘い香りに包まれだした渦彦は、振り払うように立ち上がった。祭壇前に崩れ落ちている清兵衛に駆け寄ると、鼻と口に手をやった。
「息はしてはるな。寝落ちしただけや」と確認すると、今度は祭壇の周囲を見回した。
祭壇の後ろには白装束の黒子が倒れていた。きっと後ろの隠し部屋の競市側の人間も同様の状態だろう。なら誰がこの「聖徳太子の地中石」を奪ったのだろうか。
清兵衛はこの地中石を競り落しにかかっていた。競りが完了していたのかどうかは渦彦にも明確にわからなかったが(その辺りの記憶が明瞭ではなかった)、警護の対象だと感じた。どのような値になろうとも多分清兵衛はこの地中石を落札しただろう。いやもう落札していたのかもしれない。
そうだとしたら、地中石を奪った者から奪還しなければならない。それが今夜の渦彦の第一の役目なのだ。
清兵衛も黒子も揺り動かしても目覚めなかった。大広間にいる人間も、祭壇奥の部屋の人間も同様だろう。そして渦彦自身も少し気を緩めると眠りそうになっている。
関節から頭に響いている痛みの鼓動だけが、渦彦を目覚めさせていた。
「ここにおったらまずい」と感じた渦彦は、大広間を飛び出ると本館に向かって走り出していた。そして新鮮な空気が吸えると思った場所まで来ると、大きな深呼吸と同時に強烈な木霊を使った。
正体はわからないが、この別棟から逃げる木霊を探さねばと思った。それがきっと「聖徳太子の地中石」の強奪犯に違いない。
細波ではないもう殺気に近い気を周囲に発した。いくつかの木霊があったが皆停止していた。今は動いている木霊が犯人だと思っている。
突如上方から動く木霊があった。上方といってもまるで屋根の上のような位置である。だがこれが当たりの木霊だと直感した。
ただこの木霊は無意識の反応ではなく、明確に自分に向かって打ち返してきた殺気のように感じられた。こんなことは今までなかった反応である。
いや一度だけあった。木霊を教えてくれた叔父椎根津によって打ち返されたときである。そのときと同じような無意識ではない意図された木霊だった。渦彦や椎根津同様に木霊が使える人間の反応に思えた。
頭の中が様々な疑問に溢れながらも、渦彦はその殺気のような木霊を追った。今はこれを追うしか手がかりがなかった。
別棟を抜け出て、本館もすぐに出てしまった。だが木霊はまだ捕まえている。木霊は屋根の上から地上に移動し、街の中に入ろうとしていた。
人が多くなれば木霊の特定は難しい。次第に殺気の木霊は曖昧になり、やがて多くの木霊の中に消え去ってしまった。
渦彦はそれでも木霊のあった方向に新町の街中を走り続けた。このまま走ればいずれ木津川にぶつかると思った。それは最近やっと覚えた大坂の地理からの推察だった。
このとき渦彦は前ばかりに意識がいって、後には注意が疎かだった。
この渦彦の後方から追うものがいたのだ。そのことに渦彦はまだ気が付いていなかった。
それは月読楼の周囲を警戒していた金蔵だった。月読楼から走り出た渦彦を怪しいと睨んでその後を追跡しているのだ。
地中石を奪ったと思わしき賊を追う渦彦と、その渦彦を追う金蔵。夜の大坂の街で不思議な追跡劇が始まっていた。
籐伍は遮る者がいないことを幸に、別棟の大広間に走り込んでいった。このとき籐伍は鼻や口の周りを濡れ手拭いで覆い、甘い香を嗅がないようにしていた。睡魔の原因が最初に嗅いだ甘い香だと思ったからだ。
そこで不思議な光景を見た。
大広間中で座りながら寝落ちしている人の群れである。皆固まったように座っていた。
ただ祭壇のような前に、二人の人間が転がっている。籐伍は二人を揺すったが起きる気配はなかった。二人とも気を失ったように眠っているのだ。
「鬼没盗はもうここには居れへんか。何ぞ盗んだ後やな」
そう思ったが、盗まれたのは籐伍が眠気に襲われる直前に競りに出されていた「聖徳太子の地中石」だろうと想像した。
飛鳥時代絡みのお宝に、全員が寝落ちしている犯行現場の様子。全てがこれまでの鬼没盗の手口に一致した。
籐伍はこの大広間を犯行現場として押さえておきたかったが、今夜は隠密の探索のために手がなかった。それに今は鬼没盗を追う方を優先したい。
籐伍は人のいる本館に駆け戻ると、強引に廓の人間を捕まえて命令した。
「わいは西町奉行所の仮役与力の阿刀籐伍や。別棟の大広間に鬼没盗が出よったさかい追ってる。急いで奉行所に知れせて大広間を調べてもらえ。大広間で秘密の競市が行われてるんは知ってるで、今回は競市を見逃したるさかい鬼没盗の調べに協力せえ」
それだけ言い捨てると月読楼の玄関の方に急いだ。
廓の人間がどこまで従うかはわからないが、今はこれしかできなかった。取り敢えず因果を含めておけば後で取り調べもできるだろうと思った。
月読楼を飛び出た籐伍は辺りを見回した。すると暗闇の中から突如飛び出してきた銀蔵が走り寄ってきた。
「ぼん、あっちや。あっちの方角に怪しいやつが飛び出していったで。兄やんが追ってるさかい、急いで後を追ってんか」
籐伍に叫びかけると西の方角を指差した。新町遊廓から西といえば木津川の方向だった。
「銀蔵は奉行所に応援を頼んでくれ。でけたら大広間に居てる奴らを押さえるんや。廓や競市の人間が邪魔しよるやろうけど、今なら踏み込めるかも知れへん」
そう指示すると、銀蔵が指差した方角に走り出した。多分この混乱が収まれば遊廓は奉行所の介入を拒否するだろう。
新町遊廓はこの国に幾つかある幕府公認の遊廓(江戸吉原、京島原、大坂新町、長崎丸山、非公式ながら伊勢古市)なので、本来なら容易に奉行所は介入できない。幕府に運上金を上納している各遊廓は寺社同様に高度な自治権が認められているからだ。
だが皆が眠り込んでいる今なら踏み込めるかも知れなかった。後で苦情がくるだろうが、今は少しでも鬼没盗の情報が欲しかった。
夜風を切りながら、籐伍は新町の町を走り抜けていった。
今が一番鬼没盗に近づいているという興奮が籐伍をせき立てていた。この機会を失えば、次はいつ巡り会えるかもわからない。その惧れと高揚する気持ちがないまぜになって籐伍を満たしていった。
(四)
夜の静寂に、籐伍のはぁはぁという荒い息だけが響いていた。
新町遊郭から全力で走ってきたが、前を走るはずの金蔵は闇の中に消えて見えない。
だが金蔵がこの方向に走って行ったのは間違いなかった。遊里の喧騒を抜け出て久しい。ほのかに風に乗った水の匂いがするので、もう木津川が近いのかもしれなかった。
そう思っていると、目の前を突然川堤が塞いだ。もう前に進む道はなく、左右に別れた堤沿いの道しかなかった。
「どっちへ行った」
金蔵が追った道を見失ってしまったが、まだそう遠くへは行ってはないはずだった。
突然、左手の道先の暗闇から金蔵の誰何する声が響いた。
「待たんかい。おまえ、どこのもんや。なんで新町から走って逃げよった」
籐伍は声のした方に急いで走った。
暗闇の中で金蔵が、白っぽい半纏を羽織った男の腕を鷲掴みにしていた。十手を男の首筋に当てて、そのままその場に引き据えようとしている。
「金蔵ようやった」
籐伍がそう思った瞬間、金蔵の体が闇空を舞っていた。
今夜は朔すぐの二日月なので、月の光がほとんどない闇夜だった。
だがその闇の中でも金蔵が宙を一回転して、大地に叩き付けられる姿がわかった。
金蔵は御用聞をしてもう十年以上になる。捕り方の技量もそこそこ以上だ。あの捕縛態勢に入って失敗ることなどまずなかった。
その金蔵が大地に叩き伏せられていた。
籐伍は即座に危険な相手だと判断した。
「金蔵、ここはええから小者らを呼んでこい。それまではわいが押さえる」
そういって腰に手をやった。
そこにいつも差している十手はなかった。今夜は隠密の探索だったので目立つ十手は持ってきていない。
代わりに手に触れたのは愛用の小太刀「牛若丸」だった。遊び人風情の着流しに脇差を帯びた姿、それが今夜の出たちである。
「ぼん、気つけや。こいつでけんで」
金蔵は叫びながら転がり男から離れると、軽業師のように跳ね起きた。そのまま元きた道を走り出した。まるで獣のような身軽さだった。さすがは元盗人の身のこなしである。
二日月の月光に目が慣れてきて、だんだんと男の細部が見えてきた。
「まだ若い」
それが籐伍の第一印象だった。
その若い男は両手をだらんと下げて自然体で立っている。手に得物はなく、柔術のような構えを取っていない。威嚇の力みが全くなかった。
だがそれが逆に怖かった。武術の達人ほど体に力は入っていない。脱力したような態勢から、突如疾風の技が繰り出されるのだ。
先ほど金蔵が投げ飛ばされたように。
「もういっぺんき聴くで。お前は誰や。何で新町から逃げた。競市のお宝盗んだ鬼没盗の仲間とちゃうんか」
籐伍は無警戒に若い男に近づいていった。まるで友達に近づくような気軽さである。牛若丸はまだ右手に握っておらず、ただ左手が鞘を軽く押さえているだけだった。
もしこのまま戦えば、ほぼ初撃で決着がつくだろうと思った。そのためにも体はゆったりとしておく必要がある。力が入った体では筋肉の強張りが速さを消してしまう。
無心無力が初撃の極意也。
ふと、剣術の師匠の言葉を思い出した。
籐伍は自分が全く気負っていないことが可笑しくなり、口元に微笑みさえ浮かべた。目前の男と同じように籐伍もまた体に力が入っていなかった。
相手の間合いは判らないが、あと一歩で籐伍の小太刀の間合いに入った。それにはお互いに気がついていたのかもしれなかった。
籐伍がさらに一歩前に進んだとき、二人は同時に動いた。
籐伍は左足後ろへの蹴りに力を預け、右手で撫でるように牛若丸を優しく前に抜いた。
小太刀の突き技「八艘」だった。流れるように突き出された牛若丸が、若い男の首筋のある空間を貫こうとした。
八艘はただの突きではない。一瞬刃が空中で加速して、二段階で伸びるように相手に錯覚させる。それは右手のしなやかな鞘走りと、左足後ろへの強烈な蹴りが生む突き速度の二段階変化からだ。
たとえ太刀筋を読んで左右に避けるか刃を受けようとしても、突きの速度変化に相手は一瞬反応が遅れてしまう。
今回もそうだった。牛若丸が見事に首筋を貫いたように見えた。
だがそこには若い男の首筋がなかった。刃を左右に避けたのではないのに、空間から標的が消失していた。
「あかんっ」と瞬時に思い、籐伍は二撃目の突きのために引き手を開始していた。突き技の欠点は初撃を外された後の間隙だった。
だがその引き手の軌道を籐伍は途中で強引に変えた。籐伍の視界の一番下外側から、不気味に迫り上がってくる掌底を感じ取ったからだ。
若い男は左右ではなく下への体捌きで八艘をかわし、そこから掌底を放ってきた。とても常人に可能な動きと速さではなかった。
籐伍は引き手の軌道を強引に下方へ変化させ、牛若丸の柄尻で迫り上がる掌底を受け止めた。受け止めたというよりも、柄尻で掌底を打ち砕く攻撃に近かった。
若い男の掌底攻撃を、牛若丸の柄尻で攻撃し返したのだった。
どちらの攻撃も相手をその場に留めるには不十分だった。二人は同時に後方に大きく退いた。三間ほどの空間が二人を膠着させる距離になった。
どれ程の時間膠着していたのか判らないが、少し遠くから呼び笛の音が聞こえてきた。その音はだんだんと近づいてきている。
籐伍は金蔵が配置していた小者を連れて戻ったのだと思った。
「もうすぐ捕り方がくるで。なんぼお前が強うても全員を倒すのは無理や。大人しゅうに縄についてんか」
籐伍は牛若丸をゆっくりと鞘に戻しながら、体の力を抜いていた。
若い男は争うことを諦めたのか、ふてくされたようにその場に半結跏して座り込んだ。戦意はないようだったが、妙に堂々とした座り方だった。
そして初めて口を開いた。それは思った以上に若く、綺麗な透きとおった声音だった。
「わいは盗賊やあらへん。遊廓に出た賊を追ってたんや。ここまで追ってきたら突然あの男が襲ってきよったから身を守ったんや。そしたら次は刃物持ったお前が襲ってきよった。身を守って何が悪い」
明らかに憮然とした様子だった。
籐伍は男の言葉を不思議に思った。盗賊一味でないのならなぜ追うのか。
「わいは大坂西町奉行所の仮役与力、阿刀籐伍という。今夜は探索のために新町に潜んでたが、競市を襲った賊を追ってここまできたんや。お前が賊の一味やないんなら名を名乗らんかい。役人でもない者が賊を追うんや」
そう問い詰める籐伍の後ろには、もう金蔵と何人かの小者が到着していた。皆一様に手に手に刺又や長棒を持っていた。
「わいの名は巨勢渦彦や。同修町にある少彦名神社の神人をしてる。今夜は閻魔の市参加の競り人代理の護衛として新町にきた。その市が襲われたさかい、賊の後を追ったんや。もし代理人の落札したもんが奪われてたら、取り返せなあかんからな。そしたらお前らが邪魔してきよった。邪魔した責任はとってもらうで」
そういい放つと、渦彦は腕組みをして瞑目してしまった。
籐伍の後で捕り縄を出している金蔵は縄を打つのをためらった。
「ぼん、どないしまひょう。縄かけてよろしおますか」
聞かれた籐伍も少し迷ったが、事情を詳しく聴かなければならない。この巨勢渦彦を番所に連行して状況を確認しようと思った。
「とにかく番所に連れて行け。話聞いてからどないするか決めるよって」
金蔵はいわれたように巨勢渦彦に縄をかけたが、その仕草は少し腰が引けていた。さっき投げ飛ばされたことを覚えていたからだ。
その間に籐伍は小者を側に呼んで、少彦名神社に巨勢渦彦という神人がいるのかを確認に走らせた。本当に少彦名神社の神人なら話が面倒になる。
神社に属する神人は寺社奉行支配の人間である。確かな証拠や寺社奉行の許可なしに、町奉行所が捕縛するわけにはいかないのだ。
「やれやれ、また面倒ごとが重なったな。遊廓も神社も町奉行所の手が入らん場所や。こんなんばっかやな」
籐伍は少しげんなりとした。
もう一つ気にかかることがあった。先ほどの渦彦との戦いである。
最後の瞬間、渦彦は掌底で襲ってきた。もしあのとき貫手や拳だったらどうなったのだろうかと思った。下からの攻撃に速さの点でも威力の点でも掌底はおかしかった。あの瞬間手を控えたのではないのかと思えたのだ。
縄を打たれ番所に連行されようとする渦彦に、籐伍は声をかけた。
「お前何で最後が掌底やったんや。貫手やったら勝ててかもしれへんのに」
籐伍の声に立ち止まった渦彦は、ゆっくり振り向きながら答えた。
「あんたの最初の突きには殺気があらへんかった。おもろい変化の突きやったけど、殺気の籠もってへん攻撃は怖うないわ。こっちも殺す気ない相手に禁じ手は使われへん。それにわいが掌底で狙うたんは腹やないで、あんたの肘や。引き手の肘を打って刀使えんようにするつもりやった。まさか引き手の方向を変えて、柄尻使うて攻めてくるとは思わなんだわ。それを見抜けなんだわいの負けやな」
渦彦はあっさりと自分の負けを認めた。
だが籐伍は逆に慄然とした。殺す気で八艘を放っていたら、殺し返していたといっているのだ。本気だったら負けたのは籐伍だったかもしれない。
渦彦の後ろ姿を見ながら「こいつ何者なんや」と、初めて渦彦に寒気を覚えた。素手の相手に恐怖の感じたのは籐伍も初めてのことだった。
番所に渦彦を引っ立てた籐伍のもとに、次々に報告と苦情、最後には吟味方筆頭与力丹羽からの出頭命令が届けられていた。
そのほとんどが芳しくない内容である。
まず捕縛した巨瀬渦彦はやはり少彦名神社の正式な神人であるという報告がきた。これで渦彦を長くは留め置けなくなった。何かするには江戸の寺社奉行の許可がいる。
次にきたのは新町遊廓総代からの苦情だった。本来町奉行所不介入の遊廓に、いかに盗賊現場保持のためとはいえ横紙破りに踏み込んだことへの抗議である。ただ遊廓側にもご法度の閻魔の市を開いていた後ろめたさがある。奉行所への正式抗議というよりも、籐伍に対する脅しに近かった。
遊廓からは幕府への上納金以外にも、町奉行や大坂城代などに別口の賄賂も流している。仮役与力の首などいつでも飛ばせるぞという脅しだった。
そして最も残念な報告は、閻魔の市に参加していた人物の特定ができなかったことだった。ほとんどが代理人や正体不明の競り人で本当の参加者がわからない。
結局、今回の探索で得た具体的な成果といえたのは巨勢渦彦だけだった。
もちろん閻魔の市や月読楼からの被害届などないので、鬼没盗による閻魔の市襲撃自体も公式には存在しない。
それだけに籐伍は、少しでも鬼没盗出来時の様子を渦彦から聞き出しかった。知らぬ間に籐伍は、役目以上に鬼没盗事件にのめり込み始めていた。
「なんでもええから教えて欲しいんや。今回の閻魔の市も鬼没盗の襲撃も表向きにはないことになってしもうた。そやけど鬼没盗はあそこに居てたし、渦彦は追ってた。その辺を詳しゅうに話してくれへんか。それで渦彦を捕まえよういうんとちゃうねん、心底鬼没盗のことが知りたいんや」
籐伍は半分拝むように渦彦に話していた。
最初は奉行所の役人ということで頑なだった渦彦も、妙に低姿勢で役人っぽくない籐伍を「変な奴やなぁ」と思い始めていた。
「わいも役目であそこにおったさかい、詳しいことはいわれへん。そやけど賊が出た時の話やったらしたるわ。まずあの大広間に知らん間に沈香の匂いが満ちよった。それを嗅いだ参加者は、寝落ちさせられたようやったな。わいも寝落ちしかけたけど、小指の関節外した痛みで耐えられたわ」
籐伍はいきなり渦彦の発した言葉に食いついた。
「沈香の匂い? 何やそれは。賊が出る直前からしてたあの甘い香りのことか。それでみんな寝落ちしてしもたいうんか」
渦彦はただ籐伍の言葉に頷いた。
「あれは確かに沈香の匂いや。わいの実家でも兄上が似たような匂いの沈香を調合してたから覚えてるわ。あの時は思い出されへんかったけど、今考えるとよう似た匂いや」
少し残念そうな表情で渦彦は語った。
「実家の兄上が調合してたって、渦彦の家は薬種問屋か医者なんか」
渦彦は首を振りながら「大和にある神社や」とだけいった。鴻池の御隠居のことは一切語らなかったが、なぜ盗賊の競市である「閻魔の市」に関わったかは説明した。
実家の神社の御神宝が奪われ、それが原因で父が自害したこと。そして御神宝を探すために盗賊の競市を探し出し、それにやっと護衛として参加したことなどである。
渦彦の意外な告白に籐伍は驚き、そして捕縛したことを申し訳なく思った。「こいつ若いのにえらい苦労してるんやなぁ」と少し同情したのだ。
だが私情に流されてはいられなかった。鬼没盗のことを少しでも聞き出したかった。
「その沈香で皆が眠らされたとして、何で渦彦は賊が木津川の方に逃げたってわかったんや。わいの手下で月読楼を見張ってた小者は、渦彦以外で廓の入口から出て行ったもんはおらんというてたで」
渦彦はこの問いの返答に困ってしまった。蹴速術や木霊のことを他人に語るわけにはいかなかった。
だが籐伍の方がある推察を語ってきた。
「これはわいの勝手な想像やけど、渦彦は何やけったいな武術を修得しとるんとちゃうか。わいの八艘を外したのもそうやし、金蔵を投げ飛ばした技も見たことがあらへん。わいも一応の武術は知ってるつもりやけど、渦彦の使う技はようわからんかったわ。賊を追った技もそんな内のもんか」
ほぼ籐伍の想像だったが、正鵠を射ていることに渦彦の方が驚いた。
「こいつぼーっとした役人やけど、観察力と勘はええなぁ」と感じた。
渦彦はただ「うちの神社に昔から伝わる体術や」とだけ答えた。
籐伍もそれ以上は聞き出そうとはしなかった。本筋の鬼没盗のこととは少し外れていたからだ。
「それで市で盗まれたんは、聖徳太子の地中石で間違いないんか」
籐伍はこの点を一番確認したかった。それによって今後の鬼没盗の狙うものがかなり絞られると思った。
「盗むとこ直接見たわけやないけど、直前まで祭壇に置いてあったんは確かにその地中石やったわ。わいもそのとき意識がぼやけてて盗人は見てないけどな。気がついたときにはもうのうなっとった」
それだけいうと、渦彦は少し疲れた表情になった。御隠居からの役目が果たせなかったことを思い出したからだった。
聞き取りをしていると、小者が入ってきて籐伍に耳打ちをした。巨勢渦彦の身柄引受人である少彦名神社の宮司が迎えにきたと告げたのだ。
渦彦への聴取はここまでだった。これ以上は寺社奉行の許可が必要になる。だが籐伍はここで妙案を思いついた。
「渦彦もえらい大変みたいやし、わいも今ほんまに困ってるんや。ここはひとつわいら協力せえへんか。お互いがお互いの助っ人になったら、抱えてる難題も解決する思うねん。どないやろ、わいは渦彦の探す実家の御神宝探しを手伝うさかい、渦彦は鬼没盗探索を手伝ういうんは。それに……」
ここで籐伍は言葉を切って、自分の勘に確信を持とうとした。
「渦彦の話を聞いてて、もしかしたら渦彦の実家の御神宝を盗んだんは鬼没盗かもしれへんと思えたんや。わいも渦彦もお互いに別々のもんを追ってて、結局同じ場所に行き着いたんやで。これはこの二つが繋がってるということや。やったら二人で動いた方が色々と都合がええんとちゃうやろか。わいは奉行所の力や縁故が使えるし、渦彦には鬼没盗と出会うてる経験がある。けったいな体術もな。きっとお互いもっと前に進めるはずや」
籐伍の少し能天気な提案に渦彦は返答をしなかった。いや、できなかった。籐伍の本意も解らないし、鬼没盗が御神宝奪取の下手人だという籐伍の推理に戸惑っていた。
番所に少彦名神社の阿曽宮司が入ってきた。
「渦彦はん、えらい目に逢うたなぁ。せやけどもう大丈夫やで。町奉行所はわてら神社の者を証拠もなしに捕まえられへんからな。さぁ、帰ろか」
宮司は「もう帰ってもよろしおますな」と籐伍に確認した。普段は軽妙な言葉に今は珍しく嫌味が籠もっていた。
籐伍は「どうぞ」と答えると、渦彦の耳元で「さっきの話、待っとるで」と囁いた。
宮司はまるで宝物を護るように渦彦の肩を抱いて番所を後にした。番所から少し離れてから渦彦は宮司に謝った。
「宮司はん、えらいお手間かけさせてすいまへん。御隠居様にも申し訳ないことしてしもうたのに、わざわざ来てくれはるなんて」
宮司は「かまへん、かまへん。これもお役目のうちや」と笑いながら応えた。迎えに来たのは御隠居からの指示やからと明かした。鴻池家は今回表に出られないので、少彦名神社がその代役をしているのだという。
御隠居としても一刻も早く渦彦の身柄を奉行所から取り戻したかったのだ。清兵衛はもう御隠居の保護下だという。これで鴻池と閻魔の市を繋ぐものは何もないことになる。
番所からは解放されたものの、渦彦の心は全く晴れなかった。
結果的に御隠居に命じられた役目は果たせなかった。それ以上に御神宝を追う手がかりがこれで途切れてしまったことになる。
賊に襲撃を受けたとなれば、しばらくは閻魔の市は開かれないだろう。そこに徳陀子神社の御神宝が出品されることもなくなったのだ。これからどうやって御神宝を追えばよいのか、皆目見当がつかなかった。
渦彦の脳裏に地獄からの囁きのように先程の籐伍の言葉が蘇った。
「渦彦の家の御神宝を盗んだんは鬼没盗かもしれんと思えたんや」
籐伍の言葉を振り払い、渦彦は夜空に瞬く星々を見上げた。そこには初夏に見える美しい星座が輝いていた。
「大坂で見える星も、葛城で見る星もおんなじなんやな」
心を落ち着かせるためにじっと星空を見ていたはずが、突如として沈香の匂いと屋根の上から打ち返してきた木霊のことを思い出した。漠然とだが、鬼没盗という奴らは徳陀子神社と何か関係があるのだろうかと感じた。
覚えのある沈香の匂いも打ち返された木霊も、本来門外不出の秘伝である。こんな大坂で出会うとは、どういうことなのだろうと不審に思った。
渦彦は父の自害と鬼没盗の間に、何か見えない糸が繋がっているように感じ始めたのだった。
第三幕 未然記囮策戦
(一)
翌日から籐伍は少し忙しくなった。
まず後始末として各方面への話し合いがあり、それらを丸く収めなければならなかった。何より吟味方へ探索の状況説明に追われたのだった。
筆頭与力の丹羽からは「ここまでやれとはいっておらんぞ」と、責任逃れのような釘を刺された。他の吟味方与力からも定法を守っての探索を心がけよと説教された。
ただ籐伍が今まで皆目足取りの掴めない鬼没盗に対して、初めて接触したのも事実である。吟味方は籐伍に詳しい報告書を書くように求めた。公式被害ではないにしろ、始めて鬼没盗の手口や行動がわかったのだ。
まだちゃんとした報告書を書いたことのなかった籐伍は、苦悶しながらもそれを記していった。ただそれは事実と籐伍の推理がない混ぜになったものとなっていた。
やっと「閻魔の市」襲撃の探索報告書を提出してから、逆に籐伍はこれからどう鬼没盗を追うべきかを考え込んでしまった。
今回は運よく推理が当たり鬼没盗に接敵できたが、この後が思い浮かばなかった。河原崎の与えてくれた探索手引き書をもう一度読み込んで当たるべきだろうかと悩んだ。
奉行所内でも籐伍を少し腫れ物のように扱う雰囲気が生じた。皆褒めてよいのか叱ってよいのか迷っていたのだ。自然遠巻きにされていた。
だが二人だけ籐伍を大っぴらに褒める者がいた。
一人目は同心の河原崎で、自分の渡した鬼没盗私見でここまでやれるとは思ってもいなかったと少し嬉しそうに語った。
「この後も思うように探索されるがよろしいでしょう。阿刀様と鬼没盗はどこかで思いが似ておるのやも知れまへん。我らの探索よりも、阿刀様の探索の方が相性が良いのです」
それだけいうと去っていったが、河原崎の信頼を少し勝ち得たのかも知れなかった。
そして二人目は籐伍に鬼没盗探索を下命した西町奉行だった。
籐伍の書いた報告書を読んだ西町奉行は、早速大坂城代の堀部に報告し、西町奉行所与力が鬼没盗に接敵した成果を褒められたということである。これまで姿形もわからなかった賊を、朧げながらも尻尾を掴んだのだ。
西町奉行に呼ばれた籐伍は、褒美の言葉と今後の探索により励むように命じられた。これによって奉行所内での居心地も改善された。何より定町廻り同心たちと事件について語れるようになったのだ。
これまではどこかお客さん扱いだったのが、同じ奉行所の探索者として認められたようだった。籐伍のやりすぎはともかく、賊をあそこまで追うことがいかに困難かということを、探索をする同心が一番よく知っていた。
周囲の変化とは裏腹に、籐伍は次の手に詰まった。期待されても次の手が出てこない。
籐伍は心のどこかで渦彦の来訪を待ちわびた。なぜか渦彦ともっと語れば、鬼没盗が見えてくる気がしていたのだ。ただ渦彦の来訪にはもう少し時間がかかるようだった。
渦彦は暫く少彦名神社に身を寄せた後に、鴻池の隠居所に戻った。間を置いたのは鴻池と閻魔の市の関係を悟られないためである。
隠居所に戻った渦彦はまず御隠居に謝罪した。
「お役目を果たせず申し訳ありまへん。清兵衛どのが落札したかもしれへん聖徳太子の地中石を取り返せまへんでした。落札品を守れというお役目をしくじったことになります」
深く頭を下げる渦彦に御隠居はしばらく沈黙していた。徐に煙草入れを出すと銀の煙管に煙草を詰めて火をつけ、深く一服した。
そして渦彦に閻魔の市の顛末を語り出した。
「あれは渦彦の責任とちゃうで。閻魔の市側の失態や。そもそも閻魔の市が賊に襲われることがおかしい。清兵衛が落札してたかどうかは関係あらへん。市を出るまではあっち側の責任やからな。しかも賊を追ったんは渦彦一人やという。あとは皆眠りこけてたと聞いたで。もう閻魔の市の主宰は変わらな今後やって行けへんやろな。それに比べてうちは株を上げた。これは渦彦のおかげや、ようことやってくれたな」
そういうと御隠居はにっこりと笑った。人をたらす見事な笑顔だった。
「ただ不思議なんは賊が狙った物と、わてが落とそう思うてた物が同じやったことや。これは不思議なことやで。あの地中石はほんまもんか怪しいいわくの品なんや。普通の骨董好きは手なんか出さへんやろ。なんや賊の後ろにはわてみたいな物好きか、深い因縁の者がおるんかも知れへんな」
もう一服煙草をふかすと、御隠居は考え深そうな表情になった。
「鬼没盗の後に御隠居様のような人が……」
渦彦がつぶやくと、御隠居はその言葉尻を捉えた。
「閻魔の市を襲うたんはほんまに鬼没盗なんか。そんな噂は聞いたけどな」
「わいを捕縛してた与力がそういうてましたわ。しかも……」
渦彦は言葉を切った。まだ御隠居には話すべきことではないと思った。
だが御隠居は珍しく体を乗り出すと途切らせた言葉の続きを催促した。
「しかも……何やねん。気になるがな。渦彦は賊とも接したし、奉行所の与力とも話してるんや。閻魔の市の襲撃に一番詳しいんは今は渦彦やで。わても競争相手かもしれへん鬼没盗にえらい興味あんねん。隠さんと何でも教えてんか。この通りや」
そういい煙管を横に置くと、今度は御隠居が渦彦に頭を深く下げてきた。
思っても見なかった御隠居の反応に渦彦は困惑した。御隠居に頭を上げるように懇願して、籐伍が述べた推理を語った。
「わいを捕まえた与力は、変なこというとりました。もしかしたらうちの徳陀子神社の御神宝盗んだんは鬼没盗かもしれへんて」
そこで渦彦は言葉を切った。共に協力しようという籐伍の誘いはまだ自分の心の中だけに留めた。
「ほう、それはえらいおもろい話やな。渦彦の父御が亡くなられたんはいつやったかな」
そう呟く御隠居は、少し何かを思い出しているようだった。
「今年の如月です。もう半年あまりが過ぎました」
御隠居は何度か頷いた。
「最初の鬼没盗が出たんは、確か春前やったと聞いてる。どうも徳陀子神社の事件が起こった直後のようやな。そして……これは関係ないやろうけど、わてのところに天河先生がいらはったのもその頃やった。わてが骨董収集の的を聖徳太子に絞ったのは、天河先生の助言があったからやからな」
それだけ呟くと、御隠居は本当に何かを考え込んでしまった。
「先生は偶然やろうけど、その頃からいろいろと動いてんるんやなぁ」
この言葉は渦彦に語るというよりも、自分自身に言い聞かせているように聞こえた。
渦彦と御隠居の間でしばらく沈黙が続いた。次の言葉が出ないというよりも、互いに自分自身の中で今回の件を深く内省しているからだった。
「まぁええわ。わての捜す遺物と、鬼没盗の狙うお宝がほんまに一緒やったら、いずれまた出会うやろ。それまではこれまで通りやることにしよう」
自分に言い聞かせるのと、渦彦に聞かせることを同時に語ったような言葉だった。
「これまで通りというのは……」
渦彦が確認するように呟いた。
「渦彦は書物の目録作り、合間に御神宝探しを続けるいうこっちゃ。閻魔の市はしばらくあらへんやろうからな。今はそれしかないやろ。鬼没盗の盗人働きの様子でももうちょこっとわかったら、別のことも考えられるやろうけど、今はこれしかあらへん」
御隠居はその言葉を納得させるように再び銀の煙管で煙草をふかした。
御隠居のいう「鬼没盗の盗人働き」を知るためには、奉行所の探索の様子でもわからなければ無理である。渦彦は再び脳裏に仮役与力の顔が過ぎっていた。この状態から前に進むためには、あの仮役与力に再び会う必要があるのかもしれないと思った。
籐伍が奉行所から戻ると、なぜか家内が少し賑やかだった。珍しく姉や小春の出迎えがないままに玄関から家に上がった。気になって自室へ入る前に騒がしい厨へ立ち寄った。
厨では姉の鈴、燕と小春が忙しく料理を作っていた。よく見ると真壁家の女中の梅も忙しく立ち働いている。
「どないしたんですか。まるで宴でも始めるような騒がしさやけど」
厨の土間に降りるかまちの上から籐伍は声をかけた。
一瞬皆が籐伍の方を見たが、すぐに自分の作業に戻っていった。鈴が手を休めないで籐伍に説明した。
「ああ、お帰りなさい。お出迎えせんでごめんなさいね。珍しゅうお父様が早ように帰られたんやけど、お客様を一緒に連れてはってね。それで急いで御膳の用意をしてるんよ」
そう手短にいうと忙しく料理に戻った。
「なんで梅までいてるんですか」
籐伍が尋ねると面倒臭そうに燕が答えた。
「お客さんの一人は恭兄はんやからや。ご馳走になって申し訳ないいうて、お手伝いに真壁から梅ちゃん呼でくれたんや」
そして付け加えるように呟いた。
「もうお一人のお客はんはあんたの大好きな大塩のおじさまやで。お二人を待たすわけにはいかへんので、皆で急いでんねん。あんたもそこにつっ立って邪魔せんといて」
恭兄と大塩のおじさんが、父上と一緒に家に来ている。不思議な取り合わせだが籐伍も急いで挨拶に向かおうとした。
「いてるんはお父はんの書院とちゃうで、広間の方や。ちゃんと刀置いてから行き、あんたまだ刀挿したままやで」
横目で見ていた燕が注意した。普段は大雑把な燕だが、ときに妙に気がつき姉らしくなる。意外に燕は籐伍のことを気にかけているのだった。
籐伍は自分の刀と十手を置くと、身なりを整えて広間に向かった。
広間の中からは三人の楽しそうな声がしていた。籐伍は広間の襖の前に控えると声をかけた。
「父上、籐伍です。今奉行所より戻りました。お客様がいらしてはると聞いてご挨拶に伺いました」
籐伍の呼びかけに一瞬声が止んだが、すぐ父の声が返ってきた。
「おお戻ったか。かまへんから入りなさい。みんなお前を待ってたんや」
自分を待っていたという父の返答に不思議さを覚えながら、籐伍は広間の中に入った。
中では父の念十郎と大塩が向かい合って、父の横に恭一郎が座っている。三人の前には膳が据えられ、酒と肴が置かれていた。
久しぶりの大塩が籐伍を手招きして「久しいな、まぁここに座れ」と自分の横を指した。
いわれるままに籐伍が大塩の横に座ると、にこやかな大塩が籐伍の背をたたいた。
「今回はお手柄やったな。まだ出仕間もないのに、もう賊の尻尾を掴むとは。やっぱり念十郎の息子はちゃうわ」
そういいながら自分の杯を空けると、それに酒器から新たな酒を注いで籐伍に渡した。
「まぁ飲め」
大塩は普段謹厳な人物なのだが、親しい阿刀家に来たときは妙に砕けた大酒飲みに変貌する。他人には見せない裃を脱いだ姿である。籐伍にとってはこちらの大塩の姿の方が馴染み深かった。
籐伍は杯の酒を飲み干して、大塩の膳に空杯を返した。それを待っていたように大塩が語り出した。
「今日はそっちのお奉行様に呼ばれて西町に行ったんやが、予定より早うに会見が終わって時間ができてしもた。それで久しぶりに念十郎に会いとうなってな。こいつも今日は早うに帰れるいうんで、久しぶりに一杯やろうかということになったんや。籐伍には土産も持ってきたしな」
そういいながら、空いた杯に再び酒を注いで飲み始めていた。
「なんで恭兄まで一緒なんですか」
父と大塩はまだ分かるが、不思議な取り合わせの恭一郎のことを聞いた。
「何、此奴は今日の護衛役や。わしはともかく、平八は重要人物やからな。こいつ供回りを先に東町に返してしもたんで、仕舞いの刻限にはちと早かったが恭一郎を廻り方から借りたんや。東町の大与力様の護衛にな」
顔を赤くした念十郎が楽しそうに語った。
大塩は大坂の重要人物だった。供回りなしで動くことは珍しい。
「それだけやないで、今日も西町のお奉行には鬼没盗の件を自慢されたわ。お前がもう一歩のところまで追い詰めたいうてな。東町にもその噂は流れとるが、まだ詳しいことは伝わってへん。それでお前と親しい恭一郎に話を聞こう思うてな、念十郎に頼んだんや」
今日の大塩は妙に饒舌だった。それに大塩と恭一郎は初対面ではない。籐伍がまだ酒を飲めない子供の頃は、代わりに恭一郎が大塩の酒宴に呼ばれ相手をすることも多かった。恭一郎の将来のために、東町の与力とよしみを通じさせる思惑が念十郎にあったのだろう。
恭一郎ははにかむように笑っている。
「恭一郎から閻魔の市での鬼没盗のこと、大体のあらましは聞いたで。あとは籐伍から詳しゅうに聞かしてんか。東町に帰って自慢できるわ」
どこまで本気なのか、大塩は真剣な表情で尋ねてきた。
大坂の東西奉行所は月番交代で業務を執行している。経済政策などは非番の月も行われるが、犯罪捜査に関してはその時の月番で最初に事件に着手した方が担当となる。鬼没盗の場合は西町が最初に着手したので、以降は西町の担当になったのだ。
だが東町としてもただ眺めているわけではない。いつ別の形や事件でお鉢が回ってくるか判らないので、情報収集はしている。
東町の大物与力である大塩が、ただの興味本位で事件を訊くことも籐伍を褒めることもないだろう。これもまた大塩の情報収集の一環なのだ。
もしかしたら西町奉行との会見自体も、念十郎に接触して詳細を聞き出す手管かもしれなかった。当然念十郎は、多分恭一郎もそれを踏まえた上で、こうして酒宴を張っているのだ。互いの情報戦というよりも「持ちつ持たれつ」の部分でもある。
大塩に求められるままに、籐伍は閻魔の市でのことを語った。
大塩は興味深そうに籐伍の話を聞いた。市を襲う直前にしたという「沈香の香り」については、何かを思い巡らせるように少し考え込んでいた。
籐伍が鬼没盗の狙う骨董品が飛鳥時代に関わる物で、しかも「聖徳太子」と謂れがある物なのかもしれないと私見を披露すると、大塩は「そうや、忘れてたわ」と呟いた。
「今日はお前に土産があったんや。帰りが遅うなるようやったら念十郎に託そう思うとったが、直接渡せるんやったら説明もできて好都合や」
そういいながら、後ろに置いてあった風呂敷き包みを手に取ると、中から古びた木箱を出してきた。大きくはないがお札か文書を入れるような黒い漆塗りの文箱である。
その文箱を目の上に上げて一礼すると、徐に籐伍の前に置いた。訳のわからない籐伍は、置かれた箱と大塩の顔を見比べていた。
「これが今日のわしから籐伍への土産や。この土産をどう使うかは籐伍の深慮次第やで。うまいこと使うたら鬼没盗を捕まえられるかもしれへん。そこをよう考えて使い」
そういうと酒器に残っていた酒を全て杯に注いで、旨そうに飲み干した。空になった酒器を振りながら、「鈴ちゃん、酒がのうなってしもうた」と厨に声をあげた。
その声を待っていたように、鈴と燕、小春と梅ができあがった料理を満載した膳を広間に運んできた。それぞれの前に膳を置くと、改めて酒を持ってきて皆に配った。
皆はしばらく、鈴、燕の運んだ膳の料理を美味そうに食べていた。もちろん互いに酒も注ぎ合い、飲み干している。往時によく行われていた大塩との酒宴が久々に蘇っていた。
燕が大塩の杯に酒を注ぐと「ありがとうな鈴ちゃん。そやけどえらい別嬪はんになったなあ」と、顔をしげしげと眺めて呟いた。
「お褒めいただいてありがとうございます。そやけどなぁ、おじさま。うちは燕やで」
そういいながら、恭一郎に酌をしていた鈴と顔を見合わせて微笑んだ。
「これはすまん。生まれた時から見てるのに、まだ間違えるとはわしも耄碌してしもたな」
そういいながら注がれた酒を飲み干した。
「そやけどな、二人はよう似てるんや。鈴ちゃん褒めたら自然と燕ちゃんも褒めたことになんねん。違うか念十郎」
屁理屈を捏ねながら念十郎に同意を求めた。念十郎も「その通りや。鈴も燕も二人とおらん別嬪や」と同意した。
「二人とおらんことあらへん。ちゃんとここに二人いてるわ」
そう燕が抗議すると、広間の全員が思わず笑った。
「まあ、恭兄はんは違うんやろうけどな。鈴ちゃん一人しか見えてへんし」
燕の言葉に皆の視線が恭一郎に集まった。見られた恭一郎はどう反応して良いのか判らず、珍しく下を向いてしまった。
「ねえおじさま。うちにも誰かええ人捜してくれへん。このままやったら置いてけぼりや」
そう大塩にいいながら、燕は二杯目の酌をした。
大塩は大きく頷きながら「ええか、念十郎」と尋ねた。
念十郎は「その話は又にしよう」とだけいって、小春の注いでくれた酒を飲んだ。
念十郎は鈴と燕の嫁入り話が好きではなかった。それは男親としての心情以上に、二人が生まれてから今に至る、少し辛い人生を思ってのことだ。
この時代、双子はあまり歓迎されなかった。双子出産は「畜生腹」とも呼ばれて、多くの場合生まれてすぐに一方は養子に出されるのが普通である。双子は家にとって縁起が悪く、男子なら御家騒動の元凶ともなる。
鈴と燕が生まれたときも、親戚からはどちらかを養子に出すように求められた。だが念十郎は頑としてそれに応じず、手元で二人を育てることにしたのだ。それは妻の皐月の願いでもあった。
だが同じ顔の娘が連れ立って町を歩くのは、当然目立つし注目される。武家付き合いでは眉を潜める者も多い。稽古ごとなどでも二人を一緒に受け入れる師匠も少なかった。
だが二人は世間の目など無視するように、常に一緒に行動した。今も昔も、二人は互いを自分の半身だと感じている。今日まで二人で助け合いながら、冷たい眼差しの浮世を渡ってきたという思いが強かった。
恭一郎が鈴を好いていると知りながら、鈴自身も念十郎も今日まで嫁入り話を進めなかったのはそんな心理が奥にあったからだ。
燕もそうした家族の気持ちをよく知るだけに、敢えて大塩に嫁入り先の話をしたのかもしれなかった。嫁げば皆が楽になるとどこかで思っていた。
燕は男勝りで大雑把な性格の娘だが、心根の優しさは決して鈴に負けていなかった。
そんな広間の状況とは無関係に、籐伍は置かれた漆黒の文箱を開いて、土産を見ていた。
それは古文書のようであり、籐伍にはその内容がよく判読できなかった。ただ文書の冒頭に古い字体で「未然」と記されているのだけが読めた。
籐伍は「未然」という古文書のことは全く知らなかった。
「おじさん、この未然て何ですの。どうしてこれで鬼没盗を捕まえられるんですか」
心に浮かぶ疑問の言葉をそののまま声に出していた。
燕の嫁入り先の話題をひとまず置くように、大塩は念十郎の方に向かった。何やら怪しい笑いを浮かべながら声をかけた。
「念十郎は未然記を知っておるか」
念十郎は不服そうに首をふった。
この二人は友ではあるが、ある意味東西奉行所を代表する好敵手でもある。その相手に知らぬとはいいたくはなかった。
「ならば西の大番役殿に教えてしんぜよう。未然記または未然本記とは四天王寺に伝わる秘文書のことや」
大塩の言葉に、籐伍は「あっ」と思った。そういえば鬼没盗により盗まれたお宝の中に「四天王寺の秘文書の拓本」というものがあったことを思い出した。
「四天王寺の秘文書っていうのは、あの楠木正成公が写しとったという奴ですか。確か鬼没盗の盗んだ物の中にあったと思いますが」
籐伍が声を上げると、大塩は難問を解いた子供を褒める顔になった。
「さすが籐伍じゃ。よう覚えておったな。未然記とは四天王寺に古来より伝わるといわれた、聖徳太子が記された未来を語った予言書のことよ。太平記によると楠木正成公はこの未然記を四天王寺で読んで、南朝の後醍醐天皇に味方すると決めたとも伝わっておる。その折に楠木公は未然記の一部を写し取ったといわれておるんや。そして写し文の重要な文言を石に刻んで残したともな。鬼没盗に盗まれた拓本は、楠木公が石に刻んだものの拓本であるという噂やで。ほんまかどうかはわからへんけどな」
聖徳太子による未来予言、それは日本書紀の中にも記されている。
書紀には「太子兼知未然」とあり、「太子、兼(か)ねてより未(いま)だ然(し)らざるを知る」と読む。
籐伍は頭の中で火花が散ったように感じた。飛鳥と無縁と思っていた拓本が、実は最も飛鳥に近い遺物であったことに震えた。
「籐伍は先ほど、私見としながらも鬼没盗が狙うお宝は飛鳥や聖徳太子に関わる物のように思えるというたな。わしは鬼没盗のことはよう知らんが、東町で楠木公の拓本かもしれへんいう被害物のことを聞いて、この未然記の伝説を思い出したんや。奇しくもお前の目星と、わしの推察が一致したことになるなぁ。誠に重畳なことや」
そういうと大塩は杯を燕の方に差し出した。燕は改めて大塩の杯に酒を注いでいった。
籐伍は必死に大塩の言葉を理解しながら、自分の疑問を口にした。
「しかし、楠木公の拓本はもう盗まれてます。ではこの古文書は何なんですか」
籐伍の疑問になぜか念十郎が答えた。
「そういうことか……その古文書は盗まれた拓本の大元、拓本にする前の未然記原本か楠木公が写し取った写本ということや」
そして「この詐欺師が」と呟いた。
手にした杯を飲み干すと、怒ったように小春に酒を注がせた。
すると恭一郎もゆっくりと「なるほど……囮ですか」と、何かを納得するように呟いた。
念十郎と恭一郎の言葉に、籐伍は訳がわからないという表情をした。籐伍がまだ理解できていないと察した大塩は、噛んで含めるように説明した。
「盗まれた拓本は未然記の極一部が刻まれたに過ぎぬ物や。やけどもしここに、未然記の全文を記した古文書があると知れたなら鬼没盗はどないするやろうな」
籐伍は背筋に稲妻が疾ったように感じた。そして「鬼没盗がこの古文書を盗みにやってくる」と閃いた。
「鬼没盗が盗みにきます」
そう小さく呟いた籐伍だったが、同時に新たな疑問が湧いてきた。
何故大塩がそんな未然記の原本か楠木公の写本を持っているのだろうか。極一部を記した拓本さえ貴重な遺物なのだ。いかに高名な陽明学者の大塩とはいえ、そんな伝説の未然記がここにあることがおかしかった。
その疑問を口にしようとしたとき、「この詐欺師が」という父の言葉が蘇った。そして籐伍もやっと全てを理解した。
この未然記の写本は偽物なのだ。そしてこの偽物の未然記を餌にして鬼没盗を誘き出せと大塩が示唆していることを。
恭一郎が「囮」といった言葉の意味がようやく分かった。
実戦で探索をしてきた二人は、早々に大塩の意図を理解していたのだ。
「ではこれは偽物の未然記なんですね」
言わずもがなの確認を籐伍は言葉にした。
「そういうことや。しかしなぁ、鬼没盗が本物やと思えば本物の役目は果たすもんや」
ゆっくりと何かを含んだようにいうと、大塩にしては珍しく少し悪どい笑みを浮かべた。
全員がちょっと沈黙していた。
大塩は徐に立ち上がると、ふらつきながら念十郎に頭を下げた。
「今日は馳走になったな。久しぶりに楽しゅうて飲みすぎたようや。今宵はこの辺りで帰るのがよいやろう。土産の説明もできたし、籐伍にもゆっくり考える時間がいるしなぁ」
「帰るわ」というと、ふらつきながら広間を出ようとした。
念十郎が恭一郎の方を見たので、恭一郎が「お送りいたします」といって立ち上がった。そして大塩の後を追った。
「燕ちゃん、何も心配せんでええで。この大塩が燕ちゃんの気にいる嫁入り先探したるさかいな。念十郎には文句いわせへん」
それだけいうと大塩は恭一郎に支えられ廊下を歩き出した。
「おじさま、お見送りいたします」と鈴と燕が二人を追った。
広間に残っていた空の膳を、小春と梅が手際良く厨に運んで行った。広間には籐伍と念十郎だけが取り残されていた。
二人は沈黙したまま、手酌で酒を飲んでいた。ただ二人とも心はここになく、大塩の残した土産について考えていた。
父の酒がなくなったようなので、籐伍が自分の酒器を持って父の前に座った。そして黙って父の杯に酒を注いでいった。
「父上は大塩のおじさんの土産、どう思われますか」
やっとそれだけを言葉にして酒を飲む父を見つめていた。こんなふうに父と語るのも酒を飲むのも、籐伍には初めてのことだった。それは今までよりも少し大人の男同士の関係かもしれない。
「平八は頭が良いが、ときに良すぎることがあるんや。そやからこないな誰も思いつかん奇策も思いつく。じゃが……わしは好かんやり方や。平八には世の中を自分の策で動かせると思うところがある。そやけどなぁ、それはあいつにとっても危い思い込みやと思うで」
そういうと自分の杯を籐伍に渡し、それに酒を注いだ。父に酌をしてもらうのは初めてのことだった。
「ただ鬼没盗を捕らえる妙手であるには違いないやろう。実際には難しいところもあるけどな。お前がやってみたいんやったらやったらええ。これはお前の捕り物や」
そういうと父は立ち上がり、自室に退いて行った。
後に残った籐伍は、手に持っていた偽物の未然記をしばらく見つめていたが、やがてそれを畳むと文箱に戻した。文箱をしっかりと持つと籐伍もまた自分の部屋に戻ろうとした。
ただ籐伍の心の中は「どうすれば偽未然記で鬼没盗を誘き出せるのだろうか」という思案で一杯だった。
思わぬ大塩の助け船で、再び鬼没盗を捕える方策を手にできた喜びに満ちていた。
(二)
大塩の訪問からしばらく、籐伍は偽未然記を使った囮の策謀に悩んでいた。どうやれば鬼没盗が誘き出せるのか、これはなかなかの難問だった。
父がいうように実行の部分に難題があった。
多分普通に噂を流しても、鬼没盗がそれを信ずるかどうかは怪しい。それらしい状況を用意しなければ、鬼没盗も出てはこないだろうと思われた。
これまでは分限者の秘蔵する骨董品や、閻魔の市を急襲してお宝を奪っているのである。困難さを伴い、それ以上に信憑性の高いお膳立てをする必要があった。それでないと鬼没盗もおいそれとは盗みにこないだろう。その方策をなかなか思いつかなかった。
そんなとき、不意に渦彦が籐伍を訪ねて西町奉行所を訪れた。囮の策略のことはいったん忘れて籐伍は喜んで渦彦を迎えた。
「ようこときてくれたな。待っとったで」
陽気に出迎えた籐伍とは裏腹に、渦彦は少し沈鬱な表情だった。奉行所を訪れることを、まだどこかで自分に納得させていないのかもしれない。
渦彦は籐伍に対してまず宣言した。
「わいがここに来たんは、あんたの手下になるためとちゃうで。あんたを利用するためや。それでもよかったら協力したる。五分五分の協力ならな。あんたに利用する価値があらへんかったら、後は一人でやらしてもらう。あくまでわいの目的は御神宝を探すことやからな。鬼没盗を捕らえることやあらへんで」
それだけいうと、通された籐伍の控え間に座り込んだ。渦彦はまっすぐ籐伍の目を見ながら動かなかった。
籐伍はそんな渦彦の様子をしげしげと観察しながら、少し可笑しくなった。あの初めて出会った夜と同じやなと思った。木津川の土手道で座り込んだ渦彦の姿を思い出した。
「こいつ精一杯弱みを見せんようにしてる」
よく考えればいかに不思議な強さを持つとはいえ、まだ年若い少年である。奉行所の役人と話し合いなどしたことはないだろう。それだけに甘く見られないように背伸びしているのだ。奉行所に出仕したばかりの頃の自分と同じだと思った。
籐伍は微笑みながらゆっくりと渦彦の前に座った。なんだか急に渦彦が弟のように思えた。いつも自分がいる場所に今は渦彦がいる。
「それでかまへんで、五分五分で行こう。わいも渦彦を利用させてもらうし、渦彦もわいを利用したらええ。それでお互いの目的を果たそうや。それがわいらの協力や。ただ一つ、これだけは守ってんか。お互いに秘密は無しや。そうやないと信頼が築けへんんからな。鬼没盗と渦彦の実家の御神宝に関しては何でも言い合おう」
籐伍が真剣な顔で静かに語った。それが二人の誓いの文言だった。
渦彦が黙って頷くと、籐伍も黙ったまま首肯した。それで二人は相棒になった。
何かに納得したように、渦彦の体から力が抜けるのを感じた。籐伍も表情を和らげて砕けた調子になった。
「まずは、わいから話そうか。これまでに判明しとる鬼没盗のことや」
籐伍が知る鬼没盗のことを話しだした。それを黙って聞いていた渦彦は、だんだんと心が苦しくなってきた。
この仮役与力は何の疑いも持たず、自分の知る鬼没盗のことを語っている。だが渦彦は違った。まだいくつか秘密を持っている。鴻池の御隠居のことはともかく、話していない木霊を打ち返されたことや、閻魔の市を襲った沈香が徳陀子神社の出かも知れないという疑念を隠していた。
そんな渦彦の思いとは別に、今度は籐伍が渦彦に尋ねてきた。
「今度は渦彦の実家の御神宝のこと聞かしてんか。渦彦の実家の神社は大和の葛城山にあるんやろ。どないな謂れの神社なん」
籐伍の質問に渦彦は初めて他人に実家のことを語り出した。それは籐伍にとっても少し意外な、そして思わぬ内容を含んだものだった。
徳陀子神社は大和の葛城山中腹にある千年の古社である。御祭神は少彦名命、大己貴命、神農炎帝などの医薬の神々と巨勢氏の祖神。そして多くの秘薬があることなどを語った。
「なるほどなぁ、古いとはいえ、聞く限り普通の神社やなぁ。盗まれた御神宝はその秘薬の一つやないんやな」
こうして改めて神社のことを語ることも、外の人間に意見を聞くことも初めてだった。
「兄上によるとそれはないらしいわ。大切な部分は口伝で伝えるんで、盗まれへんいうてたから、ただ……」
渦彦はここで不意に兄と仙薬洞でのことを思いだした。何冊かの沈香の調合法の冊子が失われていたことである。
渦彦とは別に、籐伍も別なことに意識が行っていた。
「そやけど徳陀子神社いうんはけったいな名前やな。地名ではないみたいやし、何かの呪文みたいや」
渦彦は自分の知る社名の由来を語り出した。
「徳陀子いうんはご先祖様の名前やいうことや。なんでも昔に巨勢徳多いう人がおって、その人は朝廷の大臣にもなったいうことで、その人をお祀りして社名にもしてるいうことらしい、徳陀子は徳多の別名やいうことや」
渦彦の言葉に籐伍は何気なく呟いた。
「ほう、凄いなあ。昔の朝廷の大臣やなんて、渦彦の家は名門やないか。武士でいうたら徳川様の側近か御老中やで。それはいつぐらいの人なん」
渦彦は昔父に教えられた社伝を思い出した。
「確か飛鳥に都があった頃の話で、何やら聖徳太子や幾代かの天子様に仕えてたらしい。父上は朝廷の護衛やら戦の先陣なんか務めてたいうてたわ」
渦彦の言葉に籐伍が驚いた。
「飛鳥の頃、聖徳太子……」
渦彦の実家は、鬼没盗が盗みの対象にしていると思われる飛鳥や聖徳太子に関わる神社だというのだ。ならばその神社の御神宝が鬼没盗に盗まれていても不思議ではない。
「まだわいの推量やけど」と籐伍は断りながら、鬼没盗の盗む対象が飛鳥や聖徳太子に関わるお宝かもしれへんと渦彦に説明した。「やっぱり鬼没盗と徳陀子神社の御神宝盗難は関係あるんかもしれへんな」と結論づけた。
籐伍の説明に渦彦もびっくりした。全く無関係と思っていた大坂の盗賊と、実家の謂れが関係をしているとは思ってもみなかった。
渦彦は再び閻魔の市で打ち返された木霊のこと、覚えのある沈香の香りを思い出した。細い細い糸だった徳陀子神社と鬼没盗の繋がりが、一段階太くなったように感じた。
だがこの事実をここで語ることは憚られた。まず大和の兄にこのことを伝えて判断を仰ごうと思った。ことは徳陀子神社にまで及ぶかもしれないのだ。何の確信もないのに軽々には語れなかった。
渦彦の思いとは別に、籐伍はさらに踏み込んで話し始めた。先日の大塩からの土産の話をしたのだ。籐伍は渦彦に対しては警戒心がなかった。
「そやから、その偽物の未然記を上手いこと使うたら、鬼没盗を誘き出せるかも知れへんねん。ただ鬼没盗に未然記が本物やと信じさせて、盗みに来るようにすることが難しい。それらしい状況を作ることが必要やからな」
籐伍は自分の頭の中をもう一度整理するように渦彦に話した。
黙って聞いていた渦彦はよくわからないと言いたげに質問した。
「鬼没盗が偽未然記を本物やと信じる状況て、具体的には何なん。例えば誰が持っとったら信じんねん」
渦彦の質問は堂々巡りをしていた籐伍の思考を解きほぐした。
確かに状況を全て一緒に考えて、今まで混乱していた。状況の要素を分解して、「いつ」「誰が」「どこに」持っていれば、偽未然記は本物らしくなるのか、と考えた方がスッキリする。芝居の舞台立てと同じだと思った。観客に納得させる舞台立てとは「時」と「場」と「人」の設定である。
そのためには、これまで鬼没盗が襲った現場を再現することが一番だと思った。
前に作った鬼没盗の箇条書きされた短冊を思い出した。襲撃現場の要素はこうだった。
「大店の主人か分限者」
「骨董好きとして有名」
「秘蔵する骨董品」
「厳しい警戒」
「なぜか漏れている秘蔵情報」
あとは……。
そこで止まっていた籐伍に、渦彦があっさりといった。
「なんや、簡単やないか。要は未然記を買えるぐらいの骨董好きの大金持ちに持ってもろうて、家を警戒してもらう。それで密かに骨董屋なんかに話したらええ。それで鬼没盗の耳にも入るんちゃうか」
渦彦の言葉に、籐伍は「あっ」と思った。確かにそれだとこれまで鬼没盗が襲った状況が再現されている。だが最後の「密かに骨董屋に話す」とはどういう意味だろうと思った。
籐伍の疑問に渦彦は自慢げに話し出した。
「ええか、わいも御神宝探すために骨董街に日参したんや。そのとき知ったことやが、骨董屋同士は情報交換してんねん。誰が、どんな骨董品を売ったか買ったかをな。つまり骨董の買い元、売り元の情報を知っとったら、誰が今何を持っとるかが、大体わかるいうことや。籐伍は鬼没盗がどうやってお宝の持ち主を知っとるかわからへんというとったが、お宝はだいたい骨董屋が運ぶもんや。ある日突然に湧いて出てきたりせん。骨董屋の後付けて行った方が鬼没盗も目当てのお宝の在処がわかるんとちゃうか」
渦彦の言葉に籐伍は唖然とした。よくそんなことを知ってると思った。
だがそれは渦彦が本当に必死になって、御神宝を探していた証だった。必死に喰らい付いていたからこそ、渦彦は骨董屋の些細なことにも気がつき観察できたのだった。
渦彦が整理してくれた現場設定を聞き、籐伍はやはり難しいと思った。
まず大金持ちの骨董好きが思い当たらない。しかも鬼没盗を誘き寄せるのだから、ことは隠密に進める必要がある。上手く鬼没盗を誘き出せたとしても、当然押し込まれるのだから危険が伴う。そこまでして奉行所に協力してくれる金持ちなどいるものだろうか。
「やっぱりあかんわ。舞台立てになる金持ちがいてへん。都合ように湧いて出るなんて、芝居と違ごうて現実にはあらへんからなぁ」
籐伍の失望する言葉に、渦彦は何かを決心してに立ち上がった。
「わいに任せたらええ。ちょうどぴったりの人紹介したるわ。その代わり、この囮の件以外は何も聞いたらあかんで。なんで協力するかもや。それやったら紹介したる。これはわいが籐伍の相棒になるいう証や」
そう語る渦彦の脳裏には鴻池の御隠居の姿があった。多分後隠居は協力してくれるという確信がある。御隠居は鬼没盗を骨董収集の競争相手と捉えていた。しかも鬼没盗に興味を持っている。何より、御隠居はこうした面白い企てに加担することが大好きなのだ。
渦彦が奉行所を訪ねた数日後、籐伍は鴻池家の隠居所にいた。
丁寧に未然記囮策のあらましと、それへの協力を要請した。横には渦彦も控えている。
二人の目の前で、御隠居は大様に銀の煙管で煙草を吹かしていた。その煙が籐伍のところにまで流れている。
「おおよその話は渦彦から聞きました。ところで阿刀様はわてのこと知っておますか」
そういうと、御隠居はもう一服煙草を吹かせた。その煙が再び籐伍の元にまで流れている。籐伍は少し煙たいと思ったが、気にせずに答えた。
「お名前は存じております。大坂で知らぬ者もおらん鴻池家の御隠居と」
御隠居は満足そうに煙管を灰皿に叩くと、中に火草を落とした。
「確か西町の諸色方にも同じお名の与力様がおられたと思いましたが」
声は少し硬くなっていたが、目はまだ笑っているようだった。
「それは私の父だと思います。私は諸色方大番役与力、阿刀念十郎の一子、籐伍と申します。今は吟味方仮役与力として鬼没盗を追っています」
御隠居は成程というように頷いた。
「お父君の阿刀様はわてら商人には難儀なお方や。なんせ袖の下が通じへん。そして何より儲けよりも公正さを優先させはる。難儀やけど、まあ不思議と信用はできるお役人や。お役人には結構珍しいけどな」
そしていきなり籐伍に聞いてきた。
「ところで鬼没盗捕縛に協力したら、どないな利がわてにありますか。それ次第で阿刀様の捕り物に協力しまひょう。どないですか」
そう何かを確かめるように籐伍の顔を覗き見た。この答え次第で否応を決めたいという意思表示に思えた。
言葉に詰まった籐伍だったが、隠居所を訪れる前に渦彦にされた忠告を思い出した。
「御隠居は変わり者やけど、『信』と『理』のない者を一番嫌うとる。『利』やないで『理』や。逆に『利』を示す者は相手にせえへん。『利』で人を転ばせる者は自身も『利』で転ぶいうてたわ。そやから籐伍の中にある『信』と『理』を話したらええ。それが一番御隠居を動かす早道や」
籐伍は鬼没盗に対する自分の姿勢を顧みた。そしてただそれのみを語ればよいのかもしれないと思った。
「御隠居に直接の利は何もありまへん。いえ、むしろ危険さえあると思います。ですが、鬼没盗を捕らえなければ世の安寧が保てません。安寧がなければ骨董を楽しむことも、商いをすることさえ危うくなります。私も最初は鬼没盗捕縛を、父や奉行所の上役に禁止された芝居小屋通い再開のための手柄にしよう思うてただけでした。しかしそれさえも世の安寧があってのことです。成り行きとはいえ半年前に仮役与力になったばかりの私が、今は鬼没盗を捕縛する任にあります。これは天が与えた試練であり、命だと思います。小さいかもしれまへんが、世の安寧を守るためのお役目です」
そこまで一気に語った籐伍だったが少し考え込んだ。付け加えるよう渦彦の方を見た。
「それにこの渦彦とも知り合え、今は友になれました。渦彦はまだ若いのに父の死という苦難を乗り越えようとしています。私の推察では渦彦の苦難の元に鬼没盗がいるように思われます。ですから私は役目である以上に、友のためにも鬼没盗を捕らえたいのです。御隠居は渦彦とご縁があると伺いました。ならば失礼ですが縁ある若者の未来のために、年の功と御名を僅かばかりでもお貸し願いたい。それが後の世への功徳だと思います」
言い切った籐伍は、御隠居に深く頭を下げた。だが心の中では「言い過ぎてしもた」と後悔の念が湧き出ていた。
怖い目になっていた御隠居は、ゆっくりとあらぬ方向に向くと大きくため息をついた。
「利は一切ないが危険はある。それやけど、後の世への功徳のために協力せえと言わはるか……。こんないなことわてに言うたん、今まで誰もおらなんだわ。腹立つ物言いやが、おもろい口上ではあったな」
沈黙したまま何かを思案していた御隠居は、徐に自分の座布団を外すと畳の上に正座した。そして両手を畳につけると、深々と籐伍に平伏した。
「阿刀様。これまでの無礼な仕儀、平にお許しくださりませ。商人が決してお武家にとる態度ではありまへんでした。ただ私はあなた様の真ん中にある物を見たかったのでございます。それゆえ不埒な振る舞いもいたしました。それにも関わらず、あなた様は真摯に自分の真ん中をお見せ下さりました。誠に痛み入りまする」
しばらく御隠居は頭を上げなかった。
どうしてよいのか困った籐伍は横の渦彦の方を見たが、渦彦も困惑した表情だった。
「わての微名と年の功、使えるもんがあったらなんぼでもご利用くだされ。それがこれまで好きに商いさせてもろうた世間様への恩返しと心得ます。もう残り少ない命や、世の安寧の為に使えるんやたら本望。利はあの世に行ってから閻魔大王に戴くことにしまっさかいに」
顔を伏せたまま御隠居は語った。
顔を上げた御隠居は破顔したような笑い顔だった。何かに満足したような表情である。
「それにや、こないなおもろい捕り物、たとえあと何年生きようとも二度とは見られへん。道頓堀にかかるどんな芝居よりおもろいで。阿刀様、是非にもこの老ぼれの願いを一つだけお聞き届けください」
籐伍と渦彦は御隠居のいう願いがわからなかった。二人は少し顔を見合わせると同時に声が出ていた。
「御隠居、願いとは何ですか」
ニヤリと嬉しそうに笑う御隠居がゆっくりと口を開いた。
「それはもちろん、鬼没盗捕縛を齧り付き席で見物させてもらうことや」
御隠居の言葉に二人は固まった。
籐伍の思惑では、御隠居の名前と隠居所を借りられたなら、御隠居自身には安全なところに一時退いてもらうつもりだった。
分限者という以上に、高齢の御隠居を押し込み盗賊を誘う場所には置いておけない。身替わりを立てるつもりだった。
だが御隠居は齧り付きで捕縛を見たいという。つまりこの場に居残るといっているのだ。これは中々難問である。籐伍が許さない以上に多分奉行所が許さないだろう。
鴻池家は奉行所に対してもかなり大口の付け届けをしている商家なのだ。その御隠居を危険に晒すことは奉行所が許さない。責任問題以上に、何かあれば直接の実入りを失う可能性があるのだ。
どう答えようか唸っていると、渦彦があっさり御隠居の希望を否定した。
「御隠居様、それは無理筋やと思います。御隠居様の身はわいが守るとしても、あんまり近すぎたら舞台が全部見えへん。ここは少し離れたところから見物するが上策やと思います。齧り付きやのうて、桟敷の方がええんちゃいますか」
御隠居は「桟敷」と呟くと、「それはどこや」と尋ねてきた。
渦彦は黙って縁側の向こうに見える隣家の屋根を指差した。隣家はある商家の主人の囲い女の家だった。
「そやけどあの家は讃岐屋はんのお妾の家やで」
そういう御隠居に渦彦は自信たっぷりに答えた。
「それは先頃までです。この前番頭はんに聞いたところでは、讃岐屋の御亭主は若いお妾を別のところに囲われたそうで、隣家のお妾はんには暇を出されたとのことでした。それで先日、引越しのご挨拶に来られたとか。そやから今は空き家やということです」
渦彦はさらに続けた。
「あの隣家の屋根の上に縁台か物干し台を作ったら、ちょうどこちらの家が丸見えにできます。こんな特等席の桟敷はあらしまへん」
実は渦彦がこの隠居所に住み始めたときから、隣家の屋根上は気になっていたのだった。あそこから覗かれれば隠居所が丸見えになると。だから御隠居と隠居所の警護を任されたときから、隣家の屋根上には気を配った。
だが逆にあの場所を手にできれば、絶好の物見場所になる。この辺りの事情を渦彦は御隠居に説明した。今後の御隠居の安全の為にもあの場所は抑えるべきだと主張した。
「なるほど、渦彦はまるで戰の軍師みたいやな。やっぱり神人にしとくにはもったいないわ。鬼没盗を罠にかけようとする阿刀様といい、二人はええ相棒やな」
御隠居は何かに得心したように頷いた。
「わかりました。残念やけど齧り付きは諦めて、桟敷席で我慢しまひょう。讃岐屋はんにはわてから話つけますさかい、どんな桟敷席作るかは、わての好きにさせてください。日本一の桟敷席作りまっさかい」
籐伍も渦彦もひとまずはほっとした。これで未然記囮策を始めることができるのだ。
ただ渦彦には鬼没盗と相まみえる前に確認すべきことがあった。
それは大和の兄に沈香の事を質問することだった。木霊のことも聞きたかったが、これは兄ではなく叔父の椎根津でないと無理だろう。なぜなら木霊は叔父独自の技だからだ。
叔父の椎根津は巨勢宗家の次男、渦彦の父飫肥人の弟として生まれた。ただ椎根津は少し変わり者で、神社の仕事には就かずに武芸者になったのだった。細かい経緯は知らないが、修行の旅から戻ってきた椎根津は「猿飛陰流」という剣術を修得していたらしい。
そして葛城山の東方、桜井の地に猿飛陰流の剣術道場を開いたのだった。
もちろん巨勢宗家の生まれなので蹴速術は修得している。いや単に修得ではなく蹴速術の真の継承者だった。巨勢家では惣領の長男が仙薬を学び、次男が蹴速術を極めることになっていた。それゆえ叔父根津は父の飫肥人よりも蹴速術が強かった。幼い頃から渦彦に蹴速術を教えるのも、主には椎根津の役目だったのだ。
それで父や兄も知らない技「木霊」を教えられたのだった。叔父によると木霊は蹴速術と猿飛陰流の探気の技を組み合わせて作ったものらしい。
なのに閻魔の市の夜、木霊が打ち返されてきた。本来木霊は叔父と自分だけが知る探気の技である。どうしてなのか渦彦には訳がわからなかった。
(三)
籐伍は「未然記囮策」の細かい仕様を考えて、それを策戦処方として筆頭与力の丹羽に提出した。策戦処方はあくまで極秘として、他の与力、同心衆にも秘密にするように進言した。どこから漏れるかわからないからだ。
極秘を承知した丹羽も、お奉行には知らせると呟いた。この処方の舞台が鴻池家の隠居所であるとあったからである。付け届け以上の、奉行と鴻池家には下が知らない関係があるかもしれない。それを慮った丹羽がお奉行の耳には入れるといったのだ。
だが奉行は実にあっさりとこの囮策を承認した。策戦処方の細部の詰めに協力してもらっていた恭一郎によると、すでに鴻池家から奉行の元に知らせがあったようだという。
籐伍や丹羽の知らない繋がりがやはり両者にはあるようだった。
細かく仕組まれた囮策ではあったが、一点「御隠居の影武者」だけがまだ未定だった。
今回の囮策の主役でもあるのだ。御隠居の顔を知る者はそう多くはないだろうが、鴻池の御隠居という威厳が最低限必要である。年恰好が似ている以上にこの要素は重要だった。
しかもかなり長期間、籐伍の目算では最低ひと月以上は影武者を続ける必要がある。そうなるとさらに人選が難しかった。
そんなとき籐伍は丹羽に呼び出された。
「阿刀よ、囮策の主役が決まったで。お奉行から推挙があったお人やから間違いあらへん。今日の夕刻に隠居所で顔合わせにしといたから行ってんか。お主もきっと納得するはずや」
丹羽には珍しく、何故か面白そうに籐伍に告げてきた。普段は笑うことがない丹羽だが、何故かこのときだけは少し笑っていた。
囮策の最重要点なだけに、どんな人だろうと思いながら籐伍は隠居所に向かった。
約束の時間よりも早めに隠居所に着いた籐伍は、渦彦に出迎えられた。渦彦は警護のため、先日来ここに寄宿していると語った。籐伍は御隠居と渦彦の関係を知らないので、渦彦の家は少彦名神社だと思っている。
「渦彦は御隠居の影武者が誰なんか知ってるんか」
心が逸っている籐伍はまず渦彦に尋ねた。
「いいや、わいもまだ知らへん。けど御隠居はその人選に納得されているようやから、まあ間違いないやろ」
渦彦はそういいながら籐伍を隠居所の大きな客間に案内した。縁側廊下から庭越しに隣家の屋根の上で普請が行われているのが見えた。
客間に座りながら籐伍はそのことを尋ねた。
「隣、上手いこと手に入ったんやな」
籐伍の言葉に渦彦は頷きながら、「えらい大普請になってしもうてる。御隠居が楽しんでるんや」と、やれやれというように呟いた。
しばらく待つと、客間に御隠居が入ってきた。嬉しそうに話し出した。
「阿刀様、わざわざご足労痛み入ります。そやけど今日はこの囮一座の大切な顔合わせや。皆で心を一つにせえへんと舞台が上手いこと進まへん。そこのところ、よろしゅうにお願いいたします」
御隠居は自分がこの囮策の実行部隊「囮一座」の座頭のようにいった。
そうこうしていると、女中が廊下に控えて「お客さまがお越しです」と告げてきた。
「来はったか。こちらにお通ししてんか、粗相のないようにな。何せ今日の主役やさかい」
御隠居に指示され女中は、「へえ」と答えて玄関の方に下がっていった。
影武者にやっと会えると、籐伍は少しワクワクした。程なく廊下を歩く足音が近づいてきた。
やがて廊下から客間に入ってきた人物を見て、籐伍は息を飲んだ。言葉が上手く出てこない。
「父上……」
その言葉さえ掠れていた。しかも入ってきた父の後ろに同心の河原崎が続いていた。
「なんで父上と河原崎はんがここにいてるんですか。今日は御隠居の影武者殿との顔合わせのはずですが……」
籐伍の混乱した表情とは裏腹に、父も河原崎も平然としている。
「籐伍、取り乱すんやない。ここはお役目の場やで」
父の言葉に、はっとした籐伍は少し居住まいを正した。
「阿刀様、今回の囮一座の主役はお父君や。これはお奉行様よりの差配やで。ありがたく思うこっちゃ」
そう語る御隠居に父が少し頭を下げた。
「鴻池の御隠居とこのような形でお会いするとは思いまへんでしたが、これもお役目。よろしゅうにお願いいたします」
そう慇懃にいうと、今度は籐伍の方に向かった。
「お前の策戦処方は読ませてもろうたで。実行には難のあるところもあったけど、その辺りはこの河原崎にあんじょうしてもらおう。ええか、もうこれはお前一人の話やない。奉行所の威信と信頼をかけた捕り物になったんや。そやからお奉行も私と河原崎をこの一座に加えたんや」
そういった念十郎だったが、ニヤリと笑うと言葉を付け加えた。
「やけどなあ、この捕り物がお前のものであることには変わりない。私は座付き作家殿の書いた戯作通りに動く役者にすぎへん。この河原崎も黒子の捕り方に徹するつもりや。そやから必要があれば何でもいいなさい」
父の言葉に、河原崎も「同意」というように籐伍に頭を下げた。
御隠居がここで口を挟んできた。
「そやけど同じ一座に阿刀様が二人おったらめんどいいなあ。行き違いがあっても困るし。どないでっしゃろ、ここはお父君を『阿刀様』、息子殿を『籐伍様』と呼ぶことにしまへんか」
一同はそれに賛同した。ただ籐伍はどうしても聞ききたい疑問があった。
「御隠居の影武者を父上がなさるのはわかりましたが、その間の父上本来のお役目、諸色方はどないなるんですか。鬼没盗を罠にかけるまで最低でもひと月はかかると思われます。その間は奉行所への出仕は叶いまへん」
念十郎が実にサバサバとした様子で籐伍の疑問に答えた。
「私はこのお役目を最後に隠居することにした。そやから諸色方の役目も数日のうちに全部引き継ぐつもりや。もちろんお奉行の許可も貰うてる。まあ御隠居の影武者は隠居生活の予行演習やな」
そう微笑みながらいう父の言葉に、籐伍が一番衝撃を受けた。父が隠居するということは、阿刀家の全てを籐伍が受け継ぐことになる。それは鬼没盗を捕縛する以上にとてつもなく重い役目に思えた。
「待ってください。なんぼなんでも急すぎます。わいはまだ全然一人前にはなってまへん」
狼狽える籐伍に父はピシャリといった。
「鬼没盗捕縛で一人前になったらええ。皆一人前になったから代替わりするんとちゃうで。代替りするから一人前になれるんや。違いますか御隠居」
話を急に振られた御隠居は、その通りというように頷いた。皆が一瞬沈黙したとき、黙っていた渦彦が何かを思うように話だした。
「私の兄は……、父の突然の死により何の準備もなく家と神社を受け継ぎました。もっと父には色々なことを教えて欲しかったと思います。私も苦難に立ち向かう兄を助けるために、奪われた御神宝を大坂で探索しているんです。役目を親父殿に見守ってもらえる籐伍は幸せ者やと思います」
そうぽつりと発した言葉に、皆がはっとした。籐伍も自分が甘えたことをいっていることに気がついた。
「お主が巨勢渦彦殿か。籐伍に協力してくれている友と聞いてるで。まだ若いのに殊勝な考えやな。今後とも籐伍のことをよろしゅうに頼むは」
そういうと念十郎は深々と渦彦に頭を下げた。それは良き友になって欲しいという父親の祈る姿のように見えた。
「まあこれで、囮一座の役者、戯作者、黒子が揃うた事になります。ここからはどうやって鬼没盗を罠にかけるかや。その辺の仕掛けをお話しいただけますか」
御隠居が籐伍の方に向かって話を振った。
籐伍は「うん」と頷くと、全員に向かって話しだした。
「まず御隠居と父上には密かに毎夜入れ替わっていただきます。できるだけ昼間は御隠居が隠居所にいて、夜間は影武者の父上が隠居所に入ってください。夜に鬼没盗の襲撃がある可能性が高いですよって。なるべく外の人間に顔を見られぬように願います。隠居所の警護のために本当は奉公人も入れ替えたいのですが、あんまりいっぺんに替えると周囲や出入りの人間にも怪しまれるので、隠居所の下人だけを御用聞の金蔵にします。河原崎はんには通常の見廻りを装って、隠居所の周囲を見張ってもらいます。一番最寄りの番所には夜間交代で、鬼没盗捕縛の同心、小者衆に控えていて貰います。河原崎はんにはこの捕り方『突入組』の指揮もお願いします」
ここまで語って、父と河原崎の顔を見た。二人は「承知」というように頷いた。それを確認すると、次に御隠居と渦彦に向かって話出した。
「御隠居には夜に父上と入れ替わったら、安全な隣家に控えていただきます。昼間には骨董屋を何人かこの家に呼んで、未然記の目利きの話をしてください。最近手に入れた古文書が聖徳太子の未然記かもしれへんいう噂を、骨董屋界隈に流して欲しいんです。町方のでも鴻池の御隠居が何やらえらいお宝を入手したらしいという噂を瓦版も利用して市中に流します。まずはこの二通りの噂で、鬼没盗をこの隠居所に誘き寄せる手筈です。さらに未然記の信憑性をダメ押しするために、高明な国学者である備中松山藩の平田篤胤先生を江戸より密かにこの隠居所にお招きして、未然記の鑑定をしてもらういう話も流します。丁度来月、御隠居の招きで平田先生が大坂に遊行されることになってるらしいんで、それを利用させてもらいます。私の推察では平田先生来訪の後が一番危ないと思います」
ここで籐伍は一拍置いて、渦彦に話しかけた。
「そやから渦彦には御隠居の警護と隣家屋根上の物干し台から周囲の探索を頼む。お前には見えへん敵を感じる力があるようやからな。何かを感じたらすぐに河原崎はんに知らせてんか」
そこまでいった籐伍は、渦彦の少し考え込む様子に気がついた。
「渦彦、なんかいうことあるんか」
渦彦にそう尋ねた籐伍は、しばらく隣に座る渦彦の横顔を見た。沈黙していた渦彦は何かを決心するように語り出した。
「先日大和の兄上から手紙が来たんやけど、『鬼没盗が使う皆を眠らせる沈香は、徳陀子神社からのうなっとった沈香調合法の中にある夢沈香かもしれへん』というてきました」
渦彦は父が死んだ後に徳陀子神社から秘薬の調合法の冊子が幾冊か失われており、その中に人を眠らす沈香「夢沈香」の調合法が含まれていたという兄からの手紙を語った。
渦彦や籐伍が閻魔の市で嗅いだ甘い匂いは「夢沈香」の匂いかもしれへんと兄綿津見がいってきたのだった。
「もしそれがほんまやったら、やっぱり徳陀子神社の御神宝強奪には鬼没盗が絡んでるいうことやで……」
籐伍が呟くと、河原崎が「それどんな匂いなんや」と聞いてきた。
渦彦は懐から紙に包まれた薬包を取り出した。それを前に置くと薬包を開いていった。
「これは兄上から送ってき夢沈香の見本です。眠りの効能はだいぶ削ってるらしいけど、匂いは同じらしいです」
夢沈香を見つめる皆の中で、河原崎が「失礼するで」といって薬包を手にした。そしてそっとその沈香を嗅いでみた。害がないと確認したのか、隣の念十郎に渡した。念十郎もその沈香を嗅ぐと、次に御隠居に渡した。
そうやって、その場の全員が夢沈香の香りを確認した。
「確かに、この匂いやった」
籐伍がぽつりというと、渦彦も頷いた。
「鬼没盗がこの隠居所を襲撃するときには、直前にこの香りがしてくるいうこちゃな。これはえらい前触れやで」
御隠居の独言に念十郎と河原崎が真剣な表情で頷いた。
「鬼没盗の使う手の内の一つが判明しただけでも、随分とこちらが有利や。この囮策きっと成功します」
珍しく河原崎が断言した。
籐伍は少し心配そうに渦彦を見たが、渦彦は何かを決意しているような表情をしていた。
「もし隠居所に鬼没盗が押し入ってきたら、父上は戦わずに退いて捕縛は河原崎はんの突入組に任せてください。今までの手口から考えて乱暴な手に出るとは思えまへんが、こちらが夢沈香で眠らされていないとなれば、強行な手段に出るかもしれまへんので。わいは突入組とは別働の組を使って、隠居所のあるこの町内から外に出る四つの道に関所を作り逃げ道を塞ぎます。それでもし突入組が取りこぼした賊がおっても、決してこの町内から外には出さんようにします。この隠居所は突入組と関所の二重の囲みに守られてる檻やいうことです」
ここで不安を感じた籐伍は渦彦に念を押した。
「ええか渦彦、徳陀子神社の夢沈香を使う鬼没盗の正体を暴きたい気持ちはわかるけど、今回は御隠居の護衛と索敵に徹してんか。皆が自分の持ち場を守らんと、綻びが出るさかいな。鬼没盗を捕まえたら、どうやって夢沈香を手に入れたんかは調べたる。もちろん御神宝のこともな」
そう釘を刺すと、渦彦の目を凝視した。
渦彦は「わかってる」というように頷いたが、籐伍はどこか不安を拭えなかった。
「ここまで仕組んだ囮策や、うまいこといくと信じようやないか」
御隠居は皆の気分を盛り上げるようにいうと、大きく柏手を打った。
すると待っていたように女中たちが朱の膳を運んで広間に入ってきた。各人の前に膳を並べると、朱塗りの酒器で盃に酒を注いで回った。
御隠居が籐伍に言葉を求めた。
「籐伍様、皆で成功を誓う盃や。ひと言お願いします」
籐伍は皆を見回しながらこの捕縛に挑む決心を語った。
「私はほんの半年前まではただの芝居好きの書生でした。そやけど今は鬼没盗を捕縛するために、思いもよらん人々と協力しようとしてます。人の運命は芝居よりも面白いと感じました。この舞台はきっと天の書いた演目やと思います。この舞台、きっと成功させましょう」
そう言葉を発すると、籐伍は自分の盃を一気に煽った。他の人々も籐伍に続くように盃を飲み干した。ただ渦彦だけは閻魔の市の夜に口にした酒の味を思い出して、恐る恐る盃に口をつけた。そしてやっぱり「不味いなぁ」と思った。
その三日後、いよいよ籐伍の立てた未然記囮策が始動した。
昼間に隣の隠れ家に頭巾を被って入った念十郎は、夜密かに御隠居と入れ替わっていた。
問題の桟敷席は、隠れ家の屋根上に広々とした物干し台として完成していた。この物干し台には隠れ家の内側から登れる内階段が設えられ、外から見られずに登れる構造だった。しかも四隅に立てた柱に黒い薄絹のような暗幕を付けており、夜になってからこの薄い暗幕を柱間に張ると夜の暗闇に同化して、物干し台自体が外から見えなくなっていた。まさに見えない桟敷席が完成したのである。
籐伍も念十郎もこの見えない桟敷席に驚いたが、渦彦だけは逆に喜んだ。夜の索敵に好都合だったからである。
順調に始まったかに思えた囮策だったが、一つ籐伍の思わなかっった事態が生じていた。姉の鈴と燕が町方の娘に扮して、隠居所と隠れ家の女中になっていたことだった。
二人は話し合い、父や籐伍の役に立ちたいと鴻池の御隠居に直訴したらしい。困った御隠居は念十郎に相談したが、「二人のしたいようにお願いいたす」と答えたという。
それで隠居所に燕を、隠れ家に鈴を女中としておいたのだった。双子の二人を一緒にすれば流石に目立つと御隠居も考えたらしい。
より危険度が高い隠居所に燕を置いたのは、燕に武芸の心得があったからだ。燕は籐伍と同じ小太刀の中条流平法を学んでいた。長刀を学ぶ鈴よりも屋内での護身に向いていると思えたからだった。
籐伍は大反対したのだが、「戦は男子のものだけやあらへんで」という二人の強い意志には結局勝てなかった。
こうして阿刀家がまるまま、隠居所と隠れ家に移り住む状態になってしまった。籐伍だけが天満橋北の家と奉行所、そして基地にしている番所を巡る生活を送ることになったのだった。
(四)
大坂市中を様々な噂話が飛び交っていた。
もちろん鴻池の御隠居が世にも稀な宝を手に入れたという噂も含まれている。やがて瓦版に「鴻池老人、未来を記す秘文を手にする」という怪奇な記事が連日世に流布されていった。
その噂を後押しするように骨董街界隈では「未然記」という言葉が囁かれ始めていた。
未然記に詳しい知識を持つ者ほど「まさかそんなものがあるはずがない」と思っていたが、彼らの思いを揺るがす新たな噂が生じたのだった。
江戸の国学者・平田篤胤が鴻池の隠居所に遊行するとの風聞である。
まだ先のことだが真実だけに、その前段の噂「未然記」の存在を多くの人が信じ始めた。平田篤胤遊行の目的が「未然記の鑑定」ではないのかという憶測がどこからともなく流れていた。
籐伍の描いた戯作に対し、観客が思惑通りの反応を示し始めたのだった。
渦彦は毎夜薄い暗幕を張った隠れ家の物干し台で、周囲の警戒と索敵にあたっていた。
御隠居の「まだ噂は広まり始めたばかりやから、今から毎晩探索せんでもええんちゃうんか」という疑問に対して、真剣な表情で渦彦は反論した。
「わいが閻魔の市で鬼没盗の襲来を見逃したんは、自分の探索の力を過信してたからです。普段からこの地の動き、いつ頃、どこで人が動くんかという知識があれば、そこから外れた反応に鬼没盗の可能性が高まります。そやから普段のこの街の様子を見てるんです」
渦彦は今でも月読楼別館の階上に感じた、不審な木霊を見過ごしてしまったことを悔やんでいた。別館の構造を知っていれば、階上の木霊にもっと注目していただろうと思う。
あの失敗を繰り返さないためにも、今回は街の状況を熟知しておこうと考えていた。何よりそれが、父の死に関わるかもしれない鬼没盗を捕らえる近道であると思った。
「今度こそ、わいの力で鬼没盗を捕まえたる」
渦彦は少し焦った思いでいっぱいだった。
実は先日きた兄からの手紙には夢沈香とは別のことも記されていた。それはまだ誰にもいってないが、渦彦にとっては衝撃的な内容だった。
「徳陀子神社の仙薬、夢沈香が奪われているかもしれへんいうことは、もう一つの秘術『蹴速術』も賊の手にあるんかもしれん」
これまでの経緯を書いた渦彦の手紙から、兄の導き出した推論だった。
「そんな阿保なことあらへんわ」と思いながらも、渦彦の脳裏には閻魔の市で打ち返された木霊のことが過ぎっていた。
もし夢沈香だけでなく蹴速術も奪われていたとしたら、蹴速術を使う賊と戦うことになるかもしれない。それは一族だけの秘術として蹴速術を受け継いだ渦彦にとって、耐えられないことだった。
兄の推論を否定するためにも、渦彦は一刻も早く鬼没盗を捕まえたかった。だからこうして毎夜、索敵をしているのだった。
町全体を覆う木霊を使いながら、渦彦は後ろから近づく木霊を感じた。それは物干し台への内階段を登ってくる木霊だった。
「毎晩ご苦労さんやね。お夜食持ってきたよって食べてね」
階段を登ってきたのは籐伍の姉、鈴だった。今は武家娘の姿ではなく町方の女中の格好になっていた。鈴が隣に座って、渦彦に熱い茶を入れてくれた。渦彦は少しドキドキとした気持ちになった。
渦彦がまだ若く女性に不慣れな面もあったが、それ以上に鈴が美しかった。これまで母や神社の婢女ぐらいとしか女性に接してこなかった渦彦にとって、鈴はまるで竜宮城の乙姫を見るような気持ちにさせた。町方の質素な女中姿なのだが気品が頭抜けていた。
茶と夜食の握り飯を渦彦に渡しながら、鈴が話し出した。
「うちら家族、渦彦はんにはえらい感謝してるんよ。それをいいたくてね」
横に座り込んだ鈴が微笑んでいた。
「籐伍がこの捕り物にえらい真剣なんは、渦彦はんと出会うたからやと思うてんねん。あの子今まではどこか夢見がちで現実よりも芝居にしか興味持たなんだのに、なんか人が変わったみたいに捕り物に取り組んでる。これはきっと厳しい運命に立ち向うてる渦彦はんと友達になったからやと思うわ。そんな籐伍の姿を見たから、父上も隠居してもええと思うたんや思うし。みんな渦彦はんのおかげや、ありがとうね」
鈴が渦彦に大きく頭を下げた。渦彦はどう答えてよいかわからずに、下を向いてしまった。この物干し台が暗闇でよかったと心底思った。渦彦は自分の顔が今は真っ赤になっているに違いないと感じた。
「そんなことありまへん。むしろわいの方が籐伍には助けられてます。御神宝の強奪と鬼没盗が関わるかもしれへんと目星つけたんも籐伍やし、こうして鬼没盗捕縛の場にいられるようにしてくれたんも籐伍です。わい一人では何もできなんだ」
これは渦彦の本音だった。結局自分一人では何もできず、籐伍や御隠居のおかげで今ここにいる。もしこの先、御神宝や父の死の謎が解けたとしても、それは皆と出会えたからだと思った。
鈴は優しく渦彦の言葉を受け止めた。
「それでええんとちゃうの。みんな一人では何もできんもんよ。渦彦はんがいてるから籐伍も大人になれるし、籐伍がいてるから渦彦はんも前に進めてる。うちかて燕ちゃんがいてへんかったら何もできへん。ここにいてるんも元は燕ちゃんの意見や。あの子、普段は籐伍と喧嘩ばっかりやけど、籐伍のこと大好きやからな。みんなそうやで。誰かがおるから頑張れるし、前にも進めるんや」
鈴の言葉に渦彦はハッとした。父が亡くなって以来、兄を助けるために一人で我武者羅に頑張ってきたつもりだった。だが結局様々な人々の手助けでここまでこられたのだ。だがそれでよいのだと鈴は認めてくれていた。
いつも責任と使命に力み返っていた渦彦だったが、その力さえ皆んなから貰っていたのかもしれないと感じた。
「ありがとうございます。何か楽になれました。鈴様はよい方ですね」
渦彦の言葉に鈴が左右に手を振った。
「鈴様なんてやめてえよ。鈴でええから。ああ、でも年下の渦彦はんからは呼び辛いか。やったら鈴姉にして。籐伍も燕ちゃんには燕姉っていうくせに、うちにはいつも姉上や。うちもホンマは鈴姉て呼ばれたかったんよ。代わりに渦彦はんがそう呼んで」
鈴が不思議な提案をしてきた。渦彦には歳の離れた妹はいたが姉はいなかった。だから姉を普段どう呼ぶべきかを直ぐには思い浮かばなかった。
だがさすがに籐伍の姉に「鈴姉」とはいえなかった。沈黙していた渦彦は、何かを思い切るように「鈴姉様ではあきまへんか」と呟いた。それが渦彦には精一杯だった。
鈴は少し不満そうにしたが、「まぁそれでもええわ」と納得した。
「でもね、呼び慣れたらきっと『様』は取ってね。約束やで」
そう優しく微笑むと、「物見頑張ってな」といい残して物干し台を降りていった。
やっと体から緊張の力が抜けた渦彦は、手に持ったままだった握り飯に齧りついた。ただの塩むすびなのだが、その味は今まで食べたことのない美味しさだった。本当に乙姫が運んだ竜宮城のご馳走だと感じた。渦彦は鈴のことを「鈴姉様」よりも「乙姫様」と呼ぶ方が素直に呼べると思った。
囮策は順調に進んでいるように思えた。
まだ隠居所に大きな変化はなかったが、いつも誰かの視線に晒されているようにも感じた。鬼没盗の目が忍び寄っているのかもしれなかった。
「鴻池の御隠居は本当に未来を手に入れたらしい」という怪奇な噂がさらに流れた。
程なく、隠居所には様々な来客が訪れていた。従来からの骨董仲間だけでなく、多くの商人や各藩の大坂蔵屋敷の用人などもいた。皆一様に未然記の閲覧と、御隠居が知る未来を訊こうとした。もしかしたらその中には鬼没盗と繋がる者もいたかもしれなかった。
御隠居は来客があると、これ見よがしに書院の棚に黒漆の文箱を置いて来客に会った。直ぐ目の前に未然記があると示しながらも、決して中を見せようとはしなかった。内容も語らなかった。客は皆、ご馳走を目前に置かれながら食べることができない飢えた犬のようになっていた。
そうしたとき、渦彦は常に襖一枚隔てた隣室に控えていた。もし強引な行動に出る者がいたら取り押さえる役目である。
そうした日々が過ぎる中で、御隠居が渦彦に漏らしたことがあった。
「籐伍様はわてに利はないとおっしゃったが、そんなことはのうなってしもうたな。今やわては未来を知る仙人のように思われてる。わての言葉で相場さえ操れるかもしれへん。これはえらい利やで。閻魔大王から取り立てんでも、この世で十分にお釣りがくるわ」
皮肉な口振りとは裏腹に、御隠居も思わぬ世間の反応にとまどっているようだった。だが同時にそれは鬼没盗の襲来が、臨界点まで近づいている証でもあった。
やがて中天に淡い朧の三日月の輝く夜がやってきた。
夏の空気には濃密な水気が満ちており世界の全てを朧に滲ませていた。
渦彦はいつものように闇に隠れた物干し台で索敵を行っていた。
この時刻になれば、街を行く遅番の奉公人ももう出歩くことはなく、道端に店を出していた饂飩の屋台も店仕舞いしている。夜廻りの拍子木が遠くから聞こえているが、きっとその夜廻りさえも籐伍が密かに差し向けた奉行所の小者に違いなかった。
濃密な水蒸気を含んだ大気がわずかに流れているのを渦彦は感じた。同時に気付かぬほどの甘い香りも水蒸気の中に滲んでいた。
ハッとした渦彦は大気の流れを見極めようとした。
大気は隠居所から隠れ家の方向に動いていた。夏の濃厚な太陽の匂いではない、何か別の香り。夢沈香の匂いかどうかはまだ判断できないほどのわずかに滲んだ香りだが、警戒は必要だった。
渦彦は隠居所の周囲に普段より少し強目の木霊を発した。それは弱すぎず、強すぎず、調整された木霊である。渦彦が極度に慎重になっていたのは、鬼没盗の中に木霊を使える人間がいるかもしれないという不安があったからだ。もしそうなら、強い木霊は感づかれてしまう。閻魔の市で強烈な木霊が打ち返されたときのように。
怪しい木霊は帰ってこないが、それが逆に渦彦を不安にさせた。
「帰ってこなさ過ぎる」
不意に何か木霊が操作されているのかもしれないと感じた。木霊は人の発する無意識の違和感の気を感じ取る技である。だがもしそんな違和感さえも操作されていたらどうなるのだろうかと思った。
不意に叔父椎根津に木霊を習ったとき、対「木霊」の返し技として「隠形」という技の存在を教えられたことを思い出した。違和感の気を隠す技である。渦彦は隠形を修得する前に京へ神人修行に旅立ったので、この隠形は会得していない。
だがもし木霊同様に隠形も使える者が鬼没盗にいるとしたら、渦彦の索敵網には引っ掛からないことになってしまう。
そう思い至った渦彦は、背中に悪寒のような冷たい汗を感じた。
考えたくはなかったが、もし鬼没盗に渦彦以上の蹴速術の使い手がいるとしたらどうなるのか。兄綿津見の手紙にあった「蹴速術も奪われているかもしれない」という言葉が渦彦を恐怖の底に叩き落とそうとしていた。
恐ろしいものに突き動かされるように、渦彦は物干し台から内階段を駆け下りて行った。
隠れ家の玄関を走り出ようとしたとき、後から御隠居の声がした。
「どないしたんやえらい慌てて。幽霊でも出たみたいな顔してるで」
御隠居は手の蝋燭台を掲げながら、渦彦の表情を見ていた。
「幽霊……、ほんまに出たかもしれまへん。河原崎さんのいてる番所に知らせに行きます」
そういうと渦彦は隠れ家から走り出て、闇の中に消えて行った。御隠居は渦彦の言葉を即座に理解した。
そして奥の女中部屋に向かって潜めた声で呼びかけた。
「鈴はん、ちょっと物干し台に上がってきてんか。何や芝居の開幕太鼓が鳴ってるらしいで。皆の芝居、見物させてもろうやないか」
鈴が出てくるのを待つのももどかしく、御隠居は一人で物干し台への内階段を登り始めていた。それは生涯でただ一度の大芝居を見ることができる桟敷席に繋がる階段だった。
隠居所ではすでに夜の眠りに家人たちは就いていた。ただ燕はまだ眠ってはいなかった。不思議とこの夜は眠れずにいたのだ。先ほどから隣で眠る女中仲間の寝息が少しおかしかった。いつもは煩く感じている寝息がしていなかった。
それに気が付かないほどの甘い香りが家内に流れている。燕は匂いには敏感で、普段から香り袋なども持っていない。だが今はどこかに香り袋を置いてあるような気がした。鈴がいつも持つ香り袋の匂いのように思えた。
「生まれてから、こないに長いこと鈴ちゃんと離れてるんは初めてやなぁ」
そう思いながら、鈴が恋しくなったのかと少し自分を訝しんだ。
だが家内の様子も少しおかしいと感じた。皆寝静まっているのだから動くものはいないはずである。だがどこかで何かが動いている、静寂の中だから感じる微妙な違和感があった。
「上?」と一瞬思ったが、屋根裏の鼠かもしれなかった。そう思いながらも、燕は次第に逆らえぬ睡魔に襲われていた。思わず眠りの世界に引き摺り込まれそうになっていた。
だがそのとき裏庭で音がした。静かなほとんど聞きお取れないほどの音だが、何か猫や小動物がフワリと大地に降り立つような感じである。
燕は鬼没盗の襲来の可能性と、夢沈香の攻撃を承知していた。
何かがおかしいと感じながら、「ほんまに賊が来たんかもしれへん」という思いがむくむくと湧いていた。
燕は静かに寝床から起き上がると、周囲で寝ている女中たちを見た。皆深い眠りに落ちている。それは深過ぎるほどの眠りだった。燕は懐に入れていた手拭いを出すと、鼻と口を覆って後ろで縛った。異変を感じたらこうするように籐伍に助言をされていた。
燕はそのまま女中部屋の出入り口に行き、そっと板戸を引いた。敷居の溝には掃除のときに蝋燭を塗っているので音はしない。
そこから廊下に顔を出し、左右の様子を伺ってみた。闇の中に動くものはなく静寂が支配している。だがやはり何かが変だった。
そのとき、「ガタン」という音が外廊下の方から聞こえてきた。燕はそれが外廊下の雨戸が外された音だと感じた。
「この家に侵入しようとしている者がいる」
鬼没盗に違いないと直感した。籐伍や父からは、もし賊に気がついても女中部屋から出ないようにいわれている。賊は家人には手を出さないので、隠居所を警戒する捕り方に任せるようにと。
だが燕は父念十郎の身が急に心配になり、影武者として眠る書院に向かった。広い隠居所なので外廊下の方を通らなくても書院には行けた。音を立てないように部屋を通り抜けようとしたとき、暗闇の中に人影を見た。それは闇に溶けたような黒装束だった。
燕は一瞬、声を出すかどうか迷った。
危険を知らせる必要はあるが、この賊を逃すわけにはいかない。
黒装束はまだ燕には気づかずに、暗闇の中で何かを探っている。燕は音を殺して襖の陰に身を隠した。そして捕り方が来るまで足止めに何をすべきかを考えた。
燕は小太刀が使えるといっても、今は寝間着姿で得物は手にはない。
「ならば」と思った燕は、大胆にも襖から黒装束に向かって、柔術の回転受け身で転がり接近した。
普通人は背後から誰かが接近してきたと気づけば、後方斜め上を見上げることが多い。地を転がって下から接近するなど思いもよらないのだ。そこに攻撃する間隙が生まれる。
一種の奇襲戦法だが、小太刀を主力にする中条流平法で用いられる、大太刀の懐に飛び込む戦法である。小太刀があればそのまま下から相手を貫けばよかった。
振り返った黒装束は、燕の姿をすぐには捉えられなかった。暗闇と視線が地から上にずれていたからだった。
接近に成功した燕は、男のすぐ下から固めた拳でガラ空きの鳩尾を強かに叩いた。そして間髪を入れずに小太刀を模した自分の手刀で黒装束の首筋を撃った。うまく急所に入ればこれで意識を混濁することができる。
だが暗闇と装束に首筋は隠され、燕の手刀は首筋より少し下を打った。
黒装束は一瞬怯んだが、すぐに燕の体に不思議な蹴り技を放ってきた。至近距離にいた燕はほぼ密着していたはずなので、普通なら足技など間に入るはずがなかった。
だが燕は横に蹴り飛ばされていた。そのまま襖に激突し、隣の部屋に転がっていった。倒れた燕はすぐには起き上がれなかった。背中に蹴りの痛みが走っていた。
黒装束は自分に起こった状況を理解するためか、ちょっとの間その場に立ち竦んでいた。だが隣の部屋に転がるのが寝間着姿の女だと認識すると、小さく舌打ちをした。そのまま書院に向かって静かに走り出していた。
この状況は黒装束にとっても予想外の出来事のようだった。
燕が起き上がれないでいると、そこに男が一人走り込んできた。
それは燕の戦う音を聞きつけた渦彦だった。倒れている燕を助け起こそうとした渦彦は、暗闇の中でその顔を見て驚いた。
「鈴姉様……」
不思議そうに呟く渦彦に燕が叫んだ。
「早うに書院へ行って。お父はんが危ない」
その言葉に渦彦は状況を把握した。燕を倒した侵入者は書院に向かったのだ。目的は未然記の強奪しかなかった。とうとう鬼没盗が出来したのだ。
「裏口から外に出てくだい。もう河原崎はんの突入組が来てるよって外は安全です。親父殿はわいが助けます」
燕が立てると確認すると、渦彦はすぐに書院へ走りだしていた。
このとき渦彦からの急報を聞いた河原崎は、手筈通りに突入組を率いて隠居所に急行していた。同時に別の番屋に控える籐伍に連絡して、町内を封鎖する関所を作るように知らせてもいる。
本来ならば鬼没盗の襲来を知らせた渦彦はそのまま隠れ家に戻り、御隠居の警護に当たるはずだった。だが渦彦は籐伍との申し合わせを破った。
番屋に知らせた後、そのまま隠居所に走り込んでいったのだ。突入組よりも早く渦彦が燕の元に現れた理由である。渦彦は何としても鬼没盗を自分の手で捕らえたかったのだ。
先行する渦彦に遅れて隠居所に着いた河原崎は、突入組の半分に隠居所の封鎖にあたらせた。そして残り半分と自分で隠居に突入したのだった。
そこで何人かの黒装束の賊と遭遇した。人数は把握できなかったが、捕り方がいきなり突入してきたことに驚いているのは明らかだった。統制が取れた動きではなかったが、各々に反撃をしてくる。
河原崎はここが正念場だと思い、呼び笛を短く三度鳴らした。そしてもう一度短く三度鳴らした。これは周囲の封鎖に当たっている捕り方に対して、見張りを残して突入を命じる笛だった。たとえこの場から逃れた賊がいたとしても、町内を関所で封鎖する籐伍の別働組が待ち構えている。ここで戦力の全投入は間違っていなかった。
捕り方の人数が増えたことで、少し乱戦に近い状況になっていた。隠居所が広いとはいえ、そこは屋内での捕り物である。全てに目が行き届くわけではなかった。
そうした状況の中で、燕はやっと裏口から外に逃れ出たのだった。裏口には恭一郎が最後の見張りとして残留していた。
「燕ちゃん、無事か」
転がり出てきた燕を見た恭一郎は、無事を確かめるように抱きしめた。はぁはぁと息をつき燕は抱きしめる恭一郎に体を預けた。
「うちでごめんな。でもやっぱりここにいてるんがうちでよかったわ。鈴ちゃんにはこんな危ないことさせられへん」
笑いながらいったが、燕は少し涙を流していた。燕も怖かったのだった。
いくつかの部屋を通り抜けた渦彦は、書院から争う音を聞いた。
書院に至る廊下の端から、薄闇の中で二人の男が争っているのが見えた。一人は無論影武者役の念十郎である。そしてもう一人は闇に溶けた黒装束の侵入者だった。
念十郎は影武者として書院で眠るとき、床には就くが眠ってはいない。
燕がしたように口と鼻を手拭いで覆い夢沈香を吸わないようにし、布団を被っていた。布団の中では片手に小太刀を握っている。その状態で毎夜朝まで過ごしていたのである。
念十郎は夜眠らないように昼間に隠れ家で睡眠をとっていた。昼夜を逆転させて警戒にあたっていたのだ。寝ずの番を幾夜も続けていると、かつて吟味方与力として盗賊を追っていた日々を思い出した。少し体の中に湧き出てくる熱い興奮を感じていた。
そうした警戒の中で、念十郎も異変を感じ取っていた。雨戸を外すわずかな音に続く、燕と黒装束が戦う音も聞いた。
だが念十郎はすぐに起きようとはせず、眠った振りを続けていた。鬼没盗をこの部屋に誘い込むためである。
思惑通りに侵入者は書院に入ってきた。
御隠居が眠っていると信じているのか、侵入者はそのまま違い棚に置いてある文箱に近づいていった。この書院の状況をよく知っているような迷いのない行動だった。
侵入者が文箱に手を伸ばそうとしたとき、念十郎は布団を跳ね除けて起き上がった。そして文箱に伸ばした侵入者の手をむんずと掴んでいた。
「すまんがこれを渡すわけにはいかんのや。代わりにこれをやろう」
そういいながら念十郎は、片手に持つ小太刀の嶺で侵入者の首筋を打ち据えようとした。それでこの侵入者を捕まえることができるはずだった。
だが意に反して、念十郎の持つ小太刀が宙を舞っていた。どういう攻撃が返されたのかは念十郎にも最初分からなかった。
だが侵入者の足が奇妙な角度に折り曲げられていた。至近距離から不思議な足技で小太刀が蹴り上げられたらしい。
さらにその足が背中の方から襲ってきた。これも人には不可能に思える蹴りだった。念十郎は男の側から廊下の方に蹴り転がされていた。
痛みを堪えて体勢を直そうとしたとき、渦彦が書院に走り込んできた。
「親父殿、大事ありまへんか」
ちらっと念十郎を見て大丈夫そうだと確認すると、侵入者と念十郎の間に割って入った。
「こいつはわいがやります。親父殿は逃げ道を塞いでください。すぐに河原崎はんが来ますよって」
渦彦は黒装束の侵入者の姿をまじまじと観察した。
黒装束は不思議な構えをとっていた。両足を肩幅に広げて自然体で立つという普通の武道で教える構えではなく、右足を大きく後ろに回して立っている。
これは……「鬼骨の構え」だと思った。蹴速術にいくつかある構えの一つで、家内のような狭い場所での戦いに適した構えだった。
思わず渦彦も同じ鬼骨の構えをとっていた。
渦彦の構えを見た黒装束は、一瞬身を硬くして後ろに退いたように見えた。そして何か信じられぬ物を見たというように呟いた。
「蹴速か、なるほどやっと先日打ち込んできた木霊に合点したわ」
そして突如一歩前に出たと思った刹那、その姿が消えていた。
いや消えたのではなく、神速の動きで深く沈み込んでいたのだった。そこからまるで天に昇る龍のような上への蹴りが放たれていた。
昇龍脚、蹴速術における基本蹴り技の一つである。神速で深く沈み込む前動作は、かつて籐伍の突き技「八艘」を避けるときに渦彦が使った動きと同じだった。
渦彦は反射的に防御の鎧脚で昇龍脚を弾いていた。
だが黒装束は地を這うように前に出ると、二撃目、三撃目の昇龍脚を続けて放ってきた。
昇龍三蓮華と呼ばれる連続技である。
これを全て鎧脚だけで防御し切るのは困難だった。二撃目は見切りで避け、三撃目は伸び切る前の脚の膝裏を手技の掌底で打って横に流した。
そして流れた脚の根元に向かって、今度は渦彦が折り畳んだ左脚で落月踵(踵落しの変化技)を逆に落として行った。これは渦彦が学んだ昇龍三蓮華に対する反撃技だった。
だが落月踵を落した先に黒装束の姿はなく、この攻撃をすでに予測していたかのように大きく横に移動していた。
少し離れると、黒装束が今度はしゃがみ込んだような態勢をとった。
渦彦は鬼骨の構えを取りながら、「蛙(かわず)か」と思わず呟いた。
渦彦の声が届いたのか、黒装束は沈み込んだ姿勢から立ち上がった。
「やめじゃ、やめじゃ。お前が蹴速を使えることはようわかった。だがこれ以上やればお前は死ぬこととなろう。それに今夜の目的は殺しではのうてこれだからな」
そういうと左手にいつから持っていたのか、黒塗りの文箱を少し掲げた。黒装束は渦彦との攻防を片手に文箱を持ったまま行っていたのだった。
「未然記は頂戴する。縁があればまたどこぞで再戦しよう。お互いこの世では稀なる相手だからな」
そういい捨てると、黒装束は突如書院の奥にある明取りの月見窓に走って体当たりした。そのまま窓を破って外に転がり出ていった。窓の向こう側は庭に続いていた。
「逃走の道を計算しているとは、この家の構造をよく知っている」
そう思わざるを得なかった。
だが外には河原崎の突入組がおり、さらにその外側では籐伍の別働組が町を封鎖している。逃げ切ることはできまいと思った。
「すみまへん、取り逃してしまいました」
残念そうにいう渦彦に、念十郎は小太刀を拾いながら礼を述べた。
「いやいや、渦彦殿のおかげで命拾いした。礼をいわなあかんわ。後のことは河原崎や籐伍に任せよう。鼻っからそういう台本やからな。わしも少し無理したかもしれへん。こりゃ後で籐伍に叱られなあかんな」
そう笑うと、家内で始まっている突入組の捕り物の様子を窺った。各所で突入組と侵入者の戦いが起こっている様子だった。
念十郎は「よいしょ」と、敷かれた布団の上に座り込んだ。
「やっぱり、ここいらが隠居する潮時やったかもしれへんな。助けが必要なようでは捕り物もできへんで」
そう呟くと、念十郎は痛そうに背中をさすっていた。それは黒装束に強かに蹴られた箇所だった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

名残雪に虹を待つ
小林一咲
歴史・時代
「虹は一瞬の美しさとともに消えゆくもの、名残雪は過去の余韻を残しながらもいずれ溶けていくもの」
雪の帳が静かに降り、時代の終わりを告げる。
信州松本藩の老侍・片桐早苗衛門は、幕府の影が薄れゆく中、江戸の喧騒を背に故郷へと踵を返した。
変わりゆく町の姿に、武士の魂が風に溶けるのを聴く。松本の雪深い里にたどり着けば、そこには未亡人となったかつての許嫁、お篠が、過ぎし日の幻のように佇んでいた。
二人は雪の丘に記憶を辿る。幼き日に虹を待ち、夢を語ったあの場所で、お篠の声が静かに響く——「まだあの虹を探しているのか」。早苗衛門は答えを飲み込み、過去と現在が雪片のように交錯する中で、自らの影を見失う。
町では新政府の風が吹き荒れ、藩士たちの誇りが軋む。早苗衛門は若者たちの剣音に耳を傾け、最後の役目を模索する。
やがて、幕府残党狩りの刃が早苗衛門を追い詰める。お篠の庇う手を振り切り、彼は名残雪の丘へ向かう——虹を待ったあの場所へ。
雪がやみ、空に淡い光が差し込むとき、追っ手の足音が近づく。
早苗衛門は剣を手に微笑み、お篠は遠くで呟く——「あなたは、まだ虹を待っていたのですね」
名残雪の中に虹がかすかに輝き、侍の魂は静かに最後の舞を舞った。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい
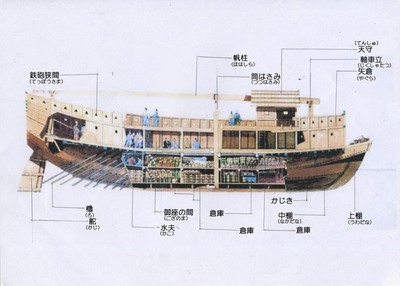

死は悪さえも魅了する
春瀬由衣
歴史・時代
バケモノと罵られた盗賊団の頭がいた。
都も安全とはいえない末法において。
町はずれは、なおのこと。
旅が命がけなのは、
道中無事でいられる保証がないから。
けれどーー盗みをはたらく者にも、逃れられない苦しみがあった。

【完結】月よりきれい
悠井すみれ
歴史・時代
職人の若者・清吾は、吉原に売られた幼馴染を探している。登楼もせずに見世の内情を探ったことで袋叩きにあった彼は、美貌に加えて慈悲深いと評判の花魁・唐織に助けられる。
清吾の事情を聞いた唐織は、彼女の情人の振りをして吉原に入り込めば良い、と提案する。客の嫉妬を煽って通わせるため、形ばかりの恋人を置くのは唐織にとっても好都合なのだという。
純心な清吾にとっては、唐織の計算高さは遠い世界のもの──その、はずだった。
嘘を重ねる花魁と、幼馴染を探す一途な若者の交流と愛憎。愛よりも真実よりも美しいものとは。
第9回歴史・時代小説大賞参加作品です。楽しんでいただけましたら投票お願いいたします。
表紙画像はぱくたそ(www.pakutaso.com)より。かんたん表紙メーカー(https://sscard.monokakitools.net/covermaker.html)で作成しました。

東へ征(ゆ)け ―神武東征記ー
長髄彦ファン
歴史・時代
日向の皇子・磐余彦(のちの神武天皇)は、出雲王の長髄彦からもらった弓矢を武器に人喰い熊の黒鬼を倒す。磐余彦は三人の兄と仲間とともに東の国ヤマトを目指して出航するが、上陸した河内で待ち構えていたのは、ヤマトの将軍となった長髄彦だった。激しい戦闘の末に長兄を喪い、熊野灘では嵐に遭遇して二人の兄も喪う。その後数々の苦難を乗り越え、ヤマト進撃を目前にした磐余彦は長髄彦と対面するが――。
『日本書紀』&『古事記』をベースにして日本の建国物語を紡ぎました。
※この作品はNOVEL DAYSとnoteでバージョン違いを公開しています。

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜
かまぼこのもと
歴史・時代
1615年5月。
徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。
堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……
豊臣家に味方する者はいない。
西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。
しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。
全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















