お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説



トラベルは冒険心と共に
つっちーfrom千葉
ホラー
アメリカ・欧州・アジアなど、様々な国からの来訪者たちが、とある広大な植物園を短時間で見学するツアーに参加していた。はしゃぎ回るタイ人親子の無節操ぶりに苛立ちを隠せないアメリカ人夫妻は、お得意の家柄自慢、人種差別発言を次々と繰り出す。次第に場の空気が重くなる中、日本からひとり参加した私は、知的なフランス美女に一目ぼれして声をかけることに。彼女は私になど魅力を感じていないようだが、簡単には諦めきれない私は、食い下がることにした。
このグループの参加者たちの最大の目的は、南米に生息する珍種の食虫植物を見ることであった。しかし、さすがは世界最大の植物園である。そこには、想像を超える生物が棲んでいたのだ。
2021年11月4日→11月15日
よろしくお願いします。


【完結】瓶詰めの悪夢
玉響なつめ
ホラー
とある男が行方不明になった。
その状況があまりに奇妙で、幽霊の仕業ではないかとそう依頼された心霊研究所所長の高杉は張り切って現場に行くことにした。
八割方、依頼主の気のせいだろうと思いながら気楽に調査を進めると、そこで彼は不可思議な現象に見舞われる。
【シャケフレークがない】
一体それはなんなのか。
※小説家になろう でも連載
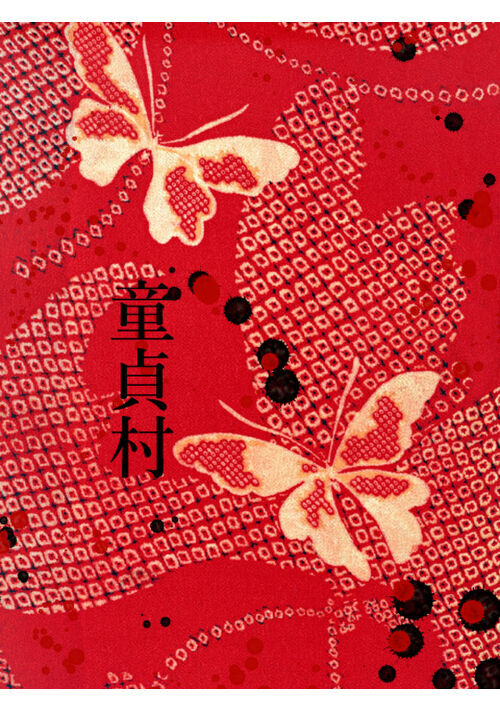
童貞村
雷尾
ホラー
動画サイトで配信活動をしている男の元に、ファンやリスナーから阿嘉黒町の奥地にある廃村の探索をしてほしいと要望が届いた。名前すらもわからないその村では、廃村のはずなのに今でも人が暮らしているだとか、過去に殺人事件があっただとか、その土地を知る者の間では禁足地扱いされているといった不穏な噂がまことしやかに囁かれていた。※BL要素ありです※
作中にでてくるユーチューバー氏は進行役件観測者なので、彼はBLしません。
※ユーチューバー氏はこちら
https://www.alphapolis.co.jp/manga/980286919/965721001

狂った夢、かなえます
クロモリ
ホラー
あなたの夢は本当に、あなたを幸せにしますか?
世にも不快な短編連作。
人形師(にんぎょうし)・蜜蘭(みつらん)は、依頼人の歪んだ夢を叶える――人間が持ちえない身体能力を授けることで。
例えば、恋する少女は浮気グセのある彼氏に悩み、容姿を変えることを望んだ。でも、ただただ美しさを夢見ていたわけではなかった。
例えば、プロボクサーの男はケガからの復帰を望んでいた。けれど、チャンピオンを夢見ていたわけではなかった。
例えにあげた依頼人たちは狂気を秘めた夢を抱いています。狂った夢の正体に、人形師・蜜蘭と大学生の助手・孝之(たかゆき)が確かめていく。
狂った夢の、その末路(まつろ)……興味がわきましたら、ぜひご覧ください。
※二日に一度の更新となります。
※カクヨム、ノベルアップ+でも同時に公開しております。

ハンニバルの3分クッキング
アサシン工房
ホラー
アメリカの住宅街で住人たちが惨殺され、金品を奪われる事件が相次いでいた。
犯人は2人組のストリートギャングの少年少女だ。
事件の犯人を始末するために出向いた軍人、ハンニバル・クルーガー中将は少年少女を容赦なく殺害。
そして、少年少女の死体を持ち帰り、軍事基地の中で人肉料理を披露するのであった!
本作のハンニバルは同作者の作品「ワイルド・ソルジャー」の時よりも20歳以上歳食ってるおじさんです。
そして悪人には容赦無いカニバリズムおじさんです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















