3 / 6
天才パティシエ!
しおりを挟む
放課後、帰り道。
「ハァ……」
これから予備校だというリカっちと十字路で分かれたあたしは、深いタメイキをついてた。その息が、冬の夕暮れのなかでちょっとだけ白く染まって……わたがしみたい。けど……。
あたしの心もわたがしみたいに軽かったら、よかったのにな。
こんな日は、「あそこ」に行くに限る。
あたしは、方向転換した。
足が、もう道を覚えてくれている。たんたんたん、って高校生っぽい茶色いローファーが、イルミネーションの光の眩しい住宅街に街音を立てる。
寒くって、ベビーピンクのマフラーを寄せて上げて、ぶるり。
もう、冬、なんだ。そう、……高二の冬。
きょうも、進路についての特別授業があった。
年明けには、進路希望を提出しなくっちゃいけない……。
進路、かあ。
パティシエ志望、ってあたしは家でも学校でも言ってるし、それを隠してはいないつもりだ。
けど、あたしのクラスは、きっとほとんどが大学や短大に進学する。
あたしも当然そうするんでしょって思われてる、と思う。お姉ちゃんだって、大学生だし。
大学。べつに、不満があるわけじゃないけど……
大学だとスイーツの勉強って、ふつう、できないよね。
お姉ちゃんは、ぜんぶ言わなくていいんだ黙っとけばいいなんて言うけど、こちとら高校生の身分でさ、好きな調理器具とかキッチンに置かせてもらうんじゃ、そんなのバレるに決まってるじゃん。
っていうか、っていうか! そのついでにムカムカ思い出すけど。
あたしは、お姉ちゃんがスイーツ嫌いだってことが、ほんっとに理解できない。食べ物の好みなんて、それぞれ。わかってるよ。あたしだって、お姉ちゃんがなんにでもタバスコかけまくるのほんとに理解できないもん。
好き嫌いは、しょうがないよね、でも。
あたし、ほんとにもったいないと思う。お姉ちゃんって。
甘いものの美味しさを知らないだなんて!
「……お姉ちゃんにもおいしいスイーツ。作れたら、あたしは天才パティシエだなあ」
あたしはしんどく呟きながら、タン、と足を止めた。
ごくふつうの住宅街の真ん中に、「そのお店」はある。
――「カフェ・ド・ブリュレ」。
フランス語でそう書かれた、焦がしたブリュレの色そのまんまの、きれいなクリームイエローの看板が目印だ。
カランコロン。
お店の扉の鐘が、かわいらしく鳴る。あたしの来店を歓迎してくれてるみたい。
あっ、クリスマス仕様になってるー。赤と緑のりぼんだ。かーわいい!
「……おっじゃましまあーす……」
あたしはこそっと顔を出して、そろそろっと店内に入った。
あっ、ヤマしいこととかがあるワケじゃないからね。
ただ、あたしにとって、このお店って……ほとんど聖域みたいなものなんだ。
店内では前のお客さんが買い物をしていた。お客さんの女のひと、背中だけだっていうのになんだかほくほくとしてるのが伝わってくるようで、さ。
どれどれ、お相手をしてるのは、っと――あれ? あの男性の店員さん、見ない顔……。
はて、とあたしは首をひねった。
このお店の店員さんのことなら、あたし、全員欠かさず顔と名字と好みのスイーツ把握して――って、別にストーカーとかじゃなくってね!?
このお店は――超一流パティシエたちにも全員、接客や店内清掃をやらせることで有名だ。
キビシーって思うけど、なにせ店長さん本人が率先して笑顔をふりまいてるから、ほかのひとたちもそうせざるをえないんだって。
……ってことは、新入りかぁ。うむうむ、などと、何様? って感じであたしは腕を組んでうなずいた。
前のお客さんが「ありがとうございます」と嬉しそうに言って、帰っていく。
笑顔で見送るエプロン姿の金髪の彼は――あれ、カッコいいじゃないの……。
けど、それならなおさら、あたし、……あなたの名前よりもまず、あなたの好きなスイーツのことが知りたい!
あたしの視線に気がつくと、新入り店員はにこっと微笑みかけてきた。
あたしもぺこりと頭を下げる。
レジと、ケーキコーナーの距離感。
彼は線が細いタイプで、笑うとカワイイ感じになる。
イケメンはイケメンなんだけど、なんかひょろひょろと気が弱そうでだいじょうぶかなって勝手ながら思った。
「なにか、お探しですか?」
「あ、あの。……お兄さんは新入りですよね?」
「……え?」
「あ、あ、えっと。その。ちがくてっ。べつにあたしストーカーとかじゃなくてっ――」
「……ストーカー、なのですか?」
「ではなくっ。なんと言いますかその、そう! このお店のファン、です。そして、スイーツのファンです!」
店員さんは怪訝そうな顔をしたけど、あたしの語りは止まらない!
「このお店ってカフェ・ド・ブリュレさんっていいますよね、けどブリュレだけじゃなくて、なんでもとっても美味しくて、あまーいんです。あたし、小さいころから甘いものって大好きで。パティシエになりたい、って……小さなころから思ってました。それで三年前、あたしが中学生のときにカフェ・ド・ブリュレさんができて――あたし、もう、おこづかいつぎ込んで週二は通っちゃってます、スイーツ課金ですね、なんちゃって、えへへ。
ここのスイーツが、ちがうのは、わかりますから。……あの、それなんで、よろしくお願いしますっ。あなたは――なんのスイーツの担当ですか?」
あたしは、にっこり。
……にっこり、した、のに。
店員さんは――なんだか一変して、ものすごくコワイ顔をしていた。
「……そういうのは、店の仕事です」
え。なんで!? ナンデ!?
何で、このひと……怒ってるワケ!?
なんか絶対零度急降下、ってカンジ。
あたしもテンパって自分でなに言ってんのかよくわかってないから!
「そ、そうですよねそうやってお店のことはパティシエさんがお店のひとだから考えるんですもんねっ!」
「と、いいますか!」
「ひゃあっ!」
やっぱりあたし、なんかもうなに言ってるのか、ワカンナイぞっ! 自分で!
「僕はお客さんにはスイーツのことだけを考えていてほしい……!」
わ。
えっ?
んんん?
あたし、きょとん。
目がきっと、点ですよ、いま。
あたしはソローリと自分の顔を自分で指さした。
「……あたしなんかもうずーっとずうううーっと、スイーツのことで頭いーっぱいですけど……? え? っていうか、あたし、なんかしました? っていうか店員さんなんか怒ってました?」
はてなマークだらけのあたし。
店員さんはばつが悪そうにあたしから視線をそらしてポリ、とイケメンな頬をイケメンな指で軽くひっかいた。
おおう。……イケメンパティシエは、なんでも画になって、良いですなぁ。
バタバタバタバタ……バタンッ!
店長さんが、勢いよくあらわれた。
ふだんは仏像のように目が細いのに、いまはクワッと覚醒してる。般若みたい、ってゆーんだって。こーゆーの。お姉ちゃんが教えてくれた。まあお姉ちゃんは鬼姉だけど。
「こらぁ、ミカド! いまだれになにをぉ、怒鳴ったぁ!」
「えっ、ミカド? エンペラー?」
「……ってなんだい、ココちゃんじゃないのぉ。いらっしゃぁい」
店長さんはふだんの仏像の顔になってくれた。ありがたやー……。
とか思ったらまた般若になった。
「ミカド! てめ、もしかして、心音の嬢ちゃんに怒鳴ったのかぁい!」
「……いえ。自分は怒鳴ってなど……」
「じゃあさっっっきの声はなんだよぉ、あぁん?」
「あ、あの、てんちょさん。あの、あたし、怒鳴られてたってか、ミカドさん? と、スイーツ談義が盛り上がりすぎったっただけっていうか。……ねっ、ですよねっ、ミカドさん?」
ミカドさんはまたしてもばつの悪そうな顔であさっての方向を見た。
「ミカドおおお! おま、なに高校生の女の子にかばわれてんだああああ!」
「……かばう、ときましたか。いやあ、困りましたねえ」
ミカドさんは、あたしの顔を真正面から見て、
めっちゃまぶしく、かっこよく、
すっごく素敵な商売スマイルで、笑ってくれた。
「……スイーツのことで頭がいっぱいなのに、かばってくださったんですか?」
ひそひそひそひそ。
「てんちょさん。なんですか。このひと」
「ううん。なんなんだろうなあ。俺もよくわかってねえんだよ。ただ、天才ブリュレパティシエってことでさぁ」
ミカドさん、スマイルのままだ。
「……まァ、ブリュレの腕は超一流だ。態度はこんなんだけどな……」
「そもそもスイーツの神職であるパティシエに他の業務をやらせるなど……」
「こんな調子なんだ。ごめんなぁ、ココちゃん。おいミカド、このコは常連の高校生の心音ちゃん。ちゃあんと覚えとけよお」
「はあ。なんで接客まで……って」
あたしはめっちゃキラキラした目で両手を握り合わせてミカドさんを見上げていた。
「天才パティシエ、なんですかっ?」
「は?」
「ミカドさんって天才パティシエなんですか!?」
「は、え、あっ、ちょ、近い、近いですから常連の高校生の心音さん」
「……ああ。そいつは、パティシエとしては、天才だよ。間違いねえ。日本じゃかえってまだ知られてねえが、本場だと、すごいんだぞ」
「すごい! すごいです……! お願いがあります。あたしを、弟子にしてくださいっ!」
ぺこりっ!
弟子ぃ? と、ミカドさんは露骨にイヤな顔をした。
店長さんが慌てて、とりあえず詫びさせるから、とミカドさんの頭をひっつかんで、下げさせた。
「ハァ……」
これから予備校だというリカっちと十字路で分かれたあたしは、深いタメイキをついてた。その息が、冬の夕暮れのなかでちょっとだけ白く染まって……わたがしみたい。けど……。
あたしの心もわたがしみたいに軽かったら、よかったのにな。
こんな日は、「あそこ」に行くに限る。
あたしは、方向転換した。
足が、もう道を覚えてくれている。たんたんたん、って高校生っぽい茶色いローファーが、イルミネーションの光の眩しい住宅街に街音を立てる。
寒くって、ベビーピンクのマフラーを寄せて上げて、ぶるり。
もう、冬、なんだ。そう、……高二の冬。
きょうも、進路についての特別授業があった。
年明けには、進路希望を提出しなくっちゃいけない……。
進路、かあ。
パティシエ志望、ってあたしは家でも学校でも言ってるし、それを隠してはいないつもりだ。
けど、あたしのクラスは、きっとほとんどが大学や短大に進学する。
あたしも当然そうするんでしょって思われてる、と思う。お姉ちゃんだって、大学生だし。
大学。べつに、不満があるわけじゃないけど……
大学だとスイーツの勉強って、ふつう、できないよね。
お姉ちゃんは、ぜんぶ言わなくていいんだ黙っとけばいいなんて言うけど、こちとら高校生の身分でさ、好きな調理器具とかキッチンに置かせてもらうんじゃ、そんなのバレるに決まってるじゃん。
っていうか、っていうか! そのついでにムカムカ思い出すけど。
あたしは、お姉ちゃんがスイーツ嫌いだってことが、ほんっとに理解できない。食べ物の好みなんて、それぞれ。わかってるよ。あたしだって、お姉ちゃんがなんにでもタバスコかけまくるのほんとに理解できないもん。
好き嫌いは、しょうがないよね、でも。
あたし、ほんとにもったいないと思う。お姉ちゃんって。
甘いものの美味しさを知らないだなんて!
「……お姉ちゃんにもおいしいスイーツ。作れたら、あたしは天才パティシエだなあ」
あたしはしんどく呟きながら、タン、と足を止めた。
ごくふつうの住宅街の真ん中に、「そのお店」はある。
――「カフェ・ド・ブリュレ」。
フランス語でそう書かれた、焦がしたブリュレの色そのまんまの、きれいなクリームイエローの看板が目印だ。
カランコロン。
お店の扉の鐘が、かわいらしく鳴る。あたしの来店を歓迎してくれてるみたい。
あっ、クリスマス仕様になってるー。赤と緑のりぼんだ。かーわいい!
「……おっじゃましまあーす……」
あたしはこそっと顔を出して、そろそろっと店内に入った。
あっ、ヤマしいこととかがあるワケじゃないからね。
ただ、あたしにとって、このお店って……ほとんど聖域みたいなものなんだ。
店内では前のお客さんが買い物をしていた。お客さんの女のひと、背中だけだっていうのになんだかほくほくとしてるのが伝わってくるようで、さ。
どれどれ、お相手をしてるのは、っと――あれ? あの男性の店員さん、見ない顔……。
はて、とあたしは首をひねった。
このお店の店員さんのことなら、あたし、全員欠かさず顔と名字と好みのスイーツ把握して――って、別にストーカーとかじゃなくってね!?
このお店は――超一流パティシエたちにも全員、接客や店内清掃をやらせることで有名だ。
キビシーって思うけど、なにせ店長さん本人が率先して笑顔をふりまいてるから、ほかのひとたちもそうせざるをえないんだって。
……ってことは、新入りかぁ。うむうむ、などと、何様? って感じであたしは腕を組んでうなずいた。
前のお客さんが「ありがとうございます」と嬉しそうに言って、帰っていく。
笑顔で見送るエプロン姿の金髪の彼は――あれ、カッコいいじゃないの……。
けど、それならなおさら、あたし、……あなたの名前よりもまず、あなたの好きなスイーツのことが知りたい!
あたしの視線に気がつくと、新入り店員はにこっと微笑みかけてきた。
あたしもぺこりと頭を下げる。
レジと、ケーキコーナーの距離感。
彼は線が細いタイプで、笑うとカワイイ感じになる。
イケメンはイケメンなんだけど、なんかひょろひょろと気が弱そうでだいじょうぶかなって勝手ながら思った。
「なにか、お探しですか?」
「あ、あの。……お兄さんは新入りですよね?」
「……え?」
「あ、あ、えっと。その。ちがくてっ。べつにあたしストーカーとかじゃなくてっ――」
「……ストーカー、なのですか?」
「ではなくっ。なんと言いますかその、そう! このお店のファン、です。そして、スイーツのファンです!」
店員さんは怪訝そうな顔をしたけど、あたしの語りは止まらない!
「このお店ってカフェ・ド・ブリュレさんっていいますよね、けどブリュレだけじゃなくて、なんでもとっても美味しくて、あまーいんです。あたし、小さいころから甘いものって大好きで。パティシエになりたい、って……小さなころから思ってました。それで三年前、あたしが中学生のときにカフェ・ド・ブリュレさんができて――あたし、もう、おこづかいつぎ込んで週二は通っちゃってます、スイーツ課金ですね、なんちゃって、えへへ。
ここのスイーツが、ちがうのは、わかりますから。……あの、それなんで、よろしくお願いしますっ。あなたは――なんのスイーツの担当ですか?」
あたしは、にっこり。
……にっこり、した、のに。
店員さんは――なんだか一変して、ものすごくコワイ顔をしていた。
「……そういうのは、店の仕事です」
え。なんで!? ナンデ!?
何で、このひと……怒ってるワケ!?
なんか絶対零度急降下、ってカンジ。
あたしもテンパって自分でなに言ってんのかよくわかってないから!
「そ、そうですよねそうやってお店のことはパティシエさんがお店のひとだから考えるんですもんねっ!」
「と、いいますか!」
「ひゃあっ!」
やっぱりあたし、なんかもうなに言ってるのか、ワカンナイぞっ! 自分で!
「僕はお客さんにはスイーツのことだけを考えていてほしい……!」
わ。
えっ?
んんん?
あたし、きょとん。
目がきっと、点ですよ、いま。
あたしはソローリと自分の顔を自分で指さした。
「……あたしなんかもうずーっとずうううーっと、スイーツのことで頭いーっぱいですけど……? え? っていうか、あたし、なんかしました? っていうか店員さんなんか怒ってました?」
はてなマークだらけのあたし。
店員さんはばつが悪そうにあたしから視線をそらしてポリ、とイケメンな頬をイケメンな指で軽くひっかいた。
おおう。……イケメンパティシエは、なんでも画になって、良いですなぁ。
バタバタバタバタ……バタンッ!
店長さんが、勢いよくあらわれた。
ふだんは仏像のように目が細いのに、いまはクワッと覚醒してる。般若みたい、ってゆーんだって。こーゆーの。お姉ちゃんが教えてくれた。まあお姉ちゃんは鬼姉だけど。
「こらぁ、ミカド! いまだれになにをぉ、怒鳴ったぁ!」
「えっ、ミカド? エンペラー?」
「……ってなんだい、ココちゃんじゃないのぉ。いらっしゃぁい」
店長さんはふだんの仏像の顔になってくれた。ありがたやー……。
とか思ったらまた般若になった。
「ミカド! てめ、もしかして、心音の嬢ちゃんに怒鳴ったのかぁい!」
「……いえ。自分は怒鳴ってなど……」
「じゃあさっっっきの声はなんだよぉ、あぁん?」
「あ、あの、てんちょさん。あの、あたし、怒鳴られてたってか、ミカドさん? と、スイーツ談義が盛り上がりすぎったっただけっていうか。……ねっ、ですよねっ、ミカドさん?」
ミカドさんはまたしてもばつの悪そうな顔であさっての方向を見た。
「ミカドおおお! おま、なに高校生の女の子にかばわれてんだああああ!」
「……かばう、ときましたか。いやあ、困りましたねえ」
ミカドさんは、あたしの顔を真正面から見て、
めっちゃまぶしく、かっこよく、
すっごく素敵な商売スマイルで、笑ってくれた。
「……スイーツのことで頭がいっぱいなのに、かばってくださったんですか?」
ひそひそひそひそ。
「てんちょさん。なんですか。このひと」
「ううん。なんなんだろうなあ。俺もよくわかってねえんだよ。ただ、天才ブリュレパティシエってことでさぁ」
ミカドさん、スマイルのままだ。
「……まァ、ブリュレの腕は超一流だ。態度はこんなんだけどな……」
「そもそもスイーツの神職であるパティシエに他の業務をやらせるなど……」
「こんな調子なんだ。ごめんなぁ、ココちゃん。おいミカド、このコは常連の高校生の心音ちゃん。ちゃあんと覚えとけよお」
「はあ。なんで接客まで……って」
あたしはめっちゃキラキラした目で両手を握り合わせてミカドさんを見上げていた。
「天才パティシエ、なんですかっ?」
「は?」
「ミカドさんって天才パティシエなんですか!?」
「は、え、あっ、ちょ、近い、近いですから常連の高校生の心音さん」
「……ああ。そいつは、パティシエとしては、天才だよ。間違いねえ。日本じゃかえってまだ知られてねえが、本場だと、すごいんだぞ」
「すごい! すごいです……! お願いがあります。あたしを、弟子にしてくださいっ!」
ぺこりっ!
弟子ぃ? と、ミカドさんは露骨にイヤな顔をした。
店長さんが慌てて、とりあえず詫びさせるから、とミカドさんの頭をひっつかんで、下げさせた。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

イケメン政治家・山下泉はコメントを控えたい
どっぐす
キャラ文芸
「コメントは控えさせていただきます」を言ってみたいがために政治家になった男・山下泉。
記者に追われ満を持してコメントを控えるも、事態は収拾がつかなくなっていく。
◆登場人物
・山下泉 若手イケメン政治家。コメントを控えるために政治家になった。
・佐藤亀男 山下の部活の後輩。無職だし暇でしょ?と山下に言われ第一秘書に任命される。
・女性記者 地元紙の若い記者。先頭に立って山下にコメントを求める。

十年後、いつかの君に会いに行く
やしろ慧
キャラ文芸
「月島、学校辞めるってよ」
元野球部のエース、慎吾は同級生から聞かされた言葉に動揺する。
月島薫。いつも背筋の伸びた、大人びたバレリーナを目指す少女は慎吾の憧れで目標だった。夢に向かってひたむきで、夢を掴めそうな、すごいやつ。
月島が目の前からいなくなったら、俺は何を目指したらいいんだろうか。
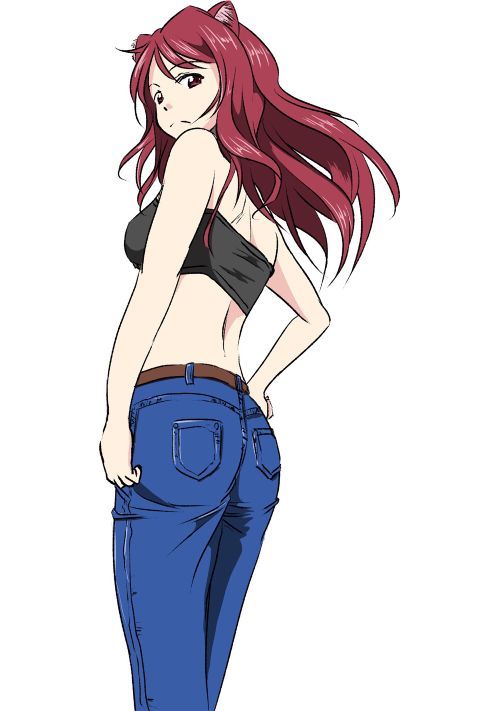
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

春風さんからの最後の手紙
平本りこ
キャラ文芸
初夏のある日、僕の人生に「春風さん」が現れた。
とある証券会社の新入社員だった僕は、成果が上がらずに打ちひしがれて、無様にも公園で泣いていた。春風さんはそんな僕を哀れんで、最初のお客様になってくれたのだ。
春風さんは僕を救ってくれた恩人だった。どこか父にも似た彼は、様々なことを教えてくれて、僕の人生は雪解けを迎えたかのようだった。
だけどあの日。いけないことだと分かっていながらも、営業成績のため、春風さんに嘘を吐いてしまった夜。春風さんとの関係は、無邪気なだけのものではなくなってしまう。
風のように突然現れて、一瞬で消えてしまった春風さん。
彼が僕に伝えたかったこととは……。

龍神山の蛙
Yoshinari F/Route-17
キャラ文芸
明治時代。
龍神の巫女である龍加美紗夜(りゅうかみ・さや)は、干ばつで水不足に陥った村を救うため、たった一人で龍神山迷い込む。龍神山には多くの妖(あやかし)が棲むと言われ、誰も近づくことのない魔の山。その山頂にある龍神湖には「主様=龍神様」が棲み、雨を降らせる力を持っているといわれている。またその生き血はあらゆる病を治し、肉には不老不死の力が宿っているという。しかし、そこで1尺(30㎝)もあろうかという蛙が紗夜の目の前に現れ口づけを懇願する。
「巫女殿、口づけを…!!」
「い…嫌ぁぁぁ!!」
16歳の経験のない乙女の唇を狙う蛙の目的は? そして紗夜は「主様」のもとに辿り着き雨を降らせてもらい、村を救うことが出来るのか? やがて紗夜の失われた記憶と蛙との過去が明らかになり、物語は急展開を見せる。
原作 Yumi F
文 Yoshinari F/Route-17

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















