4 / 7
マーメイドシンドローム
マーメイドシンドローム
しおりを挟む
その青年はいつも週末に訪れる。
質の良い生地のジャケット、細身のパンツ、それから夜のように真っ黒な髪は軽くセットされている。
気合いが入りすぎないように、でもしっかりと身なりを整えた彼は、赤の他人から見ても清潔感を身に纏った好青年だった。加えて陶器のような頬、すっと通った鼻筋。人混みに紛れきれず頭ひとつ出た背丈に、女性は皆一度は彼を振り返る。そしてうっすらと青みがかった切れ長の瞳と視線がかち合えば、彼女達は必ずと言っていいほど気まずそうに目を逸らすのだ。
彼は慣れた道をそんな視線はものともせずにぶらりと歩く。彼にとってその音はBGMであり日常であり生まれた時からのものであるので、さして今更気にならないというのが本音だった。
来館は開館とほぼ同時。ぼんやりとした目がドーム状の建物を目にした途端、一瞬きらりと輝く。待ち人がいる方が少ない水白水族館の待機列に立ち、券売機で〝大人一枚〟をぽちりと押す。開館と同時に入館する彼は、水白水族館には珍しい客だった。入り口でチケットを切ってもらい、相変わらずがらんとした館内を見回して口元を緩める。いつ来てもここは人が少ないなと彼は思う。
これで経営は問題ないのだろうか、などと青年は余計なことも考えた。この水族館の常連を長らくやっていると自負しているが、家族連れがもう少し多いのが通常ではないだろうか。だが彼はここ以外の水族館を知らないというやや風変わりな青年だったので、そんなものなのかなとも思っていた。
まあ彼はいろんな意味で〝珍しい客〟なのだが、そんなことは彼が知る由もないことだ。
彼のルートは決まっている。入り口の水白水族館の紹介が書かれたパネルから、小さな水槽をいくつか見て周り、深海の生き物たちをゆっくりと眺めた後に、館内でランチを摂る。そのあとは十三時のイルカショー、そして水白水族館の中で一番広い展示場である、大水槽のホールでスツールに腰をかけてきっかり一時間。大小様々な生き物を見ながら、ぼうっと緩やかな時間を過ごす。
特に決めてなかったルートであったが結局のところ同じルートで館内を一周するのが彼のいつもであった。もちろん季節や気候により、イルカショーがペンギンショーになったりと微々たる変化はあったが。一階、二階、そして吹き抜けと進んだ後に彼は最後に残る一箇所を訪れる。
青年は目の前を過る生き物たちから目を逸らし、腕に乗った時計の針へ目を遣った。そして無表情に近かった目尻を一瞬緩め、口元に小さく笑みを浮かべる。彼女との、デートの時間だ。
「高梨さん、こんにちは」
ほとんど荷物も入っていない鞄を肩にかけた時、馴染みのある低い声が耳を打った。振り返ると予想していた人物がにっこりと人の良さそうな笑みで眉をハの字に下げている。
「紫野単語さん、こんにちは」
高梨はすっかり顔見知りになってしまったここの支配人へぺこりと会釈した。
「今週はいらしてくださったんですね」
「もちろんですよ。課題もひと段落つきましたし」
弾んだ声を出して高梨は言った。この声と顔を知ったら彼の大学の友人たちは面を食らってしまうに違いない。あの能面イケメンの高梨がはしゃいでいる、と。現実問題、彼のここでの様子は友人達が知る予定もなく、そんな未来は訪れないのだが。
高梨の名を呼んだ男性は困ったような嬉しそうな顔で問うた。
「私が言うのもなんですが、そんなに毎週だと飽きませんかねえ」
「いいえ。やっぱりこの水族館はすごく落ち着きます。魚も海洋生物も、珊瑚やクラゲだっていつ見ても見飽きません」
薄暗い空間で水槽越しの水面を映した色の瞳で高梨はすぐさま答えた。
「それはそれは、有難いお言葉です。ここの子達は私たちが心を込めて世話をしている子達ばかりですからね」
「そうですね。僕はここの水族館しか知りませんが……水白水族館の生き物たちはみんなとても楽しそうで、自由に見えます」
そうですかと相槌を打ちながら紫野はううんと困ったように笑った。
「しかしそんなに水族館がお好きであれば、たまには別の水族館もご覧になってみてはいかがですか?」
きっとうちより素敵な展示も、広いホールもたくさんあるでしょう、と。しかし高梨は首を振ると柔らかく、けれどきっぱりその提案を否定した。
「確かにここの展示より素晴らしい場所や、美しい生き物たちは他にもいるのでしょう。 でもそこに彼女はいません」
いつもは辺りの景色を映すモニタになる瞳が、爛々と熱を宿して紫野を見つめる。その温度は触れたら溶けてしまうほどだろうか、なんて紫野はずれたことを考える。
「……今日も今から彼女のところへ?」
それ以上は余計な詮索だと紫野は話を逸らした。幼い頃から変わらない、薄く青を孕んだ瞳が照明に反射する。
「はい、もちろん」
会うたびに垢抜けていく容姿で満面の笑みを浮かべた高梨を見つめて、紫野は小さく笑った。
「そうですか。ぜひ会いに行ってあげてください。彼女はいつも退屈していますから」
そう伝えると、青年の表情はぱっと更に明るくなる。そしてさっと髪を触って、きょろきょろと辺りを見回すと紫野に一歩近づいて小声で尋ねた。
「……変なところ、ないですか?」
それがあまりにも昔と変わっていなかったので、紫野は思わずくすくすと笑ってしまう。全く、この高梨という人間はいつもそうなのだ。普段は何を考えているかわからない無表情であるのに、彼女と会う時だけは年相応、いやそれより幼いぐらいの様子を見せる。
まるで少年のように頬を赤らめる彼の全身をさっと眺めて紫野はゆっくりと伝えた。
「いつも通り、とても素敵ですよ。新しいセーターもよくお似合いです」
紫野の言葉を聞いた高梨はそうですかと小さく漏らし、ふいと目を逸らした。恥ずかしいのであればレストルームで確認をすればよいのにと思うが、誰かに客観的な意見を言って欲しいと思う時もあるのだろう。自分にはわからない感情だが。そう紫野は一人結論付けた。
「さあ、早く行ってあげてください。閉館まであと二時間しかありません」
彼の声に高梨は時計を見ると、慌てて二階へ向かうエスカレーターの方へくるりと向き直った。
「紫野さん、いつもありがとうございます」
振り返ってお礼を言うのは忘れずに。
「あの子はあと何回、ここを訪れるつもりなのでしょうか」
ぽつりと落ちる紫野の言葉は薄闇の室内に溶けていく。青年の後ろ姿が憂いた彼の瞳に焼きついた。紫野はふう、と息を吐く。これは彼がどう言ったところで変わることではない。何をしたって、言ったって。そういうものは往々にしてある。
紫野は高梨の眩しい笑顔を頭の中から追い払った。次のスケジュールを頭に思い起こして、手筈を考える。彼の頭の中は、少しずつ仕事の思考になっていく。それでいいと紫野はもう遠くなっていく痛みに近い何かに蓋をする。それは彼の能力に過ぎたことであったので概ね正解であった。
彼ははただ、見過ごすだけの。傍観者に過ぎないのだから。
僕はいつも通りエスカレーターを上がり、息を吸う。彼女との待ち合わせはやはりいつも緊張する。深い海の底のようなゴツゴツした柱が見えてくると、一瞬どくんと心臓が跳ねる。授業で見た西洋の絵画に出てきそうな柱。
身だしなみは大丈夫だ、さっき紫野さんに見てもらったところだし。彼女の目はとてもよく僕を見ている。だから今更急ごしらえのように取り繕っても仕方ないのだが、やはり好きな人には少しでもよく思ってもらいたいというのが恋をする者の性だろう。
岩のアーチを潜って奥へ進む。濃紺の絨毯は古いが丁寧に手入れがされており、ふかふかと足が沈む。決して狭いとは言えないフロアには珊瑚のような柱が四隅で天井近くまで伸びている。青みを帯びた、海の底に誘われたような空間。まるで神殿のようなその場所の大きな水槽に、彼女は住んでいる。
「あらお久しぶり、かしら」
水のように耳に馴染む音がした。丁寧に磨き上げられた硝子の中。敷き詰められた珊瑚に手を伸ばしながら、彼女が涼しげな声を発したのだった。身体中の細胞の温度が、瞬く間に上昇する。長年焦がれている癖に、彼女の声に慣れることは出来そうにない。細く伸びたうっすらと黄色の明かりが、彼女の銀糸の髪を眩く映し出している。
ここに入った瞬間、僕はいつも思う。彼女は海底の姫のようだと。
「先々週、また来るって言ったでしょ」
ガラスの周りを取り巻くように備え付けられているスツールに僕は腰を掛けた。掛けるのは結局いつも同じ場所だ。水の中でふわふわと長い彼女の髪が扇状に広がっている。そのままで彼女は心底可笑しそうな声を上げる。
「貴方の言うことが本当か嘘かなんて私にわかるはずないじゃない」
きゃらきゃらとまた彼女は笑って、くるりと水の中を一周した。
「そうかな? 君には何でもお見通しなんじゃない、ミア」
「その気になればそうかも。でも私、子供の戯れは信じないことにしているもの」
くすくす笑いながら彼女はドーム状の筒の中をするりと抜ける。ミアの曇り空を映したような、雨の一歩手前のような色の髪がゆらりと揺れる。桜の尾鰭が目の端を瞬く間に通り過ぎる。ミアの泳ぎはすごく早かったり、とろとろと漂っているだけのようであったり一貫性がない。機嫌の悪い時は僕の前に顔も出さずに隅っこの方に潜んでたり、動体視力が追いつく間もない速さで縦横無尽に彼女だけの海の中を泳ぎ続けていることもある。つまりは彼女の気分次第なのだった。まあ、最初は見られることすら嫌がられていたので、僕は現状に十分満足しているけれど。
抜けるような肌の上を流れる銀色は、空が雪原に触れたようだ。その様は何度見ても溜め息が出るほど美しく、僕はぼうと見惚れることしか出来ない。幼い頃から、ずっと。ずっと。
ミアは大きな水槽をゆったりと泳ぐ。まるで散歩でもするようにのんびりと。そしてまた僕の前に舞い戻ってくると、陸に上がってあたたかな琥珀色の大きな目で僕を見た。今日は随分とご機嫌らしい。陸と言っても砂を模した薄いクリーム色をしたプラスチックの床で、なにも童話の人魚姫のように本物の砂が撒いてあるわけではない。
そんな砂浜もどきの上に慣れた要領で身軽に腰を掛けた彼女は、僕の目の前でゆっくりと尾の鱗を撫でた。つるりとした床はミアの耀く鱗一つ一つを傷つけることがないように、丁寧に磨かれている。僕はミアの尾を見るたびに、人魚の鱗を欲しいと思う人間の気持ちを理解し難く思う。手を伸ばすことさえ躊躇ってしまうほどの美しさを、自分だけのものにしてしまおうなんて、恐れ多い。そして何よりこわい気がするから。うっすらと淡い虹色を跳ね返す小さなその一つでさえも、自分のものにしてしまうと考えるとぞわりとどこかが寒くなる。
僕がそんなことを思っているとも知らない彼女は僕が自分の手を、足を振るように、軽く尾を振る。それから彼女はハリボテの砂浜にぽつりと置かれている貝殻を手に取った。映画のセットなんがでよくありそうな、縦長の渦巻いた貝殻だ。以前訪れた時には無かったものだった。
「それ、どうしたの?」
僕は彼女の手元にある貝の経路を尋ねてみる。誰が置いたのか大体わかっていたので、答え合わせのための質問だった。
「今朝、紫野がくれたのよ。私が退屈してたから」
誰かさんが来ないせいでね。ミアはそう付け加えると頬を膨らませて僕を睨む。透き通った飴玉みたいな琥珀色の瞳。
「ごめんってば。試験が大詰めだったんだよ」
予想通りの答えに安堵しながら、僕は彼女に精一杯の謝罪が伝わるように言う。本当は僕だって会いたかった。試験なんてくだらないもの投げ出して、一日中君とお喋りをしていたかった。まあそんなことをすぐに口に出せるほど、キザにはなれなかったけど。
「わかってるわよ。人間は窮屈ね」
僕の謝罪は上手く伝わったのか、ミアはふんと鼻を鳴らしてそれ以上なにも言わなかった。そしてまた、手にした貝殻を振ってみたり、眺めてみたりする。貝殻は彼女の指先と同化してしまいそうに、真っ白だった。彼女と同じ世界線にある貝殻。ミアは貝殻にそっと耳を近づけると、眉を下げてへにゃりと笑った。
「同じ海の音がするわ」
「同じ海?」
明らかにいつもより柔らかい表情をして、彼女は内緒話をするようにそっと囁いた。
「これね、私が昔いた海にあったものなんですって」
「ミアの、故郷か」
「ええ。いいでしょう?」
ミアはふっくらと薔薇色に染まった頬を、貝殻に押し付ける。ミアに故郷があるのは知っていた。野生の人魚なんて、そもそも人魚が住む海なんて聞いたことが無かったけれど、僕は彼女の言葉を全面的に信じることにしている。
ミアの話ではこうだった。そこは人魚がいて、数は少ないけれど人間もいてすごく広い海の入り口があるのだと。彼女の話を聞いたのは随分と前だったけど、僕にとってそれはどんな御伽噺よりも魅力的だったのでよく覚えている。緑の匂いが肺を満たして、つやつやした果物が年中たくさんなって、絶え間ない波の音や陽気な住人たちの歌声があちらこちらで聞こえる小さな町。ミアの故郷はそんな海辺の町だったのだと。きっと素敵な所なんだろうねと、その時の僕はそう言葉を紡ぐのが精一杯だった。目の前のミアが遠い人のような気がして。懐かしそうに目を細める彼女の表情は、僕が目にしたことのないものだった。穏やかで、きらきらした笑みだったから。
あの時と同じ笑みをして飽きずに貝殻を耳に押し当てる彼女を見つめながら、波の音を思い出してみる。あの、ざらざらとした音。けれど不快感のない、遠くなったり近くなったりする、あの音を。ミアの町の海は僕の知っている波と同じ音で揺れるのだろうか。
「貴方にも聞かせてあげられたらよかったのに」
きゅっと両手で貝殻を抱えたミアは、すいっと僕らの隔たりまで泳いできて硝子に貝殻を押し当てる。
「ね、聞こえる?」
耳を澄ませる。しかし、僕の耳に届いたのは微かな空調の音だけだった。
「聞こえないな」
はあ、と大袈裟にミアは溜め息を吐いて貝殻を投げる。ポチャンと音を立てて、貝殻はミアの足元にあっという間に沈んでいった。
「お行儀が悪いよ、ミア。大事にしてたんじゃないの?」
ミアは貝殻の沈んだ方向をちらりと見て、それからぶんぶんと首を横に振った。
「あとで拾うわ。いいのよ、もう私のものなんだから」
眉間に皺を寄せた彼女は、怒ったような悲しいような複雑な表情をした。硝子に添えられた手のひらはいつのまにかぎゅっと指が折りたたまれていた。
「ねえミア」
「なによ」
ぶすっとした声はわかりやすく元気がない。僕には彼女の気持ちがきっと半分もわかっていないだろうけど。
「僕も聞きたかったな、ミアの住んでた海の音」
本心からの言葉を口にして、丸めた両手にそっと自分の手のひらを重ねる。また、空調の音だけが僅かに僕らの間に落ちる。
貝殻から海の音がするというのは嘘なんだよと事実を今の彼女に言うのは憚られた。僕よりもうんと長生きのくせに、無邪気な子供のように緩む頬が愛おしかったから。彼女にとって美しくて大事な嘘。それを壊してしまうべきではないことぐらい、僕にでもわかった。だってそれはただの事実でしかない。
「ねえ、透」
先に口を開いたのはミアだった。
「どうしたの?」
僕は彼女の言葉を慎重に促す。出来るだけ多くの選択肢の中から彼女を傷つけない言葉を選んだら、当たり障りのない言葉になってしまった。
「もしもの話をしてもいい?」
「いいよ」
少しだけいつものミアの語気が戻っていたので、僕は嬉しくなる。すぐに返事をした。
ミアは僕がそう答えることを知っていたのだろう。口元を緩めて、空気に溶けてしまいそうな声を紡ぐ。
「もしもね、私がまだ海にいたとするでしょう?」
「なるほどね」
彼女は少しずつ言葉を続ける。まるで答え合わせをするように。
「そうしたら、私はこの水族館にいなかったってことにならない?」
「なるね」
僕は肯定を返す。
「つまり、もし私がまだ海にいたら貴方に会うこともなかったでしょうね」
「それはそうだね。僕らはここで出会ったんだから」
もう、十数年も前の季節を思い出す。あの日の彼女は退屈そうに水の中に沈んで、瞼を閉じていた。両手をいっぱい広げてもとても届かないガラス、見向きもしない檻の中の彼女。細く水に差し込んだ光に照らされた横顔が、ただただ綺麗で。夢中になった僕は不機嫌な彼女の声に諌められるまで、べったりとガラスに張り付いていた。
「ねえ透、あの日貴方に会えた日。私運命が変わった気がしたのよ」
ミアは丸めていた指先を解いて、僕の手のひらに重ねる。伏せていた睫毛がふわりと持ち上がって、優しく煌めく彼女の大きな瞳を縁取った。
「透」
「どうしたの」
「もしも、私がここから逃げ出したいって言ったらどうする?」
それはひどく不思議な声音だった。試しているような、揶揄っているような。それでいて怯えているような、そんな。
「今日のミアは質問ばかりだね」
ゆっくりと言葉を乗せる。ミアの眼差しは痛いほど真っ直ぐに僕の心臓に刺さる。
「透」
催促するような、焦れた声が耳を打つ。僕は彼女の眼差しを受け止めながら、細胞から溢れ出る心を言葉に造り変える。
「駄目だって言うよ、だってミアがここから出たら命の危険があるかもしれない。僕は頭が良いけど、人魚のことには詳しくないし」
こつん、とガラスを手の甲で打つ。ミアは僕の回答に眉を下げて口元を引き結んだ。つまんない男ね。そう言われる心積りは出来ていたのに、棘のある言葉は降ってこなかった。
「だから」
彼女がどんな言葉を求めているのか、今の僕ならわかる気がした。きっと出会った頃には伝えられない答えだった。そうだ。あの時の彼女を思い出す。僕はあの時、彼女に呼ばれた気がした。鋭い眼差しの向こうで揺れる、同じぐらいの歳の女の子を見た気がしたんだ。あの時抱いた気持ちは何一つ変わっていない。ミアは美しくて気高くて。親しくなって知った我儘な一面や、子供っぽい感情さえ眩しくて。君は宝物みたいな女の子だ。
僕は用意していた続きを紡ぐ。吸い込んだ空気がうまく飲めなくなりそうだった。早鐘のように打つ心臓が邪魔だった。指先を握りしめる。君が、ミアがそう言ったら。
「だからもし君がここから逃げ出したいって言うのなら。ミアが逃げ出すよりも早く僕がちゃんと攫ってみせるよ」
はっと息を呑む音がした。綺麗な琥珀色の瞳孔が、縦長に大きく開いている。伝わったかはわからなかった。また外の世界を見てみたい。そんなささやかな願いを夢見る、彼女の心の近くにいたくて。ただそれだけの一心で。
「ふふ、なにそれ。馬鹿みたい」
そして、次の瞬間彼女は笑った。縦長の鋭い瞳孔は一瞬ですっかり収められていて、銀色の睫毛は柔らかい曲線を象っていた。
「僕の答えは気に入った?」
彼女の返事がわかってるくせに、尋ねる僕は傲慢だろうか。
「うん、とても」
しかしミアは素直な返事をする。これはとても珍しいことだった。そればかりではなく、ミアは頬を緩めて目尻を下げる。どうやら僕の回答が余程お気に召したようだった。
「僕がミアを攫ったら、きっと紫野さんは怒るだろうな」
僕はここの支配人の名前を挙げる。物腰が柔らかく丁寧な彼が怒る姿は目にしたことがなかったけれど。紫野さんは彼女をとても大事に思っている。それは幼い頃から見ていた僕だから、断言できた。紫野さんの愛情はこの水白水族館の生き物全てに注がれている。まあ、本当のことを言ってしまうとミアに対してだけはちょっと悔しかったりもするんだけど。
「紫野はケチだものね」
変な言葉だけ妙によく知っている彼女は、くすくすと自分の言葉にまた笑った。貴重な生き物を逃してしまったってあたふたするんだわと。
「ミア」
「…………」
「ここはお客さんも少ないから仕方がないよ。紫野さんは君たちを守るために、頑張っているんだと思うよ」
やんわりと否定する僕に、ミアは頬を膨らませる。さっきまでの穏やかさはたちまち形を潜めてしまう。
「あの男が私たちを守ってるですって? 私をこんな狭い水の中に放り込んでいるのも自分なのに?」
びたん、と尾を水の中に打ちつけて彼女は呆れたように僕を見遣った。細かい水飛沫が跳ねる。僕はその動作を見てついくすくす笑ってしまう。ミアは苛々してくると尾をびたんびたんと打ち付ける。僕の顔を見て、また目が釣り上がるミアを身振り手振りで宥めた。彼女に触れられていたら、僕はどんな風に宥めるんだろうか。
尾を打ち付ける音が止んだ頃、僕はそっと問うてみる。
「ミアは紫野さんのこと、本当に嫌いなの?」
彼女が紫野さんの話をする時は大抵不機嫌だ。それは僕も知っていたけれど。でも、本当の本当に嫌いではないんじゃないかと思う。彼女が言う〝あの男〟は紫野さんしか居ないし、そこに本当の憎さは籠っていないように思うから。
「…………わかってるわよ。あの男が本当の悪じゃないことぐらい」
機嫌の悪い声は依然として保ったまま、ミアはぼそりと呟く。少し決まり悪そうだ。
「ミアはいい子だね」
頭を撫でたくなる衝動を指先に乗せ、ガラスを撫でた。
「子供のくせに、私のことを子供扱いするなんて生意気よ」
彼女はお行儀悪くまた尾をびたん、と強く打ちつける。あまり強く打つと、美しい鱗が落ちそうではらはらする。
「うん、ごめんね」
僕は彼女の額に自分の額を重ねて詫びた。ミアがぐっと文句を飲み込んだ音が聞こえた気がした。
「最近の人間って紫野みたいな性悪か、貴方みたいなぼんやりしかいないのかしら」
はあと吐かれた溜め息は言葉の意味を丸くしてゆく。
「どうだろう。僕にはわからないな」
友達には能面って言われるし。
「そうだ!」
はっとした顔でミアは目を輝かせる。
「あなた、今度ここへお友達を連れていらっしゃいよ!」
ガラス越しに白い頬が、ゆっくり近づく。また小さく心臓がとくんと跳ねた。
「ミアはさ」
「なあに」
腹の奥が微かにざわめく。薄明かりの中の照明が、水に透けてゆらゆら揺れる。
「僕より魅力的で、君のことも理解して大好きな人が現れても僕を選んでくれる?」
自分でもわかるぐらいにぐらぐらの声だった。こつんと額を硝子につける。一枚隔てた向こう側の彼女に届かない熱が今、どうしようもなく悔しい。
「さあ、それはどうかしらね」
彼女はそれだけ言って悪戯っぽく笑うと、とぽんと水に沈みこんだ。水の中で愉しそうに笑ったミアは、きゃらきゃらと可愛らしい声を立てながら、僕の視界の端から端までを行ったり来たりする。蛍光灯の光を受けた鱗がきらきらと輝く。何度見てもその姿は美しく、僕は溜息を吐きながらその姿を両目に焼き付ける。
「ねえ、透」
「なに」
「一度だけでいいから、私貴方と紫野以外の人間と、たくさんお喋りしてみたいわ」
水面に顔を半分だけ覗かせてミアは目を輝かせる。さっきの話の続きだろう。期待一杯の眼差しは眩しくて、僕は苦笑してしまった。
「そうしたいのは山々なんだけど」
「なによ」
僕が意見したことが気に食わないらしい彼女は、水面から目だけを出した状態のままで、僕の言葉を促す。
「ミアがこんなに可愛いのを知られてしまうのは、もったいないなと思うんだって言ったら怒る……?」
喉からは情けない、ぼそぼそと呟くような声しか出なかった。
「……貴方ってお馬鹿さんなのね」
僕の言葉にどう思ったのか彼女はそのまま黙ってしまった。ちゃぽんとミアの顔が再び水に沈む。僕の目の前で一回転して、水槽の端から端までをゆっくり舞うように尾鰭を跳ねさせる。僕を横切っていく頬が熟れたばかりの林檎のようにふわりと色付いていた。それが僕の気のせいではないならば。
口元に微笑みを宿して仰向けに泳ぐ姿は、まるで女神のようだった。銀糸の柔らかく広がる髪、白く水面の光を映す肌、淡青の宝石を一つ一つ薄く削ったような丸みを帯びた鱗、それらが犇いた先には桃色の尾鰭。人間の足とはまるで違う。しっかりと筋肉が付いているであろう尾は柔らかくしなって水を掻き分ける。
僕は彼女の尾に特に惹かれていた。ミアの尾は芸術品のようでいて、けれど決して尾だけでは成立しないものだった。人魚の構造は少し本を読んだけれど、ほとんどわからなった。でもこれだけはわかる。彼女の、ミアの下半身に付いていることで、それはやっと意味を成し得るのだということは。
調べ物の合間に、人魚の肉を食すと不老不死になるという話を目にした。きっと誰もが知っている話だろう。けれどこんなにも美しい生き物を目の当たりにして、それでも手に入れたいと思う人間は本当にいるのだろうか。
彼女の自由に水を掻くその尾鰭、口元に笑みを浮かべたその表情を見る度に僕は思う。
童話の人魚姫は尾を失って二本の足を手に入れた後、はたして本当に幸せだったのかと。広い海を駆け回る鮮やかな力強い尾を失っても、二度と海を駆けることが出来なくとも良かったのだろうかと。僕が童話の登場人物なら。ミアが童話の中の人魚であるならば。好きな人が魔女に願って、こんなに美しいものを自ら失くしてしまうくらいならば。きっと自分が彼女と共に泳げるよう、彼女と同じ尾を授けてもらえるよう願うだろう。
たとえ御伽噺と同じように声を失ったとしても。彼女の、ミアの可愛らしい声を、尾を失くしてしまうよりずっといい。
そこまで考えて、僕は自分が馬鹿馬鹿しい妄想をしていたことに気がついた。現実は僕とミアは硝子を隔てた陸と海。狭い海で自由気ままに浮遊する彼女は、人魚だ。
「ねえ、透」
コンコンとミアはガラスをノックする。視線を戻すと、彼女は僕の顔を指差してにやりと笑う。
「貴方変な顔ばかりしてるわよ。どうせまたつまらないことを考えていたんでしょう」
「そうだね、そんなところかな」
僕の返事に気を良くしてミアはにこにこと笑う。
「貴方はお馬鹿さんなんだから、余計なことを考えない方がいいわ」
なんだか子供扱いされているようで少しむっとした。僕はそっぽを向く。そんな僕を見つめてミアはけらけら声を上げる。
「そんなことより、私の話を聞いてちょうだい」
「どういう話?」
彼女のきらきらした声で言われたら、そっぽ向いてなどいられないのが僕の弱い所だ。
「さっきの続きの話よ。いつか、いつかね。私を海に連れて行ってほしいの」
遠くを見たミアの瞳は相変わらず真っ直ぐでいて、少しだけ翳っているようにも見えた。
「ミアを海に?」
「そう。私がいた、とびきり綺麗な海よ」
「ミアの住んでいた海か。まずは場所から調べないと」
僕は頭の中に地図を広げる。うん、これからは地理の勉強もしなくてはならない。
「だからいつかね、いつかの話よ。その時が来たら、透。私と海に行ってほしいわ」
ミアは長い髪をかき上げて、目を伏せた。瞼に光が落ちる。口にしたくせにいつものような勢いの無い約束だった。
「じゃあ僕はもうその時まで海は取っておこうかな」
僕は子供の頃に行ったきりの、さざめきを思い出す。そして波の音はそのままに、彼女の故郷の海に想いを馳せる。見たこともない海。ミアの昔聞いたという波の音。その海はどんな色で、どんな音をしているのだろう。
「行こう、きっと」
「貴方が約束を忘れてなければね」
意地の悪い笑いがきらきらと二人の空間に落ちた。
僕は口元を緩めて、彼女の琥珀色の瞳を覗く。そこには星屑のような光が瞬いていた。
ごうごうと空調だけが響くフロアに、コツリと革靴の柔らかな音が響く。やがて姿を現したスーツ姿の男は床の絨毯をゆっくり踏んで進む。
「彼はお帰りですか」
高梨が座っていた場所へ腰を掛けながら、彼は水の中で目を閉じた彼女に問う。
「とっくにね」
「そうですか」
紫野は閉館後毎日ここを訪れる。人魚はそれが毎回煩わしくて仕方がない。毎度自分が見せ物だと位置付けられているような気がして。
「性悪」
「私がですか。何かしてしまいましたかね」
もちろん彼にそんなつもりがないことはわかっている。彼女はそういう意味では、人の気持ちに特別聡かった。けれど面と向かって文句を言っても、気にも留めないこの男を見ると苛々してしまう。
彼が私たちを守っていると高梨は言った。人魚はぎゅっと唇を噛む。あの日確かに、命が尽きるその直前にこの大きな手で彼女を引き上げたのは紫野だった。それは事実である。感謝だってしている。絶対口にはしてやらないが、ちゃんと頭では理解しているのだ。
「お前はわかっているのに尋ねるから性悪だと言うのよ」
ミアはぎりぎりと歯を鳴らす。恩があるのと、馬が合う、合わないというのはまた別の問題だ。この紳士の皮を被った飄々とした男が彼女は嫌いである。
「人魚様の考えていることなんて私には崇高すぎて分かりませんがね」
そう言って紫野はふ、と息を吐く。考えていることのほとんどが素直に顔に出る人魚はなかなかに珍しい。
「本当によく喋る口だこと ここが海なら沈めてやりたいわ」
「そんなに機嫌を悪くしないでください」
紫野は全く悪びれる様子もなく、にこりと笑う。人魚が胡散臭いと罵る笑みで。
「ねえ、紫野」
微かに聞こえる空調の音だけが、しばらく続いた後だった。人魚は静かに言葉を紡ぐ。
「……人間って何年生きるものなのかしら」
紫野は少し首元のタイを緩めて、また息を吐いた。
「…………」
「透は、あと何回私を見られるかしら」
焦ったさとも苛立ちとも困惑ともつかない声で、彼女は紫野の返事を促す。痛いほどの強い視線が紫野を射る。しかし紫野はただ視線を自分の目に収めるだけで、かぶりを振った。
「どうでしょう。こればかりは個人差がありますからね」
「……そうね。そういう生き物だったわね、人間は」
人魚は口元を引き結んで、瞼を伏せる。
「彼が人間でなければいいんじゃないですか?」
ぱっと人魚は顔を上げる。紫野の口元がゆっくり弧を描く。彼は目の前の人魚の瞳孔が、みるみる膨らんでゆくのを眺めた。
「彼を人間でなくしてしまえばいいのではないですか」
喉の奥でくつくつと笑う声が落ちる。真夜中の稲妻のような、紫野の瞳がぎらぎらと揺れる。
「…………だめよ」
低い音が人魚の口から漏れる。彼女の瞳孔はするすると小さく萎んでしまった。震える声で人魚は小さく呟く。
「透はだめ。透だけは、だめなの」
「……そうですか」
紫野は短く返事をした。だめならしかたありませんねと。もうさほど興味のない、いつもの愛想だけを乗せた笑みを見せる。
「お前は本当に性格が悪いわね」
とぷんと水に沈む寸前、人魚は唇をぎゅっと噛む。二者の間にそれ以上の会話はなかった。
紫野は体温の馴染んだスツールを立った。水に漂う銀色の髪を横切って、また来た道を引き返す。電気のパネルを押すのは忘れない。何しろここの設備は、この建物の中でもとりわけ電気を食うのだから。長い足を廊下に伸ばし、彼はああと首元に手を添える。
「人魚姫は幸せになれない運命なのでしょうか」
慣れた手付きでネクタイを締め直した彼は一人ごちて、手鏡をポケットから出す。
「まあ、私には関係のないことですね」
そうして一人納得すると、さっとタイを直し、髪を整え鏡をしまった。
暗闇に染まった館内を紫野は悠々と進む。瞼に刺さって抜けない痛みは多分気のせいだろうと思った。さあ早く仕事をして、目薬でも差さなければ。再び頭の中に犇くスケジュールを立て直す。彼の一日はまだ終われないのだった。
質の良い生地のジャケット、細身のパンツ、それから夜のように真っ黒な髪は軽くセットされている。
気合いが入りすぎないように、でもしっかりと身なりを整えた彼は、赤の他人から見ても清潔感を身に纏った好青年だった。加えて陶器のような頬、すっと通った鼻筋。人混みに紛れきれず頭ひとつ出た背丈に、女性は皆一度は彼を振り返る。そしてうっすらと青みがかった切れ長の瞳と視線がかち合えば、彼女達は必ずと言っていいほど気まずそうに目を逸らすのだ。
彼は慣れた道をそんな視線はものともせずにぶらりと歩く。彼にとってその音はBGMであり日常であり生まれた時からのものであるので、さして今更気にならないというのが本音だった。
来館は開館とほぼ同時。ぼんやりとした目がドーム状の建物を目にした途端、一瞬きらりと輝く。待ち人がいる方が少ない水白水族館の待機列に立ち、券売機で〝大人一枚〟をぽちりと押す。開館と同時に入館する彼は、水白水族館には珍しい客だった。入り口でチケットを切ってもらい、相変わらずがらんとした館内を見回して口元を緩める。いつ来てもここは人が少ないなと彼は思う。
これで経営は問題ないのだろうか、などと青年は余計なことも考えた。この水族館の常連を長らくやっていると自負しているが、家族連れがもう少し多いのが通常ではないだろうか。だが彼はここ以外の水族館を知らないというやや風変わりな青年だったので、そんなものなのかなとも思っていた。
まあ彼はいろんな意味で〝珍しい客〟なのだが、そんなことは彼が知る由もないことだ。
彼のルートは決まっている。入り口の水白水族館の紹介が書かれたパネルから、小さな水槽をいくつか見て周り、深海の生き物たちをゆっくりと眺めた後に、館内でランチを摂る。そのあとは十三時のイルカショー、そして水白水族館の中で一番広い展示場である、大水槽のホールでスツールに腰をかけてきっかり一時間。大小様々な生き物を見ながら、ぼうっと緩やかな時間を過ごす。
特に決めてなかったルートであったが結局のところ同じルートで館内を一周するのが彼のいつもであった。もちろん季節や気候により、イルカショーがペンギンショーになったりと微々たる変化はあったが。一階、二階、そして吹き抜けと進んだ後に彼は最後に残る一箇所を訪れる。
青年は目の前を過る生き物たちから目を逸らし、腕に乗った時計の針へ目を遣った。そして無表情に近かった目尻を一瞬緩め、口元に小さく笑みを浮かべる。彼女との、デートの時間だ。
「高梨さん、こんにちは」
ほとんど荷物も入っていない鞄を肩にかけた時、馴染みのある低い声が耳を打った。振り返ると予想していた人物がにっこりと人の良さそうな笑みで眉をハの字に下げている。
「紫野単語さん、こんにちは」
高梨はすっかり顔見知りになってしまったここの支配人へぺこりと会釈した。
「今週はいらしてくださったんですね」
「もちろんですよ。課題もひと段落つきましたし」
弾んだ声を出して高梨は言った。この声と顔を知ったら彼の大学の友人たちは面を食らってしまうに違いない。あの能面イケメンの高梨がはしゃいでいる、と。現実問題、彼のここでの様子は友人達が知る予定もなく、そんな未来は訪れないのだが。
高梨の名を呼んだ男性は困ったような嬉しそうな顔で問うた。
「私が言うのもなんですが、そんなに毎週だと飽きませんかねえ」
「いいえ。やっぱりこの水族館はすごく落ち着きます。魚も海洋生物も、珊瑚やクラゲだっていつ見ても見飽きません」
薄暗い空間で水槽越しの水面を映した色の瞳で高梨はすぐさま答えた。
「それはそれは、有難いお言葉です。ここの子達は私たちが心を込めて世話をしている子達ばかりですからね」
「そうですね。僕はここの水族館しか知りませんが……水白水族館の生き物たちはみんなとても楽しそうで、自由に見えます」
そうですかと相槌を打ちながら紫野はううんと困ったように笑った。
「しかしそんなに水族館がお好きであれば、たまには別の水族館もご覧になってみてはいかがですか?」
きっとうちより素敵な展示も、広いホールもたくさんあるでしょう、と。しかし高梨は首を振ると柔らかく、けれどきっぱりその提案を否定した。
「確かにここの展示より素晴らしい場所や、美しい生き物たちは他にもいるのでしょう。 でもそこに彼女はいません」
いつもは辺りの景色を映すモニタになる瞳が、爛々と熱を宿して紫野を見つめる。その温度は触れたら溶けてしまうほどだろうか、なんて紫野はずれたことを考える。
「……今日も今から彼女のところへ?」
それ以上は余計な詮索だと紫野は話を逸らした。幼い頃から変わらない、薄く青を孕んだ瞳が照明に反射する。
「はい、もちろん」
会うたびに垢抜けていく容姿で満面の笑みを浮かべた高梨を見つめて、紫野は小さく笑った。
「そうですか。ぜひ会いに行ってあげてください。彼女はいつも退屈していますから」
そう伝えると、青年の表情はぱっと更に明るくなる。そしてさっと髪を触って、きょろきょろと辺りを見回すと紫野に一歩近づいて小声で尋ねた。
「……変なところ、ないですか?」
それがあまりにも昔と変わっていなかったので、紫野は思わずくすくすと笑ってしまう。全く、この高梨という人間はいつもそうなのだ。普段は何を考えているかわからない無表情であるのに、彼女と会う時だけは年相応、いやそれより幼いぐらいの様子を見せる。
まるで少年のように頬を赤らめる彼の全身をさっと眺めて紫野はゆっくりと伝えた。
「いつも通り、とても素敵ですよ。新しいセーターもよくお似合いです」
紫野の言葉を聞いた高梨はそうですかと小さく漏らし、ふいと目を逸らした。恥ずかしいのであればレストルームで確認をすればよいのにと思うが、誰かに客観的な意見を言って欲しいと思う時もあるのだろう。自分にはわからない感情だが。そう紫野は一人結論付けた。
「さあ、早く行ってあげてください。閉館まであと二時間しかありません」
彼の声に高梨は時計を見ると、慌てて二階へ向かうエスカレーターの方へくるりと向き直った。
「紫野さん、いつもありがとうございます」
振り返ってお礼を言うのは忘れずに。
「あの子はあと何回、ここを訪れるつもりなのでしょうか」
ぽつりと落ちる紫野の言葉は薄闇の室内に溶けていく。青年の後ろ姿が憂いた彼の瞳に焼きついた。紫野はふう、と息を吐く。これは彼がどう言ったところで変わることではない。何をしたって、言ったって。そういうものは往々にしてある。
紫野は高梨の眩しい笑顔を頭の中から追い払った。次のスケジュールを頭に思い起こして、手筈を考える。彼の頭の中は、少しずつ仕事の思考になっていく。それでいいと紫野はもう遠くなっていく痛みに近い何かに蓋をする。それは彼の能力に過ぎたことであったので概ね正解であった。
彼ははただ、見過ごすだけの。傍観者に過ぎないのだから。
僕はいつも通りエスカレーターを上がり、息を吸う。彼女との待ち合わせはやはりいつも緊張する。深い海の底のようなゴツゴツした柱が見えてくると、一瞬どくんと心臓が跳ねる。授業で見た西洋の絵画に出てきそうな柱。
身だしなみは大丈夫だ、さっき紫野さんに見てもらったところだし。彼女の目はとてもよく僕を見ている。だから今更急ごしらえのように取り繕っても仕方ないのだが、やはり好きな人には少しでもよく思ってもらいたいというのが恋をする者の性だろう。
岩のアーチを潜って奥へ進む。濃紺の絨毯は古いが丁寧に手入れがされており、ふかふかと足が沈む。決して狭いとは言えないフロアには珊瑚のような柱が四隅で天井近くまで伸びている。青みを帯びた、海の底に誘われたような空間。まるで神殿のようなその場所の大きな水槽に、彼女は住んでいる。
「あらお久しぶり、かしら」
水のように耳に馴染む音がした。丁寧に磨き上げられた硝子の中。敷き詰められた珊瑚に手を伸ばしながら、彼女が涼しげな声を発したのだった。身体中の細胞の温度が、瞬く間に上昇する。長年焦がれている癖に、彼女の声に慣れることは出来そうにない。細く伸びたうっすらと黄色の明かりが、彼女の銀糸の髪を眩く映し出している。
ここに入った瞬間、僕はいつも思う。彼女は海底の姫のようだと。
「先々週、また来るって言ったでしょ」
ガラスの周りを取り巻くように備え付けられているスツールに僕は腰を掛けた。掛けるのは結局いつも同じ場所だ。水の中でふわふわと長い彼女の髪が扇状に広がっている。そのままで彼女は心底可笑しそうな声を上げる。
「貴方の言うことが本当か嘘かなんて私にわかるはずないじゃない」
きゃらきゃらとまた彼女は笑って、くるりと水の中を一周した。
「そうかな? 君には何でもお見通しなんじゃない、ミア」
「その気になればそうかも。でも私、子供の戯れは信じないことにしているもの」
くすくす笑いながら彼女はドーム状の筒の中をするりと抜ける。ミアの曇り空を映したような、雨の一歩手前のような色の髪がゆらりと揺れる。桜の尾鰭が目の端を瞬く間に通り過ぎる。ミアの泳ぎはすごく早かったり、とろとろと漂っているだけのようであったり一貫性がない。機嫌の悪い時は僕の前に顔も出さずに隅っこの方に潜んでたり、動体視力が追いつく間もない速さで縦横無尽に彼女だけの海の中を泳ぎ続けていることもある。つまりは彼女の気分次第なのだった。まあ、最初は見られることすら嫌がられていたので、僕は現状に十分満足しているけれど。
抜けるような肌の上を流れる銀色は、空が雪原に触れたようだ。その様は何度見ても溜め息が出るほど美しく、僕はぼうと見惚れることしか出来ない。幼い頃から、ずっと。ずっと。
ミアは大きな水槽をゆったりと泳ぐ。まるで散歩でもするようにのんびりと。そしてまた僕の前に舞い戻ってくると、陸に上がってあたたかな琥珀色の大きな目で僕を見た。今日は随分とご機嫌らしい。陸と言っても砂を模した薄いクリーム色をしたプラスチックの床で、なにも童話の人魚姫のように本物の砂が撒いてあるわけではない。
そんな砂浜もどきの上に慣れた要領で身軽に腰を掛けた彼女は、僕の目の前でゆっくりと尾の鱗を撫でた。つるりとした床はミアの耀く鱗一つ一つを傷つけることがないように、丁寧に磨かれている。僕はミアの尾を見るたびに、人魚の鱗を欲しいと思う人間の気持ちを理解し難く思う。手を伸ばすことさえ躊躇ってしまうほどの美しさを、自分だけのものにしてしまおうなんて、恐れ多い。そして何よりこわい気がするから。うっすらと淡い虹色を跳ね返す小さなその一つでさえも、自分のものにしてしまうと考えるとぞわりとどこかが寒くなる。
僕がそんなことを思っているとも知らない彼女は僕が自分の手を、足を振るように、軽く尾を振る。それから彼女はハリボテの砂浜にぽつりと置かれている貝殻を手に取った。映画のセットなんがでよくありそうな、縦長の渦巻いた貝殻だ。以前訪れた時には無かったものだった。
「それ、どうしたの?」
僕は彼女の手元にある貝の経路を尋ねてみる。誰が置いたのか大体わかっていたので、答え合わせのための質問だった。
「今朝、紫野がくれたのよ。私が退屈してたから」
誰かさんが来ないせいでね。ミアはそう付け加えると頬を膨らませて僕を睨む。透き通った飴玉みたいな琥珀色の瞳。
「ごめんってば。試験が大詰めだったんだよ」
予想通りの答えに安堵しながら、僕は彼女に精一杯の謝罪が伝わるように言う。本当は僕だって会いたかった。試験なんてくだらないもの投げ出して、一日中君とお喋りをしていたかった。まあそんなことをすぐに口に出せるほど、キザにはなれなかったけど。
「わかってるわよ。人間は窮屈ね」
僕の謝罪は上手く伝わったのか、ミアはふんと鼻を鳴らしてそれ以上なにも言わなかった。そしてまた、手にした貝殻を振ってみたり、眺めてみたりする。貝殻は彼女の指先と同化してしまいそうに、真っ白だった。彼女と同じ世界線にある貝殻。ミアは貝殻にそっと耳を近づけると、眉を下げてへにゃりと笑った。
「同じ海の音がするわ」
「同じ海?」
明らかにいつもより柔らかい表情をして、彼女は内緒話をするようにそっと囁いた。
「これね、私が昔いた海にあったものなんですって」
「ミアの、故郷か」
「ええ。いいでしょう?」
ミアはふっくらと薔薇色に染まった頬を、貝殻に押し付ける。ミアに故郷があるのは知っていた。野生の人魚なんて、そもそも人魚が住む海なんて聞いたことが無かったけれど、僕は彼女の言葉を全面的に信じることにしている。
ミアの話ではこうだった。そこは人魚がいて、数は少ないけれど人間もいてすごく広い海の入り口があるのだと。彼女の話を聞いたのは随分と前だったけど、僕にとってそれはどんな御伽噺よりも魅力的だったのでよく覚えている。緑の匂いが肺を満たして、つやつやした果物が年中たくさんなって、絶え間ない波の音や陽気な住人たちの歌声があちらこちらで聞こえる小さな町。ミアの故郷はそんな海辺の町だったのだと。きっと素敵な所なんだろうねと、その時の僕はそう言葉を紡ぐのが精一杯だった。目の前のミアが遠い人のような気がして。懐かしそうに目を細める彼女の表情は、僕が目にしたことのないものだった。穏やかで、きらきらした笑みだったから。
あの時と同じ笑みをして飽きずに貝殻を耳に押し当てる彼女を見つめながら、波の音を思い出してみる。あの、ざらざらとした音。けれど不快感のない、遠くなったり近くなったりする、あの音を。ミアの町の海は僕の知っている波と同じ音で揺れるのだろうか。
「貴方にも聞かせてあげられたらよかったのに」
きゅっと両手で貝殻を抱えたミアは、すいっと僕らの隔たりまで泳いできて硝子に貝殻を押し当てる。
「ね、聞こえる?」
耳を澄ませる。しかし、僕の耳に届いたのは微かな空調の音だけだった。
「聞こえないな」
はあ、と大袈裟にミアは溜め息を吐いて貝殻を投げる。ポチャンと音を立てて、貝殻はミアの足元にあっという間に沈んでいった。
「お行儀が悪いよ、ミア。大事にしてたんじゃないの?」
ミアは貝殻の沈んだ方向をちらりと見て、それからぶんぶんと首を横に振った。
「あとで拾うわ。いいのよ、もう私のものなんだから」
眉間に皺を寄せた彼女は、怒ったような悲しいような複雑な表情をした。硝子に添えられた手のひらはいつのまにかぎゅっと指が折りたたまれていた。
「ねえミア」
「なによ」
ぶすっとした声はわかりやすく元気がない。僕には彼女の気持ちがきっと半分もわかっていないだろうけど。
「僕も聞きたかったな、ミアの住んでた海の音」
本心からの言葉を口にして、丸めた両手にそっと自分の手のひらを重ねる。また、空調の音だけが僅かに僕らの間に落ちる。
貝殻から海の音がするというのは嘘なんだよと事実を今の彼女に言うのは憚られた。僕よりもうんと長生きのくせに、無邪気な子供のように緩む頬が愛おしかったから。彼女にとって美しくて大事な嘘。それを壊してしまうべきではないことぐらい、僕にでもわかった。だってそれはただの事実でしかない。
「ねえ、透」
先に口を開いたのはミアだった。
「どうしたの?」
僕は彼女の言葉を慎重に促す。出来るだけ多くの選択肢の中から彼女を傷つけない言葉を選んだら、当たり障りのない言葉になってしまった。
「もしもの話をしてもいい?」
「いいよ」
少しだけいつものミアの語気が戻っていたので、僕は嬉しくなる。すぐに返事をした。
ミアは僕がそう答えることを知っていたのだろう。口元を緩めて、空気に溶けてしまいそうな声を紡ぐ。
「もしもね、私がまだ海にいたとするでしょう?」
「なるほどね」
彼女は少しずつ言葉を続ける。まるで答え合わせをするように。
「そうしたら、私はこの水族館にいなかったってことにならない?」
「なるね」
僕は肯定を返す。
「つまり、もし私がまだ海にいたら貴方に会うこともなかったでしょうね」
「それはそうだね。僕らはここで出会ったんだから」
もう、十数年も前の季節を思い出す。あの日の彼女は退屈そうに水の中に沈んで、瞼を閉じていた。両手をいっぱい広げてもとても届かないガラス、見向きもしない檻の中の彼女。細く水に差し込んだ光に照らされた横顔が、ただただ綺麗で。夢中になった僕は不機嫌な彼女の声に諌められるまで、べったりとガラスに張り付いていた。
「ねえ透、あの日貴方に会えた日。私運命が変わった気がしたのよ」
ミアは丸めていた指先を解いて、僕の手のひらに重ねる。伏せていた睫毛がふわりと持ち上がって、優しく煌めく彼女の大きな瞳を縁取った。
「透」
「どうしたの」
「もしも、私がここから逃げ出したいって言ったらどうする?」
それはひどく不思議な声音だった。試しているような、揶揄っているような。それでいて怯えているような、そんな。
「今日のミアは質問ばかりだね」
ゆっくりと言葉を乗せる。ミアの眼差しは痛いほど真っ直ぐに僕の心臓に刺さる。
「透」
催促するような、焦れた声が耳を打つ。僕は彼女の眼差しを受け止めながら、細胞から溢れ出る心を言葉に造り変える。
「駄目だって言うよ、だってミアがここから出たら命の危険があるかもしれない。僕は頭が良いけど、人魚のことには詳しくないし」
こつん、とガラスを手の甲で打つ。ミアは僕の回答に眉を下げて口元を引き結んだ。つまんない男ね。そう言われる心積りは出来ていたのに、棘のある言葉は降ってこなかった。
「だから」
彼女がどんな言葉を求めているのか、今の僕ならわかる気がした。きっと出会った頃には伝えられない答えだった。そうだ。あの時の彼女を思い出す。僕はあの時、彼女に呼ばれた気がした。鋭い眼差しの向こうで揺れる、同じぐらいの歳の女の子を見た気がしたんだ。あの時抱いた気持ちは何一つ変わっていない。ミアは美しくて気高くて。親しくなって知った我儘な一面や、子供っぽい感情さえ眩しくて。君は宝物みたいな女の子だ。
僕は用意していた続きを紡ぐ。吸い込んだ空気がうまく飲めなくなりそうだった。早鐘のように打つ心臓が邪魔だった。指先を握りしめる。君が、ミアがそう言ったら。
「だからもし君がここから逃げ出したいって言うのなら。ミアが逃げ出すよりも早く僕がちゃんと攫ってみせるよ」
はっと息を呑む音がした。綺麗な琥珀色の瞳孔が、縦長に大きく開いている。伝わったかはわからなかった。また外の世界を見てみたい。そんなささやかな願いを夢見る、彼女の心の近くにいたくて。ただそれだけの一心で。
「ふふ、なにそれ。馬鹿みたい」
そして、次の瞬間彼女は笑った。縦長の鋭い瞳孔は一瞬ですっかり収められていて、銀色の睫毛は柔らかい曲線を象っていた。
「僕の答えは気に入った?」
彼女の返事がわかってるくせに、尋ねる僕は傲慢だろうか。
「うん、とても」
しかしミアは素直な返事をする。これはとても珍しいことだった。そればかりではなく、ミアは頬を緩めて目尻を下げる。どうやら僕の回答が余程お気に召したようだった。
「僕がミアを攫ったら、きっと紫野さんは怒るだろうな」
僕はここの支配人の名前を挙げる。物腰が柔らかく丁寧な彼が怒る姿は目にしたことがなかったけれど。紫野さんは彼女をとても大事に思っている。それは幼い頃から見ていた僕だから、断言できた。紫野さんの愛情はこの水白水族館の生き物全てに注がれている。まあ、本当のことを言ってしまうとミアに対してだけはちょっと悔しかったりもするんだけど。
「紫野はケチだものね」
変な言葉だけ妙によく知っている彼女は、くすくすと自分の言葉にまた笑った。貴重な生き物を逃してしまったってあたふたするんだわと。
「ミア」
「…………」
「ここはお客さんも少ないから仕方がないよ。紫野さんは君たちを守るために、頑張っているんだと思うよ」
やんわりと否定する僕に、ミアは頬を膨らませる。さっきまでの穏やかさはたちまち形を潜めてしまう。
「あの男が私たちを守ってるですって? 私をこんな狭い水の中に放り込んでいるのも自分なのに?」
びたん、と尾を水の中に打ちつけて彼女は呆れたように僕を見遣った。細かい水飛沫が跳ねる。僕はその動作を見てついくすくす笑ってしまう。ミアは苛々してくると尾をびたんびたんと打ち付ける。僕の顔を見て、また目が釣り上がるミアを身振り手振りで宥めた。彼女に触れられていたら、僕はどんな風に宥めるんだろうか。
尾を打ち付ける音が止んだ頃、僕はそっと問うてみる。
「ミアは紫野さんのこと、本当に嫌いなの?」
彼女が紫野さんの話をする時は大抵不機嫌だ。それは僕も知っていたけれど。でも、本当の本当に嫌いではないんじゃないかと思う。彼女が言う〝あの男〟は紫野さんしか居ないし、そこに本当の憎さは籠っていないように思うから。
「…………わかってるわよ。あの男が本当の悪じゃないことぐらい」
機嫌の悪い声は依然として保ったまま、ミアはぼそりと呟く。少し決まり悪そうだ。
「ミアはいい子だね」
頭を撫でたくなる衝動を指先に乗せ、ガラスを撫でた。
「子供のくせに、私のことを子供扱いするなんて生意気よ」
彼女はお行儀悪くまた尾をびたん、と強く打ちつける。あまり強く打つと、美しい鱗が落ちそうではらはらする。
「うん、ごめんね」
僕は彼女の額に自分の額を重ねて詫びた。ミアがぐっと文句を飲み込んだ音が聞こえた気がした。
「最近の人間って紫野みたいな性悪か、貴方みたいなぼんやりしかいないのかしら」
はあと吐かれた溜め息は言葉の意味を丸くしてゆく。
「どうだろう。僕にはわからないな」
友達には能面って言われるし。
「そうだ!」
はっとした顔でミアは目を輝かせる。
「あなた、今度ここへお友達を連れていらっしゃいよ!」
ガラス越しに白い頬が、ゆっくり近づく。また小さく心臓がとくんと跳ねた。
「ミアはさ」
「なあに」
腹の奥が微かにざわめく。薄明かりの中の照明が、水に透けてゆらゆら揺れる。
「僕より魅力的で、君のことも理解して大好きな人が現れても僕を選んでくれる?」
自分でもわかるぐらいにぐらぐらの声だった。こつんと額を硝子につける。一枚隔てた向こう側の彼女に届かない熱が今、どうしようもなく悔しい。
「さあ、それはどうかしらね」
彼女はそれだけ言って悪戯っぽく笑うと、とぽんと水に沈みこんだ。水の中で愉しそうに笑ったミアは、きゃらきゃらと可愛らしい声を立てながら、僕の視界の端から端までを行ったり来たりする。蛍光灯の光を受けた鱗がきらきらと輝く。何度見てもその姿は美しく、僕は溜息を吐きながらその姿を両目に焼き付ける。
「ねえ、透」
「なに」
「一度だけでいいから、私貴方と紫野以外の人間と、たくさんお喋りしてみたいわ」
水面に顔を半分だけ覗かせてミアは目を輝かせる。さっきの話の続きだろう。期待一杯の眼差しは眩しくて、僕は苦笑してしまった。
「そうしたいのは山々なんだけど」
「なによ」
僕が意見したことが気に食わないらしい彼女は、水面から目だけを出した状態のままで、僕の言葉を促す。
「ミアがこんなに可愛いのを知られてしまうのは、もったいないなと思うんだって言ったら怒る……?」
喉からは情けない、ぼそぼそと呟くような声しか出なかった。
「……貴方ってお馬鹿さんなのね」
僕の言葉にどう思ったのか彼女はそのまま黙ってしまった。ちゃぽんとミアの顔が再び水に沈む。僕の目の前で一回転して、水槽の端から端までをゆっくり舞うように尾鰭を跳ねさせる。僕を横切っていく頬が熟れたばかりの林檎のようにふわりと色付いていた。それが僕の気のせいではないならば。
口元に微笑みを宿して仰向けに泳ぐ姿は、まるで女神のようだった。銀糸の柔らかく広がる髪、白く水面の光を映す肌、淡青の宝石を一つ一つ薄く削ったような丸みを帯びた鱗、それらが犇いた先には桃色の尾鰭。人間の足とはまるで違う。しっかりと筋肉が付いているであろう尾は柔らかくしなって水を掻き分ける。
僕は彼女の尾に特に惹かれていた。ミアの尾は芸術品のようでいて、けれど決して尾だけでは成立しないものだった。人魚の構造は少し本を読んだけれど、ほとんどわからなった。でもこれだけはわかる。彼女の、ミアの下半身に付いていることで、それはやっと意味を成し得るのだということは。
調べ物の合間に、人魚の肉を食すと不老不死になるという話を目にした。きっと誰もが知っている話だろう。けれどこんなにも美しい生き物を目の当たりにして、それでも手に入れたいと思う人間は本当にいるのだろうか。
彼女の自由に水を掻くその尾鰭、口元に笑みを浮かべたその表情を見る度に僕は思う。
童話の人魚姫は尾を失って二本の足を手に入れた後、はたして本当に幸せだったのかと。広い海を駆け回る鮮やかな力強い尾を失っても、二度と海を駆けることが出来なくとも良かったのだろうかと。僕が童話の登場人物なら。ミアが童話の中の人魚であるならば。好きな人が魔女に願って、こんなに美しいものを自ら失くしてしまうくらいならば。きっと自分が彼女と共に泳げるよう、彼女と同じ尾を授けてもらえるよう願うだろう。
たとえ御伽噺と同じように声を失ったとしても。彼女の、ミアの可愛らしい声を、尾を失くしてしまうよりずっといい。
そこまで考えて、僕は自分が馬鹿馬鹿しい妄想をしていたことに気がついた。現実は僕とミアは硝子を隔てた陸と海。狭い海で自由気ままに浮遊する彼女は、人魚だ。
「ねえ、透」
コンコンとミアはガラスをノックする。視線を戻すと、彼女は僕の顔を指差してにやりと笑う。
「貴方変な顔ばかりしてるわよ。どうせまたつまらないことを考えていたんでしょう」
「そうだね、そんなところかな」
僕の返事に気を良くしてミアはにこにこと笑う。
「貴方はお馬鹿さんなんだから、余計なことを考えない方がいいわ」
なんだか子供扱いされているようで少しむっとした。僕はそっぽを向く。そんな僕を見つめてミアはけらけら声を上げる。
「そんなことより、私の話を聞いてちょうだい」
「どういう話?」
彼女のきらきらした声で言われたら、そっぽ向いてなどいられないのが僕の弱い所だ。
「さっきの続きの話よ。いつか、いつかね。私を海に連れて行ってほしいの」
遠くを見たミアの瞳は相変わらず真っ直ぐでいて、少しだけ翳っているようにも見えた。
「ミアを海に?」
「そう。私がいた、とびきり綺麗な海よ」
「ミアの住んでいた海か。まずは場所から調べないと」
僕は頭の中に地図を広げる。うん、これからは地理の勉強もしなくてはならない。
「だからいつかね、いつかの話よ。その時が来たら、透。私と海に行ってほしいわ」
ミアは長い髪をかき上げて、目を伏せた。瞼に光が落ちる。口にしたくせにいつものような勢いの無い約束だった。
「じゃあ僕はもうその時まで海は取っておこうかな」
僕は子供の頃に行ったきりの、さざめきを思い出す。そして波の音はそのままに、彼女の故郷の海に想いを馳せる。見たこともない海。ミアの昔聞いたという波の音。その海はどんな色で、どんな音をしているのだろう。
「行こう、きっと」
「貴方が約束を忘れてなければね」
意地の悪い笑いがきらきらと二人の空間に落ちた。
僕は口元を緩めて、彼女の琥珀色の瞳を覗く。そこには星屑のような光が瞬いていた。
ごうごうと空調だけが響くフロアに、コツリと革靴の柔らかな音が響く。やがて姿を現したスーツ姿の男は床の絨毯をゆっくり踏んで進む。
「彼はお帰りですか」
高梨が座っていた場所へ腰を掛けながら、彼は水の中で目を閉じた彼女に問う。
「とっくにね」
「そうですか」
紫野は閉館後毎日ここを訪れる。人魚はそれが毎回煩わしくて仕方がない。毎度自分が見せ物だと位置付けられているような気がして。
「性悪」
「私がですか。何かしてしまいましたかね」
もちろん彼にそんなつもりがないことはわかっている。彼女はそういう意味では、人の気持ちに特別聡かった。けれど面と向かって文句を言っても、気にも留めないこの男を見ると苛々してしまう。
彼が私たちを守っていると高梨は言った。人魚はぎゅっと唇を噛む。あの日確かに、命が尽きるその直前にこの大きな手で彼女を引き上げたのは紫野だった。それは事実である。感謝だってしている。絶対口にはしてやらないが、ちゃんと頭では理解しているのだ。
「お前はわかっているのに尋ねるから性悪だと言うのよ」
ミアはぎりぎりと歯を鳴らす。恩があるのと、馬が合う、合わないというのはまた別の問題だ。この紳士の皮を被った飄々とした男が彼女は嫌いである。
「人魚様の考えていることなんて私には崇高すぎて分かりませんがね」
そう言って紫野はふ、と息を吐く。考えていることのほとんどが素直に顔に出る人魚はなかなかに珍しい。
「本当によく喋る口だこと ここが海なら沈めてやりたいわ」
「そんなに機嫌を悪くしないでください」
紫野は全く悪びれる様子もなく、にこりと笑う。人魚が胡散臭いと罵る笑みで。
「ねえ、紫野」
微かに聞こえる空調の音だけが、しばらく続いた後だった。人魚は静かに言葉を紡ぐ。
「……人間って何年生きるものなのかしら」
紫野は少し首元のタイを緩めて、また息を吐いた。
「…………」
「透は、あと何回私を見られるかしら」
焦ったさとも苛立ちとも困惑ともつかない声で、彼女は紫野の返事を促す。痛いほどの強い視線が紫野を射る。しかし紫野はただ視線を自分の目に収めるだけで、かぶりを振った。
「どうでしょう。こればかりは個人差がありますからね」
「……そうね。そういう生き物だったわね、人間は」
人魚は口元を引き結んで、瞼を伏せる。
「彼が人間でなければいいんじゃないですか?」
ぱっと人魚は顔を上げる。紫野の口元がゆっくり弧を描く。彼は目の前の人魚の瞳孔が、みるみる膨らんでゆくのを眺めた。
「彼を人間でなくしてしまえばいいのではないですか」
喉の奥でくつくつと笑う声が落ちる。真夜中の稲妻のような、紫野の瞳がぎらぎらと揺れる。
「…………だめよ」
低い音が人魚の口から漏れる。彼女の瞳孔はするすると小さく萎んでしまった。震える声で人魚は小さく呟く。
「透はだめ。透だけは、だめなの」
「……そうですか」
紫野は短く返事をした。だめならしかたありませんねと。もうさほど興味のない、いつもの愛想だけを乗せた笑みを見せる。
「お前は本当に性格が悪いわね」
とぷんと水に沈む寸前、人魚は唇をぎゅっと噛む。二者の間にそれ以上の会話はなかった。
紫野は体温の馴染んだスツールを立った。水に漂う銀色の髪を横切って、また来た道を引き返す。電気のパネルを押すのは忘れない。何しろここの設備は、この建物の中でもとりわけ電気を食うのだから。長い足を廊下に伸ばし、彼はああと首元に手を添える。
「人魚姫は幸せになれない運命なのでしょうか」
慣れた手付きでネクタイを締め直した彼は一人ごちて、手鏡をポケットから出す。
「まあ、私には関係のないことですね」
そうして一人納得すると、さっとタイを直し、髪を整え鏡をしまった。
暗闇に染まった館内を紫野は悠々と進む。瞼に刺さって抜けない痛みは多分気のせいだろうと思った。さあ早く仕事をして、目薬でも差さなければ。再び頭の中に犇くスケジュールを立て直す。彼の一日はまだ終われないのだった。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


さよなら青薔薇さん
いご
ライト文芸
科学部部長の佐倉蒼、通称青薔薇さん。彼女が一人で活動している科学部に、ある日、サッカー部の元エース中村拓実がやってくる。
彼は最後の大会を前に、怪我でサッカーを諦めていた。
孤独の青薔薇さんと絶望の元エース、その二人が過ごす高校最後の日々。
その中で彼は、彼女はなにを感じ、なにを思うのか。
「夢叶う」未来に向かっていく二人のお話。
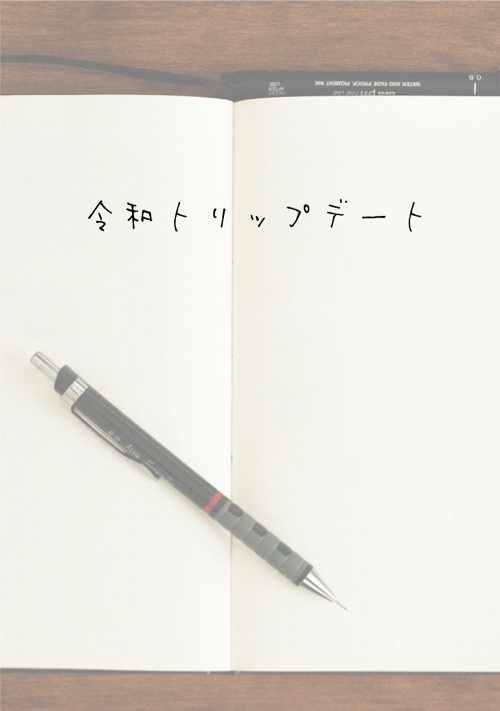
令和トリップデート
永瀬 史乃
ライト文芸
——失恋した夏の日、颯爽と現れた不思議な美青年とデートをすることに……?
意中の彼との三回目のデートをドタキャンされた咲。しつこいナンパに辟易していたところを、美青年・惣に助けられて一日限りのデートを楽しむことに。
惣とは気が合う上に、なぜか咲の名前や歳も知っていて……
カクヨム2020夏物語(SF・ミステリー小説部門)応募中。
アルファポリス版では惣サイドの物語も投稿予定。
表紙は「かんたん表紙メーカー」様HPにて作成いたしました。

宇宙に恋する夏休み
桜井 うどん
ライト文芸
大人の生活に疲れたみさきは、街の片隅でポストカードを売る奇妙な女の子、日向に出会う。
最初は日向の無邪気さに心のざわめき、居心地の悪さを覚えていたみさきだが、日向のストレートな好意に、いつしか心を開いていく。
二人を繋ぐのは夏の空。
ライト文芸賞に応募しています。

夫を愛することはやめました。
杉本凪咲
恋愛
私はただ夫に好かれたかった。毎日多くの時間をかけて丹念に化粧を施し、豊富な教養も身につけた。しかし夫は私を愛することはなく、別の女性へと愛を向けた。夫と彼女の不倫現場を目撃した時、私は強いショックを受けて、自分が隣国の王女であった時の記憶が蘇る。それを知った夫は手のひらを返したように愛を囁くが、もう既に彼への愛は尽きていた。

選ばれたのは美人の親友
杉本凪咲
恋愛
侯爵令息ルドガーの妻となったエルは、良き妻になろうと奮闘していた。しかし突然にルドガーはエルに離婚を宣言し、あろうことかエルの親友であるレベッカと関係を持った。悔しさと怒りで泣き叫ぶエルだが、最後には離婚を決意して縁を切る。程なくして、そんな彼女に新しい縁談が舞い込んできたが、縁を切ったはずのレベッカが現れる。

劇場の紫陽花
茶野森かのこ
ライト文芸
三十路を過ぎ、役者の夢を諦めた佳世の前に現れた謎の黒猫。
劇団員時代の憧れの先輩、巽に化けた黒猫のミカは、佳世の口ずさむ歌が好きだから、もう一度、あの頃のように歌ってほしいからと、半ば強制的に佳世を夢への道へ連れ戻そうとする。
ミカと始まった共同生活、ミカの本当に思うところ、ミカが佳世を通して見ていたもの。
佳世はミカと出会った事で、もう一度、夢へ顔を上げる。そんなお話です。
現代ファンタジーで、少し恋愛要素もあります。
★過去に書いたお話を修正しました。

金サン!
桃青
ライト文芸
占い師サエの仕事の相棒、美猫の金サンが、ある日突然人間の姿になりました。人間の姿の猫である金サンによって引き起こされる、ささやかな騒動と、サエの占いを巡る真理探究の話でもあります。ライトな明るさのある話を目指しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















