1 / 1
本編
しおりを挟む
1・ある初夏の昼下がり、強い風が吹いて周りに生えている木々たちが大きく揺れた。その中でも一際大きな木、「ルナの樹」も揺れる。さわさわと風で葉がこすれ合う音がする。その音がなんとも心地いい。木陰に寝転がったライオは、その風の気持ちよさに思わず笑った。ルナの樹の周りには高い草がびっしりと生えていて、それが優しく顔をくすぐる。ライオは楽しくなってますます笑った。ここはこの辺りに住む民たちから、「ルナの丘」と呼ばれている。ライオはこの場所が幼いころから大好きだった。仕事のない日や、空いた時間はいつもここにいるくらいだ。ここはライオにとって、とても大切な場所だ。
「どうしたよ、親父。今日は機嫌いいな」
ライオは笑いながら頭上にそびえたつルナの樹に向かって語り掛けた。ライオにとってルナの樹は、亡くなった父親のような存在だ。まだライオが幼かったころ、父親と一緒にこのルナの樹の下で追いかけっこをして遊んだり、二人で木陰に寝転びながらいろいろな話をしたことをライオは今でもはっきり思い出せる。当時、父親は騎士として城に勤めており、ある日殉職した。そのあっけない死にライオはとても傷付いた。父親は名誉ある死だったと、他の騎士らから何度も言われたが、小さかったライオにそんな事情が納得できるわけもなく、毎日城の近くにある騎士の詰め所に喧嘩を売りに行った。ライオは成長するにつれて騎士という職業がどんなものか理解していった。その間に自分が知っている騎士が亡くなっていくことも何度か経験した。そして、いつの間にか自分も父親のような優しくて強い騎士になりたいと願うようになっていた。愛国心が特別あったわけじゃない。父親の見ていた世界を自分も見てみたかっただけだ。ライオは今、騎士隊長として騎士団をまとめ上げている。自分は絶対に任務で死なない、ライオは自分にそう誓っている。今までも無茶な現場に遭遇したことは何度もある。だが、なんとか乗り越えてきた。その経験がライオを強くしてくれているが、事あるごとに死という現実を突きつけられて、年を経るごとに死をますます身近に感じるようにもなってきていた。ライオはひと眠りしようと心地よい風の中で目を閉じた。今日は久しぶりの非番だ。風でライオの短い黒い髪がなびく。明日から隣国との合同訓練がある。今日は出来る限りゆっくりしようと思っていた。
「・・・う!・・・ちょう!隊長!」」
「う?」
耳元で名前を叫ばれてライオが目を開けると、部下の騎士が真っ青な顔をして、ライオの体を揺さぶっていた。なにかあったのだとライオは悟る。起き上がってすぐさま腰に携えた剣に触った。手慣れた感触にライオはホッとする。今までぐっすり眠っていたおかげで、体調も万全だ。
「どうした?」
「は、国王からライオ隊長にお話があると」
ライオは嫌な予感を覚えた。大抵こういう時の予感は的中する。だが行かないわけにはいかない。相手は国王だ。ライオは立ち上がった。体をぐいと伸ばす。部下の騎士はそんなライオを静かに待っていた。
「分かった。すぐに行く。お前は詰め所で待機しろ」
「はっ」
彼が走っていくのを確認する。ライオも城に向かって駆け出した。
2・ライオの住む国、ルナリア国は世界で二番目に大きな大陸に君臨している。ここは豊かな自然に恵まれた国だ。近隣諸国とは、お互いに同盟を結び、今まで特別大きな争いもなくうまくやっている。この国は、国王が政治を取り仕きっていた。だが現国王はもう高齢だ。国民からもそれに対して不安の声があがっている。本来であれば、もう世代交代していてもおかしくない。ライオはふと遠くを見た。向こうに真っ白な城が見える。美しいあの城はこの国の誇りだ。城には三角の尖塔が左右対称に並び、天へ向かってそびえたっている。そして、城の周りにはぐるりと水路があった。それは地下の水脈に繋がっていると聞いたことがある。その水路は町中を駆け巡っており、民たちの生活水として使われている。もちろん煮沸すれば飲料水としても使える。豊かな自然を持つルナリアだからこそ出来ることだ。ルナリアの民であれば他国の人間に必ず一度はする自慢である。ライオが城内に入ると兵士たちがこぞって敬礼してくる。
「ライオ隊長、非番にすみません」
音もなくそっとライオの隣を歩いてきたのは、副隊長であるアレイだった。アレイは一言で言うと、女性と間違えてしまうほど綺麗な人だった。肩まである美しい栗色の髪の毛。細い体躯。ライオとはまるで真逆である。だが彼の実力は本物だ。ライオは彼に全幅の信頼を寄せている。
「いや、気にするな。なにがあった?」
ライオの問いにアレイは首を横に振った。アレイにも見当がつかないとなると、ますますただ事ではないようだ。ライオは改めて心の準備をした。間もなく国王のいるベッドルームに到着する。国王は高齢もあってか、ベッドの上からほとんど動けない状態にあった。食事から始まり、下の世話まですべて侍女に任せきりである。廊下を歩いていくと、突き当りに大きな両開きの扉が見える。そばには兵士が二人、槍を持って立っている。ライオの姿を見た瞬間、彼らは背筋を伸ばして敬礼してきた。当然、ライオは彼らに声を掛ける。
「ご苦労。国王陛下はどうされている?」
「はっ、ライオ様にお話があると」
「俺に?」
「はい」
やはり誰にも話の内容が分からないらしい。ここでこうしていても何も始まらない。ライオは思い切って扉をノックした。自分が来たことを大きな声で告げる。すると向こうからしわがれた声で返事が返って来た。
「入れ、ライオ」
「失礼致します」
ライオは部屋に入り、ベッドの前で跪く。侍女によって、するすると天蓋から垂れ下がっていた布が払われる。そこから現れたのは疲れ切った老人の姿だった。彼からはかつての蛮勇さは感じられない。国王はもう限界だと、誰もが感じている。それはライオの意見も変わらない。ライオは一人考えていた。確か国王には、一人子どもがいたはずだ。だが、誰もその子供の姿を見たことがない。見たことがないものを当てにするわけにもいかない。女王もまた、十数年ほど前から遠くの地方へ病気の療養に行っている。これからこの国はどうなるのかとライオの元に訴えかけて来る民もいる。
「頭を上げろ、ライオ。そなた、今日は非番だったとな」
国王は人と喋るのが好きな人だった。侍女とも親しげに話している場面をよく見かける。ライオは頭を上げて国王を見つめた。
「はい。ですが騎士たるもの、国を脅かすものはいついかなる時も全て排除致します」
国王はライオの言葉に声を上げて笑った。そしてこちらを射抜くような鋭い視線を飛ばしてくる。ライオは知らず知らずのうちに後ろへ退いていた。まだ国王には現役時と変わらない威厳と誇りがあるのだとライオは本能で悟ったのだ。
「ライオ、そなたに頼みがある。サーシャ、ワシの息子のことだ」
「えぇ?」
ライオは天がひっくり返ったような驚きを感じた。国王に子供がいるというのは一種の都市伝説的なものだろうと思っていた。だが、国王は冗談を言っているわけではないらしい。彼は白くなった顎髭を撫でながら言う。
「息子は今年で十九になる。だがこもりきりで世間をまったく知らない。ライオ、息子のサーシャを国王にする準備を始めよ」
ライオはしばらく何も返せなかった。国王がそんなライオを見ておかしそうに笑う。
「そなたはいい。素直な男だ。だから信頼するに値する」
「は・・ありがたきお言葉」
ライオは戸惑いを感じながらも頭を下げた。
「ライオ隊長!」
部屋から出てきたライオをアレイは部屋の外でずっと待っていてくれたらしい。普段のアレイなら、自分の仕事に戻っていただろう。だが、彼もまた今回の呼び出しに不穏を感じていたようだ。先程の表情がそれを物語っていた。
「アレイ、ちょっといいか」
ライオは小声で国王の子供が実際にいることを打ち明けた。アレイはそれに対して頷いている。どうやら彼はそれに勘付いていたらしい。豪快で兄貴肌のライオに比べて、アレイには優しい母親のような部分があった。
ライオには言えないことでもアレイになら言えるという騎士や兵士は多数いる。二人が揃ってこそ、ルナリア騎士団は初めて成立する。
「隊長はこれからどうされるのですか?」
アレイの問いにライオはため息をついた。だが自分がやるしか道はないようだ。気は全く乗らないが、それが仕事である。
「とりあえず、そのどこかにいる王子を引きずり出す」
「殿下がいるとしたら城の地下でしょうか。この城には地下牢があると聞いたことがあります。どうも過去に使っていたようですね」
「おいおいおい」
まさか一国の王子を地下牢に入れていたとしたら大事である。アレイはライオに構わず続ける。
「もし彼が地下牢に閉じ込められていたとしたら国の威厳に関わります」
「そうだな。このことは他の皆には黙っていることにしよう」
「隊長、早く殿下を連れ出してきてください」
「分かったよ」
ライオはそのまま地下に繋がる水路へ向かうことにした。水路へは一度、城から出て長い梯子を下りる必要がある。とんだ貧乏くじを引かされた気がするが、これは任務だと割り切る。ライオは早足で城から出た。
3・「あっついな」
城の中は風が通り涼しいが、水路は打って変わって湿気が多い。そのせいかじめじめしてなんとも不快な場所だった。立ち込める水の匂いが、またなんとも言えず、ライオを不機嫌にさせる。ライオは今日非番だったので、騎士の隊服は着ていない。もし隊服であれば更に暑かっただろう。あの服は飾りが多すぎる。ライオは水路を歩いて進む。流れて来る水の音で他の音はすべてかき消されていた。ライオは用心深く辺りを探りながら前へ進んだ。ここに不審な人物がいる可能性もある。油断はしない方がいいだろう。暗がりにだんだん目が慣れて来る。歩いていると、向こうから明かりがちらちらと漏れているのに気が付いた。はじめは錯覚かと思ったが、近付くにつれてそれは確信に変わった。誰かがここにいる。それは間違いない。思わずライオは駆け出していた。おそらくそこにいるのは王子だろう。何故彼がこんな場所にいるのか聞き出さなければならない。ライオは荒く呼吸しながら、大きな地下牢の前に立った。その中には床で寝息を立てている青年がいる。牢とはいえ、鍵はかかっていない。ライオは扉を開けて、牢の中に足を踏み入れた。眠っている小柄な青年が王子のサーシャだろうか。ライオは屈んで彼の様子を窺った。彼は良く眠っている。ライオは彼を観察した。長い腰までの金色の髪の毛、そして人形のような端正な顔立ちをしている。彼がどんな瞳を持っているのかライオは気になった。ライオは王子の肩を優しく揺さぶった。怖がらせてはいけないと思ったのだ。ライオは体も大きく目つきが鋭い。そのため、小さな子供から怖がられることが特に多かった。
「殿下、起きてください」
すうすうと彼は眠っている
「殿下」
「ん・・・」
しばらく声を掛けているとようやく王子に動きがあった。ぱちっと王子の目が開きライオを見る。その瞳は大きく、藍色をしていた。
「誰?」
「・・・私はライオといいます。殿下をお迎えに参りました」
ライオなりに穏やかに言ったつもりだったが、王子は飛び起きて牢の奥に逃げ込んでしまった。ライオは反射的に追いかけようとしてそれを諫める。王子は自分を怖がっている。追いかけたらますます怖がらせるだけだ。それだけは絶対に避けなければいけない。
「殿下、私はあなたに危害を加えません」
「やーだよ。誰が外になんかいくもんか」
「・・・・」
王子の生意気な口調にライオは苛立ちを感じずにはいられなかった。必死にそれを抑えて、ライオは王子に語り掛ける。
「国王陛下があなたをお呼びです」
「父上が?もしかして母上が帰って来たの?」
王子の声音に期待が籠っている。彼はここで母親の帰りを待っていたのだろうか。
ライオは自分が幼かったころのことを思い出した。父親が亡くなったことを受け入れられず、帰ってこない父親の帰りをずっと待ち続けていた自分を。ライオは改めて王子を見つめた。彼の金色の髪が燭台の火を受けてちらちらと輝いている。
「いえ、まだ女王陛下は戻られていません。ですが、あなた様を国民がお待ちなのです」
ライオは彼を諭すように声を掛けた。王子はぺたりとその場に座り込んでしまう。
彼の服は真新しかった。誰かが彼の面倒を見ているのは間違いない。
「なんだ。じゃあここにいる。僕は王子になりたくてなったんじゃないよ」
確かにその通りだ。ライオはしばらく王子とこのような押し問答を繰り返した。だが、毎回するりと上手くかわされてしまう。王子はライオが思っていたより、はるかに賢かった。
「殿下、ここにいてもなにも変わりません。地上で暮らせば楽しいこともあります」
「だから、やだって言ってるだろ」
「殿下」
これ以上は無理だろうかとライオは弱気になった。王子の意志は自分が思っていたよりもはるかに固い。ライオは自分の浅はかさを呪った。もっと簡単に話が進むと思っていたが、甘かった。
「分かりました。私は明日も来ます。殿下、ご自分のこれからのことをよくお考え下さい」
「やーだよ」
どこまでも王子は態度を変えるつもりはないらしい。ライオはすっかり困ってしまった。こんな経験は初めてだ。敵であれば、力づくでどうにかできる。だが相手は自分が守るべきこの国の王族だ。乱暴な手は使えない。ライオはとぼとぼと地下牢を後にした。
4・「え、殿下を連れ出せなかった?」
地下から戻ってきたライオがしょんぼりしながらアレイに伝えると、彼は首を傾げた。
「殿下は牢に閉じ込められていたわけではないんですか?」
王子は確かに地下牢にいた。だが牢には鍵がかかっていたわけでも、王子が鎖で繋がれていたわけでもない。
「では殿下は自らの意思で地下牢にいると?」
アレイはそれに心底驚いているようだ。
「ああ。女王陛下のお帰りを待っているようなんだ」
「それなら地上でも待てるでしょう」
冷静なアレイの言葉にライオはハッとなった。言われてみれば確かにその通りである。自分の思考がそこまで及ばなかったことにライオはため息を吐いた。気持ちが暗くなって視界すら狭まったように感じる。
「やっぱり俺じゃダメなんじゃないか?」
「どうしたんですか、弱気になるなんてあなたらしくもない」
「だって相手は子供だぞ。いや、十九だから成人はしているけど」
ライオがごにょごにょ言っていると、アレイはいよいよ噴き出した。
「失敬。隊長、相手が子供ならどうすればいいか分かっているでしょう?」
アレイはライオを見てもう一度笑った。いつもアレイが子供にどうしていたか、ライオは思い出す。確かアレイはいつも飴玉を持っている。ライオはようやく思いついた。
「そうか、お菓子か!」
「隊長、それだけではまだ足りません。これをどうぞ」
アレイが手渡してきたもの、それは一冊の本だった。ライオはその本のタイトルを見る。
この国、ルナリアに伝わる神話の本のようだった。この国には多数の神々がいたとされる。特に人気なのは慈愛の女神シュナだった。彼女は優しく皆を見守ってくれていると、この国には広く伝わっている。シュナを信仰する者は多い。祭りでも彼女を奉るものがある。ライオも時々、シュナの存在を近くに感じる時がある。不思議な現象なのであまり人には言わないが、幼い頃からなんとなく感じていた。シュナはそれだけ身近な神だ。
「子供にはおとぎ話が必要なんです。きっと辛抱強く待てば、王子も私たちに心を許してくれるはず」
アレイの言葉がいつにも増して心強い。
「ありがとう、アレイ。俺、明日また行ってみる」
アレイがふっと優しく笑った。
「明日、隣国と合同訓練があります。隊長、期待していますよ」
「ああ」
夜、ライオは宿舎にある自分の部屋にいた。
明日の合同訓練の日程を頭に叩き込んでいるのだ。いくら訓練とはいえ、気が抜けたものでは意味がない。戦いは一瞬が命取りとなる場合がある。他国と戦争をする予定はないが、いつどこで何が起きるか分からない。ライオはふと王子の顔を思い出した。自分に彼を次の国王になどできるのだろうか。自分は一介の騎士で、教師ではない。ある程度の教育は受けたが、ライオは成績が良い方ではなかった。ライオはため息をついて寝台に寝そべった。ルナの樹を頭に思い浮かべる。
「親父、俺どうしよう」
弱く呟くと、ふと外から強い風の音がする。木が激しく揺れているのが窓から辛うじて見えた。いつも見える月は雲で隠れている。
ライオは起き上がった。今、王子がどうしているのか無性に気になって来たのだ。このままここで一人モヤモヤ考えているより、王子の様子を見に行こうとライオは思った。アレイのアドバイス通り、買ってきた菓子と先程借りた本を革で出来た肩掛けのバッグに入れる。このバッグは騎士になった時、母親が買ってくれたものだ。とても高級で値段もよかった。このために母親は仕事でもらったわずかな給金から少しずつずっと貯めておいてくれたらしい。家を出る時、母親はライオを誇りに思うと言ってくれた。最近、家に帰っていない。父親の墓参りにも行きたい。ライオはぎゅっと拳を握った。自分は決して一人ではない。アレイや部下もいる。だが王子はどうだろう。あの冷たい地下牢でたった一人だ。ライオは宿舎を出て駆け出していた。
闇の中をライオは手探りで進んでいた。昼間来た水路とはまた様子が違って、なんだか気味が悪い。水がどうどうと流れている。近隣で雨でも降ったのだろうか?水の勢いがいつもより激しい。ライオが歩いていると、そこにちらっと明かりが見えた。ライオはホッとしてその明かりを頼りに前へ進んだ。地下牢に向かうと、王子はちょこんと座って、何かを熱心に見ていた。
「殿下」
ライオが声をかけると王子は慌てたようにそれを隠す。
「まだ僕になにか用なの?」
ライオは気にせず地下牢に入った。王子は当然逃げようとする。ライオは彼の白い手首をそっと掴んだ。
「待ってください、殿下」
王子は顔を上げない。ライオは彼に痛い思いをさせてしまったのかと慌てた。気を付けて腕を掴んだつもりだったが、自分は普通の人より力が強い。急いで王子の腕を確認する。どうやら痣になっている様子もない。ライオはそれにホッとする。
「殿下、痛かったですか?申し訳ありません」
ライオが謝ると王子はようやく顔を上げた。
彼の大きな藍色の瞳から涙がぼろぼろ流れている。ライオはいよいよ困った。自分が彼を泣かせてしまったのだ。この場合、すぐ謝るべきだとライオは判断する。
「殿下、本当に申し訳ありません。その、俺、馬鹿力で」
そうなりたくないのに、つい言い訳がましくなってしまう。ライオが焦りながら次の言葉を探していると、王子は笑った。ぐいと彼は自分の拳で涙を拭う。
「ライオだっけ?なんか君って変なの」
王子が声を上げて笑い出す。その笑顔の無邪気さにライオは見とれてしまった。
「ライオ、僕はここにいなきゃダメなんだ」
王子が力強く言う。その言葉の強さにライオは王子の言葉をすぐには否定できなかった。それでもなんとか言葉を絞り出す。
「殿下、あなたは罪人じゃありません。こんな暗い場所に一人でいるなんて」
ライオの言葉に王子は寂しそうに笑った。
「僕は十分罪人だよ。ね、いいもの持って来てくれたんでしょ?甘いにおいがする」
ライオは紙の包みをバッグから取り出した。
それは甘い樹液を固めたお菓子だ。
「わあ、美味しそう」
「殿下、ここにいなきゃいけない理由を聞いてもいいですか?」
ライオの言葉に王子はまた黙り込んでしまった。
「俺にはお話、したくないのですね」
「うん。きっとライオは幻滅するから」
王子がそう言ってそっと座り込む。ライオも彼の隣に座った。冷たい床だ。少し湿っているのか服がじわりと濡れる。あまり気持ちのいいものじゃない。ライオは王子に菓子の入った包みを渡してやる。王子は早速、菓子を口いっぱいに頬張っていた。彼がそれを噛むと、ばりばりといい音がする。
「美味いー。僕、このお菓子大好き」
ライオはホッとしていた。アレイにおすすめの菓子を聞いておいて正解だった。
「ね、まだ何か持ってるんでしょ?」
ライオはアレイに借りた本をバッグから取り出した。それに王子は目を輝かせる。彼は立ち上がって壁に掛かっていた燭台を持ってきた。火がちらちらと揺れている。
「ね、読んで見せて。僕は字を読めないんだ」
ライオはその言葉に驚いてしまった。王族で字が読めないというのは致命的である。
「殿下はいつからここに?」
「うーん、もう随分経つからね」
王子は首を傾げて考えている。
「確かここに来たのは僕が六つの時だったと記憶している」
ライオはそれにまた驚いてしまった。彼は十年以上ここで暮らしているのだ。姿を見た者がいないことにも納得できた。彼は自らここに来たのかとライオは思う。まだ六歳の小さな男の子がだ。彼に何があったのかライオとしては気になるが、まだそれを聞くのは難しいだろう。
「ね、ライオ。早く本を読んでおくれよ」
ライオは燭台の明かりを頼りに本を音読した。こんなことは初めてで、ライオは途中で何度もつっかえた。だが、王子は気にせずライオに先を催促する。話の展開が変わる度に王子は目を輝かせた。そんな王子の様子が可愛らしくて、ライオも自然と笑みがこぼれた。
「ね、ライオ。明日も来ておくれよ」
「明日は隣国との合同訓練があるのです。それを見学に来るというのは?」
ライオは王子が外に出て来てくれるのではと淡い期待を抱いて彼に尋ねた。だが、王子は首を横に振るだけだった。
5・次の日の早朝、ライオはルナリア騎士団を率いて隣国との境にある砦にやって来ていた。隣国とは陸続きで繋がっている。
ここは標高も高く、夏場の今でも涼しい。
大事な騎士たちを熱中症にさせるわけにはいかない。アレイがこちらを見て頷いて来る。どうやら全員の移動が終わったらしい。ルナリアの騎士団は数にして三百。大国の割に人数が少ないのは、ライオが実力主義を徹底しているからだ。騎士は勇敢であらねばならないとライオは常々思っている。自分を盾にしてでも民たちを守る気概が必要だと。
向こうから隣国の騎士たちもやって来る。
「ライオ殿」
手を振りながらやって来たのは隣国の騎士隊長であるスサノオだった。彼の勇猛果敢な戦闘スタイルはこちらにも噂として流れて来る。最近は戦い自体ないようだがそれに越したことはない。
「スサノオ殿。お久しぶりです」
ライオの言葉にスサノオが目を細める。長い艶のある黒い髪を後ろで一つにくくっている彼は美しい。ライオはそっと彼の隣に立った。スサノオは男性にしては小柄である。ライオが人より大きいということもある。
「スサノオ殿、今日の訓練はよろしく頼みます」
「それはこちらも同じこと。ライオ殿と手を合わせたいという騎士もいます」
二人はぎゅっと握手をした。同盟を結ぶということはお互いを信頼し合って初めて成立する。スサノオがふと顔を曇らせた。彼らしからぬ表情にライオは首を傾げる。
「スサノオ殿?どうされましたか?」
「いえ、大したことではないのですが、我が国の姫が他国へ嫁ぐことに」
「それはおめでたいことですね」
スサノオの表情は晴れない。なにか理由があるのだろう。ライオは彼の言葉を待った。
「姫はまだ十四です。世の中を知らない。私に発言する権利はないのですが、なんだか怖くなってしまって」
スサノオの気持ちがライオにも分かるような気がした。貴族同士の結婚は打算が絡んでいることがほとんどだ。自国より強い国へ娘を嫁がせることなど当然のように行われている。ライオはふと王子の顔を思い出した。彼もまた王になる。そうなれば正式な側室を迎え入れることになる。なぜかそのことにモヤついてしまう自分にライオは考えた。だが理由は分からない。
「さあライオ殿、始めましょう」
スサノオの言葉にライオは頷いた。
「くっ、たああ」
「脇が甘い!」
ライオは剣を振りかざした。ライオが相手をしているのは隣国の若い騎士だ。どうやら彼は入隊して初めての合同訓練らしい。戦う前から張り切っているのが分かった。彼の気合いは痛いほど伝わってくるのだが、それが空回ってしまっている。ライオは彼の手元を自分の剣で軽く叩いた。咄嗟のことに若い騎士は呻いて後ろに転ぶ。
「もっと基本を学べ。筋はいい」
「あ、ありがとうございます」
わあっと二人の戦いを周りで見ていた騎士たちが騒ぐ。そろそろ昼になる。先程からいい匂いがしているのが何よりの証拠だ。砦には簡易的な施設がある。そこでルナリアの女たちが食事を作ってくれているのだ。
「お昼にしますよー」
向こう側にいたアレイが大きな声で言うと、若い彼らはまたも歓声をあげた。
「隊長、大丈夫ですか?」
昼飯を食べていると向かいに座ったアレイにそっと尋ねられる。昨日は王子に付き合って随分夜更かしをしてしまった。
「ひどい顔をしているか?」
アレイにそう尋ねると苦笑される。
「そうか。今日は早く寝ないとなあ」
ライオは昨日のことを思い出していた。本を読んでやった王子の反応があまりに無邪気で可愛らしく、つい地下に長居してしまったとは言いづらい。そもそも、昨晩自分が王子のもとにいたことを誰も知らない。
「隊長、もしかしてずっと殿下の所にいたのですか?」
やはりアレイには隠し事ができない。ライオは渋々頷いた。アレイとの付き合いも長い。お互いのことは話さなくても大抵分かる。もうすっかり夫婦のような関係だ。
「やっぱり。でもその様子だと殿下とちゃんと話せたようですね」
アレイが嬉しそうに笑ってくれてライオはホッとした。昨日の王子の様子を思い出すと、ライオの頬が緩む。今日も会いに行くと言ったら王子はとても喜んでくれた。国王はここまで読んで自分を王子の元に向かわせたのだろうか。ライオはそこまで考えて、考えるのをやめた。自分がいくら考えても答えなど出ない。もし、国王の思い通りに動いていたとしても別に構わない。王子に出会えてよかったとライオは思っていた。
もう日が傾き始めている。真っ赤な太陽がギラギラと輝いていた。これからますます暑くなる。夏の暑さには十分気を付けなければいけない。
「ライオ殿」
スサノオの言葉にライオは頷いた。スサノオがすらりと腰の剣を抜く。それはライオも同じだ。最後は二人が手合わせして訓練が終わる。それが合同訓練の恒例だった。騎士たちがざわざわしながらそれを見つめている。
「参ります」
スサノオがそう言って、たんっと右足を強く前へ踏み込んできた。こちらの懐に飛び込んでくるつもりだ。ライオがそれを避けるべく彼を剣で受け止める。きいんと金属音が辺りに響き渡った。騎士たちがどよめく。
「やはり簡単にはいきませんね」
スサノオが後ろに跳ぶ。今度はライオの番だ。
剣を構えて走り出す。ライオの突進は速い上に重たい。スサノオが呻きながらライオの剣を受け止めた。
「さすがライオ殿。重たい一撃でした」
ライオは首を横に振る。ライオの一撃をここまで受け流せる剣士はなかなかいない。合同訓練は無事に終わりを告げた。
スサノオたちを見送り、自分たちも詰め所に戻るべく移動した。
「隊長、これを」
詰め所に戻り、ライオが王子の元へ行こうと支度をしていると、やって来たアレイに何かを手渡される。なんだろうとライオはそれを広げた。それは文字の一覧表だった。幼い子供が文字を覚える際に使うものである。城の図書室にそれはあったらしい。アレイが笑う。
「王子に文字を教えて差し上げては?」
「俺が?」
ライオが尋ねるとアレイが頷いて来る。
「先程まで若い者に剣技を教えていたではないですか」
アレイがあまりに目をキラキラさせながら言ってくるので、ライオは断れなかった。その表もバッグに詰める。
「じゃあ行ってくる」
「はい。お気をつけて」
ライオはまたも暗い中を、小さな明かりを頼りに歩いた。
「殿下」
地下牢の中で王子はまた眠っていた。彼はどうやら夜中起きているらしい。すっかり昼夜が逆転してしまっているようだ。それも無理はない。この暗い地下牢では昼も夜も関係ない。
「ん、ライオ。おはよ」
目を擦りながら王子は起き上がった。
「おはようございます。殿下、なにか食べましたか?」
そういえば彼はどうやって食事を摂っているのだろうとライオは疑問に思った。彼の面倒を見ている誰かがいるのは間違いないが、それを調べるのはライオには難しい。
「うん、保存食もらうから」
「ほ、保存食?」
王子は頷いて地下牢の奥から大きな缶詰を持ってきた。ライオからすれば見慣れたものである。少量でも栄養がたっぷり入っているが、味の方はいまいちという代物だ。
「美味しくないでしょう?」
ライオが思わず聞くと王子は笑った。
「罪人にはぴったりだって思わない?」
ライオはその言葉に固まってしまった。王子を縛り付けているのは見えない鎖だ。ライオは思わず彼を抱きしめていた。小柄で色白な王子はライオの腕の中で体を固くしている。ライオはそれにも悲しくなってしまう。自分が彼を怖がらせている。ライオはそう思った。王子がそっとライオの腕の中で身じろぐ。ライオは少し腕の力を緩めた。嫌だっただろうかと不安になる。だが、王子は精いっぱい背伸びをしながらライオに顔を近づけてきた。
「ライオ、どうしたの?」
「殿下、俺が怖いですか?」
「なんで?」
ライオは思わず王子の顔を上から覗き込んでいた。人形のような美しい顔立ちに、ライオはドキドキする。うっかりすると壊してしまいそうだ。それくらい王子は小さい。
「ライオ?どうしたの?」
王子がそっとライオに自分の顔を寄せてきた。あまりの近さに唇が触れそうになる。柔らかそうな唇にライオは目が釘付けになった。
「ね、ライオ。どうしたの?」
王子の唇が動く。ライオはハッとした。
「えと・・俺は昨日、殿下を泣かせてしまいました。今だってこうやって急に触ってしまって」
王子は小さく首を傾げる。
「昨日泣いたのはライオのせいじゃないよ」
「ですが・・・」
「ライオが僕に触ってくれて嬉しかったんだ」
にっこりと王子は笑った。ライオは再び彼を抱きしめていた。王子が笑っている。
「ね、ライオ。今日もお菓子ある?」
「はい、もちろん」
「わあ、嬉しいなあ」
ライオは一瞬、このまま彼を抱き上げて、地上に連れ出してしまおうかとも考えた。だがアレイから、その手はよほどのことがない限り避けるべきだと言われている。あくまでも王子の意思で地上に出てきてもらうべきだと。ライオは彼を抱き上げて膝の上に乗せた。せめて冷たい湿った床に座らせるのだけは避けてやりたい。
「ライオ、重たくないの?」
王子に問われてライオは首を横に振った。彼は驚くほど軽かった。今日もライオが持参してきた菓子を王子は全て平らげた。どうやら彼は腹が減っているようだ。それもそうだろう、栄養がたっぷり入っている保存食を食べているとはいえ、足りているはずがない。
「殿下、俺がここにお食事をお持ちしましょうか?」
いい方法がないかと模索してライオなりに一生懸命提案してみる。
「ううん、僕に食べる権利ないから」
「そんな・・・」
王子はライオの胸に頭を預けてきた。小さな王子の体温は高い。
「ライオ、昨日みたいにお話して。僕、今日はもう眠いから」
「はい」
ライオは昨日と同じように本の続きを読み始めた。すうすうと王子が寝息を立て始める。
ライオももう体力が限界だった。今日行った訓練が今更効いてきたらしい。耐えられなくなり目を閉じると、いつの間にか眠りに落ちていた。ライオが目を開けると、王子はまだすやすやと眠っていた。このまま地下にいると自分も時間の感覚がなくなってしまう。ライオは軽く焦りを覚えた。
「ん・・・」
そんな時、王子が目を開ける。ライオを見て彼はにっこり笑った。
「おはよう、ライオ」
「おはようございます、殿下」
王子がぴょんとライオの膝の上から立ち上がる。
「お風呂に入らなくちゃ。あと歯を磨くよ」
ライオは訳も分からず立ち上がった。風呂などどこにあるのだろう。ここは地下だ。王子が戸惑っているライオの腕を引っ張って、地下牢の外に出る。そして更に地下に下った。歩いていくと、真っ白なタイル張りの空間に大きな白いバスタブが置いてある場所に着く。もうもうとバスタブからから湯気が出ているのだ。ライオはこの空間の不思議さに戸惑った。急に現実感が消えた気がする。
「ね、気持ちいいからライオも入ろ」
「え」
王子は構わず服を脱ぎ捨てる。彼の真っ白な裸体にライオはなんだか変な気持ちになった。なるべく彼の体を直視しないように気を付ける。どうしてこんな気持ちになるかは分からない。自分は王子に出会ってから、なんだかおかしい。
「ね、ライオ。早く」
裸の王子がライオの腰に縋り付いて来る。ライオはあまり気乗りしなかったが服を脱いだ。
「あったかあい」
バスタブに二人が浸かるとぎゅうぎゅうだった。二人が動く度にお湯があふれて湯船からこぼれている。白のタイル張りの床を湯が流れている。その湯がどこへ流れていくのかが分からない。
「殿下、ここは誰が?」
ライオの言葉に王子は首を傾げて唸る。
「うーん、えーと・・・」
どうやら王子にもよく分かっていないらしい。
ライオは諦めて、この時間を楽しむことにした。訓練で疲れた体に熱い湯が沁みてとても気持ちいい。宿舎にも風呂はあるが、ライオが入るころにはすっかりぬるくなってしまっている。
「ライオ、気持ちいい?」
「はい、とても」
ライオが笑って答えると、王子が笑った。
「そうそう。昨日のえーと、訓練ってなにをしたの?」
ライオは昨日のことをなるべく分かりやすく王子に話した。王子が目を輝かせながら話を聞いてくれる。
「わああ、ライオって本物の騎士なんだ。ライオが読んでくれたお話にも騎士が出てきたよね」
「俺は神話の騎士ほど強くありません」
王子がライオに抱き着いて来る。それにドキッとしてしまったがライオは彼を受け止めた。ライオの耳元で王子が囁く。
「ライオはすごいよ。僕を探してここまで来るんだから」
王子のその口ぶりからすると、ライオ以外の人間が王子を探しに地下までやって来たということになる。そうなると、ライオが初めてここまで到達した人間ということなのだろうか。何故それが自分だったのか、ライオに分かるはずがない。
「僕にいろいろなことを教えてくれる優しい子がいるんだ」
「殿下、それは・・・」
ライオはつい尋ねたい衝動に駆られたが、自分を抑えた。まだ出会って数日だ。焦ってことを仕損じてしまうのは絶対に避けなければならない。
「ねえ、ライオはお母さんやお父さんと仲良し?」
「はい。仲はいいと思います。父はもう他界していますが」
ふっと王子が顔を曇らせた。そして、心配そうな表情でこちらをじっと覗き込んでくる。
「なんでお父さん、亡くなっちゃったの?」
「親父は俺と同じ騎士で、敵に切られたそうです」
「そんな・・・」
王子は下を向いたまま黙っていた。彼がそっと湯船から出る。ライオも後に続いた。
いつの間にかふかふかのタオルと綺麗な着替えが置いてある。もちろんライオの分もだ。もう不思議なことにいちいち驚いてやる元気もない。
「殿下、大丈夫ですか?」
王子はライオの問いに答えずタオルで体を拭いている。だが、背中側は濡れたままだ。ライオは見かねて、彼の背中を優しく拭いてやる。
「殿下、ちゃんと拭かないと風邪を引いてしまいます」
「ライオも死んじゃうの?」
王子は泣いていた。ライオは王子の顔が良く見えるよう屈んだ。ライオは自分の正直な気持ちを彼に話そうと思い、口を開いた。
「俺には分かりません。死なない方がいいのは分かっているんですが」
「やだ!そんなのやだ!」
王子がついに泣きじゃくり始めてしまう。ライオは困ってしまった。こんな時、どうしたら王子が安心するだろうと考えてみる。ライオはそっと王子を抱きしめた。王子が息を呑む。ライオは彼に優しく語り掛けた。
「殿下、どうやっても人間はいつか死にます。それは俺もあなたも同じです。だからこうしてお互いが生きている内にいろいろ挑戦してみませんか?」
王子がハッとしたような顔をする。
「ライオは僕に地上に来て欲しいの?」
「はい」
ライオの言葉に王子は困っているようだった。まだ彼の見えない鎖は断ち切れていない。ライオは注意深く王子の様子を見守った。彼が困っているのを敢えて助けてやらないことにする。
「ぼ、僕、字だって読めないし、十九にもなるのにこんなだけど大丈夫?」
王子の言葉に思わず噴き出しそうになったライオである。どうやら王子にも自分が同年代より幼いという自覚はあったようだ。ライオはさらに王子を抱き寄せた。王子がライオの首に縋り付いて来る。
「殿下は賢い方です。字は俺が教えます。きっとすぐに覚えますよ」
「ほ、ほんと?」
「殿下、いきなり地上で生活するのは難しいでしょう。俺と少しずつ練習してみませんか?」
「れん・・・しゅう?」
「はい」
「ん、いいよ。ちょっとだけね」
ライオは心の中でものすごく喜んだ。まだスタート地点に立っただけだが、ここまで苦労した甲斐があった。
「ライオ、すごく嬉しそう」
じろっと王子に睨まれてライオは咳払いをしてごまかした。
6・「ついにここまで来ましたか」
詰め所に戻ったライオは食事を摂りながらアレイに地下で起きたことを報告していた。アレイはライオの分の書類仕事をしてくれている。どうやらライオが思っていたより、地上では時間が経っていたらしい。ライオはとにかく腹が減ってしょうがなかった。もりもりと豪快に飯をかきこむ。アレイがそんなライオの様子にくすりと笑う。
「その様子だと食事は期待できなさそうですね」
「ああ、なんて言ったってあるのは保存食だけだからな」
「保存食しか食べていないなら殿下は体が弱っている可能性がありますね」
それにライオは不安になった。アレイの言うことは最もである。確かに王子は体が小さい。食事量が関係ないとは言い切れない。
「なあアレイ。確かお前、医師免許持ってたよな?」
「一応ですが」
「今日俺と一緒に地下へ来てくれないか?」
「分かりました」
王子がアレイに対してどんな反応を見せるか分からない。だが、彼が地上で暮らせるように、いろいろな人間と関わる練習をした方がいい。ライオは最後の一口を飲み込んだ。地下からライオがここに帰る際、王子は外に出る訓練に対して不安を口にしていた。だからこそ、少しでも外の雰囲気に慣れてもらいたい。アレイならきっと上手くやってくれるだろう。そんな期待もあった。
夕方、訓練が終わり、ライオが訓練場に座って剣の手入れをしていると、部下の騎士たちがぞろぞろと集まってきた。
「どうした?お前たち」
「ライオ隊長、我々、美味しい菓子を買って参りました。どうぞ」
ライオがそれを受け取ると騎士たちが歓声を上げる。
「ライオ隊長にいい人が出来たと聞きまして」
ライオはきょとんとした。だがその方が好都合かもしれないとすぐに思う。
「あ、ああ。いい人というか、ちょっと気になるだけだ」
「さすが隊長!冷静ですね!」
「・・・・はは」
まさか自国の王子が地下牢で生活をしているなんて口が裂けても言えるはずがない。そんなことも知らない騎士たちはわいわい騒いでいる。
「隊長、お相手はどのような方なんですか?」
「きっとお美しい方なんでしょうね」
「えーと」
口々に問われて、ライオは困った。どのように切り抜けるか考えたが、いい案が思いつかない。
「ライオ隊長。仕事をしますよ」
向こうから涼やかな声で名前を呼ばれる。顔を上げるとアレイだった。ライオは助かったと思いながら立ち上がった。
「お前たちも早く体を休めなさい」
「はい!アレイ副隊長!」
騎士たちが素直に宿舎に戻っていく。
「ありがとう、アレイ」
「いいえ。隊長は本当に若者に懐かれますね」
アレイが口に手を当ててくすくす笑っている。
「いや、結構な確率で怖がられてるけど」
「それは最初だけですよ。皆、あなたを慕っています。自信を持ってください」
アレイの言葉が嬉しい。二人はそのまま地下に潜った。アレイは黒い革製のバッグを持っている。
「アレイ、そのバッグ」
「はい。城勤めの医師から医療器具を一式借りてきました。私に対処できない可能性もありますがその時はちゃんとした医師を連れてくればいいので」
「そうか」
ライオは王子の様子を思い出した。彼は小さい以外は健康なように見えた。だが病気の中には隠れるのが上手なものもある。地下牢に着くと王子はまたも眠っていた。アレイが辺りを見回して顔をしかめている。暗くじめじめとしたこの場所を良く思うのはドブネズミくらいだ。
「こんな場所にお一人で」
「ああ。そうなんだ」
ライオはそっと扉を開けて地下牢の中に入った。王子が起きる様子はない。アレイも続いて中に入る。
「殿下、起きてください」
「ん」
ライオが優しく王子の体を揺さぶると王子は気怠そうに目を開けた。
「おはよう、ライオ」
「おはようございます。殿下」
王子が目を擦りながら体を起こした。そこで初めてアレイの姿が目に入ったらしい。彼は慌ててライオの後ろに隠れた。
「ライオ、この人誰?女神様?」
王子が隠れながら小声で尋ねて来る。ライオは思わず笑ってしまった。
「アレイっていいます。俺の部下です」
「ええ?騎士って女の人でもなれるんだ」
「アレイは男ですよ」
「ええ?」
アレイが王子と同じ目線になるように屈んだ。
「殿下、私はアレイといいます。殿下のお体の様子が気になり参りました」
「体?どこもなんともないよ?」
王子はアレイと普通に話している。ライオはそれにホッとしていた。アレイは王子に向かって優しく笑う。この笑顔に皆、コロッとなってしまう。アレイの必殺技だ。ライオではこうはいかないだろう。
「一応診察させてくださると助かるのですが」
アレイの言葉に王子は渋々といった様子で頷いた。アレイが聴診器を取り出して装着している。
「アレイは騎士で、お医者さんなの?」
「はい。騎士はケガをすることも多いので応急処置が出来る者も必要なのですよ」
「やっぱりそうなんだ」
突然、王子の声の調子が落ちる。死に対して王子は人より敏感だ。過去に何かあったのだろうかとライオは考える。
「大丈夫ですよ、私たちはそうならないよう毎日訓練をしています」
「くんれん・・・」
アレイが王子の服をたくし上げて、聴診器を王子の胸に当て始めた。
「殿下、大きく呼吸をしてみましょうか」
王子が素直に応じる。一通り診察が終わり、アレイが器具をバッグにしまう。そしてアレイは王子をじっと見た。
「殿下、もう少し食べる量を増やしてみませんか?あなたの年齢からして今の状態では、痩せすぎです。栄養をもっと摂らなければ」
アレイの言葉に王子はうつむいたまま何も言わない。ライオもアレイも王子の言葉を根気強く待った。王子がようやく顔を上げる。
「あのね、僕が地上に出たらどうなるの?
二人が戦いで死ななくて済むのかなあ?」
ライオもアレイも王子の言葉にお互いの顔を見合わせた。アレイは王子の前に跪いた。ライオもそれに倣う。彼は未来の国王なのだ。自分の命をかけて守るべき人である。
「それはあなた様次第です、殿下」
「でも僕、こんなだし無理かも」
アレイが優しく王子の両肩を掴む。そんなアレイに王子は驚いているようだ。
「始める前から諦めていたらもったいないですよ。殿下はこれからもっと成長できます」
「アレイの言う通りです」
ライオも王子に笑いかけた。王子は二人の顔を見比べて、こくりと頷く。
「わかった。僕、れんしゅうする、頑張る」
「殿下」
ライオは思わず王子を抱き上げて喜んでしまった。王子がそんなライオにしがみついて来る。
「ねえ、今日はお菓子ないの?」
ライオは先ほど部下からもらったお菓子を王子に渡した。彼はすっかりお菓子が気に入ったらしい。
これが地上に出るきっかけになればとライオは静かに祈った。
7・「えーと、えーと」
王子が自分の名前をペンで書く練習をしている。アレイがこの前、渡してくれた文字の一覧表を牢の壁に貼っている。ライオが木で作った机と椅子もアレイと二人でここまで運び込んできた。なんともシュールな光景だが、今はそうするのがベストだとアレイとライオは判断した。王子は一文字一文字、文字表を確認しながら紙に文字を書いていく。勉強は昨日から始めた。
「サーシャ、と」
ライオが隣から覗き込むと正しく書けているようだった。
「ねえ、ライオって書いてもいい?」
「もちろんです」
王子が可愛くて、ライオはついにこにこしてしまう。幼い頃、弟か妹が欲しくて両親にわがままを言ったことを思い出した。だが王子は弟というより、もっと違う感情のような気がする。だが、ライオにはその感情がなにか分からなかった。
「ら、い、お」
王子が自分の名前を一生懸命書いてくれてライオは嬉しい。
「これでライオにお手紙が書けるね」
「本当ですね」
王子は他の文字の練習を始めた。読むだけなら王子はほとんど完璧だった。まだ知らない単語も多いが、それはこれから覚えていけばいい。
「ねえライオ。僕が地上に出ていいのかな」
王子がふと不安そうに言う。
「地上でも俺が殿下を守ります」
「うん・・・」
ライオの言葉に王子はうつむいて黙ってしまった。最近特にこういうことが増えている。
王子にはなにか地上に出られない理由があるのだ。それをなんとか聞き出したいところだが、無理はしないとアレイと話し合って決めている。
「殿下、地上には大きな木があります」
ライオは空気を変えようと明るく言ってみた。
「あ、ルナの樹だよね」
ライオがこの間、話した内容を王子は覚えていてくれたらしい。
「僕もライオと行ってみたいな」
「はい。行きましょう」
「・・・うん」
王子は困ったように頷いて再び文字の練習を始めた。
8・「地上に出られない理由・・・・」
アレイが顎に手を当てて考えている。ライオは頷いた。今は夕方、訓練を終えた二人は城内にある図書室に来ている。王子が何故頑なに地下から出てこないのかを探ろうと思ったのだ。ライオは国に関わる資料を片っ端から取り出した。アレイがそれを、一枚ずつページを捲り確認している。
「どうやら王子は秘匿扱いで生まれたようですね」
「なんでだ?」
「それが書いてあったら苦労しません」」
アレイの言うとおりだ。ライオも椅子に座って資料を捲る。
「ん?」
ライオはふと気になった。資料のページが一部ごっそり抜けている。年代的に言えば、女王が地方へ療養に向かったころだろうか。
「なんでここだけページがないんだ?」
「誰かが故意にやったとしか思えませんね」
アレイがそう呟いて、あ、と声を上げた。
「女王の写真がありません」
「おいおい」
二人はそこでしばらく資料と格闘した。窓の外が暗さで見えなくなってくるころ、ライオは気になる記述を見つけた。それは城勤めの侍女が妊娠したというものだった。数行の記録だったが、もしかしたらとライオは思い、アレイを呼んだ。
その日の深夜、ライオは地下牢を目指した。
今日はまだ涼しい。だがライオは緊張していた。顔が熱い。これから先程の資料が何を表していたのか、王子に告げなければならない。彼はきっと傷付くだろう。地下牢に行くと王子が机に突っ伏して眠っていた。一人でずっと勉強をしていたようだ。ライオは起こさないように彼を抱き上げた。
「ん、ライオ。来てくれたんだ」
「眠っていても大丈夫ですよ」
「僕、ライオと一緒にいたい」
そう言われて嬉しくないはずがない。ライオは自分の膝に王子を乗せた。王子がライオの首にしがみついてくる。そして王子にまっすぐ見つめられた。
「ね、ライオ。僕がなんでここにいるか分かった?アレイと調べたんでしょ?僕、ちゃんと知ってるんだから」
王子にそう言われて、ライオは彼の頭を優しく撫でた。彼の流れるような金色の髪がきらきらして美しい。王子を保護する誰かはライオたちの様子をそっと探るのが上手いようだ。王子は笑っている。だが冷たい、寂しそうな笑みだった。ライオはその表情を見て悲しくなる。王子は幼い時、全てを悟って一人ここに来たのだ。もうここから死ぬまで出てこないつもりで。ライオは大きく呼吸した。ここで引き下がるわけにはいかない。ここに来た時点で心は決まっている。
「殿下がここにいる理由、それは殿下の出生が関係あるのですね?」
王子はこくりと頷いた。そして話し出す。
「僕は母上の本当の子供じゃない。父上が気まぐれに抱いた侍女の子供なんだよ」
「ですが、国王陛下と血は繋がっています」
王子は首を横に振る。
「母上もそう言ってくれたよ。でもだんだん母上の具合が悪くなった。療養に行く日、僕はお見送りも出来なかったんだ。だって僕のせいで母上は具合が悪くなったんだから」
「殿下・・・」
王子がしゃくりあげ始める。ライオは思わず彼を抱きしめていた。王子が抱えている傷はライオが思っていたよりはるかに深く、大きかった。王子が自分を罪人だと言っていた理由。それがようやく分かった。本当に優しい子だとライオは思う。
「殿下、お話してくれてありがとうございます。あなたは本当にお強い方です」
「ライオ、僕なんかが国王になっていいの?」
王子の大きな瞳から涙が次々と溢れて来る。
ライオは彼の顔を自分のハンカチで拭ってやった。そして言い聞かせるように言う。
「殿下、あなたはまぎれもなくこの国、ルナリアの王子なのです」
王子はしばらく泣きじゃくっていた。だがそれもピークが過ぎ、落ち着いてきたようだった。
「ごめんなさい、いっぱい泣いちゃった」
王子が照れたように笑いながら言う。ライオはこの時、彼を愛しいと思った。まっすぐでクリアなその感情にライオは自身の体に雷鳴が走ったかのような衝撃を受けた。自分がずっと王子を愛おしく思っていたことにようやく気が付いたのだ。点が線で繋がるとはまさにこのことだろう。
「ライオ?どうしたの?」
王子はライオの気など知らず聞いてくる。
「い、いえ。なんでもありません」
ライオは心臓が今にも爆発するのではないかと思うほど、ドキドキしていた。まさか初めて好きになった相手が年下の同性で、しかも自分より身分が上の王子だとは誰も思わないだろう。
「ライオ、変なの。急に黙っちゃうし」
王子が拗ねたように言う。
「申し訳ありません」
ライオはそう言うので精一杯だった。
「ね、ライオ。僕ね、お手紙書いたんだ。読んでくれる?」
王子が差し出してきたのは白い封筒だ。ライオはそれを受け取った。この封筒は便せんと共にアレイが王子のために持ってきたものだ。
「ライオに読んで欲しくていっぱい書いたよ」
「ありがとうございます、殿下」
王子の笑顔が可愛らしくてライオは顔が熱くなった。だが王子はこれから国王になり、跡継ぎを作るという義務がある。自分は陰から彼を支える立場だ。それでもいいとライオは思った。彼を守るためなら命すら惜しくない。この国のために自分が出来ることは全てしよう、ライオは騎士になって初めてそう思った。
「では俺は地上に戻ります。殿下、また来ます」
「ありがとう、ライオ」
ライオは地下牢から地上へ向かった。先程の涼しい風はいつの間にか止んで、蒸し暑くなっている。だが、ライオの胸には王子からもらった手紙がある。彼が自分に対してなんと書いてくれたのか、読むのがとても楽しみだった。
「戻った」
明け方、宿舎に戻るとアレイはいつも通り書類仕事をしてくれていた。彼はいつもなにかしら仕事をしている。いつ寝ているのだろうと騎士の間で噂になっているのをライオは知っていた。それに本来ならばこれは、ライオがやるべき仕事である。ここのところずっと、騎士団をアレイ一人に任せきりにしてしまっている。そろそろ自分も通常業務に戻らねばまずいとライオは思っていた。
「アレイ、あとは俺がやろう」
「それは出来ません。あなたは国王陛下より、殿下を国王にする命を受けているはず」
確かにその通りだ。だが自分がその命を果たすのに適任かと言われると怪しくなってくる。
「俺はもう殿下のそばにいない方がいいのかもしれない」
そう小さく漏らしたらアレイに驚いたように見つめられた。
「殿下と喧嘩でもしたんですか?」
「いや、そうじゃない、そうじゃないけど」
ライオはアレイにどう話すべきか迷った。だが彼に隠し事は無理だろう。ライオは元から嘘を吐くのが苦手だ。それくらいならば正直に話す方が潔いといえる。
「その・・・えーと、俺は王子が好きなんだ。つまり、恋をしている」
いよいよ白状してしまうとアレイが息を吐くのが聞こえる。あまりの気まずさにライオはその場から全速力で逃げ出したくなった。
「そんなの最初から知ってます」
アレイがやれやれと肩をすくめて見せるのでライオは固まってしまった。
「え、知ってたのか?」
「はい」
ライオは急激に恥ずかしくなってきた。
「さすがに殿下は気が付いてないだろ?」
慌てて確認で聞いてみたが、アレイは首を横に振っている。
「いいえ。殿下はとても賢い方ですし」
「じゃあ気が付いてなかったのは・・・」
「多分、隊長だけかと」
ライオは宿舎の白い壁にもたれかかった。やってしまったと思う。アレイは再び書類に目を通している。少しでも時間が惜しいのだろう。急ぎの仕事も中にはある。ライオはすうと深呼吸した。とりあえず自分は落ち着かなければいけない。
「アレイ、俺はだめなやつか?」
そう思わず泣き声で聞いたらアレイに鼻で笑われた。アレイが何を言いたいのかライオには分かる。付き合いが長いから可能なことだ。
アレイはこう言っている。『突き進め』と。
「隊長、訓練が始まるまで休んでください」
「分かった、そうさせてもらう」
9・その日の夜、訓練を一通り終えて部屋に戻ってきたライオは、すっかりくたびれた隊服を脱いで、灰色のシャツに黒いゆったりしたパンツを着た。この格好ならラフすぎるということもないので、いざという時でも外へ飛び出していける。ライオはベッドに座って、王子からの手紙を読むことにした。
白い封筒をペーパーナイフで切り、中身を取り出す。便せんが二枚入っていた。ライオは便せんに目を通す。王子はまだペンに慣れていないのか、ところどころ文字が掠れている。便せんにびっしりと文字が書かれている。
「殿下・・・」
手紙には、ライオに対するお礼や、ライオが大好きだと繰り返し書いてあった。その言葉に目頭にじんと来るものがある。可愛らしい王子の顔が蘇って来た。今すぐにでも王子に会いたい。ライオはそのまま地下牢へ向かった。暗い水路を通るのにもすっかり慣れっこになってきてしまっている。ライオはいつものように地下牢からの明かりを見つけてホッとした。地下牢に着くと、王子がこちらに背を向けて座っている。
「殿下」
そっと声を掛けると彼はびくりと背中を震わせた。彼が熱心に見ていたもの、それは女王の写真だった。
「あなたが持っていらしたんですね」
ライオがそう声を掛けると王子は笑った。
「うん。泥棒になる?」
「いいえ。あなたのお母様の写真です。家族の写真を持っているのは普通ですよ」
「ライオは僕が嫌にならないんだね」
王子の試すような口調にライオは困ってしまった。
「なんであなたが嫌になるんですか?」
王子がライオの言葉に口を尖らせる。
「だって僕、いわゆるひきこもりでしょ?社会に適応できない駄目人間だし」
ライオはその言葉に驚いてしまった。ふと牢の奥を見ると沢山の本が積まれている。ちらっと見えたタイトルからして、医学や社会学関連のもののようだ。いつの間に、とライオは絶句してしまった。王子が賢いことは知っていたが、ここまでとは思わなかった。
「アレイに借りてきてってお願いした」
「ここの本、全て読まれたんですか?」
「うん。僕、時間あるし、本が大好きになった」
王子がそう言って万歳する。そんな王子に、ライオは慌てて言った。
「殿下は駄目人間ではないですよ。アレイが言っていたじゃないですか。始める前から諦めるのはもったいないって」
ライオの言葉に王子が目を伏せる。やはり王子は美しい人だ。
「うん、よく分かってるよ。諦めるってすごく簡単だもん。でも、つい弱気になるんだ」
ライオは彼を抱きしめた。王子は小さくて温かい。とても愛おしい存在だ。世界にたった一人しかいない。もし、彼を失ったらライオは自分が何をするか分からない。
「俺も諦めようとしたことが何度もあります」
「ライオが?なんで?何を諦めたの?」
ライオは当時を振り返って思わず笑ってしまった。王子がそれに首を傾げている。
「俺が新人騎士だったころ、隣国と同盟を結ぼうと国境を越えようとした時に、山賊たちに背後から襲われて、本当に死ぬかと思いました」
「ひええ」
ライオは他にも、自分の命を諦めようとしたエピソードを、いくつか王子に語った。その度に王子がびっくりした表情をするのが可愛らしい。
「やっぱりライオってすごいなあ。僕じゃ多分、すぐ死んでるなあ」
ライオはふと閃いた。もしかしたら王子と一緒に地上に出られるかもしれない。
「殿下は神様に願い事をしたことはありますか?」
「願い事・・・・。うん、小さい時はいっぱいしてた。全部叶わなかったけど」
「それはどんなお願いをされていたんですか?」
王子はそれに少し顔を赤らめる。
「好きなお菓子がお空から沢山降ってこないかな・・とか。あ、今はしてないからね?」
ライオはその可愛らしさに悶えそうになった。この王子はどこまでも可愛らしい。
「一番お願いしたのは、母上のこと。病気が早く良くなりますようにって」
「殿下に仕えることができて俺は本当に誇らしいです」
「なんか照れちゃうな。ね、ライオ、もしかして今から僕を連れて地上に行こうって考えてる?」
王子の勘の鋭さにライオは驚いた。国王にも言われたが、自分は分かりやすいらしい。
「えーと、今なら夜ですし、誰もいません。その・・・外に出る練習です」
ライオの言葉に王子は息を吐いた。その反応に、無理かと思ったが王子がこう聞いてくる。
「どこに行くの?」
ライオは嬉しくなった。やっと王子を外に連れ出せるかもしれないと思うと、気持ちが高揚してしまう。
「ルナの樹です。そこなら俺たちの願い事をいつでも聞いてくれますよ」
「うん、いいよ。僕、そこに行ってみたいな。練習だよね」
王子の気が変わらないうちにとライオは思った。よく考えると、王子は靴も履いていない。彼はずっと裸足だった。それなら自分が「ルナの丘」まで抱えていけばいい。ライオは王子を抱き上げた。地上に近付くにつれて、王子は緊張していく。無理もない。彼はずっと一人で地下にいたのだから。ライオは彼の背中を優しく撫でた。これで少しでも緊張がほぐれてくれればいい。
「ねえライオ、地上って怖くない?」
「大丈夫ですよ。何も怖くありません」
ライオの肩に王子がぎゅっとしがみついて来る。しばらく歩いていると向こうから外の涼しい空気が流れ込んできた。ライオはその清々しさにホッとした。王子も深呼吸をしている。向こうに大きな月が見える。それがルナリアという国名の由来になった理由だ。
「なんか気持ちいい。それに涼しいね」
王子がそう漏らしてライオは笑った。外の魅力に彼が気が付いてくれることがなによりも大事だ。ライオは彼を背負って水路からの梯子を上った。空には沢山の星々が明るく輝いている。ライオはそのまま町に出た。今はもう真夜中だ。ルナリアの町は静かに二人を迎え入れてくれる。今営業している店は酒場くらいだろうか。
「わ、星が綺麗。夜ってこんな感じなんだ。忘れてた・・・」
王子が頭上を見て呟く。穏やかに風が吹いている。ライオは頷いて「ルナの丘」を目指した。厳めしい城門を出て、しばらく歩くと向こう側に「ルナの丘」が見えて来る。
「あれです、殿下。ルナの丘ですよ」
こんもりとした丘をライオは指で示した。王子がそれに息を呑む。
「あそこにルナの樹があるんだね」
「はい。俺が子供の時、親父とあそこでいっぱい遊んだんです」
「へえ、いいなあ。ライオ」
王子の声に羨望が混じっている。ライオはそれに切なくなってしまった。王子は六歳からあの暗い冷たい牢に一人でいたのだ。自分の意思でとはいえ、辛い日々だっただろう。ライオはつとめて明るく言った。
「殿下、あなたがよろしければ俺と一緒に遊びましょう」
「ほんと?じゃあ僕といっぱい遊んでね」
「はい」
「ライオ大好き。約束だよ」
大好きというワードにライオはドキッとしてしまった。嬉しいが複雑な気持ちでもある。王子に恋をしていても絶対に叶わない恋だ。ライオは王子を抱えたまま丘を登り始めた。途中、急な斜面になっているがライオはずっと登っているのでこの道に慣れている。丘の上に辿り着いてライオは王子を地面に降ろした。ここなら柔らかい草が生えているので、足を怪我することもないだろう。
「わあ、ふかふか」
王子がぴょんぴょんと跳ねている。その様子にライオは笑ってしまった。王子の反応に癒されている自分に気が付く。
「ライオ、外って気持ちいいね。空気もすごく美味しい」
すーはーと王子が呼吸している。王子が地下に籠ってから初めての外出だ。約十数年ぶりの外出に王子も嬉しそうだった。
「ね、ライオ。これがルナの樹?」
王子がルナの樹の太い幹にそっと触れる。彼は目を閉じた。すると、樹が光り始める。ざわざわと風が吹き始めた。他の木々も呼応するようにぼんやり光り始めている。ライオはそれをただ見ていることしか出来なかった。
「ライオ」
優しい声が頭に響いて来る。ライオはあたりを見渡した。だが、王子の他に誰かがいる気配はない。王子がこちらを見つめている。なんだか様子がおかしい。ライオは彼の目線まで屈んだ。そこで彼を通して誰かが自分に向かって話しかけているのだとようやく気が付く。
「殿下?どうされたのですか?」
「ライオ、私の名前はシュナ。いつもサーシャに優しくしてくれてありがとう」
「え、シュナ様?」
まさか神話で有名な神の名前がここで出て来るとは思わなかった。シュナが穏やかな声で言う。
「サーシャは自分を責め、自分をずっと戒めてきました。あなたがそれを終わらせてくれたのです。本当にありがとう」
「何故、シュナ様は俺に話しかけてくださったのですか?」
シュナが王子の体を借りて笑っている。普段の王子と違う表情に、ライオはシュナの存在を現実のものだと受け入れることが出来た。
「私はここでずっとあなたを見ていました。大きく強く成長する姿を見ていました。私にとってはどんな人間も大事な子供です。サーシャもあなたもそのうちの一人、大事な子」
シュナの愛の深さにライオは驚かされた。さすが慈愛の女神である。
「ライオ、ギレー渓谷に向かいなさい。そこで真実の愛を見つけるのです」
「え?」
この間、そんな地名を見た記憶がある。ライオは必死に思い出そうとした。ふと王子を見ると彼は眠たそうにしている。立っていられなくなったのか、その場に座り込んでしまう。いつの間にかシュナの姿はもうない。不思議な現象だ。神と会話するなどめったに出来る経験ではない。シュナはやはり自分を見ていてくれた。自分の気の所為ではなかった。ライオは心の中でシュナに礼を言った。
「ん、ライオ。もう帰りたい」
「殿下、そうですね。戻りましょう」
「うん」
王子を抱き上げてライオは再び水路を抜け、地下牢へ戻った。王子は途中からライオの腕の中ですやすや眠っていた。地下牢の床に王子を寝かせる。床が固くて体が痛くなるから柔らかなマットを持ってこようと何度も提案していたが王子に毎回却下されていた。今度は勝手に持ち込もうとライオは決意する。ふとライオはシュナの言葉を思い出す。「ギレー渓谷」。確かそれは女王が療養に向かった地のはずだ。何故そこに行くべきかは分からない。だが、王子が女王に会いたがっているのは間違いない。ギレー渓谷はここからそう遠くはない。ライオは道のりを頭の中で確認していた。だが、まだ王子は外の世界に慣れていない。もし行くのならもう少し待とうとライオは思った。焦ることはない。王子は確実に前へ進んでいる。
⒑・「殿下が地上に出たうえに、その体にシュナ様が宿った?」
次の日、宿舎にある執務室でそうアレイに報告すると、彼は驚いていた。ライオも彼と同じくらい驚いているので気持ちが良く分かる。
「その話が確かならば、殿下には神々からの宣託の力があるのでしょう。でもまさか上位の神であるシュナ様が直々に現れるとは」
アレイはしばらくぶつぶつ呟いていた。
「ねえ、美味しいお菓子買って」
突然、小さな白い手が下からぬっと飛び出して来て、二人は驚いた。その正体は王子である。
「殿下?」
にこにこと王子は笑っていた。真っ白な服に金色の糸で植物が縁どられた豪華な服を着ている、輝く金色の髪の毛がサラサラと流れる姿はまさに王子という名に相応しい。
「早く。おやつ食べたい」
王子は二人の驚きなど全く気にしていないようだ。彼は自らの足でここまで来たのだろうか。今日は立派な金色の靴も履いている。そんな姿に、彼が今までも普通に地上で生活していたのではないかという錯覚すら覚える。だが、間違いなく王子は地下で死んだように生きていた。ライオは地上に出てきた彼をますます尊敬した。一人で決断し、行動する。それは大人になるためには必要なスキルだ。
「殿下、どうやってここに?」
アレイの言葉に王子は困ったように笑った。
「朝起きたら、もう地下牢にはいちゃいけないよって言われちゃって。この服を着ていれば地上でも安全だって言うから歩いて来ちゃった」
どうやら王子は、その誰かの保護対象から外されたらしい。その方が王子にとってもいいだろう。ライオはふと、シュナの声を思い出していた。真実の愛を探せと。それが何なのかは分からないが、ライオは改めて王子とギレー渓谷に行ってみる気になっていた。一度は様子を見ようと思ったが、王子はこうして自ら地上に出て来てくれた。
「ね、ライオ。さっき、ギレー渓谷って言ってなかった?そこには母上がいるよね?」
ライオは頷いた。ここまで来て王子に隠す必要はないだろう。ライオは王子に向かって尋ねた。彼が神からの託宣を受けられることについて、そして自分と一緒にギレー渓谷に行かないかと。託宣について王子は上手く説明が出来ないようだった。彼は託宣を行うと記憶を失ってしまうようである。
「ライオが一緒にギレー渓谷まで行ってくれるの?」
王子が表情を輝かせる。ライオは頷いた。
「はい。殿下は俺が守ります。ここからギレー渓谷はそこまで離れていません。出立の前に国王にお許しを頂きましょう」
「父上と話すのも久しぶりだなあ」
王子がのんびりと言う。彼はまだ事態の重要さを実感していないらしい。十数年も地下に閉じこもっていた息子が急に目の前に出てきたらどうなるのだろう。ライオは少し不安だった。
「殿下、行きましょう」
「はーい」
城内に入り、国王の部屋に向かう道すがら、侍女や兵士が王子を見て驚いたような表情をする。彼は輝いているように見えるから余計だ。ライオは国王のベッドルームの扉をノックした。扉の前に立っていた兵士たちがライオにいろいろ尋ねたそうにしていたが、ライオはそれを無視した。部屋の中に聞こえるように声を張る。
「国王陛下、サーシャ殿下をお連れしました」
「入れ」
王子と共に国王のベッドルームに入る。ライオはベッドの前で跪いた。王子はそんなライオを困ったように見つめている。
「やっと帰って来たか、息子よ」
布が取り払われ国王の姿が現れた。今、十数年ぶりの時を経て、父子が対面する。
「父上、お久しぶりです。僕は今まで地下で自らを戒めていました」
「知っておる。サーシャ、これからどうする?」
国王は機嫌よく笑っていた。今日はなんだか調子もよさそうに見える。王子の存在は絶大だろう。
「はい、ライオと共にギレー渓谷に行きます。母上にも僕が元気だと報せたいのです」
王子の言葉に国王が片眉を上げる。鋭い眼光が飛んできた。だが、王子は動じない。
「サーシャ、早く国王になれ」
王子は国王の言葉にふっと笑った。
「父上、僕はギレー渓谷に行って参ります。詳しいお話はまた後日」
王子は頭を一度下げるとすたすたと部屋の外に歩いていこうとする。ライオも一礼をして慌てて彼を追いかけた。
「殿下、よかったのですか?」
王子は振り返らない。彼にも分かっているのだろう。相手は実の父親とはいえ、国王だ。王子の行動はあまりにも非礼だった。
「うん。ね、ライオ。準備してもう行こう」
「分かりました。すぐ支度をします」
王子と途中で別れてライオが宿舎に戻ると、アレイがすでに二人分の荷物を用意してくれていた。この部下はよく分かっている。
「殿下のことですから、すぐにでも行きたいと言われるかと思いまして」
「ああ、その通りだ。助かるよ」
ライオは二人分の荷物を担いだ。ここからは馬に乗って移動する。厩舎に行くと既に王子が馬の背中を撫でていた。どれも力自慢の馬ばかりだ。その中の一頭に荷物を担がせる。その馬はライオの相棒と言えるべき存在だ。
「ね、ライオ。行く前におやつ買ってくれる?」
どうやら先程のことを忘れていなかったらしい。ライオは頷いた。城下町は今日も賑わっている。特に城からすぐ出た大通りには市場があり、様々なものが売られている。王子の好きな菓子もそのうちのひとつだ。馬を引いたライオが店に近付くと店主がにこやかに話しかけてくる。ライオは日ごろから町の者とよく話をするようにしていた。そうすることで、普段見かけない不審な人物や、いつもとちょっと違うことなどを話してもらいやすくなる。町を守るのも、もちろん騎士の務めだ。ライオの後ろから王子が店の中を覗いている。
「ライオ隊長!今日も愛しい君にお菓子の差し入れですかな?」
「いや、えーと、その」
ライオが困っていると後ろから王子が言う。
「お菓子は僕の分だよ、おじさま」
王子がそう言って笑うと彼の周りまできらきらと明るく華やいで見えるから不思議だ。店主はそんな王子を見つめて驚いていた。
「あのね、おじさま、このお菓子を三つと、このお菓子を四つ下さい」
「ああ、はい。毎度あり」
ライオが現金を支払う。王子はもう受け取ったばかりの菓子を一つ平らげている。
「美味―い。僕、これ好き」
それはライオが、最初に王子に渡した甘い樹液を固めたお菓子だった。嬉しそうな王子にライオは思わず頬が緩んだ。
「殿下、出かける前に何か屋台で買って食べていきましょう」
「僕、食べていいの?」
「もちろんです。あなたはただでさえ食べていらっしゃらないのに」
「ライオ、いつもありがと」
楽しそうな王子を連れて町の屋台で軽く食べられそうなものをいろいろ買った。王子が串に刺さった大きな肉にかぶりついている。
「わ、美味しいお肉。久しぶりに食べた」
「ルナリアの食材は全て一流を誇りますから」
「うん、お料理のレシピ本にも書いてあった」
王子はすっかり読書にハマったらしい。今では幅広いジャンルの本を読んでいるようだ。
「殿下は本当にお勉強がお好きなのですね」
次に王子は大きなエビが刺さった串焼きを食べ始めている。彼は腹が空いていたらしい。食べながら王子は言った。
「僕が知らないことで周りの皆が困ったら嫌だもの」
「殿下、そこまで気負わなくても大丈夫ですよ」
「うん、僕をライオが守ってくれるんだよね?知ってるよ」
二人は城門をくぐり、町から出た。門の外には急に自然が広がっている。こういう時に自然の力強さに驚かされる。風が吹き、二人の髪の毛をさらさらと撫でる。
「ふわあ、気持ちいい!暑いけど楽しい」
「まずはルナの丘を目指しましょう。ギレー渓谷はここからそこまで離れていません。歩いて三日ほどです」
ライオの言葉に王子はぐっと拳を握りしめる。
「僕、これから冒険に出るんだね!」
「はい。俺があなたを必ずお守りします」
王子を馬に乗せ、ライオはルナの丘を目指した。そこからギレー渓谷を目指す。馬を引きながらライオは歩いた。ルナの丘にたどり着くと強い風が吹いて来る。それがただの風ではないような気がした。ふと父親の顔が思い浮かぶ。目の前にはルナの樹があった。
「親父、俺、行ってくるよ」
小声で言ったつもりだったが王子には聞こえていたらしい。
「ライオのお父さん、ここにいるんだ」
「はい。ずっとここで遊んでもらっていたんです」
ライオの言葉に王子は笑って、きゅっと両手を体の前で握った。そして目を閉じる。まるで神への祈りのようだ。
「ライオのお父さん、ライオは僕を守ってくれるよ。いつも僕に優しくしてくれる」
また風が吹く。父親は確かに自分を見ていてくれているのではないかと思う。生と死を分かつもの、それは薄い膜のようなものなのかもしれない。それでも生と死は絶対に交わることがない。
「ライオのお父さん、嬉しそうだね」
ライオはその言葉に泣きそうになった。だが、今は泣いている場合ではない。自分にはギレー渓谷に向かうという目的がある。ライオは北へ向かって歩き出した。太陽が沈み始めるころ、ライオはそこで休憩を入れることにした。すっかり山中に入っている。今日は出発が遅かった。その分、明日早めに起きて出発すればいい。ギレー渓谷にある集落に着くまではもちろん野宿だ。この辺りはあまりにも自然が豊かで、人が定着せず、村や町もない。だからこそ静かなギレー渓谷に療養に行くというのはルナリアでは珍しい話ではなかった。渓谷は空気が美味しく、体にいいとされている。だが一度行くと二度と帰ってこられないという噂があるのもまた事実である。ギレー渓谷は死に近付いている人を呼び出す、というのだ。ライオはそれが不安だった。杞憂だといいが、向こうに着いたら女王の生存を確認しなければいけない。以前まで手紙が度々送られてきていたが、それもここ数年は途絶えている。ライオは考えながら焚火に火をつけた。これも父が教えてくれた。
「わあ、ライオすごいね」
「火があれば動物が近づいてこないのです」
「そうなんだ」
王子がライオの隣に座って肩によりかかって来た。王子の髪がライオの日焼けした腕に触れる。サラサラでくすぐったい。
「ね、ライオ。僕この前、君にお手紙を書いたと思うんだけど」
「はい、とても嬉しかったです」
「そうじゃなくて!」
ライオには王子の意図が読めず、考えた。そんなライオを見て王子が頬を膨らませる。
「僕、君にラブレターを書いたんだけど」
「あ!」
ライオは顔が熱くなってくるのを感じた。王子はあの手紙で自分に告白をしてくれていたのだと今更になって気が付く。
「ね、ライオ。僕、君が大好き。君は?」
ライオは困った。嬉しくないわけがない。だが自分はただの騎士に過ぎない。王子の相手になどなれない。身分が違い過ぎる。
「お、俺は・・・」
ライオはすぐ答えられない自分が嫌だった。「やっぱり、難しいよね」
王子は寂しそうに笑ってライオから離れた。彼にも身分の差についてよく分かっているのだろう。王子にまっすぐ見据えられる。
「僕はこれからもずっとライオを好きでいる。それだけは忘れないでね」
王子の言葉にライオは頷くのが精一杯だった。自分をここまで信じて受け入れてくれる人はなかなかいない。好き、というたった二文字には収まりきらない感情が湧いて来る。
「ライオ」
名前を呼ばれてそちらを向くと、王子に唇を奪われていた。王子がぺろりと唇を舐める。
「ライオとキスするのは僕だけ」
「で、殿下。駄目です、こんな」
ライオがうろたえていると、王子が笑った。
「ね、ライオ。お腹空いた。早くご飯」
いろいろ言いたいことがあったが、口では王子に敵わないと知っている。ライオは黙って夕餉の支度を始めることにした。
⒒・明け方が近づいている。ライオは火の番をしていた。王子はライオの隣ですやすやと眠っている。王子は夕飯をたっぷり食べていた。今日の彼を見ていて、やっと人並みに食べていると感じた。ライオは王子の頭を撫でながら、あたりを探った。滅多に見かけないがこの辺りには狼がいる。自分だけならまだ何とかなるが、今日は王子がいる。警戒するに越したことはない。
「ライオ、君は寝ないの?」
王子が目を覚ましたらしい。頭を軽く持ち上げた。
「俺なら大丈夫ですよ。よく休んでください」
ライオの言葉に王子は起き上がった。
「ライオが寝ないなら僕も寝ないもん」
「殿下・・・」
王子がライオに抱き着いて来る。ライオが彼を抱き寄せてやると満足そうに笑う。
「ライオ、だーいすき」
「っ・・・・・」
王子の可愛らしさに理性を奪われそうになる。だがライオはなんとか踏みとどまった。自分の任務を頭の中で繰り返し唱える。あくまでこれは王子の護衛という任務なのだと。
「ちぇ、ライオってば頑固だなあ」
どうやら王子は狙ってやっていたようだ。その周到さにライオは恐ろしくなった。いわゆる色仕掛けである。王子は笑う。
「ライオ、好き。ぎゅってして」
そう言われて腕を伸ばされる。ライオは困ったが彼を抱きしめた。火で温められたせいか、王子の体がいつもより温かい。
「ライオはこうして僕を抱っこしてくれるのになんでキスはしてくれないの?」
そう純粋に問われてライオは返事に困った。だが答えないわけにはいかない。ライオは自分なりに必死に言葉を紡いだ。
「殿下とキスされるのは俺ではなく、あなたのもとに嫁いでくる姫様です」
そう自分で言っておいて声が震えた。本音ではそんなのは絶対嫌だった。だがもう決めたのだ。自分は王子ら王族とルナリアを守るのだと。だが自分の意思が揺らいでいることは無視できない。とても危険な状態だ。
「姫様?僕って誰かと結婚しないといけないの?」
王子が首を傾げて聞いて来る。ライオは頷いた。その方が王子も幸せだと、なんとか自分で思いこもうとした。
「そんなのやーだよ、だ」
「殿下?」
いつの間にか、王子に自分の両頬を掴まれていた。王子の唇は柔らかい。ふにっという唇の感触でキスをされていることに気が付く。今度は先ほどとは全く違った深いキスだった。王子の舌がライオの口内に押し入って来る。いけない、とライオは思った。だがそんな理性は数舜しか持たなかった。いつの間にかライオは無我夢中で王子を求めていた。王子の頭を手で抱き寄せて、自分に抵抗できないようにした。ライオの貪るようなキスに王子は一生懸命応えてくれている。
「ん・・っつ・・・らい、お、すき」
王子の舌を吸って口内をこれでもかと犯した。王子がそれに感じてくれている。ライオの中の雄としての本能がそうさせている。
「あ・・ら、いお・・・・もっと」
いよいよ我慢出来ず、ライオは王子を地面に組み敷いていた。王子がそんなライオを見て笑う。それがまた艶っぽい。
「来て、ライオ」
ライオはそこで自分がしていることに気が付いた。慌てて王子から離れる。
「殿下、申し訳ありません」
王子がつまらなさそうに起き上がる。
「ライオの意気地なし」
ライオはただ頭を下げ続けた。いつの間にか朝日が昇ってきている。そろそろ朝食を食べて出発した方がいいだろう。ライオは焚火に集めておいた乾いた枝を入れて火が消えないようにした。
「すぐ食事の準備をします」
ライオは自分の欲求の深さにおののいていた。まさか、自分があんなに乱暴に王子を抱こうとしてしまうとは思わなかった。それは今までの反動であることは分かっていたが、あまりにも乱暴だ。王子にケガをさせてしまう所だった。
「殿下、俺が怖くないのですか?」
「ライオが怖いわけないでしょ。ずっと僕を愛してくれてるじゃん」
やはりライオが王子を好きでいるということは王子にも分かっていたようだ。ライオはどう返事をしていいものか困った。だが伝えるべきことは伝えなければならない。
「俺が殿下を好きでいるわけにはいかないのです。俺はただの騎士であなたは王子だ。身分の差がありすぎます」
ライオの言葉に王子が息を吐く。王子は何かを考えているようだ。
「ね、ライオ。僕を信じてくれる?」
「え?」
王子のことはずっと信じている。ライオはその言葉に虚を突かれた。王子が何をしようとしているか、ライオにはさっぱり分からない。そんなことをしている内に焚火にあてていた鍋の中の水が沸騰してきた。ライオはその中に、干し肉と生の米、スパイスを数種入れる。しばらく煮込むといい香りが漂い始めた。
「わあ、これも美味しそうだね」
「少し癖があるのですが、美味いですよ」
「ライオはお料理も出来るんだね」
「簡単な物だけです」
しばらく煮込んで、食器に盛り付ける。王子はそれを美味いと平らげた。王子が喜んでくれるたびにライオは嬉しくなる。そして愛情が深くなるのを感じていた。食べ終わり片づけ、焚火を消す。二人は再びギレー渓谷を目指した。
⒓・ギレー渓谷を目指して、二日目の昼。王子は初日にライオが購入した菓子をバリバリ食べていた。
「ね、ライオも一緒に食べよう」
馬に跨ったままの状態で王子が菓子の入った包みを差し出してくる。ライオはあまり甘いものが得意ではない。だが言われるがまま食べてみるとそこまで甘くなかった。噛むとバリバリと小気味のいい音が響く。
「美味いですね」
「でしょう?美味しいの、これ!」
王子といるとなんだか自分らしくいられる。ライオはずっとそう感じている。彼に出会えて本当に良かったとライオは噛みしめていた。
「ね、ライオ。ギレーまであとどれくらい?」
「そうですね、もう一晩野宿をして早足で歩けば明日の夕方には着けるかと」
「ライオばっかり歩かせて大変じゃない?」
「いいえ。俺は慣れていますから」
しばらく足場の悪い山道を馬を引いて歩く。でこぼこの道に王子は驚いたり、笑ったりした。もう太陽が沈みかけている。ライオは剣の柄を握った。いつの間にか狼に取り囲まれている。王子が小さく悲鳴を上げる。ライオは慌てなかった。狼たちが牙を剥き出しにしてこちらを威嚇してくる。ライオは一番大きな狼を睨みつけ叫んだ。狼たちがそれに怯えてちりじりになって逃げていく。
「ライオ、すごい」
「殿下、怖い思いをさせて申し訳ありません」
「ライオのせいじゃないよ。すごいもん」
ライオは再び山道を歩きだした。ようやく一つ山を越えた。渓谷までもう間もなくだ。今日はここで休むことにした。王子がごろりと横になって火を見つめている。彼の髪の毛と瞳が火を受けてキラキラと輝いている。
「明日ついにギレー渓谷に着くんだね」
「はい。きっと女王陛下も喜ばれるでしょう」
「そうかな?」
ライオは王子を見つめた。彼がライオを見て寂しそうに笑う。
「母上は僕を恨んでいるかもしれない」
「そんなこと・・・」
王子はそのまま目を閉じてしまった。疲れていないはずがない。ここまで慣れない長時間の移動をしている。ライオは彼に、持ってきていた自分の上着を掛けてやった。ここまで歩き通しのライオも当然疲れている。少し休もうと目を閉じた。気が付くと空が赤い。もう明け方だった。ライオはあたりを確認した。特に異常もない。王子もすやすやと寝息を立てている。ライオは彼の頭を撫でた。王子が可愛くて愛おしくてたまらない。ライオは思わず呟いていた。
「俺はあなたが好きです、サーシャ殿下」
「それ、本当?」
ぱちりと王子が目を開けた。どうやら彼は起きていたらしい。ライオは困って頷いた。嘘を吐く理由などない。
「僕も。僕もライオが大好き!ずっと好き!」
「殿下」
王子がライオに飛びついて来る。それをライオは受け止めた。二人はしばらくじゃれ合っていた。お互いに笑い合う。すごく幸せな時間だ。ライオは王子を膝から降ろした。そろそろ出発する準備をしなければならない。朝食を食べた二人は、再び出発した。
⒔・夕日が岩肌を照らしている。ライオはあたりを見回しながら歩いていた。馬も疲れてきている。ここはもうギレー渓谷のはずだ。集落まで間近だろう。
「うわあ、ここがギレー渓谷」
馬の上で王子が珍しそうにあたりをきょろきょろと見回している。近くに川が流れているのか、水が流れる音がする。ライオは更に奥まで進んだ。王子がはっと息を呑む。そこには確かに集落があった。その瞬間、王子が馬から飛び降りて走り出した。彼の逸る気持ちも分かる。向こうにいたのは女王その人だったからだ。
「母上!」
「サーシャ!」
二人は抱き合った。ライオはホッとしながらその光景を見つめていた。女王は存命だった。渓谷の噂はただの噂だったのだ。人という生き物は噂が大好きなのである。それはどんな時代も変わらないだろう。
「サーシャ、どうやってここに」
「ライオが連れて来てくれた!」
王子が嬉しそうに笑ってライオを指さす。女王がライオに頭を下げた。それに驚いてしまうライオである。
「女王陛下、頭を上げてください。私はただ殿下をお守りしていただけです」
「いいえ、ライオ。シュナから話は全て聞いています」
「え?」
ここで何故シュナの名前が出てくるのだろう。ライオは戸惑いを隠せなかった。女王が笑う。
「シュナを通して城の様子を探っていたのは私です。サーシャのこともシュナに仕える精霊に任せていました。サーシャ、この母を許してくれますか?」
「母上は僕を嫌いになったんじゃないの?」
女王は王子を抱きしめた。
「ずっとあなたに辛い思いをさせているのは知っていました。私はどうしてもここを離れられなかったのです。でもその役目ももう終わった」
女王が空を見上げる。既に空は濃い紫色に変わって来ていた。もうすぐ夜が来る。
「サーシャ、ライオ。理由は私の家で話します。来て頂戴」
二人は女王に頷いた。女王の家は他の家と変わらず、質素な造りだった。それにライオは自分の生家を重ねる。父、母と三人で暮らした実家を思い出す。父は騎士の仕事が休みになると必ず家に帰って来てくれた。ライオはそれが毎回楽しみで、父の帰ってくる日は必ず家の外で待っていた。
女王は二人の為に甘いお茶と菓子を出してくれた。ライオはどうしたものかと迷って、それに口を付けた。熱くて甘いお茶は疲れた体に沁みる。焼き菓子もまた美味い。
「二人にちゃんと話さなくてはいけませんね」
女王は語り始める。王子とライオは、彼女の言葉に耳を傾けた。
・・・事の発端は今から十九年前に遡る。それは城に仕える侍女の妊娠だった。侍女は自分の腹に宿るのは国王の子だと言ったのである。その時、国王と女王の間に子供はいなかった。そのため、周りの人間は慌てた。侍女の子供が生まれれば、その子に王位継承権が回ってくることになる。国王はこの時、威厳と自信にあふれた男だった。ライオもそれは知っていた。今の姿とは、かけ離れているので別人だと勘違いしてしまうくらいだ。国王はその侍女を抱いたらしい。健康で若かった彼女はすぐ妊娠した。当然、女王はそれに怒り狂った。侍女を城から追放しようとしたのである。だが女王には子供がいない。そのため、彼女の意見は通らなかった。それどころか、侍女を愛妾にという声が響いたくらいだ。だが、そのすぐ後、侍女が病で倒れたのである。大事な王位継承権を持つ子供を孕んでいる侍女を死なせるわけにはいかない。女王も自分に子供がいないことをなんとか受け入れ、彼女の看病をした。そこで、女王自身が身籠っていることに気が付いたのだ。女王は恐れた。可愛い子供たちを王位継承権という権利の為に争わせたくなかったからだ。女王の中では、侍女の子供も自らの腹の中にいる子供も、同じくらい大事な存在になっていた。だから王子を秘匿という形で産んだのだ。そこまで話を聞いていたライオはハッと気が付いた。
「では、サーシャ殿下には腹違いのごきょうだいがいらっしゃるのですか?」
ライオの言葉に女王は首を横に振る。
「侍女・・・イライザの子供は死産でした。やはり彼女のかかった病気の影響が大きかったのでしょう。イライザ自身もそれがショックだったのだと思います。小さなサーシャをとても可愛がってくれましたが、イライザは病気になってしまいました」
女王は話を続けた。サーシャが表向きでは侍女の子供だと認知されたこと、そして女王はイライザを看病するためにギレー渓谷へ向かったことを。王子はその時に自ら牢に閉じこもったのだ。今から十三年前の話である。
「じゃ、じゃあ僕は母上の本当の子供なの?」
王子がおそるおそる、女王に尋ねる。
「そうですよ、可愛いサーシャ」
「でも、イライザさんは?」
王子の言葉に女王が寂しそうに目を細める。
「彼女はつい先日亡くなりました。ずっと危ない状態が続いていたのです」
「そうだったんだ」
王子が顔をうつむける。王子にとって死は身近なものだ。ライオもたまらなかった。
「サーシャ、あなたはこれからどうしますか?あなたは国王に・・・・」
王子が女王の言葉を遮るように言う。
「僕、牢の中でいろいろな本を読んだんだよ。そこで分かった。僕は王族という権利を放棄する。普通の市民として生きる」
「サーシャ!なんてことを!」
女王は驚いている。無理もない。ライオだって同じくらい驚いている。王子はライオに抱き着いてくる。ライオは思わず彼を抱きとめていた。
「僕、国を守りたい。ライオと一緒に!」
「サーシャ、では我が国の政治はどうするつもりなのですか?」
とても重要なことだ。王子は笑う。
「王政はもう古いよ。みんなで考えて、みんなでいい国にしよ。王様が一人で威張っている時代はもう終わり」
「サーシャ、あなたという子は」
女王が額に手を当てている。ライオとしてはなにも発言できなかった。王子が自分を選んでくれたこともまだ信じられない。あの時、王子は自分を信じて欲しいと言った。このことだったのだとようやく分かる。
「ライオ、あなたはどうなのですか?騎士として公正に判断するのです」
女王にそう言われると緊張するが、ライオは無意識に王子を抱き寄せていた。
「俺もサーシャ殿下と共に国を守ります」
「ライオ!本当?本当にいいの?」
「はい」
女王が優しく笑った。その笑顔はシュナと同じくらい愛で溢れたものだった。
「二人共、よく分かりました。国王もきっとあなたたちの想いを受け入れてくれるでしょう」
女王の言葉が心強い。二人はお互いの顔を見て笑い合った。
⒕・ライオとサーシャは女王と共にルナリア国に帰って来ている。国王にサーシャは自分なりに考えたことを精一杯話した。それは隣で聞いていたライオも当然知っている。サーシャは政治を王族ではなく民にゆだねることや、自分を王族ではなく、市民として認めて欲しいと国王に要求した。国王はそれを聞いて面白そうだと呟いたのである。もう夜だ。二人は宿舎にあるライオの部屋にいる。
「ね、ラーイオ」
後ろからサーシャに甘えたように抱き着いてこられて、ライオはびくっとなった。彼の可愛らしさにライオはすっかりやられてしまっている。今まで、よく理性が持ったものだと自分を褒めてやりたいくらいだ。
「殿下、俺は・・・」
「もう殿下じゃないよ。ただのサーシャだよ」
「さ、サーシャ」
言葉にすると、より自分の心臓が跳ね上がるようだ。彼を抱きたい、今すぐ触りたい、ずっとそう願っている。
「なあに?ライオ」
ライオはサーシャを抱き上げた。もう我慢できない。美味しそうな餌を目の前に、お預けを食らった犬のような気持ちだ。
「好きだ、サーシャ」
「うん、ライオ、僕も君が大好きだよ」
彼をベッドに押し倒すとサーシャが笑った。
「ライオって時々、野性の狼みたいだよね」
「嫌ならしない」
むすっとライオが膨れるとサーシャがまた笑い声をあげる。
「ライオが我慢できないんでしょ」
ライオは言葉に詰まってしまった。サーシャの言うとおりだったからだ。相変わらず口では彼に敵わないらしい。
「俺はサーシャが欲しいんだ」
「うん。ライオにあげるよ。大好きだもん」
二人はそっと口づけ合った。愛しているという言葉だけではもう足りない。お互いの心に、体に、この気持ちを刻み付けたい。ライオはサーシャの服をたくし上げた。白い肌が露わになる。それにライオはドキリとした。この間、一緒に風呂に入った時はあまり見ないように気を付けていたが、今日は違う。彼の全てを目に焼き付けたかった。彼の一瞬一瞬を忘れたくない。サーシャの胸を優しく撫でる。サーシャはくすぐったいのか笑った。くに、と乳首を優しく摘まんだ瞬間、サーシャが悲鳴を上げる。どうやら不思議な感触だったらしい。サーシャがライオの手に縋って来る。
「ライオ、僕、おかしいよ。なんか胸が熱い」
「大丈夫だよ。俺も熱いから」
うん、とサーシャがライオに頷いて来る。ライオはサーシャの乳首を捏ねるように撫でまわした。先程まで柔らかかったものがだんだん硬く芯を持ってくる。
「あ、ライオ、そこばっかり、嫌だ!」
面白くなって両側の乳首を優しく捏ねていたら、サーシャにいやいやと抵抗された。だが、つい悪戯心が出てしまうライオである。サーシャの言葉を無視して今度は乳首を口に含んでみる。誤って乳首を噛まないよう気を付けながら舌で味わう。サーシャの声にだんだん甘さが混じってくる。改めてサーシャが可愛いとライオは思った。もっとと喘ぎながらサーシャがライオの頭を撫でてくる。きっと気持ちいいのだろう。
「ん、っう、ああぁ・・・ライオ」
ライオがサーシャの下半身を撫でると、彼の雄はすでに屹立していた。じんわりと先が濡れている。
「あ、やだ・・・恥ずかしい」
困ったように言うサーシャにライオは更に興奮する。もっと彼を可愛がりたい。そして愛したい。そう思った。サーシャの履いていたパンツを下着ごとずりおろす。ぷるんと性器が露わになる。サーシャは恥ずかしかったのか、大きな目をぎゅっと閉じた。ライオは彼を自分の方に抱き寄せた。耳元で優しく囁いてみる。
「サーシャのすごく可愛い。触っていいか?」
「っつ!・・・や、ライオの馬鹿」
サーシャが真っ赤な顔でふるふると首を横に振っている。その姿がまた可愛らしい。
「サーシャ。俺にお前をくれるんだろ?さっきそう言った」
また囁いてみるとサーシャはようやく目を見開いた。ライオを涙目でじっと見つめて来る。
「優しくしてね?痛いのやだよ?」
「ああ、気を付ける」
サーシャの性器をそっと手で握るとサーシャが震えた。ライオの手は人より大きく、指も太い。そして、サーシャは人より小さい。サーシャの性器を手のひらで包み込むよう優しく愛撫してやると、サーシャが啼き始める。
「気持ちいいか?サーシャ」
「ん、うんっ、気持ちいい」
「イキそうか?」
「んっ、分かんない・・っやあ」
「あんまり自分でしたことないのか?」
「ん・・・僕、一人でしたことない」
ライオは起き上がってサーシャを膝に乗せてやる。サーシャは真っ赤な顔で荒い呼吸をしていた。くたりとライオの肩にもたれかかって来る。ライオは彼の額に口づけた。急な性行為の刺激に体が耐えられなかったのだろう。ライオはゆるゆると指で彼の性器を扱いてやる。サーシャは荒い呼吸をしながら喘いでいる。くちくちと音がする。
「んう、ああぁ、あああ」
ぴゅっと精液がわずかだが飛び散った。
「っはあ、はあ・・・・」
「サーシャ、またしような」
ライオがそう言って彼の頭を撫でるとサーシャはコクリと頷いた。そんなところも可愛らしい。サーシャの隣に自分も寝転がる。市民になったサーシャは、学校に通い始めていた。年齢は十九のサーシャだが、ちゃんと学校に通った経験がない。そんなサーシャにアレイは、一年間学校に通ってみてはどうかと進めたのだ。サーシャは学校に通うかどうか、かなり悩んだようだった。はじめは出来ないとアレイに断りを入れようとしていたサーシャだったが、アレイはいつもの必殺スマイルを彼に炸裂させたのである。
「サーシャ様、学校が終わったらライオ隊長があなたを迎えに行きますよ。でしょう?隊長」
勝手な約束にライオは驚いたが、サーシャはそれを聞いて嬉しそうに笑った。そんな笑顔を見てしまえば断れるわけがない。それから毎日、ライオは朝と夕方にサーシャを学校まで送り迎えに行くようになった。
「ん、ライオ。僕、寝てた?」
まだサーシャには快感の余韻が残っているのか、意識がぼうっとしているようだ。ライオは彼の頭を優しく撫でる。
「気持ちよかったか?」
「ん。えっち初めてした」
「えっちじゃないぞ。まだ挿れてない」
ライオの言葉にサーシャは固まった。そして絞り出すように言う。
「まだえっちじゃなかったんだ・・・」
「いいさ。またしよう」
「うん」
お互いに見つめ合って笑った。サーシャがライオの体のそばにすり寄って来る。彼の体温は変わらず高く、熱い。先程自分がイケていなかったせいか、ライオの下半身が熱を持ち始めている。サーシャはそれに気が付いたようだ。彼は真っ赤な顔でライオに言う。
「ねえ、やっぱり今する?」
「このままだとサーシャに乱暴しそうだ」
「ひええ。それって痛いの?」
「嘘だよ。優しくする」
サーシャの汗の匂いを感じてライオはますます興奮した。サーシャを優しく、だが動けないように組み敷く。サーシャがぼんやりとこちらを見つめてきた。
「えっちって気持ちいい?」
いつもより甘ったるい声でサーシャが尋ねて来る。ライオは彼に答えた。
「ああ。ゆっくりするよ。きっと気持ちいい」
「うん、大好き。ライオ」
ライオはサーシャの唇にキスを何度もした。首筋、胸とだんだん下へ移動していく。サーシャはキスの度に体を震わせる。
「ん、らい、お」
ライオはサーシャの尻を優しく撫でた。サーシャがそれに反応する。ライオは彼の後孔に指を当てた。
「サーシャ、もう少し力を抜けるか?」
「うん」
サーシャは、かなり汗をかいている。それはライオも一緒だった。夜になり随分涼しくなったが、今は真夏だ。窓は開いている。それでも暑いことに変わりない。ライオがぐっと指に力をこめるとサーシャが顔を歪ませる。きっと苦しいのだろう。ライオは慎重に指を奥に進めた。押し広げるように指を中に入れていく。
「ん、ライオ、お腹苦しい」
「そうだよな。大丈夫。ゆっくりする」
指を一回、ずるっと引き抜いてもう一度挿入する。少しずつ柔らかくなってきた。ライオが指の本数を増やし更に奥を攻めると、サーシャが突然喘いだ。
「や、なんっ、か・・・へん」
どうやら気持ちいい所に偶然当たったらしい。ライオはそこを指の腹でぐりぐりと捏ね回した。
「んぅ、あ、ライオ、そこ気持ちいい」
サーシャが感じてくれて、ライオは嬉しかった。だが、指では限界がある。ライオは指を引き抜いた。
「サーシャ、挿れていいか?」
「ライオの・・・」
サーシャが呟いて真っ赤になった。彼は頷く。
「ライオと一緒に気持ちよくなれるね」
「ああ。そうだよ」
ライオは自分の雄を彼の尻にあてがう。サーシャがぎゅっと体を強張らせた。
「サーシャ、怖いか?」
「うん。でもライオだから平気だよ」
ライオはサーシャの中へ押し入る。その圧力にサーシャは叫んだ。
「あ、らい・・お、苦し・・・ン」
「サーシャ、大丈夫。もうちょっと」
サーシャがライオの背中にしがみついて来る。それがまた可愛くて仕方ない。ライオは更に奥を目指した。もちろん、ライオもサーシャに締め付けられて苦しい。そして今すぐにでも達しそうだった。それをなんとか堪える。
「あ、ライオ・・ライオ」
ライオが入って来るのが苦しいのかサーシャの腰ががくがくと震えている。
「サーシャ、入ったよ。もう動くから」
「うん、好き、大好きだよ、ライオ」
「俺もだよ、サーシャ」
ライオがゆっくり律動を始める。サーシャの小さな体が一緒に揺さぶられている。
「ああ、んあ、らい、お」
「サーシャ、可愛い。ずっと俺のだっ・・」
「んん、あ、ライオ、僕・・・もう」
「一緒にいこう」
「っああぁぁ」
二人はベッドに並んで横になっていた。
「ライオとえっちしちゃった」
照れたようにサーシャが言う。ライオは彼を抱き寄せた。愛おしくてたまらない。
「サーシャは本当に可愛いな」
ライオがそう呟くとサーシャが困ったようにこちらを見上げてきた。
「僕、男なのにこのままで大丈夫?」
「サーシャはそのままでいい」
ライオがそう言って彼の頭を撫でるとサーシャが抱き着いて来る。
「ライオ、僕を地下から連れ出してくれて、本当にありがとう」
「いや、俺は何もしてないよ。サーシャの意思でここまで来たんだ。すごいよ」
「ライオ・・・」
二人はまた口づけ合った。明日も二人は忙しい。早めに休んだ方がいいだろう。ライオが燭台の火を消すと月明かりが部屋を照らす。
「ライオ、おやすみなさい。大好きだよ」
「サーシャ、おやすみ。俺もだよ」
ライオは永遠の愛を彼に誓う。 完
「どうしたよ、親父。今日は機嫌いいな」
ライオは笑いながら頭上にそびえたつルナの樹に向かって語り掛けた。ライオにとってルナの樹は、亡くなった父親のような存在だ。まだライオが幼かったころ、父親と一緒にこのルナの樹の下で追いかけっこをして遊んだり、二人で木陰に寝転びながらいろいろな話をしたことをライオは今でもはっきり思い出せる。当時、父親は騎士として城に勤めており、ある日殉職した。そのあっけない死にライオはとても傷付いた。父親は名誉ある死だったと、他の騎士らから何度も言われたが、小さかったライオにそんな事情が納得できるわけもなく、毎日城の近くにある騎士の詰め所に喧嘩を売りに行った。ライオは成長するにつれて騎士という職業がどんなものか理解していった。その間に自分が知っている騎士が亡くなっていくことも何度か経験した。そして、いつの間にか自分も父親のような優しくて強い騎士になりたいと願うようになっていた。愛国心が特別あったわけじゃない。父親の見ていた世界を自分も見てみたかっただけだ。ライオは今、騎士隊長として騎士団をまとめ上げている。自分は絶対に任務で死なない、ライオは自分にそう誓っている。今までも無茶な現場に遭遇したことは何度もある。だが、なんとか乗り越えてきた。その経験がライオを強くしてくれているが、事あるごとに死という現実を突きつけられて、年を経るごとに死をますます身近に感じるようにもなってきていた。ライオはひと眠りしようと心地よい風の中で目を閉じた。今日は久しぶりの非番だ。風でライオの短い黒い髪がなびく。明日から隣国との合同訓練がある。今日は出来る限りゆっくりしようと思っていた。
「・・・う!・・・ちょう!隊長!」」
「う?」
耳元で名前を叫ばれてライオが目を開けると、部下の騎士が真っ青な顔をして、ライオの体を揺さぶっていた。なにかあったのだとライオは悟る。起き上がってすぐさま腰に携えた剣に触った。手慣れた感触にライオはホッとする。今までぐっすり眠っていたおかげで、体調も万全だ。
「どうした?」
「は、国王からライオ隊長にお話があると」
ライオは嫌な予感を覚えた。大抵こういう時の予感は的中する。だが行かないわけにはいかない。相手は国王だ。ライオは立ち上がった。体をぐいと伸ばす。部下の騎士はそんなライオを静かに待っていた。
「分かった。すぐに行く。お前は詰め所で待機しろ」
「はっ」
彼が走っていくのを確認する。ライオも城に向かって駆け出した。
2・ライオの住む国、ルナリア国は世界で二番目に大きな大陸に君臨している。ここは豊かな自然に恵まれた国だ。近隣諸国とは、お互いに同盟を結び、今まで特別大きな争いもなくうまくやっている。この国は、国王が政治を取り仕きっていた。だが現国王はもう高齢だ。国民からもそれに対して不安の声があがっている。本来であれば、もう世代交代していてもおかしくない。ライオはふと遠くを見た。向こうに真っ白な城が見える。美しいあの城はこの国の誇りだ。城には三角の尖塔が左右対称に並び、天へ向かってそびえたっている。そして、城の周りにはぐるりと水路があった。それは地下の水脈に繋がっていると聞いたことがある。その水路は町中を駆け巡っており、民たちの生活水として使われている。もちろん煮沸すれば飲料水としても使える。豊かな自然を持つルナリアだからこそ出来ることだ。ルナリアの民であれば他国の人間に必ず一度はする自慢である。ライオが城内に入ると兵士たちがこぞって敬礼してくる。
「ライオ隊長、非番にすみません」
音もなくそっとライオの隣を歩いてきたのは、副隊長であるアレイだった。アレイは一言で言うと、女性と間違えてしまうほど綺麗な人だった。肩まである美しい栗色の髪の毛。細い体躯。ライオとはまるで真逆である。だが彼の実力は本物だ。ライオは彼に全幅の信頼を寄せている。
「いや、気にするな。なにがあった?」
ライオの問いにアレイは首を横に振った。アレイにも見当がつかないとなると、ますますただ事ではないようだ。ライオは改めて心の準備をした。間もなく国王のいるベッドルームに到着する。国王は高齢もあってか、ベッドの上からほとんど動けない状態にあった。食事から始まり、下の世話まですべて侍女に任せきりである。廊下を歩いていくと、突き当りに大きな両開きの扉が見える。そばには兵士が二人、槍を持って立っている。ライオの姿を見た瞬間、彼らは背筋を伸ばして敬礼してきた。当然、ライオは彼らに声を掛ける。
「ご苦労。国王陛下はどうされている?」
「はっ、ライオ様にお話があると」
「俺に?」
「はい」
やはり誰にも話の内容が分からないらしい。ここでこうしていても何も始まらない。ライオは思い切って扉をノックした。自分が来たことを大きな声で告げる。すると向こうからしわがれた声で返事が返って来た。
「入れ、ライオ」
「失礼致します」
ライオは部屋に入り、ベッドの前で跪く。侍女によって、するすると天蓋から垂れ下がっていた布が払われる。そこから現れたのは疲れ切った老人の姿だった。彼からはかつての蛮勇さは感じられない。国王はもう限界だと、誰もが感じている。それはライオの意見も変わらない。ライオは一人考えていた。確か国王には、一人子どもがいたはずだ。だが、誰もその子供の姿を見たことがない。見たことがないものを当てにするわけにもいかない。女王もまた、十数年ほど前から遠くの地方へ病気の療養に行っている。これからこの国はどうなるのかとライオの元に訴えかけて来る民もいる。
「頭を上げろ、ライオ。そなた、今日は非番だったとな」
国王は人と喋るのが好きな人だった。侍女とも親しげに話している場面をよく見かける。ライオは頭を上げて国王を見つめた。
「はい。ですが騎士たるもの、国を脅かすものはいついかなる時も全て排除致します」
国王はライオの言葉に声を上げて笑った。そしてこちらを射抜くような鋭い視線を飛ばしてくる。ライオは知らず知らずのうちに後ろへ退いていた。まだ国王には現役時と変わらない威厳と誇りがあるのだとライオは本能で悟ったのだ。
「ライオ、そなたに頼みがある。サーシャ、ワシの息子のことだ」
「えぇ?」
ライオは天がひっくり返ったような驚きを感じた。国王に子供がいるというのは一種の都市伝説的なものだろうと思っていた。だが、国王は冗談を言っているわけではないらしい。彼は白くなった顎髭を撫でながら言う。
「息子は今年で十九になる。だがこもりきりで世間をまったく知らない。ライオ、息子のサーシャを国王にする準備を始めよ」
ライオはしばらく何も返せなかった。国王がそんなライオを見ておかしそうに笑う。
「そなたはいい。素直な男だ。だから信頼するに値する」
「は・・ありがたきお言葉」
ライオは戸惑いを感じながらも頭を下げた。
「ライオ隊長!」
部屋から出てきたライオをアレイは部屋の外でずっと待っていてくれたらしい。普段のアレイなら、自分の仕事に戻っていただろう。だが、彼もまた今回の呼び出しに不穏を感じていたようだ。先程の表情がそれを物語っていた。
「アレイ、ちょっといいか」
ライオは小声で国王の子供が実際にいることを打ち明けた。アレイはそれに対して頷いている。どうやら彼はそれに勘付いていたらしい。豪快で兄貴肌のライオに比べて、アレイには優しい母親のような部分があった。
ライオには言えないことでもアレイになら言えるという騎士や兵士は多数いる。二人が揃ってこそ、ルナリア騎士団は初めて成立する。
「隊長はこれからどうされるのですか?」
アレイの問いにライオはため息をついた。だが自分がやるしか道はないようだ。気は全く乗らないが、それが仕事である。
「とりあえず、そのどこかにいる王子を引きずり出す」
「殿下がいるとしたら城の地下でしょうか。この城には地下牢があると聞いたことがあります。どうも過去に使っていたようですね」
「おいおいおい」
まさか一国の王子を地下牢に入れていたとしたら大事である。アレイはライオに構わず続ける。
「もし彼が地下牢に閉じ込められていたとしたら国の威厳に関わります」
「そうだな。このことは他の皆には黙っていることにしよう」
「隊長、早く殿下を連れ出してきてください」
「分かったよ」
ライオはそのまま地下に繋がる水路へ向かうことにした。水路へは一度、城から出て長い梯子を下りる必要がある。とんだ貧乏くじを引かされた気がするが、これは任務だと割り切る。ライオは早足で城から出た。
3・「あっついな」
城の中は風が通り涼しいが、水路は打って変わって湿気が多い。そのせいかじめじめしてなんとも不快な場所だった。立ち込める水の匂いが、またなんとも言えず、ライオを不機嫌にさせる。ライオは今日非番だったので、騎士の隊服は着ていない。もし隊服であれば更に暑かっただろう。あの服は飾りが多すぎる。ライオは水路を歩いて進む。流れて来る水の音で他の音はすべてかき消されていた。ライオは用心深く辺りを探りながら前へ進んだ。ここに不審な人物がいる可能性もある。油断はしない方がいいだろう。暗がりにだんだん目が慣れて来る。歩いていると、向こうから明かりがちらちらと漏れているのに気が付いた。はじめは錯覚かと思ったが、近付くにつれてそれは確信に変わった。誰かがここにいる。それは間違いない。思わずライオは駆け出していた。おそらくそこにいるのは王子だろう。何故彼がこんな場所にいるのか聞き出さなければならない。ライオは荒く呼吸しながら、大きな地下牢の前に立った。その中には床で寝息を立てている青年がいる。牢とはいえ、鍵はかかっていない。ライオは扉を開けて、牢の中に足を踏み入れた。眠っている小柄な青年が王子のサーシャだろうか。ライオは屈んで彼の様子を窺った。彼は良く眠っている。ライオは彼を観察した。長い腰までの金色の髪の毛、そして人形のような端正な顔立ちをしている。彼がどんな瞳を持っているのかライオは気になった。ライオは王子の肩を優しく揺さぶった。怖がらせてはいけないと思ったのだ。ライオは体も大きく目つきが鋭い。そのため、小さな子供から怖がられることが特に多かった。
「殿下、起きてください」
すうすうと彼は眠っている
「殿下」
「ん・・・」
しばらく声を掛けているとようやく王子に動きがあった。ぱちっと王子の目が開きライオを見る。その瞳は大きく、藍色をしていた。
「誰?」
「・・・私はライオといいます。殿下をお迎えに参りました」
ライオなりに穏やかに言ったつもりだったが、王子は飛び起きて牢の奥に逃げ込んでしまった。ライオは反射的に追いかけようとしてそれを諫める。王子は自分を怖がっている。追いかけたらますます怖がらせるだけだ。それだけは絶対に避けなければいけない。
「殿下、私はあなたに危害を加えません」
「やーだよ。誰が外になんかいくもんか」
「・・・・」
王子の生意気な口調にライオは苛立ちを感じずにはいられなかった。必死にそれを抑えて、ライオは王子に語り掛ける。
「国王陛下があなたをお呼びです」
「父上が?もしかして母上が帰って来たの?」
王子の声音に期待が籠っている。彼はここで母親の帰りを待っていたのだろうか。
ライオは自分が幼かったころのことを思い出した。父親が亡くなったことを受け入れられず、帰ってこない父親の帰りをずっと待ち続けていた自分を。ライオは改めて王子を見つめた。彼の金色の髪が燭台の火を受けてちらちらと輝いている。
「いえ、まだ女王陛下は戻られていません。ですが、あなた様を国民がお待ちなのです」
ライオは彼を諭すように声を掛けた。王子はぺたりとその場に座り込んでしまう。
彼の服は真新しかった。誰かが彼の面倒を見ているのは間違いない。
「なんだ。じゃあここにいる。僕は王子になりたくてなったんじゃないよ」
確かにその通りだ。ライオはしばらく王子とこのような押し問答を繰り返した。だが、毎回するりと上手くかわされてしまう。王子はライオが思っていたより、はるかに賢かった。
「殿下、ここにいてもなにも変わりません。地上で暮らせば楽しいこともあります」
「だから、やだって言ってるだろ」
「殿下」
これ以上は無理だろうかとライオは弱気になった。王子の意志は自分が思っていたよりもはるかに固い。ライオは自分の浅はかさを呪った。もっと簡単に話が進むと思っていたが、甘かった。
「分かりました。私は明日も来ます。殿下、ご自分のこれからのことをよくお考え下さい」
「やーだよ」
どこまでも王子は態度を変えるつもりはないらしい。ライオはすっかり困ってしまった。こんな経験は初めてだ。敵であれば、力づくでどうにかできる。だが相手は自分が守るべきこの国の王族だ。乱暴な手は使えない。ライオはとぼとぼと地下牢を後にした。
4・「え、殿下を連れ出せなかった?」
地下から戻ってきたライオがしょんぼりしながらアレイに伝えると、彼は首を傾げた。
「殿下は牢に閉じ込められていたわけではないんですか?」
王子は確かに地下牢にいた。だが牢には鍵がかかっていたわけでも、王子が鎖で繋がれていたわけでもない。
「では殿下は自らの意思で地下牢にいると?」
アレイはそれに心底驚いているようだ。
「ああ。女王陛下のお帰りを待っているようなんだ」
「それなら地上でも待てるでしょう」
冷静なアレイの言葉にライオはハッとなった。言われてみれば確かにその通りである。自分の思考がそこまで及ばなかったことにライオはため息を吐いた。気持ちが暗くなって視界すら狭まったように感じる。
「やっぱり俺じゃダメなんじゃないか?」
「どうしたんですか、弱気になるなんてあなたらしくもない」
「だって相手は子供だぞ。いや、十九だから成人はしているけど」
ライオがごにょごにょ言っていると、アレイはいよいよ噴き出した。
「失敬。隊長、相手が子供ならどうすればいいか分かっているでしょう?」
アレイはライオを見てもう一度笑った。いつもアレイが子供にどうしていたか、ライオは思い出す。確かアレイはいつも飴玉を持っている。ライオはようやく思いついた。
「そうか、お菓子か!」
「隊長、それだけではまだ足りません。これをどうぞ」
アレイが手渡してきたもの、それは一冊の本だった。ライオはその本のタイトルを見る。
この国、ルナリアに伝わる神話の本のようだった。この国には多数の神々がいたとされる。特に人気なのは慈愛の女神シュナだった。彼女は優しく皆を見守ってくれていると、この国には広く伝わっている。シュナを信仰する者は多い。祭りでも彼女を奉るものがある。ライオも時々、シュナの存在を近くに感じる時がある。不思議な現象なのであまり人には言わないが、幼い頃からなんとなく感じていた。シュナはそれだけ身近な神だ。
「子供にはおとぎ話が必要なんです。きっと辛抱強く待てば、王子も私たちに心を許してくれるはず」
アレイの言葉がいつにも増して心強い。
「ありがとう、アレイ。俺、明日また行ってみる」
アレイがふっと優しく笑った。
「明日、隣国と合同訓練があります。隊長、期待していますよ」
「ああ」
夜、ライオは宿舎にある自分の部屋にいた。
明日の合同訓練の日程を頭に叩き込んでいるのだ。いくら訓練とはいえ、気が抜けたものでは意味がない。戦いは一瞬が命取りとなる場合がある。他国と戦争をする予定はないが、いつどこで何が起きるか分からない。ライオはふと王子の顔を思い出した。自分に彼を次の国王になどできるのだろうか。自分は一介の騎士で、教師ではない。ある程度の教育は受けたが、ライオは成績が良い方ではなかった。ライオはため息をついて寝台に寝そべった。ルナの樹を頭に思い浮かべる。
「親父、俺どうしよう」
弱く呟くと、ふと外から強い風の音がする。木が激しく揺れているのが窓から辛うじて見えた。いつも見える月は雲で隠れている。
ライオは起き上がった。今、王子がどうしているのか無性に気になって来たのだ。このままここで一人モヤモヤ考えているより、王子の様子を見に行こうとライオは思った。アレイのアドバイス通り、買ってきた菓子と先程借りた本を革で出来た肩掛けのバッグに入れる。このバッグは騎士になった時、母親が買ってくれたものだ。とても高級で値段もよかった。このために母親は仕事でもらったわずかな給金から少しずつずっと貯めておいてくれたらしい。家を出る時、母親はライオを誇りに思うと言ってくれた。最近、家に帰っていない。父親の墓参りにも行きたい。ライオはぎゅっと拳を握った。自分は決して一人ではない。アレイや部下もいる。だが王子はどうだろう。あの冷たい地下牢でたった一人だ。ライオは宿舎を出て駆け出していた。
闇の中をライオは手探りで進んでいた。昼間来た水路とはまた様子が違って、なんだか気味が悪い。水がどうどうと流れている。近隣で雨でも降ったのだろうか?水の勢いがいつもより激しい。ライオが歩いていると、そこにちらっと明かりが見えた。ライオはホッとしてその明かりを頼りに前へ進んだ。地下牢に向かうと、王子はちょこんと座って、何かを熱心に見ていた。
「殿下」
ライオが声をかけると王子は慌てたようにそれを隠す。
「まだ僕になにか用なの?」
ライオは気にせず地下牢に入った。王子は当然逃げようとする。ライオは彼の白い手首をそっと掴んだ。
「待ってください、殿下」
王子は顔を上げない。ライオは彼に痛い思いをさせてしまったのかと慌てた。気を付けて腕を掴んだつもりだったが、自分は普通の人より力が強い。急いで王子の腕を確認する。どうやら痣になっている様子もない。ライオはそれにホッとする。
「殿下、痛かったですか?申し訳ありません」
ライオが謝ると王子はようやく顔を上げた。
彼の大きな藍色の瞳から涙がぼろぼろ流れている。ライオはいよいよ困った。自分が彼を泣かせてしまったのだ。この場合、すぐ謝るべきだとライオは判断する。
「殿下、本当に申し訳ありません。その、俺、馬鹿力で」
そうなりたくないのに、つい言い訳がましくなってしまう。ライオが焦りながら次の言葉を探していると、王子は笑った。ぐいと彼は自分の拳で涙を拭う。
「ライオだっけ?なんか君って変なの」
王子が声を上げて笑い出す。その笑顔の無邪気さにライオは見とれてしまった。
「ライオ、僕はここにいなきゃダメなんだ」
王子が力強く言う。その言葉の強さにライオは王子の言葉をすぐには否定できなかった。それでもなんとか言葉を絞り出す。
「殿下、あなたは罪人じゃありません。こんな暗い場所に一人でいるなんて」
ライオの言葉に王子は寂しそうに笑った。
「僕は十分罪人だよ。ね、いいもの持って来てくれたんでしょ?甘いにおいがする」
ライオは紙の包みをバッグから取り出した。
それは甘い樹液を固めたお菓子だ。
「わあ、美味しそう」
「殿下、ここにいなきゃいけない理由を聞いてもいいですか?」
ライオの言葉に王子はまた黙り込んでしまった。
「俺にはお話、したくないのですね」
「うん。きっとライオは幻滅するから」
王子がそう言ってそっと座り込む。ライオも彼の隣に座った。冷たい床だ。少し湿っているのか服がじわりと濡れる。あまり気持ちのいいものじゃない。ライオは王子に菓子の入った包みを渡してやる。王子は早速、菓子を口いっぱいに頬張っていた。彼がそれを噛むと、ばりばりといい音がする。
「美味いー。僕、このお菓子大好き」
ライオはホッとしていた。アレイにおすすめの菓子を聞いておいて正解だった。
「ね、まだ何か持ってるんでしょ?」
ライオはアレイに借りた本をバッグから取り出した。それに王子は目を輝かせる。彼は立ち上がって壁に掛かっていた燭台を持ってきた。火がちらちらと揺れている。
「ね、読んで見せて。僕は字を読めないんだ」
ライオはその言葉に驚いてしまった。王族で字が読めないというのは致命的である。
「殿下はいつからここに?」
「うーん、もう随分経つからね」
王子は首を傾げて考えている。
「確かここに来たのは僕が六つの時だったと記憶している」
ライオはそれにまた驚いてしまった。彼は十年以上ここで暮らしているのだ。姿を見た者がいないことにも納得できた。彼は自らここに来たのかとライオは思う。まだ六歳の小さな男の子がだ。彼に何があったのかライオとしては気になるが、まだそれを聞くのは難しいだろう。
「ね、ライオ。早く本を読んでおくれよ」
ライオは燭台の明かりを頼りに本を音読した。こんなことは初めてで、ライオは途中で何度もつっかえた。だが、王子は気にせずライオに先を催促する。話の展開が変わる度に王子は目を輝かせた。そんな王子の様子が可愛らしくて、ライオも自然と笑みがこぼれた。
「ね、ライオ。明日も来ておくれよ」
「明日は隣国との合同訓練があるのです。それを見学に来るというのは?」
ライオは王子が外に出て来てくれるのではと淡い期待を抱いて彼に尋ねた。だが、王子は首を横に振るだけだった。
5・次の日の早朝、ライオはルナリア騎士団を率いて隣国との境にある砦にやって来ていた。隣国とは陸続きで繋がっている。
ここは標高も高く、夏場の今でも涼しい。
大事な騎士たちを熱中症にさせるわけにはいかない。アレイがこちらを見て頷いて来る。どうやら全員の移動が終わったらしい。ルナリアの騎士団は数にして三百。大国の割に人数が少ないのは、ライオが実力主義を徹底しているからだ。騎士は勇敢であらねばならないとライオは常々思っている。自分を盾にしてでも民たちを守る気概が必要だと。
向こうから隣国の騎士たちもやって来る。
「ライオ殿」
手を振りながらやって来たのは隣国の騎士隊長であるスサノオだった。彼の勇猛果敢な戦闘スタイルはこちらにも噂として流れて来る。最近は戦い自体ないようだがそれに越したことはない。
「スサノオ殿。お久しぶりです」
ライオの言葉にスサノオが目を細める。長い艶のある黒い髪を後ろで一つにくくっている彼は美しい。ライオはそっと彼の隣に立った。スサノオは男性にしては小柄である。ライオが人より大きいということもある。
「スサノオ殿、今日の訓練はよろしく頼みます」
「それはこちらも同じこと。ライオ殿と手を合わせたいという騎士もいます」
二人はぎゅっと握手をした。同盟を結ぶということはお互いを信頼し合って初めて成立する。スサノオがふと顔を曇らせた。彼らしからぬ表情にライオは首を傾げる。
「スサノオ殿?どうされましたか?」
「いえ、大したことではないのですが、我が国の姫が他国へ嫁ぐことに」
「それはおめでたいことですね」
スサノオの表情は晴れない。なにか理由があるのだろう。ライオは彼の言葉を待った。
「姫はまだ十四です。世の中を知らない。私に発言する権利はないのですが、なんだか怖くなってしまって」
スサノオの気持ちがライオにも分かるような気がした。貴族同士の結婚は打算が絡んでいることがほとんどだ。自国より強い国へ娘を嫁がせることなど当然のように行われている。ライオはふと王子の顔を思い出した。彼もまた王になる。そうなれば正式な側室を迎え入れることになる。なぜかそのことにモヤついてしまう自分にライオは考えた。だが理由は分からない。
「さあライオ殿、始めましょう」
スサノオの言葉にライオは頷いた。
「くっ、たああ」
「脇が甘い!」
ライオは剣を振りかざした。ライオが相手をしているのは隣国の若い騎士だ。どうやら彼は入隊して初めての合同訓練らしい。戦う前から張り切っているのが分かった。彼の気合いは痛いほど伝わってくるのだが、それが空回ってしまっている。ライオは彼の手元を自分の剣で軽く叩いた。咄嗟のことに若い騎士は呻いて後ろに転ぶ。
「もっと基本を学べ。筋はいい」
「あ、ありがとうございます」
わあっと二人の戦いを周りで見ていた騎士たちが騒ぐ。そろそろ昼になる。先程からいい匂いがしているのが何よりの証拠だ。砦には簡易的な施設がある。そこでルナリアの女たちが食事を作ってくれているのだ。
「お昼にしますよー」
向こう側にいたアレイが大きな声で言うと、若い彼らはまたも歓声をあげた。
「隊長、大丈夫ですか?」
昼飯を食べていると向かいに座ったアレイにそっと尋ねられる。昨日は王子に付き合って随分夜更かしをしてしまった。
「ひどい顔をしているか?」
アレイにそう尋ねると苦笑される。
「そうか。今日は早く寝ないとなあ」
ライオは昨日のことを思い出していた。本を読んでやった王子の反応があまりに無邪気で可愛らしく、つい地下に長居してしまったとは言いづらい。そもそも、昨晩自分が王子のもとにいたことを誰も知らない。
「隊長、もしかしてずっと殿下の所にいたのですか?」
やはりアレイには隠し事ができない。ライオは渋々頷いた。アレイとの付き合いも長い。お互いのことは話さなくても大抵分かる。もうすっかり夫婦のような関係だ。
「やっぱり。でもその様子だと殿下とちゃんと話せたようですね」
アレイが嬉しそうに笑ってくれてライオはホッとした。昨日の王子の様子を思い出すと、ライオの頬が緩む。今日も会いに行くと言ったら王子はとても喜んでくれた。国王はここまで読んで自分を王子の元に向かわせたのだろうか。ライオはそこまで考えて、考えるのをやめた。自分がいくら考えても答えなど出ない。もし、国王の思い通りに動いていたとしても別に構わない。王子に出会えてよかったとライオは思っていた。
もう日が傾き始めている。真っ赤な太陽がギラギラと輝いていた。これからますます暑くなる。夏の暑さには十分気を付けなければいけない。
「ライオ殿」
スサノオの言葉にライオは頷いた。スサノオがすらりと腰の剣を抜く。それはライオも同じだ。最後は二人が手合わせして訓練が終わる。それが合同訓練の恒例だった。騎士たちがざわざわしながらそれを見つめている。
「参ります」
スサノオがそう言って、たんっと右足を強く前へ踏み込んできた。こちらの懐に飛び込んでくるつもりだ。ライオがそれを避けるべく彼を剣で受け止める。きいんと金属音が辺りに響き渡った。騎士たちがどよめく。
「やはり簡単にはいきませんね」
スサノオが後ろに跳ぶ。今度はライオの番だ。
剣を構えて走り出す。ライオの突進は速い上に重たい。スサノオが呻きながらライオの剣を受け止めた。
「さすがライオ殿。重たい一撃でした」
ライオは首を横に振る。ライオの一撃をここまで受け流せる剣士はなかなかいない。合同訓練は無事に終わりを告げた。
スサノオたちを見送り、自分たちも詰め所に戻るべく移動した。
「隊長、これを」
詰め所に戻り、ライオが王子の元へ行こうと支度をしていると、やって来たアレイに何かを手渡される。なんだろうとライオはそれを広げた。それは文字の一覧表だった。幼い子供が文字を覚える際に使うものである。城の図書室にそれはあったらしい。アレイが笑う。
「王子に文字を教えて差し上げては?」
「俺が?」
ライオが尋ねるとアレイが頷いて来る。
「先程まで若い者に剣技を教えていたではないですか」
アレイがあまりに目をキラキラさせながら言ってくるので、ライオは断れなかった。その表もバッグに詰める。
「じゃあ行ってくる」
「はい。お気をつけて」
ライオはまたも暗い中を、小さな明かりを頼りに歩いた。
「殿下」
地下牢の中で王子はまた眠っていた。彼はどうやら夜中起きているらしい。すっかり昼夜が逆転してしまっているようだ。それも無理はない。この暗い地下牢では昼も夜も関係ない。
「ん、ライオ。おはよ」
目を擦りながら王子は起き上がった。
「おはようございます。殿下、なにか食べましたか?」
そういえば彼はどうやって食事を摂っているのだろうとライオは疑問に思った。彼の面倒を見ている誰かがいるのは間違いないが、それを調べるのはライオには難しい。
「うん、保存食もらうから」
「ほ、保存食?」
王子は頷いて地下牢の奥から大きな缶詰を持ってきた。ライオからすれば見慣れたものである。少量でも栄養がたっぷり入っているが、味の方はいまいちという代物だ。
「美味しくないでしょう?」
ライオが思わず聞くと王子は笑った。
「罪人にはぴったりだって思わない?」
ライオはその言葉に固まってしまった。王子を縛り付けているのは見えない鎖だ。ライオは思わず彼を抱きしめていた。小柄で色白な王子はライオの腕の中で体を固くしている。ライオはそれにも悲しくなってしまう。自分が彼を怖がらせている。ライオはそう思った。王子がそっとライオの腕の中で身じろぐ。ライオは少し腕の力を緩めた。嫌だっただろうかと不安になる。だが、王子は精いっぱい背伸びをしながらライオに顔を近づけてきた。
「ライオ、どうしたの?」
「殿下、俺が怖いですか?」
「なんで?」
ライオは思わず王子の顔を上から覗き込んでいた。人形のような美しい顔立ちに、ライオはドキドキする。うっかりすると壊してしまいそうだ。それくらい王子は小さい。
「ライオ?どうしたの?」
王子がそっとライオに自分の顔を寄せてきた。あまりの近さに唇が触れそうになる。柔らかそうな唇にライオは目が釘付けになった。
「ね、ライオ。どうしたの?」
王子の唇が動く。ライオはハッとした。
「えと・・俺は昨日、殿下を泣かせてしまいました。今だってこうやって急に触ってしまって」
王子は小さく首を傾げる。
「昨日泣いたのはライオのせいじゃないよ」
「ですが・・・」
「ライオが僕に触ってくれて嬉しかったんだ」
にっこりと王子は笑った。ライオは再び彼を抱きしめていた。王子が笑っている。
「ね、ライオ。今日もお菓子ある?」
「はい、もちろん」
「わあ、嬉しいなあ」
ライオは一瞬、このまま彼を抱き上げて、地上に連れ出してしまおうかとも考えた。だがアレイから、その手はよほどのことがない限り避けるべきだと言われている。あくまでも王子の意思で地上に出てきてもらうべきだと。ライオは彼を抱き上げて膝の上に乗せた。せめて冷たい湿った床に座らせるのだけは避けてやりたい。
「ライオ、重たくないの?」
王子に問われてライオは首を横に振った。彼は驚くほど軽かった。今日もライオが持参してきた菓子を王子は全て平らげた。どうやら彼は腹が減っているようだ。それもそうだろう、栄養がたっぷり入っている保存食を食べているとはいえ、足りているはずがない。
「殿下、俺がここにお食事をお持ちしましょうか?」
いい方法がないかと模索してライオなりに一生懸命提案してみる。
「ううん、僕に食べる権利ないから」
「そんな・・・」
王子はライオの胸に頭を預けてきた。小さな王子の体温は高い。
「ライオ、昨日みたいにお話して。僕、今日はもう眠いから」
「はい」
ライオは昨日と同じように本の続きを読み始めた。すうすうと王子が寝息を立て始める。
ライオももう体力が限界だった。今日行った訓練が今更効いてきたらしい。耐えられなくなり目を閉じると、いつの間にか眠りに落ちていた。ライオが目を開けると、王子はまだすやすやと眠っていた。このまま地下にいると自分も時間の感覚がなくなってしまう。ライオは軽く焦りを覚えた。
「ん・・・」
そんな時、王子が目を開ける。ライオを見て彼はにっこり笑った。
「おはよう、ライオ」
「おはようございます、殿下」
王子がぴょんとライオの膝の上から立ち上がる。
「お風呂に入らなくちゃ。あと歯を磨くよ」
ライオは訳も分からず立ち上がった。風呂などどこにあるのだろう。ここは地下だ。王子が戸惑っているライオの腕を引っ張って、地下牢の外に出る。そして更に地下に下った。歩いていくと、真っ白なタイル張りの空間に大きな白いバスタブが置いてある場所に着く。もうもうとバスタブからから湯気が出ているのだ。ライオはこの空間の不思議さに戸惑った。急に現実感が消えた気がする。
「ね、気持ちいいからライオも入ろ」
「え」
王子は構わず服を脱ぎ捨てる。彼の真っ白な裸体にライオはなんだか変な気持ちになった。なるべく彼の体を直視しないように気を付ける。どうしてこんな気持ちになるかは分からない。自分は王子に出会ってから、なんだかおかしい。
「ね、ライオ。早く」
裸の王子がライオの腰に縋り付いて来る。ライオはあまり気乗りしなかったが服を脱いだ。
「あったかあい」
バスタブに二人が浸かるとぎゅうぎゅうだった。二人が動く度にお湯があふれて湯船からこぼれている。白のタイル張りの床を湯が流れている。その湯がどこへ流れていくのかが分からない。
「殿下、ここは誰が?」
ライオの言葉に王子は首を傾げて唸る。
「うーん、えーと・・・」
どうやら王子にもよく分かっていないらしい。
ライオは諦めて、この時間を楽しむことにした。訓練で疲れた体に熱い湯が沁みてとても気持ちいい。宿舎にも風呂はあるが、ライオが入るころにはすっかりぬるくなってしまっている。
「ライオ、気持ちいい?」
「はい、とても」
ライオが笑って答えると、王子が笑った。
「そうそう。昨日のえーと、訓練ってなにをしたの?」
ライオは昨日のことをなるべく分かりやすく王子に話した。王子が目を輝かせながら話を聞いてくれる。
「わああ、ライオって本物の騎士なんだ。ライオが読んでくれたお話にも騎士が出てきたよね」
「俺は神話の騎士ほど強くありません」
王子がライオに抱き着いて来る。それにドキッとしてしまったがライオは彼を受け止めた。ライオの耳元で王子が囁く。
「ライオはすごいよ。僕を探してここまで来るんだから」
王子のその口ぶりからすると、ライオ以外の人間が王子を探しに地下までやって来たということになる。そうなると、ライオが初めてここまで到達した人間ということなのだろうか。何故それが自分だったのか、ライオに分かるはずがない。
「僕にいろいろなことを教えてくれる優しい子がいるんだ」
「殿下、それは・・・」
ライオはつい尋ねたい衝動に駆られたが、自分を抑えた。まだ出会って数日だ。焦ってことを仕損じてしまうのは絶対に避けなければならない。
「ねえ、ライオはお母さんやお父さんと仲良し?」
「はい。仲はいいと思います。父はもう他界していますが」
ふっと王子が顔を曇らせた。そして、心配そうな表情でこちらをじっと覗き込んでくる。
「なんでお父さん、亡くなっちゃったの?」
「親父は俺と同じ騎士で、敵に切られたそうです」
「そんな・・・」
王子は下を向いたまま黙っていた。彼がそっと湯船から出る。ライオも後に続いた。
いつの間にかふかふかのタオルと綺麗な着替えが置いてある。もちろんライオの分もだ。もう不思議なことにいちいち驚いてやる元気もない。
「殿下、大丈夫ですか?」
王子はライオの問いに答えずタオルで体を拭いている。だが、背中側は濡れたままだ。ライオは見かねて、彼の背中を優しく拭いてやる。
「殿下、ちゃんと拭かないと風邪を引いてしまいます」
「ライオも死んじゃうの?」
王子は泣いていた。ライオは王子の顔が良く見えるよう屈んだ。ライオは自分の正直な気持ちを彼に話そうと思い、口を開いた。
「俺には分かりません。死なない方がいいのは分かっているんですが」
「やだ!そんなのやだ!」
王子がついに泣きじゃくり始めてしまう。ライオは困ってしまった。こんな時、どうしたら王子が安心するだろうと考えてみる。ライオはそっと王子を抱きしめた。王子が息を呑む。ライオは彼に優しく語り掛けた。
「殿下、どうやっても人間はいつか死にます。それは俺もあなたも同じです。だからこうしてお互いが生きている内にいろいろ挑戦してみませんか?」
王子がハッとしたような顔をする。
「ライオは僕に地上に来て欲しいの?」
「はい」
ライオの言葉に王子は困っているようだった。まだ彼の見えない鎖は断ち切れていない。ライオは注意深く王子の様子を見守った。彼が困っているのを敢えて助けてやらないことにする。
「ぼ、僕、字だって読めないし、十九にもなるのにこんなだけど大丈夫?」
王子の言葉に思わず噴き出しそうになったライオである。どうやら王子にも自分が同年代より幼いという自覚はあったようだ。ライオはさらに王子を抱き寄せた。王子がライオの首に縋り付いて来る。
「殿下は賢い方です。字は俺が教えます。きっとすぐに覚えますよ」
「ほ、ほんと?」
「殿下、いきなり地上で生活するのは難しいでしょう。俺と少しずつ練習してみませんか?」
「れん・・・しゅう?」
「はい」
「ん、いいよ。ちょっとだけね」
ライオは心の中でものすごく喜んだ。まだスタート地点に立っただけだが、ここまで苦労した甲斐があった。
「ライオ、すごく嬉しそう」
じろっと王子に睨まれてライオは咳払いをしてごまかした。
6・「ついにここまで来ましたか」
詰め所に戻ったライオは食事を摂りながらアレイに地下で起きたことを報告していた。アレイはライオの分の書類仕事をしてくれている。どうやらライオが思っていたより、地上では時間が経っていたらしい。ライオはとにかく腹が減ってしょうがなかった。もりもりと豪快に飯をかきこむ。アレイがそんなライオの様子にくすりと笑う。
「その様子だと食事は期待できなさそうですね」
「ああ、なんて言ったってあるのは保存食だけだからな」
「保存食しか食べていないなら殿下は体が弱っている可能性がありますね」
それにライオは不安になった。アレイの言うことは最もである。確かに王子は体が小さい。食事量が関係ないとは言い切れない。
「なあアレイ。確かお前、医師免許持ってたよな?」
「一応ですが」
「今日俺と一緒に地下へ来てくれないか?」
「分かりました」
王子がアレイに対してどんな反応を見せるか分からない。だが、彼が地上で暮らせるように、いろいろな人間と関わる練習をした方がいい。ライオは最後の一口を飲み込んだ。地下からライオがここに帰る際、王子は外に出る訓練に対して不安を口にしていた。だからこそ、少しでも外の雰囲気に慣れてもらいたい。アレイならきっと上手くやってくれるだろう。そんな期待もあった。
夕方、訓練が終わり、ライオが訓練場に座って剣の手入れをしていると、部下の騎士たちがぞろぞろと集まってきた。
「どうした?お前たち」
「ライオ隊長、我々、美味しい菓子を買って参りました。どうぞ」
ライオがそれを受け取ると騎士たちが歓声を上げる。
「ライオ隊長にいい人が出来たと聞きまして」
ライオはきょとんとした。だがその方が好都合かもしれないとすぐに思う。
「あ、ああ。いい人というか、ちょっと気になるだけだ」
「さすが隊長!冷静ですね!」
「・・・・はは」
まさか自国の王子が地下牢で生活をしているなんて口が裂けても言えるはずがない。そんなことも知らない騎士たちはわいわい騒いでいる。
「隊長、お相手はどのような方なんですか?」
「きっとお美しい方なんでしょうね」
「えーと」
口々に問われて、ライオは困った。どのように切り抜けるか考えたが、いい案が思いつかない。
「ライオ隊長。仕事をしますよ」
向こうから涼やかな声で名前を呼ばれる。顔を上げるとアレイだった。ライオは助かったと思いながら立ち上がった。
「お前たちも早く体を休めなさい」
「はい!アレイ副隊長!」
騎士たちが素直に宿舎に戻っていく。
「ありがとう、アレイ」
「いいえ。隊長は本当に若者に懐かれますね」
アレイが口に手を当ててくすくす笑っている。
「いや、結構な確率で怖がられてるけど」
「それは最初だけですよ。皆、あなたを慕っています。自信を持ってください」
アレイの言葉が嬉しい。二人はそのまま地下に潜った。アレイは黒い革製のバッグを持っている。
「アレイ、そのバッグ」
「はい。城勤めの医師から医療器具を一式借りてきました。私に対処できない可能性もありますがその時はちゃんとした医師を連れてくればいいので」
「そうか」
ライオは王子の様子を思い出した。彼は小さい以外は健康なように見えた。だが病気の中には隠れるのが上手なものもある。地下牢に着くと王子はまたも眠っていた。アレイが辺りを見回して顔をしかめている。暗くじめじめとしたこの場所を良く思うのはドブネズミくらいだ。
「こんな場所にお一人で」
「ああ。そうなんだ」
ライオはそっと扉を開けて地下牢の中に入った。王子が起きる様子はない。アレイも続いて中に入る。
「殿下、起きてください」
「ん」
ライオが優しく王子の体を揺さぶると王子は気怠そうに目を開けた。
「おはよう、ライオ」
「おはようございます。殿下」
王子が目を擦りながら体を起こした。そこで初めてアレイの姿が目に入ったらしい。彼は慌ててライオの後ろに隠れた。
「ライオ、この人誰?女神様?」
王子が隠れながら小声で尋ねて来る。ライオは思わず笑ってしまった。
「アレイっていいます。俺の部下です」
「ええ?騎士って女の人でもなれるんだ」
「アレイは男ですよ」
「ええ?」
アレイが王子と同じ目線になるように屈んだ。
「殿下、私はアレイといいます。殿下のお体の様子が気になり参りました」
「体?どこもなんともないよ?」
王子はアレイと普通に話している。ライオはそれにホッとしていた。アレイは王子に向かって優しく笑う。この笑顔に皆、コロッとなってしまう。アレイの必殺技だ。ライオではこうはいかないだろう。
「一応診察させてくださると助かるのですが」
アレイの言葉に王子は渋々といった様子で頷いた。アレイが聴診器を取り出して装着している。
「アレイは騎士で、お医者さんなの?」
「はい。騎士はケガをすることも多いので応急処置が出来る者も必要なのですよ」
「やっぱりそうなんだ」
突然、王子の声の調子が落ちる。死に対して王子は人より敏感だ。過去に何かあったのだろうかとライオは考える。
「大丈夫ですよ、私たちはそうならないよう毎日訓練をしています」
「くんれん・・・」
アレイが王子の服をたくし上げて、聴診器を王子の胸に当て始めた。
「殿下、大きく呼吸をしてみましょうか」
王子が素直に応じる。一通り診察が終わり、アレイが器具をバッグにしまう。そしてアレイは王子をじっと見た。
「殿下、もう少し食べる量を増やしてみませんか?あなたの年齢からして今の状態では、痩せすぎです。栄養をもっと摂らなければ」
アレイの言葉に王子はうつむいたまま何も言わない。ライオもアレイも王子の言葉を根気強く待った。王子がようやく顔を上げる。
「あのね、僕が地上に出たらどうなるの?
二人が戦いで死ななくて済むのかなあ?」
ライオもアレイも王子の言葉にお互いの顔を見合わせた。アレイは王子の前に跪いた。ライオもそれに倣う。彼は未来の国王なのだ。自分の命をかけて守るべき人である。
「それはあなた様次第です、殿下」
「でも僕、こんなだし無理かも」
アレイが優しく王子の両肩を掴む。そんなアレイに王子は驚いているようだ。
「始める前から諦めていたらもったいないですよ。殿下はこれからもっと成長できます」
「アレイの言う通りです」
ライオも王子に笑いかけた。王子は二人の顔を見比べて、こくりと頷く。
「わかった。僕、れんしゅうする、頑張る」
「殿下」
ライオは思わず王子を抱き上げて喜んでしまった。王子がそんなライオにしがみついて来る。
「ねえ、今日はお菓子ないの?」
ライオは先ほど部下からもらったお菓子を王子に渡した。彼はすっかりお菓子が気に入ったらしい。
これが地上に出るきっかけになればとライオは静かに祈った。
7・「えーと、えーと」
王子が自分の名前をペンで書く練習をしている。アレイがこの前、渡してくれた文字の一覧表を牢の壁に貼っている。ライオが木で作った机と椅子もアレイと二人でここまで運び込んできた。なんともシュールな光景だが、今はそうするのがベストだとアレイとライオは判断した。王子は一文字一文字、文字表を確認しながら紙に文字を書いていく。勉強は昨日から始めた。
「サーシャ、と」
ライオが隣から覗き込むと正しく書けているようだった。
「ねえ、ライオって書いてもいい?」
「もちろんです」
王子が可愛くて、ライオはついにこにこしてしまう。幼い頃、弟か妹が欲しくて両親にわがままを言ったことを思い出した。だが王子は弟というより、もっと違う感情のような気がする。だが、ライオにはその感情がなにか分からなかった。
「ら、い、お」
王子が自分の名前を一生懸命書いてくれてライオは嬉しい。
「これでライオにお手紙が書けるね」
「本当ですね」
王子は他の文字の練習を始めた。読むだけなら王子はほとんど完璧だった。まだ知らない単語も多いが、それはこれから覚えていけばいい。
「ねえライオ。僕が地上に出ていいのかな」
王子がふと不安そうに言う。
「地上でも俺が殿下を守ります」
「うん・・・」
ライオの言葉に王子はうつむいて黙ってしまった。最近特にこういうことが増えている。
王子にはなにか地上に出られない理由があるのだ。それをなんとか聞き出したいところだが、無理はしないとアレイと話し合って決めている。
「殿下、地上には大きな木があります」
ライオは空気を変えようと明るく言ってみた。
「あ、ルナの樹だよね」
ライオがこの間、話した内容を王子は覚えていてくれたらしい。
「僕もライオと行ってみたいな」
「はい。行きましょう」
「・・・うん」
王子は困ったように頷いて再び文字の練習を始めた。
8・「地上に出られない理由・・・・」
アレイが顎に手を当てて考えている。ライオは頷いた。今は夕方、訓練を終えた二人は城内にある図書室に来ている。王子が何故頑なに地下から出てこないのかを探ろうと思ったのだ。ライオは国に関わる資料を片っ端から取り出した。アレイがそれを、一枚ずつページを捲り確認している。
「どうやら王子は秘匿扱いで生まれたようですね」
「なんでだ?」
「それが書いてあったら苦労しません」」
アレイの言うとおりだ。ライオも椅子に座って資料を捲る。
「ん?」
ライオはふと気になった。資料のページが一部ごっそり抜けている。年代的に言えば、女王が地方へ療養に向かったころだろうか。
「なんでここだけページがないんだ?」
「誰かが故意にやったとしか思えませんね」
アレイがそう呟いて、あ、と声を上げた。
「女王の写真がありません」
「おいおい」
二人はそこでしばらく資料と格闘した。窓の外が暗さで見えなくなってくるころ、ライオは気になる記述を見つけた。それは城勤めの侍女が妊娠したというものだった。数行の記録だったが、もしかしたらとライオは思い、アレイを呼んだ。
その日の深夜、ライオは地下牢を目指した。
今日はまだ涼しい。だがライオは緊張していた。顔が熱い。これから先程の資料が何を表していたのか、王子に告げなければならない。彼はきっと傷付くだろう。地下牢に行くと王子が机に突っ伏して眠っていた。一人でずっと勉強をしていたようだ。ライオは起こさないように彼を抱き上げた。
「ん、ライオ。来てくれたんだ」
「眠っていても大丈夫ですよ」
「僕、ライオと一緒にいたい」
そう言われて嬉しくないはずがない。ライオは自分の膝に王子を乗せた。王子がライオの首にしがみついてくる。そして王子にまっすぐ見つめられた。
「ね、ライオ。僕がなんでここにいるか分かった?アレイと調べたんでしょ?僕、ちゃんと知ってるんだから」
王子にそう言われて、ライオは彼の頭を優しく撫でた。彼の流れるような金色の髪がきらきらして美しい。王子を保護する誰かはライオたちの様子をそっと探るのが上手いようだ。王子は笑っている。だが冷たい、寂しそうな笑みだった。ライオはその表情を見て悲しくなる。王子は幼い時、全てを悟って一人ここに来たのだ。もうここから死ぬまで出てこないつもりで。ライオは大きく呼吸した。ここで引き下がるわけにはいかない。ここに来た時点で心は決まっている。
「殿下がここにいる理由、それは殿下の出生が関係あるのですね?」
王子はこくりと頷いた。そして話し出す。
「僕は母上の本当の子供じゃない。父上が気まぐれに抱いた侍女の子供なんだよ」
「ですが、国王陛下と血は繋がっています」
王子は首を横に振る。
「母上もそう言ってくれたよ。でもだんだん母上の具合が悪くなった。療養に行く日、僕はお見送りも出来なかったんだ。だって僕のせいで母上は具合が悪くなったんだから」
「殿下・・・」
王子がしゃくりあげ始める。ライオは思わず彼を抱きしめていた。王子が抱えている傷はライオが思っていたよりはるかに深く、大きかった。王子が自分を罪人だと言っていた理由。それがようやく分かった。本当に優しい子だとライオは思う。
「殿下、お話してくれてありがとうございます。あなたは本当にお強い方です」
「ライオ、僕なんかが国王になっていいの?」
王子の大きな瞳から涙が次々と溢れて来る。
ライオは彼の顔を自分のハンカチで拭ってやった。そして言い聞かせるように言う。
「殿下、あなたはまぎれもなくこの国、ルナリアの王子なのです」
王子はしばらく泣きじゃくっていた。だがそれもピークが過ぎ、落ち着いてきたようだった。
「ごめんなさい、いっぱい泣いちゃった」
王子が照れたように笑いながら言う。ライオはこの時、彼を愛しいと思った。まっすぐでクリアなその感情にライオは自身の体に雷鳴が走ったかのような衝撃を受けた。自分がずっと王子を愛おしく思っていたことにようやく気が付いたのだ。点が線で繋がるとはまさにこのことだろう。
「ライオ?どうしたの?」
王子はライオの気など知らず聞いてくる。
「い、いえ。なんでもありません」
ライオは心臓が今にも爆発するのではないかと思うほど、ドキドキしていた。まさか初めて好きになった相手が年下の同性で、しかも自分より身分が上の王子だとは誰も思わないだろう。
「ライオ、変なの。急に黙っちゃうし」
王子が拗ねたように言う。
「申し訳ありません」
ライオはそう言うので精一杯だった。
「ね、ライオ。僕ね、お手紙書いたんだ。読んでくれる?」
王子が差し出してきたのは白い封筒だ。ライオはそれを受け取った。この封筒は便せんと共にアレイが王子のために持ってきたものだ。
「ライオに読んで欲しくていっぱい書いたよ」
「ありがとうございます、殿下」
王子の笑顔が可愛らしくてライオは顔が熱くなった。だが王子はこれから国王になり、跡継ぎを作るという義務がある。自分は陰から彼を支える立場だ。それでもいいとライオは思った。彼を守るためなら命すら惜しくない。この国のために自分が出来ることは全てしよう、ライオは騎士になって初めてそう思った。
「では俺は地上に戻ります。殿下、また来ます」
「ありがとう、ライオ」
ライオは地下牢から地上へ向かった。先程の涼しい風はいつの間にか止んで、蒸し暑くなっている。だが、ライオの胸には王子からもらった手紙がある。彼が自分に対してなんと書いてくれたのか、読むのがとても楽しみだった。
「戻った」
明け方、宿舎に戻るとアレイはいつも通り書類仕事をしてくれていた。彼はいつもなにかしら仕事をしている。いつ寝ているのだろうと騎士の間で噂になっているのをライオは知っていた。それに本来ならばこれは、ライオがやるべき仕事である。ここのところずっと、騎士団をアレイ一人に任せきりにしてしまっている。そろそろ自分も通常業務に戻らねばまずいとライオは思っていた。
「アレイ、あとは俺がやろう」
「それは出来ません。あなたは国王陛下より、殿下を国王にする命を受けているはず」
確かにその通りだ。だが自分がその命を果たすのに適任かと言われると怪しくなってくる。
「俺はもう殿下のそばにいない方がいいのかもしれない」
そう小さく漏らしたらアレイに驚いたように見つめられた。
「殿下と喧嘩でもしたんですか?」
「いや、そうじゃない、そうじゃないけど」
ライオはアレイにどう話すべきか迷った。だが彼に隠し事は無理だろう。ライオは元から嘘を吐くのが苦手だ。それくらいならば正直に話す方が潔いといえる。
「その・・・えーと、俺は王子が好きなんだ。つまり、恋をしている」
いよいよ白状してしまうとアレイが息を吐くのが聞こえる。あまりの気まずさにライオはその場から全速力で逃げ出したくなった。
「そんなの最初から知ってます」
アレイがやれやれと肩をすくめて見せるのでライオは固まってしまった。
「え、知ってたのか?」
「はい」
ライオは急激に恥ずかしくなってきた。
「さすがに殿下は気が付いてないだろ?」
慌てて確認で聞いてみたが、アレイは首を横に振っている。
「いいえ。殿下はとても賢い方ですし」
「じゃあ気が付いてなかったのは・・・」
「多分、隊長だけかと」
ライオは宿舎の白い壁にもたれかかった。やってしまったと思う。アレイは再び書類に目を通している。少しでも時間が惜しいのだろう。急ぎの仕事も中にはある。ライオはすうと深呼吸した。とりあえず自分は落ち着かなければいけない。
「アレイ、俺はだめなやつか?」
そう思わず泣き声で聞いたらアレイに鼻で笑われた。アレイが何を言いたいのかライオには分かる。付き合いが長いから可能なことだ。
アレイはこう言っている。『突き進め』と。
「隊長、訓練が始まるまで休んでください」
「分かった、そうさせてもらう」
9・その日の夜、訓練を一通り終えて部屋に戻ってきたライオは、すっかりくたびれた隊服を脱いで、灰色のシャツに黒いゆったりしたパンツを着た。この格好ならラフすぎるということもないので、いざという時でも外へ飛び出していける。ライオはベッドに座って、王子からの手紙を読むことにした。
白い封筒をペーパーナイフで切り、中身を取り出す。便せんが二枚入っていた。ライオは便せんに目を通す。王子はまだペンに慣れていないのか、ところどころ文字が掠れている。便せんにびっしりと文字が書かれている。
「殿下・・・」
手紙には、ライオに対するお礼や、ライオが大好きだと繰り返し書いてあった。その言葉に目頭にじんと来るものがある。可愛らしい王子の顔が蘇って来た。今すぐにでも王子に会いたい。ライオはそのまま地下牢へ向かった。暗い水路を通るのにもすっかり慣れっこになってきてしまっている。ライオはいつものように地下牢からの明かりを見つけてホッとした。地下牢に着くと、王子がこちらに背を向けて座っている。
「殿下」
そっと声を掛けると彼はびくりと背中を震わせた。彼が熱心に見ていたもの、それは女王の写真だった。
「あなたが持っていらしたんですね」
ライオがそう声を掛けると王子は笑った。
「うん。泥棒になる?」
「いいえ。あなたのお母様の写真です。家族の写真を持っているのは普通ですよ」
「ライオは僕が嫌にならないんだね」
王子の試すような口調にライオは困ってしまった。
「なんであなたが嫌になるんですか?」
王子がライオの言葉に口を尖らせる。
「だって僕、いわゆるひきこもりでしょ?社会に適応できない駄目人間だし」
ライオはその言葉に驚いてしまった。ふと牢の奥を見ると沢山の本が積まれている。ちらっと見えたタイトルからして、医学や社会学関連のもののようだ。いつの間に、とライオは絶句してしまった。王子が賢いことは知っていたが、ここまでとは思わなかった。
「アレイに借りてきてってお願いした」
「ここの本、全て読まれたんですか?」
「うん。僕、時間あるし、本が大好きになった」
王子がそう言って万歳する。そんな王子に、ライオは慌てて言った。
「殿下は駄目人間ではないですよ。アレイが言っていたじゃないですか。始める前から諦めるのはもったいないって」
ライオの言葉に王子が目を伏せる。やはり王子は美しい人だ。
「うん、よく分かってるよ。諦めるってすごく簡単だもん。でも、つい弱気になるんだ」
ライオは彼を抱きしめた。王子は小さくて温かい。とても愛おしい存在だ。世界にたった一人しかいない。もし、彼を失ったらライオは自分が何をするか分からない。
「俺も諦めようとしたことが何度もあります」
「ライオが?なんで?何を諦めたの?」
ライオは当時を振り返って思わず笑ってしまった。王子がそれに首を傾げている。
「俺が新人騎士だったころ、隣国と同盟を結ぼうと国境を越えようとした時に、山賊たちに背後から襲われて、本当に死ぬかと思いました」
「ひええ」
ライオは他にも、自分の命を諦めようとしたエピソードを、いくつか王子に語った。その度に王子がびっくりした表情をするのが可愛らしい。
「やっぱりライオってすごいなあ。僕じゃ多分、すぐ死んでるなあ」
ライオはふと閃いた。もしかしたら王子と一緒に地上に出られるかもしれない。
「殿下は神様に願い事をしたことはありますか?」
「願い事・・・・。うん、小さい時はいっぱいしてた。全部叶わなかったけど」
「それはどんなお願いをされていたんですか?」
王子はそれに少し顔を赤らめる。
「好きなお菓子がお空から沢山降ってこないかな・・とか。あ、今はしてないからね?」
ライオはその可愛らしさに悶えそうになった。この王子はどこまでも可愛らしい。
「一番お願いしたのは、母上のこと。病気が早く良くなりますようにって」
「殿下に仕えることができて俺は本当に誇らしいです」
「なんか照れちゃうな。ね、ライオ、もしかして今から僕を連れて地上に行こうって考えてる?」
王子の勘の鋭さにライオは驚いた。国王にも言われたが、自分は分かりやすいらしい。
「えーと、今なら夜ですし、誰もいません。その・・・外に出る練習です」
ライオの言葉に王子は息を吐いた。その反応に、無理かと思ったが王子がこう聞いてくる。
「どこに行くの?」
ライオは嬉しくなった。やっと王子を外に連れ出せるかもしれないと思うと、気持ちが高揚してしまう。
「ルナの樹です。そこなら俺たちの願い事をいつでも聞いてくれますよ」
「うん、いいよ。僕、そこに行ってみたいな。練習だよね」
王子の気が変わらないうちにとライオは思った。よく考えると、王子は靴も履いていない。彼はずっと裸足だった。それなら自分が「ルナの丘」まで抱えていけばいい。ライオは王子を抱き上げた。地上に近付くにつれて、王子は緊張していく。無理もない。彼はずっと一人で地下にいたのだから。ライオは彼の背中を優しく撫でた。これで少しでも緊張がほぐれてくれればいい。
「ねえライオ、地上って怖くない?」
「大丈夫ですよ。何も怖くありません」
ライオの肩に王子がぎゅっとしがみついて来る。しばらく歩いていると向こうから外の涼しい空気が流れ込んできた。ライオはその清々しさにホッとした。王子も深呼吸をしている。向こうに大きな月が見える。それがルナリアという国名の由来になった理由だ。
「なんか気持ちいい。それに涼しいね」
王子がそう漏らしてライオは笑った。外の魅力に彼が気が付いてくれることがなによりも大事だ。ライオは彼を背負って水路からの梯子を上った。空には沢山の星々が明るく輝いている。ライオはそのまま町に出た。今はもう真夜中だ。ルナリアの町は静かに二人を迎え入れてくれる。今営業している店は酒場くらいだろうか。
「わ、星が綺麗。夜ってこんな感じなんだ。忘れてた・・・」
王子が頭上を見て呟く。穏やかに風が吹いている。ライオは頷いて「ルナの丘」を目指した。厳めしい城門を出て、しばらく歩くと向こう側に「ルナの丘」が見えて来る。
「あれです、殿下。ルナの丘ですよ」
こんもりとした丘をライオは指で示した。王子がそれに息を呑む。
「あそこにルナの樹があるんだね」
「はい。俺が子供の時、親父とあそこでいっぱい遊んだんです」
「へえ、いいなあ。ライオ」
王子の声に羨望が混じっている。ライオはそれに切なくなってしまった。王子は六歳からあの暗い冷たい牢に一人でいたのだ。自分の意思でとはいえ、辛い日々だっただろう。ライオはつとめて明るく言った。
「殿下、あなたがよろしければ俺と一緒に遊びましょう」
「ほんと?じゃあ僕といっぱい遊んでね」
「はい」
「ライオ大好き。約束だよ」
大好きというワードにライオはドキッとしてしまった。嬉しいが複雑な気持ちでもある。王子に恋をしていても絶対に叶わない恋だ。ライオは王子を抱えたまま丘を登り始めた。途中、急な斜面になっているがライオはずっと登っているのでこの道に慣れている。丘の上に辿り着いてライオは王子を地面に降ろした。ここなら柔らかい草が生えているので、足を怪我することもないだろう。
「わあ、ふかふか」
王子がぴょんぴょんと跳ねている。その様子にライオは笑ってしまった。王子の反応に癒されている自分に気が付く。
「ライオ、外って気持ちいいね。空気もすごく美味しい」
すーはーと王子が呼吸している。王子が地下に籠ってから初めての外出だ。約十数年ぶりの外出に王子も嬉しそうだった。
「ね、ライオ。これがルナの樹?」
王子がルナの樹の太い幹にそっと触れる。彼は目を閉じた。すると、樹が光り始める。ざわざわと風が吹き始めた。他の木々も呼応するようにぼんやり光り始めている。ライオはそれをただ見ていることしか出来なかった。
「ライオ」
優しい声が頭に響いて来る。ライオはあたりを見渡した。だが、王子の他に誰かがいる気配はない。王子がこちらを見つめている。なんだか様子がおかしい。ライオは彼の目線まで屈んだ。そこで彼を通して誰かが自分に向かって話しかけているのだとようやく気が付く。
「殿下?どうされたのですか?」
「ライオ、私の名前はシュナ。いつもサーシャに優しくしてくれてありがとう」
「え、シュナ様?」
まさか神話で有名な神の名前がここで出て来るとは思わなかった。シュナが穏やかな声で言う。
「サーシャは自分を責め、自分をずっと戒めてきました。あなたがそれを終わらせてくれたのです。本当にありがとう」
「何故、シュナ様は俺に話しかけてくださったのですか?」
シュナが王子の体を借りて笑っている。普段の王子と違う表情に、ライオはシュナの存在を現実のものだと受け入れることが出来た。
「私はここでずっとあなたを見ていました。大きく強く成長する姿を見ていました。私にとってはどんな人間も大事な子供です。サーシャもあなたもそのうちの一人、大事な子」
シュナの愛の深さにライオは驚かされた。さすが慈愛の女神である。
「ライオ、ギレー渓谷に向かいなさい。そこで真実の愛を見つけるのです」
「え?」
この間、そんな地名を見た記憶がある。ライオは必死に思い出そうとした。ふと王子を見ると彼は眠たそうにしている。立っていられなくなったのか、その場に座り込んでしまう。いつの間にかシュナの姿はもうない。不思議な現象だ。神と会話するなどめったに出来る経験ではない。シュナはやはり自分を見ていてくれた。自分の気の所為ではなかった。ライオは心の中でシュナに礼を言った。
「ん、ライオ。もう帰りたい」
「殿下、そうですね。戻りましょう」
「うん」
王子を抱き上げてライオは再び水路を抜け、地下牢へ戻った。王子は途中からライオの腕の中ですやすや眠っていた。地下牢の床に王子を寝かせる。床が固くて体が痛くなるから柔らかなマットを持ってこようと何度も提案していたが王子に毎回却下されていた。今度は勝手に持ち込もうとライオは決意する。ふとライオはシュナの言葉を思い出す。「ギレー渓谷」。確かそれは女王が療養に向かった地のはずだ。何故そこに行くべきかは分からない。だが、王子が女王に会いたがっているのは間違いない。ギレー渓谷はここからそう遠くはない。ライオは道のりを頭の中で確認していた。だが、まだ王子は外の世界に慣れていない。もし行くのならもう少し待とうとライオは思った。焦ることはない。王子は確実に前へ進んでいる。
⒑・「殿下が地上に出たうえに、その体にシュナ様が宿った?」
次の日、宿舎にある執務室でそうアレイに報告すると、彼は驚いていた。ライオも彼と同じくらい驚いているので気持ちが良く分かる。
「その話が確かならば、殿下には神々からの宣託の力があるのでしょう。でもまさか上位の神であるシュナ様が直々に現れるとは」
アレイはしばらくぶつぶつ呟いていた。
「ねえ、美味しいお菓子買って」
突然、小さな白い手が下からぬっと飛び出して来て、二人は驚いた。その正体は王子である。
「殿下?」
にこにこと王子は笑っていた。真っ白な服に金色の糸で植物が縁どられた豪華な服を着ている、輝く金色の髪の毛がサラサラと流れる姿はまさに王子という名に相応しい。
「早く。おやつ食べたい」
王子は二人の驚きなど全く気にしていないようだ。彼は自らの足でここまで来たのだろうか。今日は立派な金色の靴も履いている。そんな姿に、彼が今までも普通に地上で生活していたのではないかという錯覚すら覚える。だが、間違いなく王子は地下で死んだように生きていた。ライオは地上に出てきた彼をますます尊敬した。一人で決断し、行動する。それは大人になるためには必要なスキルだ。
「殿下、どうやってここに?」
アレイの言葉に王子は困ったように笑った。
「朝起きたら、もう地下牢にはいちゃいけないよって言われちゃって。この服を着ていれば地上でも安全だって言うから歩いて来ちゃった」
どうやら王子は、その誰かの保護対象から外されたらしい。その方が王子にとってもいいだろう。ライオはふと、シュナの声を思い出していた。真実の愛を探せと。それが何なのかは分からないが、ライオは改めて王子とギレー渓谷に行ってみる気になっていた。一度は様子を見ようと思ったが、王子はこうして自ら地上に出て来てくれた。
「ね、ライオ。さっき、ギレー渓谷って言ってなかった?そこには母上がいるよね?」
ライオは頷いた。ここまで来て王子に隠す必要はないだろう。ライオは王子に向かって尋ねた。彼が神からの託宣を受けられることについて、そして自分と一緒にギレー渓谷に行かないかと。託宣について王子は上手く説明が出来ないようだった。彼は託宣を行うと記憶を失ってしまうようである。
「ライオが一緒にギレー渓谷まで行ってくれるの?」
王子が表情を輝かせる。ライオは頷いた。
「はい。殿下は俺が守ります。ここからギレー渓谷はそこまで離れていません。出立の前に国王にお許しを頂きましょう」
「父上と話すのも久しぶりだなあ」
王子がのんびりと言う。彼はまだ事態の重要さを実感していないらしい。十数年も地下に閉じこもっていた息子が急に目の前に出てきたらどうなるのだろう。ライオは少し不安だった。
「殿下、行きましょう」
「はーい」
城内に入り、国王の部屋に向かう道すがら、侍女や兵士が王子を見て驚いたような表情をする。彼は輝いているように見えるから余計だ。ライオは国王のベッドルームの扉をノックした。扉の前に立っていた兵士たちがライオにいろいろ尋ねたそうにしていたが、ライオはそれを無視した。部屋の中に聞こえるように声を張る。
「国王陛下、サーシャ殿下をお連れしました」
「入れ」
王子と共に国王のベッドルームに入る。ライオはベッドの前で跪いた。王子はそんなライオを困ったように見つめている。
「やっと帰って来たか、息子よ」
布が取り払われ国王の姿が現れた。今、十数年ぶりの時を経て、父子が対面する。
「父上、お久しぶりです。僕は今まで地下で自らを戒めていました」
「知っておる。サーシャ、これからどうする?」
国王は機嫌よく笑っていた。今日はなんだか調子もよさそうに見える。王子の存在は絶大だろう。
「はい、ライオと共にギレー渓谷に行きます。母上にも僕が元気だと報せたいのです」
王子の言葉に国王が片眉を上げる。鋭い眼光が飛んできた。だが、王子は動じない。
「サーシャ、早く国王になれ」
王子は国王の言葉にふっと笑った。
「父上、僕はギレー渓谷に行って参ります。詳しいお話はまた後日」
王子は頭を一度下げるとすたすたと部屋の外に歩いていこうとする。ライオも一礼をして慌てて彼を追いかけた。
「殿下、よかったのですか?」
王子は振り返らない。彼にも分かっているのだろう。相手は実の父親とはいえ、国王だ。王子の行動はあまりにも非礼だった。
「うん。ね、ライオ。準備してもう行こう」
「分かりました。すぐ支度をします」
王子と途中で別れてライオが宿舎に戻ると、アレイがすでに二人分の荷物を用意してくれていた。この部下はよく分かっている。
「殿下のことですから、すぐにでも行きたいと言われるかと思いまして」
「ああ、その通りだ。助かるよ」
ライオは二人分の荷物を担いだ。ここからは馬に乗って移動する。厩舎に行くと既に王子が馬の背中を撫でていた。どれも力自慢の馬ばかりだ。その中の一頭に荷物を担がせる。その馬はライオの相棒と言えるべき存在だ。
「ね、ライオ。行く前におやつ買ってくれる?」
どうやら先程のことを忘れていなかったらしい。ライオは頷いた。城下町は今日も賑わっている。特に城からすぐ出た大通りには市場があり、様々なものが売られている。王子の好きな菓子もそのうちのひとつだ。馬を引いたライオが店に近付くと店主がにこやかに話しかけてくる。ライオは日ごろから町の者とよく話をするようにしていた。そうすることで、普段見かけない不審な人物や、いつもとちょっと違うことなどを話してもらいやすくなる。町を守るのも、もちろん騎士の務めだ。ライオの後ろから王子が店の中を覗いている。
「ライオ隊長!今日も愛しい君にお菓子の差し入れですかな?」
「いや、えーと、その」
ライオが困っていると後ろから王子が言う。
「お菓子は僕の分だよ、おじさま」
王子がそう言って笑うと彼の周りまできらきらと明るく華やいで見えるから不思議だ。店主はそんな王子を見つめて驚いていた。
「あのね、おじさま、このお菓子を三つと、このお菓子を四つ下さい」
「ああ、はい。毎度あり」
ライオが現金を支払う。王子はもう受け取ったばかりの菓子を一つ平らげている。
「美味―い。僕、これ好き」
それはライオが、最初に王子に渡した甘い樹液を固めたお菓子だった。嬉しそうな王子にライオは思わず頬が緩んだ。
「殿下、出かける前に何か屋台で買って食べていきましょう」
「僕、食べていいの?」
「もちろんです。あなたはただでさえ食べていらっしゃらないのに」
「ライオ、いつもありがと」
楽しそうな王子を連れて町の屋台で軽く食べられそうなものをいろいろ買った。王子が串に刺さった大きな肉にかぶりついている。
「わ、美味しいお肉。久しぶりに食べた」
「ルナリアの食材は全て一流を誇りますから」
「うん、お料理のレシピ本にも書いてあった」
王子はすっかり読書にハマったらしい。今では幅広いジャンルの本を読んでいるようだ。
「殿下は本当にお勉強がお好きなのですね」
次に王子は大きなエビが刺さった串焼きを食べ始めている。彼は腹が空いていたらしい。食べながら王子は言った。
「僕が知らないことで周りの皆が困ったら嫌だもの」
「殿下、そこまで気負わなくても大丈夫ですよ」
「うん、僕をライオが守ってくれるんだよね?知ってるよ」
二人は城門をくぐり、町から出た。門の外には急に自然が広がっている。こういう時に自然の力強さに驚かされる。風が吹き、二人の髪の毛をさらさらと撫でる。
「ふわあ、気持ちいい!暑いけど楽しい」
「まずはルナの丘を目指しましょう。ギレー渓谷はここからそこまで離れていません。歩いて三日ほどです」
ライオの言葉に王子はぐっと拳を握りしめる。
「僕、これから冒険に出るんだね!」
「はい。俺があなたを必ずお守りします」
王子を馬に乗せ、ライオはルナの丘を目指した。そこからギレー渓谷を目指す。馬を引きながらライオは歩いた。ルナの丘にたどり着くと強い風が吹いて来る。それがただの風ではないような気がした。ふと父親の顔が思い浮かぶ。目の前にはルナの樹があった。
「親父、俺、行ってくるよ」
小声で言ったつもりだったが王子には聞こえていたらしい。
「ライオのお父さん、ここにいるんだ」
「はい。ずっとここで遊んでもらっていたんです」
ライオの言葉に王子は笑って、きゅっと両手を体の前で握った。そして目を閉じる。まるで神への祈りのようだ。
「ライオのお父さん、ライオは僕を守ってくれるよ。いつも僕に優しくしてくれる」
また風が吹く。父親は確かに自分を見ていてくれているのではないかと思う。生と死を分かつもの、それは薄い膜のようなものなのかもしれない。それでも生と死は絶対に交わることがない。
「ライオのお父さん、嬉しそうだね」
ライオはその言葉に泣きそうになった。だが、今は泣いている場合ではない。自分にはギレー渓谷に向かうという目的がある。ライオは北へ向かって歩き出した。太陽が沈み始めるころ、ライオはそこで休憩を入れることにした。すっかり山中に入っている。今日は出発が遅かった。その分、明日早めに起きて出発すればいい。ギレー渓谷にある集落に着くまではもちろん野宿だ。この辺りはあまりにも自然が豊かで、人が定着せず、村や町もない。だからこそ静かなギレー渓谷に療養に行くというのはルナリアでは珍しい話ではなかった。渓谷は空気が美味しく、体にいいとされている。だが一度行くと二度と帰ってこられないという噂があるのもまた事実である。ギレー渓谷は死に近付いている人を呼び出す、というのだ。ライオはそれが不安だった。杞憂だといいが、向こうに着いたら女王の生存を確認しなければいけない。以前まで手紙が度々送られてきていたが、それもここ数年は途絶えている。ライオは考えながら焚火に火をつけた。これも父が教えてくれた。
「わあ、ライオすごいね」
「火があれば動物が近づいてこないのです」
「そうなんだ」
王子がライオの隣に座って肩によりかかって来た。王子の髪がライオの日焼けした腕に触れる。サラサラでくすぐったい。
「ね、ライオ。僕この前、君にお手紙を書いたと思うんだけど」
「はい、とても嬉しかったです」
「そうじゃなくて!」
ライオには王子の意図が読めず、考えた。そんなライオを見て王子が頬を膨らませる。
「僕、君にラブレターを書いたんだけど」
「あ!」
ライオは顔が熱くなってくるのを感じた。王子はあの手紙で自分に告白をしてくれていたのだと今更になって気が付く。
「ね、ライオ。僕、君が大好き。君は?」
ライオは困った。嬉しくないわけがない。だが自分はただの騎士に過ぎない。王子の相手になどなれない。身分が違い過ぎる。
「お、俺は・・・」
ライオはすぐ答えられない自分が嫌だった。「やっぱり、難しいよね」
王子は寂しそうに笑ってライオから離れた。彼にも身分の差についてよく分かっているのだろう。王子にまっすぐ見据えられる。
「僕はこれからもずっとライオを好きでいる。それだけは忘れないでね」
王子の言葉にライオは頷くのが精一杯だった。自分をここまで信じて受け入れてくれる人はなかなかいない。好き、というたった二文字には収まりきらない感情が湧いて来る。
「ライオ」
名前を呼ばれてそちらを向くと、王子に唇を奪われていた。王子がぺろりと唇を舐める。
「ライオとキスするのは僕だけ」
「で、殿下。駄目です、こんな」
ライオがうろたえていると、王子が笑った。
「ね、ライオ。お腹空いた。早くご飯」
いろいろ言いたいことがあったが、口では王子に敵わないと知っている。ライオは黙って夕餉の支度を始めることにした。
⒒・明け方が近づいている。ライオは火の番をしていた。王子はライオの隣ですやすやと眠っている。王子は夕飯をたっぷり食べていた。今日の彼を見ていて、やっと人並みに食べていると感じた。ライオは王子の頭を撫でながら、あたりを探った。滅多に見かけないがこの辺りには狼がいる。自分だけならまだ何とかなるが、今日は王子がいる。警戒するに越したことはない。
「ライオ、君は寝ないの?」
王子が目を覚ましたらしい。頭を軽く持ち上げた。
「俺なら大丈夫ですよ。よく休んでください」
ライオの言葉に王子は起き上がった。
「ライオが寝ないなら僕も寝ないもん」
「殿下・・・」
王子がライオに抱き着いて来る。ライオが彼を抱き寄せてやると満足そうに笑う。
「ライオ、だーいすき」
「っ・・・・・」
王子の可愛らしさに理性を奪われそうになる。だがライオはなんとか踏みとどまった。自分の任務を頭の中で繰り返し唱える。あくまでこれは王子の護衛という任務なのだと。
「ちぇ、ライオってば頑固だなあ」
どうやら王子は狙ってやっていたようだ。その周到さにライオは恐ろしくなった。いわゆる色仕掛けである。王子は笑う。
「ライオ、好き。ぎゅってして」
そう言われて腕を伸ばされる。ライオは困ったが彼を抱きしめた。火で温められたせいか、王子の体がいつもより温かい。
「ライオはこうして僕を抱っこしてくれるのになんでキスはしてくれないの?」
そう純粋に問われてライオは返事に困った。だが答えないわけにはいかない。ライオは自分なりに必死に言葉を紡いだ。
「殿下とキスされるのは俺ではなく、あなたのもとに嫁いでくる姫様です」
そう自分で言っておいて声が震えた。本音ではそんなのは絶対嫌だった。だがもう決めたのだ。自分は王子ら王族とルナリアを守るのだと。だが自分の意思が揺らいでいることは無視できない。とても危険な状態だ。
「姫様?僕って誰かと結婚しないといけないの?」
王子が首を傾げて聞いて来る。ライオは頷いた。その方が王子も幸せだと、なんとか自分で思いこもうとした。
「そんなのやーだよ、だ」
「殿下?」
いつの間にか、王子に自分の両頬を掴まれていた。王子の唇は柔らかい。ふにっという唇の感触でキスをされていることに気が付く。今度は先ほどとは全く違った深いキスだった。王子の舌がライオの口内に押し入って来る。いけない、とライオは思った。だがそんな理性は数舜しか持たなかった。いつの間にかライオは無我夢中で王子を求めていた。王子の頭を手で抱き寄せて、自分に抵抗できないようにした。ライオの貪るようなキスに王子は一生懸命応えてくれている。
「ん・・っつ・・・らい、お、すき」
王子の舌を吸って口内をこれでもかと犯した。王子がそれに感じてくれている。ライオの中の雄としての本能がそうさせている。
「あ・・ら、いお・・・・もっと」
いよいよ我慢出来ず、ライオは王子を地面に組み敷いていた。王子がそんなライオを見て笑う。それがまた艶っぽい。
「来て、ライオ」
ライオはそこで自分がしていることに気が付いた。慌てて王子から離れる。
「殿下、申し訳ありません」
王子がつまらなさそうに起き上がる。
「ライオの意気地なし」
ライオはただ頭を下げ続けた。いつの間にか朝日が昇ってきている。そろそろ朝食を食べて出発した方がいいだろう。ライオは焚火に集めておいた乾いた枝を入れて火が消えないようにした。
「すぐ食事の準備をします」
ライオは自分の欲求の深さにおののいていた。まさか、自分があんなに乱暴に王子を抱こうとしてしまうとは思わなかった。それは今までの反動であることは分かっていたが、あまりにも乱暴だ。王子にケガをさせてしまう所だった。
「殿下、俺が怖くないのですか?」
「ライオが怖いわけないでしょ。ずっと僕を愛してくれてるじゃん」
やはりライオが王子を好きでいるということは王子にも分かっていたようだ。ライオはどう返事をしていいものか困った。だが伝えるべきことは伝えなければならない。
「俺が殿下を好きでいるわけにはいかないのです。俺はただの騎士であなたは王子だ。身分の差がありすぎます」
ライオの言葉に王子が息を吐く。王子は何かを考えているようだ。
「ね、ライオ。僕を信じてくれる?」
「え?」
王子のことはずっと信じている。ライオはその言葉に虚を突かれた。王子が何をしようとしているか、ライオにはさっぱり分からない。そんなことをしている内に焚火にあてていた鍋の中の水が沸騰してきた。ライオはその中に、干し肉と生の米、スパイスを数種入れる。しばらく煮込むといい香りが漂い始めた。
「わあ、これも美味しそうだね」
「少し癖があるのですが、美味いですよ」
「ライオはお料理も出来るんだね」
「簡単な物だけです」
しばらく煮込んで、食器に盛り付ける。王子はそれを美味いと平らげた。王子が喜んでくれるたびにライオは嬉しくなる。そして愛情が深くなるのを感じていた。食べ終わり片づけ、焚火を消す。二人は再びギレー渓谷を目指した。
⒓・ギレー渓谷を目指して、二日目の昼。王子は初日にライオが購入した菓子をバリバリ食べていた。
「ね、ライオも一緒に食べよう」
馬に跨ったままの状態で王子が菓子の入った包みを差し出してくる。ライオはあまり甘いものが得意ではない。だが言われるがまま食べてみるとそこまで甘くなかった。噛むとバリバリと小気味のいい音が響く。
「美味いですね」
「でしょう?美味しいの、これ!」
王子といるとなんだか自分らしくいられる。ライオはずっとそう感じている。彼に出会えて本当に良かったとライオは噛みしめていた。
「ね、ライオ。ギレーまであとどれくらい?」
「そうですね、もう一晩野宿をして早足で歩けば明日の夕方には着けるかと」
「ライオばっかり歩かせて大変じゃない?」
「いいえ。俺は慣れていますから」
しばらく足場の悪い山道を馬を引いて歩く。でこぼこの道に王子は驚いたり、笑ったりした。もう太陽が沈みかけている。ライオは剣の柄を握った。いつの間にか狼に取り囲まれている。王子が小さく悲鳴を上げる。ライオは慌てなかった。狼たちが牙を剥き出しにしてこちらを威嚇してくる。ライオは一番大きな狼を睨みつけ叫んだ。狼たちがそれに怯えてちりじりになって逃げていく。
「ライオ、すごい」
「殿下、怖い思いをさせて申し訳ありません」
「ライオのせいじゃないよ。すごいもん」
ライオは再び山道を歩きだした。ようやく一つ山を越えた。渓谷までもう間もなくだ。今日はここで休むことにした。王子がごろりと横になって火を見つめている。彼の髪の毛と瞳が火を受けてキラキラと輝いている。
「明日ついにギレー渓谷に着くんだね」
「はい。きっと女王陛下も喜ばれるでしょう」
「そうかな?」
ライオは王子を見つめた。彼がライオを見て寂しそうに笑う。
「母上は僕を恨んでいるかもしれない」
「そんなこと・・・」
王子はそのまま目を閉じてしまった。疲れていないはずがない。ここまで慣れない長時間の移動をしている。ライオは彼に、持ってきていた自分の上着を掛けてやった。ここまで歩き通しのライオも当然疲れている。少し休もうと目を閉じた。気が付くと空が赤い。もう明け方だった。ライオはあたりを確認した。特に異常もない。王子もすやすやと寝息を立てている。ライオは彼の頭を撫でた。王子が可愛くて愛おしくてたまらない。ライオは思わず呟いていた。
「俺はあなたが好きです、サーシャ殿下」
「それ、本当?」
ぱちりと王子が目を開けた。どうやら彼は起きていたらしい。ライオは困って頷いた。嘘を吐く理由などない。
「僕も。僕もライオが大好き!ずっと好き!」
「殿下」
王子がライオに飛びついて来る。それをライオは受け止めた。二人はしばらくじゃれ合っていた。お互いに笑い合う。すごく幸せな時間だ。ライオは王子を膝から降ろした。そろそろ出発する準備をしなければならない。朝食を食べた二人は、再び出発した。
⒔・夕日が岩肌を照らしている。ライオはあたりを見回しながら歩いていた。馬も疲れてきている。ここはもうギレー渓谷のはずだ。集落まで間近だろう。
「うわあ、ここがギレー渓谷」
馬の上で王子が珍しそうにあたりをきょろきょろと見回している。近くに川が流れているのか、水が流れる音がする。ライオは更に奥まで進んだ。王子がはっと息を呑む。そこには確かに集落があった。その瞬間、王子が馬から飛び降りて走り出した。彼の逸る気持ちも分かる。向こうにいたのは女王その人だったからだ。
「母上!」
「サーシャ!」
二人は抱き合った。ライオはホッとしながらその光景を見つめていた。女王は存命だった。渓谷の噂はただの噂だったのだ。人という生き物は噂が大好きなのである。それはどんな時代も変わらないだろう。
「サーシャ、どうやってここに」
「ライオが連れて来てくれた!」
王子が嬉しそうに笑ってライオを指さす。女王がライオに頭を下げた。それに驚いてしまうライオである。
「女王陛下、頭を上げてください。私はただ殿下をお守りしていただけです」
「いいえ、ライオ。シュナから話は全て聞いています」
「え?」
ここで何故シュナの名前が出てくるのだろう。ライオは戸惑いを隠せなかった。女王が笑う。
「シュナを通して城の様子を探っていたのは私です。サーシャのこともシュナに仕える精霊に任せていました。サーシャ、この母を許してくれますか?」
「母上は僕を嫌いになったんじゃないの?」
女王は王子を抱きしめた。
「ずっとあなたに辛い思いをさせているのは知っていました。私はどうしてもここを離れられなかったのです。でもその役目ももう終わった」
女王が空を見上げる。既に空は濃い紫色に変わって来ていた。もうすぐ夜が来る。
「サーシャ、ライオ。理由は私の家で話します。来て頂戴」
二人は女王に頷いた。女王の家は他の家と変わらず、質素な造りだった。それにライオは自分の生家を重ねる。父、母と三人で暮らした実家を思い出す。父は騎士の仕事が休みになると必ず家に帰って来てくれた。ライオはそれが毎回楽しみで、父の帰ってくる日は必ず家の外で待っていた。
女王は二人の為に甘いお茶と菓子を出してくれた。ライオはどうしたものかと迷って、それに口を付けた。熱くて甘いお茶は疲れた体に沁みる。焼き菓子もまた美味い。
「二人にちゃんと話さなくてはいけませんね」
女王は語り始める。王子とライオは、彼女の言葉に耳を傾けた。
・・・事の発端は今から十九年前に遡る。それは城に仕える侍女の妊娠だった。侍女は自分の腹に宿るのは国王の子だと言ったのである。その時、国王と女王の間に子供はいなかった。そのため、周りの人間は慌てた。侍女の子供が生まれれば、その子に王位継承権が回ってくることになる。国王はこの時、威厳と自信にあふれた男だった。ライオもそれは知っていた。今の姿とは、かけ離れているので別人だと勘違いしてしまうくらいだ。国王はその侍女を抱いたらしい。健康で若かった彼女はすぐ妊娠した。当然、女王はそれに怒り狂った。侍女を城から追放しようとしたのである。だが女王には子供がいない。そのため、彼女の意見は通らなかった。それどころか、侍女を愛妾にという声が響いたくらいだ。だが、そのすぐ後、侍女が病で倒れたのである。大事な王位継承権を持つ子供を孕んでいる侍女を死なせるわけにはいかない。女王も自分に子供がいないことをなんとか受け入れ、彼女の看病をした。そこで、女王自身が身籠っていることに気が付いたのだ。女王は恐れた。可愛い子供たちを王位継承権という権利の為に争わせたくなかったからだ。女王の中では、侍女の子供も自らの腹の中にいる子供も、同じくらい大事な存在になっていた。だから王子を秘匿という形で産んだのだ。そこまで話を聞いていたライオはハッと気が付いた。
「では、サーシャ殿下には腹違いのごきょうだいがいらっしゃるのですか?」
ライオの言葉に女王は首を横に振る。
「侍女・・・イライザの子供は死産でした。やはり彼女のかかった病気の影響が大きかったのでしょう。イライザ自身もそれがショックだったのだと思います。小さなサーシャをとても可愛がってくれましたが、イライザは病気になってしまいました」
女王は話を続けた。サーシャが表向きでは侍女の子供だと認知されたこと、そして女王はイライザを看病するためにギレー渓谷へ向かったことを。王子はその時に自ら牢に閉じこもったのだ。今から十三年前の話である。
「じゃ、じゃあ僕は母上の本当の子供なの?」
王子がおそるおそる、女王に尋ねる。
「そうですよ、可愛いサーシャ」
「でも、イライザさんは?」
王子の言葉に女王が寂しそうに目を細める。
「彼女はつい先日亡くなりました。ずっと危ない状態が続いていたのです」
「そうだったんだ」
王子が顔をうつむける。王子にとって死は身近なものだ。ライオもたまらなかった。
「サーシャ、あなたはこれからどうしますか?あなたは国王に・・・・」
王子が女王の言葉を遮るように言う。
「僕、牢の中でいろいろな本を読んだんだよ。そこで分かった。僕は王族という権利を放棄する。普通の市民として生きる」
「サーシャ!なんてことを!」
女王は驚いている。無理もない。ライオだって同じくらい驚いている。王子はライオに抱き着いてくる。ライオは思わず彼を抱きとめていた。
「僕、国を守りたい。ライオと一緒に!」
「サーシャ、では我が国の政治はどうするつもりなのですか?」
とても重要なことだ。王子は笑う。
「王政はもう古いよ。みんなで考えて、みんなでいい国にしよ。王様が一人で威張っている時代はもう終わり」
「サーシャ、あなたという子は」
女王が額に手を当てている。ライオとしてはなにも発言できなかった。王子が自分を選んでくれたこともまだ信じられない。あの時、王子は自分を信じて欲しいと言った。このことだったのだとようやく分かる。
「ライオ、あなたはどうなのですか?騎士として公正に判断するのです」
女王にそう言われると緊張するが、ライオは無意識に王子を抱き寄せていた。
「俺もサーシャ殿下と共に国を守ります」
「ライオ!本当?本当にいいの?」
「はい」
女王が優しく笑った。その笑顔はシュナと同じくらい愛で溢れたものだった。
「二人共、よく分かりました。国王もきっとあなたたちの想いを受け入れてくれるでしょう」
女王の言葉が心強い。二人はお互いの顔を見て笑い合った。
⒕・ライオとサーシャは女王と共にルナリア国に帰って来ている。国王にサーシャは自分なりに考えたことを精一杯話した。それは隣で聞いていたライオも当然知っている。サーシャは政治を王族ではなく民にゆだねることや、自分を王族ではなく、市民として認めて欲しいと国王に要求した。国王はそれを聞いて面白そうだと呟いたのである。もう夜だ。二人は宿舎にあるライオの部屋にいる。
「ね、ラーイオ」
後ろからサーシャに甘えたように抱き着いてこられて、ライオはびくっとなった。彼の可愛らしさにライオはすっかりやられてしまっている。今まで、よく理性が持ったものだと自分を褒めてやりたいくらいだ。
「殿下、俺は・・・」
「もう殿下じゃないよ。ただのサーシャだよ」
「さ、サーシャ」
言葉にすると、より自分の心臓が跳ね上がるようだ。彼を抱きたい、今すぐ触りたい、ずっとそう願っている。
「なあに?ライオ」
ライオはサーシャを抱き上げた。もう我慢できない。美味しそうな餌を目の前に、お預けを食らった犬のような気持ちだ。
「好きだ、サーシャ」
「うん、ライオ、僕も君が大好きだよ」
彼をベッドに押し倒すとサーシャが笑った。
「ライオって時々、野性の狼みたいだよね」
「嫌ならしない」
むすっとライオが膨れるとサーシャがまた笑い声をあげる。
「ライオが我慢できないんでしょ」
ライオは言葉に詰まってしまった。サーシャの言うとおりだったからだ。相変わらず口では彼に敵わないらしい。
「俺はサーシャが欲しいんだ」
「うん。ライオにあげるよ。大好きだもん」
二人はそっと口づけ合った。愛しているという言葉だけではもう足りない。お互いの心に、体に、この気持ちを刻み付けたい。ライオはサーシャの服をたくし上げた。白い肌が露わになる。それにライオはドキリとした。この間、一緒に風呂に入った時はあまり見ないように気を付けていたが、今日は違う。彼の全てを目に焼き付けたかった。彼の一瞬一瞬を忘れたくない。サーシャの胸を優しく撫でる。サーシャはくすぐったいのか笑った。くに、と乳首を優しく摘まんだ瞬間、サーシャが悲鳴を上げる。どうやら不思議な感触だったらしい。サーシャがライオの手に縋って来る。
「ライオ、僕、おかしいよ。なんか胸が熱い」
「大丈夫だよ。俺も熱いから」
うん、とサーシャがライオに頷いて来る。ライオはサーシャの乳首を捏ねるように撫でまわした。先程まで柔らかかったものがだんだん硬く芯を持ってくる。
「あ、ライオ、そこばっかり、嫌だ!」
面白くなって両側の乳首を優しく捏ねていたら、サーシャにいやいやと抵抗された。だが、つい悪戯心が出てしまうライオである。サーシャの言葉を無視して今度は乳首を口に含んでみる。誤って乳首を噛まないよう気を付けながら舌で味わう。サーシャの声にだんだん甘さが混じってくる。改めてサーシャが可愛いとライオは思った。もっとと喘ぎながらサーシャがライオの頭を撫でてくる。きっと気持ちいいのだろう。
「ん、っう、ああぁ・・・ライオ」
ライオがサーシャの下半身を撫でると、彼の雄はすでに屹立していた。じんわりと先が濡れている。
「あ、やだ・・・恥ずかしい」
困ったように言うサーシャにライオは更に興奮する。もっと彼を可愛がりたい。そして愛したい。そう思った。サーシャの履いていたパンツを下着ごとずりおろす。ぷるんと性器が露わになる。サーシャは恥ずかしかったのか、大きな目をぎゅっと閉じた。ライオは彼を自分の方に抱き寄せた。耳元で優しく囁いてみる。
「サーシャのすごく可愛い。触っていいか?」
「っつ!・・・や、ライオの馬鹿」
サーシャが真っ赤な顔でふるふると首を横に振っている。その姿がまた可愛らしい。
「サーシャ。俺にお前をくれるんだろ?さっきそう言った」
また囁いてみるとサーシャはようやく目を見開いた。ライオを涙目でじっと見つめて来る。
「優しくしてね?痛いのやだよ?」
「ああ、気を付ける」
サーシャの性器をそっと手で握るとサーシャが震えた。ライオの手は人より大きく、指も太い。そして、サーシャは人より小さい。サーシャの性器を手のひらで包み込むよう優しく愛撫してやると、サーシャが啼き始める。
「気持ちいいか?サーシャ」
「ん、うんっ、気持ちいい」
「イキそうか?」
「んっ、分かんない・・っやあ」
「あんまり自分でしたことないのか?」
「ん・・・僕、一人でしたことない」
ライオは起き上がってサーシャを膝に乗せてやる。サーシャは真っ赤な顔で荒い呼吸をしていた。くたりとライオの肩にもたれかかって来る。ライオは彼の額に口づけた。急な性行為の刺激に体が耐えられなかったのだろう。ライオはゆるゆると指で彼の性器を扱いてやる。サーシャは荒い呼吸をしながら喘いでいる。くちくちと音がする。
「んう、ああぁ、あああ」
ぴゅっと精液がわずかだが飛び散った。
「っはあ、はあ・・・・」
「サーシャ、またしような」
ライオがそう言って彼の頭を撫でるとサーシャはコクリと頷いた。そんなところも可愛らしい。サーシャの隣に自分も寝転がる。市民になったサーシャは、学校に通い始めていた。年齢は十九のサーシャだが、ちゃんと学校に通った経験がない。そんなサーシャにアレイは、一年間学校に通ってみてはどうかと進めたのだ。サーシャは学校に通うかどうか、かなり悩んだようだった。はじめは出来ないとアレイに断りを入れようとしていたサーシャだったが、アレイはいつもの必殺スマイルを彼に炸裂させたのである。
「サーシャ様、学校が終わったらライオ隊長があなたを迎えに行きますよ。でしょう?隊長」
勝手な約束にライオは驚いたが、サーシャはそれを聞いて嬉しそうに笑った。そんな笑顔を見てしまえば断れるわけがない。それから毎日、ライオは朝と夕方にサーシャを学校まで送り迎えに行くようになった。
「ん、ライオ。僕、寝てた?」
まだサーシャには快感の余韻が残っているのか、意識がぼうっとしているようだ。ライオは彼の頭を優しく撫でる。
「気持ちよかったか?」
「ん。えっち初めてした」
「えっちじゃないぞ。まだ挿れてない」
ライオの言葉にサーシャは固まった。そして絞り出すように言う。
「まだえっちじゃなかったんだ・・・」
「いいさ。またしよう」
「うん」
お互いに見つめ合って笑った。サーシャがライオの体のそばにすり寄って来る。彼の体温は変わらず高く、熱い。先程自分がイケていなかったせいか、ライオの下半身が熱を持ち始めている。サーシャはそれに気が付いたようだ。彼は真っ赤な顔でライオに言う。
「ねえ、やっぱり今する?」
「このままだとサーシャに乱暴しそうだ」
「ひええ。それって痛いの?」
「嘘だよ。優しくする」
サーシャの汗の匂いを感じてライオはますます興奮した。サーシャを優しく、だが動けないように組み敷く。サーシャがぼんやりとこちらを見つめてきた。
「えっちって気持ちいい?」
いつもより甘ったるい声でサーシャが尋ねて来る。ライオは彼に答えた。
「ああ。ゆっくりするよ。きっと気持ちいい」
「うん、大好き。ライオ」
ライオはサーシャの唇にキスを何度もした。首筋、胸とだんだん下へ移動していく。サーシャはキスの度に体を震わせる。
「ん、らい、お」
ライオはサーシャの尻を優しく撫でた。サーシャがそれに反応する。ライオは彼の後孔に指を当てた。
「サーシャ、もう少し力を抜けるか?」
「うん」
サーシャは、かなり汗をかいている。それはライオも一緒だった。夜になり随分涼しくなったが、今は真夏だ。窓は開いている。それでも暑いことに変わりない。ライオがぐっと指に力をこめるとサーシャが顔を歪ませる。きっと苦しいのだろう。ライオは慎重に指を奥に進めた。押し広げるように指を中に入れていく。
「ん、ライオ、お腹苦しい」
「そうだよな。大丈夫。ゆっくりする」
指を一回、ずるっと引き抜いてもう一度挿入する。少しずつ柔らかくなってきた。ライオが指の本数を増やし更に奥を攻めると、サーシャが突然喘いだ。
「や、なんっ、か・・・へん」
どうやら気持ちいい所に偶然当たったらしい。ライオはそこを指の腹でぐりぐりと捏ね回した。
「んぅ、あ、ライオ、そこ気持ちいい」
サーシャが感じてくれて、ライオは嬉しかった。だが、指では限界がある。ライオは指を引き抜いた。
「サーシャ、挿れていいか?」
「ライオの・・・」
サーシャが呟いて真っ赤になった。彼は頷く。
「ライオと一緒に気持ちよくなれるね」
「ああ。そうだよ」
ライオは自分の雄を彼の尻にあてがう。サーシャがぎゅっと体を強張らせた。
「サーシャ、怖いか?」
「うん。でもライオだから平気だよ」
ライオはサーシャの中へ押し入る。その圧力にサーシャは叫んだ。
「あ、らい・・お、苦し・・・ン」
「サーシャ、大丈夫。もうちょっと」
サーシャがライオの背中にしがみついて来る。それがまた可愛くて仕方ない。ライオは更に奥を目指した。もちろん、ライオもサーシャに締め付けられて苦しい。そして今すぐにでも達しそうだった。それをなんとか堪える。
「あ、ライオ・・ライオ」
ライオが入って来るのが苦しいのかサーシャの腰ががくがくと震えている。
「サーシャ、入ったよ。もう動くから」
「うん、好き、大好きだよ、ライオ」
「俺もだよ、サーシャ」
ライオがゆっくり律動を始める。サーシャの小さな体が一緒に揺さぶられている。
「ああ、んあ、らい、お」
「サーシャ、可愛い。ずっと俺のだっ・・」
「んん、あ、ライオ、僕・・・もう」
「一緒にいこう」
「っああぁぁ」
二人はベッドに並んで横になっていた。
「ライオとえっちしちゃった」
照れたようにサーシャが言う。ライオは彼を抱き寄せた。愛おしくてたまらない。
「サーシャは本当に可愛いな」
ライオがそう呟くとサーシャが困ったようにこちらを見上げてきた。
「僕、男なのにこのままで大丈夫?」
「サーシャはそのままでいい」
ライオがそう言って彼の頭を撫でるとサーシャが抱き着いて来る。
「ライオ、僕を地下から連れ出してくれて、本当にありがとう」
「いや、俺は何もしてないよ。サーシャの意思でここまで来たんだ。すごいよ」
「ライオ・・・」
二人はまた口づけ合った。明日も二人は忙しい。早めに休んだ方がいいだろう。ライオが燭台の火を消すと月明かりが部屋を照らす。
「ライオ、おやすみなさい。大好きだよ」
「サーシャ、おやすみ。俺もだよ」
ライオは永遠の愛を彼に誓う。 完
0
お気に入りに追加
22
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

神獣の僕、ついに人化できることがバレました。
猫いちご
BL
神獣フェンリルのハクです!
片思いの皇子に人化できるとバレました!
突然思いついた作品なので軽い気持ちで読んでくださると幸いです。
好評だった場合、番外編やエロエロを書こうかなと考えています!
本編二話完結。以降番外編。

魔王様の瘴気を払った俺、何だかんだ愛されてます。
柴傘
BL
ごく普通の高校生東雲 叶太(しののめ かなた)は、ある日突然異世界に召喚されてしまった。
そこで初めて出会った大型の狼の獣に助けられ、その獣の瘴気を無意識に払ってしまう。
すると突然獣は大柄な男性へと姿を変え、この世界の魔王オリオンだと名乗る。そしてそのまま、叶太は魔王城へと連れて行かれてしまった。
「カナタ、君を私の伴侶として迎えたい」
そう真摯に告白する魔王の姿に、不覚にもときめいてしまい…。
魔王×高校生、ド天然攻め×絆され受け。
甘々ハピエン。

【完結・BL】DT騎士団員は、騎士団長様に告白したい!【騎士団員×騎士団長】
彩華
BL
とある平和な国。「ある日」を境に、この国を守る騎士団へ入団することを夢見ていたトーマは、無事にその夢を叶えた。それもこれも、あの日の初恋。騎士団長・アランに一目惚れしたため。年若いトーマの恋心は、日々募っていくばかり。自身の気持ちを、アランに伝えるべきか? そんな悶々とする騎士団員の話。
「好きだって言えるなら、言いたい。いや、でもやっぱ、言わなくても良いな……。ああ゛―!でも、アラン様が好きだって言いてぇよー!!」


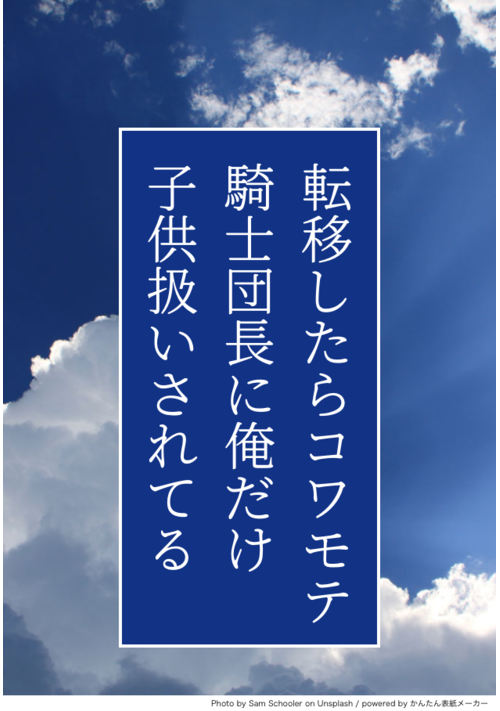
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。


帝国皇子のお婿さんになりました
クリム
BL
帝国の皇太子エリファス・ロータスとの婚姻を神殿で誓った瞬間、ハルシオン・アスターは自分の前世を思い出す。普通の日本人主婦だったことを。
そして『白い結婚』だったはずの婚姻後、皇太子の寝室に呼ばれることになり、ハルシオンはひた隠しにして来た事実に直面する。王族の姫が19歳まで独身を貫いたこと、その真実が暴かれると、出自の小王国は滅ぼされかねない。
「それなら皇太子殿下に一服盛りますかね、主様」
「そうだね、クーちゃん。ついでに血袋で寝台を汚してなんちゃって既成事実を」
「では、盛って服を乱して、血を……主様、これ……いや、まさかやる気ですか?」
「うん、クーちゃん」
「クーちゃんではありません、クー・チャンです。あ、主様、やめてください!」
これは隣国の帝国皇太子に嫁いだ小王国の『姫君』のお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















