4 / 8
第二章:後半
しおりを挟む
ーーーーーーーーーーー次の日ーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーー休日ーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーー6:50---------------
俺は朝、起きる。
「っく~・・・」
ベットから地面に降り立つ。
身体を伸ばして、全身の固まったように感じる身体をほぐしていく。
扉を開けて、下に降りて行くと先に妹が起きており、朝ごはんの準備をしていた。
「おはよう、兄貴」
「おはよう、俺より早いなんてな」
「何だか眠れなくてね」
妹はそう言って、テーブルの上に白身の魚と豆腐の味噌汁とほうれん草の胡麻和えと真っ白のご飯が置かれていた。
「美味しそう」
「普段はやらないだけなのよ?」
「誰に言い訳してるんだよ」
「いや、兄貴が私って料理できない子なんじゃないかなって思ってる気がして」
「そんなことはないけど」
「本当?」
「本当だって」
「ならいいけど」
2人分の皿が乗り終え朝食の時間を始められる。
「美味いなこれ」
「そう?」
妹は素っ気無い感じだけど、口元が微笑んでるのが見えて俺の言葉は間違って無かったんだと安心する。
「今日1日大丈夫なのか?」
俺は予定があるのか確認しておく。
もしもあるってなら妹を置いて俺1人で進まなければならないだろう。
「大丈夫、今日1日は都合空けといたから」
「そうか」
準備は大丈夫そうだった。
朝食も軽く済ませ、俺は自室へと向かう。
その際、妹とは離れて行動する。
妹は妹の部屋にゲーム機の台があるので、どうしても別々になる必要があるのだ。
「じゃ、また」
「うん、ゲームの世界で」
俺は扉を閉めて、自分の部屋にあるゲーム機を起動する。
VRゴーグルとケーブルを繋げて、俺はベットに横たわりながら顔に装着する。
電源が入ると、俺は次第に意識が遠のいていくのが分かる。
ーーーーーーーーーーーーーゲームの世界ーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー9:00---------
次に目が覚めたのはトンネルの中だった。
あの独特の浮遊感があって、俺はゲームの中にちゃんと入れたんだなって思えた。
最初のワープポイントに到着すると、先に妹が来ていて彼女の姿を確認できた。
妹は普段、セーラー服を着てることが多いからか、ゲームの世界だと魔女の格好なので何だかにコスプレに見える。
「なに、じろじろ見て」
「いや、魔女の格好ってハロウィンっぽいなって思って」
「まぁ、そうだけど」
「俺は海パンだろ?季節感が合わないなって思ってね」
「・・・」
「・・・」
「じゃ、行こっか」
「ああ」
変な間があったけれど、何か言うわけでもなかった。
俺達が向かうべきは雪原のシルバー・ウルフ退治だ。
欲しいのはアイスソード。話によれはシルバーウルフを退治すればドロップアイテムとして手に入るって話だ。
「雪原は・・・」
「あのワープポイントだろ?」
石碑に文字が刻まれている。
これに触れれば雪原。
恐らくじゃなく、確実にここに入れば雪原に行けるだろう。
「じゃあ、入るわよ」
「おう」
石碑に触れると、青い光が次第に大きくなっていく。
俺達は光に包まれる・・・。
ーーーーーーーーーーーーーー第1ステージ:雪原(朝方)ーーーーーーーーーーーーーー
数秒もしないうちに光が次第に弱まっていき、銀色の雪景色が次第に見えてきた。
「ここが・・・」
「寒っっ」
海パン一丁で、さび付いた剣だけを持ってるのが今の俺。
酷い格好だ。
ゲーム内だから雪の世界で低体温で死ぬ事は無いが、気分的に寒い気がしていた。
「そんな格好してるから・・・」
妹は少し呆れていた。
「仕方ないだろ、金ないんだ。このまま頑張るぞ」
「はいはい」
歩いていて気づいたことがあるが、確かに現実的な死は存在しないが、ゲーム的な死は存在する。
どういうことかと言えば、定数ダメージが自分に入る仕組みになっていた。
「妹よ」
「なに?」
「俺の体力が・・・赤だ」
「ねぇぇぇぇえええええええ!」
妹の声がフェードインしてくる。
「いや、でも死ぬわけじゃなさそうだ」
「でも一撃でも喰らったら死ぬでしょうが!」
「ははっ・・・」
乾いた笑いが出てくる。雪原なのだから乾いた笑いとはこれいかに。
湿地帯ではしっとりした笑いだろうか?
何て変なことを思う。
「ねぇ、私の邪魔しにきたの?それとも友達を助けるため?どっち?」
「友達を助けるに決まってるだろ」
「じゃあ、そのふざけた格好は何?」
「大丈夫だって、これでも何とかなるって。ゲームクリアした後って自分に制限かけてプレイするだろ?結構、そういうの慣れてるからさ。
大丈夫、大丈夫」
「不安しかない!」
雪原を2人で歩いてるときに、妹にそんな説教をされる。
「出てきたぜ・・・」
地面からずぼっ、ずぼっと何かが複数出てくる。
アイススライムって奴らだ。
道を塞がれてしまう。
だけど、相手はザコモンスター。
敵ではない。
「アクアランス!」
妹は水の槍を飛ばしてアイススライムを攻撃する。
氷相手に水の攻撃だからダメージの量は少ないはずだが、レベル差があるお陰でかなり効果的なダメージが入る。
「ひょおおおおおおっ」
変な掛け声と共に、俺は剣で突き刺して攻撃する。
別に黙ってても攻撃に変化は無いので声を出す必要は無いが、声を出すと気分的にやる気が出るのでそうしてる。
初期装備だが、レベル差が俺もあるのでアイススライムは結構簡単に倒せる。
「数が多いから面倒だけど、これなら簡単ね」
チャリン、チャリンとお金がどんどん増えていく。
経験値は少ないが、今欲しいのは前に進むための道と資金だ。
この2つを同時に満たせるのでアイススライムを素通りするわけにはいかない。
「道、開いたぜ」
「進むわ」
「OK」
俺は目の前の1体を切り倒す。
すると妹がそれに合わせて走って前進してくる。
先に妹の方が奥へと進んでいった。
俺もそれに続くように走っていく。
妹もただ黙って見てるのではなく、アクアランスを飛ばして道を進むのを援護してくれる。
俺達は取りあえずは第一ステージ突破ってところだ。
ステージを突破したと実感できるのはモンスターたちが境目からその先へは侵入してこない点にある。
このゲーム『アストラル・オンライン』はブロック事にステージが分かれてる。
第一ステージ、第二ステージ、第三ステージ(最終ステージ)に分かれてる。
ゲーム会社はわざと、その間の境目の間隔をあける事で体感的にステージを突破したと実感させるというわけだ。
そして、ステージの移動をする境目が実は間隔があって、そこは安全地帯。
モンスターが出入りすることが出来ない場所になってる。
そうすることでステージごとに準備を与えられるので難易度が簡単になってるというわけだ。
初心者でも楽しめるよう設計してるのだ。
ーーーーーーーーーーーー第2ステージ:雪原(昼頃)ーーーーーーーーーーーーーーーー
ダメージはそこまで入ってないので、俺達はそのまま準備を整える事無く第2ステージへを向かっていく。
「気のせいか、吹雪が強くなってきた気が・・・」
「シルバー・ウルフに近づいてるのかも」
「どういうことだ?」
「シルバーウルフが歩く所に吹雪ありって掲示板の投稿に見かけたの」
「吹雪が味方してる?」
「かもしれないわね」
「そうだと厄介だな」
シルバーウルフは俺達がゲームに飽きてやらなくなり始めてから登場したモンスターだ。
俺達はアップデート前のゲームしかしたことがないから、敵がどんな感じなのか想像がつかないのだ。
「止まって」
「どうした?」
妹に制止され、俺は思わず走るのを止めてしまう。
「あれ」
「ん?」
涼音が指差す先には真っ白のオオカミが居た。
「シルバーウルフ?」
「早いお出ましだな、手間が省けるってもんだ」
俺は切りかかる。
だけど、あっさり倒されてしまう。
後には雪だけが残る。
「これは・・・」
「なんだよ、こんなあっけないもんなのか?」
「モドキよ」
「モドキ?」
「ええ、シルバーウルフの偽者ってこと」
「なんだよ、そんなモンスターも居るのか」
「そうみたいね、でも、こいつらを倒していけばそのうち親玉がやってくるかも」
「ってことは倒し続けてればいいんだな?」
「多分・・・」
「よっしゃ、狩って狩って狩りまくるぞ!」
俺は剣を振るって、モドキ共を倒していく。
残るのは雪だけという点から、俺は何だか氷の彫刻を相手に戦ってるような気分になる。
反撃の意思は無く、ただ、道を邪魔するだけの存在。
「アクアランス」
妹も魔法を唱えて、サクッと倒す。
「吹雪で敵が見えにくいな・・・」
何だか吹雪が段々と強くなってきたような気がする。
「そうね、でも、集中しないと」
「分かってるよ」
悪天候の中、俺達はひたすらにモドキ達を倒していく。
経験値も薄く、金も手に入らないので何だか作業感が強い。それでも、これをしないと目的が果たせないのだから仕方が無い。
「涼」
妹が短い言葉で俺を呼ぶ。
「なんだよ、無駄話なら後で聞くぜ?」
「そんなんじゃないわ、見て」
残ったモドキたちが奥へ逃げていく。
「ってことは第3ステージに行けるってことか?」
「そういうことになるわ」
「アイテムくれ」
「何のアイテム?」
「攻撃系のアイテムとか持ってないか?」
「火炎球なら」
野球のボールのような見た目で、持ってるときは普通のボールだが敵に命中すると発火するという代物だ。
氷結系の敵にダメージ大と書かれてる。
「いいね、頂戴」
「外さないでよ?」
「わーってるって」
俺は妹からアイテムをもらう。
それをポケット・・・には仕舞えないのでパンツの中に突っ込んだ。
「それ、絶対返さないでね」
「なんでだよ、やばくなったらお前に返すよ」
「気持ち的に要らない」
「汚くないって!」
「汚いよ!」
そんなやり取りをしつつ、俺達は次のエリアに向かって行った。
ーーーーーーーーーー第3ステージ:雪山(夕方)ーーーーーーーーーー
時間帯が夕方になったからか、辺りは暗くなってきた。
先程の朝のエリアと比べて視界がかなり悪いと思う。
「気をつけろよ、最終エリアなんだ。ボスはここにいる筈だから」
「わかってるって兄貴」
奥に進むと、なにやらがさごそと動く物体を発見したのでボスかと思ったけれど、モドキたちだった。
「追うぞ」
「うん」
モドキたちは走って奥へ奥へとドンドン暗いほう、暗いほうへ行く。
太陽の光を雪原の山が覆い隠し、光が感じられなくなる方へ・・・。
「逃がすかよ」
俺はさらに追跡しようとするが、妹に肩を掴まれる。
「待って」
「なんだよ、大したことない奴らだぜ。ボスが来るまで・・・」
「来たの」
「来たって」
その言葉でハッとする。
もどき共とは違う何かが、そこにはいた。
見た目はモドキ共と多くは変わらない。
だけど、威圧感や、敵意はモドキ共とは明らかに別種だ。
違うと感じさせるのは白銀のような毛ではなく、真っ赤な燃えるような瞳がついてることだった。
「・・・」
疾駆。
例え話をしよう。
俺は現実世界で、街中で荒っぽい車を見かけた。
どうして荒っぽいと感じたのか?
それは、目の前を通り過ぎるときに風を感じたからだ。
歩道に居る俺はいつもあれを危ない運転手が乗っているものだと思っていた。
きっと俺が見たであろう車は法定速度なんて守る気は一切無いんだろう。
俺は今、それと同じことを思った。
何かが犯されてる暴風の気配。
シルバーウルフは妹に噛み付いていた。
「涼音!」
俺は剣を刺してやろうとオオカミの身体目掛けて突進するものの、いとも簡単に避けられ、それどころか妹が連れ去れることになった。
「くっ、このっ・・・!」
妹は魔法使いだ。杖で殴ることをしているが、役職とは違う行動を取ってるのだから本質ではないだろう。
魔法使いは魔法を他の役職よりも上手に扱うから魔法使いなのだ。
杖で殴るのが魔法使いではない。
つまりは、ダメージは大したものを入れられない。
「待て!」
シルバーウルフを追いかけるも、足が追いつかない。
身体能力の差だろうか。
俺の足では遠ざかる一方だ。
まるで乗り物に乗ってる相手と足で徒競走をしてるみたいに。
俺は諦めたくなってくる。
乗り物相手に本気で走るなんて馬鹿げてる。初めから勝負なんて成立してないのだと自分に言い訳をし始める。
足が次第に遅くなっていく。
氷結の定数ダメージが入ってる所為ではない。自らの選択で足が遅くなってるのだ。
どうせ妹はゲームなんだから死ぬわけ無い。
そんな言い訳が成り立つ。
だからこそ余計に俺は頑張るって行為を放棄しようと思うのだ。
走らなくてもいいじゃないか。
そんなことを考える。
遠くで何かが発光してる。青い光・・・。
妹の魔法だ。
アイツはまだ戦う気なんだ。
負けるつもりはないんだ。
なら、きっと追いつけるはずだ。
攻撃が刺されば、相手は動きを止めるはずだから。
走れば・・・行ける?
さっきまでの情けない考えを振り払い。俺は再び走り始める。
まだ始まったばかりじゃないか。
諦めるのは早いだろ?
「ぉぉぉぉぉおおおおおおお!」
「兄貴!?」
姿が見えた。
シルバーウルフは俺の方を始めて向いた気がする。
だけど、何処か嘲笑・・・。
見下したような、そんな笑みが感じられた。
獣とは思えない、人間臭さ。
海パンだもんな、馬鹿馬鹿しいよな・・・。
でも、俺は本気だぜ・・・?
俺は剣を手に持って槍投げの要領で投擲の準備をする。
遠いなら、足が遅いなら、別な方法で詰めてやれ。
「せーのっ」
俺は錆びた剣を投擲しシルバーウルフの身体に命中させる。
錆びた剣だろうが剣は剣だ。ノーダメージってことはないだろうと思うぜ。
「・・・!」
シルバーウルフはたまらず咥えていたものを地面に落とす。
俺はそれを地面に落ちる前にキャッチして、後退して距離を取る。
「さんきゅ、兄貴」
血のエフェクトが妹に入ってる。
ボロボロのマント、肌には傷跡のような模様が。
ダメージが大きいだろうと思えた。
「悪い、少し遅れた」
「大丈夫、体力は減ったけど死んでないもの」
「それならよかった」
「・・・」
シルバーウルフはこちらの方をじっと見てくる。
今の俺は武器が無く。手ぶらなわけだが、身体に刺さった錆びた剣が俺への警戒を高めてくれた。
コイツは何をしてくるんだ?他になにか秘策があるんじゃないのか?
そんな思いがあるのではと俺はコイツの考えが読めたように思えた。
「グリーン・ポーション」
妹は自分に回復アイテムを使った。
ゲージが黄色で危ない信号が出ていたが、緑になっていったのでひとまずは安心だ。
一撃でやられる心配は消えた。
どっちかって言えば俺は赤だから俺の方がやばかったりはするのだが。
「それって俺にも使える?」
「使えないわけじゃないけど、兄貴は定数ダメージ入るでしょ。それだったら私優先の方が無駄が少ない気がする」
「・・・それもそうだな」
俺が受けるであろう定数ダメージの分を妹は浮かせることが出来る。
だったら妹にのみ回復アイテムを使うってのは一応の筋は通ってると思う。
だけど俺がやられたとき、俺が拠点からこの雪原にまで戻る間はタイムラグがあることになるだろう。
ということは妹は1人でシルバーウルフと対峙しなければいけなくなる。
そうなるのは危険だろう。
できることなら、俺は生存していたほうがいい。
2対1って有利の状況を崩したくはない。
「アクアランス!」
妹は魔法を唱える。
シルバーウルフはそれに気づくとさっと避ける。
俺は道具袋から石ころを取り出し、投げつけて攻撃に一応参加する。
「無いよりはマシだろ・・・」
だけど、ひょい、ひょいと避けていく。
やっぱり剣が刺さったのは偶然か?
「アオォォォーン」
シルバーウルフが空に向かって吠える。
「なんだ?」
夕方といっても、真っ暗ではなかった。
けれど遠吠えと共に、世界が真っ黒に変わっていく。
ーーーーーーーーーーー第3ステージ:雪山(夜)ーーーーーーーーーーーー
今まで空には太陽があったはずなのに、動画の再生速度を上げたみたいに太陽があっという間に沈んでいく。
すると空は黒く染め上がり、満月が姿を表す。
「深遠の遠吠え」
「なんだそれ」
「シルバーウルフが使ってくる技の1つにそんなのがあるって確か掲示板に・・・」
「どんな効果なんだよ」
「私だって、分からないわよ!」
妹は悲鳴に近いような声で言ってくる。
悪寒。
体温が下がってるから感じるのではなく、生理的嫌悪感とでも言えばいいだろうか。
直感で自分は今、殺されるのだと理解できたような感じだ。
事実、そうなるんだろう。
頭で理解してるけれど、身体がそれに追いつかないなんてことはよくあることだと思う。
頭の中で格闘技のチャンピオンに勝てる妄想をすることがあるけれど勝率はいつも100%だ。
何故なら妄想なのだから自分のさじ加減でどうとでもなるからだ。
でも、今は違う。ウルフはゲームのAIだけど、それは1つの現実であり、今は戦うべき相手なのだ。
思い通りに行かない、行くわけがないんだ。
俺は今、宙に浮いてる。
肺の中に異物を感じる。
あぁ、俺は食われてるんだ。
「兄貴!」
剣の仕返しだろう。
血が流れ落ちる。
でも、これはゲームのエフェクトだから現実で死ぬわけじゃない。
死ぬはずがないんだ。
だけど、俺は今、恐怖している。
「うわぁああああああああ!」
スマホの電源をシャットダウンするときみたいに俺の意識はプツンと消え去った。
ーーーーーーーー???ーーーーーーーーーーーー
あれ・・・。
何してたんだっけ?
俺は教室で机に突っ伏すように寝ていたみたいだ。
腕には俺の顔の痕が少しだけついていて、赤くなってるのがその証拠だ。
「なぁ、りょう」
その声で俺を呼ぶのは誰だろう。
「誰・・・?」
「性質の悪い冗談だぜ、俺だよ、ほむら」
正面の席に座ってるほむらは俺の方へ身体を向けるために身体を捻って後ろを向くような格好をしていた。
授業中・・・いや、休み時間だろうか。
他の生徒はおらず、いるのは俺と、アイツだけ。
だから、そんな風に思ったんだ。
「他の人は・・・?」
「他のヤツは先に行ったんだ」
「なんだよ・・・。みんな冷たいんだな」
「ハハッ、そうかもな」
ほむらは楽しそうに笑う。
「お前は?」
「俺?」
ほむらは自分のことを人差し指で指す。
「お前も、他の生徒と同じように行かないといけないんじゃないのか?」
「そうかもな」
「じゃあ、なんで」
「お前、寝てただろ?」
「俺?」
「お前が起きて一緒に行かなきゃ意味無いだろ?」
「そっか」
「でも、お前は起きた。まだ間に合うぜ。一緒に行こう」
ほむらが言ってるのは移動教室のことだろう。
俺はアイツの言うとおり、一緒に行く事に決めた。
行くには立ち上がらなきゃな。
席に座ったままでは、一緒に行けないもんな。
寝ていたら余計に駄目だよな。
フッと世界が真っ暗になった。
だけど、不思議と恐くは無かった。
ーーーーーーーーーーー第3ステージ:雪山(夜)ーーーーーーーーーーーー
目の前は雪原だった。
それは奇跡と言えるような出来事だと思う。
ゲームのシステム上。ダメージを超過したのならば、現実世界に送り返されるはずなんだ。
でも、俺は敗北にはならず、そのまま目を覚ましたんだ。
ゲームの続行。
イレギュラー。
奇跡。
頭の中にそんなことがよぎる。
俺はついてるんだ。
運がいい。
自分はラッキーボーイ。
何かが俺って人間の人生の後押しをしてくれてるんだ。
そのことが実感できた。
そうだ、俺は戦ってたはずなんだ。
シルバーウルフは俺の事を死んだものと判断したのか、地面に捨てていた。
少し離れたところで、妹が1人で戦ってるのが目に入ってきた。
行かなくては。
俺は立ち上がり、妹の下へ向かう。
「涼音」
「兄貴、遅い・・・」
妹はすでにかなりのダメージを負っていて、服はボロボロで杖を支えにかろうじて立ってるという感じだった。
辺りの雪には血の斑点が出来ており、妹が懸命に逃げ回っていたことを教えてくれた。
シルバーウルフは俺の存在に気づいた。
だけど、すぐに襲ってくるのではなく再び遠吠えをする。
「ヴァォオオオオン!」
それは怒声。感情を酷く打ちつけられるような衝撃を感じる。
今は真夜中になってるんだ。
今更遠吠えしたって何の意味があるんだって思ってたけれど、そうじゃない。
突如、吹雪が吹き荒れる。
シルバーウルフは、それに乗じて姿を隠す。
「くそ、どこ行きやがった!」
俺は悔しくて、そんなことを叫んだ。
でも、これは悪手だろう。
「兄貴、避けて!」
妹の声と共に、背後から気配を感じる。
「おわっ」
シルバーウルフが噛み付こうとしてきた。
もう一度、あの攻撃を当たってしまったらどうなるかわからない。
今度こそ、助からないはず。
奇跡ってのは2度も起こらないはずだからだ。
吹雪が止まる事無く、強風が吹き荒れ、とてもじゃないが敵の存在を確認できない。
どうすれば、アイツを捕まえることが出来るのだろうか。
俺は案が浮かばず、途方に暮れていた。
でも、妹はそうじゃなかった。
「あのさ、兄貴」
「なんだよ、今は集中してるんだ後にしてくれ」
「私をオトリに・・・」
「バカ、何言ってるんだよ」
「お願い聞いて、ちゃんと理由があるの」
「理由ってどんな」
「回復アイテムが切れちゃったの。でもね、私は体力が赤」
「そんな」
やり直しが効かない。
もしも2人とも倒れてしまえば今まで与えていたダメージの量が全て回復してしまい。
初めから、やり直さなくてはいけなくなる。
それでは時間が掛かってしまうだろう。
一ヶ月でほむらのことを学校に復学させるという約束を守れなくなってしまうかもしれない。
「噛み付いてる間ってどちらかが今度こそ死んでしまうかもしれないけど、どっちかは攻撃のチャンスだと思うの」
「攻撃中は噛み付くことが出来ないからか・・・?」
「そう」
「でも、それならお前の方が」
「私の得意な技は水魔法。アクアランス。氷結系のボスには不利だと思わない?」
「それは・・・」
「さっき渡した火炎球。命中は低いけど、当たったらきっと私の魔法よりダメージはいるはず」
「それなら一緒に戦えば」
「持久戦になった負ける・・・。回復アイテムが無いって言ったでしょう?」
「だけど!」
「兄貴だったらきっと、やれるって信じてるから」
「そんな」
「だから私をオトリにして兄貴」
妹の考えにも一理あるって思った。だけど。
「それは逆じゃ駄目なのか・・・?」
「駄目」
「どうして」
「火炎球は兄貴が持ってるし、それは兄貴にしか使えない」
「お、おい。汚いからイヤだってのか?今はそんな冗談を言ってる場合じゃないだろ」
「違う、そうじゃないの」
「じゃあ、なんで」
「さっき剣を投擲した兄貴のスキルの高さを自分でも実感できたでしょう?」
「それは、まぁ・・・」
「私には投擲のスキルが無いの」
「えっ?」
「誰にでも当てられるってわけじゃないの。
兄貴は適当にスキルを振ったのかもしれないけれど、スキルってのは必ず何かに当てられる。
普通は考えて割り振ると思うんだけど兄貴はそうじゃなかった。勝手に割り振ってくれるオートでやった。
機械がそれに付き合った結果、投擲のスキルを上げる事になっていた。
普通だったら、そんな無駄な事するなって怒ってた。でも、今はどういうわけか役に立ってる」
「・・・」
「兄貴には投擲の才能があるの」
「俺にそんなスキルが・・・」
「だから兄貴が行った方がいいの」
「妹をオトリにするってのは何だか兄貴的に気分悪いというか、なんというか・・・」
俺は今更体裁のようなものを気にし始める。
こんな状況で気にするのも場違いかも知れないが、急にそんなことを思い始めたのだ。
「前に妹である私の金に手をつけたんだから兄貴としての面目は0に近いでしょ。それに本当に死ぬわけじゃないんだから。
本当に傷つくわけじゃないんだから気にしないで兄貴」
「・・・」
迷っていた。
それでいいのか?
作戦は悪くないと思うけど、それで実際上手く行くのだろうか。
何より俺自身、生き残れるかどうかの不安が大きいってのもある。
シルバーウルフは強いモンスターだ。
妹が消えて、俺もついでに敗北する可能性の方が大きいんじゃないかって気がする。
「兄貴、これ」
妹はコートを脱いで薄着になる。
キャミソールのような肩を出した格好になり、かなり寒そうだった。
「お前、なにして」
「氷結の定数ダメージが無くなるはず。身に着けて」
「いや、これはお前のだろ。お前が着てろよ」
「どうせもうボロボロだし、着るつもりないから捨てると思う。だからせめて兄貴の役に最後に立たせてあげて」
「・・・」
俺は妹の着ていたコートを着る。
実際に温度を感じるわけではないが、海パンのときと比べればかなり温かいって思うには充分だった。
「アクアランス!」
妹は上空に撃つ。
これは倒すための魔法じゃない、見つかるための魔法だ。
攻撃は空中で霧散して消えていった。
その魔力に反応したのか、シルバーウルフは姿を現して妹に噛み付く。
俺はそれを防ごうとしたが妹はいいのって目で訴えてきた。
妹の気持ちを否定するわけにはいかない。
俺はただ、この瞬間だけは見てるだけなんだ。妹が攻撃されるのを。
オオカミが噛み砕くように妹を攻撃すると。
エフェクトとはいえ、血が噴出し、グロテスクな印象があった。
叫びたい気持ちでいっぱいだった。
妹は消滅した。
頭の中では死んでないってのは理解していた。
けれど、目の前で消えるってのはどうにも心の中に不安を感じさせる。
もしかしたら、本当に死んでしまったのではないかって。
デスゲームが発生したのではと。
でも、今やるべきことはそれじゃないんだ。
俺が心に灯すべきは悲しみじゃない。怒りなんだと。
よくも妹を。
心に闘志を燃やす。
心はホットに、頭はクールに行こう。
頭の中がすーっとしていて、理性がはっきりと残ってるって思えた。
俺は火炎球を持って、シルバーウルフに狙いを定める。
妹を倒したという実感、余韻。
油断してる。
そう思った俺は、先程の剣の投擲の感覚を思い出して必ず当てると強い意志を出して投げつける。
「・・・!」
シルバーウルフは痛そうな表情を浮かべる。
火傷。
身体は炎上し、シルバーウルフが苦痛に喘ぐの感じる。
俺は倒せるって思えた。
でも、雪原の最終ボスを名乗ってるだけあって簡単に倒される気は無いんだろう。
シルバーウルフは燃える身体を気にする素振りを見せず、俺に突進してくる。
俺は体制を崩し、立ち居地を俺は把握してなかったのが原因だろう。
そのまま崖に落ちていく。
シルバーウルフと共に、俺は回転をしながら落ちていく。
「あああああぁっ!」
死にたくない、負けたくない!
心にそう叫び続ける。
咄嗟に目に入ったのは、錆びた剣。
俺はそれを掴んだ。
すると、上手い具合にシルバーウルフの毛並みがクッションとなって衝撃を和らげていた。
その代わりに、回転に巻き込まれたシルバーウルフは地面叩きつけられるような格好になってダメージを加算していった。
俺はこのまま剣を離さなければシルバーウルフに大打撃を与えられると確信し、さらには俺のダメージが無効になってる
この状況を手放すわけにはいかないと、さびた剣を絶対に離さないぞという思いだった。
「くっ、おおおおおおお・・・」
「・・・!」
シルバーウルフは離して欲しくてたまらないという感じだったけれど、急斜面を転んで、転んで、転び続けてるのに、
そんな器用な真似をすることは出来ず、俺と一緒に斜面が無くなって平地に行くまで回転は終わることはなかった。
「うわっ」
「・・・」
俺とシルバーウルフは地面に激突し、地面に放りだされる形になってしまう。
俺達はすでに第一ステージまで降り立ってしまったことに気づいた。
だけど剣は握り続けたままで、離すことは無く、一緒に飛んで行く。
「べふぅ」
雪に埋もれる。
このままではやられると思った俺は、すぐに顔を出し、剣を構えた。
だけど、すでにシルバーウルフの姿は無く。この場に残っていたのは俺だけなんだ。
何処に消えたんだろう?
そう思ったが、答えはすぐに分かった。
それを教えてくれたのは、ずっと握っていたはずのさびた剣だった。
いつのまにか、白銀の美しい刀身へと姿を変えており、シルバーウルフの姿はもう何処にも無かった。
ーーーーーーーーー始まりの村(昼)ーーーーーーーーー
シルバーウルフに勝った。
その事実が俺の胸に感動を与えてくれるのを実感できた。
手には勝利の証である、アイスソードが握られている。
俺は思わず、剣を見てニヤついてしまった。
宿屋で妹の再会を待ってる間、俺は剣を眺めて時間を潰していた。
これがシルバーウルフを倒したやつだけがもらえる剣かと思ってうっとりしていたんだ。
「兄貴」
りおんだ。
妹はゲームに負けたけれど、無事、死ぬ事は無く。
こうして再びゲームの世界に舞い戻ってきた。
少しの間とはいえ、本当に死んでしまったのではと俺は不安になっていた。
だから、こうして妹と会えたってのはホッとするような出来事だったんだ。
だけど、会ってそうそうこんなことを言われる。
「兄貴、何だか変態っぽい」
「・・・勝った俺にかける言葉か?」
「だって、私のあげたコート。さらにボロボロになって海パンがちらっと見えるし」
「仕方ないだろ激闘の末ってやつだ」
「まぁ、いいけどさ」
「それより見ろよ」
俺はかつて、さびた剣だったモノをを見せた。
「わぁ、綺麗」
白銀に染まった刀身は雪を類想させる、美しい品だと思う。
今の俺と掛け合わせると余計に変態感が増すけれど、まぁ、それを差し引いても美しい剣だ。
「だろ、こいつがきっとアイスソードだと思うんだよ」
「確証は無いの?」
「ああ、見た目は綺麗だけど、これがレッドドラゴンを倒すために必要な剣かと言われてもどうかなって感じだな」
妹は杖を取り出し、こんなことをしてくる。
「アクアランス!」
妹が魔法を唱えると、水で出来た槍が俺の方へ飛んでくる。
「危ねっ」
俺は咄嗟の判断で、アイスソードで防ぐ。
刀身が折れてしまうのではと思ったが、そんなことは起きなかった。
水の槍は凍り、地面にゴトリと鈍い音を立てて落ちたからだ。
「本物みたいね」
「あのなぁ、こういうのは試す前に一言確認取るもんだぜ?」
「でも、平気だったでしょ?」
「平気だから言いってもんじゃないだろ。もしも偽者だったらどうするんだ?」
「そのときは兄貴が倒れるかもね」
「・・・」
そんなことをさらりと言ってくる。
恐い妹だぜ。
さっきのコートの優しさを忘れるほどに俺的にはショックだった。
ーーーーーーーーーーーーーーー休日ーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーー6:50---------------
俺は朝、起きる。
「っく~・・・」
ベットから地面に降り立つ。
身体を伸ばして、全身の固まったように感じる身体をほぐしていく。
扉を開けて、下に降りて行くと先に妹が起きており、朝ごはんの準備をしていた。
「おはよう、兄貴」
「おはよう、俺より早いなんてな」
「何だか眠れなくてね」
妹はそう言って、テーブルの上に白身の魚と豆腐の味噌汁とほうれん草の胡麻和えと真っ白のご飯が置かれていた。
「美味しそう」
「普段はやらないだけなのよ?」
「誰に言い訳してるんだよ」
「いや、兄貴が私って料理できない子なんじゃないかなって思ってる気がして」
「そんなことはないけど」
「本当?」
「本当だって」
「ならいいけど」
2人分の皿が乗り終え朝食の時間を始められる。
「美味いなこれ」
「そう?」
妹は素っ気無い感じだけど、口元が微笑んでるのが見えて俺の言葉は間違って無かったんだと安心する。
「今日1日大丈夫なのか?」
俺は予定があるのか確認しておく。
もしもあるってなら妹を置いて俺1人で進まなければならないだろう。
「大丈夫、今日1日は都合空けといたから」
「そうか」
準備は大丈夫そうだった。
朝食も軽く済ませ、俺は自室へと向かう。
その際、妹とは離れて行動する。
妹は妹の部屋にゲーム機の台があるので、どうしても別々になる必要があるのだ。
「じゃ、また」
「うん、ゲームの世界で」
俺は扉を閉めて、自分の部屋にあるゲーム機を起動する。
VRゴーグルとケーブルを繋げて、俺はベットに横たわりながら顔に装着する。
電源が入ると、俺は次第に意識が遠のいていくのが分かる。
ーーーーーーーーーーーーーゲームの世界ーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー9:00---------
次に目が覚めたのはトンネルの中だった。
あの独特の浮遊感があって、俺はゲームの中にちゃんと入れたんだなって思えた。
最初のワープポイントに到着すると、先に妹が来ていて彼女の姿を確認できた。
妹は普段、セーラー服を着てることが多いからか、ゲームの世界だと魔女の格好なので何だかにコスプレに見える。
「なに、じろじろ見て」
「いや、魔女の格好ってハロウィンっぽいなって思って」
「まぁ、そうだけど」
「俺は海パンだろ?季節感が合わないなって思ってね」
「・・・」
「・・・」
「じゃ、行こっか」
「ああ」
変な間があったけれど、何か言うわけでもなかった。
俺達が向かうべきは雪原のシルバー・ウルフ退治だ。
欲しいのはアイスソード。話によれはシルバーウルフを退治すればドロップアイテムとして手に入るって話だ。
「雪原は・・・」
「あのワープポイントだろ?」
石碑に文字が刻まれている。
これに触れれば雪原。
恐らくじゃなく、確実にここに入れば雪原に行けるだろう。
「じゃあ、入るわよ」
「おう」
石碑に触れると、青い光が次第に大きくなっていく。
俺達は光に包まれる・・・。
ーーーーーーーーーーーーーー第1ステージ:雪原(朝方)ーーーーーーーーーーーーーー
数秒もしないうちに光が次第に弱まっていき、銀色の雪景色が次第に見えてきた。
「ここが・・・」
「寒っっ」
海パン一丁で、さび付いた剣だけを持ってるのが今の俺。
酷い格好だ。
ゲーム内だから雪の世界で低体温で死ぬ事は無いが、気分的に寒い気がしていた。
「そんな格好してるから・・・」
妹は少し呆れていた。
「仕方ないだろ、金ないんだ。このまま頑張るぞ」
「はいはい」
歩いていて気づいたことがあるが、確かに現実的な死は存在しないが、ゲーム的な死は存在する。
どういうことかと言えば、定数ダメージが自分に入る仕組みになっていた。
「妹よ」
「なに?」
「俺の体力が・・・赤だ」
「ねぇぇぇぇえええええええ!」
妹の声がフェードインしてくる。
「いや、でも死ぬわけじゃなさそうだ」
「でも一撃でも喰らったら死ぬでしょうが!」
「ははっ・・・」
乾いた笑いが出てくる。雪原なのだから乾いた笑いとはこれいかに。
湿地帯ではしっとりした笑いだろうか?
何て変なことを思う。
「ねぇ、私の邪魔しにきたの?それとも友達を助けるため?どっち?」
「友達を助けるに決まってるだろ」
「じゃあ、そのふざけた格好は何?」
「大丈夫だって、これでも何とかなるって。ゲームクリアした後って自分に制限かけてプレイするだろ?結構、そういうの慣れてるからさ。
大丈夫、大丈夫」
「不安しかない!」
雪原を2人で歩いてるときに、妹にそんな説教をされる。
「出てきたぜ・・・」
地面からずぼっ、ずぼっと何かが複数出てくる。
アイススライムって奴らだ。
道を塞がれてしまう。
だけど、相手はザコモンスター。
敵ではない。
「アクアランス!」
妹は水の槍を飛ばしてアイススライムを攻撃する。
氷相手に水の攻撃だからダメージの量は少ないはずだが、レベル差があるお陰でかなり効果的なダメージが入る。
「ひょおおおおおおっ」
変な掛け声と共に、俺は剣で突き刺して攻撃する。
別に黙ってても攻撃に変化は無いので声を出す必要は無いが、声を出すと気分的にやる気が出るのでそうしてる。
初期装備だが、レベル差が俺もあるのでアイススライムは結構簡単に倒せる。
「数が多いから面倒だけど、これなら簡単ね」
チャリン、チャリンとお金がどんどん増えていく。
経験値は少ないが、今欲しいのは前に進むための道と資金だ。
この2つを同時に満たせるのでアイススライムを素通りするわけにはいかない。
「道、開いたぜ」
「進むわ」
「OK」
俺は目の前の1体を切り倒す。
すると妹がそれに合わせて走って前進してくる。
先に妹の方が奥へと進んでいった。
俺もそれに続くように走っていく。
妹もただ黙って見てるのではなく、アクアランスを飛ばして道を進むのを援護してくれる。
俺達は取りあえずは第一ステージ突破ってところだ。
ステージを突破したと実感できるのはモンスターたちが境目からその先へは侵入してこない点にある。
このゲーム『アストラル・オンライン』はブロック事にステージが分かれてる。
第一ステージ、第二ステージ、第三ステージ(最終ステージ)に分かれてる。
ゲーム会社はわざと、その間の境目の間隔をあける事で体感的にステージを突破したと実感させるというわけだ。
そして、ステージの移動をする境目が実は間隔があって、そこは安全地帯。
モンスターが出入りすることが出来ない場所になってる。
そうすることでステージごとに準備を与えられるので難易度が簡単になってるというわけだ。
初心者でも楽しめるよう設計してるのだ。
ーーーーーーーーーーーー第2ステージ:雪原(昼頃)ーーーーーーーーーーーーーーーー
ダメージはそこまで入ってないので、俺達はそのまま準備を整える事無く第2ステージへを向かっていく。
「気のせいか、吹雪が強くなってきた気が・・・」
「シルバー・ウルフに近づいてるのかも」
「どういうことだ?」
「シルバーウルフが歩く所に吹雪ありって掲示板の投稿に見かけたの」
「吹雪が味方してる?」
「かもしれないわね」
「そうだと厄介だな」
シルバーウルフは俺達がゲームに飽きてやらなくなり始めてから登場したモンスターだ。
俺達はアップデート前のゲームしかしたことがないから、敵がどんな感じなのか想像がつかないのだ。
「止まって」
「どうした?」
妹に制止され、俺は思わず走るのを止めてしまう。
「あれ」
「ん?」
涼音が指差す先には真っ白のオオカミが居た。
「シルバーウルフ?」
「早いお出ましだな、手間が省けるってもんだ」
俺は切りかかる。
だけど、あっさり倒されてしまう。
後には雪だけが残る。
「これは・・・」
「なんだよ、こんなあっけないもんなのか?」
「モドキよ」
「モドキ?」
「ええ、シルバーウルフの偽者ってこと」
「なんだよ、そんなモンスターも居るのか」
「そうみたいね、でも、こいつらを倒していけばそのうち親玉がやってくるかも」
「ってことは倒し続けてればいいんだな?」
「多分・・・」
「よっしゃ、狩って狩って狩りまくるぞ!」
俺は剣を振るって、モドキ共を倒していく。
残るのは雪だけという点から、俺は何だか氷の彫刻を相手に戦ってるような気分になる。
反撃の意思は無く、ただ、道を邪魔するだけの存在。
「アクアランス」
妹も魔法を唱えて、サクッと倒す。
「吹雪で敵が見えにくいな・・・」
何だか吹雪が段々と強くなってきたような気がする。
「そうね、でも、集中しないと」
「分かってるよ」
悪天候の中、俺達はひたすらにモドキ達を倒していく。
経験値も薄く、金も手に入らないので何だか作業感が強い。それでも、これをしないと目的が果たせないのだから仕方が無い。
「涼」
妹が短い言葉で俺を呼ぶ。
「なんだよ、無駄話なら後で聞くぜ?」
「そんなんじゃないわ、見て」
残ったモドキたちが奥へ逃げていく。
「ってことは第3ステージに行けるってことか?」
「そういうことになるわ」
「アイテムくれ」
「何のアイテム?」
「攻撃系のアイテムとか持ってないか?」
「火炎球なら」
野球のボールのような見た目で、持ってるときは普通のボールだが敵に命中すると発火するという代物だ。
氷結系の敵にダメージ大と書かれてる。
「いいね、頂戴」
「外さないでよ?」
「わーってるって」
俺は妹からアイテムをもらう。
それをポケット・・・には仕舞えないのでパンツの中に突っ込んだ。
「それ、絶対返さないでね」
「なんでだよ、やばくなったらお前に返すよ」
「気持ち的に要らない」
「汚くないって!」
「汚いよ!」
そんなやり取りをしつつ、俺達は次のエリアに向かって行った。
ーーーーーーーーーー第3ステージ:雪山(夕方)ーーーーーーーーーー
時間帯が夕方になったからか、辺りは暗くなってきた。
先程の朝のエリアと比べて視界がかなり悪いと思う。
「気をつけろよ、最終エリアなんだ。ボスはここにいる筈だから」
「わかってるって兄貴」
奥に進むと、なにやらがさごそと動く物体を発見したのでボスかと思ったけれど、モドキたちだった。
「追うぞ」
「うん」
モドキたちは走って奥へ奥へとドンドン暗いほう、暗いほうへ行く。
太陽の光を雪原の山が覆い隠し、光が感じられなくなる方へ・・・。
「逃がすかよ」
俺はさらに追跡しようとするが、妹に肩を掴まれる。
「待って」
「なんだよ、大したことない奴らだぜ。ボスが来るまで・・・」
「来たの」
「来たって」
その言葉でハッとする。
もどき共とは違う何かが、そこにはいた。
見た目はモドキ共と多くは変わらない。
だけど、威圧感や、敵意はモドキ共とは明らかに別種だ。
違うと感じさせるのは白銀のような毛ではなく、真っ赤な燃えるような瞳がついてることだった。
「・・・」
疾駆。
例え話をしよう。
俺は現実世界で、街中で荒っぽい車を見かけた。
どうして荒っぽいと感じたのか?
それは、目の前を通り過ぎるときに風を感じたからだ。
歩道に居る俺はいつもあれを危ない運転手が乗っているものだと思っていた。
きっと俺が見たであろう車は法定速度なんて守る気は一切無いんだろう。
俺は今、それと同じことを思った。
何かが犯されてる暴風の気配。
シルバーウルフは妹に噛み付いていた。
「涼音!」
俺は剣を刺してやろうとオオカミの身体目掛けて突進するものの、いとも簡単に避けられ、それどころか妹が連れ去れることになった。
「くっ、このっ・・・!」
妹は魔法使いだ。杖で殴ることをしているが、役職とは違う行動を取ってるのだから本質ではないだろう。
魔法使いは魔法を他の役職よりも上手に扱うから魔法使いなのだ。
杖で殴るのが魔法使いではない。
つまりは、ダメージは大したものを入れられない。
「待て!」
シルバーウルフを追いかけるも、足が追いつかない。
身体能力の差だろうか。
俺の足では遠ざかる一方だ。
まるで乗り物に乗ってる相手と足で徒競走をしてるみたいに。
俺は諦めたくなってくる。
乗り物相手に本気で走るなんて馬鹿げてる。初めから勝負なんて成立してないのだと自分に言い訳をし始める。
足が次第に遅くなっていく。
氷結の定数ダメージが入ってる所為ではない。自らの選択で足が遅くなってるのだ。
どうせ妹はゲームなんだから死ぬわけ無い。
そんな言い訳が成り立つ。
だからこそ余計に俺は頑張るって行為を放棄しようと思うのだ。
走らなくてもいいじゃないか。
そんなことを考える。
遠くで何かが発光してる。青い光・・・。
妹の魔法だ。
アイツはまだ戦う気なんだ。
負けるつもりはないんだ。
なら、きっと追いつけるはずだ。
攻撃が刺されば、相手は動きを止めるはずだから。
走れば・・・行ける?
さっきまでの情けない考えを振り払い。俺は再び走り始める。
まだ始まったばかりじゃないか。
諦めるのは早いだろ?
「ぉぉぉぉぉおおおおおおお!」
「兄貴!?」
姿が見えた。
シルバーウルフは俺の方を始めて向いた気がする。
だけど、何処か嘲笑・・・。
見下したような、そんな笑みが感じられた。
獣とは思えない、人間臭さ。
海パンだもんな、馬鹿馬鹿しいよな・・・。
でも、俺は本気だぜ・・・?
俺は剣を手に持って槍投げの要領で投擲の準備をする。
遠いなら、足が遅いなら、別な方法で詰めてやれ。
「せーのっ」
俺は錆びた剣を投擲しシルバーウルフの身体に命中させる。
錆びた剣だろうが剣は剣だ。ノーダメージってことはないだろうと思うぜ。
「・・・!」
シルバーウルフはたまらず咥えていたものを地面に落とす。
俺はそれを地面に落ちる前にキャッチして、後退して距離を取る。
「さんきゅ、兄貴」
血のエフェクトが妹に入ってる。
ボロボロのマント、肌には傷跡のような模様が。
ダメージが大きいだろうと思えた。
「悪い、少し遅れた」
「大丈夫、体力は減ったけど死んでないもの」
「それならよかった」
「・・・」
シルバーウルフはこちらの方をじっと見てくる。
今の俺は武器が無く。手ぶらなわけだが、身体に刺さった錆びた剣が俺への警戒を高めてくれた。
コイツは何をしてくるんだ?他になにか秘策があるんじゃないのか?
そんな思いがあるのではと俺はコイツの考えが読めたように思えた。
「グリーン・ポーション」
妹は自分に回復アイテムを使った。
ゲージが黄色で危ない信号が出ていたが、緑になっていったのでひとまずは安心だ。
一撃でやられる心配は消えた。
どっちかって言えば俺は赤だから俺の方がやばかったりはするのだが。
「それって俺にも使える?」
「使えないわけじゃないけど、兄貴は定数ダメージ入るでしょ。それだったら私優先の方が無駄が少ない気がする」
「・・・それもそうだな」
俺が受けるであろう定数ダメージの分を妹は浮かせることが出来る。
だったら妹にのみ回復アイテムを使うってのは一応の筋は通ってると思う。
だけど俺がやられたとき、俺が拠点からこの雪原にまで戻る間はタイムラグがあることになるだろう。
ということは妹は1人でシルバーウルフと対峙しなければいけなくなる。
そうなるのは危険だろう。
できることなら、俺は生存していたほうがいい。
2対1って有利の状況を崩したくはない。
「アクアランス!」
妹は魔法を唱える。
シルバーウルフはそれに気づくとさっと避ける。
俺は道具袋から石ころを取り出し、投げつけて攻撃に一応参加する。
「無いよりはマシだろ・・・」
だけど、ひょい、ひょいと避けていく。
やっぱり剣が刺さったのは偶然か?
「アオォォォーン」
シルバーウルフが空に向かって吠える。
「なんだ?」
夕方といっても、真っ暗ではなかった。
けれど遠吠えと共に、世界が真っ黒に変わっていく。
ーーーーーーーーーーー第3ステージ:雪山(夜)ーーーーーーーーーーーー
今まで空には太陽があったはずなのに、動画の再生速度を上げたみたいに太陽があっという間に沈んでいく。
すると空は黒く染め上がり、満月が姿を表す。
「深遠の遠吠え」
「なんだそれ」
「シルバーウルフが使ってくる技の1つにそんなのがあるって確か掲示板に・・・」
「どんな効果なんだよ」
「私だって、分からないわよ!」
妹は悲鳴に近いような声で言ってくる。
悪寒。
体温が下がってるから感じるのではなく、生理的嫌悪感とでも言えばいいだろうか。
直感で自分は今、殺されるのだと理解できたような感じだ。
事実、そうなるんだろう。
頭で理解してるけれど、身体がそれに追いつかないなんてことはよくあることだと思う。
頭の中で格闘技のチャンピオンに勝てる妄想をすることがあるけれど勝率はいつも100%だ。
何故なら妄想なのだから自分のさじ加減でどうとでもなるからだ。
でも、今は違う。ウルフはゲームのAIだけど、それは1つの現実であり、今は戦うべき相手なのだ。
思い通りに行かない、行くわけがないんだ。
俺は今、宙に浮いてる。
肺の中に異物を感じる。
あぁ、俺は食われてるんだ。
「兄貴!」
剣の仕返しだろう。
血が流れ落ちる。
でも、これはゲームのエフェクトだから現実で死ぬわけじゃない。
死ぬはずがないんだ。
だけど、俺は今、恐怖している。
「うわぁああああああああ!」
スマホの電源をシャットダウンするときみたいに俺の意識はプツンと消え去った。
ーーーーーーーー???ーーーーーーーーーーーー
あれ・・・。
何してたんだっけ?
俺は教室で机に突っ伏すように寝ていたみたいだ。
腕には俺の顔の痕が少しだけついていて、赤くなってるのがその証拠だ。
「なぁ、りょう」
その声で俺を呼ぶのは誰だろう。
「誰・・・?」
「性質の悪い冗談だぜ、俺だよ、ほむら」
正面の席に座ってるほむらは俺の方へ身体を向けるために身体を捻って後ろを向くような格好をしていた。
授業中・・・いや、休み時間だろうか。
他の生徒はおらず、いるのは俺と、アイツだけ。
だから、そんな風に思ったんだ。
「他の人は・・・?」
「他のヤツは先に行ったんだ」
「なんだよ・・・。みんな冷たいんだな」
「ハハッ、そうかもな」
ほむらは楽しそうに笑う。
「お前は?」
「俺?」
ほむらは自分のことを人差し指で指す。
「お前も、他の生徒と同じように行かないといけないんじゃないのか?」
「そうかもな」
「じゃあ、なんで」
「お前、寝てただろ?」
「俺?」
「お前が起きて一緒に行かなきゃ意味無いだろ?」
「そっか」
「でも、お前は起きた。まだ間に合うぜ。一緒に行こう」
ほむらが言ってるのは移動教室のことだろう。
俺はアイツの言うとおり、一緒に行く事に決めた。
行くには立ち上がらなきゃな。
席に座ったままでは、一緒に行けないもんな。
寝ていたら余計に駄目だよな。
フッと世界が真っ暗になった。
だけど、不思議と恐くは無かった。
ーーーーーーーーーーー第3ステージ:雪山(夜)ーーーーーーーーーーーー
目の前は雪原だった。
それは奇跡と言えるような出来事だと思う。
ゲームのシステム上。ダメージを超過したのならば、現実世界に送り返されるはずなんだ。
でも、俺は敗北にはならず、そのまま目を覚ましたんだ。
ゲームの続行。
イレギュラー。
奇跡。
頭の中にそんなことがよぎる。
俺はついてるんだ。
運がいい。
自分はラッキーボーイ。
何かが俺って人間の人生の後押しをしてくれてるんだ。
そのことが実感できた。
そうだ、俺は戦ってたはずなんだ。
シルバーウルフは俺の事を死んだものと判断したのか、地面に捨てていた。
少し離れたところで、妹が1人で戦ってるのが目に入ってきた。
行かなくては。
俺は立ち上がり、妹の下へ向かう。
「涼音」
「兄貴、遅い・・・」
妹はすでにかなりのダメージを負っていて、服はボロボロで杖を支えにかろうじて立ってるという感じだった。
辺りの雪には血の斑点が出来ており、妹が懸命に逃げ回っていたことを教えてくれた。
シルバーウルフは俺の存在に気づいた。
だけど、すぐに襲ってくるのではなく再び遠吠えをする。
「ヴァォオオオオン!」
それは怒声。感情を酷く打ちつけられるような衝撃を感じる。
今は真夜中になってるんだ。
今更遠吠えしたって何の意味があるんだって思ってたけれど、そうじゃない。
突如、吹雪が吹き荒れる。
シルバーウルフは、それに乗じて姿を隠す。
「くそ、どこ行きやがった!」
俺は悔しくて、そんなことを叫んだ。
でも、これは悪手だろう。
「兄貴、避けて!」
妹の声と共に、背後から気配を感じる。
「おわっ」
シルバーウルフが噛み付こうとしてきた。
もう一度、あの攻撃を当たってしまったらどうなるかわからない。
今度こそ、助からないはず。
奇跡ってのは2度も起こらないはずだからだ。
吹雪が止まる事無く、強風が吹き荒れ、とてもじゃないが敵の存在を確認できない。
どうすれば、アイツを捕まえることが出来るのだろうか。
俺は案が浮かばず、途方に暮れていた。
でも、妹はそうじゃなかった。
「あのさ、兄貴」
「なんだよ、今は集中してるんだ後にしてくれ」
「私をオトリに・・・」
「バカ、何言ってるんだよ」
「お願い聞いて、ちゃんと理由があるの」
「理由ってどんな」
「回復アイテムが切れちゃったの。でもね、私は体力が赤」
「そんな」
やり直しが効かない。
もしも2人とも倒れてしまえば今まで与えていたダメージの量が全て回復してしまい。
初めから、やり直さなくてはいけなくなる。
それでは時間が掛かってしまうだろう。
一ヶ月でほむらのことを学校に復学させるという約束を守れなくなってしまうかもしれない。
「噛み付いてる間ってどちらかが今度こそ死んでしまうかもしれないけど、どっちかは攻撃のチャンスだと思うの」
「攻撃中は噛み付くことが出来ないからか・・・?」
「そう」
「でも、それならお前の方が」
「私の得意な技は水魔法。アクアランス。氷結系のボスには不利だと思わない?」
「それは・・・」
「さっき渡した火炎球。命中は低いけど、当たったらきっと私の魔法よりダメージはいるはず」
「それなら一緒に戦えば」
「持久戦になった負ける・・・。回復アイテムが無いって言ったでしょう?」
「だけど!」
「兄貴だったらきっと、やれるって信じてるから」
「そんな」
「だから私をオトリにして兄貴」
妹の考えにも一理あるって思った。だけど。
「それは逆じゃ駄目なのか・・・?」
「駄目」
「どうして」
「火炎球は兄貴が持ってるし、それは兄貴にしか使えない」
「お、おい。汚いからイヤだってのか?今はそんな冗談を言ってる場合じゃないだろ」
「違う、そうじゃないの」
「じゃあ、なんで」
「さっき剣を投擲した兄貴のスキルの高さを自分でも実感できたでしょう?」
「それは、まぁ・・・」
「私には投擲のスキルが無いの」
「えっ?」
「誰にでも当てられるってわけじゃないの。
兄貴は適当にスキルを振ったのかもしれないけれど、スキルってのは必ず何かに当てられる。
普通は考えて割り振ると思うんだけど兄貴はそうじゃなかった。勝手に割り振ってくれるオートでやった。
機械がそれに付き合った結果、投擲のスキルを上げる事になっていた。
普通だったら、そんな無駄な事するなって怒ってた。でも、今はどういうわけか役に立ってる」
「・・・」
「兄貴には投擲の才能があるの」
「俺にそんなスキルが・・・」
「だから兄貴が行った方がいいの」
「妹をオトリにするってのは何だか兄貴的に気分悪いというか、なんというか・・・」
俺は今更体裁のようなものを気にし始める。
こんな状況で気にするのも場違いかも知れないが、急にそんなことを思い始めたのだ。
「前に妹である私の金に手をつけたんだから兄貴としての面目は0に近いでしょ。それに本当に死ぬわけじゃないんだから。
本当に傷つくわけじゃないんだから気にしないで兄貴」
「・・・」
迷っていた。
それでいいのか?
作戦は悪くないと思うけど、それで実際上手く行くのだろうか。
何より俺自身、生き残れるかどうかの不安が大きいってのもある。
シルバーウルフは強いモンスターだ。
妹が消えて、俺もついでに敗北する可能性の方が大きいんじゃないかって気がする。
「兄貴、これ」
妹はコートを脱いで薄着になる。
キャミソールのような肩を出した格好になり、かなり寒そうだった。
「お前、なにして」
「氷結の定数ダメージが無くなるはず。身に着けて」
「いや、これはお前のだろ。お前が着てろよ」
「どうせもうボロボロだし、着るつもりないから捨てると思う。だからせめて兄貴の役に最後に立たせてあげて」
「・・・」
俺は妹の着ていたコートを着る。
実際に温度を感じるわけではないが、海パンのときと比べればかなり温かいって思うには充分だった。
「アクアランス!」
妹は上空に撃つ。
これは倒すための魔法じゃない、見つかるための魔法だ。
攻撃は空中で霧散して消えていった。
その魔力に反応したのか、シルバーウルフは姿を現して妹に噛み付く。
俺はそれを防ごうとしたが妹はいいのって目で訴えてきた。
妹の気持ちを否定するわけにはいかない。
俺はただ、この瞬間だけは見てるだけなんだ。妹が攻撃されるのを。
オオカミが噛み砕くように妹を攻撃すると。
エフェクトとはいえ、血が噴出し、グロテスクな印象があった。
叫びたい気持ちでいっぱいだった。
妹は消滅した。
頭の中では死んでないってのは理解していた。
けれど、目の前で消えるってのはどうにも心の中に不安を感じさせる。
もしかしたら、本当に死んでしまったのではないかって。
デスゲームが発生したのではと。
でも、今やるべきことはそれじゃないんだ。
俺が心に灯すべきは悲しみじゃない。怒りなんだと。
よくも妹を。
心に闘志を燃やす。
心はホットに、頭はクールに行こう。
頭の中がすーっとしていて、理性がはっきりと残ってるって思えた。
俺は火炎球を持って、シルバーウルフに狙いを定める。
妹を倒したという実感、余韻。
油断してる。
そう思った俺は、先程の剣の投擲の感覚を思い出して必ず当てると強い意志を出して投げつける。
「・・・!」
シルバーウルフは痛そうな表情を浮かべる。
火傷。
身体は炎上し、シルバーウルフが苦痛に喘ぐの感じる。
俺は倒せるって思えた。
でも、雪原の最終ボスを名乗ってるだけあって簡単に倒される気は無いんだろう。
シルバーウルフは燃える身体を気にする素振りを見せず、俺に突進してくる。
俺は体制を崩し、立ち居地を俺は把握してなかったのが原因だろう。
そのまま崖に落ちていく。
シルバーウルフと共に、俺は回転をしながら落ちていく。
「あああああぁっ!」
死にたくない、負けたくない!
心にそう叫び続ける。
咄嗟に目に入ったのは、錆びた剣。
俺はそれを掴んだ。
すると、上手い具合にシルバーウルフの毛並みがクッションとなって衝撃を和らげていた。
その代わりに、回転に巻き込まれたシルバーウルフは地面叩きつけられるような格好になってダメージを加算していった。
俺はこのまま剣を離さなければシルバーウルフに大打撃を与えられると確信し、さらには俺のダメージが無効になってる
この状況を手放すわけにはいかないと、さびた剣を絶対に離さないぞという思いだった。
「くっ、おおおおおおお・・・」
「・・・!」
シルバーウルフは離して欲しくてたまらないという感じだったけれど、急斜面を転んで、転んで、転び続けてるのに、
そんな器用な真似をすることは出来ず、俺と一緒に斜面が無くなって平地に行くまで回転は終わることはなかった。
「うわっ」
「・・・」
俺とシルバーウルフは地面に激突し、地面に放りだされる形になってしまう。
俺達はすでに第一ステージまで降り立ってしまったことに気づいた。
だけど剣は握り続けたままで、離すことは無く、一緒に飛んで行く。
「べふぅ」
雪に埋もれる。
このままではやられると思った俺は、すぐに顔を出し、剣を構えた。
だけど、すでにシルバーウルフの姿は無く。この場に残っていたのは俺だけなんだ。
何処に消えたんだろう?
そう思ったが、答えはすぐに分かった。
それを教えてくれたのは、ずっと握っていたはずのさびた剣だった。
いつのまにか、白銀の美しい刀身へと姿を変えており、シルバーウルフの姿はもう何処にも無かった。
ーーーーーーーーー始まりの村(昼)ーーーーーーーーー
シルバーウルフに勝った。
その事実が俺の胸に感動を与えてくれるのを実感できた。
手には勝利の証である、アイスソードが握られている。
俺は思わず、剣を見てニヤついてしまった。
宿屋で妹の再会を待ってる間、俺は剣を眺めて時間を潰していた。
これがシルバーウルフを倒したやつだけがもらえる剣かと思ってうっとりしていたんだ。
「兄貴」
りおんだ。
妹はゲームに負けたけれど、無事、死ぬ事は無く。
こうして再びゲームの世界に舞い戻ってきた。
少しの間とはいえ、本当に死んでしまったのではと俺は不安になっていた。
だから、こうして妹と会えたってのはホッとするような出来事だったんだ。
だけど、会ってそうそうこんなことを言われる。
「兄貴、何だか変態っぽい」
「・・・勝った俺にかける言葉か?」
「だって、私のあげたコート。さらにボロボロになって海パンがちらっと見えるし」
「仕方ないだろ激闘の末ってやつだ」
「まぁ、いいけどさ」
「それより見ろよ」
俺はかつて、さびた剣だったモノをを見せた。
「わぁ、綺麗」
白銀に染まった刀身は雪を類想させる、美しい品だと思う。
今の俺と掛け合わせると余計に変態感が増すけれど、まぁ、それを差し引いても美しい剣だ。
「だろ、こいつがきっとアイスソードだと思うんだよ」
「確証は無いの?」
「ああ、見た目は綺麗だけど、これがレッドドラゴンを倒すために必要な剣かと言われてもどうかなって感じだな」
妹は杖を取り出し、こんなことをしてくる。
「アクアランス!」
妹が魔法を唱えると、水で出来た槍が俺の方へ飛んでくる。
「危ねっ」
俺は咄嗟の判断で、アイスソードで防ぐ。
刀身が折れてしまうのではと思ったが、そんなことは起きなかった。
水の槍は凍り、地面にゴトリと鈍い音を立てて落ちたからだ。
「本物みたいね」
「あのなぁ、こういうのは試す前に一言確認取るもんだぜ?」
「でも、平気だったでしょ?」
「平気だから言いってもんじゃないだろ。もしも偽者だったらどうするんだ?」
「そのときは兄貴が倒れるかもね」
「・・・」
そんなことをさらりと言ってくる。
恐い妹だぜ。
さっきのコートの優しさを忘れるほどに俺的にはショックだった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

NPCが俺の嫁~リアルに連れ帰る為に攻略す~
ゆる弥
SF
親友に誘われたVRMMOゲーム現天獄《げんてんごく》というゲームの中で俺は運命の人を見つける。
それは現地人(NPC)だった。
その子にいい所を見せるべく活躍し、そして最終目標はゲームクリアの報酬による願い事をなんでも一つ叶えてくれるというもの。
「人が作ったVR空間のNPCと結婚なんて出来るわけねーだろ!?」
「誰が不可能だと決めたんだ!? 俺はネムさんと結婚すると決めた!」
こんなヤバいやつの話。

深淵の星々
Semper Supra
SF
物語「深淵の星々」は、ケイロン-7という惑星を舞台にしたSFホラーの大作です。物語は2998年、銀河系全体に広がる人類文明が、ケイロン-7で謎の異常現象に遭遇するところから始まります。科学者リサ・グレイソンと異星生物学者ジョナサン・クインが、この異常現象の謎を解明しようとする中で、影のような未知の脅威に直面します。
物語は、リサとジョナサンが影の源を探し出し、それを消し去るために命を懸けた戦いを描きます。彼らの犠牲によって影の脅威は消滅しますが、物語はそれで終わりません。ケイロン-7に潜む真の謎が明らかになり、この惑星自体が知的存在であることが示唆されます。
ケイロン-7の守護者たちが姿を現し、彼らが人類との共存を求めて接触を試みる中で、エミリー・カーペンター博士がその対話に挑みます。エミリーは、守護者たちが脅威ではなく、共に生きるための調和を求めていることを知り、人類がこの惑星で新たな未来を築くための道を模索することを決意します。
物語は、恐怖と希望、未知の存在との共存というテーマを描きながら、登場人物たちが絶望を乗り越え、未知の未来に向かって歩む姿を追います。エミリーたちは、ケイロン-7の守護者たちとの共存のために調和を探り、新たな挑戦と希望に満ちた未来を築こうとするところで物語は展開していきます。

キンメッキ ~金色の感染病~
木岡(もくおか)
SF
ある年のある日を境に世界中で大流行した感染病があった。
突然に現れたその病は非常に強力で、医者や専門家たちが解決策を見つける間もなく広まり、世界中の人間達を死に至らしめていった。
加えてその病には年齢の高いものほど発症しやすいという特徴があり、二か月も経たないうちに世界から大人がいなくなってしまう。
そして残された子供たちは――脅威から逃れた後、広くなった地球でそれぞれの生活を始める――
13歳の少年、エイタは同じ地域で生き残った他の子供達と共同生活を送っていた。感染病の脅威が収まった後に大型の公民館で始まった生活の中、エイタはある悩みを抱えて過ごしていた……。
金色の感染病が再び動き出したときにエイタの運命が大きく動き出す。

鉄錆の女王機兵
荻原数馬
SF
戦車と一体化した四肢無き女王と、荒野に生きる鉄騎士の物語。
荒廃した世界。
暴走したDNA、ミュータントの跳梁跋扈する荒野。
恐るべき異形の化け物の前に、命は無残に散る。
ミュータントに攫われた少女は
闇の中で、赤く光る無数の目に囲まれ
絶望の中で食われ死ぬ定めにあった。
奇跡か、あるいはさらなる絶望の罠か。
死に場所を求めた男によって助け出されたが
美しき四肢は無残に食いちぎられた後である。
慈悲無き世界で二人に迫る、甘美なる死の誘惑。
その先に求めた生、災厄の箱に残ったものは
戦車と一体化し、戦い続ける宿命。
愛だけが、か細い未来を照らし出す。

エンシェントソルジャー ~古の守護者と無属性の少女~
ロクマルJ
SF
百万年の時を越え
地球最強のサイボーグ兵士が目覚めた時
人類の文明は衰退し
地上は、魔法と古代文明が入り混じる
ファンタジー世界へと変容していた。
新たなる世界で、兵士は 冒険者を目指す一人の少女と出会い
再び人類の守り手として歩き出す。
そして世界の真実が解き明かされる時
人類の運命の歯車は 再び大きく動き始める...
※書き物初挑戦となります、拙い文章でお見苦しい所も多々あるとは思いますが
もし気に入って頂ける方が良ければ幸しく思います
週1話のペースを目標に更新して参ります
よろしくお願いします
▼表紙絵、挿絵プロジェクト進行中▼
イラストレーター:東雲飛鶴様協力の元、表紙・挿絵を制作中です!
表紙の原案候補その1(2019/2/25)アップしました
後にまた完成版をアップ致します!
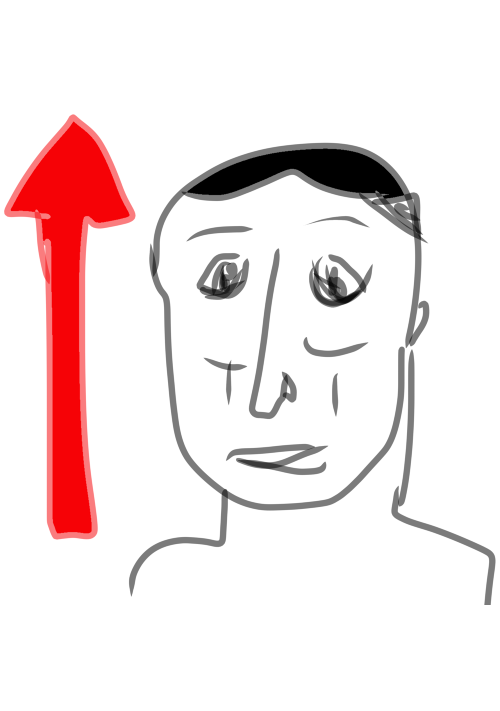
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

H.E.A.V.E.N.~素早さを極振りしたら、エラい事になった~
陰猫(改)
SF
人生が終わると言う都市伝説のあるVRゲームを購入した坂田糀はその真相を知るべく、H.E.A.V.E.N.と呼ばれるゲームを始める。
しかし、そのゲームは思いもよらない代物であった。
陰猫(改)が送る実験的な小説第……何弾だっけ?
今回はリアル過ぎたVRを私なりに書いて見ました。
今回もなろうから持って来ました。
ジャンル別にVRがないのでキャラ文芸と言う形でお送りしますーーって、なんか、SF扱いになってる!
Σ(; ゚Д゚)!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















