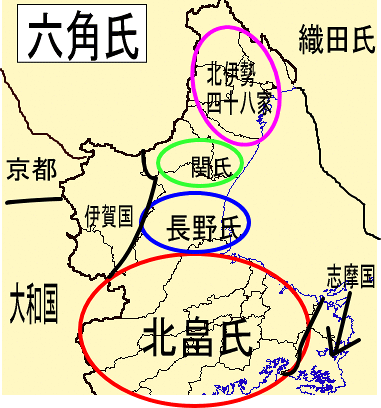10 / 19
【伊勢湾制圧編】地之果丸
しおりを挟む
(一)
九鬼嘉隆が大湊の船大工に製造を依頼した安宅船が完成した。
以前にも書いたが安宅船とは、船首から船尾まで総矢倉として、厚い板で装甲された船のことである。装甲には弓や鉄砲を撃つ為の狭間(銃眼)があった。また素早く敵船に乗り移れるよう、楯板が外側に倒れ船の橋渡しができる作りになっていた。船底は防水区画を設け、船体の一部が破損しても浸水が他に及ばないなど、多くの工夫がされていたようである。この時の嘉隆の安宅船は船体が椋の木でできており、およそ八十挺櫓ほどだったと推察される。
ちなみにこの当時安宅船には、大湊で建造された伊勢型安宅船と、おもに瀬戸内海上で使用された二成型の安宅船とがあった。
伊勢型安宅船の特徴としては、船首に『戸立水押』が採用していることが一つ。棚(外板)と敷(船底)で構成された棚板構造で、横の強度は横梁によって支えていること。櫓と帆両用の中世的な船型であることなどがあげられる。
早速、嘉隆は伊勢湾から尾張方面に向かって船を動かした。その日はやや肌寒かった。夜明け前出立。やがて東の空が薄紅に染まりはじめる。闇夜に慟哭を続けていた海は、ここでまったく別の表情をみせる。遠い地へと誘う海、淡くゆっくりと夢を語りかけてくる海。珊瑚礁は、志摩の国を追われ海上をさすらう嘉隆の心を、しばし癒すのに十分であった。
『俺はもう後戻りせぬ。信長様とともに、この船で例え九州であろうと奥州であろうと、そのはるか彼方であろうと赴いてみせる。そして戦って、戦って、戦いぬいてみせる。そして必ずや、信長様を天下へと渡す橋になってみせる』
嘉隆は心中固くそう誓うのだった。
嘉隆は片手に酒の入った瓢箪を手にし、片手には朝餉の椀が握られていた。
嘉隆のこの日の朝餉は、志摩地方の郷土料理といっていい『手こね寿司』だった。かつおを薄く切り、一昼夜特製のタレに漬け、酢飯とあわせた寿司料理である。薬味として大葉、しょうが、のりなどを散らして食べた。
カツオ漁で忙しい漁師が獲ったカツオをぶつ切りにし、ごはんにまぜあわせて、手でこねて食べたのが発祥といわれている。準備に時間のかからない料理として、この地方では定番料理として定着したのであった。嘉隆はそれを世話しなく喉にかきこむと、ついには箸を捨て手つかみで食べた。
「恐れながら殿、そろそろ尾張にござる」
背後で金剛九兵衛がいった。
「九兵衛よ、わしはこの船を地之果丸と名づけることにした」
「それはまた変わった名にござるな」
「うむ、信長様とともに地の果てまでも赴く。それ故に地之果丸じゃ」
嘉隆が力強く言いきった時異変はおこった。突如として船体が激しくゆれ、乗組員のうち数名が、立っていることさえできずその場に転倒した。
「何事じゃ! もしや敵の襲撃か?」
嘉隆もかすかに動揺した。敵であるとしたら何者であろうか? もしや伊勢の北畠であろうか?
「申し上げます。ただいまの船体の揺れは、鯨の衝突によるものと判明」
それは全長十メートルにも及ぶマッコウ鯨だった。普段は深海におり、ダイオウイカ等を主食とし、めったに海面に姿を現すことがない。ただ巨大なだけでなく、超音波を使い仲間と会話するともいわれ知能も高い。海面を泳ぐその姿は、まさしく海の化物といってよい。
「小癪な奴!」
嘉隆はその姿を目で追いながら、種子島銃の火縄に着火した。狙いを定めると引き金に手をかけた。轟音があたりに響きわたり。硝煙の香り、そして海の色がたちまちのうちに真っ赤に染まっていく。
「わしに背く者は、皆あの海の化物と同じ目にあわせてくれん! いかに巨大な敵であろうと必ず倒してみせる」
嘉隆は今一度必勝を心に誓うのだった。
それから数ヶ月が過ぎた。織田水軍創設を依頼した小牧山の信長のもとには、安宅船が完成したとの報以来、なに一つ新しい報告はなかった。
「一益、例の志摩の田舎者はその後、いかがなった?」
信長はそれとなく滝川一益にたずねた。
「それが病に倒れたとのことでござる」
一益が言葉を濁しながらいった。
「病? いかような病じゃ?」
「それが原因不明にござる。どうやら乱心に近いようで、夜毎意味不明なことを叫んでは、周りの者を困らせているとのこと」
「うぬ、大事な時だというに……。名医をさしむけて治療をさせよ」
信長はにがり切った表情でいった。
(二)
「己、北畠具教! 己、小浜民部!」
夜が来て、またしても嘉隆の乱心が始まった。槍をふりかざしたかと思うと、憎き相手の名を叫び暴れ狂い 、猛り狂う。すでに側近くに仕えていた者のうち数名が 、嘉隆の乱心の犠牲となり命を落としていた。
しかしこの日、金剛九兵衛はある悲壮な覚悟をもって、乱心の主君を諌めようとしていた。
「お前達 、とりあえず下がっていろ。わしが良しというまで、決して入ってはならぬ。奥方もしばし席を外されよ」
よもや偽物とは知らず、九兵衛は奥方にも退室をうながした。こうして嘉隆に仕える部屋の女達、あれいは小姓等は全て人払いされる。部屋には嘉隆と九兵衛、それに滝川市郎兵衛だけとなった。
嘉隆はしばし狂気の様相を呈していたが、己より体格ではるかに勝る金剛九兵衛の鋭い眼光と目が合うと、しばし平静を取り戻した。
「なんだ九兵衛ではないか。どうしたというのだこんな夜更けに」
嘉隆は手にしていた槍を置き、表向きは穏やかに尋ねた。
「恐れながら、家臣として諫止に参りました。昨日も一昨日も側近くに仕える者を、手討ちにしたとか。主がこの有様では、九鬼家が壊れてしまいまする。どうか今後はこのようなことなきよう、切にお願いつかまつる」
九兵衛は頭を下げて頼んだ。
「ではなにか、お前はわしの側に落ち度があるというのか? あまりにも機転がきかぬので、切り捨てたまでのこと。高々小姓の命ではないか。切り捨てたところでどうということはない」
「もう一度頼み申す。今後はこのようなことなきよう。どうかお願いつかまつる」
九兵衛が今一度懇願した。
「何をいうか。信長様とて……」
「黙れ! 右馬允!」
嘉隆が全ていい終わらないうちに、部屋全体に響きわたるほどの凄まじい怒号が飛んだ。さすがの嘉隆もしばし驚き、戦慄して言葉を失った。
「己! 誰に向かって口をきいておるのだ。右馬允だと?」
九兵衛は鬼の形相を浮べ、そして立ち上がった。
「主、主足らざれば、臣、臣足らず! 今の貴様に人の主を語る資格はない!」
嘉隆は真っ青になった。年齢は嘉隆のほうが一つ、二つほど年長である。しかし九兵衛は子供の頃から体格が良く、幼い頃よくとっくみ合いをして、その度ごとに嘉隆は負けた。その時分の怖かった思い出が再び脳裏をよぎった。
「九兵衛乱心! 方々出会え!」
嘉隆は絶叫したが、むろん周囲には猫の子一匹いなかった。
「叫んでも無駄だ! 右馬允!」
嘉隆が躊躇している間にも、九兵衛は嘉隆の目の前に置いてあった食事用の膳を、荒々しく蹴り飛ばし、嘉隆の胸倉をつかんだ。酒のとっくりが鈍い音を立てて割れる音がした。怪力でねじふせられたため、嘉隆はしばし苦悶の表情をうかべ、激しくせきを繰り返した。
「一体どうしたというのだ九兵衛! 気でも違ったのか?」
「黙れ愚か者! 亡きおじい様より、そして兄君からも九鬼の家を託されたこと、もう忘れたというか! 今は九鬼家存亡の時。乱心している余裕などないことわからんのか! このままでは信長様とて、いずれお主に愛想つかすこと必定。それがわからぬほど御主は愚かなのか?」
嘉隆の胸倉をつかんだままの九兵衛の両の腕が、興奮からか悔しさから、激しく震えていた。
「供に唐・天竺まで赴くと約束したではありませぬか……」
今度は一転して、九兵衛の声は悲痛なものになった。
「主よ……。どうか我が命を奪ってくだされ」
ようやく平静に戻った九兵衛は、つかんでいた手を放し、三歩ほど後ずさりして片膝をついた。
「臣下として申し上げたいことはこれまででござる。金剛九兵衛無礼は腹切ってお詫び申す。どうか心改め、家臣・領民にとり良き主であられるよう……」
そこまでいって九兵衛は、抜刀して刀身を喉元に押し当てた。
「待て、待たぬか、そなたが腹を切る必要などない」
九兵衛の態度が豹変したのでしばし安堵した嘉隆は、今度は腹を切るといいだしたので、再び驚きとにかく止めようとした。
「恐れながら、それがしからもお願いつかまつる」
口を挟んだのは滝川市郎兵衛だった。
「これ以上乱心を続ければ、九鬼家は滅びまする。どうしても正気に戻れぬと仰せなら、それがしも九兵衛殿とともに腹切りまする。九鬼家が滅びる様など見たいとは思いませぬ」
嘉隆は、しばし両者の顔を見比べ、そして拳を強く奮わせた。ある種の後悔が嘉隆の胸を去来していた。
(三)
嘉隆は己の夢の中にいた。
眼下は海である。波の音がひっきりなしにさざめく砂浜で、嘉隆は仰向けになって倒れていた。その光景を麻鳥が、不敵を笑みをうかべながら見下ろしていた。
強靭な意志をおもわせるひきしまった薄い朱唇、やや重たげな瞼の陰の、可憐といっていい哀愁的な黒眸。こうして見ると驚くほどいい女である。
「さらばだな。私はお前の兄と妻を奪った。なれど私もお前のおかげで全てを失った。これも定めと思いあきらめてもらおう」
麻鳥が背を向けたその時である。突如として嘉隆が目を見開き、鋭い刃が麻鳥の右の肩をかすめた。
「そうかお前がわしの兄と妻の命を奪ったのか? 許せん小癪な女め、ここで成敗してくれる」
羽交い絞めにされた麻鳥だったが、すばやく危急を脱し、天空をくるくると舞い刀をかまえた。その時麻鳥は、嘉隆に向かって奇妙なものを投げつけた。それはヒトデだった。
「己、これは一体……?」
かっての浄隆同様、全身が干からびていく。ついに嘉隆は地に伏した。
麻鳥は、息を切らせながらその光景を見守っていたが、今度こそ戦いが終わったことを確信し、安堵のため息をついた。しかしそれもつかの間だった。突然背後から何者かに、刃を喉元に突きつけられたのである。
「今のわしにそなたの術は通用せん。覚悟するがいい」
目の前で死んだはずの嘉隆だった。今一度麻鳥を羽交い絞めにする。
「己! 放せ放さぬか!」
ものすごい力である。麻鳥がいかほど抗おうと無駄だった。ついには麻鳥は服をすべてはがされ、その場に倒された。
どれほど時間が経っただろうか? 両者は激しいやり取りの後、いずれも砂浜に倒れていた。
「こうして満月を見ているとあの日のことを思い出す」
麻鳥は過去を語り始めた。麻鳥は大和の生まれで、母親が西国に赴いた際、賊徒に襲撃され数ヶ月後に生まれたという。こうした不幸の出生であるにも関わらず、母はかろうじて麻鳥を育てようとした。
しかしそれも母親に別の男ができてから変わった。母親の新たな愛人は麻鳥を憎み、母親の目を盗んで川に捨てようとした。まだ三歳児だった麻鳥が、その時目撃したのが満月だった。結局麻鳥は甲賀の忍に助けられ、忍びの道を歩むことになる。
「そなたも根なし草か……わしと同じじゃな。わしも志摩の国を追われ信長殿に仕えることになったが、この先どうなることやら」
「ならば私とともに、二度覚めぬ夢の国へでも行くか」
「なんじゃそれは、そのような世界があるのか」
嘉隆は上半身をおこした。
「私は不覚にもお前にほれた。お前とならどこへでもゆく」
麻鳥は真顔でいうので、嘉隆は少しだけ信じる気になった。ところがその時異変はおこった。
「なりませぬぞ! その者の言葉信じてはいけませぬ」
突然眼下の波浪が激しくなった。その波の中心に一人の女がいた。
「篠!」
嘉隆は思わず叫んだ。やがて凄まじい波しぶきが麻鳥だけを飲み込んでしまう。両者は水中で凄まじい格闘をし、さすがの麻鳥も水を大量に飲み込み、ついに人事不肖となった。
「篠、許してやってくれ。聞けばこの女も哀れな星のもとに生まれた女なのだ」
嘉隆はあえて命ごいした。
「妻と兄を殺されたこと忘れたのですか? 貴方はこの者にたぶらかされております。されどいいでしょう。もはやこの者は、忍びとしての能力は喪失したも同然。今となっては何もできませぬ。嘉隆様が危急のおりには、またかけつけまする。しばしさらばにございます」
篠は消え、嘉隆は夢から覚めた。すでに麻鳥の姿はなかった。こうして麻鳥は嘉隆の前から消えたが、いずれまた、不幸な形で再会するのである。
(四)
二年ほどの歳月が流れた。永禄十年(一五六七)、織田信長は木下藤吉郎等の活躍もあり、念願の美濃攻略をついに果たす。美濃・稲葉山城の斉藤竜興は追放され、信長はただちに国政の中心を小牧山から美濃へと移し、稲葉山を岐阜と改めた。
美濃の国は日本国のほぼ中央を占め、常に東西の勢力が激突する要衝の地である。そして岐阜城は標高三二九メートルという高地にあった。
信長の居館は、現在冠木門と虎口の土塁が復元されている。山麓の一段高くなった千畳敷には、かつてポルトガルの宣教師ルイス・フロイスも紹介した楼閣(信長の住居)が建てられていた。天守からは、長良川が貫流する様を眺めることができた。東に恵那山・木曾御岳山、北には乗鞍・日本アルプス、また西に伊吹・養老・鈴鹿の山系が連なる。南には濃尾平野が豊かに開け、木曾の流れが悠然と伊勢湾に注ぐさまを一望することもできた。
そしてこの頃から、信長は有名な『天下布武』の印判を使用し始めた。信長にとり『天下布武』の手始めは伊勢攻略にあった。都への道を確保するためにも、信長は美濃の次になんとしても、伊勢を支配下におきたかった。
すでに美濃攻略のめどが立ち始めた永禄十年には、同時並行的に滝川一益に命じて北伊勢攻略をも命じてもいる。
伊勢の国の歴史を伊勢神宮と切り離して考えるのは難しい。では何故、俗に八百万の神の国といわれる我が国の中でも、最高の格式を誇るといっていい伊勢神宮がこの地にあるのか? やはり伊勢の国が、それほど日本史において重要な地であることと無縁ではないだろう。そして信長も重々それを承知していた。
伊勢の国とその周辺こそ、多様な顔を持った土地もめずらしい。約千八百キロという縦に長く連なる土地で、東側は遠浅の内湾と黒潮が波打つ海岸線である。西側は千七百メートルを越える大台ヶ原中心として、鈴鹿山脈、台高山脈と、山地がまるで壁のようである。
山地、丘陵、平野部、そして海岸と様々な地形環境があり、そのほぼ中央に西南日本を二部する中央構造線が走っている。
気候もまた雑多である。平野部の温暖な東海型気候、山地性の気候、熊野灘沿岸の気候とそれぞれが異なる。
こうした雑多な風土の影響なのか、戦国時代の伊勢の国は、著しく統一性を欠いていた。
最大勢力はもちろん南伊勢を支配する国司北畠氏であるが、その勢力圏はあくまで南伊勢に限られていた。中勢には神戸・関・長野といった諸豪族が割拠し、さらに尾張と直接接する北伊勢には、実に四十八もの小豪族が割拠していた。
こうした中でも国司北畠氏と中伊勢の長野氏は、南北朝時代から犬猿の仲だった。しかしそれも近年両国の間で妥協が成立し、今の長野氏の主は北畠具教の次男・具藤だった。
しかしこの北畠による、ある意味長野氏の乗っ取りには、長野氏に仕える家臣団の反発もかなりのものだった。家中の主だった者のほとんどは、まだ若い具藤に心服していなかった。
ほどなく織田勢による北伊勢侵攻が開始される。織田勢の総大将は滝川一益だった。甲賀忍者上がりのこの男にとり、合戦前の調略こそ得意中の得意であり、まさに一益のつけいる隙はここにあった。信長による伊勢侵攻は、永禄十一年(一五六八)本格的に開始されるのであった。
九鬼嘉隆が大湊の船大工に製造を依頼した安宅船が完成した。
以前にも書いたが安宅船とは、船首から船尾まで総矢倉として、厚い板で装甲された船のことである。装甲には弓や鉄砲を撃つ為の狭間(銃眼)があった。また素早く敵船に乗り移れるよう、楯板が外側に倒れ船の橋渡しができる作りになっていた。船底は防水区画を設け、船体の一部が破損しても浸水が他に及ばないなど、多くの工夫がされていたようである。この時の嘉隆の安宅船は船体が椋の木でできており、およそ八十挺櫓ほどだったと推察される。
ちなみにこの当時安宅船には、大湊で建造された伊勢型安宅船と、おもに瀬戸内海上で使用された二成型の安宅船とがあった。
伊勢型安宅船の特徴としては、船首に『戸立水押』が採用していることが一つ。棚(外板)と敷(船底)で構成された棚板構造で、横の強度は横梁によって支えていること。櫓と帆両用の中世的な船型であることなどがあげられる。
早速、嘉隆は伊勢湾から尾張方面に向かって船を動かした。その日はやや肌寒かった。夜明け前出立。やがて東の空が薄紅に染まりはじめる。闇夜に慟哭を続けていた海は、ここでまったく別の表情をみせる。遠い地へと誘う海、淡くゆっくりと夢を語りかけてくる海。珊瑚礁は、志摩の国を追われ海上をさすらう嘉隆の心を、しばし癒すのに十分であった。
『俺はもう後戻りせぬ。信長様とともに、この船で例え九州であろうと奥州であろうと、そのはるか彼方であろうと赴いてみせる。そして戦って、戦って、戦いぬいてみせる。そして必ずや、信長様を天下へと渡す橋になってみせる』
嘉隆は心中固くそう誓うのだった。
嘉隆は片手に酒の入った瓢箪を手にし、片手には朝餉の椀が握られていた。
嘉隆のこの日の朝餉は、志摩地方の郷土料理といっていい『手こね寿司』だった。かつおを薄く切り、一昼夜特製のタレに漬け、酢飯とあわせた寿司料理である。薬味として大葉、しょうが、のりなどを散らして食べた。
カツオ漁で忙しい漁師が獲ったカツオをぶつ切りにし、ごはんにまぜあわせて、手でこねて食べたのが発祥といわれている。準備に時間のかからない料理として、この地方では定番料理として定着したのであった。嘉隆はそれを世話しなく喉にかきこむと、ついには箸を捨て手つかみで食べた。
「恐れながら殿、そろそろ尾張にござる」
背後で金剛九兵衛がいった。
「九兵衛よ、わしはこの船を地之果丸と名づけることにした」
「それはまた変わった名にござるな」
「うむ、信長様とともに地の果てまでも赴く。それ故に地之果丸じゃ」
嘉隆が力強く言いきった時異変はおこった。突如として船体が激しくゆれ、乗組員のうち数名が、立っていることさえできずその場に転倒した。
「何事じゃ! もしや敵の襲撃か?」
嘉隆もかすかに動揺した。敵であるとしたら何者であろうか? もしや伊勢の北畠であろうか?
「申し上げます。ただいまの船体の揺れは、鯨の衝突によるものと判明」
それは全長十メートルにも及ぶマッコウ鯨だった。普段は深海におり、ダイオウイカ等を主食とし、めったに海面に姿を現すことがない。ただ巨大なだけでなく、超音波を使い仲間と会話するともいわれ知能も高い。海面を泳ぐその姿は、まさしく海の化物といってよい。
「小癪な奴!」
嘉隆はその姿を目で追いながら、種子島銃の火縄に着火した。狙いを定めると引き金に手をかけた。轟音があたりに響きわたり。硝煙の香り、そして海の色がたちまちのうちに真っ赤に染まっていく。
「わしに背く者は、皆あの海の化物と同じ目にあわせてくれん! いかに巨大な敵であろうと必ず倒してみせる」
嘉隆は今一度必勝を心に誓うのだった。
それから数ヶ月が過ぎた。織田水軍創設を依頼した小牧山の信長のもとには、安宅船が完成したとの報以来、なに一つ新しい報告はなかった。
「一益、例の志摩の田舎者はその後、いかがなった?」
信長はそれとなく滝川一益にたずねた。
「それが病に倒れたとのことでござる」
一益が言葉を濁しながらいった。
「病? いかような病じゃ?」
「それが原因不明にござる。どうやら乱心に近いようで、夜毎意味不明なことを叫んでは、周りの者を困らせているとのこと」
「うぬ、大事な時だというに……。名医をさしむけて治療をさせよ」
信長はにがり切った表情でいった。
(二)
「己、北畠具教! 己、小浜民部!」
夜が来て、またしても嘉隆の乱心が始まった。槍をふりかざしたかと思うと、憎き相手の名を叫び暴れ狂い 、猛り狂う。すでに側近くに仕えていた者のうち数名が 、嘉隆の乱心の犠牲となり命を落としていた。
しかしこの日、金剛九兵衛はある悲壮な覚悟をもって、乱心の主君を諌めようとしていた。
「お前達 、とりあえず下がっていろ。わしが良しというまで、決して入ってはならぬ。奥方もしばし席を外されよ」
よもや偽物とは知らず、九兵衛は奥方にも退室をうながした。こうして嘉隆に仕える部屋の女達、あれいは小姓等は全て人払いされる。部屋には嘉隆と九兵衛、それに滝川市郎兵衛だけとなった。
嘉隆はしばし狂気の様相を呈していたが、己より体格ではるかに勝る金剛九兵衛の鋭い眼光と目が合うと、しばし平静を取り戻した。
「なんだ九兵衛ではないか。どうしたというのだこんな夜更けに」
嘉隆は手にしていた槍を置き、表向きは穏やかに尋ねた。
「恐れながら、家臣として諫止に参りました。昨日も一昨日も側近くに仕える者を、手討ちにしたとか。主がこの有様では、九鬼家が壊れてしまいまする。どうか今後はこのようなことなきよう、切にお願いつかまつる」
九兵衛は頭を下げて頼んだ。
「ではなにか、お前はわしの側に落ち度があるというのか? あまりにも機転がきかぬので、切り捨てたまでのこと。高々小姓の命ではないか。切り捨てたところでどうということはない」
「もう一度頼み申す。今後はこのようなことなきよう。どうかお願いつかまつる」
九兵衛が今一度懇願した。
「何をいうか。信長様とて……」
「黙れ! 右馬允!」
嘉隆が全ていい終わらないうちに、部屋全体に響きわたるほどの凄まじい怒号が飛んだ。さすがの嘉隆もしばし驚き、戦慄して言葉を失った。
「己! 誰に向かって口をきいておるのだ。右馬允だと?」
九兵衛は鬼の形相を浮べ、そして立ち上がった。
「主、主足らざれば、臣、臣足らず! 今の貴様に人の主を語る資格はない!」
嘉隆は真っ青になった。年齢は嘉隆のほうが一つ、二つほど年長である。しかし九兵衛は子供の頃から体格が良く、幼い頃よくとっくみ合いをして、その度ごとに嘉隆は負けた。その時分の怖かった思い出が再び脳裏をよぎった。
「九兵衛乱心! 方々出会え!」
嘉隆は絶叫したが、むろん周囲には猫の子一匹いなかった。
「叫んでも無駄だ! 右馬允!」
嘉隆が躊躇している間にも、九兵衛は嘉隆の目の前に置いてあった食事用の膳を、荒々しく蹴り飛ばし、嘉隆の胸倉をつかんだ。酒のとっくりが鈍い音を立てて割れる音がした。怪力でねじふせられたため、嘉隆はしばし苦悶の表情をうかべ、激しくせきを繰り返した。
「一体どうしたというのだ九兵衛! 気でも違ったのか?」
「黙れ愚か者! 亡きおじい様より、そして兄君からも九鬼の家を託されたこと、もう忘れたというか! 今は九鬼家存亡の時。乱心している余裕などないことわからんのか! このままでは信長様とて、いずれお主に愛想つかすこと必定。それがわからぬほど御主は愚かなのか?」
嘉隆の胸倉をつかんだままの九兵衛の両の腕が、興奮からか悔しさから、激しく震えていた。
「供に唐・天竺まで赴くと約束したではありませぬか……」
今度は一転して、九兵衛の声は悲痛なものになった。
「主よ……。どうか我が命を奪ってくだされ」
ようやく平静に戻った九兵衛は、つかんでいた手を放し、三歩ほど後ずさりして片膝をついた。
「臣下として申し上げたいことはこれまででござる。金剛九兵衛無礼は腹切ってお詫び申す。どうか心改め、家臣・領民にとり良き主であられるよう……」
そこまでいって九兵衛は、抜刀して刀身を喉元に押し当てた。
「待て、待たぬか、そなたが腹を切る必要などない」
九兵衛の態度が豹変したのでしばし安堵した嘉隆は、今度は腹を切るといいだしたので、再び驚きとにかく止めようとした。
「恐れながら、それがしからもお願いつかまつる」
口を挟んだのは滝川市郎兵衛だった。
「これ以上乱心を続ければ、九鬼家は滅びまする。どうしても正気に戻れぬと仰せなら、それがしも九兵衛殿とともに腹切りまする。九鬼家が滅びる様など見たいとは思いませぬ」
嘉隆は、しばし両者の顔を見比べ、そして拳を強く奮わせた。ある種の後悔が嘉隆の胸を去来していた。
(三)
嘉隆は己の夢の中にいた。
眼下は海である。波の音がひっきりなしにさざめく砂浜で、嘉隆は仰向けになって倒れていた。その光景を麻鳥が、不敵を笑みをうかべながら見下ろしていた。
強靭な意志をおもわせるひきしまった薄い朱唇、やや重たげな瞼の陰の、可憐といっていい哀愁的な黒眸。こうして見ると驚くほどいい女である。
「さらばだな。私はお前の兄と妻を奪った。なれど私もお前のおかげで全てを失った。これも定めと思いあきらめてもらおう」
麻鳥が背を向けたその時である。突如として嘉隆が目を見開き、鋭い刃が麻鳥の右の肩をかすめた。
「そうかお前がわしの兄と妻の命を奪ったのか? 許せん小癪な女め、ここで成敗してくれる」
羽交い絞めにされた麻鳥だったが、すばやく危急を脱し、天空をくるくると舞い刀をかまえた。その時麻鳥は、嘉隆に向かって奇妙なものを投げつけた。それはヒトデだった。
「己、これは一体……?」
かっての浄隆同様、全身が干からびていく。ついに嘉隆は地に伏した。
麻鳥は、息を切らせながらその光景を見守っていたが、今度こそ戦いが終わったことを確信し、安堵のため息をついた。しかしそれもつかの間だった。突然背後から何者かに、刃を喉元に突きつけられたのである。
「今のわしにそなたの術は通用せん。覚悟するがいい」
目の前で死んだはずの嘉隆だった。今一度麻鳥を羽交い絞めにする。
「己! 放せ放さぬか!」
ものすごい力である。麻鳥がいかほど抗おうと無駄だった。ついには麻鳥は服をすべてはがされ、その場に倒された。
どれほど時間が経っただろうか? 両者は激しいやり取りの後、いずれも砂浜に倒れていた。
「こうして満月を見ているとあの日のことを思い出す」
麻鳥は過去を語り始めた。麻鳥は大和の生まれで、母親が西国に赴いた際、賊徒に襲撃され数ヶ月後に生まれたという。こうした不幸の出生であるにも関わらず、母はかろうじて麻鳥を育てようとした。
しかしそれも母親に別の男ができてから変わった。母親の新たな愛人は麻鳥を憎み、母親の目を盗んで川に捨てようとした。まだ三歳児だった麻鳥が、その時目撃したのが満月だった。結局麻鳥は甲賀の忍に助けられ、忍びの道を歩むことになる。
「そなたも根なし草か……わしと同じじゃな。わしも志摩の国を追われ信長殿に仕えることになったが、この先どうなることやら」
「ならば私とともに、二度覚めぬ夢の国へでも行くか」
「なんじゃそれは、そのような世界があるのか」
嘉隆は上半身をおこした。
「私は不覚にもお前にほれた。お前とならどこへでもゆく」
麻鳥は真顔でいうので、嘉隆は少しだけ信じる気になった。ところがその時異変はおこった。
「なりませぬぞ! その者の言葉信じてはいけませぬ」
突然眼下の波浪が激しくなった。その波の中心に一人の女がいた。
「篠!」
嘉隆は思わず叫んだ。やがて凄まじい波しぶきが麻鳥だけを飲み込んでしまう。両者は水中で凄まじい格闘をし、さすがの麻鳥も水を大量に飲み込み、ついに人事不肖となった。
「篠、許してやってくれ。聞けばこの女も哀れな星のもとに生まれた女なのだ」
嘉隆はあえて命ごいした。
「妻と兄を殺されたこと忘れたのですか? 貴方はこの者にたぶらかされております。されどいいでしょう。もはやこの者は、忍びとしての能力は喪失したも同然。今となっては何もできませぬ。嘉隆様が危急のおりには、またかけつけまする。しばしさらばにございます」
篠は消え、嘉隆は夢から覚めた。すでに麻鳥の姿はなかった。こうして麻鳥は嘉隆の前から消えたが、いずれまた、不幸な形で再会するのである。
(四)
二年ほどの歳月が流れた。永禄十年(一五六七)、織田信長は木下藤吉郎等の活躍もあり、念願の美濃攻略をついに果たす。美濃・稲葉山城の斉藤竜興は追放され、信長はただちに国政の中心を小牧山から美濃へと移し、稲葉山を岐阜と改めた。
美濃の国は日本国のほぼ中央を占め、常に東西の勢力が激突する要衝の地である。そして岐阜城は標高三二九メートルという高地にあった。
信長の居館は、現在冠木門と虎口の土塁が復元されている。山麓の一段高くなった千畳敷には、かつてポルトガルの宣教師ルイス・フロイスも紹介した楼閣(信長の住居)が建てられていた。天守からは、長良川が貫流する様を眺めることができた。東に恵那山・木曾御岳山、北には乗鞍・日本アルプス、また西に伊吹・養老・鈴鹿の山系が連なる。南には濃尾平野が豊かに開け、木曾の流れが悠然と伊勢湾に注ぐさまを一望することもできた。
そしてこの頃から、信長は有名な『天下布武』の印判を使用し始めた。信長にとり『天下布武』の手始めは伊勢攻略にあった。都への道を確保するためにも、信長は美濃の次になんとしても、伊勢を支配下におきたかった。
すでに美濃攻略のめどが立ち始めた永禄十年には、同時並行的に滝川一益に命じて北伊勢攻略をも命じてもいる。
伊勢の国の歴史を伊勢神宮と切り離して考えるのは難しい。では何故、俗に八百万の神の国といわれる我が国の中でも、最高の格式を誇るといっていい伊勢神宮がこの地にあるのか? やはり伊勢の国が、それほど日本史において重要な地であることと無縁ではないだろう。そして信長も重々それを承知していた。
伊勢の国とその周辺こそ、多様な顔を持った土地もめずらしい。約千八百キロという縦に長く連なる土地で、東側は遠浅の内湾と黒潮が波打つ海岸線である。西側は千七百メートルを越える大台ヶ原中心として、鈴鹿山脈、台高山脈と、山地がまるで壁のようである。
山地、丘陵、平野部、そして海岸と様々な地形環境があり、そのほぼ中央に西南日本を二部する中央構造線が走っている。
気候もまた雑多である。平野部の温暖な東海型気候、山地性の気候、熊野灘沿岸の気候とそれぞれが異なる。
こうした雑多な風土の影響なのか、戦国時代の伊勢の国は、著しく統一性を欠いていた。
最大勢力はもちろん南伊勢を支配する国司北畠氏であるが、その勢力圏はあくまで南伊勢に限られていた。中勢には神戸・関・長野といった諸豪族が割拠し、さらに尾張と直接接する北伊勢には、実に四十八もの小豪族が割拠していた。
こうした中でも国司北畠氏と中伊勢の長野氏は、南北朝時代から犬猿の仲だった。しかしそれも近年両国の間で妥協が成立し、今の長野氏の主は北畠具教の次男・具藤だった。
しかしこの北畠による、ある意味長野氏の乗っ取りには、長野氏に仕える家臣団の反発もかなりのものだった。家中の主だった者のほとんどは、まだ若い具藤に心服していなかった。
ほどなく織田勢による北伊勢侵攻が開始される。織田勢の総大将は滝川一益だった。甲賀忍者上がりのこの男にとり、合戦前の調略こそ得意中の得意であり、まさに一益のつけいる隙はここにあった。信長による伊勢侵攻は、永禄十一年(一五六八)本格的に開始されるのであった。
0
お気に入りに追加
25
あなたにおすすめの小説

戦国九州三国志
谷鋭二
歴史・時代
戦国時代九州は、三つの勢力が覇権をかけて激しい争いを繰り返しました。南端の地薩摩(鹿児島)から興った鎌倉以来の名門島津氏、肥前(現在の長崎、佐賀)を基盤にした新興の龍造寺氏、そして島津同様鎌倉以来の名門で豊後(大分県)を中心とする大友家です。この物語ではこの三者の争いを主に大友家を中心に描いていきたいと思います。

歴史改変戦記 「信長、中国を攻めるってよ」
高木一優
SF
タイムマシンによる時間航行が実現した近未来、大国の首脳陣は自国に都合の良い歴史を作り出すことに熱中し始めた。歴史学者である私の書いた論文は韓国や中国で叩かれ、反日デモが起る。豊臣秀吉が大陸に侵攻し中華帝国を制圧するという内容だ。学会を追われた私に中国の女性エージェントが接触し、中国政府が私の論文を題材として歴史介入を行うことを告げた。中国共産党は織田信長に中国の侵略を命じた。信長は朝鮮半島を蹂躙し中国本土に攻め入る。それは中華文明を西洋文明に対抗させるための戦略であった。
もうひとつの歴史を作り出すという思考実験を通じて、日本とは、中国とは、アジアとは何かを考えるポリティカルSF歴史コメディー。

鎌倉最後の日
もず りょう
歴史・時代
かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

天竜川で逢いましょう 起きたら関ヶ原の戦い直前の石田三成になっていた 。そもそも現代人が生首とか無理なので平和な世の中を作ろうと思います。
岩 大志
歴史・時代
ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。
けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。
髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。
戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!?

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

織田信長IF… 天下統一再び!!
華瑠羅
歴史・時代
日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。
この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。
主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。
※この物語はフィクションです。

札束艦隊
蒼 飛雲
歴史・時代
生まれついての勝負師。
あるいは、根っからのギャンブラー。
札田場敏太(さつたば・びんた)はそんな自身の本能に引きずられるようにして魑魅魍魎が跋扈する、世界のマーケットにその身を投じる。
時は流れ、世界はその混沌の度を増していく。
そのような中、敏太は将来の日米関係に危惧を抱くようになる。
亡国を回避すべく、彼は金の力で帝国海軍の強化に乗り出す。
戦艦の高速化、ついでに出来の悪い四姉妹は四一センチ砲搭載戦艦に改装。
マル三計画で「翔鶴」型空母三番艦それに四番艦の追加建造。
マル四計画では戦時急造型空母を三隻新造。
高オクタン価ガソリン製造プラントもまるごと買い取り。
科学技術の低さもそれに工業力の貧弱さも、金さえあればどうにか出来る!

改造空母機動艦隊
蒼 飛雲
歴史・時代
兵棋演習の結果、洋上航空戦における空母の大量損耗は避け得ないと悟った帝国海軍は高価な正規空母の新造をあきらめ、旧式戦艦や特務艦を改造することで数を揃える方向に舵を切る。
そして、昭和一六年一二月。
日本の前途に暗雲が立ち込める中、祖国防衛のために改造空母艦隊は出撃する。
「瑞鳳」「祥鳳」「龍鳳」が、さらに「千歳」「千代田」「瑞穂」がその数を頼みに太平洋艦隊を迎え撃つ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる