46 / 57
【第四章】関ヶ原・九州情勢
しおりを挟む
時世はとどまることを知らない。徳川家康は秀吉の死後、じょじょにその野望の本性を露わにしようとしていた。まず諸大名との縁組により、己をとりまく地歩を踏み固めようとはかる。
奥州の伊達政宗の娘と、自らの六男松平忠輝との婚約を成立させたのをかわきりとし、さらに福島正則・蜂須賀家政・加藤清正等にも縁談をもちかける。
豊臣政権下の掟では大名同士の勝手な政略結婚は禁止されており、これは明らかに家康の違法行為である。最初に家康を断罪したのは五奉行石田三成だった。問罪使を送るも、家康は言を左右にするだけで謝罪の言葉一つない。
慶長四年(一五九九)三月三日、三成をはじめとする反家康派に衝撃が走る。生前秀吉が最も頼りとし諸大名の中で唯一、家康に対抗できるだけの勢力をもった加賀の前田利家が、病のため急逝したのである。
ここから家康の独走が始まる。家康は自らが天下の覇権を握るためには、他の何人かと天下分け目の合戦を行い、これに勝利して己の力を世に誇示する必要があると考えていた。
そのためまず、亡き利家の後を継いだ前田利常に謀反の疑いありとして問責使を送る。しかし利常は自らの生母までも家康のもとにさしだし、その矛先をかわした。
家康の挑発に乗ったのは会津の上杉景勝だった。同じく謀反の疑いありとして景勝の上洛をうながすも、景勝はこれを拒否。上杉家家老直江兼続は、後世直江状といわれる激烈かつ痛烈な挑戦状を家康に叩きつけ、ここに家康は嫌でも上杉討伐にたたざるをえなくなった。
家康が会津討伐のため東国に赴けば、その隙をついて石田三成が西国の諸将に呼びかけ、反家康の旗をあげるのは、時間の問題だったのである。
慶長五年(一六〇〇)七月、石田三成はついに打倒家康を決意した。居城佐和山でその覚悟のほどを、まず二十年来の盟友である越前敦賀領主大谷吉継にうちあけた。
「なんと挙兵に及ばれると、その方正気か?」
吉継は、その半ば見えない目で三成をまじまじと見た。大谷吉継は近江の国の出身で四十二歳(豊後大友家の仕官だったという説もあるが真偽は不明)。数年前から業病をわずらい白い頭巾で顔を覆っていた。視力もかなり弱くなっている。
「確かに徳川は関東に二百五十万石の領土を持ち、我等の到底及ばない敵かもしれぬ。なれど徳川憎しの気運は今世に満ち満ちておりまする。我等秀頼君を奉じ立てば、表向きは徳川に従う豊臣恩顧の者等も、大義を重んずれば我等に味方するより他ござりますまい。さすれば我等に勝機なしとは必ずしもいえませぬ」
と、三成は熱弁をふるう。
「愚かな、問題は石高だけではない。徳川憎しの気運世に満ち満ちておると汝は今いうたが、汝憎しの気運もまた世に満ちておる。果たしていかほどの者が、そなたに従うと思っておるのじゃ」
吉継は三成の言を一蹴した。
「そこを無理を承知でお願いしたい。昨今の家康の専横は目に余る。今それがしは毛利家の使僧安国寺殿を通じて、毛利輝元殿に総大将として出馬を願っておりまする。それがしの言に従わぬ者も、毛利殿の言葉には従いまする」
「なんと!」
吉継はかすかに驚いた。
「まずはこれを見られよ」
と石田三成は地図を広げ、自らの必勝の策を説き始めた。
三成の策とは、
一・毛利輝元を西軍総大将の座にすえること
二・三成の兄正澄を近江愛知川に派遣し、会津遠征に向かう諸将を引き止めること
三・京・大坂にいる大名・諸将の妻子を人質にとること
これらの計画の他に具体的な家康迎撃策は、毛利輝元が大坂城に入り、大谷吉継は北陸方面に進出。三成自身は美濃・尾張方面に進出し拠点確保につとめる。さらに家康が西上してきた場合、毛利輝元をして濃尾方面でこれを撃滅する。などというものであった。
吉継は思わず唸った。見事であるといわざるをえない。ただしあくまで机上の理論としてである。合戦の実際が、当初絵に描いたように進行することは古来稀といっていい。一旦事が始まれば、どのように人が動き結末がいかなるものか天のみが知る。だが三成は事が計画通りに進行すると信じていた。官僚三成の限界といっていいだろう。
結局大谷吉継は無謀な挙兵と知りながら、あえて三成とともに死ぬ覚悟を決める。一つには業病のため余命幾ばくもないことを、吉継自身が察していたからでもあった。
三成から大将として出馬要請を受けた毛利輝元は、七月十七日には大坂城西の丸にのりこみ、正式に三成等西軍の統帥の位置につく。一方で毛利勢は九州・豊前門司に上陸し、毛利吉成の小倉城を占領した。さらに隣接する四国・阿波や伊予にも出兵している。
さらに輝元は、上陸にあたって身柄をあずかっていた大友家の前国主大友吉統にも目をつけた。吉統は朝鮮での戦いにおいて思わぬ行き違いから、小西行長を見殺しにしてしまうという大失態を演じてしまった。この報を受けた秀吉が大友家にくだした制裁措置は、全領国没収という、最も重いものだった。鎌倉以来の名門大友家は事実上滅亡し、大友吉統は、かっての宿敵毛利家の食客に身を落としていた。
輝元は吉統に大友家復興の最後の機会であるとし、馬百頭・具足百領・長槍百本・鉄砲三百丁・銀子三千枚等を貸し与え九州に赴かせた。むろん毛利家にしてみれば吉統は単なる『駒』でしかないが、吉統始め大友家旧臣達にとり千載一遇の好機に思えた。
この吉統の動きに敏感に反応した者がいた。かっての大友豊州三老の一人吉弘鑑理の孫で、大友家が事実上滅亡した後、黒田家次いで立花家に仕えていた吉弘統幸だった。統幸は吉統の九州上陸の噂を耳にすると、突如として一通の置き文を残し立花家を後にする。
「恐れながら、いかなることが書かれておりましたか?」
と、立花家家老薦野増時が立花宗茂に尋ねた。
手紙は、旧主大友吉統が毛利家の捨て駒になることを、自分は見て見ぬふりをすることができない。吉統に万一の事があれば、自分は亡き宗麟に黄泉路であわせる顔がなく、大友家に最後の忠勤を励むは今をおいて他にない。立花家に対する恩は忘れがたいが、今は暇乞いを願いたい。という内容のものだった。
「うむ我が父、義父ともに亡くなってから、大友家も人が絶えて久しいが、今まだ、かように忠義な者がおるとはのう」
宗茂は改めて、鎌倉以来の名門大友家という存在を考えずにはいられなかった。
統幸は、わずかな供を連れて道中を急いでいた。ところが途中山道で盗賊に襲われてしまう。抵抗するも多勢に無勢、ついには路銀を全て奪われ、無残にも地に伏してしまうのである。
一方立花家でも東西いずれの側につくかをめぐって、議論が紛糾していた。
「我が立花家は三成殿にお味方し、家康殿と戦うこととする」
軍議の流れが次第、次第に家康に味方し、三成等からの誘いを断るべしという方向に傾こうとする頃、宗茂は突如として鶴の一声をあげ居並ぶ家臣達を驚かせた。
「この柳川十三万石は、まぎれもなく故太閤殿下より拝領したもの。そして徳川殿の豊臣家の天下を奪わんとする野心は明白。例え他の者が誰一人として豊臣の旗のもとに集わずとも、我等だけでも味方するが武士の道」
だが、この宗茂の言葉に家中の者の多くが反対した。
『恐れながら、家康殿に野心明白と申しまするが、三成とて戦勝のあかつきには、豊臣家をないがしろにするやも知れませぬ』
『それがし、こたびの戦まぎれもなく徳川殿の勝ちと考えまする。殿は立花家を潰すつもりでござるか』
『朝鮮の役以来誼を通じている肥後の加藤清正殿からも、徳川殿へお味方するよう、書状がまいっておりまする。清正殿の好意を無にしてはなりませぬ』
「もうよいわ今日の軍議はこれまでじゃ。おまえ達下がってよい」
さしもの宗茂も半ばうんざりしたように、軍議を一方的に打ち切ってしまった。
自らの居室に戻った宗茂を、間もなく妻のぎん千代が訪ねた。
「恐れながら殿、軍議にて三成殿に味方することを決断なされたとか、それはなりませぬ。こたびの戦、まぎれもなく徳川殿に利あると存じまする」
「女子がですぎた口を聞くものではない!」
宗茂は声を荒げた。
「殿は女子の分際でと申しまするが、その女子の浅はかな思慮をもってしても、こたび家康殿に利あることは明らかでござりまする。殿は父君道雪様の意思を無にするおつもりでございましょうか?」
「ならば聞こう我が義父ならば、こたびいかようにしたと思う?」
ぎん千代はしばし言葉を失った。ぎん千代の心の乱れを見透かしたように宗茂は、
「そういえば、そなたに見せたいものがあった」
と、不意に一編の巻物をぎん千代に手渡した。それは見事な女人の絵だった。
「それはのう、ぎん千代、我が義父がそなたを描かせたものよ。わしはこたび討ち死にするやもしれぬ。あれいは腹切らねばならぬやもしれぬ。なれど武士には時として、命にかえても守らねばならぬ節義というものがある。じゃがそなたは、わしが死んだ後は刀槍を捨て、女として生きよ。わしが申したきはそれだけじゃ」
ぎん千代は、しばし宗茂が遠い存在になったように思え、不意にその胸に抱きついた。両者にも運命の時が近づいたいた。
豊前中津。ここに風雲に乗じて一旗上げんと野心に燃える、一人の初老の男の姿があった。かっての秀吉の懐刀黒田官兵衛、出家して如水である。黒田如水は文禄・慶長の役の際も軍監として朝鮮に渡ったが、石田三成等若手奉行衆と対立し、秀吉の思わぬ勘気をこうむることとなった。そのため出家して俗世を捨てたかのようにも思えたが、その野望まで捨てたわけではない。
「三成ごときが、家康を相手に一戦しようとは片腹痛いわい。小童が錯乱しおったか」
と如水は中津城ではき捨てるようにいった。黒田家は瀬戸内に早船による通報システムを置き、上方の情勢変化は三日で豊前まで達する。
「恐れながら大殿は、やはり家康殿にこの戦、利があるとお考えか? 長政様を家康殿のもとに赴かせたは、むろん三成より家康殿を高く買っているということでござりましょうか?」
黒田家家臣井上九郎右衛門は、如水の腹の底をうかがうかのように尋ねた。如水の嫡子黒田長政は、すでに家康に従い遠く会津まで出兵していた。そのため如水の手元に残された兵はわずかである。
「なに三成ごときが乱を起こすは、片腹痛いかぎりであるが、家康とて天下の主たる器ではないわ」
「なれば大殿は、ゆくゆく天下の主たるお方はいずこにおわすと?」
「わからぬか? 天下を取るは三成でも家康でもない。このわしじゃ」
「なんと仰せられた?」
「太閤もかって申したのをそなたも存じておろう。自ら亡き後天下を手にするは、このわしであると。恐らくこたびの戦、短時日にて決着はつくまい。さすれば九州は、この老骨がたちどころに制して素早く上方にはせ上る。家康、三成ともに痛手を負ったところで、わしが天下を制することとなる」
「お言葉なれど、我が黒田家の士卒の大半は御嫡子長政殿に従い会津に赴いておりまする。九州を平定するにしても兵が少なすぎるかと……」
九郎右衛門は、如水の自身過剰ぶりにやや呆れながらも疑念をていした。
「九郎右衛門よ、武士たるもの常に有事の際の心構えができておらねばならぬ。わしが日頃吝嗇のそしりを受けてまで、金銭米穀を蓄えしは何故だと思う?」
如水は自信に満ちた様子でいった。そしてただちに天下取りのための募兵にかかるのである。蓄えの全てを放出し、九州中の牢人をかき集め、その数およそ三千五百。応募者の中には混乱に乗じて、銀子の二重取りを図る不届き者もいたが、如水は役人に見て見ぬふりをするよう申しわたしていた。おそらく如水は本気で天下を掌握するつもであったのだろう。だが如水の野心を砕いたもの、それは他ならぬ嫡子長政だった……。
肥前の国、ここにも天下を二分する乱を前に去就に迷う一人の男がいた。鍋島直茂である。すでに直茂は、龍造寺家の政権を事実上簒奪していたといってよい。浮世の相場師として類稀な才に恵まれた直茂であったが、今回ばかりは悩みに悩んでいた。
直茂もまた如水同様、大坂に最も有能な家臣を駐屯させ瀬戸内を帆走する船をもって、情報が数日をもって肥前に達する伝達機構をもっていた。そして如水同様当初は『三成ずれが……』という思いが強かった。だが三成等西軍に集う兵の数は、多くて三万ほどという直茂の予測をはるかに越えるものだった。さらに日本列島を分断して、会津の上杉とともに家康を挟撃するという三成の構想の雄大さも、長年狭い肥前の野をかけめぐってきた直茂の想像を越えるものだった。
「そなたは、こたびの戦いずれに利があると思うか?」
と六十三歳の直茂は、二十一歳の嫡子勝茂に問うた。
「されば人望からしても、実戦における経歴からしても、家康殿ははるかに三成をしのいでおるものと存じます。なれど大義という面においては、家康殿は不利にござりまする。家康殿がゆくゆくその威をもって、豊臣家の政権を簒奪しようとする野心、果たして豊臣恩顧の諸将が黙って見過ごすか否か……」
「威をもって政権を簒奪しようとする野心とな……」
直茂の表情が曇った。勝茂の不覚は自らの言葉が、龍造寺家の政権を奪った直茂にも当てはまることに、気付いていないことだった。
『人とは不義なるもの……不仁なるもの……』
不意に旧主隆信の言葉が、直茂の脳裏をよぎった。
「父上、どこかお体でも悪うござりますか?」
「勝茂よ大器はあえて事に乗ずる。小器はうかと乗せられるもの。人の心を知る者こそ最後に勝利する。大義などというものは、戦に勝利すれば自然とついてくるものじゃ。家康殿に刃向かってはならぬ。ゆくゆく天下は徳川のものとなる」
直茂は最終決断をくだした。さらに直茂のしたたかさは、銀五百貫という莫大な費用をもって、恐らく主戦場となるであろう東海地方の米を買い占めてしまったことである。勝ち易きと思う側に兵糧米を持参する腹であった。
しかしその直茂も予想できない事態が勃発する。鍋島勢を率い大坂に赴いた勝茂が、近江路を行軍中、愛知川に設けられた三成の兄正澄の関所の前で思わぬ足止めをくい、不本意にも西軍の一翼をになうこととなってしまったことである。
大友吉統は豊後に上陸し、久方ぶりとなる九州の山河をあおぎ見た。そして別府湾に面する立石城を拠点とした。その立石城に不意の来客があった。男は一見すると物乞いそのものである。
「なんだお前は、そなたのような者がうろつく場所ではないわ。去れ去れ」
城の警護の兵士は、即座に物乞いを追い払おうとした。
「いや待て見覚えがある顔じゃ、もしや貴方様は……」
門番の一人が、物乞いの正体に気付いた。
「吉統様に取り次いでくれ。大友家旧臣吉弘統幸、主の危急を知り急ぎかけつけたと……」
それはあまりに力ない声だった。
「なるほどのう。道中山賊にでくわすとは、そなたも不運な男よのう」
正装した統幸は、あらためて吉統に拝謁した。
「じゃが命まで奪われなかったことは不幸中の幸い。この吉統そなたほどの忠義の者を、危うく野垂れ死にさせるところであった」
「もったいのうお言葉、はせ参じたかいがあったというもの」
「うむ、そなたにはいずれ豊後を取り戻した後、どこなりと褒美の土地をあたえるぞ」
統幸の表情が瞬時曇った。
「あいや待たれよ毛利は信用なりませぬ。殿を利用するだけ利用して、事が成就したあかつきには約束を反古にしてしまうことは、十分に考えられまする」
「馬鹿な、わしは毛利より多額の銭と兵を借りてしまった。今更後には退けんのじゃ」
「恐れながら殿は、大内輝弘殿のことをご存知か?」
大内輝弘は、大友家と毛利家が刃を交えた永禄十二年の多々良浜合戦のおり、大友宗麟の要請により、大内家再興の志とともに毛利の背後を突くべく周防に上陸した。むろん軍勢等は全て宗麟が貸し与えた。だが末路は悲惨だった。即座に軍を返した吉川元春・小早川隆景の部隊により手痛い反撃にあい、山口での抵抗を諦め海路での脱出経路を探るべく海沿いをさまようも、追撃厳しく富海の茶臼山にて自害して果てたのである。
「大内輝弘殿を見殺しにしたは確かに先君の不徳。なれど政(まつりごと)とは時として、かくも非常なものなのでござります」
「わしをかような者と同じというか!」
臆病になったのか、吉統は悲鳴にも似た声をあげた。
『相変わらず意思の弱い方じゃ……』
統幸はため息をついた。
『この方では、こたびの風雲を乗りきれたとしても、あれいは大友の先行きは最早ありえぬかもしれぬ……』
統幸は決心した。例え事やぶれたとしても、名門大友家の名に恥じぬ引き際を、自らの手で演出するということをである。それが吉弘統幸にとり、亡き宗麟への最後の忠義でもあった……。
奥州の伊達政宗の娘と、自らの六男松平忠輝との婚約を成立させたのをかわきりとし、さらに福島正則・蜂須賀家政・加藤清正等にも縁談をもちかける。
豊臣政権下の掟では大名同士の勝手な政略結婚は禁止されており、これは明らかに家康の違法行為である。最初に家康を断罪したのは五奉行石田三成だった。問罪使を送るも、家康は言を左右にするだけで謝罪の言葉一つない。
慶長四年(一五九九)三月三日、三成をはじめとする反家康派に衝撃が走る。生前秀吉が最も頼りとし諸大名の中で唯一、家康に対抗できるだけの勢力をもった加賀の前田利家が、病のため急逝したのである。
ここから家康の独走が始まる。家康は自らが天下の覇権を握るためには、他の何人かと天下分け目の合戦を行い、これに勝利して己の力を世に誇示する必要があると考えていた。
そのためまず、亡き利家の後を継いだ前田利常に謀反の疑いありとして問責使を送る。しかし利常は自らの生母までも家康のもとにさしだし、その矛先をかわした。
家康の挑発に乗ったのは会津の上杉景勝だった。同じく謀反の疑いありとして景勝の上洛をうながすも、景勝はこれを拒否。上杉家家老直江兼続は、後世直江状といわれる激烈かつ痛烈な挑戦状を家康に叩きつけ、ここに家康は嫌でも上杉討伐にたたざるをえなくなった。
家康が会津討伐のため東国に赴けば、その隙をついて石田三成が西国の諸将に呼びかけ、反家康の旗をあげるのは、時間の問題だったのである。
慶長五年(一六〇〇)七月、石田三成はついに打倒家康を決意した。居城佐和山でその覚悟のほどを、まず二十年来の盟友である越前敦賀領主大谷吉継にうちあけた。
「なんと挙兵に及ばれると、その方正気か?」
吉継は、その半ば見えない目で三成をまじまじと見た。大谷吉継は近江の国の出身で四十二歳(豊後大友家の仕官だったという説もあるが真偽は不明)。数年前から業病をわずらい白い頭巾で顔を覆っていた。視力もかなり弱くなっている。
「確かに徳川は関東に二百五十万石の領土を持ち、我等の到底及ばない敵かもしれぬ。なれど徳川憎しの気運は今世に満ち満ちておりまする。我等秀頼君を奉じ立てば、表向きは徳川に従う豊臣恩顧の者等も、大義を重んずれば我等に味方するより他ござりますまい。さすれば我等に勝機なしとは必ずしもいえませぬ」
と、三成は熱弁をふるう。
「愚かな、問題は石高だけではない。徳川憎しの気運世に満ち満ちておると汝は今いうたが、汝憎しの気運もまた世に満ちておる。果たしていかほどの者が、そなたに従うと思っておるのじゃ」
吉継は三成の言を一蹴した。
「そこを無理を承知でお願いしたい。昨今の家康の専横は目に余る。今それがしは毛利家の使僧安国寺殿を通じて、毛利輝元殿に総大将として出馬を願っておりまする。それがしの言に従わぬ者も、毛利殿の言葉には従いまする」
「なんと!」
吉継はかすかに驚いた。
「まずはこれを見られよ」
と石田三成は地図を広げ、自らの必勝の策を説き始めた。
三成の策とは、
一・毛利輝元を西軍総大将の座にすえること
二・三成の兄正澄を近江愛知川に派遣し、会津遠征に向かう諸将を引き止めること
三・京・大坂にいる大名・諸将の妻子を人質にとること
これらの計画の他に具体的な家康迎撃策は、毛利輝元が大坂城に入り、大谷吉継は北陸方面に進出。三成自身は美濃・尾張方面に進出し拠点確保につとめる。さらに家康が西上してきた場合、毛利輝元をして濃尾方面でこれを撃滅する。などというものであった。
吉継は思わず唸った。見事であるといわざるをえない。ただしあくまで机上の理論としてである。合戦の実際が、当初絵に描いたように進行することは古来稀といっていい。一旦事が始まれば、どのように人が動き結末がいかなるものか天のみが知る。だが三成は事が計画通りに進行すると信じていた。官僚三成の限界といっていいだろう。
結局大谷吉継は無謀な挙兵と知りながら、あえて三成とともに死ぬ覚悟を決める。一つには業病のため余命幾ばくもないことを、吉継自身が察していたからでもあった。
三成から大将として出馬要請を受けた毛利輝元は、七月十七日には大坂城西の丸にのりこみ、正式に三成等西軍の統帥の位置につく。一方で毛利勢は九州・豊前門司に上陸し、毛利吉成の小倉城を占領した。さらに隣接する四国・阿波や伊予にも出兵している。
さらに輝元は、上陸にあたって身柄をあずかっていた大友家の前国主大友吉統にも目をつけた。吉統は朝鮮での戦いにおいて思わぬ行き違いから、小西行長を見殺しにしてしまうという大失態を演じてしまった。この報を受けた秀吉が大友家にくだした制裁措置は、全領国没収という、最も重いものだった。鎌倉以来の名門大友家は事実上滅亡し、大友吉統は、かっての宿敵毛利家の食客に身を落としていた。
輝元は吉統に大友家復興の最後の機会であるとし、馬百頭・具足百領・長槍百本・鉄砲三百丁・銀子三千枚等を貸し与え九州に赴かせた。むろん毛利家にしてみれば吉統は単なる『駒』でしかないが、吉統始め大友家旧臣達にとり千載一遇の好機に思えた。
この吉統の動きに敏感に反応した者がいた。かっての大友豊州三老の一人吉弘鑑理の孫で、大友家が事実上滅亡した後、黒田家次いで立花家に仕えていた吉弘統幸だった。統幸は吉統の九州上陸の噂を耳にすると、突如として一通の置き文を残し立花家を後にする。
「恐れながら、いかなることが書かれておりましたか?」
と、立花家家老薦野増時が立花宗茂に尋ねた。
手紙は、旧主大友吉統が毛利家の捨て駒になることを、自分は見て見ぬふりをすることができない。吉統に万一の事があれば、自分は亡き宗麟に黄泉路であわせる顔がなく、大友家に最後の忠勤を励むは今をおいて他にない。立花家に対する恩は忘れがたいが、今は暇乞いを願いたい。という内容のものだった。
「うむ我が父、義父ともに亡くなってから、大友家も人が絶えて久しいが、今まだ、かように忠義な者がおるとはのう」
宗茂は改めて、鎌倉以来の名門大友家という存在を考えずにはいられなかった。
統幸は、わずかな供を連れて道中を急いでいた。ところが途中山道で盗賊に襲われてしまう。抵抗するも多勢に無勢、ついには路銀を全て奪われ、無残にも地に伏してしまうのである。
一方立花家でも東西いずれの側につくかをめぐって、議論が紛糾していた。
「我が立花家は三成殿にお味方し、家康殿と戦うこととする」
軍議の流れが次第、次第に家康に味方し、三成等からの誘いを断るべしという方向に傾こうとする頃、宗茂は突如として鶴の一声をあげ居並ぶ家臣達を驚かせた。
「この柳川十三万石は、まぎれもなく故太閤殿下より拝領したもの。そして徳川殿の豊臣家の天下を奪わんとする野心は明白。例え他の者が誰一人として豊臣の旗のもとに集わずとも、我等だけでも味方するが武士の道」
だが、この宗茂の言葉に家中の者の多くが反対した。
『恐れながら、家康殿に野心明白と申しまするが、三成とて戦勝のあかつきには、豊臣家をないがしろにするやも知れませぬ』
『それがし、こたびの戦まぎれもなく徳川殿の勝ちと考えまする。殿は立花家を潰すつもりでござるか』
『朝鮮の役以来誼を通じている肥後の加藤清正殿からも、徳川殿へお味方するよう、書状がまいっておりまする。清正殿の好意を無にしてはなりませぬ』
「もうよいわ今日の軍議はこれまでじゃ。おまえ達下がってよい」
さしもの宗茂も半ばうんざりしたように、軍議を一方的に打ち切ってしまった。
自らの居室に戻った宗茂を、間もなく妻のぎん千代が訪ねた。
「恐れながら殿、軍議にて三成殿に味方することを決断なされたとか、それはなりませぬ。こたびの戦、まぎれもなく徳川殿に利あると存じまする」
「女子がですぎた口を聞くものではない!」
宗茂は声を荒げた。
「殿は女子の分際でと申しまするが、その女子の浅はかな思慮をもってしても、こたび家康殿に利あることは明らかでござりまする。殿は父君道雪様の意思を無にするおつもりでございましょうか?」
「ならば聞こう我が義父ならば、こたびいかようにしたと思う?」
ぎん千代はしばし言葉を失った。ぎん千代の心の乱れを見透かしたように宗茂は、
「そういえば、そなたに見せたいものがあった」
と、不意に一編の巻物をぎん千代に手渡した。それは見事な女人の絵だった。
「それはのう、ぎん千代、我が義父がそなたを描かせたものよ。わしはこたび討ち死にするやもしれぬ。あれいは腹切らねばならぬやもしれぬ。なれど武士には時として、命にかえても守らねばならぬ節義というものがある。じゃがそなたは、わしが死んだ後は刀槍を捨て、女として生きよ。わしが申したきはそれだけじゃ」
ぎん千代は、しばし宗茂が遠い存在になったように思え、不意にその胸に抱きついた。両者にも運命の時が近づいたいた。
豊前中津。ここに風雲に乗じて一旗上げんと野心に燃える、一人の初老の男の姿があった。かっての秀吉の懐刀黒田官兵衛、出家して如水である。黒田如水は文禄・慶長の役の際も軍監として朝鮮に渡ったが、石田三成等若手奉行衆と対立し、秀吉の思わぬ勘気をこうむることとなった。そのため出家して俗世を捨てたかのようにも思えたが、その野望まで捨てたわけではない。
「三成ごときが、家康を相手に一戦しようとは片腹痛いわい。小童が錯乱しおったか」
と如水は中津城ではき捨てるようにいった。黒田家は瀬戸内に早船による通報システムを置き、上方の情勢変化は三日で豊前まで達する。
「恐れながら大殿は、やはり家康殿にこの戦、利があるとお考えか? 長政様を家康殿のもとに赴かせたは、むろん三成より家康殿を高く買っているということでござりましょうか?」
黒田家家臣井上九郎右衛門は、如水の腹の底をうかがうかのように尋ねた。如水の嫡子黒田長政は、すでに家康に従い遠く会津まで出兵していた。そのため如水の手元に残された兵はわずかである。
「なに三成ごときが乱を起こすは、片腹痛いかぎりであるが、家康とて天下の主たる器ではないわ」
「なれば大殿は、ゆくゆく天下の主たるお方はいずこにおわすと?」
「わからぬか? 天下を取るは三成でも家康でもない。このわしじゃ」
「なんと仰せられた?」
「太閤もかって申したのをそなたも存じておろう。自ら亡き後天下を手にするは、このわしであると。恐らくこたびの戦、短時日にて決着はつくまい。さすれば九州は、この老骨がたちどころに制して素早く上方にはせ上る。家康、三成ともに痛手を負ったところで、わしが天下を制することとなる」
「お言葉なれど、我が黒田家の士卒の大半は御嫡子長政殿に従い会津に赴いておりまする。九州を平定するにしても兵が少なすぎるかと……」
九郎右衛門は、如水の自身過剰ぶりにやや呆れながらも疑念をていした。
「九郎右衛門よ、武士たるもの常に有事の際の心構えができておらねばならぬ。わしが日頃吝嗇のそしりを受けてまで、金銭米穀を蓄えしは何故だと思う?」
如水は自信に満ちた様子でいった。そしてただちに天下取りのための募兵にかかるのである。蓄えの全てを放出し、九州中の牢人をかき集め、その数およそ三千五百。応募者の中には混乱に乗じて、銀子の二重取りを図る不届き者もいたが、如水は役人に見て見ぬふりをするよう申しわたしていた。おそらく如水は本気で天下を掌握するつもであったのだろう。だが如水の野心を砕いたもの、それは他ならぬ嫡子長政だった……。
肥前の国、ここにも天下を二分する乱を前に去就に迷う一人の男がいた。鍋島直茂である。すでに直茂は、龍造寺家の政権を事実上簒奪していたといってよい。浮世の相場師として類稀な才に恵まれた直茂であったが、今回ばかりは悩みに悩んでいた。
直茂もまた如水同様、大坂に最も有能な家臣を駐屯させ瀬戸内を帆走する船をもって、情報が数日をもって肥前に達する伝達機構をもっていた。そして如水同様当初は『三成ずれが……』という思いが強かった。だが三成等西軍に集う兵の数は、多くて三万ほどという直茂の予測をはるかに越えるものだった。さらに日本列島を分断して、会津の上杉とともに家康を挟撃するという三成の構想の雄大さも、長年狭い肥前の野をかけめぐってきた直茂の想像を越えるものだった。
「そなたは、こたびの戦いずれに利があると思うか?」
と六十三歳の直茂は、二十一歳の嫡子勝茂に問うた。
「されば人望からしても、実戦における経歴からしても、家康殿ははるかに三成をしのいでおるものと存じます。なれど大義という面においては、家康殿は不利にござりまする。家康殿がゆくゆくその威をもって、豊臣家の政権を簒奪しようとする野心、果たして豊臣恩顧の諸将が黙って見過ごすか否か……」
「威をもって政権を簒奪しようとする野心とな……」
直茂の表情が曇った。勝茂の不覚は自らの言葉が、龍造寺家の政権を奪った直茂にも当てはまることに、気付いていないことだった。
『人とは不義なるもの……不仁なるもの……』
不意に旧主隆信の言葉が、直茂の脳裏をよぎった。
「父上、どこかお体でも悪うござりますか?」
「勝茂よ大器はあえて事に乗ずる。小器はうかと乗せられるもの。人の心を知る者こそ最後に勝利する。大義などというものは、戦に勝利すれば自然とついてくるものじゃ。家康殿に刃向かってはならぬ。ゆくゆく天下は徳川のものとなる」
直茂は最終決断をくだした。さらに直茂のしたたかさは、銀五百貫という莫大な費用をもって、恐らく主戦場となるであろう東海地方の米を買い占めてしまったことである。勝ち易きと思う側に兵糧米を持参する腹であった。
しかしその直茂も予想できない事態が勃発する。鍋島勢を率い大坂に赴いた勝茂が、近江路を行軍中、愛知川に設けられた三成の兄正澄の関所の前で思わぬ足止めをくい、不本意にも西軍の一翼をになうこととなってしまったことである。
大友吉統は豊後に上陸し、久方ぶりとなる九州の山河をあおぎ見た。そして別府湾に面する立石城を拠点とした。その立石城に不意の来客があった。男は一見すると物乞いそのものである。
「なんだお前は、そなたのような者がうろつく場所ではないわ。去れ去れ」
城の警護の兵士は、即座に物乞いを追い払おうとした。
「いや待て見覚えがある顔じゃ、もしや貴方様は……」
門番の一人が、物乞いの正体に気付いた。
「吉統様に取り次いでくれ。大友家旧臣吉弘統幸、主の危急を知り急ぎかけつけたと……」
それはあまりに力ない声だった。
「なるほどのう。道中山賊にでくわすとは、そなたも不運な男よのう」
正装した統幸は、あらためて吉統に拝謁した。
「じゃが命まで奪われなかったことは不幸中の幸い。この吉統そなたほどの忠義の者を、危うく野垂れ死にさせるところであった」
「もったいのうお言葉、はせ参じたかいがあったというもの」
「うむ、そなたにはいずれ豊後を取り戻した後、どこなりと褒美の土地をあたえるぞ」
統幸の表情が瞬時曇った。
「あいや待たれよ毛利は信用なりませぬ。殿を利用するだけ利用して、事が成就したあかつきには約束を反古にしてしまうことは、十分に考えられまする」
「馬鹿な、わしは毛利より多額の銭と兵を借りてしまった。今更後には退けんのじゃ」
「恐れながら殿は、大内輝弘殿のことをご存知か?」
大内輝弘は、大友家と毛利家が刃を交えた永禄十二年の多々良浜合戦のおり、大友宗麟の要請により、大内家再興の志とともに毛利の背後を突くべく周防に上陸した。むろん軍勢等は全て宗麟が貸し与えた。だが末路は悲惨だった。即座に軍を返した吉川元春・小早川隆景の部隊により手痛い反撃にあい、山口での抵抗を諦め海路での脱出経路を探るべく海沿いをさまようも、追撃厳しく富海の茶臼山にて自害して果てたのである。
「大内輝弘殿を見殺しにしたは確かに先君の不徳。なれど政(まつりごと)とは時として、かくも非常なものなのでござります」
「わしをかような者と同じというか!」
臆病になったのか、吉統は悲鳴にも似た声をあげた。
『相変わらず意思の弱い方じゃ……』
統幸はため息をついた。
『この方では、こたびの風雲を乗りきれたとしても、あれいは大友の先行きは最早ありえぬかもしれぬ……』
統幸は決心した。例え事やぶれたとしても、名門大友家の名に恥じぬ引き際を、自らの手で演出するということをである。それが吉弘統幸にとり、亡き宗麟への最後の忠義でもあった……。
0
お気に入りに追加
63
あなたにおすすめの小説
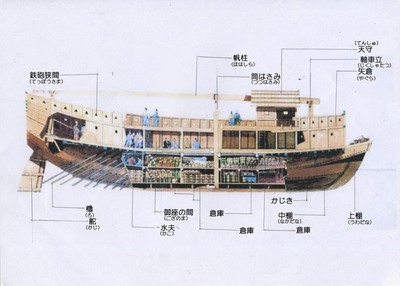

命の番人
小夜時雨
歴史・時代
時は春秋戦国時代。かつて名を馳せた刀工のもとを一人の怪しい男が訪ねてくる。男は刀工に刀を作るよう依頼するが、彼は首を縦には振らない。男は意地になり、刀を作ると言わぬなら、ここを動かぬといい、腰を下ろして--。
二人の男の奇妙な物語が始まる。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~
橋本洋一
歴史・時代
この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。
記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。
これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語
※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります
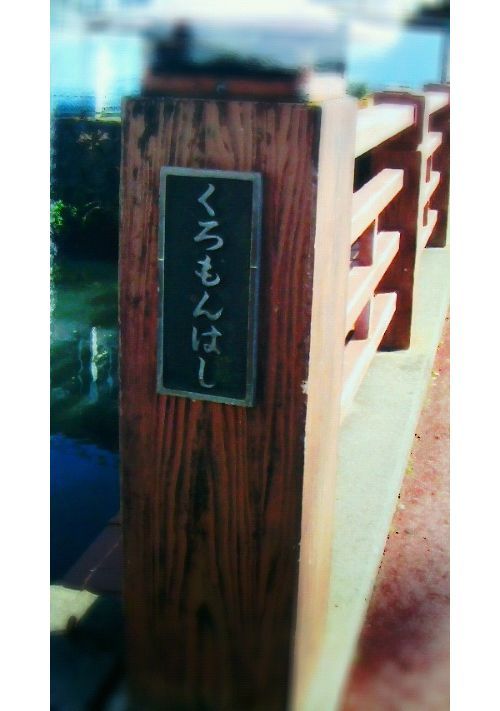
肥後の春を待ち望む
尾方佐羽
歴史・時代
秀吉の天下統一が目前になった天正の頃、肥後(熊本)の国主になった佐々成政に対して国人たちが次から次へと反旗を翻した。それを先導した国人の筆頭格が隈部親永(くまべちかなが)である。彼はなぜ、島津も退くほどの強大な敵に立ち向かったのか。国人たちはどのように戦ったのか。そして、九州人ながら秀吉に従い国人衆とあいまみえることになった若き立花統虎(宗茂)の胸中は……。

抜け忍料理屋ねこまんま
JUN
歴史・時代
里を抜けた忍者は、抜け忍として追われる事になる。久磨川衆から逃げ出した忍者、疾風、八雲、狭霧。彼らは遠く離れた地で新しい生活を始めるが、周囲では色々と問題が持ち上がる。目立ってはいけないと、影から解決を図って平穏な毎日を送る兄弟だが、このまま無事に暮らしていけるのだろうか……?

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















