39 / 57
【第三章】文禄の役 碧蹄館の戦い
しおりを挟む朝鮮各地で義兵の蜂起に苦しみ、李舜臣に制海権を握られた日本軍の戦況は、日毎に悪化していった。ここにさらに衝撃的な事態が生ずる。朝鮮王朝の度々の要請により、ついに中国・明王朝が動きだしたのである。
中国・明王朝は、太祖洪武帝こと朱元璋により一三六八年に建国された。朱元璋なる人物は、元は社会の最下層の乞食坊主で、いわば才覚と実力だけで大中華の皇帝にまでなった、傑物中の傑物である。その点日本の豊臣秀吉と似ているといえば似ている。
この王朝の全盛期は太祖の孫、明朝三代目成祖永楽帝の時世で、この時代明王朝は宦官の鄭和という者をして、遠くアフリカ東海岸まで艦隊を派遣している。日本でいえば、室町幕府の三代将軍義満の時世のことである。
明王朝の国威というものは、あれいはそれ以前に中国大陸を支配した、漢や唐をも上回っていたかもしれない。
小西行長は、黒田長政、大友吉統(義統あらため)等の助力もえて、文禄元年六月すでに平壌を征服していた。朝鮮宣祖王は、さらに北方寧辺まで逃亡し、明国の援軍が来着するのを今や遅しと待っていた。
七月、明軍は動きだした。祖承君という将軍に五千の兵が従い、鴨緑江を越え、七月十五日夜半、小西行長始めとする日本側の大軍が駐屯する平壌城へ殺到した。だが日本兵は、初めて見る明国兵に最初動揺しながらも力戦し、鉄砲を乱射し、ついにはこれを撃退する。明国側では武将三人が負傷し、祖承君自身も傷を負った。
日本側は逃げる明国軍を追撃すべきであったろう。だが動かなった。またしても小西行長が、朝鮮王との交渉を試みていたのである。ここに明国朝廷の使節を名乗る、奇怪な人物が登場する。沈惟敬なる明国人で、遊撃将軍なる肩書きを持っていたが、その実、元はならず者であったといわれる。そして筋金入りの詐欺漢とでもいうべき食わせ者で、明国朝廷に日本側の事情通と偽り、自らを売りこみ、小西行長をも結果的に騙してしまう。
行長は、この沈惟敬なる人物を信じ、講和交渉のための条件を提出した。すなわち、秀吉を日本国王に封じ朝貢を実現させることと、朝鮮大同江以南の割譲である。むろん、この大同江以南の割譲という講和条件は、朝鮮王朝を蚊帳の外においた日明両国の密約であった。
行長は、明国朝廷に交渉に赴いた沈惟敬の帰りをひたすら待った。そうこうしている間に、年が明けて文禄二年となった。この間明帝国では、後顧の憂いであった北方寧夏でのモンゴル人の叛乱が鎮圧され、和平どころか日本打倒のため、着々と軍備を整えていたのである。
「一体いつまでここで待てばよろしいのか、小西殿」
軍議の席上声を荒げたのは、秀吉の懐刀黒田如水の嫡男黒田長政だった。この人物は眉がちょうど八の字のように垂れ下がっていて、そのためどこか気弱な印象を人に与えるが、その実器量は尋常一様ではない。
「沈惟敬なる者と約束した交渉期限は、とうの昔に過ぎ去りましたぞ。もしやしたら講和とは真っ赤な偽りではござらぬのか?」
「それがしもそう思いまする。あれいは時を稼ぎ、敵は軍備を万全とする腹では?」
と長政に同意したのは、行長の娘婿でもある宗義智だった。
「待たれよ、事は大事ゆえ明国の朝廷も決めかねているものと存ずる」
と、行長が反論する。
「まずはそれがしを信じていただきたい。それがし、若年の頃より明国にも赴き、かの国の者を各々方より存じておるつもりじゃ。かの国の者等は、決して真偽に反するようなふるまいは致しもうさぬはず」
とはいったものの、行長は明国の民の表裏相反する気質をも知っており、自らの言葉に一時疑念をもたずにはいられなかった。
「ならば何故に沈惟敬なる者は、ここに戻らぬのじゃ」
長政はいら立った。
「交渉事とは、ある種かけでござる」
「急がねばなりませんぞ、すでに冬の季節、わが軍の大半は南国育ち、戦となれば不利でござる」
果たして長政の予感は、不幸な形で的中してしまうのである。
この間も明軍は平壌に迫っていた。大将は李如松という、北方遊牧民との戦いで度々武功をたてた老練な将で、率いる兵およそ五万。戦端は突如として開かれることとなる。行長が待ちに待った沈惟敬が不意に戻ってきて、
「交渉のため李如松将軍が、近く平壌に派遣されることとなった。貴公等におかれては、出迎えの準備をなされよ」
と偽りをいった。だが小西は信じた。小西は決して愚鈍な男ではない。商人上がりとはいえ、知力も胆力も常人以上に優れている。ところが沈惟敬という、ある種の詐欺漢を単純に信じてしまうのである。一同に正装させ、城門の外で李如松将軍の来着を待っていた行長にもたらされたものは、交渉事ではなく、明らかに合戦の支度であるという、物見の知らせだった。
「いかがなされるおつもりか! 敵は五万はいるという。ひきかえ我等は一万五千ほど!」
正装したままの宗義智が声を荒げる。
「拙者の生涯の不覚、この上は腹切っておわび致す所存」
さすがの行長も、聞きとれぬほどの声だった。
「父上が腹切っても詮なき事、合戦の支度じゃ!」
義智は城内に向かい、大音声をあげた。
一方、黒田長政は一旦漢城まで退き、全軍団統一して事に当たるべきと、使者をもって説いたが、行長はこれをも退けた。理由は漢城に退くことにより、講和交渉に齟齬をきたしてしまうからであった。
一月七日黎明、明・朝鮮連合軍による攻撃は、かって日本軍が見たことのない、射石砲により開始された。太鼓の音が響きわたり、明軍は隊列を整え一直線に城に迫る。明軍はそのほとんどが騎兵である。そして日本の刀や槍では傷一つ付けることができない、鋼鉄製の鎧に身を包んでいた。攻城兵器として彼等は、井桁の高楼を組み城に迫る。さらにカタパルト式の大砲が、これを援護した。その威力は計り知れず、
『その響き、万雷のごとく、山岳、震撼す。火箭を乱射し、烟焔数十里にみなぎり、咫尺分かたず、ただ吶喊の声、砲響にまじわるを聞く』
という有様であった。
さらに日本兵を驚かせたのは、明国兵の中にシャム国(現在のタイ)や東南アジア出身の兵まで含まれていたことだった。明王朝がこれらの国に兵を送り、多くの現地人が明国に帰化した。そして彼等は明軍の兵士となったのである。これらとは別に、ポルトガル人の雇われ兵までいた。明人や朝鮮人なら外形日本兵とさして変わらないが、明らかに肌の色からして違う兵卒は、それだけで日本兵を畏怖させることとなった。
日本軍は鉄砲を乱射し、明軍を再三に渡って押し返したが、数の差、兵器の差はいかんともしがたく、行長も万策尽きた。
「かくなりたるうえは、鳳山まで撤退するより他ありませぬ」
宗義智がいい、行長もそれに従う。凄惨を極める撤退劇が始まった。まず手負いの者が雪降る野に捨てられた。さらに日本兵は朝鮮の厳寒に対する備えが、ほぼ皆無であった。兵士達は雪の上を草鞋で行進しなければならず、多くの者が凍傷にかかり、足の指を失う事態にまでなった。
鳳山には大友吉統が砦を構えていた。だがここに不幸な行き違いが生じる。大友の陣に小西行長が討ち死にしたという誤報が広まり、大友全軍が浮き足立ったのである。
「今はもうこれまで、事ここに至った以上、全軍討って出て果てましょうぞ」
と出撃を主張したのは、かって若輩の身ながら豊後で、島津義弘の大軍を退けた志賀親次だった。だが吉統は動揺しているのか、意味不明の言葉を発してはいるが、家臣達には聞き取れない。大友吉統は、ひどい吃音だったといわれる。
「待たれい、敵は大軍、今は兵を退く時でござろう」
と撤退論を口にしたのは、耳川の合戦で父である吉弘鎮信を失って以来、大友氏の勢力挽回に生涯を捧げてきた吉弘統幸だった。
「馬鹿な! いかに敵が大軍とはいえ、一戦もせず逃げるは武門の恥」
と志賀親次が反論する。
「ここが豊後であるなら、拙者も戦することに異論はござらぬ。されど、今ここには守るべき領土もなかれば領民もござらぬ。そもそもこたびの戦は、太閤殿下が手前勝手に始められた戦。かような戦で吉統様を無碍に死なせるわけにはいかぬ!」
「さりながら……」
「この吉弘統幸、先君が丹生島城でお倒れになったおり、吉統様と大友家を頼むと後事を託された。もし万一の時は、拙者腹切ってでも太閤殿下をお諌めいたす!」
吉弘統幸は語を強くし、出撃を主張する志賀親次等を押し切った。行長がたどりついた頃には、鳳山には一兵もいなかった。行長はこの後、かろうじて黒田長政の竜泉城までたどりついたが、具足一つすら身にまとっていない体であったといわれる。
黒田長政、小西行長等は、小早川隆景、立花宗茂等のいる京畿道・開城まで撤退する。さらに一同は漢城にまで軍を退いた。そしてここに、咸鏡道に赴いた加藤清正・鍋島直茂等を除く、朝鮮在陣諸侯の多くが集結した。軍議が開かれるが、明軍強しの噂は、すでに諸侯の知るところであり、座の空気は苦しいものとなった。籠城か決戦か、やがて軍議の方向は籠城策やむなしの方角へ傾き始める。
「それがし討ってでるべきと思いまする。敵は大軍、しかも強兵なれど、ここは千載一遇 の好機にかけるより他なきかと」
と決戦を主張したのは立花宗茂だった。
「控えよ立花左近!」
と、この遠征軍の事実上の総大将をつとめる、宇喜多秀家が一喝した。
「そなたは戦すると申すが、敵の鎧は我等の弓矢を寄せつけず、我国の戦では使用されたことのない兵器を、数多所持していると聞く。かような兵といかように戦すると申すか」
宇喜多秀家は声を荒げた。秀家は自らと同じく年若の宗茂に、ある種の敵愾心のようなものをもっていたのである。
「恐れながら、それがしも決戦すべきと存じる。そして先陣は、ここにおる立花左近殿をおいて他にないものと存ずる」
諸将が一斉に声の主の方角を見た。むろん宗茂も振り返った。それは、この年齢六十一となった小早川隆景だった。
「拙者は昔、父元就に従い、数限りなく大友の兵と刃を交えたが、特にここにおわす立花左近殿の父道雪殿の兵は手強く、恥ずかしながらそれがし、幾度も苦渋をなめさせられもうした。立花殿の兵三千は、他家の一万にも匹敵するであろう。こたびの戦の先陣は立花殿以外になきものと存ずる」
老将の凛呼とした声に、軍議の方角は一変することとなる。この時すでに、明の李如松率いる十万の部隊は、開城にまで迫ろうとしていた。
宗茂は、漢城から約二十キロの碧蹄館に登り眼下の風景を、小早川秀包と馬の轡を並べて見下ろしていた。碧蹄館とは、明使節接遇のための館という意味で地名になったという。両側に丘陵が迫り、南北に長い谷をなし、その谷底は一面水田もしくは湿地である。宗茂、秀包いずれの脳裏にも、やがてこの地を埋めつくすであろう明兵の姿が思い描かれていた。
「敵は聞きしに勝る強敵と聞くが、左近そなたかような敵と、いかようにして戦するつもりじゃ?」
「今はわしにもわからぬ。ただわしは、立花の名に恥じぬよう戦するのみじゃ」
と秀包の問いに対し、宗茂はやや頼りなげなことをいった。
「そうか策はなしか、あれいは我等、この朝鮮の野に屍をさらすことになるやもしれんのう」
秀包はかすかに遠い目をした。
「我が父が申しておったぞ、昨夜そなたの義父が夢枕に立たれ、そなたのことを頼むと一言残して消えたと」
宗茂は、表情に驚きの色をうかべた。
「いやはや、よもやかっての宿敵に、息子にも等しいそなたのことを託されるとはと、父も苦笑しておったわい」
秀包もまた笑みをうかべた。
「それはそうと、わしもそなたに見せたいものがあるのじゃ」
秀包が懐から取りだしのは十字架だった。
「こたびの遠征に際し、我妻がくれたものよ。そして、そなたのかっての主君の形見でもある」
宗茂は、さらに驚きの色をうかべた。秀包もまた妻の影響もあり切支丹の洗礼を受けており、シマオ・フィンデナオという洗礼名まで持っていた。
「そなたの父上の形見故、そなたが大事に持っておればよいと何度もいうたが、妻がどうしてもというので、ありがたく頂戴した……。思えば我等不思議な縁で結ばれておるものよのう。敵として戦い、そして今この朝鮮の野で、陣を同じくすることになるとは……。宗茂死ぬなよ、そなたが死ぬくらいなら、わしが死ぬ。わしが死んでも、そなたを生かさねばならぬような気がしてならんのじゃ」
秀包は宗茂の手を握った。この時宗茂二十七歳、秀包もまた同じ年。あれいは義兄弟の契りまでかわした秀包とも、これが今生の別れになるかもしれぬ。そう思うと宗茂もまた万感の思いであった。
この時明将李如松の不覚は、あれほど日本軍を悩ました大砲無しで、決戦に望もうとしたことだった。すでに李如松は日本軍を侮っていた。自らの直属部隊である騎兵隊に、戦での功をたてさせようとはかったのである。
一月二十六日未明、李如松と明兵は碧蹄館に軍勢を進め、先鋒部隊二千が、宗茂の臣十時伝右衛門率いる五百の物見兵と遭遇した。ただちに伝令は宗茂のもとへ走る。白銀色の鎧に身を包んだ塊が、次第、次第に迫ってくる。この時、明兵の前に最初に立ちはだかった武者がいた。
「聞け異国の兵ども! 我こそは、かの本能寺の変のおり、信長公に一番槍を付けた天野源右衛門であるぞ、我が武勇とくとご覧あれ!」
むろん言葉が通じるわけがない。だがその気迫に、明兵もまた一時静寂があった。源右衛門は明兵と槍を交えること数合、ついには矢で肩を射ぬかれ馬から転がり落ちた。
「源右衛門に続け!」
伝右衛門の号令とともに、隆景をして三千で一万に相当するといわしめた、立花勢が明兵に攻めかかる。
伝令を受け、宗茂は戦場に急ぎ参じた。だが宗茂率いる一隊が到着する頃には、伝右衛門はすでにこの世の人ではなかった。十時隊は力戦し、敵の先鋒部隊を一時押し返したものの、続いて現われた明軍第二軍一万八千に三方より攻められ、ついに討ち死にしたのである。
「例え我異国の野に果てようと……我鬼となり、必ずや若殿をお守り致す」
それが、この道雪以来の立花家股肱の臣の最期の言葉だった。
「伝右衛門の死を無駄にするな! 皆かかれい!」
宗茂もまた力戦奮闘し、明兵は二千の兵を失い再び後退を余儀なくされる。ここに小早川勢、宇喜多勢三万八千が立花勢三千と合流した。
やがて両軍は対峙したまま動かなくなる。宗茂は小丸山に陣取り、敵の様子をうかがう。やがて十万の明兵が、静かに、ゆっくりと、息を殺しながら迫ってくる。それはまるで、天地山河が一つの意思のもとに統率され、動めいているかのような軍兵だった。さしもの宗茂も、これほどの大軍相手に合戦したことはない。他の日本側の諸侯も、しばし声をも失った。宇喜多秀家は、高鳴る鼓動とはやる心を抑えきれず、
「全軍突撃!」
とやや自制心を欠いた命令を、揮下の将兵に降してしまう。
「いかん、まだ早い! 早すぎる!」
老練な将隆景は思わず叫んだ。隆景のいうとおり、宇喜多隊の突撃は卵が山に向かっていくようなものだった。たちまちのうちに粉砕され、宇喜多勢は後退する。これにより日本側の他の部隊も動揺した。鋼鉄製の鎧に身を包んだ明軍は、まるで鉄でできた化け物が人を蹴散らすかのように、日本軍をものともしない。
だが宗茂は小丸山に陣取り動こうとしなかった。正面から当たっても撃退される。ならば時を待ち、乾坤一擲の機にかけるしかない。
明兵は逃げる日本兵を追い、足場の悪いぬかるみに入った。突如として激しい雨が降り出し、明兵の足場を泥沼へと変えた。その時である。
「いまぞ突撃!」
雷鳴と同時に、宗茂の虎のような大音声が戦場に響きわたった。立花隊は一斉に山を降り明軍に殺到する。ここに予想外の事態がおこった。動きのとれない明兵は、たちまちのうちに立花隊の鉄砲・弓の餌食となり、異常な混乱状態となったのである。
李如松ら明軍は北方の女真族との戦いなどで、常に広大な平原を騎兵で疾駆して戦いに勝利してきた。一方、寡兵とはいえ敵を狭い土地に誘いこんで戦うことは、日本の戦国武将達の得意とするところだった。
小早川隆景が父元就とともに、約五倍から六倍の陶晴賢の軍を撃破した厳島の戦い。島津家久が数倍の龍造寺隆信の軍に勝利した、沖田畷の戦いなどその代表例である。
「立花隊に遅れるな進め!」
隆景もまた采配を一閃、小早川秀包も槍を奮い突撃する。戦いは闇の中、壮絶な激戦となる。だがやはり勝敗を決したのは立花勢の阿修羅のような奮闘ぶりだった。明兵もまた立花勢を恐れ、牛の刻(午前十二時)ついに明将李如松が戦線を離脱。勝敗は決定的となった。立花宗茂はこの激戦で騎馬まで血塗れとなり、四つの甲首を鞍の双方に付け、刀は歪んで鞘に戻せなくなるほどの奮戦だった。そしてようやく勝利を確信したその時、宗茂にとって不幸な出来事がおこる。死に者狂いの敵兵が放った矢が、宗茂の左肩に命中。宗茂は馬から転げ落ち意識を失いかけたのである。
「宗茂しっかりせい! そなたに死なれては、わしはそなたの義父に、なんと詫びたらよいのじゃ」
板輿に乗せられて運ばれてきた宗茂に、小早川隆景が必死に声をかける。宗茂はかすかに薄目を開いた。そのとき宗茂には隆景の顔が、義父道雪に見えた。宗茂は自らが死出の旅路に赴くとおもった。
「父上、それがしは立花の名に恥じませんでしたぞ……」
それだけいうと、宗茂は再び意識を失った。
宗茂は三日三晩生死の境をさまよったが、かろうじて命を失うことはなかった。
この敗戦で、明国は日本兵の手強さを知った。一方の日本側もまた、この戦勝以後戦線を打開することができなくなる。戦役は泥沼と化し、やがて明・朝鮮と日本との間に講和の空気が少しずつめばえ始めるのである。
0
お気に入りに追加
63
あなたにおすすめの小説
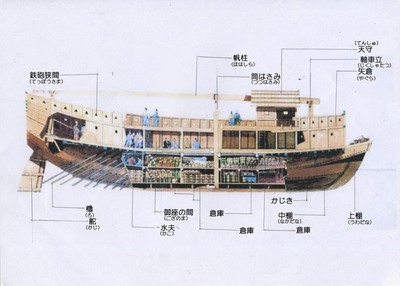

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

抜け忍料理屋ねこまんま
JUN
歴史・時代
里を抜けた忍者は、抜け忍として追われる事になる。久磨川衆から逃げ出した忍者、疾風、八雲、狭霧。彼らは遠く離れた地で新しい生活を始めるが、周囲では色々と問題が持ち上がる。目立ってはいけないと、影から解決を図って平穏な毎日を送る兄弟だが、このまま無事に暮らしていけるのだろうか……?

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

とべない天狗とひなの旅
ちはやれいめい
歴史・時代
人間嫌いで悪行の限りを尽してきた天狗、フェノエレーゼ。
主君サルタヒコの怒りを買い、翼を封じられ人里に落とされてしまう。
「心から人間に寄り添い助けろ。これ以上悪さをすると天狗に戻れなくなるぞ」
とべなくなったフェノエレーゼの事情を知って、人里の童女ヒナが、旅についてきた。
人間嫌いの偏屈天狗と、天真爛漫な幼女。
翼を取り戻すため善行を積む旅、はじまりはじまり。
絵・文 ちはやれいめい
https://mypage.syosetu.com/487329/
フェノエレーゼデザイン トトさん
https://mypage.syosetu.com/432625/

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

旧式戦艦はつせ
古井論理
歴史・時代
真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

この争いの絶えない世界で ~魔王になって平和の為に戦いますR
ばたっちゅ
ファンタジー
相和義輝(あいわよしき)は新たな魔王として現代から召喚される。
だがその世界は、世界の殆どを支配した人類が、僅かに残る魔族を滅ぼす戦いを始めていた。
無為に死に逝く人間達、荒廃する自然……こんな無駄な争いは止めなければいけない。だが人類にもまた、戦うべき理由と、戦いを止められない事情があった。
人類を会話のテーブルまで引っ張り出すには、結局戦争に勝利するしかない。
だが魔王として用意された力は、死を予感する力と全ての文字と言葉を理解する力のみ。
自分一人の力で戦う事は出来ないが、強力な魔人や個性豊かな魔族たちの力を借りて戦う事を決意する。
殺戮の果てに、互いが共存する未来があると信じて。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















