34 / 57
34.俺、首輪をはめられる
しおりを挟む
「よし! 今日の昼は完成だ!」
『カンセイダ!』
真似っこ大好きのエンに癒やされた俺は、研究室の方へ顔を出す。昼食の準備が終わったら声を掛けるようシンシアに言われていたのだ。
「あ、来たんだしー?」
「いや、呼んだのシンシアだろ」
俺がツッコむと、シンシアが「それもそーか」と頭を掻いた。なお、本日の爪は薄紫色だ。
「ってことで、これねー」
シンシアは俺にとある物体を突き出した。これ、俺の認識が正しければ、なんだかよろしくないものな気がするんだが……。
「これ、って、首輪、だよな?」
黒い皮のベルト状のものに、ちょっと厳めしい鋲が打ってある。もっとベルトが長ければ腰に装着するものだと胸を張って言えたんだが……。
「そだよー。はい、付けてー」
「いや、なんで首輪を付けなきゃなんないんだ?」
「え? だって主席の宿題だしー?」
「は? ミモさんが俺にそんな……って!」
あの常識人なミモさんに限って、そんなことをするわけがない、と反論しようと思ったところで、シンシアは強引に俺の首にベルトを巻く。はっきり言って、犬とかに付ける首輪にしか見えないコレをどうしろと? 俺には特殊な趣味はないぞ?
「んー? 予想通り、かなー?」
シンシアは俺を色々な方向から眺め、うんうん、と一人勝手に頷いている。
「はい、見てみてー」
ぐいぐい押しつけられた手鏡は、まさか呪いの鏡とかやないよな? 随分と前にお邸で耳にした怪談が蘇り、背筋がぞわりと粟立った。
――――あれは、鏡の中の自分とジャンケンして勝った話だったか。いや、夜中に鏡を覗き込んだら、誰もいない筈の後ろに血みどろの女が映って、慌てて逃げるが、鏡という鏡に血みどろの女が映るようになり、しかもだんだんその女が近づいてきて……
「いや、この鏡、変だろ」
「変じゃないよー?」
鏡を覗き込むと、何故か俺が映っていなかった。その代わりに映っているのは、研究所では見たことのない魔族の男。何やら疑わしいことがあるようで、鏡の向こう側からこちらをじっと見つめている。
「うわー、自分を見つめちゃったりして、ちょーキモー」
「はぁ!?」
俺は隣ではやし立てているシンシアに向き直った。聞き捨てならない。俺は断じて自己愛陶酔者じゃない!
「だーかーらー、それ、ミケだって」
「どういうことだ?」
「ミケを魔族っぽく見せるチョーカーだっての」
シンシアの説明に、俺はもう一度鏡の向こうの自分と向き合った。
魔族特有の灰色の肌。瞳は黒だし、髪も栗色のままだ。ただ、肌が灰色だというだけで、印象がほとんど別物になってしまっている。さらに、生え際あたりにちょこんと生えているのは、角、か?
ただ、一つだけ、俺が言えることは――
「これは、絶対に、チョーカーじゃないだろう!」
痛々しい黒の首輪に、シンシアのセンスを疑う。ファッションセンスの問題なのかもしれないが、俺はこれをアクセサリーとして受けいれられない。
「えー? チョーカーだよー。ねぇ、シャーくん、これってチョーカーだよねー?」
呼ばれたシャラウィは、俺を見るなりきょとんとした。
「シンシア姉さん、部外者は入れちゃダメって主席に言われてるんだねぃ」
「違うって、これミケだってばさー」
「ミケーレ? ……もしかして、首のそれが変装用の? 相変わらずシンシア姉さんのセンスはそっち方面なんだねぃ」
やれやれ、と言った様子で肩をすくめたシャラウィは、「人のセンスにケチつける気!?」と半ば本気で背中をばちこーんと叩かれていた。容赦ないな、シンシア。
「ミケーレ、こればっかりはシンシア姉さんの尖ったセンスのせいなんだねぃ。シンシア姉さんはそういう系が好きだから仕方ないんだねぃ」
諦めろと俺に諭すシャラウィは、自分の机に戻ると何かを書き込んでまたすぐに戻ってきた。
「しばらくは、これを付けてた方がいいんだねぃ」
シャラウィは俺の右胸と背中に何かを張る。なんだろうと思って胸を見れば「ミケーレ」と名前が書かれていた。いまさら名札とか必要か?と首を傾げる。
「僕みたいに、部外者と間違える研究員がいるかもしれないんだねぃ。皆が慣れるまでは、それを張っておくといいと思うんだねぃ」
「確かに、追い出されちゃかなわんな」
シャラウィの配慮はありがたく受け取っておくことにして、問題は目の前で頬を膨らませつつ胸を張る、なんて器用なことをしているシンシアをどうするか、だ。
「何よ、尖ったセンスとか言いたい放題して!」
「ちなみに、別のデザインのチョーカーにする予定は」
「あるわけないじゃん、めんどー!」
その後、ミモさんがやってきて、シンシアの作った魔族偽装用のチョーカーにゴーサインを出したので、俺は一日中首輪を付けることが決定してしまった。ミモさんは、デザインとかには頓着せず、しっかり偽装しているかどうかの能力重視らしい。
一日中首輪を付けてるからって、そういうセンスでも、そういう趣味でもないからな! と外に向かって叫びたくなった俺を、きっと誰も責めないだろう。制作者のシンシア以外。
『カンセイダ!』
真似っこ大好きのエンに癒やされた俺は、研究室の方へ顔を出す。昼食の準備が終わったら声を掛けるようシンシアに言われていたのだ。
「あ、来たんだしー?」
「いや、呼んだのシンシアだろ」
俺がツッコむと、シンシアが「それもそーか」と頭を掻いた。なお、本日の爪は薄紫色だ。
「ってことで、これねー」
シンシアは俺にとある物体を突き出した。これ、俺の認識が正しければ、なんだかよろしくないものな気がするんだが……。
「これ、って、首輪、だよな?」
黒い皮のベルト状のものに、ちょっと厳めしい鋲が打ってある。もっとベルトが長ければ腰に装着するものだと胸を張って言えたんだが……。
「そだよー。はい、付けてー」
「いや、なんで首輪を付けなきゃなんないんだ?」
「え? だって主席の宿題だしー?」
「は? ミモさんが俺にそんな……って!」
あの常識人なミモさんに限って、そんなことをするわけがない、と反論しようと思ったところで、シンシアは強引に俺の首にベルトを巻く。はっきり言って、犬とかに付ける首輪にしか見えないコレをどうしろと? 俺には特殊な趣味はないぞ?
「んー? 予想通り、かなー?」
シンシアは俺を色々な方向から眺め、うんうん、と一人勝手に頷いている。
「はい、見てみてー」
ぐいぐい押しつけられた手鏡は、まさか呪いの鏡とかやないよな? 随分と前にお邸で耳にした怪談が蘇り、背筋がぞわりと粟立った。
――――あれは、鏡の中の自分とジャンケンして勝った話だったか。いや、夜中に鏡を覗き込んだら、誰もいない筈の後ろに血みどろの女が映って、慌てて逃げるが、鏡という鏡に血みどろの女が映るようになり、しかもだんだんその女が近づいてきて……
「いや、この鏡、変だろ」
「変じゃないよー?」
鏡を覗き込むと、何故か俺が映っていなかった。その代わりに映っているのは、研究所では見たことのない魔族の男。何やら疑わしいことがあるようで、鏡の向こう側からこちらをじっと見つめている。
「うわー、自分を見つめちゃったりして、ちょーキモー」
「はぁ!?」
俺は隣ではやし立てているシンシアに向き直った。聞き捨てならない。俺は断じて自己愛陶酔者じゃない!
「だーかーらー、それ、ミケだって」
「どういうことだ?」
「ミケを魔族っぽく見せるチョーカーだっての」
シンシアの説明に、俺はもう一度鏡の向こうの自分と向き合った。
魔族特有の灰色の肌。瞳は黒だし、髪も栗色のままだ。ただ、肌が灰色だというだけで、印象がほとんど別物になってしまっている。さらに、生え際あたりにちょこんと生えているのは、角、か?
ただ、一つだけ、俺が言えることは――
「これは、絶対に、チョーカーじゃないだろう!」
痛々しい黒の首輪に、シンシアのセンスを疑う。ファッションセンスの問題なのかもしれないが、俺はこれをアクセサリーとして受けいれられない。
「えー? チョーカーだよー。ねぇ、シャーくん、これってチョーカーだよねー?」
呼ばれたシャラウィは、俺を見るなりきょとんとした。
「シンシア姉さん、部外者は入れちゃダメって主席に言われてるんだねぃ」
「違うって、これミケだってばさー」
「ミケーレ? ……もしかして、首のそれが変装用の? 相変わらずシンシア姉さんのセンスはそっち方面なんだねぃ」
やれやれ、と言った様子で肩をすくめたシャラウィは、「人のセンスにケチつける気!?」と半ば本気で背中をばちこーんと叩かれていた。容赦ないな、シンシア。
「ミケーレ、こればっかりはシンシア姉さんの尖ったセンスのせいなんだねぃ。シンシア姉さんはそういう系が好きだから仕方ないんだねぃ」
諦めろと俺に諭すシャラウィは、自分の机に戻ると何かを書き込んでまたすぐに戻ってきた。
「しばらくは、これを付けてた方がいいんだねぃ」
シャラウィは俺の右胸と背中に何かを張る。なんだろうと思って胸を見れば「ミケーレ」と名前が書かれていた。いまさら名札とか必要か?と首を傾げる。
「僕みたいに、部外者と間違える研究員がいるかもしれないんだねぃ。皆が慣れるまでは、それを張っておくといいと思うんだねぃ」
「確かに、追い出されちゃかなわんな」
シャラウィの配慮はありがたく受け取っておくことにして、問題は目の前で頬を膨らませつつ胸を張る、なんて器用なことをしているシンシアをどうするか、だ。
「何よ、尖ったセンスとか言いたい放題して!」
「ちなみに、別のデザインのチョーカーにする予定は」
「あるわけないじゃん、めんどー!」
その後、ミモさんがやってきて、シンシアの作った魔族偽装用のチョーカーにゴーサインを出したので、俺は一日中首輪を付けることが決定してしまった。ミモさんは、デザインとかには頓着せず、しっかり偽装しているかどうかの能力重視らしい。
一日中首輪を付けてるからって、そういうセンスでも、そういう趣味でもないからな! と外に向かって叫びたくなった俺を、きっと誰も責めないだろう。制作者のシンシア以外。
0
お気に入りに追加
145
あなたにおすすめの小説

転生悪役令嬢に仕立て上げられた幸運の女神様は家門から勘当されたので、自由に生きるため、もう、ほっといてください。今更戻ってこいは遅いです
青の雀
ファンタジー
公爵令嬢ステファニー・エストロゲンは、学園の卒業パーティで第2王子のマリオットから突然、婚約破棄を告げられる
それも事実ではない男爵令嬢のリリアーヌ嬢を苛めたという冤罪を掛けられ、問答無用でマリオットから殴り飛ばされ意識を失ってしまう
そのショックで、ステファニーは前世社畜OL だった記憶を思い出し、日本料理を提供するファミリーレストランを開業することを思いつく
公爵令嬢として、持ち出せる宝石をなぜか物心ついたときには、すでに貯めていて、それを原資として開業するつもりでいる
この国では婚約破棄された令嬢は、キズモノとして扱われることから、なんとか自立しようと修道院回避のために幼いときから貯金していたみたいだった
足取り重く公爵邸に帰ったステファニーに待ち構えていたのが、父からの勘当宣告で……
エストロゲン家では、昔から異能をもって生まれてくるということを当然としている家柄で、異能を持たないステファニーは、前から肩身の狭い思いをしていた
修道院へ行くか、勘当を甘んじて受け入れるか、二者択一を迫られたステファニーは翌早朝にこっそり、家を出た
ステファニー自身は忘れているが、実は女神の化身で何代前の過去に人間との恋でいさかいがあり、無念が残っていたので、神界に帰らず、人間界の中で転生を繰り返すうちに、自分自身が女神であるということを忘れている
エストロゲン家の人々は、ステファニーの恩恵を受け異能を覚醒したということを知らない
ステファニーを追い出したことにより、次々に異能が消えていく……
4/20ようやく誤字チェックが完了しました
もしまだ、何かお気づきの点がありましたら、ご報告お待ち申し上げておりますm(_)m
いったん終了します
思いがけずに長くなってしまいましたので、各単元ごとはショートショートなのですが(笑)
平民女性に転生して、下剋上をするという話も面白いかなぁと
気が向いたら書きますね

【完結】悪役令嬢に転生したけど、王太子妃にならない方が幸せじゃない?
みちこ
ファンタジー
12歳の時に前世の記憶を思い出し、自分が悪役令嬢なのに気が付いた主人公。
ずっと王太子に片思いしていて、将来は王太子妃になることしか頭になかった主人公だけど、前世の記憶を思い出したことで、王太子の何が良かったのか疑問に思うようになる
色々としがらみがある王太子妃になるより、このまま公爵家の娘として暮らす方が幸せだと気が付く

少し冷めた村人少年の冒険記
mizuno sei
ファンタジー
辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。
トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。
優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。

【完結】転生7年!ぼっち脱出して王宮ライフ満喫してたら王国の動乱に巻き込まれた少女戦記 〜愛でたいアイカは救国の姫になる
三矢さくら
ファンタジー
【完結しました】異世界からの召喚に応じて6歳児に転生したアイカは、護ってくれる結界に逆に閉じ込められた結果、山奥でサバイバル生活を始める。
こんなはずじゃなかった!
異世界の山奥で過ごすこと7年。ようやく結界が解けて、山を下りたアイカは王都ヴィアナで【天衣無縫の無頼姫】の異名をとる第3王女リティアと出会う。
珍しい物好きの王女に気に入られたアイカは、なんと侍女に取り立てられて王宮に!
やっと始まった異世界生活は、美男美女ぞろいの王宮生活!
右を見ても左を見ても「愛でたい」美人に美少女! 美男子に美少年ばかり!
アイカとリティア、まだまだ幼い侍女と王女が数奇な運命をたどる異世界王宮ファンタジー戦記。
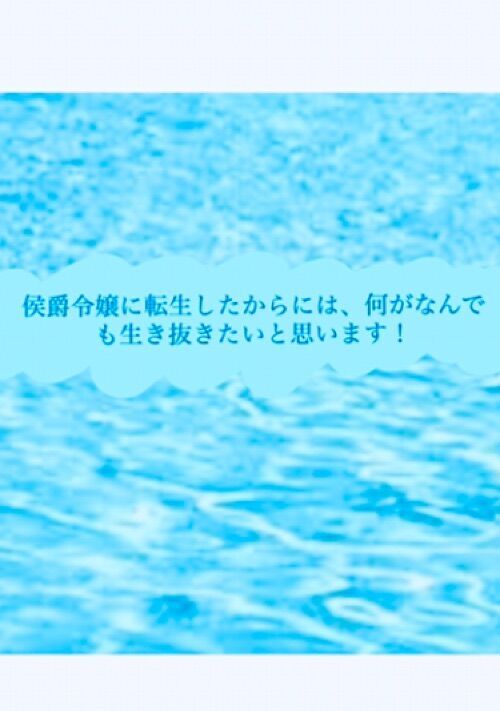
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

私のお父様とパパ様
棗
ファンタジー
非常に過保護で愛情深い二人の父親から愛される娘メアリー。
婚約者の皇太子と毎月あるお茶会で顔を合わせるも、彼の隣には幼馴染の女性がいて。
大好きなお父様とパパ様がいれば、皇太子との婚約は白紙になっても何も問題はない。
※箱入り娘な主人公と娘溺愛過保護な父親コンビのとある日のお話。
追記(2021/10/7)
お茶会の後を追加します。
更に追記(2022/3/9)
連載として再開します。

どうも、死んだはずの悪役令嬢です。
西藤島 みや
ファンタジー
ある夏の夜。公爵令嬢のアシュレイは王宮殿の舞踏会で、婚約者のルディ皇子にいつも通り罵声を浴びせられていた。
皇子の罵声のせいで、男にだらしなく浪費家と思われて王宮殿の使用人どころか通っている学園でも遠巻きにされているアシュレイ。
アシュレイの誕生日だというのに、エスコートすら放棄して、皇子づきのメイドのミュシャに気を遣うよう求めてくる皇子と取り巻き達に、呆れるばかり。
「幼馴染みだかなんだかしらないけれど、もう限界だわ。あの人達に罰があたればいいのに」
こっそり呟いた瞬間、
《願いを聞き届けてあげるよ!》
何故か全くの別人になってしまっていたアシュレイ。目の前で、アシュレイが倒れて意識不明になるのを見ることになる。
「よくも、義妹にこんなことを!皇子、婚約はなかったことにしてもらいます!」
義父と義兄はアシュレイが状況を理解する前に、アシュレイの体を持ち去ってしまう。
今までミュシャを崇めてアシュレイを冷遇してきた取り巻き達は、次々と不幸に巻き込まれてゆき…ついには、ミュシャや皇子まで…
ひたすら一人づつざまあされていくのを、呆然と見守ることになってしまった公爵令嬢と、怒り心頭の義父と義兄の物語。
はたしてアシュレイは元に戻れるのか?
剣と魔法と妖精の住む世界の、まあまあよくあるざまあメインの物語です。
ざまあが書きたかった。それだけです。

凡人がおまけ召喚されてしまった件
根鳥 泰造
ファンタジー
勇者召喚に巻き込まれて、異世界にきてしまった祐介。最初は勇者の様に大切に扱われていたが、ごく普通の才能しかないので、冷遇されるようになり、ついには王宮から追い出される。
仕方なく冒険者登録することにしたが、この世界では希少なヒーラー適正を持っていた。一年掛けて治癒魔法を習得し、治癒剣士となると、引く手あまたに。しかも、彼は『強欲』という大罪スキルを持っていて、倒した敵のスキルを自分のものにできるのだ。
それらのお蔭で、才能は凡人でも、数多のスキルで能力を補い、熟練度は飛びぬけ、高難度クエストも熟せる有名冒険者となる。そして、裏では気配消去や不可視化スキルを活かして、暗殺という裏の仕事も始めた。
異世界に来て八年後、その暗殺依頼で、召喚勇者の暗殺を受けたのだが、それは祐介を捕まえるための罠だった。祐介が暗殺者になっていると知った勇者が、改心させよう企てたもので、その後は勇者一行に加わり、魔王討伐の旅に同行することに。
最初は脅され渋々同行していた祐介も、勇者や仲間の思いをしり、どんどん勇者が好きになり、勇者から告白までされる。
だが、魔王を討伐を成し遂げるも、魔王戦で勇者は祐介を庇い、障害者になる。
祐介は、勇者の嘘で、病院を作り、医師の道を歩みだすのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















