お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

日本鬼士 -JAPAN・Alternative・SAMURAI-
きりたぽん
ファンタジー
神聖なる力の輝きに溢れる選ばれし、正義と秩序の国。
対するは、蒸気の煙に紛れ蠱毒の檻壊れし、混沌の国。
天空より舞い降りし使途が、正義の剣を振りかざせば、外骨格の鎧を纏いし異形の武者が、顎を開き進撃する。
魔導を極めし者達が、与えられし鎧を装着するなら、魑魅魍魎を供物に捧げ、蒸気のブリキを揺り動かす。
これは、異世界の大河物語。

天才たちとお嬢様
釧路太郎
キャラ文芸
綾乃お嬢様には不思議な力があるのです。
なぜだかわかりませんが、綾乃お嬢様のもとには特別な才能を持った天才が集まってしまうのです。
最初は神山邦弘さんの料理の才能惚れ込んだ綾乃お嬢様でしたが、邦宏さんの息子の将浩さんに秘められた才能に気付いてからは邦宏さんよりも将浩さんに注目しているようです。
様々なタイプの天才の中でもとりわけ気づきにくい才能を持っていた将浩さんと綾乃お嬢様の身の回りで起こる楽しくも不思議な現象はゆっくりと二人の気持ちを変化させていくのでした。
この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」に投稿しております

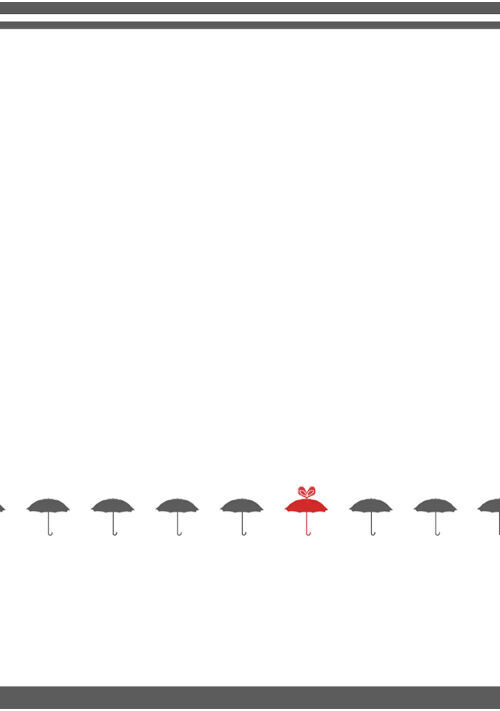
こちら夢守市役所あやかしよろず相談課
木原あざみ
キャラ文芸
異動先はまさかのあやかしよろず相談課!? 変人ばかりの職場で始まるほっこりお役所コメディ
✳︎✳︎
三崎はな。夢守市役所に入庁して三年目。はじめての異動先は「旧館のもじゃおさん」と呼ばれる変人が在籍しているよろず相談課。一度配属されたら最後、二度と異動はないと噂されている夢守市役所の墓場でした。 けれど、このよろず相談課、本当の名称は●●よろず相談課で――。それっていったいどういうこと? みたいな話です。
第7回キャラ文芸大賞奨励賞ありがとうございました。

ハードボイルド探偵・篤藩次郎(淳ちゃん)
黒猫
キャラ文芸
ハードボイルドとは何か。その定義を教えてやろう。
それはズバリ、酒と女だ。
ちなみに俺は、どっちも弱い。
というか、そういうのは仕事には持ち込まないモンだからな、むしろ弱くて良かった。つくづく、そう思う。
そしてこれは、我がハードボイルド探偵事務所に舞い込んだ妙な依頼と、それを見事に解決したハードボイルドな俺と由紀奈の大活躍の記録の数々だ。
ああ、由紀奈というのは従姪で、口の悪い、俺の助手だ。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。


第四の壁を突破したので、新しい主人公に全てを押し付けて俺はモブになる。
宗真匠
キャラ文芸
自分が生きる世界が作り物だったとしたら、あなたはどうしますか?
フィクションと現実を隔てる概念『第四の壁』。柊木灯(ひいらぎとう)はある日、その壁を突破し、自身がラブコメ世界の主人公だったことを知った。
自分の過去も他者の存在もヒロインからの好意さえ全てが偽りだと知った柊木は、物語のシナリオを壊すべく、主人公からモブに成り下がることを決意した。
そのはずなのに、気がつけば幼馴染やクラスの美少女優等生、元気な後輩にギャル少女、完全無欠の生徒会長までもが柊木との接触を図り、女の子に囲まれる日々を取り戻してしまう。
果たして柊木はこの世界を受け入れて主人公となるのか、それとも……?
※小説家になろうからの転載作品です。本編は完結してますので、気になる方はそちらでもどうぞ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















