お気に入りに追加
60
あなたにおすすめの小説

幼妻は、白い結婚を解消して国王陛下に溺愛される。
秋月乃衣
恋愛
旧題:幼妻の白い結婚
13歳のエリーゼは、侯爵家嫡男のアランの元へ嫁ぐが、幼いエリーゼに夫は見向きもせずに初夜すら愛人と過ごす。
歩み寄りは一切なく月日が流れ、夫婦仲は冷え切ったまま、相変わらず夫は愛人に夢中だった。
そしてエリーゼは大人へと成長していく。
※近いうちに婚約期間の様子や、結婚後の事も書く予定です。
小説家になろう様にも掲載しています。

悪役令嬢ってこれでよかったかしら?
砂山一座
恋愛
第二王子の婚約者、テレジアは、悪役令嬢役を任されたようだ。
場に合わせるのが得意な令嬢は、婚約者の王子に、場の流れに、ヒロインの要求に、流されまくっていく。
全11部 完結しました。
サクッと読める悪役令嬢(役)。

婚約破棄された検品令嬢ですが、冷酷辺境伯の子を身籠りました。 でも本当はお優しい方で毎日幸せです
青空あかな
恋愛
旧題:「荷物検査など誰でもできる」と婚約破棄された検品令嬢ですが、極悪非道な辺境伯の子を身籠りました。でも本当はお優しい方で毎日心が癒されています
チェック男爵家長女のキュリティは、貴重な闇魔法の解呪師として王宮で荷物検査の仕事をしていた。
しかし、ある日突然婚約破棄されてしまう。
婚約者である伯爵家嫡男から、キュリティの義妹が好きになったと言われたのだ。
さらには、婚約者の権力によって検査係の仕事まで義妹に奪われる。
失意の中、キュリティは辺境へ向かうと、極悪非道と噂される辺境伯が魔法実験を行っていた。
目立たず通り過ぎようとしたが、魔法事故が起きて辺境伯の子を身ごもってしまう。
二人は形式上の夫婦となるが、辺境伯は存外優しい人でキュリティは温かい日々に心を癒されていく。
一方、義妹は仕事でミスばかり。
闇魔法を解呪することはおろか見破ることさえできない。
挙句の果てには、闇魔法に呪われた荷物を王宮内に入れてしまう――。
※おかげさまでHOTランキング1位になりました! ありがとうございます!
※ノベマ!様で短編版を掲載中でございます。
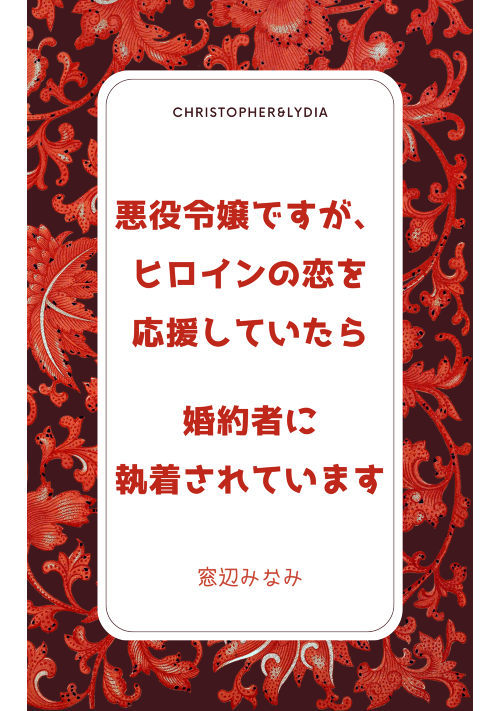
悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています
窓辺ミナミ
ファンタジー
悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。
シナリオ通りなら、死ぬ運命。
だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!
騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!
というわけで、私、悪役やりません!
来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。
あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!
気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。
悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

果たされなかった約束
家紋武範
恋愛
子爵家の次男と伯爵の妾の娘の恋。貴族の血筋と言えども不遇な二人は将来を誓い合う。
しかし、ヒロインの妹は伯爵の正妻の子であり、伯爵のご令嗣さま。その妹は優しき主人公に密かに心奪われており、結婚したいと思っていた。
このままでは結婚させられてしまうと主人公はヒロインに他領に逃げようと言うのだが、ヒロインは妹を裏切れないから妹と結婚して欲しいと身を引く。
怒った主人公は、この姉妹に復讐を誓うのであった。
※サディスティックな内容が含まれます。苦手なかたはご注意ください。

[完結]私を巻き込まないで下さい
シマ
恋愛
私、イリーナ15歳。賊に襲われているのを助けられた8歳の時から、師匠と一緒に暮らしている。
魔力持ちと分かって魔法を教えて貰ったけど、何故か全然発動しなかった。
でも、魔物を倒した時に採れる魔石。石の魔力が無くなると使えなくなるけど、その魔石に魔力を注いで甦らせる事が出来た。
その力を生かして、師匠と装具や魔道具の修理の仕事をしながら、のんびり暮らしていた。
ある日、師匠を訪ねて来た、お客さんから生活が変わっていく。
え?今、話題の勇者様が兄弟子?師匠が王族?ナニそれ私、知らないよ。
平凡で普通の生活がしたいの。
私を巻き込まないで下さい!
恋愛要素は、中盤以降から出てきます
9月28日 本編完結
10月4日 番外編完結
長い間、お付き合い頂きありがとうございました。

疲れきった退職前女教師がある日突然、異世界のどうしようもない貴族令嬢に転生。こっちの世界でも子供たちの幸せは第一優先です!
ミミリン
恋愛
小学校教師として長年勤めた独身の皐月(さつき)。
退職間近で突然異世界に転生してしまった。転生先では醜いどうしようもない貴族令嬢リリア・アルバになっていた!
私を陥れようとする兄から逃れ、
不器用な大人たちに助けられ、少しずつ現世とのギャップを埋め合わせる。
逃れた先で出会った訳ありの美青年は何かとからかってくるけど、気がついたら成長して私を支えてくれる大切な男性になっていた。こ、これは恋?
異世界で繰り広げられるそれぞれの奮闘ストーリー。
この世界で新たに自分の人生を切り開けるか!?

【完結】溺愛婚約者の裏の顔 ~そろそろ婚約破棄してくれませんか~
瀬里
恋愛
(なろうの異世界恋愛ジャンルで日刊7位頂きました)
ニナには、幼い頃からの婚約者がいる。
3歳年下のティーノ様だ。
本人に「お前が行き遅れになった頃に終わりだ」と宣言されるような、典型的な「婚約破棄前提の格差婚約」だ。
行き遅れになる前に何とか婚約破棄できないかと頑張ってはみるが、うまくいかず、最近ではもうそれもいいか、と半ばあきらめている。
なぜなら、現在16歳のティーノ様は、匂いたつような色香と初々しさとを併せ持つ、美青年へと成長してしまったのだ。おまけに人前では、誰もがうらやむような溺愛ぶりだ。それが偽物だったとしても、こんな風に夢を見させてもらえる体験なんて、そうそうできやしない。
もちろん人前でだけで、裏ではひどいものだけど。
そんな中、第三王女殿下が、ティーノ様をお気に召したらしいという噂が飛び込んできて、あきらめかけていた婚約破棄がかなうかもしれないと、ニナは行動を起こすことにするのだが――。
全7話の短編です 完結確約です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















