23 / 24
妖精猫は老女とお別れした
その6
しおりを挟むアサガオのお墓は屋敷からほど近い丘の上。キレイな沢山の花が咲き乱れるそこに立てられた。その隣にはアサガオの旦那さんのお墓もあった。
沢山の花束をそえて、妖精猫はアサガオのお墓を見つめる。
しかしそこにはもうあの笑顔はない。もう二度と会うことはない。妖精猫の尻尾はずっとだらんと下がったままだった。
「……にゃあにゃあ、もしかしたらアサガオちゃんがもう少し長く生きられる方法とかあったのかな…何でも治しちゃう薬草とか探せば良かったのかな…」
独り言のようにお墓の前で話す妖精猫。そんな彼へ、隣にいたマリンが答える。
「もしかしたらあったかもしれないわね。けれど…貴方の足じゃ間に合わなかったかもしれない。だったら最期のときまで一緒にいられた方がアサガオも幸せだったと思うわ」
マリンへ振り向いた妖精猫は、その真っ赤になった目で見つめながら言った。
「それでも、アサガオちゃんともっと一緒にいたかったよ。どうしてアサガオちゃんとぼくはおんなじ時間を生きられなかったんだろう…みんなおんなじ長さで生きられないんだろう…」
「それは……どうしてかしらね」
マリンは妖精猫の疑問に何も答えられなかった。それはきっと、教えてもらうだけじゃなく妖精猫自身が見つけなきゃいけない答えだと思ったからだった。
「……貴方の質問の答えにはならないかもしれないけれど……これ」
そう言って、マリンがポケットから取り出したのは、一通の手紙だった。
「アサガオが貴方にって…」
「ぼくに?」
手紙を受け取った妖精猫は慎重に手紙の封をきった。
とても高級そうな紙の封筒。その中に入っていたアサガオからの最期のメッセージを読む。
妖精猫さんへ
この手紙をアンタが読んでいるということは、それはつまり私が息を引き取った後ということになるだろうね。
最近はしゃべるのも中々大変でね。だから手紙にしたためることにしたよ。それに、手紙で書いた方が素直な気持ちで書けそうな気がしたからね。
妖精猫さんは出会った頃からあたしのことをずっとステキだとキレイだとほめてくれていたね。正直なところ、あたしは変な猫さんだと思ってすごく恥ずかしかった。だけど、本当はとても嬉しかったんだよ。
けどね、素直にはなれなくていつもツンツンしてた…なんだか太陽みたいに輝いていたアンタがとても眩しすぎてさ。そんな奴があたしなんかを、本当はほめてくれないだろうって、ずっとひねくれてたんだね。どっちが子供なんだって話だろう?
この通り、あたしは本当はステキでもキレイでもない。ただの一般人なのさ。それなのに、アンタはいつだって真っ直ぐにほめてくれて、大好きでいてくれて。最初は恥ずかしくて、だんだんとうっとおしく思ったときもあったけれどさ。
今にして思えばとてつもなく嬉しかったんだ。幸せだったんだよ。
ありがとうね、妖精猫さん。あたしも本当は、とってもとっても大好きだったよ。
悲しくなったり苦しくなったり怒ったり笑ったりするくらい。本当はずっとずっと、大切で大好きだったんだよ。
だからもう、今のあたしに欲しいものなんて何もないんだよ。だって、欲しかったものは全部妖精猫がくれたからね。
ただ一つ、心残りなのは…あたしがいなくなった後に、妖精猫さんがどうしてるかってことだけさ。今度は三十年以上も泣かれちゃあ、たまったもんじゃないからさ。
妖精猫さん、アンタの長い長い生涯の中ではあたしなんて、ちっぽけな小動物みたいなもんなんだ。だから、これ以上苦しまないでおくれ、悲しみ続けないでおくれ。
あたしと出会うことはもう二度とないけれど、この先、あたしのような人と出会える機会は沢山ある。
きっとまた、あたし以上のステキでキレイな子とだって出会えるさ。
そしてまた、妖精猫さんの太陽みたいな素直な明るさや純粋な笑顔が、その子たちを救うんだよ。
それがまた、アンタの全てになってくれるさ。あたしはそう信じてる。
最期に、あたしのもう一つの宝物を、妖精猫さんに渡しておくよ。
嫁いだときに大切にしていた宝物のほとんどは捨てられたって言ったけどね、本当は、これだけは捨てられないよう常に首にかけて持っていたんだよ。
って、その話をするのがなんだか照れくさくて、今の今まで秘密にしてたんだけどね。
これを大切に持っていてくれても良い、売っぱらっちゃって金にしても良い、他の誰かに託すことだってアンタの自由さ。
これから先は、アンタのために生きておくれ。それがあたしの願いだよ。
妖精猫は手紙の内容を読んだ後、封筒を逆さまにしてみた。
わずかにふくらみのあったそこからは、淡い白銀色の真珠のペンダントが出てきた。
「人魚の涙……」
間違いなくそれは妖精猫が贈ったもので、大切に身につけてくれていたのかその輝きは少しばかりくすんでいた。
「これだけは持っていてくれたんだね。ありがとう、アサガオちゃん」
妖精猫はペンダントをもう一度、大事に封筒へしまいながら、お墓に向かってお礼を言った。
返事が聞こえてくることはない。それでも、妖精猫の脳裏には笑顔で答えてくれるアサガオの姿があった。
それまで明るかった空はいつの間にか夕暮れとなっており、周囲の物物は赤く白く染められていっていた。
少し肌寒さもあって、妖精猫は思わず身体をぶるりとさせる。
「そういえば…妖精猫さんはこれからどうするの? まさかまたここで三十年も泣き続けるなんて、しないわよね」
マリンにそう尋ねられた妖精猫は、頭をかきながら、苦笑いをして言った。
「にゃはは、もうそんなことはしないよ。とりあえずまたあの酒場に帰ろうと思うんだ。だってあそこはアサガオちゃんとの思い出の場所だからね」
そう答えた妖精猫に対し、マリンは寂しそうな顔を俯かせる。
「あの酒場はね……閉店しちゃったのよ」
「え?」
「この前、酒場の仲間から手紙が届いたの。読んでみたらマスターが病気で亡くなったって。歳も歳だったからそれは仕方がないことでしょうけれど……」
マリンの話に驚きを隠せずにいる妖精猫。その真っ直ぐな視線から逃げるように顔を背けながら、マリンは続けて言う。
「……それで新たに酒場を引き継いでくれる人がいなくなってしまって、閉店するしかなかったんだって。元々、もう随分と建物も古くなっていたし…それもまた、仕方がないことよ」
マリンは妖精猫を納得させるようにそう話してはいた。が、その横顔はとてもとても寂しそうで。
妖精猫もまた、悲しみに尻尾をだらんと下げる。
「……にゃあ…ぼくが。ぼくが酒場を引き継ぐよ!」
すると突然。思いついた顔でそう言うと妖精猫はその場から立ち上がった。
さっきまで下がっていた尻尾も今はピンと立っている。
「ぼくが新しいマスターになれば酒場は閉店にならなくて済むってことでしょ?」
「そうだけど…引き継ぐなんて大変なことよ。それにさっきも言ったけど、酒場はもうボロボロになってきていたから建物も直さなくちゃいけないの」
簡単に言って何とかなるものじゃない。マリンは妖精猫にそう説明するものの、妖精猫の決意は強く。絶対に揺らぐことはない。
「それでも、ぼくにとってあそこはアサガオちゃんともマリンちゃんとだって、ハリボテとだって大切な思い出の場所だから。ぼくが―――生まれて始めて大好きな人が出来た場所だから…どんなものもいつかは無くなっちゃうかもしれないけど、今はまだ無くしたくないよ」
こうなってしまったら、もう妖精猫は何がなんでも突っ走ってしまう。ということをよく知っているマリン。彼女はしばらく迷った後、深いため息を吐いてから言った。
「……わかったわ。私も協力してあげるから、出来る限りのことをしてみましょう?」
マリンの言葉を聞いた妖精猫は大喜びでぴょんぴょんとその場を飛び跳ねた。
「にゃあにゃあ、やった! がんばろうね、マリンちゃん」
「ええ…がんばりましょうね」
そう言うと妖精猫はマリンに向かってにんまりと、満面の笑みを見せた。
マリンもまた、彼の頭を優しく撫でながら返すように微笑んでくれた。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

エーデルヴァイス夫人は笑わない
緋島礼桜
児童書・童話
レイハウゼンの町から外れた森の奥深く。
湖畔の近くにはそれはもう大きくて立派な屋敷が建っていました。
そこでは、旦那を亡くしたエーデルヴァイス夫人が余生を過ごしていたと言います。
しかし、夫人が亡くなってから誰も住んでいないというのに、その屋敷からは夜な夜な笑い声や泣き声が聞こえてくるというのです…。
+++++
レイハウゼンの町で売れない画家をしていた主人公オットーはある日、幼馴染のテレーザにこう頼まれます。
「エーデルヴァイス夫人の屋敷へ行って夫人を笑わせて来て」
ちょっと変わった依頼を受けたオットーは、笑顔の夫人の絵を描くため、いわくつきの湖近くにある屋敷へと向かうことになるのでした。
しかしそこで待っていたのは、笑顔とは反対の恐ろしい体験でした―――。
+++++
ホラーゲームにありそうな設定での小説になります。
ゲームブック風に選択肢があり、エンディングも複数用意されています。
ホラー要素自体は少なめ。
子供向け…というよりは大人向けの児童書・童話かもしれません。

ナミダルマン
ヒノモト テルヲ
児童書・童話
だれかの流したナミダが雪になって、それが雪ダルマになると、ナミダルマンになります。あなたに話しかけるために、どこかに立っているかもしれません。あれ、こんなところに雪ダルマがなんて、思いがけないところにあったりして。そんな雪ダルマにまつわる短いお話を集めてみました。

タロウのひまわり
光野朝風
児童書・童話
捨て犬のタロウは人間不信で憎しみにも近い感情を抱きやさぐれていました。
ある日誰も信用していなかったタロウの前にタロウを受け入れてくれる存在が現れます。
タロウはやがて受け入れてくれた存在に恩返しをするため懸命な行動に出ます。
出会いと別れ、そして自己犠牲のものがたり。

魔王の飼い方説明書
ASOBIVA
児童書・童話
恋愛小説を書く予定でしたが
魔界では魔王様と恐れられていたが
ひょんな事から地球に異世界転生して女子高生に拾われてしまうお話を書いています。
短めのクスッと笑えるドタバタこめでぃ。
実際にあるサービスをもじった名称や、魔法なども滑り倒す覚悟でふざけていますがお許しを。
是非空き時間にどうぞ(*^_^*)
あなたも魔王を飼ってみませんか?
魔王様と女子高生の365日後もお楽しみに。
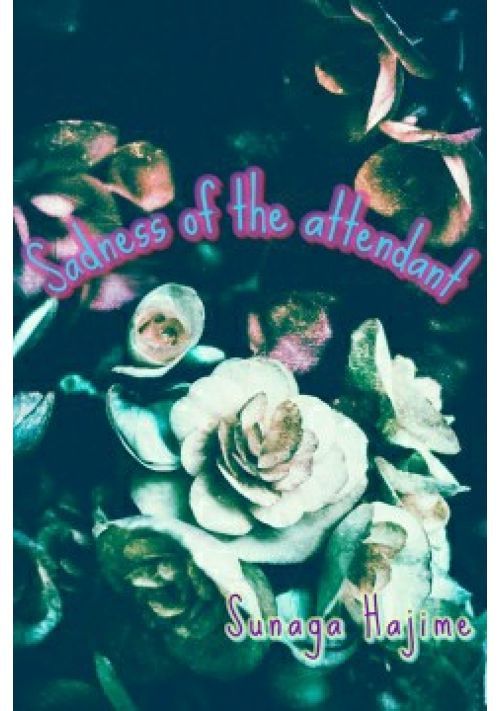
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

空をとぶ者
ハルキ
児童書・童話
鳥人族であるルヒアは村を囲む神のご加護のおかげで外の人間による戦争の被害を受けずに済んでいる。しかし、そのご加護は村の人が誰かひとりでも村の外に出るとそれが消えてしまう。それに村の中からは外の様子を確認できない決まりになっている。それでも鳥人族は1000年もの間、神からの提示された決まりを守り続けていた。しかし、ルヒアと同い年であるタカタは外の世界に興味を示している。そして、ついに、ご加護の決まりが破かれる・・・

子猫マムの冒険
杉 孝子
児童書・童話
ある小さな町に住む元気な子猫、マムは、家族や友達と幸せに暮らしていました。
しかしある日、偶然見つけた不思議な地図がマムの冒険心をかきたてます。地図には「星の谷」と呼ばれる場所が描かれており、そこには願いをかなえる「星のしずく」があると言われていました。
マムは友達のフクロウのグリムと一緒に、星の谷を目指す旅に出ることを決意します。

月星人と少年
ピコ
児童書・童話
都会育ちの吉太少年は、とある事情で田舎の祖母の家に預けられる。
その家の裏手、竹藪の中には破天荒に暮らす小さな小さな姫がいた。
「拾ってもらう作戦を立てるぞー!おー!」
「「「「おー!」」」」
吉太少年に拾ってもらいたい姫の話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















