お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

【完結】亡き冷遇妃がのこしたもの〜王の後悔〜
なか
恋愛
「セレリナ妃が、自死されました」
静寂をかき消す、衛兵の報告。
瞬間、周囲の視線がたった一人に注がれる。
コリウス王国の国王––レオン・コリウス。
彼は正妃セレリナの死を告げる報告に、ただ一言呟く。
「構わん」……と。
周囲から突き刺さるような睨みを受けても、彼は気にしない。
これは……彼が望んだ結末であるからだ。
しかし彼は知らない。
この日を境にセレリナが残したものを知り、後悔に苛まれていくことを。
王妃セレリナ。
彼女に消えて欲しかったのは……
いったい誰か?
◇◇◇
序盤はシリアスです。
楽しんでいただけるとうれしいです。

ママの大事な寝ぼすけメシア
ちみあくた
児童書・童話
毎日がんばるシングルマザーのユカリさんにとって、何より大事な宝物は一人娘のタマキちゃんです。
毎日、グッスリ眠って、たくさん夢を見るタマキちゃん。
一見、何処にでもいる子供のありふれた姿に思えましたが、実はそれだけではありません。
夢の中でタマキちゃんは、世界を救う救世主の力をふるっていました。
そして、その夢は或る夜、現実の世界に大きな異変を呼び起こしてしまうのです……
エブリスタ、小説家になろう、ノベルアップ+、にも投稿しております。

亡くなった王太子妃
沙耶
恋愛
王妃の茶会で毒を盛られてしまった王太子妃。
侍女の証言、王太子妃の親友、溺愛していた妹。
王太子妃を愛していた王太子が、全てを気付いた時にはもう遅かった。
なぜなら彼女は死んでしまったのだから。

月星人と少年
ピコ
児童書・童話
都会育ちの吉太少年は、とある事情で田舎の祖母の家に預けられる。
その家の裏手、竹藪の中には破天荒に暮らす小さな小さな姫がいた。
「拾ってもらう作戦を立てるぞー!おー!」
「「「「おー!」」」」
吉太少年に拾ってもらいたい姫の話です。

五年目の浮気、七年目の破局。その後のわたし。
あとさん♪
恋愛
大恋愛での結婚後、まるまる七年経った某日。
夫は愛人を連れて帰宅した。(その愛人は妊娠中)
笑顔で愛人をわたしに紹介する夫。
え。この人、こんな人だったの(愕然)
やだやだ、気持ち悪い。離婚一択!
※全15話。完結保証。
※『愚かな夫とそれを見限る妻』というコンセプトで書いた第四弾。
今回の夫婦は子無し。騎士爵(ほぼ平民)。
第一弾『妻の死を人伝てに聞きました。』
第二弾『そういうとこだぞ』
第三弾『妻の死で思い知らされました。』
それぞれ因果関係のない独立したお話です。合わせてお楽しみくださると一興かと。
※この話は小説家になろうにも投稿しています。
※2024.03.28 15話冒頭部分を加筆修正しました。

懐妊を告げずに家を出ます。最愛のあなた、どうかお幸せに。
梅雨の人
恋愛
最愛の夫、ブラッド。
あなたと共に、人生が終わるその時まで互いに慈しみ、愛情に溢れる時を過ごしていけると信じていた。
その時までは。
どうか、幸せになってね。
愛しい人。
さようなら。

盲目魔女さんに拾われた双子姉妹は恩返しをするそうです。
桐山一茶
児童書・童話
雨が降り注ぐ夜の山に、捨てられてしまった双子の姉妹が居ました。
山の中には恐ろしい魔物が出るので、幼い少女の力では山の中で生きていく事なんか出来ません。
そんな中、双子姉妹の目の前に全身黒ずくめの女の人が現れました。
するとその人は優しい声で言いました。
「私は目が見えません。だから手を繋ぎましょう」
その言葉をきっかけに、3人は仲良く暮らし始めたそうなのですが――。
(この作品はほぼ毎日更新です)
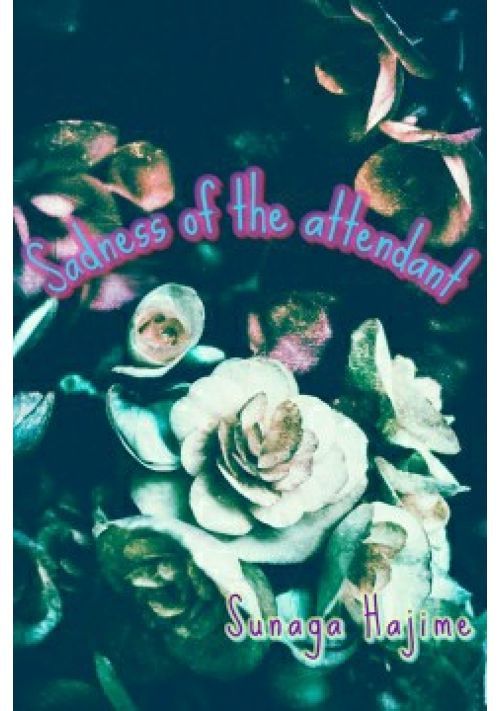
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















