26 / 31
君にありがとう
大河side 2P
しおりを挟む
その日の帰り。
決勝戦で負けたというのと、3年生の先輩が引退したということがまだどこか夢のようで、俺は部室前のベンチで1人ぼうっと座っていた。
現実を受け止めきれていないのは、3年生じゃない。
俺のほうだ。
先輩たちがどれだけ声をかけてくれたとしても、あの3ランホームランが悔やんでも悔やみきれないっ…。
――そして。
あの俺の失態を、きっと悠も莉子も見ていた。
この大会が終わるまでは野球に専念すると決めて、莉子との関係を曖昧にして…。
結果、負けてしまった。
…莉子に合わせる顔がない。
それに、こんな情けない俺を見て、きっと莉子は愛想を尽かせたはずだ。
『莉子のことだけは…もう負けたくないっ』
思い出される…悠の言葉。
もしかしたら今頃、悠と莉子は――。
…そんなことを考えていたとき。
だれもいないはずのこの場に、足音が聞こえた。
目を向けると、それは3年生のマネージャーの先輩だった。
「…先輩。どうしたんですか?」
もう、みんな帰ってしまったというのに。
「ちょっと、大河に話したいことがあって」
「俺に…?」
…なんだろうか。
やっぱり、俺の今日の出来の悪さについてだろうか。
そう思っていると――。
「もしかしたら、気づいてるかもしれへんけど…。あたし…、大河のことが好きやねん」
思いもよらないその言葉に、一瞬ポカンとしてしまった。
『もしかしたら、気づいてるかもしれない』…?
…いや、まったく。
これっぽっちも気づいていなかった。
「実は、大河が入部したころからいいなって思ってて。後輩やのに、優しいし頼り甲斐もあるし」
「そんな…。俺なんて…」
「それに、家まで送ってくれたときもそうやった。遠いのに、文句も言わずにいっしょにきてくれて」
「…それは、野球部員として当然のことをしたまでです」
「『野球部員』…かっ」
先輩は、少し寂しそうにつぶやいた。
「やから、今度は『野球部員』としてじゃなくて、『1人の男』として、あたしのことを見てくれへんかな…?」
「1人の…男?」
「そう。あたしは今日、野球部を引退した。もう野球部員やない。つまり、『部内恋愛禁止』なんていう掟も関係ない」
俺の隣に座る先輩がぐっと体を寄せてくる。
「大河、今の彼女とうまくいってへんのやろ…?」
その言葉を聞いて、頭の中に莉子の顔が浮かぶ。
「あたしやったら、ずっと大河を支える自信がある。だって、マネージャーとしてそばで大河を見てきたんやから」
上目遣いで、俺を見つめる先輩。
だけど、その先輩と視線を合わせることはなかった。
なぜなら、俺は違うことを考えていたから。
さっき先輩は、俺のことを『支える』と言ってくれた。
――だけど、そうじゃない。
俺は、だれかに『支えてもらいたい』んじゃなくて、俺が『支えたい』んだ。
そう。
あの日、莉子に約束した――。
『莉子には、野球部のマネージャーとしてこれまでたくさん支えてきてもらった。やから、次は俺が莉子を支えたい。…莉子の彼氏としてっ』
どうして俺は、あのときの言葉を今まで忘れていたのだろうか。
莉子が悲しいとき、つらいとき…。
俺が支えるって、誓ったはずなのに。
今俺が向き合わなければならないのは、隣にいるマネージャーの先輩なんかじゃない。
…莉子だ!
もしかしたら、莉子はもう悠と――。
手遅れかもしれない。
今さら謝ったって、許してもらえないかもしれない。
それでも、今は莉子に会いたい。
「…先輩、すみません」
俺は立ち上がって、先輩に頭を下げた。
「俺、やっぱり今の彼女のことがむちゃくちゃ好きなんですっ。だから、先輩の気持ちには応えられません…!本当にすみません!」
俺は荷物をまとめると、急いでその場をあとにした。
今は、すぐにでも莉子に会いたい。
会って、これまでのことを謝りたい。
そして、改めて気持ちを伝えたい。
駆け足で、部室の角を曲がった。
すると、――そのとき。
「…うわぁ!」
突然人影が現れて、思いもよらず俺は変な声を上げてしまった。
見ると、そこに立っていたのは…莉子だった。
「り…、莉子?」
まさか、莉子がこんなところにいるとも思っていなくて――。
一瞬、戸惑った。
「…こんなところで、なにしてんの?」
と聞いてみたものの、すぐにハッとした。
「もしかして…。さっきの先輩との会話…、全部聞こえてた?」
俺がおそるおそる尋ねると、莉子は頬を膨らませながらゆっくりとうなずいた。
「…聞いてたよ。あのマネージャーの先輩から告白されてたのも、全部」
や…やっぱり。
この距離だから、耳をすませば聞こえるだろう。
せっかく莉子に謝りに行こうと思っていたのに――。
見られてはマズいところを見られてしまった…。
…しかし。
「…だから、全部聞いてた。大河が、わたしのことをむちゃくちゃ好きだっていうのも、全部」
そう言って、プイッと顔を背ける莉子。
しかし、その頬は赤かった。
久しぶりに会った莉子。
久しぶりに会話した莉子。
本当なら、もっといろんなことを話してわかってもらう必要があるのだろうけど――。
その仕草があまりにもかわいすぎて、俺は思わず莉子を抱きしめていた。
「ちょっと…大河!なにす――」
「ごめん。ちょっとの間だけ、こうさせて」
俺がそう言うと、莉子は抵抗するのを諦めて、俺の腕の中にすっぽりと収まった。
そのあと、公園に場所を移して、俺と莉子は話をした。
そこで、初めて知った。
莉子は、マネージャーの先輩との距離が近いことに、ずっとモヤモヤしていたと。
その不安が爆発して――。
『大河は、自覚がなさすぎなんだよ!見ればわかるじゃん…!下心丸見えで、マネージャーの仕事をしてるのっ!』
あんなことを言ってしまったのだと。
あのときの俺は、マネージャーを悪く言われたことに思わず腹を立ててしまった。
しかし、今日先輩に告白されて、莉子が言っていたことはあながち間違いではなかったことに気づかされた。
確かに、俺が逆の立場だったら不安になっていたはずだ。
莉子が、他の男に言い寄られていると思ったら。
現に、それが『悠』だ。
悠は、莉子に告白した。
莉子がなんて返事をしたかはわからないが、それが今日の試合のメンタルに多少なりとも影響したのは事実だった。
「莉子は…。悠とは…どうなったん?」
俺だって、莉子と悠の関係が気になって仕方がない。
ここで、すでに莉子が悠を選んでいたのなら、俺は潔く身を引くしかない。
そう思った。
――しかし。
「悠とは、なにもないよ」
莉子から、そんな言葉が返ってきた。
「…えっ。でもお前、悠に告白されたんじゃ…」
「告白はされたよ。…でも断った、さっき。やっぱり、わたしが好きなのは…大河だからさ」
そう言って、恥ずかしそうに俺に目を向ける莉子。
悠とは付き合っていないとわかった安堵と。
それでも俺のことを好きでいてくれたという、うれしさとで――。
俺は思わず、目の奥が熱くなった。
「…俺。莉子のことを突き放すようなことを言ったのに…」
「そんなの…わたしだって、大河を疑うようなことを言っちゃった…」
――だから。
「「…ごめんっ!!」」
同時にそう言って頭を下げたとき、お互いの額がぶつかった。
その痛みに一瞬顔をゆがめるも、なんだかおかしくなってきて…。
自然と笑いが込み上げてきた。
時間はかかったけど、ようやくそれぞれの誤解を解くことができた。
それに、わかったこともあった。
俺たちは、なんだかんだでお互いのことが好きなんだって。
それは、これからもきっとそうだろう。
「…莉子。もう絶対離れへんから」
「うん。わたしも」
夕暮れ時の公園。
見つめ合う俺たちの影は――。
そっと唇が重なったのだった。
その後、悠と話す機会があった。
「また莉子を泣かせるようなことがあったら、今度は本気で奪いにいく」
と、釘を刺された。
悠の本当の気持ちを知って、久々に思いきりぶつかった。
だけどそれを乗り越えた俺たちの仲は、前よりも確実に深まった。
そして、悠といっしょにさらに練習に励んだ。
それからの学校生活は、あっという間だった。
決勝戦で負けたというのと、3年生の先輩が引退したということがまだどこか夢のようで、俺は部室前のベンチで1人ぼうっと座っていた。
現実を受け止めきれていないのは、3年生じゃない。
俺のほうだ。
先輩たちがどれだけ声をかけてくれたとしても、あの3ランホームランが悔やんでも悔やみきれないっ…。
――そして。
あの俺の失態を、きっと悠も莉子も見ていた。
この大会が終わるまでは野球に専念すると決めて、莉子との関係を曖昧にして…。
結果、負けてしまった。
…莉子に合わせる顔がない。
それに、こんな情けない俺を見て、きっと莉子は愛想を尽かせたはずだ。
『莉子のことだけは…もう負けたくないっ』
思い出される…悠の言葉。
もしかしたら今頃、悠と莉子は――。
…そんなことを考えていたとき。
だれもいないはずのこの場に、足音が聞こえた。
目を向けると、それは3年生のマネージャーの先輩だった。
「…先輩。どうしたんですか?」
もう、みんな帰ってしまったというのに。
「ちょっと、大河に話したいことがあって」
「俺に…?」
…なんだろうか。
やっぱり、俺の今日の出来の悪さについてだろうか。
そう思っていると――。
「もしかしたら、気づいてるかもしれへんけど…。あたし…、大河のことが好きやねん」
思いもよらないその言葉に、一瞬ポカンとしてしまった。
『もしかしたら、気づいてるかもしれない』…?
…いや、まったく。
これっぽっちも気づいていなかった。
「実は、大河が入部したころからいいなって思ってて。後輩やのに、優しいし頼り甲斐もあるし」
「そんな…。俺なんて…」
「それに、家まで送ってくれたときもそうやった。遠いのに、文句も言わずにいっしょにきてくれて」
「…それは、野球部員として当然のことをしたまでです」
「『野球部員』…かっ」
先輩は、少し寂しそうにつぶやいた。
「やから、今度は『野球部員』としてじゃなくて、『1人の男』として、あたしのことを見てくれへんかな…?」
「1人の…男?」
「そう。あたしは今日、野球部を引退した。もう野球部員やない。つまり、『部内恋愛禁止』なんていう掟も関係ない」
俺の隣に座る先輩がぐっと体を寄せてくる。
「大河、今の彼女とうまくいってへんのやろ…?」
その言葉を聞いて、頭の中に莉子の顔が浮かぶ。
「あたしやったら、ずっと大河を支える自信がある。だって、マネージャーとしてそばで大河を見てきたんやから」
上目遣いで、俺を見つめる先輩。
だけど、その先輩と視線を合わせることはなかった。
なぜなら、俺は違うことを考えていたから。
さっき先輩は、俺のことを『支える』と言ってくれた。
――だけど、そうじゃない。
俺は、だれかに『支えてもらいたい』んじゃなくて、俺が『支えたい』んだ。
そう。
あの日、莉子に約束した――。
『莉子には、野球部のマネージャーとしてこれまでたくさん支えてきてもらった。やから、次は俺が莉子を支えたい。…莉子の彼氏としてっ』
どうして俺は、あのときの言葉を今まで忘れていたのだろうか。
莉子が悲しいとき、つらいとき…。
俺が支えるって、誓ったはずなのに。
今俺が向き合わなければならないのは、隣にいるマネージャーの先輩なんかじゃない。
…莉子だ!
もしかしたら、莉子はもう悠と――。
手遅れかもしれない。
今さら謝ったって、許してもらえないかもしれない。
それでも、今は莉子に会いたい。
「…先輩、すみません」
俺は立ち上がって、先輩に頭を下げた。
「俺、やっぱり今の彼女のことがむちゃくちゃ好きなんですっ。だから、先輩の気持ちには応えられません…!本当にすみません!」
俺は荷物をまとめると、急いでその場をあとにした。
今は、すぐにでも莉子に会いたい。
会って、これまでのことを謝りたい。
そして、改めて気持ちを伝えたい。
駆け足で、部室の角を曲がった。
すると、――そのとき。
「…うわぁ!」
突然人影が現れて、思いもよらず俺は変な声を上げてしまった。
見ると、そこに立っていたのは…莉子だった。
「り…、莉子?」
まさか、莉子がこんなところにいるとも思っていなくて――。
一瞬、戸惑った。
「…こんなところで、なにしてんの?」
と聞いてみたものの、すぐにハッとした。
「もしかして…。さっきの先輩との会話…、全部聞こえてた?」
俺がおそるおそる尋ねると、莉子は頬を膨らませながらゆっくりとうなずいた。
「…聞いてたよ。あのマネージャーの先輩から告白されてたのも、全部」
や…やっぱり。
この距離だから、耳をすませば聞こえるだろう。
せっかく莉子に謝りに行こうと思っていたのに――。
見られてはマズいところを見られてしまった…。
…しかし。
「…だから、全部聞いてた。大河が、わたしのことをむちゃくちゃ好きだっていうのも、全部」
そう言って、プイッと顔を背ける莉子。
しかし、その頬は赤かった。
久しぶりに会った莉子。
久しぶりに会話した莉子。
本当なら、もっといろんなことを話してわかってもらう必要があるのだろうけど――。
その仕草があまりにもかわいすぎて、俺は思わず莉子を抱きしめていた。
「ちょっと…大河!なにす――」
「ごめん。ちょっとの間だけ、こうさせて」
俺がそう言うと、莉子は抵抗するのを諦めて、俺の腕の中にすっぽりと収まった。
そのあと、公園に場所を移して、俺と莉子は話をした。
そこで、初めて知った。
莉子は、マネージャーの先輩との距離が近いことに、ずっとモヤモヤしていたと。
その不安が爆発して――。
『大河は、自覚がなさすぎなんだよ!見ればわかるじゃん…!下心丸見えで、マネージャーの仕事をしてるのっ!』
あんなことを言ってしまったのだと。
あのときの俺は、マネージャーを悪く言われたことに思わず腹を立ててしまった。
しかし、今日先輩に告白されて、莉子が言っていたことはあながち間違いではなかったことに気づかされた。
確かに、俺が逆の立場だったら不安になっていたはずだ。
莉子が、他の男に言い寄られていると思ったら。
現に、それが『悠』だ。
悠は、莉子に告白した。
莉子がなんて返事をしたかはわからないが、それが今日の試合のメンタルに多少なりとも影響したのは事実だった。
「莉子は…。悠とは…どうなったん?」
俺だって、莉子と悠の関係が気になって仕方がない。
ここで、すでに莉子が悠を選んでいたのなら、俺は潔く身を引くしかない。
そう思った。
――しかし。
「悠とは、なにもないよ」
莉子から、そんな言葉が返ってきた。
「…えっ。でもお前、悠に告白されたんじゃ…」
「告白はされたよ。…でも断った、さっき。やっぱり、わたしが好きなのは…大河だからさ」
そう言って、恥ずかしそうに俺に目を向ける莉子。
悠とは付き合っていないとわかった安堵と。
それでも俺のことを好きでいてくれたという、うれしさとで――。
俺は思わず、目の奥が熱くなった。
「…俺。莉子のことを突き放すようなことを言ったのに…」
「そんなの…わたしだって、大河を疑うようなことを言っちゃった…」
――だから。
「「…ごめんっ!!」」
同時にそう言って頭を下げたとき、お互いの額がぶつかった。
その痛みに一瞬顔をゆがめるも、なんだかおかしくなってきて…。
自然と笑いが込み上げてきた。
時間はかかったけど、ようやくそれぞれの誤解を解くことができた。
それに、わかったこともあった。
俺たちは、なんだかんだでお互いのことが好きなんだって。
それは、これからもきっとそうだろう。
「…莉子。もう絶対離れへんから」
「うん。わたしも」
夕暮れ時の公園。
見つめ合う俺たちの影は――。
そっと唇が重なったのだった。
その後、悠と話す機会があった。
「また莉子を泣かせるようなことがあったら、今度は本気で奪いにいく」
と、釘を刺された。
悠の本当の気持ちを知って、久々に思いきりぶつかった。
だけどそれを乗り越えた俺たちの仲は、前よりも確実に深まった。
そして、悠といっしょにさらに練習に励んだ。
それからの学校生活は、あっという間だった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
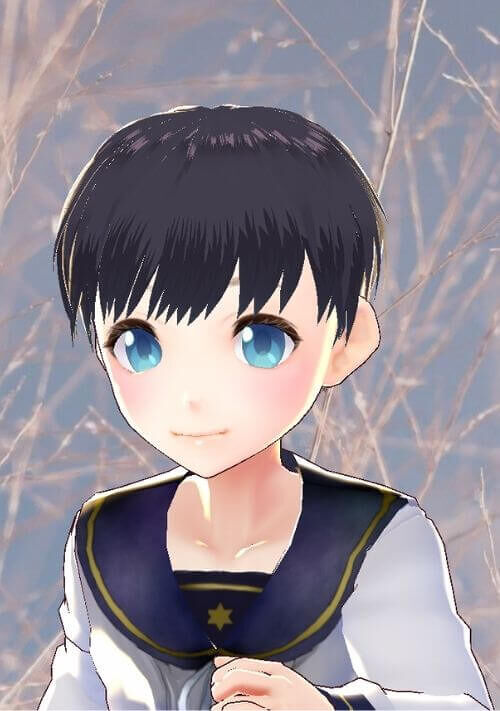
小虎|僕を愛して身代わりになってくれた彼が、霊能者になるなんて!!
宇美
青春
友情と不思議とノスタルジーと……
♪.:*:’゜☆.:*:’゜♪.:*:’゜☆.:*:・’゜♪.:*:・’゜☆.:*:・’゜♪.:*:・’゜
東京で暮らすスグルには、故郷に忘れられない幼馴染がいた。
いつも自分を犠牲にして助けてくれた彼に、僕は何もしてあげられなかった。
優しく切ないブロマンス。
♪.:*:’゜☆.:*:’゜♪.:*:’゜☆.:*:・’゜♪.:*:・’゜☆.:*:・’゜♪.:*:・’゜
昭和末期から平成初期の日本の田舎町を舞台とした、ノスタルジックな男の子の友情物語です。
あやかしも出てきます。
約10万字。文庫本一冊ぐらいの長さです。
下記のキーワードに一つでもピンときた方は、ぜひぜひお読みください(^▽^)/
幼馴染/青春/友情と愛情/ブロマンス/あやかし/神社/不思議な物語/美少年/泣ける/切ない/昭和末期/平成初期/ノスタルジー/郷愁

傷つけて、傷つけられて……そうして僕らは、大人になっていく。 ――「本命彼女はモテすぎ注意!」サイドストーリー 佐々木史帆――
玉水ひひな
青春
「本命彼女はモテすぎ注意! ~高嶺に咲いてる僕のキミ~」のサイドストーリー短編です!
ヒロインは同作登場の佐々木史帆(ささきしほ)です。
本編試し読みで彼女の登場シーンは全部出ているので、よろしければ同作試し読みを読んでからお読みください。
《あらすじ》
憧れの「高校生」になった【佐々木史帆】は、彼氏が欲しくて堪まらない。
同じクラスで一番好みのタイプだった【桐生翔真(きりゅうしょうま)】という男子にほのかな憧れを抱き、何とかアプローチを頑張るのだが、彼にはいつしか、「高嶺の花」な本命の彼女ができてしまったようで――!
---
二万字弱の短編です。お時間のある時に読んでもらえたら嬉しいです!

公爵様、契約通り、跡継ぎを身籠りました!-もう契約は満了ですわよ・・・ね?ちょっと待って、どうして契約が終わらないんでしょうかぁぁ?!-
猫まんじゅう
恋愛
そう、没落寸前の実家を助けて頂く代わりに、跡継ぎを産む事を条件にした契約結婚だったのです。
無事跡継ぎを妊娠したフィリス。夫であるバルモント公爵との契約達成は出産までの約9か月となった。
筈だったのです······が?
◆◇◆
「この結婚は契約結婚だ。貴女の実家の財の工面はする。代わりに、貴女には私の跡継ぎを産んでもらおう」
拝啓、公爵様。財政に悩んでいた私の家を助ける代わりに、跡継ぎを産むという一時的な契約結婚でございましたよね・・・?ええ、跡継ぎは産みました。なぜ、まだ契約が完了しないんでしょうか?
「ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいませええ!この契約!あと・・・、一体あと、何人子供を産めば契約が満了になるのですッ!!?」
溺愛と、悪阻(ツワリ)ルートは二人がお互いに想いを通じ合わせても終わらない?
◆◇◆
安心保障のR15設定。
描写の直接的な表現はありませんが、”匂わせ”も気になる吐き悪阻体質の方はご注意ください。
ゆるゆる設定のコメディ要素あり。
つわりに付随する嘔吐表現などが多く含まれます。
※妊娠に関する内容を含みます。
【2023/07/15/9:00〜07/17/15:00, HOTランキング1位ありがとうございます!】
こちらは小説家になろうでも完結掲載しております(詳細はあとがきにて、)

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

機械娘の機ぐるみを着せないで!
ジャン・幸田
青春
二十世紀末のOVA(オリジナルビデオアニメ)作品の「ガーディアンガールズ」に憧れていたアラフィフ親父はとんでもない事をしでかした! その作品に登場するパワードスーツを本当に開発してしまった!
そのスーツを娘ばかりでなく友人にも着せ始めた! そのとき、トラブルの幕が上がるのであった。

鮫島さんは否定形で全肯定。
河津田 眞紀
青春
鮫島雷華(さめじまらいか)は、学年一の美少女だ。
しかし、男子生徒から距離を置かれている。
何故なら彼女は、「異性からの言葉を問答無用で否定してしまう呪い」にかかっているから。
高校一年の春、早くも同級生から距離を置かれる雷華と唯一会話できる男子生徒が一人。
他者からの言葉を全て肯定で返してしまう究極のイエスマン・温森海斗(ぬくもりかいと)であった。
海斗と雷華は、とある活動行事で同じグループになる。
雷華の親友・未空(みく)や、不登校気味な女子生徒・翠(すい)と共に発表に向けた準備を進める中で、海斗と雷華は肯定と否定を繰り返しながら徐々に距離を縮めていく。
そして、海斗は知る。雷華の呪いに隠された、驚愕の真実を――
全否定ヒロインと超絶イエスマン主人公が織りなす、不器用で切ない青春ラブストーリー。

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















