153 / 183
第3部 他殺か心中か
ディベロッパーからゼネコンへ
しおりを挟む
「これからはな、不動産の時代でっせ、藤原はん。あんたもあないな所で燻ってんと、稼いで稼いで、もっとビッグになりなはれ」
どこで仕立てるのか、真っ赤なスーツを身に纏い、太い葉巻を口にして鼻息荒く語る大力には、同じ年とは思えない風格が漂っていた。女たちを両横にはべらせ、高級シャンパンを惜しげもなく振る舞うその男の粗野ではあるが猛々しい所作に、健吾は男の本能ともいうべき原初的な渇望を喚起させられた。
折しも日本は急速な経済成長を遂げ、石炭から石油へのエネルギー革命によって様々な産業が発達していたが、石油の高騰によってその景気に陰りを見せ始めていた。そんな中、不動産価格が急騰している肌感は田舎で細々と商売をしている健吾にもあった
大力が連れて行ってくれたのはドルチェという高級クラブで、それから何回か大力のお供で健吾もその店を訪れたが、代金は全て大力が払ってくれた。そして、健吾の頭の中では富士子の存在が日に日に大きくなっていった。
そしていつしか、健吾は一人でドルチェに出向くようになっていた。店前でわざわざ告げなくても、富士子は健吾の口座となり、店に入ると同時にすっと彼女は健吾の横に寄り添った。初めて一人で行った時には健吾は大力を真似てシャンパンを開けさせたが、会計の時には目を丸くしてしまった。値段を聞くのも無粋だと大力に代金のことを聞かずにいたことを後悔した。セット料金と合わせるとまさかの10万越えで、月収の三分の一が一瞬で消えてしまったのだ。
それでも健吾は富士子会いに、貯蓄を削りながらせっせと通った。そんな健吾の席にオーナーの白鳥麻衣子が挨拶で着いた時だった。特に派手な印象は受けなかったが、まるでどこかの大企業の秘書のような穏やかだが厳格さも感じさせる口調で、彼女は言った。
「あなた、無理をしてはいけませんよ。お仕事に支障がない程度に、遊びに来て下さいね」
それはあくまで健吾を気遣っての言葉だったのだろうが、それを言われた健吾はひどく馬鹿にされた気がした。あなたにはこんな高級な店は相応しくない、そう言われた気がしたのだ。まるで小さな子どもに言い聞かせるようなオーナーの口調が、返って健吾の悔しさを湧き立たせた。
だが無理をしているのは間違いなかった。
地元のスナックで一回数千円払うのとは桁が違う。きっと数多の羽振りのいい社長連中を接客してきたドルチェのオーナーはそんな自分の懐事情を看過していたのだろう。健吾は自分の甲斐性の無さを落ち込んだが、今更店通いを止めるには、彼はもう北新地の高級クラブの雰囲気に、というよりは富士子の魅力に、どっぷりと浸かってしまっていた。
気がつくと、健吾は大力の持ち込んだ仕事を優先的に受けるようになっていた。彼の仕事は近所のじいさんばあさんの細々とした要望を聞いて回るのとは実入りが違っていた。大力はどこかから安い物件を仕入れてきては、健吾にリフォームさせてまた転売するということを繰り返していたが、その差額だけでも結構な額が入っていたようだ。だが大力はそんなチマチマとした仕事を良しとする男ではなかった。
「藤原はん、これからの時代はな、ディベロッパーいうて、内装だけやのうて、何もない土地から計画して、箱もんをしっかり仕上げて売りに出す、そういうでっかいことせな、儲かりまへん。どうです?うちもディベロッパーの会社を起こすっちゅうのは」
「でぃ、でぃべろっぱー、ですか?」
「藤原はん、べろべろばーみたいなイントネーションで言いなはんな、ディベロッパー、でんがな」
そう言って大笑いする大力を見ながら、この男は何を言ってるのだろうと初めは半信半疑で聞いていた。しかし大力は至極真面目で、あれよあれよという間に健吾が親の代から引き継いだ敷地に鉄筋建ての会社を建設し始めた。
「いや、大力さん、俺は一介の工務店のオヤジに過ぎません。ディベロッパーやなんて、ちょっと荷が過ぎますわ」
健吾はそう言って躊躇していたのだったが、
「何言ってますの藤原はん、これからの時代の社長はな、何でもかんでも自分でやる必要おまへん。出来るやつを雇ったらええんや。アウトソーシングいうてな、何も自分とこで雇わんでも、必要な時に外注するだけでもええんや。人の力借りてどんどん儲ける、それがこれからの時代の社長や。なあ、藤原はん。ワシの言う通りにしとったら、おまはんを一端の社長にしたるからな」
「しゃ…社長に…ですか?」
「そうやがな。いつまでも工務店のおっさんやなんて、そんな野暮ったい肩書捨てなはれ。どんとでっかい会社を立ち上げようやないか。そやな、藤原建設なんてどうです?『藤原建設代表取締役社長』それがあんたの新しい肩書や!」
大力には大風呂敷をぶち上げるだけでなく、それを実現させる行動力があった。そうして健吾はただの内装屋のおっさんから建設会社の社長になった。現場の指揮はそれなりの経歴の人間を雇って任せるようになってたので、健吾はただ社長然として座っているだけで良かった。それでも羽振りだけはどんどんよくなり、健吾は連日北新地に繰り出し、富士子との逢瀬を重ねた。
そして気がついた頃には、藤原建設は大力の所属する裏の組織のフロント企業になってしまっていた──。
それでも大力の言った通り、藤原建設は破竹の勢いで業績を伸ばした。日本のあらゆる土地が底値を知らぬように高騰仕出し、いわゆるバブル景気に日本は突入していた。藤原建設の事業もどんどん大掛かりとなり、末はフジケン興業と名を改めて駅前の一等地に10階建てのビルを構える一端のゼネコン企業になっていた。
大力は次々によく分からない素性の者を雇い入れ、会社の中にどういう部署があり、彼らがどういう仕事をしているのか、健吾には把握出来なくなっていた。健吾もただ黙って見ていた訳ではなく、宅建士や不動産鑑定士などの資格を出来るだけ取って口の挟めるところは割って入ってはいたが、ほとんどの現場では口を出すことを許されず、大きな事業の前ではお飾りの社長に甘んじていた。
それでも腐らずに会社に居られたのは、大力が何かにつけて健吾の顔を立てたからだった。社員の前は元より、対外的にも必要な時には健吾を連れ回し、社交界を賑わす面々に紹介して回った。そうして健吾の対面は保たれ、健吾自身もそれなりの風格を宿していった。だが心の芯の部分では、自分に頭を垂れる者たちは結局背後に控える大力が怖くてそうしているのだと分かっていた。自分などいつすげ替えられてもいい頭なのだ、そう考えるとどこか薄ら寒い隙間風がピューピューと吹いてともすれば悴んでしまいがちになるのを、日々のアルコールと自分を取り巻く女たちの色気で何とかやり過ごしていたのだった。
「あれ?藤原さんやないですか?こんなとこで何されてるんです?」
いきなり声をかけられ、健吾は悔恨の入り混じった回想から現実に頭を起こした。座っていた土手を見上げると、背後の堤防に通る道を、一人の老人が散歩をしていた。こちらに怪訝な顔を向けるその老人の姿を認め、健吾は顔をしかめた。もしかしたら、今一番会いたくなかった人物かもしれない……。
「あ、ああ、ちょっとな……娘を亡くしましてな、仕事に手がつかんで、ふらふらと、ね」
この老人に嘘を言っても仕方がないと、健吾は自分の今の状況を的確に話した。老人はそれを聞き、訳知り顔で頷く。
「ニュースで観ましたよ。この度は…誠にご愁傷さまなことで……」
会社の連中や仕事上の知り合い、果ては新地のホステスまで、もう何人からそんな言葉をかけられただろう。みんな決まって、健吾を見ると何をどう言っていいか分からないというような困った顔になり、何とか口に出した言葉も途中で曖昧に途切れさせる。いつものように神妙に頷いて返すと、目の前の老人は他の人間では絶対に言えない言葉を放った。
「まあ、自業自得ですわな。あんたのこれまでの所業を思ったら」
一瞬、何を言われたのか分からなかった。
自業自得……
そんなことは分かってる!
それは、人からは絶対に言われたくない言葉で、健吾は皮下脂肪の多めの肌を泡立たせた。
「あ、あんたに何が分かる!最愛の娘を亡くした人間の気持ちが!あんたに、何が分かる!!」
気がつくと立ち上がり、激昂していた。頭に血が一気に上り、少食になって貧血気味だった身体が立ち眩みを起こてよろける。老人が手を添えようとしたのを、パシンと払い除けた。そしてそのまま倒れ込み、砂利が粗く転がるアスファルトに顔を押し付け、号泣した。
どこで仕立てるのか、真っ赤なスーツを身に纏い、太い葉巻を口にして鼻息荒く語る大力には、同じ年とは思えない風格が漂っていた。女たちを両横にはべらせ、高級シャンパンを惜しげもなく振る舞うその男の粗野ではあるが猛々しい所作に、健吾は男の本能ともいうべき原初的な渇望を喚起させられた。
折しも日本は急速な経済成長を遂げ、石炭から石油へのエネルギー革命によって様々な産業が発達していたが、石油の高騰によってその景気に陰りを見せ始めていた。そんな中、不動産価格が急騰している肌感は田舎で細々と商売をしている健吾にもあった
大力が連れて行ってくれたのはドルチェという高級クラブで、それから何回か大力のお供で健吾もその店を訪れたが、代金は全て大力が払ってくれた。そして、健吾の頭の中では富士子の存在が日に日に大きくなっていった。
そしていつしか、健吾は一人でドルチェに出向くようになっていた。店前でわざわざ告げなくても、富士子は健吾の口座となり、店に入ると同時にすっと彼女は健吾の横に寄り添った。初めて一人で行った時には健吾は大力を真似てシャンパンを開けさせたが、会計の時には目を丸くしてしまった。値段を聞くのも無粋だと大力に代金のことを聞かずにいたことを後悔した。セット料金と合わせるとまさかの10万越えで、月収の三分の一が一瞬で消えてしまったのだ。
それでも健吾は富士子会いに、貯蓄を削りながらせっせと通った。そんな健吾の席にオーナーの白鳥麻衣子が挨拶で着いた時だった。特に派手な印象は受けなかったが、まるでどこかの大企業の秘書のような穏やかだが厳格さも感じさせる口調で、彼女は言った。
「あなた、無理をしてはいけませんよ。お仕事に支障がない程度に、遊びに来て下さいね」
それはあくまで健吾を気遣っての言葉だったのだろうが、それを言われた健吾はひどく馬鹿にされた気がした。あなたにはこんな高級な店は相応しくない、そう言われた気がしたのだ。まるで小さな子どもに言い聞かせるようなオーナーの口調が、返って健吾の悔しさを湧き立たせた。
だが無理をしているのは間違いなかった。
地元のスナックで一回数千円払うのとは桁が違う。きっと数多の羽振りのいい社長連中を接客してきたドルチェのオーナーはそんな自分の懐事情を看過していたのだろう。健吾は自分の甲斐性の無さを落ち込んだが、今更店通いを止めるには、彼はもう北新地の高級クラブの雰囲気に、というよりは富士子の魅力に、どっぷりと浸かってしまっていた。
気がつくと、健吾は大力の持ち込んだ仕事を優先的に受けるようになっていた。彼の仕事は近所のじいさんばあさんの細々とした要望を聞いて回るのとは実入りが違っていた。大力はどこかから安い物件を仕入れてきては、健吾にリフォームさせてまた転売するということを繰り返していたが、その差額だけでも結構な額が入っていたようだ。だが大力はそんなチマチマとした仕事を良しとする男ではなかった。
「藤原はん、これからの時代はな、ディベロッパーいうて、内装だけやのうて、何もない土地から計画して、箱もんをしっかり仕上げて売りに出す、そういうでっかいことせな、儲かりまへん。どうです?うちもディベロッパーの会社を起こすっちゅうのは」
「でぃ、でぃべろっぱー、ですか?」
「藤原はん、べろべろばーみたいなイントネーションで言いなはんな、ディベロッパー、でんがな」
そう言って大笑いする大力を見ながら、この男は何を言ってるのだろうと初めは半信半疑で聞いていた。しかし大力は至極真面目で、あれよあれよという間に健吾が親の代から引き継いだ敷地に鉄筋建ての会社を建設し始めた。
「いや、大力さん、俺は一介の工務店のオヤジに過ぎません。ディベロッパーやなんて、ちょっと荷が過ぎますわ」
健吾はそう言って躊躇していたのだったが、
「何言ってますの藤原はん、これからの時代の社長はな、何でもかんでも自分でやる必要おまへん。出来るやつを雇ったらええんや。アウトソーシングいうてな、何も自分とこで雇わんでも、必要な時に外注するだけでもええんや。人の力借りてどんどん儲ける、それがこれからの時代の社長や。なあ、藤原はん。ワシの言う通りにしとったら、おまはんを一端の社長にしたるからな」
「しゃ…社長に…ですか?」
「そうやがな。いつまでも工務店のおっさんやなんて、そんな野暮ったい肩書捨てなはれ。どんとでっかい会社を立ち上げようやないか。そやな、藤原建設なんてどうです?『藤原建設代表取締役社長』それがあんたの新しい肩書や!」
大力には大風呂敷をぶち上げるだけでなく、それを実現させる行動力があった。そうして健吾はただの内装屋のおっさんから建設会社の社長になった。現場の指揮はそれなりの経歴の人間を雇って任せるようになってたので、健吾はただ社長然として座っているだけで良かった。それでも羽振りだけはどんどんよくなり、健吾は連日北新地に繰り出し、富士子との逢瀬を重ねた。
そして気がついた頃には、藤原建設は大力の所属する裏の組織のフロント企業になってしまっていた──。
それでも大力の言った通り、藤原建設は破竹の勢いで業績を伸ばした。日本のあらゆる土地が底値を知らぬように高騰仕出し、いわゆるバブル景気に日本は突入していた。藤原建設の事業もどんどん大掛かりとなり、末はフジケン興業と名を改めて駅前の一等地に10階建てのビルを構える一端のゼネコン企業になっていた。
大力は次々によく分からない素性の者を雇い入れ、会社の中にどういう部署があり、彼らがどういう仕事をしているのか、健吾には把握出来なくなっていた。健吾もただ黙って見ていた訳ではなく、宅建士や不動産鑑定士などの資格を出来るだけ取って口の挟めるところは割って入ってはいたが、ほとんどの現場では口を出すことを許されず、大きな事業の前ではお飾りの社長に甘んじていた。
それでも腐らずに会社に居られたのは、大力が何かにつけて健吾の顔を立てたからだった。社員の前は元より、対外的にも必要な時には健吾を連れ回し、社交界を賑わす面々に紹介して回った。そうして健吾の対面は保たれ、健吾自身もそれなりの風格を宿していった。だが心の芯の部分では、自分に頭を垂れる者たちは結局背後に控える大力が怖くてそうしているのだと分かっていた。自分などいつすげ替えられてもいい頭なのだ、そう考えるとどこか薄ら寒い隙間風がピューピューと吹いてともすれば悴んでしまいがちになるのを、日々のアルコールと自分を取り巻く女たちの色気で何とかやり過ごしていたのだった。
「あれ?藤原さんやないですか?こんなとこで何されてるんです?」
いきなり声をかけられ、健吾は悔恨の入り混じった回想から現実に頭を起こした。座っていた土手を見上げると、背後の堤防に通る道を、一人の老人が散歩をしていた。こちらに怪訝な顔を向けるその老人の姿を認め、健吾は顔をしかめた。もしかしたら、今一番会いたくなかった人物かもしれない……。
「あ、ああ、ちょっとな……娘を亡くしましてな、仕事に手がつかんで、ふらふらと、ね」
この老人に嘘を言っても仕方がないと、健吾は自分の今の状況を的確に話した。老人はそれを聞き、訳知り顔で頷く。
「ニュースで観ましたよ。この度は…誠にご愁傷さまなことで……」
会社の連中や仕事上の知り合い、果ては新地のホステスまで、もう何人からそんな言葉をかけられただろう。みんな決まって、健吾を見ると何をどう言っていいか分からないというような困った顔になり、何とか口に出した言葉も途中で曖昧に途切れさせる。いつものように神妙に頷いて返すと、目の前の老人は他の人間では絶対に言えない言葉を放った。
「まあ、自業自得ですわな。あんたのこれまでの所業を思ったら」
一瞬、何を言われたのか分からなかった。
自業自得……
そんなことは分かってる!
それは、人からは絶対に言われたくない言葉で、健吾は皮下脂肪の多めの肌を泡立たせた。
「あ、あんたに何が分かる!最愛の娘を亡くした人間の気持ちが!あんたに、何が分かる!!」
気がつくと立ち上がり、激昂していた。頭に血が一気に上り、少食になって貧血気味だった身体が立ち眩みを起こてよろける。老人が手を添えようとしたのを、パシンと払い除けた。そしてそのまま倒れ込み、砂利が粗く転がるアスファルトに顔を押し付け、号泣した。
1
お気に入りに追加
11
あなたにおすすめの小説

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

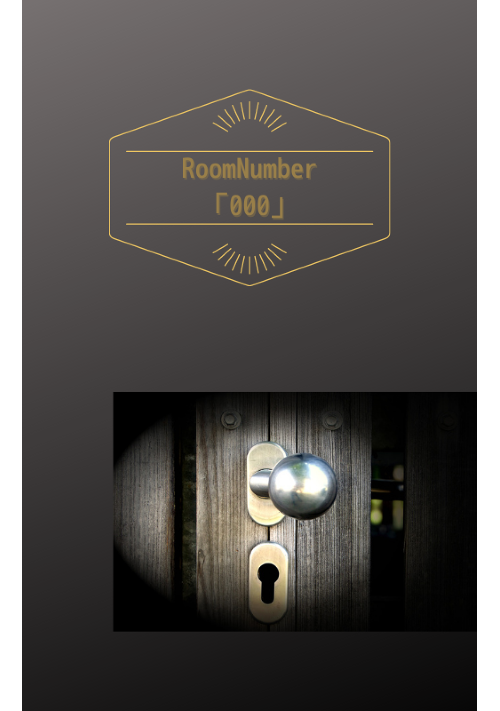
RoomNunmber「000」
誠奈
ミステリー
ある日突然届いた一通のメール。
そこには、報酬を与える代わりに、ある人物を誘拐するよう書かれていて……
丁度金に困っていた翔真は、訝しみつつも依頼を受け入れ、幼馴染の智樹を誘い、実行に移す……が、そこである事件に巻き込まれてしまう。
二人は密室となった部屋から出ることは出来るのだろうか?
※この作品は、以前別サイトにて公開していた物を、作者名及び、登場人物の名称等加筆修正を加えた上で公開しております。
※BL要素かなり薄いですが、匂わせ程度にはありますのでご注意を。

【R-18】クリしつけ
蛙鳴蝉噪
恋愛
男尊女卑な社会で女の子がクリトリスを使って淫らに教育されていく日常の一コマ。クリ責め。クリリード。なんでもありでアブノーマルな内容なので、精神ともに18歳以上でなんでも許せる方のみどうぞ。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















