104 / 183
第2部 萌未の手記
二つの病室
しおりを挟む
三連休が明けてクリスマスの日、あたしはさくらの入院している病院へ向かった。
黒田店長から病院名を聞き、電話で確かめるとさくらはすでに面会謝絶が解けて普通病棟に移ったということだった。
病院へ向かう途中で百貨店に寄り、美味しそうなケーキを見繕う。さくらが食べられるかどうかは分からないけど、ほっぺたを膨らませてにこにこ食べるさくらの姿を思い浮かべながら、丸くて可愛らしいのをいくつか選んだ。
街は明日には取り払われるであろうクリスマスの飾り付けやイルミネーションで煌めいている。年頃の女の子たちが行き交うのを見て、あたしもあんなにキャピキャピしていたら毎日が楽しいのかな、と、自分の姿を重ね合わせてみる。そんなパラレルワールドのあたしの隣には優しく微笑む志保姉がいる──
胸が、ギシギシと鳴る。
やっぱりな…
やっぱりダメだ。
あたしが年頃の女の子らしく明るく振る舞うための世界のピースは永遠に失われた。
あたしは百貨店のアーケードを抜け、病院に向けてタクシーを走らせた。
受付で聞いてさくらの病室へ行くと、そこは二人部屋で、カーテンで仕切られた一方のベッドの横にはポッチャリとした、でもどこかさくらに似ている年配の女性が座っていた。
『三枝沙紀』
病室の扉のネームプレートの一つにはそう記されていた。
「あの…」
声をかけようとすると、その座っていた女性はあたしに気づき、
「ああ、沙紀の…お店の…?」
と逆に声をかけてくれた。
「あ、はい…」
「母ちゃん、誰、誰ぇ?」
カーテンで仕切られた奥の窓側から聞き慣れた声が聞こえる。手前のベッドは空だった。
「どうぞ、こっちに」
手招きされて奥に進むと、ベッドの背を少し上げ、頭をやや上げて寝ているさくらの姿があった。
「めぐみちゃん」
さくらは思ったより血色が良く、あたしの顔を見るとにっこりと微笑んだ。パジャマの胸元から首まで、サラシのように巻かれた包帯が見えている。それを見て、安堵と悲しみの入り交ざった感情が沸き起こり、涙が溢れてきた。
「さくらちゃん…ごめんね。あたしのために…」
お母さんがそっとあたしに丸椅子を回してくれる。
「まあ座りんしゃいな。そげに立っとらんと」
「あ、あの…娘さんがこんなことになったのはあたしのせいなんです。本当にすみません」
あたしはお母さんに向き直って頭を下げる。
「なんも。この子から聞いちょるよ。あんたのせいやない。まあ~それにしても沙紀にこーんなべっぴんさんの友達がおるなんて、母ちゃんびっくりやけん」
「そやろ?めぐみちゃんな、店で一番綺麗なんよ」
「そんな…ありがとうございます…」
お母さんの柔らかい言葉に涙がさらに溢れ、お母さんはティッシュ箱を渡してくれた。
「さあさあ、そげに泣いちょらんと。ほな、母ちゃん買いもん行って来るわ。何か欲しいもんないね?」
「うーんと、マンガ」
「マンガて、どんなね?」
「母ちゃんに任せる。少女マンガ雑誌、適当に買ってきて」
「はいはい。ほな、ごゆっくりね」
お母さんは気を使ってくれたのか、あたしとさくらを残して病室から出ていった。
「優しそうなお母さんやね」
「うん。ねえ、めぐみちゃん、それ、何?」
「あ、これ?さくらちゃん、食べれるかなあ?」
あたしは持ってきたケーキの箱を開けて見せた。
「わあ~可愛い!食べたい食べたい!めぐみちゃん、一緒に食べよ?」
ナースステーションで皿とフォークを2セット借り、それぞれにケーキを取り分けて、片方をさくらに渡す。
「めぐみちゃん、メリークリスマス、やね」
「うん、メリークリスマス」
「うわあ~美味しい!ほんまはね、まだ病院食しか食べたらあかんねんけど、こんなに美味しいの、ぜーんぶ食べちゃいたいよ」
「ね、その…怪我、痛くない?大丈夫?」
大丈夫じゃない訳ない。
あんなにグッサリとグラスか刺さっていたのだ。
あたしの間の抜けた質問に、さくらはにっこりと微笑んだ。
「うん、じっとしてたら痛くないよ。でもね、もうちょっと左やったら、心臓に刺さって死んでたかもしれなかったんやって」
「そう…ごめんね、あたしのために…なんでこんな無茶したの?」
さくらのあどけない顔が滲んでくる。
「まーた!めぐみちゃん、顔上げて!さくらね、気がついたら前に飛び出てたの。だってね、めぐみちゃんはさくらのこと、お友達だって言ってくれたから。だから、さくら嬉しいんだぁ、めぐみちゃんのこと守ってあげれて。それにね、聞こえたよ、めぐみちゃんがさくら、さくら~って呼ぶの。痛かったけど、嬉しかったんだぁ」
「もう!死んでたかもしれないのに、何言ってるの」
「えへへぇ。あのね、めぐみちゃん、お願いがあるんやけど…」
「なあに?何でも言って」
「じゃあ…沙紀って呼んでみて。あの時みたいな感じで、沙紀ぃって」
「何よ、それ。そんなんでいいの?」
「うんうん。早くぅ」
「じゃあ…沙紀」
「もっと」
「沙紀!」
「もっと強く!」
「沙紀いぃ!」
「はーい!」
「何これ」
そこで、二人で笑い合う。
「あのね、これからも沙紀って呼び捨てで呼んで欲しいな」
「いいよ。沙紀、か。さくらが咲くみたいで素敵な本名と源氏名の組み合わせね。じゃあ、沙紀もあたしのこと、萌未って呼び捨てにしてね?」
「ええ~めぐみちゃんはちょっと呼び捨てしづらいなあ…」
「だーめ!あたしたち、大切なお友達でしょ?だったら、呼んでみて」
あたしの言葉に、さくらは少し頬を赤らめて破顔し、そしておずおずと、あたしの名前を口にした。
「えーと、めぐみ…ん」
「ん?」
「めぐみん。そう、めぐみんがいい!」
「もう!しょうがないなあ…」
「めぐみん?」
「なあに、沙紀?」
「めぐみん」
「沙紀」
「めーぐーみん!」
「はーあーい!て、何これ」
病室にコロコロとした笑い声が響いた。
それから──
お母さんが帰ってから病室を辞すと、あたしは受付で教えてもらったもう一つの病室へと向かう。
金曜日に救急で運び込まれた二人の病室、と言えばすぐに教えてくれた。
その病室はさくらの上のフロアーにあり、個室だった。
開放的だったさくらの病室と違い、ドアがしっかりと閉められていた。
ドアの前で立ち止まって中の様子を伺うが、物音一つしない。
あたしは入るのをためらった。
(もう水商売は出来ないだろうって)
なっちゃんが言ってた。この病室の中は間違いなくさっきみたいな平和な空間ではない。あたしはノックをしかけたが、思いとどまった。きっと綺羅ママはあたしの顔なんか見たくないだろう。
それどころか、今あたしが顔を出せば、怒りで血が逆流して傷を悪化させてしまうかもしれない。そうなるとあたしにとっても逆効果だ。あたしは何としても綺羅ママから情報を聞き出さなければならない。
でも今すぐは無理かもしれない…
それに、あの傷ではきっとしゃべるのもままならないだろう。
もう少し時間が経ってから、ちゃんと戦略を考えて訪れよう、と、あたしは病室の位置だけを確かめ、その場を離れることにした。
12月も最終週に入り、あたしはさくらの怪我の状態が心配ないことを確認すると、その日は通常通り出勤した。本当は鋭気を養って家でゆっくりしたかったが、そうは出来ない理由があった。それは、宮本の口座のことだ。黒田店長にさくらの入院している病院名を聞いた時に、綺羅ママがすでに退店扱いになっていることを聞いた。
いくら勝負に負けたとはいえ、あんな惨状が起こり、酷い怪我まで負ってしまった綺羅ママのことを思うと酷な気もしたが、店としては綺羅ママの口座のうち、年末年始のうちに動かせるものは動かしてしまいたいと店長は言う。
実際に出勤してみると、店の非常階段へ向かう待機スペースに綺羅ママの口座一覧が張り出されていた。
『以下の口座が欲しい人は正月休みのうちに挨拶しておくように』
と但し書きされた紙にはズラッと会社名とお客さんの氏名が列挙されていて、その中には、フジケン興業の藤原健吾と宮本拓也の名前もあった。
あたしは黒田店長を捕まえて聞く。
「ね、今度こそ宮本さん、あたしの口座に出来るよね?」
その質問に店長は眉根を寄せ、何でそんなに宮本の口座に拘るのかと聞いてきたが、そこはあたしも口座を持ってみたいからとか何とか言って誤魔化した。
「まあ貼り出した紙に書いてある通り、早いもん勝ちやな。ほんまは口座が空いたら店預かりになるとこやけど、今回はオーナーママからも移せる口座は早めに移すようにとの指示が出てる。なので、宮本が萌未口座でいいって言いさえしたら、それで完了や」
その言葉を聞き、あたしはいよいよだ、と思った。
いろいろ紆余曲折はあったが、これでやっと志保姉の敵討ちに一歩踏み込むことができる───と。
黒田店長から病院名を聞き、電話で確かめるとさくらはすでに面会謝絶が解けて普通病棟に移ったということだった。
病院へ向かう途中で百貨店に寄り、美味しそうなケーキを見繕う。さくらが食べられるかどうかは分からないけど、ほっぺたを膨らませてにこにこ食べるさくらの姿を思い浮かべながら、丸くて可愛らしいのをいくつか選んだ。
街は明日には取り払われるであろうクリスマスの飾り付けやイルミネーションで煌めいている。年頃の女の子たちが行き交うのを見て、あたしもあんなにキャピキャピしていたら毎日が楽しいのかな、と、自分の姿を重ね合わせてみる。そんなパラレルワールドのあたしの隣には優しく微笑む志保姉がいる──
胸が、ギシギシと鳴る。
やっぱりな…
やっぱりダメだ。
あたしが年頃の女の子らしく明るく振る舞うための世界のピースは永遠に失われた。
あたしは百貨店のアーケードを抜け、病院に向けてタクシーを走らせた。
受付で聞いてさくらの病室へ行くと、そこは二人部屋で、カーテンで仕切られた一方のベッドの横にはポッチャリとした、でもどこかさくらに似ている年配の女性が座っていた。
『三枝沙紀』
病室の扉のネームプレートの一つにはそう記されていた。
「あの…」
声をかけようとすると、その座っていた女性はあたしに気づき、
「ああ、沙紀の…お店の…?」
と逆に声をかけてくれた。
「あ、はい…」
「母ちゃん、誰、誰ぇ?」
カーテンで仕切られた奥の窓側から聞き慣れた声が聞こえる。手前のベッドは空だった。
「どうぞ、こっちに」
手招きされて奥に進むと、ベッドの背を少し上げ、頭をやや上げて寝ているさくらの姿があった。
「めぐみちゃん」
さくらは思ったより血色が良く、あたしの顔を見るとにっこりと微笑んだ。パジャマの胸元から首まで、サラシのように巻かれた包帯が見えている。それを見て、安堵と悲しみの入り交ざった感情が沸き起こり、涙が溢れてきた。
「さくらちゃん…ごめんね。あたしのために…」
お母さんがそっとあたしに丸椅子を回してくれる。
「まあ座りんしゃいな。そげに立っとらんと」
「あ、あの…娘さんがこんなことになったのはあたしのせいなんです。本当にすみません」
あたしはお母さんに向き直って頭を下げる。
「なんも。この子から聞いちょるよ。あんたのせいやない。まあ~それにしても沙紀にこーんなべっぴんさんの友達がおるなんて、母ちゃんびっくりやけん」
「そやろ?めぐみちゃんな、店で一番綺麗なんよ」
「そんな…ありがとうございます…」
お母さんの柔らかい言葉に涙がさらに溢れ、お母さんはティッシュ箱を渡してくれた。
「さあさあ、そげに泣いちょらんと。ほな、母ちゃん買いもん行って来るわ。何か欲しいもんないね?」
「うーんと、マンガ」
「マンガて、どんなね?」
「母ちゃんに任せる。少女マンガ雑誌、適当に買ってきて」
「はいはい。ほな、ごゆっくりね」
お母さんは気を使ってくれたのか、あたしとさくらを残して病室から出ていった。
「優しそうなお母さんやね」
「うん。ねえ、めぐみちゃん、それ、何?」
「あ、これ?さくらちゃん、食べれるかなあ?」
あたしは持ってきたケーキの箱を開けて見せた。
「わあ~可愛い!食べたい食べたい!めぐみちゃん、一緒に食べよ?」
ナースステーションで皿とフォークを2セット借り、それぞれにケーキを取り分けて、片方をさくらに渡す。
「めぐみちゃん、メリークリスマス、やね」
「うん、メリークリスマス」
「うわあ~美味しい!ほんまはね、まだ病院食しか食べたらあかんねんけど、こんなに美味しいの、ぜーんぶ食べちゃいたいよ」
「ね、その…怪我、痛くない?大丈夫?」
大丈夫じゃない訳ない。
あんなにグッサリとグラスか刺さっていたのだ。
あたしの間の抜けた質問に、さくらはにっこりと微笑んだ。
「うん、じっとしてたら痛くないよ。でもね、もうちょっと左やったら、心臓に刺さって死んでたかもしれなかったんやって」
「そう…ごめんね、あたしのために…なんでこんな無茶したの?」
さくらのあどけない顔が滲んでくる。
「まーた!めぐみちゃん、顔上げて!さくらね、気がついたら前に飛び出てたの。だってね、めぐみちゃんはさくらのこと、お友達だって言ってくれたから。だから、さくら嬉しいんだぁ、めぐみちゃんのこと守ってあげれて。それにね、聞こえたよ、めぐみちゃんがさくら、さくら~って呼ぶの。痛かったけど、嬉しかったんだぁ」
「もう!死んでたかもしれないのに、何言ってるの」
「えへへぇ。あのね、めぐみちゃん、お願いがあるんやけど…」
「なあに?何でも言って」
「じゃあ…沙紀って呼んでみて。あの時みたいな感じで、沙紀ぃって」
「何よ、それ。そんなんでいいの?」
「うんうん。早くぅ」
「じゃあ…沙紀」
「もっと」
「沙紀!」
「もっと強く!」
「沙紀いぃ!」
「はーい!」
「何これ」
そこで、二人で笑い合う。
「あのね、これからも沙紀って呼び捨てで呼んで欲しいな」
「いいよ。沙紀、か。さくらが咲くみたいで素敵な本名と源氏名の組み合わせね。じゃあ、沙紀もあたしのこと、萌未って呼び捨てにしてね?」
「ええ~めぐみちゃんはちょっと呼び捨てしづらいなあ…」
「だーめ!あたしたち、大切なお友達でしょ?だったら、呼んでみて」
あたしの言葉に、さくらは少し頬を赤らめて破顔し、そしておずおずと、あたしの名前を口にした。
「えーと、めぐみ…ん」
「ん?」
「めぐみん。そう、めぐみんがいい!」
「もう!しょうがないなあ…」
「めぐみん?」
「なあに、沙紀?」
「めぐみん」
「沙紀」
「めーぐーみん!」
「はーあーい!て、何これ」
病室にコロコロとした笑い声が響いた。
それから──
お母さんが帰ってから病室を辞すと、あたしは受付で教えてもらったもう一つの病室へと向かう。
金曜日に救急で運び込まれた二人の病室、と言えばすぐに教えてくれた。
その病室はさくらの上のフロアーにあり、個室だった。
開放的だったさくらの病室と違い、ドアがしっかりと閉められていた。
ドアの前で立ち止まって中の様子を伺うが、物音一つしない。
あたしは入るのをためらった。
(もう水商売は出来ないだろうって)
なっちゃんが言ってた。この病室の中は間違いなくさっきみたいな平和な空間ではない。あたしはノックをしかけたが、思いとどまった。きっと綺羅ママはあたしの顔なんか見たくないだろう。
それどころか、今あたしが顔を出せば、怒りで血が逆流して傷を悪化させてしまうかもしれない。そうなるとあたしにとっても逆効果だ。あたしは何としても綺羅ママから情報を聞き出さなければならない。
でも今すぐは無理かもしれない…
それに、あの傷ではきっとしゃべるのもままならないだろう。
もう少し時間が経ってから、ちゃんと戦略を考えて訪れよう、と、あたしは病室の位置だけを確かめ、その場を離れることにした。
12月も最終週に入り、あたしはさくらの怪我の状態が心配ないことを確認すると、その日は通常通り出勤した。本当は鋭気を養って家でゆっくりしたかったが、そうは出来ない理由があった。それは、宮本の口座のことだ。黒田店長にさくらの入院している病院名を聞いた時に、綺羅ママがすでに退店扱いになっていることを聞いた。
いくら勝負に負けたとはいえ、あんな惨状が起こり、酷い怪我まで負ってしまった綺羅ママのことを思うと酷な気もしたが、店としては綺羅ママの口座のうち、年末年始のうちに動かせるものは動かしてしまいたいと店長は言う。
実際に出勤してみると、店の非常階段へ向かう待機スペースに綺羅ママの口座一覧が張り出されていた。
『以下の口座が欲しい人は正月休みのうちに挨拶しておくように』
と但し書きされた紙にはズラッと会社名とお客さんの氏名が列挙されていて、その中には、フジケン興業の藤原健吾と宮本拓也の名前もあった。
あたしは黒田店長を捕まえて聞く。
「ね、今度こそ宮本さん、あたしの口座に出来るよね?」
その質問に店長は眉根を寄せ、何でそんなに宮本の口座に拘るのかと聞いてきたが、そこはあたしも口座を持ってみたいからとか何とか言って誤魔化した。
「まあ貼り出した紙に書いてある通り、早いもん勝ちやな。ほんまは口座が空いたら店預かりになるとこやけど、今回はオーナーママからも移せる口座は早めに移すようにとの指示が出てる。なので、宮本が萌未口座でいいって言いさえしたら、それで完了や」
その言葉を聞き、あたしはいよいよだ、と思った。
いろいろ紆余曲折はあったが、これでやっと志保姉の敵討ちに一歩踏み込むことができる───と。
1
お気に入りに追加
11
あなたにおすすめの小説

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

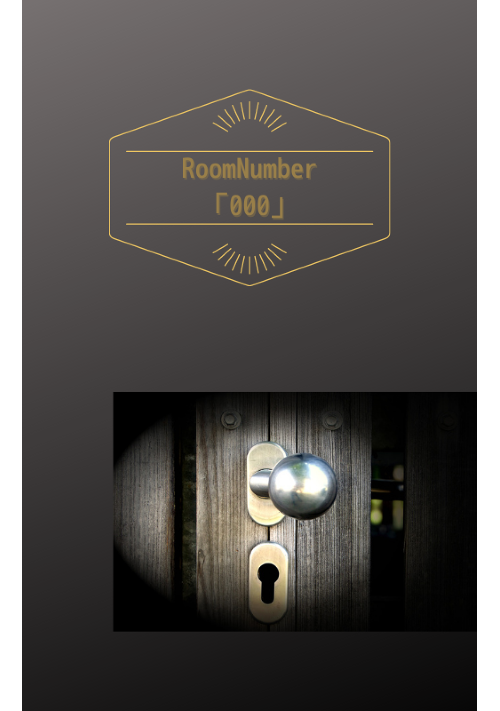
RoomNunmber「000」
誠奈
ミステリー
ある日突然届いた一通のメール。
そこには、報酬を与える代わりに、ある人物を誘拐するよう書かれていて……
丁度金に困っていた翔真は、訝しみつつも依頼を受け入れ、幼馴染の智樹を誘い、実行に移す……が、そこである事件に巻き込まれてしまう。
二人は密室となった部屋から出ることは出来るのだろうか?
※この作品は、以前別サイトにて公開していた物を、作者名及び、登場人物の名称等加筆修正を加えた上で公開しております。
※BL要素かなり薄いですが、匂わせ程度にはありますのでご注意を。

【R-18】クリしつけ
蛙鳴蝉噪
恋愛
男尊女卑な社会で女の子がクリトリスを使って淫らに教育されていく日常の一コマ。クリ責め。クリリード。なんでもありでアブノーマルな内容なので、精神ともに18歳以上でなんでも許せる方のみどうぞ。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















