15 / 183
第1部 高級クラブのお仕事
芸姑と旦那の関係性
しおりを挟む
萌未には彼氏がいっぱいいて、自分もそのうちの一人に加えてくれると言う、涼平は彼女の滑らかな唇の感触と甘美な舌の艶かしさを再度堪能しながら、その提案をどこか物悲しい思いで反芻した。唇を離し、そんな涼平の顔色を伺う萌未の表情は幾分幼く見え、それはメイクを落としているからだけではないように思えた。
「俺なんて貧乏やし、かっこよくもないし、将来性もないのに?」
「かっこよくないことないよ。あたし、涼平の顔、好きよ」
萌未はそう言って涼平の頬を優しく撫でる。そんなふうに顔を撫でられるのは、涼平の記憶では祖母にそうしてもらって以来だった。
「ね、涼平のこと、もっと教えて?」
目を細めて微笑む萌未の顔が、今度は大人びて見える。表情ひとつで印象がコロコロ変わる彼女に、涼平はまた不思議な郷愁に捕らわれる。
「俺の…何を?」
「そうねぇ、例えば、どんな子どもだった?」
「別に普通の子やったよ。祖父が彫刻家でね、よくアトリエに忍び込んで何か造ったりしてたなあ…」
「そう…手先が器用なのね。ね、おばあちゃんは?どんな人やの?」
「ん?何で?」
「きのうね、涼平、ばあちゃん、ばあちゃんって寝言言ってたわよ」
「え…それは恥ずかしいな…。俺、ばあちゃん子やったからね」
「おばあちゃん、生きてはるの?」
「もう三年も前に亡くなったよ」
「そう…その時、悲しかった?」
「そりゃあね、もう大泣きしたよ」
「ね、おばあちゃんのこと、今でも好き?」
「うん。ばあちゃんは俺にとって原点やからね」
「ふーん…」
そこまで会話すると、萌未はぶるぶるっと身体を震わせ、毛布の中に頭を潜らせた。涼平もそれを追うように彼女の真横に頭を滑らせる。毛布の中で、萌未が涼平にしがみついた。萌未の小さな頭に頬を押し当て、涼平は彼女に対して胸を締め付けるような切なさと愛おしさを感じながら、在りし日の祖母のことを回想した。
祖母のことでまず思い出すのは、三味線の音色だ。その律動的な響きには、いつも物悲しさをまとっていた。涼平は祖母の弾いてくれる曲目を全く知らなかったが、曲調が明るく陽気なものであっても、音色の中には一抹の寂しさを感じていた。
祖母はその三味線の腕を、芸姑時代に磨いたらしい。祖母は九州は門司の大衆食堂を営む家庭の七人兄弟の末っ子として生まれ、京都の置屋に奉公に出された。祖母は自分の舞妓から芸姑時代にかけてのことを涼平にあまり語ってくれなかったが、涼平は祖母が若い頃京都で芸姑をしていたことだけは父から聞いて知っていた。
涼平の祖父が亡くなったのは、涼平が中学三年に上がった年のことだった。父と祖父とは反りが合わず、父は社会に出ると同時に実家を離れ、盆と正月の挨拶以外は祖父の家に寄り付こうとしなかった。祖父は京都府の辺鄙な山間の地に住居兼アトリエを構え、父は子どもの頃、そこから一時間以上もかけて学校に通うのに苦労したと、酒精に浸る度によく愚痴っていた。涼平は小学校に上がると一人でも祖父のアトリエに赴いた。そして祖父が亡くなっても、山奥に一人暮らしになってしまった祖母によく顔を見せた。
父は年老いた祖母に一緒に暮らすことを打診しているようだったが、祖母はそれを断り、ひっそりと山奥の一人暮らしを続けていた。涼平は幼少期よりどちらかといえば祖父よりも祖母の方に慕っていて、祖母が一人暮らしになってからもせっせとアトリエを訪れた。祖母を訪れた帰りしな、山道を下る涼平を見送ってくれる姿がやけに小さく、頼りなく見え、切なさに胸を締めつけられた感覚を今も覚えている。そして結局祖父が亡くなった三年後に、祖父を追うように祖母も逝ってしまった。
涼平はつらつらと、優しかった祖母のことを思い出しながら語った。そしてふと横の萌未に目を向けると、萌未は肩を震わせていた。
「え、泣いてるの?」
「ううん、寒いねん」
萌未はそう言って一層涼平にしがみつく。涼平は腕に彼女の頭の重みを感じながら、その細い肩を抱いた。それからしばらく、静かな時間が流れた。穏やかな時間だった。一見派手で奔放に見える萌未のか細い儚げな姿になぜか祖母の姿がリンクし、美伽に対するのとはまた違った、特別な感情が湧き上がるのを感じていた。
「ね、芸子さんと旦那さんの関係って知ってる?」
萌未はふと思いついたように、そんな質問をした。ドラマや映画なんかでイメージとしては何となく知っているが詳しく語るまでは知らなかった。
「昔の芸子さんってね、この人と思う旦那さんに施しを受ける代わりに、芸子である限りはその旦那さんにずっと尽くすのよ。旦那さんは自分の世話する芸子さんに舞妓の頃から生涯に渡って金銭的な援助をするの。今でやったら何億っていう額になる場合もあったらしいよ。それが旦那さんの甲斐性なのね。でもね、芸を売ってる誇りから旦那さんを作らない芸子さんもいたの」
萌未はそこまで話すと、顎下から涼平の顔を覗き込んだ。
「今は旦那制度みたいなのはないらしいけどね。でもホステス、特に高級クラブのホステスの仕事ってちょっと似てるとこあるの。ね、涼平はあたしのこと、どっちのタイプと思う?旦那さんを作るタイプと、作らないタイプ」
正直、学生である萌未がそこまで真剣にホステスの仕事のことを考えてるとは思えなかったから、涼平には後者のように思えた。だがきのう席に出してくれた高そうなボトルや、客に買ってもらったという高級ブランドのバッグなどが頭を過ぎり、答えに詰まった。
(好きな人いるわよ、いーっぱい)
大勢の旦那さん、あるいは特定の金持ちの旦那さんが萌未を世話しているイメージを思い描くと、それは妙にしっくりきた。自分にも旦那さん的な人がいる、それを伝えたくて芸姑の話をし出したのだろうか……そんなことを考えながら、ただ萌未の顔を見つめていた。
と突然、
ブーン、ブーン、ブーン
と携帯のバイブ音が鳴り響いた。萌未はガバッと起き上がってベッドの横のサイドテーブルから携帯を取った。
「はい、はい、すみません、わかりました…」
電話に出た彼女はひたすら謝っていた。
「大丈夫?」
「うん、雅子ママがきのうの件でね」
話し終えた彼女にそう聞くと、ペロッと舌を出す。
「そう言えばきのう謝りに行くって言ってたけど、もしかしたら今から?」
「ううん、でも今日、詫び同伴になっちゃった。いややなぁ…」
彼女はテーブルの目覚まし時計を見て、もう昼前やない、とびっくりしたように言った。
「涼平のせいで午前中の講義に出そびれちゃったわ」
そう言って持っていた携帯を涼平の目の前でぷらぷらする。携帯に付けていたストラップがぷらぷらと揺れた。
「ね、これ、可愛いでしょ?」
そのストラップは赤い古ぼけた木片で何度も触れられた手すりのような鈍い光沢を放ち、何の形かは涼平には分からなかったが、いつもブランドもので身を固めている萌未にしてはひどくみすぼらしい物に見えた。
「それ、何の形?」
「これはね、幸運をもたらしてくれるラッキーアイテムなのよ。涼平も欲しい?」
「何言ってるの。プレゼントならもうきのう充分にしてもらったよ。ていうかさ、きのうのクラブの飲み代、いくらやったん?シャレードのシャンパンは誕生日祝いとしてありがたくいただくとして、さすがにその後はもらい過ぎやから、飲み代くらいは払うよ」
「きのうのは全部あたしの奢りやって言ったでしょ?値段なんて聞かなくていいのよ」
「そうはいかないよ。夏美さんが社会見学って言ってたけど、それを知らないとちゃんと社会見学したことにならへんやろ?」
「聞いたら目玉飛び出すかもよ」
「いいから」
萌未は面倒臭い、というようにため息をついた。
「ボトルはおろしてないから5万くらいかな?ワインはなっちゃんが出してくれたけど、3万くらいのやつやったと思う」
夏美さんに聞いてはいたが、やはり目玉が飛び出るくらい高い。
「一応あたしは高級クラブのホステスですからね、そんなもんなのよ。ああいうとこは一瞬でも座ったら5万くらいになるの」
「それ、俺払うよ」
「いい加減にしなさい。奢りって言ってるでしょ?それに、働いてもいないくせにどうやって払うのよ」
萌未は今度は大きくため息を吐き、サイドテーブルに置いてあった煙草を一本咥えて火を点けた。涼平はそんな萌未にしっかりとした視線を送りながら、毅然とした口調で言った。
「俺、黒服になる」
「俺なんて貧乏やし、かっこよくもないし、将来性もないのに?」
「かっこよくないことないよ。あたし、涼平の顔、好きよ」
萌未はそう言って涼平の頬を優しく撫でる。そんなふうに顔を撫でられるのは、涼平の記憶では祖母にそうしてもらって以来だった。
「ね、涼平のこと、もっと教えて?」
目を細めて微笑む萌未の顔が、今度は大人びて見える。表情ひとつで印象がコロコロ変わる彼女に、涼平はまた不思議な郷愁に捕らわれる。
「俺の…何を?」
「そうねぇ、例えば、どんな子どもだった?」
「別に普通の子やったよ。祖父が彫刻家でね、よくアトリエに忍び込んで何か造ったりしてたなあ…」
「そう…手先が器用なのね。ね、おばあちゃんは?どんな人やの?」
「ん?何で?」
「きのうね、涼平、ばあちゃん、ばあちゃんって寝言言ってたわよ」
「え…それは恥ずかしいな…。俺、ばあちゃん子やったからね」
「おばあちゃん、生きてはるの?」
「もう三年も前に亡くなったよ」
「そう…その時、悲しかった?」
「そりゃあね、もう大泣きしたよ」
「ね、おばあちゃんのこと、今でも好き?」
「うん。ばあちゃんは俺にとって原点やからね」
「ふーん…」
そこまで会話すると、萌未はぶるぶるっと身体を震わせ、毛布の中に頭を潜らせた。涼平もそれを追うように彼女の真横に頭を滑らせる。毛布の中で、萌未が涼平にしがみついた。萌未の小さな頭に頬を押し当て、涼平は彼女に対して胸を締め付けるような切なさと愛おしさを感じながら、在りし日の祖母のことを回想した。
祖母のことでまず思い出すのは、三味線の音色だ。その律動的な響きには、いつも物悲しさをまとっていた。涼平は祖母の弾いてくれる曲目を全く知らなかったが、曲調が明るく陽気なものであっても、音色の中には一抹の寂しさを感じていた。
祖母はその三味線の腕を、芸姑時代に磨いたらしい。祖母は九州は門司の大衆食堂を営む家庭の七人兄弟の末っ子として生まれ、京都の置屋に奉公に出された。祖母は自分の舞妓から芸姑時代にかけてのことを涼平にあまり語ってくれなかったが、涼平は祖母が若い頃京都で芸姑をしていたことだけは父から聞いて知っていた。
涼平の祖父が亡くなったのは、涼平が中学三年に上がった年のことだった。父と祖父とは反りが合わず、父は社会に出ると同時に実家を離れ、盆と正月の挨拶以外は祖父の家に寄り付こうとしなかった。祖父は京都府の辺鄙な山間の地に住居兼アトリエを構え、父は子どもの頃、そこから一時間以上もかけて学校に通うのに苦労したと、酒精に浸る度によく愚痴っていた。涼平は小学校に上がると一人でも祖父のアトリエに赴いた。そして祖父が亡くなっても、山奥に一人暮らしになってしまった祖母によく顔を見せた。
父は年老いた祖母に一緒に暮らすことを打診しているようだったが、祖母はそれを断り、ひっそりと山奥の一人暮らしを続けていた。涼平は幼少期よりどちらかといえば祖父よりも祖母の方に慕っていて、祖母が一人暮らしになってからもせっせとアトリエを訪れた。祖母を訪れた帰りしな、山道を下る涼平を見送ってくれる姿がやけに小さく、頼りなく見え、切なさに胸を締めつけられた感覚を今も覚えている。そして結局祖父が亡くなった三年後に、祖父を追うように祖母も逝ってしまった。
涼平はつらつらと、優しかった祖母のことを思い出しながら語った。そしてふと横の萌未に目を向けると、萌未は肩を震わせていた。
「え、泣いてるの?」
「ううん、寒いねん」
萌未はそう言って一層涼平にしがみつく。涼平は腕に彼女の頭の重みを感じながら、その細い肩を抱いた。それからしばらく、静かな時間が流れた。穏やかな時間だった。一見派手で奔放に見える萌未のか細い儚げな姿になぜか祖母の姿がリンクし、美伽に対するのとはまた違った、特別な感情が湧き上がるのを感じていた。
「ね、芸子さんと旦那さんの関係って知ってる?」
萌未はふと思いついたように、そんな質問をした。ドラマや映画なんかでイメージとしては何となく知っているが詳しく語るまでは知らなかった。
「昔の芸子さんってね、この人と思う旦那さんに施しを受ける代わりに、芸子である限りはその旦那さんにずっと尽くすのよ。旦那さんは自分の世話する芸子さんに舞妓の頃から生涯に渡って金銭的な援助をするの。今でやったら何億っていう額になる場合もあったらしいよ。それが旦那さんの甲斐性なのね。でもね、芸を売ってる誇りから旦那さんを作らない芸子さんもいたの」
萌未はそこまで話すと、顎下から涼平の顔を覗き込んだ。
「今は旦那制度みたいなのはないらしいけどね。でもホステス、特に高級クラブのホステスの仕事ってちょっと似てるとこあるの。ね、涼平はあたしのこと、どっちのタイプと思う?旦那さんを作るタイプと、作らないタイプ」
正直、学生である萌未がそこまで真剣にホステスの仕事のことを考えてるとは思えなかったから、涼平には後者のように思えた。だがきのう席に出してくれた高そうなボトルや、客に買ってもらったという高級ブランドのバッグなどが頭を過ぎり、答えに詰まった。
(好きな人いるわよ、いーっぱい)
大勢の旦那さん、あるいは特定の金持ちの旦那さんが萌未を世話しているイメージを思い描くと、それは妙にしっくりきた。自分にも旦那さん的な人がいる、それを伝えたくて芸姑の話をし出したのだろうか……そんなことを考えながら、ただ萌未の顔を見つめていた。
と突然、
ブーン、ブーン、ブーン
と携帯のバイブ音が鳴り響いた。萌未はガバッと起き上がってベッドの横のサイドテーブルから携帯を取った。
「はい、はい、すみません、わかりました…」
電話に出た彼女はひたすら謝っていた。
「大丈夫?」
「うん、雅子ママがきのうの件でね」
話し終えた彼女にそう聞くと、ペロッと舌を出す。
「そう言えばきのう謝りに行くって言ってたけど、もしかしたら今から?」
「ううん、でも今日、詫び同伴になっちゃった。いややなぁ…」
彼女はテーブルの目覚まし時計を見て、もう昼前やない、とびっくりしたように言った。
「涼平のせいで午前中の講義に出そびれちゃったわ」
そう言って持っていた携帯を涼平の目の前でぷらぷらする。携帯に付けていたストラップがぷらぷらと揺れた。
「ね、これ、可愛いでしょ?」
そのストラップは赤い古ぼけた木片で何度も触れられた手すりのような鈍い光沢を放ち、何の形かは涼平には分からなかったが、いつもブランドもので身を固めている萌未にしてはひどくみすぼらしい物に見えた。
「それ、何の形?」
「これはね、幸運をもたらしてくれるラッキーアイテムなのよ。涼平も欲しい?」
「何言ってるの。プレゼントならもうきのう充分にしてもらったよ。ていうかさ、きのうのクラブの飲み代、いくらやったん?シャレードのシャンパンは誕生日祝いとしてありがたくいただくとして、さすがにその後はもらい過ぎやから、飲み代くらいは払うよ」
「きのうのは全部あたしの奢りやって言ったでしょ?値段なんて聞かなくていいのよ」
「そうはいかないよ。夏美さんが社会見学って言ってたけど、それを知らないとちゃんと社会見学したことにならへんやろ?」
「聞いたら目玉飛び出すかもよ」
「いいから」
萌未は面倒臭い、というようにため息をついた。
「ボトルはおろしてないから5万くらいかな?ワインはなっちゃんが出してくれたけど、3万くらいのやつやったと思う」
夏美さんに聞いてはいたが、やはり目玉が飛び出るくらい高い。
「一応あたしは高級クラブのホステスですからね、そんなもんなのよ。ああいうとこは一瞬でも座ったら5万くらいになるの」
「それ、俺払うよ」
「いい加減にしなさい。奢りって言ってるでしょ?それに、働いてもいないくせにどうやって払うのよ」
萌未は今度は大きくため息を吐き、サイドテーブルに置いてあった煙草を一本咥えて火を点けた。涼平はそんな萌未にしっかりとした視線を送りながら、毅然とした口調で言った。
「俺、黒服になる」
1
お気に入りに追加
11
あなたにおすすめの小説

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

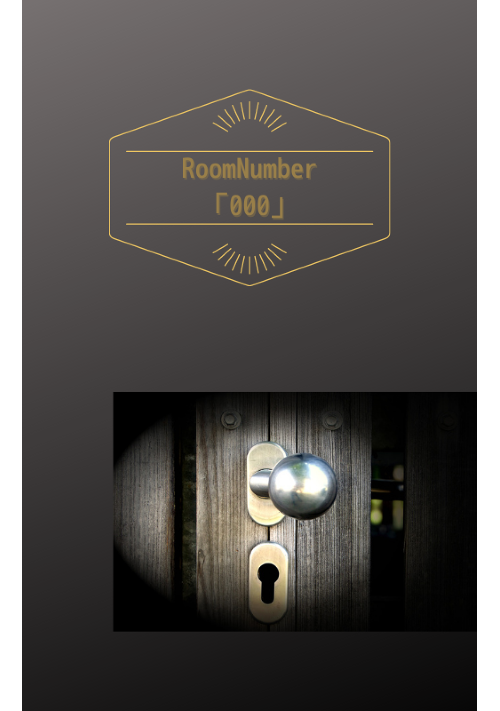
RoomNunmber「000」
誠奈
ミステリー
ある日突然届いた一通のメール。
そこには、報酬を与える代わりに、ある人物を誘拐するよう書かれていて……
丁度金に困っていた翔真は、訝しみつつも依頼を受け入れ、幼馴染の智樹を誘い、実行に移す……が、そこである事件に巻き込まれてしまう。
二人は密室となった部屋から出ることは出来るのだろうか?
※この作品は、以前別サイトにて公開していた物を、作者名及び、登場人物の名称等加筆修正を加えた上で公開しております。
※BL要素かなり薄いですが、匂わせ程度にはありますのでご注意を。

【R-18】クリしつけ
蛙鳴蝉噪
恋愛
男尊女卑な社会で女の子がクリトリスを使って淫らに教育されていく日常の一コマ。クリ責め。クリリード。なんでもありでアブノーマルな内容なので、精神ともに18歳以上でなんでも許せる方のみどうぞ。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















