13 / 127
第1章:東の魔の森編
第13話:君は聖女
しおりを挟む
「実は、君のことは国王に話すべきじゃなかったと後悔していたんだ」
握っていた手を離して、クルトはソファに深く座りなおした。ミヤコも離された手がすっと冷たくなるのを感じながら、ワインを持ち直しクルトの話を聞く体制に入った。
「君と話した後、僕はすぐに国王に面会を求めたんだ。視力が…ほとんど失明しかけていた視力が戻り魔力も戻った。毒素が体から抜けたことが嘘みたいで嬉しくて、聖女の力ですら直せなかったものが治った、と考えもなく言ってしまってね」
はあ、とクルトがため息をついたので、ミヤコも「ああ、それで聖女のプライドを傷つけたんだな」と理解した。
「僕の国の聖女は国王の妃でね。でも、聖女というのは純真無垢で神に仕えなければいけない。国王ですら、その、手を出してはいけないんだ。わかるね?」
「はあ。白い結婚とか言う奴ですね」
「それで、誰かに汚されるよりは王が保護をしたほうがより安全だということでね。その当時王はまだ若く、正妃がいなかったから聖女が正妃ということで落ち着いた。そのあとで、側室として実質の王妃を娶り全ては丸く収まったはずだったんだ」
ああ、これは、ダメな話なんだな。丸く治らなかったということなんでしょう。王様が手を出したか、聖女が乱れたか。
ミヤコはふんふん、と頷いて先を促した。
「しばらくして、実質の王妃だったカサブランカ妃が崩御して、王太子は聖女によって育てられた。その王太子が15歳になった年に、あのバカ…失礼、モンファルト王子が聖女を襲ったんだ」
「ええっ!?」
ナンテコッタイ。義母を襲う子供ってどうなの!?どういう教育をしたの?
「その、貞操は守られたらしいんだけど、それ以来聖女は集中力が欠けたというか、なんかこう守るべきものが変わったというか。とにかく、国のために聖女の力を使うよりも、自分の身を守るために力を使うようになってしまって」
「……まあ。気持ちはわからないでもないですね。」
「この数十年、聖女の瘴気の浄化能力が落ちてきていてね。神官たちも頑張っているんだが、20年ほど前に魔性植物の方が活発になって迷宮が生まれてしまった。その上、王子の聖女暴行未遂事件。それで、僕たちのような討伐隊ができたわけなんだけれど」
「えっ。クルトさん、討伐隊員だったんですか」
討伐隊って、魔物ハンターってやつですよね。危ない仕事なんですよね。あっ体調崩していたのって、もしかしてそのせいだったのかな。
「討伐隊長だった。ビャッカランの毒を受けるまではね。それで隊を脱退したんだ。視力が落ちて魔法も使いこなせなくなったから仕方がない。それから3年ほど、ここで食堂の経営をしながら薬の研究をしていたんだ」
どこか苛立たしく、吐き出すようにクルトは続けた。
「だけど、それはそれでよかったんだ。聖女の力が弱ってからそれまで魔法と彼女の力だけで医療が進んでいて、薬草については忘れ去られていた。薬草を探すのも育てるのも時間がかかるし何より魔性植物の瘴気にかかったら全滅するか魔性植物になるかだったから。でも昔の人は薬草を使っていたし、ポーションも作っていた。
その調合方法を調べるのに何年もかかってしまって。なんとか回復薬は作れるようになったんだけど…解毒剤は無理だった。僕の毒はすでに全身を廻っていたし情報が少なすぎたというのもあるけれど、何せ片目は使えないし、体力もかなり落ちていたからね。本当にもうダメだと思った。ミヤのあの飲み物は本当に僕にとっては奇跡だったんだ」
そこでクルトは顔を上げて、ミヤコを見据えた。
「ミヤの知識は、僕にとってとても大事なことなんだって解ってもらえたかな?」
「はい…まあ。でも聖女は無理ですが」
「時々でもダメか?」
「…あの、聖女って純真無垢じゃないとダメって言いませんでした?」
「うん?」
「えっと、わたし、純真無垢じゃないんで」
「…えっ」
「…えって…ええ、まあ」
「す、すまない。ちょっと不意打ちを食らった」
「ええ?」
「ミヤはその、まだ16かそこらだろう?」
ああ、そうきたか。
異世界人にとっても脅威のアジア人の奥義『見た目若くて年齢不詳』。西洋人でも騙されるアジア人の容貌は異世界人にも通用したのか。
「わたし、25歳です。ついこの間まで、結婚を前提に付き合っていた人がいたんで。処女じゃないんです、あいにく」
クルトは大口を開けたまま、真っ赤になって硬直して何も言わなくなってしまった。暴露してから、恥ずかしくなったミヤコはちょっと不機嫌に顔を赤らめて、横を向いた。
「…相手が二股かけてて。向こうの女の家族が、権力を奮って彼に将来の仕事を斡旋したので、向こうの女と結婚するからってことになって。もういいや、と思ってとっとと実家に帰ってきたんです。あんな節操のない男は、こちらからも願いさげでしたから。ここは祖母の住んでた家で、わたしも昔はここで育ったんですよ。こんな扉があるとは、思いもしませんでしたが」
一気に言ってしまうと、何だかすっきりした気分になったので、ミヤコはもう一口温くなったワインに口をつけた。
「なので、聖女は無理ですよ。でも、食堂のお掃除くらいならお手伝いできますけど?」
ミヤコがそう付け加えると、その機会を逃す手はないと思ったのかクルトは我に返って嬉しそうに目を輝かせた。
「それでは、契約を結ばないか?タダ働きとは言わない。給金…は価値が違うかもしれんな。僕もこちらで手伝えることがあれば手伝うというのはどうかな。僕は精霊と意思の疎通ができる。ミヤのハーブ園の育成を早めたり、加護をつけたりのお願いもできると思う。それで作った例の除菌剤やら洗剤やらを使って、僕の店を掃除してはくれないだろうか。もちろん収穫は僕も手伝おう」
「それは助かります」
ああよかった、とクルトは余程気を張っていたのかどっかりと坐り直し、ぬるいワインを一気に煽った。
まあ、いわゆる掃除婦みたいなものだものね。あの悪臭をなくすためなら別に問題はない様にも思う。なんかよくわからない効果が付いてるけど、健康的にいられるなら、それくらい。
それに収穫に男手があると助かるのは本当だし、もう少しこのイケメンと関われると思うと…。
いいじゃん、それくらい。ねぇ?
「もう少し、ホットワイン飲みますか」
とミヤコが聞けば、にっこり笑って是非と答える。
ミヤコはキッチンに戻って、新たにホットワインを作り、ついでにつまみも、とグリッシーニにスパニッシュハムを巻きつけたものとピクルス、オリーブを持ってきた。
「ミヤにかかると、食べ物は魔法にかかったように美味しくなるな」
クルトは温かいワインを受け取ると、目の前に差し出されたつまみに目をむいた。
ミヤは留学で学んだことや、祖母から学んだことをかいつまんで話し、別れた恋人との経緯も語った。二人とも少し飲みすぎたのかも知れない。ミヤはすっかりくつろいで、舌もよく回った。クルトがウンウンと相槌を打ったり、眉をしかめて意見をしたり、一緒に笑ったりしたのでミヤもついつい話し過ぎてしまった。
その内、クルトもポツリポツリと自分のことを話し始めた。
「僕にも、婚約者がいたんだ。マリゴールドと言ってね、王族の娘だったからちょっと堅苦しいところもあったけど笑顔の可愛いしっかりした人でね。僕と同じ風の使い手だった」
ミヤコは小首を傾げ、頷いた。
「いた」ということは今は「いない」のだろうか。
「僕が毒にやられて、風魔法が使えなくなって…彼女も去っていったよ。僕らみたいな討伐隊員が魔法を使えないのは、無駄に等しいから。役立たずのレッテルを貼られて、彼女を幸せにすることはできなくなった」
「それは…辛かったね」
「それは、まあ……。でも、そのおかげで僕はゆっくり自分を見つめ直すことができた。世界の価値観もこの3年の間に変わったし…何よりも君に会えた」
クルトは揺れるワインを見つめ、フッと笑う。
「王に会いに行った時にさ、しゃしゃり出てきた聖女になんと言われたと思う?毒が抜けてよかったとか、討伐隊の皆は大丈夫かとかそんなことじゃなくてさ。回復したのならさっさと討伐隊に復帰しろ、だったんだよ。その上、討伐が終わったら、マリゴールドとの復縁も考えてやるだってさ」
あはは、とクルトは自笑する。
「クルトさん…」
「マリはもう他の男と結婚して子供もいるのにだよ。神殿にどっかり腰掛けて、聖女らしいこともしないくせに『男はみんな聖女を汚そうとしている』とか被害妄想にかられて表に出てこなくなって、挙句君を連れて来いとか…」
「ふざけるな、ですよねえ」
クルトの表情がだんだん険しくなってくるのを見て、ミヤは宥めようとその先をつなげて言う。思わず握りこぶしにもなってしまった。だが、クルトははっとしてミヤコの顔を見上げ、途端に表情がゆるゆると崩れ、泣きそうな顔で笑う。
「本当に、何度も言うけど。ミヤに出会わなかったら、僕は今生きていなかった。あの日の瘴気できっと…」
だから、とクルトは付け加える。
「ありがとう、ミヤ。君がどう言おうと、僕にとって君は聖女だ」
==========
読んでいただきありがとうございました。
握っていた手を離して、クルトはソファに深く座りなおした。ミヤコも離された手がすっと冷たくなるのを感じながら、ワインを持ち直しクルトの話を聞く体制に入った。
「君と話した後、僕はすぐに国王に面会を求めたんだ。視力が…ほとんど失明しかけていた視力が戻り魔力も戻った。毒素が体から抜けたことが嘘みたいで嬉しくて、聖女の力ですら直せなかったものが治った、と考えもなく言ってしまってね」
はあ、とクルトがため息をついたので、ミヤコも「ああ、それで聖女のプライドを傷つけたんだな」と理解した。
「僕の国の聖女は国王の妃でね。でも、聖女というのは純真無垢で神に仕えなければいけない。国王ですら、その、手を出してはいけないんだ。わかるね?」
「はあ。白い結婚とか言う奴ですね」
「それで、誰かに汚されるよりは王が保護をしたほうがより安全だということでね。その当時王はまだ若く、正妃がいなかったから聖女が正妃ということで落ち着いた。そのあとで、側室として実質の王妃を娶り全ては丸く収まったはずだったんだ」
ああ、これは、ダメな話なんだな。丸く治らなかったということなんでしょう。王様が手を出したか、聖女が乱れたか。
ミヤコはふんふん、と頷いて先を促した。
「しばらくして、実質の王妃だったカサブランカ妃が崩御して、王太子は聖女によって育てられた。その王太子が15歳になった年に、あのバカ…失礼、モンファルト王子が聖女を襲ったんだ」
「ええっ!?」
ナンテコッタイ。義母を襲う子供ってどうなの!?どういう教育をしたの?
「その、貞操は守られたらしいんだけど、それ以来聖女は集中力が欠けたというか、なんかこう守るべきものが変わったというか。とにかく、国のために聖女の力を使うよりも、自分の身を守るために力を使うようになってしまって」
「……まあ。気持ちはわからないでもないですね。」
「この数十年、聖女の瘴気の浄化能力が落ちてきていてね。神官たちも頑張っているんだが、20年ほど前に魔性植物の方が活発になって迷宮が生まれてしまった。その上、王子の聖女暴行未遂事件。それで、僕たちのような討伐隊ができたわけなんだけれど」
「えっ。クルトさん、討伐隊員だったんですか」
討伐隊って、魔物ハンターってやつですよね。危ない仕事なんですよね。あっ体調崩していたのって、もしかしてそのせいだったのかな。
「討伐隊長だった。ビャッカランの毒を受けるまではね。それで隊を脱退したんだ。視力が落ちて魔法も使いこなせなくなったから仕方がない。それから3年ほど、ここで食堂の経営をしながら薬の研究をしていたんだ」
どこか苛立たしく、吐き出すようにクルトは続けた。
「だけど、それはそれでよかったんだ。聖女の力が弱ってからそれまで魔法と彼女の力だけで医療が進んでいて、薬草については忘れ去られていた。薬草を探すのも育てるのも時間がかかるし何より魔性植物の瘴気にかかったら全滅するか魔性植物になるかだったから。でも昔の人は薬草を使っていたし、ポーションも作っていた。
その調合方法を調べるのに何年もかかってしまって。なんとか回復薬は作れるようになったんだけど…解毒剤は無理だった。僕の毒はすでに全身を廻っていたし情報が少なすぎたというのもあるけれど、何せ片目は使えないし、体力もかなり落ちていたからね。本当にもうダメだと思った。ミヤのあの飲み物は本当に僕にとっては奇跡だったんだ」
そこでクルトは顔を上げて、ミヤコを見据えた。
「ミヤの知識は、僕にとってとても大事なことなんだって解ってもらえたかな?」
「はい…まあ。でも聖女は無理ですが」
「時々でもダメか?」
「…あの、聖女って純真無垢じゃないとダメって言いませんでした?」
「うん?」
「えっと、わたし、純真無垢じゃないんで」
「…えっ」
「…えって…ええ、まあ」
「す、すまない。ちょっと不意打ちを食らった」
「ええ?」
「ミヤはその、まだ16かそこらだろう?」
ああ、そうきたか。
異世界人にとっても脅威のアジア人の奥義『見た目若くて年齢不詳』。西洋人でも騙されるアジア人の容貌は異世界人にも通用したのか。
「わたし、25歳です。ついこの間まで、結婚を前提に付き合っていた人がいたんで。処女じゃないんです、あいにく」
クルトは大口を開けたまま、真っ赤になって硬直して何も言わなくなってしまった。暴露してから、恥ずかしくなったミヤコはちょっと不機嫌に顔を赤らめて、横を向いた。
「…相手が二股かけてて。向こうの女の家族が、権力を奮って彼に将来の仕事を斡旋したので、向こうの女と結婚するからってことになって。もういいや、と思ってとっとと実家に帰ってきたんです。あんな節操のない男は、こちらからも願いさげでしたから。ここは祖母の住んでた家で、わたしも昔はここで育ったんですよ。こんな扉があるとは、思いもしませんでしたが」
一気に言ってしまうと、何だかすっきりした気分になったので、ミヤコはもう一口温くなったワインに口をつけた。
「なので、聖女は無理ですよ。でも、食堂のお掃除くらいならお手伝いできますけど?」
ミヤコがそう付け加えると、その機会を逃す手はないと思ったのかクルトは我に返って嬉しそうに目を輝かせた。
「それでは、契約を結ばないか?タダ働きとは言わない。給金…は価値が違うかもしれんな。僕もこちらで手伝えることがあれば手伝うというのはどうかな。僕は精霊と意思の疎通ができる。ミヤのハーブ園の育成を早めたり、加護をつけたりのお願いもできると思う。それで作った例の除菌剤やら洗剤やらを使って、僕の店を掃除してはくれないだろうか。もちろん収穫は僕も手伝おう」
「それは助かります」
ああよかった、とクルトは余程気を張っていたのかどっかりと坐り直し、ぬるいワインを一気に煽った。
まあ、いわゆる掃除婦みたいなものだものね。あの悪臭をなくすためなら別に問題はない様にも思う。なんかよくわからない効果が付いてるけど、健康的にいられるなら、それくらい。
それに収穫に男手があると助かるのは本当だし、もう少しこのイケメンと関われると思うと…。
いいじゃん、それくらい。ねぇ?
「もう少し、ホットワイン飲みますか」
とミヤコが聞けば、にっこり笑って是非と答える。
ミヤコはキッチンに戻って、新たにホットワインを作り、ついでにつまみも、とグリッシーニにスパニッシュハムを巻きつけたものとピクルス、オリーブを持ってきた。
「ミヤにかかると、食べ物は魔法にかかったように美味しくなるな」
クルトは温かいワインを受け取ると、目の前に差し出されたつまみに目をむいた。
ミヤは留学で学んだことや、祖母から学んだことをかいつまんで話し、別れた恋人との経緯も語った。二人とも少し飲みすぎたのかも知れない。ミヤはすっかりくつろいで、舌もよく回った。クルトがウンウンと相槌を打ったり、眉をしかめて意見をしたり、一緒に笑ったりしたのでミヤもついつい話し過ぎてしまった。
その内、クルトもポツリポツリと自分のことを話し始めた。
「僕にも、婚約者がいたんだ。マリゴールドと言ってね、王族の娘だったからちょっと堅苦しいところもあったけど笑顔の可愛いしっかりした人でね。僕と同じ風の使い手だった」
ミヤコは小首を傾げ、頷いた。
「いた」ということは今は「いない」のだろうか。
「僕が毒にやられて、風魔法が使えなくなって…彼女も去っていったよ。僕らみたいな討伐隊員が魔法を使えないのは、無駄に等しいから。役立たずのレッテルを貼られて、彼女を幸せにすることはできなくなった」
「それは…辛かったね」
「それは、まあ……。でも、そのおかげで僕はゆっくり自分を見つめ直すことができた。世界の価値観もこの3年の間に変わったし…何よりも君に会えた」
クルトは揺れるワインを見つめ、フッと笑う。
「王に会いに行った時にさ、しゃしゃり出てきた聖女になんと言われたと思う?毒が抜けてよかったとか、討伐隊の皆は大丈夫かとかそんなことじゃなくてさ。回復したのならさっさと討伐隊に復帰しろ、だったんだよ。その上、討伐が終わったら、マリゴールドとの復縁も考えてやるだってさ」
あはは、とクルトは自笑する。
「クルトさん…」
「マリはもう他の男と結婚して子供もいるのにだよ。神殿にどっかり腰掛けて、聖女らしいこともしないくせに『男はみんな聖女を汚そうとしている』とか被害妄想にかられて表に出てこなくなって、挙句君を連れて来いとか…」
「ふざけるな、ですよねえ」
クルトの表情がだんだん険しくなってくるのを見て、ミヤは宥めようとその先をつなげて言う。思わず握りこぶしにもなってしまった。だが、クルトははっとしてミヤコの顔を見上げ、途端に表情がゆるゆると崩れ、泣きそうな顔で笑う。
「本当に、何度も言うけど。ミヤに出会わなかったら、僕は今生きていなかった。あの日の瘴気できっと…」
だから、とクルトは付け加える。
「ありがとう、ミヤ。君がどう言おうと、僕にとって君は聖女だ」
==========
読んでいただきありがとうございました。
10
お気に入りに追加
858
あなたにおすすめの小説

遺棄令嬢いけしゃあしゃあと幸せになる☆婚約破棄されたけど私は悪くないので侯爵さまに嫁ぎます!
天田れおぽん
ファンタジー
婚約破棄されましたが私は悪くないので反省しません。いけしゃあしゃあと侯爵家に嫁いで幸せになっちゃいます。
魔法省に勤めるトレーシー・ダウジャン伯爵令嬢は、婿養子の父と義母、義妹と暮らしていたが婚約者を義妹に取られた上に家から追い出されてしまう。
でも優秀な彼女は王城に住み、個性的な人たちに囲まれて楽しく仕事に取り組む。
一方、ダウジャン伯爵家にはトレーシーの親戚が乗り込み、父たち家族は追い出されてしまう。
トレーシーは先輩であるアルバス・メイデン侯爵令息と王族から依頼された仕事をしながら仲を深める。
互いの気持ちに気付いた二人は、幸せを手に入れていく。
。oOo。.:♥:.。oOo。.:♥:.。oOo。.:♥:.。oOo。.:♥:.
他サイトにも連載中
2023/09/06 少し修正したバージョンと入れ替えながら更新を再開します。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m

白い結婚を言い渡されたお飾り妻ですが、ダンジョン攻略に励んでいます
時岡継美
ファンタジー
初夜に旦那様から「白い結婚」を言い渡され、お飾り妻としての生活が始まったヴィクトリアのライフワークはなんとダンジョンの攻略だった。
侯爵夫人として最低限の仕事をする傍ら、旦那様にも使用人たちにも内緒でダンジョンのラスボス戦に向けて準備を進めている。
しかし実は旦那様にも何やら秘密があるようで……?
他サイトでは「お飾り妻の趣味はダンジョン攻略です」のタイトルで公開している作品を加筆修正しております。
誤字脱字報告ありがとうございます!

【完結】緑の手を持つ花屋の私と、茶色の手を持つ騎士団長
五城楼スケ(デコスケ)
ファンタジー
〜花が良く育つので「緑の手」だと思っていたら「癒しの手」だったようです〜
王都の隅っこで両親から受け継いだ花屋「ブルーメ」を経営するアンネリーエ。
彼女のお店で売っている花は、色鮮やかで花持ちが良いと評判だ。
自分で花を育て、売っているアンネリーエの店に、ある日イケメンの騎士が現れる。
アンネリーエの作る花束を気に入ったイケメン騎士は、一週間に一度花束を買いに来るようになって──?
どうやらアンネリーエが育てている花は、普通の花と違うらしい。
イケメン騎士が買っていく花束を切っ掛けに、アンネリーエの隠されていた力が明かされる、異世界お仕事ファンタジーです。
*HOTランキング1位、エールに感想有難うございました!とても励みになっています!
※花の名前にルビで解説入れてみました。読みやすくなっていたら良いのですが。(;´Д`)
話の最後にも花の名前の解説を入れてますが、間違ってる可能性大です。
雰囲気を味わってもらえたら嬉しいです。
※完結しました。全41話。
お読みいただいた皆様に感謝です!(人´∀`).☆.。.:*・゚

転生した元悪役令嬢は地味な人生を望んでいる
花見 有
恋愛
前世、悪役令嬢だったカーラはその罪を償う為、処刑され人生を終えた。転生して中流貴族家の令嬢として生まれ変わったカーラは、今度は地味で穏やかな人生を過ごそうと思っているのに、そんなカーラの元に自国の王子、アーロンのお妃候補の話が来てしまった。

雪解けの白い結婚 〜触れることもないし触れないでほしい……からの純愛!?〜
川奈あさ
恋愛
セレンは前世で夫と友人から酷い裏切りを受けたレスられ・不倫サレ妻だった。
前世の深い傷は、転生先の心にも残ったまま。
恋人も友人も一人もいないけれど、大好きな魔法具の開発をしながらそれなりに楽しい仕事人生を送っていたセレンは、祖父のために結婚相手を探すことになる。
だけど凍り付いた表情は、舞踏会で恐れられるだけで……。
そんな時に出会った壁の花仲間かつ高嶺の花でもあるレインに契約結婚を持ちかけられる。
「私は貴女に触れることもないし、私にも触れないでほしい」
レインの条件はひとつ、触らないこと、触ることを求めないこと。
実はレインは女性に触れられると、身体にひどいアレルギー症状が出てしまうのだった。
女性アレルギーのスノープリンス侯爵 × 誰かを愛することが怖いブリザード令嬢。
過去に深い傷を抱えて、人を愛することが怖い。
二人がゆっくり夫婦になっていくお話です。

追放された悪役令嬢はシングルマザー
ララ
恋愛
神様の手違いで死んでしまった主人公。第二の人生を幸せに生きてほしいと言われ転生するも何と転生先は悪役令嬢。
断罪回避に奮闘するも失敗。
国外追放先で国王の子を孕んでいることに気がつく。
この子は私の子よ!守ってみせるわ。
1人、子を育てる決心をする。
そんな彼女を暖かく見守る人たち。彼女を愛するもの。
さまざまな思惑が蠢く中彼女の掴み取る未来はいかに‥‥
ーーーー
完結確約 9話完結です。
短編のくくりですが10000字ちょっとで少し短いです。

旦那様、前世の記憶を取り戻したので離縁させて頂きます
結城芙由奈@コミカライズ発売中
恋愛
【前世の記憶が戻ったので、貴方はもう用済みです】
ある日突然私は前世の記憶を取り戻し、今自分が置かれている結婚生活がとても理不尽な事に気が付いた。こんな夫ならもういらない。前世の知識を活用すれば、この世界でもきっと女1人で生きていけるはず。そして私はクズ夫に離婚届を突きつけた―。
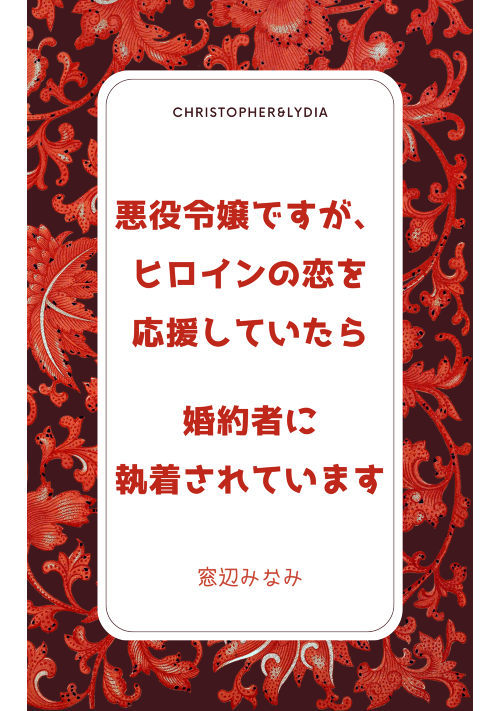
悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています
窓辺ミナミ
ファンタジー
悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。
シナリオ通りなら、死ぬ運命。
だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!
騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!
というわけで、私、悪役やりません!
来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。
あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!
気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。
悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















