26 / 30
A「私こそが狩人」
第25話 狩人の愉悦
しおりを挟む
赤ずきんはきっと自らの血液を頭から被り、それを「猫下誠人(ねこもとまこと)」という人間に化ける為のガワにしていたのだろう。被っていたガワと、警官の制服がドロりと溶けた。そして露わとなるのは、赤いケープを被った少女だ。
見開かれた双色の双眸も、脱ぎ捨てたガワから漂う甘ったるい血液の匂いも。その全てが、幼い華怜(かれん)の記憶に刻み込まれたものと一致した。
唯一違うのは声音だが、それは彼女が独学で会得した変声術なのだろう。喉の辺りを弄れば、聞き覚えのある笑い声が聞こえてきた。
「クスクス……なぁんで、バレちゃったのかなぁ」
一〇年だ。それだけの月日を経て、大上(おおがみ)華怜はようやく自らの宿敵と再会を果たすことになった。
「久しぶりだね、獲物のお嬢ちゃん。ううん、今はもうお姉ちゃんか」
「馴れ馴れしく話しかけないでよ、反吐が出る」
「クスクス。クスクス。一〇年前のあの夜、私に殴りかかってきた時と変わらないね。……けど、やっぱり解せないなぁ。確かに君の持っている情報があれば、赤ずきんは誰かに化けて、警視庁のデータベースを弄ってたって仮説までは立てられると思う。だけど、そこから『猫下誠人=私』ってまでは気づけないと思うの」
「そうね、少なくとも出頭する前までは貴女が誰に化けてるかなんて皆目検討も付かなかった。……だけど、今思い返してみれば、かぐや姫の言動から変だったのよ」
「かぐや姫……? それって『デストロイヤー・かぐちゃん』のこと?」
彼女は仲間内でそんな風に呼ばれていたのか。
それはさておき、彼女は殺害対象の優先度をレッドフード→自分の順にしていた。これが赤ずきんの要望だったなら、この時点で違和感を持つべきだったのだ。
華怜とレッドフードが二人並んでいた場合、本来赤ずきんが真っ先に消しておきたいと思うのは、互いに殺し合う関係にある自らの片割れなのだから。さらに言えば、この段階で赤ずきんから見た自分は、レッドフードと共謀関係にある一人の警察官でしかない。わざわざ殺す価値もないモブに過ぎないのだ。
「それでも尚、貴女にはレッドフードより私を殺したいと思う動機があった」
赤ずきんは猫下誠人に化けて、警視庁のデータベースを幾度と弄ってきた。恐らくはその際に誤操作か何かで、自分のプロフィールを開いてしまったのだろう。
そして、彼女は確信したのだ。少しばかり成長しているが、この「大上華怜」という警察官は、一〇年前に自分が殺したはずの少女ではないかと。
「私もちょっと考えてみたの。────狩人を気取る貴女が、殺したはずの獲物が生きていると知った時、どんなリアクションを見せるかを」
往生際をわきまえない獲物に腹を立てるだろうか? それとも自らの詰めの甘さを悔しがるだろうか?
いいや、違う。狩人気取りの彼女はきっと、こう考えたはずだ。
「貴女はきっと嬉しかったんでしょ? あの夜の続きができるから。もう一度、狩人VS獲物のハンティングゲームを楽しめるって、」
彼女のハンティングスタイルは、単に後ろからマスケット銃をぶっ放すだけじゃない。時には敢えて弾丸を外し、ある程度までは獲物を泳がせる。きっと、その過程に見られる足掻きやドラマ性を楽しんでいたのだろう。
だから、大上華怜=一〇年前の少女と悟っても、ある程度は泳がせることにした。警視庁特務課・幻想人(フェアリスト)対策班に所属する華怜が復讐のために牙を研ぎ、どのように自分に迫ってくるかの駆け引きを楽しみたかったから。
きっと、かぐや姫を刺客として送り込んだのも、彼女にとっては猟犬に獲物を追わせる程度の感覚だったのだろう。追い立てられ、危機に陥った獲物がどんな反応を見せるか観察するのも、狩人にとっては一つの娯楽なのだから。
幻想人「赤ずきん」の裏。────この世界に生まれ落ちた彼女が見出した答えは「自らこそが狩人」であると定義するもの。そのアイデンティティに従うのであれば、一度狩り損ねた獲物を無視することなんてもうできない。
それ故に、彼女は「大上華怜」へ異様な執着を抱いたのだ。
「じゃあ、そんな貴女の獲物が、何かを企んでるってバレバレのまま出頭してきたのならどうするか? 貴女が狩人を気取るなら、私を無視することなんてできないはずよ」
「クスクス。クスクス。じゃあ、君がワザと捕まったのは、警察内部に潜んだ私を探し出す為なんかじゃなくて、自分自身をエサに私を誘き出すためだったんだね」
そして案の定、彼女は華恋の前に現れた。仮初のガワを被り、事情聴取という大義名分を立てたところまでは良かっただろう。
だが、警察官には「二人一組で行動する」という原則がある。それに取り調べの場では、容疑者と警察官の間でどんなやり取りが交わされたか、必ず記録係を一人立てなければならない。
にも、関わらず猫下誠人は一人だったのだ。
「つまりね、貴女は最後の最後で私の罠にハマるだけでは飽き足らず、凡ミスをやらかしたのよッ!」
華怜は積年の憎悪を乗せて、舌先を「べぇ」と突き出してやった。
だが、赤ずきんも憎たらしい笑い方を止めようとしない。
「クスクス。……確かに詰めが甘いのは私のクセなのかもね。現に一〇年前も、お嬢ちゃんを仕留め損ねたわけだし。……けど、なんでだろう? 全っ然、腹が立たないんだ! それどころか、ちょっと嬉しいかも! 狩人である私のことを、こんなに理解してくれる人なんて、今まで一人もいなかったから!」
「私は、貴女のことなんて、理解したくもなかったわよッ!」
狂人の真似とて大路を走らば即ち狂人なり、という。
赤ずきんの思考をここまで深く理解できるのは、華怜の思考が少しずつ彼女に似てきた為か。
これはきっと、危うい兆候なのだろう。だが、赤ずきんの思考をトレースしたからこそ、次に彼女が何をするかが手に取るように分かってしまった。
「さぁ! あの夜の続きをしましょう!!」
赤ずきんが手にかけたウィッカーバケットから、愛銃たるマスケットを引き抜くと同時。華怜はその鋒を掴み、強引に銃身を逸らしてみせた。
「何があの夜の続きよ、ふざけるなッ!」
さらに、彼女の顔面に膝蹴りを叩き込む。
「そもそも貴女は狩人に向いないのよ。微塵も堪え性がないんだから」
それは華怜が思いつける最大限の皮肉だった。
「堪え性か……確かに、それも狩人には必須技能だね。教えてくれてありがとう、お姉さん! 貴女のおかげで明日の私は、もっと完璧な狩人になれる。凡ミスも詰めの甘さもない、理想の狩人にねッ!」
「このイカれっぷり……どおりでレッドフードも貴女と同列扱いされるのを嫌がったわけね」
彼女の血液が仕込まれた弾丸は、思うがままに軌道が変わる。だから銃身を逸らされていようと、お構いなしに引き金を引いた。
銃声と共に、赤い軌跡の弧が描かれて。華怜は仄かに香る血液の香りから、咄嗟に義手である右側を盾にするも、簡単に弾かれてしまった。
頭から病室の壁に突っ込んで、義肢が纏っていたホログラムも剥離してしまう。
「ッ……⁉」
「わぁ、何それ⁉ 機械の腕⁉」
思い返されるのは一〇年前。────華怜は赤ずきんの凶弾を三発も受けて、一度事切れてしまった。
だが、奇跡か。それとも神のイタズラか。搬送された先の病院で、息を吹き返したのだ。
「……各部偽装ホログラム、並びにリミッターを解除」
初めは、自分だけが生き残った運命を呪った。
両親の後を追おうとしたことだって、一度や二度じゃない。
「……神経接続デバイスを省略」
だが、華怜は知ってしまった。
この社会には自分と同じような「理不尽」を被った被害者や遺族が、山程いることを。
そして、誰もが持ち合わせた当然の権利を、己の快楽や愉悦の為に踏み躙る、獣以下の害獣たちがいることを。
「……痛覚シャットダウン」
この鋼と電子部品から成る身体は、そんな被害者や遺族に代わって、害獣を屠る為に手に入れたものだ。戦い、自らが正義の礎になる覚悟だって、富田(とんだ)重工の実験台になるとサインした時点で、もうとっくに済ませてある。
華怜は機械仕掛けの拳を握り締め、今一度立ち上がった。
それに私情だってある─────百千桃佳とレッドフード。この短期間の逃亡生活で出来た素敵な友達に報いるためには、今ここで赤ずきんに拳を叩き込むしかないのだろう。
「何が、明日の私は完璧な狩人になれる、だ? 勘違いしないでよ。貴女はここで終わる。今、ここでねッ!」
見開かれた双色の双眸も、脱ぎ捨てたガワから漂う甘ったるい血液の匂いも。その全てが、幼い華怜(かれん)の記憶に刻み込まれたものと一致した。
唯一違うのは声音だが、それは彼女が独学で会得した変声術なのだろう。喉の辺りを弄れば、聞き覚えのある笑い声が聞こえてきた。
「クスクス……なぁんで、バレちゃったのかなぁ」
一〇年だ。それだけの月日を経て、大上(おおがみ)華怜はようやく自らの宿敵と再会を果たすことになった。
「久しぶりだね、獲物のお嬢ちゃん。ううん、今はもうお姉ちゃんか」
「馴れ馴れしく話しかけないでよ、反吐が出る」
「クスクス。クスクス。一〇年前のあの夜、私に殴りかかってきた時と変わらないね。……けど、やっぱり解せないなぁ。確かに君の持っている情報があれば、赤ずきんは誰かに化けて、警視庁のデータベースを弄ってたって仮説までは立てられると思う。だけど、そこから『猫下誠人=私』ってまでは気づけないと思うの」
「そうね、少なくとも出頭する前までは貴女が誰に化けてるかなんて皆目検討も付かなかった。……だけど、今思い返してみれば、かぐや姫の言動から変だったのよ」
「かぐや姫……? それって『デストロイヤー・かぐちゃん』のこと?」
彼女は仲間内でそんな風に呼ばれていたのか。
それはさておき、彼女は殺害対象の優先度をレッドフード→自分の順にしていた。これが赤ずきんの要望だったなら、この時点で違和感を持つべきだったのだ。
華怜とレッドフードが二人並んでいた場合、本来赤ずきんが真っ先に消しておきたいと思うのは、互いに殺し合う関係にある自らの片割れなのだから。さらに言えば、この段階で赤ずきんから見た自分は、レッドフードと共謀関係にある一人の警察官でしかない。わざわざ殺す価値もないモブに過ぎないのだ。
「それでも尚、貴女にはレッドフードより私を殺したいと思う動機があった」
赤ずきんは猫下誠人に化けて、警視庁のデータベースを幾度と弄ってきた。恐らくはその際に誤操作か何かで、自分のプロフィールを開いてしまったのだろう。
そして、彼女は確信したのだ。少しばかり成長しているが、この「大上華怜」という警察官は、一〇年前に自分が殺したはずの少女ではないかと。
「私もちょっと考えてみたの。────狩人を気取る貴女が、殺したはずの獲物が生きていると知った時、どんなリアクションを見せるかを」
往生際をわきまえない獲物に腹を立てるだろうか? それとも自らの詰めの甘さを悔しがるだろうか?
いいや、違う。狩人気取りの彼女はきっと、こう考えたはずだ。
「貴女はきっと嬉しかったんでしょ? あの夜の続きができるから。もう一度、狩人VS獲物のハンティングゲームを楽しめるって、」
彼女のハンティングスタイルは、単に後ろからマスケット銃をぶっ放すだけじゃない。時には敢えて弾丸を外し、ある程度までは獲物を泳がせる。きっと、その過程に見られる足掻きやドラマ性を楽しんでいたのだろう。
だから、大上華怜=一〇年前の少女と悟っても、ある程度は泳がせることにした。警視庁特務課・幻想人(フェアリスト)対策班に所属する華怜が復讐のために牙を研ぎ、どのように自分に迫ってくるかの駆け引きを楽しみたかったから。
きっと、かぐや姫を刺客として送り込んだのも、彼女にとっては猟犬に獲物を追わせる程度の感覚だったのだろう。追い立てられ、危機に陥った獲物がどんな反応を見せるか観察するのも、狩人にとっては一つの娯楽なのだから。
幻想人「赤ずきん」の裏。────この世界に生まれ落ちた彼女が見出した答えは「自らこそが狩人」であると定義するもの。そのアイデンティティに従うのであれば、一度狩り損ねた獲物を無視することなんてもうできない。
それ故に、彼女は「大上華怜」へ異様な執着を抱いたのだ。
「じゃあ、そんな貴女の獲物が、何かを企んでるってバレバレのまま出頭してきたのならどうするか? 貴女が狩人を気取るなら、私を無視することなんてできないはずよ」
「クスクス。クスクス。じゃあ、君がワザと捕まったのは、警察内部に潜んだ私を探し出す為なんかじゃなくて、自分自身をエサに私を誘き出すためだったんだね」
そして案の定、彼女は華恋の前に現れた。仮初のガワを被り、事情聴取という大義名分を立てたところまでは良かっただろう。
だが、警察官には「二人一組で行動する」という原則がある。それに取り調べの場では、容疑者と警察官の間でどんなやり取りが交わされたか、必ず記録係を一人立てなければならない。
にも、関わらず猫下誠人は一人だったのだ。
「つまりね、貴女は最後の最後で私の罠にハマるだけでは飽き足らず、凡ミスをやらかしたのよッ!」
華怜は積年の憎悪を乗せて、舌先を「べぇ」と突き出してやった。
だが、赤ずきんも憎たらしい笑い方を止めようとしない。
「クスクス。……確かに詰めが甘いのは私のクセなのかもね。現に一〇年前も、お嬢ちゃんを仕留め損ねたわけだし。……けど、なんでだろう? 全っ然、腹が立たないんだ! それどころか、ちょっと嬉しいかも! 狩人である私のことを、こんなに理解してくれる人なんて、今まで一人もいなかったから!」
「私は、貴女のことなんて、理解したくもなかったわよッ!」
狂人の真似とて大路を走らば即ち狂人なり、という。
赤ずきんの思考をここまで深く理解できるのは、華怜の思考が少しずつ彼女に似てきた為か。
これはきっと、危うい兆候なのだろう。だが、赤ずきんの思考をトレースしたからこそ、次に彼女が何をするかが手に取るように分かってしまった。
「さぁ! あの夜の続きをしましょう!!」
赤ずきんが手にかけたウィッカーバケットから、愛銃たるマスケットを引き抜くと同時。華怜はその鋒を掴み、強引に銃身を逸らしてみせた。
「何があの夜の続きよ、ふざけるなッ!」
さらに、彼女の顔面に膝蹴りを叩き込む。
「そもそも貴女は狩人に向いないのよ。微塵も堪え性がないんだから」
それは華怜が思いつける最大限の皮肉だった。
「堪え性か……確かに、それも狩人には必須技能だね。教えてくれてありがとう、お姉さん! 貴女のおかげで明日の私は、もっと完璧な狩人になれる。凡ミスも詰めの甘さもない、理想の狩人にねッ!」
「このイカれっぷり……どおりでレッドフードも貴女と同列扱いされるのを嫌がったわけね」
彼女の血液が仕込まれた弾丸は、思うがままに軌道が変わる。だから銃身を逸らされていようと、お構いなしに引き金を引いた。
銃声と共に、赤い軌跡の弧が描かれて。華怜は仄かに香る血液の香りから、咄嗟に義手である右側を盾にするも、簡単に弾かれてしまった。
頭から病室の壁に突っ込んで、義肢が纏っていたホログラムも剥離してしまう。
「ッ……⁉」
「わぁ、何それ⁉ 機械の腕⁉」
思い返されるのは一〇年前。────華怜は赤ずきんの凶弾を三発も受けて、一度事切れてしまった。
だが、奇跡か。それとも神のイタズラか。搬送された先の病院で、息を吹き返したのだ。
「……各部偽装ホログラム、並びにリミッターを解除」
初めは、自分だけが生き残った運命を呪った。
両親の後を追おうとしたことだって、一度や二度じゃない。
「……神経接続デバイスを省略」
だが、華怜は知ってしまった。
この社会には自分と同じような「理不尽」を被った被害者や遺族が、山程いることを。
そして、誰もが持ち合わせた当然の権利を、己の快楽や愉悦の為に踏み躙る、獣以下の害獣たちがいることを。
「……痛覚シャットダウン」
この鋼と電子部品から成る身体は、そんな被害者や遺族に代わって、害獣を屠る為に手に入れたものだ。戦い、自らが正義の礎になる覚悟だって、富田(とんだ)重工の実験台になるとサインした時点で、もうとっくに済ませてある。
華怜は機械仕掛けの拳を握り締め、今一度立ち上がった。
それに私情だってある─────百千桃佳とレッドフード。この短期間の逃亡生活で出来た素敵な友達に報いるためには、今ここで赤ずきんに拳を叩き込むしかないのだろう。
「何が、明日の私は完璧な狩人になれる、だ? 勘違いしないでよ。貴女はここで終わる。今、ここでねッ!」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

The Outer Myth :Ⅰ ~目覚めの少女と嘆きの神~
とちのとき
SF
少女達が紡ぐのは、絆と神話の続き・・・。
主人公の女子高生、豊受イナホ。彼女は神々と人々が当たり前のように共存する地、秋津国で平凡な生活を送っていた。しかし、そこでは未知なる危険生物・クバンダにより平和が蝕まれつつあった。何の取り柄もない彼女はある事件をきっかけに母の秘密を探る事になり、調査を進めるうち運命の渦へと巻き込まれていく。その最中、ニホンからあらゆる漂流物が流れ着く摩訶不思議な池、霞み池に、記憶を失った人型AGI(汎用人工知能)の少女ツグミが漂着する。彼女との出会いが少年少女達を更なる冒険へと導くのだった。
【アウターミス パート1~目覚めの少女と嘆きの神~】は、近未来和風SFファンタジー・完結保証・挿絵有(生成AI使用無し)・各章間にパロディ漫画付き☆不定期更新なのでお気に入り登録推奨
【作者より】
他サイトで投稿していたフルリメイクになります。イラスト製作と並行して更新しますので、不定期且つノロノロになるかと。完全版が読めるのはアルファポリスだけ!
本作アウターミスは三部作予定です。現在第二部のプロットも進行中。乞うご期待下さい!
過去に本作をイメージしたBGMも作りました。ブラウザ閲覧の方は目次下部のリンクから。アプリの方はYouTube内で「とちのとき アウターミス」と検索。で、視聴できます

私はお母様の奴隷じゃありません。「出てけ」とおっしゃるなら、望み通り出ていきます【完結】
小平ニコ
ファンタジー
主人公レベッカは、幼いころから母親に冷たく当たられ、家庭内の雑務を全て押し付けられてきた。
他の姉妹たちとは明らかに違う、奴隷のような扱いを受けても、いつか母親が自分を愛してくれると信じ、出来得る限りの努力を続けてきたレベッカだったが、16歳の誕生日に突然、公爵の館に奉公に行けと命じられる。
それは『家を出て行け』と言われているのと同じであり、レベッカはショックを受ける。しかし、奉公先の人々は皆優しく、主であるハーヴィン公爵はとても美しい人で、レベッカは彼にとても気に入られる。
友達もでき、忙しいながらも幸せな毎日を送るレベッカ。そんなある日のこと、妹のキャリーがいきなり公爵の館を訪れた。……キャリーは、レベッカに支払われた給料を回収しに来たのだ。
レベッカは、金銭に対する執着などなかったが、あまりにも身勝手で悪辣なキャリーに怒り、彼女を追い返す。それをきっかけに、公爵家の人々も巻き込む形で、レベッカと実家の姉妹たちは争うことになる。
そして、姉妹たちがそれぞれ悪行の報いを受けた後。
レベッカはとうとう、母親と直接対峙するのだった……

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

女子高生は卒業間近の先輩に告白する。全裸で。
矢木羽研
恋愛
図書委員の女子高生(小柄ちっぱい眼鏡)が、卒業間近の先輩男子に告白します。全裸で。
女の子が裸になるだけの話。それ以上の行為はありません。
取って付けたようなバレンタインネタあり。
カクヨムでも同内容で公開しています。

Dマシンドール 迷宮王の遺産を受け継ぐ少女
草乃葉オウル
ファンタジー
世界中にダンジョンと呼ばれる異空間が現れてから三十年。人類はダンジョンの脅威に立ち向かうため、脳波による遠隔操作が可能な人型異空間探査機『ダンジョン・マシンドール』を開発した。これにより生身では危険かつ非効率的だったダンジョンの探査は劇的に進み、社会はダンジョンから得られる未知の物質と技術によってさらなる発展を遂げていた。
そんな中、ダンジョンともマシンとも無関係な日々を送っていた高校生・萌葱蒔苗《もえぎまきな》は、突然存在すら知らなかった祖父の葬儀に呼ばれ、1機のマシンを相続することになる。しかも、その祖父はマシンドール開発の第一人者にして『迷宮王』と呼ばれる現代の偉人だった。
なぜ両親は祖父の存在を教えてくれなかったのか、なぜ祖父は会ったこともない自分にマシンを遺したのか……それはわからない。でも、マシンを得たならやるべきことは1つ。ダンジョンに挑み、モンスターを倒し、手に入れた素材でマシンをカスタム! そして最強の自分専用機を造り上げる! それが人を、世界を救うことに繋がっていくことを、蒔苗はまだ知らない。
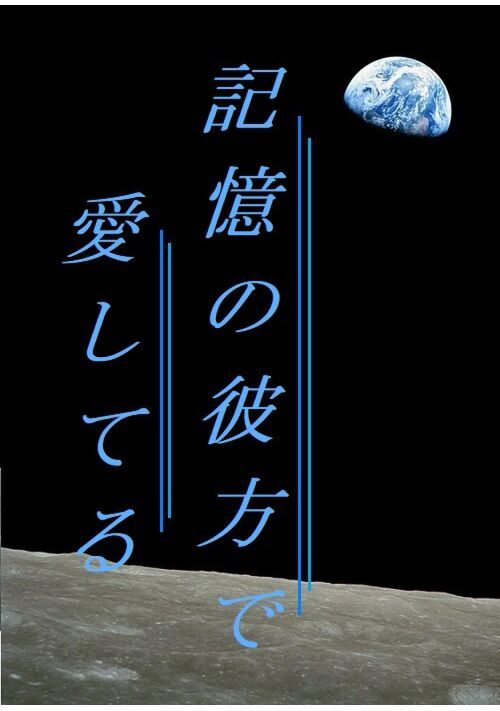
記憶の彼方で愛してる
志賀雅基
SF
◆いつからか/僕の中に誰かいる//温もりの残滓/俺は失くしちゃいないのに◆
〔ディアプラスBL小説大賞第三次選考通過作〕[全11話]
所轄署の刑事課強行犯係の刑事である真由機が朝起きると見知らぬ女性と寝ていた。何処で拾ったのか知れぬ女性が目覚めて喋るとじつは男。毛布の下を見てもやはり男。愕然としつつ出勤すると45ACP弾で射殺された男性発見の報が入る。アパートに戻っても謎な男は居座っていたが、そいつの持ち物と思しき45ACP弾使用拳銃をマユキは発見してしまい当然の疑いが芽生えた。
▼▼▼
【シリーズ中、何処からでもどうぞ】
【全性別対応/BL特有シーンはストーリーに支障なく回避可能です】
【エブリスタ・ノベルアップ+に掲載】

【R18】闇堕ちバレリーナ~悲鳴は届かない~
月島れいわ
恋愛
憧れのバレエ団の入団テストに合格した玲於奈。
大学もあと一年というところで退学を決めた。
かつてのようなお嬢様ではいられなくなった。
それでも前途は明るいはずだったのにーーーー想像もしなかった官能レッスンが待っていた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















