25 / 30
A「私こそが狩人」
第24話 チェイスゲームの終わりに
しおりを挟む
大上華怜(おおがみかれん)は、院内に設けられた特別監視病室に囚われていた。
白一色の内装は心身が落ち着く一方で、どこか閉塞感を感じてしまう。窓には格子が嵌め込まれ、唯一の脱出路とも言えるドアの向こうには、きっと見張りの警官達が控えているのだろう。
そして、ベッドで横になった華怜の真横。備え付けの椅子に腰掛けた青年が、聴取内容を手持ちの端末にまとめていた。
「まさか、幻想人(フェアリスト)には表と裏の二人がいただなんて⁉ 流石のスーパーエリートである僕もビックリですよ⁉」
猫下誠人(ねこもとまこと)巡査。初めにそう名乗った彼は、声と口調から察するに、自分と刃を交えた〈ウルフパック〉のドライバーで間違えないのだろう。
「あのさ……その妙に芝居がかった喋り方って、同僚からウザがられない?」
「んー、特にそういうことを言われた覚えはありませんね。それに今は取り調べの最中ですので、大上〝元〟巡査部長は、僕に聞かれたことだけを答えてくれれば良いんですよ」
悪意のない顔で。それでも「元」というフレーズを強調してくるのは、ナチュラルに彼の性格が悪いからだろう。
それを薄々察しながらも、華怜は問われた内容に答え続けた。
幻想人には表と裏が存在すること。赤ずきんの裏を追い詰める為、レッドフードに共謀を持ちかけられ、乗じたこと。
そういう「知られても構わない内容」は淡々に答えてやるが、幾つかの「知られては不味い内容」は嘘で対応する。
「レッドフードは今どうしてるのか?」なんて質問、もってのほかだ。
「さぁ? 下水道の中ではぐれて、それっきりだから。私も彼女の行方を知らないの」
「はぁ……貴女はそんな下手な嘘で、このスーパーエリートを騙せると思っているのでしょうか?」
勿論、思ってなどいない。だからこそ、両者の間には険悪な空気が流れるのだろう。
「まっ、それはおいおい調べれば良いでしょう。……だけど、やっぱり分からないですね。大上さん、貴女はどうして自ら出頭することを選んだんですか?」
猫下は眉間の辺りを摘みながら、考えている素振りを見せた。
「逃げるのが疲れたとか、良心の呵責に耐えきれなくなったとか。そんなベタな理由で自分から捕まりに来たわけでもないでしょう。だって貴女の眼は今もギラついているんだから。まるで、目標を定めた獣みたくね」
お前は、一体何を企んでいる? ────薄っすらと開かれた彼の瞳の奥は、そう言いたげだった。
目標を定めた眼をしているのはお互い様だ。
「けど、そうね……コレは別に話しても構わない内容か」
華怜がわざわざ出頭することを選んだ理由。それは「ある可能性」に気づいてしまったことに起因する。
「幻想人『赤ずきん』の裏。彼女だけが今日まで誰にも捕まらなかったのは、どうしてだと思う?」
警察は一〇年間、赤ずきんを捕えることが出来なかった。それどころかここ数年は、彼女に纏わる目撃証言や情報提供がピタリと途絶えているのが現状だ。
では、果たしてそんなことが本当にあり得るのだろうか?
街中には監視カメラと、幻想人が発する信号に反応するスキャナーが無数に設置されている。レッドフードは百千桃佳(ももちちももか)に協力を仰ぐことで、それら機器に捕捉されることを避けてはいたが、そんな彼女でさえ手配書の顔を覚えていたタクシードライバーに通報されてしまった。
「レッドフードはあれでも、かなり頭のキレる幻想人だ。外出だって必要最低限に済ませるし、普段はアジトにずっと潜伏している。だけど、赤ずきんの裏は違うの。彼女は今でも不定期に快楽的な殺人を楽しんでは、己が狩人であることに酔いしれている」
それは無論、レッドフード以上に捕まるリスクを高めてしまうような愚行でもある。なのに、どうして赤ずきんに纏わる情報だけが不自然に途絶えてしまったのか?
「初めは彼女にも、百千さんみたいな異能を有した幻想人か、監視カメラを誤魔化せる幻想人が味方にいるって考えたの。だけど、彼女達が結成したコミュニティの名簿リストを見る限り、そんな都合のいい味方はいなかった」
つまり、赤ずきんが自分に纏わる情報を全て抹消するなど、本来は不可能であるはずなのだ。
行動を起こしたからには、必ず何かしらの痕跡が残ってしまう。この鉄則に例外はない。
「だけど、たった一つだけ裏技があるの。凄くシンプルな方法なのに、それを成功させるだけで、誰も彼女に追いつけなくなる裏技がね」
それは裏技中の裏技。ミステリーならば禁じ手だった。
「────幻想人の異能や情報をまとめた警視庁のデータベース。そこに記された情報を削除・改竄してしまえばいいのよ」
幻想人が捕まってしまう最大の要因は、自らが発してしまう固有の信号だ。だが、固有の信号であるからこそ、データベースの登録情報は改竄されてしまえば、スキャナーはもう二度と二人の赤ずきんを捕捉できなくなってしまう。
下水道に逃げ延びた際、〈ウルフパック〉のセンサーがレッドフードを捕捉できなかったのも、それが要因であり、同時に華怜がこの裏技に気づくキッカケでもあった。
「なるほど、前提条件の変更ですか……確かにそれっぽい仮説ですが、ちょっと無理がありません? 幻想人が、警視庁のデータベースを遠隔でクラックできると思いませんし。直接改竄しようにも、それこそ厳重なセキュリティの中に飛び込む自殺行為なんじゃ」
猫下の指摘はもっともだ。常識的に考えれば、ただの幻想人が警視庁内部に潜り込み、データベースを改竄できるわけがない。道中で誰かに見つかり、包囲されるのが精々のオチだろう。
当然、華怜もその反論は予測している。
「赤ずきんが有した本来の異能は「血液操作」ではなく、「赤いものを思うがままに操れる」というもの。これが本当に厄介でね、元が赤いものであれば、その色彩や触感まで自由に弄ることができるの」
赤い血液を弾丸に仕込めば、軌道を遠隔で操ることが出来ることも。ワイヤー状に引き伸ばせば、ビル間を渡り歩くことができることも。果ては、赤いというだけのパトランプを無条件で起爆させることさえ出来る。
彼女らが有した異能の万能性は、既にレッドフードが飽きるほど見せてくれた。
では、真っ赤に染めた袋などを頭から被ったとして。その色彩や材質を操作することで、他人のガワを装うことは出来ないだろうか?
「要はハリウッドの特殊メイクみたいなものよ。異能を用いて、他者に化ける為のマスクを自作するの」
これに関しては出頭する以前に、レッドフードに可能かを試してもらった。適当に拾ってきたビニール袋を血液で着色し、彼女に被らせる。そして、自分に化けるよう頼んでみたのだ。
結果、完成したマスクは華怜の顔とは似ても似つかない物だった。目鼻のバランスが特に酷く、ハロウィン用のコスプレと言われた方がまだ信じられる。
ただ、肌の質感や髪の滑らかさなどの一要素ごとに着目すれば、自身のものと見分けがつかない程の再現度を誇っていたのも事実だ。
きっと、ここからは練度の問題なのだろう。練習を繰り返せば、レッドフードだってそれなりの変装用マスクを作ることが出来ると確信できた。
「じゃあ、まさかですよ……幻想人『赤ずきん』の裏は、自らの異能で警察内部の誰かに化けて、データベースを堂々と弄ってたってことですか⁉」
「私の仮説が正しければ、そうなるはず」
「で、では……大上さん! 貴女がわざわざ出頭してまで警察内部に戻ってきた理由は、」
警察という群れの中に、赤ずきんという異分子が紛れ込んでいる。その可能性に気づいたからこそ、華怜は一度離反した組織に戻ってきたのだ。今度こそ尻尾を掴み、その喉元に牙を突き立てるために────
「よいしょっと!」
もう傷は十分に癒えた。数日ぶりの柔らかなベッドには名残惜しさも感じたが、それでも華怜は勢いよく上体を起こした。
「と言うわけだから、そこを退いてくれない? 猫下巡査」
だからと言って、警察官である彼が「はいどうぞ」と道を譲ってくれるわけもない。
だが、華怜が拳を固めると同時、猫下の取ったリアクションは意外なものであった。
「あっはは! まさか、まさかの展開ですよ。これはスーパーエリートの僕でさえ、予想がつかなかったなぁ!」
彼は楽し気に笑うも、それはすぐに終わってしまう。
開いているか、閉じているのか曖昧な瞳をさらに細めて、彼はポツリと言葉を漏らした。
「ねぇ、大上さん。僕がどうして警察官になったか知ってます?」
「いや、知らないわよ……私たちって、殆ど初対面みたいなものだし……」
「あはは、そう言えば、そうですよね。けど、僕らって意外と似たもの同士だと思うんですよ。だって、僕が警察官になった動機も貴方と同じ、復讐なんですから」
曰く、猫下は幼かった妹を赤ずきんに殺されてしまったらしい。
「それって本当の話?」
「本当ですよ。それに大上さんの仮説が正しければ、僕の妹の仇が、この組織内の誰かに化けていることになる。警視総監かな? それとも警視庁長かな? もしかして、意外な人物……辰巳(たつみ)警部だったり!」
「……さぁ、どうかしらね」
「とにかくですよ。察するに大上さんは、赤ずきんが警察内部の誰に化けているかまでは掴めていない。だから出頭してまで、それが誰かを暴こうとした。────でしたら、僕と共謀しませんか? ターゲットは同じ。それに警察官である僕のアシストがあれば、貴女はより確実に誰が赤ずきんかを暴くことができる。ねっ、悪くない条件でしょ」
猫下は手を差し出してきた。握手を求めているのだ。
「…………」
こんな展開にデジャヴを感じてしまうのは、以前にもレッドフードから似たような誘いを受けてことがあるからだ。
華怜は目的達成のためならば、手段を選ばない。嫌悪していた幻想人とさえ手を結んだのだから、今更猫下と共謀
関係になることにも抵抗はない。
それに彼からは所々、レッドフードに似た物を感じた。
「確かに。貴方と組めば、私にもメリットがありそうね」
ただ、似ているのはあくまで表面状の態度だけであって。彼とレッドフードが秘める本質的な部分は、徹頭徹尾まで乖離していた。
「なんて、私が〝貴女〟の臭い芝居に騙されると、本気で思ってたの?」
華怜は握手に応じるフリをして、猫下のノーガードだった横っ面を殴り付けた。
さらに畳み掛けるよう、起きあがろうとした〝彼女〟の腹部をありったけの力で蹴り飛ばす。
「ようやく追い付いたわよ、猫下誠人巡査……ううん、幻想人『赤ずきん』ッ!」
白一色の内装は心身が落ち着く一方で、どこか閉塞感を感じてしまう。窓には格子が嵌め込まれ、唯一の脱出路とも言えるドアの向こうには、きっと見張りの警官達が控えているのだろう。
そして、ベッドで横になった華怜の真横。備え付けの椅子に腰掛けた青年が、聴取内容を手持ちの端末にまとめていた。
「まさか、幻想人(フェアリスト)には表と裏の二人がいただなんて⁉ 流石のスーパーエリートである僕もビックリですよ⁉」
猫下誠人(ねこもとまこと)巡査。初めにそう名乗った彼は、声と口調から察するに、自分と刃を交えた〈ウルフパック〉のドライバーで間違えないのだろう。
「あのさ……その妙に芝居がかった喋り方って、同僚からウザがられない?」
「んー、特にそういうことを言われた覚えはありませんね。それに今は取り調べの最中ですので、大上〝元〟巡査部長は、僕に聞かれたことだけを答えてくれれば良いんですよ」
悪意のない顔で。それでも「元」というフレーズを強調してくるのは、ナチュラルに彼の性格が悪いからだろう。
それを薄々察しながらも、華怜は問われた内容に答え続けた。
幻想人には表と裏が存在すること。赤ずきんの裏を追い詰める為、レッドフードに共謀を持ちかけられ、乗じたこと。
そういう「知られても構わない内容」は淡々に答えてやるが、幾つかの「知られては不味い内容」は嘘で対応する。
「レッドフードは今どうしてるのか?」なんて質問、もってのほかだ。
「さぁ? 下水道の中ではぐれて、それっきりだから。私も彼女の行方を知らないの」
「はぁ……貴女はそんな下手な嘘で、このスーパーエリートを騙せると思っているのでしょうか?」
勿論、思ってなどいない。だからこそ、両者の間には険悪な空気が流れるのだろう。
「まっ、それはおいおい調べれば良いでしょう。……だけど、やっぱり分からないですね。大上さん、貴女はどうして自ら出頭することを選んだんですか?」
猫下は眉間の辺りを摘みながら、考えている素振りを見せた。
「逃げるのが疲れたとか、良心の呵責に耐えきれなくなったとか。そんなベタな理由で自分から捕まりに来たわけでもないでしょう。だって貴女の眼は今もギラついているんだから。まるで、目標を定めた獣みたくね」
お前は、一体何を企んでいる? ────薄っすらと開かれた彼の瞳の奥は、そう言いたげだった。
目標を定めた眼をしているのはお互い様だ。
「けど、そうね……コレは別に話しても構わない内容か」
華怜がわざわざ出頭することを選んだ理由。それは「ある可能性」に気づいてしまったことに起因する。
「幻想人『赤ずきん』の裏。彼女だけが今日まで誰にも捕まらなかったのは、どうしてだと思う?」
警察は一〇年間、赤ずきんを捕えることが出来なかった。それどころかここ数年は、彼女に纏わる目撃証言や情報提供がピタリと途絶えているのが現状だ。
では、果たしてそんなことが本当にあり得るのだろうか?
街中には監視カメラと、幻想人が発する信号に反応するスキャナーが無数に設置されている。レッドフードは百千桃佳(ももちちももか)に協力を仰ぐことで、それら機器に捕捉されることを避けてはいたが、そんな彼女でさえ手配書の顔を覚えていたタクシードライバーに通報されてしまった。
「レッドフードはあれでも、かなり頭のキレる幻想人だ。外出だって必要最低限に済ませるし、普段はアジトにずっと潜伏している。だけど、赤ずきんの裏は違うの。彼女は今でも不定期に快楽的な殺人を楽しんでは、己が狩人であることに酔いしれている」
それは無論、レッドフード以上に捕まるリスクを高めてしまうような愚行でもある。なのに、どうして赤ずきんに纏わる情報だけが不自然に途絶えてしまったのか?
「初めは彼女にも、百千さんみたいな異能を有した幻想人か、監視カメラを誤魔化せる幻想人が味方にいるって考えたの。だけど、彼女達が結成したコミュニティの名簿リストを見る限り、そんな都合のいい味方はいなかった」
つまり、赤ずきんが自分に纏わる情報を全て抹消するなど、本来は不可能であるはずなのだ。
行動を起こしたからには、必ず何かしらの痕跡が残ってしまう。この鉄則に例外はない。
「だけど、たった一つだけ裏技があるの。凄くシンプルな方法なのに、それを成功させるだけで、誰も彼女に追いつけなくなる裏技がね」
それは裏技中の裏技。ミステリーならば禁じ手だった。
「────幻想人の異能や情報をまとめた警視庁のデータベース。そこに記された情報を削除・改竄してしまえばいいのよ」
幻想人が捕まってしまう最大の要因は、自らが発してしまう固有の信号だ。だが、固有の信号であるからこそ、データベースの登録情報は改竄されてしまえば、スキャナーはもう二度と二人の赤ずきんを捕捉できなくなってしまう。
下水道に逃げ延びた際、〈ウルフパック〉のセンサーがレッドフードを捕捉できなかったのも、それが要因であり、同時に華怜がこの裏技に気づくキッカケでもあった。
「なるほど、前提条件の変更ですか……確かにそれっぽい仮説ですが、ちょっと無理がありません? 幻想人が、警視庁のデータベースを遠隔でクラックできると思いませんし。直接改竄しようにも、それこそ厳重なセキュリティの中に飛び込む自殺行為なんじゃ」
猫下の指摘はもっともだ。常識的に考えれば、ただの幻想人が警視庁内部に潜り込み、データベースを改竄できるわけがない。道中で誰かに見つかり、包囲されるのが精々のオチだろう。
当然、華怜もその反論は予測している。
「赤ずきんが有した本来の異能は「血液操作」ではなく、「赤いものを思うがままに操れる」というもの。これが本当に厄介でね、元が赤いものであれば、その色彩や触感まで自由に弄ることができるの」
赤い血液を弾丸に仕込めば、軌道を遠隔で操ることが出来ることも。ワイヤー状に引き伸ばせば、ビル間を渡り歩くことができることも。果ては、赤いというだけのパトランプを無条件で起爆させることさえ出来る。
彼女らが有した異能の万能性は、既にレッドフードが飽きるほど見せてくれた。
では、真っ赤に染めた袋などを頭から被ったとして。その色彩や材質を操作することで、他人のガワを装うことは出来ないだろうか?
「要はハリウッドの特殊メイクみたいなものよ。異能を用いて、他者に化ける為のマスクを自作するの」
これに関しては出頭する以前に、レッドフードに可能かを試してもらった。適当に拾ってきたビニール袋を血液で着色し、彼女に被らせる。そして、自分に化けるよう頼んでみたのだ。
結果、完成したマスクは華怜の顔とは似ても似つかない物だった。目鼻のバランスが特に酷く、ハロウィン用のコスプレと言われた方がまだ信じられる。
ただ、肌の質感や髪の滑らかさなどの一要素ごとに着目すれば、自身のものと見分けがつかない程の再現度を誇っていたのも事実だ。
きっと、ここからは練度の問題なのだろう。練習を繰り返せば、レッドフードだってそれなりの変装用マスクを作ることが出来ると確信できた。
「じゃあ、まさかですよ……幻想人『赤ずきん』の裏は、自らの異能で警察内部の誰かに化けて、データベースを堂々と弄ってたってことですか⁉」
「私の仮説が正しければ、そうなるはず」
「で、では……大上さん! 貴女がわざわざ出頭してまで警察内部に戻ってきた理由は、」
警察という群れの中に、赤ずきんという異分子が紛れ込んでいる。その可能性に気づいたからこそ、華怜は一度離反した組織に戻ってきたのだ。今度こそ尻尾を掴み、その喉元に牙を突き立てるために────
「よいしょっと!」
もう傷は十分に癒えた。数日ぶりの柔らかなベッドには名残惜しさも感じたが、それでも華怜は勢いよく上体を起こした。
「と言うわけだから、そこを退いてくれない? 猫下巡査」
だからと言って、警察官である彼が「はいどうぞ」と道を譲ってくれるわけもない。
だが、華怜が拳を固めると同時、猫下の取ったリアクションは意外なものであった。
「あっはは! まさか、まさかの展開ですよ。これはスーパーエリートの僕でさえ、予想がつかなかったなぁ!」
彼は楽し気に笑うも、それはすぐに終わってしまう。
開いているか、閉じているのか曖昧な瞳をさらに細めて、彼はポツリと言葉を漏らした。
「ねぇ、大上さん。僕がどうして警察官になったか知ってます?」
「いや、知らないわよ……私たちって、殆ど初対面みたいなものだし……」
「あはは、そう言えば、そうですよね。けど、僕らって意外と似たもの同士だと思うんですよ。だって、僕が警察官になった動機も貴方と同じ、復讐なんですから」
曰く、猫下は幼かった妹を赤ずきんに殺されてしまったらしい。
「それって本当の話?」
「本当ですよ。それに大上さんの仮説が正しければ、僕の妹の仇が、この組織内の誰かに化けていることになる。警視総監かな? それとも警視庁長かな? もしかして、意外な人物……辰巳(たつみ)警部だったり!」
「……さぁ、どうかしらね」
「とにかくですよ。察するに大上さんは、赤ずきんが警察内部の誰に化けているかまでは掴めていない。だから出頭してまで、それが誰かを暴こうとした。────でしたら、僕と共謀しませんか? ターゲットは同じ。それに警察官である僕のアシストがあれば、貴女はより確実に誰が赤ずきんかを暴くことができる。ねっ、悪くない条件でしょ」
猫下は手を差し出してきた。握手を求めているのだ。
「…………」
こんな展開にデジャヴを感じてしまうのは、以前にもレッドフードから似たような誘いを受けてことがあるからだ。
華怜は目的達成のためならば、手段を選ばない。嫌悪していた幻想人とさえ手を結んだのだから、今更猫下と共謀
関係になることにも抵抗はない。
それに彼からは所々、レッドフードに似た物を感じた。
「確かに。貴方と組めば、私にもメリットがありそうね」
ただ、似ているのはあくまで表面状の態度だけであって。彼とレッドフードが秘める本質的な部分は、徹頭徹尾まで乖離していた。
「なんて、私が〝貴女〟の臭い芝居に騙されると、本気で思ってたの?」
華怜は握手に応じるフリをして、猫下のノーガードだった横っ面を殴り付けた。
さらに畳み掛けるよう、起きあがろうとした〝彼女〟の腹部をありったけの力で蹴り飛ばす。
「ようやく追い付いたわよ、猫下誠人巡査……ううん、幻想人『赤ずきん』ッ!」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

The Outer Myth :Ⅰ ~目覚めの少女と嘆きの神~
とちのとき
SF
少女達が紡ぐのは、絆と神話の続き・・・。
主人公の女子高生、豊受イナホ。彼女は神々と人々が当たり前のように共存する地、秋津国で平凡な生活を送っていた。しかし、そこでは未知なる危険生物・クバンダにより平和が蝕まれつつあった。何の取り柄もない彼女はある事件をきっかけに母の秘密を探る事になり、調査を進めるうち運命の渦へと巻き込まれていく。その最中、ニホンからあらゆる漂流物が流れ着く摩訶不思議な池、霞み池に、記憶を失った人型AGI(汎用人工知能)の少女ツグミが漂着する。彼女との出会いが少年少女達を更なる冒険へと導くのだった。
【アウターミス パート1~目覚めの少女と嘆きの神~】は、近未来和風SFファンタジー・完結保証・挿絵有(生成AI使用無し)・各章間にパロディ漫画付き☆不定期更新なのでお気に入り登録推奨
【作者より】
他サイトで投稿していたフルリメイクになります。イラスト製作と並行して更新しますので、不定期且つノロノロになるかと。完全版が読めるのはアルファポリスだけ!
本作アウターミスは三部作予定です。現在第二部のプロットも進行中。乞うご期待下さい!
過去に本作をイメージしたBGMも作りました。ブラウザ閲覧の方は目次下部のリンクから。アプリの方はYouTube内で「とちのとき アウターミス」と検索。で、視聴できます

私はお母様の奴隷じゃありません。「出てけ」とおっしゃるなら、望み通り出ていきます【完結】
小平ニコ
ファンタジー
主人公レベッカは、幼いころから母親に冷たく当たられ、家庭内の雑務を全て押し付けられてきた。
他の姉妹たちとは明らかに違う、奴隷のような扱いを受けても、いつか母親が自分を愛してくれると信じ、出来得る限りの努力を続けてきたレベッカだったが、16歳の誕生日に突然、公爵の館に奉公に行けと命じられる。
それは『家を出て行け』と言われているのと同じであり、レベッカはショックを受ける。しかし、奉公先の人々は皆優しく、主であるハーヴィン公爵はとても美しい人で、レベッカは彼にとても気に入られる。
友達もでき、忙しいながらも幸せな毎日を送るレベッカ。そんなある日のこと、妹のキャリーがいきなり公爵の館を訪れた。……キャリーは、レベッカに支払われた給料を回収しに来たのだ。
レベッカは、金銭に対する執着などなかったが、あまりにも身勝手で悪辣なキャリーに怒り、彼女を追い返す。それをきっかけに、公爵家の人々も巻き込む形で、レベッカと実家の姉妹たちは争うことになる。
そして、姉妹たちがそれぞれ悪行の報いを受けた後。
レベッカはとうとう、母親と直接対峙するのだった……

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

Dマシンドール 迷宮王の遺産を受け継ぐ少女
草乃葉オウル
ファンタジー
世界中にダンジョンと呼ばれる異空間が現れてから三十年。人類はダンジョンの脅威に立ち向かうため、脳波による遠隔操作が可能な人型異空間探査機『ダンジョン・マシンドール』を開発した。これにより生身では危険かつ非効率的だったダンジョンの探査は劇的に進み、社会はダンジョンから得られる未知の物質と技術によってさらなる発展を遂げていた。
そんな中、ダンジョンともマシンとも無関係な日々を送っていた高校生・萌葱蒔苗《もえぎまきな》は、突然存在すら知らなかった祖父の葬儀に呼ばれ、1機のマシンを相続することになる。しかも、その祖父はマシンドール開発の第一人者にして『迷宮王』と呼ばれる現代の偉人だった。
なぜ両親は祖父の存在を教えてくれなかったのか、なぜ祖父は会ったこともない自分にマシンを遺したのか……それはわからない。でも、マシンを得たならやるべきことは1つ。ダンジョンに挑み、モンスターを倒し、手に入れた素材でマシンをカスタム! そして最強の自分専用機を造り上げる! それが人を、世界を救うことに繋がっていくことを、蒔苗はまだ知らない。

女子高生は卒業間近の先輩に告白する。全裸で。
矢木羽研
恋愛
図書委員の女子高生(小柄ちっぱい眼鏡)が、卒業間近の先輩男子に告白します。全裸で。
女の子が裸になるだけの話。それ以上の行為はありません。
取って付けたようなバレンタインネタあり。
カクヨムでも同内容で公開しています。

【R18】闇堕ちバレリーナ~悲鳴は届かない~
月島れいわ
恋愛
憧れのバレエ団の入団テストに合格した玲於奈。
大学もあと一年というところで退学を決めた。
かつてのようなお嬢様ではいられなくなった。
それでも前途は明るいはずだったのにーーーー想像もしなかった官能レッスンが待っていた。
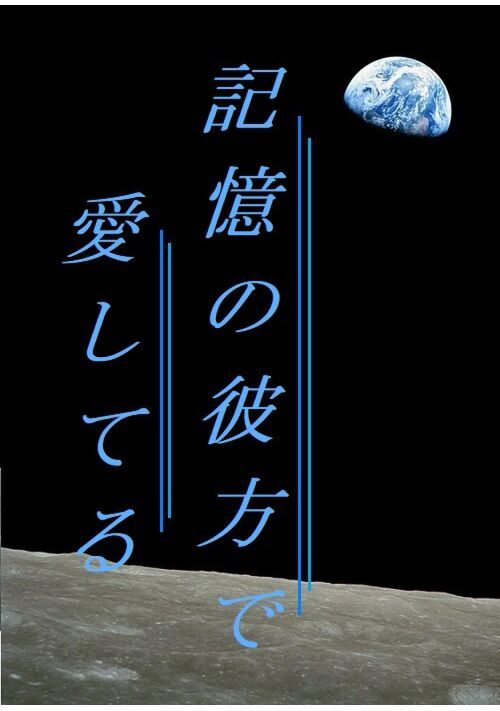
記憶の彼方で愛してる
志賀雅基
SF
◆いつからか/僕の中に誰かいる//温もりの残滓/俺は失くしちゃいないのに◆
〔ディアプラスBL小説大賞第三次選考通過作〕[全11話]
所轄署の刑事課強行犯係の刑事である真由機が朝起きると見知らぬ女性と寝ていた。何処で拾ったのか知れぬ女性が目覚めて喋るとじつは男。毛布の下を見てもやはり男。愕然としつつ出勤すると45ACP弾で射殺された男性発見の報が入る。アパートに戻っても謎な男は居座っていたが、そいつの持ち物と思しき45ACP弾使用拳銃をマユキは発見してしまい当然の疑いが芽生えた。
▼▼▼
【シリーズ中、何処からでもどうぞ】
【全性別対応/BL特有シーンはストーリーに支障なく回避可能です】
【エブリスタ・ノベルアップ+に掲載】
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















