29 / 59
10
1
しおりを挟む
「酔わはると、眠ってしまう」と教えてくれたのは、上七軒の芸妓をしていた君菊という女だった。色が白い京美人という風情で、柳腰に色気のある女だった。土方は、君菊の所に通う時に、何故か、島田を誘うことがあった。
『おい、島田君。餅でも食いに行こう』
大声で島田を呼びつけて、半ば無理矢理連れ出す。壬生の屯所だったか、西本願寺だったか、不動村だったか。何度も、島田は、土方に誘われて、北野の君菊の家を訪なった。
なぜ、女の所に通うのに、島田を誘うのか、理由は聞かなかった。勿論、島田の前で、君菊と情を交わすわけではないので、そういう時は、こっそりと忍んでくるのだろう。
君菊の住まいは、こぢんまりとした家だった。さっぱりとした雰囲気で、囲われた女の家というような、ねっとりした雰囲気がないのは、島田には何となくありがたかった。土方が個人的な付き合いを持つ女との、そういう空気を感じたくはない。
君菊の家に行くと、いつも、餅が用意されていた。土方は『餅を食いに行こう』と誘っているので、君菊は島田の為に餅を用意しておく。土方も一つや二つは食べるが、山のように用意された餅は、島田の為だ。
「このあたりに、美味い餅屋があるんだよ」と得意そうに土方は島田に餅を勧める。島田は、甘党な上に、相撲取りに間違えられるほどの巨漢で、よく食べる。餅や饅頭などは、あればあるだけ食いたくなる。二、三十個は食べられる。それを見越して、君菊は、島田の為に山のように餅を用意する。
「島田はんは、よう、お食べになるから、見ていて気持ちがええわ」と笑う仕草が、楚々としている。色の白い小柄な女だった。
「……俺は、この京言葉って言うのが、なよなよしていて、なんだか、はぐらかされているようで好きではなかったんだが、君菊の声を聞いているうちに、京言葉も悪く無いと思うようになってきた」
土方の言葉通り、君菊は、何とも言えない柔らかな声音だった。媚びているのでもなく、ツンと澄ましているのでもなく、何となく、言葉の端々に、暖かみを感じることが出来る声音で、それが、耳にも、荒れた心にも、何とも甘く響く。それが溜まらなくなって、囲ったのだろう、と島田は思った。
土方の精神は、それほど、強靱ではない。頑なで、てこでも曲がらないような強さはあるが、しなやかさはない。それでは、いずれ、ポキリと折れる。
餅は真っ白で、中に餡が入っている。なんとも美味い。島田が餅に夢中になっている間、土方と君菊は、様々な遣り取りをしている。芸妓の君菊を島田は知らないが、君菊は鳴物や笛が得意だったらしく、土方は興味津々に君菊に習っている。
「あら、土方はん。その龍笛、どうしましたん? うちの差し上げたものと違います」
龍笛持参で来たのだが、藪蛇だったらしい。何人かこういう女が居て、間違って、その女から貰った龍笛を持ってきてしまったようだ。マメなようで、若干抜けている。
「いや……すまん」と素直に謝ると、ころころと君菊は笑う。
「構いまへん。つぎは、間違わんといて下さい……今日は、笛のお稽古は止めましょう」
笛まで持参した土方は、少々がっかりしたようだが、「じゃあ、和歌で」と持ち直した。
「お和歌……土方はん、お好きどすな」
島田も、土方が俳句を作っているというのは、知っている。新撰組の局内でも有名な話だが、土方の俳句を見たことがある者は、殆ど居ない。沖田けは一度、句集を見たことがあると言っていたが、島田が土方に頼み込んでも、土方は頑として見せてはくれなかった。
(和歌もつくられるのだろうか)と島田は思った。
俳句よりも、和歌の方が古めかしくて高尚な感じがする。だが、なんとなく(辞世なら、和歌かもしれないな)と思ったからには、やはり、後に残るものへの見栄もあるので、和歌の勉強もしておいた方が良いような気には、なってきた。
「……敷島の道は、新町の若鶴太夫か、島原の花君太夫にお聞きにならはるのが一番どす。お二人は、さすがに当代切っての名太夫。お和歌もさらさらと……」
「さらさらと、和歌を作ってはくれるけれどね、教えてはくれないのだよ」
「まぁ、土方はん。うちをお和歌やお囃子の先生と思うてはりますの?」
くすくすと笑う君菊の前で、土方は頬を赤らめた。島田を誘ってここに来る時は、女の君菊ではなく、師匠の君菊に会いに来ているようだった。
「憎らしいお人やなぁ……それでも、憎めへんお人や………」
『おい、島田君。餅でも食いに行こう』
大声で島田を呼びつけて、半ば無理矢理連れ出す。壬生の屯所だったか、西本願寺だったか、不動村だったか。何度も、島田は、土方に誘われて、北野の君菊の家を訪なった。
なぜ、女の所に通うのに、島田を誘うのか、理由は聞かなかった。勿論、島田の前で、君菊と情を交わすわけではないので、そういう時は、こっそりと忍んでくるのだろう。
君菊の住まいは、こぢんまりとした家だった。さっぱりとした雰囲気で、囲われた女の家というような、ねっとりした雰囲気がないのは、島田には何となくありがたかった。土方が個人的な付き合いを持つ女との、そういう空気を感じたくはない。
君菊の家に行くと、いつも、餅が用意されていた。土方は『餅を食いに行こう』と誘っているので、君菊は島田の為に餅を用意しておく。土方も一つや二つは食べるが、山のように用意された餅は、島田の為だ。
「このあたりに、美味い餅屋があるんだよ」と得意そうに土方は島田に餅を勧める。島田は、甘党な上に、相撲取りに間違えられるほどの巨漢で、よく食べる。餅や饅頭などは、あればあるだけ食いたくなる。二、三十個は食べられる。それを見越して、君菊は、島田の為に山のように餅を用意する。
「島田はんは、よう、お食べになるから、見ていて気持ちがええわ」と笑う仕草が、楚々としている。色の白い小柄な女だった。
「……俺は、この京言葉って言うのが、なよなよしていて、なんだか、はぐらかされているようで好きではなかったんだが、君菊の声を聞いているうちに、京言葉も悪く無いと思うようになってきた」
土方の言葉通り、君菊は、何とも言えない柔らかな声音だった。媚びているのでもなく、ツンと澄ましているのでもなく、何となく、言葉の端々に、暖かみを感じることが出来る声音で、それが、耳にも、荒れた心にも、何とも甘く響く。それが溜まらなくなって、囲ったのだろう、と島田は思った。
土方の精神は、それほど、強靱ではない。頑なで、てこでも曲がらないような強さはあるが、しなやかさはない。それでは、いずれ、ポキリと折れる。
餅は真っ白で、中に餡が入っている。なんとも美味い。島田が餅に夢中になっている間、土方と君菊は、様々な遣り取りをしている。芸妓の君菊を島田は知らないが、君菊は鳴物や笛が得意だったらしく、土方は興味津々に君菊に習っている。
「あら、土方はん。その龍笛、どうしましたん? うちの差し上げたものと違います」
龍笛持参で来たのだが、藪蛇だったらしい。何人かこういう女が居て、間違って、その女から貰った龍笛を持ってきてしまったようだ。マメなようで、若干抜けている。
「いや……すまん」と素直に謝ると、ころころと君菊は笑う。
「構いまへん。つぎは、間違わんといて下さい……今日は、笛のお稽古は止めましょう」
笛まで持参した土方は、少々がっかりしたようだが、「じゃあ、和歌で」と持ち直した。
「お和歌……土方はん、お好きどすな」
島田も、土方が俳句を作っているというのは、知っている。新撰組の局内でも有名な話だが、土方の俳句を見たことがある者は、殆ど居ない。沖田けは一度、句集を見たことがあると言っていたが、島田が土方に頼み込んでも、土方は頑として見せてはくれなかった。
(和歌もつくられるのだろうか)と島田は思った。
俳句よりも、和歌の方が古めかしくて高尚な感じがする。だが、なんとなく(辞世なら、和歌かもしれないな)と思ったからには、やはり、後に残るものへの見栄もあるので、和歌の勉強もしておいた方が良いような気には、なってきた。
「……敷島の道は、新町の若鶴太夫か、島原の花君太夫にお聞きにならはるのが一番どす。お二人は、さすがに当代切っての名太夫。お和歌もさらさらと……」
「さらさらと、和歌を作ってはくれるけれどね、教えてはくれないのだよ」
「まぁ、土方はん。うちをお和歌やお囃子の先生と思うてはりますの?」
くすくすと笑う君菊の前で、土方は頬を赤らめた。島田を誘ってここに来る時は、女の君菊ではなく、師匠の君菊に会いに来ているようだった。
「憎らしいお人やなぁ……それでも、憎めへんお人や………」
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

母の下着 タンスと洗濯籠の秘密
MisakiNonagase
青春
この物語は、思春期という複雑で繊細な時期を生きる少年の内面と、彼を取り巻く家族の静かなる絆を描いた作品です。
颯真(そうま)という一人の高校生の、ある「秘密」を通して、私たちは成長の過程で誰もが抱くかもしれない戸惑い、罪悪感、そしてそれらを包み込む家族の無言の理解に触れます。
物語は、現在の颯真と恋人・彩花との関係から、中学時代にさかのぼる形で展開されます。そこで明らかになるのは、彼がかつて母親の下着に対して抱いた抑えがたい好奇心と、それに伴う一連の行為です。それは彼自身が「歪んだ」と感じる過去の断片であり、深い恥ずかしさと自己嫌悪を伴う記憶です。
しかし、この物語の核心は、単なる過去の告白にはありません。むしろ、その行為に「気づいていたはず」の母親が、なぜ一言も問い詰めず、誰にも告げず、ただ静かに見守り続けたのか——という問いにこそあります。そこには、親子という関係を超えた、深い人間理解と、言葉にされない優しさが横たわっています。
センシティブな題材を、露骨な描写や扇情的な表現に頼ることなく、あくまで颯真の内省的な視点から丁寧に紡ぎ出しています。読者は、主人公の痛みと恥ずかしさを共有しながら、同時に、彼を破綻から救った「沈黙の救済」の重みと温かさを感じ取ることでしょう。
これは、一つの過ちと、その赦しについての物語です。また、成長とは時に恥ずかしい過去を背負いながら、他者の無償の寛容さによって初めて前を向けるようになる過程であること、そして家族の愛が最も深く現れるのは、時に何も言わない瞬間であることを、静かにしかし確かに伝える物語です。
どうか、登場人物たちの静かなる心の襞に寄り添いながら、ページをめくってください。

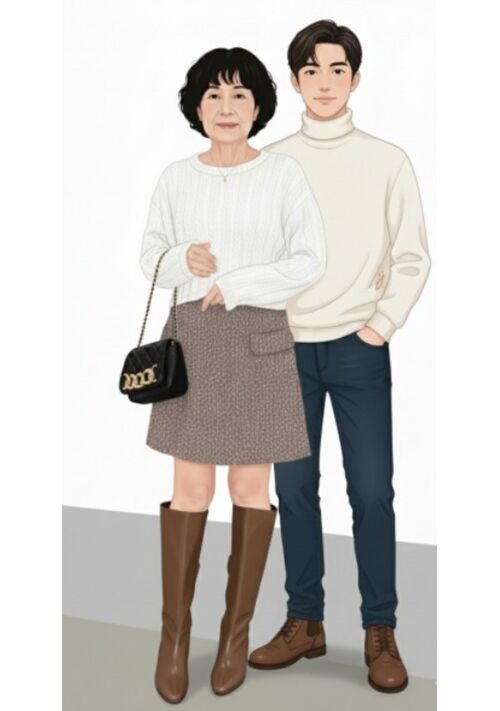
還暦の性 若い彼との恋愛模様
MisakiNonagase
恋愛
還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。
そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。
その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。
全7話

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

本能寺からの決死の脱出 ~尾張の大うつけ 織田信長 天下を統一す~
bekichi
歴史・時代
戦国時代の日本を背景に、織田信長の若き日の物語を語る。荒れ狂う風が尾張の大地を駆け巡る中、夜空の星々はこれから繰り広げられる壮絶な戦いの予兆のように輝いている。この混沌とした時代において、信長はまだ無名であったが、彼の野望はやがて天下を揺るがすことになる。信長は、父・信秀の治世に疑問を持ちながらも、独自の力を蓄え、異なる理想を追求し、反逆者とみなされることもあれば期待の星と讃えられることもあった。彼の目標は、乱世を統一し平和な時代を創ることにあった。物語は信長の足跡を追い、若き日の友情、父との確執、大名との駆け引きを描く。信長の人生は、斎藤道三、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康、伊達政宗といった時代の英傑たちとの交流とともに、一つの大きな物語を形成する。この物語は、信長の未知なる野望の軌跡を描くものである。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















