お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

鎌倉古民家カフェ「かおりぎ」
水川サキ
ライト文芸
旧題」:かおりぎの庭~鎌倉薬膳カフェの出会い~
【私にとって大切なものが、ここには満ちあふれている】
彼氏と別れて、会社が倒産。
不運に見舞われていた夏芽(なつめ)に、父親が見合いを勧めてきた。
夏芽は見合いをする前に彼が暮らしているというカフェにこっそり行ってどんな人か見てみることにしたのだが。
静かで、穏やかだけど、たしかに強い生彩を感じた。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。
三矢さくら
ファンタジー
【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎
長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?
しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。
ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。
といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。
とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!
フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!
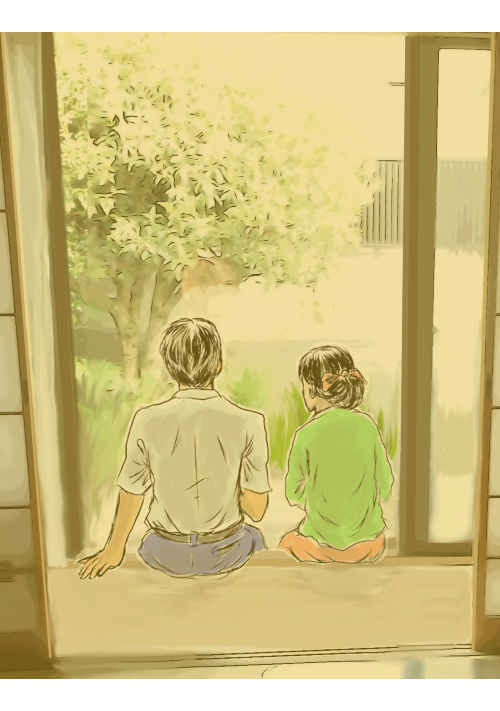
雨音
宮ノ上りよ
ライト文芸
夫を亡くし息子とふたり肩を寄せ合って生きていた祐子を日々支え力づけてくれたのは、息子と同い年の隣家の一人娘とその父・宏の存在だった。子ども達の成長と共に親ふたりの関係も少しずつ変化して、そして…。
※時代設定は1980年代後半~90年代後半(最終のエピソードのみ2010年代)です。現代と異なる点が多々あります。(学校週六日制等)

パワハラ女上司からのラッキースケベが止まらない
セカイ
ライト文芸
新入社員の『俺』草野新一は入社して半年以上の間、上司である椿原麗香からの執拗なパワハラに苦しめられていた。
しかしそんな屈辱的な時間の中で毎回発生するラッキースケベな展開が、パワハラによる苦しみを相殺させている。
高身長でスタイルのいい超美人。おまけにすごく巨乳。性格以外は最高に魅力的な美人上司が、パワハラ中に引き起こす無自覚ラッキースケベの数々。
パワハラはしんどくて嫌だけれど、ムフフが美味しすぎて堪らない。そんな彼の日常の中のとある日の物語。
※他サイト(小説家になろう・カクヨム・ノベルアッププラス)でも掲載。

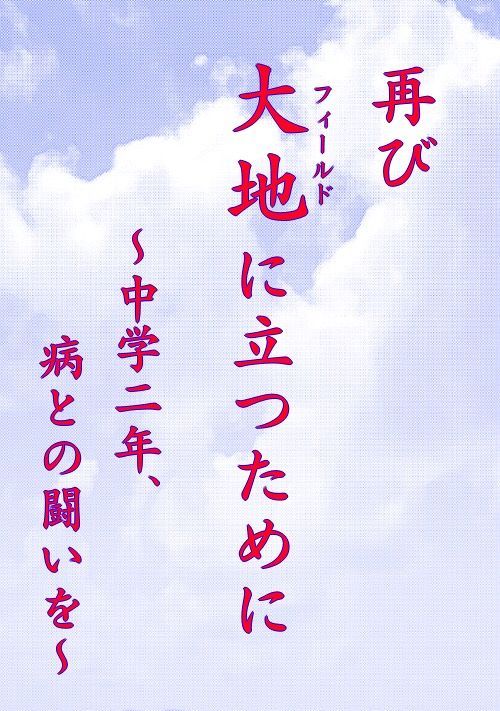
再び大地(フィールド)に立つために 〜中学二年、病との闘いを〜
長岡更紗
ライト文芸
島田颯斗はサッカー選手を目指す、普通の中学二年生。
しかし突然 病に襲われ、家族と離れて一人で入院することに。
中学二年生という多感な時期の殆どを病院で過ごした少年の、闘病の熾烈さと人との触れ合いを描いた、リアルを追求した物語です。
※闘病中の方、またその家族の方には辛い思いをさせる表現が混ざるかもしれません。了承出来ない方はブラウザバックお願いします。
※小説家になろうにて重複投稿しています。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる
農民ヤズ―
ファンタジー
「ようこそおいでくださいました。勇者さま」
そんな言葉から始まった異世界召喚。
呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?
そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!
このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。
勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定
私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。
ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。
他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。
なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















