2 / 8
しゃれこうべの誘惑2
しおりを挟む
情けのためではなく、己の助平な心持ちのためにやり始めるとは口が裂けても言えなかった。
安次郎は快い返事に上機嫌で「では頼んだぞ!」と笑顔で帰っていった。
安請け合いをしたかもしれんと、しゃれこうべを見ながら溜息を一つついた松兵衛は、もう一度夜にしっかりといろりの火に当てながら見たが、薄気味悪いといえばそうだが、どこか惹きつけられるものがある。歯並びもよし、全体に傷一つない。よく良い状態のまま見つかったものだと感心すらした。
考えていてもしょうがない。まずは朝を待ってから取り掛かるかと、睡眠後早朝から粘土を貼り付ける作業をしだした。
最初は苦心したが、慣れてくると粘土の凹凸もなくなり、少しずつムラのない形を成すようになってきた。
まずは頭部からしっかりと肉付けしていく。その後ヘラで形を整えながら徐々にあご側へと貼り付けていくが、困ったことが起きた。
鼻の骨がないため想像で作るしかない。はて、千代の形は、などと思い浮かべる。
不意に頬を染めてにやける松兵衛の脳裏には、何度となくまぐわった光景がしっかりと焼き付いている。何度となく思い浮かべ、一度として叶わなかった夢。そのせいで何度子種を虚空に解き放ったか数知れぬ。
ムクムクともたげてくる男根の痛みにも耐え、松兵衛は一心不乱に粘土をつけていった。
没頭してみると、それほど時間はかからなかった。耳も鼻と同じように「こんなものか」という具合で作れた。
気がつけば夕闇が迫ろうかというところで出来上がったから、二日とかからなかったのだ。
瞳のところは空洞ではさすがに気色が悪かったので目を閉じる形をとった。出来上がってみると千代に似てなくもない。髪がないせいで、まだ実感がわかない。下手に持ち上げてしまうと顎の方が落ちてしまうので、置いておかなければならなかった。
「よし、髪を植えてやろう」
さて、千代の髪はというと、前は綺麗に揃えてあり、肩口まで伸びた髪はいつも艶めいていた。探すのにそれほど苦労はしないだろうとタカをくくっていたが、翌日探してみると難儀な事であった。
出床と言って、外で髪結い業をしている箇所をあたってみたが、徒労に終わった。男の髪のみを切る場所であるから、当然の結果であったが、廻り髪結いならば女の家やその手の店に出入りすることもあるだろうと、場所を突き止め四人目にようやく髪があると言った髪結いに出会った。
ぜひとも譲って欲しいことを告げると「一分銀六枚」と法外な値段を要求してくるので怒りすら込み上げてきて食い下がった松兵衛に、若いすました成り立ちのこの男は、いかにも馬鹿にしたような流し目で興味なさそうにあちらを向き、
「この髪はそこらの町民のものではございません。由緒あるお家柄の人の物で不運にも若後家となりまして出家を決意なされたのです。私が手に入れた髪の中でも上もの。お兄様もご事情おありでしょうが、私も涙を呑みまして、その銭勘定になったのです」
と、すっと耳の奥へ通るような涼しげで色気すらあるような声で言われたが、だが松兵衛は腹の虫がざわつき「何が涙を呑んでだ。氷水でピシャリ冷やし続けたような血も涙もない顔しやがって」と心の中で悪態をついていた。
実際どこか千代を失った文十郎のようでもある。毎日顔色を白くして幽霊のようだが、持っていた美しさまで即座に消えるわけではない。覇気がないだけ動きがゆらりと遊女のようなしなやかな身のこなしをする時があって胸を打たれることがあった。この床屋も女ばかりを相手にしているのだろうか。男相手の無骨な様相とはまったく違って仕草一つ一つにどこか艶がある。
文十郎と似通ったところを見つけてしまうと、どこか哀れにも思えてくる。松兵衛は文十郎のことを思い浮かべて一芝居打つ事にした。
安次郎は快い返事に上機嫌で「では頼んだぞ!」と笑顔で帰っていった。
安請け合いをしたかもしれんと、しゃれこうべを見ながら溜息を一つついた松兵衛は、もう一度夜にしっかりといろりの火に当てながら見たが、薄気味悪いといえばそうだが、どこか惹きつけられるものがある。歯並びもよし、全体に傷一つない。よく良い状態のまま見つかったものだと感心すらした。
考えていてもしょうがない。まずは朝を待ってから取り掛かるかと、睡眠後早朝から粘土を貼り付ける作業をしだした。
最初は苦心したが、慣れてくると粘土の凹凸もなくなり、少しずつムラのない形を成すようになってきた。
まずは頭部からしっかりと肉付けしていく。その後ヘラで形を整えながら徐々にあご側へと貼り付けていくが、困ったことが起きた。
鼻の骨がないため想像で作るしかない。はて、千代の形は、などと思い浮かべる。
不意に頬を染めてにやける松兵衛の脳裏には、何度となくまぐわった光景がしっかりと焼き付いている。何度となく思い浮かべ、一度として叶わなかった夢。そのせいで何度子種を虚空に解き放ったか数知れぬ。
ムクムクともたげてくる男根の痛みにも耐え、松兵衛は一心不乱に粘土をつけていった。
没頭してみると、それほど時間はかからなかった。耳も鼻と同じように「こんなものか」という具合で作れた。
気がつけば夕闇が迫ろうかというところで出来上がったから、二日とかからなかったのだ。
瞳のところは空洞ではさすがに気色が悪かったので目を閉じる形をとった。出来上がってみると千代に似てなくもない。髪がないせいで、まだ実感がわかない。下手に持ち上げてしまうと顎の方が落ちてしまうので、置いておかなければならなかった。
「よし、髪を植えてやろう」
さて、千代の髪はというと、前は綺麗に揃えてあり、肩口まで伸びた髪はいつも艶めいていた。探すのにそれほど苦労はしないだろうとタカをくくっていたが、翌日探してみると難儀な事であった。
出床と言って、外で髪結い業をしている箇所をあたってみたが、徒労に終わった。男の髪のみを切る場所であるから、当然の結果であったが、廻り髪結いならば女の家やその手の店に出入りすることもあるだろうと、場所を突き止め四人目にようやく髪があると言った髪結いに出会った。
ぜひとも譲って欲しいことを告げると「一分銀六枚」と法外な値段を要求してくるので怒りすら込み上げてきて食い下がった松兵衛に、若いすました成り立ちのこの男は、いかにも馬鹿にしたような流し目で興味なさそうにあちらを向き、
「この髪はそこらの町民のものではございません。由緒あるお家柄の人の物で不運にも若後家となりまして出家を決意なされたのです。私が手に入れた髪の中でも上もの。お兄様もご事情おありでしょうが、私も涙を呑みまして、その銭勘定になったのです」
と、すっと耳の奥へ通るような涼しげで色気すらあるような声で言われたが、だが松兵衛は腹の虫がざわつき「何が涙を呑んでだ。氷水でピシャリ冷やし続けたような血も涙もない顔しやがって」と心の中で悪態をついていた。
実際どこか千代を失った文十郎のようでもある。毎日顔色を白くして幽霊のようだが、持っていた美しさまで即座に消えるわけではない。覇気がないだけ動きがゆらりと遊女のようなしなやかな身のこなしをする時があって胸を打たれることがあった。この床屋も女ばかりを相手にしているのだろうか。男相手の無骨な様相とはまったく違って仕草一つ一つにどこか艶がある。
文十郎と似通ったところを見つけてしまうと、どこか哀れにも思えてくる。松兵衛は文十郎のことを思い浮かべて一芝居打つ事にした。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


北武の寅 <幕末さいたま志士伝>
海野 次朗
歴史・時代
タイトルは『北武の寅』(ほくぶのとら)と読みます。
幕末の埼玉人にスポットをあてた作品です。主人公は熊谷北郊出身の吉田寅之助という青年です。他に渋沢栄一(尾高兄弟含む)、根岸友山、清水卯三郎、斎藤健次郎などが登場します。さらにベルギー系フランス人のモンブランやフランスお政、五代才助(友厚)、松木弘安(寺島宗則)、伊藤俊輔(博文)なども登場します。
根岸友山が出る関係から新選組や清河八郎の話もあります。また、渋沢栄一やモンブランが出る関係からパリ万博などパリを舞台とした場面が何回かあります。
前作の『伊藤とサトウ』と違って今作は史実重視というよりも、より「小説」に近い形になっているはずです。ただしキャラクターや時代背景はかなり重複しております。『伊藤とサトウ』でやれなかった事件を深掘りしているつもりですので、その点はご了承ください。
(※この作品は「NOVEL DAYS」「小説家になろう」「カクヨム」にも転載してます)
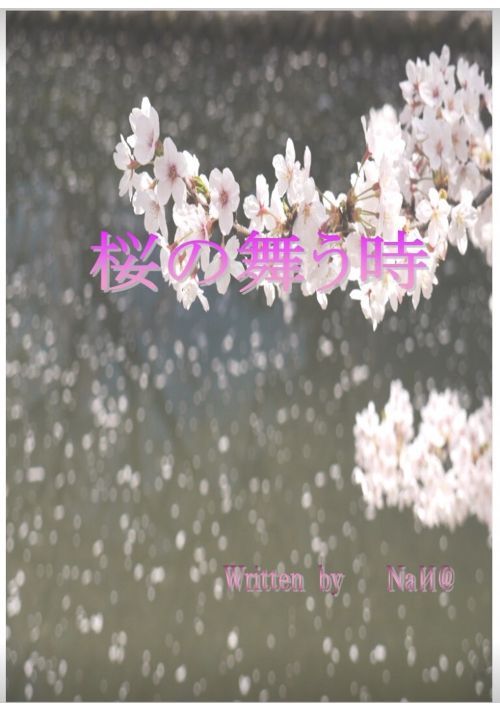
桜の舞う時
唯川さくら
歴史・時代
『約束する。いつか…いつかきっと…』
咲き誇る桜になって、帰ってくるよ…。
フィリピン ルソン島決戦 ―― 燃え上がる太陽 ―― 染矢 雪斗
『この国は…負けて目覚める…。…それでも…それでも俺は…。』
大切な友の帰る場所を、守りたい ―――――。
神風 ―― 桜色の空 ―― 相澤 剣
『…なんぼ遠くに離れても、この世におらんでも…。』
俺らはずっと友達やからなあっ…!!
ヒロシマ ―― 雨の跡 ―― 赤羽 光
『…地位も名誉もいらない…。人の心も自分の命も失ってかまわない…。』
僕にはそれよりも、守りたいものがあるんだよ…。
フィリピン ルソン島決戦 ―― 燃え上がる太陽 ―― 影山 龍二
『勝てると思って戦ってるんじゃない。俺たちはただ…』
平和な未来を信じて戦ってるんだ…。
沖縄本土決戦 ―― パイヌカジの吹く日 ―― 宜野座 猛
あなたには 彼らの声が 聞こえますか?
『桜が咲くと、“おかえり”って言いたくなるのは…あの人たちに言えなかったからかな…?』
桜の舞う時 written by 唯川さくら

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

つわもの -長連龍-
夢酔藤山
歴史・時代
能登の戦国時代は遅くに訪れた。守護大名・畠山氏が最後まで踏み止まり、戦国大名を生まぬ独特の風土が、遅まきの戦乱に晒された。古くから能登に根を張る長一族にとって、この戦乱は幸でもあり不幸でもあった。
裏切り、また裏切り。
大国である越後上杉謙信が迫る。長続連は織田信長の可能性に早くから着目していた。出家させていた次男・孝恩寺宗顒に、急ぎ信長へ救援を求めるよう諭す。
それが、修羅となる孝恩寺宗顒の第一歩だった。
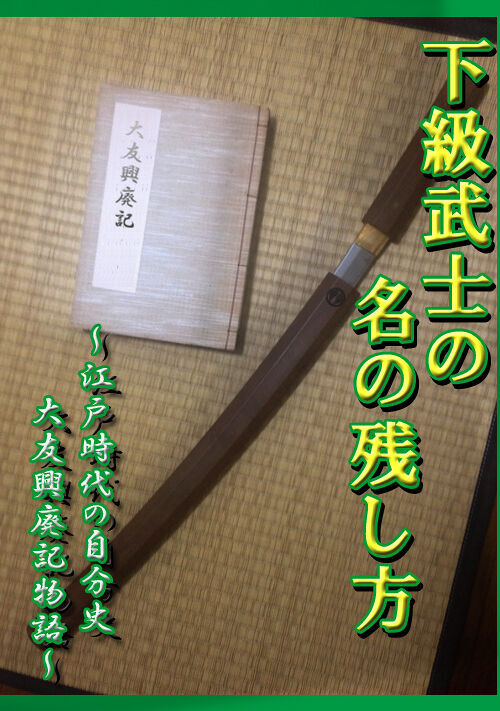
下級武士の名の残し方 ~江戸時代の自分史 大友興廃記物語~
黒井丸
歴史・時代
~本作は『大友興廃記』という実在の軍記をもとに、書かれた内容をパズルのように史実に組みこんで作者の一生を創作した時代小説です~
武士の親族として伊勢 津藩に仕える杉谷宗重は武士の至上目的である『家名を残す』ために悩んでいた。
大名と違い、身分の不安定な下級武士ではいつ家が消えてもおかしくない。
そのため『平家物語』などの軍記を書く事で家の由緒を残そうとするがうまくいかない。
方と呼ばれる王道を書けば民衆は喜ぶが、虚飾で得た名声は却って名を汚す事になるだろう。
しかし、正しい事を書いても見向きもされない。
そこで、彼の旧主で豊後佐伯の領主だった佐伯權之助は一計を思いつく。


リュサンドロス伝―プルターク英雄伝より―
N2
歴史・時代
古代ギリシアの著述家プルタルコス(プルターク)の代表作『対比列伝(英雄伝)』は、ギリシアとローマの指導者たちの伝記集です。
そのなかには、マンガ『ヒストリエ』で紹介されるまでわが国ではほとんど知るひとのなかったエウメネスなど、有名ではなくとも魅力的な生涯を送った人物のものがたりが収録されています。
いままでに4回ほど完全邦訳されたものが出版されましたが、現在流通しているのは西洋古典叢書版のみ。名著の訳がこれだけというのは少しさみしい気がします。
そこで英文から重訳するかたちで翻訳を試みることにしました。
底本はJohn Dryden(1859)のものと、Bernadotte Perrin(1919)を用いました。
沢山いる人物のなかで、まずエウメネス、つぎにニキアスの伝記を取り上げました。この「リュサンドロス伝」は第3弾です。
リュサンドロスは軍事大国スパルタの将軍で、ペロポネソス戦争を終わらせた人物です。ということは平和を愛する有徳者かといえばそうではありません。策謀を好み性格は苛烈、しかし現場の人気は高いという、いわば“悪のカリスマ”です。シチリア遠征の後からお話しがはじまるので、ちょうどニキアス伝の続きとして読むこともできます。どうぞ最後までお付き合いください。
※区切りの良いところまで翻訳するたびに投稿していくので、ぜんぶで何項目になるかわかりません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















