お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

呪王の鹿~南宮大社380年目の謎に挑む~
hoshinatasuku
ミステリー
関ヶ原の戦いで全焼し、再建から380年が経過した美濃一之宮・南宮大社。江戸初期より社殿に巧みに隠されてきた暗号に気付いた若き史学博士・坂城真。真は亡き祖母と交わした約束を思い出し解読に挑む。幼馴染みで役場観光係の八神姫香と共に謎解きを進めるのだが、解けたそれは戦国の世を収束させた徳川家への呪法だった。そして突如解読を阻む怪しい者が現れ、真は執拗に狙われてゆく。
【なろう・カクヨムでも同小説を投稿済】
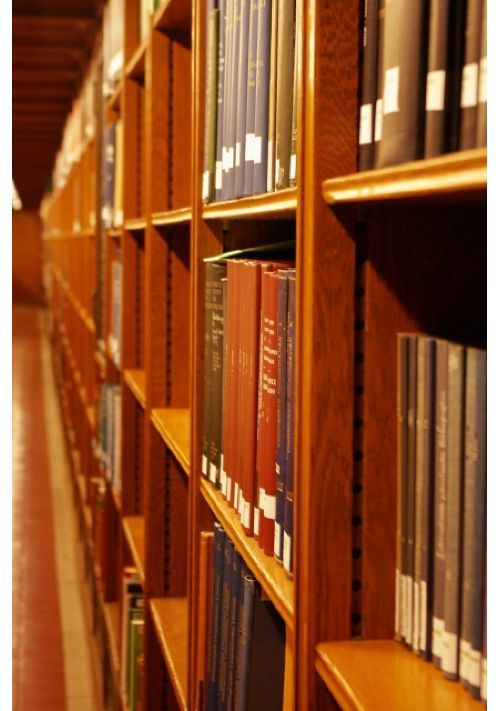
文学少女のラブレター
シャルロット(Charlotte)
ミステリー
俊介と真衣は仲良しの先輩と後輩。
読書好きな二人は、今日も高校の図書館でばったり会う。
そんなとき、同級生の真由が持ち込んだとある暗号。
俊介はその解読に取り組むが。。。
高校生たちの甘酸っぱい想いが揺れる、青春ミステリー【全3話】

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
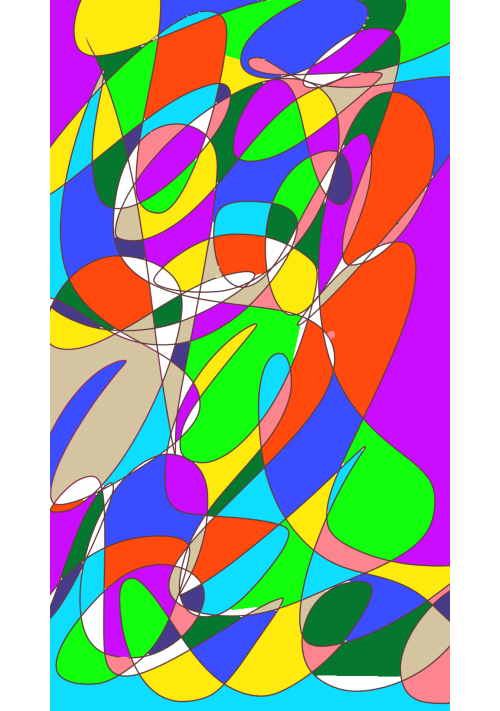

この満ち足りた匣庭の中で 二章―Moon of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
それこそが、赤い満月へと至るのだろうか――
『満ち足りた暮らし』をコンセプトとして発展を遂げてきたニュータウン、満生台。
更なる発展を掲げ、電波塔計画が進められ……そして二〇一二年の八月、地図から消えた街。
鬼の伝承に浸食されていく混沌の街で、再び二週間の物語は幕を開ける。
古くより伝えられてきた、赤い満月が昇るその夜まで。
オートマティスム、鬼封じの池、『八〇二』の数字。
ムーンスパロー、周波数帯、デリンジャー現象。
ブラッドムーン、潮汐力、盈虧院……。
ほら、また頭の中に響いてくる鬼の声。
逃れられない惨劇へ向けて、私たちはただ日々を重ねていく――。
出題篇PV:https://www.youtube.com/watch?v=1mjjf9TY6Io

ヘリオポリスー九柱の神々ー
soltydog369
ミステリー
古代エジプト
名君オシリスが治めるその国は長らく平和な日々が続いていた——。
しかし「ある事件」によってその均衡は突如崩れた。
突如奪われた王の命。
取り残された兄弟は父の無念を晴らすべく熾烈な争いに身を投じていく。
それぞれの思いが交錯する中、2人が選ぶ未来とは——。
バトル×ミステリー
新感覚叙事詩、2人の復讐劇が幕を開ける。

パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















