20 / 38
冬を越える形
2
しおりを挟む*
「白久亜学園の俳句部、か」
翌日。少女たちが座っていた縁側で、ひとりの男があぐらをかいている。組んだ脚の内側で眠る子犬が一匹。段ボールに入って捨てられていたのを彼が拾い、世話しているのだが、ふた月経って随分と大きくなった。雑種だが大型犬の血が流れているらしく、いずれ狼のように育つことを見越して「ロボ」と名付けたとのこと。
「公民館で小さな展示会を開いた際、隣のエリアで句が掲示されていたな。高校生三人だけの小さな部活動だった。短冊って言うんだっけ? あの細長い色紙に毛筆で書かれたものが並んでいた」
彼は近所に住んでいる写真家で、名を林堂玲という。夏が終わる頃に知り合い、秋にここで個展を開き、今も友人関係を築いている。撮影の対象は「自然」とのことで、気付けば旅に出ていることも多かったが、子犬を拾ってからは落ち着いた生活を送っているようだ。波久亜学園の生徒たちとは道ですれ違う程度の関係だが、胡桃とは既知の仲だった。彼女は彼の写真を買ったことがある。
林堂の話を受けて、疑問に思ったことを私は話した。
「高校生三人? 部員は四人だと聞いたが」
当初、胡桃は他のふたりを単なる同学年の友人だと紹介していたが、やがて部活動の仲間でもあるとも告げた。廃部同然だった俳句部に、友人を誘って入部したらしい。具体的な人数を尋ねたことはないが、昨日山茶花が「私たち四人だけで」と言っていたので、四人いるのだろう。寄り道が許されないのか、帰る方向が全くの反対なのか、姿を見たことはないが。
「四人だと言っていたのか。じゃあ、増えたんだろうな」
林堂はさらりと返し、納得した様子を見せる。しかし私はどこか違和感を覚えていた。まだ言葉にまとめることができないものの。しかし考え込んでいても仕方がない。嘘をつくようなことでもなし、と流した。
「しかし、高校生が俳句というのはなかなか渋いな」
ロボの赤い首輪を指先で弄びながら林堂は言う。結わえられた小さな鈴がチリチリと転がった。それでも子犬に起きる気配はない。私も近くへにじり寄り、その愛らしい顔を覗き込んだ。
「随分と熱心に取り組んでいるようだ。雅号で呼び合ったりもして」
「胡桃さんの雅号は何というんだ?」
「彼女の場合、胡桃という苗字をそのまま使っている。他の部員が百合だとか山茶花だとか名乗っているから、植物で揃えたのかな」
「胡桃は秋、百合は夏、山茶花は冬の季語だ」
ぼんやりと空を見上げてそう話す。私もつられて同じ場所を見れば、雀の飛び立つところが見えた。昨日もこんなことがあったな、と思い返す。このあたりの田圃にはいつも雀がいる。彼女らの去った後、山茶花の詠んだ句について少し勉強してみた。原則として俳句には季語が必要で、あの場合は寒雀――と思いきや、実はココアも冬の季語だ。情景や植物、自然現象に限らず、飲食物まで季語になるのは面白いと感じた。
おもむろに視線を下ろし、私の顔を見てから彼は話を続ける。
「残るひとりは春の季語を雅号にしているのかもな」
「……季節がばらけているのは偶然だと思うが」
最初から部員が四人止まりだと知った上で季節を割り当てたわけではあるまい。仲間内で立ち上げた同好会ではなく、あくまで学校の部活動なのだから。見知らぬ生徒が入部を望めば、無条件で受け入れることになる。そうなればすぐに崩れてしまう法則なんて採用しないだろう。私は、百合と山茶花の本名を思い出そうとした。一度は聞いたことがあるはずだ。案外と、胡桃のように本名由来のシンプルな名付けかもしれない。しかしどうにも引き出しを開けることができず、数秒後には諦めた。
「これを機に、君も初めてみたらどうだ」
「何を?」
「俳句だよ。心が豊かになる……んじゃないか? 俺も詳しくはないが」
突然の提案に面食らったが、一笑に付することもできない。俳句を嗜む彼女たちは、高校生とは思えないほどの落ち着きと気品を持ち合わせていた。もちろん上流家庭の令嬢という前提はあるものの、異性の目がない女子校育ちなら、もう少し粗野な振る舞いをしてもおかしくはない。とはいえ。
「俳句じゃ腹は満たせないからなあ……」
現在の私は、有り体に言えば無職だ。家具屋のアルバイトを細々と続けているものの、所属していた劇団が解散し、劇団員という肩書も失った。たった一度だけ自宅で個展を開いたというのは、職とカウントして良いものか。
林堂は座った状態のまま、ぐるりと当たりを見渡した。この縁側は当然ながら和室に繋がっており、襖で仕切られた先にはサンルームがある。
「この和室に書を展示すれば、俳句を収入に繋げることができるんじゃないか?」
彼の提案を今度こそは一笑に付する。そういったことは依頼があってから話すものだ。こんな田舎の崩れかけた民家に、誰が大事な作品を預けるものか。そう考えてすぐ、目の前の男が二ヶ月前にここで個展を開いたばかりであることを思い出した。もっとも、あれは慈善事業のようなものだったのだが。いずれは綺麗に改築して何かに使いたいと話す私のために、練習台になってくれただけだ。
「声が掛からない限り、そんな企画は無理だな。こちらから提案できるほど立派な設備でもないし。立地もゴミだ」
「ゴミなのか。近くに波久亜学園があるが」
「学生をターゲットにした展示をするつもりか? 確かにあそこは大学まで一貫だから、所属する人数は桁違いだが……」
林堂の膝の間で、子犬がもぞもぞと身じろぎをする。やっと目を覚ましたようだ。その動きに気を取られながらも、私は少しだけ真剣に考えてみた。生徒たちのためにここを使うなら何ができるだろう? 勉強になるような展示物を集めて、校外学習に利用してもらうとか? 貴重な資料を扱うためのノウハウなどない。私の持っている人脈は、あちこちに散った元劇団員、家具屋のボス、そしてここにいるフリーの写真家くらいだ。林堂はやけに博識なので頼りになるが、そう何度も世話にはなれない。
「いっそ、学校の方から声を掛けてくれたらいいのにな」
私の言葉に、今度は林堂が笑う番だった。なんだ、君だって現状を理解しているじゃないか。声には出さずに反駁する。壁はひび割れ、全体が東側へ傾き、最大限の世辞を込めても「ノスタルジィ」と称することしかできない。こんなみすぼらしい民家と波久亜学園に繋がりが生じるなど、それこそ天地が返るような出来事なのだ。
目を覚ました子犬がちりりと鈴を鳴らし、身震いをする。小さな口を最大限に開けてあくびをすると、庭先を舞う枯葉に向かって無意味に鳴いた。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

日給二万円の週末魔法少女 ~夏木聖那と三人の少女~
海獺屋ぼの
ライト文芸
ある日、女子校に通う夏木聖那は『魔法少女募集』という奇妙な求人広告を見つけた。
そして彼女はその求人の日当二万円という金額に目がくらんで週末限定の『魔法少女』をすることを決意する。
そんな普通の女子高生が魔法少女のアルバイトを通して大人へと成長していく物語。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

フリー台本と短編小説置き場
きなこ
ライト文芸
自作のフリー台本を思いつきで綴って行こうと思います。
短編小説としても楽しんで頂けたらと思います。
ご使用の際は、作品のどこかに"リンク"か、"作者きなこ"と入れていただけると幸いです。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
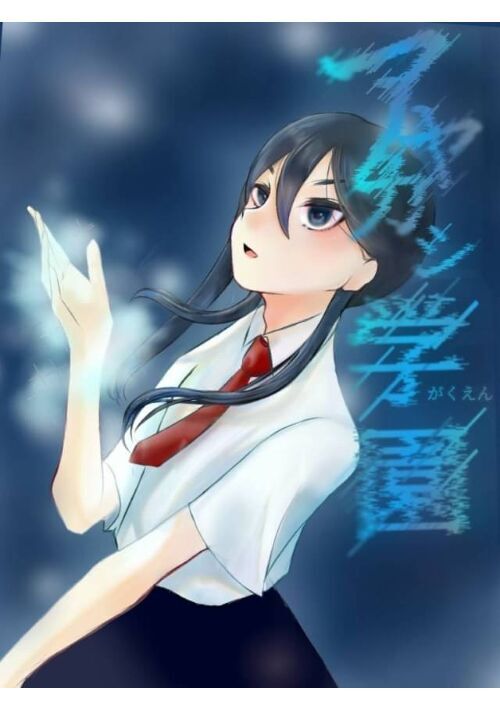
アヤカシ学園 N o.2
白凪 琥珀
ライト文芸
私立六花学園に転校してきた、妖怪雨女の清水葵。消極的で引っ込み思案だったが、クラスメイトの冬馬渚や同室の霧島蕾華など個性豊かな友達ができ、少しずつ葵に変化が見える。
3人1チームの実技訓練が始まる!
だが、妖術のコントロールが苦手な葵は
この訓練に不安を感じていて、、

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

揺らめくフレッシュグリーン
マスカレード
ライト文芸
少し天然な高校生青木|理花《ことは》は、親友の岸野薫子と同じ同級生の瀬尾大智に恋をした。
友人からライバルに変った時に生じた闘争心や嫉妬心に揺り動かされる二人。そして思わぬ事態が発生し、大智が見せた勇気ある行動。青春時代の痛みや熱い胸の思いを時にコミカルに、そして時に深く問題を投げかける。
表紙絵は、マカロンKさんのフリーアイコンを使用しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















