お気に入りに追加
12
あなたにおすすめの小説

闇に蠢く
野村勇輔(ノムラユーリ)
ホラー
関わると行方不明になると噂される喪服の女(少女)に関わってしまった相原奈央と相原響紀。
響紀は女の手にかかり、命を落とす。
さらに奈央も狙われて……
イラスト:ミコトカエ(@takoharamint)様
※無断転載等不可

あなたになりたかった
月琴そう🌱*
キャラ文芸
カプセルから生まれたヒトとアンドロイドの物語
一人のカプセルベビーに一体のアンドロイド
自分たちには見えてない役割はとても重い
けれどふたりの関係は長い年月と共に他には変えられない大切なものになる
自分の最愛を見送る度彼らはこう思う
「あなたになりたかった」

佐世保黒猫アンダーグラウンド―人外ジャズ喫茶でバイト始めました―
御結頂戴
キャラ文芸
高校一年生のカズキは、ある日突然現れた“黒い虎のような猫”ハヤキに連れられて
長崎の佐世保にかつて存在した、駅前地下商店街を模倣した異空間
【佐世保地下異界商店街】へと迷い込んでしまった。
――神・妖怪・人外が交流や買い物を行ない、浮世の肩身の狭さを忘れ楽しむ街。
そんな場所で、カズキは元の世界に戻るために、種族不明の店主が営むジャズ喫茶
(もちろんお客は人外のみ)でバイトをする事になり、様々な騒動に巻き込まれる事に。
かつての時代に囚われた世界で、かつて存在したもの達が生きる。そんな物語。
--------------
主人公:和祁(カズキ)。高校一年生。なんか人外に好かれる。
相棒 :速来(ハヤキ)。長毛種で白い虎模様の黒猫。人型は浅黒い肌に金髪のイケメン。
店主 :丈牙(ジョウガ)。人外ジャズ喫茶の店主。人当たりが良いが中身は腹黒い。
※字数少な目で、更新時は一日に数回更新の時もアリ。
1月からは更新のんびりになります。

(同級生+アイドル÷未成年)×オッサン≠いちゃらぶ
まみ夜
キャラ文芸
様々な分野の専門家、様々な年齢を集め、それぞれ一芸をもっている学生が講師も務めて教え合う教育特区の学園へ出向した五十歳オッサンが、十七歳現役アイドルと同級生に。
【ご注意ください】
※物語のキーワードとして、摂食障害が出てきます
※ヒロインの少女には、ストーカー気質があります
※主人公はいい年してるくせに、ぐちぐち悩みます
第二巻(ホラー風味)は現在、更新休止中です。
続きが気になる方は、お気に入り登録をされると再開が通知されて便利かと思います。
表紙イラストはAI作成です。
(セミロング女性アイドルが彼氏の腕を抱く 茶色ブレザー制服 アニメ)

横浜で空に一番近いカフェ
みつまめ つぼみ
キャラ文芸
大卒二年目のシステムエンジニア千晴が出会ったのは、千年を生きる妖狐。
転職を決意した千晴の転職先は、ランドマークタワー高層にあるカフェだった。
最高の展望で働く千晴は、新しい仕事を通じて自分の人生を考える。
新しい職場は高層カフェ! 接客業は忙しいけど、眺めは最高です!

戦国姫 (せんごくき)
メマリー
キャラ文芸
戦国最強の武将と謳われた上杉謙信は女の子だった⁈
不思議な力をもって生まれた虎千代(のちの上杉謙信)は鬼の子として忌み嫌われて育った。
虎千代の師である天室光育の勧めにより、虎千代の中に巣食う悪鬼を払わんと妖刀「鬼斬り丸」の力を借りようする。
鬼斬り丸を手に入れるために困難な旅が始まる。
虎千代の旅のお供に選ばれたのが天才忍者と名高い加当段蔵だった。
旅を通して虎千代に魅かれていく段蔵。
天界を揺るがす戦話(いくさばなし)が今ここに降臨せしめん!!

月宮殿の王弟殿下は怪奇話がお好き
星来香文子
キャラ文芸
【あらすじ】
煌神国(こうじんこく)の貧しい少年・慧臣(えじん)は借金返済のために女と間違えられて売られてしまう。
宦官にされそうになっていたところを、女と見間違うほど美しい少年がいると噂を聞きつけた超絶美形の王弟・令月(れいげつ)に拾われ、慧臣は男として大事な部分を失わずに済む。
令月の従者として働くことになったものの、令月は怪奇話や呪具、謎の物体を集める変人だった。
見えない王弟殿下と見えちゃう従者の中華風×和風×ファンタジー×ライトホラー
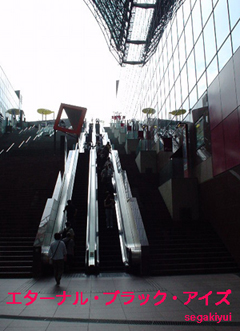
『エターナル・ブラック・アイズ』
segakiyui
キャラ文芸
『年齢・性別・経験問わず。当方親切に指導いたしますので、安心安全、ご心配無用。保険も使えます』。マンションのポストに入っていた『占い師求む』のチラシに導かれて、鷹栖瑞穂は『エターナル・アイズ』の占い師になる。家族を失った炎の記憶がつながる事件に、同僚の『グリーン・アイズ』とともに立ち向かう。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















