12 / 26
三話 犬
3
しおりを挟む
「俺はサツキさんに拾われて救われたので……だから、俺にとってサツキさんは飼い主というか、ご主人様というか。ご主人様の言いつけを守って最低限の生活ができれば充分だって、それで満足する忠犬になれって、自分をいつも戒めてました」
俺の下手な説明を聞いたサツキさんは、瞠目してからしょんぼりと肩を落とす。
「そっかあ……君がそんな風に考えたなんて、想像もしたことなかったよ。ぼくは哲くんと対等な立ち場の人間でありたいと思ってたけど、雇用の関係上それは難しいよね。気をつけて接してきたつもりだったけど、哲くんにそんな辛い思いをさせてたなんて気づかなかった。ぼくは雇い主失格だなあ。ごめん……」
「いっいや、俺が勝手にそう思ってただけなんで! サツキさんは良い雇い主ですよ」
意気消沈して頭を垂れるサツキさん。焦って両肩を支えれば、彼はゆらりと面を上げて力なく笑ってみせる。
「本当? なんかぼく、言わせてない?」
「そんなことないです。だって俺」
――あなたのことが、本当に好きなんですよ。
そう続けることを、躊躇ってしまう。
小首を傾げて「?」の表情をする雇い主に見つめられ、思わず視線を逸らす。場を取り繕おうと、話題を変えることにした。
「あの、そういえばさっき、好きな人って……」
「あー、あれは……突然変なこと言ってごめん。驚かせちゃったよね」
サツキさんは歯切れ悪く、ものすごく気まずそうな顔をして言う。ああ、と俺はやっと諒解した。何者かに取り憑かれた助手を助けるため、彼は敢えて突拍子もないことを口にしたのだ、と。俺が好きだなんて、真実であるはずがない。当然のことだ。
それなのに、視界がじわりと滲むのが情けない。俺がサツキさんと釣り合うはずがないのに。
「いえ……そんな」
「ずっと黙ってたけど、ぼくね……哲くんのこと好きなんだ。その、性的な意味で」
ほら見ろ、サツキさんは俺のことを性的な意味で好きで……え?
いま、彼は何と言った? 呆気に取られるとはこのことを言うのだろう。ぽかん、と馬鹿みたいに口を開けて相手を見つめる。
両手を無意味にわたわたと動かし、頬を紅潮させたサツキさんがそこにいた。
「こ、こんなこと急に言われても困るよね! 本当にごめん。あ、最初に声かけたときは完全にビジネスライクな気持ちで、邪な感情はなかったんだよ。信用ないと思うけど」
「あ、いや……そんなことは」
「除霊を手伝ってもらってるうちに、哲くんの無防備な顔とか、綺麗な項とか見るとムラムラ来ちゃうようになって……あ、でも無理にヤりたいとかそういう感情はないから! できれば一緒に気持ちよくなりたいっていうか……あーもう、ぼく変なこと言ってるね……」
いつも飄々としているサツキさんがあからさまに狼狽えている。ほとんど頭を抱えそうになるほど混乱している彼を見るのは初めてだった。しかも、俺に関することでこんな風になっているのだ。信じられなかった。
サツキさんの独白は自虐的な方向に転がっていく。
「除霊のときもね……哲くんを哲くんとして抱きたいから、降ろした人の名前で呼ばなかったりしてたんだ。哲くんには意識がないから、関係ないのに……気持ち悪いよね、そういうの」
「え」思いがけない告白に目を瞠った。言われてみれば情事の際、俺は確かに体を貸した人の名で呼ばれた覚えがない。サツキさんがそんなことを考えていたなんて。
俺は少々ばつが悪い心持ちになりながら、胸に仕舞っていた事実を伝えた。
「気持ち悪くないですよ。それに、俺も隠してたことがあります。降霊してるとき、ほんの少しだけだけど自意識があるんです。俺のままでいるとサツキさんがやりにくいかなと思って、今まで嘘ついてました。本当に、すみません」
「えっ、そうなの? うわー、恥ずかし……」
サツキさんはとうとう、両手で顔を覆ってしまう。
「じゃあ、ぼくが除霊をわざと長引かせようとしてたのも……分かってたってことだよね?」
「あ、それってマユミさんのときの……?」
「あああ、うん、そう……。哲くんの反応が可愛くて、もっと見たいと思っちゃって、それであんなことを――」
サツキさんはあのとき、俺が達しそうになるのを鈴口を塞ぐことで防いだ。あれはつまり、俺と繋がっている時間を引き伸ばそうとしたからなのか。祓い屋としては非難されるべき行為なのかもしれないが、それでも。
嬉しいと思ってしまった。だって、ずっと一方通行だと信じていた矢印が、相手からも自分に向かってきていたなんて、誰が想像するだろう。
そのとき不意に、遥か遠くの方から犬の遠吠えがかすかに響いてきた。瞬間、理解する。俺はサツキさんを噛みたいと思っていたわけではない、ということを。
この人■、■■たい――そうではない。
この人■、■■たい。
俺は本当は伝えたかったのだ。俺がどれだけ、サツキさんに好意を抱いているかを。たとえそれが、二人の関係を決定的に変え、自らの立場を危うくしてしまうことであっても。
「あの、俺も。サツキさんのこと、ずっと好きでした」
ほろりと気負いなく零れた本音。
刹那、サツキさんの目が大きく見開かれる。「えっ!?」と頓狂な声が上げ、相手が弾かれたように立ち上がる。鼻先が触れ合いそうな距離に気後れし、反射的に一歩下がったところを、相手がずいと詰めてきた。ち、近いです、サツキさん。
いつもは脱力して垂れぎみになっているサツキさんの眉が、きりりと平行に近くなっていた。緊張感漲る、迫真の表情である。
「好きって、ほんとう?」
「はい。たぶん、俺の方が先に好きになってたと思います。だからあの、全部……嫌じゃないですよ。むしろ、嬉しいというか……サツキさんに好きと言ってもらえるなんて、信じられないくらいです。――サツキさんのことを考えて、一人でしたりしてたので」
息を飲む気配がする。自慰のオカズにしているだなんて引かせてしまいそうだが、サツキさんも腹の内を明かしてくれたので、これでイーブンだ。
そろりと手が伸びてきて、こちらの指先をやんわりと握りこむ。
「そうだったんだね。ぼくたち、知らないあいだに両想いだった……ってことかあ」
「そうみたい、ですね」
腕を差し伸べれば抱擁できる距離で俺たちは見つめ合う。いつしか甘い雰囲気に飲まれていて、慣れない空気にそわそわするものの、それでも目を逸らそうとは思わない。
これまで好意を表に出さないよう、必死に圧し殺してきたけれど、いま相手に対する互いの感情は開示されてしまった。
じゃあ――もう我慢しなくていいってこと?
「ぼく、もう我慢しなくていい……?」
俺の心理を読んだような言葉にはっとする。サツキさんは切ないほど真摯な、それでいてぎらぎらした瞳を俺に向けていた。こちらがうなずききらないうちに、性急に唇が重なる。
ぶわりと体温が上がって、胸の内側に大輪の花が次々と咲くように思えた。経験したことのない多幸感にくらくらする。
「ん、ふ……」
サツキさんの指がシャツの裾から中に入ってくる。そこで気づいた。さっきまで自分がうなされながら眠っていて、汗びっしょりで飛び起きたことを。
慌てて俺よりやや小柄な体躯を押し退ける。
「しゃ、シャワー! シャワー浴びさせて下さい、いま汗臭いと思うんで……!」
「ぼくは別に気にしないけど……哲くんが気になるなら。あ、そうだ」
サツキさんが良いことを思いついたと言わんばかりににぱっと笑う。
「一緒に入ろっか」
「えっ」
「駄目かなあ? まだ今の哲くんを一人にするのは心配だし……何もしないから。ねえ、いいでしょ?」
うう、狡い。そんな上目遣いでねだられたら断れるはずがない。
ばくばくと存在を主張する心臓に鎮まれ鎮まれと念じながら、俺は小さく首を縦に振った。
俺の下手な説明を聞いたサツキさんは、瞠目してからしょんぼりと肩を落とす。
「そっかあ……君がそんな風に考えたなんて、想像もしたことなかったよ。ぼくは哲くんと対等な立ち場の人間でありたいと思ってたけど、雇用の関係上それは難しいよね。気をつけて接してきたつもりだったけど、哲くんにそんな辛い思いをさせてたなんて気づかなかった。ぼくは雇い主失格だなあ。ごめん……」
「いっいや、俺が勝手にそう思ってただけなんで! サツキさんは良い雇い主ですよ」
意気消沈して頭を垂れるサツキさん。焦って両肩を支えれば、彼はゆらりと面を上げて力なく笑ってみせる。
「本当? なんかぼく、言わせてない?」
「そんなことないです。だって俺」
――あなたのことが、本当に好きなんですよ。
そう続けることを、躊躇ってしまう。
小首を傾げて「?」の表情をする雇い主に見つめられ、思わず視線を逸らす。場を取り繕おうと、話題を変えることにした。
「あの、そういえばさっき、好きな人って……」
「あー、あれは……突然変なこと言ってごめん。驚かせちゃったよね」
サツキさんは歯切れ悪く、ものすごく気まずそうな顔をして言う。ああ、と俺はやっと諒解した。何者かに取り憑かれた助手を助けるため、彼は敢えて突拍子もないことを口にしたのだ、と。俺が好きだなんて、真実であるはずがない。当然のことだ。
それなのに、視界がじわりと滲むのが情けない。俺がサツキさんと釣り合うはずがないのに。
「いえ……そんな」
「ずっと黙ってたけど、ぼくね……哲くんのこと好きなんだ。その、性的な意味で」
ほら見ろ、サツキさんは俺のことを性的な意味で好きで……え?
いま、彼は何と言った? 呆気に取られるとはこのことを言うのだろう。ぽかん、と馬鹿みたいに口を開けて相手を見つめる。
両手を無意味にわたわたと動かし、頬を紅潮させたサツキさんがそこにいた。
「こ、こんなこと急に言われても困るよね! 本当にごめん。あ、最初に声かけたときは完全にビジネスライクな気持ちで、邪な感情はなかったんだよ。信用ないと思うけど」
「あ、いや……そんなことは」
「除霊を手伝ってもらってるうちに、哲くんの無防備な顔とか、綺麗な項とか見るとムラムラ来ちゃうようになって……あ、でも無理にヤりたいとかそういう感情はないから! できれば一緒に気持ちよくなりたいっていうか……あーもう、ぼく変なこと言ってるね……」
いつも飄々としているサツキさんがあからさまに狼狽えている。ほとんど頭を抱えそうになるほど混乱している彼を見るのは初めてだった。しかも、俺に関することでこんな風になっているのだ。信じられなかった。
サツキさんの独白は自虐的な方向に転がっていく。
「除霊のときもね……哲くんを哲くんとして抱きたいから、降ろした人の名前で呼ばなかったりしてたんだ。哲くんには意識がないから、関係ないのに……気持ち悪いよね、そういうの」
「え」思いがけない告白に目を瞠った。言われてみれば情事の際、俺は確かに体を貸した人の名で呼ばれた覚えがない。サツキさんがそんなことを考えていたなんて。
俺は少々ばつが悪い心持ちになりながら、胸に仕舞っていた事実を伝えた。
「気持ち悪くないですよ。それに、俺も隠してたことがあります。降霊してるとき、ほんの少しだけだけど自意識があるんです。俺のままでいるとサツキさんがやりにくいかなと思って、今まで嘘ついてました。本当に、すみません」
「えっ、そうなの? うわー、恥ずかし……」
サツキさんはとうとう、両手で顔を覆ってしまう。
「じゃあ、ぼくが除霊をわざと長引かせようとしてたのも……分かってたってことだよね?」
「あ、それってマユミさんのときの……?」
「あああ、うん、そう……。哲くんの反応が可愛くて、もっと見たいと思っちゃって、それであんなことを――」
サツキさんはあのとき、俺が達しそうになるのを鈴口を塞ぐことで防いだ。あれはつまり、俺と繋がっている時間を引き伸ばそうとしたからなのか。祓い屋としては非難されるべき行為なのかもしれないが、それでも。
嬉しいと思ってしまった。だって、ずっと一方通行だと信じていた矢印が、相手からも自分に向かってきていたなんて、誰が想像するだろう。
そのとき不意に、遥か遠くの方から犬の遠吠えがかすかに響いてきた。瞬間、理解する。俺はサツキさんを噛みたいと思っていたわけではない、ということを。
この人■、■■たい――そうではない。
この人■、■■たい。
俺は本当は伝えたかったのだ。俺がどれだけ、サツキさんに好意を抱いているかを。たとえそれが、二人の関係を決定的に変え、自らの立場を危うくしてしまうことであっても。
「あの、俺も。サツキさんのこと、ずっと好きでした」
ほろりと気負いなく零れた本音。
刹那、サツキさんの目が大きく見開かれる。「えっ!?」と頓狂な声が上げ、相手が弾かれたように立ち上がる。鼻先が触れ合いそうな距離に気後れし、反射的に一歩下がったところを、相手がずいと詰めてきた。ち、近いです、サツキさん。
いつもは脱力して垂れぎみになっているサツキさんの眉が、きりりと平行に近くなっていた。緊張感漲る、迫真の表情である。
「好きって、ほんとう?」
「はい。たぶん、俺の方が先に好きになってたと思います。だからあの、全部……嫌じゃないですよ。むしろ、嬉しいというか……サツキさんに好きと言ってもらえるなんて、信じられないくらいです。――サツキさんのことを考えて、一人でしたりしてたので」
息を飲む気配がする。自慰のオカズにしているだなんて引かせてしまいそうだが、サツキさんも腹の内を明かしてくれたので、これでイーブンだ。
そろりと手が伸びてきて、こちらの指先をやんわりと握りこむ。
「そうだったんだね。ぼくたち、知らないあいだに両想いだった……ってことかあ」
「そうみたい、ですね」
腕を差し伸べれば抱擁できる距離で俺たちは見つめ合う。いつしか甘い雰囲気に飲まれていて、慣れない空気にそわそわするものの、それでも目を逸らそうとは思わない。
これまで好意を表に出さないよう、必死に圧し殺してきたけれど、いま相手に対する互いの感情は開示されてしまった。
じゃあ――もう我慢しなくていいってこと?
「ぼく、もう我慢しなくていい……?」
俺の心理を読んだような言葉にはっとする。サツキさんは切ないほど真摯な、それでいてぎらぎらした瞳を俺に向けていた。こちらがうなずききらないうちに、性急に唇が重なる。
ぶわりと体温が上がって、胸の内側に大輪の花が次々と咲くように思えた。経験したことのない多幸感にくらくらする。
「ん、ふ……」
サツキさんの指がシャツの裾から中に入ってくる。そこで気づいた。さっきまで自分がうなされながら眠っていて、汗びっしょりで飛び起きたことを。
慌てて俺よりやや小柄な体躯を押し退ける。
「しゃ、シャワー! シャワー浴びさせて下さい、いま汗臭いと思うんで……!」
「ぼくは別に気にしないけど……哲くんが気になるなら。あ、そうだ」
サツキさんが良いことを思いついたと言わんばかりににぱっと笑う。
「一緒に入ろっか」
「えっ」
「駄目かなあ? まだ今の哲くんを一人にするのは心配だし……何もしないから。ねえ、いいでしょ?」
うう、狡い。そんな上目遣いでねだられたら断れるはずがない。
ばくばくと存在を主張する心臓に鎮まれ鎮まれと念じながら、俺は小さく首を縦に振った。
0
お気に入りに追加
35
あなたにおすすめの小説
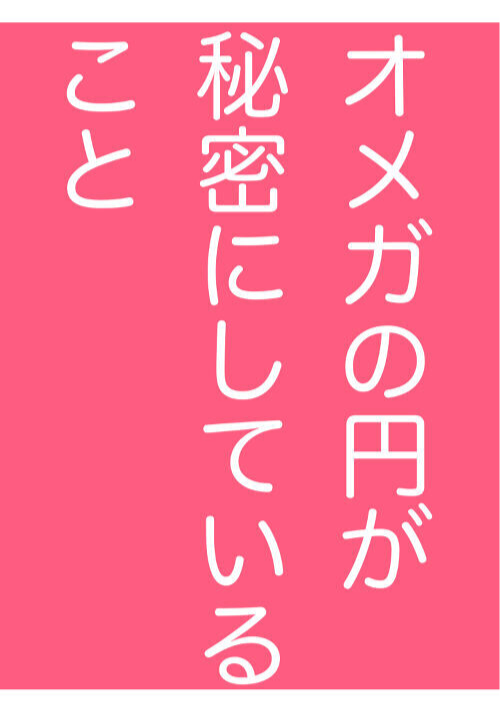
【完結】オメガの円が秘密にしていること
若目
BL
オメガの富永円(28歳)には、自分のルールがある。
「職場の人にオメガであることを知られないように振る舞うこと」「外に出るときはメガネとマスク、首の拘束具をつけること」「25年前に起きた「あの事件」の当事者であることは何としてでも隠し通すこと」
そんな円の前に、純朴なアルファの知成が現れた。
ある日、思いがけず彼と関係を持ってしまい、その際に「好きです、付き合ってください。」と告白され、心は揺らぐが……
純朴なアルファ×偏屈なオメガの体格差BLです
18禁シーンには※つけてます

【完結】スーツ男子の歩き方
SAI
BL
イベント会社勤務の羽山は接待が続いて胃を壊しながらも働いていた。そんな中、4年付き合っていた彼女にも振られてしまう。
胃は痛い、彼女にも振られた。そんな羽山の家に通って会社の後輩である高見がご飯を作ってくれるようになり……。
ノンケ社会人羽山が恋愛と性欲の迷路に迷い込みます。そして辿り着いた答えは。
後半から性描写が増えます。
本編 スーツ男子の歩き方 30話
サイドストーリー 7話
順次投稿していきます。
※サイドストーリーはリバカップルの話になります。
※性描写が入る部分には☆をつけてあります。
10/18 サイドストーリー2 亨の場合の投稿を開始しました。全5話の予定です。

しのぶ想いは夏夜にさざめく
叶けい
BL
看護師の片倉瑠維は、心臓外科医の世良貴之に片想い中。
玉砕覚悟で告白し、見事に振られてから一ヶ月。約束したつもりだった花火大会をすっぽかされ内心へこんでいた瑠維の元に、驚きの噂が聞こえてきた。
世良先生が、アメリカ研修に行ってしまう?
その後、ショックを受ける瑠維にまで異動の辞令が。
『……一回しか言わないから、よく聞けよ』
世良先生の哀しい過去と、瑠維への本当の想い。

【完結】遍く、歪んだ花たちに。
古都まとい
BL
職場の部下 和泉周(いずみしゅう)は、はっきり言って根暗でオタクっぽい。目にかかる長い前髪に、覇気のない視線を隠す黒縁眼鏡。仕事ぶりは可もなく不可もなく。そう、凡人の中の凡人である。
和泉の直属の上司である村谷(むらや)はある日、ひょんなことから繁華街のホストクラブへと連れて行かれてしまう。そこで出会ったNo.1ホスト天音(あまね)には、どこか和泉の面影があって――。
「先輩、僕のこと何も知っちゃいないくせに」
No.1ホスト部下×堅物上司の現代BL。


初恋はおしまい
佐治尚実
BL
高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。
高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。
※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。
今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















