47 / 51
第47章 刺客
しおりを挟む
結局、ただ死を待つだけの十三人の男女の切なる思いに押し切られたナナは、彼らに闇の洗礼を与えるしかなかった。三日間に分けて行われたナナの吸血行為で十人が生き残り、更にその中からマリクを含めて八人の人間が彼らの思惑通り、無事にヴァンパイアへと転生を果たした。もちろんナナはシンガポールで若い警官の血を呑んで我を忘れた経験から、自身の身体を頑丈な鎖で何重にも縛らせた上で、銀の弾が詰まった散弾銃で狙わせるという万全の対策を講じて吸血行為を行った。毎夜、人目に付かない深夜の屋内競技場の資材管理部屋で行われたそれは何らかの秘密結社の儀式を想わせた。その行為の際、ナナの策は功を奏して吸血の影響で無意識に暴れ出す自身の身体を何とか抑え込むことができた。もちろん銀の散弾で楽に死なせてもらえるという密かな思いもあったが、それだけは成功しなかった。だが二人の志願者だけは違った。彼らはヴァンパイアに転生して間もなく、血への渇望をナナのように理性と鎖ではどうにも抑えられなくなり、これ以上手が付けられなくなる寸前に他の転生者によって命を絶たれた。そしてすべてが終わった後、ナナは転生前と転生後に犠牲になった彼ら五人も覚悟の上だったとマリクや新たな仲間たちから言葉をかけられた。だが、そんなものは何の慰めにもならなかった。直接的にせよ間接的にせよナナの吸血行為が彼らの命を奪ったことに変わりがなかったからだ。ただ一つだけ計算違いがあった。映画や本で馴れ親しんだヴァンパイアとは反対に、自らの意思において行った一連の吸血行為以来、ナナの心は急速に疲弊し、その影響は身体まで著しく蝕みはじめた。人間であろうとすればするほど、もっと血を呑みたいという衝動を抑えれば抑えるほど、その影響は大きく、一日の中で何度も襲ってくる内臓を捩じ切られるような激痛に立っていられなくなることもしばしばだった。だからといって身も心も完全なヴァンパイアになってしまえば楽になるのにとは微塵も考えなかった。そんなことより、ナナはいっそのこと自分も転生後におかしくなった二人のように殺害してもらえれば、どんなに楽になれるのだろうかと夢想した。それほど、彼女の心だけは人間でい続けたいという執着と、人間の血を吸う嫌悪感は強いものだったのだ。そんな日々の中、彼女の理性は身体を苛む激痛を辛うじて受け流すことに今のところ成功していた、それがいつまで続くかは彼女自身にもわからなかったが。
そして今回で三回目となる新生ヴァンパイアのミーティングが薄暗い資材管理部屋の片隅ではじまった。
「僕らが転生して、もう十日目だよ。もっと仲間を増やさなきゃ」
開口一番、顔にまだあどけなさが残る若いヴァンパイアが賛同を促すように仲間たちの顔を見回し、最後にナナのやつれ切った顔に視線を止めた。ナナは物憂げに頭を上げると聞きたくもないという仕草で片手を振って、その意見を退けた。それを見た若いヴァンパイアは、今度は向かいに腰掛けている綺麗な赤毛をボブに切りそろえた年かさの女ヴァンパイアに意見を求めた。
「アンナはどうなの?」
「そうね……」
「『そうね』だけじゃ、わかんないよ」
「ケン。あなたの言うとおりだと思うわ。だから、ナナがやってくれないんだったら、次は私らがやるしかないわね……」
消極的なアンナの賛同に、その場が静まり返った。つい二日前も味方を増やす負担をナナばかりにかけまいと吸血行為を行った二人の仲間がその直後からおかしくなったからだ。変異したH5N1ウィルスに侵された人血が影響したのか、ナナにだけその耐性があったのか真相は全くわからなかったが、吸血を行った方も、吸血された方も完全に理性をなくし、手が付けられないほど凶暴化したため、銀の散弾による仲間の殺害を余儀なくされていたのだ。
「卑怯な言い方だな、ケン。そんな言い方で選択を迫るものじゃない」
沈黙を破ってナナを擁護した壮年のヴァンパイアにケンがすぐさま反論した。
「でも他に方法がないよ」ケンと呼ばれた若いヴァンパイアはまくし立てた。「僕らが転生したのは何のためだい。ブロドリップが言ったように奴の仲間になるためか。そんな馬鹿な。奴を殺すためだろ?!」
「いい加減にしろ。ナナはヴァンパイア・ハンター製造機ではなかろう!」壮年のヴァンパイアは白髪交じりの立派な口髭を震わせた。「彼女は儂らの命を救ってくれた恩人だぞ。しかし彼女を見たまえ。儂らの要求を喜んでいるように見えるかね?」
「でも」と、小鼻にピアスをした若い女ヴァンパイアが口を挟んだ。「ケンの言い分にも一理あるわ」
「みんな落ち着けよ。毎回仲間割れするために集まってるわけじゃないんだから」
マリクの言葉に再び沈黙が訪れた。
「そうね」年かさのアンナが口を開いた。「さっきのは私の失言だったわ。許してね、ナナ」
「なに言ってんの、アンナ。子どもの敵討ちをするんじゃなかったのかい。それはもう無しにすんの。僕は誰がなんて言おうと両親の敵を取るぞ!」
「やめなよ、ケン」
若い女ヴァンパイアが堪りかねて再び口を挟んだが、ケンは止まらなかった。
「いや、やめない。奴は両親を殺したとき、僕にはっきりこう言ったんだ。『最近は食べすぎなのか、どんな人間も旨くなくてねぇ』って。しかも欠伸をかみ殺しながらさ。それって何なの。奴にとって人間はスナック菓子以下なのかい。あんたたちだって似たような目に遭わされてきたんだろ!」ケンは先ほど自分をたしなめた口髭のヴァンパイアを指差した。「ニコライだって、目の前で息子と孫が殺された恨みを忘れたわけ?!」
「よくお聞き!」アンナはニコライが口を開く前に声を荒げた。そして鋭い眼光でケンを射すくめた。「人を人とも思わない。目的のために仲間に対しても手段を択ばない。そんなこと、まるであのブロドリップと同じじゃないか。私たちは、あの悪魔を滅ぼすためにはどんなことだってすると誓ったさ。もちろん、そのための犠牲だって厭わない。だからヴァンパイアになった。それに転生に失敗して仲間も死んだ。でも、これは違うわよ。奴と闘う前から、それとわかった上で恩人に死ぬかもしれないような苦痛を強いるなんて」
「馬鹿じゃないの、アンナは!」
「ケン!」ニコライが掴みかからんばかりにケンに詰め寄ったが、彼は怯まなかった。
「そうかい。そうかい。わかったよ。色々言いながら、結局あんたたち年寄りは怖いんだ。一度命を取り留めたら、また失うのは恐ろしいからね。いいさ。やらないなら、やらないで。でも僕は一人でもやってやるからな」
「誰もやらないなんて言ってないぞ」
「へぇ」マリクの反論にケンは見下したような視線を向けた。「じゃぁ、あんたがリスクを承知でナナの代わりに仲間を増やすって言うの?」
「俺はやらない。ナナもやらない。ここにいる誰も仲間を増やすことで、もう危険に晒されることはしない」
「はぁ。あんた、もっと賢いと思ってたよ」
「臨機応変さに欠けるガキのお前よりはな」マリクは声を上げかけたケンを制して言葉を続けた。「攻撃はここにいる俺たちだけでやる」
ざわめきの中に疑念と不満が飛び交った。それが少し収まるのを待って、マリクは再び口を開いた。
「みんな聞いてくれ。数には数で対抗しようとしたのが、そもそもの間違いだ。最初からブロドリップの軍団に匹敵する数を揃えることなんて無理だったんだ。だから、こっちは少人数で仕掛けることにする」
「それこそ犬死だ」
「だったら君は抜けてかまわんよ。儂はマリクの意見に賛成だ」
ニコライの静かな物言いがケンの反論を封じたが、若い女ヴァンパイアが疑問を投げかけた。
「じゃぁ、いま病気で苦しんでる連中は、あたしたちみたいに反撃の機会も貰えずに、ただ死んでくだけなの。あたしみたいに生き残った家族のために、ヴァンパイアになって、ブロドリップを斃したいっていう奴もいるはずなのに……」
その場の沈黙が何よりの答えだった。その空気に堪えかねたかのようにニコライが話を先に進めた
「彼らの恨みも儂らで晴らす。で、作戦はマリク?」
「手下どもの目を盗んで奴の根城に潜り込む。そして奴だけをピンポイントで狙う」と、マリク。「奇襲になるから、もちろん太陽の出てる昼間の攻撃になる」
誰ともなしに口笛が鳴ったが、誰もが呆気に取られて、それを咎める者はなかった。
「わかった。で、根城はジェロン島の地下区画?」暫くして、今まで黙っていた無口なヴァンパイアがマリクの案にぼそりと賛同の意を表した。
「あぁ」マリクは無口なヴァンパイアに頷き返した。「その公算は大だな、コルテス。というより、そこしか考えられない。情報によれば、奴はジェロン島の地下に莫大な金を注ぎこんでた。自分の根城にするにはもってこいだ。そうだったよな、ナナ?」
「えぇ」と、ナナ。「建設関係者と資材を大量投入してたみたいだったから、ルーと私は大富豪用のシェルターだと思ってたわ。それに一週間前のヴァンパイアの攻撃者の死体の中にジェロンで見知ったエンジニアの顔が幾つもあった」
「話になんないよ」若い女ヴァンパイアが声を上げた。「数だって奴らの方が圧倒的に有利なんだ。まったく正気じゃない」
「儂らは皆正気じゃないよ、キャス。それより問題なのは何人生きて奴に迫れるかだ」
「いえ、問題はもっと根本的なことよ」
「なにが問題だ?」と、マリクは発言者のアンナに尋ねた。
「『なにが問題』かって?」アンナは大きく息をついた。「私たちは、そのジェロン島とやらの地下に人間から誰一人招待されたことなんてないのよ。そして今の私たちはヴァンパイア。奴がマリクの言う根城で眠っていたとして。じゃぁ、どうやって、そこに入り込めばいいの。警備のことを言ってるんじゃないわよ。入れたとしても、先週、攻めてきた奴らみたいに何もできないまま身体中から血を噴き出して死ぬことになったら元も子もないのよ」
「それは、どうかな」ニコライは皆の顔を見回した。「ナナは招待もされないのに城砦の中に入れた。儂らは、そのナナに生まれ変わらせてもらった。少なくとも招待状はいらんと思う。ヴァンパイアがヴァンパイアの根城に行くんだ。人間がいる家を訪問するわけじゃない」
「でも失敗したら」とケン。
「とにかく、やってみるしかない」
無口なコルテスの二度目の呟きがすべてだった。後には誰の言葉もなかった。
*
決して少なくない問題を抱えながらも、三日後に討伐パーティは出発した。ナナを入れて総勢七名。移動はブロドリップの侵攻前にナナが見つけて連れ戻していた陸棲烏賊を使うことになった。行程三日目にナナたち一行はジェロン島に到着した。だが死を覚悟した遠征も、せっかくの奇襲も大きな肩すかしで幕を閉じることとなった。
*
地平線の遥か向こうのジェロン島は小さな岩場に小高く積もった雪の吹き溜まりのように見えた。陸棲烏賊の橇のスピードを落として徐々に近づいてゆくと、それがただの吹き溜まりではなく、雪と氷のベールをまとった文明の残滓であることが見てとれる。人の姿だけが消え去ったオフィスビル。それに隣接する研究棟や簡易レストランなど最低限の生活欲求を満たすための一握りの商業施設。ジェロン島に上陸を果たしたナナたち一行は、かつてそれらを結んでいた道路をさらに先へと進んだ。そして最後まで工事車両と人員が大量投入されていた工場区画を遠く見通せる建設放棄地にたどり着くと、各々が双眼鏡を登山用遮光ゴーグルに当てて、凍てついた工場一棟一棟をつぶさに観察し始めた。たとえ昼間であってもブロドリップの手下が予期せぬ訪問者を警戒していないとも限らないからだ。だが双眼鏡の中の工場群の周辺で動くものといえば緩やかに吹き渡る風に舞い上げられる粉雪のほかは何もなかった。暫くそれらを観察して安全を確認したリーダー格のマリクは皆に前進を指示した。しかし、ナナたち一行が移動を再開しようとした、ちょうどその時、雪で半ば埋もれた一棟の工場の車両用鉄扉がきしんだ音を周囲に鳴り響かせた。巨大な鉄扉が開ききると中から白い化学防護服に全身をすっぽり包み込んだ人影が二つ現れた。防護ヘルメットと一体になったフェイスプレートが陽光を遮るために真っ黒に塗りつぶされていることから、彼らがただの人間でないのは明らかだ。
一行に緊張が走った。ナナたちは建設放棄地にうち捨てられた資材の山に素早く身を潜め、ブロドリップの手下と思しき化学防護服の動きをマリクとアンナ、そしてケンの三人が見守った。幸いこちらに気付いている様子はない。彼らは何の警戒もなく、四辻にある信号機の上にひらりと飛び上がると、そこに赤黒い小さなビニール袋を、元々は同じであったであろう凍りついた物と交換して吊り下げた。簡単な作業を終えた二人は一通り辺りを見渡すと諦めたように肩を落として雪上に下り、もと来た鉄扉の奥へと姿を消した。
「緊急輸血用の備蓄血液パック一単位だわ」
以前はERの看護師だったアンナが双眼鏡から目を離さずに呟いた。
「本当か?」
「見まちがえるもんですか」アンナは双眼鏡から目を離さず即答した。「B型陽性。パックに印字された血液型まで読めるわよ」
「でも自分たちの食料を、なぜあんな所に吊り下げるんだ?」
「ジェラートにして食べたかったんじゃないの」
「笑えないな、ケン」相変わらず癇に障る言質が目立つケンを一瞥したマリクは、資材の陰に身を潜める仲間を振り返った。
「とにかく、奴らがブロドリップの手下なのは間違いなさそうだ。そして入り口もわかった」
ナナたち一行は更に一時間ほど鉄扉に動きがないのを確認すると、橇の荷台に積まれた断熱包装の中から銀の弾がたっぷり詰まったショットガンを取り出した。一行は武器を握り締め、陸棲烏賊と橇をその場に残すと蛙飛びに似た跳躍を繰り返して手下が消えた鉄扉まで素早く移動を開始した。工場前に到着したナナはすぐさま重い扉に手をかけると、音を立てないように少し隙間を開けて中を覗き見た。大型航空機の整備場を思わせる恐ろしく広い工場内は明かりもなく、空っぽの空間が闇に溶けこむように広がっているだけだった。そこに動くものはおろか人影すらないことを再確認したナナは、ニコライに頷きかけると二人で人一人が潜り抜けられるだけの隙間を開いた。そしてナナを先頭に一向は意を決して次々と中に侵入した。十秒、二十秒。そして三分……。周囲を警戒しながらヴァンパイアたちは永遠とも思える時間の中、固唾を呑んで来るかもしれないその時を待ち受けた。
「招待状はいらなかったようだな」
腕時計から顔を上げたニコライの一言に、みな安堵のため息を漏らした。
「さぁ、次だ」
そう。血の詰まった風船みたいに身体が弾けなかったのなら、マリクの言うように次だ。目標は地下のシェルターなのだ。厳重な警備はそこからだろう。ナナは小さく頷いた。
やがてナナたちは鉄扉と反対の端に地下への階段を認めると、今度はマリクとケンを先頭に一層の警戒心を持って一歩一歩下へ降りていった。湿り気も温かみも微塵も感じられない凍てついた階段は限りなく続くかと思われた。ふと階上を見上げるとヴァンパイアの目をもってすら、階段入口がぼんやりと見えるほど深く降りていたことに気付かされた。やっと地下フロアに着くころには緊張を強いられた筋肉が石のようにかちこちに固まり、ナナは手にしたショットガンが腕や身体と一体化した錯覚に襲われた。地下のフロアは一行が居るところを中心に蜘蛛の脚のように狭い回廊が放射状に伸び拡がり、それぞれの先は闇に沈んだように何も見えず、冷たく乾いた空気だけが淀んでいるだけだった。
「何なんだ、ここ。さっきの奴らはどこに行った?」
「黙れ」
「でも……」
「いいから黙ってろ、小僧」
ケンをたしなめたマリクの緊迫した声から焦りを感じ取った一行に不安が走った。
「マリク」ニコライがマリクに小声で話しかけた。「こう静かじゃ、罠を勘ぐってみるべきかもしれんぞ」
「罠?」と、背後を警戒していたキャスがマリクの代わりに反応した。「罠なら罠で上等さ。片っ端から見つけしだい葬ってやるわ」
「慌てないで」今度はアンナが声を高ぶらせた。「眠ってるのよ。今は昼間だってことを忘れたの?」
「それくらいわかってるわよ。でも、奴らの根城っていうんなら、見張りの一人ぐらいはいるはずでしょ」
「みんな動くな」
コルテスの抑制の効いた低音が一行の会話を遮った。皆の目はキャスに向けられたコルテスのショットガンに釘つけになった。しかし、コルテスの目はキャスの後ろに続く一本の回廊の奥深くを油断なく見据えていた。
「ゆっくりと、こっちへ出て来い」
コルテスの断固とした物言いに、いつの間にいたのか、それともずっとそこに潜んで皆の話を聞いていたのか、両手を顔の高さに上げた若い男が回廊の暗闇からゆっくりと現れた。首から下が化学防護服なのは、さっき表で見た二人の内の一人だろう。
「撃つなよ。俺は警戒するほど危険な男じゃない。手を下ろしてもいいか?」
コルテスの武器が、まだ自分に向いているのにうんざりしながらも、その若い男は再び口を開いた。
「あんたたちもヴァンパイアなんだろ。仲間を撃つつもりか?」
「俺たちは、お前の仲間なんかじゃない!」ケンの怒声が回廊に響いた。
「仲間でなくてもヴァンパイアには違いないだろ。そんな体温の低い人間がいるわけはないからな」男は肩まで上げた片手で、ゆっくりとナナたち一行の口から出る極端に少ない水蒸気を指し示した。
「動くな」
「喋るのはいいか?」
コルテスの再度の警告に落ち着き払って、そう応じた若い男にケンが再び食って掛かった。
「黙れ!」
「なら、どうすればいい?」
「黙ってればいいんだ。殺すぞ!」
「やめろ、ケン。彼に話させろ!」
溜まりかねたマリクが割って入ったが、ケンの怒気は収まらなかった。
「俺たちは、こいつらを殺しに来たんじゃないのか。なんで止めるんだ?!」
「儂らの狙いは、あくまでブロドリップ。しかし邪魔するようなら容赦はせん。そういうことだ」
マリクに加勢したニコライは、そう言い放つとケンに鋭い眼光を向けてから若い男に頷いた。
「喋る許可をどうも、髭の旦那。ただ、一つだけはっきりさせておきたい」男はゆっくりと両手を下げた。「俺はあんたらに脅されて話すんじゃない。対等な立場で話し合うために口を開くんだってことを。もちろん、そのための準備はこっちだって怠ってはいない」
その言葉に、ケンだけでなく仲裁に入ったニコライまで気色ばんだが、それも一瞬のことだった。一行が気付いたときには、周りすべての回廊から、ひしめき合うヴァンパイアの静かな息遣いが聞こえ始めていたからだ。
「さぁ、話し合おう。ここでお互い殺しあったって良いことなんかないからな」
*
放射状に広がった通路の一本から奥に進んだところに殺風景だが、天井が高く広々としたシェルターがあった。シェルターの片隅には教会のように十字架と祭壇が設えられており、ナナたち一行を少なからず驚かせた。彼らは案内役の若い男と警護のヴァンパイアたちとともに祭壇近くのベンチに腰を下ろすと彼らの話に耳を傾け始めた。話し合いは互いの集団間に暴力沙汰こそもたらさなかったものの、一触即発の緊張が沈静化するまで、かなりの時間を要した。もっともそこには人数的に劣勢な外来者集団に自暴自棄な行動を起こされ、自分たちが損害を被るのを避けたかった受け手側集団の譲歩も大きく働いたのは言うまでもない。しかし、その譲歩ですらケンとキャスの気持ちを緩和するには至らなかった。そこでニコライとコルテスが視察と称して話し合いの場から二人を連れだすことになった。受け手側も今の自分たちのことを、ぜひ見てほしいと快諾したのは言うまでもない。ただ意外だったのはアンナまでが彼らとの同行を申し出たことだ。おそらく子供のヴァンパイアもいるという話に心惹かれてのことだろう。マリクとナナはそんな彼らが出発するのを尻目に防護服の若い男との腹を割った話し合いを進めていった。
「あんたらはブロドリックの命令には逆らえない」とマリクが口火を切った。「だから何度も砦を襲った。それはわかる。でもなぜ奴は、この期に及んで突然あんたたちを見捨てた?」
「わからん。でも、もうどうだっていい。始祖……いや、あいつは」化学防護服の若い男はその名前を意識的に「あいつ」と言い直した。「食糧を作る触媒を残していった。さしあたり、それで充分なのさ。と言うより、これ以上、あいつとは係わり合いになりたくはない。俺たちだって理不尽な命令で多くの仲間を失ったんだ。縁が切れたのなら、もうそっとしておいてほしいというのが正直なところだ」
「えらく疎まれたもんだな、奴も」
「俺たちが増えすぎたのか、人間が減りすぎたからなのかはわからんが、あいつは、まるで性格が変わっちまった。まるで甘やかされ続けた駄々っ子がオモチャを手に入れられなかった時みたいに、いつもイライラして当り散らしてた。気まぐれに仲間同士で死ぬまで戦わせたり、何日も眠り込んで棺から出てこないこともあった。心配して調子はどうかと尋ねただけで喉を裂かれた仲間もいる。先月なんかは思いついたように北米まで二百名の仲間を遠征に連れて行ったはいいが、一人っきりで戻ってきて理由も話さない。最近の俺たちは、あいつの一挙手一投足にすっかり怯えきってたんだ。そして、とうとう戻ってこなくなった。こんなことは初めてだ」
「奴に捨てられたということか、お前さんたちは?」
「よしてくれ。これ幸いに、俺たちの方が奴との縁を切ったんだ」
若いヴァンパイアはニコライの問いかけに、祭壇の十字架に顎をしゃくってみせた。
「だったら、貢物よろしく表に掲げられた人血は、奴のためじゃないのね?」
ナナは未だ警戒の解け切れぬ目で若い男を見据えた。
「当たり前だろ。あれは、あんた用の餌だよ。言ってみれば目印みたいなものさ。でも、こんなに仲間がいたなんて思いもしなかったよ」
「餌ねぇ……」と、ナナの代わりにマリクが苦々しく応じた。
「長い道中だ」若い男がナナを見た。「きっと飢えてると思ったんだ。すまない。気を悪くしたんなら謝る」
「でも、なぜ私がここへ来ると?」
「俺たちは人間に招待されない限り小部屋にだって入れない忌み者さ。でもヴァンパイアが世の中に存在する以上、人間には『もしかしたら……』という不安は常について回る。人間としては宿敵ブロドリック一味の情報を多く持っているにこしたことはない。そして砦にはヴァンパイアはあんた一人。人間の敵だぞ。きっと、あんたは快くは思われてないだろ。だったら、少しでも自分の立場を良くしようと、情報収集のため、ここに来るしかない。そう結論を出すのは難しいことじゃなかった。ただ意外だったのは、情報収集どころか、あいつを滅ぼしに来るなんて思いもしなかったってことさ」
「時に創造主に盾つく愚かなヴァンパイアもいるのよ、私みたいに」
ナナは自分が奇襲を言い出した本人であるかのように自嘲気味に溜め息をついた。そんなナナを弁護しようとマリクが口を開きかけたとき、数名のヴァンパイアとともにニコライが回廊の奥から現れた。彼はナナとマリクに頷くと、手の中の給水ボトルを差し出した。
「彼らの言う通りだ。ただの海水を口にし続けて緩慢に弱ってゆくより遥かにいい。まぁ、ブロドリップの血液が触媒になっているという胸糞の悪さを忘れることができればだが」
マリクはボトルの蓋を開けると、黄色い液体に恐る恐る鼻を近づけて臭いを嗅いだ。
「無臭だ」若い男がマリクに顔を向けた。「俺たちは“精進水”と呼んでいる。それを作る触媒は、あいつの血だが、直接、海水に混ぜたりするわけじゃない。血を密閉したボトルを近くに置いておくだけで何ガロンもの海水が手品みたいにそいつに変わってくれる。蒸留すればタブレットにすることだってできる。だが味には徹底的な個人差がある。俺は桃だと思うが、リンゴだと言い張る者もいる」
若い男の視線を受け、今まで一言も口を開かなかった丸顔のヴァンパイアが遠慮がちに手を挙げて「そう、僕はオレンジの味を感じます」と小声でぼそぼそ呟いた。
「アンナもオレンジ。だが、コルテスは苺だと」ニコライが言い添えた。「我々の味覚をどう刺激するのか謎だが、全員に共通するのは果物の味だということかな。ちなみに儂はメロン味だった」
「なるほどな。ところで、ケンたちの姿が見えないが?」
「あぁ。外の空気を吸いに行ったよ」
ニコライの口調から、ケンとキャスは外の空気を吸いに行ったのではなく、頭を冷やさせるために外に連れ出されたのだと察したが、マリクはただ「そうか」とだけ応じた。そんなマリクたちを見て若い男が身を乗り出した。
「俺たちに対するあんたたちの思いは、それぞれ複雑だと思う。でも、俺たちはあんたたちを飢えから完全に解放することができる。是非そうしたいと思ってもいる。これは俺たちの総意だ。それに人間たちを助けることもできる、彼らをヴァンパイアに転生させるってことじゃなくな」
「それは、ありがたい申し出だな」マリクの言葉に警戒の色が滲んだ。
「だから……」若い男は言いよどんだ。
「『だから』?」と、オウム返しにマリク。
「俺たちの頼みを聞いてくれないか?」
「そらきた」ニコライが鼻白んだ。「死んだ婆様が昔から言ってたもんだ。『ただより高価なものはない』とな」
「待ってくれ! 話す前から判断しないでくれ」
「わかった。話せよ」と、マリク。
「少し出すぎた願いだとはわかってるんだが」若い男は意を決したようにマリクの目をまっすぐに見詰めた。「俺たちも城砦に、あの街に住まわせてくれないか、あんたたちのように」
「馬鹿なことを言うな!」マリクが次の言葉を発するまで数瞬を要した。この申し出が彼にとっても相当意外だったに違いない。「残った人間たちがヴァンパイアと生活することを許すわけがない。わかるだろ、それくらい。あの伝染病でどれだけ犠牲になったか知ってるのか?!」
「今ごろは全滅してるかもしれない」
「言って良いことと悪いことがあるぞ」
気色ばんだニコライに若い男がばつの悪そうな顔を向けた。
「すまない、本当に。失言だ、許してくれ。でも、ここには親を失った小さな子や、ここで生まれた子もたくさんいるんだ。なぁ、あんたも、さっき見てきたろう。あの子らをこんなところに置いておかないでくれ。確かに橋を渡れば立派な街はあるが、ただそれだけだ。中身なんて何もない空っぽの空間みたいなもんだ。でも、あの城砦は街だ。街には、まともな人間らしい生活と教育……文化がある。それをあの子たちに与えてやってほしいんだ。それに、もしブロドリップが戻って来たらと思うと……」
ヴァンパイアの口から“人間らしい”という言葉が出ても誰も笑わなかった。それどころか、その場の全員がブラム氷期とブロドリップに自分たちが奪われたものが何だったかを、その言葉は思い出させた。
「しかしお前たちは」と、無口なコルテスが淡々と応じた。「人間に有害なウイルスの感染源」
「俺たちは街に着く寸前に発症した。微妙な身体の変化もあった。でも半日だけだ。そこからは、あっと言う間に快方に向かって体温は三十二度。脈拍も通常通り一分間に三十四だ。誰ももう感染源にはならない。安全だ。それに見返りも用意してある」
「見返り?」
「発電所。あ……あの街には……それが必要だと思います」丸顔のヴァンパイアがマリクの「見返り」という言葉に応じて、おどおどと口を挟んだ。
「残念だな。我々は、もう原子炉は持ってる」
「黒煙型の旧式は放射線の遮蔽も難しいし、出力を上げると危険です。事故が起こる。始祖からは……あぁ、ごめんなさい。ブ……ブロドリックは城砦……街は色々な施設が稼働し始めてるから、あれでは、すぐに電力供給が追い付かなくなるはずだと言ってました。僕なら解決できると思います」
言葉に詰まりながらも一気にそこまで喋ると丸顔のヴァンパイアは乾いた唇を舐めて皆の反応を伺った。沈黙の中、若い男が話を続けるように目配せしたので、彼は大きく息を吸い込むと、先程よりも、ややゆっくりとした口調で再び話しはじめた。
「僕は当初、あなたたちの街のエネルギープラントの設計者でした。2004年の海洋地震でインド南部の原発が事故を起こしかけたので、スマトラでも原発はご法度になったんです。だから“アルキメデスのスクリュー”を改良進化させた“アルキメディアン・ホンダ・システム”の潮汐発電を使うことになりました。でも氷期が来てそんなことも言ってられなくなったんです。実験稼働まで、あと少しだったのに。ほんとに少しだったんです」
「潮汐発電……海は凍って波もないのにかね?」ニコライが探るような声を上げた。
「凍ってるのは表面だけ」と、丸顔のヴァンパイア。「木星の凍りついた第二衛星だって海中には潮汐力があるんです。地球が凍りついたって問題ない。城砦の目と鼻の先には手付かずの安全なリアクターがあるんです。建屋と長いラインは耐震用に地下区画に設置してます。そう……まるで、その……大きくて……長い廊下を地下室みたいにして、幾つも、幾つも区切って作ったんです。それが完成してたんです、僕がまだ人間だったころに」
「しかし信用できるのかね」ニコライは訝しげに口をすぼめた。「その潮汐リアクターとやらは、まだ実験段階なんだろ?」
「ここも既にそのリアクターの小型のものを使ってますよ」丸顔ヴァンパイアの声は小さかったが、自信に満ちていた。「海が浅くて大きなものは設置できませんでしたが、故障もない」
「なぁ」若い男の口調が再び熱を帯びた「電力問題も解決できるんだ。それでも駄目なら……いや俺たち大人が駄目でもいい。でも、子どもたちだけは面倒を見てやってくれないか。せめて快適なベッドと教育、いやブロドリップからの安全だけでも与えてやってくれ。頼む」
「わたしからもお願いよ」いつの間にかアンナが回廊の入り口の一つに立っていた。彼女はいたわるように一人のヴァンパイアの女に寄り添っていた。妊娠しているのか、その女のお腹は大きかった。「娘のジェイミーよ。転生して、ここに居たの」
「なぁ、あんたからも仲間に頼んでくれないか」若い男は、これが最後とばかりナナに哀願の目を向けた。「今さら、こんなこと言いたくはないが、あんたは俺に借りもあるはずだろ」
初めて顔を見たときからナナには彼が何者なのかわかっていた。彼はナナが血を呑み干した、あの時、彼女のアパート前に駆けつけた若い警官だった。
*
激論の末、ナナたちはジェロン島にいたヴァンパイアの思いを砦の人間たちに伝えるパイプ役になり、彼らを連れて行くことを承諾した。それに激しく反発したケンとキャスは、ナナたちに怒りの矛先を向けたが、どうにもならないと知ると、翌朝、皆が寝静まってから橇に持てるだけの食糧タブレットを積み込んで黙って島を抜け出した。彼らの置手紙にはブロドリップを地の果てまでも追い詰めて滅ぼしてみせると決意の殴り書きがしたためてあった。むろん、食糧と橇を盗んだことに対する謝罪の言葉は一言も書かれていなかった。この一件でナナたちとジェロン島の集団に一時的に不穏な空気が流れたが、それもすぐに影を潜めた。未来に進むためには、いがみ合ってばかりはいられないと、二つの集団の全員がわかっていたからだ。ナナたち一行は、シンと自己紹介した防護服の若い警官を筆頭に、二次性徴を終えたばかりの少年少女七名のヴァンパイア使節を伴って徒歩で城砦に向かうことになった。当初、ナナたちは子どもを重大な危険に晒すかもしれないこの決定に難色を示したが、使節団のほとんどを子どもで編成した方が人間の警戒感を少しでも緩和できるのではないか。また子どもを連れてゆくことで人間の慈悲心に訴えかけられるのではないかというジェロン島のヴァンパイアの強い総意に押し切られることになったのだ。もちろん城砦にいる人間に対する配慮はそれだけでは不十分だ。シンたちは自ら紐状の工業用導爆線でネックレスを作り、そこに警察無線を改造した起爆装置を取り付けて首に巻きつけ、いつでも自分たち自身を無力化できるようにした。もっとも、それぐらいしても人間たちが話のテーブルについてくれる可能性は多くはないだろうが。
そして今回で三回目となる新生ヴァンパイアのミーティングが薄暗い資材管理部屋の片隅ではじまった。
「僕らが転生して、もう十日目だよ。もっと仲間を増やさなきゃ」
開口一番、顔にまだあどけなさが残る若いヴァンパイアが賛同を促すように仲間たちの顔を見回し、最後にナナのやつれ切った顔に視線を止めた。ナナは物憂げに頭を上げると聞きたくもないという仕草で片手を振って、その意見を退けた。それを見た若いヴァンパイアは、今度は向かいに腰掛けている綺麗な赤毛をボブに切りそろえた年かさの女ヴァンパイアに意見を求めた。
「アンナはどうなの?」
「そうね……」
「『そうね』だけじゃ、わかんないよ」
「ケン。あなたの言うとおりだと思うわ。だから、ナナがやってくれないんだったら、次は私らがやるしかないわね……」
消極的なアンナの賛同に、その場が静まり返った。つい二日前も味方を増やす負担をナナばかりにかけまいと吸血行為を行った二人の仲間がその直後からおかしくなったからだ。変異したH5N1ウィルスに侵された人血が影響したのか、ナナにだけその耐性があったのか真相は全くわからなかったが、吸血を行った方も、吸血された方も完全に理性をなくし、手が付けられないほど凶暴化したため、銀の散弾による仲間の殺害を余儀なくされていたのだ。
「卑怯な言い方だな、ケン。そんな言い方で選択を迫るものじゃない」
沈黙を破ってナナを擁護した壮年のヴァンパイアにケンがすぐさま反論した。
「でも他に方法がないよ」ケンと呼ばれた若いヴァンパイアはまくし立てた。「僕らが転生したのは何のためだい。ブロドリップが言ったように奴の仲間になるためか。そんな馬鹿な。奴を殺すためだろ?!」
「いい加減にしろ。ナナはヴァンパイア・ハンター製造機ではなかろう!」壮年のヴァンパイアは白髪交じりの立派な口髭を震わせた。「彼女は儂らの命を救ってくれた恩人だぞ。しかし彼女を見たまえ。儂らの要求を喜んでいるように見えるかね?」
「でも」と、小鼻にピアスをした若い女ヴァンパイアが口を挟んだ。「ケンの言い分にも一理あるわ」
「みんな落ち着けよ。毎回仲間割れするために集まってるわけじゃないんだから」
マリクの言葉に再び沈黙が訪れた。
「そうね」年かさのアンナが口を開いた。「さっきのは私の失言だったわ。許してね、ナナ」
「なに言ってんの、アンナ。子どもの敵討ちをするんじゃなかったのかい。それはもう無しにすんの。僕は誰がなんて言おうと両親の敵を取るぞ!」
「やめなよ、ケン」
若い女ヴァンパイアが堪りかねて再び口を挟んだが、ケンは止まらなかった。
「いや、やめない。奴は両親を殺したとき、僕にはっきりこう言ったんだ。『最近は食べすぎなのか、どんな人間も旨くなくてねぇ』って。しかも欠伸をかみ殺しながらさ。それって何なの。奴にとって人間はスナック菓子以下なのかい。あんたたちだって似たような目に遭わされてきたんだろ!」ケンは先ほど自分をたしなめた口髭のヴァンパイアを指差した。「ニコライだって、目の前で息子と孫が殺された恨みを忘れたわけ?!」
「よくお聞き!」アンナはニコライが口を開く前に声を荒げた。そして鋭い眼光でケンを射すくめた。「人を人とも思わない。目的のために仲間に対しても手段を択ばない。そんなこと、まるであのブロドリップと同じじゃないか。私たちは、あの悪魔を滅ぼすためにはどんなことだってすると誓ったさ。もちろん、そのための犠牲だって厭わない。だからヴァンパイアになった。それに転生に失敗して仲間も死んだ。でも、これは違うわよ。奴と闘う前から、それとわかった上で恩人に死ぬかもしれないような苦痛を強いるなんて」
「馬鹿じゃないの、アンナは!」
「ケン!」ニコライが掴みかからんばかりにケンに詰め寄ったが、彼は怯まなかった。
「そうかい。そうかい。わかったよ。色々言いながら、結局あんたたち年寄りは怖いんだ。一度命を取り留めたら、また失うのは恐ろしいからね。いいさ。やらないなら、やらないで。でも僕は一人でもやってやるからな」
「誰もやらないなんて言ってないぞ」
「へぇ」マリクの反論にケンは見下したような視線を向けた。「じゃぁ、あんたがリスクを承知でナナの代わりに仲間を増やすって言うの?」
「俺はやらない。ナナもやらない。ここにいる誰も仲間を増やすことで、もう危険に晒されることはしない」
「はぁ。あんた、もっと賢いと思ってたよ」
「臨機応変さに欠けるガキのお前よりはな」マリクは声を上げかけたケンを制して言葉を続けた。「攻撃はここにいる俺たちだけでやる」
ざわめきの中に疑念と不満が飛び交った。それが少し収まるのを待って、マリクは再び口を開いた。
「みんな聞いてくれ。数には数で対抗しようとしたのが、そもそもの間違いだ。最初からブロドリップの軍団に匹敵する数を揃えることなんて無理だったんだ。だから、こっちは少人数で仕掛けることにする」
「それこそ犬死だ」
「だったら君は抜けてかまわんよ。儂はマリクの意見に賛成だ」
ニコライの静かな物言いがケンの反論を封じたが、若い女ヴァンパイアが疑問を投げかけた。
「じゃぁ、いま病気で苦しんでる連中は、あたしたちみたいに反撃の機会も貰えずに、ただ死んでくだけなの。あたしみたいに生き残った家族のために、ヴァンパイアになって、ブロドリップを斃したいっていう奴もいるはずなのに……」
その場の沈黙が何よりの答えだった。その空気に堪えかねたかのようにニコライが話を先に進めた
「彼らの恨みも儂らで晴らす。で、作戦はマリク?」
「手下どもの目を盗んで奴の根城に潜り込む。そして奴だけをピンポイントで狙う」と、マリク。「奇襲になるから、もちろん太陽の出てる昼間の攻撃になる」
誰ともなしに口笛が鳴ったが、誰もが呆気に取られて、それを咎める者はなかった。
「わかった。で、根城はジェロン島の地下区画?」暫くして、今まで黙っていた無口なヴァンパイアがマリクの案にぼそりと賛同の意を表した。
「あぁ」マリクは無口なヴァンパイアに頷き返した。「その公算は大だな、コルテス。というより、そこしか考えられない。情報によれば、奴はジェロン島の地下に莫大な金を注ぎこんでた。自分の根城にするにはもってこいだ。そうだったよな、ナナ?」
「えぇ」と、ナナ。「建設関係者と資材を大量投入してたみたいだったから、ルーと私は大富豪用のシェルターだと思ってたわ。それに一週間前のヴァンパイアの攻撃者の死体の中にジェロンで見知ったエンジニアの顔が幾つもあった」
「話になんないよ」若い女ヴァンパイアが声を上げた。「数だって奴らの方が圧倒的に有利なんだ。まったく正気じゃない」
「儂らは皆正気じゃないよ、キャス。それより問題なのは何人生きて奴に迫れるかだ」
「いえ、問題はもっと根本的なことよ」
「なにが問題だ?」と、マリクは発言者のアンナに尋ねた。
「『なにが問題』かって?」アンナは大きく息をついた。「私たちは、そのジェロン島とやらの地下に人間から誰一人招待されたことなんてないのよ。そして今の私たちはヴァンパイア。奴がマリクの言う根城で眠っていたとして。じゃぁ、どうやって、そこに入り込めばいいの。警備のことを言ってるんじゃないわよ。入れたとしても、先週、攻めてきた奴らみたいに何もできないまま身体中から血を噴き出して死ぬことになったら元も子もないのよ」
「それは、どうかな」ニコライは皆の顔を見回した。「ナナは招待もされないのに城砦の中に入れた。儂らは、そのナナに生まれ変わらせてもらった。少なくとも招待状はいらんと思う。ヴァンパイアがヴァンパイアの根城に行くんだ。人間がいる家を訪問するわけじゃない」
「でも失敗したら」とケン。
「とにかく、やってみるしかない」
無口なコルテスの二度目の呟きがすべてだった。後には誰の言葉もなかった。
*
決して少なくない問題を抱えながらも、三日後に討伐パーティは出発した。ナナを入れて総勢七名。移動はブロドリップの侵攻前にナナが見つけて連れ戻していた陸棲烏賊を使うことになった。行程三日目にナナたち一行はジェロン島に到着した。だが死を覚悟した遠征も、せっかくの奇襲も大きな肩すかしで幕を閉じることとなった。
*
地平線の遥か向こうのジェロン島は小さな岩場に小高く積もった雪の吹き溜まりのように見えた。陸棲烏賊の橇のスピードを落として徐々に近づいてゆくと、それがただの吹き溜まりではなく、雪と氷のベールをまとった文明の残滓であることが見てとれる。人の姿だけが消え去ったオフィスビル。それに隣接する研究棟や簡易レストランなど最低限の生活欲求を満たすための一握りの商業施設。ジェロン島に上陸を果たしたナナたち一行は、かつてそれらを結んでいた道路をさらに先へと進んだ。そして最後まで工事車両と人員が大量投入されていた工場区画を遠く見通せる建設放棄地にたどり着くと、各々が双眼鏡を登山用遮光ゴーグルに当てて、凍てついた工場一棟一棟をつぶさに観察し始めた。たとえ昼間であってもブロドリップの手下が予期せぬ訪問者を警戒していないとも限らないからだ。だが双眼鏡の中の工場群の周辺で動くものといえば緩やかに吹き渡る風に舞い上げられる粉雪のほかは何もなかった。暫くそれらを観察して安全を確認したリーダー格のマリクは皆に前進を指示した。しかし、ナナたち一行が移動を再開しようとした、ちょうどその時、雪で半ば埋もれた一棟の工場の車両用鉄扉がきしんだ音を周囲に鳴り響かせた。巨大な鉄扉が開ききると中から白い化学防護服に全身をすっぽり包み込んだ人影が二つ現れた。防護ヘルメットと一体になったフェイスプレートが陽光を遮るために真っ黒に塗りつぶされていることから、彼らがただの人間でないのは明らかだ。
一行に緊張が走った。ナナたちは建設放棄地にうち捨てられた資材の山に素早く身を潜め、ブロドリップの手下と思しき化学防護服の動きをマリクとアンナ、そしてケンの三人が見守った。幸いこちらに気付いている様子はない。彼らは何の警戒もなく、四辻にある信号機の上にひらりと飛び上がると、そこに赤黒い小さなビニール袋を、元々は同じであったであろう凍りついた物と交換して吊り下げた。簡単な作業を終えた二人は一通り辺りを見渡すと諦めたように肩を落として雪上に下り、もと来た鉄扉の奥へと姿を消した。
「緊急輸血用の備蓄血液パック一単位だわ」
以前はERの看護師だったアンナが双眼鏡から目を離さずに呟いた。
「本当か?」
「見まちがえるもんですか」アンナは双眼鏡から目を離さず即答した。「B型陽性。パックに印字された血液型まで読めるわよ」
「でも自分たちの食料を、なぜあんな所に吊り下げるんだ?」
「ジェラートにして食べたかったんじゃないの」
「笑えないな、ケン」相変わらず癇に障る言質が目立つケンを一瞥したマリクは、資材の陰に身を潜める仲間を振り返った。
「とにかく、奴らがブロドリップの手下なのは間違いなさそうだ。そして入り口もわかった」
ナナたち一行は更に一時間ほど鉄扉に動きがないのを確認すると、橇の荷台に積まれた断熱包装の中から銀の弾がたっぷり詰まったショットガンを取り出した。一行は武器を握り締め、陸棲烏賊と橇をその場に残すと蛙飛びに似た跳躍を繰り返して手下が消えた鉄扉まで素早く移動を開始した。工場前に到着したナナはすぐさま重い扉に手をかけると、音を立てないように少し隙間を開けて中を覗き見た。大型航空機の整備場を思わせる恐ろしく広い工場内は明かりもなく、空っぽの空間が闇に溶けこむように広がっているだけだった。そこに動くものはおろか人影すらないことを再確認したナナは、ニコライに頷きかけると二人で人一人が潜り抜けられるだけの隙間を開いた。そしてナナを先頭に一向は意を決して次々と中に侵入した。十秒、二十秒。そして三分……。周囲を警戒しながらヴァンパイアたちは永遠とも思える時間の中、固唾を呑んで来るかもしれないその時を待ち受けた。
「招待状はいらなかったようだな」
腕時計から顔を上げたニコライの一言に、みな安堵のため息を漏らした。
「さぁ、次だ」
そう。血の詰まった風船みたいに身体が弾けなかったのなら、マリクの言うように次だ。目標は地下のシェルターなのだ。厳重な警備はそこからだろう。ナナは小さく頷いた。
やがてナナたちは鉄扉と反対の端に地下への階段を認めると、今度はマリクとケンを先頭に一層の警戒心を持って一歩一歩下へ降りていった。湿り気も温かみも微塵も感じられない凍てついた階段は限りなく続くかと思われた。ふと階上を見上げるとヴァンパイアの目をもってすら、階段入口がぼんやりと見えるほど深く降りていたことに気付かされた。やっと地下フロアに着くころには緊張を強いられた筋肉が石のようにかちこちに固まり、ナナは手にしたショットガンが腕や身体と一体化した錯覚に襲われた。地下のフロアは一行が居るところを中心に蜘蛛の脚のように狭い回廊が放射状に伸び拡がり、それぞれの先は闇に沈んだように何も見えず、冷たく乾いた空気だけが淀んでいるだけだった。
「何なんだ、ここ。さっきの奴らはどこに行った?」
「黙れ」
「でも……」
「いいから黙ってろ、小僧」
ケンをたしなめたマリクの緊迫した声から焦りを感じ取った一行に不安が走った。
「マリク」ニコライがマリクに小声で話しかけた。「こう静かじゃ、罠を勘ぐってみるべきかもしれんぞ」
「罠?」と、背後を警戒していたキャスがマリクの代わりに反応した。「罠なら罠で上等さ。片っ端から見つけしだい葬ってやるわ」
「慌てないで」今度はアンナが声を高ぶらせた。「眠ってるのよ。今は昼間だってことを忘れたの?」
「それくらいわかってるわよ。でも、奴らの根城っていうんなら、見張りの一人ぐらいはいるはずでしょ」
「みんな動くな」
コルテスの抑制の効いた低音が一行の会話を遮った。皆の目はキャスに向けられたコルテスのショットガンに釘つけになった。しかし、コルテスの目はキャスの後ろに続く一本の回廊の奥深くを油断なく見据えていた。
「ゆっくりと、こっちへ出て来い」
コルテスの断固とした物言いに、いつの間にいたのか、それともずっとそこに潜んで皆の話を聞いていたのか、両手を顔の高さに上げた若い男が回廊の暗闇からゆっくりと現れた。首から下が化学防護服なのは、さっき表で見た二人の内の一人だろう。
「撃つなよ。俺は警戒するほど危険な男じゃない。手を下ろしてもいいか?」
コルテスの武器が、まだ自分に向いているのにうんざりしながらも、その若い男は再び口を開いた。
「あんたたちもヴァンパイアなんだろ。仲間を撃つつもりか?」
「俺たちは、お前の仲間なんかじゃない!」ケンの怒声が回廊に響いた。
「仲間でなくてもヴァンパイアには違いないだろ。そんな体温の低い人間がいるわけはないからな」男は肩まで上げた片手で、ゆっくりとナナたち一行の口から出る極端に少ない水蒸気を指し示した。
「動くな」
「喋るのはいいか?」
コルテスの再度の警告に落ち着き払って、そう応じた若い男にケンが再び食って掛かった。
「黙れ!」
「なら、どうすればいい?」
「黙ってればいいんだ。殺すぞ!」
「やめろ、ケン。彼に話させろ!」
溜まりかねたマリクが割って入ったが、ケンの怒気は収まらなかった。
「俺たちは、こいつらを殺しに来たんじゃないのか。なんで止めるんだ?!」
「儂らの狙いは、あくまでブロドリップ。しかし邪魔するようなら容赦はせん。そういうことだ」
マリクに加勢したニコライは、そう言い放つとケンに鋭い眼光を向けてから若い男に頷いた。
「喋る許可をどうも、髭の旦那。ただ、一つだけはっきりさせておきたい」男はゆっくりと両手を下げた。「俺はあんたらに脅されて話すんじゃない。対等な立場で話し合うために口を開くんだってことを。もちろん、そのための準備はこっちだって怠ってはいない」
その言葉に、ケンだけでなく仲裁に入ったニコライまで気色ばんだが、それも一瞬のことだった。一行が気付いたときには、周りすべての回廊から、ひしめき合うヴァンパイアの静かな息遣いが聞こえ始めていたからだ。
「さぁ、話し合おう。ここでお互い殺しあったって良いことなんかないからな」
*
放射状に広がった通路の一本から奥に進んだところに殺風景だが、天井が高く広々としたシェルターがあった。シェルターの片隅には教会のように十字架と祭壇が設えられており、ナナたち一行を少なからず驚かせた。彼らは案内役の若い男と警護のヴァンパイアたちとともに祭壇近くのベンチに腰を下ろすと彼らの話に耳を傾け始めた。話し合いは互いの集団間に暴力沙汰こそもたらさなかったものの、一触即発の緊張が沈静化するまで、かなりの時間を要した。もっともそこには人数的に劣勢な外来者集団に自暴自棄な行動を起こされ、自分たちが損害を被るのを避けたかった受け手側集団の譲歩も大きく働いたのは言うまでもない。しかし、その譲歩ですらケンとキャスの気持ちを緩和するには至らなかった。そこでニコライとコルテスが視察と称して話し合いの場から二人を連れだすことになった。受け手側も今の自分たちのことを、ぜひ見てほしいと快諾したのは言うまでもない。ただ意外だったのはアンナまでが彼らとの同行を申し出たことだ。おそらく子供のヴァンパイアもいるという話に心惹かれてのことだろう。マリクとナナはそんな彼らが出発するのを尻目に防護服の若い男との腹を割った話し合いを進めていった。
「あんたらはブロドリックの命令には逆らえない」とマリクが口火を切った。「だから何度も砦を襲った。それはわかる。でもなぜ奴は、この期に及んで突然あんたたちを見捨てた?」
「わからん。でも、もうどうだっていい。始祖……いや、あいつは」化学防護服の若い男はその名前を意識的に「あいつ」と言い直した。「食糧を作る触媒を残していった。さしあたり、それで充分なのさ。と言うより、これ以上、あいつとは係わり合いになりたくはない。俺たちだって理不尽な命令で多くの仲間を失ったんだ。縁が切れたのなら、もうそっとしておいてほしいというのが正直なところだ」
「えらく疎まれたもんだな、奴も」
「俺たちが増えすぎたのか、人間が減りすぎたからなのかはわからんが、あいつは、まるで性格が変わっちまった。まるで甘やかされ続けた駄々っ子がオモチャを手に入れられなかった時みたいに、いつもイライラして当り散らしてた。気まぐれに仲間同士で死ぬまで戦わせたり、何日も眠り込んで棺から出てこないこともあった。心配して調子はどうかと尋ねただけで喉を裂かれた仲間もいる。先月なんかは思いついたように北米まで二百名の仲間を遠征に連れて行ったはいいが、一人っきりで戻ってきて理由も話さない。最近の俺たちは、あいつの一挙手一投足にすっかり怯えきってたんだ。そして、とうとう戻ってこなくなった。こんなことは初めてだ」
「奴に捨てられたということか、お前さんたちは?」
「よしてくれ。これ幸いに、俺たちの方が奴との縁を切ったんだ」
若いヴァンパイアはニコライの問いかけに、祭壇の十字架に顎をしゃくってみせた。
「だったら、貢物よろしく表に掲げられた人血は、奴のためじゃないのね?」
ナナは未だ警戒の解け切れぬ目で若い男を見据えた。
「当たり前だろ。あれは、あんた用の餌だよ。言ってみれば目印みたいなものさ。でも、こんなに仲間がいたなんて思いもしなかったよ」
「餌ねぇ……」と、ナナの代わりにマリクが苦々しく応じた。
「長い道中だ」若い男がナナを見た。「きっと飢えてると思ったんだ。すまない。気を悪くしたんなら謝る」
「でも、なぜ私がここへ来ると?」
「俺たちは人間に招待されない限り小部屋にだって入れない忌み者さ。でもヴァンパイアが世の中に存在する以上、人間には『もしかしたら……』という不安は常について回る。人間としては宿敵ブロドリック一味の情報を多く持っているにこしたことはない。そして砦にはヴァンパイアはあんた一人。人間の敵だぞ。きっと、あんたは快くは思われてないだろ。だったら、少しでも自分の立場を良くしようと、情報収集のため、ここに来るしかない。そう結論を出すのは難しいことじゃなかった。ただ意外だったのは、情報収集どころか、あいつを滅ぼしに来るなんて思いもしなかったってことさ」
「時に創造主に盾つく愚かなヴァンパイアもいるのよ、私みたいに」
ナナは自分が奇襲を言い出した本人であるかのように自嘲気味に溜め息をついた。そんなナナを弁護しようとマリクが口を開きかけたとき、数名のヴァンパイアとともにニコライが回廊の奥から現れた。彼はナナとマリクに頷くと、手の中の給水ボトルを差し出した。
「彼らの言う通りだ。ただの海水を口にし続けて緩慢に弱ってゆくより遥かにいい。まぁ、ブロドリップの血液が触媒になっているという胸糞の悪さを忘れることができればだが」
マリクはボトルの蓋を開けると、黄色い液体に恐る恐る鼻を近づけて臭いを嗅いだ。
「無臭だ」若い男がマリクに顔を向けた。「俺たちは“精進水”と呼んでいる。それを作る触媒は、あいつの血だが、直接、海水に混ぜたりするわけじゃない。血を密閉したボトルを近くに置いておくだけで何ガロンもの海水が手品みたいにそいつに変わってくれる。蒸留すればタブレットにすることだってできる。だが味には徹底的な個人差がある。俺は桃だと思うが、リンゴだと言い張る者もいる」
若い男の視線を受け、今まで一言も口を開かなかった丸顔のヴァンパイアが遠慮がちに手を挙げて「そう、僕はオレンジの味を感じます」と小声でぼそぼそ呟いた。
「アンナもオレンジ。だが、コルテスは苺だと」ニコライが言い添えた。「我々の味覚をどう刺激するのか謎だが、全員に共通するのは果物の味だということかな。ちなみに儂はメロン味だった」
「なるほどな。ところで、ケンたちの姿が見えないが?」
「あぁ。外の空気を吸いに行ったよ」
ニコライの口調から、ケンとキャスは外の空気を吸いに行ったのではなく、頭を冷やさせるために外に連れ出されたのだと察したが、マリクはただ「そうか」とだけ応じた。そんなマリクたちを見て若い男が身を乗り出した。
「俺たちに対するあんたたちの思いは、それぞれ複雑だと思う。でも、俺たちはあんたたちを飢えから完全に解放することができる。是非そうしたいと思ってもいる。これは俺たちの総意だ。それに人間たちを助けることもできる、彼らをヴァンパイアに転生させるってことじゃなくな」
「それは、ありがたい申し出だな」マリクの言葉に警戒の色が滲んだ。
「だから……」若い男は言いよどんだ。
「『だから』?」と、オウム返しにマリク。
「俺たちの頼みを聞いてくれないか?」
「そらきた」ニコライが鼻白んだ。「死んだ婆様が昔から言ってたもんだ。『ただより高価なものはない』とな」
「待ってくれ! 話す前から判断しないでくれ」
「わかった。話せよ」と、マリク。
「少し出すぎた願いだとはわかってるんだが」若い男は意を決したようにマリクの目をまっすぐに見詰めた。「俺たちも城砦に、あの街に住まわせてくれないか、あんたたちのように」
「馬鹿なことを言うな!」マリクが次の言葉を発するまで数瞬を要した。この申し出が彼にとっても相当意外だったに違いない。「残った人間たちがヴァンパイアと生活することを許すわけがない。わかるだろ、それくらい。あの伝染病でどれだけ犠牲になったか知ってるのか?!」
「今ごろは全滅してるかもしれない」
「言って良いことと悪いことがあるぞ」
気色ばんだニコライに若い男がばつの悪そうな顔を向けた。
「すまない、本当に。失言だ、許してくれ。でも、ここには親を失った小さな子や、ここで生まれた子もたくさんいるんだ。なぁ、あんたも、さっき見てきたろう。あの子らをこんなところに置いておかないでくれ。確かに橋を渡れば立派な街はあるが、ただそれだけだ。中身なんて何もない空っぽの空間みたいなもんだ。でも、あの城砦は街だ。街には、まともな人間らしい生活と教育……文化がある。それをあの子たちに与えてやってほしいんだ。それに、もしブロドリップが戻って来たらと思うと……」
ヴァンパイアの口から“人間らしい”という言葉が出ても誰も笑わなかった。それどころか、その場の全員がブラム氷期とブロドリップに自分たちが奪われたものが何だったかを、その言葉は思い出させた。
「しかしお前たちは」と、無口なコルテスが淡々と応じた。「人間に有害なウイルスの感染源」
「俺たちは街に着く寸前に発症した。微妙な身体の変化もあった。でも半日だけだ。そこからは、あっと言う間に快方に向かって体温は三十二度。脈拍も通常通り一分間に三十四だ。誰ももう感染源にはならない。安全だ。それに見返りも用意してある」
「見返り?」
「発電所。あ……あの街には……それが必要だと思います」丸顔のヴァンパイアがマリクの「見返り」という言葉に応じて、おどおどと口を挟んだ。
「残念だな。我々は、もう原子炉は持ってる」
「黒煙型の旧式は放射線の遮蔽も難しいし、出力を上げると危険です。事故が起こる。始祖からは……あぁ、ごめんなさい。ブ……ブロドリックは城砦……街は色々な施設が稼働し始めてるから、あれでは、すぐに電力供給が追い付かなくなるはずだと言ってました。僕なら解決できると思います」
言葉に詰まりながらも一気にそこまで喋ると丸顔のヴァンパイアは乾いた唇を舐めて皆の反応を伺った。沈黙の中、若い男が話を続けるように目配せしたので、彼は大きく息を吸い込むと、先程よりも、ややゆっくりとした口調で再び話しはじめた。
「僕は当初、あなたたちの街のエネルギープラントの設計者でした。2004年の海洋地震でインド南部の原発が事故を起こしかけたので、スマトラでも原発はご法度になったんです。だから“アルキメデスのスクリュー”を改良進化させた“アルキメディアン・ホンダ・システム”の潮汐発電を使うことになりました。でも氷期が来てそんなことも言ってられなくなったんです。実験稼働まで、あと少しだったのに。ほんとに少しだったんです」
「潮汐発電……海は凍って波もないのにかね?」ニコライが探るような声を上げた。
「凍ってるのは表面だけ」と、丸顔のヴァンパイア。「木星の凍りついた第二衛星だって海中には潮汐力があるんです。地球が凍りついたって問題ない。城砦の目と鼻の先には手付かずの安全なリアクターがあるんです。建屋と長いラインは耐震用に地下区画に設置してます。そう……まるで、その……大きくて……長い廊下を地下室みたいにして、幾つも、幾つも区切って作ったんです。それが完成してたんです、僕がまだ人間だったころに」
「しかし信用できるのかね」ニコライは訝しげに口をすぼめた。「その潮汐リアクターとやらは、まだ実験段階なんだろ?」
「ここも既にそのリアクターの小型のものを使ってますよ」丸顔ヴァンパイアの声は小さかったが、自信に満ちていた。「海が浅くて大きなものは設置できませんでしたが、故障もない」
「なぁ」若い男の口調が再び熱を帯びた「電力問題も解決できるんだ。それでも駄目なら……いや俺たち大人が駄目でもいい。でも、子どもたちだけは面倒を見てやってくれないか。せめて快適なベッドと教育、いやブロドリップからの安全だけでも与えてやってくれ。頼む」
「わたしからもお願いよ」いつの間にかアンナが回廊の入り口の一つに立っていた。彼女はいたわるように一人のヴァンパイアの女に寄り添っていた。妊娠しているのか、その女のお腹は大きかった。「娘のジェイミーよ。転生して、ここに居たの」
「なぁ、あんたからも仲間に頼んでくれないか」若い男は、これが最後とばかりナナに哀願の目を向けた。「今さら、こんなこと言いたくはないが、あんたは俺に借りもあるはずだろ」
初めて顔を見たときからナナには彼が何者なのかわかっていた。彼はナナが血を呑み干した、あの時、彼女のアパート前に駆けつけた若い警官だった。
*
激論の末、ナナたちはジェロン島にいたヴァンパイアの思いを砦の人間たちに伝えるパイプ役になり、彼らを連れて行くことを承諾した。それに激しく反発したケンとキャスは、ナナたちに怒りの矛先を向けたが、どうにもならないと知ると、翌朝、皆が寝静まってから橇に持てるだけの食糧タブレットを積み込んで黙って島を抜け出した。彼らの置手紙にはブロドリップを地の果てまでも追い詰めて滅ぼしてみせると決意の殴り書きがしたためてあった。むろん、食糧と橇を盗んだことに対する謝罪の言葉は一言も書かれていなかった。この一件でナナたちとジェロン島の集団に一時的に不穏な空気が流れたが、それもすぐに影を潜めた。未来に進むためには、いがみ合ってばかりはいられないと、二つの集団の全員がわかっていたからだ。ナナたち一行は、シンと自己紹介した防護服の若い警官を筆頭に、二次性徴を終えたばかりの少年少女七名のヴァンパイア使節を伴って徒歩で城砦に向かうことになった。当初、ナナたちは子どもを重大な危険に晒すかもしれないこの決定に難色を示したが、使節団のほとんどを子どもで編成した方が人間の警戒感を少しでも緩和できるのではないか。また子どもを連れてゆくことで人間の慈悲心に訴えかけられるのではないかというジェロン島のヴァンパイアの強い総意に押し切られることになったのだ。もちろん城砦にいる人間に対する配慮はそれだけでは不十分だ。シンたちは自ら紐状の工業用導爆線でネックレスを作り、そこに警察無線を改造した起爆装置を取り付けて首に巻きつけ、いつでも自分たち自身を無力化できるようにした。もっとも、それぐらいしても人間たちが話のテーブルについてくれる可能性は多くはないだろうが。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

蠍の舌─アル・ギーラ─
希彗まゆ
ミステリー
……三十九。三十八、三十七
結珂の通う高校で、人が殺された。
もしかしたら、自分の大事な友だちが関わっているかもしれない。
調べていくうちに、やがて結珂は哀しい真実を知ることになる──。
双子の因縁の物語。

それでもミステリと言うナガレ
崎田毅駿
ミステリー
流連也《ながれれんや》は子供の頃に憧れた名探偵を目指し、開業する。だが、たいした実績も知名度もなく、警察に伝がある訳でもない彼の所に依頼はゼロ。二ヶ月ほどしてようやく届いた依頼は家出人捜し。実際には徘徊老人を見付けることだった。憧れ、脳裏に描いた名探偵像とはだいぶ違うけれども、流は真摯に当たり、依頼を解決。それと同時に、あることを知って、ますます名探偵への憧憬を強くする。
他人からすればミステリではないこともあるかもしれない。けれども、“僕”流にとってはそれでもミステリなんだ――本作は、そんなお話の集まり。
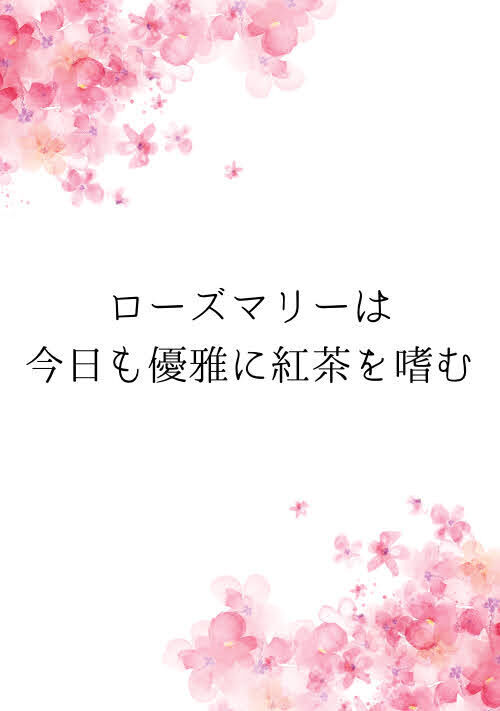
ローズマリーは今日も優雅に紅茶を嗜む(声劇台本用)
ソウル
ミステリー
ローズマリー家は王家の依頼や命令を遂行する名門家
ローズマリー家には奇妙で不気味な事件が舞い降りる
これは、ローズマリー家が華麗に事件を解決する物語

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

#彼女を探して・・・
杉 孝子
ホラー
佳苗はある日、SNSで不気味なハッシュタグ『#彼女を探して』という投稿を偶然見かける。それは、特定の人物を探していると思われたが、少し不気味な雰囲気を醸し出していた。日が経つにつれて、そのタグの投稿が急増しSNS上では都市伝説の話も出始めていた。

紅い瞳の魔女
タニマリ
ファンタジー
シャオンは魔女である。
幼い頃に母を目の前で殺され、その犯人を探すために人間の魔法学校へと入学してきた。
魔女の特徴である類《たぐい》まれなる美貌と紅い瞳を隠すために普段は男として生活しているのだが……
超美少年になっているもんだから目立ちまくっていた。
同じ学校に入学してきたツクモという少年は入学式の日に男の姿であるシャオンに一目惚れをしてしまう。
シャオンが男と知り猛烈に落ち込むツクモ……
それでもしつこくつきまとってくるツクモにシャオンは素っ気ない態度をとって遠ざけようとしていたのだが、ある夜、女へと戻る姿をツクモに見られてしまい、魔女だということもバレてしまう。
そんなツクモにも人には言えない秘密があるようで……
☆表紙のイラストは自作です。エブリスタの方では挿絵もたくさん載せていますので、もし興味のある方は覗いて見てください(❁ᴗ͈ ᴗ͈)”

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

月の後宮~孤高の皇帝の寵姫~
真木
恋愛
新皇帝セルヴィウスが即位の日に閨に引きずり込んだのは、まだ十三歳の皇妹セシルだった。大好きだった兄皇帝の突然の行為に混乱し、心を閉ざすセシル。それから十年後、セシルの心が見えないまま、セルヴィウスはある決断をすることになるのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















